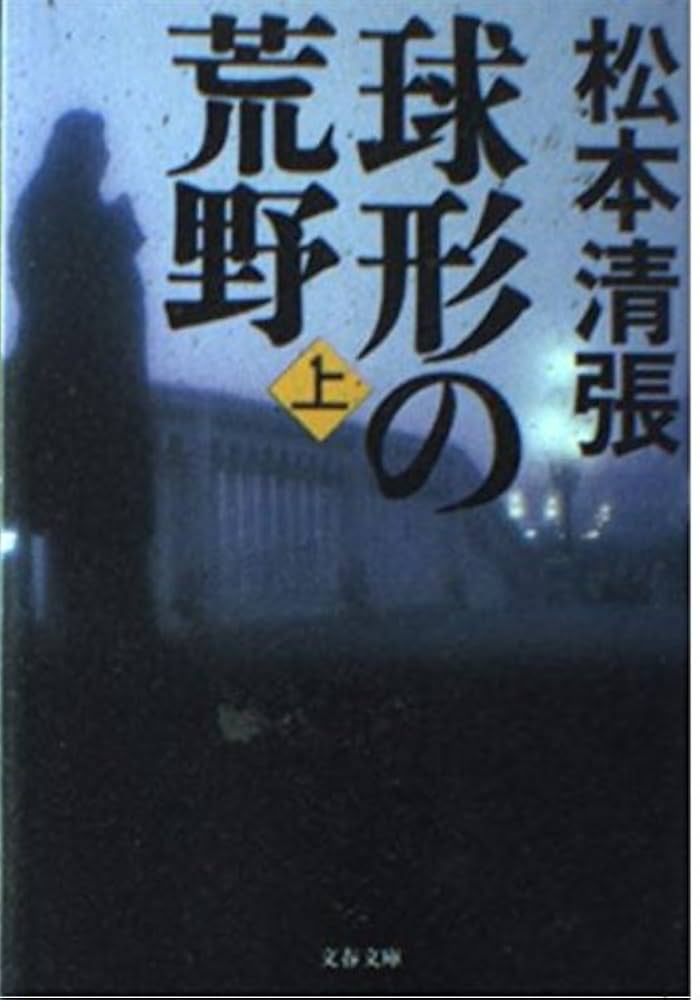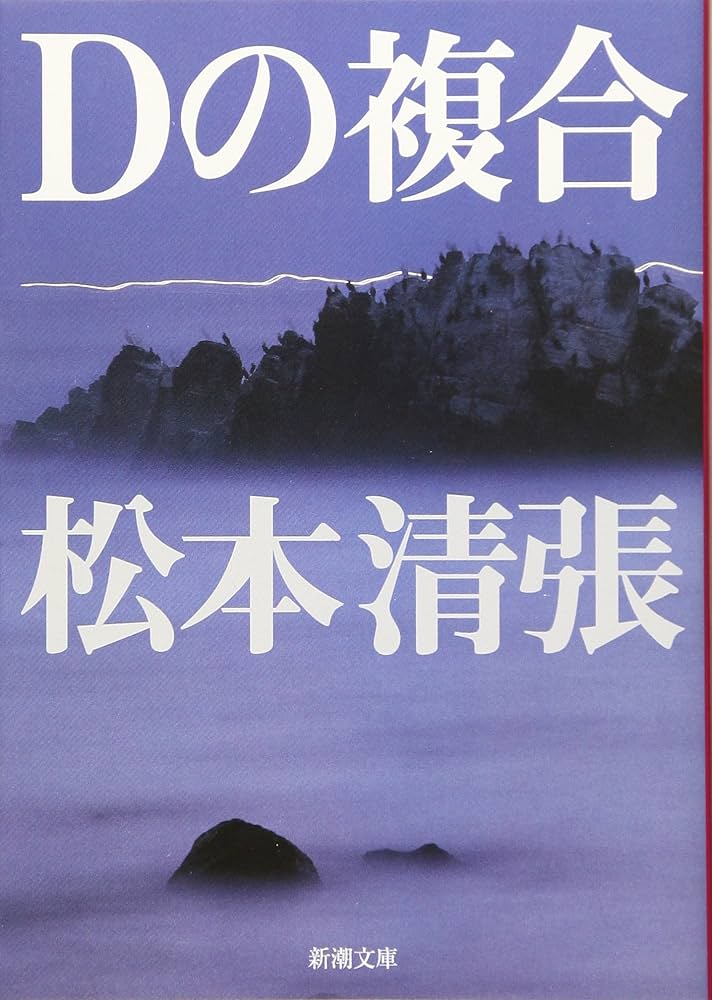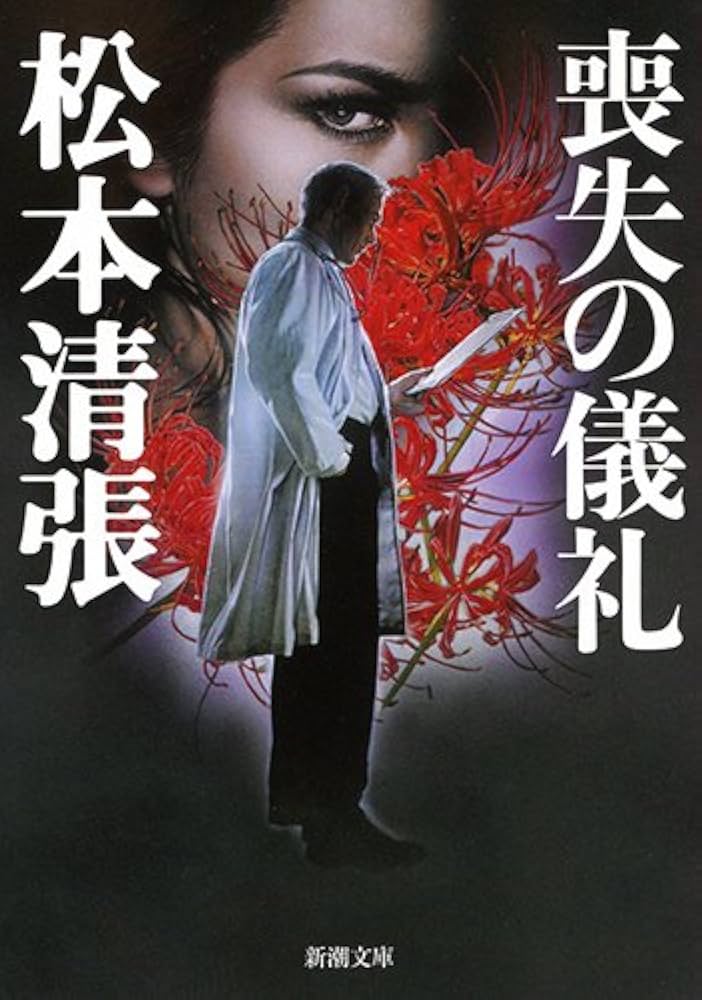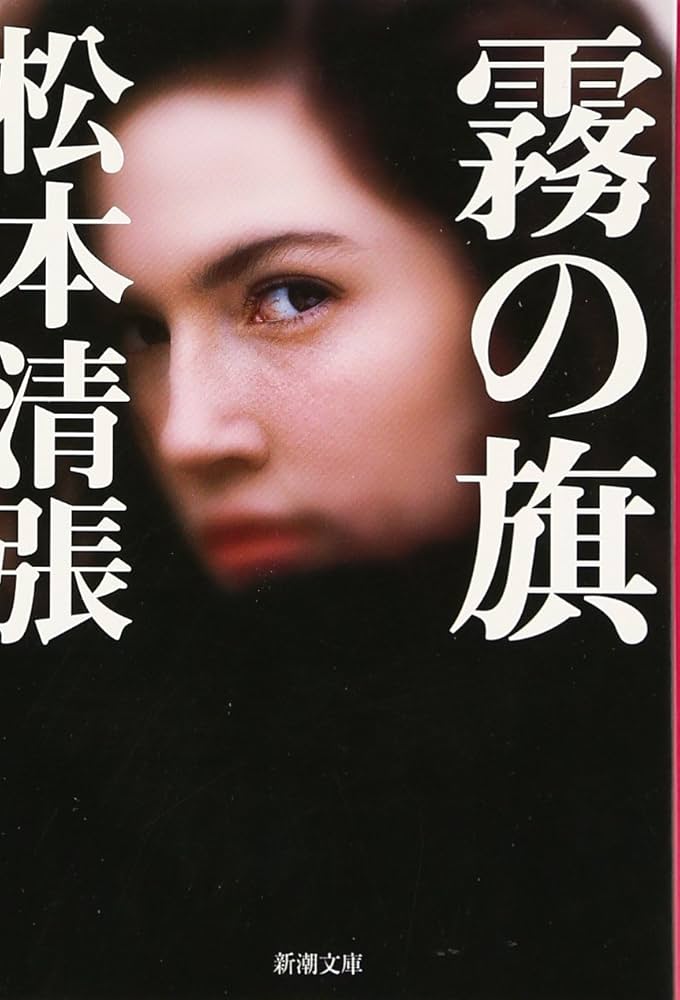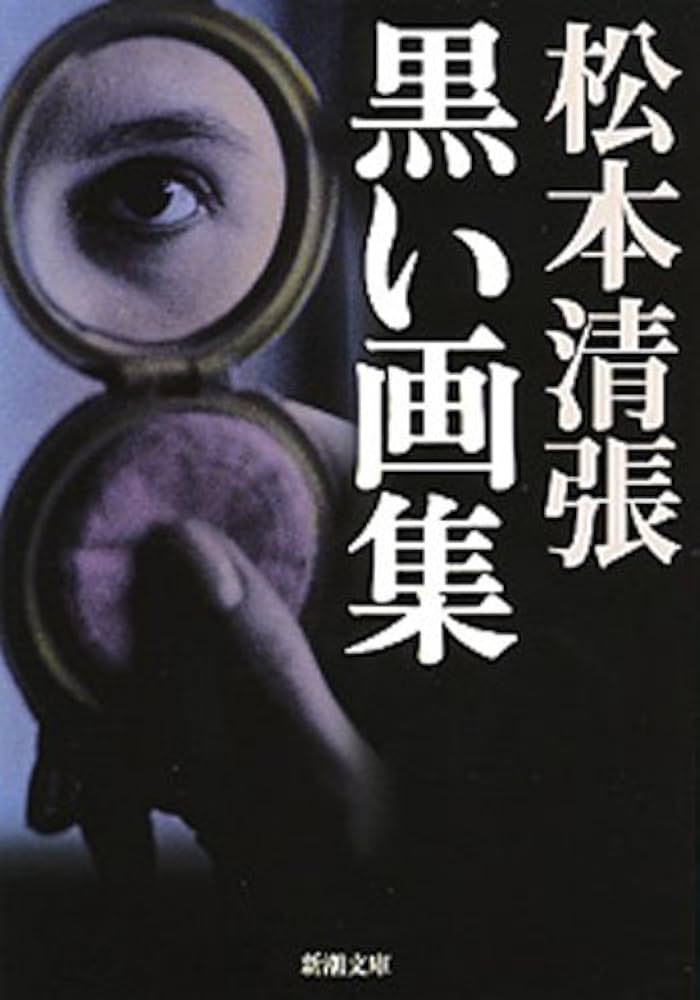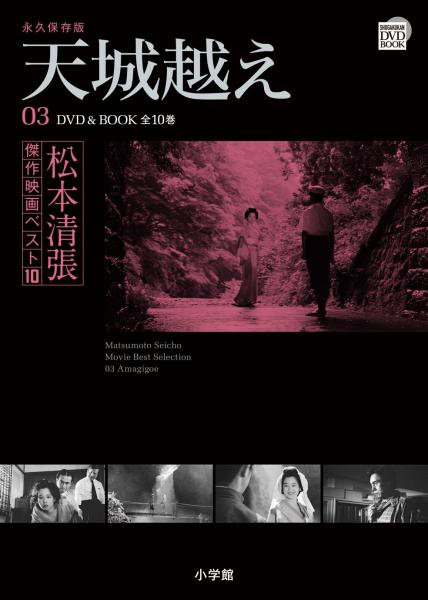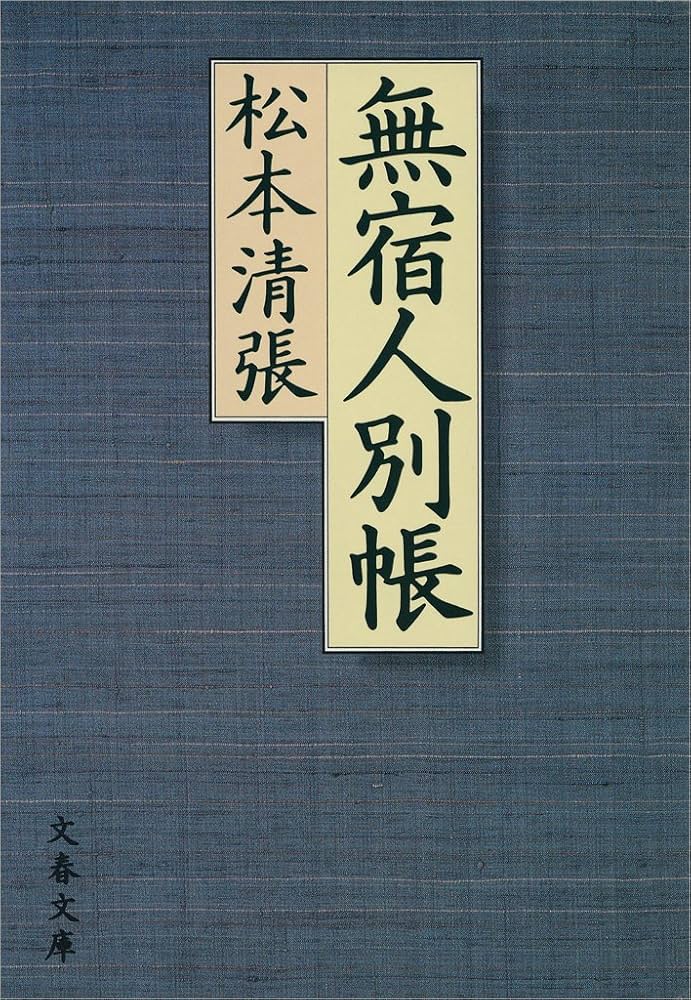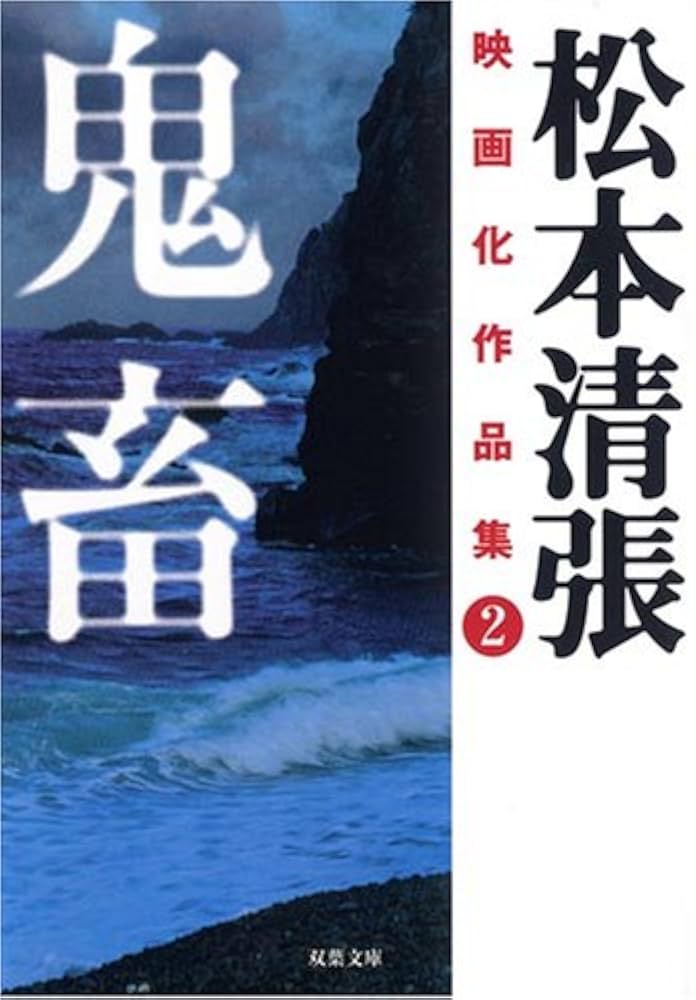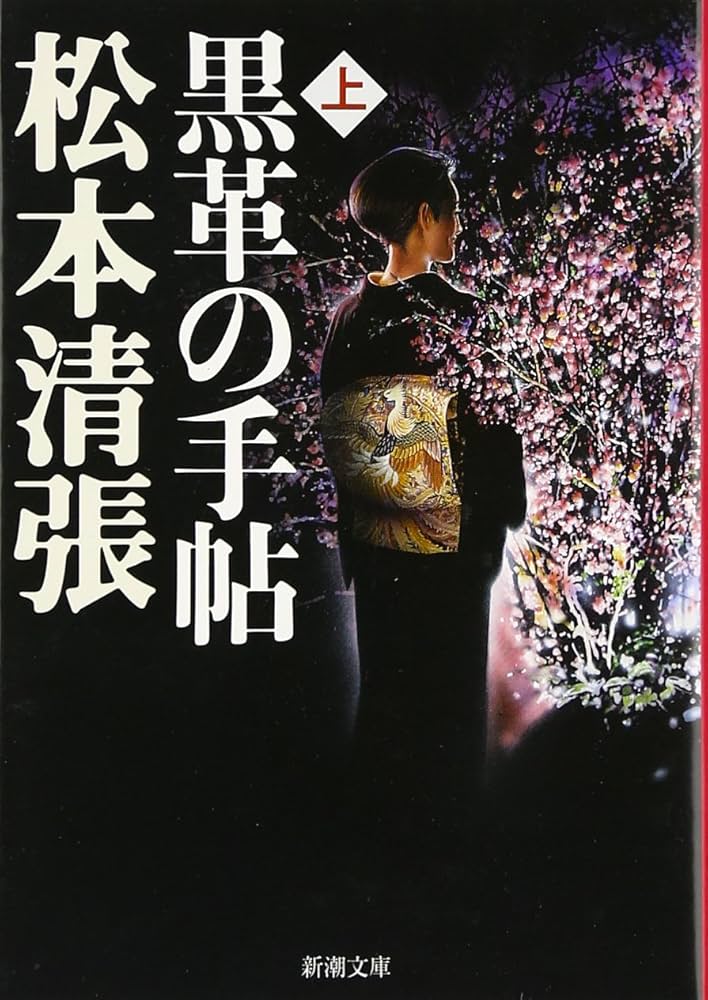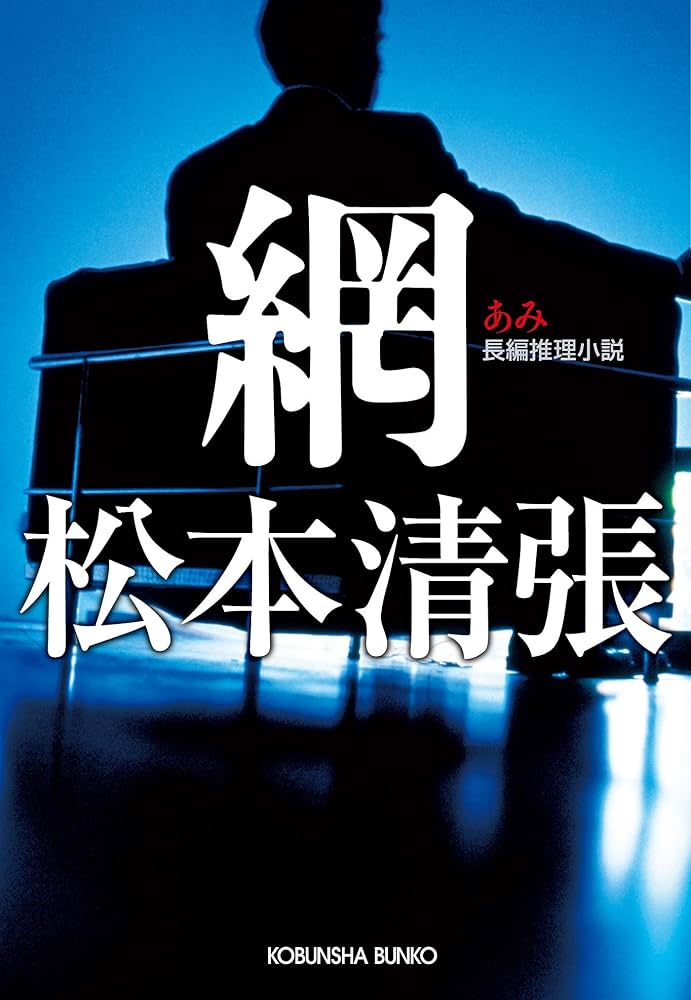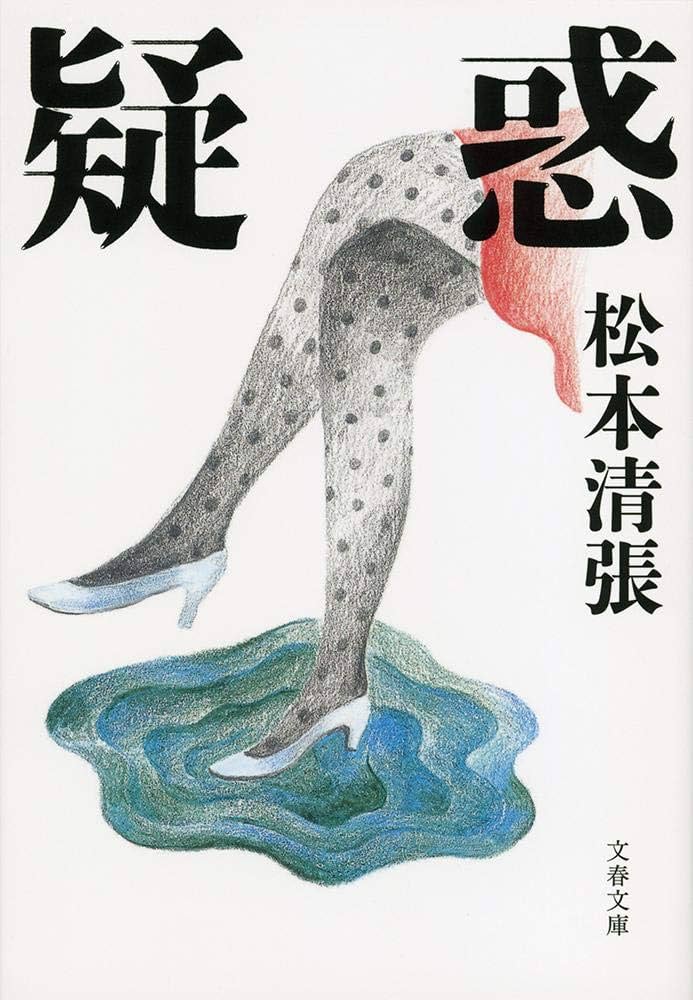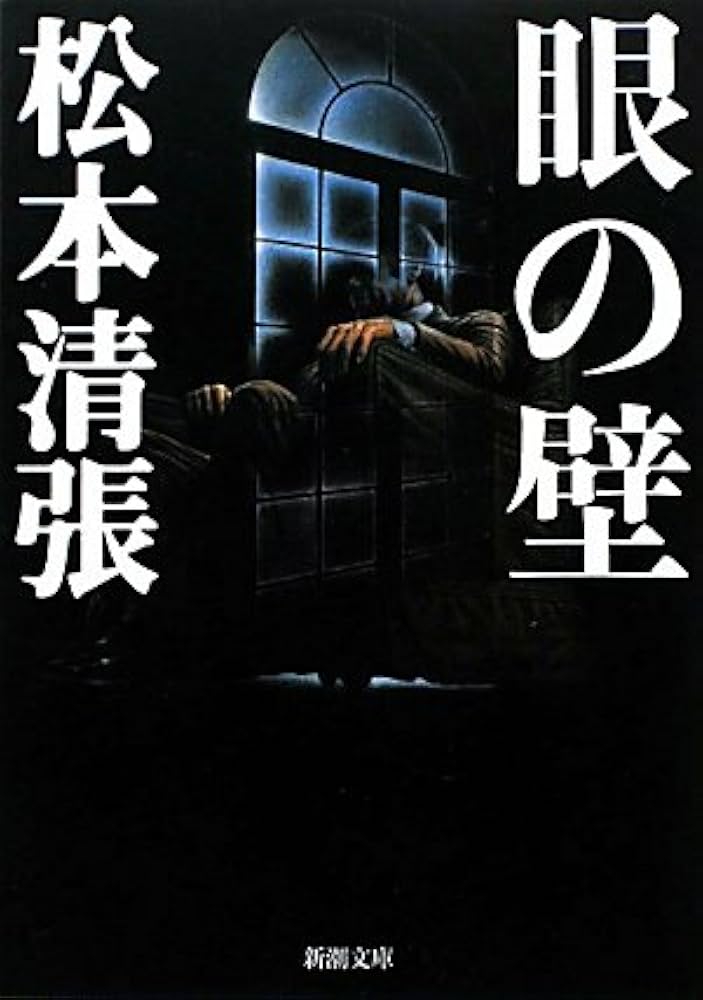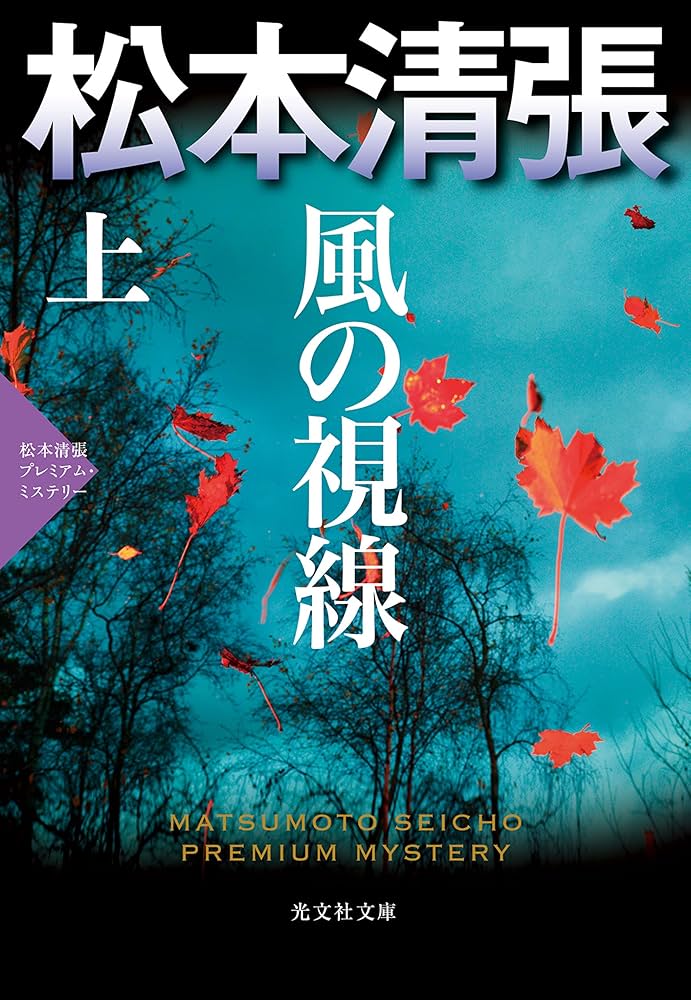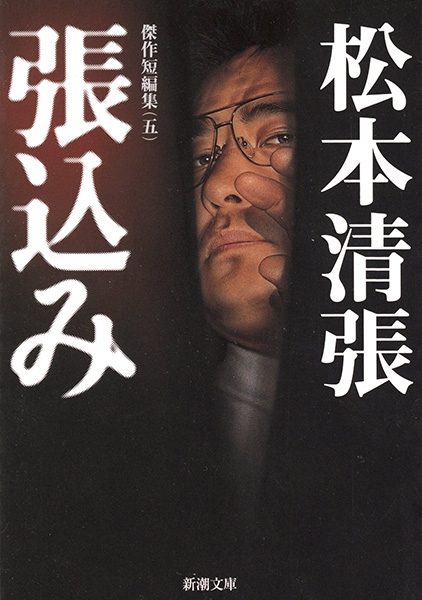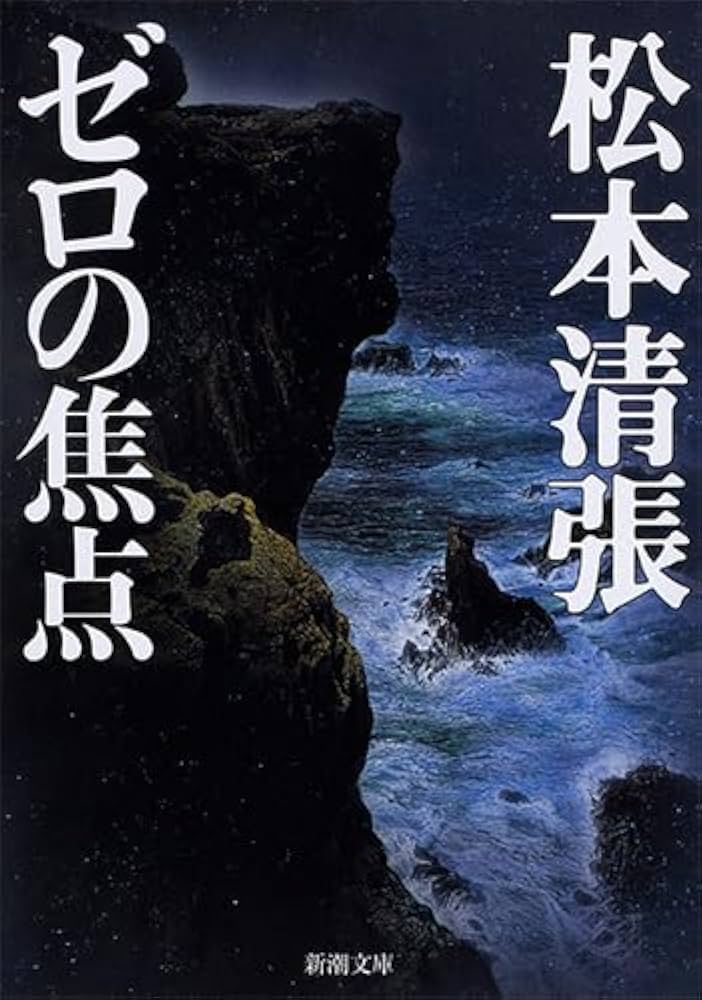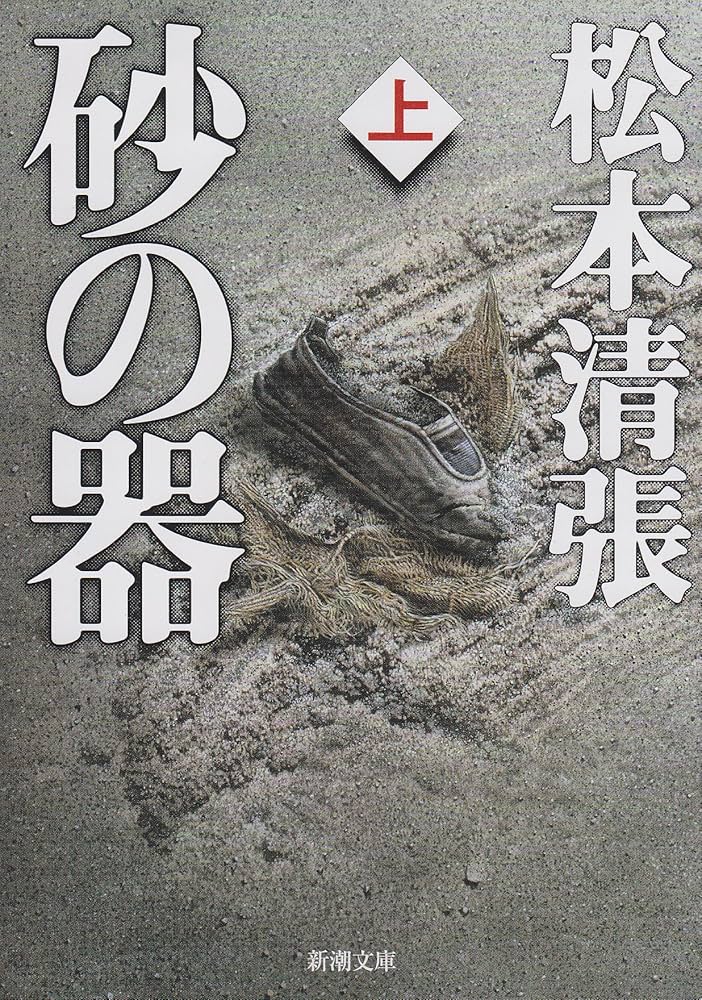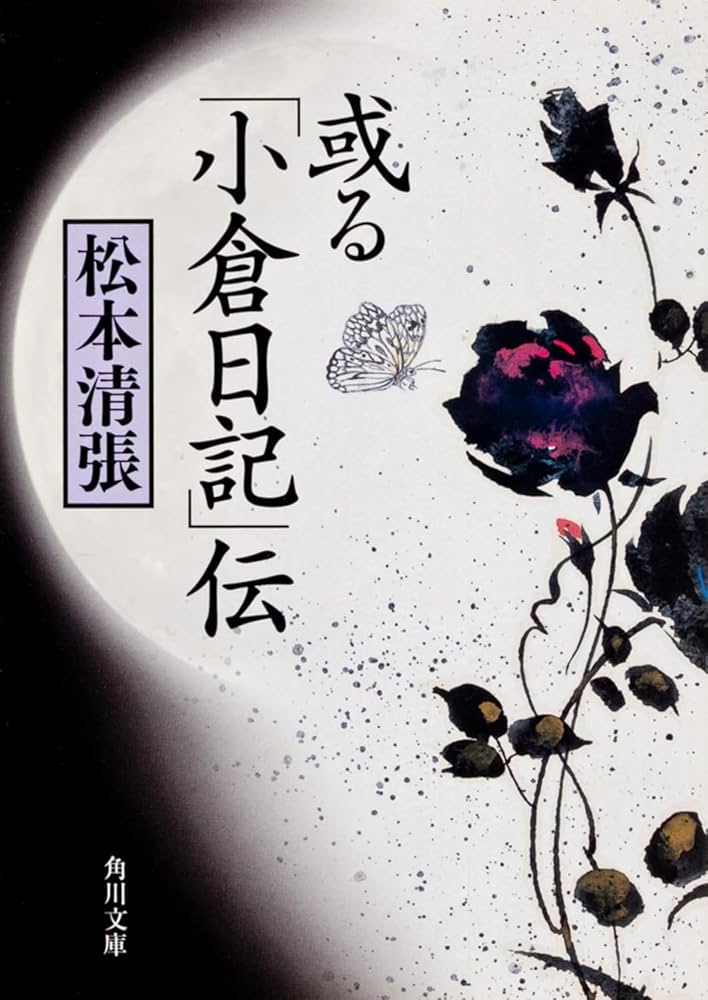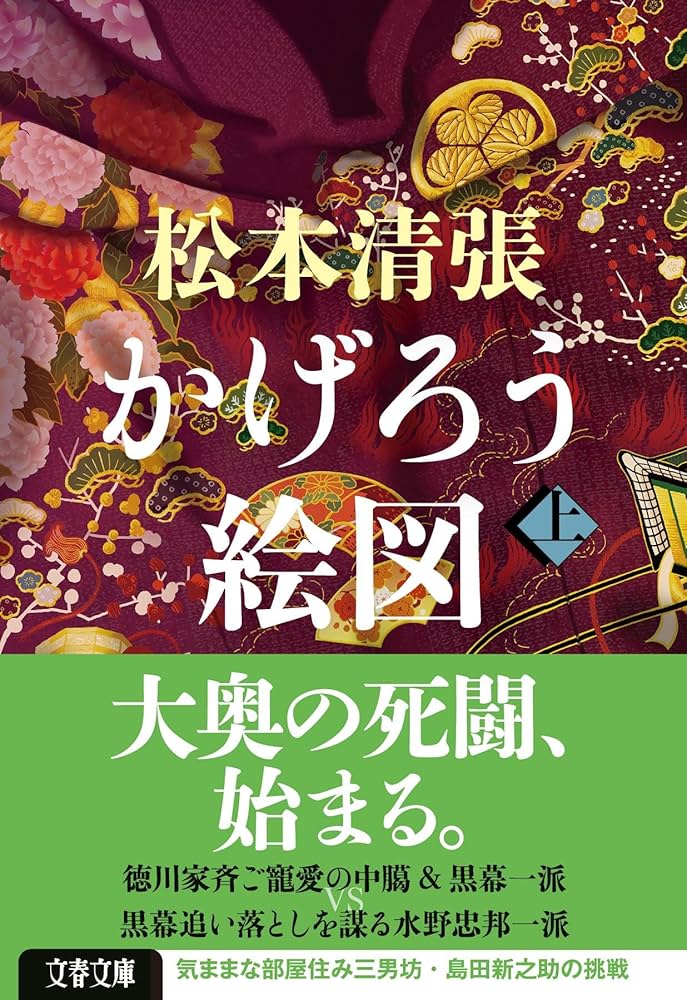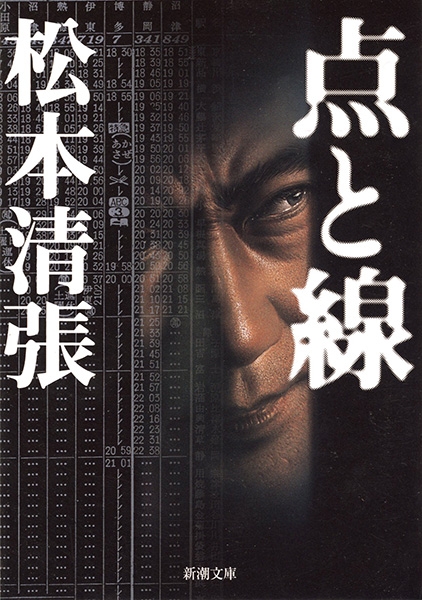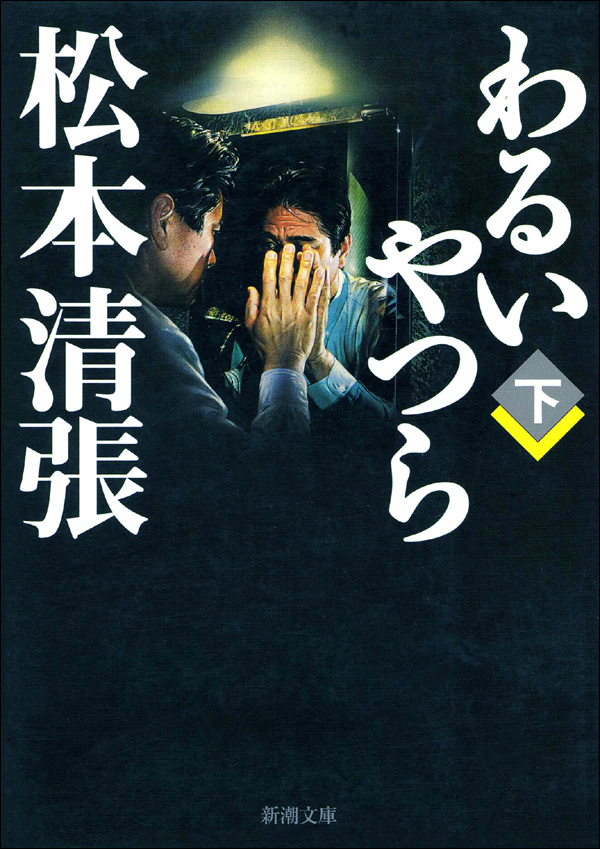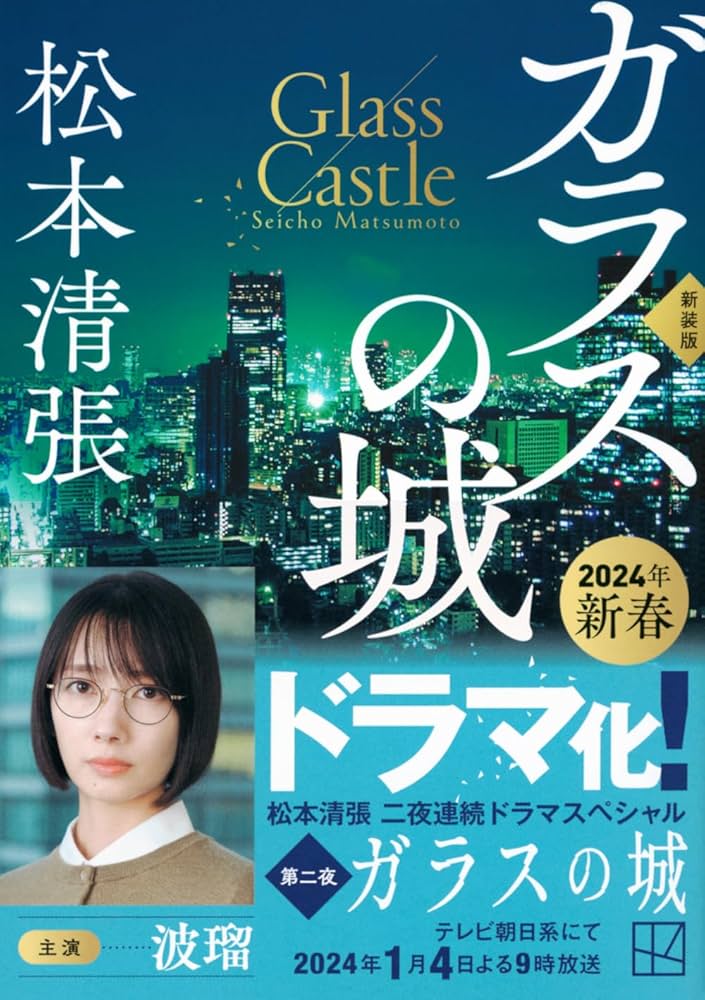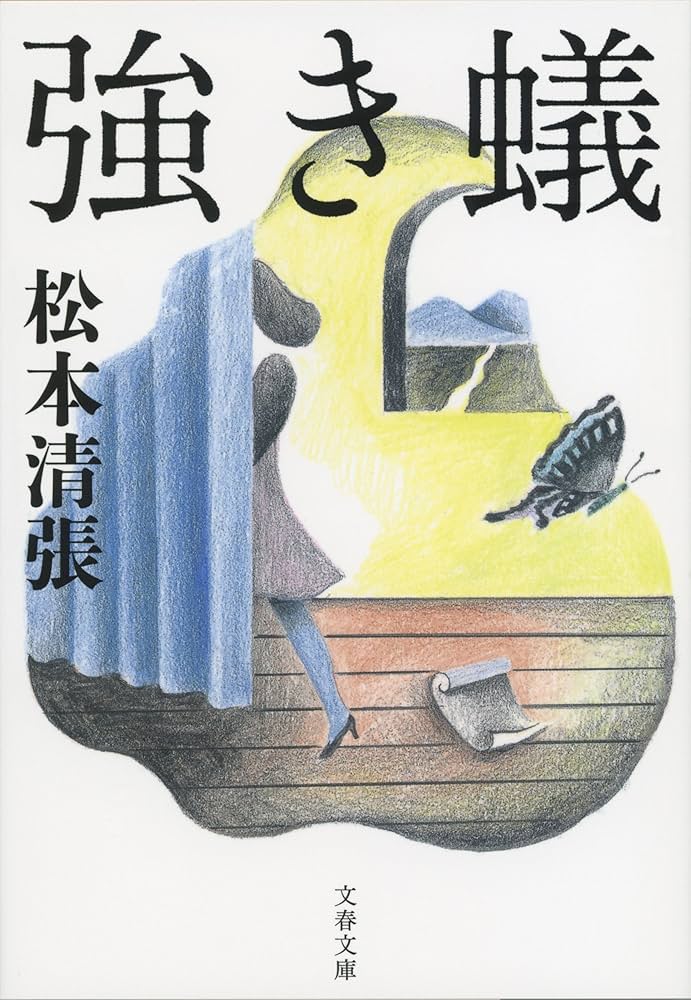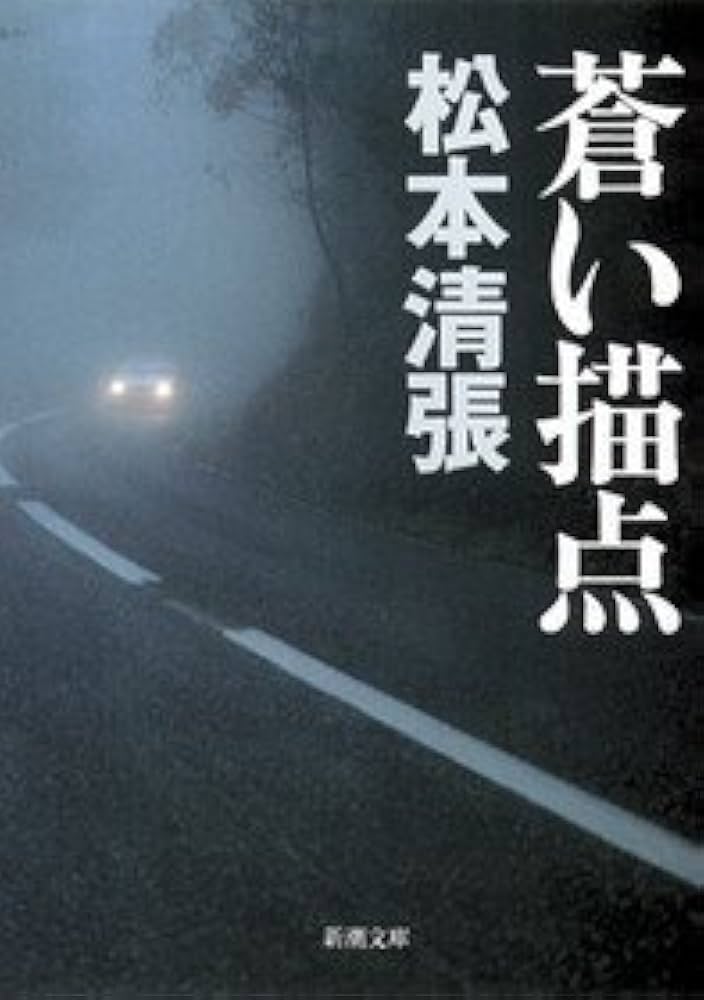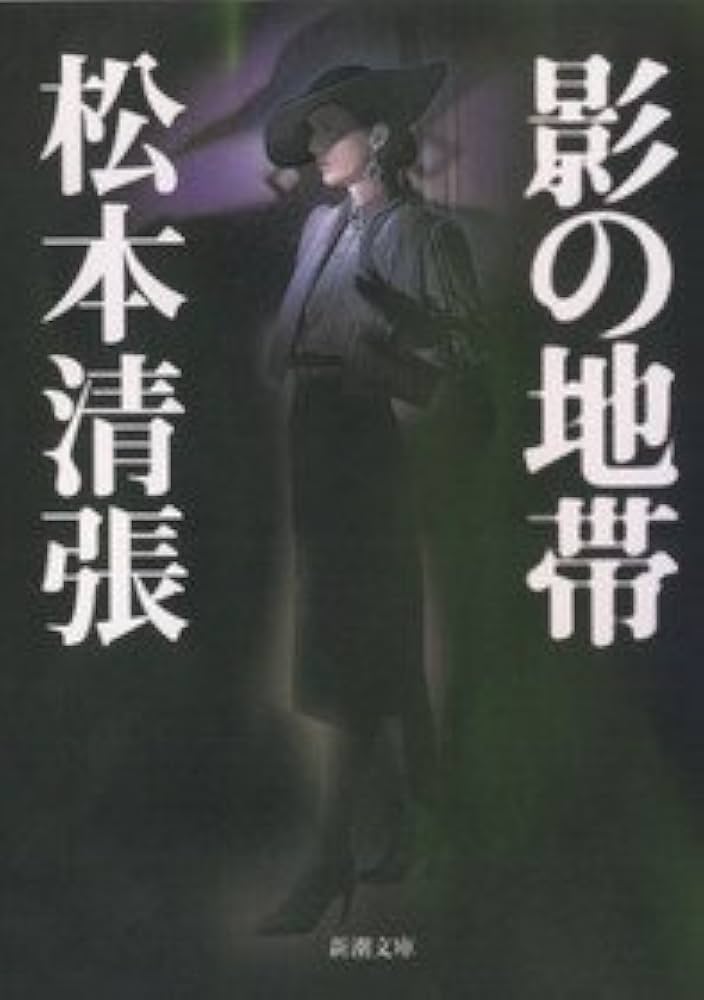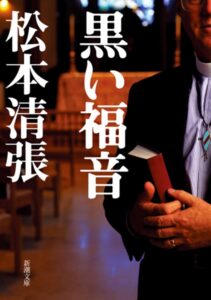 小説「黒い福音」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「黒い福音」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
松本清張作品の中でも、ひときわ異様な熱量と憤りが込められているのが、この『黒い福音』ではないでしょうか。実際に起きた未解決事件を題材に、フィクションの力を借りてその深層に切り込んだ本作は、単なる推理小説の枠をはるかに超えています。
物語は、聖なる仮面をかぶった教会の腐敗から始まります。その闇が、一人の純真な青年神父を蝕み、やがて悲劇的な殺人事件へと繋がっていくのです。そして後半は、執念の刑事があと一歩まで犯人を追い詰めながらも、見えざる巨大な壁に阻まれ、正義が踏みにじられていく様が描かれます。
この記事では、まず物語の骨子となるあらすじを紹介し、その後で、なぜこの結末でなければならなかったのか、作者が何を告発したかったのか、核心に触れるネタバレを含んだ詳しい感想を綴っていきます。読後に残る重い余韻の正体を、一緒に探っていきましょう。
「黒い福音」のあらすじ
物語の舞台は、戦後日本に設立されたカトリック教会「グリエルモ教会」。そこは、神聖な祈りの場であると同時に、救援物資の横流しといった不正行為で築かれた、腐敗の温床でもありました。中心にいるのは、老獪なビリエ神父と、その裏仕事を手伝う謎の女性・江原ヤス子です。
数年後、この教会に若く敬虔なシャルル・トルベック神父が赴任してきます。しかし、清廉であったはずの彼の魂は、教会の偽善と、日本の女性信者たちからの熱狂的な崇拝に触れるうち、少しずつ歪んでいきました。彼はやがて、信者の一人である美しい生田世津子と出会い、禁断の恋に落ちてしまいます。
世津子への愛は本物でした。しかし、教会はさらなる巨悪――麻薬の密輸計画を企てており、国際線のスチュワーデスとなった世津子を「運び屋」として利用しようと画策します。その非情な計画の説得役を命じられたのが、恋人であるトルベック神父でした。彼は愛と、教会への服従との間で引き裂かれます。
世津子の敬虔な信仰心は、この犯罪への加担を断固として拒否します。その清廉な心が、自らの命運を決定づけてしまうことも知らずに。計画の漏洩を恐れた教会は、トルベックに恐るべき命令を下します。物語はここから、一人の女性の死を巡る、痛ましい事件の真相へと向かっていくのです。
「黒い福音」の長文感想(ネタバレあり)
この物語の感想を語る上で、まず触れなければならないのは、本作が現実の事件、通称「BOACスチュワーデス殺人事件」に着想を得ているという事実です。重要参考人とされた外国人神父が捜査の網をかいくぐるように日本を去り、事件は迷宮入りとなりました。この法治国家としてあるまじき結末に、作者である松本清張が抱いたであろう、やり場のない憤り。そのマグマのような感情が、この『黒い福音』という作品を生み出したのだと感じずにはいられません。
物語は大きく二つのパートに分かれています。前半が事件に至るまでの倒錯した人間模様を描く「犯罪編」、そして後半が事件の真相に迫る刑事たちの苦闘を描く「推理編」です。この構成によって、私たちはまず犯罪の根源にあるおぞましい腐敗の構造をじっくりと見せつけられ、次にその構造に挑む正義がいかに無力であるかを、これでもかと突きつけられるのです。
物語の始まりは、終戦直後の武蔵野に建つグリエルモ教会。この教会の礎が、すでに不浄のものでした。海外から送られてくる救援物資、いわゆるララ物資を横流しし、闇市で売りさばいて莫大な利益を得る。飢えに苦しむ人々を救うべき聖職者が、その救いの手を汚し、私腹を肥やしていたのです。この冒頭部分を読むだけで、胸に重いものがこみ上げてきます。
その腐敗の中心にいるのが、ビリエ神父と、その愛人であり共犯者でもある江原ヤス子。聖書の翻訳と偽ってヤス子の家に入り浸り、闇物資の取引と情事に耽る。この二人の関係は、聖職者の堕落を象徴しています。やがて不正が警察の知るところとなりますが、教会側は管区長のマルタン神父を筆頭に、日本の警察を侮りきった尊大な態度で臨み、信者である日本人協力者にすべての罪を被せて切り捨てます。この時点で、彼らにとって日本の法律も信者の人生も、組織防衛の前では塵芥に等しいことが明確に示されます。
そして7年の歳月が流れ、教会が不正な資金で大きく発展した頃、一人の若き神父が赴任してきます。シャルル・トルベック。敬虔で、女性を知らない純真な青年。物語の悲劇の主役です。彼のような清らかな魂が、この澱んだ空気の中でいかにして蝕まれていくのか。その過程が実に丹念に描かれます。
最初は戸惑いながらミサを執り行うトルベックでしたが、外国人神父というだけで有り難がる女性信者たちの熱い視線に、彼はこれまで知らなかった快感を覚えてしまいます。虚栄心という名の甘い毒です。そして、ビリエ神父とヤス子の隠そうともしない関係を目の当たりにし、彼の心にあった聖職者への理想は完全に崩壊します。信じていたものが偽りだと知った時、心に空いた穴を埋めたのは、女性信者たちとの刹那的な肉体関係でした。
そんなトルベックの前に現れるのが、後に犠牲者となる生田世津子です。教会のピクニックで出会った二人。集団に馴染めず、どこか孤独な影を持つ者同士として、強く惹かれ合います。ここでの描写は、破滅へ向かう前の、束の間の純粋な恋愛として描かれており、だからこそ後の悲劇性が際立ちます。トルベックにとっても、世津子への想いは遊びではなく、真実の愛情だったはずなのです。
しかし、二人のささやかな愛は、教会の巨大な悪意の前にはあまりにも無力でした。教会は、麻薬密輸という新たな犯罪に手を染めていました。本作の題名である「黒い福音」とは、教会の維持拡大のためならば、いかなる犯罪も神の御業として正当化してしまう、この倒錯した論理そのものを指しているのでしょう。そして、その密輸の「運び屋」として、国際線のスチュワーデスになった世津子に白羽の矢が立ちます。
世津子を説得し、犯罪計画に引きずり込むという汚れ役を命じられたのは、恋人であるトルベ-ックでした。愛する女性を、自らが仕える組織の犯罪に巻き込まなければならない。彼の葛藤は想像を絶するものがあったでしょう。しかし、彼は教会という絶対的な権威に逆らうことができません。この時点で、彼の魂は半分死んでいたのかもしれません。
この物語における唯一の光は、生田世津子の清廉さでした。彼女はトルベックから計画を打ち明けられますが、その敬虔な信仰心と、人間としての真っ当な倫理観から、きっぱりと協力を拒否します。愛する人からの頼みであっても、罪は罪として受け入れられない。このあまりにも正しい彼女の判断が、自らの死の引き金を引いてしまうという皮肉。これほど残酷な展開があるでしょうか。
計画の漏洩を恐れた教会は、トルベックに「世津子を殺せ」と命じます。組織防衛のための「必要な犠牲」なのだと。彼の罪悪感を麻痺させ、追い詰めていく教会のやり口は、悪魔の囁きそのものです。そして、彼はついにその命令を実行してしまう。愛する世津子を自らの車に乗せ、人気のない場所で、その手で首を絞める。信頼しきっている相手からの行為だったからか、彼女はほとんど抵抗もせず、安らかな顔で息絶えたと描写されます。この静かな死の場面は、本作で最も悲しく、そして冒涜的な瞬間です。
ここから物語の視点は警察側に移り、後半の「推理編」が始まります。川で発見された世津子の遺体。所轄署は自殺と早合点しますが、警視庁捜査一課のベテラン刑事、藤沢六郎、通称「ロクサン」だけが、その安らかな死に顔に他殺の匂いを嗅ぎ取ります。彼の刑事としての勘が、この難事件の扉をこじ開けるのです。
藤沢と若手の市村刑事のコンビによる、地道な聞き込み捜査が始まります。この部分は、松本清張作品の真骨頂ともいえるパートです。一つ一つの情報を足で稼ぎ、パズルのピースをはめていくように、少しずつ真相に近づいていく過程は、読んでいて胸が躍ります。やがて、事件現場近くで目撃された「外国人ナンバーのルノー」という決定的な証言に辿り着き、捜査線はグリエルモ教会へと繋がります。
そして藤沢は、トルベックが事件直後、不自然にも車のタイヤを5本すべて新品に交換している事実を突き止めます。これは現場に残したタイヤ痕を消すための、動かぬ証拠隠滅工作でした。藤沢が「犯人の尻尾を掴んだ」と確信したこの瞬間は、読者にとってもカタルシスを感じる場面です。しかし、この物語は、ここからが本当の地獄なのです。
藤沢たちの前に立ちはだかったのは、グリエルモ教会という治外法権の「聖域」でした。神父たちは非協力的な態度に終始し、捜査を「宗教弾圧だ」と非難してきます。トルベックへの接触は阻まれ、「神に仕える者が殺人を犯すはずがない」と信じる信者たちが、警察への抗議活動を行う。純粋な信仰心が、結果として犯罪者を守る壁となってしまう。この構造の根深さに、藤沢だけでなく読者もまた、歯噛みする思いをさせられます。
そして、捜査にとどめを刺したのは、日本政府からの見えざる圧力でした。外国人神父の殺人容疑というスキャンダルは、国際問題になりかねない。特に首相の欧州歴訪を控えた時期であり、政府は国家の体面を保つことを、一人の国民の命の尊厳よりも優先したのです。藤沢たちの正義は、「国益」という名の巨大な力によって、いともたやすく握り潰されてしまいます。
そして、あのあまりにも有名な、そしてあまりにも無力感を誘う結末が訪れます。捜査の手が緩んだ隙に、トルベック神父は堂々と出国手続きを済ませ、飛行機で日本を去っていく。藤沢たちは、空港でその姿をただ見送ることしかできないのです。日本の法律は、彼を裁きの場に引きずり出すことすらできなかった。完全なる敗北です。この結末は、ミステリーの定石である「犯人逮捕による事件解決」を期待する読者を裏切ります。しかし、これこそが松本清張が伝えたかった、この国の現実だったのでしょう。
『黒い福音』が告発するものは、単なる教会の腐敗に留まりません。それは、組織や国家といった権力が、自己保存のためにはいかに冷酷になれるかという、普遍的な真理です。トルベック神父の魂を殺し、藤沢刑事の正義を打ち砕いた「黒い福音」は、私たちの社会のすぐ隣に、今も存在しているのかもしれない。そう思わせるだけの力が、この物語にはあります。読後に残るのは、解決されない事件への怒りと、守られなかった命への哀悼、そして社会への深い絶望です。しかし、この作品を読むことで、私たちはこの理不尽さを決して忘れないでいられる。それこそが、松本清張が文学を通して成し遂げた、最も偉大な「告発」だったのだと私は思います。
まとめ
松本清張の『黒い福音』は、実際に起きた未解決事件を背景に、聖職者の堕落と殺人を描き、その背後にある巨大な権力の壁を告発した社会派ミステリーの傑作です。物語は、不正にまみれた教会で純真な神父が蝕まれ、恋人を手にかけるまでの悲劇を丹念に追います。
後半では、執念の刑事が真相に迫りますが、その正義は「聖域」である教会と、国家の体面を優先する政治的圧力の前に無残にも打ち砕かれます。犯人が国外へ逃亡するという、救いのない結末は、読者に強烈な無力感と憤りを突きつけます。
このカタルシスのない終わり方こそが、本作の核心です。作者はフィクションの力を用いて、現実社会に存在する理不尽と、法の限界を鋭く描き出しました。
単なる謎解きに終わらない、社会の病理に深く切り込んだ重厚な物語であり、松本清張の作家としての執念を感じさせる一冊です。読後、その重い問いかけが長く心に残ることは間違いないでしょう。