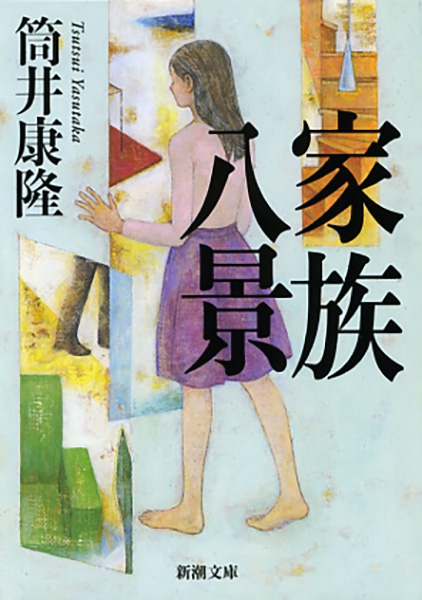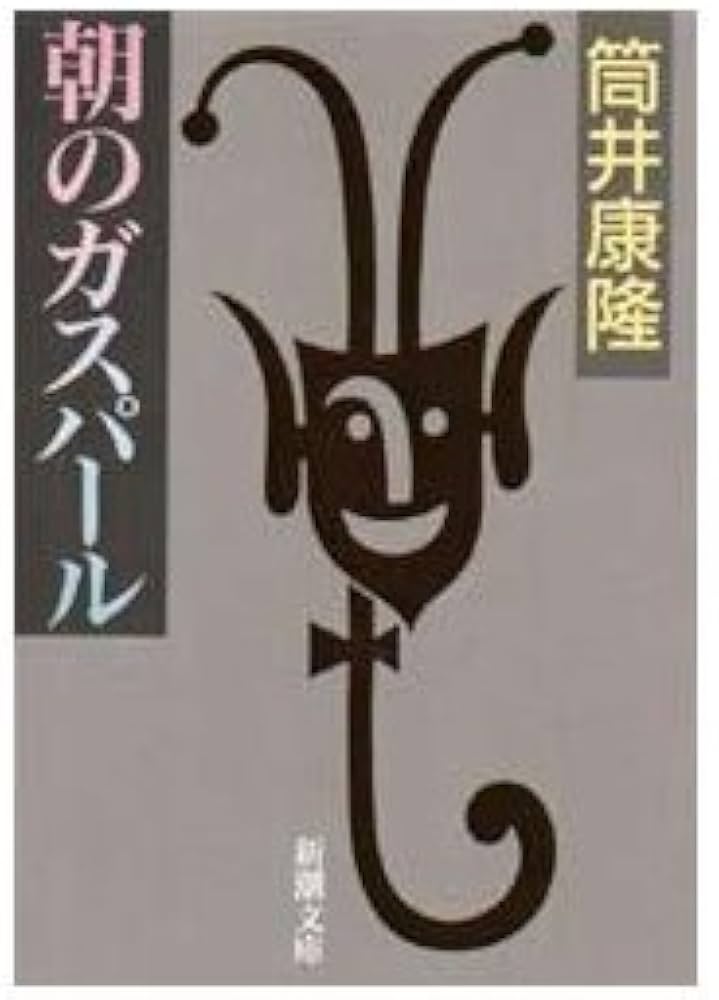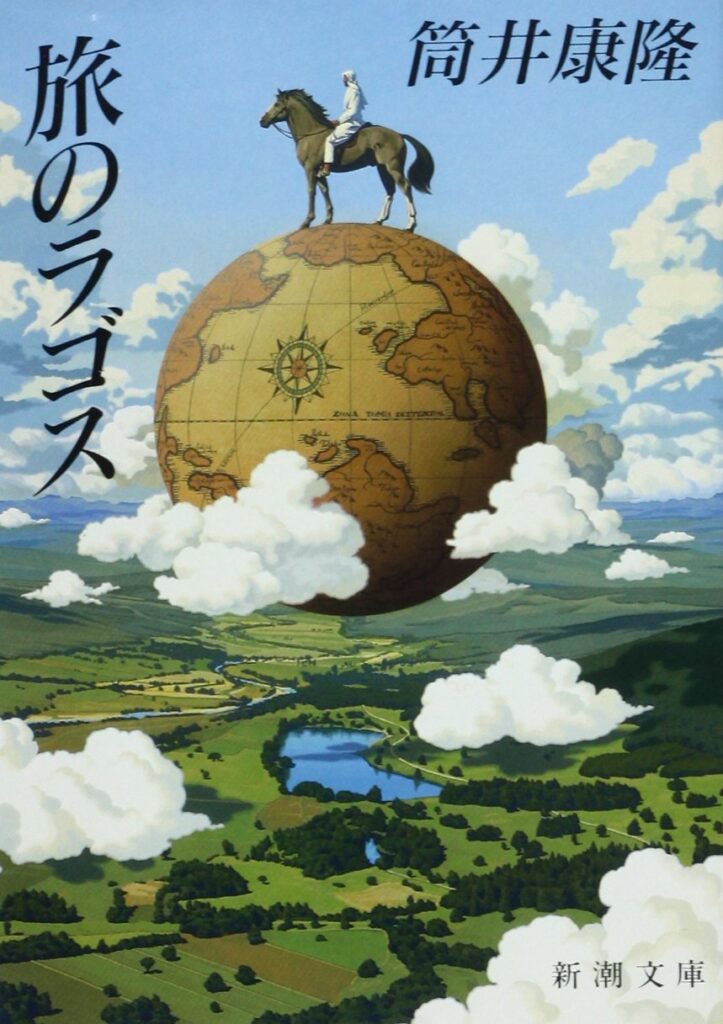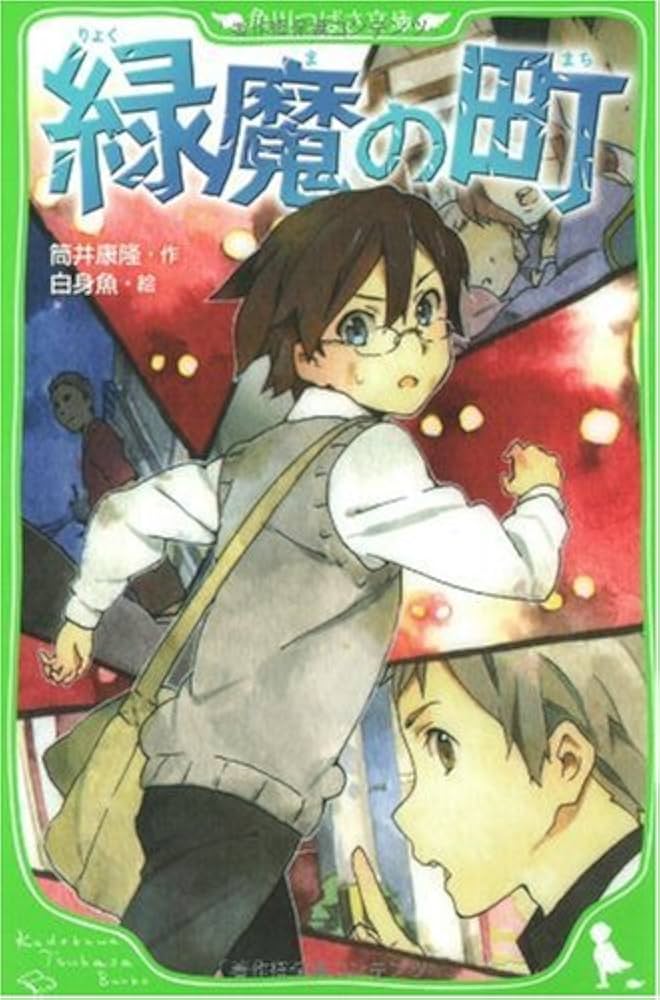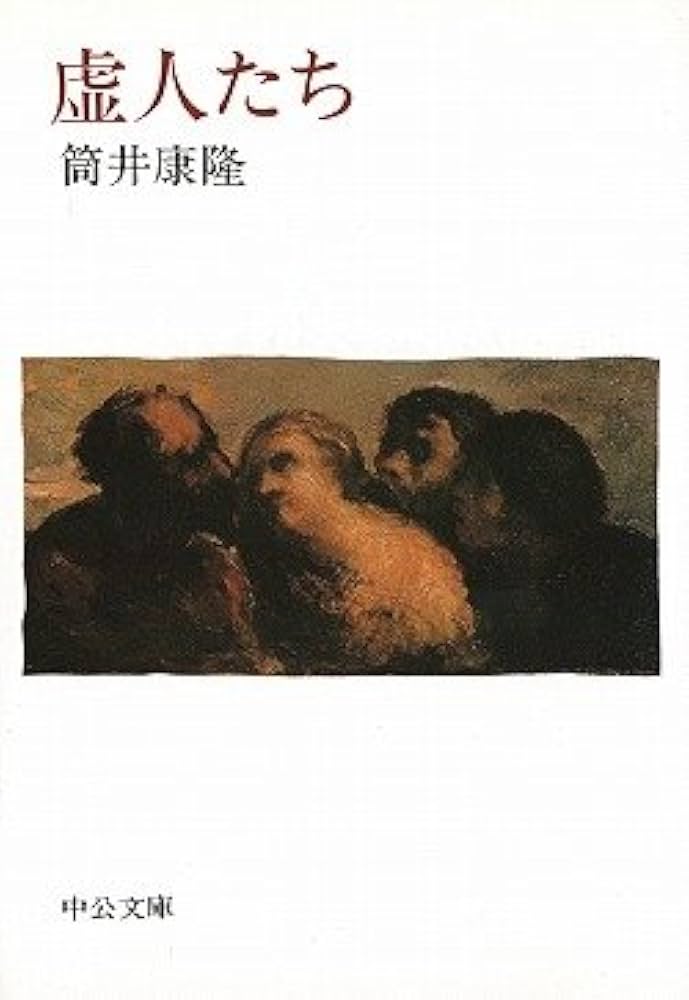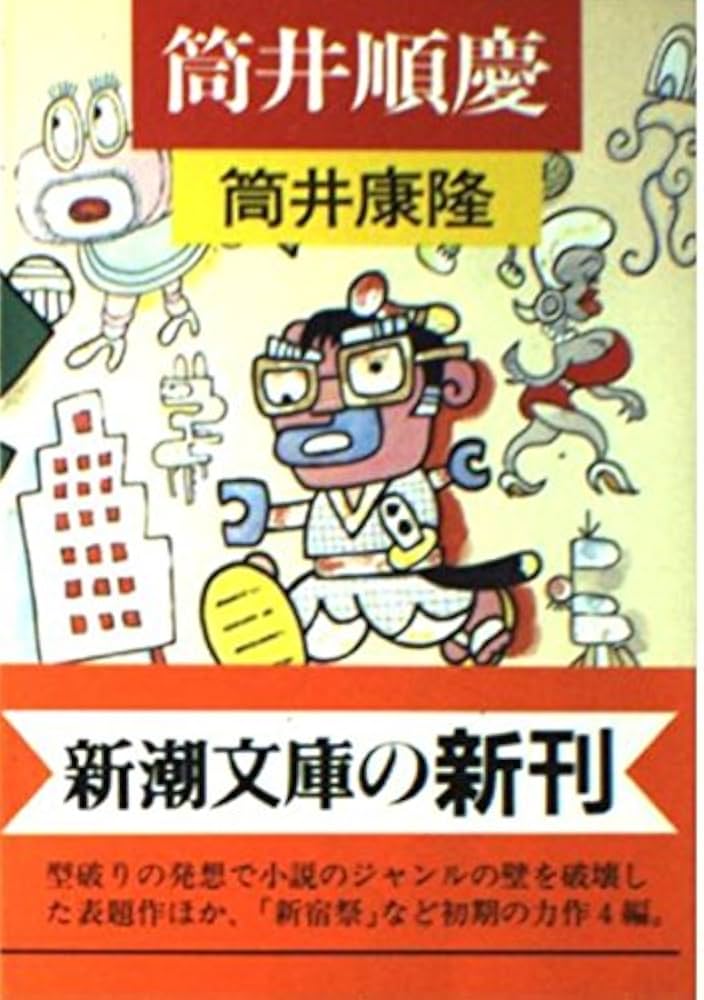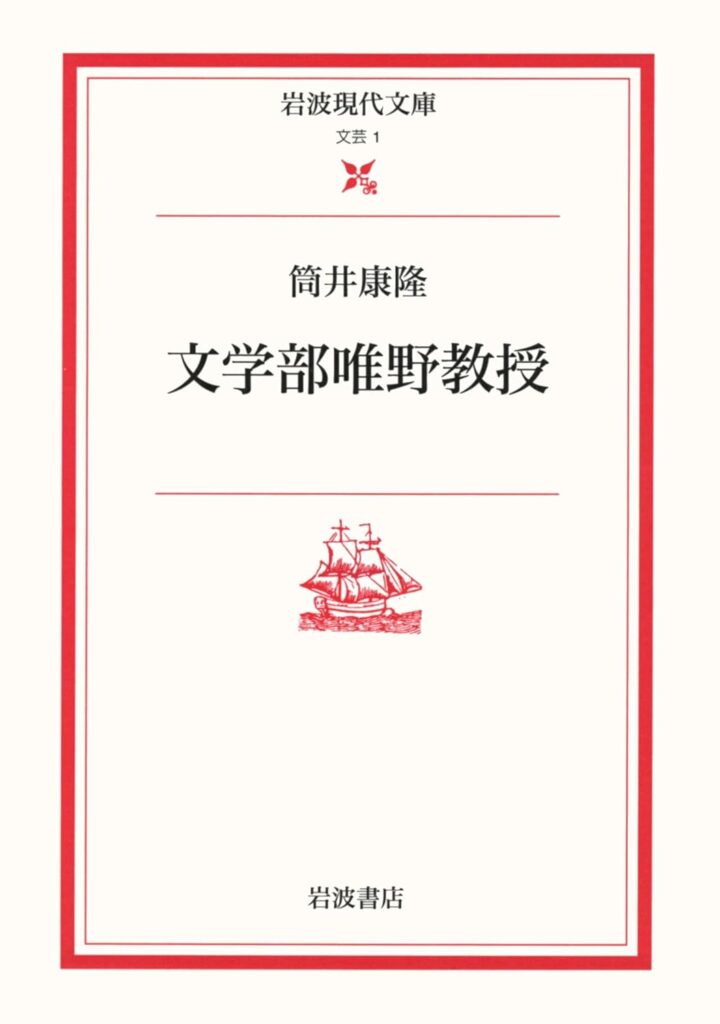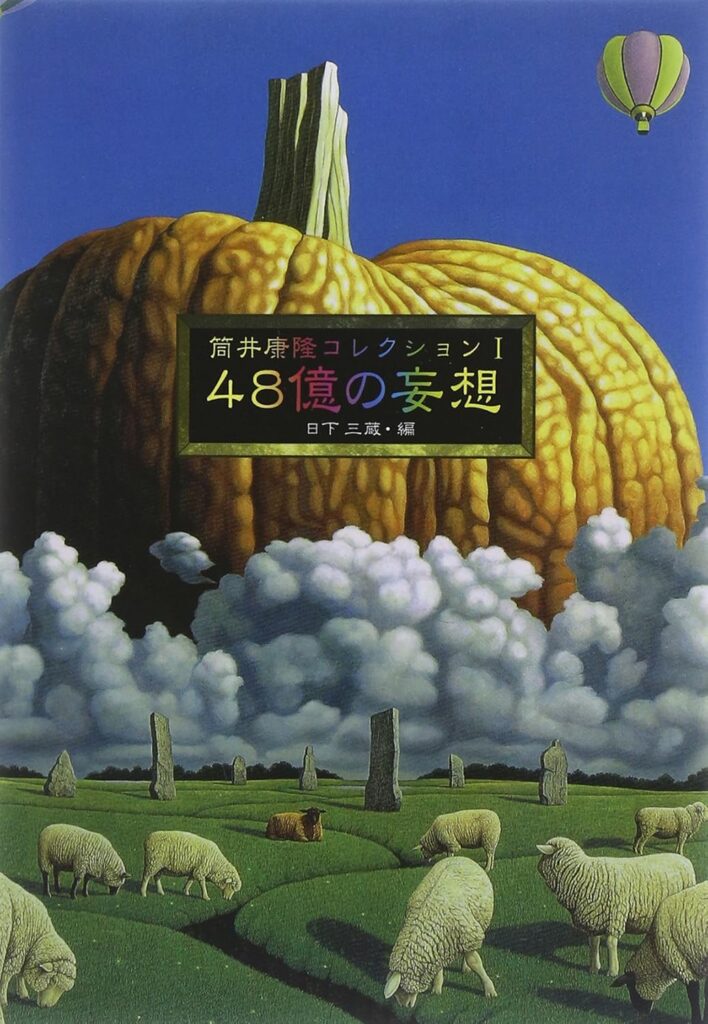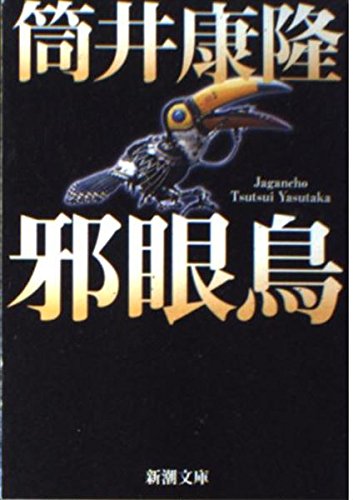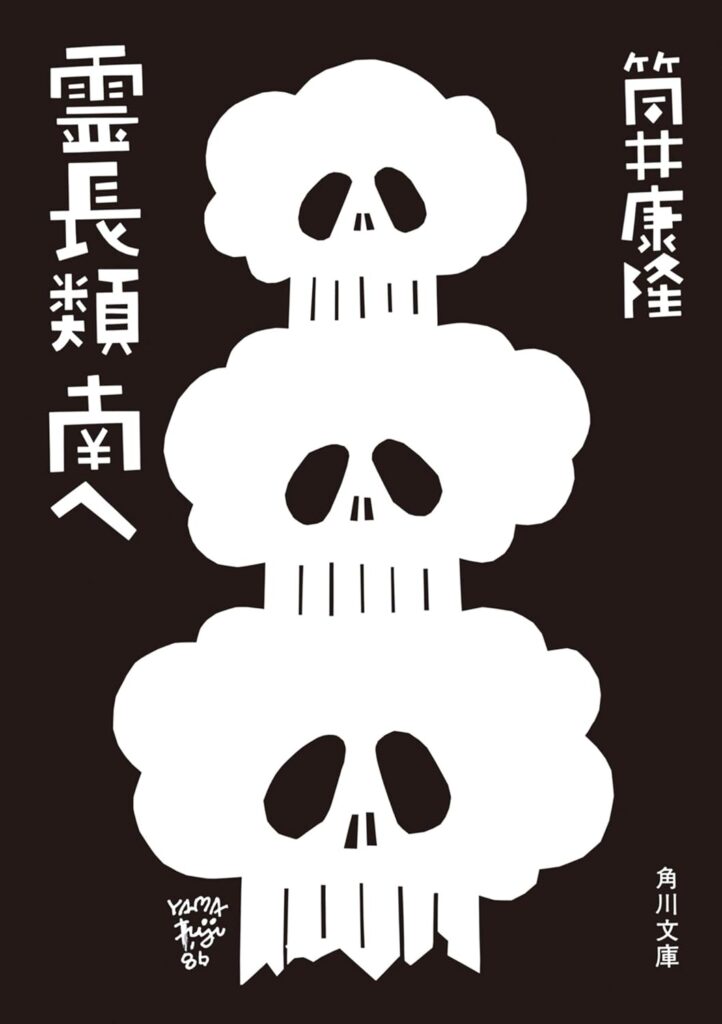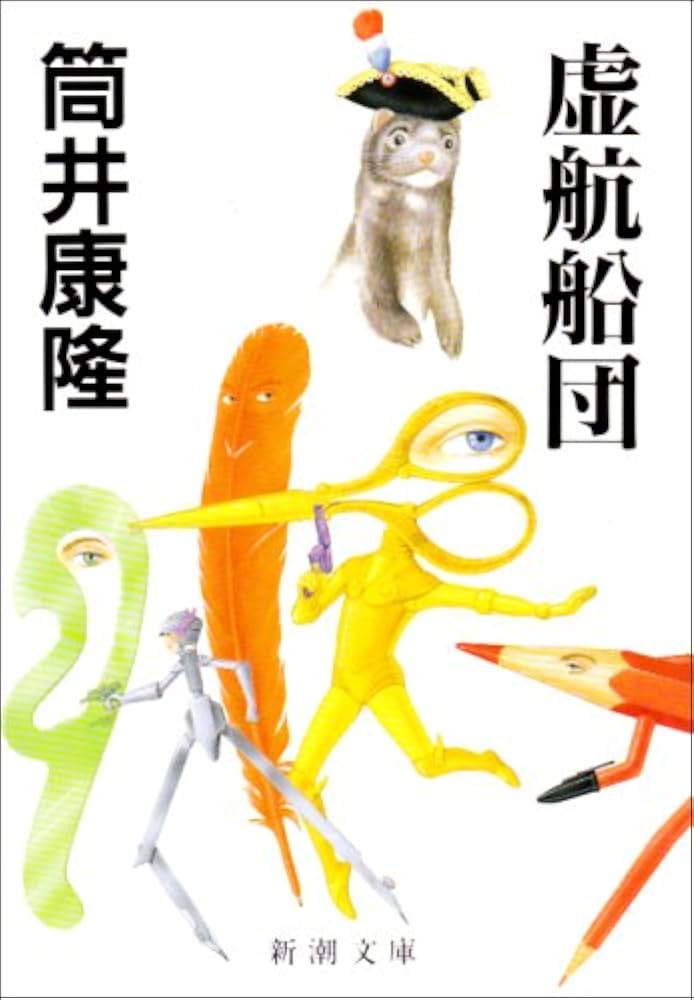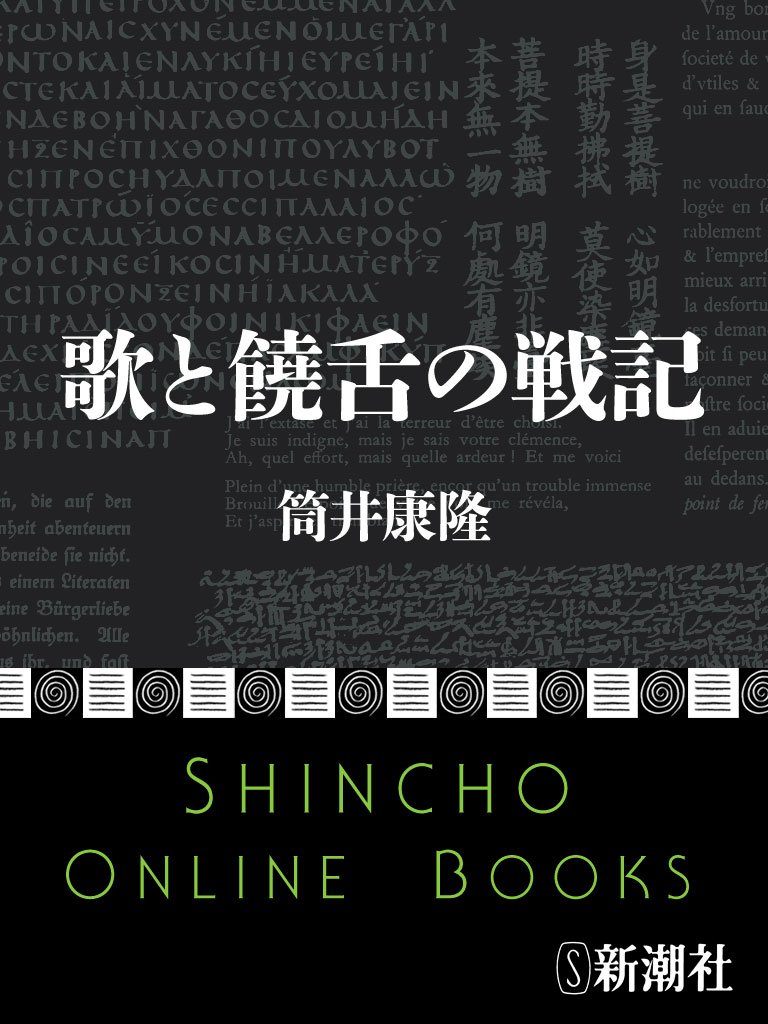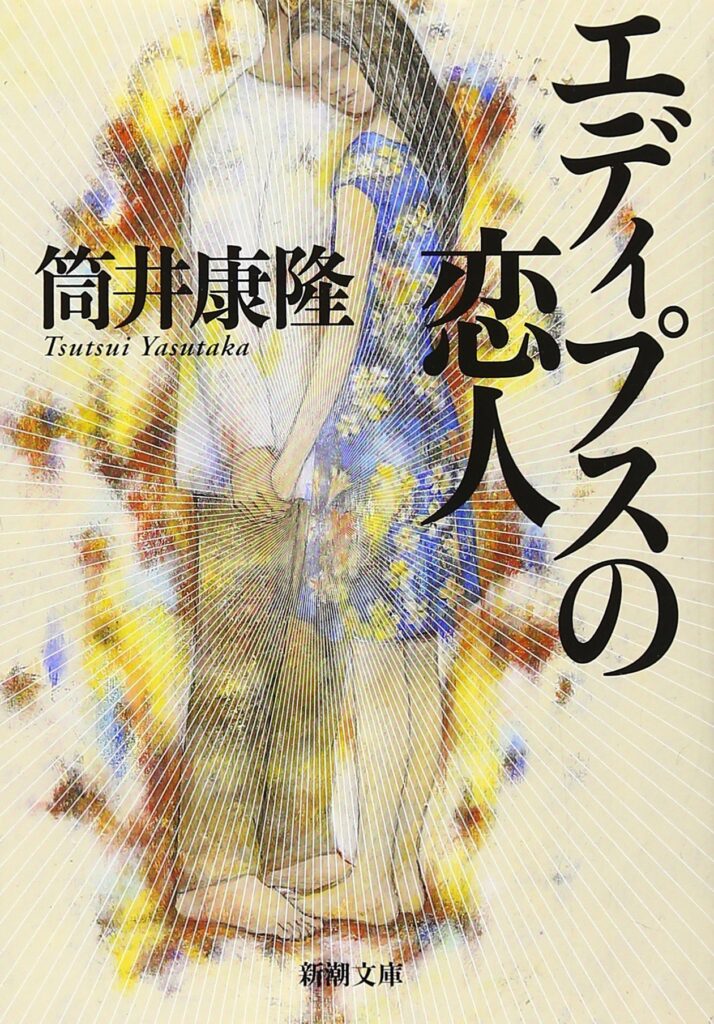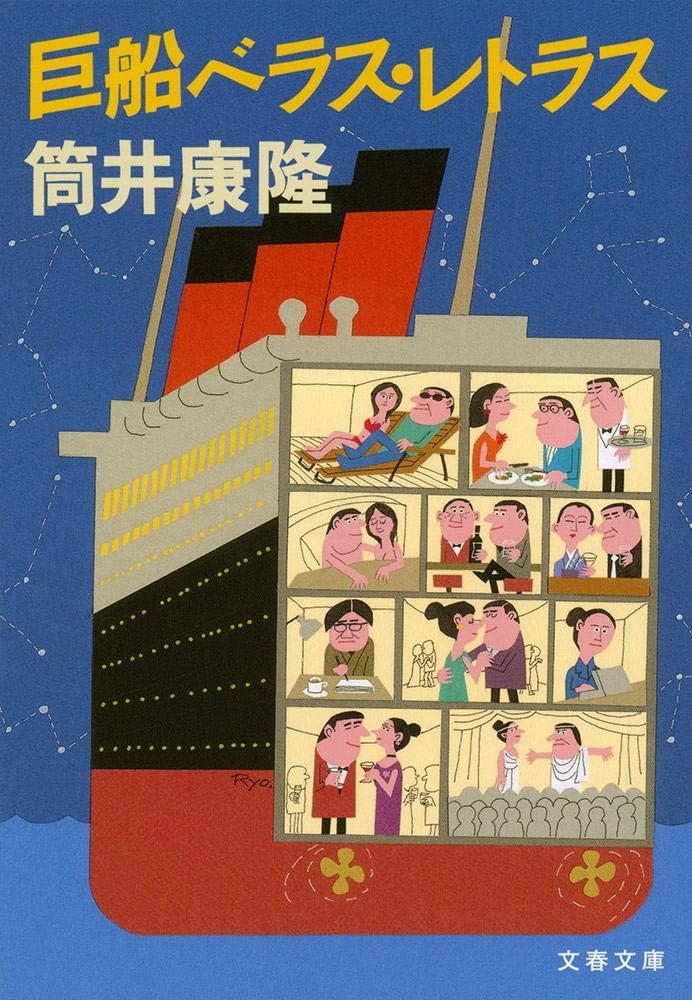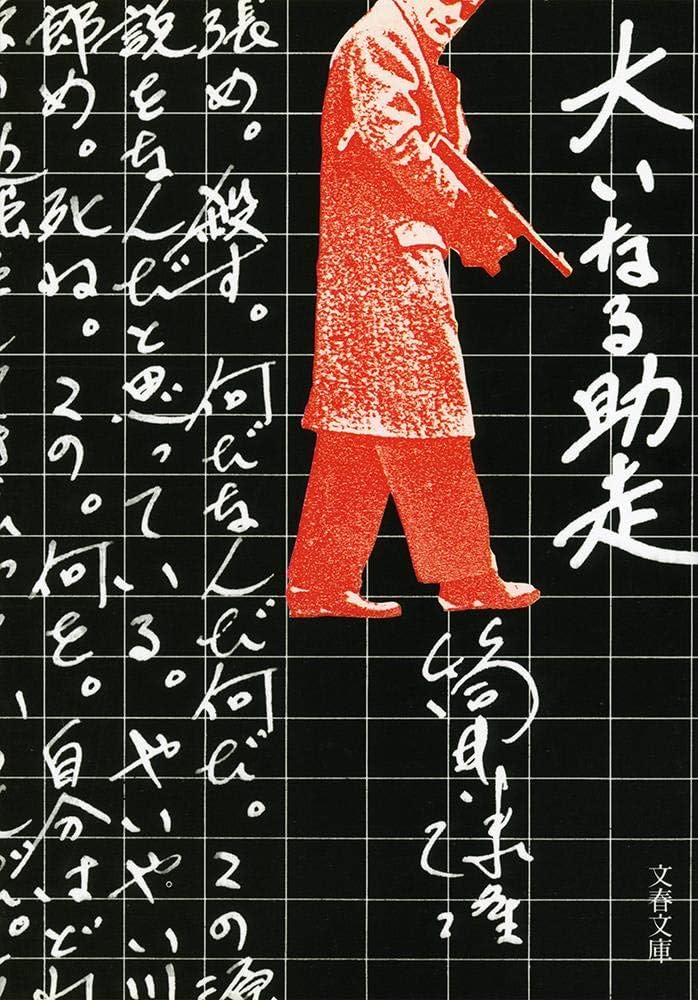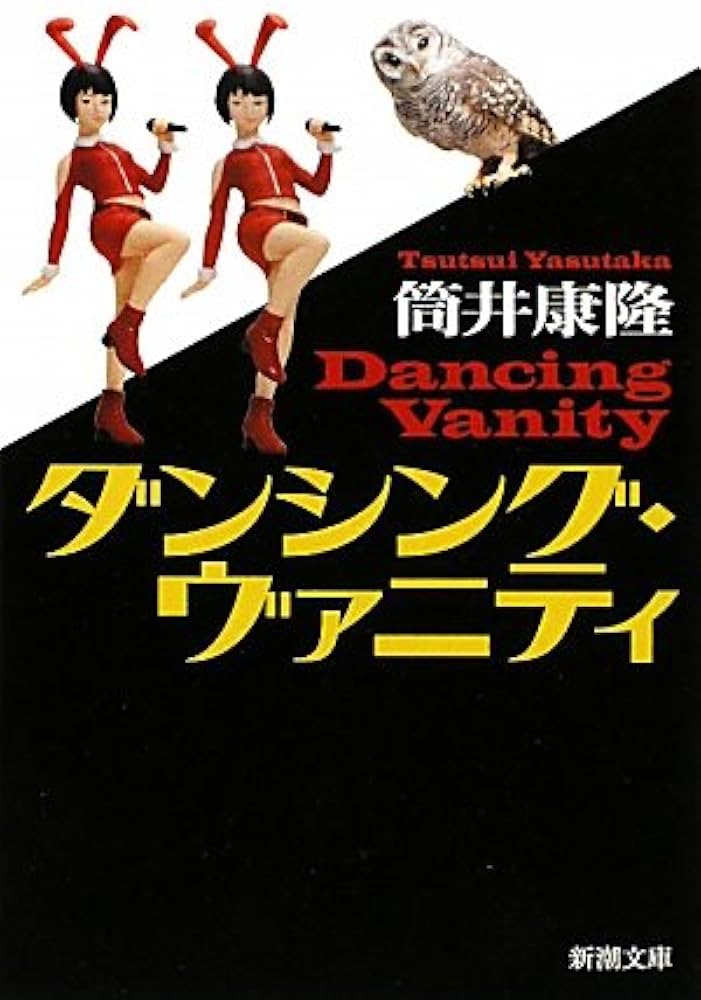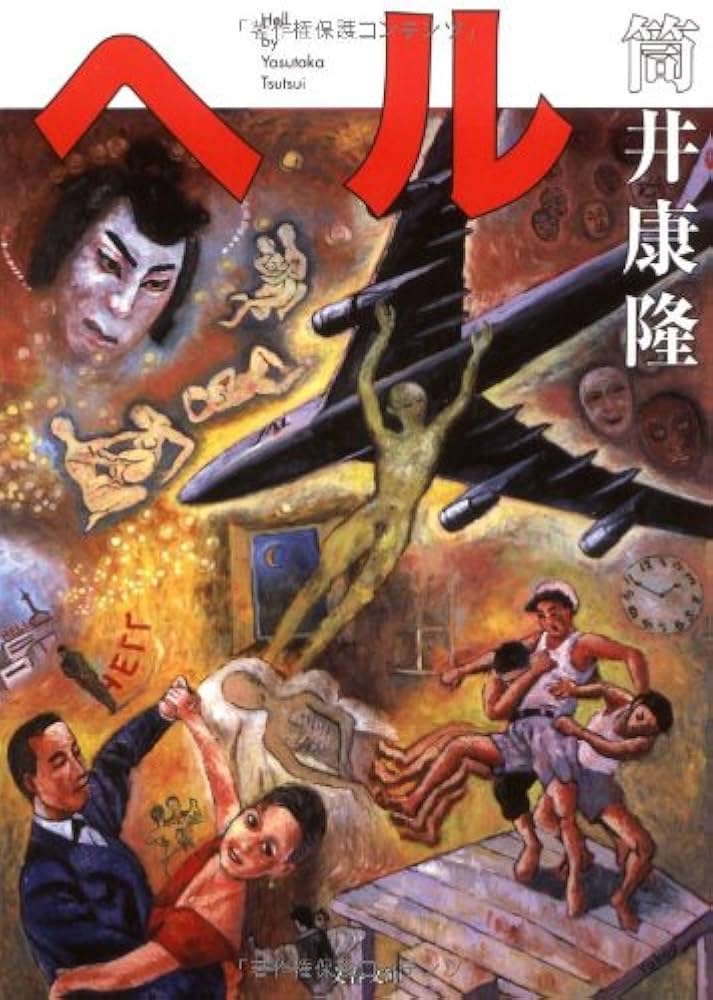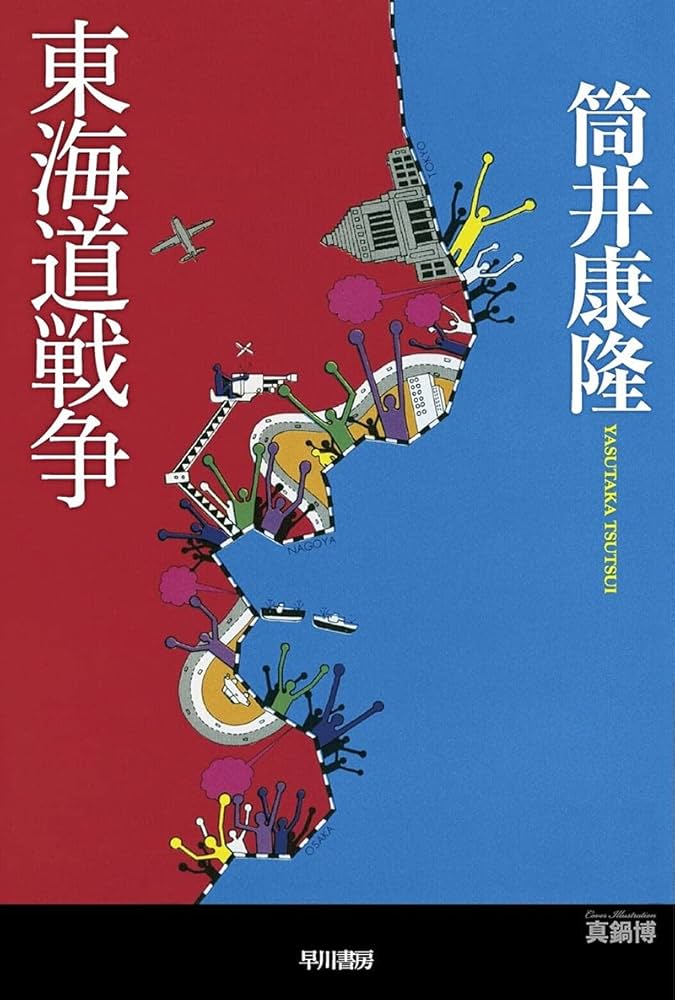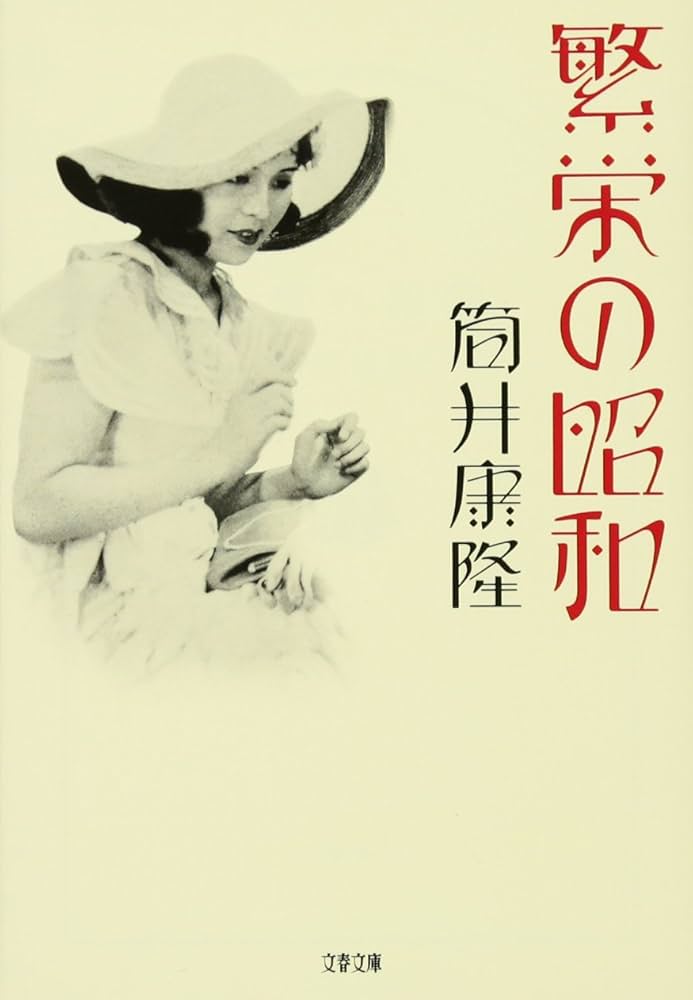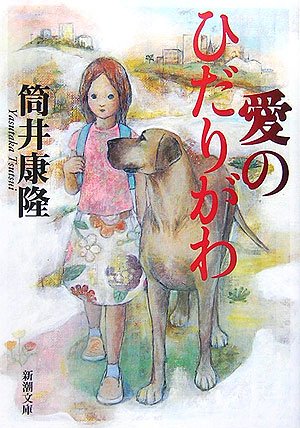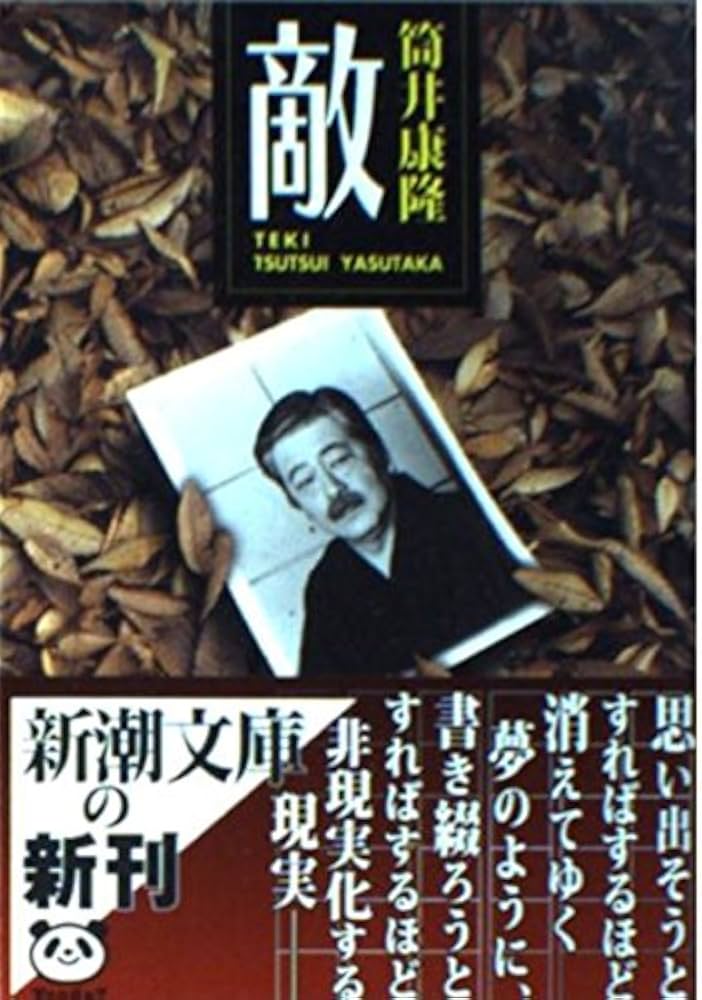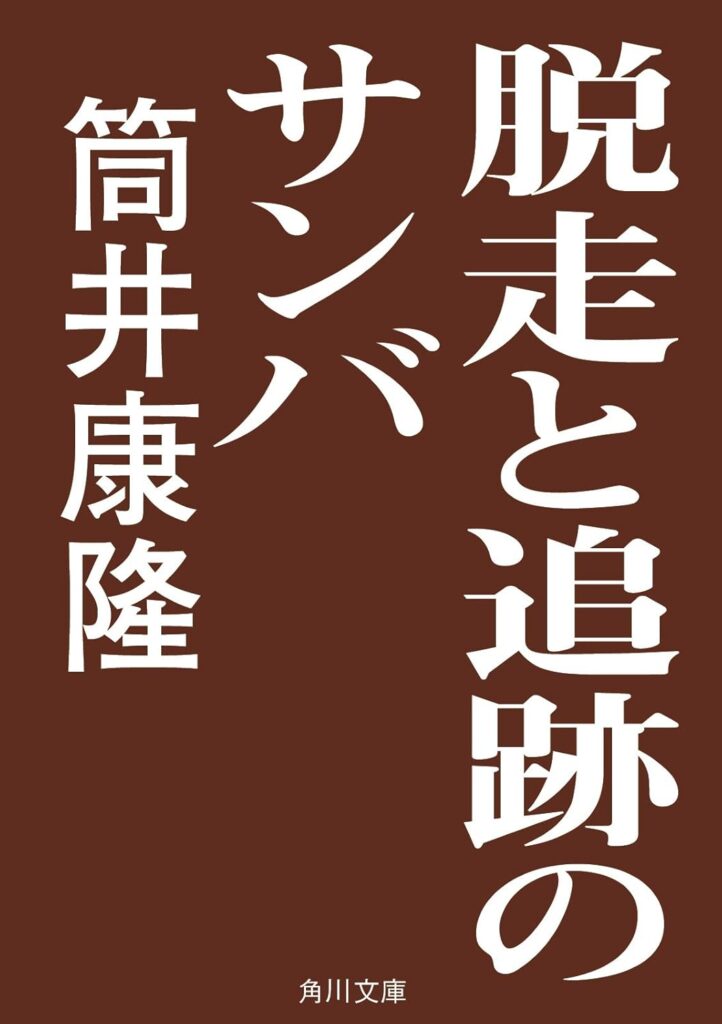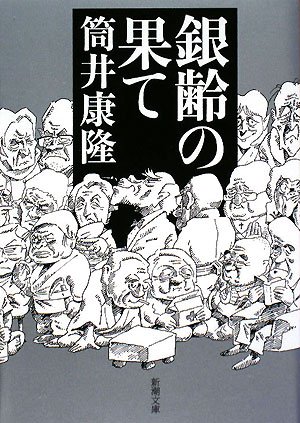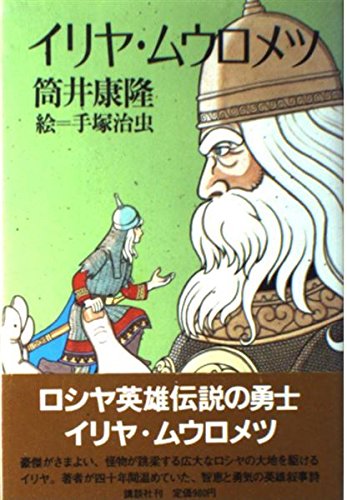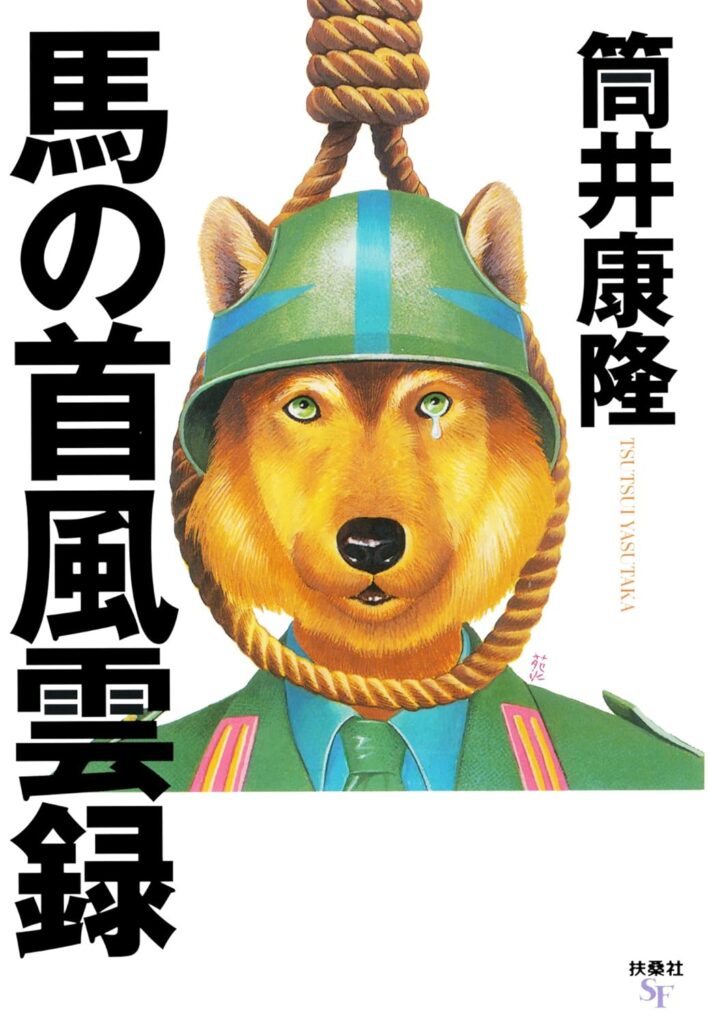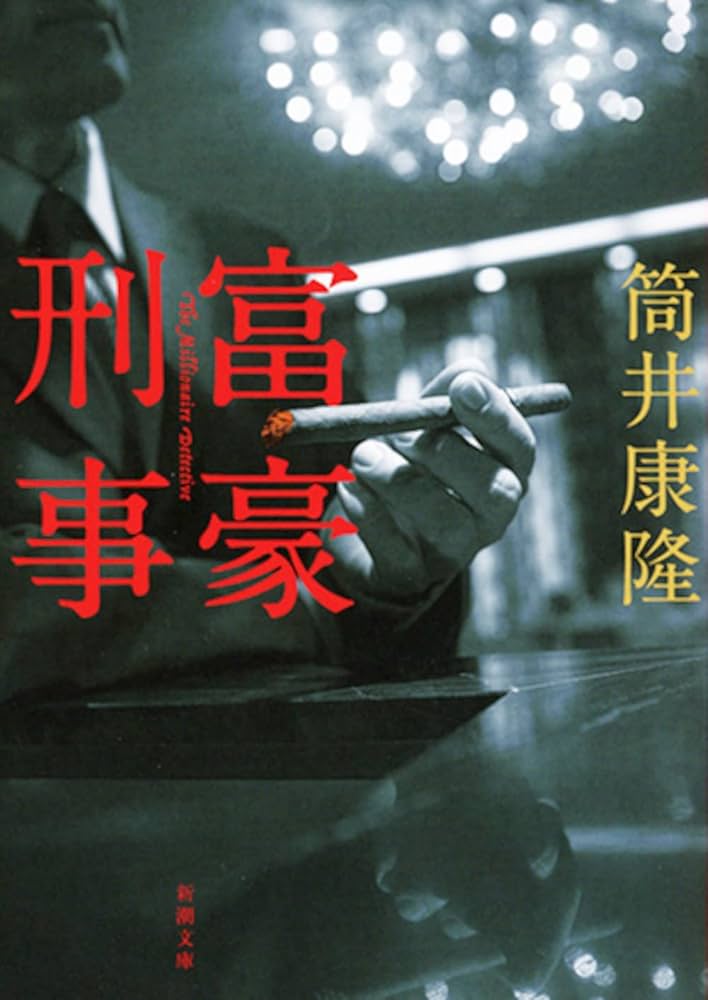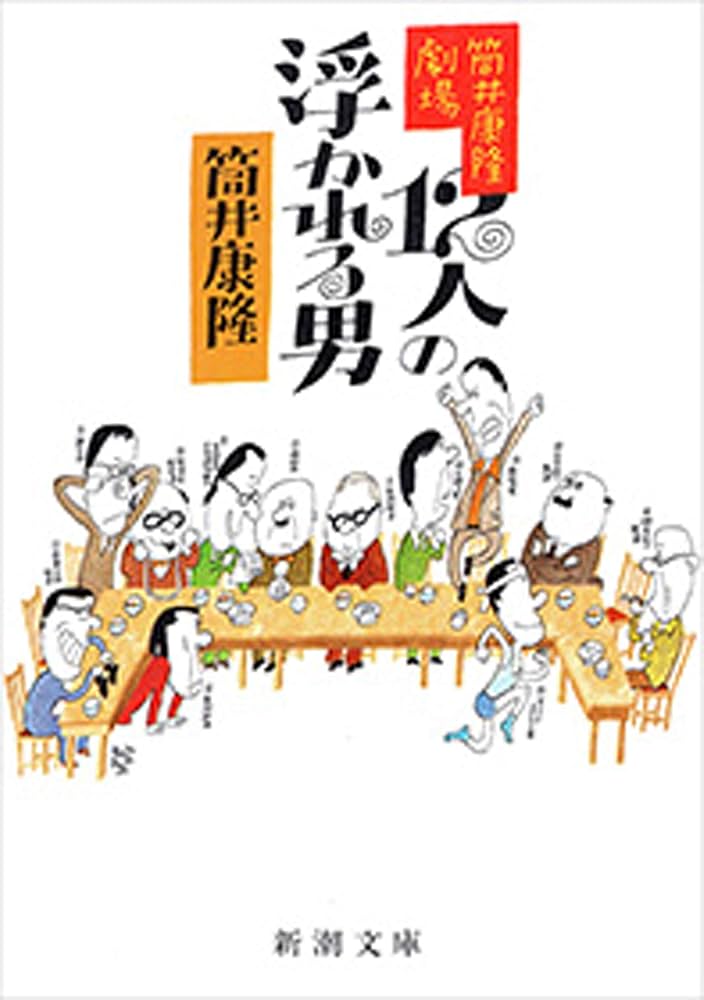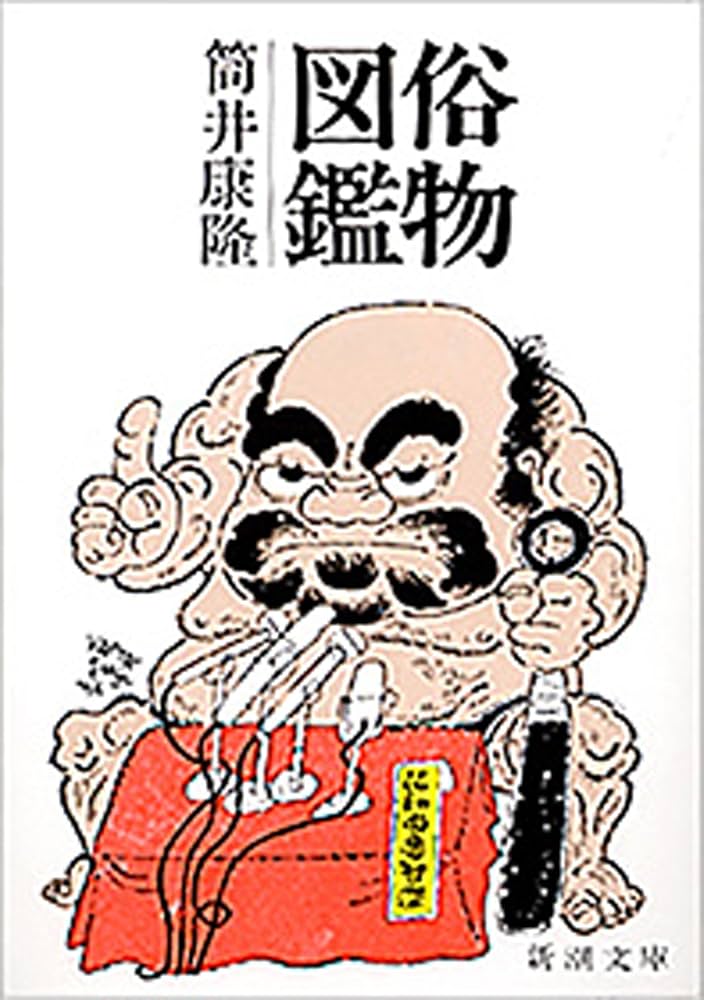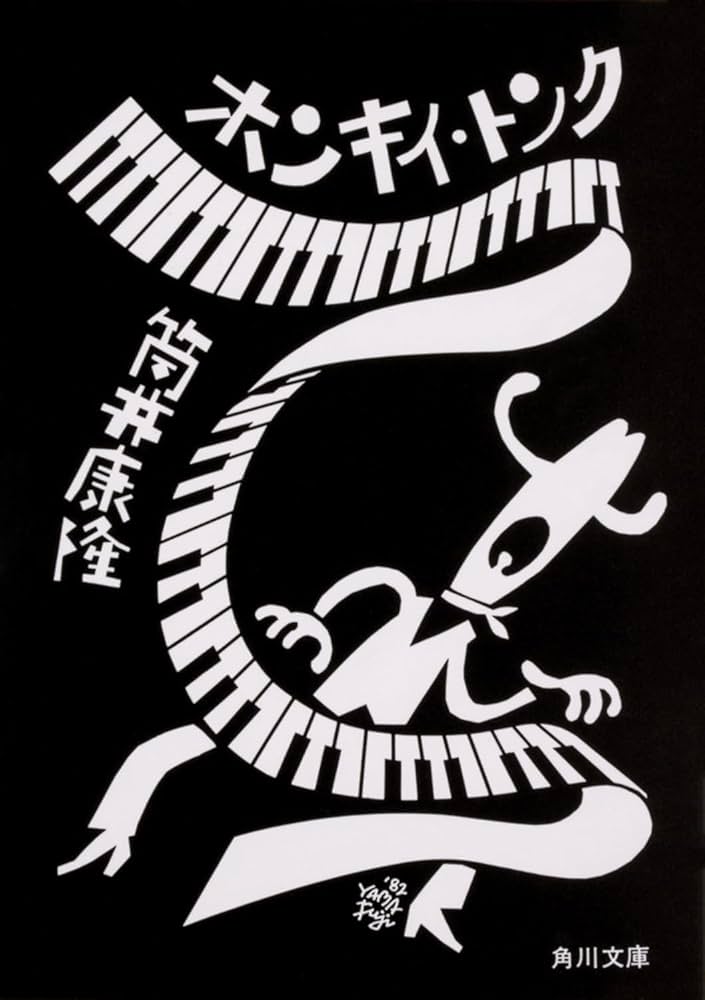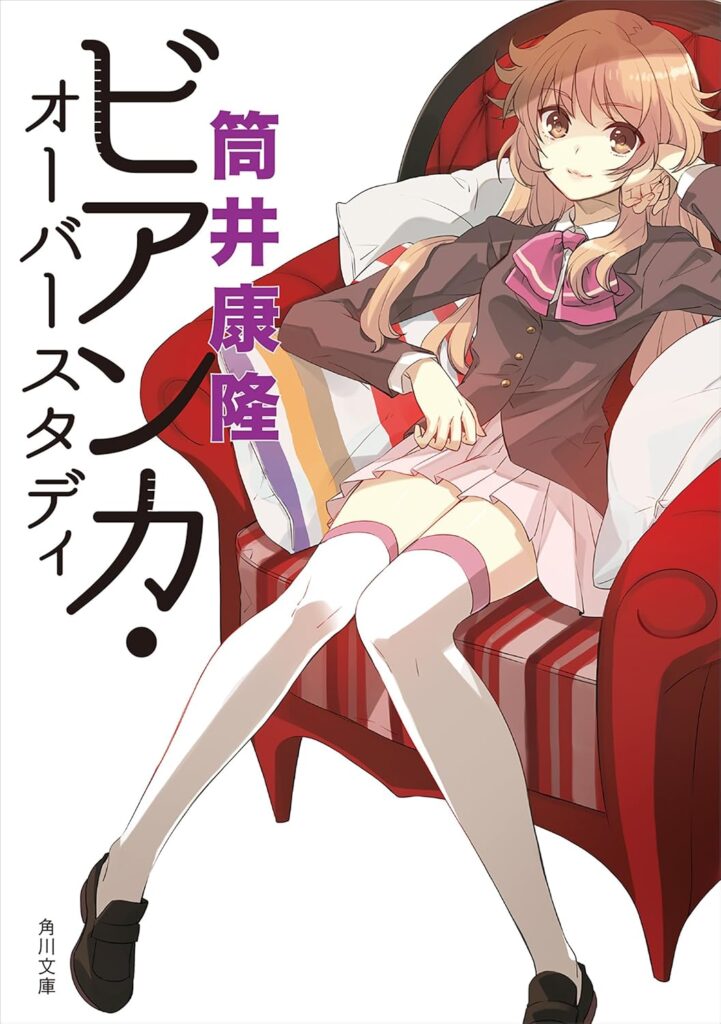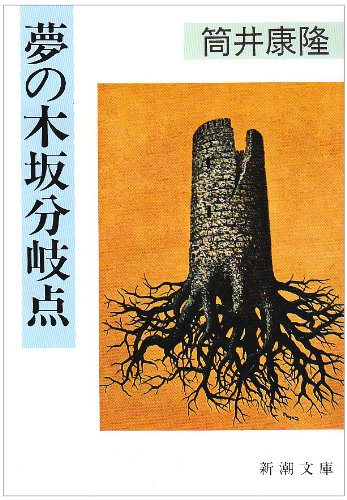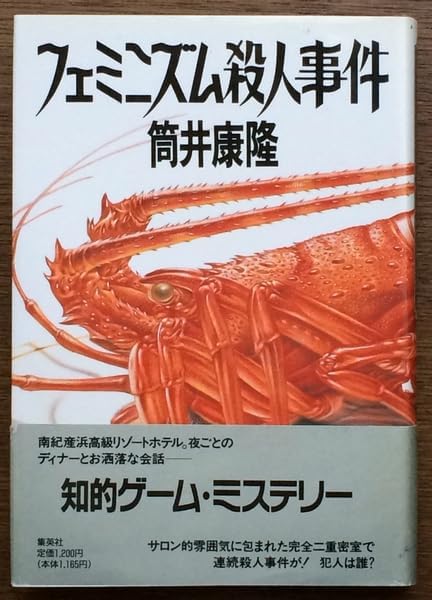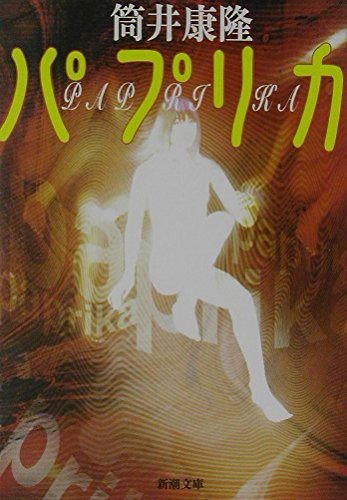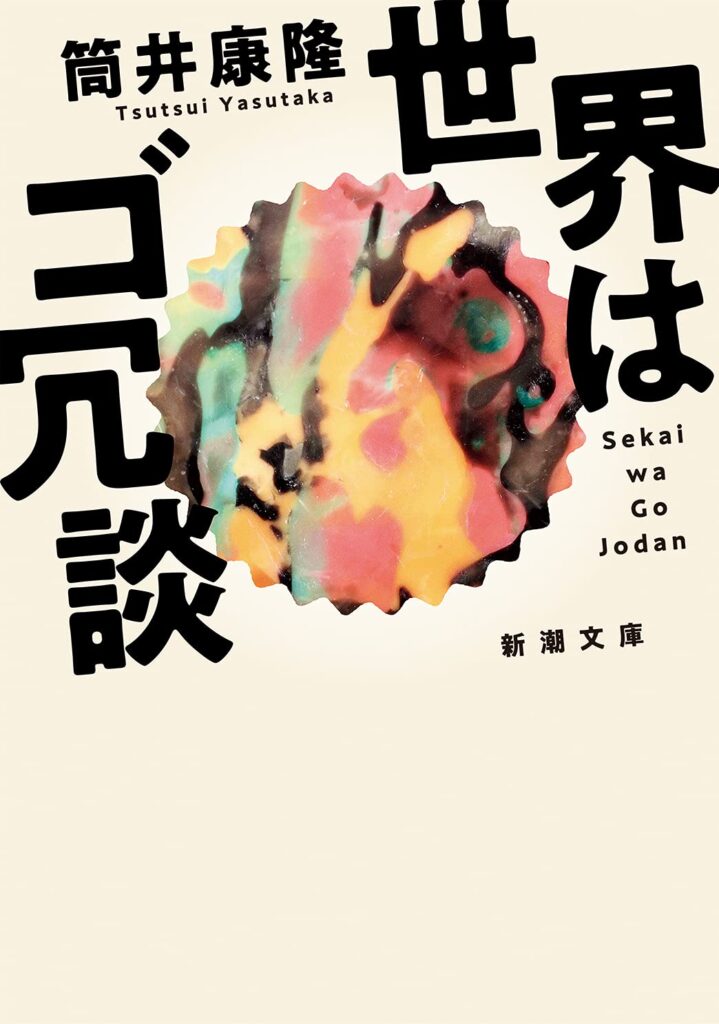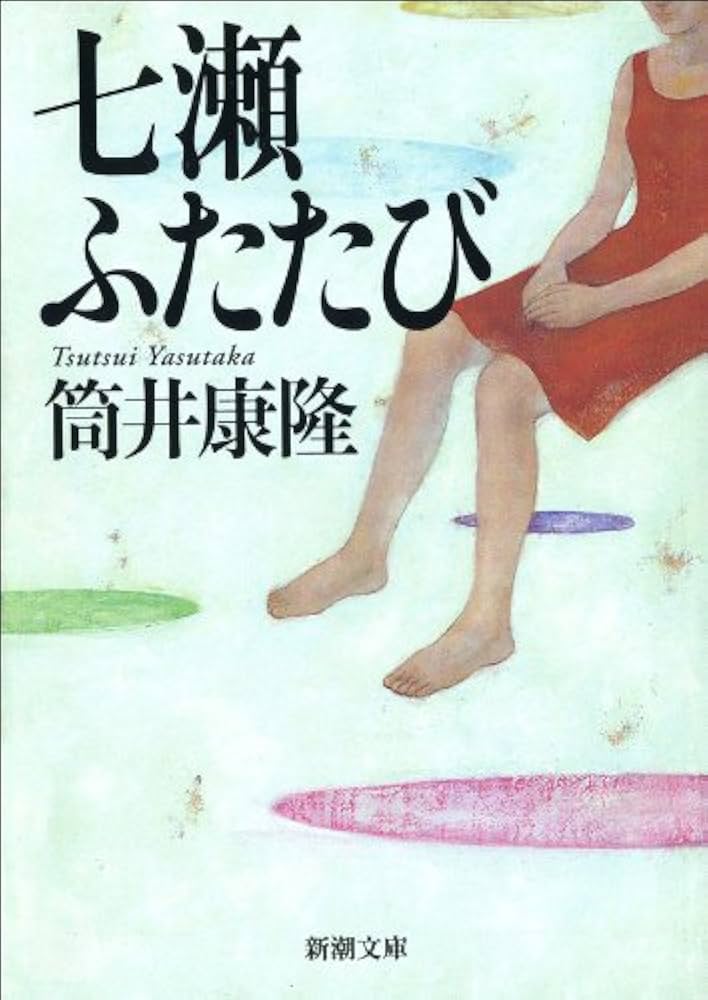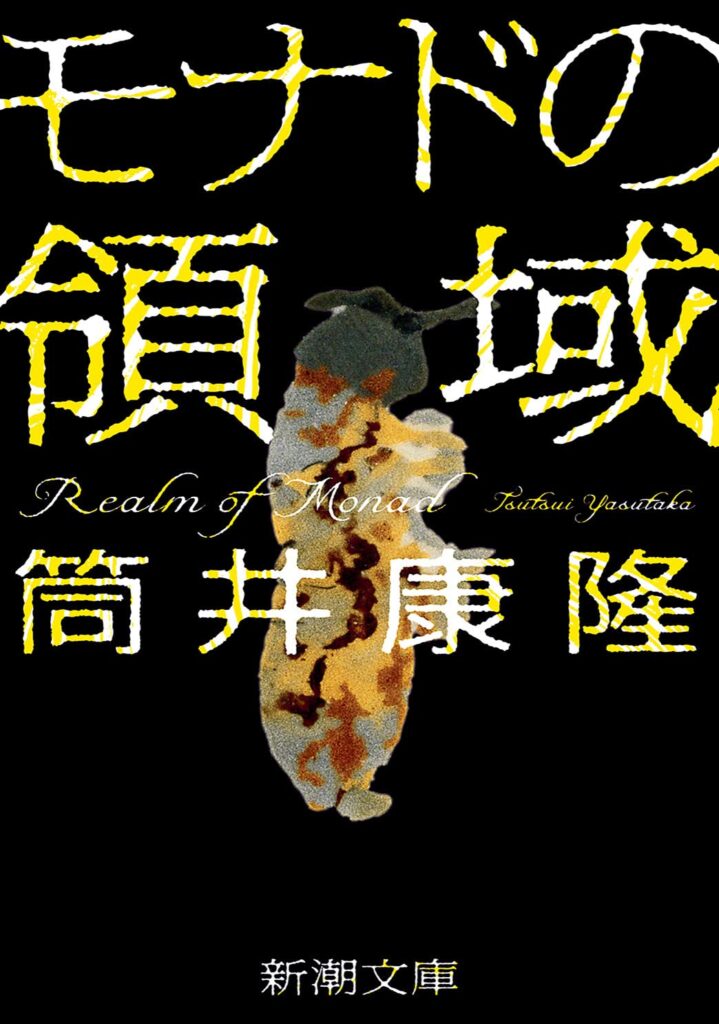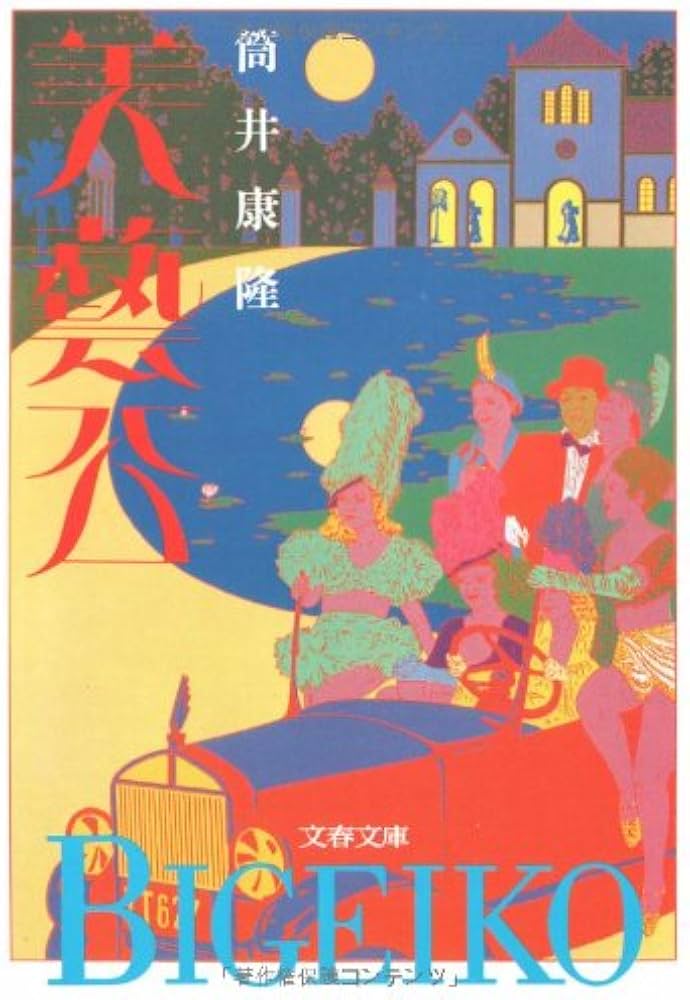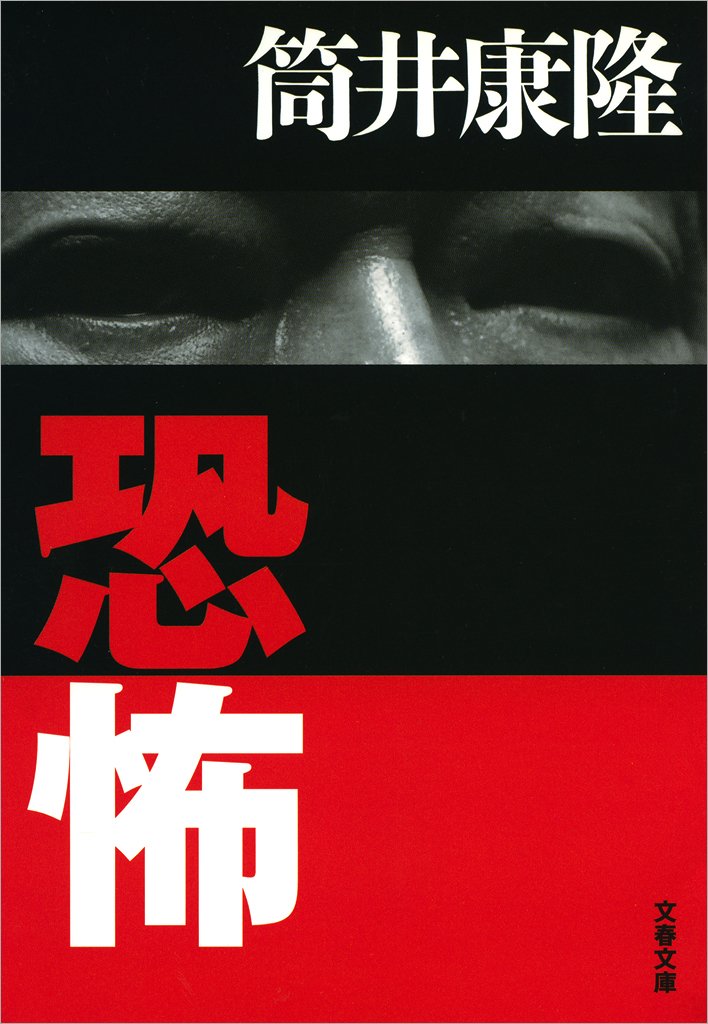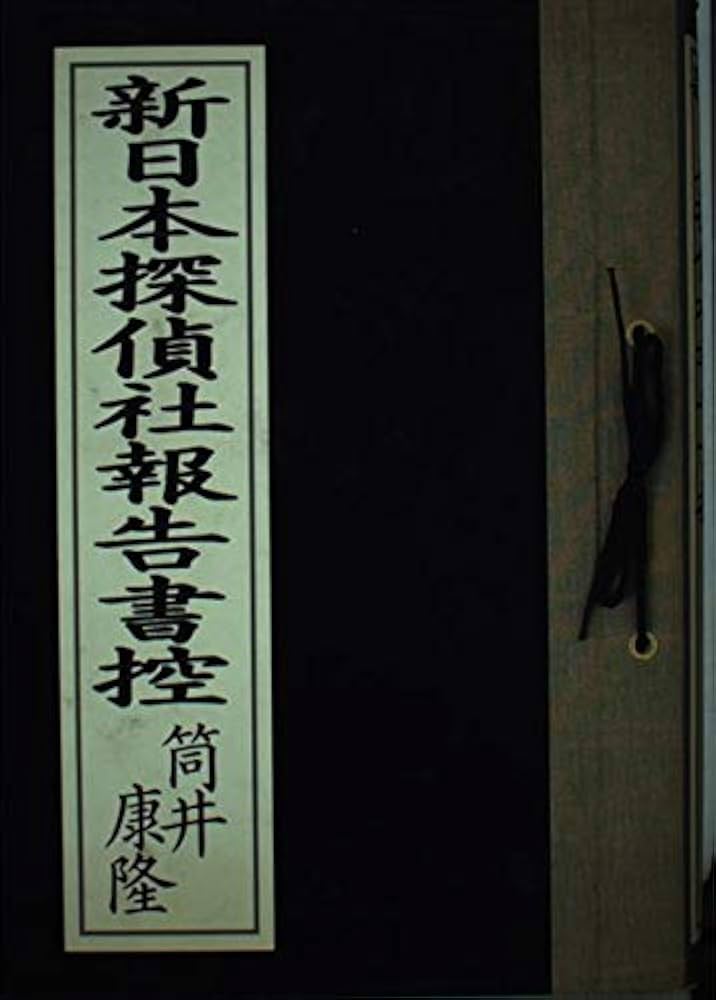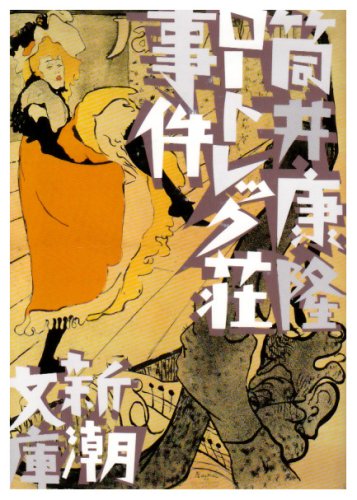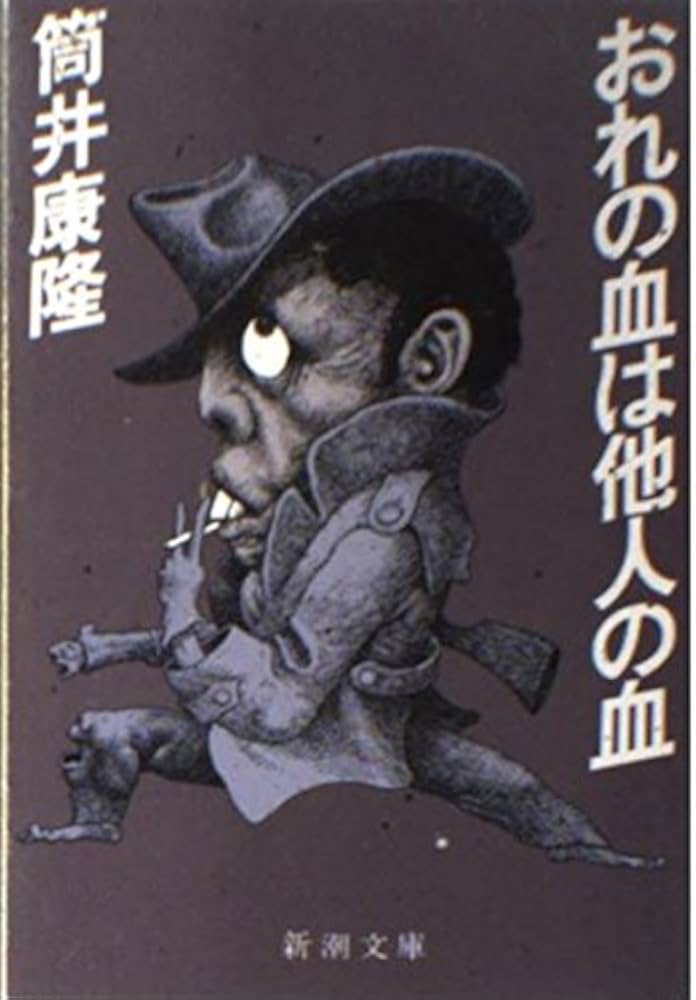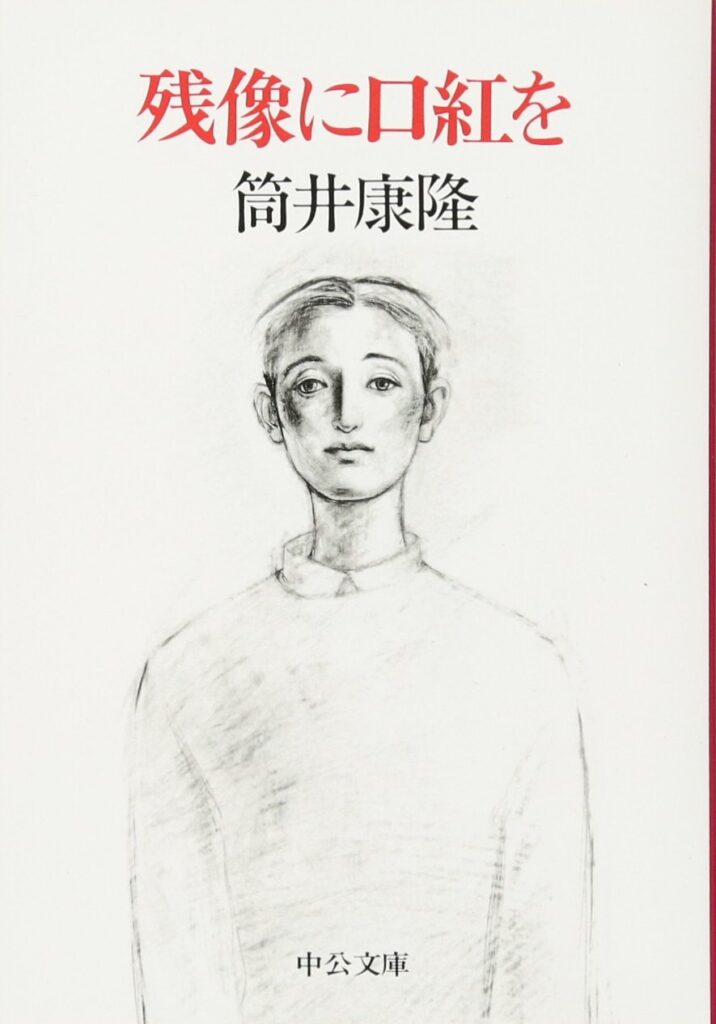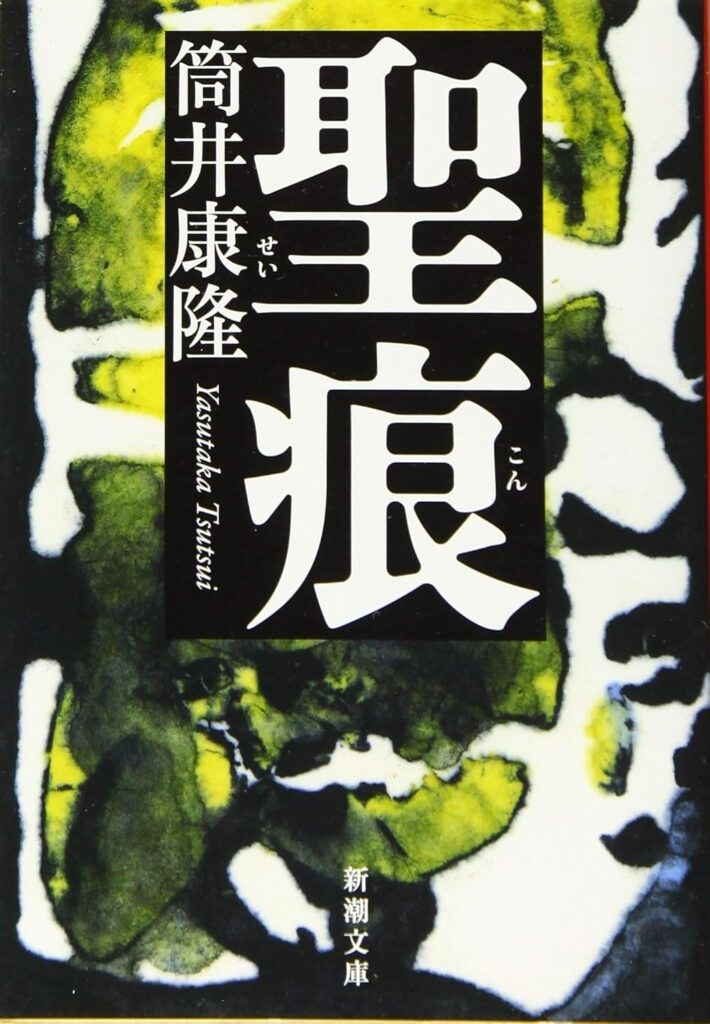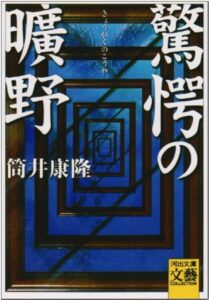 小説「驚愕の曠野」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「驚愕の曠野」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、読んだ者の心に深く、そして不吉な爪痕を残すことで知られています。筒井康隆氏の作品群の中でも、特にその構造的な恐ろしさで際立っており、一度足を踏み入れたら二度と元の世界観には戻れないかのような感覚に襲われるでしょう。単に怖い、グロテスクという言葉だけでは到底表現しきれない、悪夢そのものを体験させる仕掛けが施されているのです。
本記事では、まず物語の導入部分と、その不穏な世界観がどのようなものかをご紹介します。ここではまだ、物語の核心に触れることは避けますので、未読の方もご安心ください。しかし、その後のセクションでは、この物語がなぜこれほどまでに恐ろしいのか、その構造の秘密に深く踏み込んでいきます。
この記事を読み進めることは、あなた自身が物語の迷宮に足を踏み入れることに他なりません。物語の登場人物たちが体験する果てしない絶望と恐怖の連鎖、そして読む者と読まれる者の境界が崩壊していく様を、ネタバレを交えてじっくりと解き明かしていきます。この悪夢の構造を、どうぞ最後までお確かめください。
小説「驚愕の曠野」のあらすじ
物語は、どこか隔絶された場所で、「お姉さん」が子供たちに一冊の古めかしい本を読み聞かせている、という牧歌的とも思える光景から始まります。しかし、その朗読は唐突に「第三三二巻」から始まり、物語が既に長大な過程を経てきたことを示唆します。読まれる物語は「唆界(そかい)」と呼ばれる、瘴気が立ち込め、巨大な害虫や怪物が跋扈する荒涼とした曠野が舞台です。
そこでは、影二や洞六といった男たちが、絶えず命の危険に晒されながら、終わりの見えない旅を続けています。彼らは怪物と戦い、時には仲間同士で殺し合うことさえあります。しかし、この世界の最も異様な点は、死が終わりではないということです。惨たらしい死を遂げたはずの登場人物は、何度も蘇り、再び同じような、あるいはさらに過酷な状況に投げ込まれるのです。
読み聞かせが進むうち、聞き手である子供たちの一人、「ぼく」は気づき始めます。自分たちのいるこの世界と、物語の中の「唆界」が、不気味なほど似ていることに。そして、物語の語り手である「お姉さん」の身に、ある決定的な出来事が起こります。
この出来事をきっかけに、物語を読む者と読まれる物語、その二つの世界の境界線は急速に曖昧になっていきます。安全な場所から物語を眺めているはずだった子供たちは、徐々にその恐ろしい物語の中心へと引きずり込まれていくのでした。
小説「驚愕の曠野」の長文感想(ネタバレあり)
この物語に触れた最初の印象は、その圧倒的なまでの悪意と絶望感でした。読み進めるほどに、物語の表面的な残酷さの奥に、読者の精神そのものを浸食してくるような、計算され尽くした構造的な恐怖が潜んでいることに気づかされます。これは単なるホラーの枠には収まらない、一種の文学的トラウマを植え付けるための装置のようです。
物語は、読者を安心させるための足場を最初から用意してくれません。読み聞かせという形式を取りながら、その物語は膨大な巻数を持つ書物の中途から語り始められます。始まりも終わりも提示されないまま、私たちは荒涼とした「唆界」のただ中に放り込まれるのです。この感覚こそ、作品全体を貫く根源的な不安の始まりでした。
枠物語となる「読み聞かせ」の場面は、一見すると安全な領域のように思えます。しかし、語り手である「お姉さん」が朗読の途中で突然死んでしまうことで、この安全神話はあっけなく崩壊します。死という、内部物語のテーマが、語りの世界そのものに侵入してきた瞬間です。この出来事は、二つの世界が地続きであることを示す、最初の、そして最も衝撃的な亀裂だったと言えるでしょう。
「お姉さん」の死後、恐怖に震えながらも朗読を引き継ぐ少年「ぼく」の存在が、この物語の恐ろしさをさらに加速させます。彼は、物語の世界と自分たちの現実との間に存在する不気味な共通点に気づき、「これ本当は、地獄なんじゃないか」「ぼくたちのいるここだってやっぱり同じようなものなんだよね」と口にします。この疑念は、やがて確信へと変わり、読者をも巻き込んでいくのです。
内部物語の舞台である「唆界」の描写は、徹底して救いがありません。瘴気が立ち込め、得体の知れない怪物がうごめく不毛の大地。そこで描かれるのは、生存のための絶え間ない闘争です。登場人物たちは「塩漬け肉」という最低限の食糧を頼りに、ただ生き延びるためだけに、殺し、殺されます。この暴力の連鎖は、読む者の神経をじわじわとすり減らしていきます。
そして、この物語の核心的なルール、「死んでも再生する」という現象が明らかになります。しかし、それは希望ではありません。再生するたびに、彼らは同じ、あるいはそれ以上に過酷な運命を繰り返すのです。記憶はしばしば断片的で、自分がなぜここにいるのか、何をすべきなのかも定かでないまま、苦しみの螺旋をひたすら下り続けます。これは、輪廻転生の概念を、最も残酷な形で歪めた地獄絵図に他なりません。
物語が進むと、この地獄が単層ではないことが判明します。唆界で死んだ者が行き着く「爛界」、さらにその下には「批界」という領域が存在し、地獄の階層がどこまで続いているのかさえ分かりません。自分たちがいる場所が、より上位の「訣界」にとっての魔界であるという事実が明かされるに至っては、登場人物たちの絶望は底なしとなります。逃げ場などどこにもなく、死さえも救いにはならない世界。この無限に続く階層構造の提示は、読者の心をへし折るのに十分な威力を持っています。
この絶望的な世界観は、仏教的な宇宙観を悪意をもってパロディ化したものと言えるでしょう。悟りや解脱といった救済の道は完全に閉ざされ、転生はより深い苦しみへの下降しか意味しません。「十八神将」といった仏教由来の言葉が、ここでは悪魔的な階層の名称として使われ、本来の意味を転倒させています。聖なる概念が穢され、絶望を補強するために利用される様は、この物語の持つ悪意の深さを物語っています。
物語の構造は、登場人物の一人である堯が、廃墟で散らばった紙片を発見する場面で、決定的な変容を遂げます。その紙片こそ、彼らが囚われている物語そのものの断片だったのです。堯がそれを読み始めると、小説の体裁もまた、断片的で途切れ途切れの記述に変わります。世界の崩壊と、物語の結束性の崩壊とが、完全にシンクロする瞬間です。
このメタフィクション的な仕掛けこそ、『驚愕の曠野』という作品の心臓部です。物語が、物語の中で読まれ、その行為によって変容し、さらに登場人物の運命を規定していく。ある断片には、この物語には特定の作者がおらず、書いた者も登場人物となって死ぬ可能性があり、それは読者にさえ当てはまり得ると記されています。この一節は、安全な場所から物語を傍観しているつもりの読者の足元を、根こそぎ奪い去る宣告なのです。
物語は単なるテキストではなく、読んだ者を取り込んで自己を永続させる、悪意ある生命体のようなものとして描かれます。堯が断片を拾い集めて読む行為は、物語の終焉ではなく、むしろ物語が新たな形態へと進化し、生き延びるためのプロセスの一部でしかありませんでした。物語の「粉砕」は、登場人物たちが人間性を失い怪物へと変容していく様を、そのまま文章の形式で表現しているのです。
そして物語は、最も恐ろしい結論へと収束していきます。断片的な記述が続く中で、内部物語の登場人物たちと、枠物語の「お姉さん」や「子供たち」の境界線は、ついに完全に溶解します。数え切れないほどの死と再生、そしておぞましい変容の果てに、かつて曠野をさまよっていた者たちが、次なる物語の語り手である「お姉さん」や聞き手である「子供たち」そのものになる、という循環の構造が暗示されるのです。
これは、物語の読者が、いずれはその物語の登場人物になる運命にあることを示しています。読み聞かせのサイクルは、苦しみのサイクルそのものであり、一度聞き手として参加してしまった者は、次のサイクルでは演者として曠野へ送られる。この逃れられないループ構造こそ、この物語が「底なし沼」と評される所以でしょう。
最終ページは、一枚の紙の表裏に書かれた、ごく短い文章で構成されています。そこでは、これまでの記憶がすべて奪われたことが語られ、「五英」という、かつて怪物であったはずの存在が立ちあがります。そして、「お姉さん」となった人物が、子供たちに向かってこう呼びかけるのです。「みんな揃ったのね。ではおねえさんと一緒に、これからみんなで唆界へ行きましょう」と。
この最後の誘いは、あまりにも冷たく、そして絶望的です。これは集団での破滅への行進であり、悪夢の新たな始まりを告げる号令です。記憶を消し去るというプロセスが組み込まれていることで、この苦しみのサイクルは永遠に繰り返されることが保証されています。なぜなら、自分たちがこれから向かう場所の完全な恐怖を覚えていたならば、誰も自ら足を踏み出そうとはしないでしょうから。
つまり、この物語のプロットは、それ自体が罠として機能しているのです。枠物語、内部物語、階層的な地獄、そしてメタフィクション的な断片化といった全ての要素が、読者を捕らえ、この永劫回帰の悪夢に引きずり込むために、緻密に配置されています。怪物や暴力といった直接的な恐怖は、この巨大な構造的恐怖を際立たせるための部品に過ぎません。
私たちが体験するのは、登場人物たちの物語なのではなく、物語というシステムそのものの恐ろしさです。物語は登場人物を消費し、読者を消費し、それによって自らを永続させていく。その冷徹で、非人間的なメカニズムを、まざまざと見せつけられるのです。読後、自分のいる現実世界さえも、いつか誰かに語られる「唆界」の一部なのではないかという、拭いがたい疑念に取り憑かれることになります。
『驚愕の曠野』は、物語を読むという行為の根源的な危うさを突きつけてきます。私たちは普段、物語と現実との間に安全な一線を引いていますが、この作品はその境界線を破壊し、読者自身が物語の一部であり、その残酷な論理から逃れられない可能性を突きつけます。これほどまでに、読書という体験そのものを揺るがし、存在論的な不安を掻き立てる作品には、そうそう出会えるものではありません。まさに悪夢のような、忘れがたい一冊でした。
まとめ
筒井康隆氏の小説『驚愕の曠野』は、読む者に強烈な体験を強いる、他に類を見ない作品です。物語は、読み聞かせの場面(枠物語)と、その中で語られる「唆界」という地獄(内部物語)の二重構造で進行しますが、やがてその境界は崩壊し、読む者と読まれる者が一体化していく様を描きます。
この物語の恐怖の本質は、その残酷な描写以上に、計算され尽くした構造そのものにあります。死と再生を繰り返す登場人物、どこまでも続く階層的な地獄、そして物語自体が断片化していくメタフィクション的な展開。これらすべてが、読者を逃れられない悪夢のループへと誘うための仕掛けとして機能しているのです。
結末では、物語の登場人物が次の物語の語り手や聞き手になるという、永続する循環が示唆されます。これは、この物語を読むという行為自体が、その恐ろしいサイクルへの参加を意味するという、背筋の凍るような暗示です。救いはなく、ただ深淵への再突入だけが待っているのです。
『驚愕の曠野』は、物語というものの持つ根源的な力を、最も恐ろしい形で示した一冊と言えるでしょう。読後、あなたの世界を見る目は、もう以前と同じではいられないかもしれません。それほどの衝撃を与える、まさしく「驚愕」の物語です。