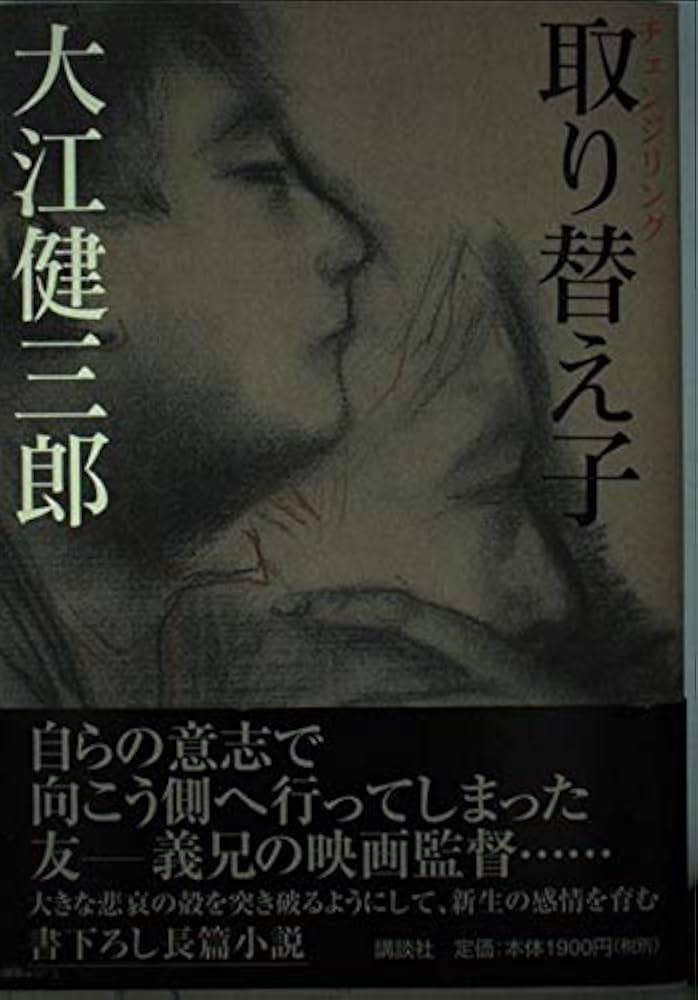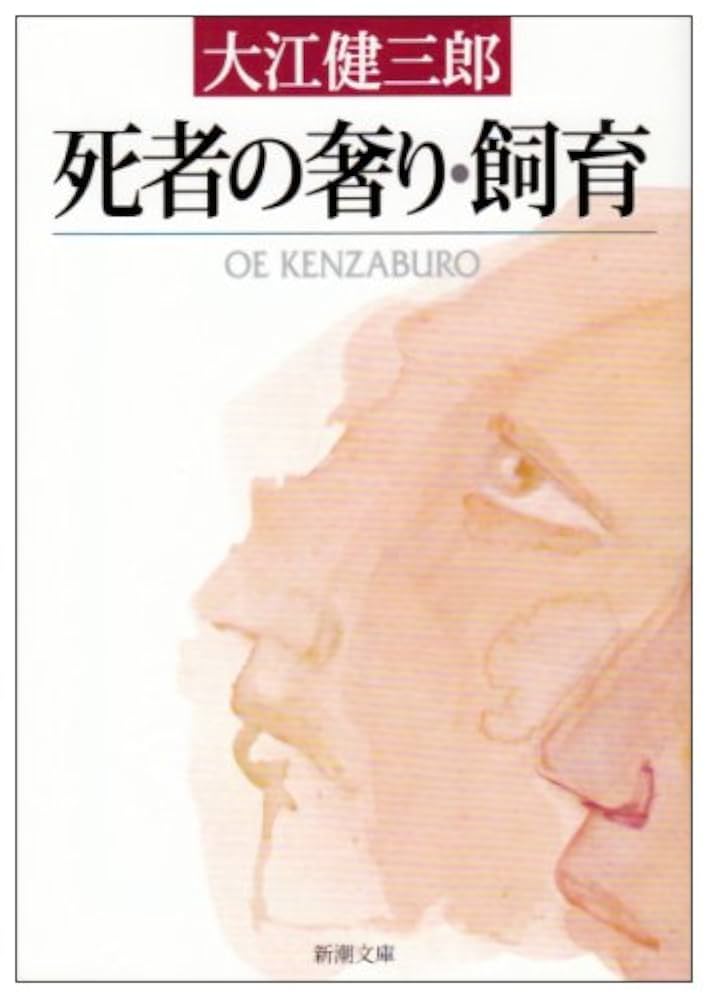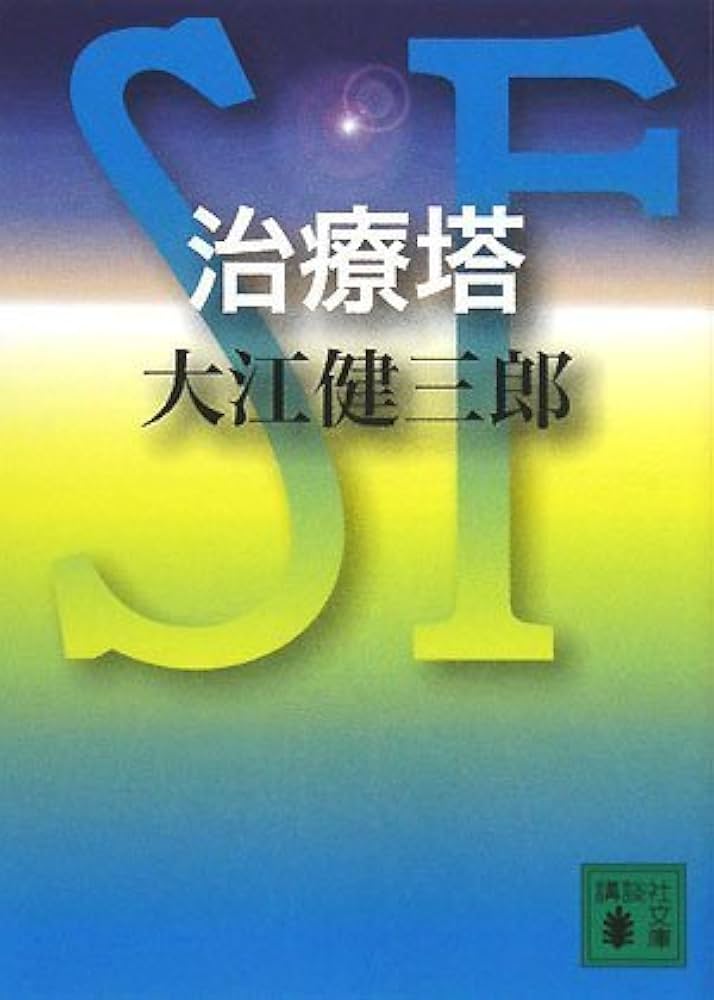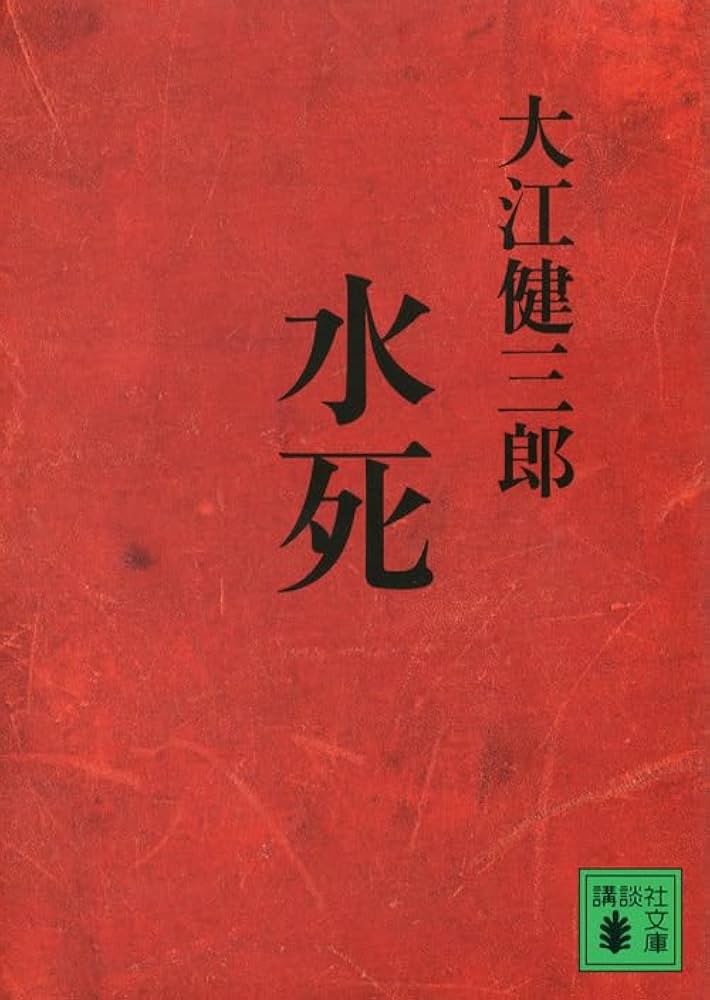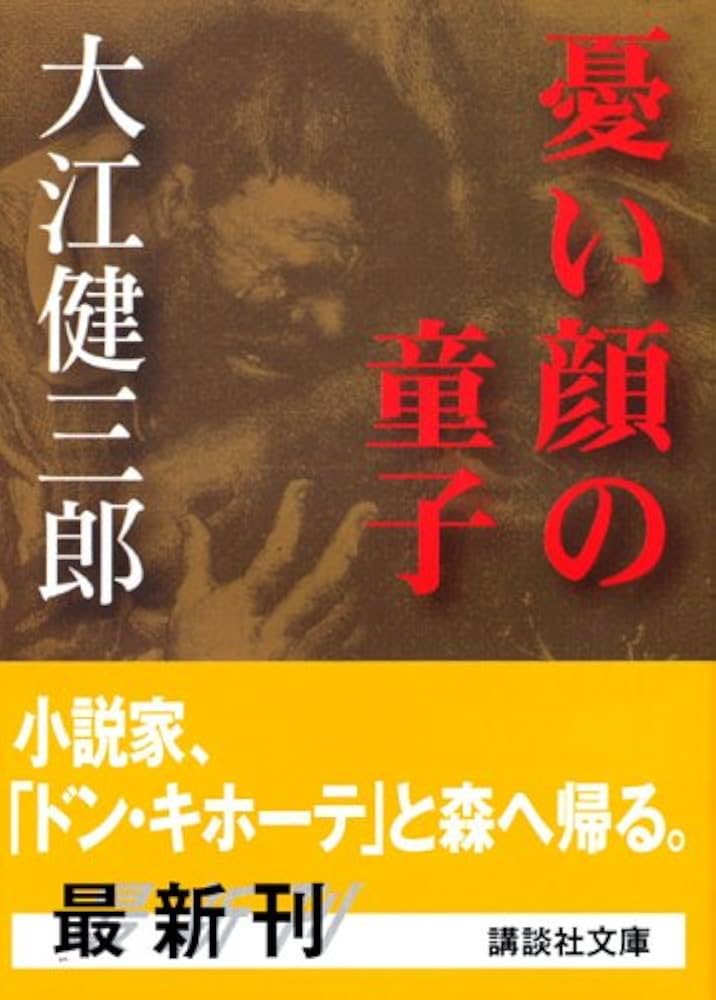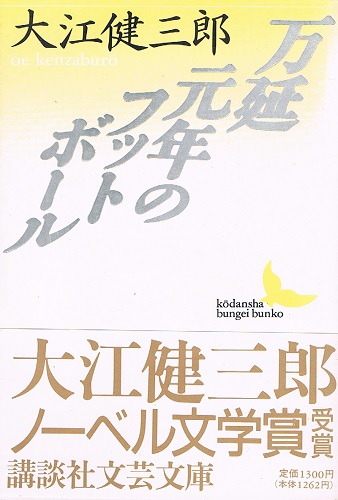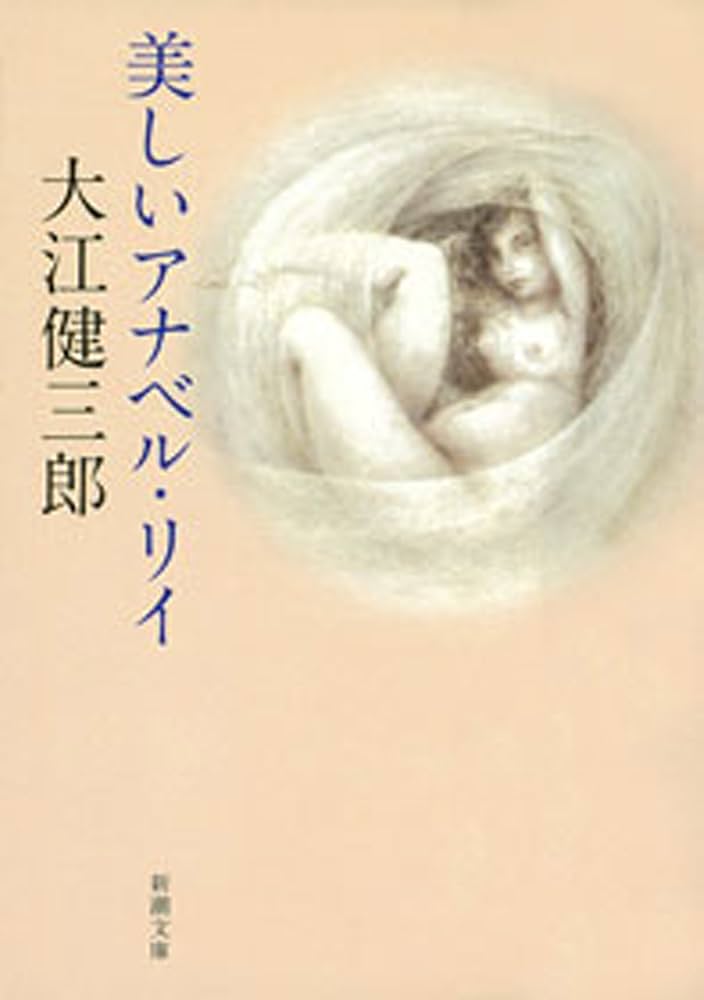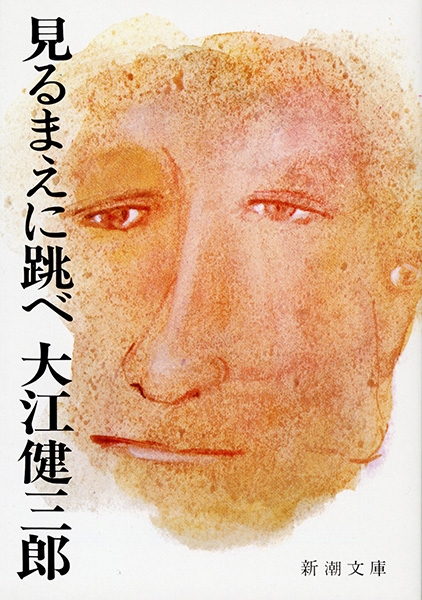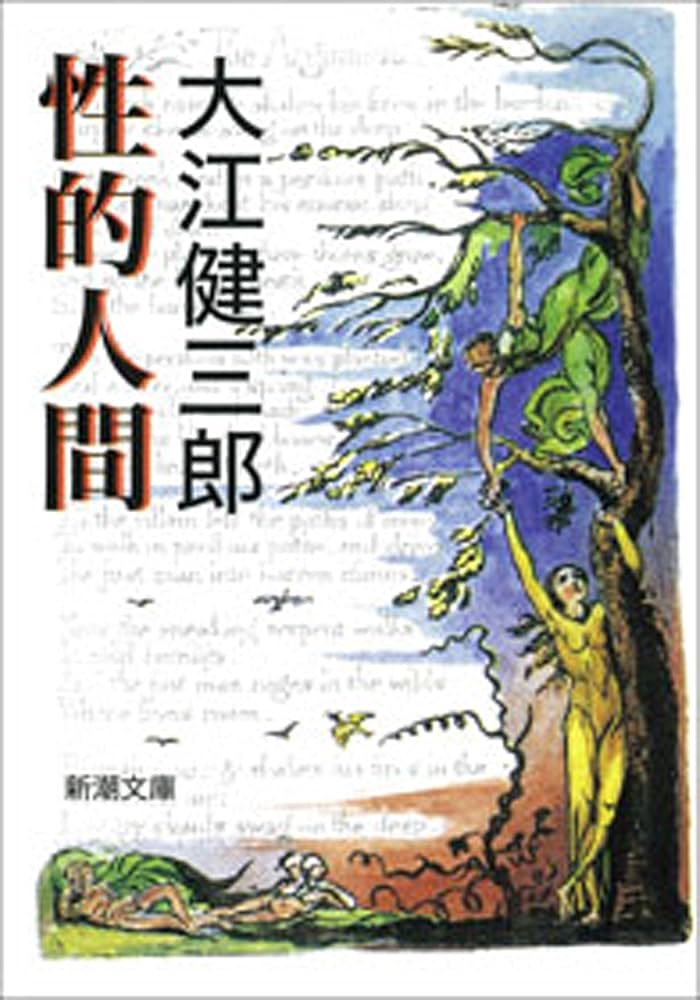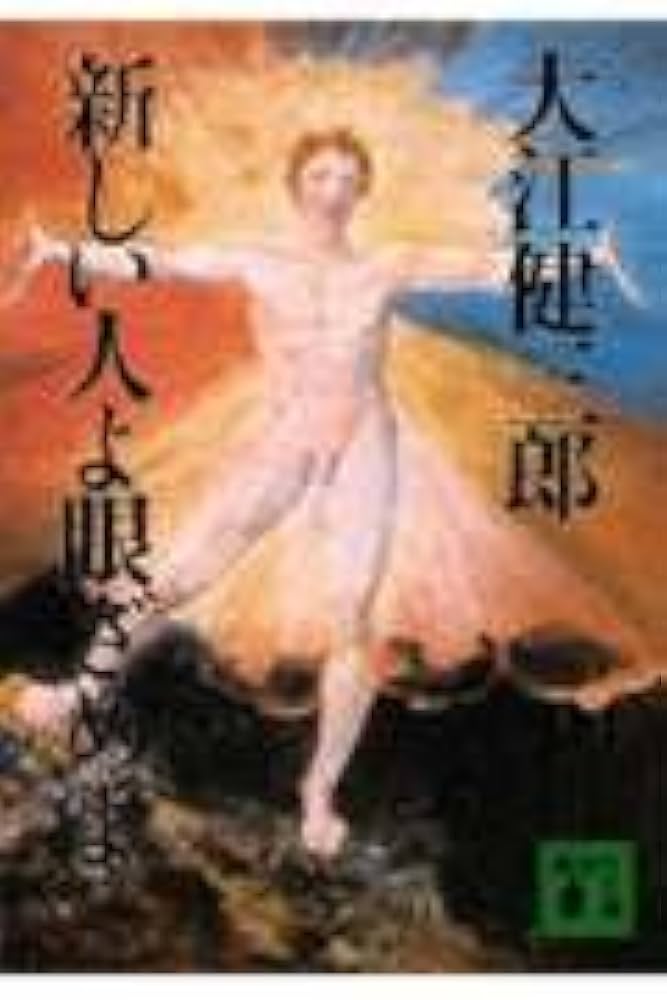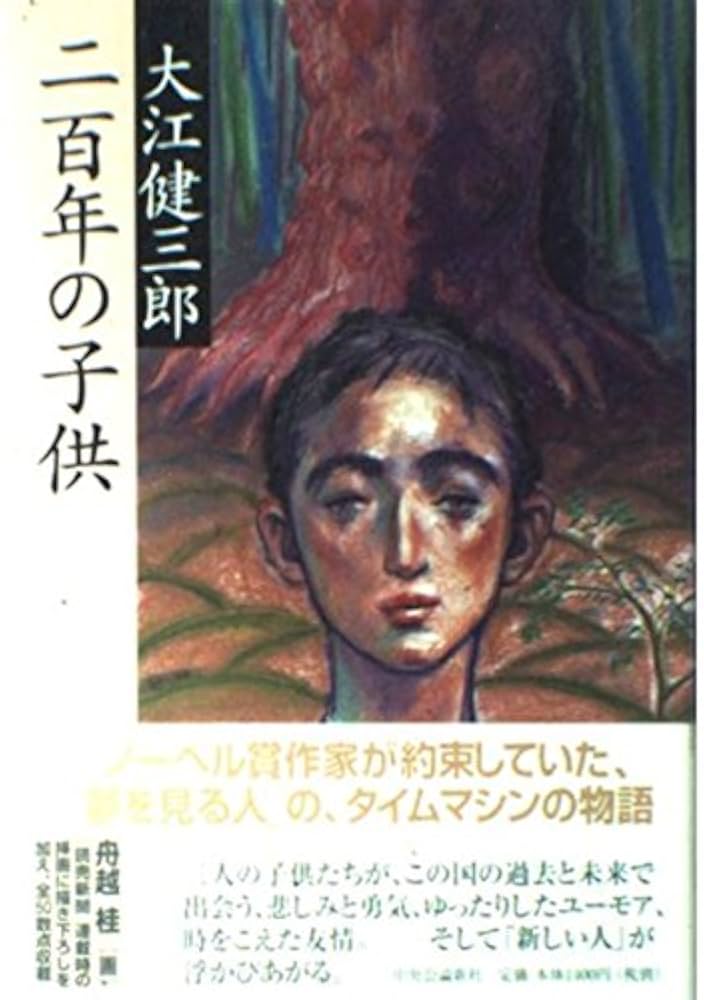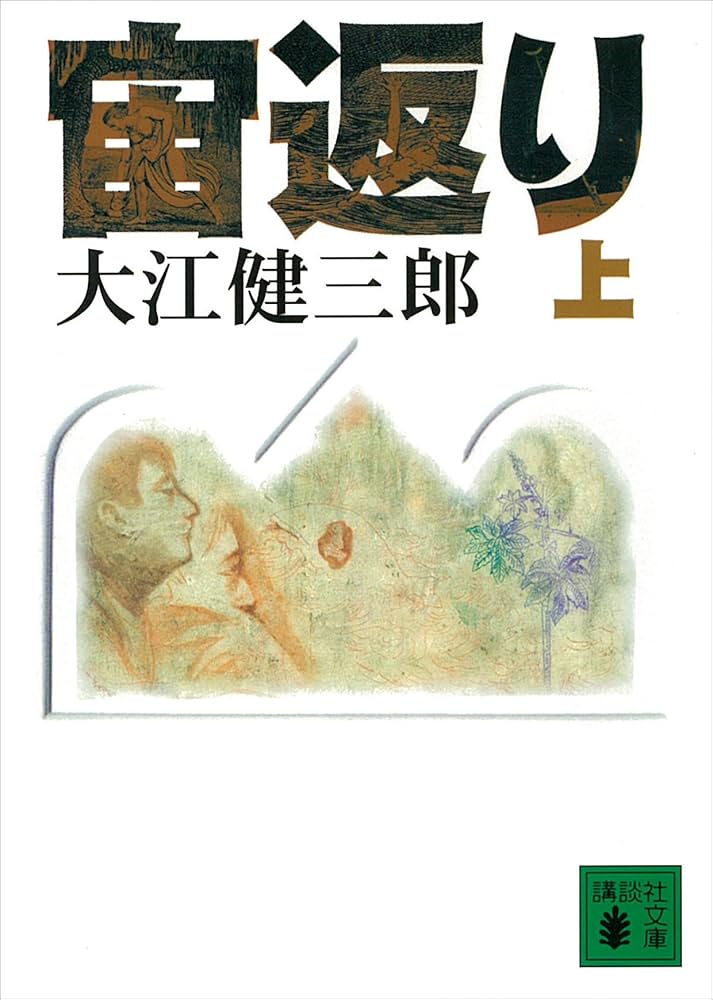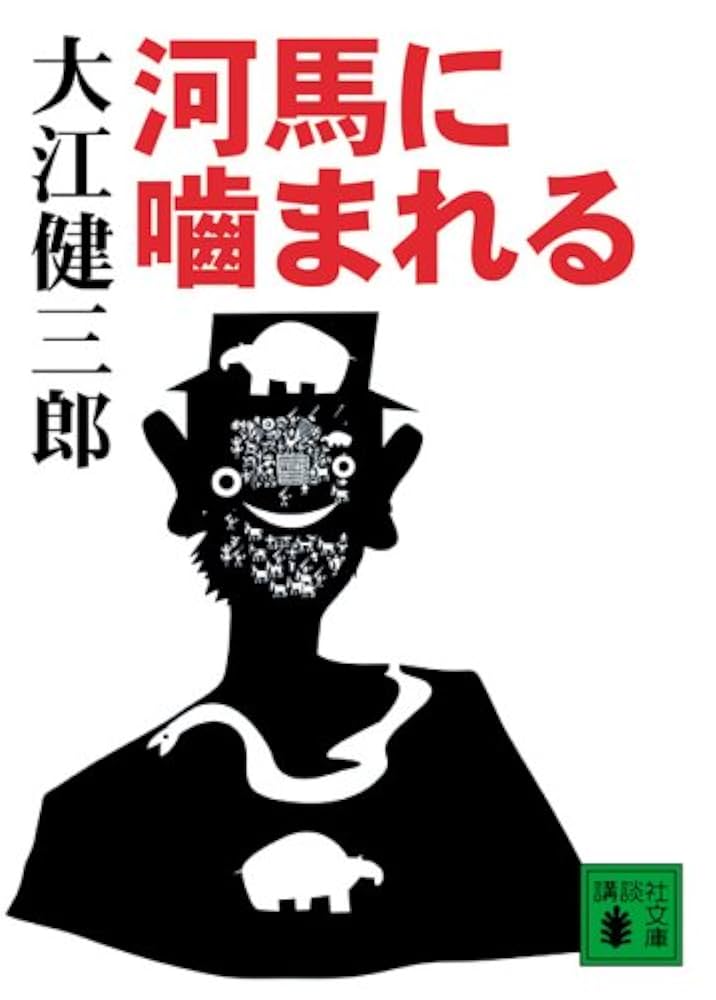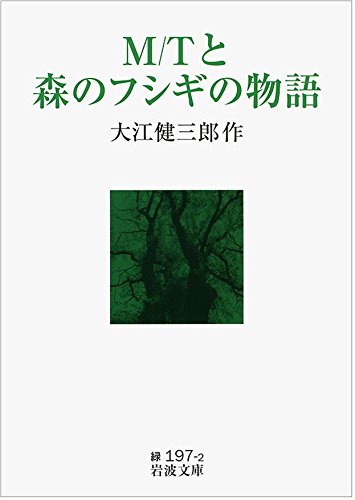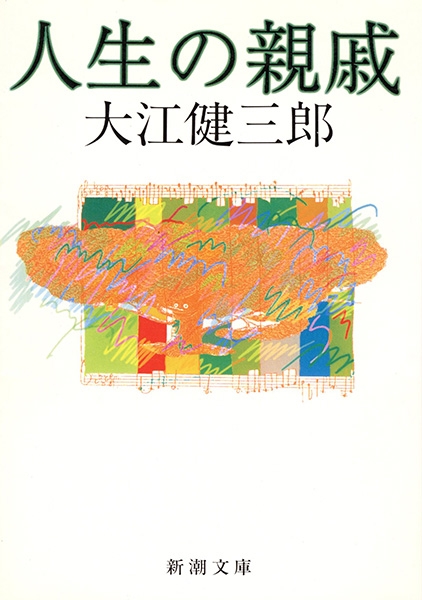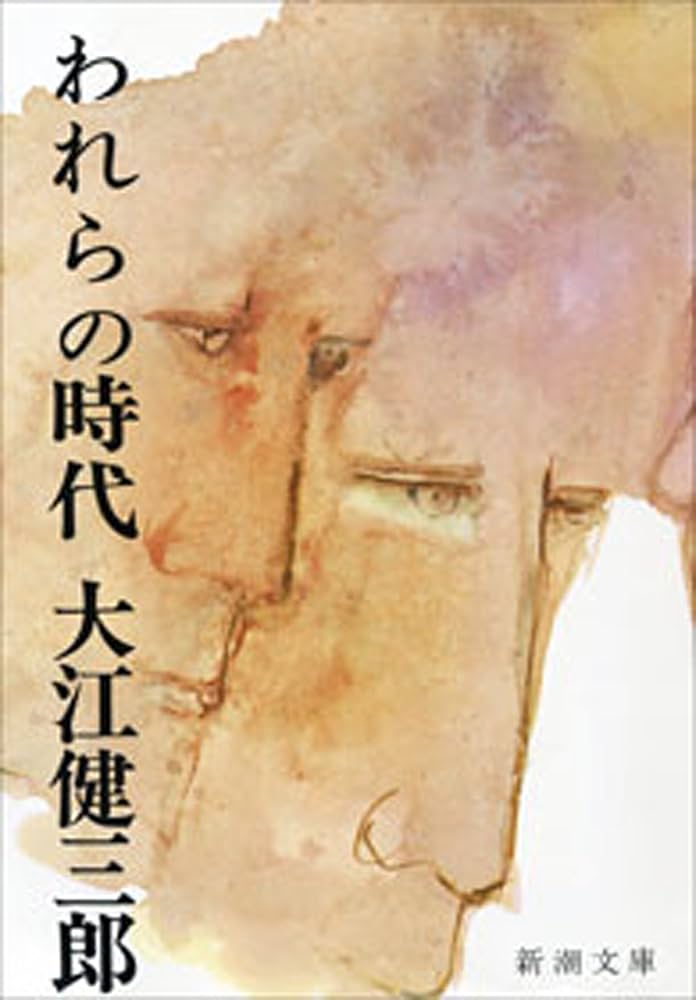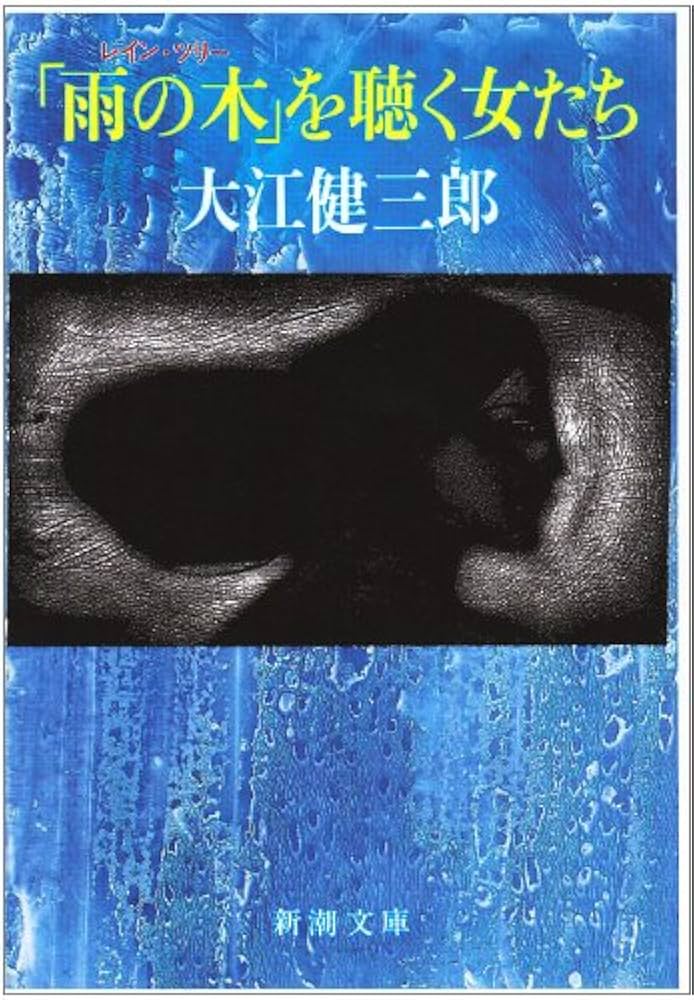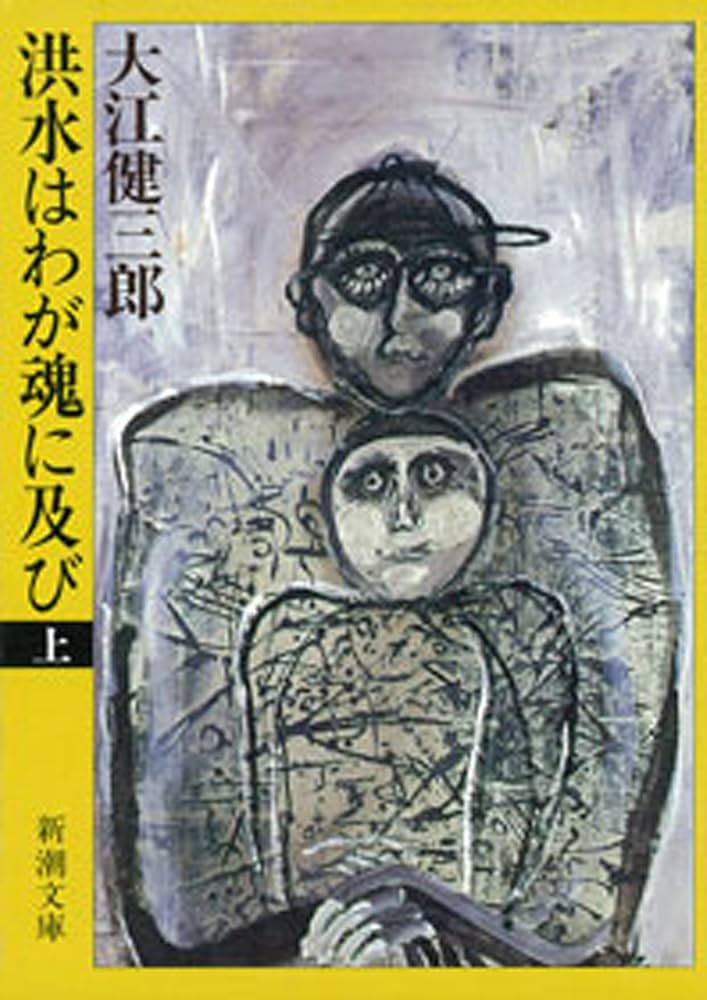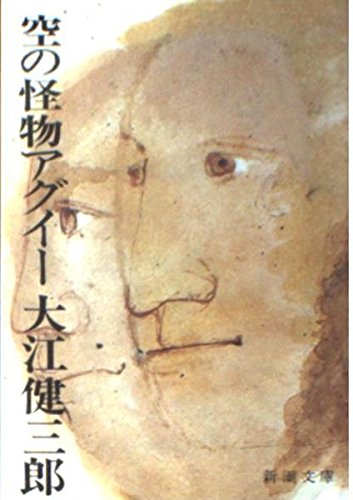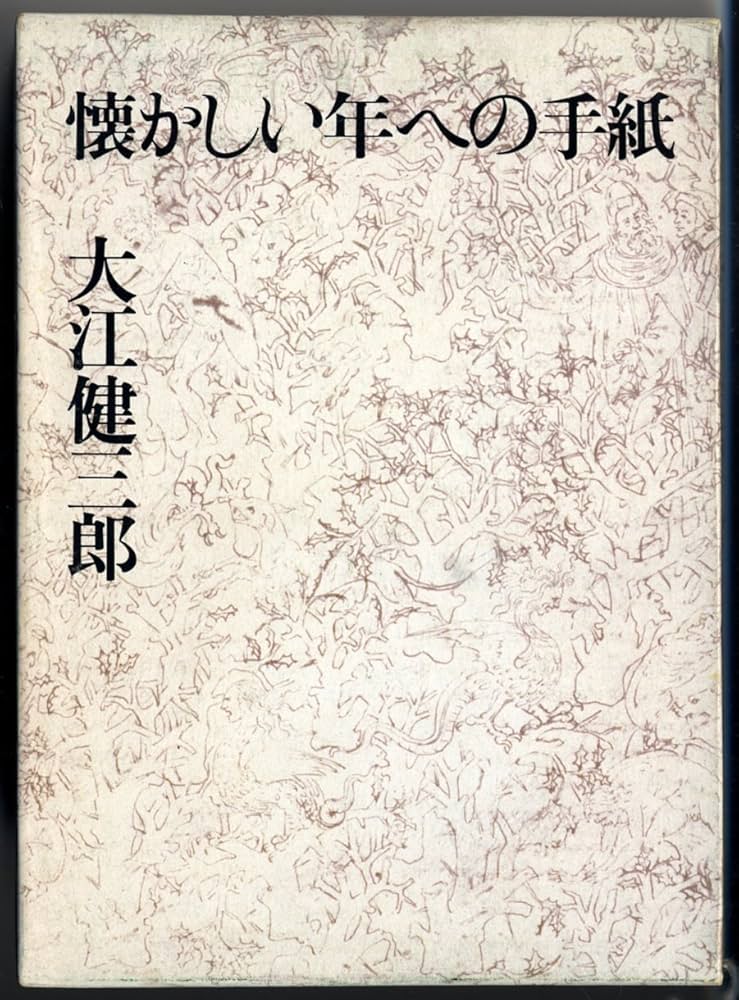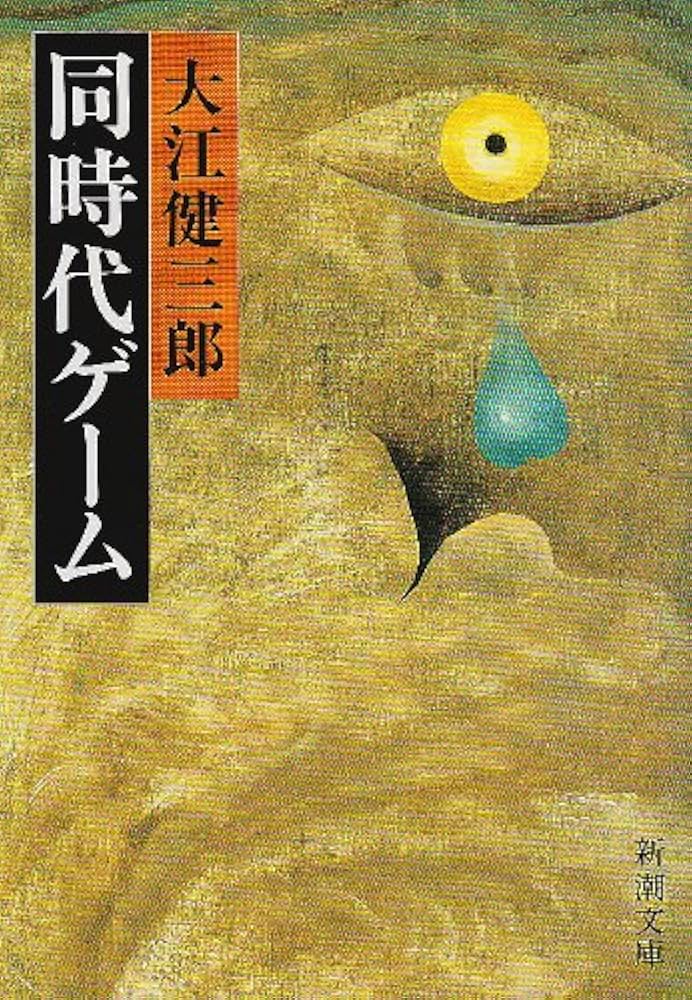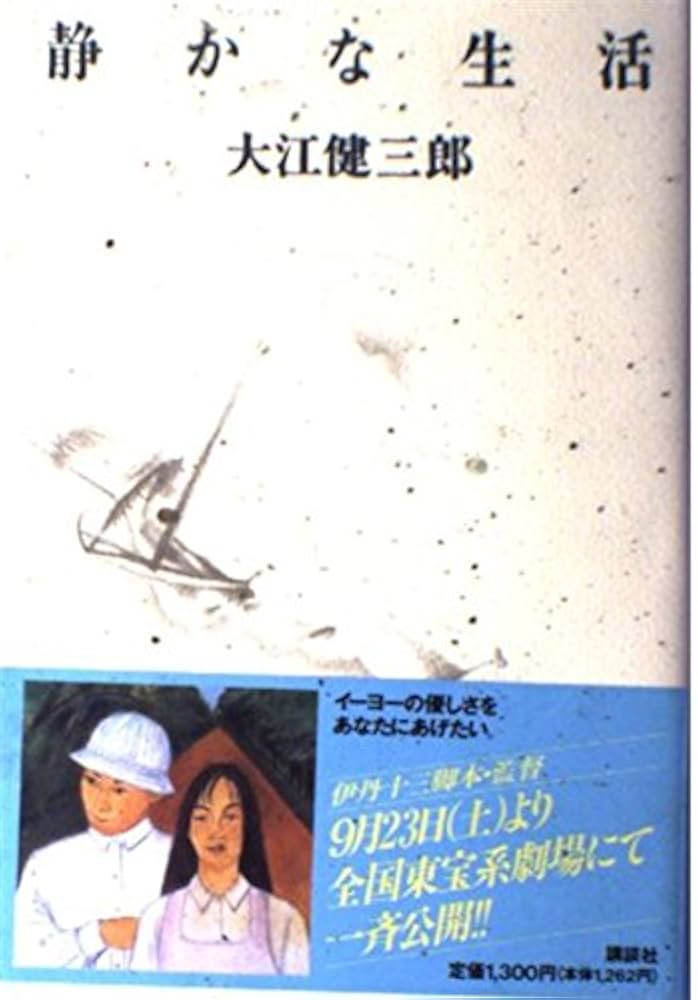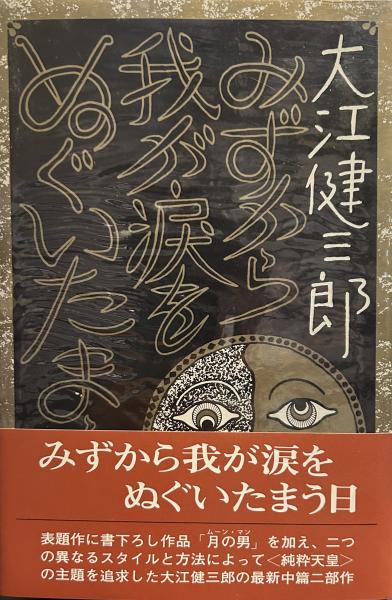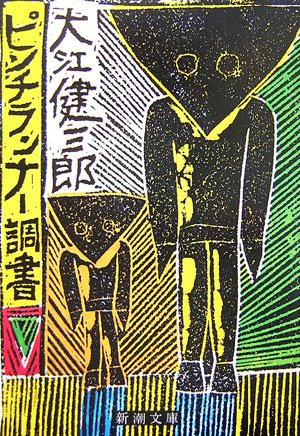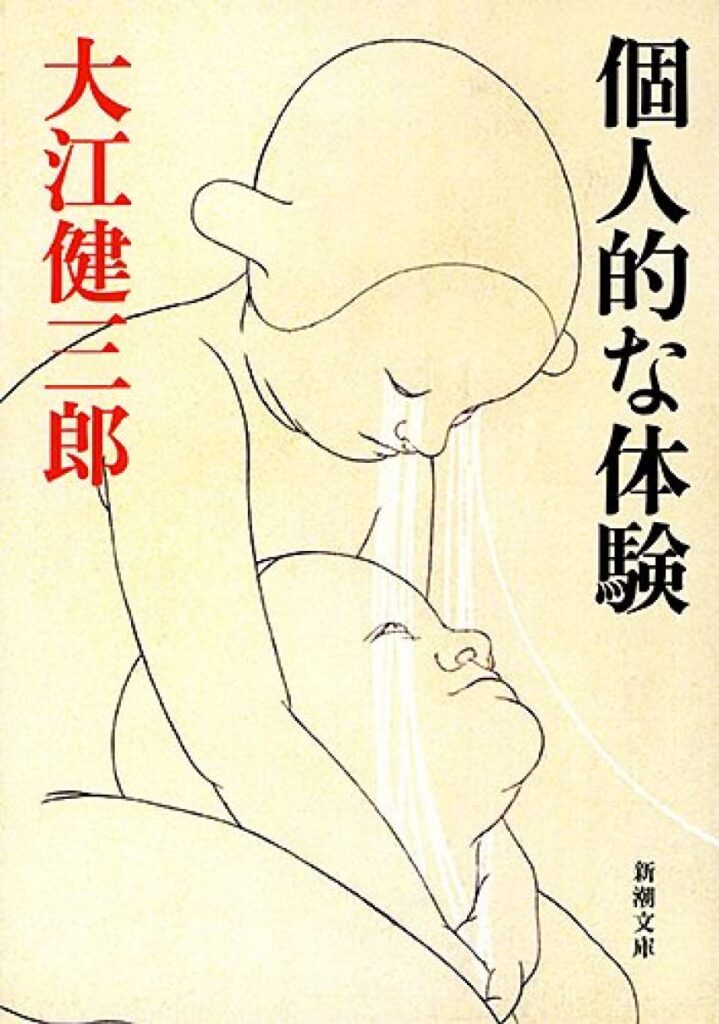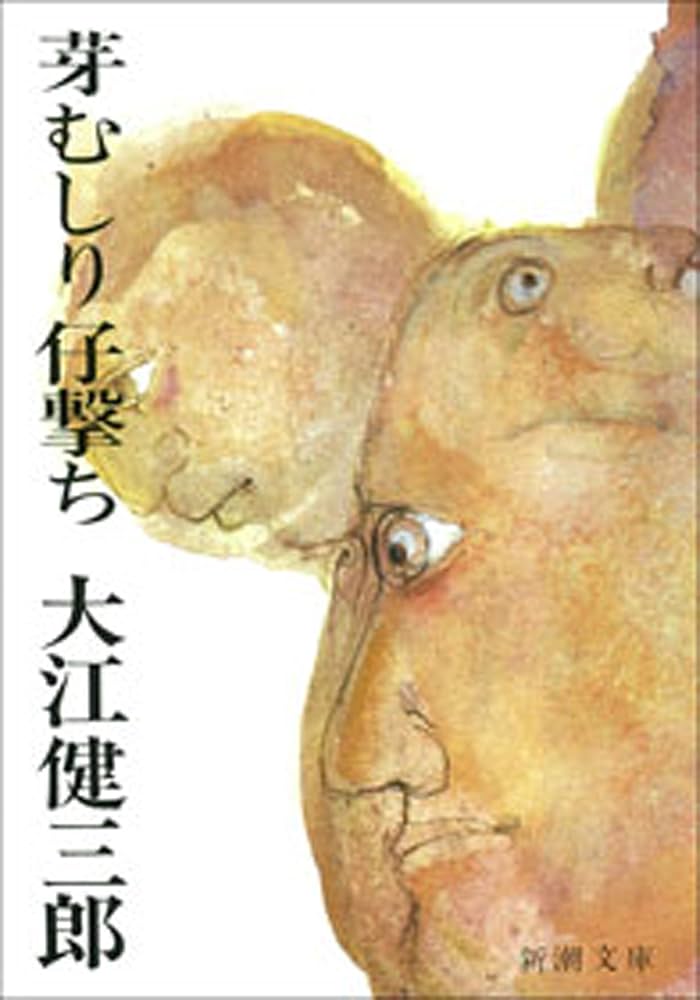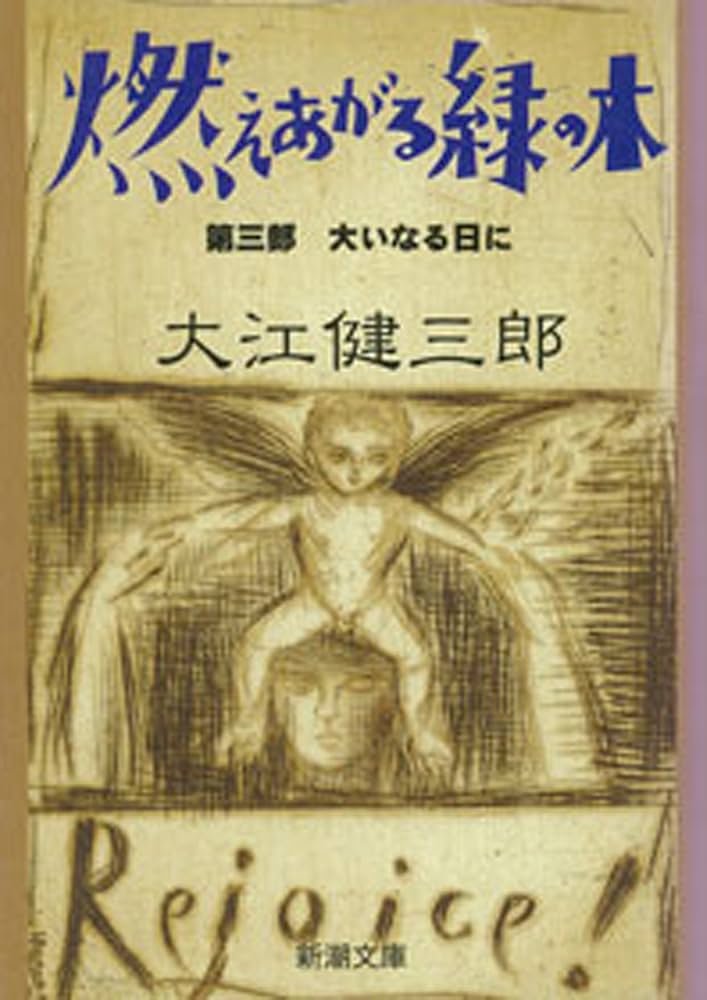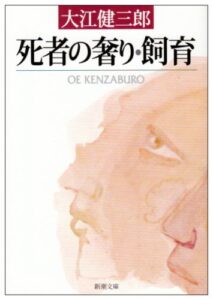 小説「飼育」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、1958年に発表され、当時23歳だった大江健-三郎氏に芥川賞をもたらした短編小説です。 戦争という巨大な非日常が、人々の日常や人間関係を静かに、しかし残酷に変えていく様子が描かれています。
小説「飼育」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、1958年に発表され、当時23歳だった大江健-三郎氏に芥川賞をもたらした短編小説です。 戦争という巨大な非日常が、人々の日常や人間関係を静かに、しかし残酷に変えていく様子が描かれています。
物語の舞台は、外界から隔絶された日本の谷間の村です。 主人公である少年「僕」の視点を通して、一人の黒人兵士との出会いと別れが描かれます。この出会いが、少年の心を大きく揺さぶり、彼の子供時代に終わりを告げることになるのです。この記事では、衝撃的な結末を含む『飼育』の物語の核心に迫ります。
この記事を読むことで、『飼育』がどのような物語なのか、その魅力と問題提起を深く理解できるはずです。特に、物語の結末に関するネタバレ情報を含みますので、これから読もうと考えている方はご注意ください。しかし、この結末を知ることで、物語の細部に込められた意味をより一層感じ取ることができるでしょう。
それでは、大江健三郎氏が描いた、無垢な少年が残酷な現実に直面する物語『飼育』の世界を、一緒に深く味わっていきましょう。無垢と残酷さが交錯するこの物語は、きっとあなたの心に何かを残すはずです。
「飼育」のあらすじ
戦争末期の日本の山奥、谷間にある孤立した村が物語の舞台です。主人公の少年「僕」は、弟や友人たちと閉鎖的ながらも穏やかな毎日を送っていました。村は「町」の人々から見下されており、村人も劣等感を抱いています。 戦争は、遠い世界の出来事のように感じられていました。
ある日、敵国の軍用機が村の近くに墜落し、村の大人たちは生き残った一人の黒人兵を「獲物」として捕らえます。 大人は彼の処遇に困り、県の指令を待つ間、彼を「飼う」ことに決めました。 「僕」の家である共同倉庫の地下倉が、その飼育場所となったのです。
当初は恐怖の対象であった黒人兵も、世話役となった「僕」や子供たちと交流するうちに、少しずつ心を通わせていきます。 言葉は通じなくとも、一緒に水浴びをしたり、黒人兵がその器用さで壊れた義足を修理したりと、牧歌的な日々が続きました。 「僕」と黒人兵の間には、支配する側とされる側の関係を超えた、人間的な絆が芽生え始めていました。
しかし、その穏やかな共生関係は、県の指令によって突然終わりを迎えます。黒人兵の身柄を県へ引き渡すことが決まったのです。自分に迫る運命を察した黒人兵は恐怖にかられ豹変し、昨日までの友好的な関係は完全に崩壊します。物語は、予期せぬ悲劇的な結末へと向かっていくのです。
「飼育」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の結末に触れる本格的な感想になります。まだ結末を知りたくない方はご注意ください。『飼育』が突きつけるのは、子供時代の無垢な世界が、大人の世界の残酷な論理によっていかに破壊されるかという、痛ましい現実です。
穏やかだった共生関係は、黒人兵の移送が決まったことで脆くも崩れ去ります。運命を察知した黒人兵は、「僕」を人質にして地下倉に立てこもります。 昨日までの友人は、恐怖によって獰猛な「獣」へと変貌してしまいました。この豹変こそが、物語の最初の大きなネタバレであり、悲劇の始まりを告げる合図なのです。
村人たちは「僕」を救出しようとしますが、人質にされているため手出しができません。膠着状態が続くなか、業を煮やした村人たちが地下倉の蓋を破壊し始めます。追い詰められた黒人兵が「僕」の首を絞めたその瞬間、塊の中から進み出た「僕」の父親が、憎悪の表情で鉈を振り下ろしました。
その一撃は、黒人兵が防御のためにかざした「僕」の左手ごと、彼の頭蓋を砕きました。 この凄惨な結末は、物語全体を貫く最大のネタバレです。信じていた父親の手によって、信じようとしていた友と共に自らも傷つけられる。この経験が、「僕」から子供である時間を永遠に奪い去るのです。
なぜこのような悲劇が起きたのでしょうか。それは、村という閉鎖的な共同体が持つ排他性と暴力性に根差しています。 最初、黒人兵は「獲物」であり、人間以下の存在でした。しかし交流を通じて、彼は「人間」としての個性を持ち始めます。村人たちにとっても、子供たちにとっても、彼は特別な存在になりかけていました。
しかし、県の「引き渡し」という命令は、彼を再び「モノ」へと引き戻します。村の秩序を保つために、共同体は異物を排除しなければならない。その論理の前では、芽生えかけた人間的な絆など無力でした。父親の行動は、息子を守るためというよりも、共同体の秩序を守るための暴力だったと言えるかもしれません。
『飼育』における「僕」の視点は、この物語の残酷さを際立たせています。子供の純粋な目は、大人たちの世界の矛盾や欺瞞を映し出します。黒人兵に対して「僕」が抱いたのは、恐怖よりも好奇心や、ある種の憧れでした。彼のたくましい肉体や、自分たちの知らない世界の匂いは、「僕」にとって魅力的に映ったのです。
だからこそ、彼の裏切りと父親の暴力は、「僕」の心を深く引き裂きます。信じていた二つの存在から同時に裏切られるという経験は、あまりにも過酷です。 「僕はもう子供ではない」という最後のモノローグは、単なる成長の証ではなく、無垢な世界との決別を宣言する痛切な叫びなのです。
物語に登場する他の人物も象徴的です。例えば、村と町を繋ぐ役人である「書記」は、外界の論理を村に持ち込む存在です。 彼の存在が、最終的な悲劇の引き金となります。そして物語の最後、自暴自棄になった書記が子供たちの橇遊びに加わり事故死する場面は、この村に救いがないことを暗示しているかのようです。
また、主人公の友人である兎口(みつくち)など、他の子供たちの存在も重要です。彼らは大人の残酷さを無邪気に模倣し、時に増幅させます。彼らの存在は、悪意のない残酷さという、もう一つの人間の側面を浮き彫りにしています。
『飼育』という題名が持つ意味も深く考えさせられます。人間が人間を「飼う」という行為そのものが、異常な状況の始まりでした。それは人間性を奪い、相手を動物と同じレベルに貶める行為です。しかし、物語が進むにつれて、「飼う」側と「飼われる」側の関係は曖昧になっていきます。
黒人兵は子供たちに影響を与え、村の日常に変化をもたらしました。ある意味では、村人たちもまた、黒人兵という非日常によって「飼いならされて」いたのかもしれません。支配する側とされる側の境界線が揺らぐ中で、人間とは何か、尊厳とは何かという問いが静かに投げかけられます。
大江健三郎氏の硬質で感覚的な文体も、この物語の大きな魅力です。 湿った土の匂いや、黒人兵の体臭、夏の光と影といった五感を刺激する描写が、閉鎖的な村の空気を濃密に描き出しています。そのリアルな描写が、物語の終盤で描かれる非現実的なほどの暴力を、より一層際立たせるのです。
この小説が発表されたのは1958年。戦争の記憶が生々しい時代でした。 『飼育』は、戦争そのものを直接描くのではなく、戦争がもたらした「異常」が、いかに人々の日常を侵食し、人間性を破壊していくかを描いています。それは、戦争を体験していない世代にとっても、普遍的な問題として響きます。
ネタバレを知った上で『飼育』を再読すると、何気ない描写の一つ一つに悲劇の予兆が隠されていることに気づかされます。子供たちと黒人兵の間に流れる穏やかな時間でさえ、その後の結末を知っていると、切なく、そして恐ろしく感じられます。この読後感の重さこそが、『飼育』という作品が持つ力の証明でしょう。
この物語は、差別や偏見、集団心理の恐ろしさといった、現代社会にも通じるテーマを内包しています。 異質なものを排除しようとする共同体の論理や、一度貼られたレッテルが個人の人間性をいかに覆い隠してしまうか。そうした問題は、形を変えて私たちの周りにも存在しています。
結局のところ、『飼育』は子供時代の終わりを描いた物語です。 しかし、それは単なる成長譚ではありません。理不尽な暴力によって強制的に終わらされた、喪失の物語です。「僕」が失ったのは、左手の自由だけではありません。人を信じる心、世界の美しさを素直に受け止める無垢な魂そのものだったのです。
この物語に救いはありません。読後に残るのは、ずっしりとした重苦しさと、答えの出ない問いです。しかし、その重さこそが、『飼育』が文学として持つ誠実さの表れなのかもしれません。目を背けたくなるような人間の暗部を、容赦なく描き出す。その力強さが、この作品を時代を超えた名作たらしめているのだと感じます。
まとめ:「飼育」のあらすじ・ネタバレ・長文感想
この記事では、大江健三郎氏の芥川賞受賞作『飼育』について、あらすじから結末のネタバレを含む深い感想までを語ってきました。この物語は、戦争中の孤立した村を舞台に、一人の少年と黒人兵との出会いから悲劇的な結末までを描いています。
物語の核心は、少年「僕」と黒人兵の間に芽生えた人間的な絆が、村という共同体の論理と、父親という最も信頼すべき存在によって無残に断ち切られる点にあります。この衝撃的な出来事を通して、「僕」は無垢な子供時代に終わりを告げ、残酷な大人の世界へと足を踏み入れることになるのです。
この記事で展開した長文の感想では、物語の結末に至る背景や、登場人物たちの行動原理、そして「飼育」という行為が問いかける人間性の本質について深く掘り下げてみました。ネタバレを知ることで、この物語が持つ重層的な意味合いをより理解していただけたのではないでしょうか。
『飼育』は、単なる昔の小説ではありません。差別、偏見、集団心理といった、現代にも通じる普遍的なテーマを内包しており、読む者に鋭い問いを投げかけます。読後に重い余韻を残す作品ですが、それこそがこの物語の持つ力であり、文学の醍醐味だと言えるでしょう。