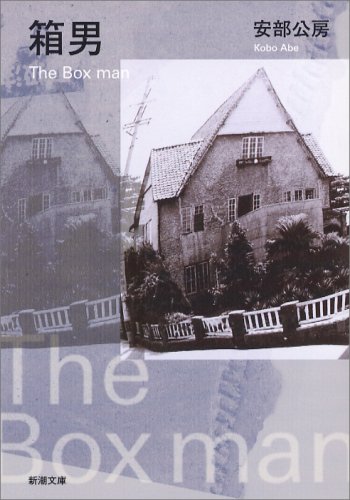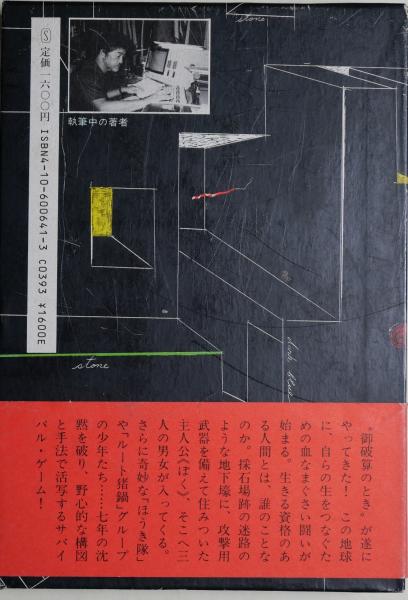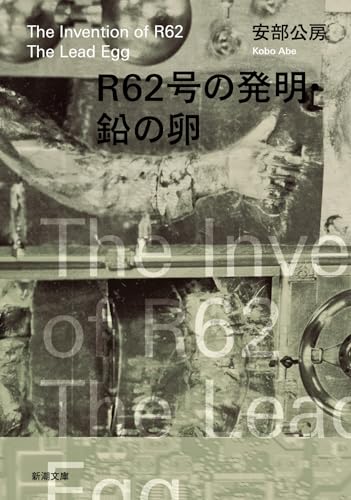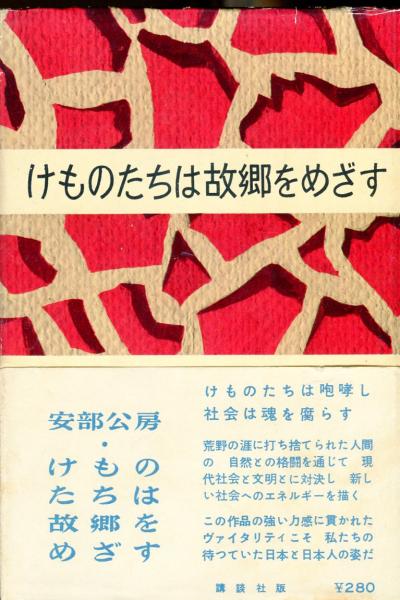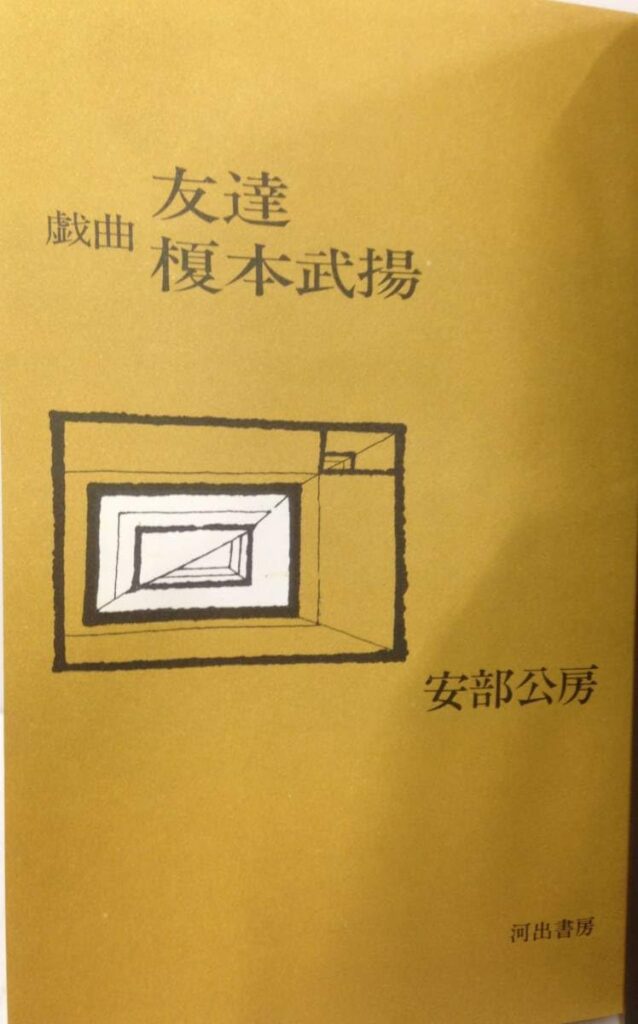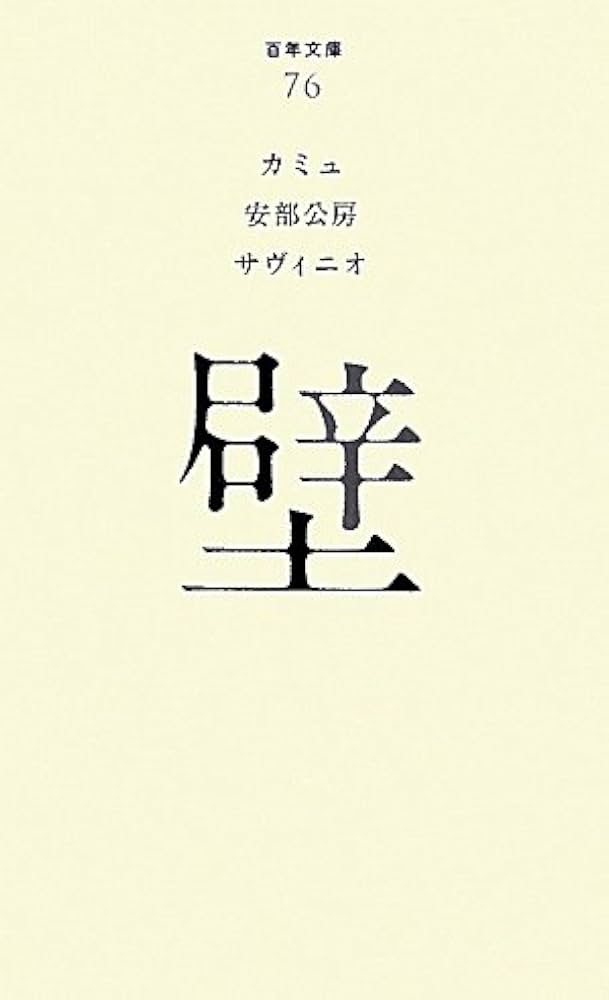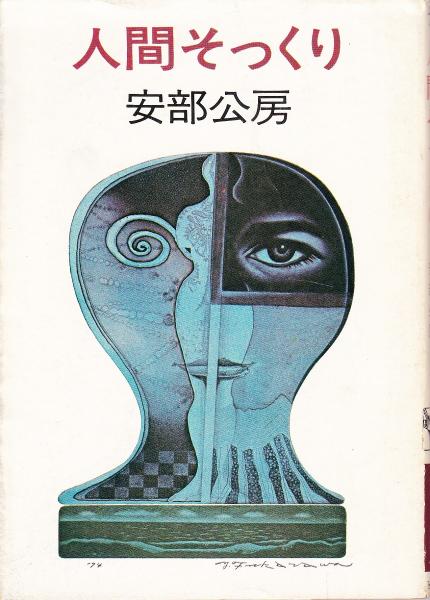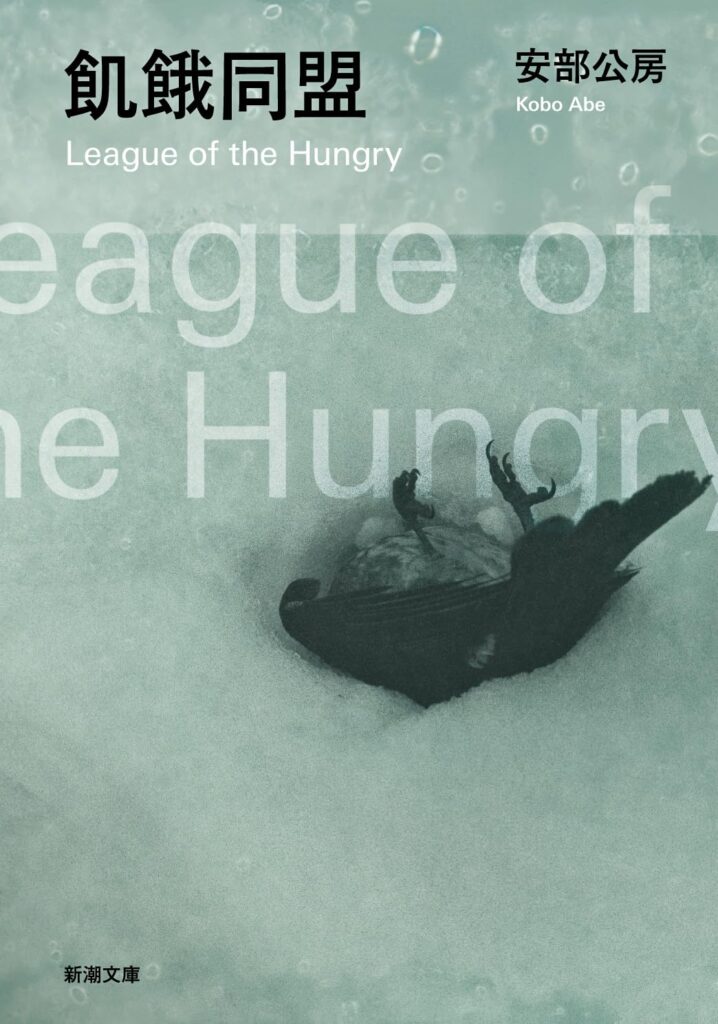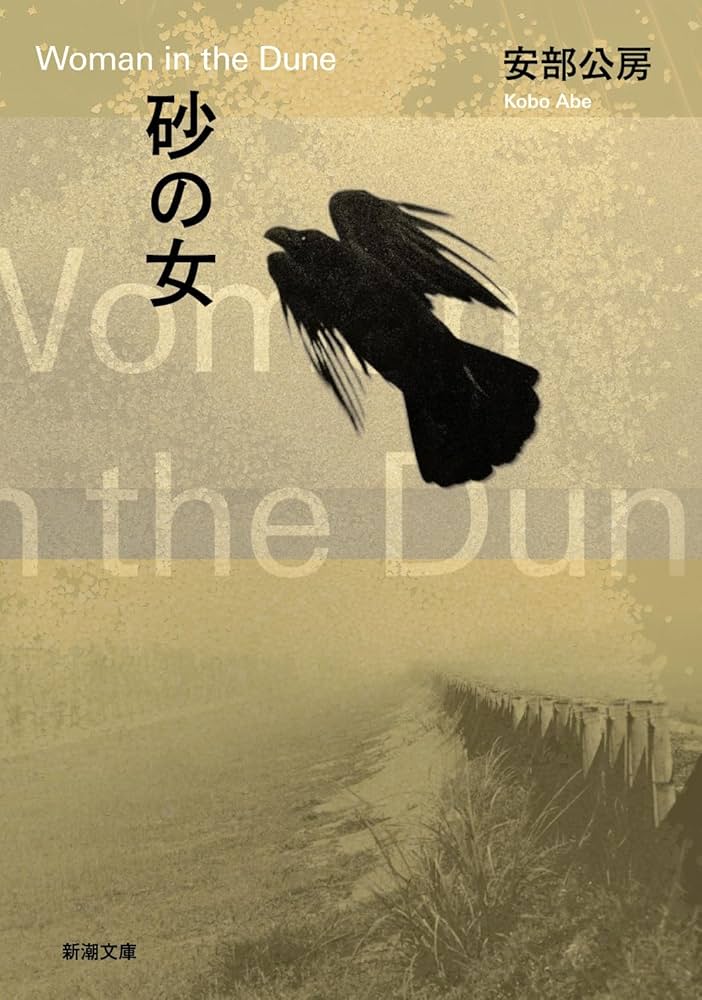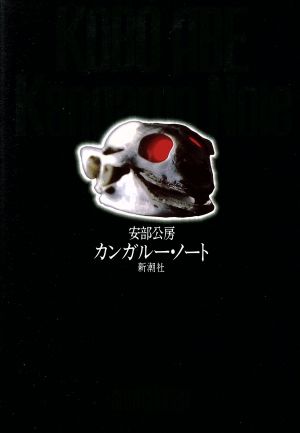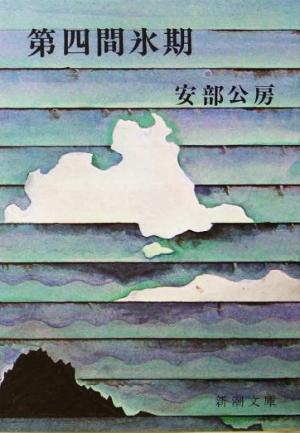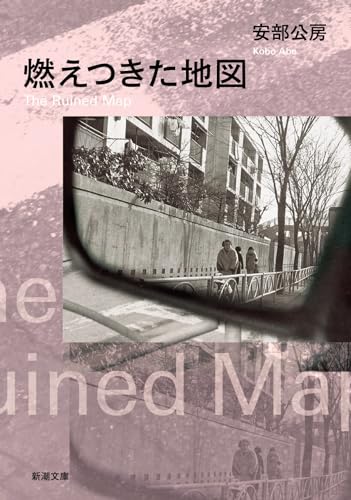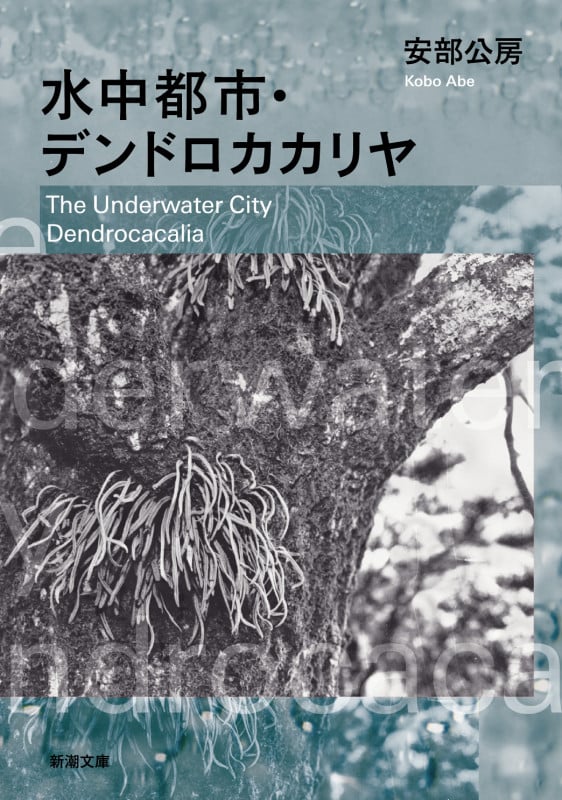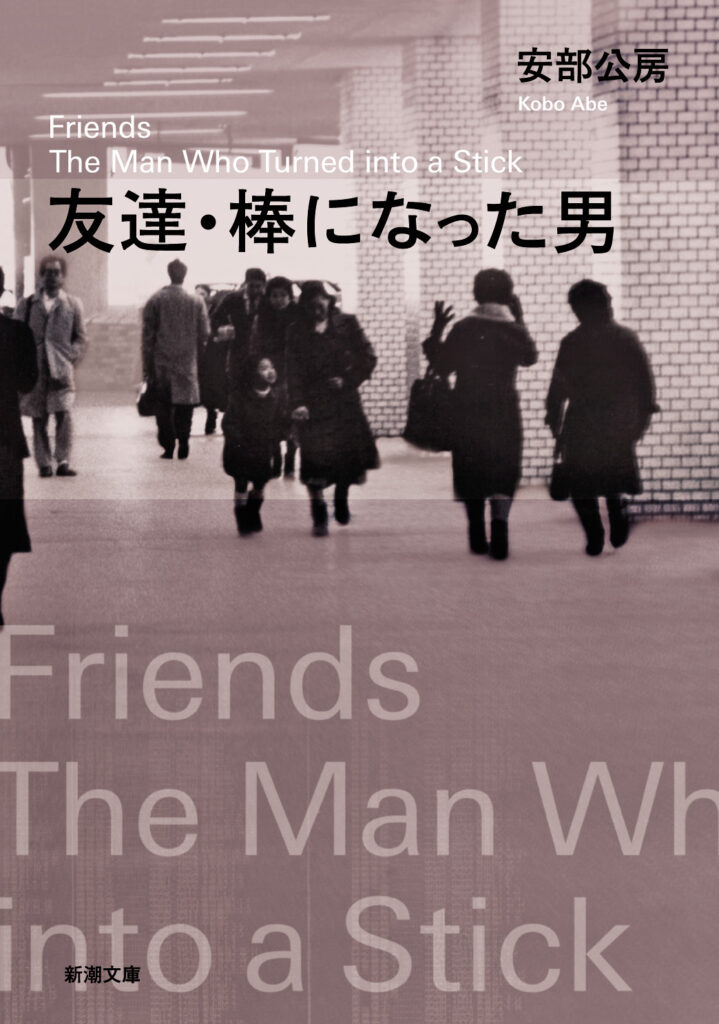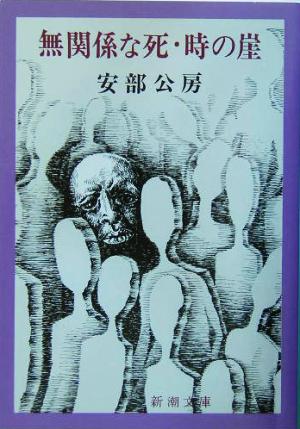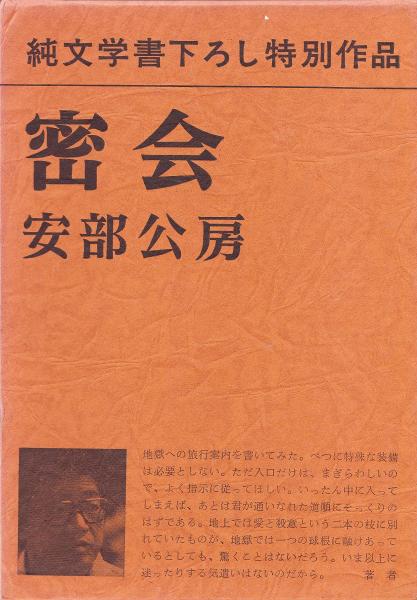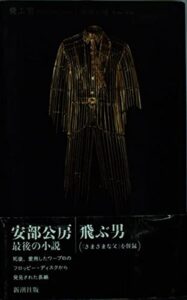 小説「飛ぶ男」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「飛ぶ男」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
安部公房の最後の作品、未完の遺稿として知られるこの物語は、彼の死後にワープロのデータから発見されました。この事実だけでも、読む前から特別な感慨を抱かせます。未完であるということが、かえって物語の持つ謎やテーマ性を際立たせ、読者の想像力をどこまでもかき立てるのです。
物語の始まりは、あまりにも唐突で、そして現代的です。携帯電話で話しながら、パジャマ姿の男が夜明け前の空をゆっくりと飛んでいく。この異様でありながらどこか滑稽な光景から、安部公房ならではの不条理な世界が幕を開けます。日常に亀裂を入れる非日常の侵入、それは安部文学が繰り返し描いてきた光景に他なりません。
この記事では、まず物語の骨子となる部分のあらすじをご紹介します。そして、核心に迫るネタバレを含んだ深い読み解きと、私自身の個人的な感想を詳しく語っていきます。この未完の傑作が、現代に生きる私たちに何を問いかけてくるのか、一緒に考えていければ幸いです。
「飛ぶ男」のあらすじ
ある夏の夜明け、中学校教師の保根治(ほね おさむ)は、窓の外に信じがたい光景を目にします。パジャマ姿の中年男が、携帯電話で話しながら、時速数キロというありえないほどの低速で空を水平に飛んでいくのです。保根は不眠症に悩まされ、自室にこもり、奇妙なオブジェ作りに没頭することで外界との接触を断っていました。この奇怪な目撃体験は、彼の閉じた日常に波紋を広げます。
同じ光景を、もう一人の人物が目撃していました。小文字並子(こもんじ なみこ)という29歳の女性です。過去の経験から極度の男性不信に陥っている彼女は、その「飛ぶ男」に対して衝動的に護身用の空気銃の引き金を引いてしまいます。彼女にとって、それは恐怖からの防衛行為であると同時に、歪んだ形で対象と関わろうとする欲望の表れでもありました。
やがて、保根のアパートの電話が鳴ります。相手は、あの「飛ぶ男」でした。彼は「あんたの腹違いの弟なんだ」「親父に追われている」と告げます。この一本の電話が、孤立していた保根を、抗いがたい物語の中心へと引きずり込んでいくのです。保根の静かで歪んだ聖域は、空飛ぶ弟と、その弟を「獲物」として追い求める並子によって、なし崩しに侵犯されていきます。
保根は、並子の執拗な追及から、傷を負って助けを求めてきた「弟」を匿うことを決意します。それは同情からか、あるいは突然目の前に現れた「家族」という絆への戸惑いからか。こうして、孤独だった三人の男女の奇妙で危険な関係が、狭いアパートの一室で始まるのでした。物語の結末を知らないまま、読者はこの不穏な共同生活の行方を見守ることになります。
「飛ぶ男」の長文感想(ネタバレあり)
この『飛ぶ男』という物語について語ることは、完成された作品を論じるのとは全く異なる、特別な体験を伴います。なにしろ、この物語は作家の死によって永遠に中断されてしまったのですから。しかし、その未完性こそが、本作を安部公房の作品群の中でもひときわ異彩を放つ、忘れがたい一作にしているのだと私は感じています。ここからは、物語の核心に触れるネタバレを含みつつ、その魅力を存分に語らせていただきたいと思います。
まず、冒頭のシーンの衝撃は計り知れません。「ある夏の朝、たぶん四時五分ごろ、氷雨本町二丁目四番地の上空を人間そっくりの物体が南西方向に滑走していった」。この即物的な描写からして、すでに安部公房の世界です。その物体は、着古したパジャマ姿で、信じられないほどゆっくりと、しかも携帯電話で話しながら飛んでいる。自由や超越の象徴であるはずの「飛翔」が、この上なく陳腐で日常的なディテールと結びつけられることで、読む者の心を強くざわつかせます。
この光景を目撃するのが、三人の孤独な人間であるという設定が、また見事です。一人目は主人公の保根治。彼は不眠症と鬱に悩み、自分の名前にちなんだ紙製の骨格標本を愛でるという、内向的で孤立した人物。彼の部屋は、彼自身が作り上げた歪んだ聖域であり、世界からのシェルターでした。彼の孤独は、現代社会に生きる多くの人々が抱える心理的な孤立を象徴しているように思えます。
二人目の目撃者、小文字並子もまた強烈な個性の持ち主です。彼女は「年季の入った男性嫌い」で、パラノイアに苛まれ、護身用に空気銃を所持しています。彼女の孤独は、過去のトラウマに起因する社会的な孤立です。彼女が飛ぶ男に銃弾を撃ち込む行為は、単なるパニックではなく、歪んだコミュニケーションの試みでした。「彼女は恋を射止めたのだ」という一文には、彼女の病理の根深さが凝縮されており、読んでいるこちらが眩暈を覚えるほどです。
そして三人目の目撃者である匿名の暴力団員。彼は腎臓の持病のために偶然その光景を目にしますが、関わり合いを避けて見て見ぬふりをします。彼の存在は、保根と並子がこの不条理な出来事に巻き込まれていくのが、ある種の「選択」であったことを示唆しているように感じられます。彼は、不条理から顔を背ける大多数の象徴なのかもしれません。この三者三様の孤独が、物語の基盤を形成しています。
物語が大きく動くのは、飛ぶ男からの電話と、並子による銃撃という二つの事件がほぼ同時に起こる場面です。飛ぶ男は保根に「あんたの腹違いの弟なんだ」と告げます。この電話は、保根が築き上げてきた心理的な壁をいとも簡単に突き破る侵入行為です。それまで抽象的な「目撃対象」でしかなかった存在が、いきなり「家族」という最もプライベートな関係性を主張してくるのですから、彼の動揺は察するに余りあります。
一方で、並子はその飛ぶ男を撃ち落とそうとします。これは彼女なりの「接続」の試みであり、暴力的な所有欲の表れです。キューピッドの矢ならぬ、空気銃の弾丸。このグロテスクなねじれこそが、安部作品の登場人物を特徴づける歪みなのでしょう。彼女は自分の「獲物」を匿っているに違いないと確信し、保根のアパートへ乗り込んできます。
保根のアパートという「聖域」が、並子によって土足で踏み荒らされる場面は、本作のハイライトの一つです。保根が大切にしていた収集物が無造作にかき回され、彼の秩序は暴力的に破壊されます。外界からの侵入を拒んできた男が、最も望まない形で他者との濃密な対立に引きずり込まれる。この皮肉な展開に、私は安部公房の容赦のなさを感じました。
そして、ついに傷を負った「飛ぶ男」が、マジシャン「マリ・ジャンプ」と名乗って保根の部屋に避難してきます。ここで保根の心理に決定的な変化が訪れます。それまで観念的な存在だった「『弟』」が、生身の、手当てを必要とする「弟」へと変わるのです。このカギ括弧が取れる瞬間こそ、保根が不条理な現実を受け入れ、物語の能動的な参加者となった瞬間だったのでしょう。
保根がマリ・ジャンプを受け入れたのは、攻撃的な侵入者である並子という、より直接的な脅威の存在があったからかもしれません。二つの脅威の間で、彼は血縁を主張し、より無力に見える弟の側につくことを選択します。こうして、孤独だった個人たちが、歪んだ仮初めの「家族」を形成していく。この過程は、読んでいて息苦しくなるほどの緊張感に満ちています。
ここで物語の背景を理解する上で欠かせないのが、同時収録された前日譚『さまざまな父』です。この短い物語が、すべてを説明する鍵となります。ネタバレになりますが、マリ・ジャンプの父は、息子に飛ぶ薬を与え、自分は透明になる薬を飲みます。そして、息子の飛翔能力を金儲けの道具として利用するために、透明なまま彼を追い続けているのです。
さらに衝撃的なのは、この透明な父が、保根が死んだと信じていた自身の父親でもあったという事実です。つまり、保根とマリ・ジャンプは、同じ一人の「ろくでもない父親」によって、一方は捨てられ、もう一方は搾取されるという形で人生を狂わされた異母兄弟だったのです。ここで「家族」というものが、安息の場ではなく、支配と搾取のシステムとして描かれていることに戦慄を覚えます。
父の「透明性」は、実に象徴的です。それは、現代社会における目に見えない権力やシステムのメタファーとして機能します。会社や国家といった巨大な機構が、個人の生を規定し、時には搾取する。その構造が、この歪んだ親子関係に凝縮されているかのようです。息子の飛翔は、もはや自由の証ではなく、父からも社会からも追われる原因となる「呪い」でしかありません。
物語には、並子が勤務する「氷雨発酵研」をめぐる企業ドラマの存在もほのめかされています。株価操作や計画倒産といった不穏な影がちらつき、彼女の個人的なパラノイアが、実は社会の巨大な病理と無関係ではない可能性が示唆されます。このサブプロットがもし書き進められていれば、物語は奇妙な家庭劇の枠を超え、より広範な社会批判の様相を呈していたかもしれません。
そして、物語は唐突な終わりを迎えます。並子の追及を察知したマリ・ジャンプは、手当てを終えると、再び窓から飛び去っていきます。原稿は、ここで途切れているのです。残されたのは、再び一人になったものの、自らの忌まわしい出自という重荷を背負わされた保根と、目的を果たせなかった並子、そして今もどこかで見ているであろう透明な父の存在です。
この結末の不在は、読者に強烈な印象を残します。しかし、私はここにこそ、安部公房らしい「結末」があるように思えてなりません。彼の描く登場人物は、『砂の女』や『箱男』のように、しばしば解決のない状況や、出口のない迷宮に囚われます。この『飛ぶ男』もまた、登場人物たちを、そして私たち読者を、宙吊りの状態のまま置き去りにするのです。
安部公房が探求し続けた「異化」というテーマが、この物語では「飛翔」という形で現れます。しかし、それは決して輝かしい変身ではありません。飛ぶ男は、人間的な条件から切り離され、周囲に恐怖と苛立ちを与える「病原菌」のような存在として描かれます。この変容は、救いではなく、むしろ深刻な疎外の始まりなのです。
結論として、『飛ぶ男』は未完でありながら、安部公房の文学的テーマが見事に結晶化した作品だと言えます。不条理の侵入、都市に生きる人間の孤独、機能不全に陥った共同体、そして変容の恐怖。これらすべてが、凝縮されて詰まっています。この断片的な物語は、私たち読者に解釈の余地を無限に与えてくれます。残された断片から物語の全体像を想像し、登場人物たちの行く末に思いを馳せる。それこそが、この未完の傑作との最良の付き合い方なのかもしれません。
まとめ
安部公房の遺稿『飛ぶ男』は、未完であるがゆえに、かえって強烈な問いを私たちに投げかけてきます。物語のあらすじを追うだけでも、日常に潜む不条理や、現代人が抱える根源的な孤独といった、安部文学に共通するテーマが色濃く現れていることがわかります。
核心部分のネタバレに触れると、物語はさらに深みを増します。空を飛ぶ弟と、彼を搾取する透明な父。この設定は、単なる奇抜な空想に留まらず、家族という共同体が孕む支配と搾取の構造、ひいては社会システムそのものへの鋭い批判として機能しています。保根や並子といった登場人物たちの歪みは、彼らを取り巻く世界の歪みを映す鏡なのです。
この物語には、明確な結末がありません。しかし、そのことが、安部公房の作品世界における「救いのなさ」や「終わりのない状況」を最も純粋な形で体現しているようにも思えます。読者は、登場人物たちと共に、解決のない宙吊りの状態に置かれるのです。この読書体験こそが、本作の最大の価値かもしれません。
もしあなたが、安部公房の作り出す迷宮的な世界に足を踏み入れたいと考えるなら、この『飛ぶ男』は避けて通れない一作です。完成された物語とは違う、断片から全体を想像する知的な興奮と、心に深く突き刺さるような問いが、あなたを待っているはずです。