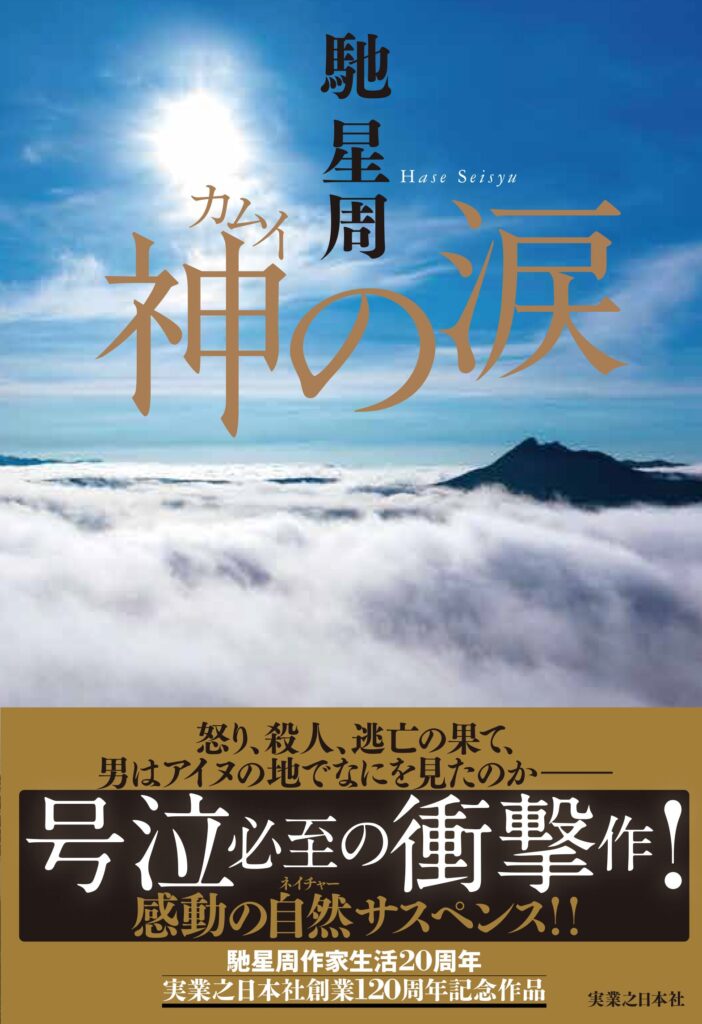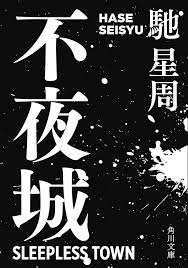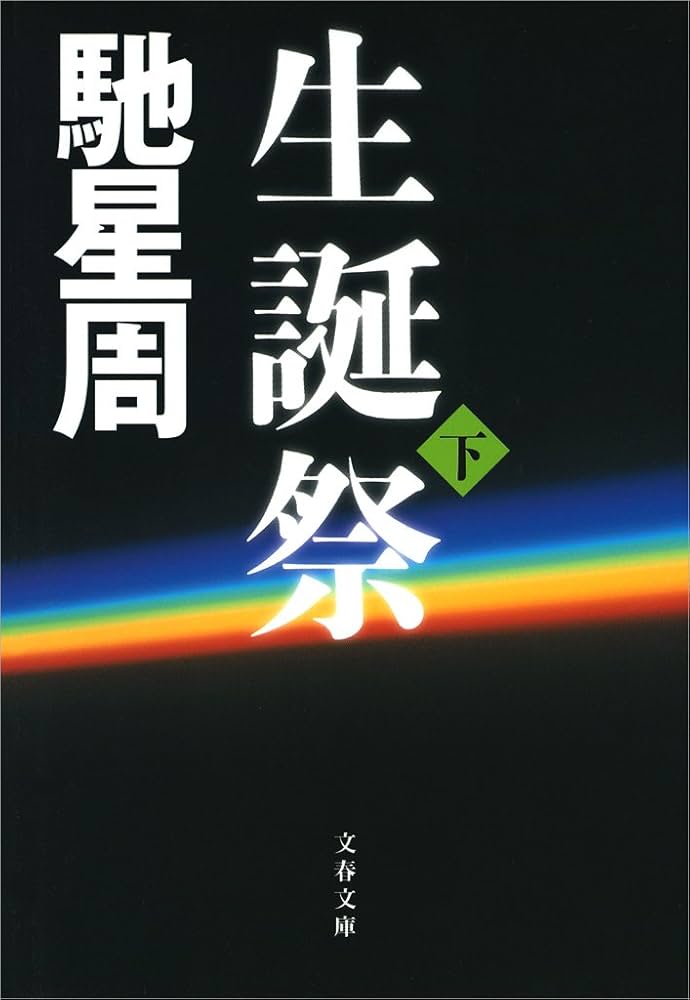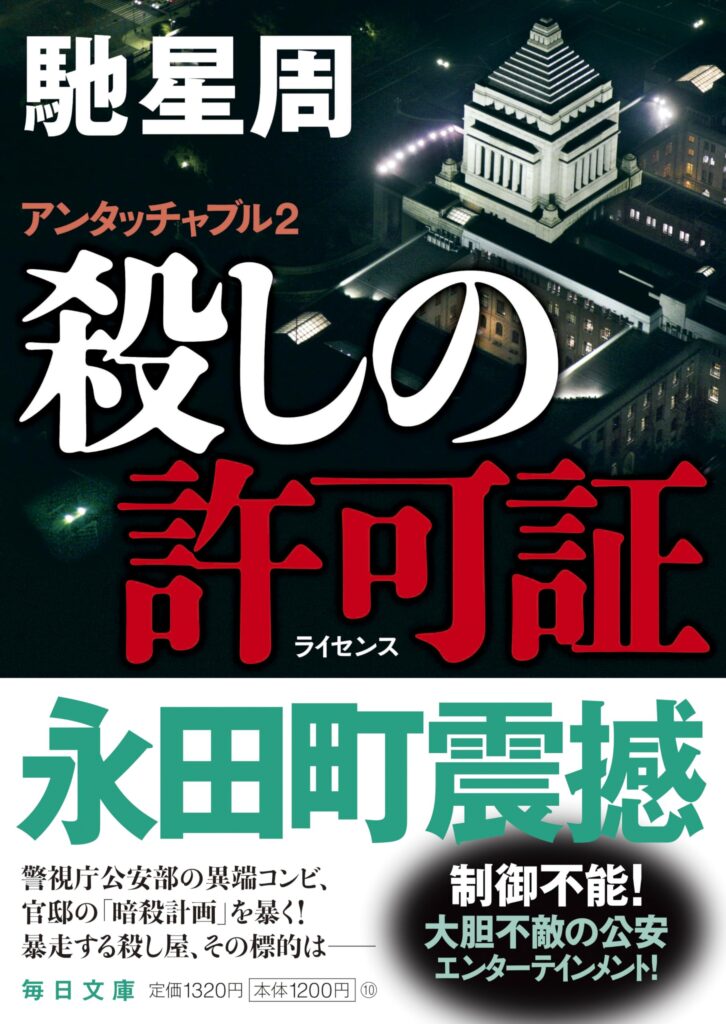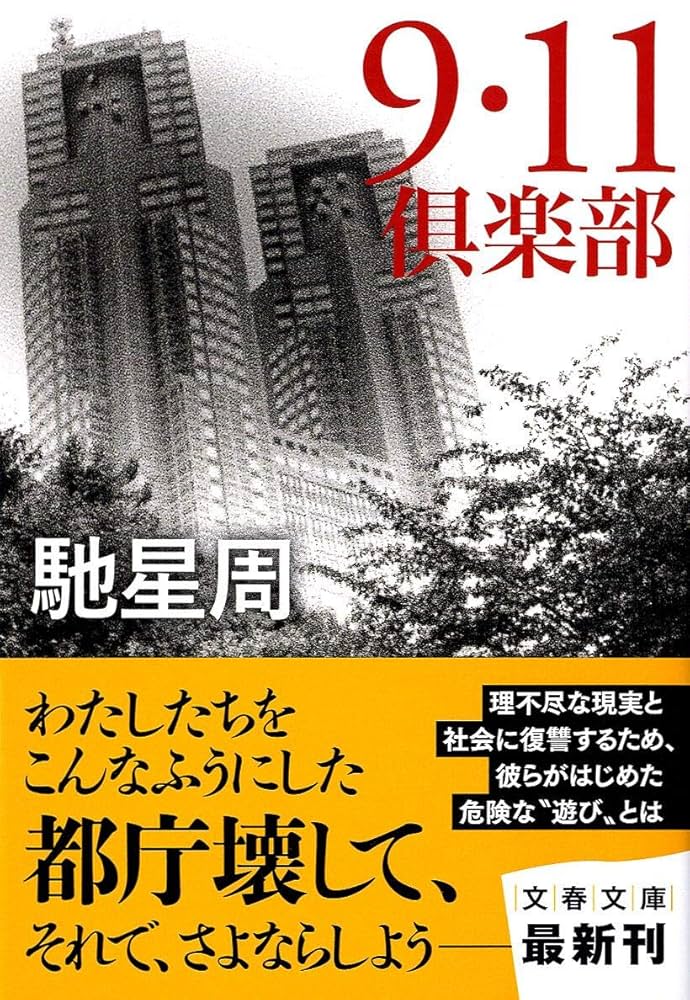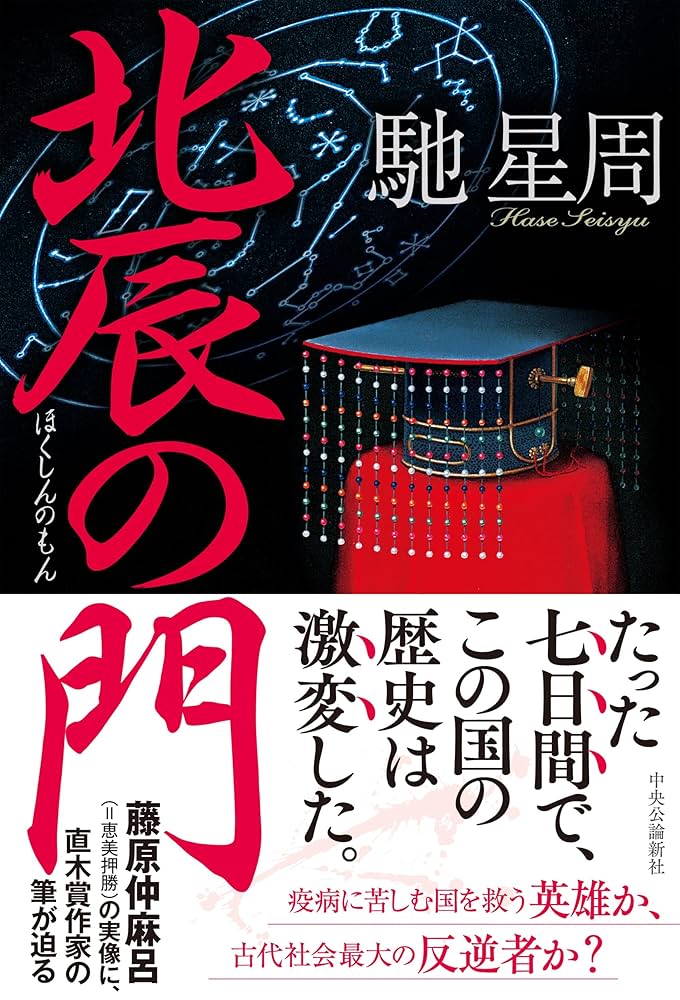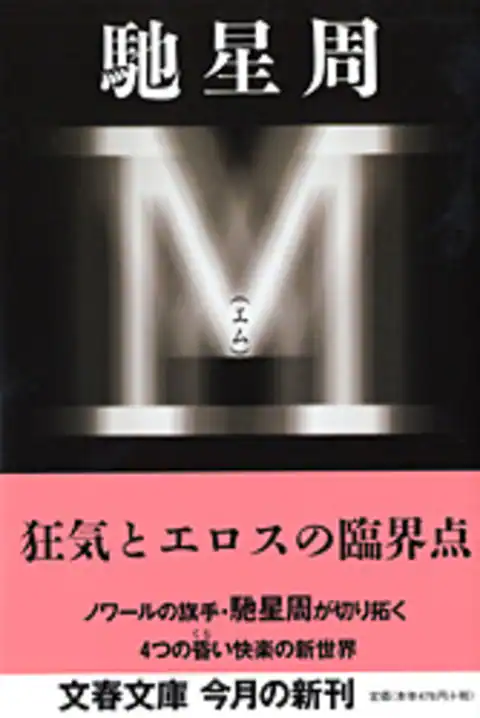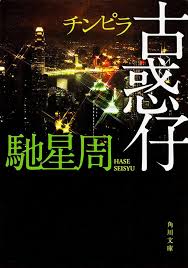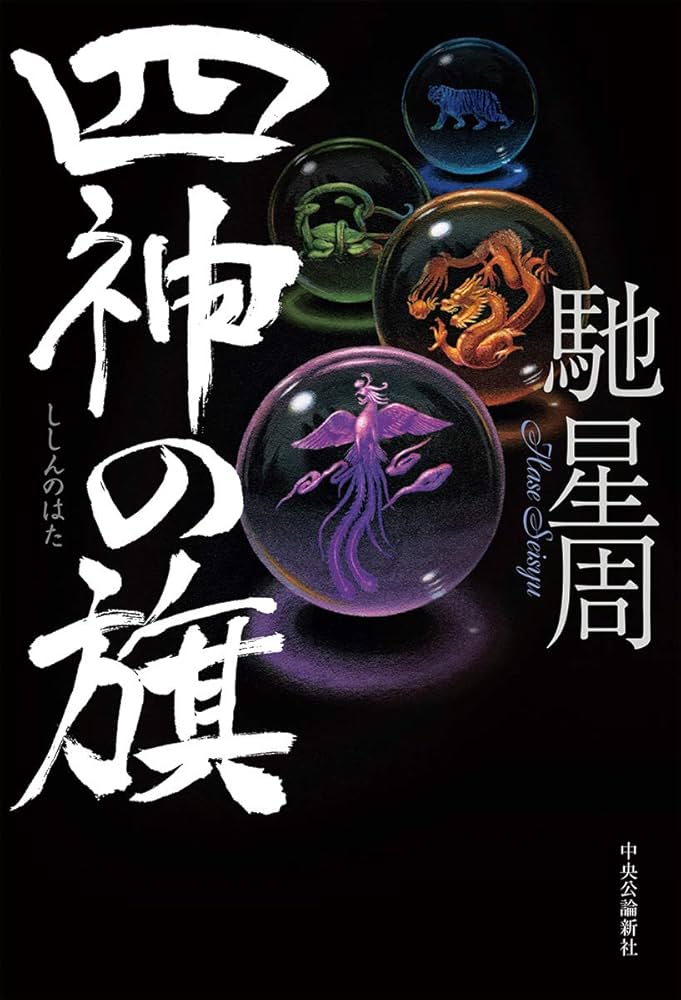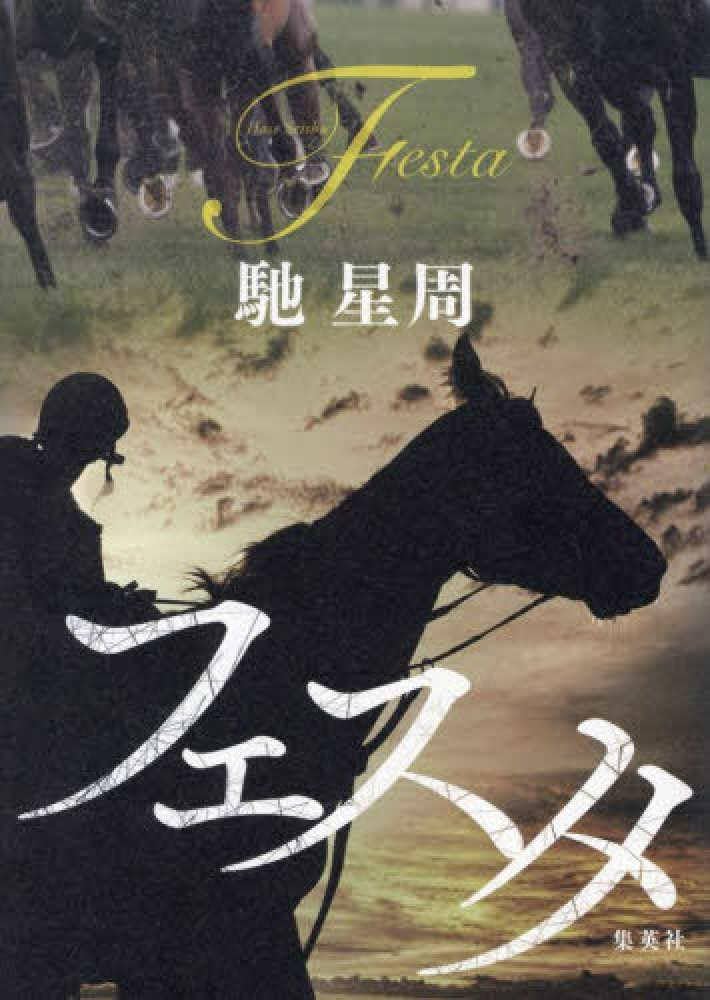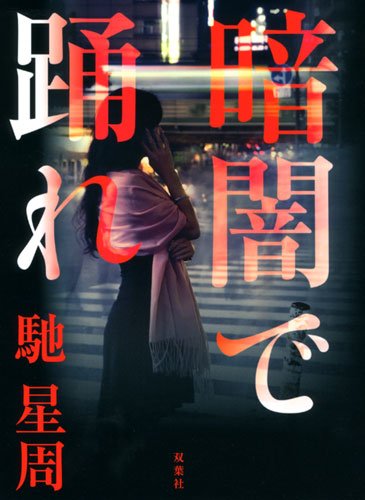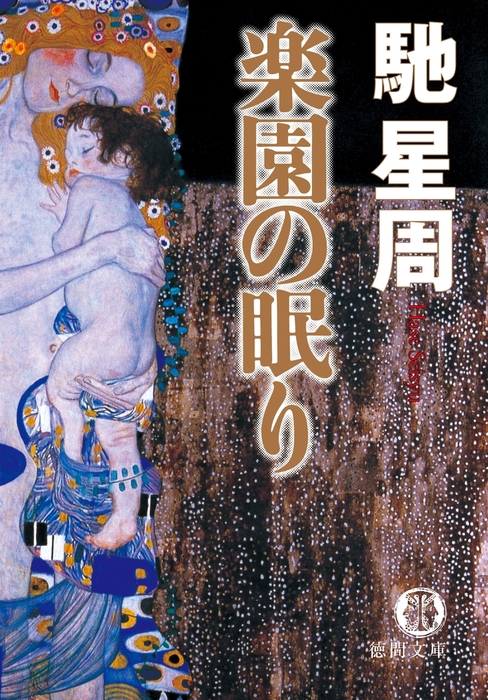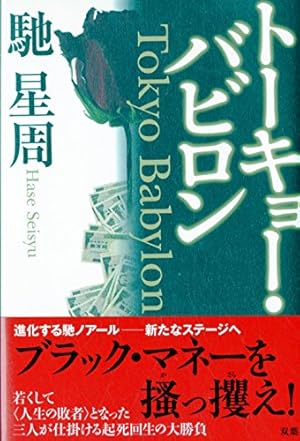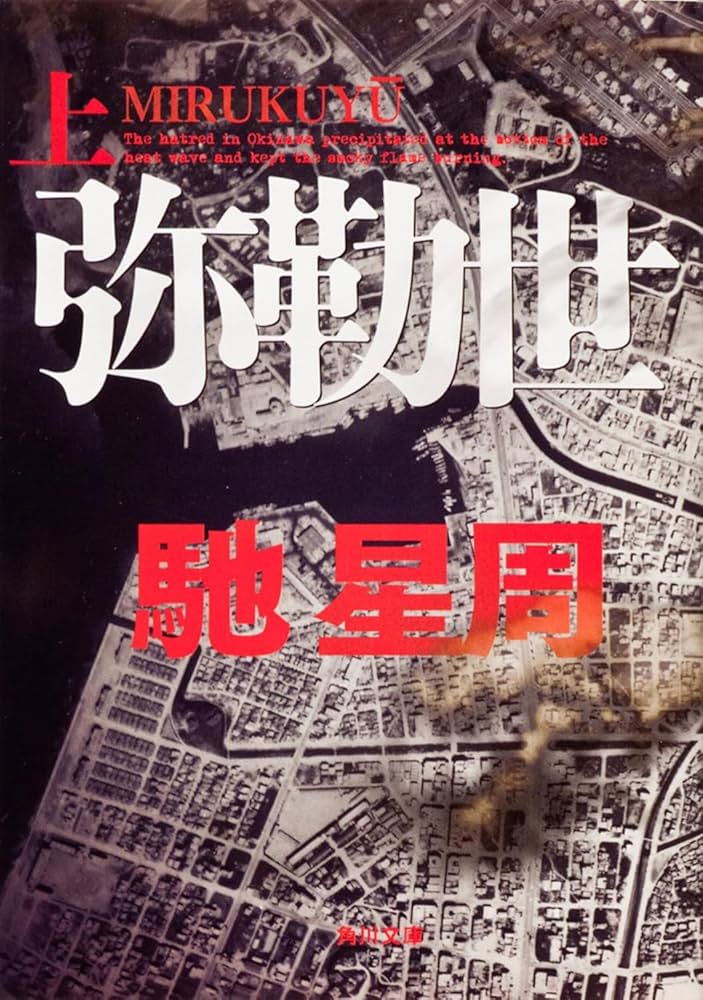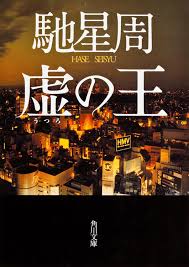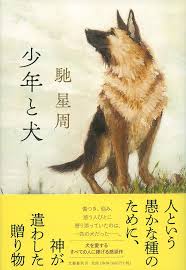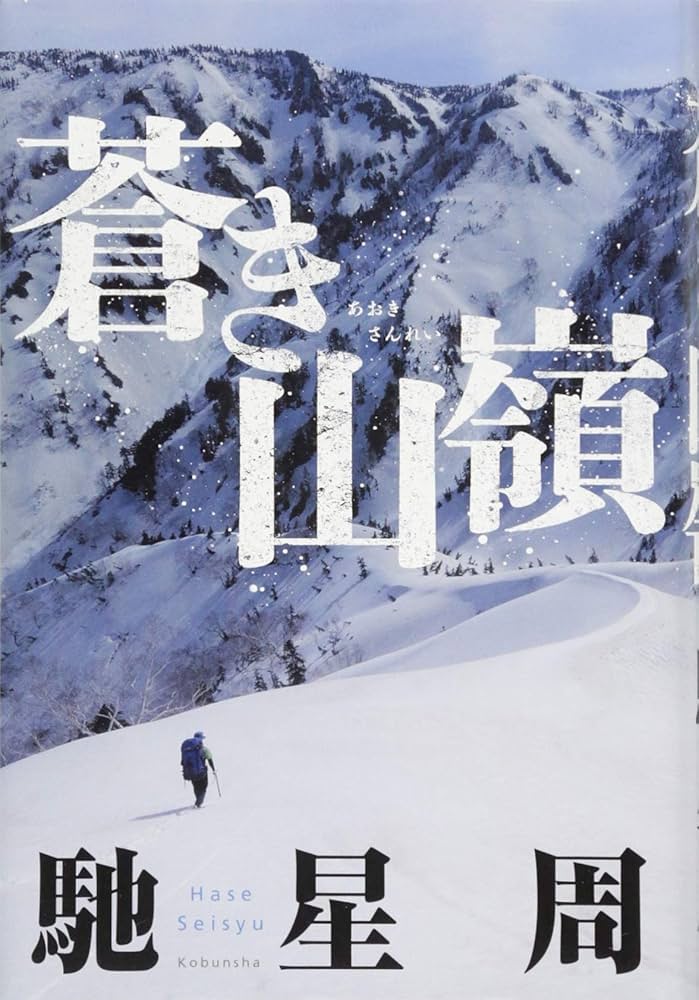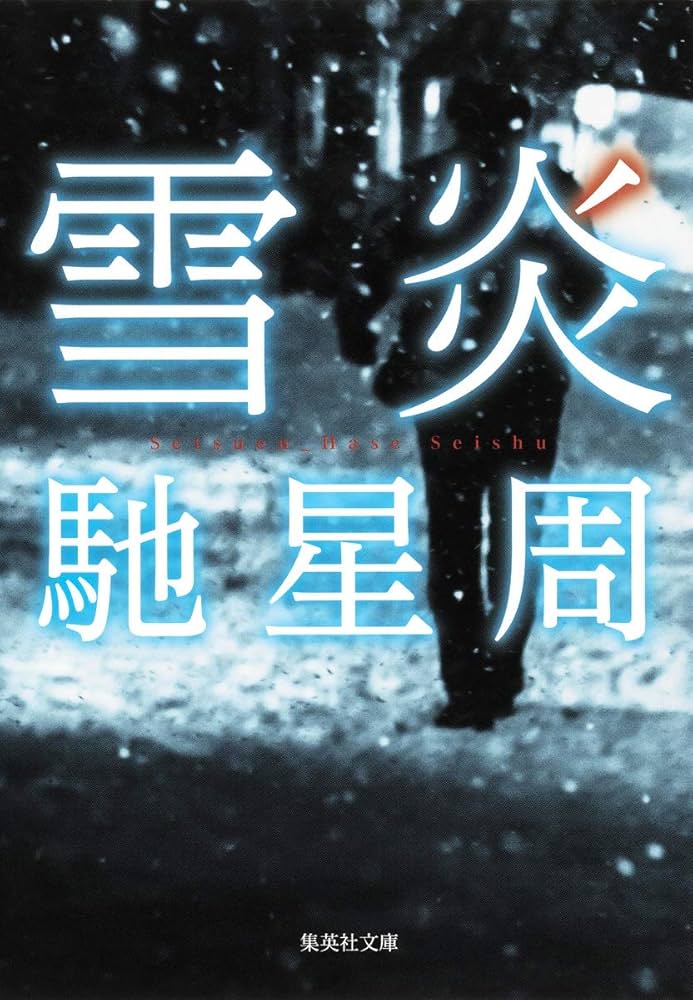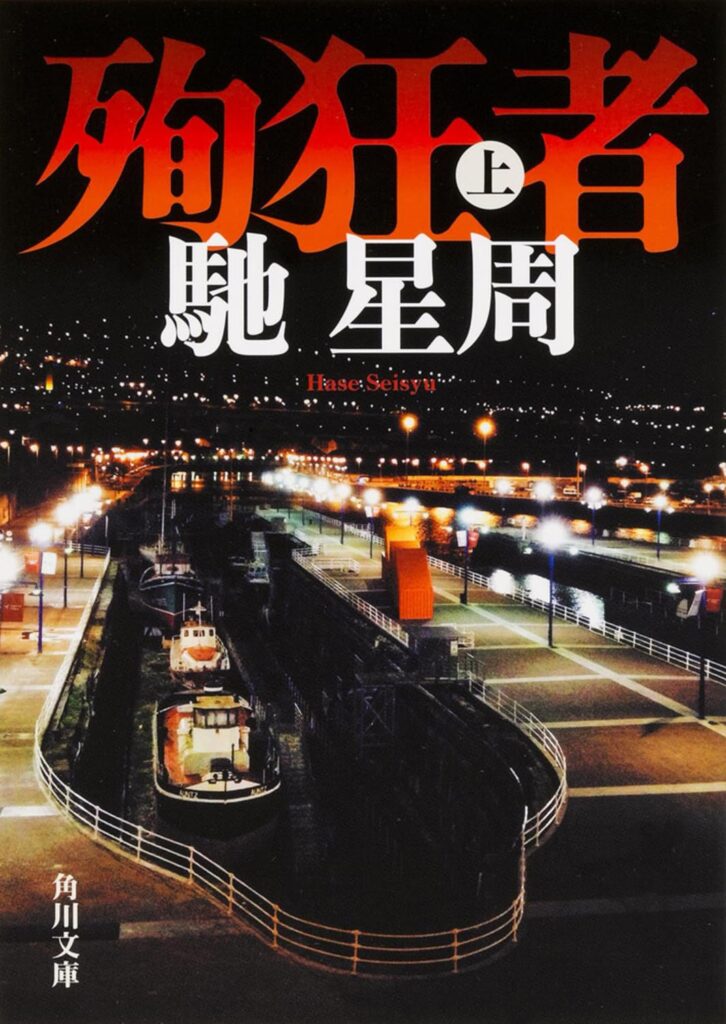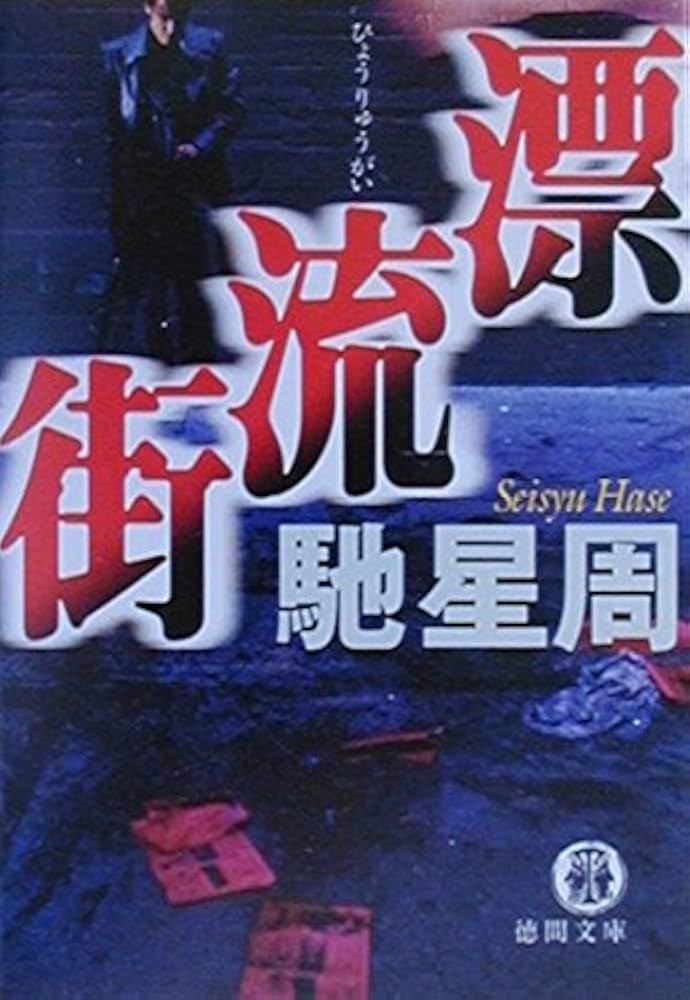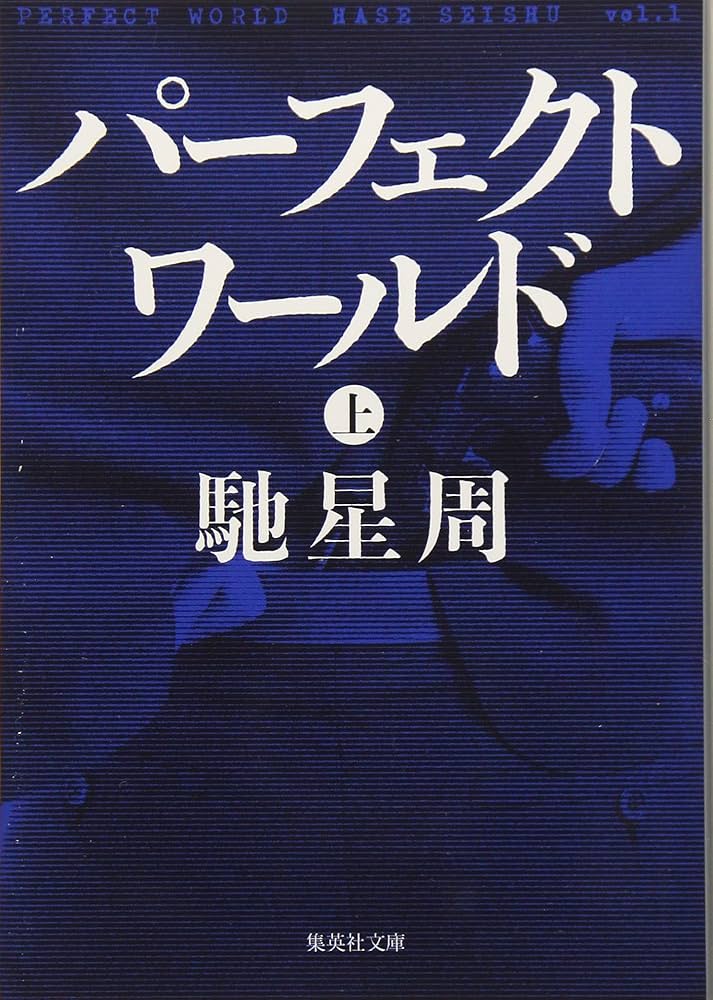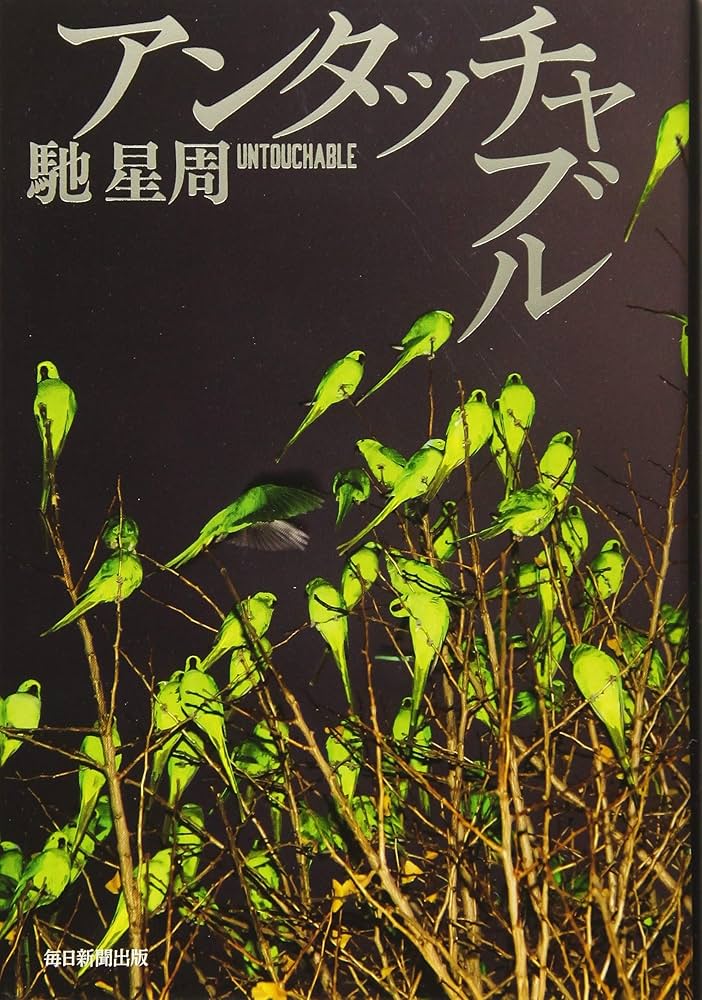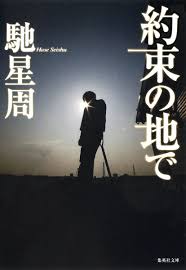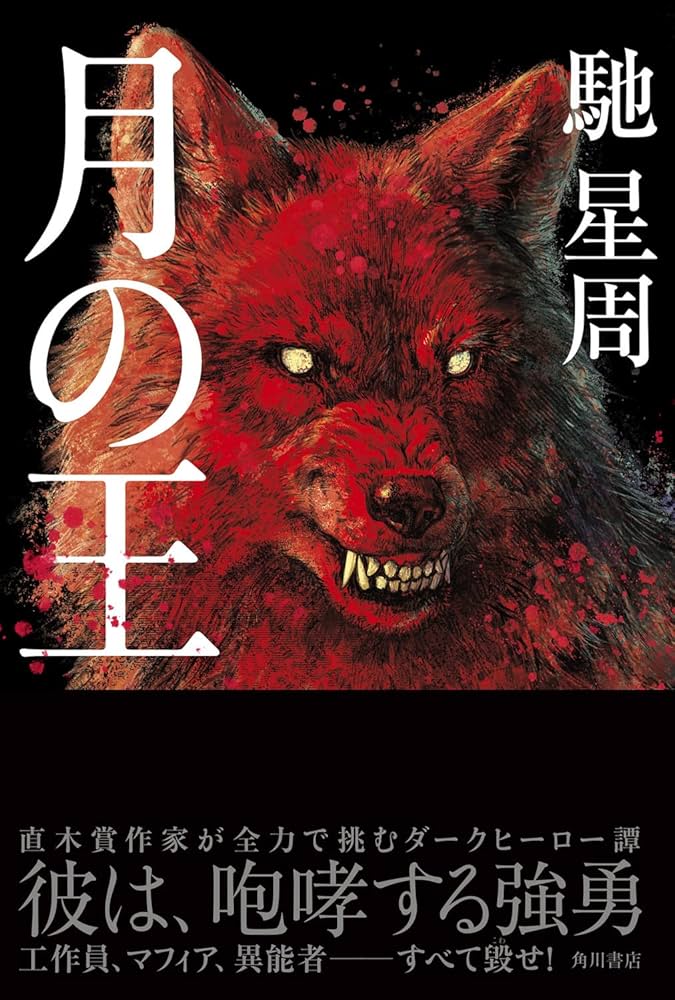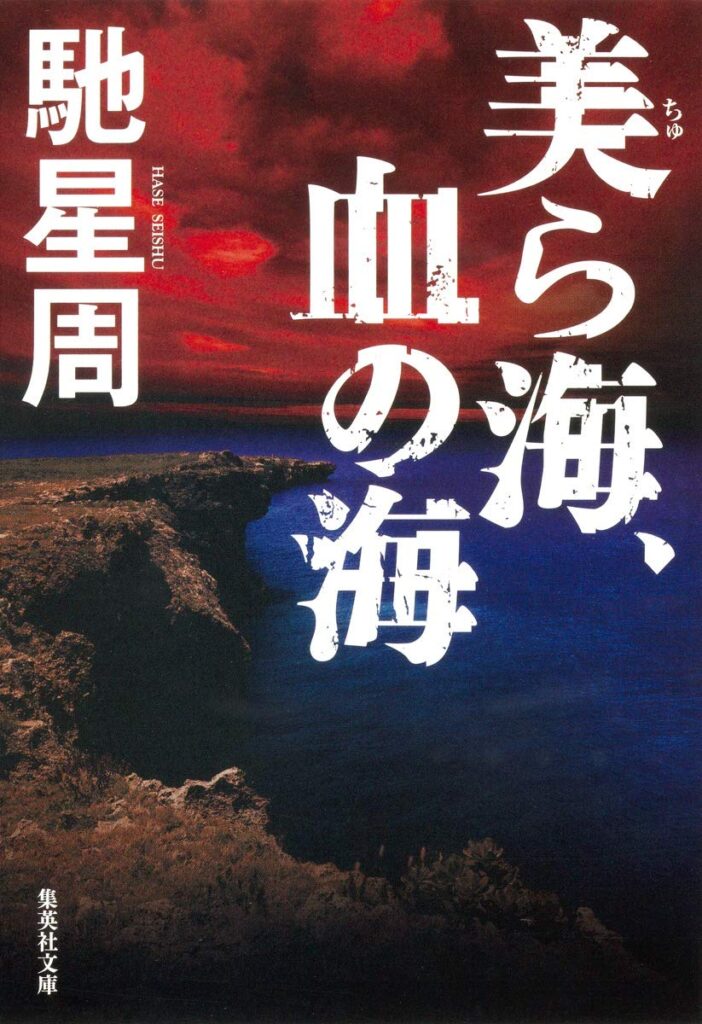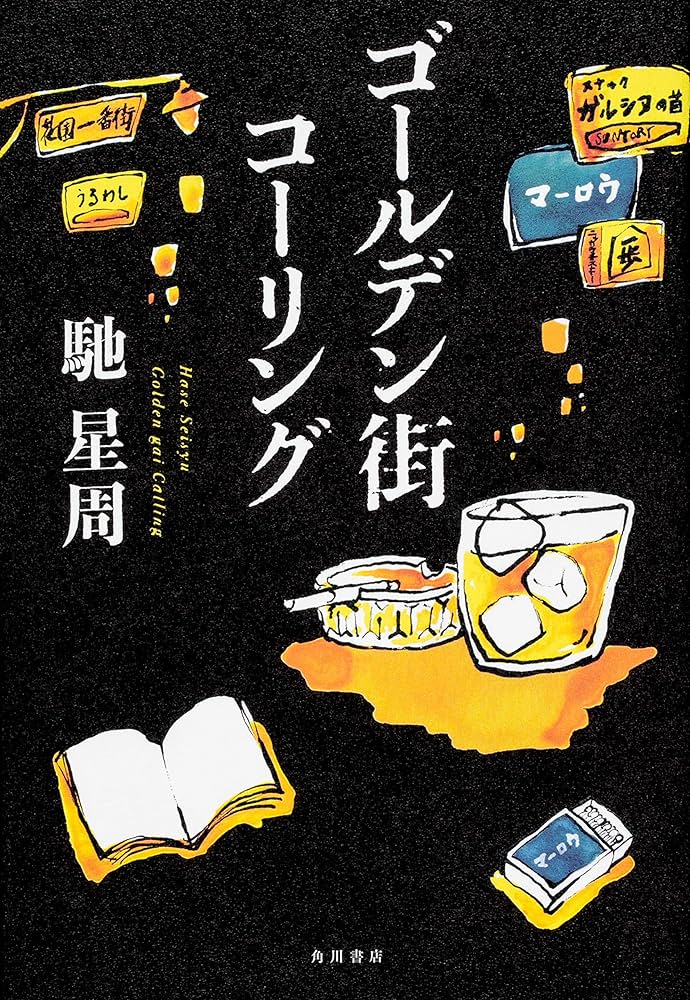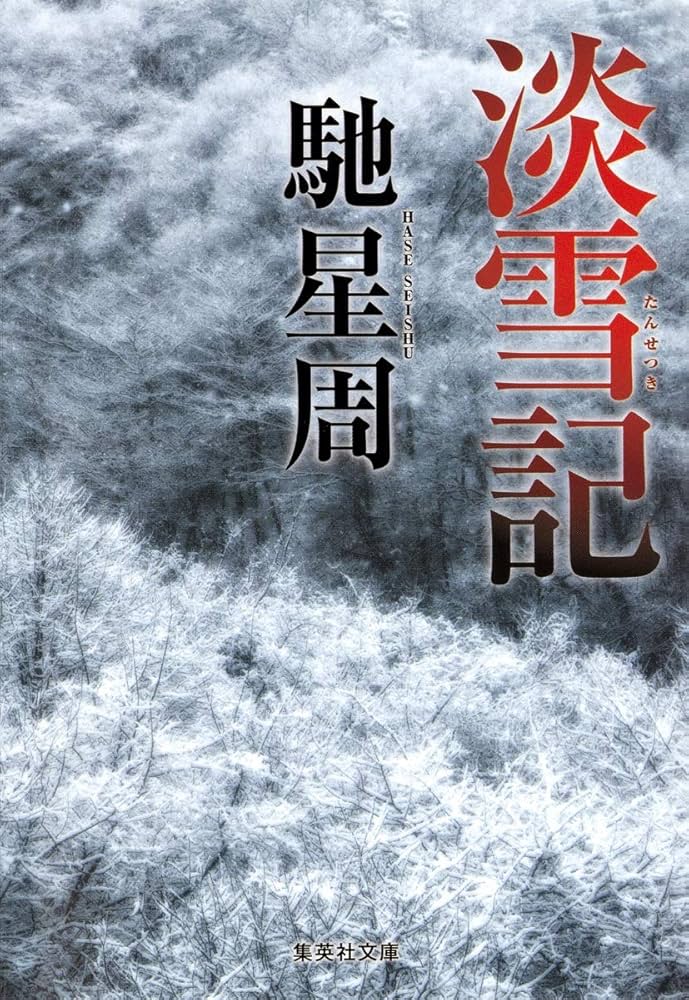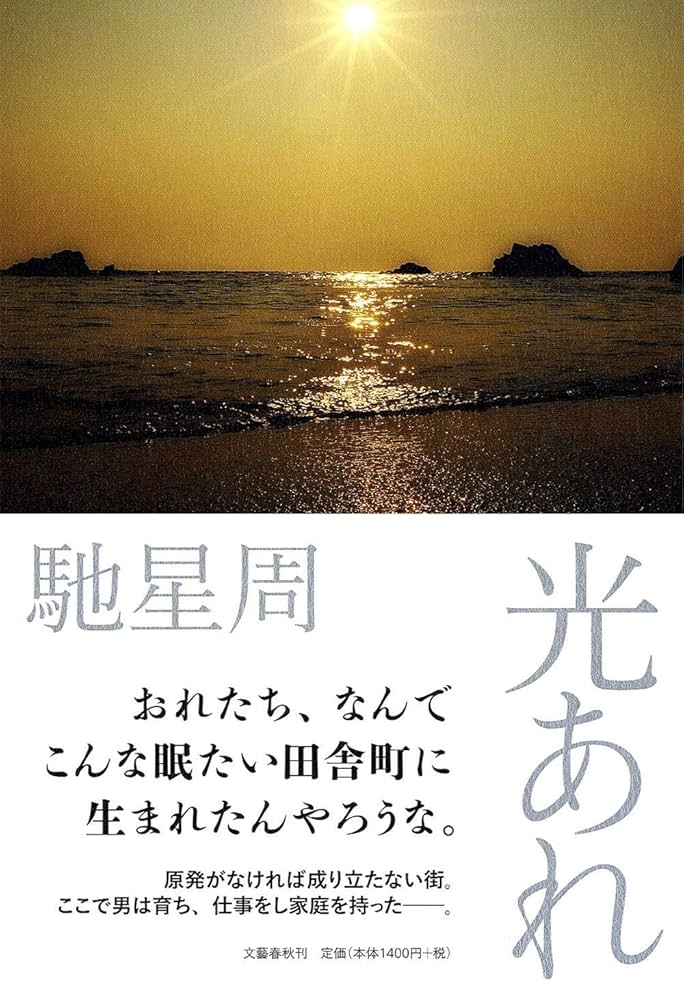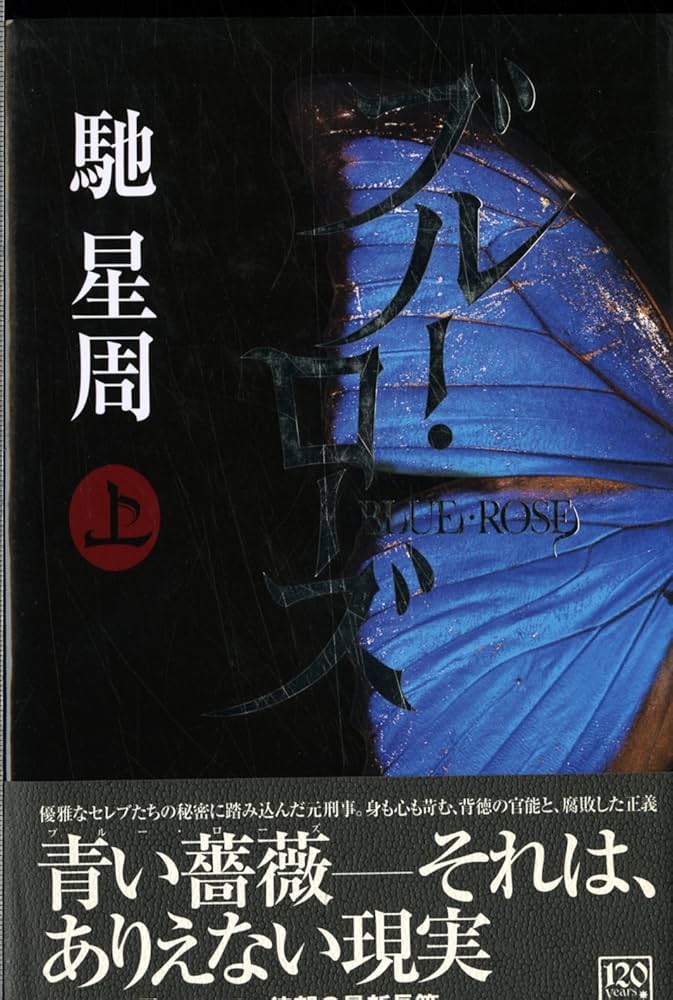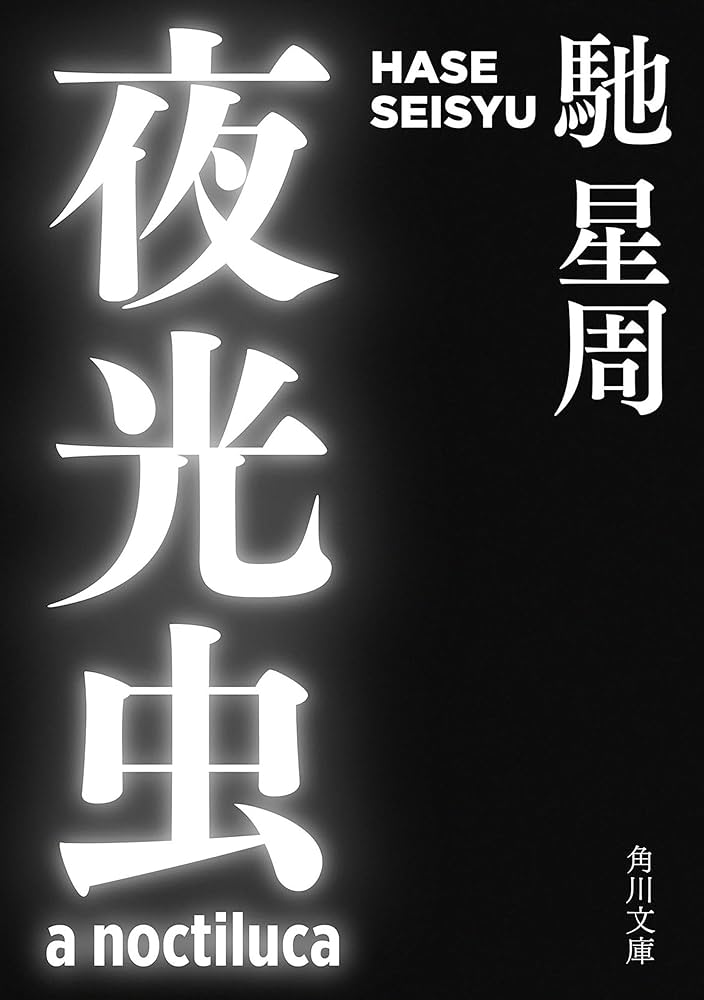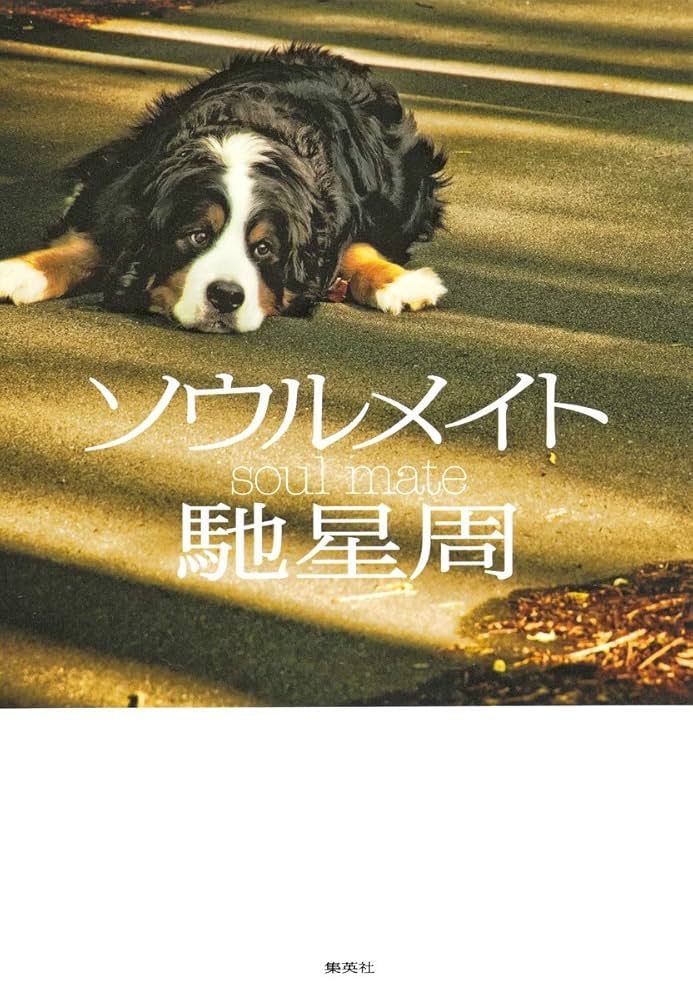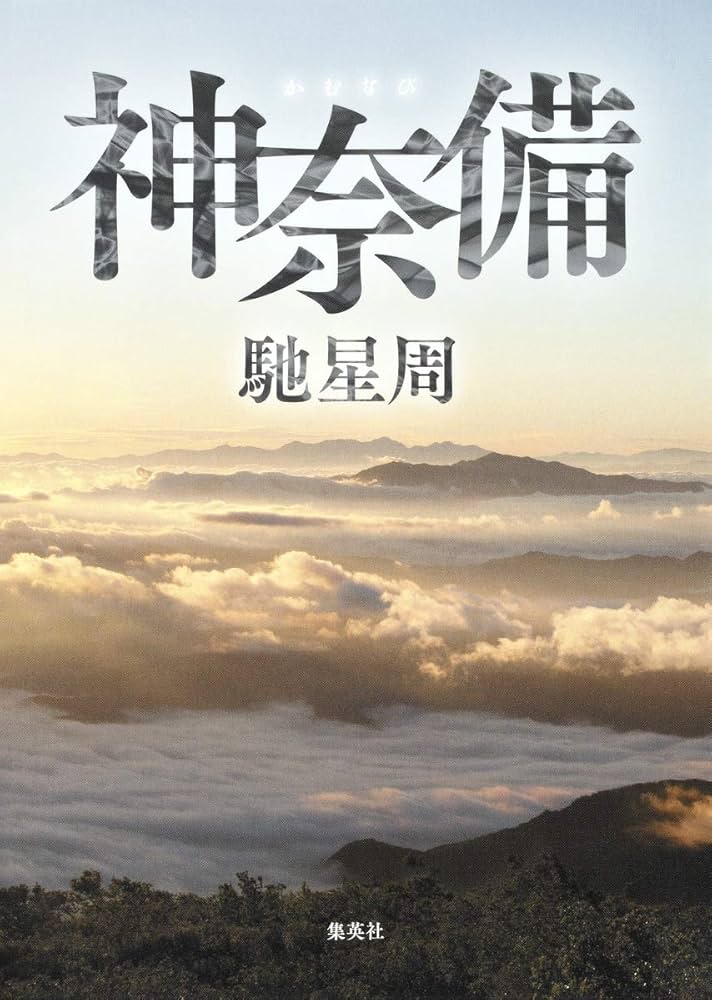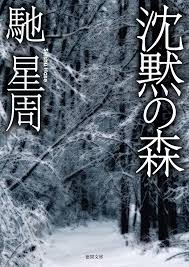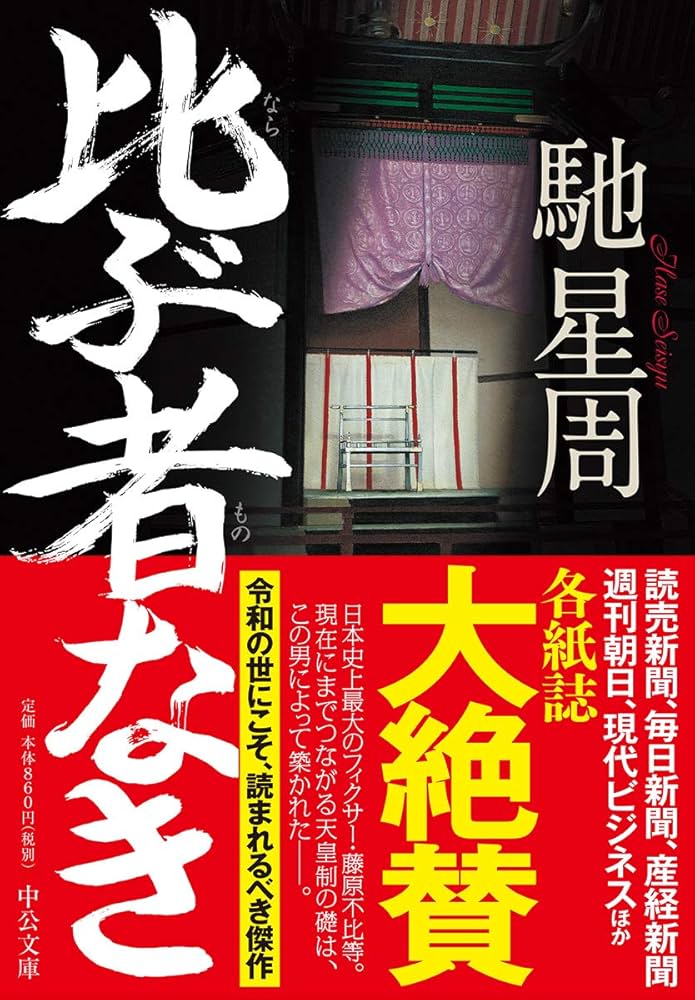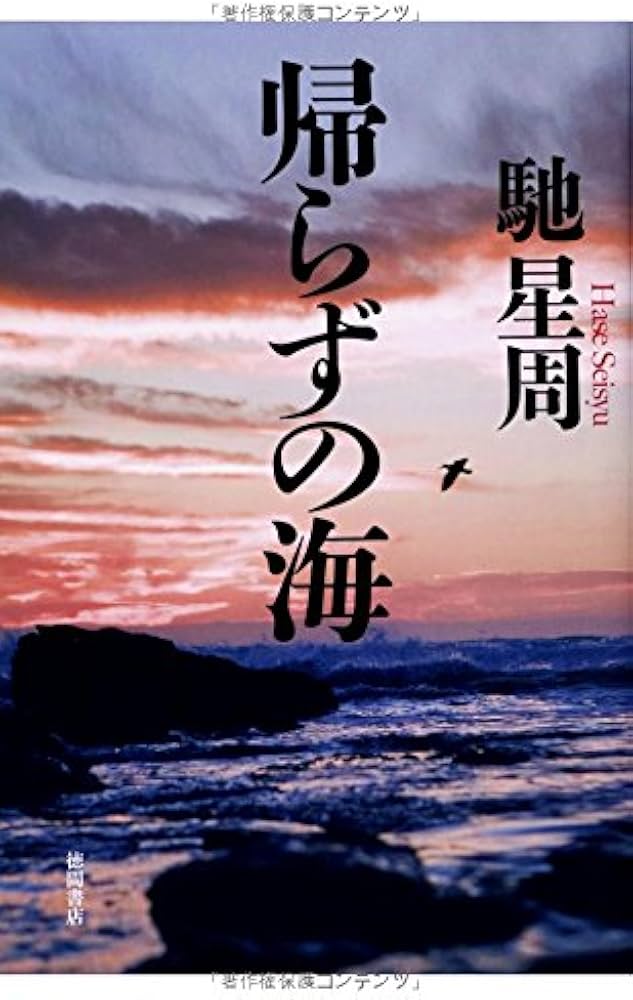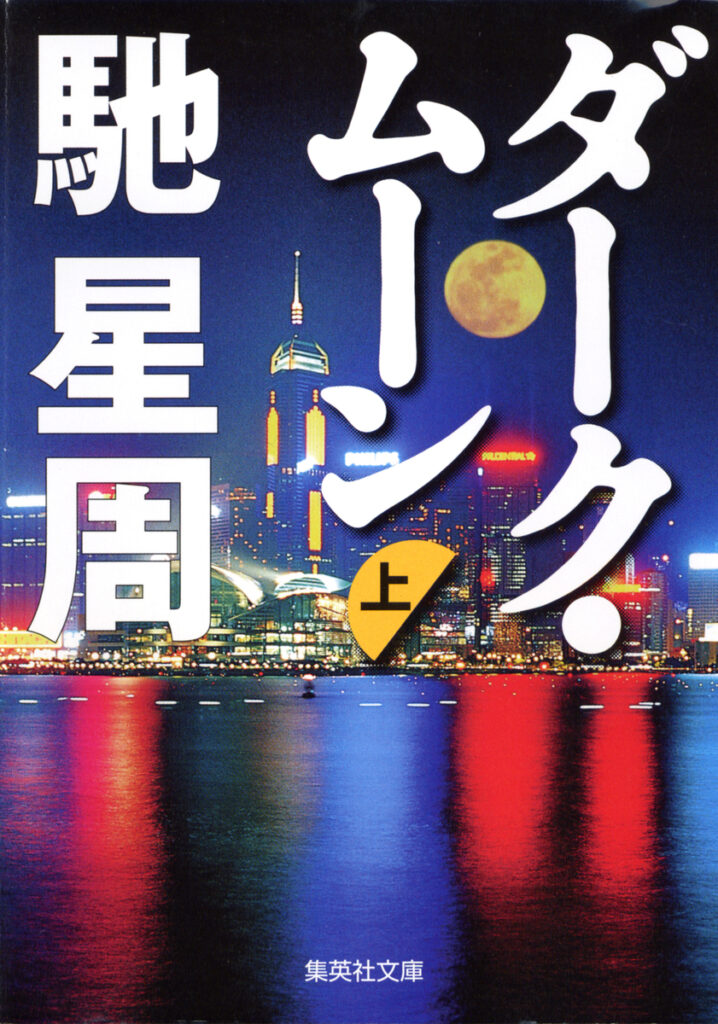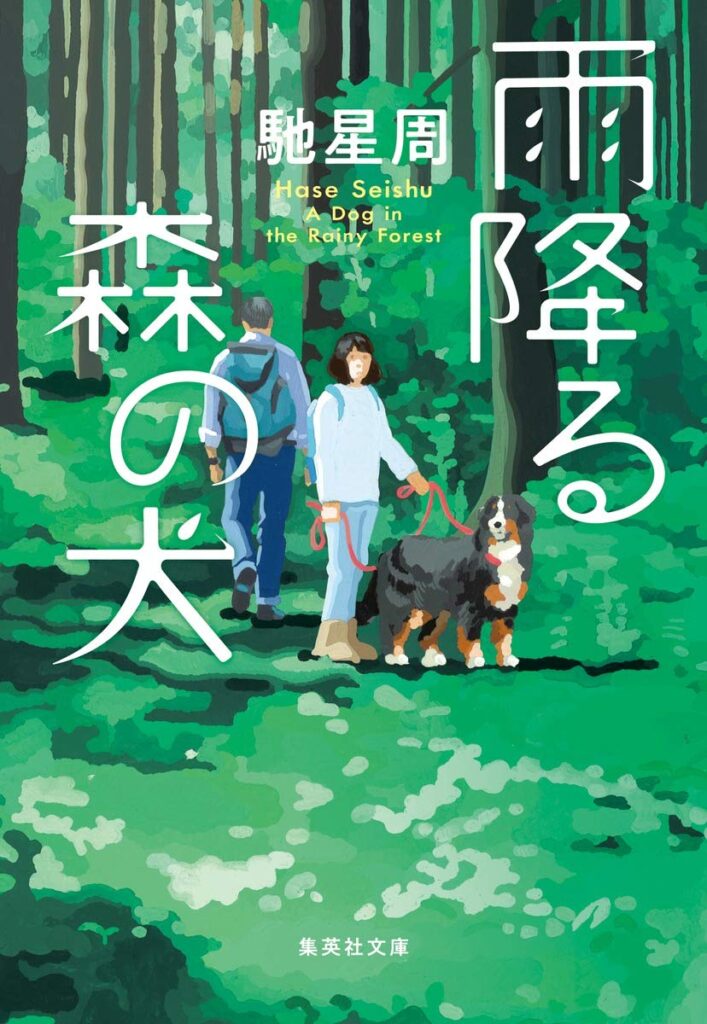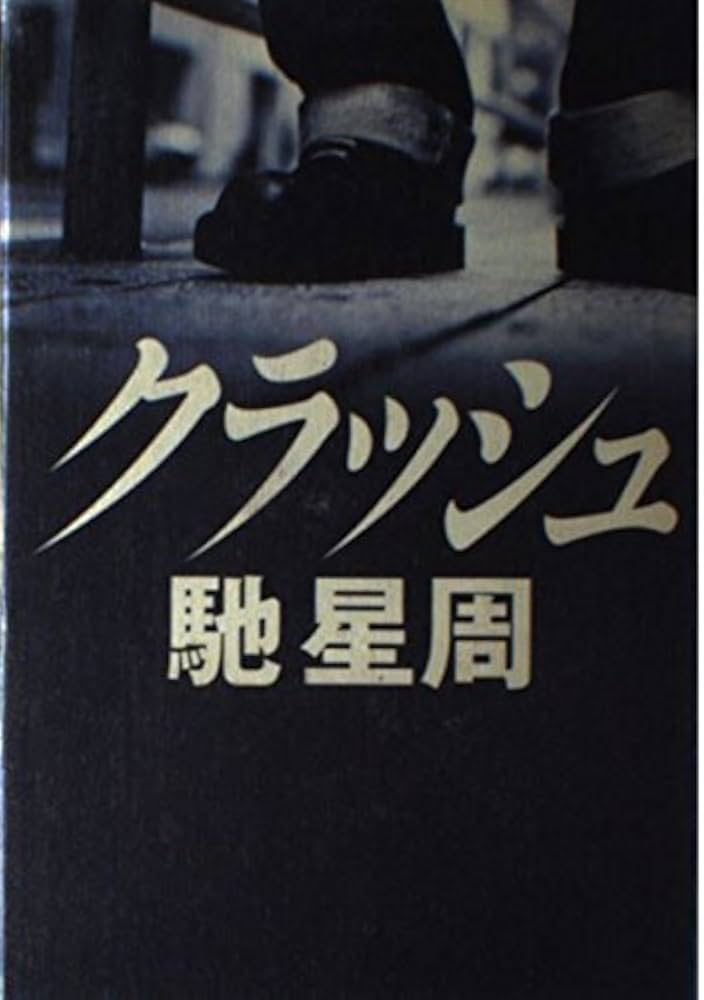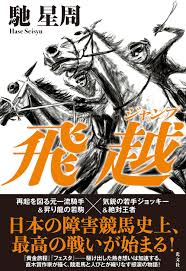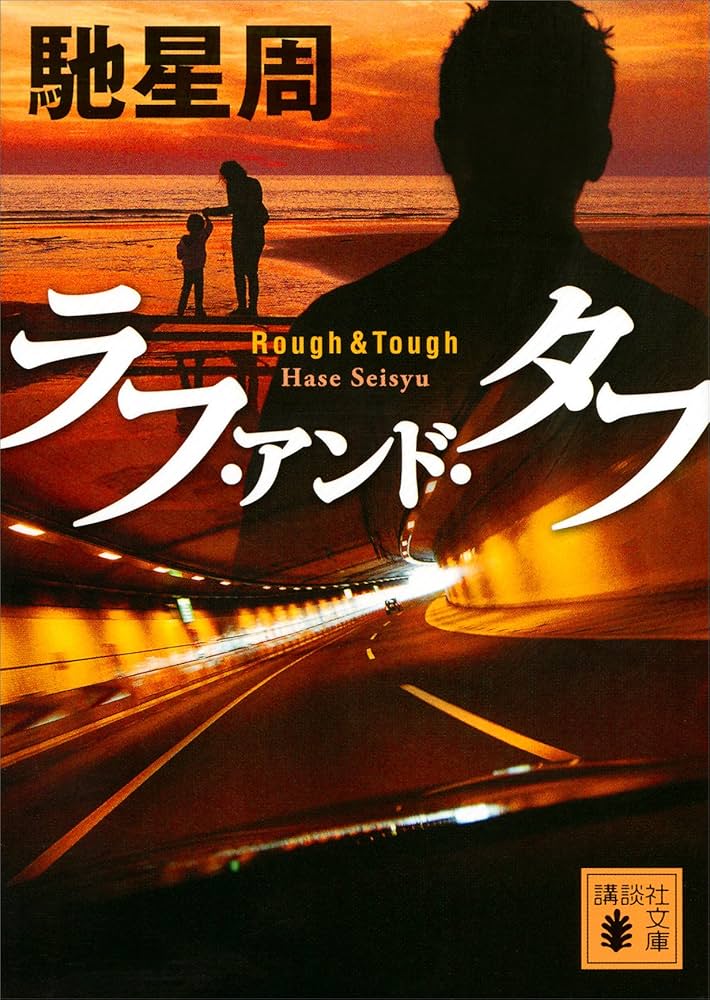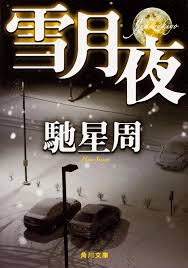 小説「雪月夜」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「雪月夜」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
本書は、馳星周さんが描く物語の中でも、特に凍てつくような絶望と、抜き差しならない人間関係の深淵を覗かせる傑作です。物語の舞台は、極寒の地、北海道根室。この閉塞した国境の町で繰り広げられる、金と裏切り、そして暴力の連鎖は、読む者の心を強く揺さぶります。
この物語の中心にいるのは、幸司と裕司という二人の男。彼らの歪んだ絆は、もはや友情などという生易しい言葉では言い表せません。憎しみ合いながらも、互いがいなければ存在できないかのような、呪いにも似た関係性。この二人の関係が、物語のすべての原動力となっています。
本記事では、このどうしようもなく救いのない物語の顛末を、結末まで含めて詳細に語っていきます。物語がどのように始まり、登場人物たちがどのように破滅へと突き進んでいくのか。そのすべてを、私の心に残った印象と共に、じっくりとお伝えしていきたいと思います。
「雪月夜」のあらすじ
主人公の内林幸司は、故郷である北海道根室で、ロシア人船員を相手にしたうだつの上がらない商売をして暮らしています。かつて抱いた夢にも破れ、今はただ息を潜めるように日々をやり過ごす彼の前に、ある日、忌まわしい過去の象徴ともいえる男が現れます。
その男の名は、山口裕司。幸司の幼馴染であり、東京でヤクザとなった彼は、圧倒的な暴力で幸司を支配してきました。裕司の突然の帰郷は、幸司の燻っていた日常に、再び暴力の匂いを持ち込みます。裕司は幸司に、一つの命令を下します。それは、彼らの共通の知り合いである敬二という男を探し出せ、というものでした。
敬二は、裕司が所属する組織から2億円という大金を横領し、この根室に逃げ込んでいるというのです。幸司は、裕司への恐怖と憎しみを抱きながらも、この命令を拒むことができません。こうして彼は、否応なく大金を巡る危険な探索に巻き込まれていくことになります。
しかし、2億円という大金の匂いは、幸司と裕司だけのものではありませんでした。地元のヤクザ、腐敗した警官、悪徳な政治家といった、町の暗部で蠢く者たちが次々とこの争奪戦に嗅ぎつけ、参入してきます。事態は、裏切りと暴力が渦巻く、血で血を洗う様相を呈していくのです。
「雪月夜」の長文感想(ネタバレあり)
この物語を読み終えたとき、心に残るのは、美しい物語に触れた後のような温かい感動ではありません。むしろ、体の芯から凍りつくような、それでいて奇妙に澄み切った静寂です。これこそが、馳星周さんの描くノワールの真髄なのだと、改めて感じ入りました。
物語の舞台である根室の描写が、まず圧巻です。吐く息は白く、肌を刺すような寒気。どこまでも続くかのような灰色の空と雪景色。この物理的な寒さが、登場人物たちの心の荒涼とした風景と完璧に重なり合います。彼らはこの町から出たくても出られない。経済的にも、精神的にも、この凍てついた土地に縛り付けられています。この閉塞感が、物語全体を支配する逃れられない運命の予感として、ずっと低く響き渡っています。
そして、この物語の心臓部ともいえるのが、幸司と裕司の関係です。幸司は、裕司の暴力に怯え、彼を憎みながらも、その支配から決して逃れようとしません。いや、できないのです。一方の裕司も、幸司を暴力で支配することでしか、彼との繋がりを確かめられないかのようです。彼らの間にあるのは、依存と憎悪が表裏一体となった、呪縛そのものです。
作中で繰り返される「裕司は幸司を殴る。幸司は裕司に嘘をつく」という一節は、彼らの関係性のすべてを物語っています。物理的な力でねじ伏せようとする裕司と、唯一の武器である「嘘」で対抗しようとする幸司。しかし、幸司のつく嘘は、その場しのぎにしかならず、結局はさらに深い泥沼へと自らを追い込んでいきます。この二人の姿は、まるで互いを映す合わせ鏡のようで、見ていて痛々しく、そして目が離せなくなります。
物語を動かすきっかけとなるのは、2億円という大金です。しかし、読み進めていくうちに、この金自体には大した意味がないのだと気づかされます。金は、登場人物たちの心の奥底に眠っていた欲望や暴力性を解き放つための、単なる触媒に過ぎません。彼らは金が欲しいのではなく、もしかすると、すべてを破壊し、破滅するための口実が欲しかっただけなのかもしれない、とさえ思えてきます。
敬二が横領した大金を巡って、根室のハイエナたちが動き出す場面は、この物語のもう一つの見どころです。地元のヤクザ、警察官、市会議員。本来であれば対立するはずの立場である彼らが、金の前では善悪の区別なく、ただ己の欲望のために牙を剥きます。ここには、社会のシステムそのものが内包する腐敗が、根室という小さな町をモデルケースとして、赤裸々に描き出されています。
この裏切りの連鎖の中で、主人公である幸司の内面も、少しずつ、しかし確実に変貌していきます。最初は裕司の暴力にただ耐えるだけだった彼が、自らも暴力の世界に足を踏み入れていくのです。極限状態に置かれた人間が、いかにして倫理観を麻痺させ、獣のようになっていくのか。その過程の描写は、凄まじいものがあります。
幸司が、自分を陥れた者たちに対して「おまえらみんな呪われろ」と吐き捨てる場面は、彼の変貌を象徴する重要な転換点です。それは、彼がそれまで保っていた、か細い理性の糸がぷつりと切れた瞬間であり、自らが破滅の世界の住人であることを受け入れた宣言のようにも聞こえました。もはや彼は、かつての気弱な男ではありません。
物語のクライマックス、雪原で繰り広げられる最終決戦は、まさに圧巻の一言です。生き残った全ての登場人物が一堂に会し、最後の奪い合いを始めます。しかし、そこに戦略や交渉といった駆け引きはもはや存在しません。あるのは、剥き出しの暴力と殺意だけです。人々は驚くほどあっけなく、そして無意味に死んでいきます。
この凄惨な殺戮の場面を読みながら、私は奇妙な虚しさを感じていました。あれほどまでに求められた2億円は、一体何だったのか。多くの命が失われ、雪原が血に染まっていく中で、金の価値は完全に失われ、ただの紙切れの塊となっていきます。この徹底したニヒリズムこそが、この物語が到達した一つの境地なのでしょう。
そして、他のすべての登場人物が舞台から消え去った後、雪原に残されるのは、やはり幸司と裕司の二人だけです。物語は、始まったときと同じように、この二人の関係へと帰着します。彼らの二十年以上にわたる歪んだ関係に、ここでようやく終止符が打たれるのです。
その結末は、決してどちらかが勝利し、生き残るというものではありません。彼らは、互いを滅ぼし合うことでしか、この呪縛から解放されることはないのです。共に死ぬこと。それだけが、彼らに残された唯一の道でした。この結末は、悲しいというよりも、むしろ必然であったと感じられます。彼らは、こうなるべくして生きてきたのです。
死の間際、幸司は一つの真実にたどり着きます。自分は、ずっと裕司と違う人間だと思い込もうとしてきた。しかし、本当はそうではなかった。自分と裕司は、根っこの部分で同じ存在だったのだ、と。この最後の悟りは、幸司にとって最大の絶望であり、同時に、彼が自分自身に吐き続けてきた最大の「嘘」からの解放でもあったのかもしれません。
この物語には、希望や救いは一切ありません。登場人物たちは誰一人として幸福になることなく、全員が破滅へと向かっていきます。しかし、だからこそ、人間の本質的な業や、逃れることのできない宿命といったテーマが、より純粋な形で浮かび上がってくるのです。
美しい情景を思い起こさせる「雪月夜」という題名が、この血塗られた物語に付けられているのは、非常に印象的です。静かで冷たい月が、眼下で繰り広げられる人間の愚かな争いを、ただ無感動に見下ろしている。そんな光景が目に浮かぶようです。読み終えた後、心に残るこの冷たく重い余韻こそが、「雪月夜」という作品の持つ、抗い難い魅力なのだと思います。
それは、人間の魂の最も暗い部分を、一切の感傷を排して描ききった、見事な物語です。私たちは、この物語を通して、幸司と裕司という二人の男の破滅的な人生を追体験します。そして、読み終えたとき、私たちの心にも、冷たく美しい月光に照らされた、静かな雪原が広がっているのです。
まとめ
小説「雪月夜」は、馳星周さんの真骨頂ともいえる、徹底したノワール作品でした。物語は終始、凍てつくような緊張感と絶望に満ちており、読者を息もつかせぬまま破滅的な結末へと導いていきます。
物語の核となるのは、幸司と裕司という二人の男の、憎悪と依存が絡み合った共生関係です。この歪んだ絆が、2億円という大金を巡る血なまぐさい事件を引き起こし、関わる人間すべてを不幸の渦へと巻き込んでいきます。その様は、まさに圧巻です。
安易な希望や救いを求める方には、決してお勧めできません。しかし、人間のどうしようもない業や、魂の暗部に触れるような、深淵を覗くような読書体験を求める方にとっては、これ以上ない一冊となるでしょう。
読み終えた後に残るのは、温かい感動ではなく、冷たく澄み切った静寂です。しかし、その静寂こそが、この物語の価値を何よりも雄弁に物語っています。人間の暗部を描ききった、紛れもない傑作です。