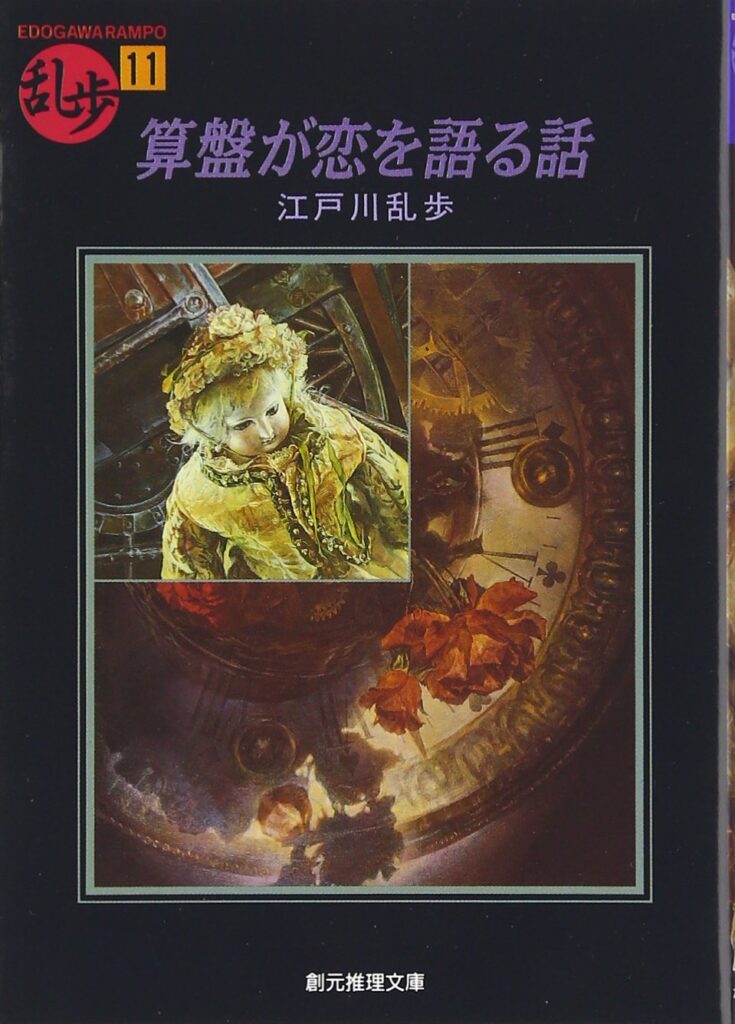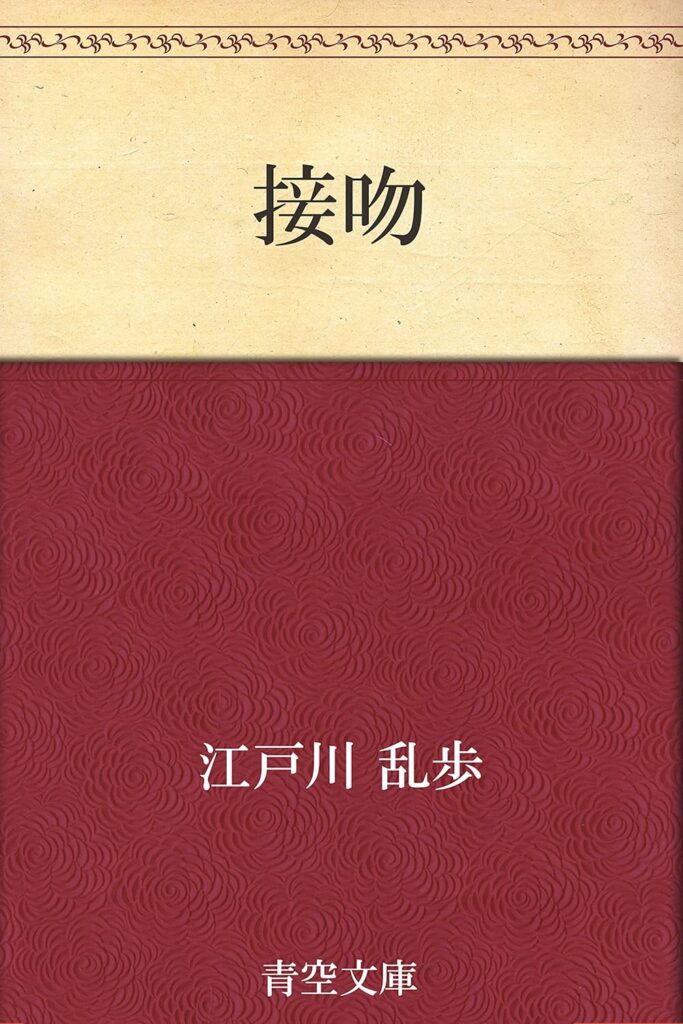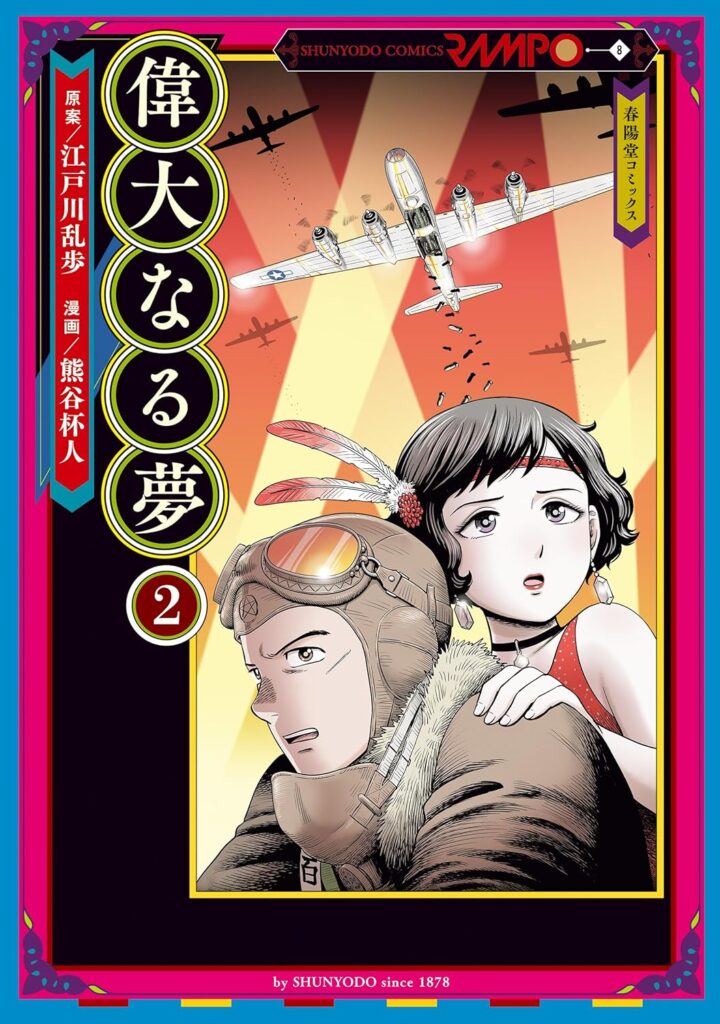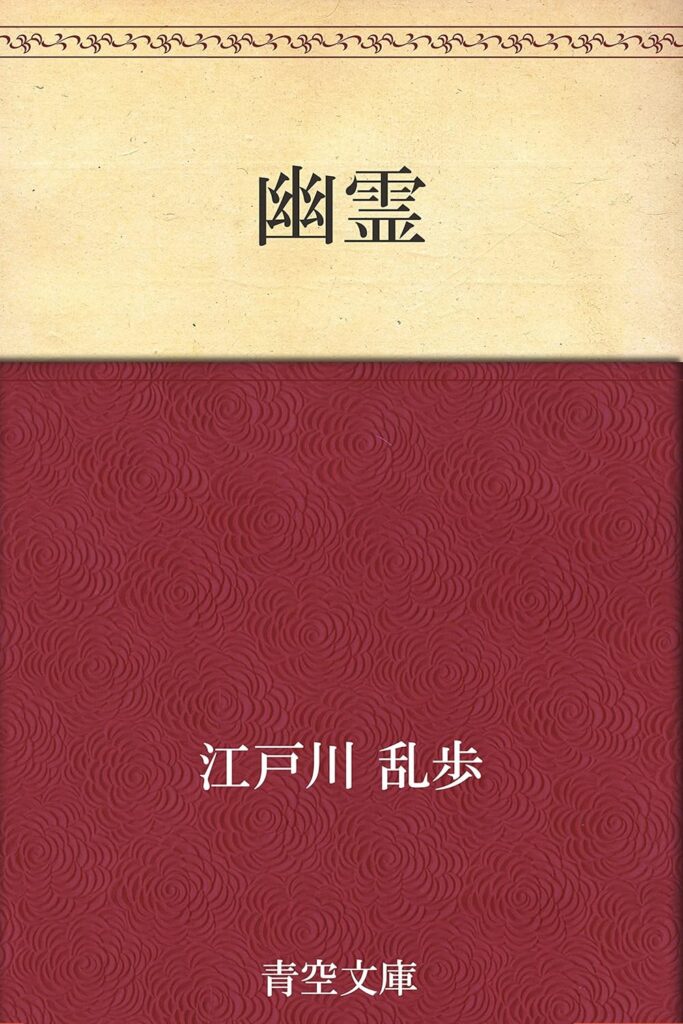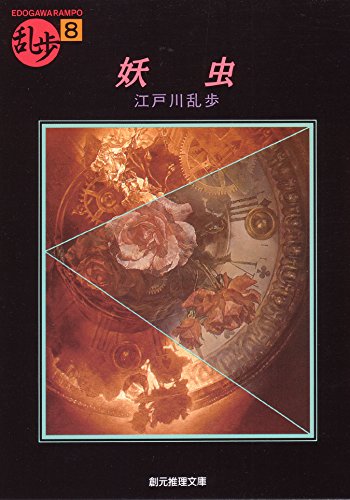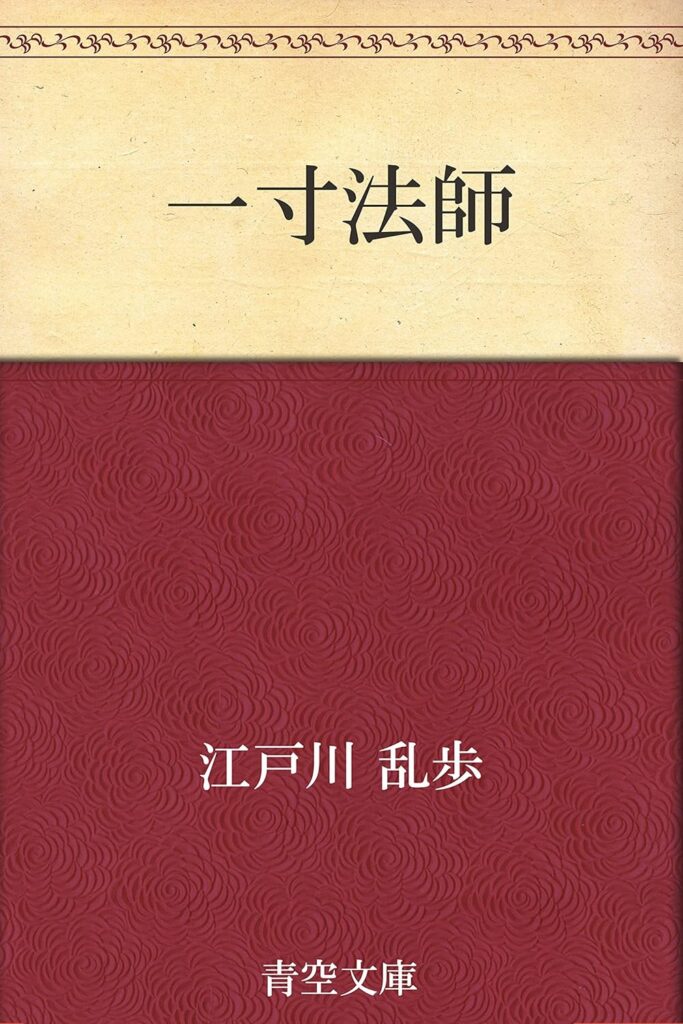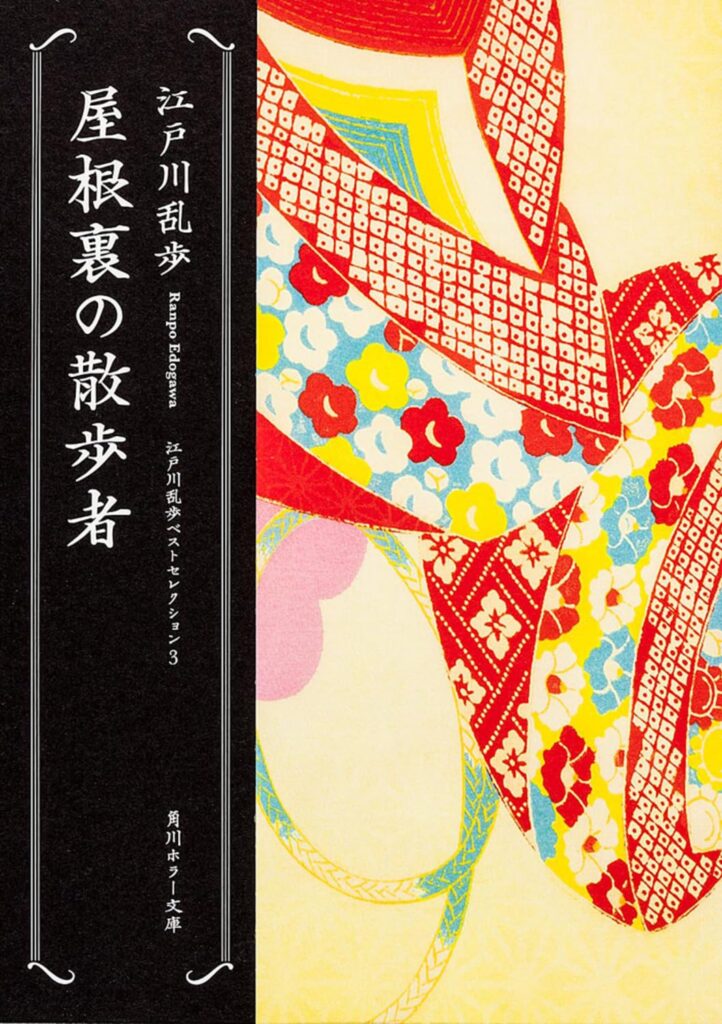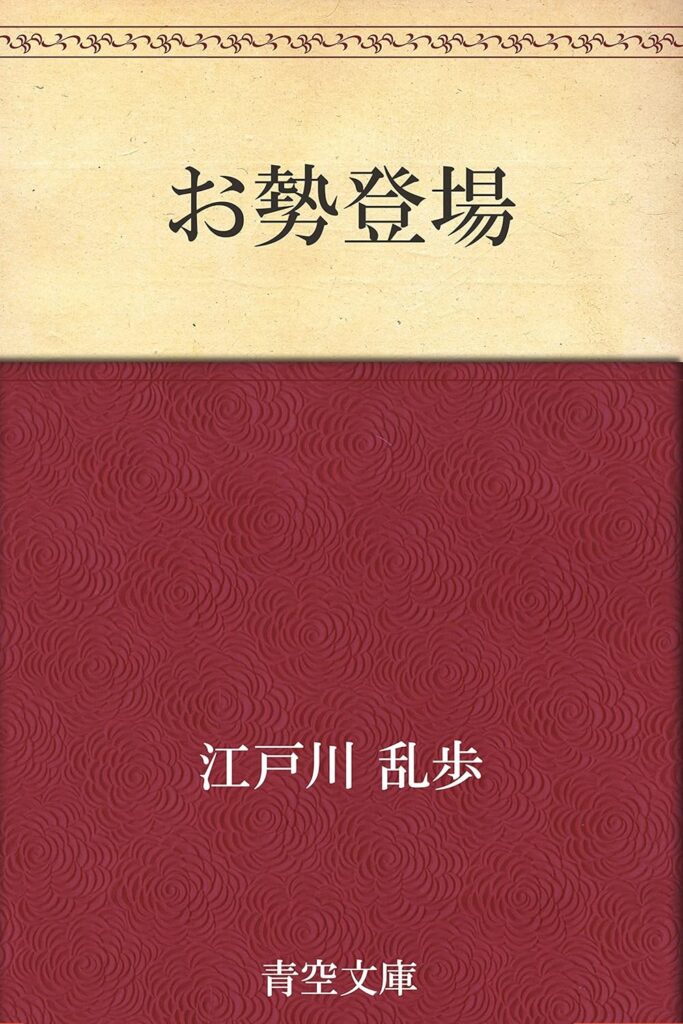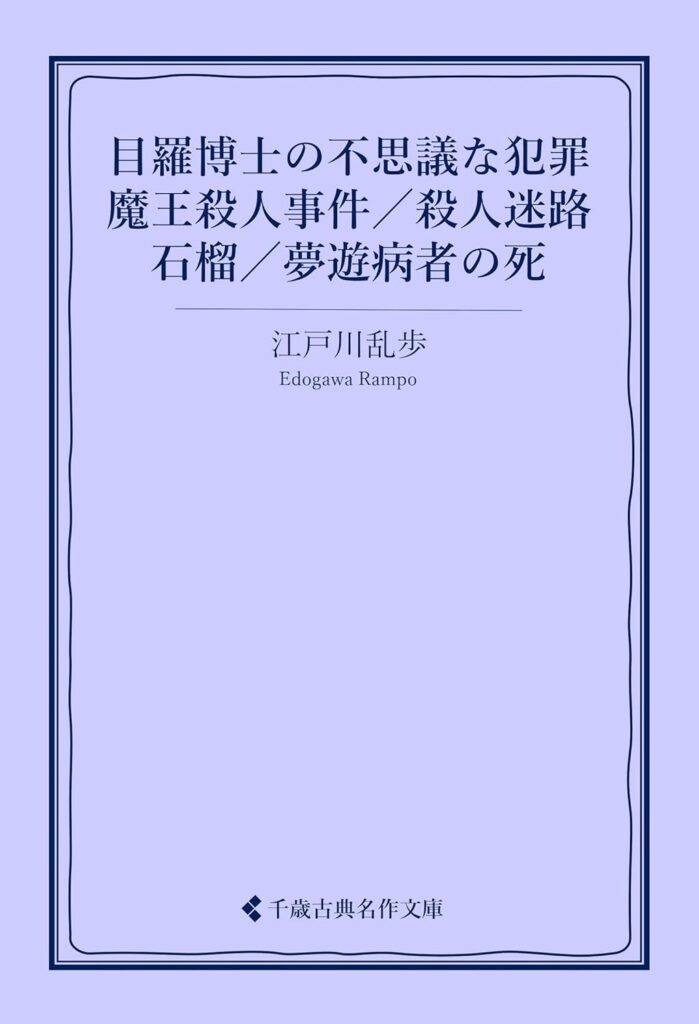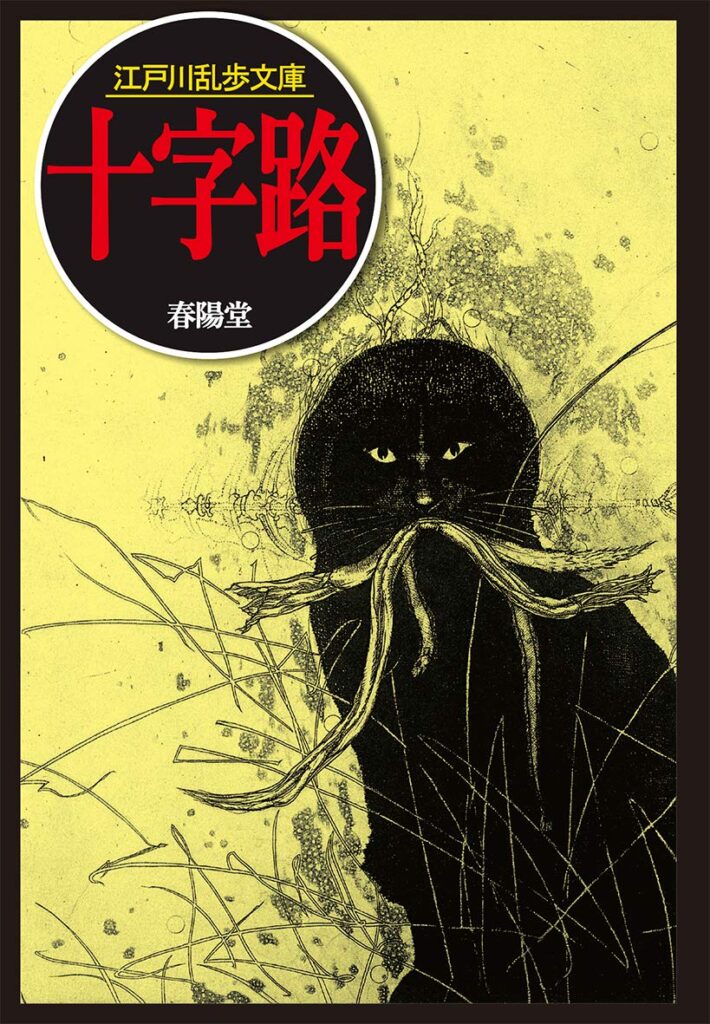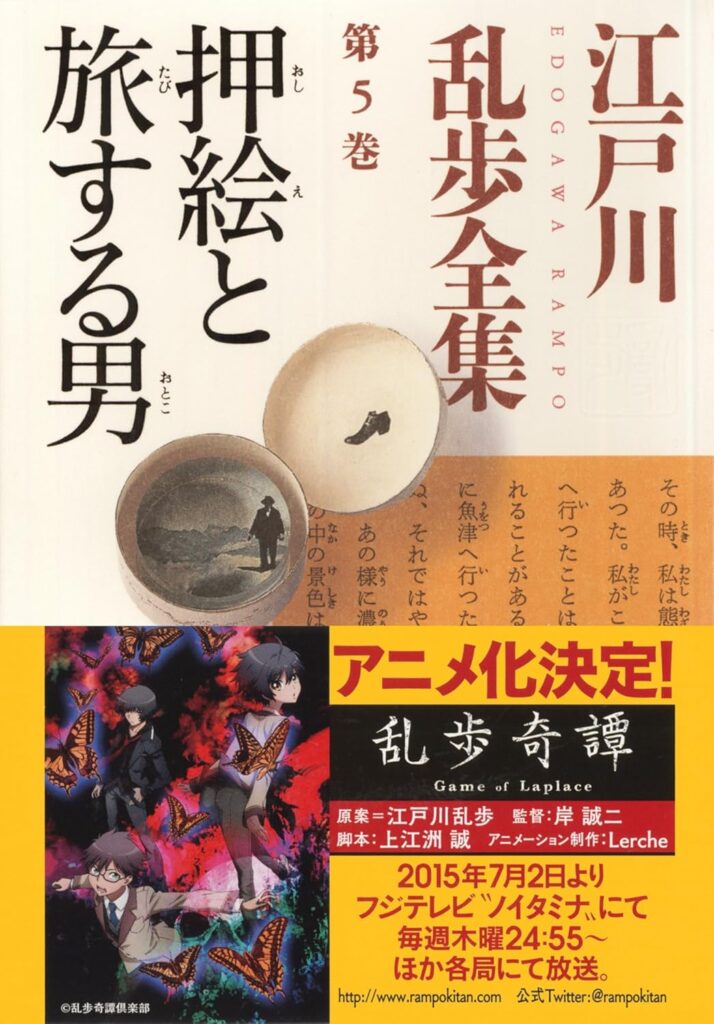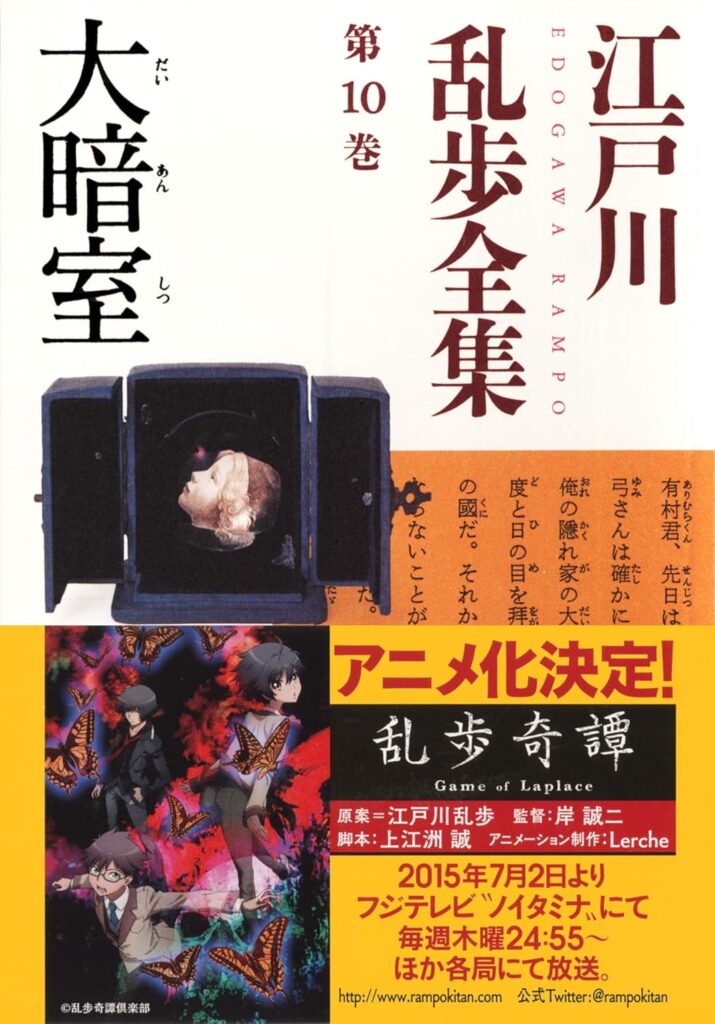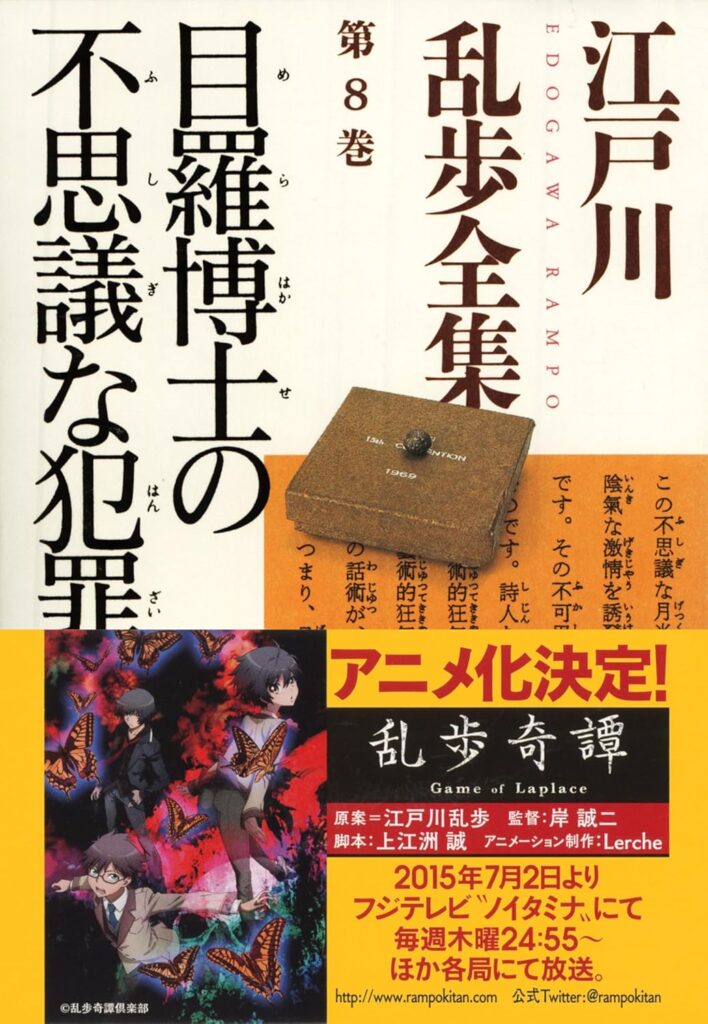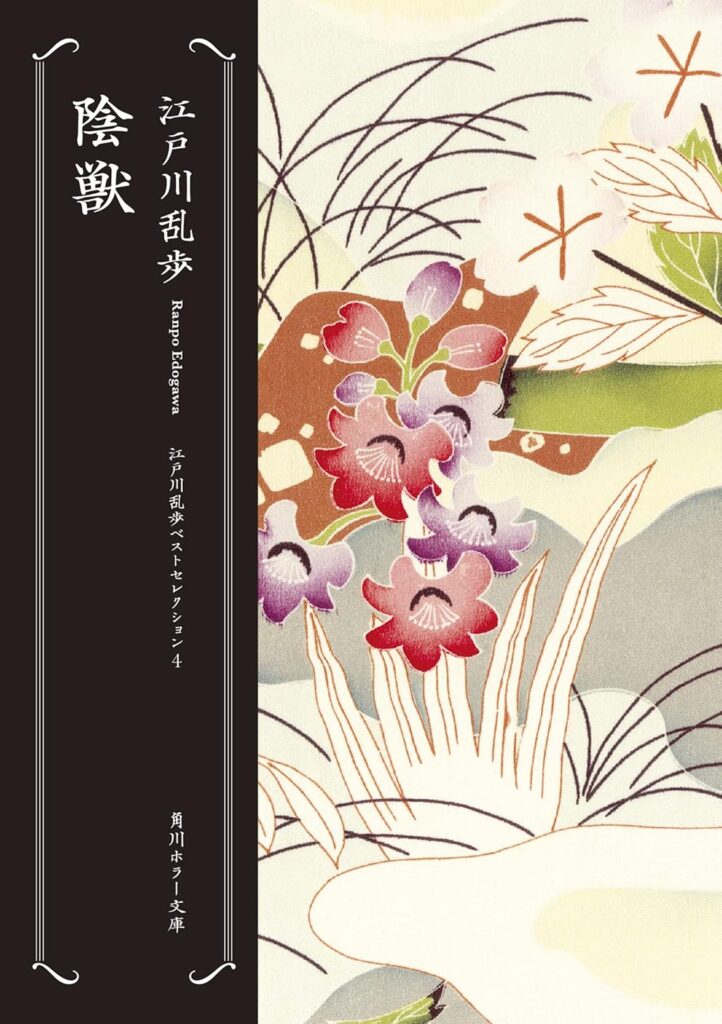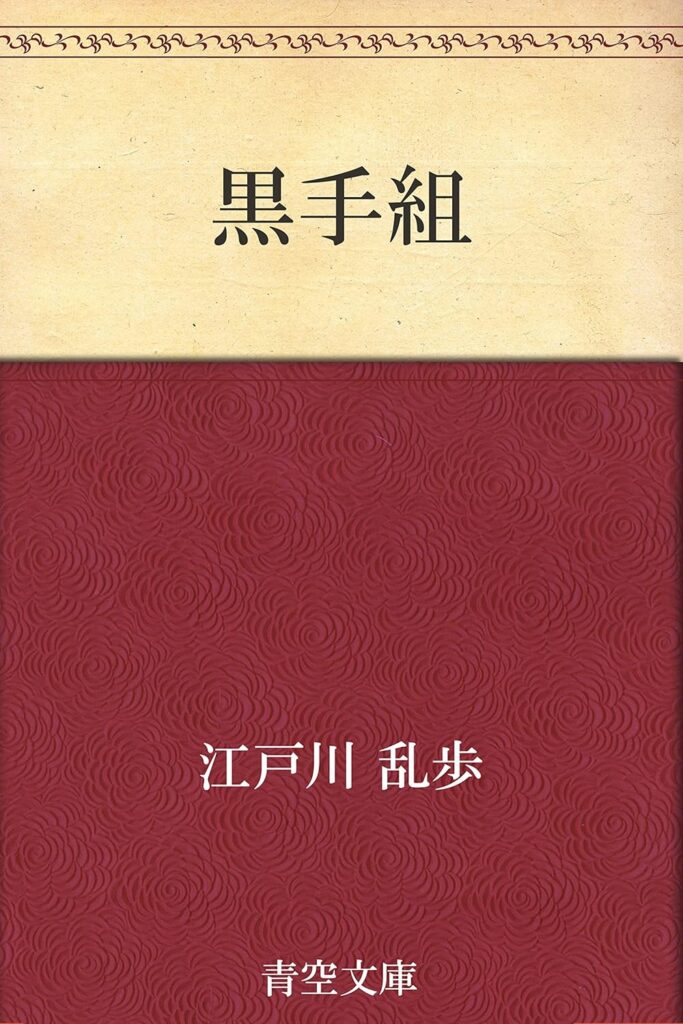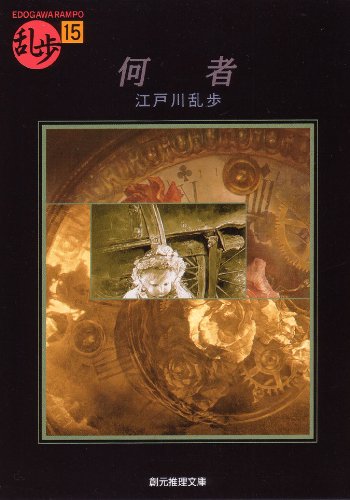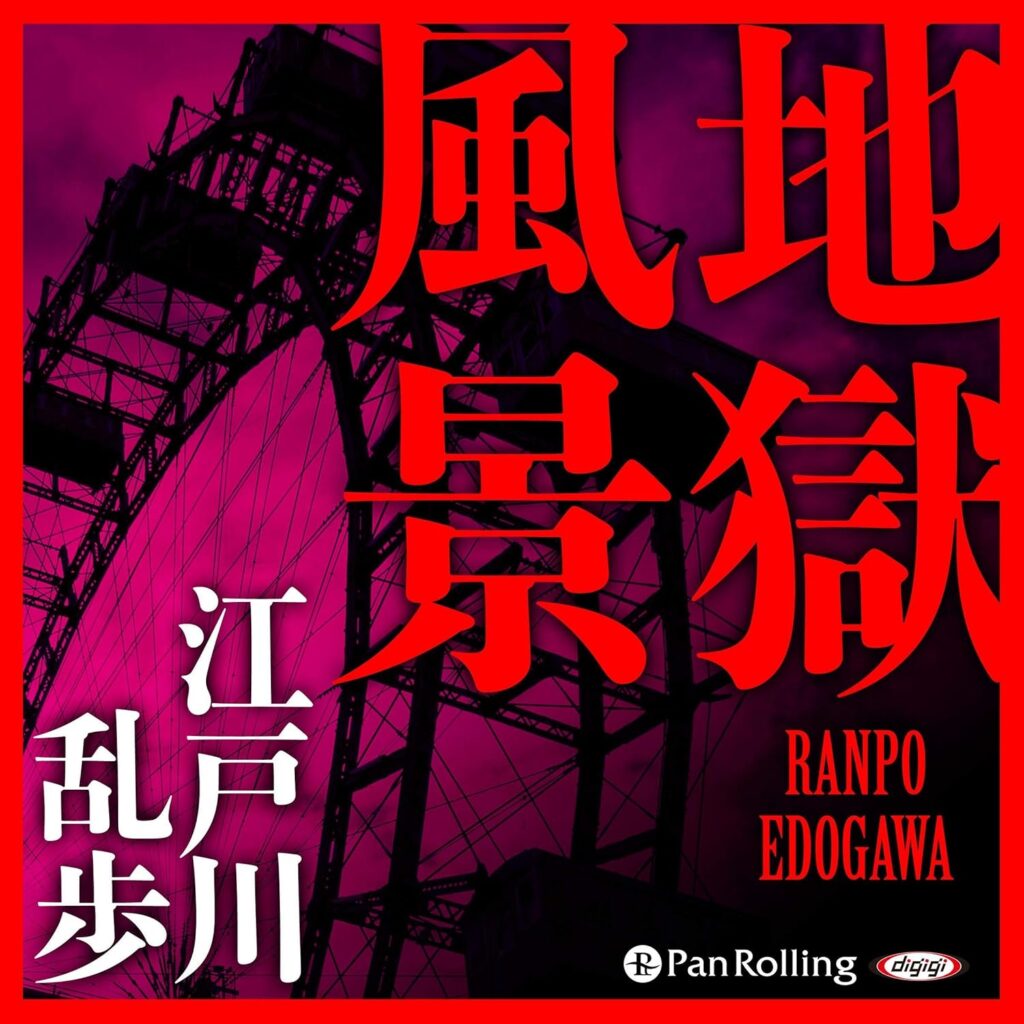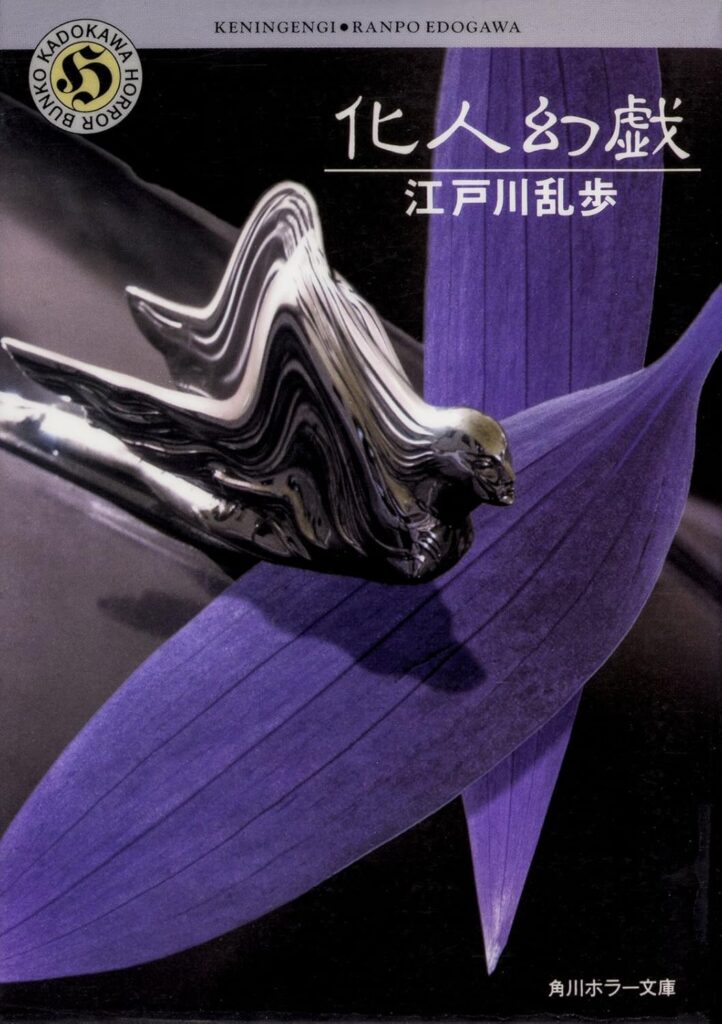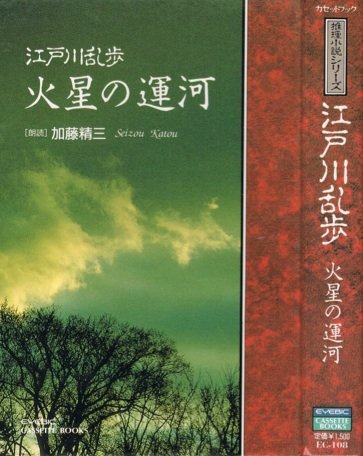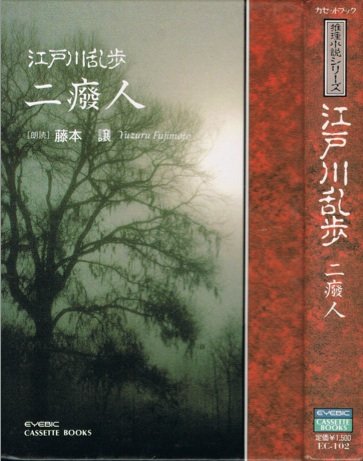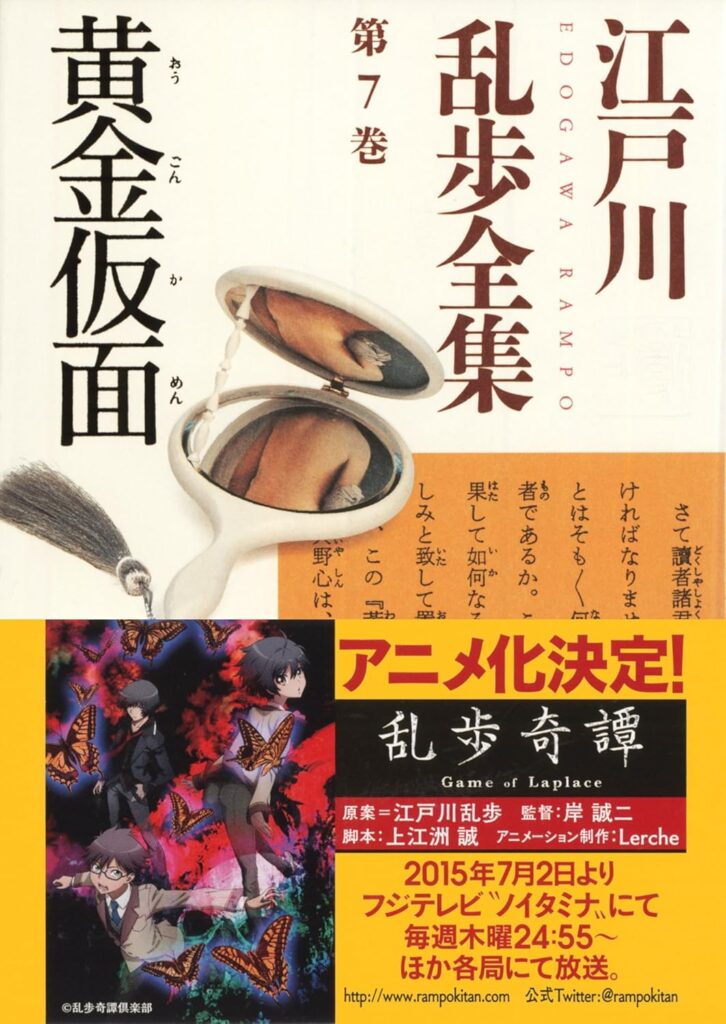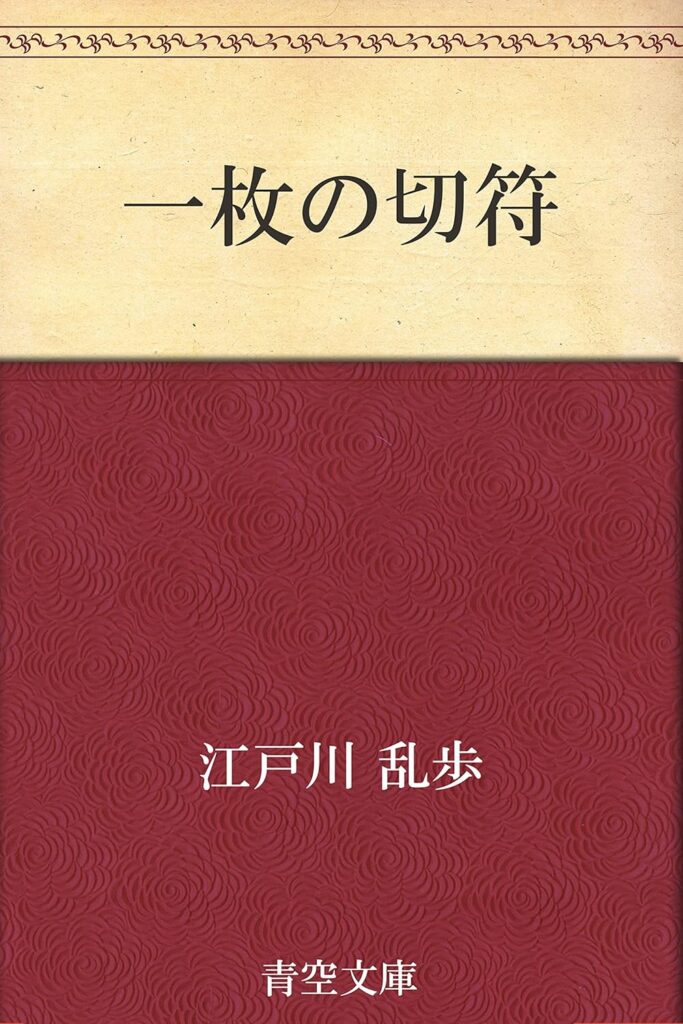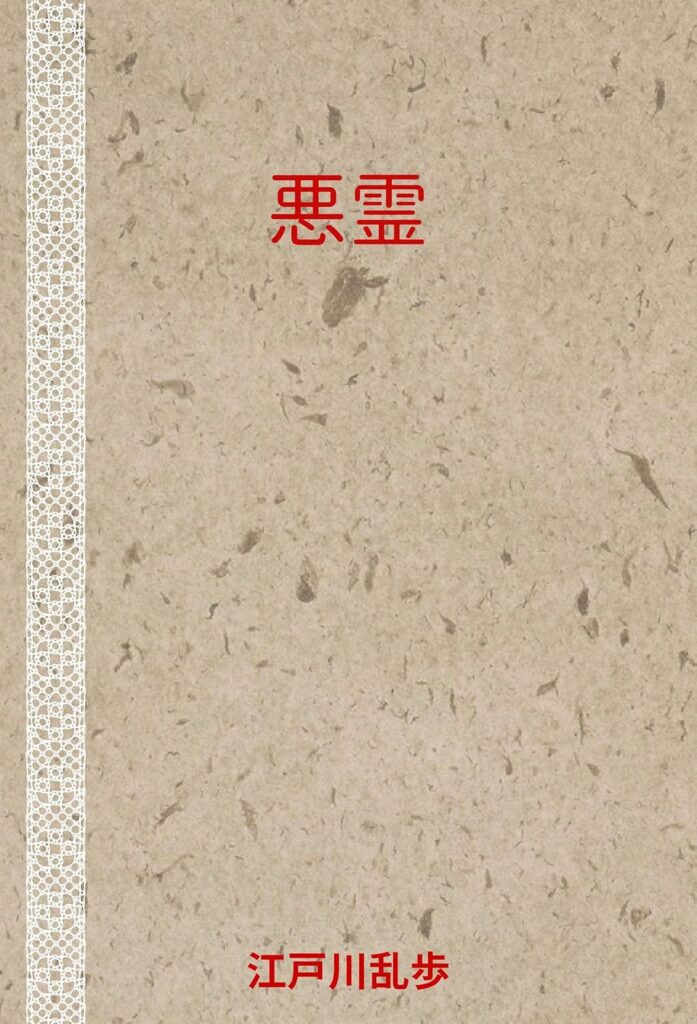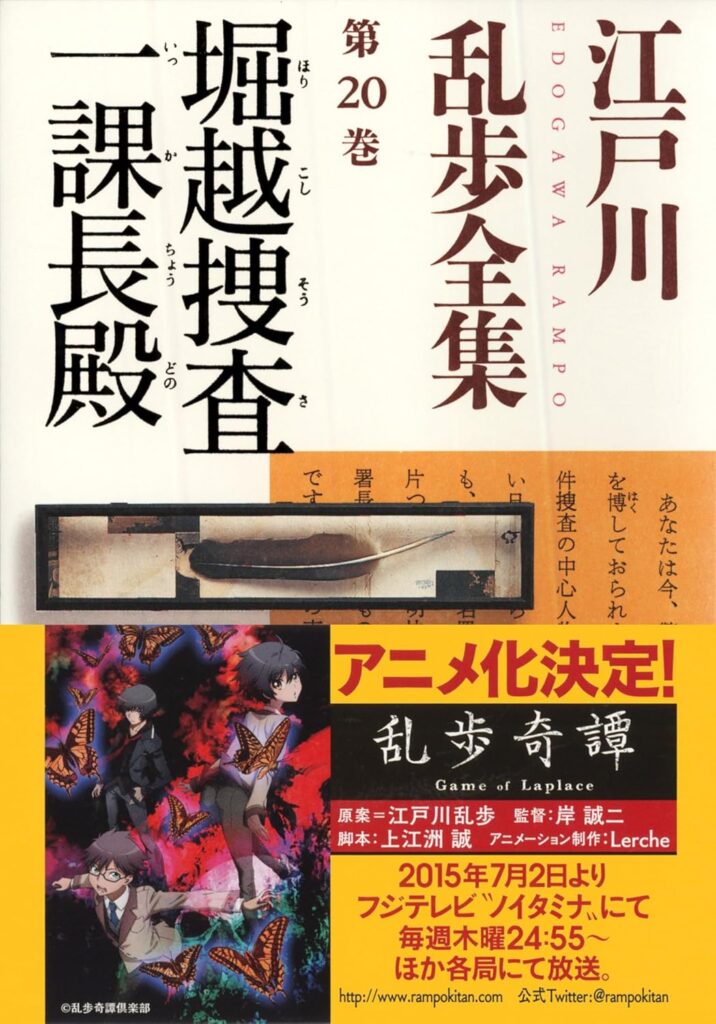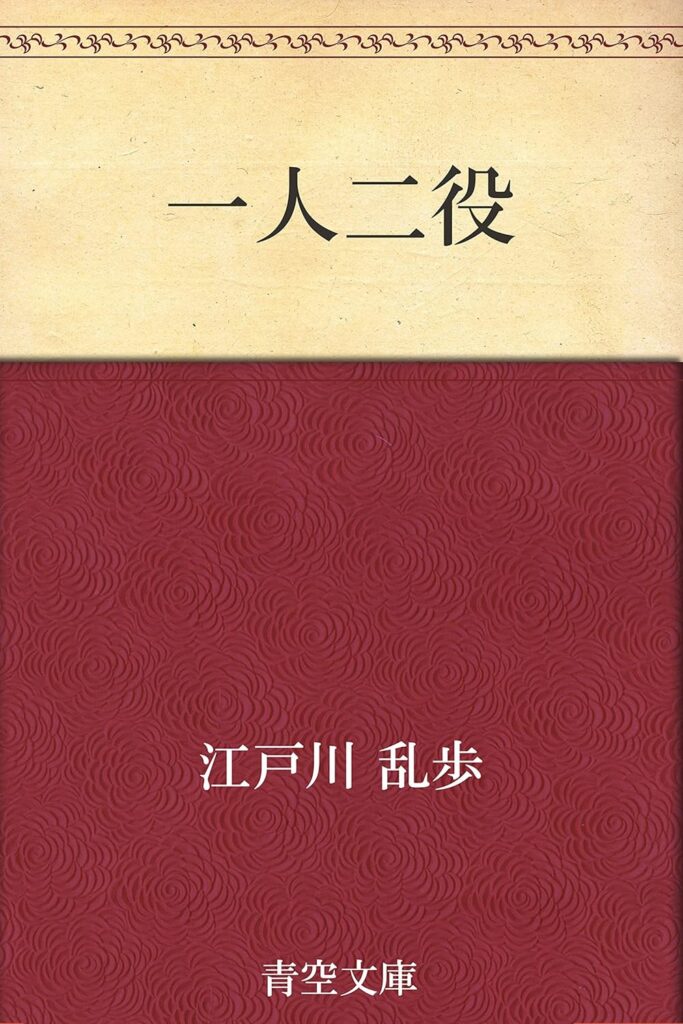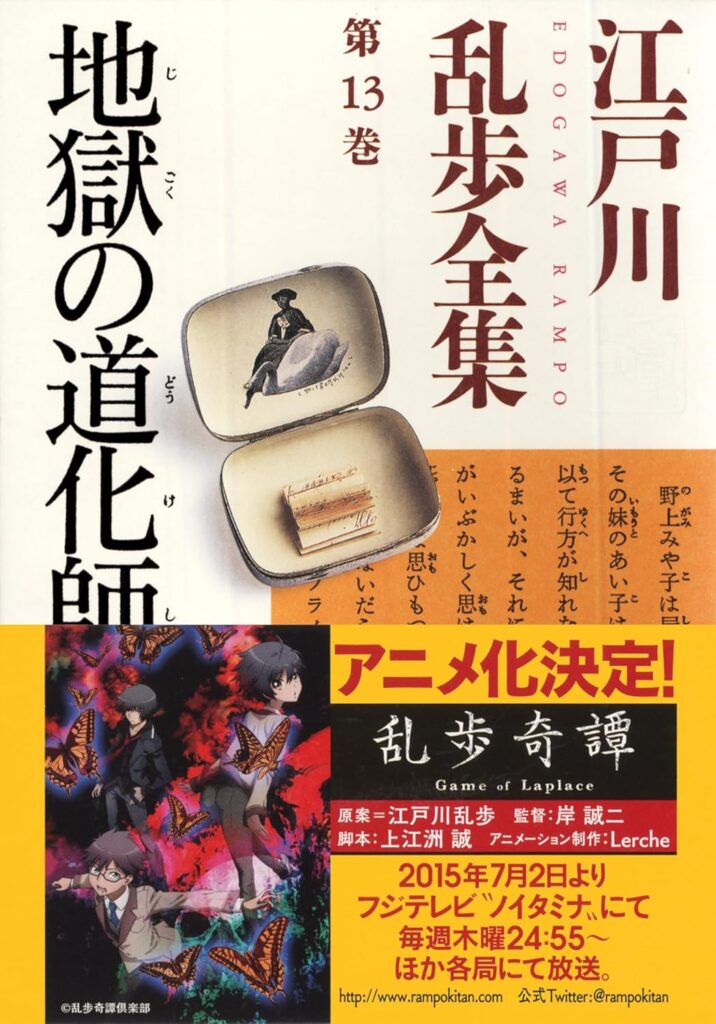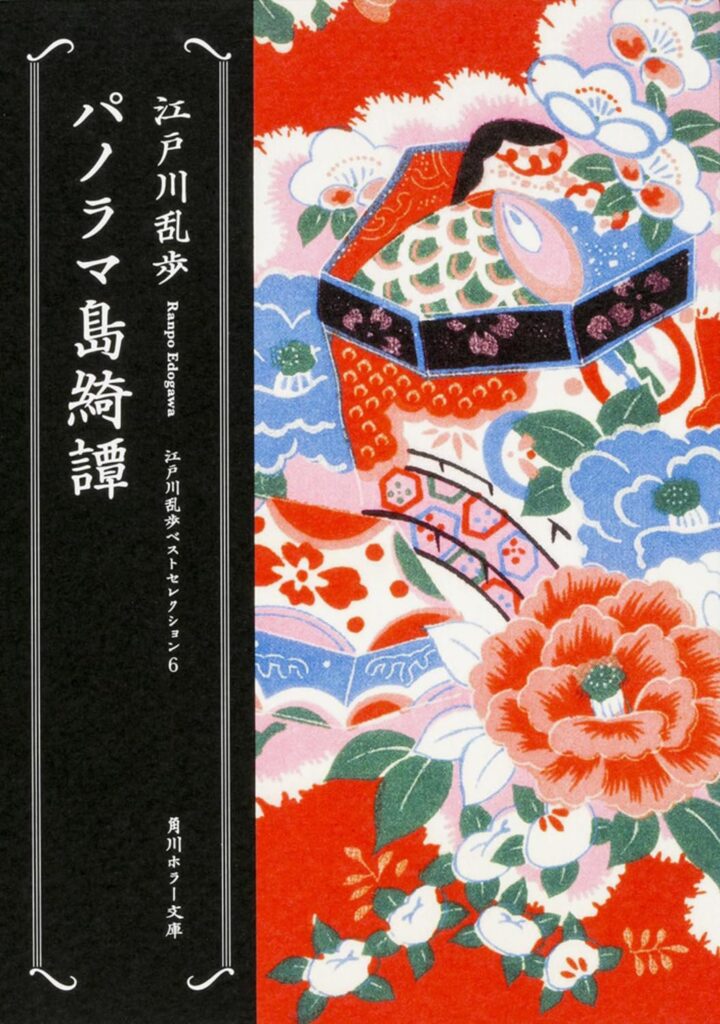小説「防空壕」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「防空壕」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
江戸川乱歩が戦後に発表したこの短編「防空壕」は、東京大空襲という極限状況下での一夜の出来事を描いています。戦争の持つ凄惨さだけでなく、その中で生まれる歪んだ美意識や、人間の記憶の曖昧さ、そして男女の視点の違いが鮮やかに描き出されているんですよ。
物語は、市川清一という男性の回想から始まります。彼は空襲の夜、偶然避難した防空壕で出会った美しい女性との忘れられない体験を語ります。しかし、物語はそれだけでは終わりません。後半では、別の人物の視点から同じ夜の出来事が語られ、読者は驚きの真実を知ることになるのです。
この記事では、まず「防空壕」の物語の詳しい流れ、つまりあらすじを追いかけます。そして、物語の核心に触れるネタバレ情報と、そこから感じたこと、考えたことを、たっぷりと感想として書き記していきます。乱歩作品ならではの、人間の心の奥底を覗き込むような体験を、ぜひ一緒に味わってみてください。
小説「防空壕」のあらすじ
物語は、市川清一という名の男性が、友人らしき相手に自身の体験を語る形で始まります。彼はまず、火事を例に出しながら、空襲という大規模な破壊行為の中に存在する「美」について語ります。凄絶でありながらも、一種の美しさに心を奪われた、と。そして、話題は東京大空襲の夜の出来事へと移っていきます。
仕事を終えた市川が、灯火管制で真っ暗な夜道を歩いていると、空襲警報が鳴り響きました。最初は遠くのことのように感じていましたが、次第に爆撃は激しさを増し、彼のいる地域にも焼夷弾が降り注ぎ始めます。彼は大塚辻町あたりで、立派な屋敷に設けられた頑丈なコンクリート造りの防空壕を見つけ、そこへ避難することにしました。
手回し式の小さな懐中電灯だけを頼りに防空壕の奥へ進むと、そこには息をのむほど美しい女性が一人、ぽつんと座っていました。市川は彼女に声をかけ、隣に座るよう促します。外では激しい空襲が続いており、心細かったのでしょう、女性は市川の隣に腰掛けます。暗闇と恐怖の中、二人の距離は自然と縮まっていきました。
市川の手が女性に触れると、彼女はそれを拒むどころか、強く握り返してきました。まるで互いの存在を確かめ合うかのように、二人は暗闇の中で激しく求め合い、体を重ね合わせます。爆撃の轟音も遠のくような、情熱的な時間でした。しかし、その後、市川は意識を失ってしまいます。
どれくらいの時間が経ったのか、市川が目を覚ますと、隣にいたはずの美しい女性の姿はどこにもありませんでした。防空壕には複数の出入り口があったため、彼女は別の出口から去ったのだろう、と市川は考えます。彼は持っていたわずかな灯りで、彼女がいた場所に何か残されていないか探しますが、何も見つかりませんでした。
戦後、市川はその夜の出来事が忘れられず、あの「女神」のような女性の行方を捜し続けます。大塚界隈で聞き込みをしたりもしましたが、彼女を見つけることはできませんでした。ただ、宮園とみという名の老婦人が、同じ夜にその防空壕に避難したが誰もいなかった、と証言したことを知ります。市川にとって、あの夜の出来事は、空襲の美しさとともに、生涯忘れられない、神秘的で美しい思い出として心に刻まれることになったのです。
小説「防空壕」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは物語の核心、つまりネタバレを含んだ感想をたっぷりと語らせていただきますね。市川さんのロマンティックな(?)回想で終わるかと思いきや、この「防空壕」という物語の本当の面白さは、後半の「宮園とみの話」で明らかになる仕掛けにあるんです。
市川さんの語りが終わり、読者が「ああ、戦争の中にもこんな美しい出会いがあったのか…」なんて感傷に浸りかけたところで、場面は戦後の温泉街へと移ります。そこで登場するのが、宮園とみというおばあさん。彼女が客に請われるままに語り始めたのが、なんと、あの東京大空襲の夜、例の防空壕での体験談だったのです。
とみさんは「あたしのようなおばあちゃんにも、色っぽい話はあったわよ。ほほほっ」なんて笑いながら、防空壕に避難した時のことを話し始めます。暗闇の中にいると、一人の男が入ってきた。そして、「魔がさしたと言うんでしょうか」、その男に求められるままに、一夜限りの関係を持った、と。夜が明けると、なんだか恥ずかしくなって、相手の名前も知らないまま早々にその場を立ち去った、と語るのです。
ここでピンときますよね。そうです、市川さんが防空壕で出会い、生涯の「女神」として心に刻んだ美しい女性…その正体は、この宮園とみさんだった、というわけです!市川さんが暗闇の中で若く美しいと信じ込んだ相手は、実は当時からすでにおばあさんだった、というこの驚愕の事実。この落差、この皮肉!これぞ江戸川乱歩、と言いたくなるような、見事などんでん返しです。
さらにとみさんは後日談として、しばらくしてから市川と名乗る男性が訪ねてきたことを語ります。市川さんは「防空壕で大変な美人を抱いた」と思い込んでいる様子だったため、「恥ずかしくって本当のことなんか言えないでしょう」と、とみさんは真実を告げずに追い返した、というのです。市川さんの美しい思い出は、彼一人の完全な勘違い、幻想だったことが、ここで決定的に示されます。
この結末を知ってから、もう一度市川さんの話を読み返すと、彼の語る言葉一つ一つが、全く違った響きを持って聞こえてきます。彼が空襲の光景に見たという「美」。暗闇の中で出会った女性を「女神」とまで称賛する言葉。それらが、なんと滑稽で、哀れで、そして人間臭いものだったことか。市川さんの主観の中では、それは一点の曇りもない真実であり、美しい思い出だったのでしょう。しかし、客観的な事実(とみさんの語る)は、あまりにもかけ離れていました。
この物語は、人間の「記憶」や「認識」がいかに曖昧で、主観に左右されるものであるかを鋭く突いています。特に、暗闇という視覚情報が著しく制限された状況、そして空襲という極限状態の心理が、市川さんの認識を大きく歪ませたのでしょう。彼は、暗闇の中で相手の姿を正確に捉えることができず、自身の願望や理想を相手に投影してしまったのかもしれません。「若く美しい女性であってほしい」という無意識の願望が、「女神」という幻想を作り上げたのではないでしょうか。
一方で、宮園とみさんの語り口は、市川さんの感傷的な語りとは対照的に、どこか飄々としていて現実的です。「魔がさした」と言いつつも、その出来事を老婆になってから「色っぽい話」として笑い飛ばせるような、ある種のしたたかさ、あるいは客観性のようなものを感じさせます。彼女にとっては、それは美しいロマンスではなく、あくまで異常な状況下での一時の過ち、といった程度の認識なのかもしれません。同じ出来事を体験しても、当事者の立場や感性によって、その意味合いは全く異なってくるのですね。
そして、この物語の背景にある「戦争」、特に「東京大空襲」という設定が、非常に重要な意味を持っていると感じます。死と破壊がすぐ隣にある極限状況は、人々の倫理観や常識を麻痺させ、普段なら考えられないような行動を引き起こします。市川さんが空襲の光景に「美」を感じたというのも、日常が崩壊した異常な心理状態の表れと言えるかもしれません。破壊の中に美を見出すという倒錯した感覚は、戦争という狂気がもたらすものなのでしょう。
また、暗い防空壕の中での密会というシチュエーションも、閉鎖的で、どこか非現実的な空間を作り出しています。外の世界の惨状から隔絶された暗闇の中では、理性よりも本能が、現実よりも幻想が力を持ちやすくなるのかもしれません。市川さんのロマンス(?)が成立し得たのも、この特殊な環境があったからこそでしょう。
江戸川乱歩作品の特徴として、「語り」の巧みさが挙げられますが、この「防空壕」もその例に漏れません。市川さんの一人称による回想は、読者を彼の主観的な世界へと引き込みます。まるで怪談話を聞いているような、あるいは秘密の告白を聞いているような、独特の臨場感がありますよね。『人間椅子』や『鏡地獄』など、乱歩の他の作品にも見られるように、この「語り」の形式自体が、物語の怪しさや面白さを増幅させているように感じます。
市川さんの美しい(と思い込んでいる)体験談を聞かせた後で、とみさんの身も蓋もない(?)告白を突きつける。この構成の見事さには、本当に唸らされます。一度持ち上げられた期待や感傷が、一気に突き落とされるような感覚。しかし、それは不快などんでん返しではなく、人間の持つ可笑しみや哀しみ、そして記憶の不確かさという普遍的なテーマを、鮮やかに描き出すための効果的な仕掛けなのです。
市川さんにとっては、勘違いだったとはいえ、あの夜の出来事は生涯忘れられない美しい思い出として残り続けるのでしょう。真実を知らないままの方が、彼にとっては幸せだったのかもしれません。そう考えると、少し切ない気持ちにもなります。一方で、とみさんにとっては、それは過去の一つの出来事であり、笑い話の種にもなる。この対照的な二人の姿を通して、乱歩は人間の多様な生き様や、記憶との向き合い方を描いているようにも思えます。
美とは何か、若さとは何か、そして愛とは何か。極限状態に置かれた人間の心理を通して、これらの問いを投げかけてくるような、短くも非常に深い余韻を残す作品です。単なる猟奇的な話や怪奇譚としてだけでなく、人間の本質に迫る文学作品としても、読み応えのある一編だと感じました。戦争という重いテーマを扱いながらも、最後には人間の滑稽さや愛おしさを感じさせる、乱歩ならではの味わいが凝縮されていると思います。
まとめ
江戸川乱歩の短編小説「防空壕」は、読後に複雑な感情を残す、非常に印象深い作品でした。物語の前半で語られる、東京大空襲の夜の防空壕での、市川清一という男性のロマンティックな体験談。暗闇の中で出会った美しい女性との情熱的な一夜は、彼にとって生涯忘れられない思い出となります。
しかし、物語の後半で宮園とみという老婆の口から語られる真実は、その美しい思い出を根底から覆します。市川が「女神」と信じた相手は、実は老婆だったという衝撃の結末。この見事などんでん返しによって、人間の記憶がいかに主観的で曖昧なものであるか、そして極限状況が人の認識をどれほど歪ませるかが鮮やかに描き出されます。
市川の感傷的な語りと、とみの飄々とした語りの対比も絶妙です。同じ出来事を体験しながらも、二人の記憶と認識は全く異なっています。戦争という異常な状況下で生まれた、美と醜、真実と虚構が入り混じったこの物語は、読者に人間の心の不可思議さや、記憶の持つ意味について深く考えさせてくれます。
ネタバレを知ってしまうと、市川の語る「美」や「女神」が滑稽に思えるかもしれませんが、彼にとってはそれが真実であり、支えとなる思い出だったのかもしれません。そんな人間の哀しさや愛おしさをも感じさせる、乱歩ならではの深みを持った一作と言えるでしょう。ぜひ、その巧みな語りと衝撃の結末を味わってみてください。