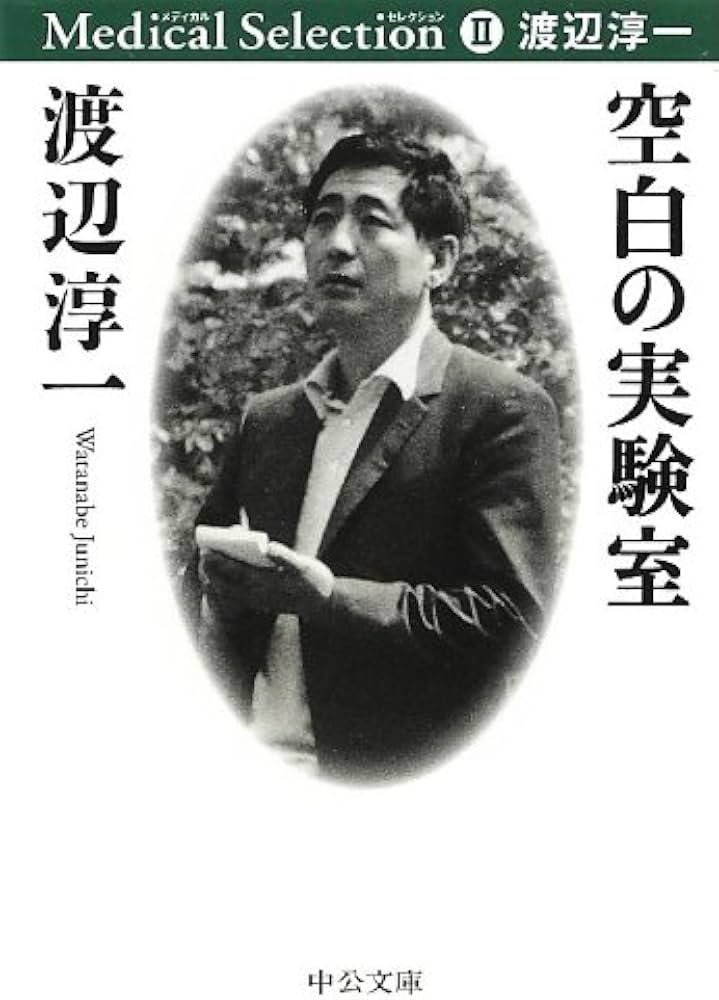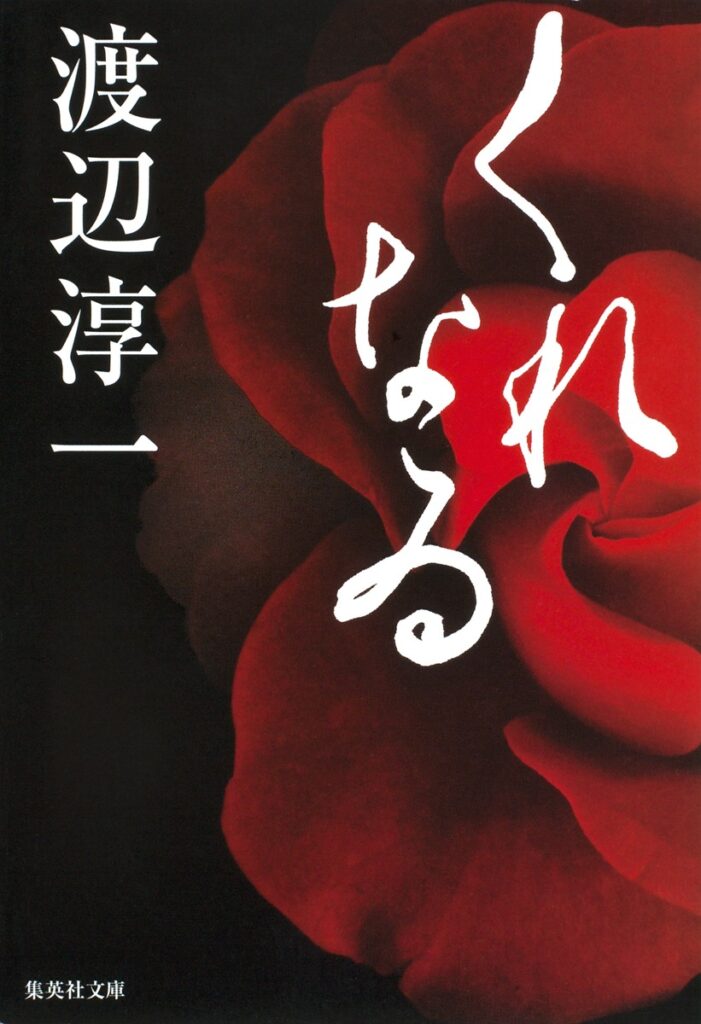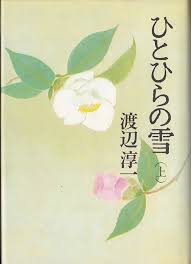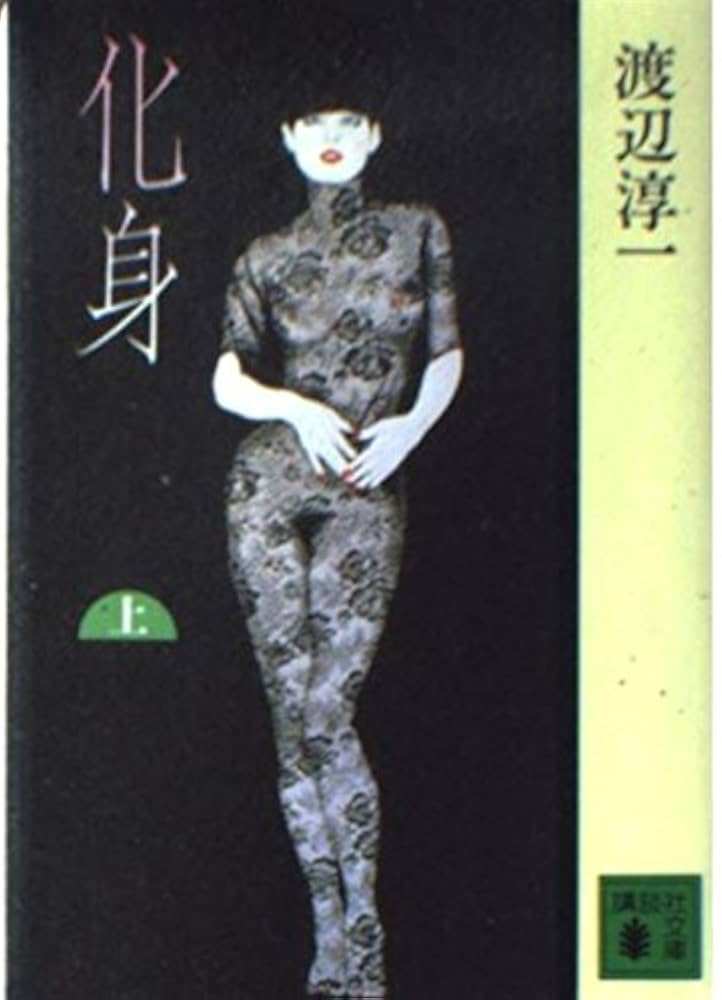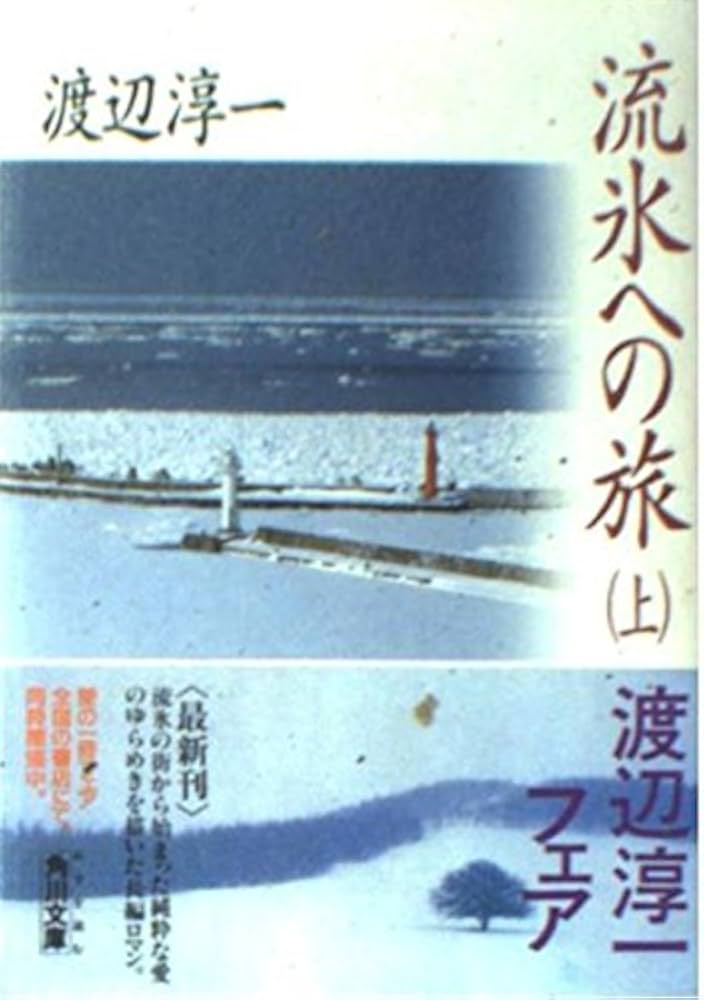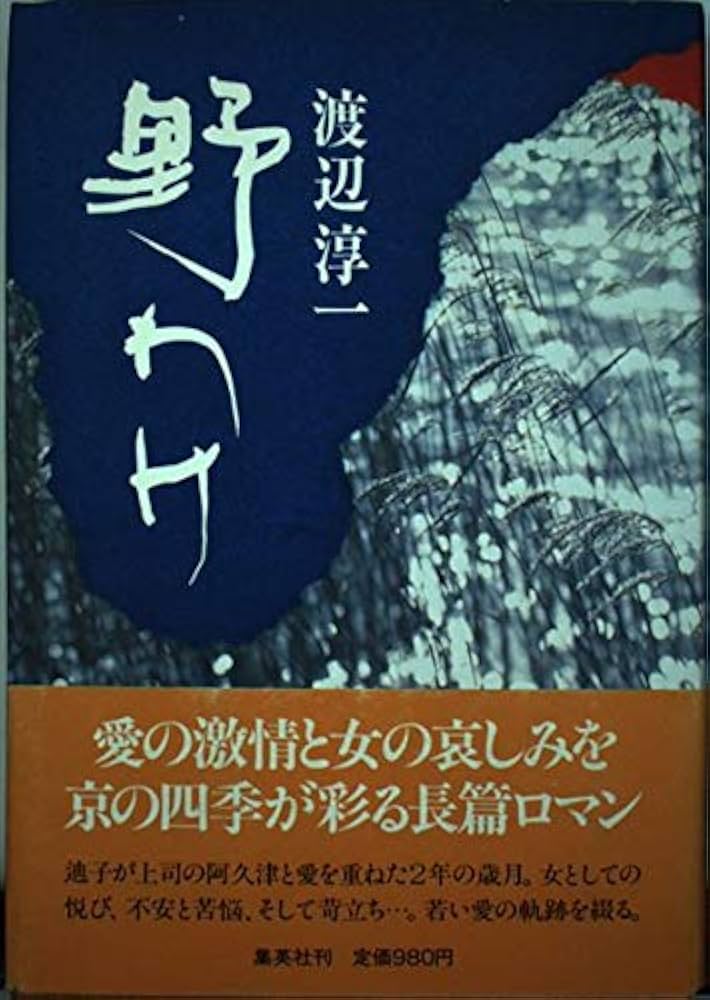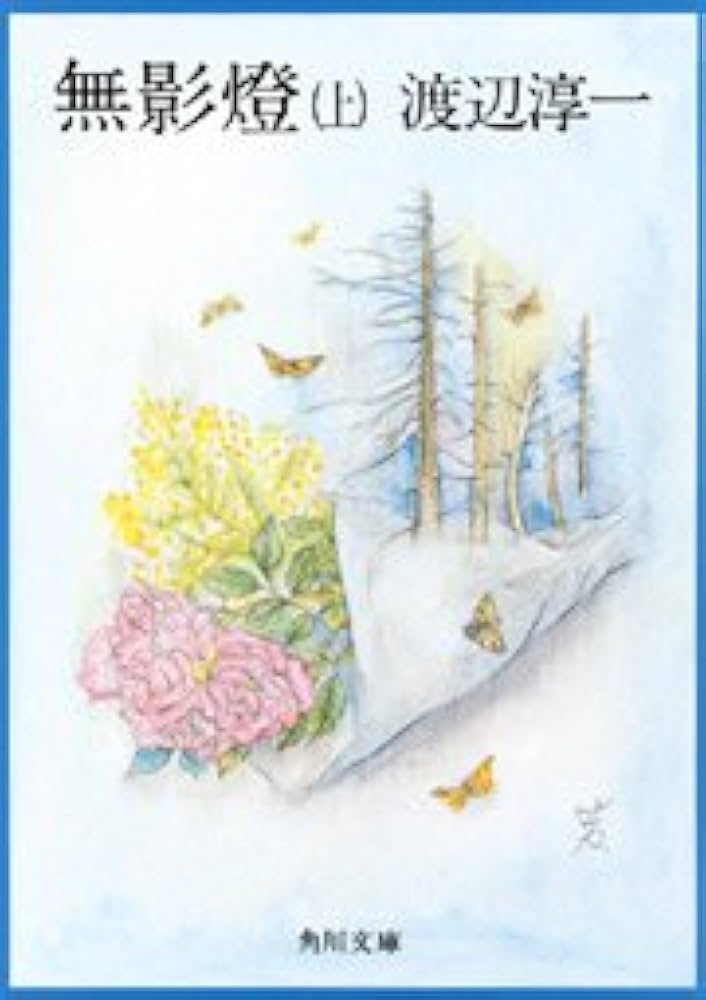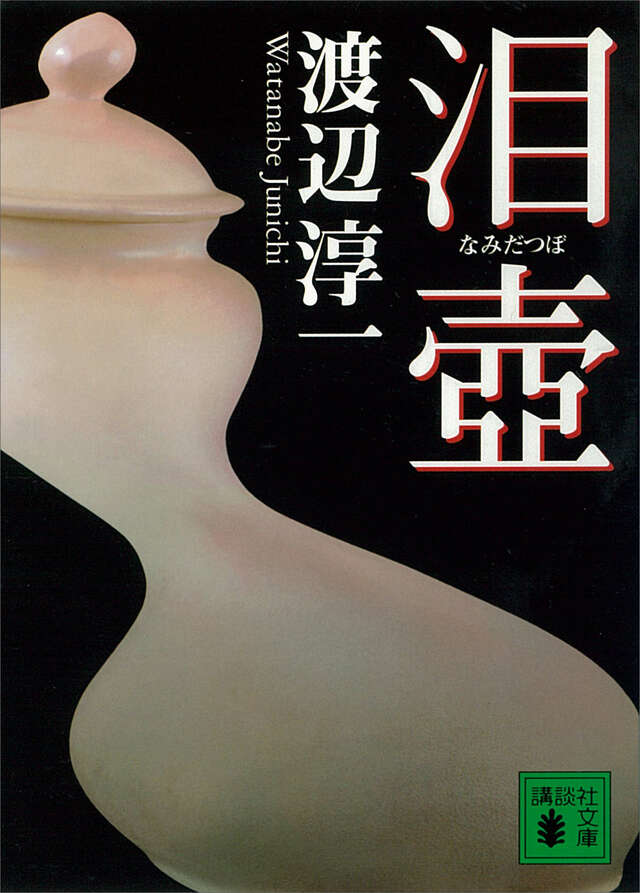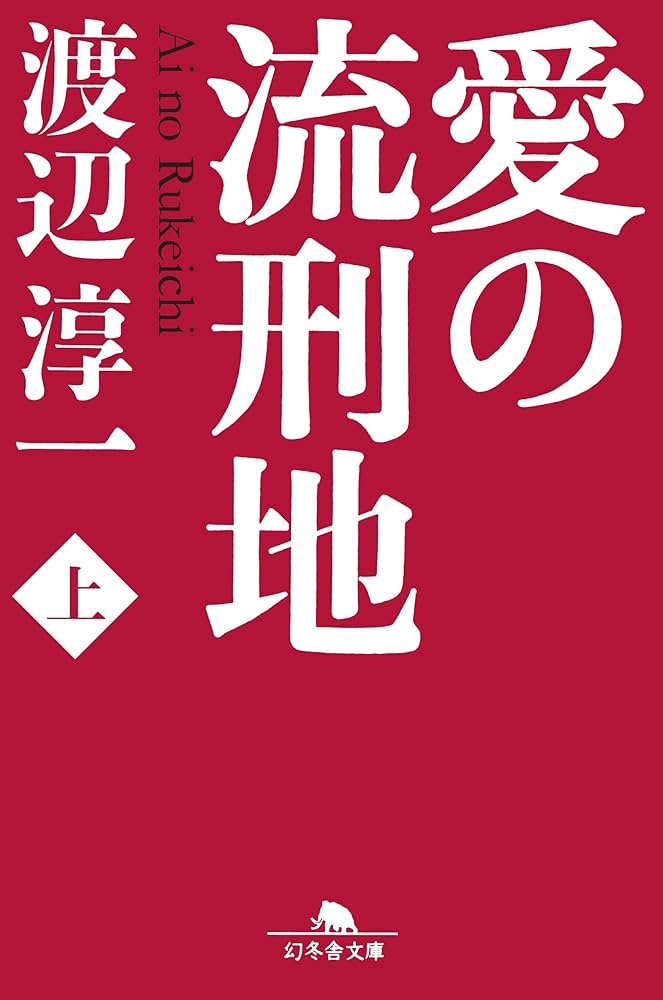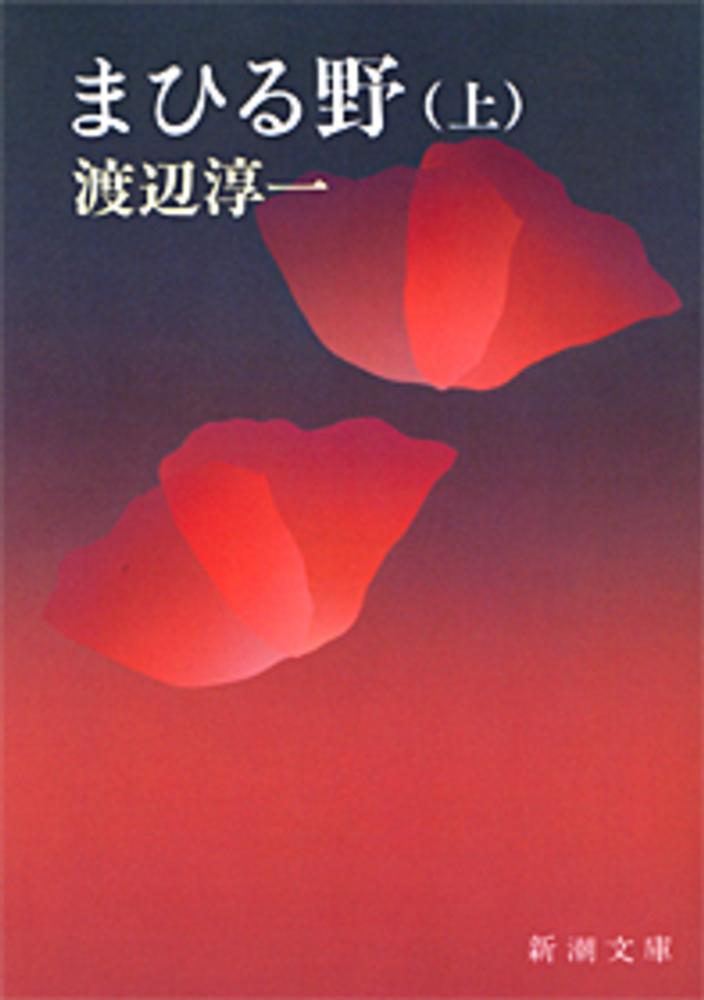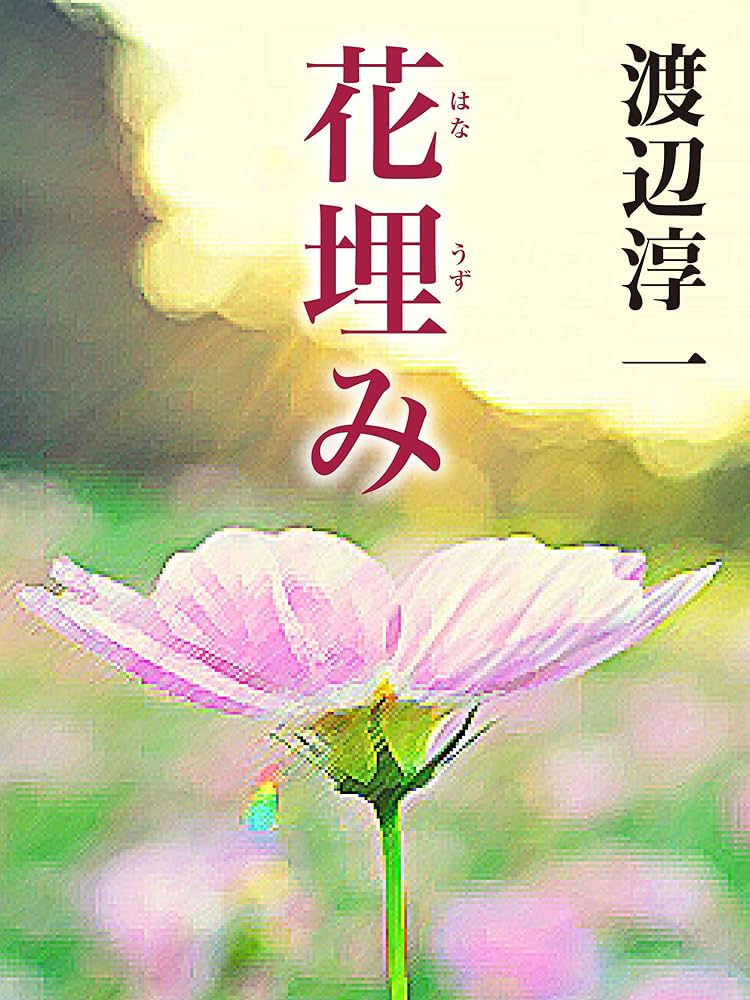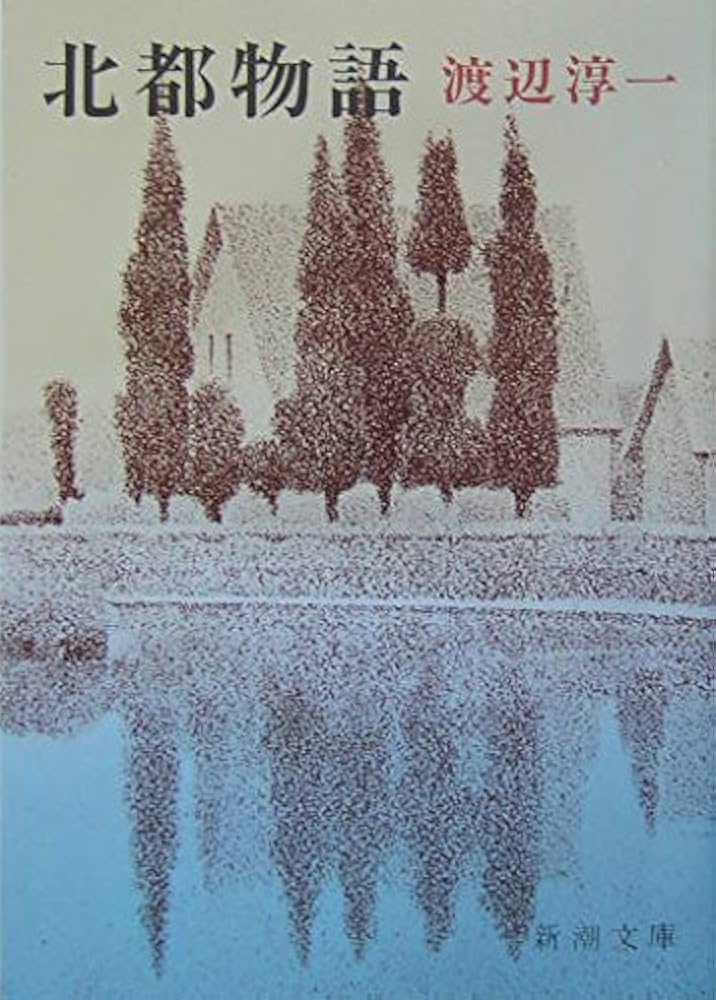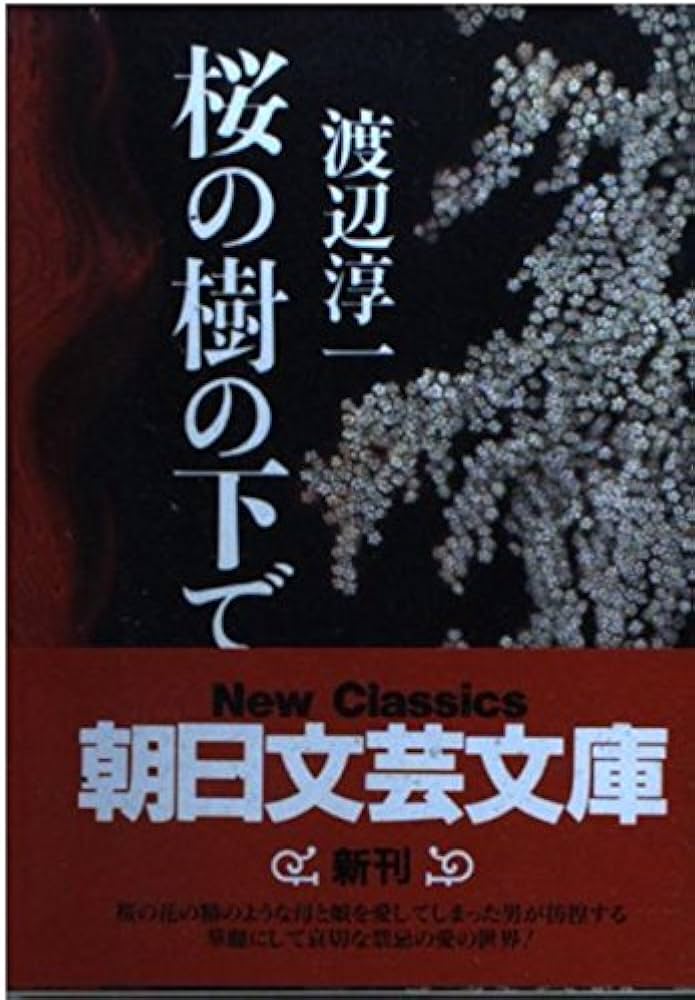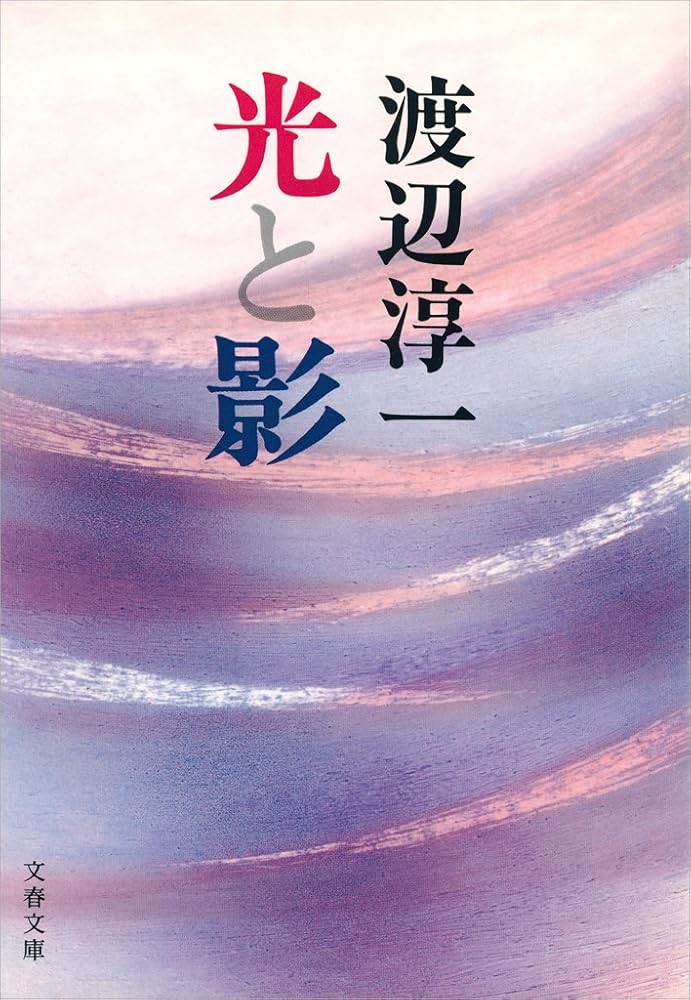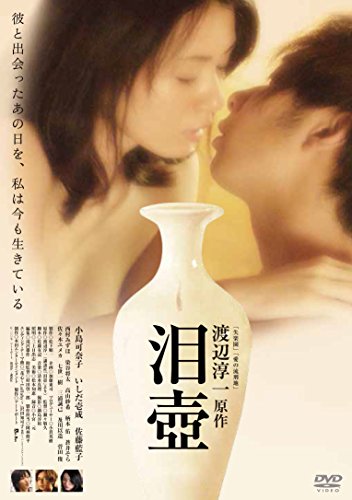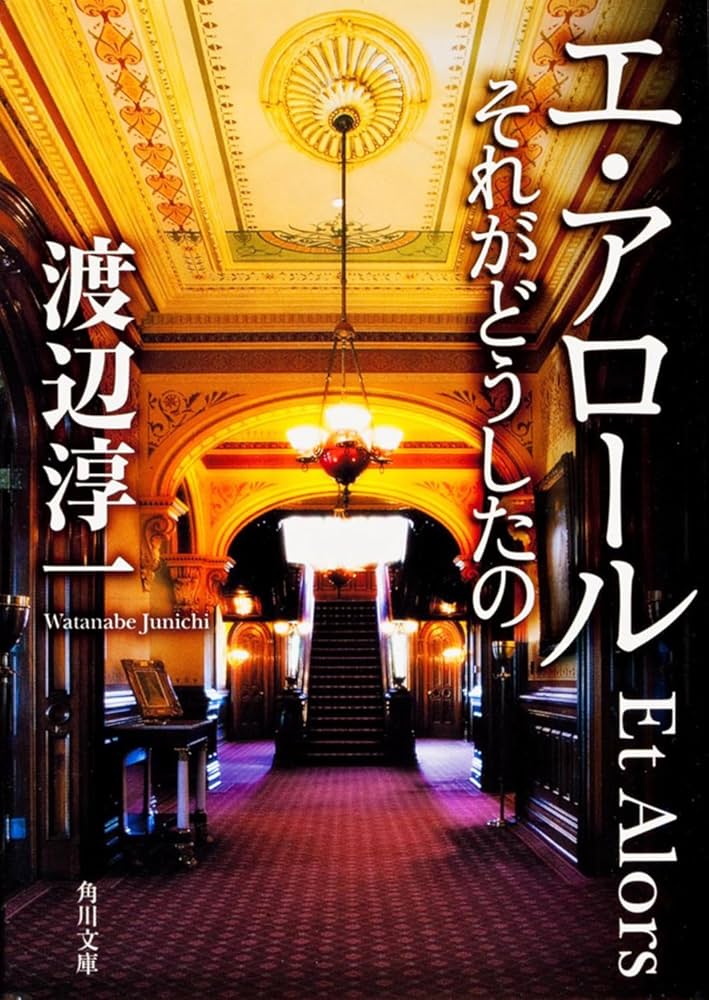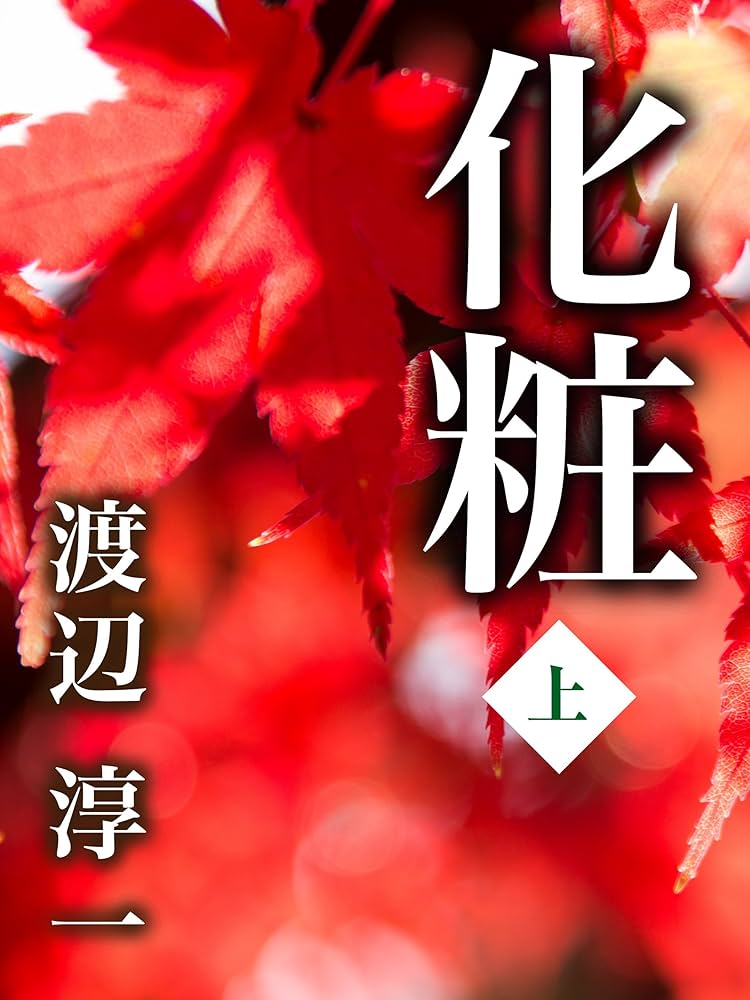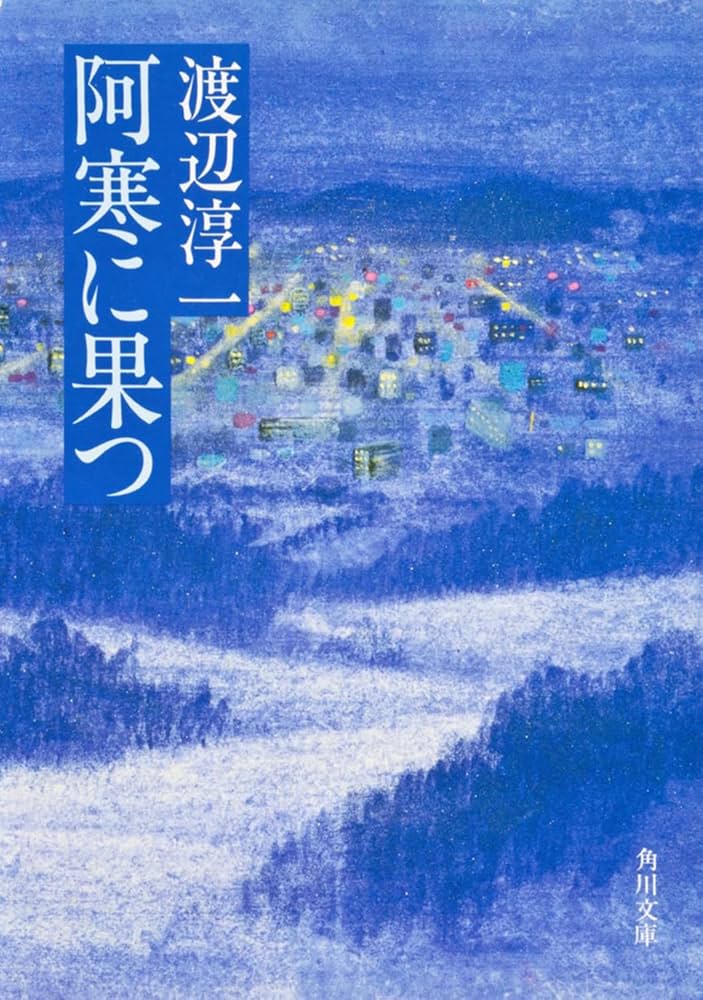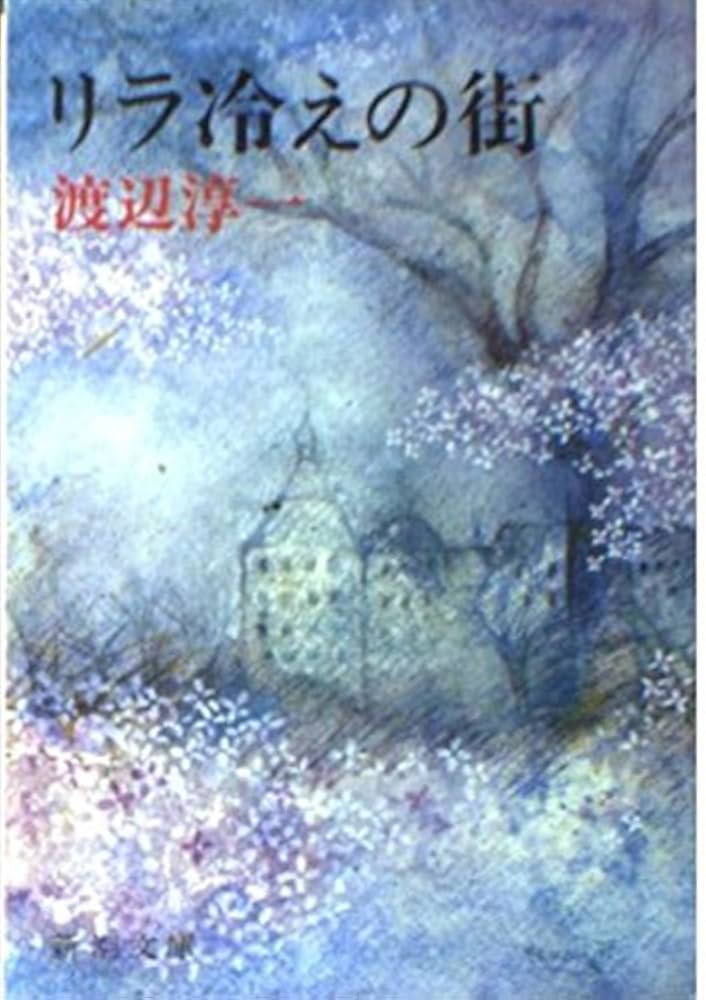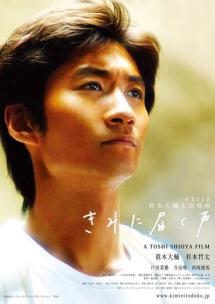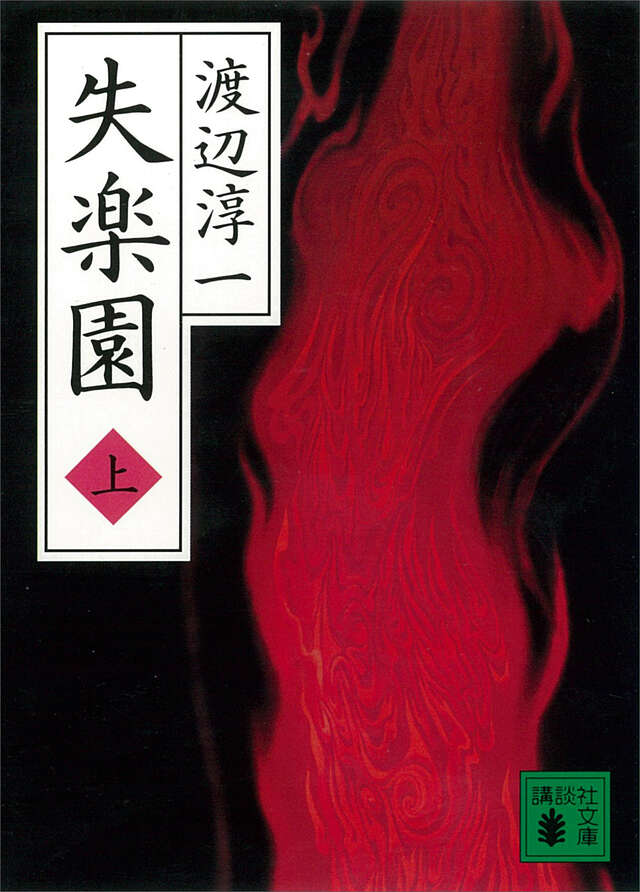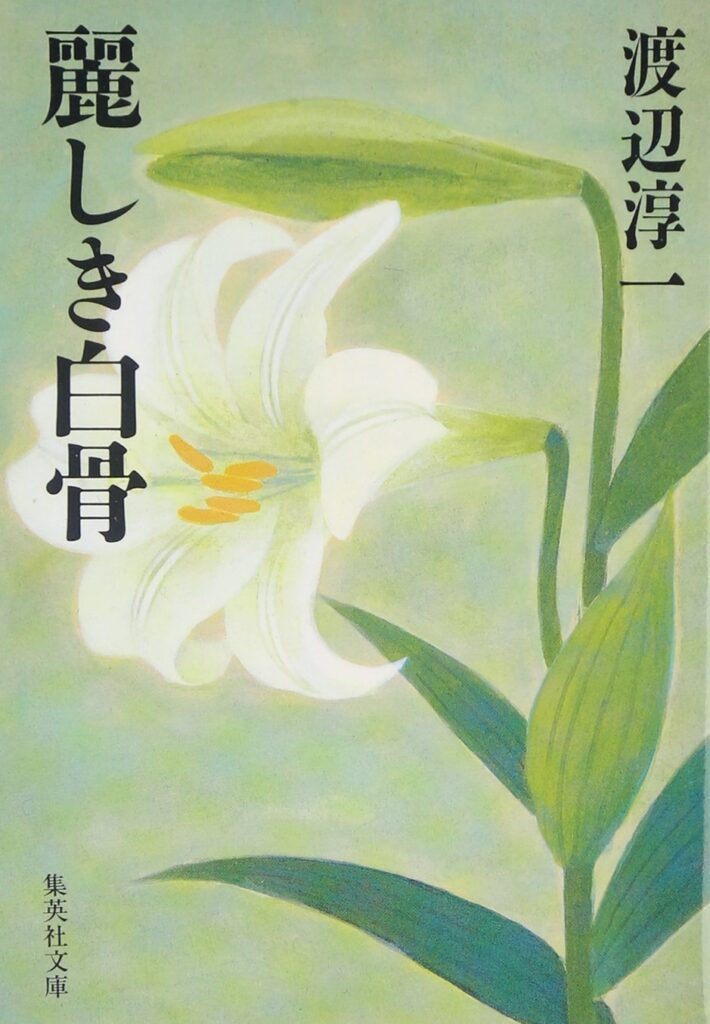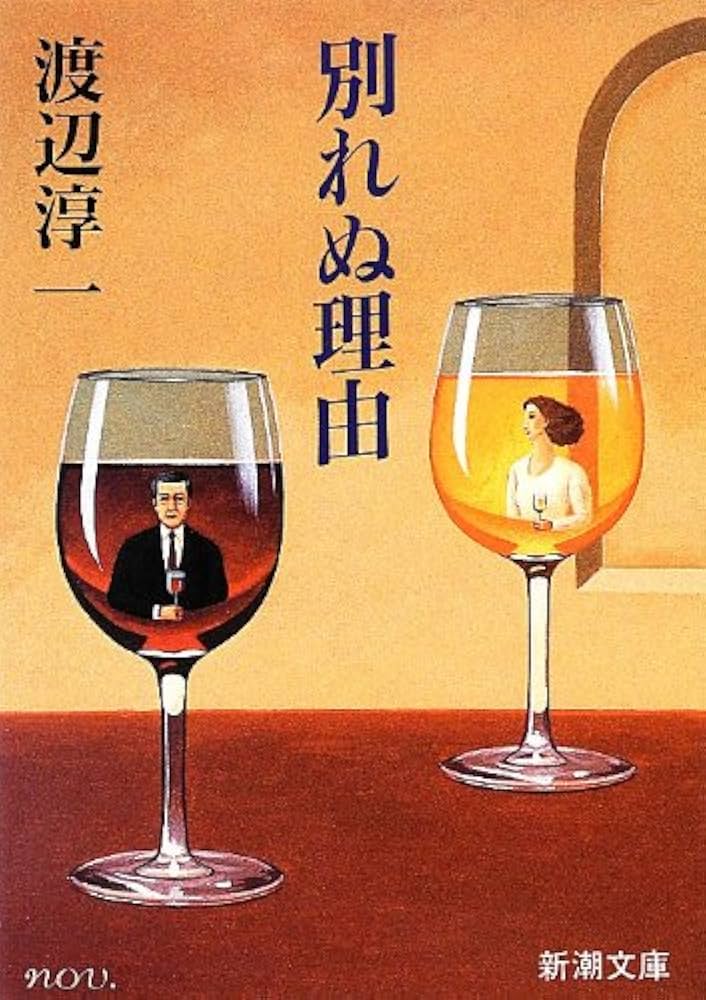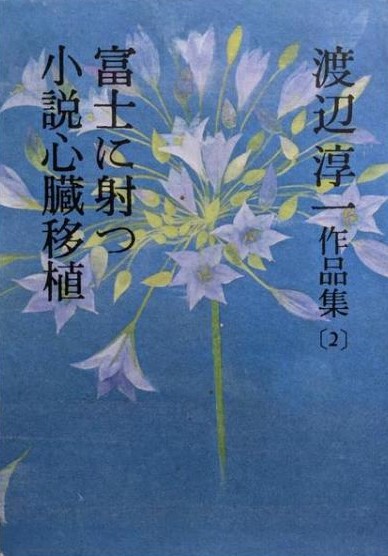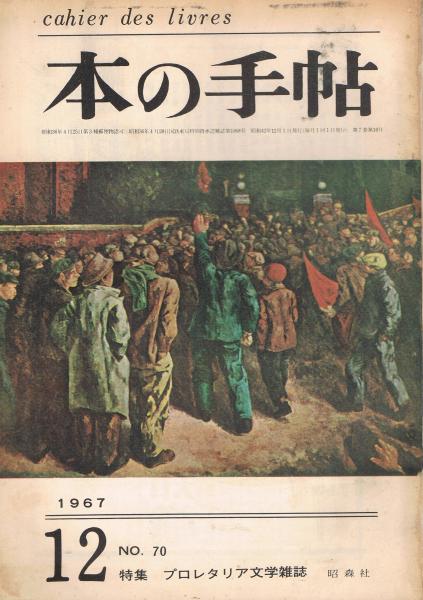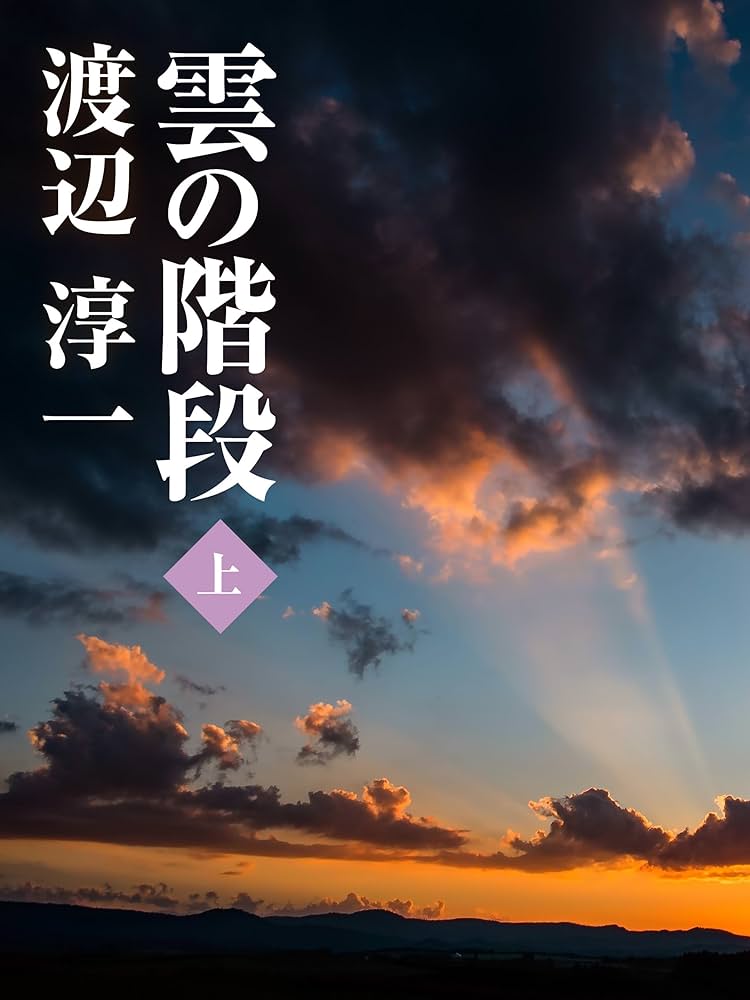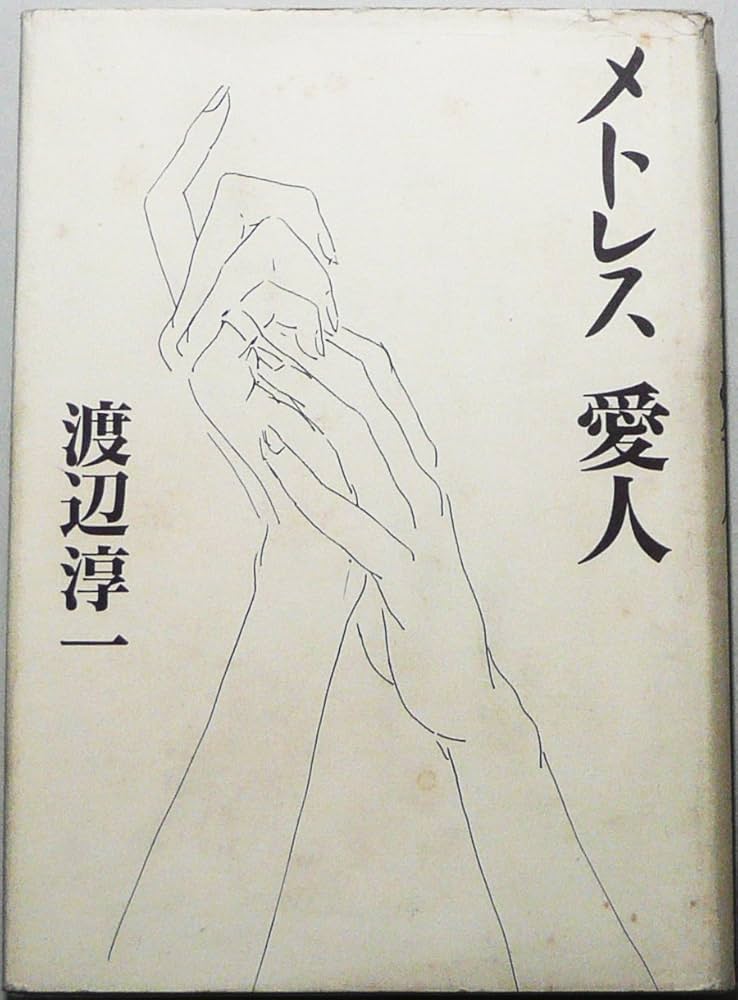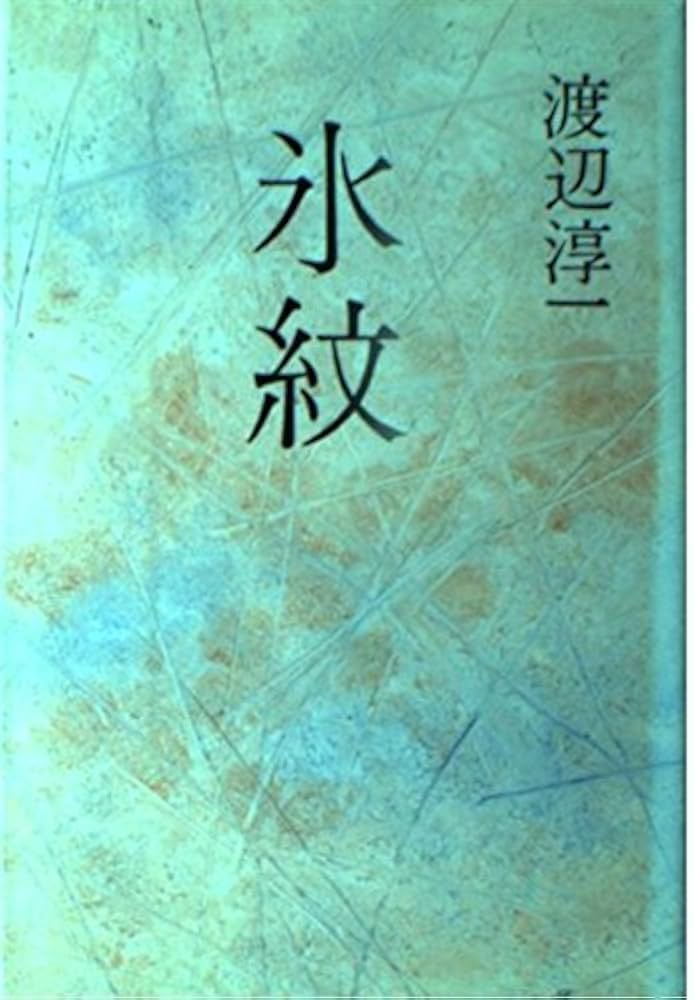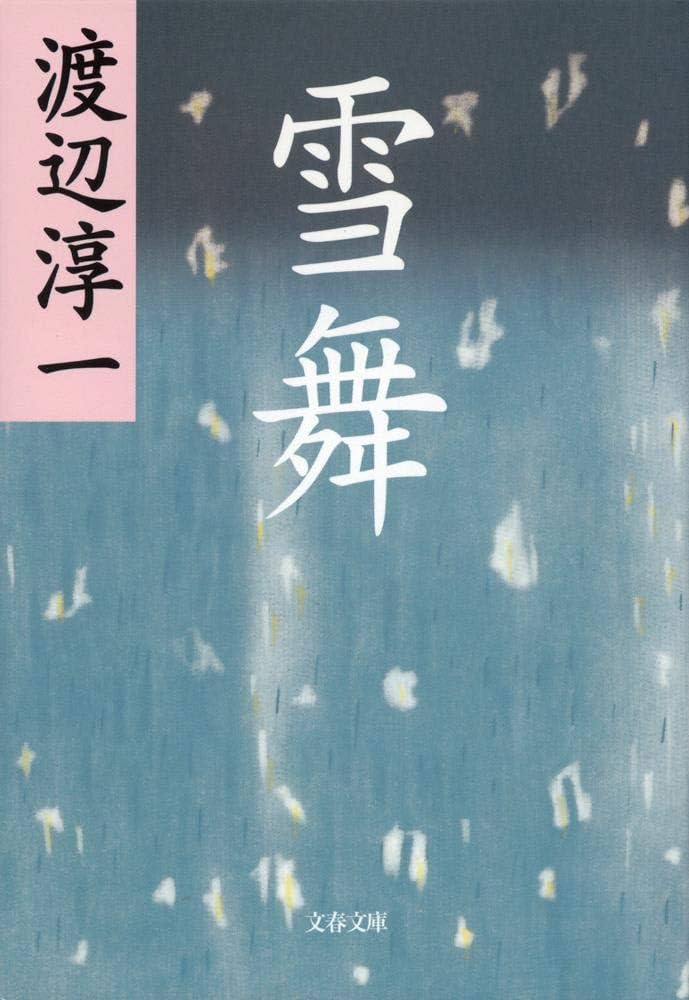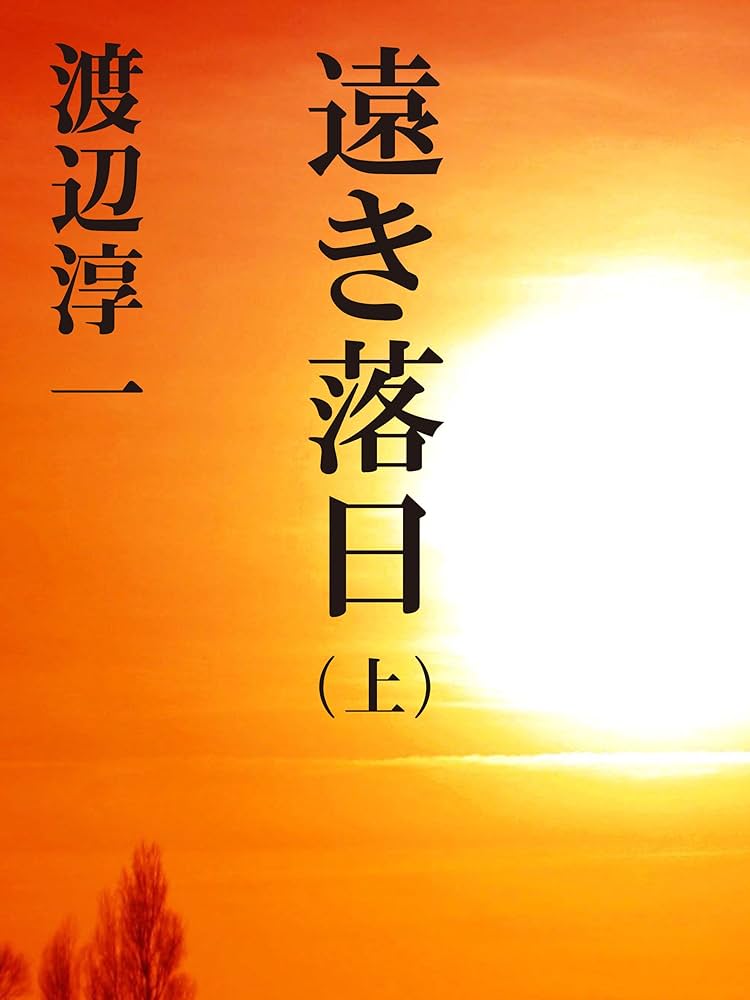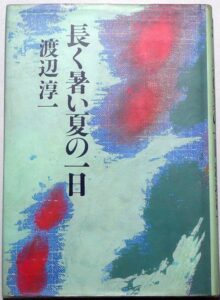 小説「長く暑い夏の一日」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「長く暑い夏の一日」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
本作は、1985年に発表された渡辺淳一氏の長編医療小説です。元医師である作家が、その知識と経験を注ぎ込み、臓器移植という当時の最先端医療が抱える技術的な希望と、法整備が追いつかない社会の現実との狭間で苦悩する人間たちを描き出しています。
物語の時間は、わずか一日に凝縮されています。この手法により、登場人物たちが背負う凄まじいプレッシャーが読者にも伝わり、ページをめくる手が止まらなくなるほどの緊迫感を生み出しています。まさに息もつかせぬ展開が待っています。
タイトルの「長く暑い夏の一日」とは、単なる気候の表現ではありません。それは、新しい医療への期待という「熱」と、倫理的な課題や社会制度との「摩擦」によって沸騰寸前だった、当時の医療界そのものを象徴しているのです。この一日を通して、医療の進歩が私たち人間に投げかける、根源的な問いを深く考えさせられます。
「長く暑い夏の一日」のあらすじ
東京の大学病院に勤める若き外科医、尾津。彼の元に、ある夏の午後、一本の緊急連絡が入ります。箱根の病院で交通事故に遭った患者が脳死状態に陥り、腎臓提供の可能性が出てきたという知らせでした。この電話が、壮絶な「時間との戦い」の始まりを告げる合図となります。
尾津は、提供される腎臓を自らの手で摘出するため、迷うことなく箱根へ向かう決意を固めます。しかし、物語の舞台である1985年当時、脳死はまだ法的に「人の死」と認められていませんでした。脳死状態のドナーから臓器を摘出する行為は、法的なグレーゾーンにあり、極めて危険な任務だったのです。
一方、東京の大学病院では、腎不全に苦しみ、ドナーを待ち続ける少年、経太郎がいました。知らせを受けた移植チームは、とてつもない賭けに出ます。まだ尾津が臓器を手にし、東京へ戻る前に、経太郎の移植準備手術を開始してしまったのです。手術台の上で開腹されたまま、臓器の到着を待つ少年。その命は、完全に尾津の双肩にかかっていました。
ところが、尾津を乗せた車が東名高速道路に入った直後、大規模な交通事故が発生し、高速道路は完全に封鎖されてしまいます。東京への道が断たれた絶望的な状況下で、一刻一刻と価値を失っていく移植腎。尾津の焦燥と、手術室で待つ者たちの祈りが、夏の暑さの中で交錯します。
「長く暑い夏の一日」の長文感想(ネタバレあり)
私がこの物語を手に取ってまず感じたのは、その圧倒的なリアリティでした。元外科医である渡辺淳一氏だからこそ描ける、医療現場の息遣い、医師たちの内面の葛espół、そして生命の尊厳をめぐる深い問いかけが、ページの中から溢れ出してくるようでした。
本作の舞台は1985年。今でこそ臓器移植は確立された医療技術の一つですが、当時はまさに黎明期でした。脳死という概念が社会的に広く受け入れられておらず、法整備も追いついていない。そんな時代に、医師たちがどれほどの重圧を背負い、どれほどの覚悟を持ってメスを握っていたのかを、この物語は克明に描き出しています。
物語の主人公である外科医・尾津が、箱根で脳死状態の患者から腎臓を摘出する場面は、その象徴です。心臓がまだ動いている人間から臓器を取り出すという行為。それは、純粋な医療行為であると同時に、社会的な非難や法的なリスクと常に隣り合わせの、危険な綱渡りでもありました。家族の同意を取り付ける場面の緊張感は、当時の医師たちが直面した倫理的なジレンマを生々しく伝えてきます。
物語の舞台設定もまた、秀逸だと感じました。医療の最先端が集まる東京と、風光明媚な観光地である箱根。その二つを結ぶ大動脈、東名高速道路。この地理的な条件が、後に物語の核心となる交通麻痺という危機を、非常に現実的なものとして読者に突きつけます。夏の行楽シーズンの高速道路という、誰もが経験したことのある日常の風景が、一転して生命を脅かす絶望的な壁となるのです。
そして、東京の大学病院で下される、もう一つの重大な決断。レシピエントである少年・経太郎の体を、臓器が到着する前に開腹してしまうという、常軌を逸した判断です。これは、臓器が体外にある時間(虚血時間)を少しでも短くし、移植の成功率を上げたいという、純粋な医学的合理性に基づいたものでした。
しかし、それは同時に、もし臓器が届かなかった場合、少年を無意味な危険に晒すことになるという、計り知れない倫理的リスクを伴う賭けでもあります。この一点において、物語は単なるサスペンスから、現代医療が抱える倫理の深淵を覗き込む、重厚な人間ドラマへと昇華していくのです。医療の奇跡を追求するために、一体どこまでのリスクが許されるのか。この問いは、読んでいる私の胸にも重く突き刺さりました。
物語の中盤は、尾津医師の絶望的な旅路に焦点が当てられます。交通事故による高速道路の完全封鎖。進むことも戻ることもできない車内で、尾津が感じる焦燥感、こみ上げるパニック、そして一人の少年の命を預かる責任の重さ。その心理描写は、読んでいるこちらの息まで詰まらせるほどでした。
車を捨て、見知らぬ箱根の裏道を、臓器の入ったクーラーボックスを抱えてひた走る尾津の姿は、まさに孤独な英雄のようでした。しかし、彼が立ち向かうのは、神話に出てくるような怪物ではありません。交通事故や交通渋滞といった、現代社会にありふれた日常の綻びなのです。この設定が、物語に強烈な現実感を与えています。
最先端の医療技術や、エリート医師たちの知性が、たった一台の車の事故によって、いとも簡単に無力化されてしまう。この構図は、複雑に絡み合いながらも、実はいかに脆弱な基盤の上に成り立っているかという、現代の救命システムの現実を浮き彫りにしています。尾津の奮闘は、そのシステムの穴を必死に埋めようとする、人間のか弱くも尊い抵抗の姿そのものでした。
視点が再び東京の手術室に戻ると、そこには絶望的な空気が漂っています。尾津からの連絡は途絶え、時間だけが刻一刻と過ぎていく。この待ち時間の描写が、また見事なのです。希望が少しずつ削り取られていく家族の姿、そしてなすすべもなく立ち尽くす医療チームの無力感。読者もまた、彼らと共に祈るような気持ちで、ただひたすらに尾津の帰還を待つことになります。
ここで物語は、さらなる絶望を突きつけます。教授の一人が最後の手段として提案した、父親の腎臓を使った生体腎移植。しかし、その望みも、血液型が不適合であるという冷徹な医学的事実の前に打ち砕かれます。この展開は、物語のサスペンスを極限まで高めると同時に、深い感動を呼び起こしました。
息子のために自らの体の一部を差し出すことを厭わない父親の愛情。それでも、生物学的な法則という、人の力ではどうにもならない壁が存在する。このどうしようもない現実が、見ず知らずの誰かから提供される適合臓器というものが、いかに奇跡的で、いかに尊いものであるかを、逆説的に私たちに教えてくれます。尾津が運ぶ小さな箱の重みが、ここで読者の心の中で、決定的な意味を持つことになるのです。
そして、物語はついにクライマックスを迎えます。疲労困憊の尾津が、奇跡的に病院へたどり着く場面。彼の姿を認めた瞬間の、院内の安堵と興奮が入り混じった空気感が、手に取るように伝わってきました。ここから、渡辺淳一氏の真骨頂である、手術シーンの詳細な描写が始まります。
血管を吻合し、血流を再開させた瞬間、それまで血の気を失っていた灰色の腎臓に、温かい血液が流れ込み、見る見るうちに生命の証であるピンク色を取り戻していく。そして、やがて尿管から、新しい生命の始まりを告げる一滴の尿が排泄される。この場面に、私は思わず息を呑みました。
劇的なセリフや派手なアクションではなく、手術台の上で起こる、静かで、しかし何よりも雄弁な生命の現象そのものを、物語の頂点に据える。これこそ、医療という行為の本質を深く理解している作家だからこそ可能な、至高の筆致だと感じ入りました。全ての混乱と焦燥、そして努力が、この静かな生物学的な勝利のためにあったのだと、深く納得させられた瞬間でした。
しかし、この物語の真の素晴らしさは、手術の成功で終わらない点にあると私は思います。物語の最後は、死闘を終えた外科医たちが、夜が明けた医局で静かに過ごす場面で締めくくられます。大げさな祝杯も、歓喜の声もありません。そこにあるのは、極度の疲労と深い安堵、そして共に途方もない重圧を分かち合った者たちだけが共有できる、静かな連帯感です。
この医局の場面のリアリティは、医師であった渡辺氏にしか描けない、特別な領域だと感じました。華々しい英雄譚として物語を終えるのではなく、医療とは心身をすり減らす過酷な労働であり、その重荷は手術が終わった後も、医師たちの心に長く残り続けるのだという、一つの真実がここにありました。この静かな余韻こそが、本作を忘れがたい作品にしているのだと思います。
『長く暑い夏の一日』は、単なる医療サスペンス小説ではありません。それは、1980年代という、日本の医療が大きな転換点を迎えていた時代の、極めて重要な記録文学でもあります。技術が先行し、法や倫理がそれに追いつかない中で、現場の医師たちがどれほどの葛藤を抱えていたか。本作を読むことで、私たちはその歴史的な瞬間を追体験することができます。
この物語は、当時の医師たちへの、そして医療という不確実なものに立ち向かい続けるすべての人々への、力強い賛歌でもあります。新しい技術という希望の光と、それに伴う未知のリスクという影。その両方を背負いながら、目の前の命を救うために奮闘する人間の姿は、時代を超えて私たちの胸を打ちます。深い人間性への探求が、この物語に普遍的な輝きを与えているのです。
まとめ
渡辺淳一氏の『長く暑い夏の一日』は、臓器移植の黎明期を舞台に、たった一日の出来事を濃密に描いた、傑作医療小説です。あらすじを追うだけでも、その息詰まるような緊張感が伝わってくるのではないでしょうか。
物語は、極限状況に置かれた医師たちの葛藤や、生命の尊厳という重いテーマを扱いながらも、一級のエンターテインメントとして読者を引き込みます。ネタバレを読んで結末を知っていてもなお、そこに至るまでの過程の描写は、何度読んでも心を揺さぶられる力を持っています。
私の感想としても、この作品が描き出す医療現場のリアリティと、登場人物たちの深い人間ドラマには、ただただ圧倒されました。医療の進歩と倫理の狭間で繰り広げられる、長く、そして暑い一日の物語は、きっとあなたの心にも深い余韻を残すことでしょう。
まだこの作品を読んだことのない方には、ぜひ一度手に取っていただくことを強くお勧めします。そして、すでに読んだことがある方も、本記事をきっかけに再読していただければ、新たな発見があるかもしれません。