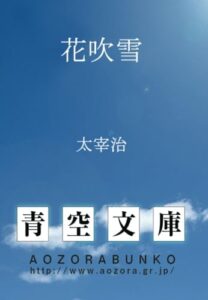 小説「花吹雪」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治の作品の中でも、少し変わった味わいを持つこの短編は、読むたびに新しい発見があるように感じられます。特に、登場人物たちのどこか滑稽で、それでいて愛おしい姿が印象的です。
小説「花吹雪」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治の作品の中でも、少し変わった味わいを持つこの短編は、読むたびに新しい発見があるように感じられます。特に、登場人物たちのどこか滑稽で、それでいて愛おしい姿が印象的です。
物語の中心となるのは、少々風変わりな大学教師、黄村先生。彼の突飛な持論と行動が、周囲を巻き込みながら展開していきます。一見すると荒唐無稽な話のようでありながら、その根底には人間誰しもが持つであろう弱さや見栄、そしてささやかな矜持のようなものが描かれている気がしてなりません。
この記事では、まず「花吹雪」がどのような物語であるか、結末に触れつつ詳しくお話しします。物語の核心部分にも言及しますので、まだ読んでいないけれど結末は知りたくない、という方はご注意くださいね。物語の展開を知った上で、さらに深く作品を味わいたい方のために、後半では詳細な感想を述べています。
なぜ黄村先生は武術に目覚めたのか、文豪たちの意外な逸話は何を意味するのか、そして桜舞い散る中で起こった出来事は何を象徴しているのか。私なりに感じたこと、考えたことを、存分に語らせていただきたいと思います。太宰治の世界に、少しでも深く触れるきっかけになれば幸いです。
小説「花吹雪」のあらすじ
物語は、語り手である「私」が、大学教師である黄村先生(おうそんせんせい)の家に招かれる場面から始まります。黄村先生は時折、「私」や学生たちを集めては持論を披露するのが常なのですが、この日のテーマは「男子たる者、腕っぷしが強くなければならぬ」というものでした。先生曰く、武術の心得があれば、知的な仕事、例えば文学作品などにも自ずと風格や重みが備わるというのです。
先生は、文学と武術は縁遠いものと考えられがちだが、それは間違いだと力説します。柔道で高段位でも取れば、作品への批判もなくなるだろう、それは殴られることを恐れてではなく、作品自体が立派になるからだと主張します。そして、語り手「私」の作品を引き合いに出し、愚痴やいやみばかりと評されるのは、精神的な強さ、確固たる自信がないからだと指摘するのでした。
この持論を補強するために、先生は明治の文豪、森鷗外と夏目漱石の「武勇伝」を紹介します。鷗外は、宴席で自身に嫌味を言った記者と取っ組み合いの喧嘩をした逸話があり、その文章には「凜乎(りんこ)たる気韻」があったと評します。漱石についても、銭湯で無礼な職人を一喝したエピソードを挙げ、裸で相手を威圧できるのは腕力に自信がある証拠であり、彼の作品にもその気概が表れているはずだと論じました。
先生の熱弁に、普段は先生の突飛な言動にやや呆れ気味の「私」も、自身の弱さを省みて感じ入るところがありました。かつて酔った学生に絡まれた際、恐怖で足が震え、それを正直に告白して事なきを得た経験を思い出し、鷗外や漱石のような毅然とした態度が取れなかった自分を恥じます。キリストでさえ、時には神殿の商人たちを鞭で追い払ったではないか、と先生の論に引き込まれていくのでした。
すっかり武術の重要性を確信した黄村先生は、自らも実践しようと思い立ちます。弓道場へ足を運びますが、慣れない手つきで弦を頬に打ち付けてしまい、痛い思いをする始末。それでも精神だけは会得した気になり、武者震いしながら歩いていたところ、日頃から馬が合わない近所の老画伯、杉田氏に屋台で遭遇し、嫌味を言われてしまいます。
いつもなら泣き寝入りするところですが、武術の精神(?)に目覚めた先生は違いました。画伯を呼び止め、決闘を申し込みます。しかし、殴り返されることを想定し、大事な入れ歯を外して地面に置いたため、啖呵は歯切れの悪いものに。それでも果敢に画伯の頬を張ると、溜飲を下げて立ち去ろうとします。ところが、季節は春。満開の桜から絶えず花びらが舞い落ち、地面に置いたはずの入れ歯が花吹雪に埋もれて見えなくなってしまったのです。先生は狼狽し、必死に入れ歯を探し始めます。殴られた画伯も、その様子を見て、一緒に探し始めてくれるのでした。
小説「花吹雪」の長文感想(ネタバレあり)
太宰治の「花吹雪」、何度読んでも実に味わい深い作品ですよね。黄村先生という、なんとも愛すべき人物造形にまず引き込まれます。大学の先生でありながら、どこか世間ずれしていて、突拍子もない思いつきで周囲を振り回す。でも、どこか憎めない。彼の語る「男子たるもの腕っぷしが強くあれ」という持論も、最初は「また始まったか」と思わせつつ、聞いているうちに妙な説得力を感じてしまうから不思議です。
この作品を読むたびに、黄村先生の姿に、太宰治自身の屈折した自意識や、弱さへの裏返しのような願望が投影されているのではないかと感じます。先生が熱弁する「腕に覚えさえあれば、知的な仕事にも自然と風格が出る」という言葉。これは、ひ弱で繊細な精神を持つと自認していた(あるいは、そう見られていた)太宰自身の、ある種の憧れやコンプレックスの表れだったのかもしれません。
先生が持ち出す鷗外や漱石の武勇伝も面白いですよね。軍医として戦地も経験した鷗外が記者と取っ組み合いの喧嘩をした話、漱石が銭湯で職人を一喝した話。これらのエピソードを通して、黄村先生(そして太宰)は、彼らの文学に感じられる「凜乎たる気韻」の源泉を、その身体的な強さや、いざとなれば腕力に訴えることも辞さない気概に見出そうとしているようです。
「凜乎たる気韻」という表現、実に的確だと思いませんか。鷗外や漱石の文章には、確かに、現代の作家にはないような、背筋が伸びるような、ある種の厳しさや格調高さが感じられます。それが本当に武術の心得に由来するものかは分かりませんが、黄村先生がそう主張する気持ちは、なんとなく理解できる気がします。精神的な強靭さと身体的な強靭さが、どこかで結びついているのではないか、という感覚です。
参考資料として提示された文章にある、明治の七宝作家、並河靖之のエピソードも興味深いですね。彼が元々馬術の名手であったこと、そして彼の作品が持つ「清澄な静けさの奥から醸される、絶対的な存在感」が、鷗外や漱石の文章に通じる「凜乎たる気韻」と結びつけて語られています。これもまた、「身体的な鍛錬や能力が、芸術的な表現に影響を与える」という黄村先生の(そして太宰の?)考えを補強する材料になるのかもしれません。
一方で、語り手である「私」の反応も、この作品の重要な要素です。彼は、黄村先生の突飛な言動に呆れつつも、その言葉に心を動かされ、自身の弱さを省みます。酔った学生に絡まれた時の情けない対応を思い出し、「僕だって柔道五段か何かであったなら、あんな無礼者は、ゆるして置かんのだが」と悔しがる姿は、読者自身の心の中にあるかもしれない弱さや不甲斐なさと共鳴する部分ではないでしょうか。
キリストの例まで持ち出して武術の重要性を説く黄村先生の論に、「私」が引き込まれていく過程は、滑稽でありながらも、どこか切実です。「右の頬を打たれたなら左の頬を」という教えも、それは強者が持つ余裕であって、自分のような弱者がただ殴られるがままになっているのとは違うのだ、という解釈。そして「キリストだって、いざという時には、やったのだ」と、意外な側面を見出す。このあたり、太宰らしい理屈っぽさと、弱者の自己正当化にも似た切なさが滲み出ています。
そして物語は、黄村先生がその持論を実践しようとして起こる、クライマックスの入れ歯紛失事件へと向かいます。弓道で弦に頬を打たれるという、早くも挫折を予感させるエピソードを挟みつつ、いよいよ宿敵(?)の杉田老画伯との対決。意気込んで啖呵を切ろうとするも、入れ歯を外したために歯切れが悪くなるあたり、もう笑いをこらえるのが大変です。
しかし、この滑稽な騒動の結末が、また素晴らしい。殴った相手である黄村先生の入れ歯を、殴られたはずの杉田老画伯が一緒になって探してくれる。しかも、箒まで借りてきて、桜の花びらをかき分けながら。「あ! ありましたあ!」と、自分のことのように喜んでくれる老画伯。この場面には、人間の意地や対立を超えた、どこか温かいものが流れているように感じます。
入れ歯が見つかった嬉しさと、老画伯の邪念のない親切心に対する感謝。「入歯なんかどうでもいいというような気持にさえ相成り」ながらも、やはり見つかって嬉しい。その複雑な心境で口にした入れ歯には、桜の花びらが付着していて、「幽かに渋い味」がする。この描写が、なんとも言えません。春の美しい情景の中で繰り広げられた、あまりにも人間臭いドタバタ劇。その最後に残ったほろ苦い味覚は、人生の機微そのものを象徴しているかのようです。
そして、お詫びにと頬を差し出す先生に対し、老画伯が「よし来た」とばかりに、思い切り殴り返す。手加減なしの一撃に、先生は目から星が出る思いをするわけですが、その相手を「かれもまた、なかなかの馬鹿者に候」と評するところに、またおかしみと、ある種の諦観、そして奇妙な連帯感のようなものが感じられます。結局、腕っぷしを強くしようという試みは、とんだ騒動に終わったわけですが、その過程で、もっと大切な何か、人間同士の滑稽さや愛おしさのようなものに触れたのではないでしょうか。
太宰治は、しばしば「弱者の文学」と評されます。三島由紀夫が批判したように、「治りたがらない病人」のようなイメージを持たれることもあります。しかし、「花吹雪」を読むと、太宰は決して単に弱さを描いているだけではないと感じます。むしろ、人間の持つ弱さ、滑稽さ、見栄、意地、そういったものを全てひっくるめて、温かい眼差しで見つめている。そして、それを読者に「サーヴィス」として提供してくれる。黄村先生や「私」の姿に、読者は自分自身の情けなさや可笑しさを見出し、どこか救われたような気持ちになるのかもしれません。
この作品には、鷗外や漱石のような「凜乎たる気韻」はないかもしれません。しかし、そこには、満開の桜の下で繰り広げられる人間喜劇のような、えもいわれぬおかしみと、入れ歯に付いた桜の花びらのような、ほろ苦くも忘れがたい味わいがあります。それこそが、太宰治だけが持つ、唯一無二の魅力なのではないでしょうか。武術を身につけることの是非はともかく、人と人との間に起こる、思いがけない出来事や感情の綾を描き出す手腕は、やはり見事と言うほかありません。読むたびに、黄村先生と老画伯の姿が目に浮かび、ふふっと笑ってしまう、そんな作品です。
まとめ
太宰治の短編「花吹雪」は、一風変わった大学教師・黄村先生が「男子たるもの腕っぷしが強くあるべし」という持論を掲げ、それを実践しようとして騒動を巻き起こす物語です。そのあらすじは、先生の熱弁から始まり、鷗外や漱石の武勇伝の紹介、そしてクライマックスの入れ歯紛失事件へと展開します。結末では、いがみ合っていたはずの老画伯との間に奇妙な和解が訪れ、ほろ苦い余韻を残します。
この物語の魅力は、まず黄村先生というキャラクターの滑稽さと愛おしさにあります。彼の突飛な言動は笑いを誘いますが、その根底には人間の弱さや見栄、そしてささやかな矜持が見え隠れします。語り手「私」の視点を通して、読者もまた自身の内面と向き合うことになるでしょう。鷗外や漱石のエピソードは、「武術と文学」というテーマに深みを与え、考えさせられる点があります。
感想として特筆すべきは、やはり入れ歯紛失から和解に至るまでの、桜舞い散る情景の中での描写です。人間の滑稽さ、意地の張り合い、そして予期せぬ優しさや連帯感が、美しい情景と相まって鮮やかに描かれています。入れ歯に付着した桜の花びらの「渋い味」は、この作品の持つ独特の味わいを象徴しているようです。
「花吹雪」は、太宰治の他の代表作とは少し異なる趣を持ちながらも、人間の弱さや愚かさを温かく見つめる太宰ならではの視線が貫かれています。読後には、登場人物たちの人間臭さに思わず笑みがこぼれ、同時に人生のほろ苦さや複雑さについて、ふと考えさせられるような、そんな深い印象を残す作品だと言えるでしょう。




























































