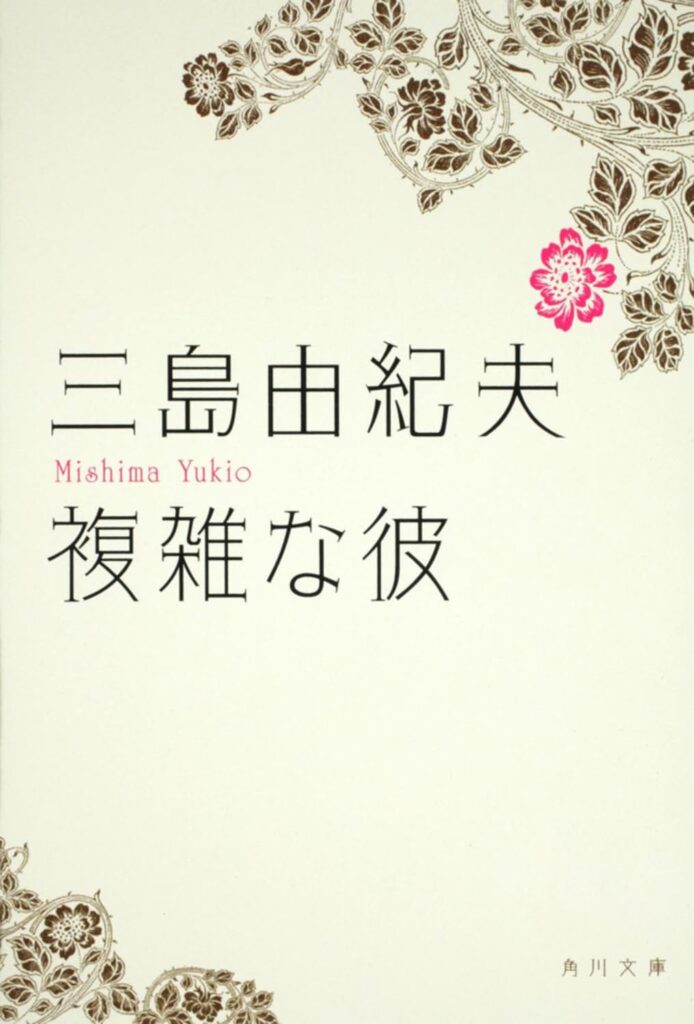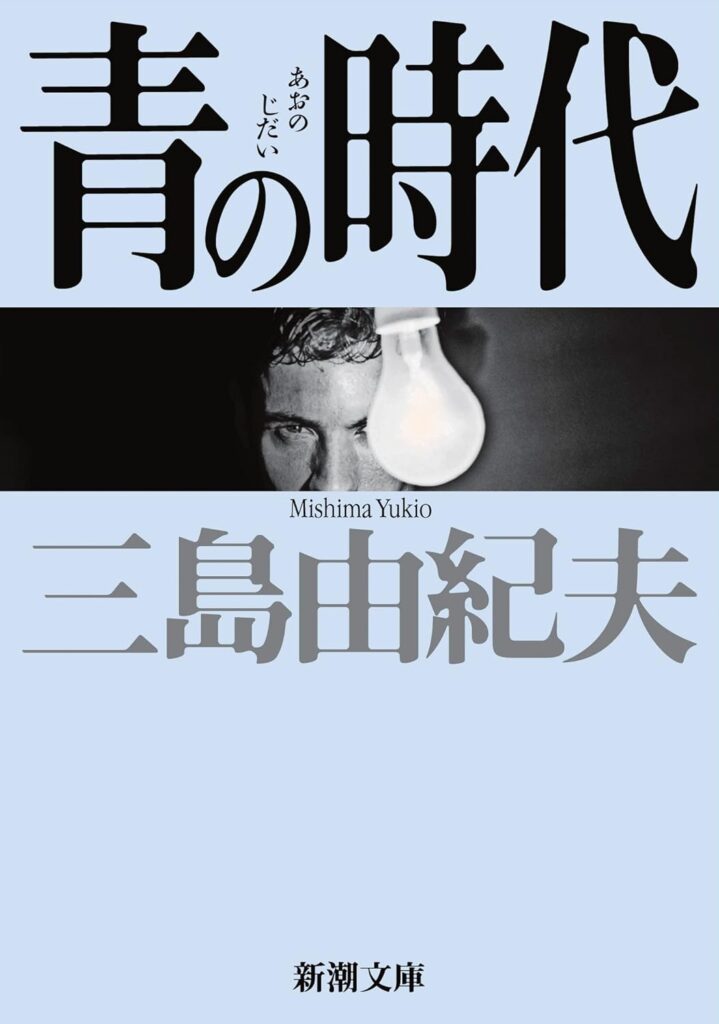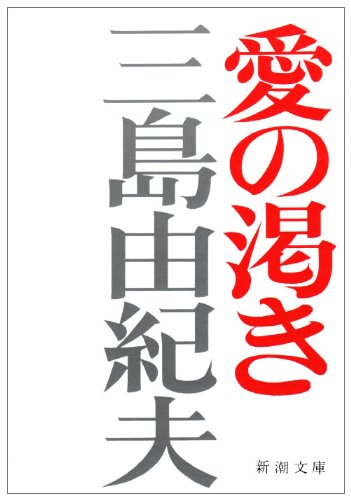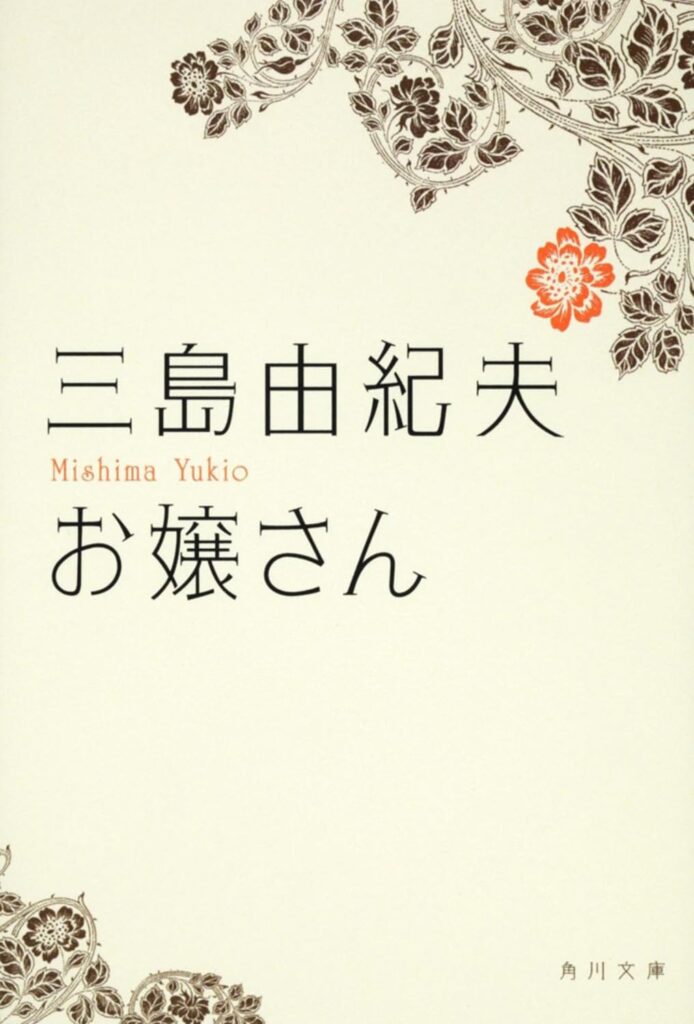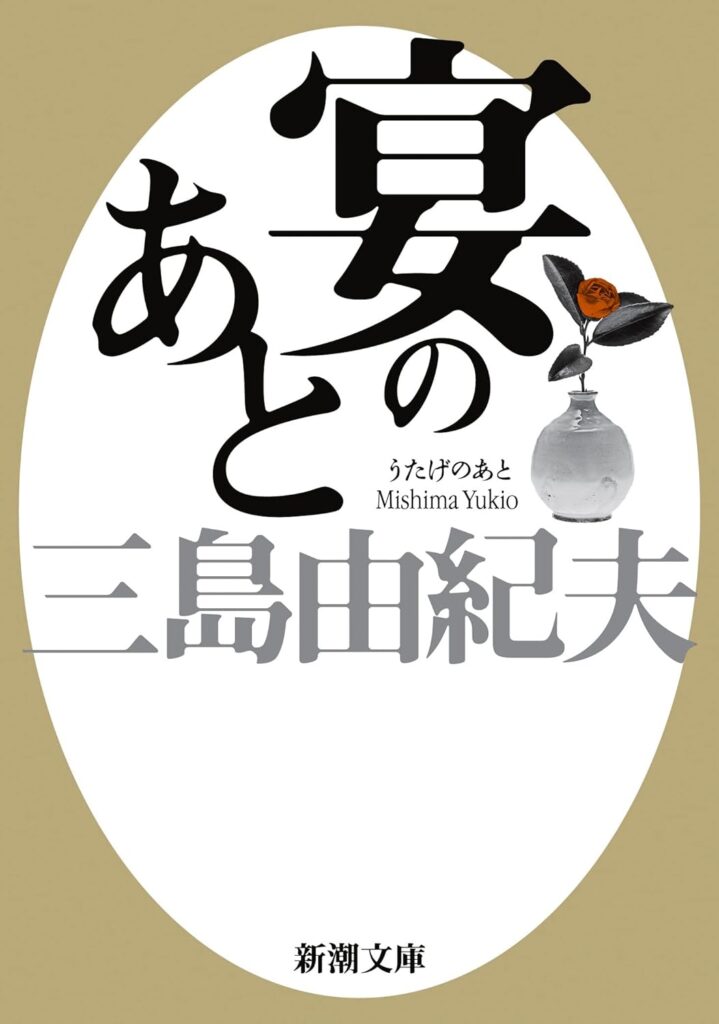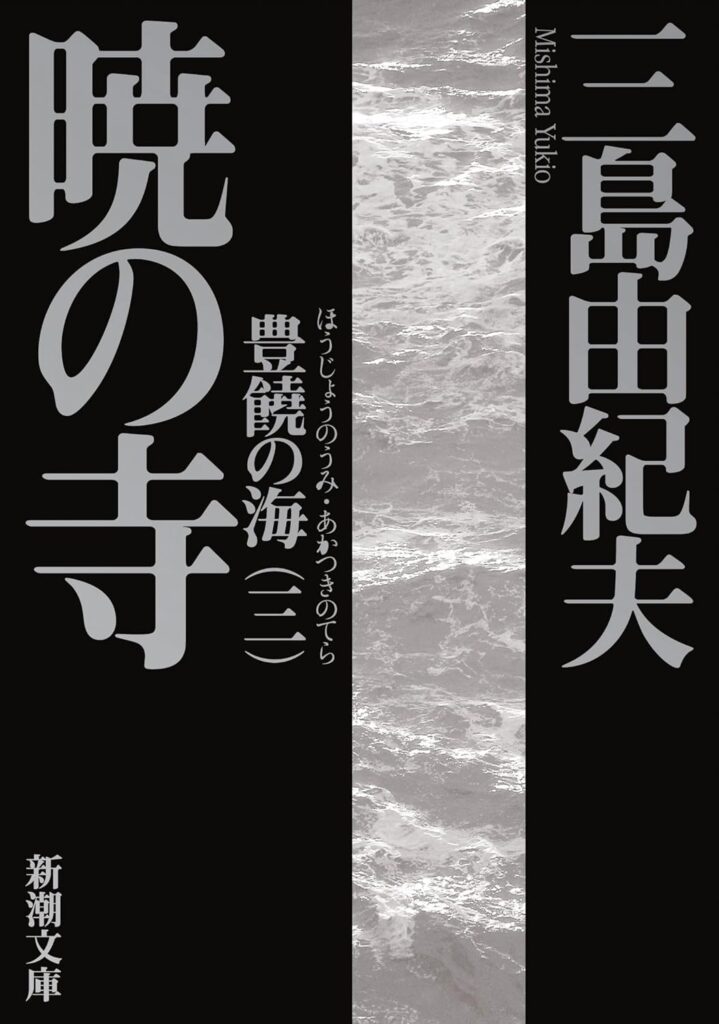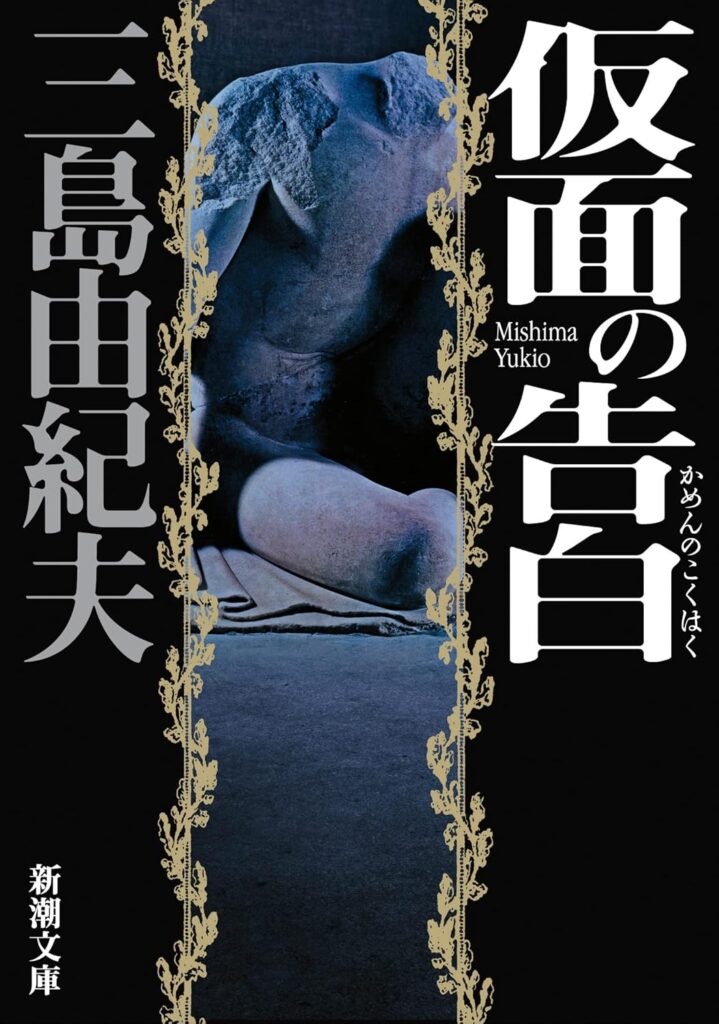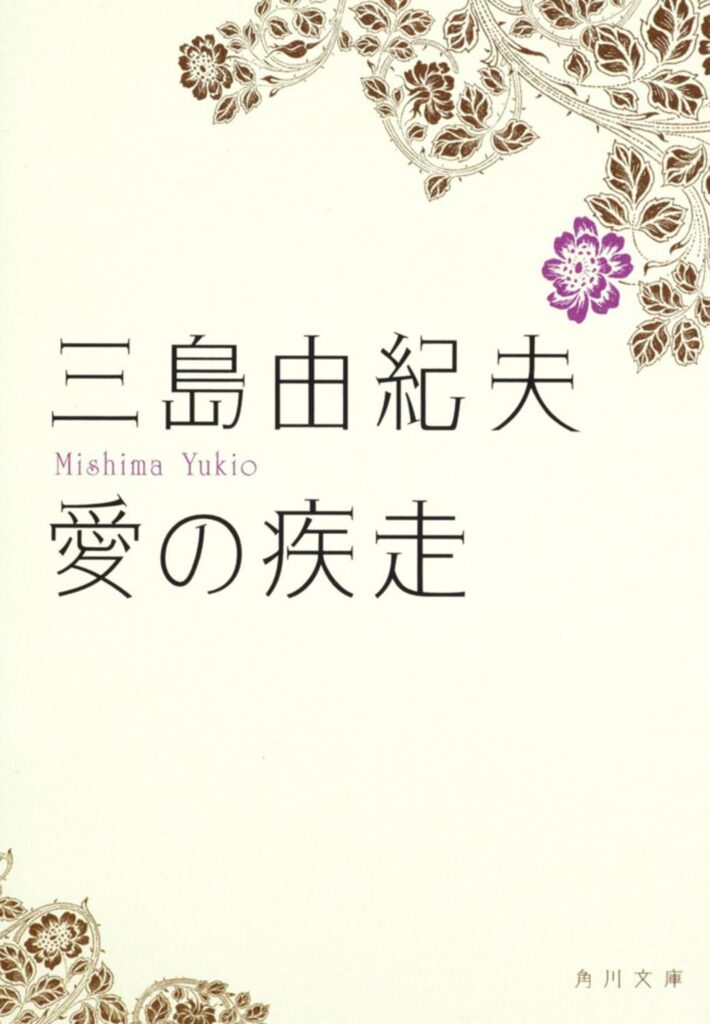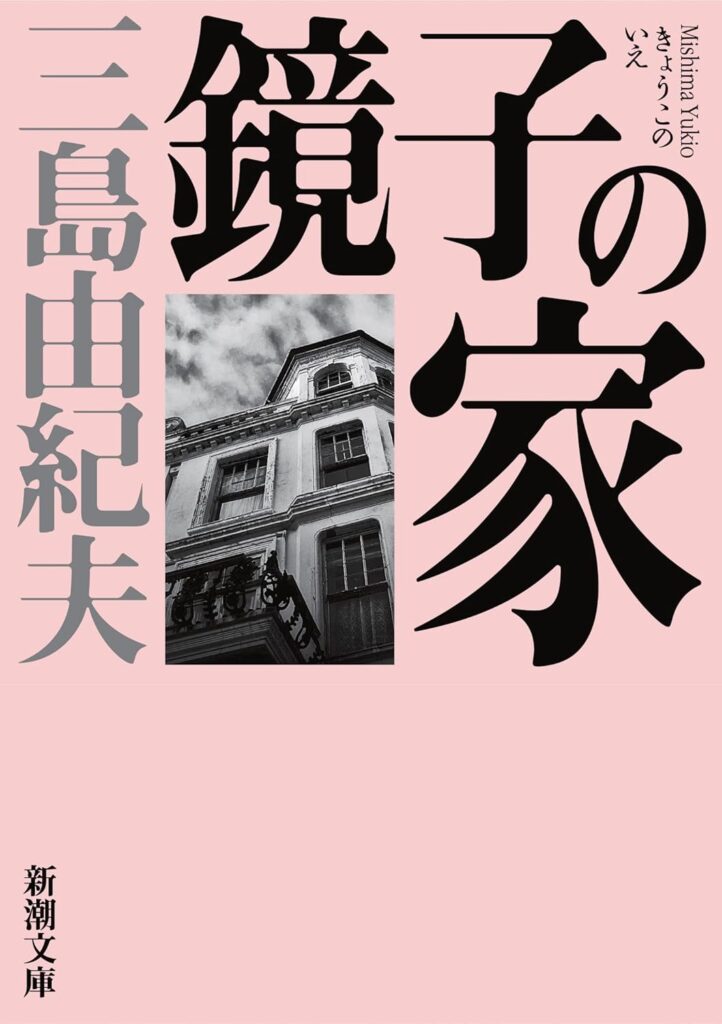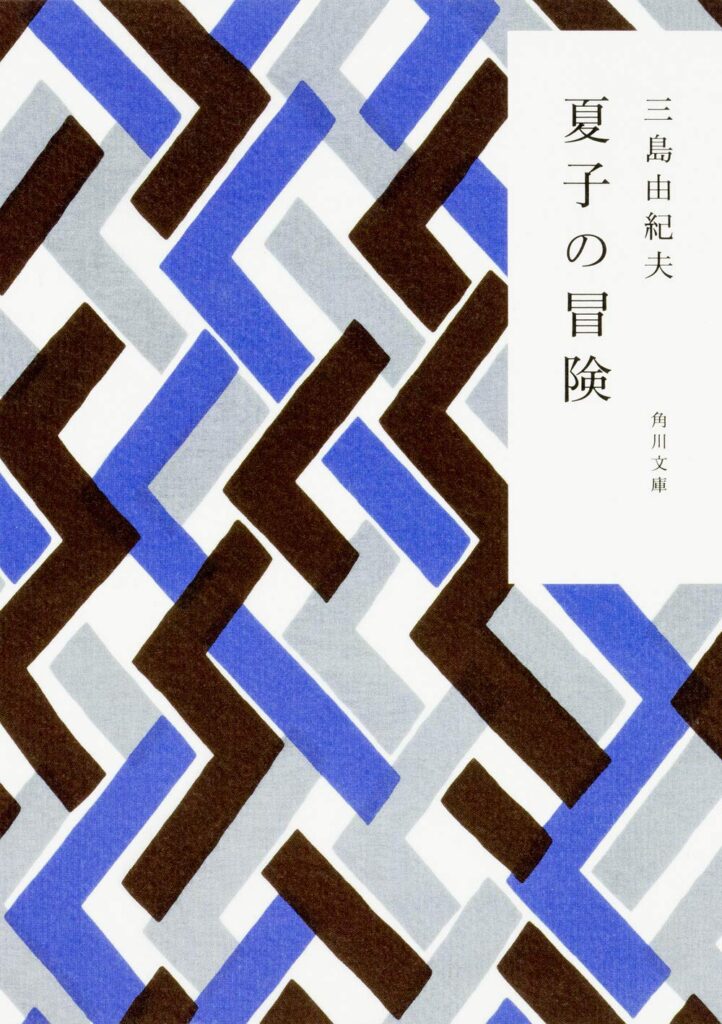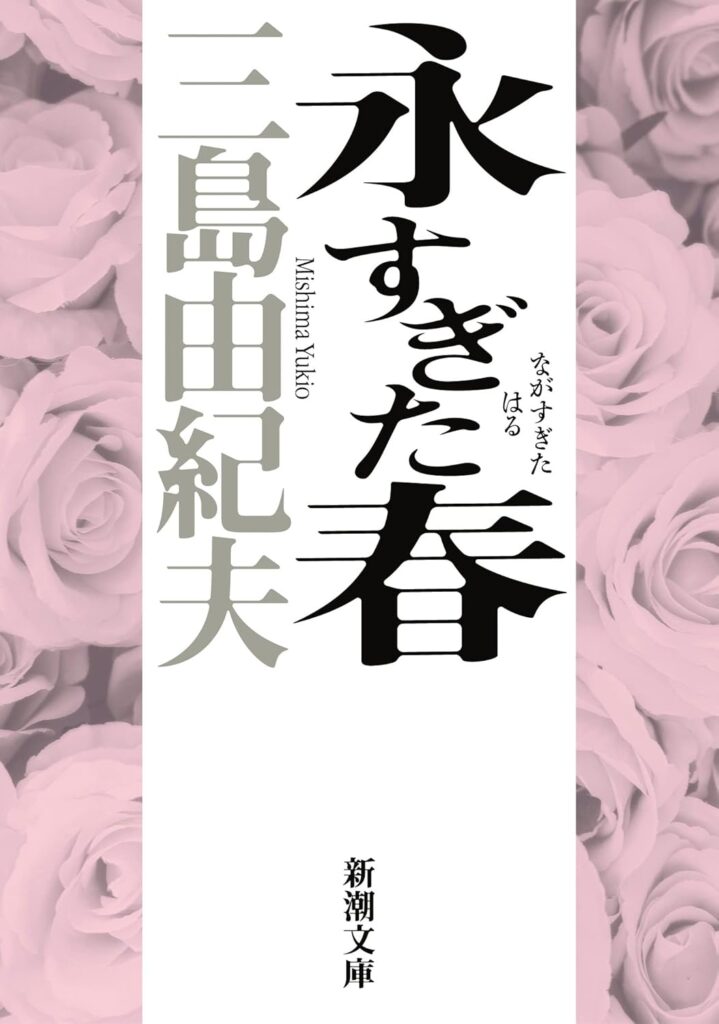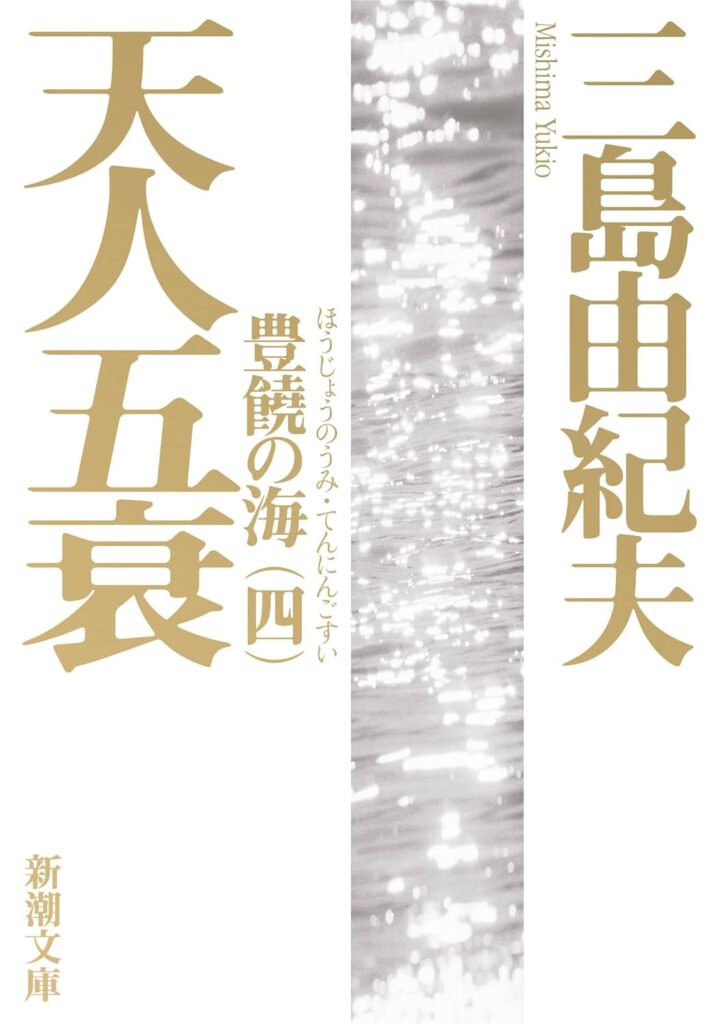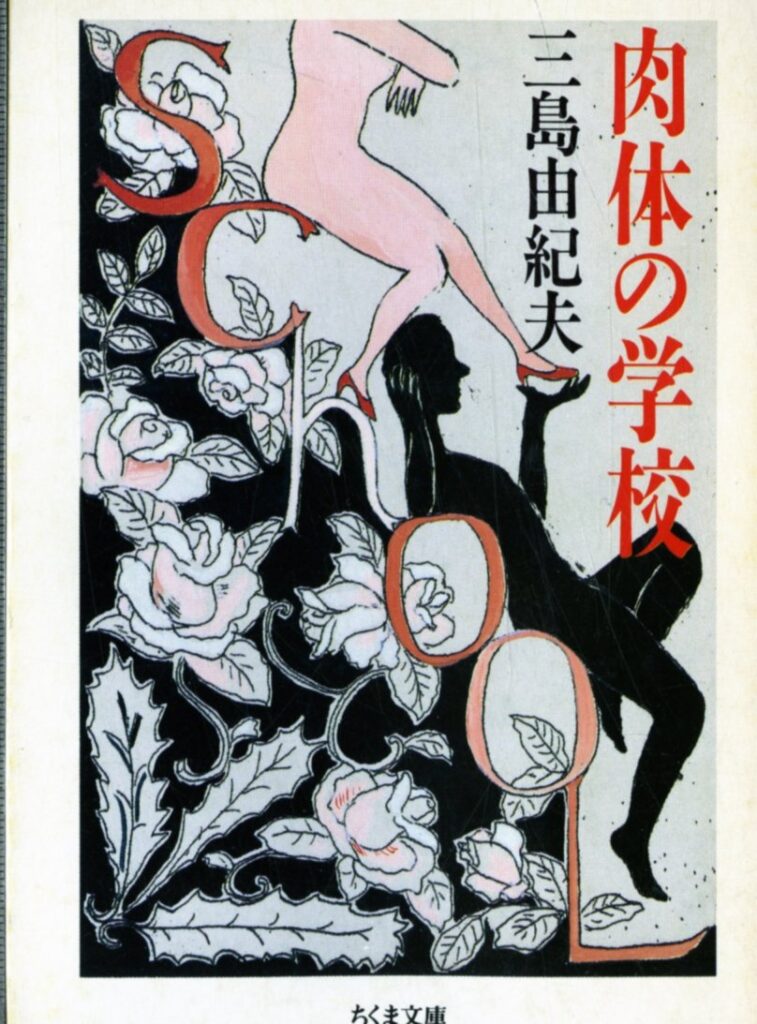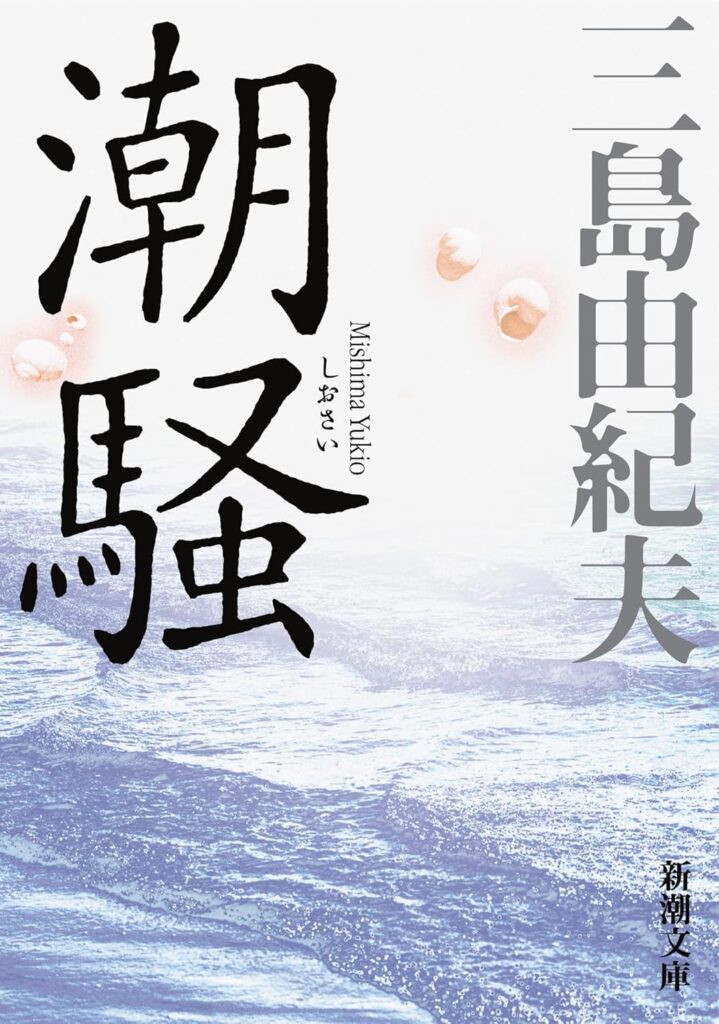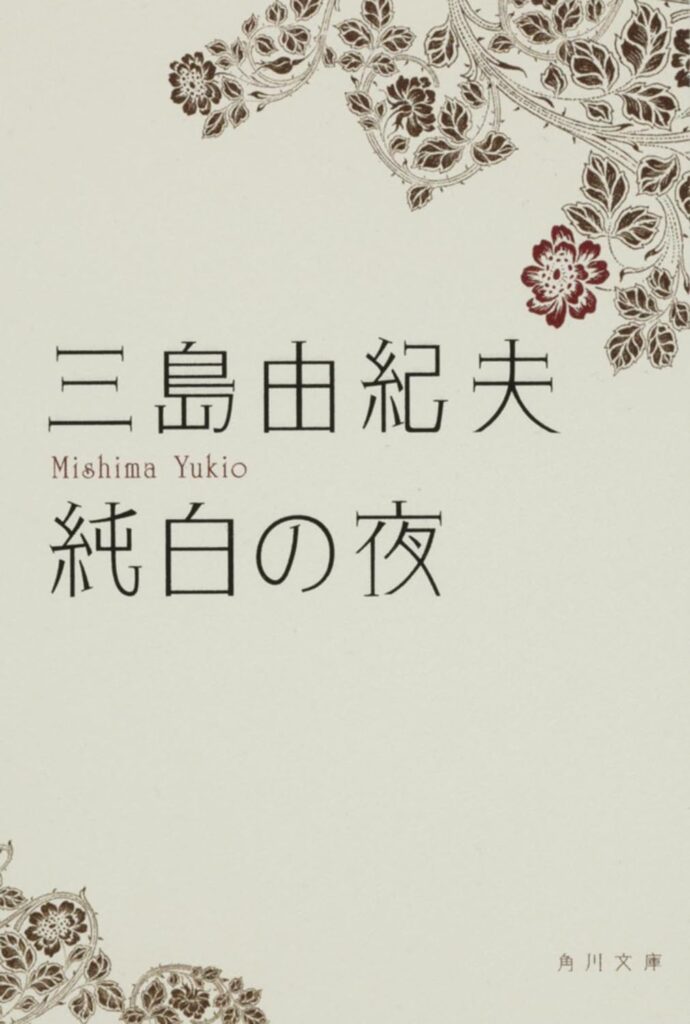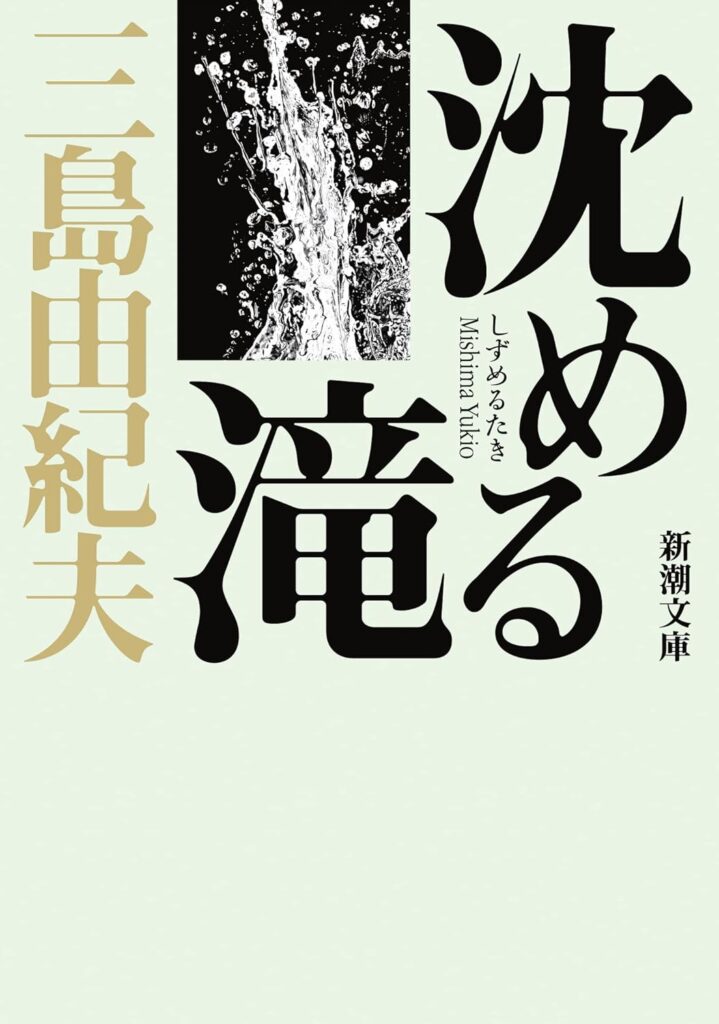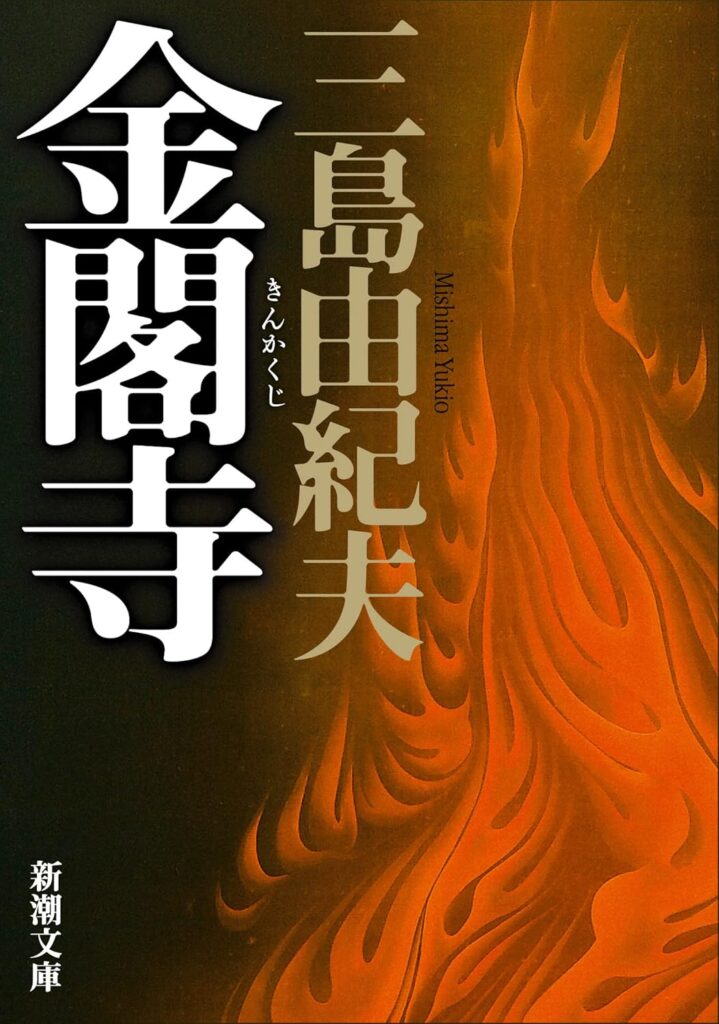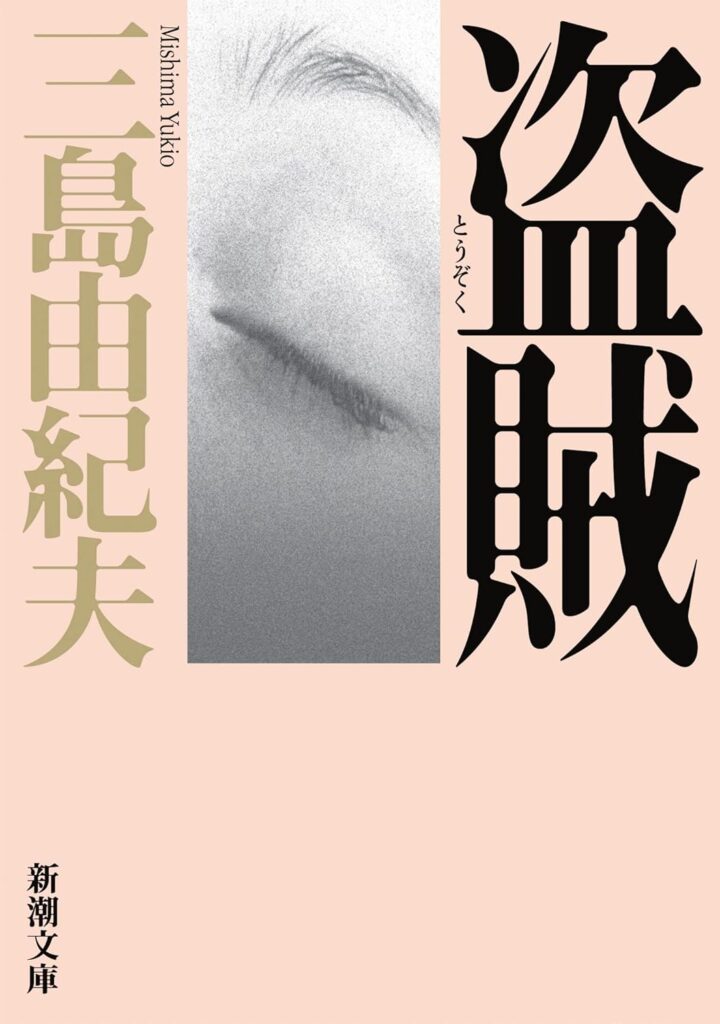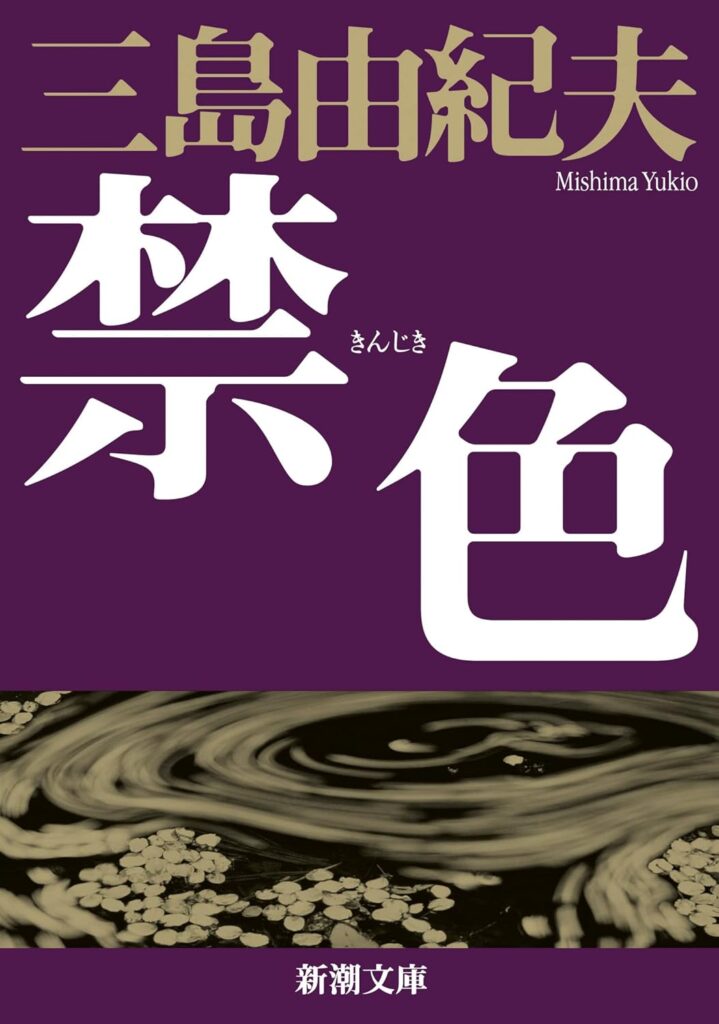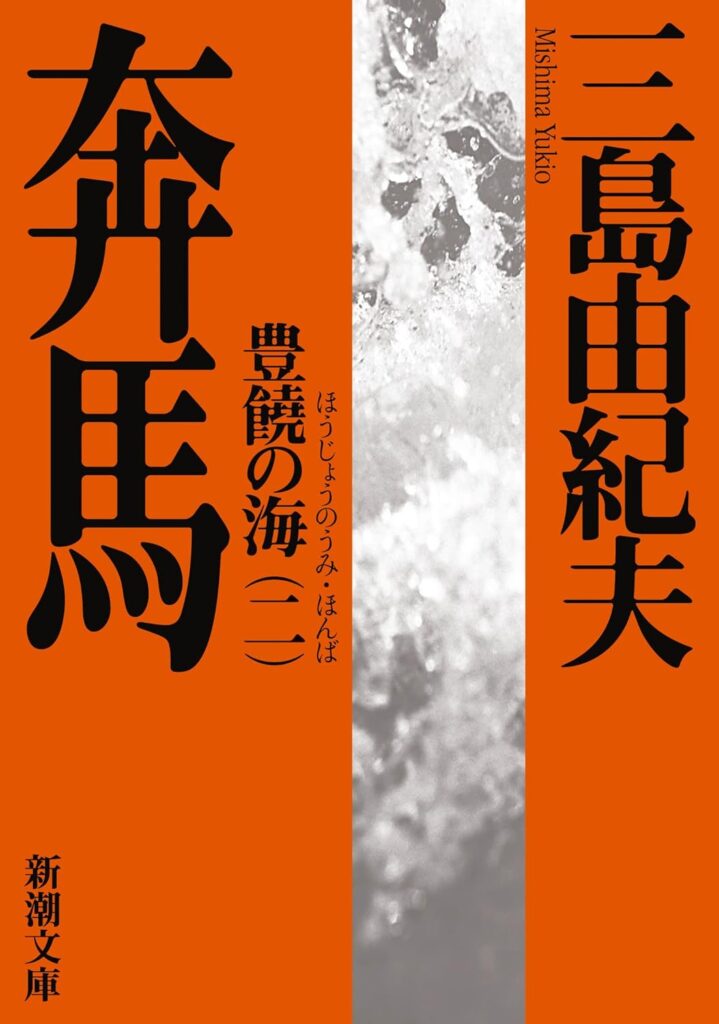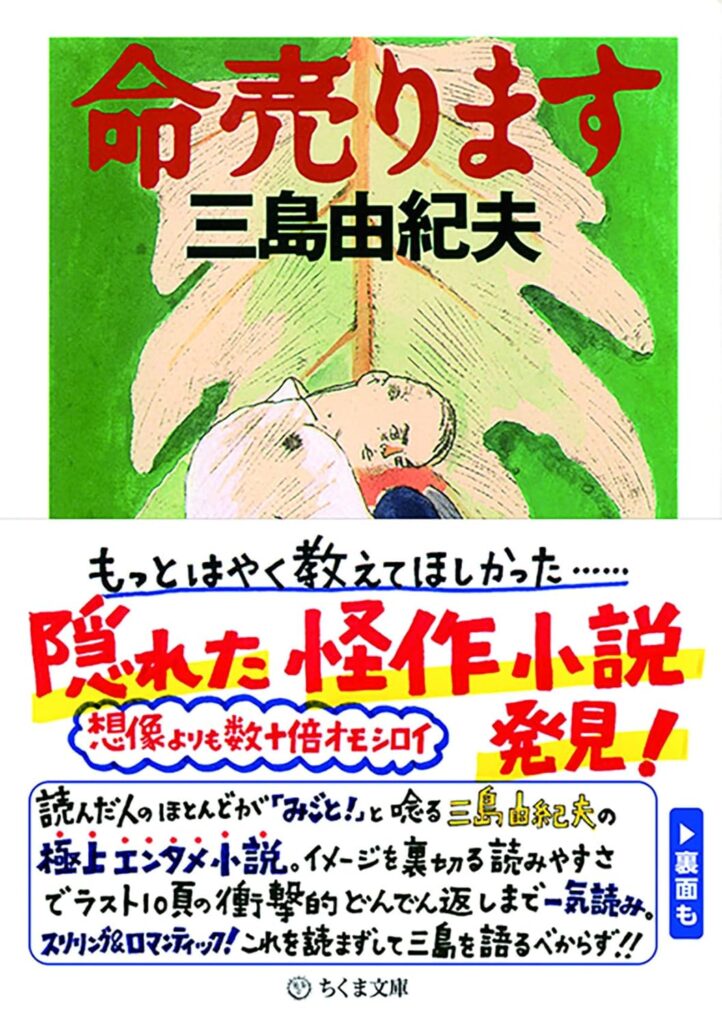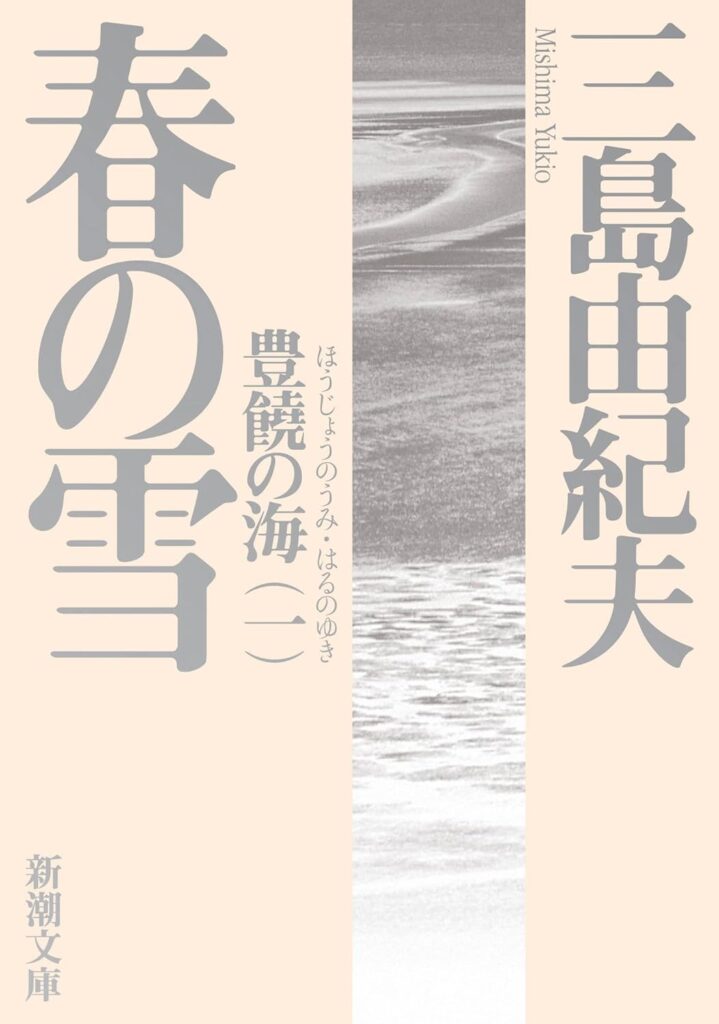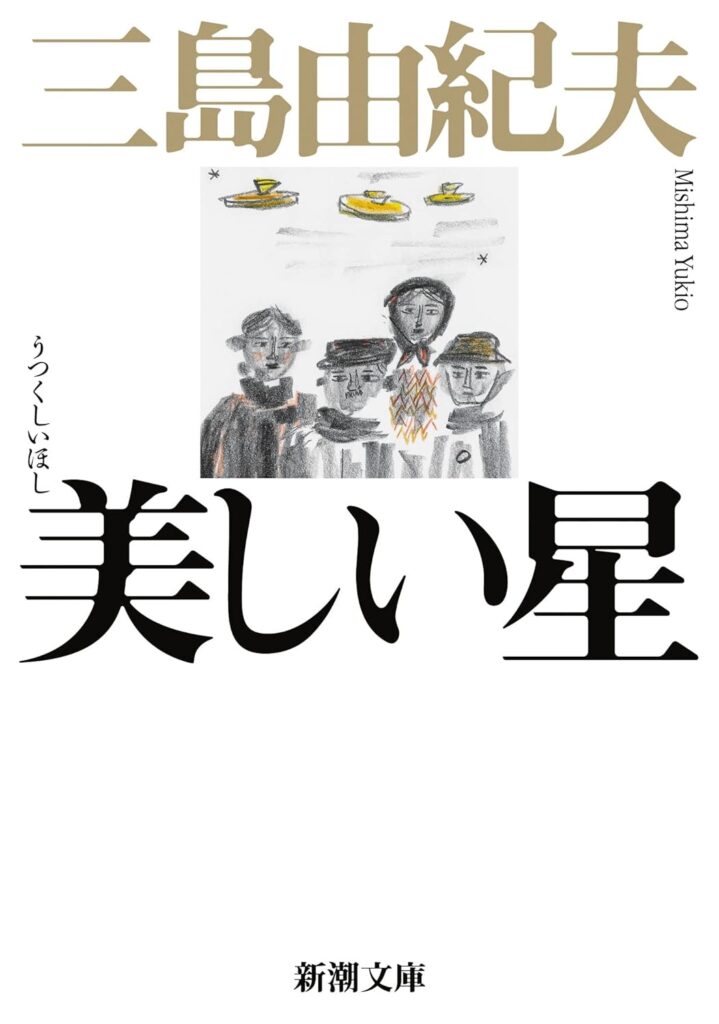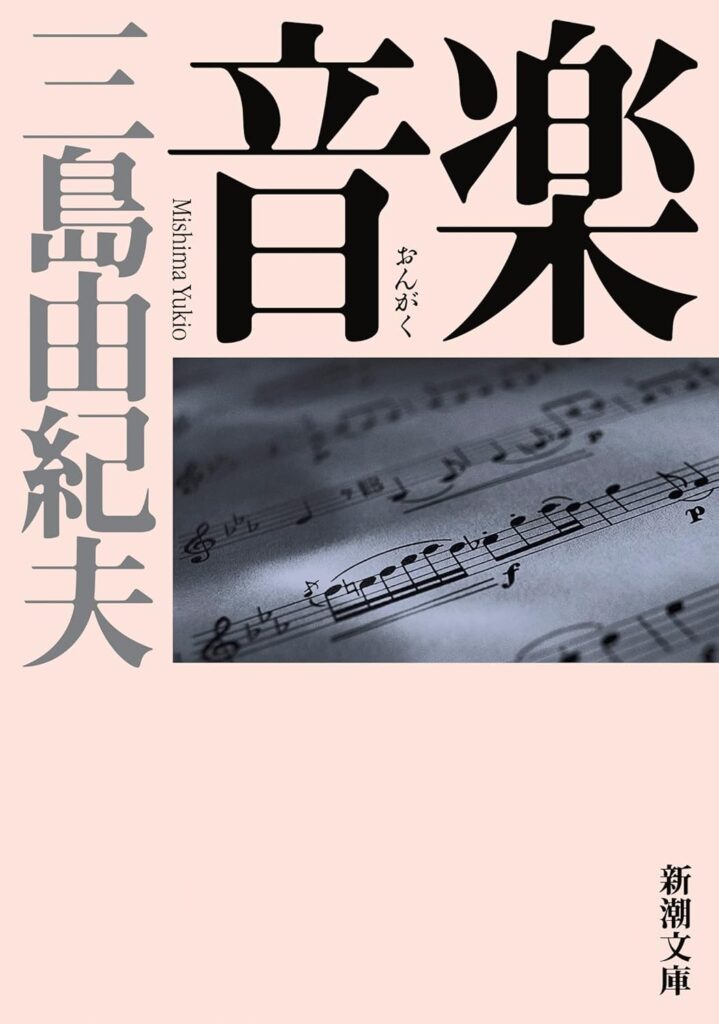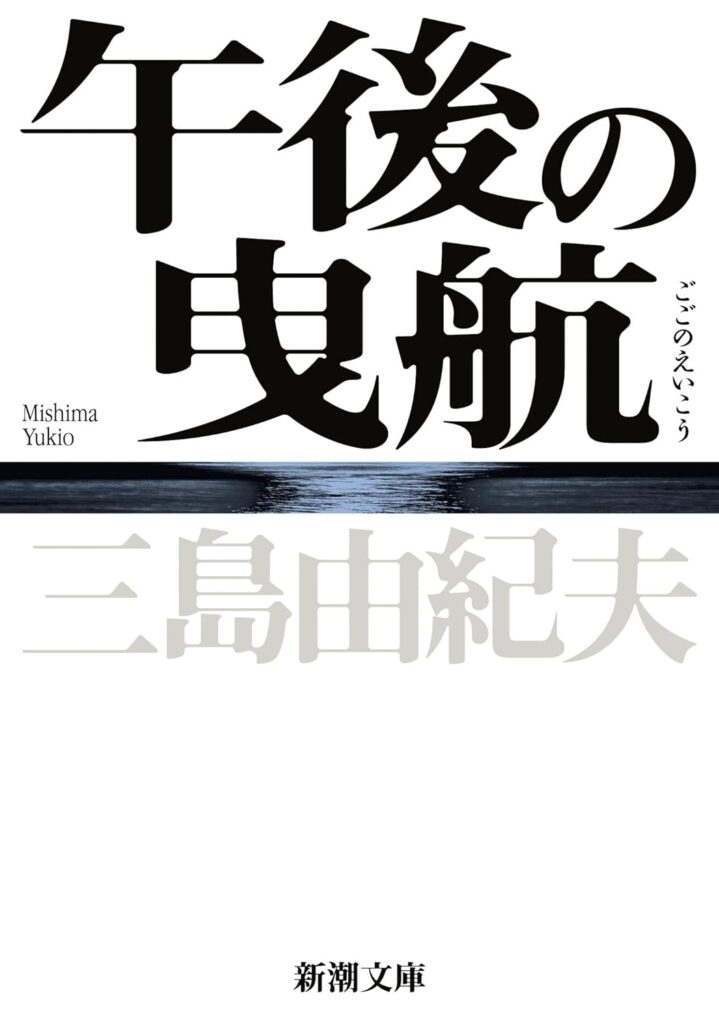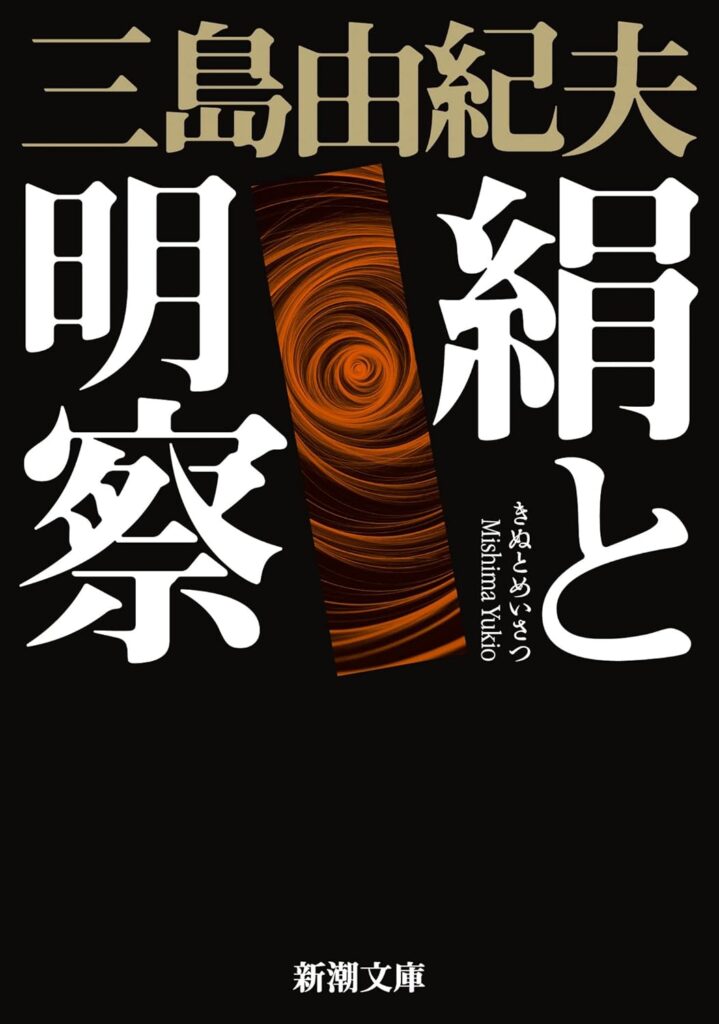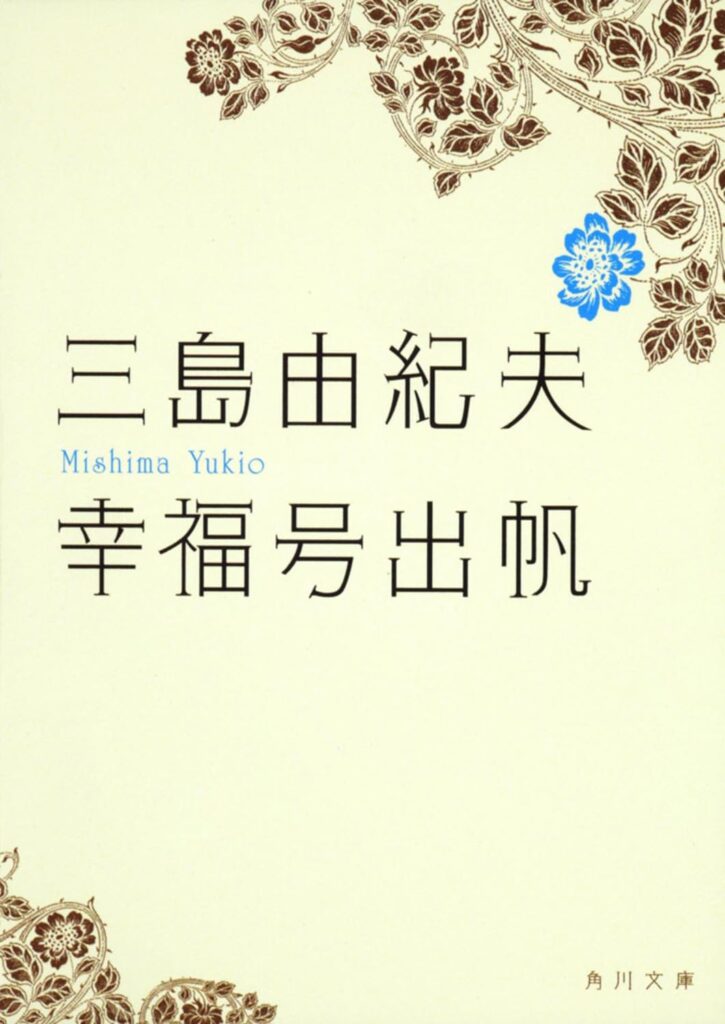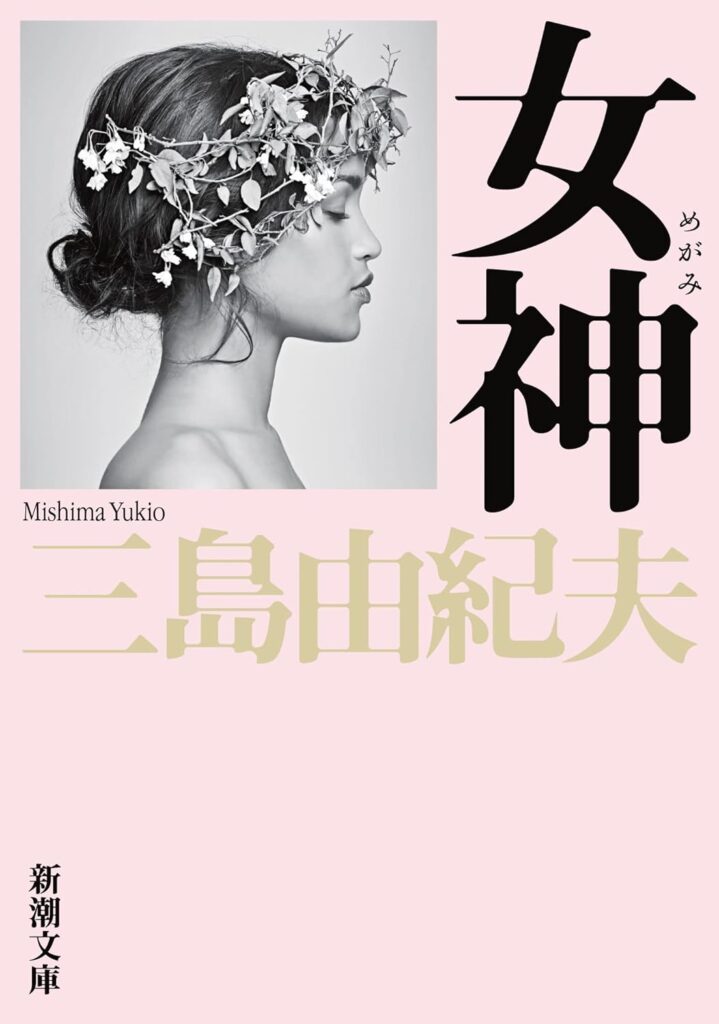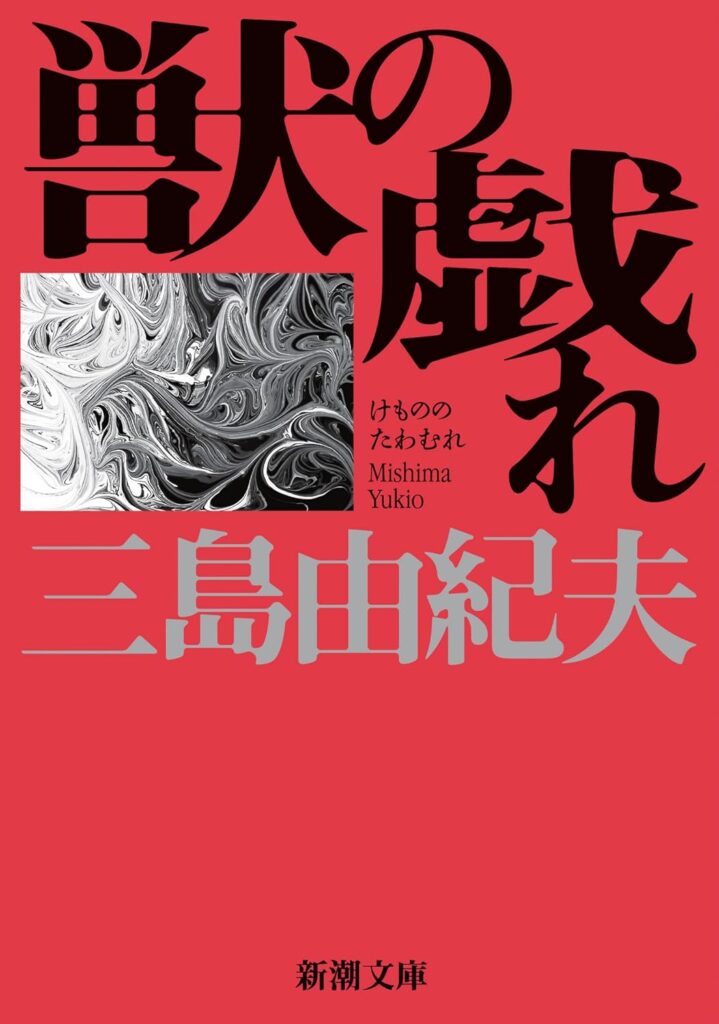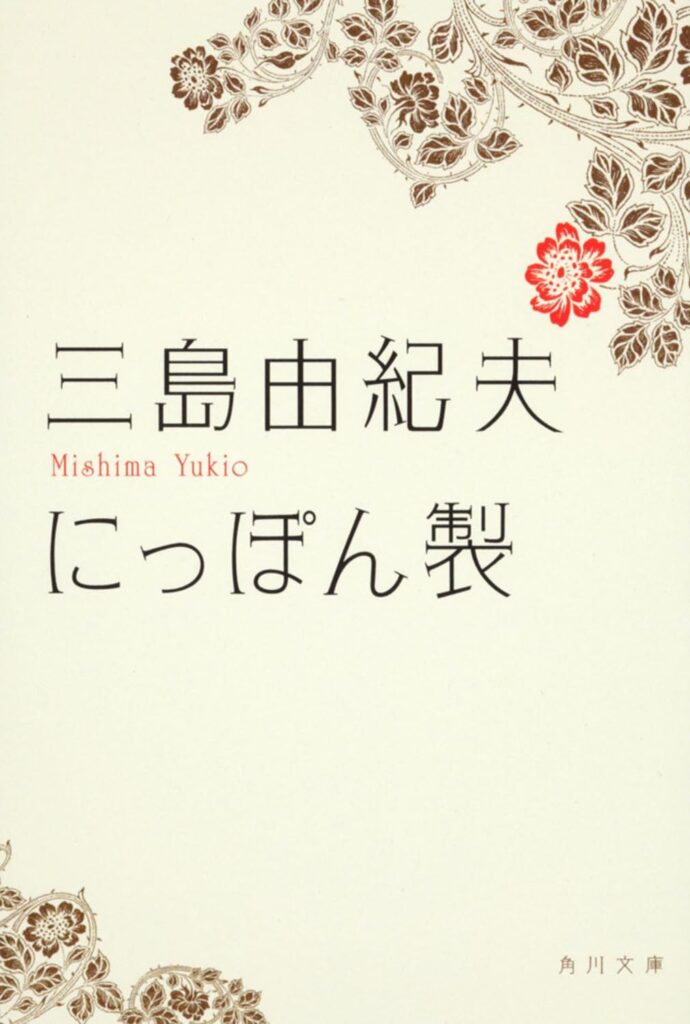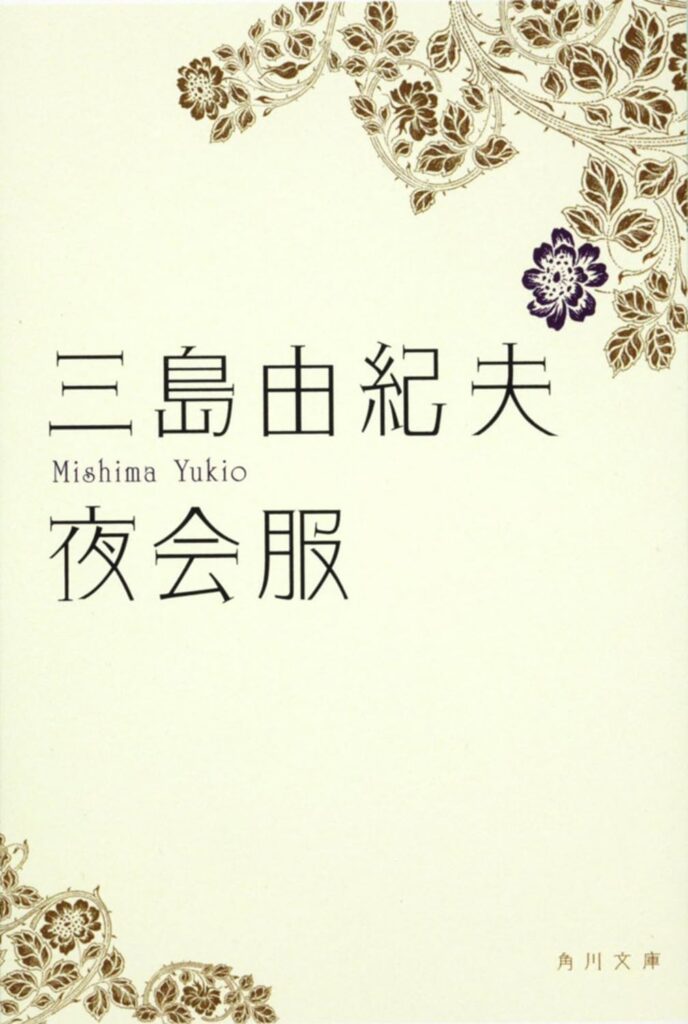小説「美徳のよろめき」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、一見すると華やかで何不自由ない生活を送る上流階級の夫人、倉越節子の心の揺らぎと、それが引き起こす出来事を描いた作品です。彼女の日常に潜む退屈と、満たされない渇望が、ある出会いをきっかけに大きく動き出します。
小説「美徳のよろめき」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、一見すると華やかで何不自由ない生活を送る上流階級の夫人、倉越節子の心の揺らぎと、それが引き起こす出来事を描いた作品です。彼女の日常に潜む退屈と、満たされない渇望が、ある出会いをきっかけに大きく動き出します。
節子の夫である一郎は仕事に多忙で、家庭を顧みることが少ない人物。夫婦の間には、もはや情熱と呼べるものはなく、穏やかではあるものの、どこか空虚な時間が流れています。そんな中、節子はかつて知己のあった青年、土屋と再会し、禁断の関係へと足を踏み入れてしまいます。この物語は、当時の社会における女性の立場や道徳観を背景に、一人の女性の心の奥深くを鋭くえぐり出しています。
読者は、節子の行動を通じて、人間の内に秘められた欲望や、社会的な規範との間で揺れ動く心理を垣間見ることになるでしょう。そして、彼女が最終的にどのような結末を迎えるのか、その過程で何を感じ、何を選ぶのか、目が離せない展開が待っています。この記事では、物語の核心に触れつつ、その魅力や奥深さについて、じっくりとお伝えしていきたいと思います。
本作品は、三島由紀夫ならではの緻密な心理描写と、洗練された文体で綴られており、発表から長い年月を経た今もなお、多くの読者を惹きつけてやみません。節子の「よろめき」が何を意味するのか、そして彼女の選択が私たちに何を問いかけるのか。一緒に物語の世界へ深く分け入ってみましょう。
小説「美徳のよろめき」のあらすじ
倉越節子は、誰もが羨むような恵まれた環境で育ち、名家の倉越一郎と結婚した28歳の若妻です。彼女の日常は、一見すると穏やかで満ち足りているように見えました。しかし、その胸の内には、夫との間に存在する埋めがたい溝と、繰り返される日々の単調さからくる空虚感が渦巻いていました。夫の一郎は仕事人間で、家庭を顧みることはほとんどありません。息子の菊夫はまだ幼く、節子の孤独を癒やすには至りません。
そんなある日、節子は舞踏会で土屋という青年と再会します。彼は節子が結婚する前から面識のあった男性で、洗練された魅力を持つ人物でした。この再会が、節子の退屈な日常に波紋を投じます。土屋は節子に近づき、ある日の午後、彼女の家の近くの駅で待っていると囁くのです。節子はその誘いを一度は無視しようとしますが、心のどこかで彼の訪問を期待している自分に気づきます。
やがて節子は土屋との密会を重ねるようになります。それは、これまでの貞淑な妻としての自分を裏切る行為であり、背徳的な喜びと罪悪感が入り混じる複雑な感情を彼女にもたらしました。節子の友人である与志子は、彼女の行動をある程度察しながらも、時にはその秘密の恋に手を貸すような素振りも見せます。節子は、この許されない関係にますます深くのめり込んでいくのでした。
しかし、そんな関係にも変化が訪れます。節子は予期せぬ妊娠に気づき、動揺します。土屋との関係にも、次第に不穏な影が差し始めます。土屋には別の女性の存在がちらつき、節子は初めての激しい嫉妬心に駆られます。彼女は誰にも相談できず、一人で苦悩を抱え込み、中絶手術を受けることを決意します。
手術を終え、心身ともに疲れ果てた節子。そんな彼女のもとに、土屋が他の女性と親密にしているという情報がもたらされます。この裏切りは、節子に深い絶望感を与え、土屋との関係の終わりを悟らせます。彼女は、これまで自分が築き上げてきたもの、そして失ったものの大きさを痛感するのでした。
ある日、節子は政府の要職にある父、藤井景安に食事に招かれます。そこで父が語ったのは、社会的なスキャンダルの恐ろしさと、自らの立場を守るための覚悟でした。父の「今の私はしあわせだ」という言葉は、節子の胸に深く突き刺さります。節子は、これ以上父に迷惑をかけることはできないと悟り、土屋との関係に完全に終止符を打つことを決意するのでした。彼女は土屋への想いを綴った手紙を書きますが、それを投函することなく破り捨てます。再び、長く退屈な午後が彼女の日常に戻ってきたのでした。
小説「美徳のよろめき」の長文感想(ネタバレあり)
三島由紀夫が描き出す「美徳のよろめき」の世界は、表面的な華やかさの裏に潜む人間の心の闇や、社会の規範と個人の欲望との相克を鋭く描き出した物語だと感じます。主人公である倉越節子の心理描写は特に秀逸で、読者は彼女の心の揺れ動きに共感したり、あるいは反発を覚えたりしながら、物語に深く引き込まれていくことでしょう。
節子は、上流階級の出身で、何不自由ない生活を送っているように見えます。しかし、その内面は、夫との精神的な繋がりの欠如や、繰り返される日常への倦怠感で満たされていません。彼女の心にぽっかりと空いた穴は、夫の一郎が仕事にかまけて家庭を顧みないことで、さらに深まっていきます。一郎は、節子の心の渇望に気づこうともせず、ただ黙々と会社と家を往復する日々。この夫婦のコミュニケーション不全は、節子が禁断の恋へと踏み出す大きな要因の一つと言えるのではないでしょうか。
土屋との出会いは、そんな節子の心に一筋の光を投げかけたように見えたかもしれません。彼は、夫にはない洗練された物腰と情熱的なアプローチで節子を魅了します。節子が土屋との関係にのめり込んでいく様は、まるで乾いた大地が水を求めるかのようです。しかし、その関係は初めから危うさをはらんでいました。「よろめき」という言葉が示す通り、それは確固たるものではなく、いつ崩れてもおかしくない不安定なものだったのです。
節子の友人である与志子の存在も、この物語において興味深い役割を担っています。彼女は節子の秘密を知りつつも、それを積極的に止めるわけでもなく、どこか遊戯的な態度で節子の恋を見守っているようにさえ見えます。与志子の存在は、当時の上流社会の一部の退廃的な雰囲気や、道徳観の揺らぎを象徴しているのかもしれません。彼女の助けを借りて、節子は土屋との逢瀬を重ねていきますが、それは同時に、社会的な規範からの逸脱を加速させることにも繋がりました。
物語が転機を迎えるのは、節子の妊娠と、それに続く土屋の裏切りです。節子は土屋の子を身ごもりますが、その事実は彼女に幸福ではなく、さらなる苦悩をもたらします。そして、土屋が他の女性と親密な関係にあることを知った時、節子の心は嫉妬と絶望で引き裂かれます。ここで描かれる節子の感情の激しさは、それまで彼女が抑圧してきたものが、いかに大きかったかを物語っています。彼女にとって土屋との恋は、単なる火遊びではなく、失われた自己を取り戻すための必死の試みだったのかもしれません。
しかし、その試みもまた、脆くも崩れ去ります。土屋の軽薄さと不誠実さは、節子にとって耐え難いものでした。彼女が土屋との関係を清算する決意を固める直接的なきっかけは、父・藤井景安の言葉でした。政府高官である父は、自身のスキャンダルが社会的な破滅を意味することを冷静に語ります。そして、「今の私はしあわせだ」と呟くのです。この父の言葉は、節子にとって重く響きます。それは、彼女自身の行動が、愛する家族にまで取り返しのつかない影響を及ぼす可能性を突きつけられた瞬間だったのではないでしょうか。
この作品における「美徳」とは一体何なのかを考えさせられます。節子が守ろうとした「美徳」は、社会的な体面や家柄、夫への貞淑といった、外的な規範であったように思えます。しかし、彼女の心は、そうした規範だけでは満たされず、「よろめき」を経験することでしか、生きている実感を得られなかったのかもしれません。それは、当時の社会において、女性が自己を実現する道が極めて限られていたことの表れとも言えるでしょう。
節子の行動は、決して褒められたものではありません。しかし、三島由紀夫は、彼女を単純な不貞の女として断罪するのではなく、その内面にある複雑な感情や、時代背景が生んだ悲劇性を丁寧に描き出しています。だからこそ、読者は節子の弱さや愚かさを感じつつも、どこかで彼女の苦悩に共感してしまうのかもしれません。
物語の終盤、節子は土屋への思いを断ち切るために、彼への手紙を書きます。そこには、彼と過ごした日々の思い出や感謝の言葉が綴られていました。しかし、彼女はその手紙を投函することなく、破り捨ててしまいます。この行為は、何を意味するのでしょうか。それは、過去との完全な決別であり、同時に、決して満たされることのなかった恋への諦念と、静かな悲しみの表れなのかもしれません。
あるいは、手紙を破り捨てるという行為自体が、節子にとって最後の主体的な選択であり、よろめいた末にたどり着いた、ささやかな自己肯定の形だったとも解釈できるかもしれません。彼女は社会的な「美徳」の枠組みの中に戻ることを選びましたが、その心の中には、決して消えることのない「よろめき」の記憶が刻まれたことでしょう。
三島由紀夫の文体は、この物語に独特の緊張感と格調高さをもたらしています。登場人物たちの会話や心理描写は、計算され尽くした言葉で綴られており、読者を作品世界へと深く誘います。特に、節子の心の揺れ動きを捉える筆致は鋭く、彼女の感情の機微が手に取るように伝わってきます。
また、1950年代後半という時代背景も、この物語を理解する上で重要な要素です。戦後の復興期を経て、日本社会が新たな価値観を模索していた時代。伝統的な家父長制度や貞淑の観念が残りつつも、西洋文化の流入などにより、個人の自由や生き方が問い直され始めた時期でもありました。節子の苦悩は、そうした過渡期の社会における女性の生きづらさを反映しているとも言えるでしょう。
「美徳のよろめき」は、単なる不倫小説として片付けることのできない、人間の本質に迫る深遠なテーマを内包した作品です。愛とは何か、幸福とは何か、そして社会の中で個人はいかに生きるべきか。節子の物語は、現代の私たちにも多くの問いを投げかけてきます。
この物語を通じて、私たちは、人間という存在の複雑さ、そして時に矛盾を抱えながらも生きていくことの哀しみと美しさを感じ取ることができるのではないでしょうか。節子が再び手に入れた「彫像のように微動だにしない」午後の時間は、彼女にとって安らぎなのか、それとも新たな牢獄なのか。その答えは、読者一人ひとりの解釈に委ねられているように思います。
最終的に、節子は社会的な破滅を回避し、日常へと回帰します。しかし、彼女の心に残った傷跡や、経験した感情の深さは、決して消えることはないでしょう。それは、彼女が生きた証であり、彼女だけの真実なのかもしれません。この物語は、読み終えた後も、登場人物たちの運命や、彼らが抱えていたであろう言葉にならない思いについて、深く考えさせられる作品です。
まとめ
小説「美徳のよろめき」は、上流階級の若妻、倉越節子が心の渇きから禁断の恋に踏み出し、その過程で経験する心の葛藤や社会との軋轢を描いた、三島由紀夫による濃密な物語です。節子の夫、一郎との間には感情的な隔たりがあり、満たされない日々を送る中で、彼女は土屋という青年と再会し、危険な関係へと身を投じます。
物語は、節子の内面を深く掘り下げ、彼女が感じる退屈、刺激への渇望、そして罪悪感や嫉妬といった複雑な感情を鮮やかに描き出しています。予期せぬ妊娠、そして愛人である土屋の裏切りという試練を経て、節子は大きな決断を迫られることになります。特に、政府高官である父の言葉は、彼女の運命を大きく左右するきっかけとなりました。
この作品は、単に個人の情愛のもつれを描くだけでなく、当時の日本の社会における「美徳」とは何か、そして個人の幸福と社会的な規範との間で揺れ動く人間の姿を問いかけています。節子が最終的に選んだ道、そして彼女が土屋への手紙を破り捨てる場面は、多くの解釈を呼び、読者に深い余韻を残します。
三島由紀夫の洗練された筆致と、登場人物たちの緻密な心理描写によって、この物語は時代を超えて多くの読者を魅了し続けています。節子の「よろめき」が私たちに何を語りかけるのか、ぜひ一度手に取って感じていただきたい作品です。