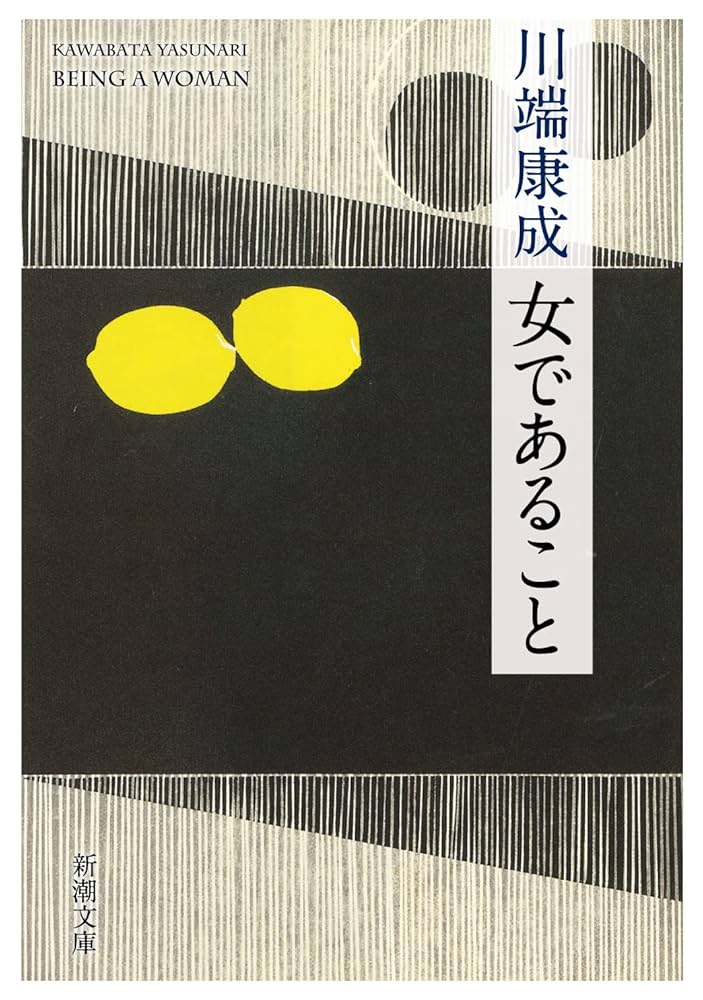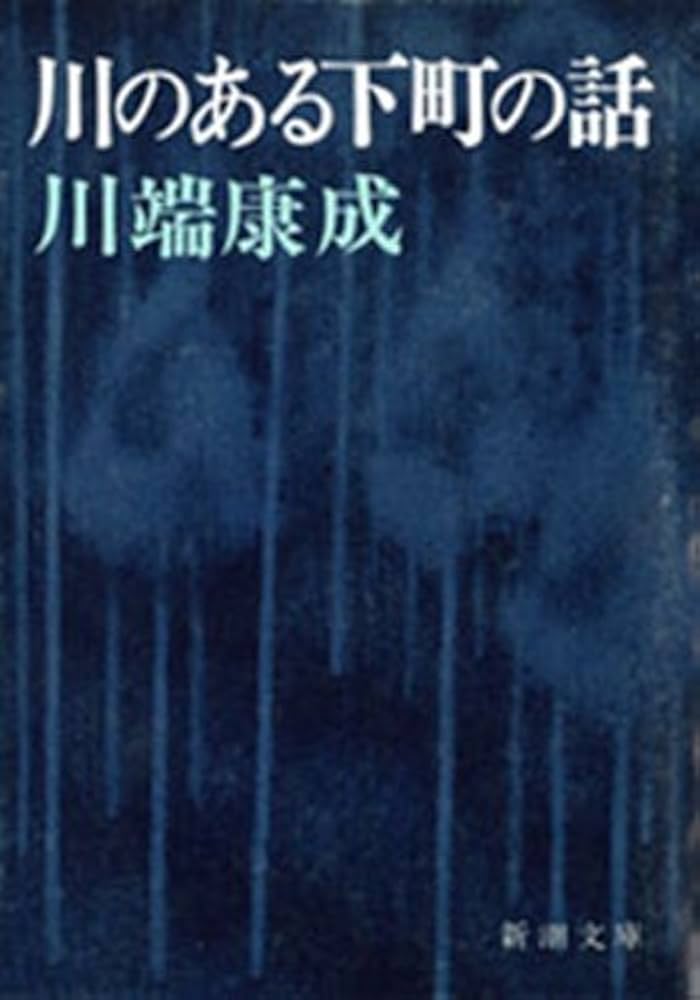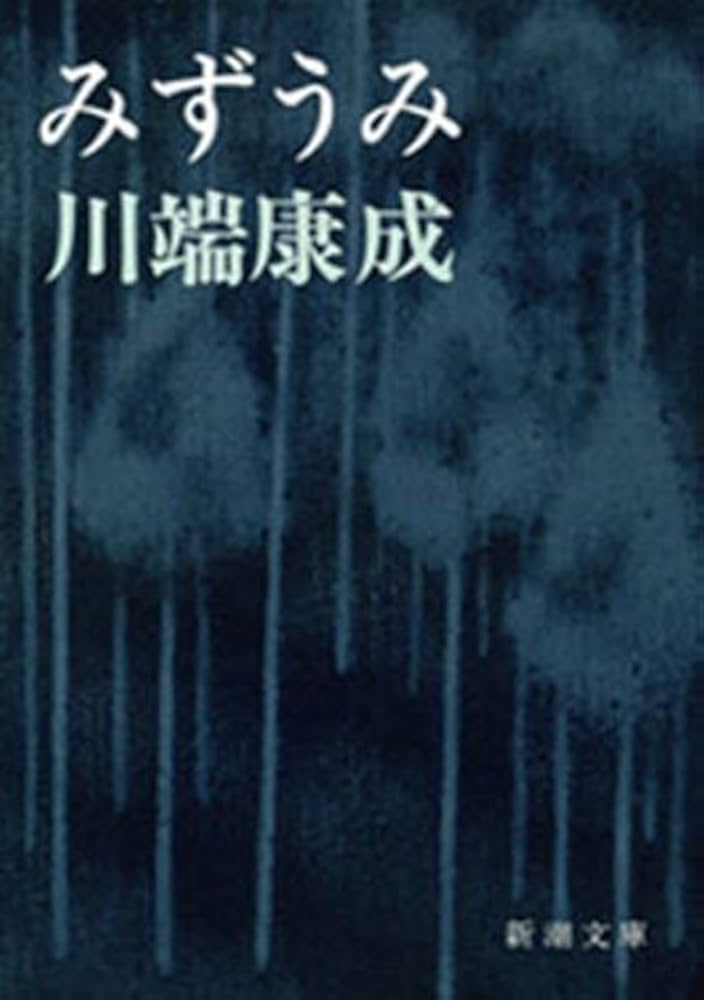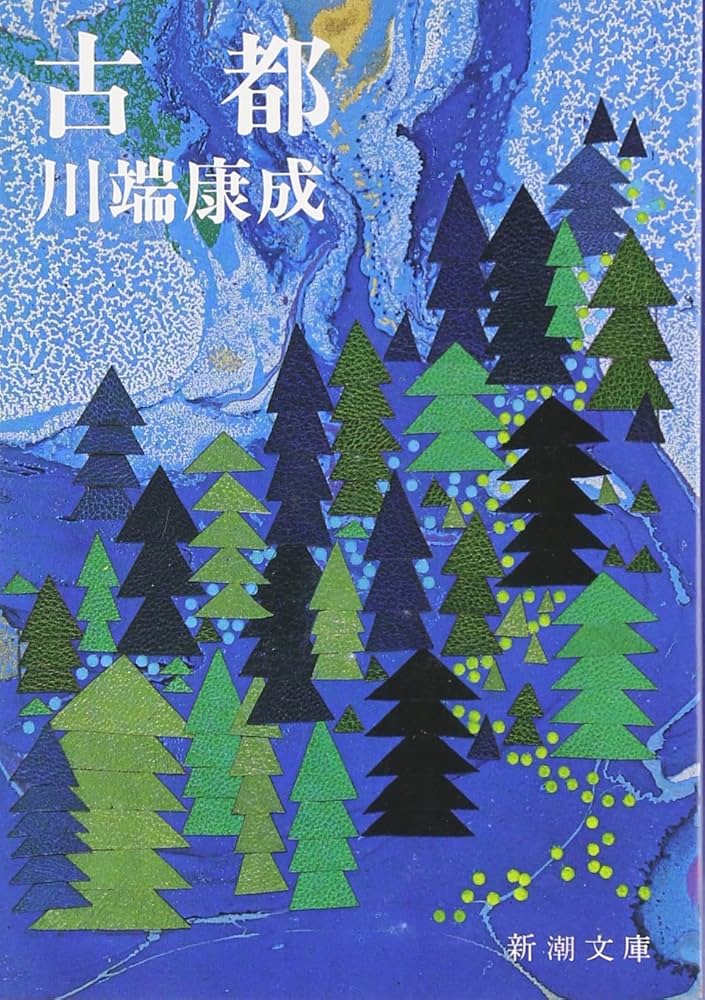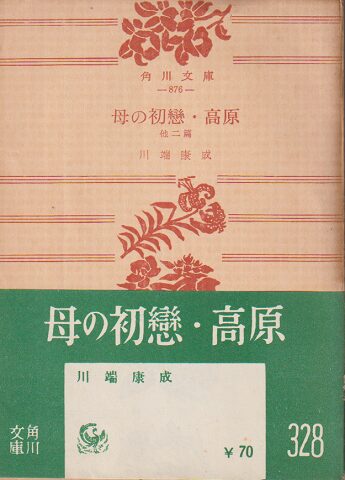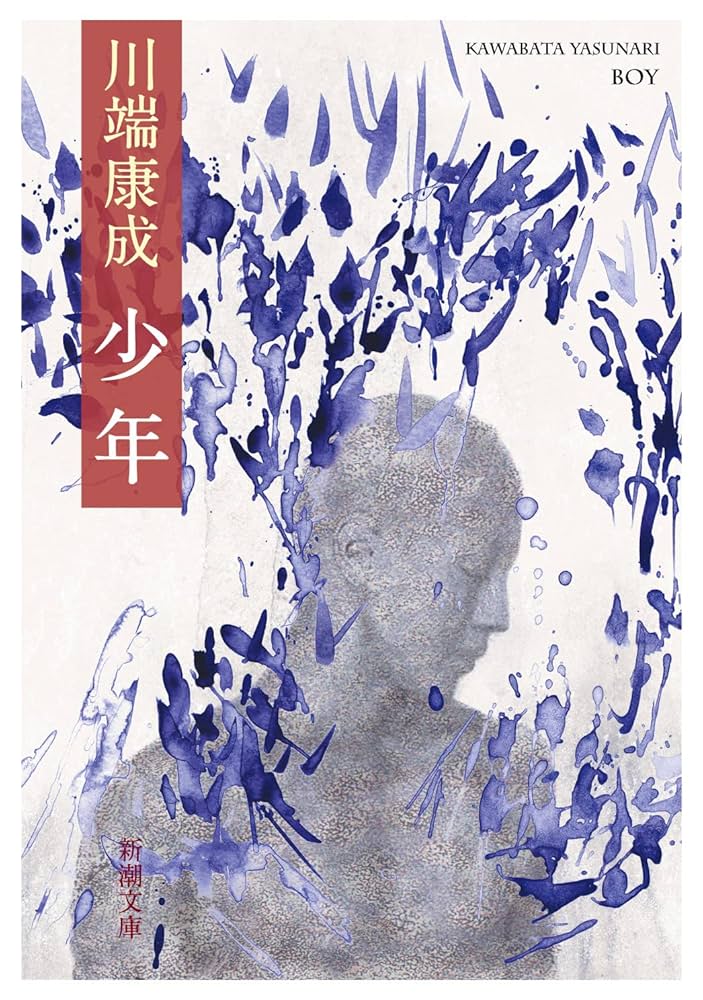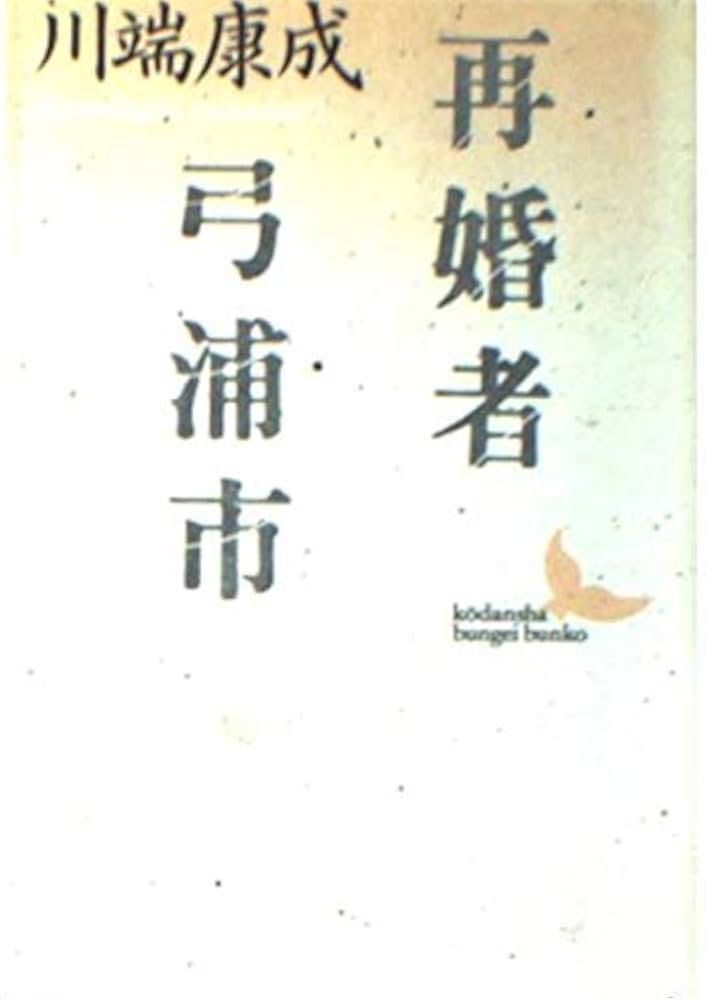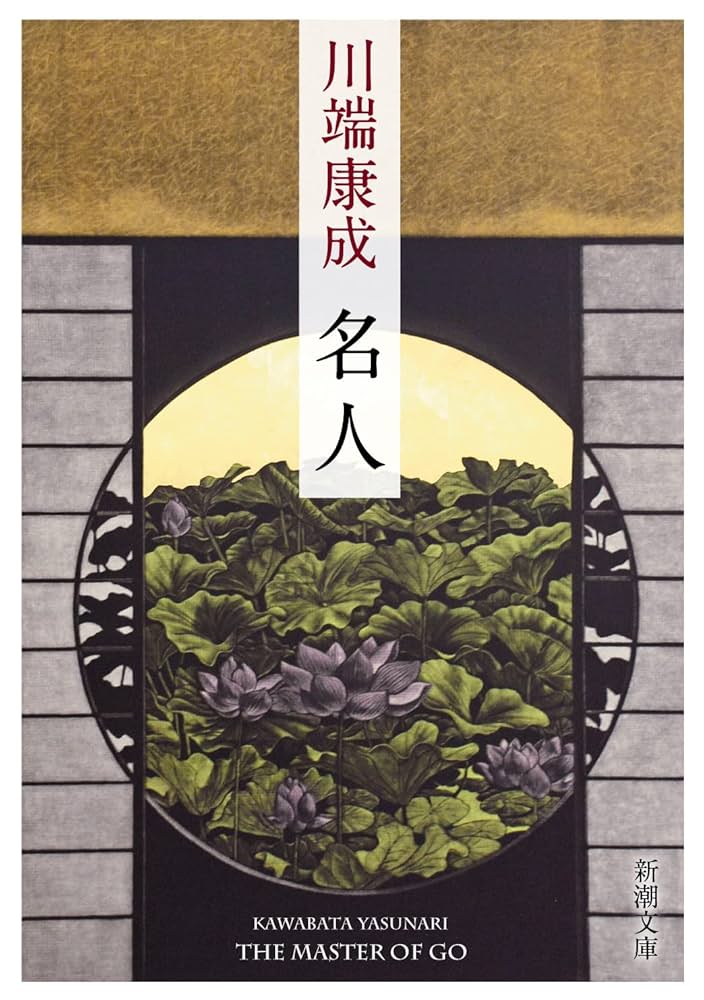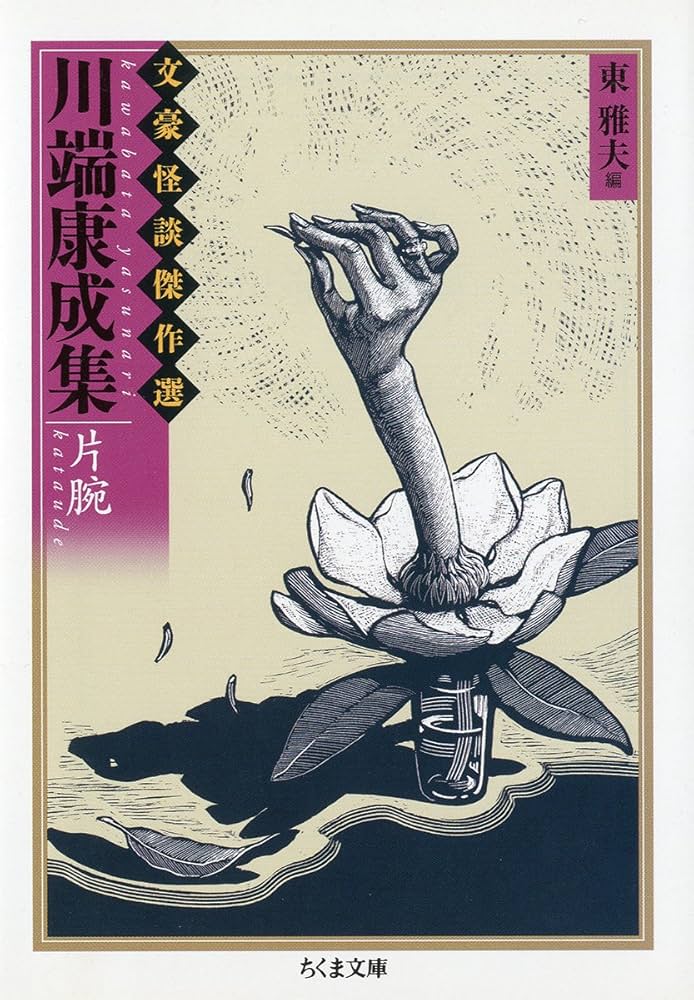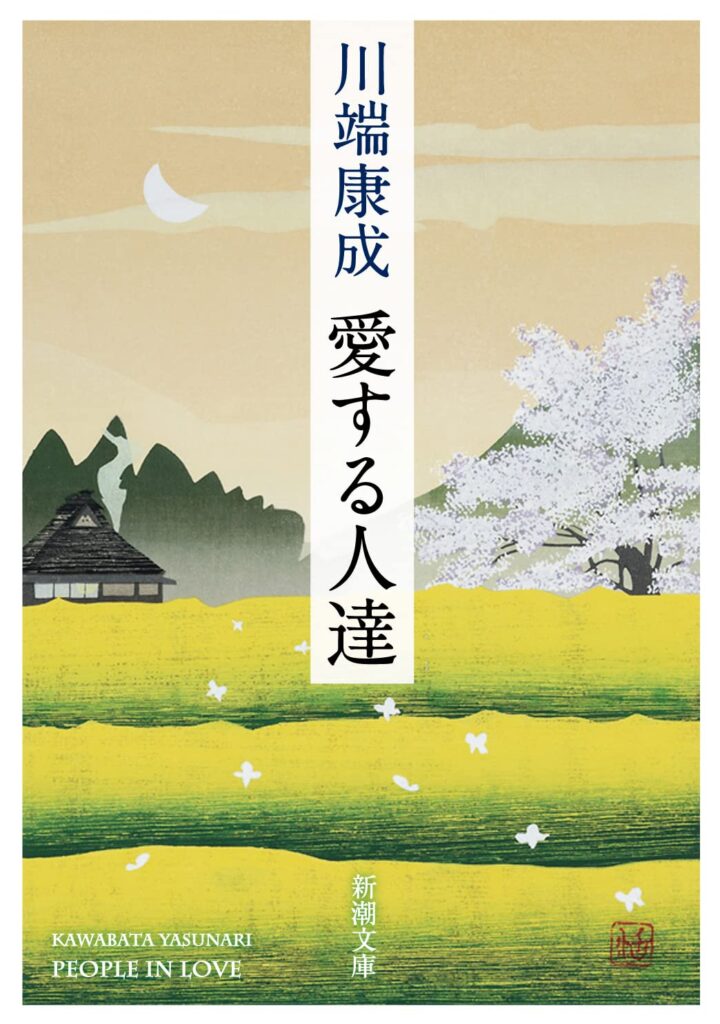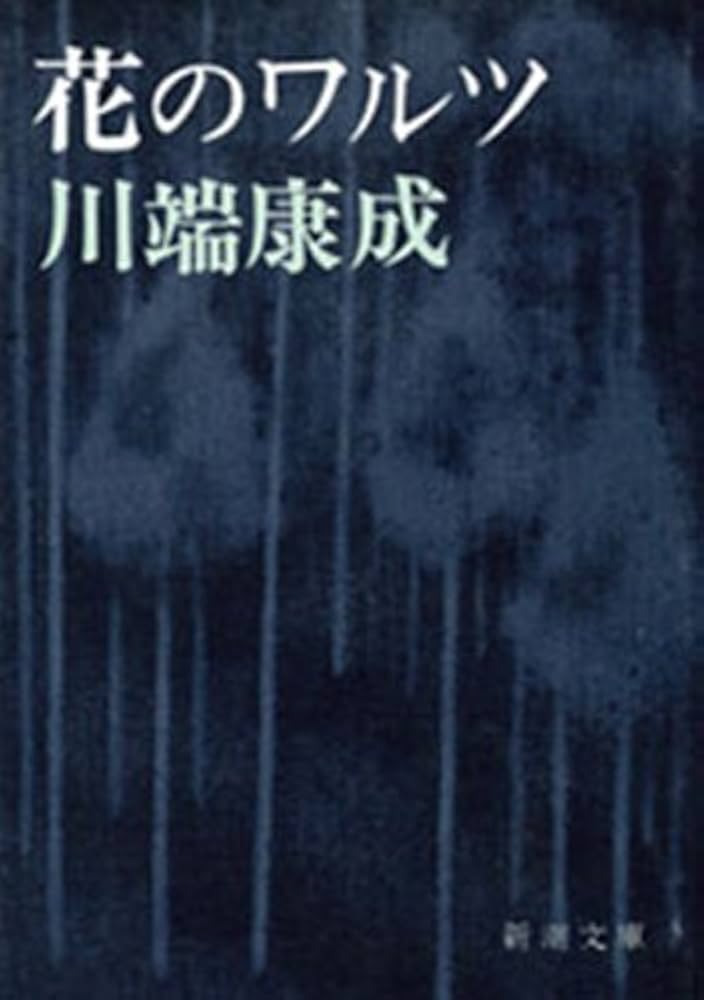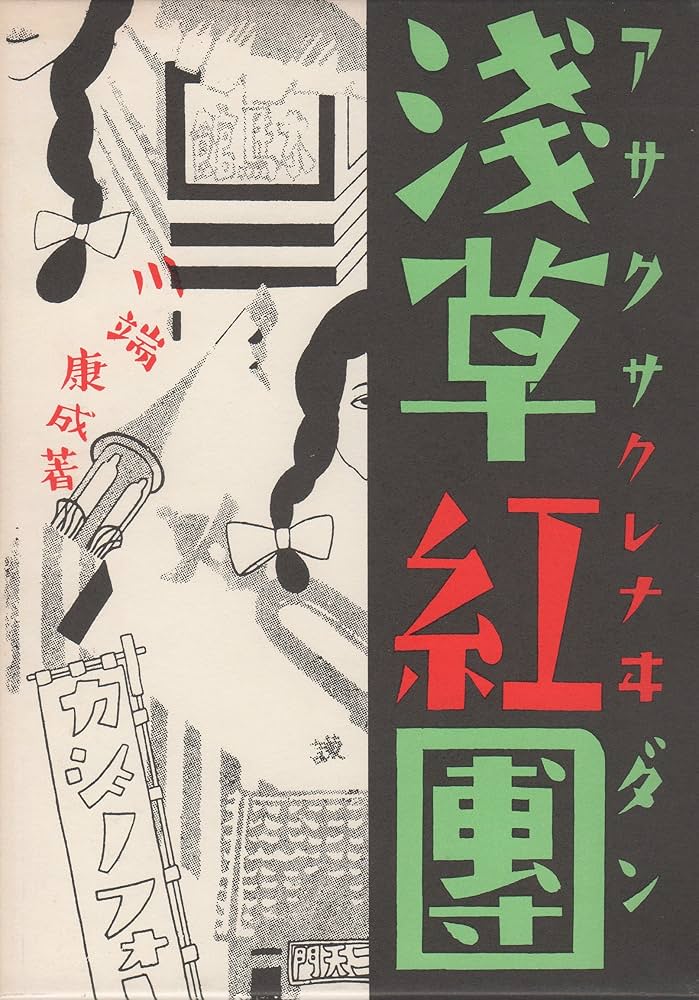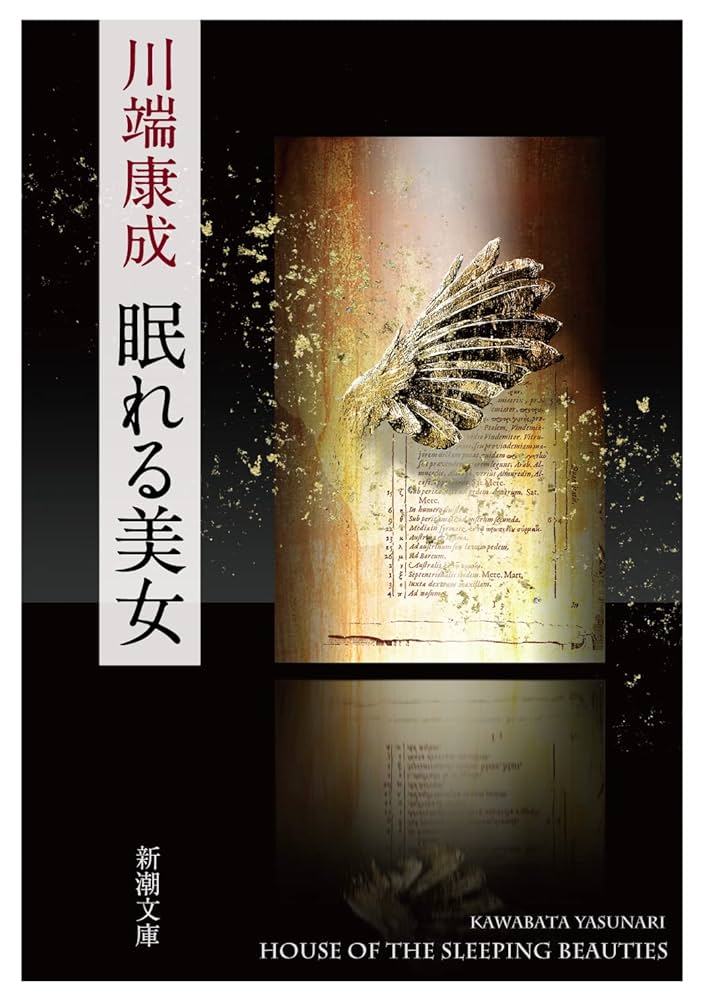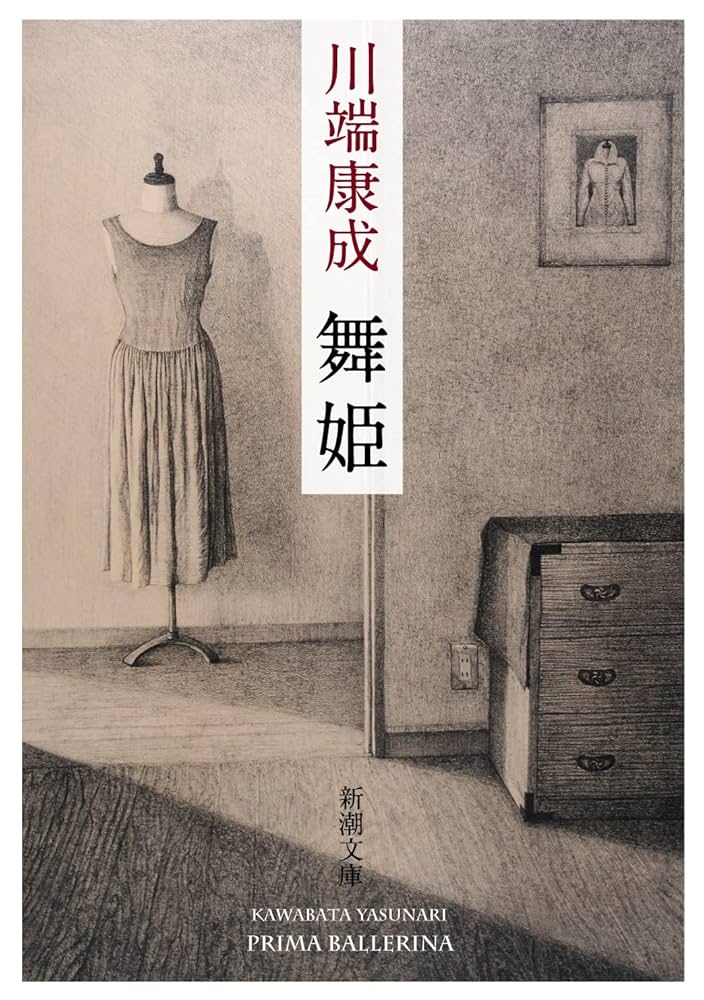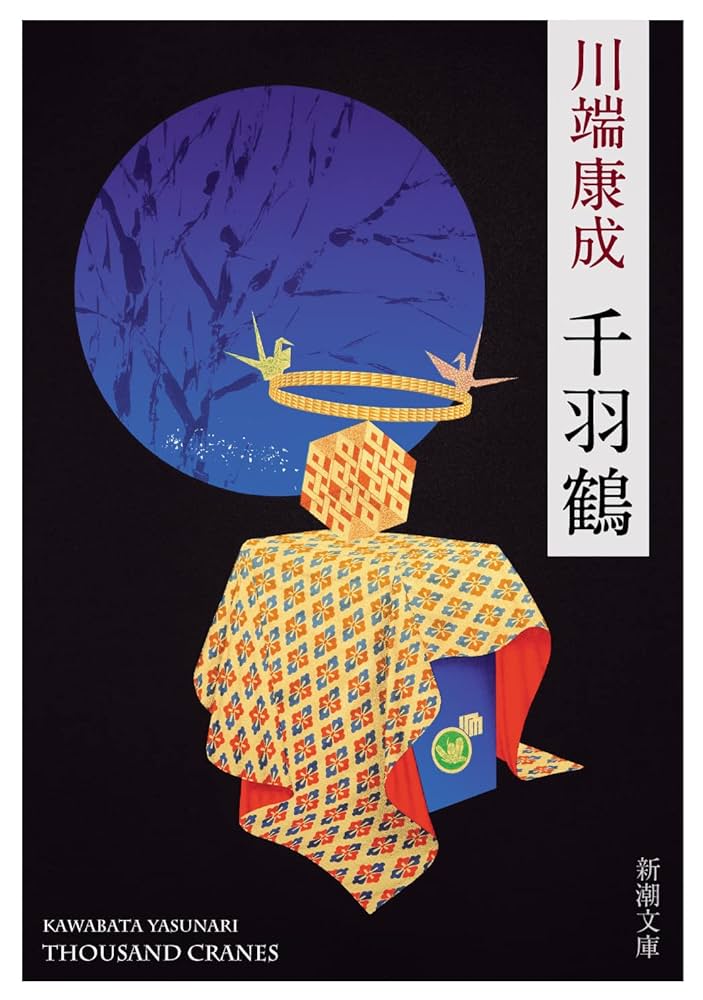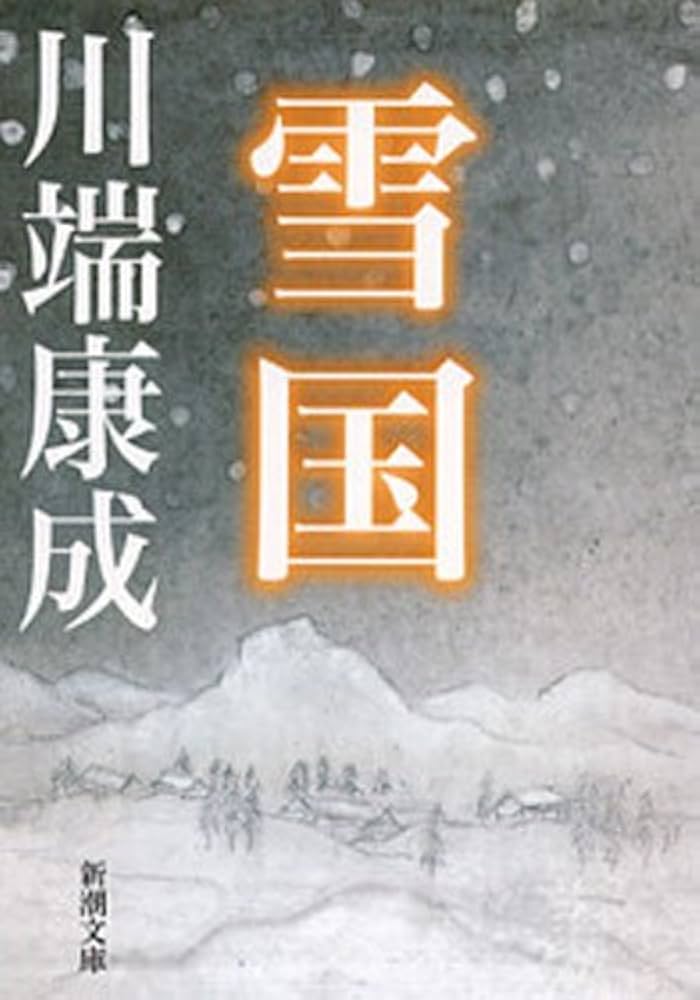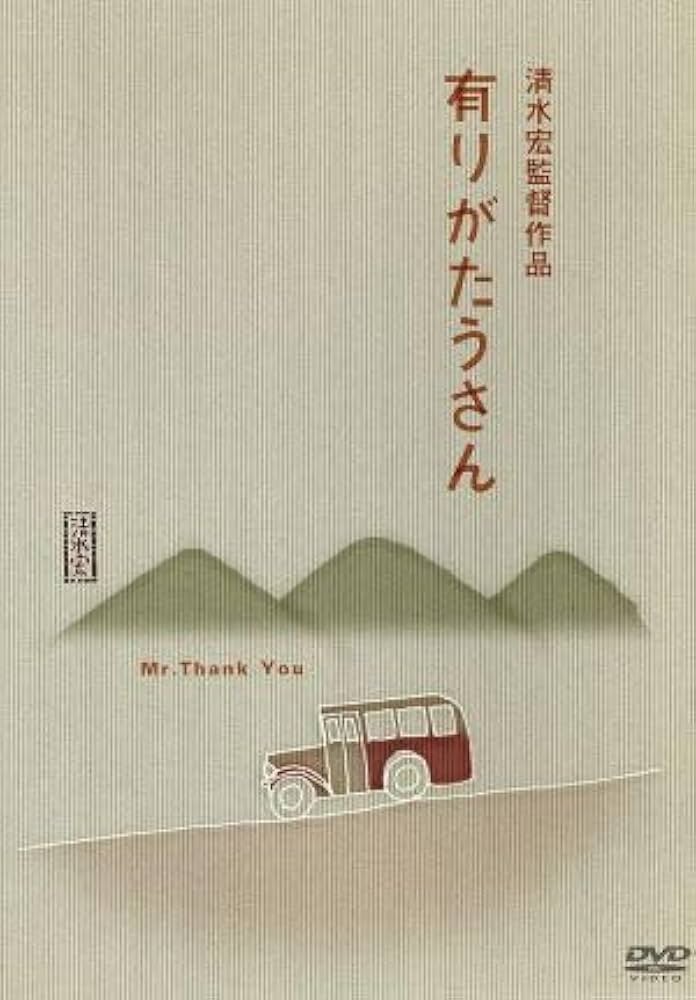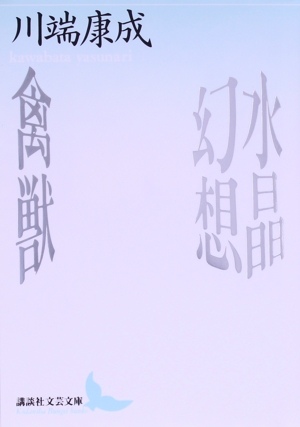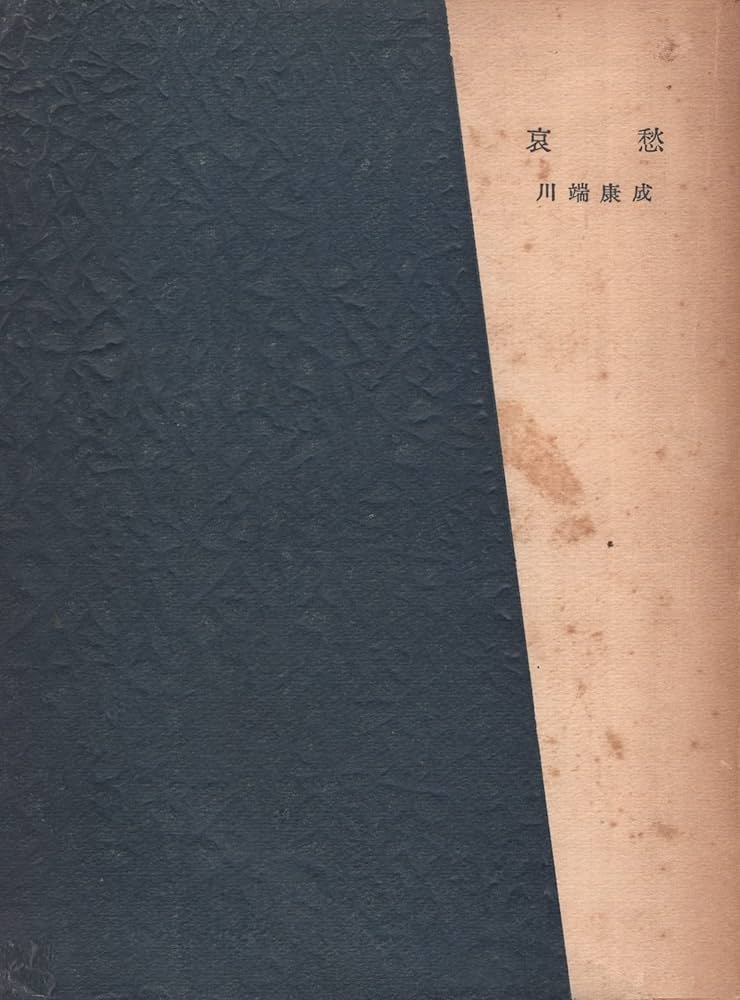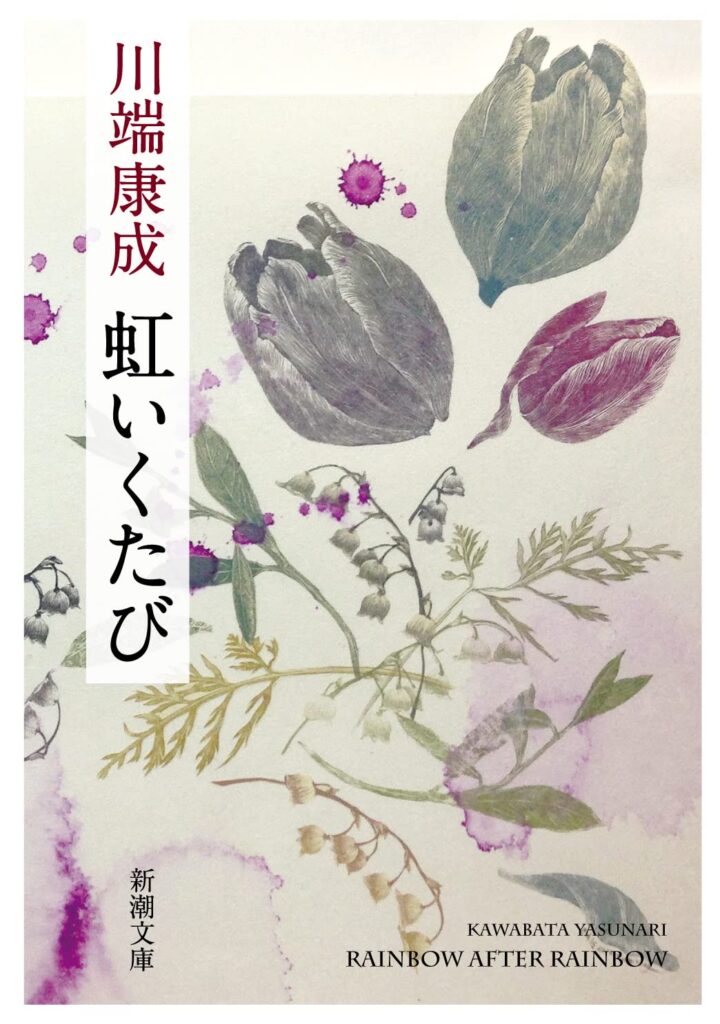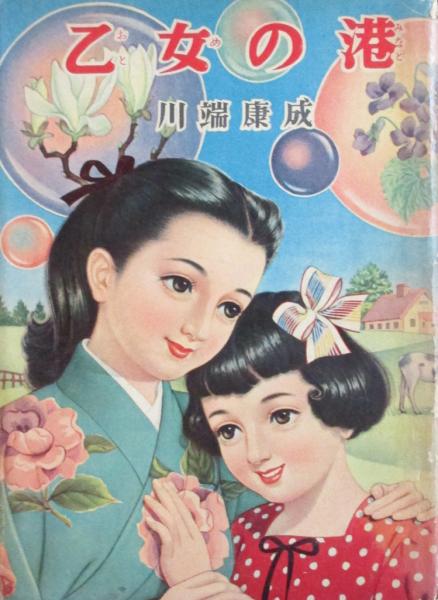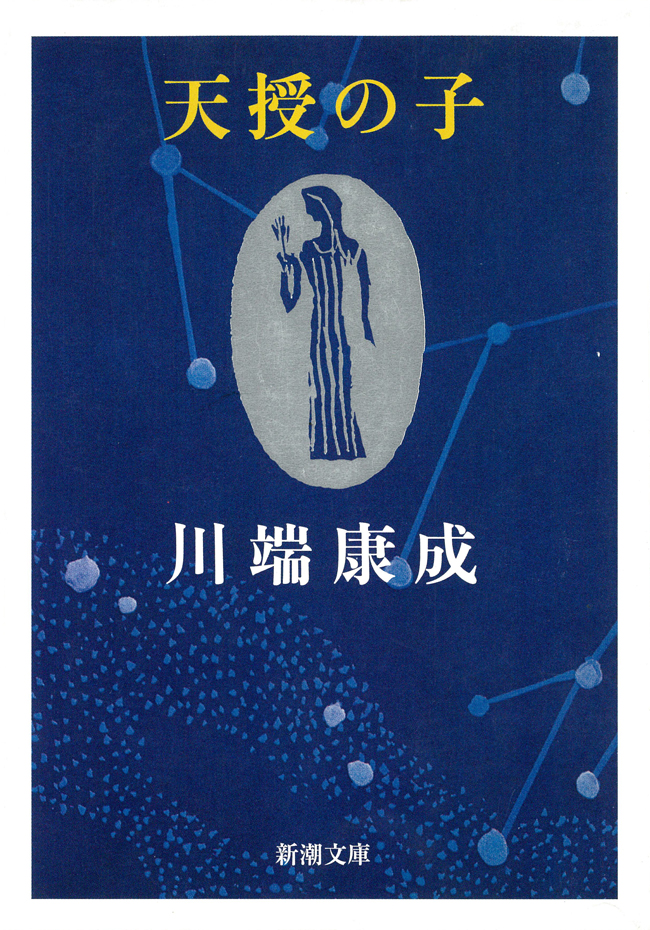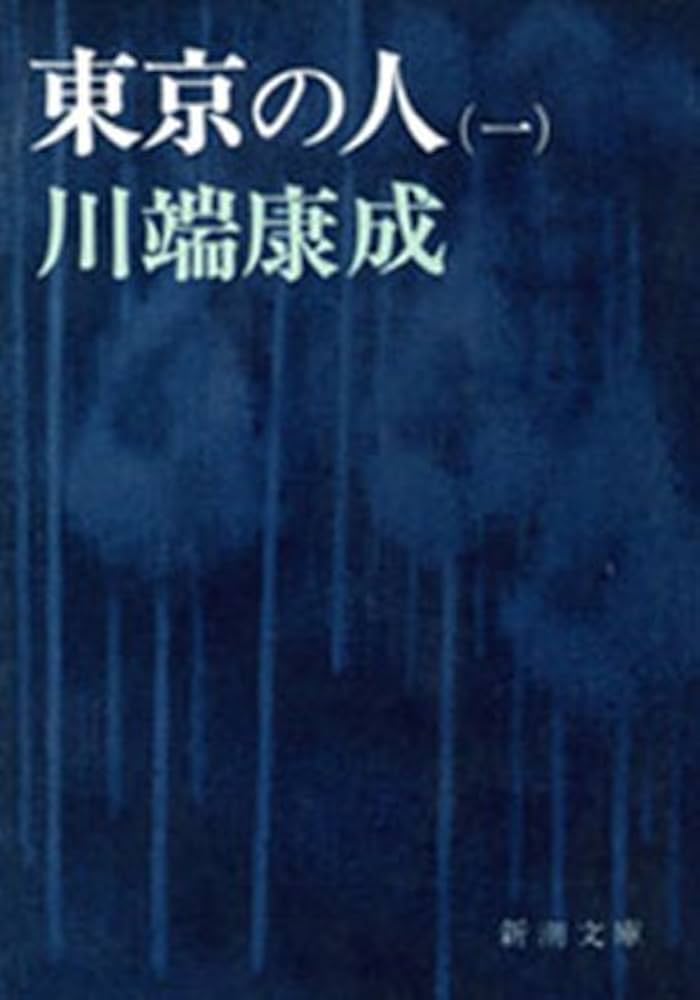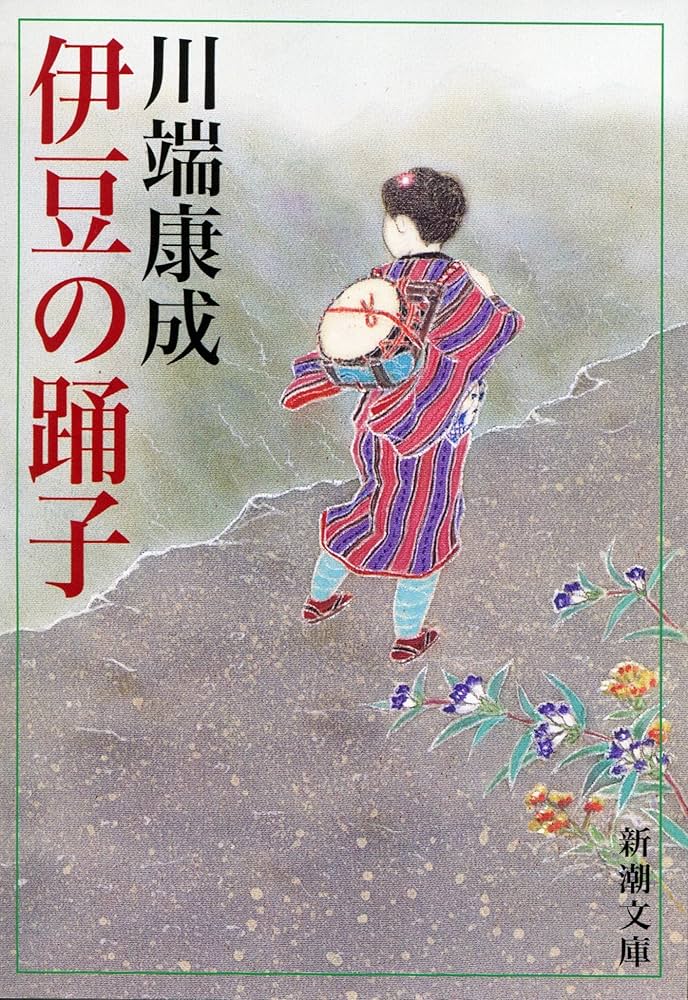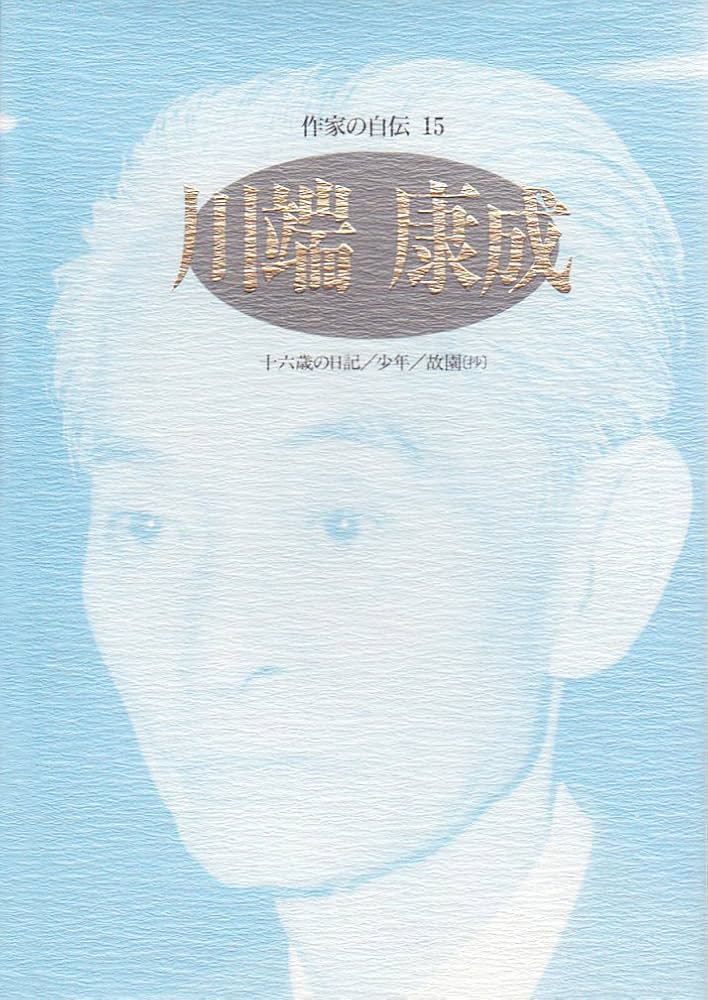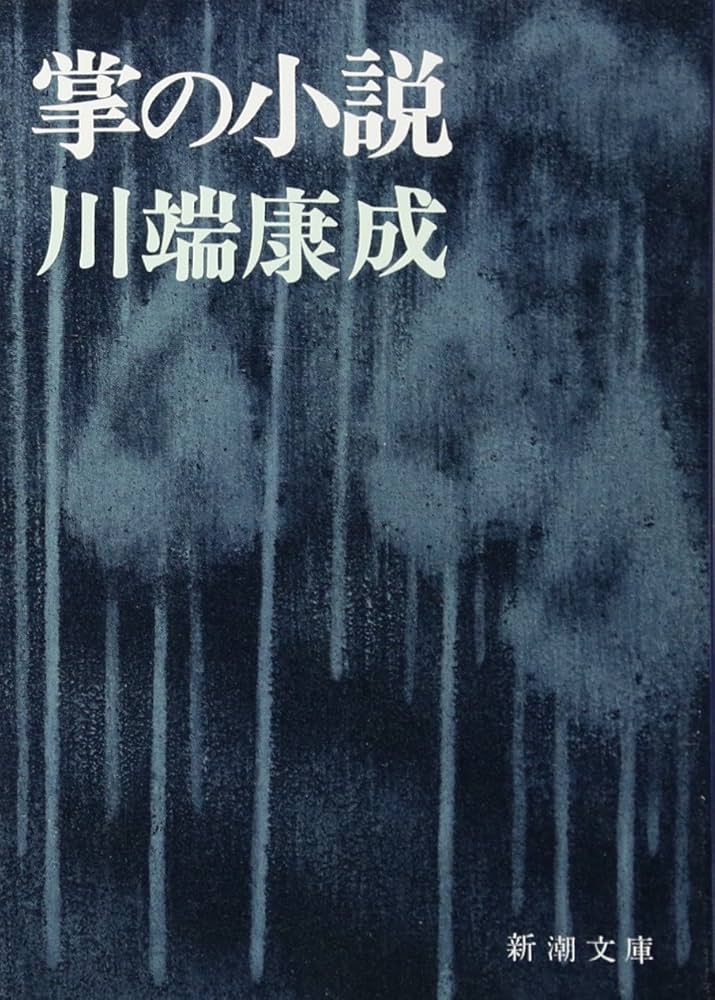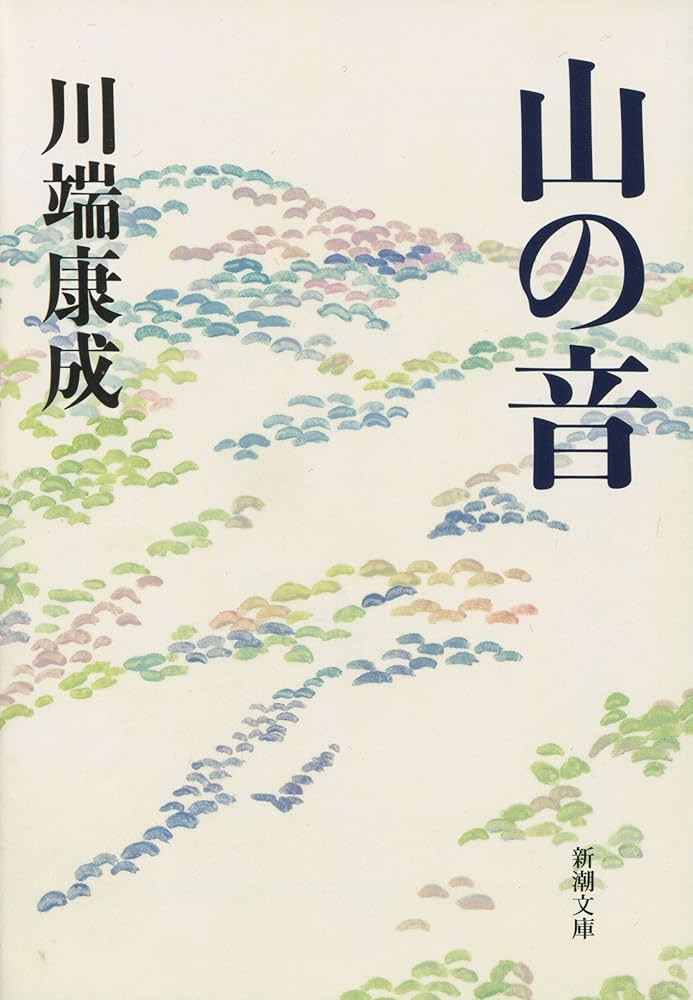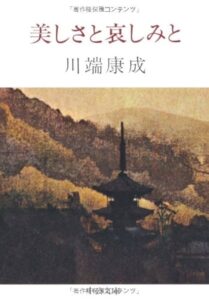 小説「美しさと哀しみと」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「美しさと哀しみと」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
ノーベル文学賞作家・川端康成の晩年の傑作として知られるこの物語は、そのタイトルが示す通り、息をのむほどの「美しさ」と、胸を締め付けるような「哀しみ」が分かちがたく織り交ぜられています。一見すると、過去の恋愛を引きずる男女の再会を描いた恋愛小説のように思えるかもしれません。
しかし、その奥底には、人間の愛憎が渦巻く、恐ろしくも妖しい世界が広がっています。本記事では、物語の核心に触れる部分も隠さずに、その衝撃的な展開を追っていきます。これから作品を読もうと考えている方は、この先の「ネタバレ」にご注意ください。
この記事を通して、単なる物語の紹介に留まらず、登場人物たちの心の深淵や、川端康成が描きたかったであろうテーマについて、深く掘り下げていきます。この美しくも残酷な物語が、あなたの心にどのような波紋を広げるのか、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。
「美しさと哀しみと」のあらすじ
物語は、著名な小説家である大木年雄が、かつて深く愛した女性、上野音子に会うため、年の瀬の京都へ向かうところから始まります。24年前、大木は妻子持ちでありながら、まだ16歳の少女だった音子と許されない恋に落ちました。その関係は音子の妊娠と死産、そして自殺未遂という悲劇的な結末を迎え、二人は引き裂かれたのです。
大木は、その痛ましい体験を基にした小説『十六七の少女』を発表し、作家としての名声を得ました。一方、音子は心の傷を抱えたまま京都で日本画家となり、今は40歳。穏やかながらも、どこか影のある生活を送っています。大木は感傷的な思いから音子に連絡を取り、24年ぶりの再会を望むのでした。
京都で大木を待っていたのは、音子とその若き内弟子、坂見けい子でした。けい子は、少年のような中性的な美しさと、人を惑わすような妖しい魅力を放つ少女です。彼女は師である音子を狂信的に敬愛しており、二人の間には師弟関係を超えた強い絆が存在します。このけい子の存在が、止まっていた三人の運命の歯車を、静かに、そして狂おしく回し始めることになります。
再会を果たした大木と音子。しかし、その間には常にけい子が介在し、二人の間には緊張が走ります。けい子は、師である音子から過去のすべてを聞き出し、大木に対して激しい憎悪と嫉妬を募らせていきます。そして、音子のための「復讐」を心に誓うのです。その復讐計画は、やがて大木の無垢な息子・太一郎をも巻き込み、誰も予測し得なかった悲劇的な結末へと突き進んでいきます。
「美しさと哀しみと」の長文感想(ネタバレあり)
この物語は、単に過去の恋愛の清算を描いた作品ではありません。それは、人の心の奥底に潜む「魔」と、美という名の毒がもたらす悲劇についての、壮絶な物語であると私は感じています。ここからは、物語の核心に触れる多くの「ネタバレ」を含みますので、その点をご留意の上、お読み進めください。
物語の根底に横たわるのは、24年前に刻まれた、決して癒えることのない傷です。妻子ある小説家・大木と16歳の少女・音子の恋。この関係は、初めから破滅の匂いをはらんでいました。若さゆえの純粋さと残酷さが入り混じった情熱は、やがて音子の妊娠、そして死産という最悪の結末を迎えます。この経験は、彼女の人生から「母になること」を永遠に奪い去りました。
さらに注目すべきは、大木の行動です。彼はこの悲劇的な体験を『十六七の少女』という小説に昇華させ、作家としての地位を確立します。これは芸術という名の下に行われた、音子の苦悩の「搾取」と言えるのではないでしょうか。彼は自らの罪悪感を美しい物語へと転換することで、その重みから逃れようとしたのです。芸術の創造性が、時として他者の犠牲の上に成り立つという残酷な現実を、川端康成は冷徹に見つめています。
この搾取の構造には、もう一人の重要な犠牲者がいます。大木の妻、文子です。彼女は夫の不倫の苦しみに耐えながら、その不倫小説の原稿を清書するという、精神的な拷問に等しい行為を強いられます。物語の中で美しく描かれる音子とは対照的に、嫉妬に苦しむ自身の存在はほとんど無視される。この屈辱と心労が、彼女の流産に繋がったことも示唆されており、文子の哀しみもまた、この物語の重要な底流を成しています。
一方で、被害者であるはずの音子自身もまた、芸術の毒に侵されていきます。大木の小説によって美化された過去は、彼女の中で現実の苦い記憶を上書きし、一種の「歓喜と満足」さえ与えます。彼女は自らの悲劇を耽美的に受け入れ、「美しい哀しみ」の中に閉じこもることで、時を止めてしまったのです。未来へ進むことをやめた音子の姿は、痛々しくも、どこか甘美な停滞を感じさせます。
そして24年の時を経て、物語は再び動き出します。京都へ向かう大木の動機は、真摯な贖罪というよりは、過去を美化し、感傷に浸ろうとする自己中心的なノスタルジアに過ぎません。この安易な再会への欲求が、眠っていた「魔」を呼び覚ます引き金となるのです。
その「魔」の化身こそ、音子の内弟子、坂見けい子です。彼女の登場シーンから、物語は不穏な空気に包まれます。「少し気違いさんです」という音子の紹介の言葉通り、けい子は常軌を逸した存在です。その中性的な美しさと、人を射抜くような強い眼差しは、彼女がこの物語の異物であり、破壊者であることを予感させます。
音子とけい子の関係は、単なる師弟愛では説明できない、倒錯した共依存関係にあります。音子は、かつて大木が自分に向けたであろう愛情を、安全な対象であるけい子に注ぎます。そこには母性愛、自己愛、そして同性愛的な欲望が複雑に絡み合っています。けい子の側もまた、音子に対して狂信的ともいえる献身を見せ、二人の世界は完結しているかのように見えました。
しかし、大木の出現は、この閉じた世界に波紋を広げます。音子の心がいまだに大木に揺れ動く様を目の当たりにしたけい子は、燃えるような嫉妬に駆られます。彼女にとって大木は、師の過去を傷つけた加害者であると同時に、現在の愛を脅かす恋敵でもあったのです。「あたしは先生の復讐をしてやりたいんです」。この言葉は、純粋な義憤からではなく、師を独占したいという利己的な欲望から発せられたものでした。
音子の態度は、ここでも受動的です。彼女はけい子の計画の恐ろしさに気づきながらも、それを本気で止めようとはしません。これは、彼女自身が心の奥底で抑圧してきた大木への憎悪や報復心を、けい子が代行してくれることへの、暗黙の同意だったのかもしれません。音子の「美しい哀しみ」が、けい子という能動的な「魔」を生み出したのです。
復讐計画は、まず鎌倉の大木家への潜入から始まります。けい子は、大木の息子・太一郎を最初の標的に定めます。国文学を学ぶ、物静かで純粋な青年である太一郎は、けい子の妖しい魅力の前に、なすすべもなく心を奪われてしまいます。彼の純粋さこそが、彼を悲劇へと導く最大の要因となるのです。
次にけい子は、大木本人に接近し、一夜を共にします。しかし、それは決して身を捧げる行為ではありません。彼女は自らの体を使い、大木を巧みに操り、精神的に追い詰めていきます。この出来事を音子に報告することで、音子の心にさえ嫉妬の波紋を広げ、師弟の関係性における自らの優位性を確立しようとします。彼女の行動は、すべてが計算された冷徹な復讐劇の一部なのです。
そして、復讐の矛先は、再び無垢なる息子・太一郎へと向けられます。夏、京都を訪れた太一郎を、けい子は破滅へと誘います。「音子先生の復讐を太一郎さんでやるんだ」。その決意は、京都の美しい風景とはあまりにも不釣り合いな、暗い輝きを放っていました。
この復讐の構造は、「親の因果が子に報う」という言葉を、最も残酷な形で具現化しています。かつて大木の罪によって、生まれるはずだった音子との子供(非嫡出子)が失われました。それに対する復讐として、けい子は、大木の正統な血筋であり、未来そのものである太一郎(嫡男)の命を奪おうとするのです。この恐ろしい対比構造によって、大木の罪が決して消えることなく、巡り巡って彼自身を、そして彼の家族を破壊することが示されます。
物語のクライマックスは、風光明媚な琵琶湖で訪れます。けい子に誘われるまま、太一郎はモーターボートを湖に走らせます。その直前、けい子は周到にも大木家に電話をかけ、二人の居場所を告げていました。電話口で取り乱す母・文子の声を聞いてもなお、太一郎はけい子の引力から逃れることができません。そして湖上で、「事故」は起こります。小説では直接的な描写こそありませんが、けい子が太一郎を死に至らしめたことは明白です。愛の歓喜の絶頂で実行された、冷酷な殺人でした。
物語は、この悲劇の直後、唐突に幕を閉じます。ラジオで事故を知り、ホテルのベッドで鎮静剤を打たれて眠るけい子を見つめる音子。ただそれだけの情景が描かれ、読者は静寂と圧倒的な悲劇の余韻の中に突き放されます。息子の死という究極の悲嘆を突きつけられるであろう大木と文子の姿は、そこにはありません。
この結末は何を意味するのでしょうか。それは、もはや救いようのない、砕け散ってしまった世界の姿そのものです。大木と文子は、償うことのできない罪の代償として、未来を奪われました。音子は、自らが許容した復讐によっておぞましい犯罪の共犯者となり、長年かけて築き上げた「美しい哀しみ」の世界は暴力的な現実の前に粉々に砕け散りました。そして勝利者であるはずのけい子もまた、その手には破壊と死の空虚さしか残らなかったでしょう。
川端康成がこの作品で描いたのは、「美しさ」と「哀しみ」の危険な関係性です。京都や鎌倉の風光明媚な「美しさ」は、人間の醜い情念が渦巻くドラマの背景となり、音子の悲劇的な過去という「美しさ」は、結果として他者を破滅させる「哀しみ」の種子となりました。痛みを美化することは、決して癒しにはならず、むしろ他者を蝕む「美しい毒」を培養する行為に他ならない。この物語は、解決されない過去が持つ破壊的な力と、抑圧された感情が歪んだ形で発露した時の恐ろしさを描いた、痛烈な警句なのです。
まとめ
川端康成の「美しさと哀しみと」は、単なる恋愛の物語ではなく、人間の心の深淵に潜む愛と憎しみ、罪と罰、そして芸術の功罪を鋭くえぐり出した、文学の極致ともいえる作品です。その美しい文章の裏には、読む者の心を凍らせるような恐ろしい世界が広がっています。
この記事では、物語の結末に至るまでの詳細なあらすじと、その背景にある登場人物たちの心理を、多くのネタバレを含みながら解説してきました。24年の時を経て再会した男女、そしてその間に現れた妖しい少女。彼らの運命が交錯し、やがて悲劇的な結末へと突き進んでいく様は、一度読んだら忘れられない強烈な印象を残します。
「美しい哀しみ」の中に安住しようとした音子の受動性が、いかにして「魔」であるけい子を生み出し、取り返しのつかない破滅を招いたのか。この物語は、過去と向き合うことの難しさと、美化された感情がはらむ危険性を、私たちに静かに、しかし力強く語りかけてきます。
まだこの傑作に触れたことのない方は、ぜひ一度手に取ってみることをお勧めします。そして、すでに読まれた方も、この記事をきっかけに再読していただくことで、新たな発見があるかもしれません。この美しくも哀しい物語の世界に、もう一度浸ってみてはいかがでしょうか。