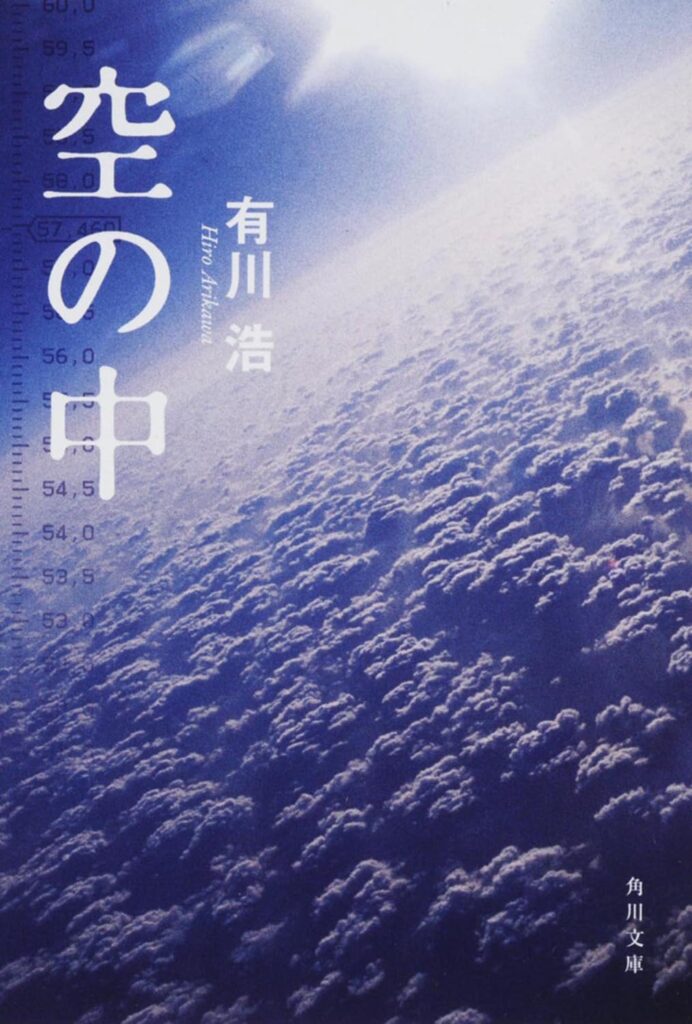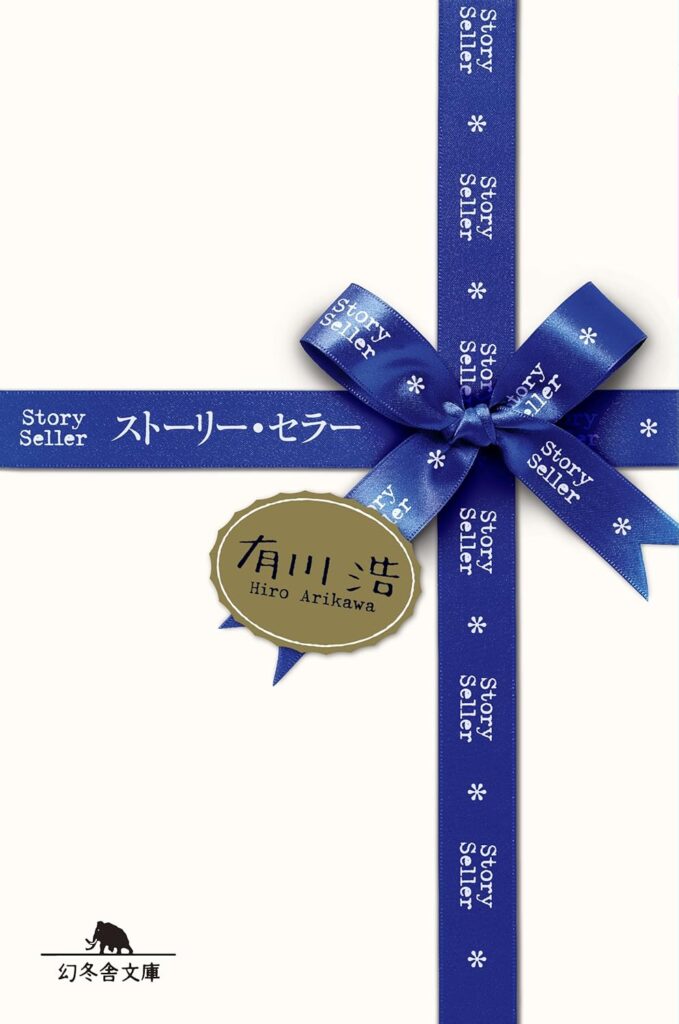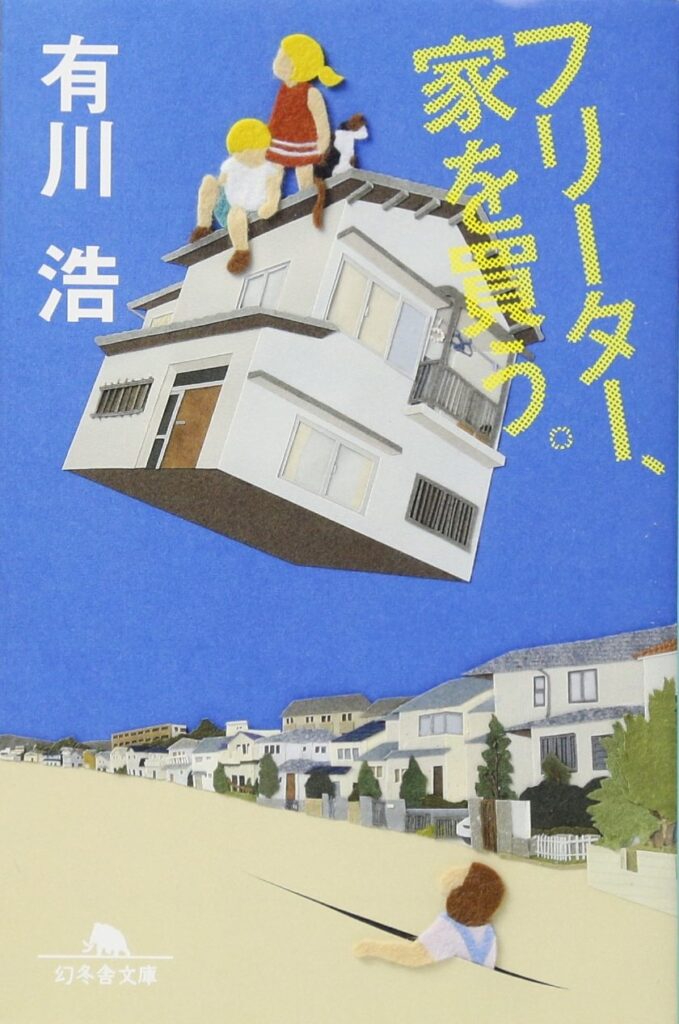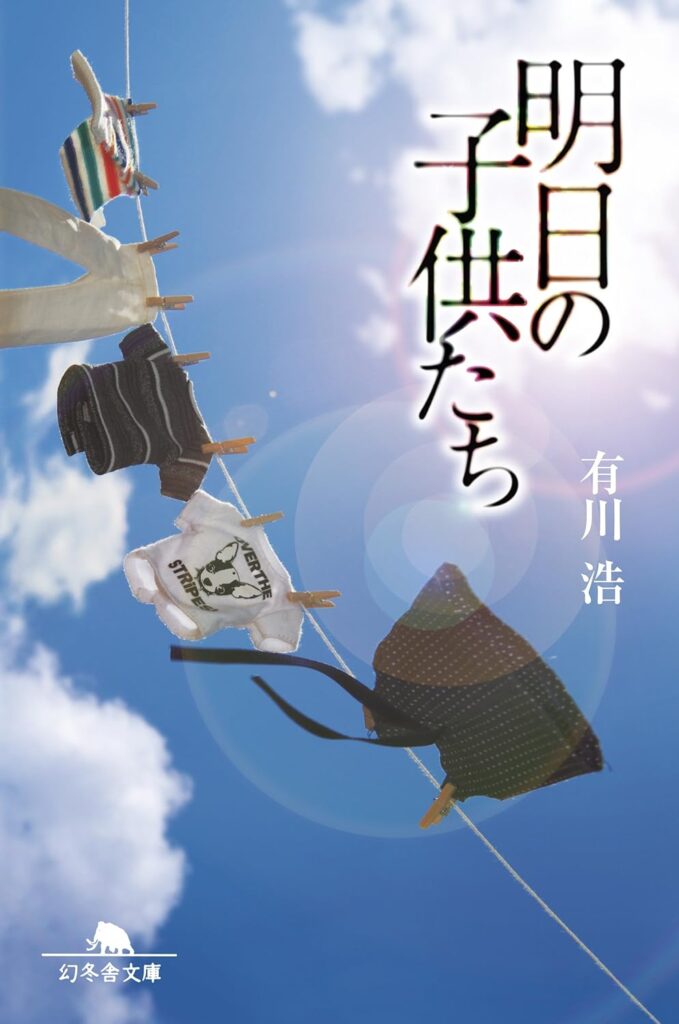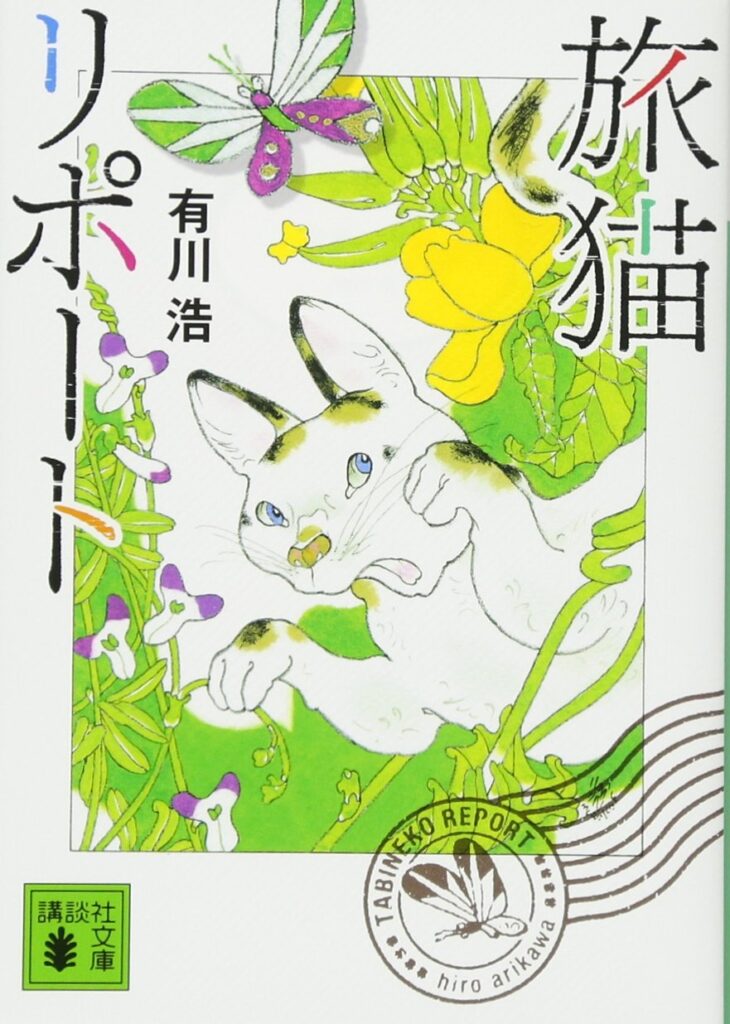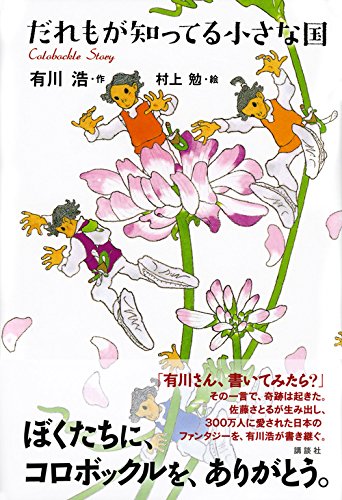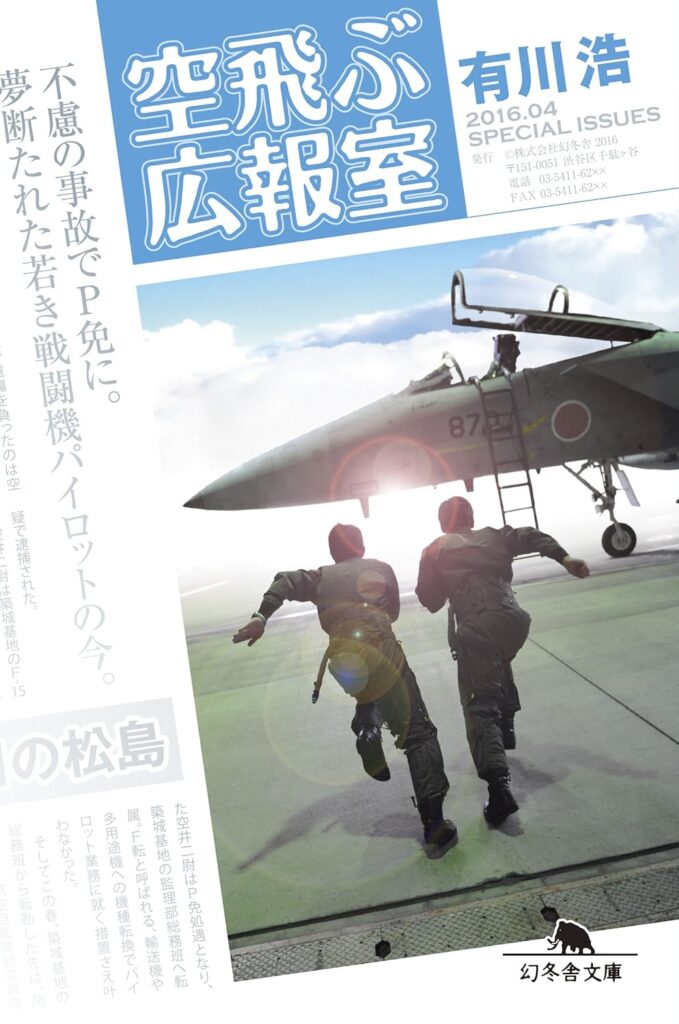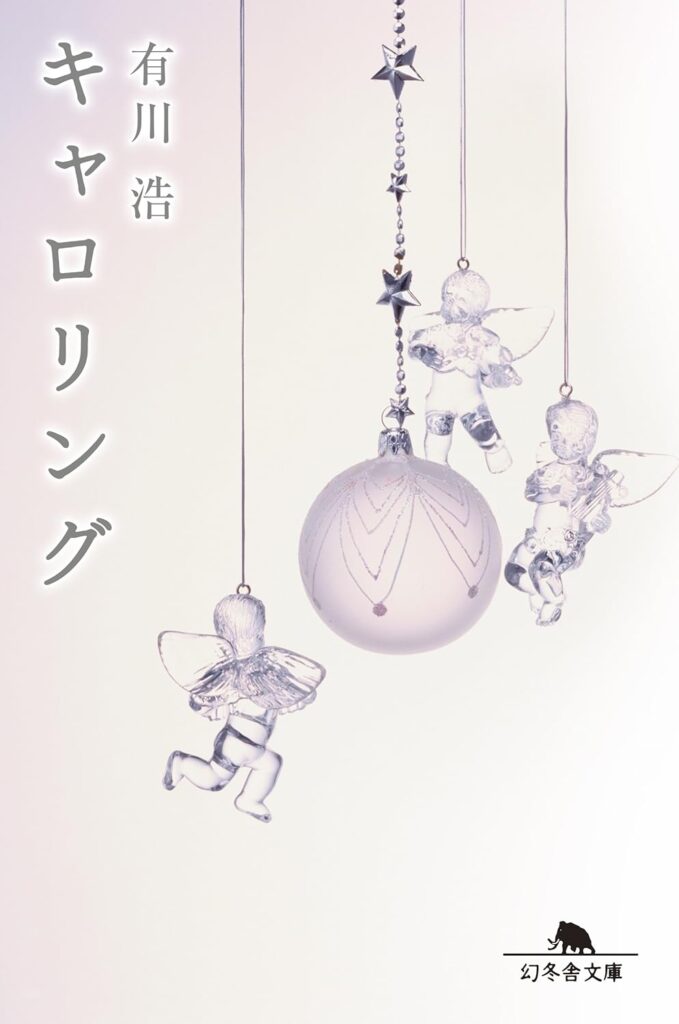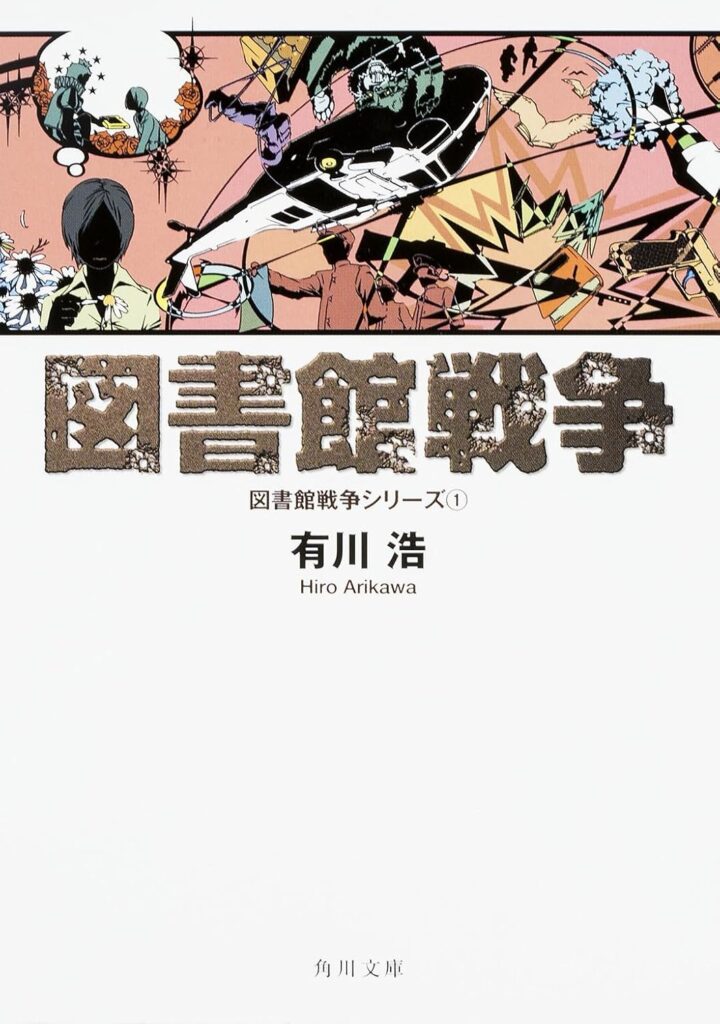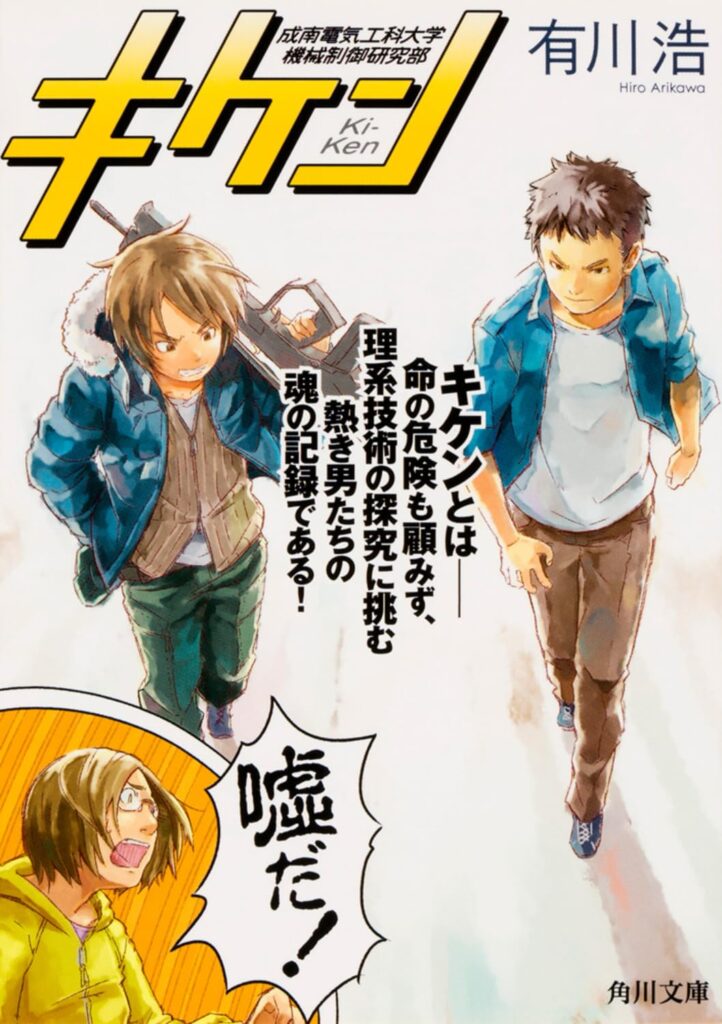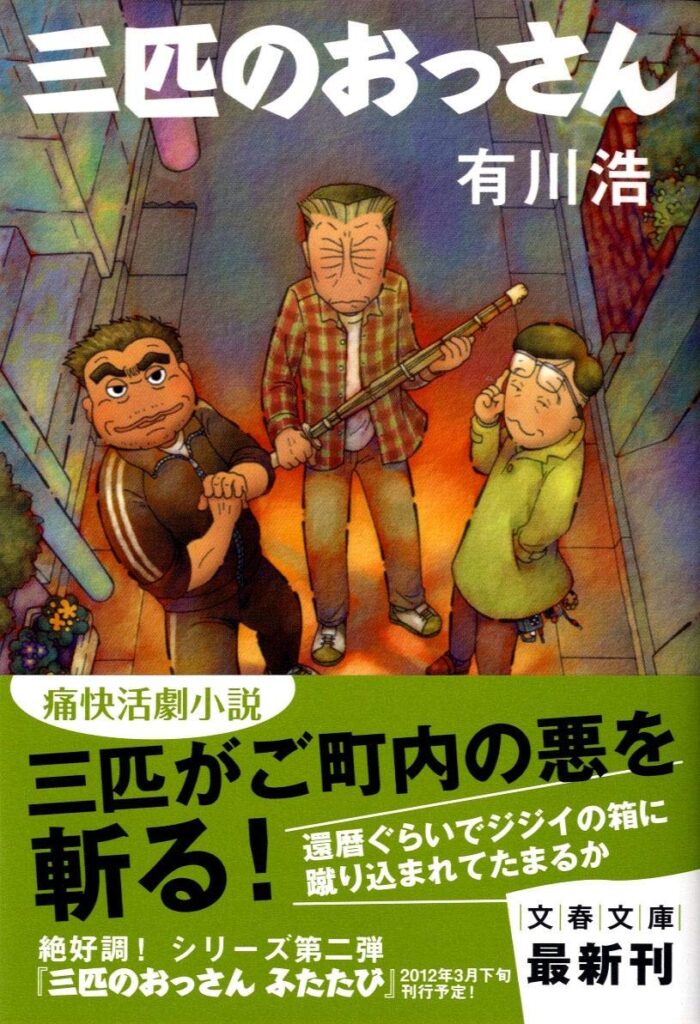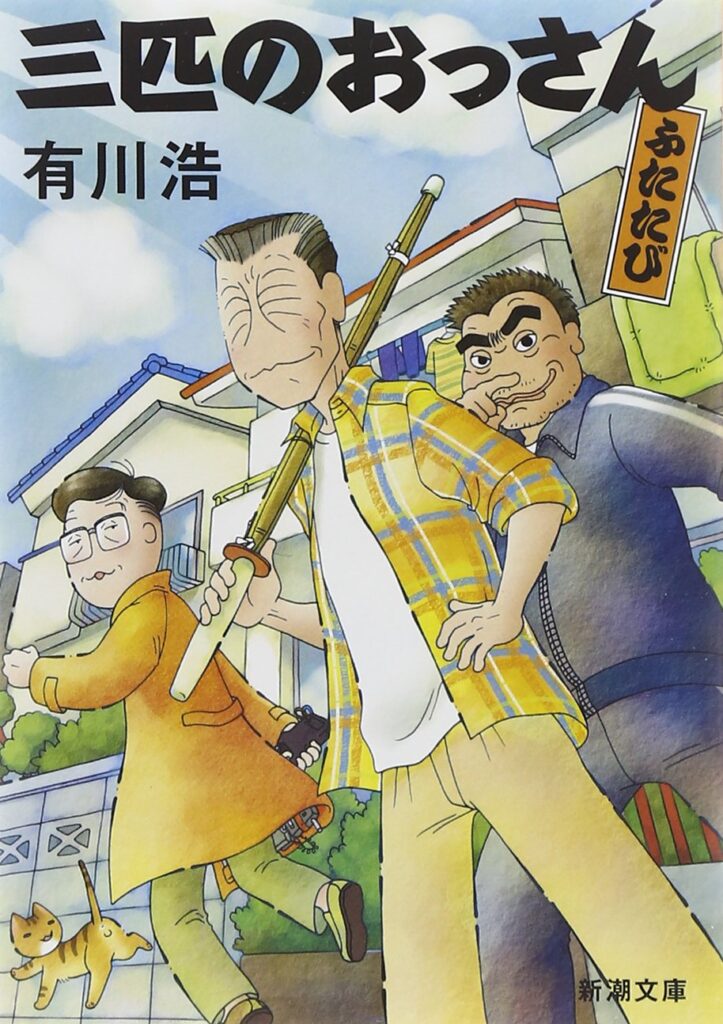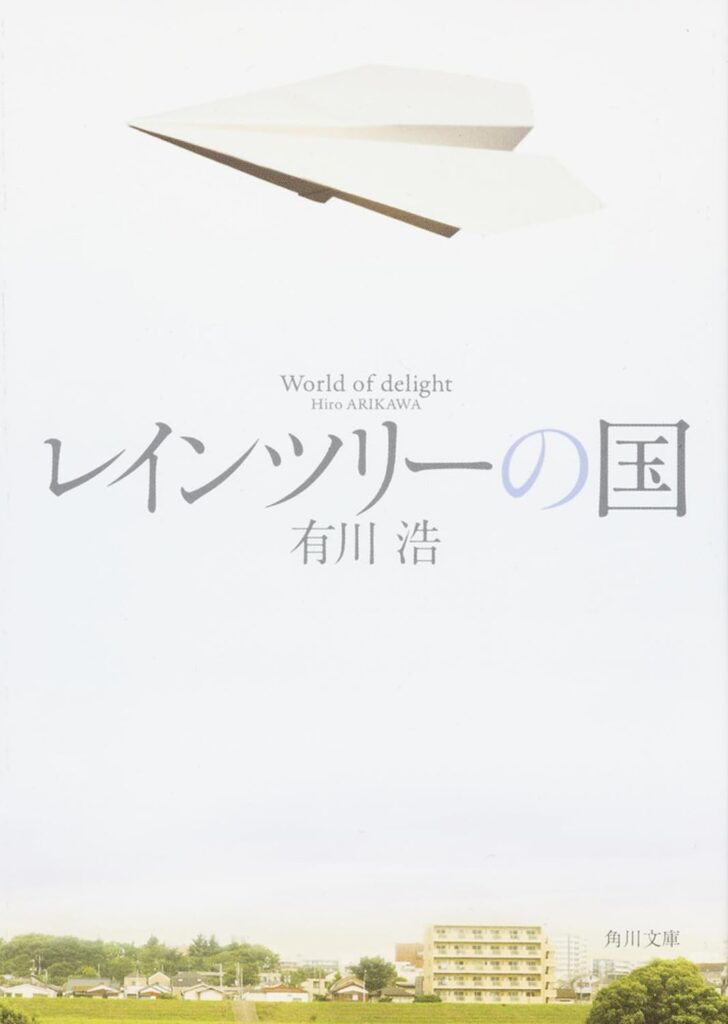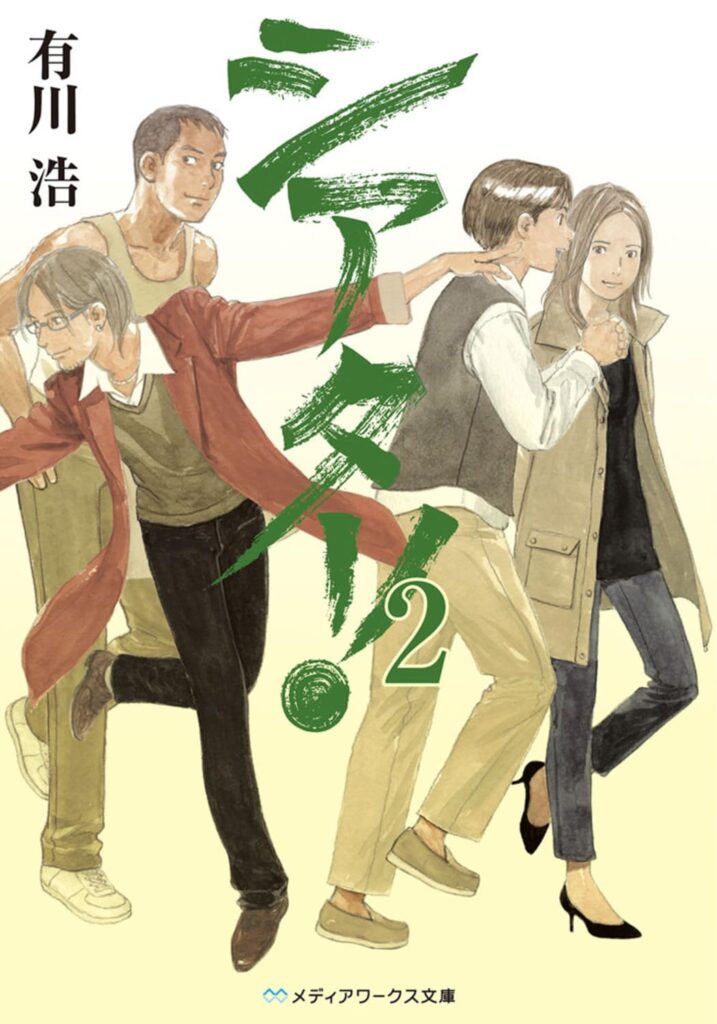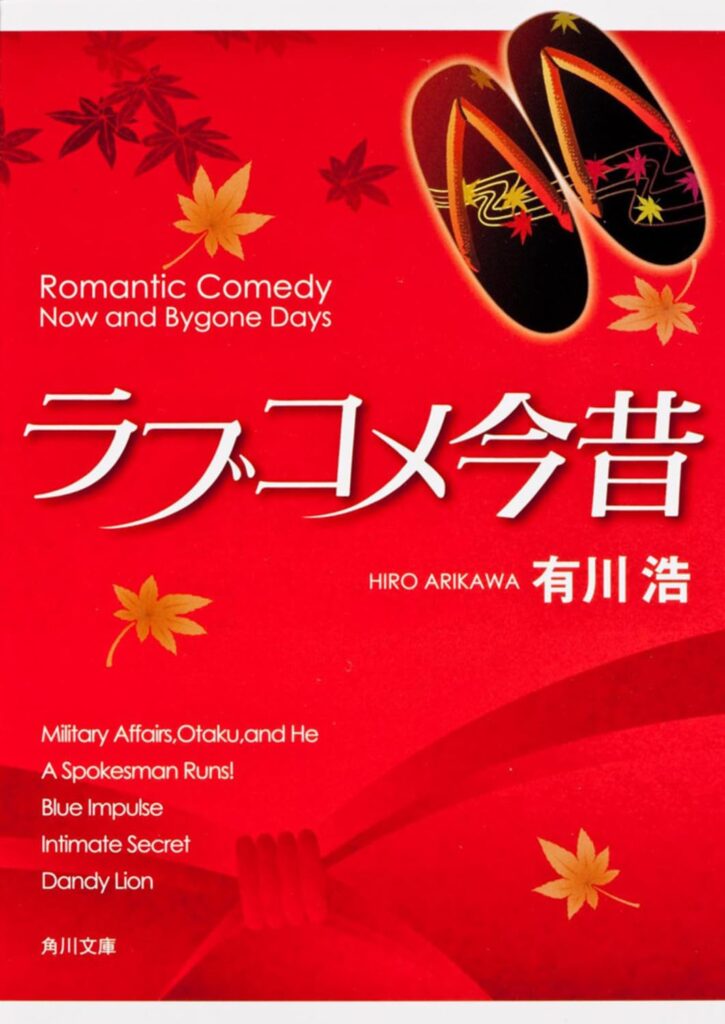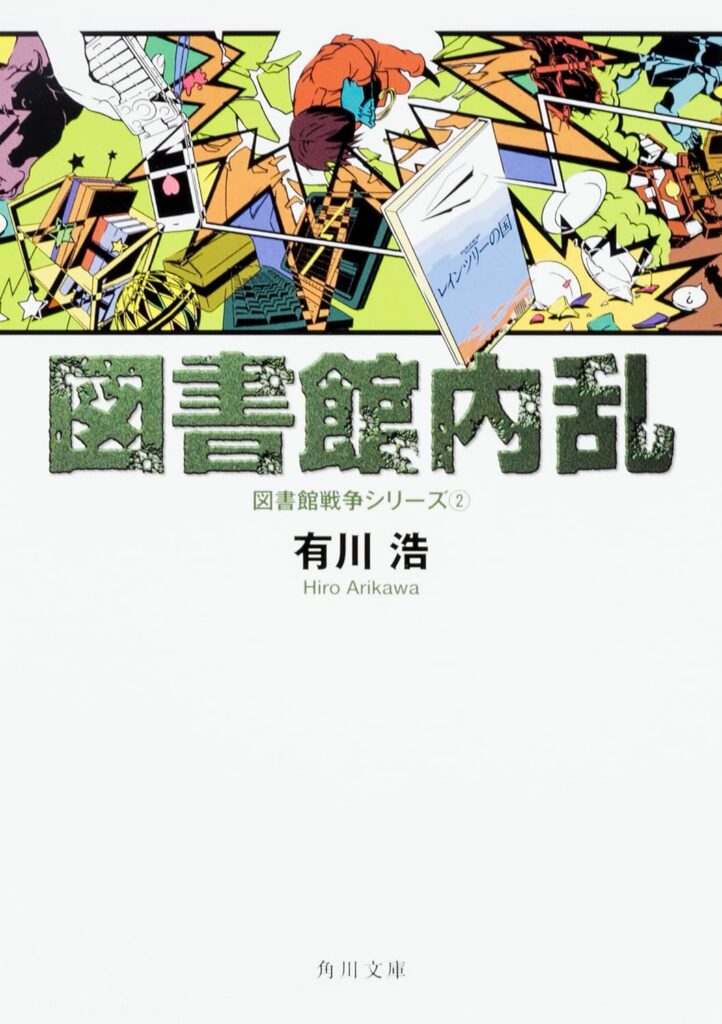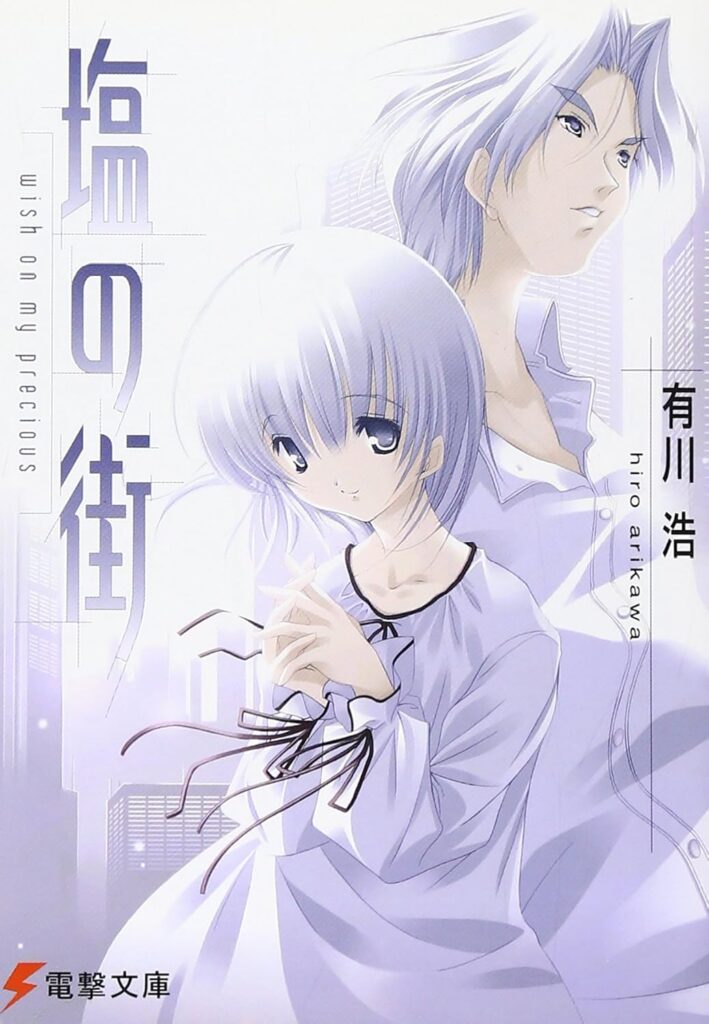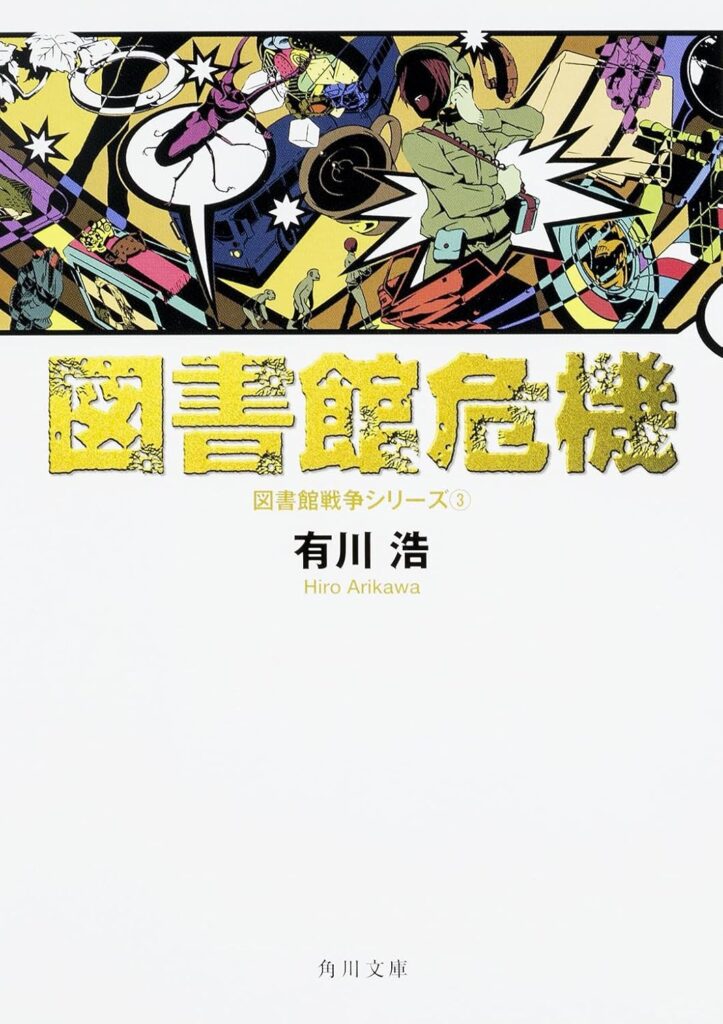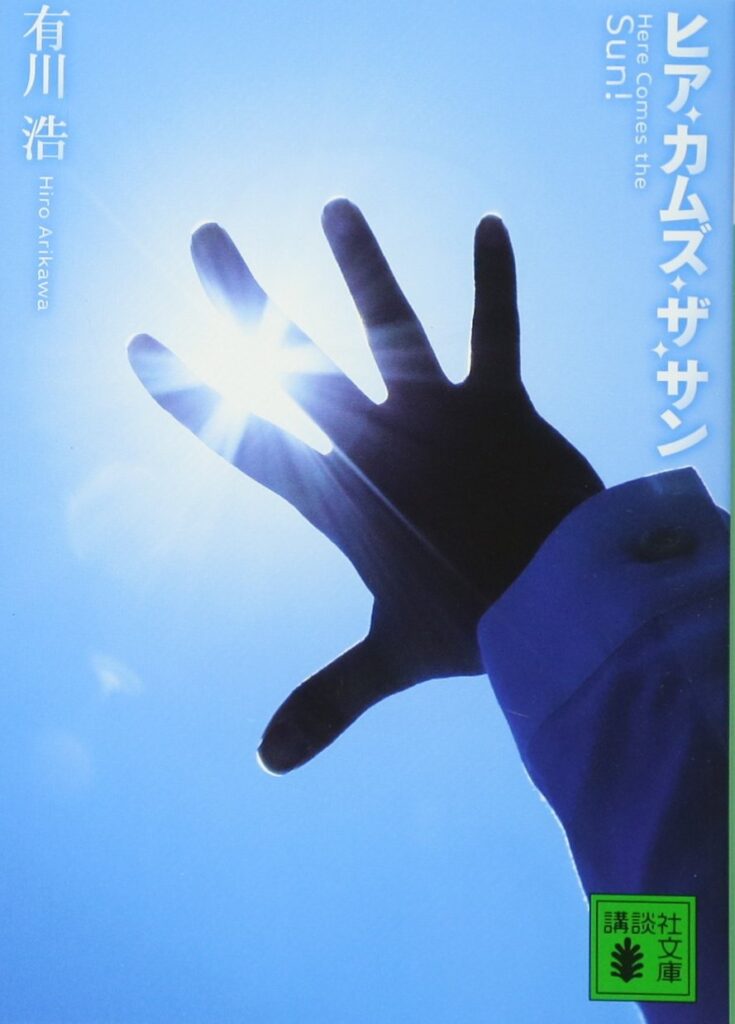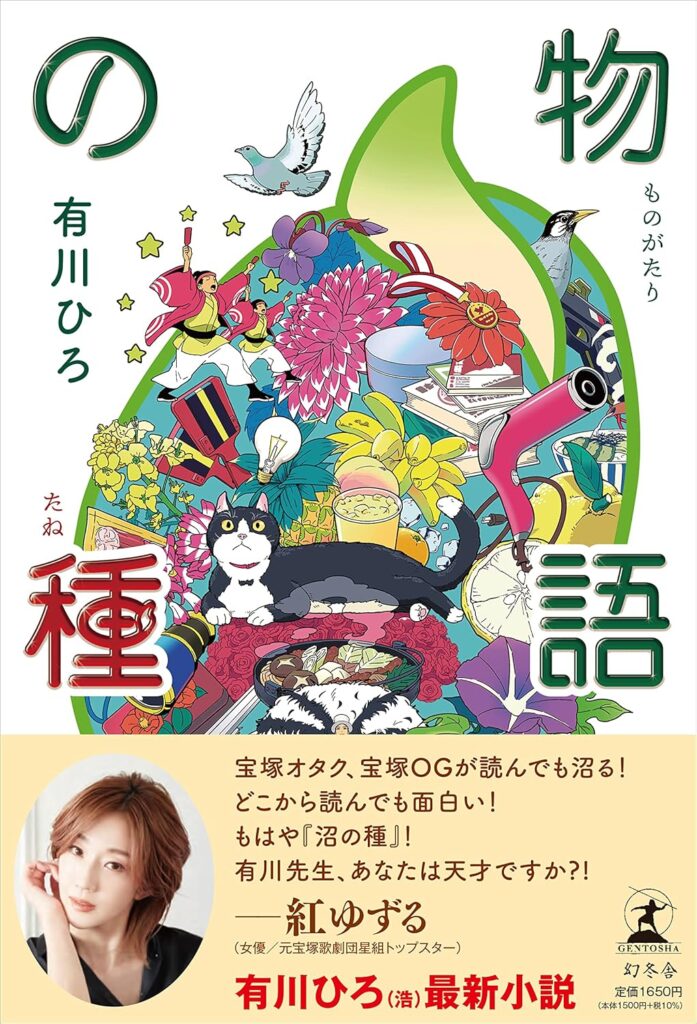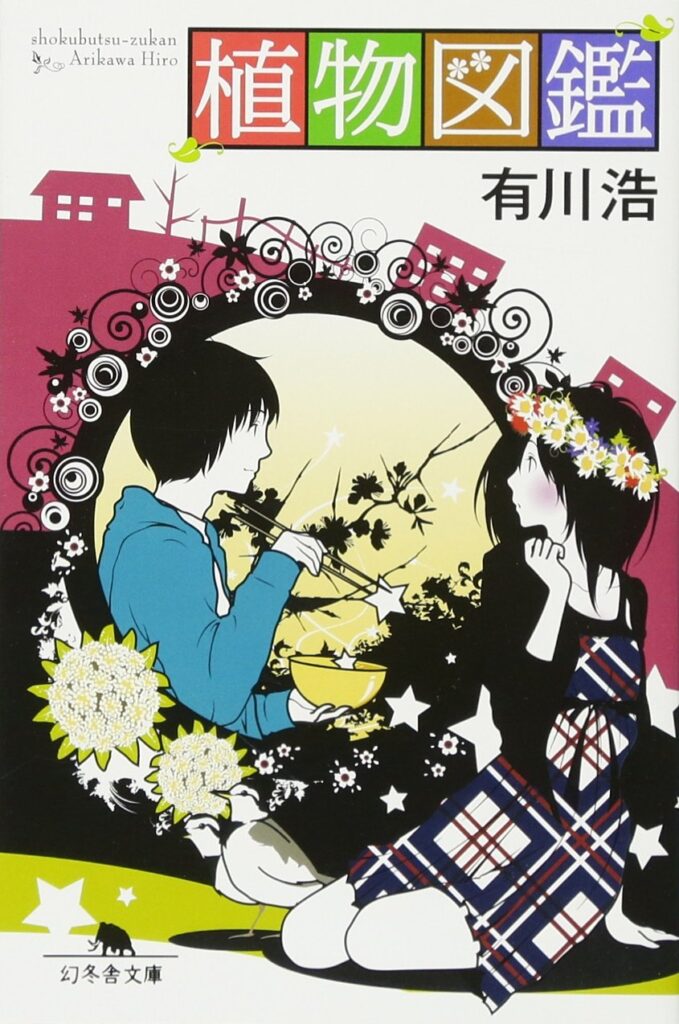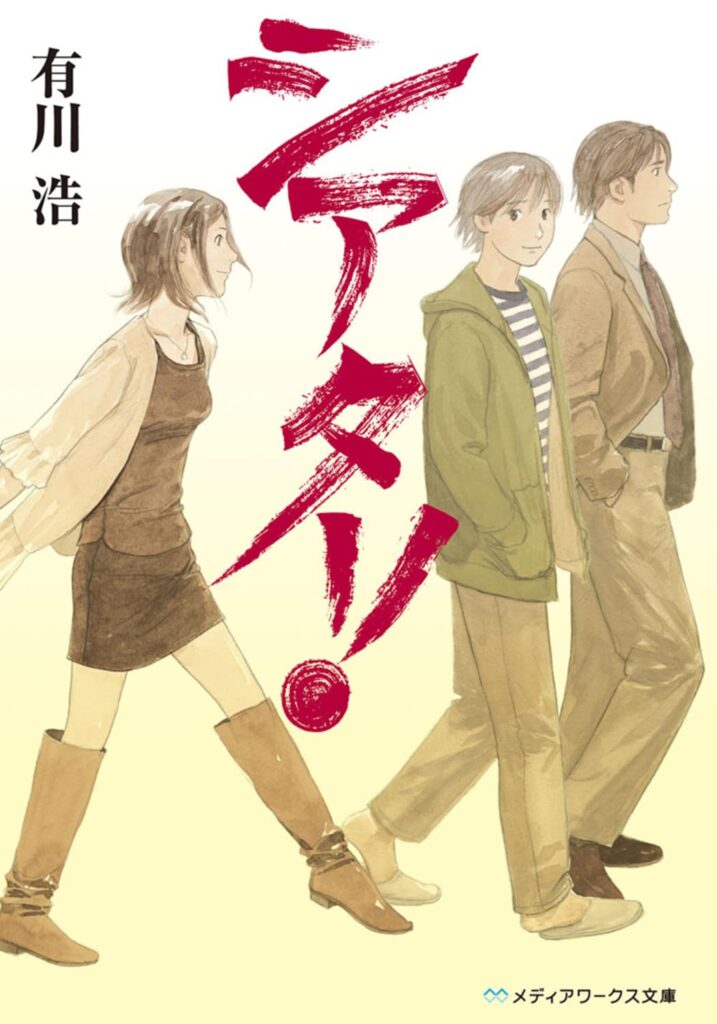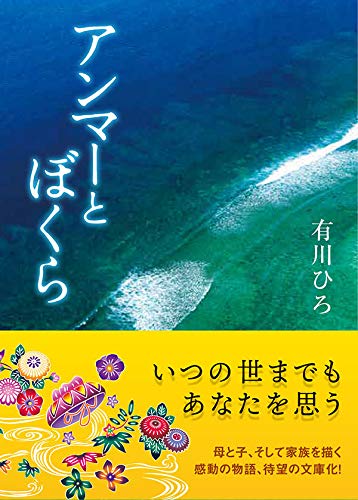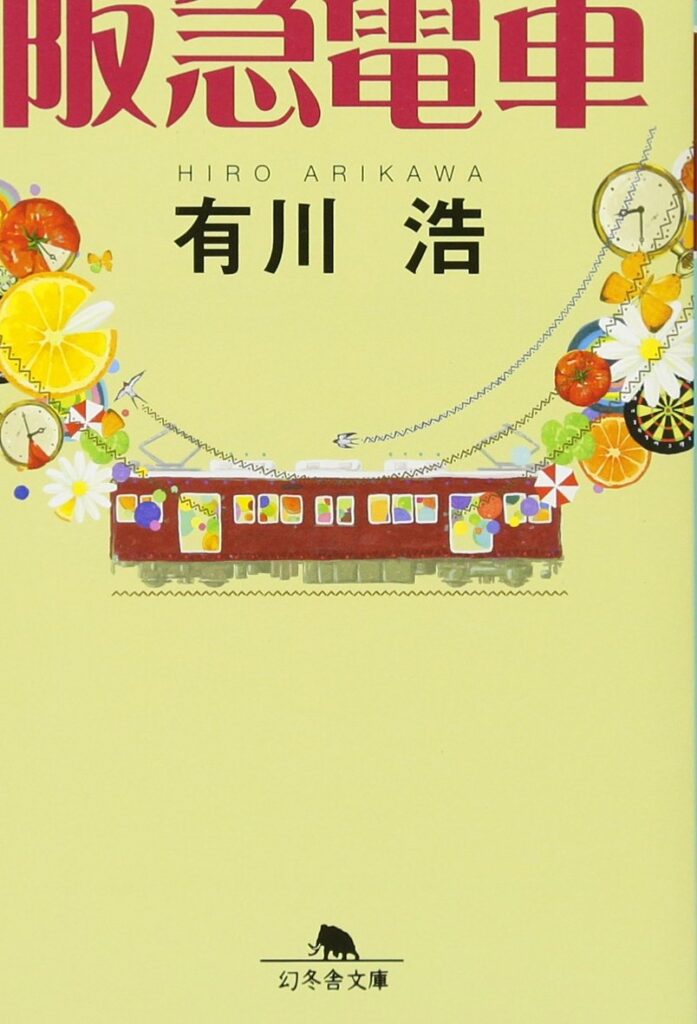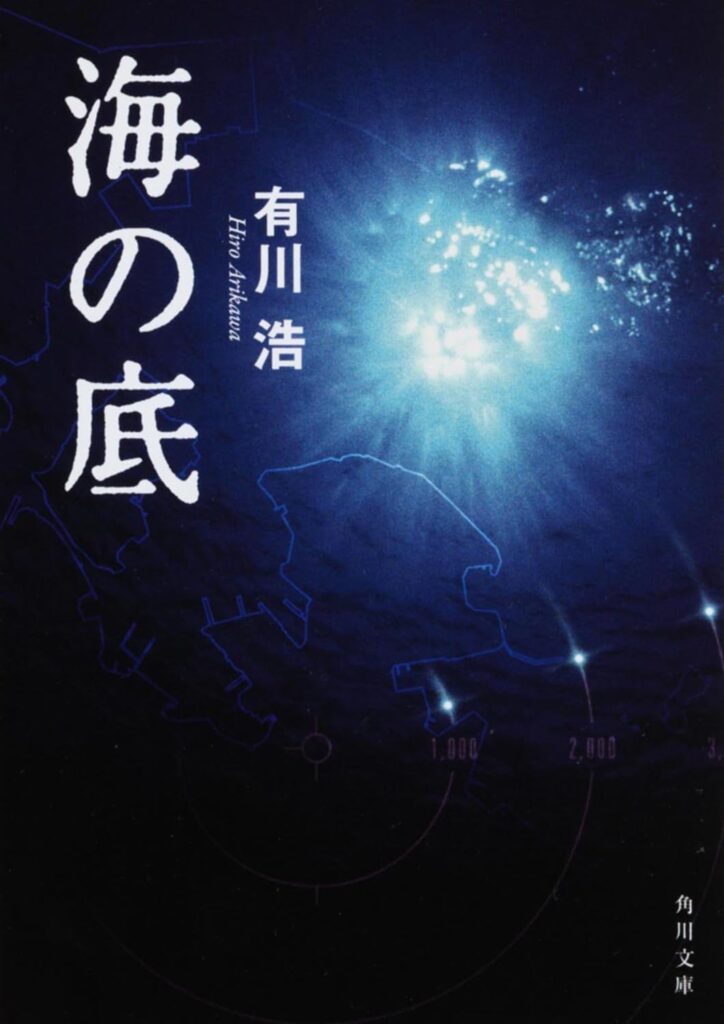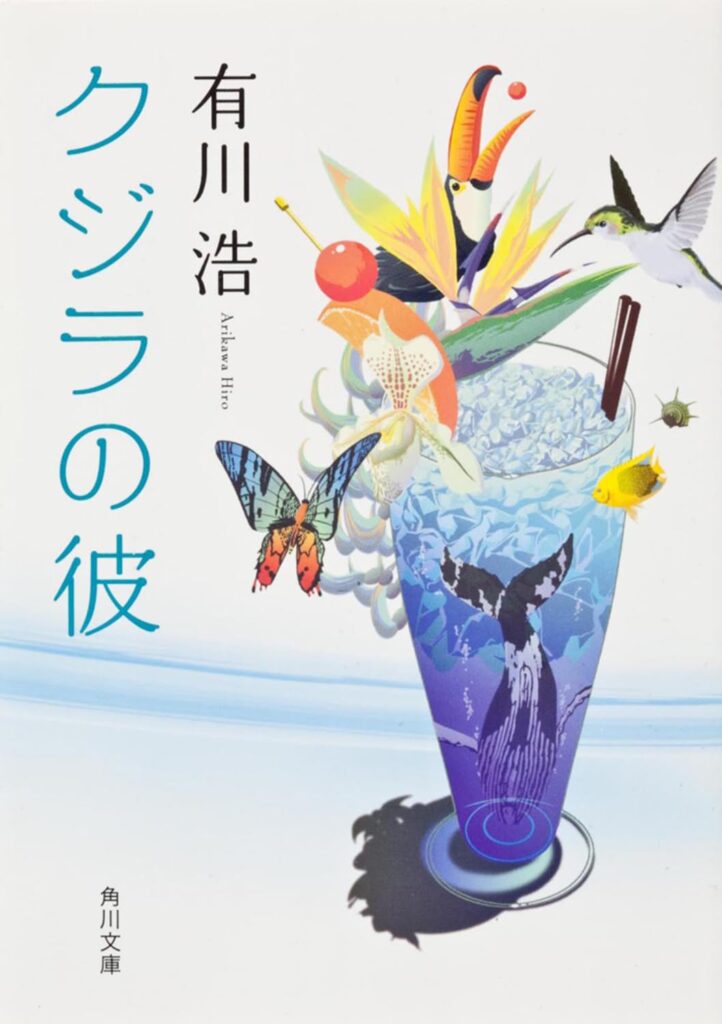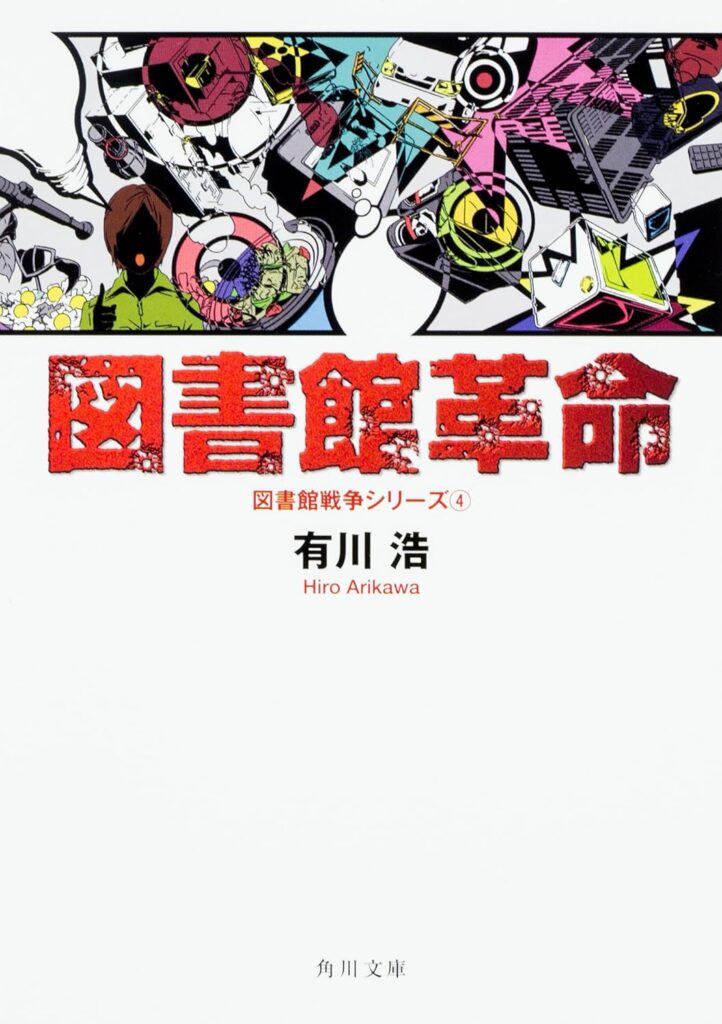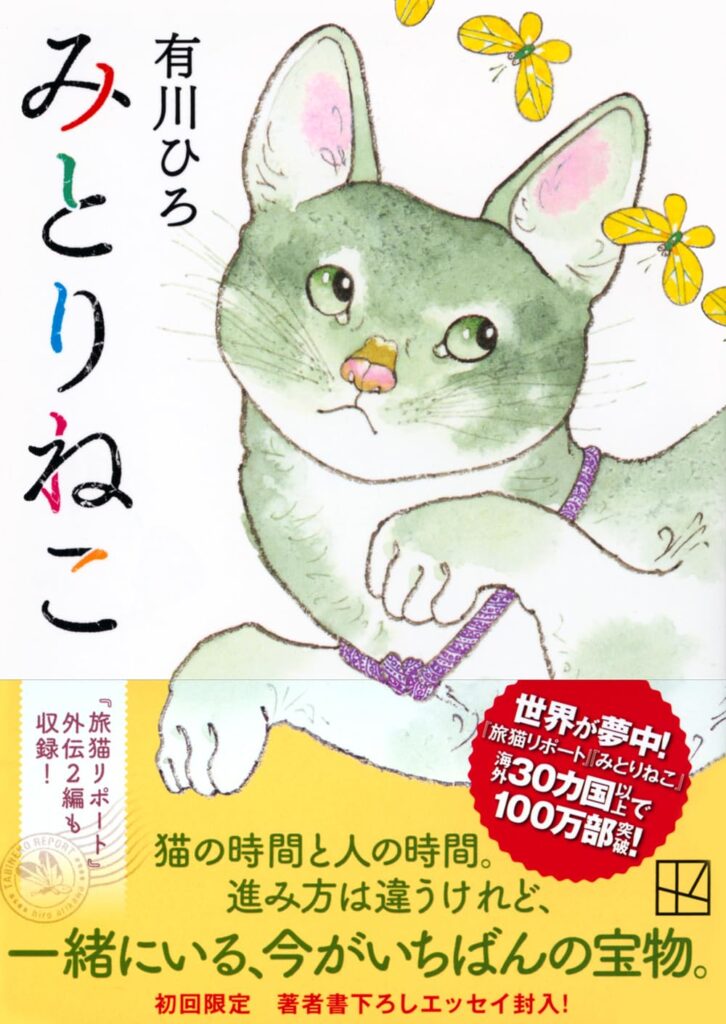小説「県庁おもてなし課」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「県庁おもてなし課」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、高知県庁に新しくできた「おもてなし課」が舞台です。主人公の掛水史貴(かけみず ふみたか)くんをはじめとする職員たちが、高知の観光を盛り上げようと一生懸命に奮闘するお話ですね。でも、最初はなかなかうまくいかないんです。県庁ならではの考え方や仕事の進め方が、民間感覚とはズレていたりして。そこに、高知県出身の人気作家・吉門喬介(よしかど きょうすけ)さんが現れて、掛水くんたちに厳しくも的確なアドバイスをしていくことになります。
この記事では、物語がどのように進んでいくのか、登場人物たちがどう変化していくのか、そして気になる結末まで、詳しくお伝えしていきます。もちろん、私が読んで感じたこと、考えたことも、たっぷりと語らせていただきますね。有川浩さんらしい、胸が温かくなるようなエピソードや、思わずキュンとしてしまう恋愛模様も描かれていますので、そのあたりも楽しんでいただけたら嬉しいです。
小説「県庁おもてなし課」のあらすじ
高知県の観光客誘致のため、県庁内に「おもてなし課」が新設されました。そこに配属された若手職員の掛水史貴は、やる気に満ちています。最初に課が取り組んだのは、高知出身の有名人の名刺の裏に県内施設のクーポンをつけ、配ってもらうという企画でした。掛水は早速、高知県出身の人気作家・吉門喬介に協力を依頼します。しかし、吉門は企画の意図や効果に疑問を呈し、掛水に厳しい指摘を突きつけます。この出会いが、おもてなし課の運命を大きく変えることになるのでした。
吉門の指摘を受け、掛水は県庁の仕事の進め方、特に時間に対する意識が民間とは大きく異なることを痛感します。吉門のアドバイスに従い、掛水はアルバイトの明神多紀(みょうじん たき)の協力を得て、かつて県庁で「パンダ誘致論」を唱えて左遷されたという人物、清遠和政(きよとお かずまさ)について調べ始めます。多紀の優秀さに気づいた掛水は、吉門の「民間感覚を持つ若い女性を入れるべき」という助言を思い出し、彼女をおもてなし課の臨時職員として迎え入れます。
掛水と多紀は、清遠が経営する「民宿きよとお」を訪ねます。最初は県庁に恨みを持つ娘の佐和(さわ)に水をかけられるなど、前途多難でしたが、なんとか清遠本人に会うことができ、彼をおもてなし課のコンサルタントとして招くことに成功します。清遠は「高知まるごとレジャーランド構想」という壮大なプランを提案。高知の豊かな自然という宝を活かしきれていない現状を指摘し、それらを繋ぎ合わせることで県全体を魅力的なレジャーランドにできると語ります。掛水と多紀は清遠と共に県内各地を巡り、高知の隠れた魅力と、「おもてなし」には観光客目線、特にトイレのような基本的な設備がいかに重要かを学びます。
しかし、かつての「パンダ誘致論」の件で清遠を快く思わない県庁上層部の圧力により、清遠は突然コンサルタントを解雇されてしまいます。計画は頓挫しかけ、掛水と多紀は落ち込みますが、清遠と、彼を取材していた吉門は冷静でした。実は、吉門は清遠の元義理の息子であり、佐和とは元義兄妹、そして互いに想い合う関係だったのです。清遠の解雇をきっかけに、吉門は佐和に想いを伝え、二人は結ばれます。一方、掛水と多紀は清遠から学んだ「おもてなしマインド」を胸に、自分たちの力でプロジェクトを再始動。吉門も作家としての影響力を使い、掛水との対談記事などを通して計画を後押しします。掛水と多紀の間にも、特別な感情が芽生え始めていました。
小説「県庁おもてなし課」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは小説「県庁おもてなし課」を読んだ私の個人的な思いを、ネタバレも気にせずに語っていきたいと思います。いやあ、読み終わった後、なんとも言えない温かい気持ちと、高知に行ってみたい!という強い衝動に駆られましたね。
まず、この物語の大きな魅力は、やっぱり登場人物たちだと思うんです。主人公の掛水くん。最初は本当に「ザ・公務員」というか、真面目で一生懸命なんだけど、どこか世間ずれしているというか、県庁の常識が当たり前になっている青年でした。でも、吉門さんという強烈な存在に出会って、ガツンとやられるわけです。民間感覚の厳しさ、スピード感、そして何より「当事者意識」を持つことの大切さを、身をもって学んでいく。彼の素直さと柔軟さが、吉門さんの厳しい言葉をただのダメ出しではなく、成長の糧として吸収していく力になったんですね。多紀ちゃんが現れてからは、彼女の的確な仕事ぶりや、県庁職員ではない視点からの意見に刺激を受け、さらに視野が広がっていく様子が、読んでいてとても応援したくなりました。
そして、アルバイトから臨時職員になる明神多紀ちゃん。彼女の存在は、この物語の清涼剤であり、推進力でもありますよね。掛水くんとは対照的に、最初から民間感覚というか、地に足のついた視点を持っている。それでいて、決して冷めているわけではなく、掛水くんの熱意や、おもてなし課のやろうとしていることに真摯に向き合っていく。彼女がいたからこそ、掛水くんも県庁の殻を破りやすくなったし、おもてなし課全体も変わっていくきっかけになったんだと思います。掛水くんとの間に芽生える、あの初々しい恋愛模様も、読んでいて本当に微笑ましかったですね。有川浩さんの描く恋愛って、どうしてこう、まっすぐで、読んでいるこっちが照れてしまうくらいピュアなんでしょうか。二人の不器用ながらも、少しずつ距離が縮まっていく様子は、物語の大きな楽しみの一つでした。
吉門喬介さん、この人は本当に強烈なキャラクターでしたね。人気作家でありながら、故郷である高知への想いは人一倍強い。掛水くんに対しては、最初から容赦ない言葉を浴びせかけます。「だからお役所仕事は!」と何度も言いたくなるような、県庁の体質への苛立ちを隠そうともしない。でも、それは決して意地悪からではなく、高知を本気で良くしたいという熱い想いの裏返しなんですよね。彼の言葉は厳しいけれど、常に的確で、本質を突いている。そして、ただ批判するだけでなく、どうすれば良くなるのか、具体的な道筋を示してくれる。掛水くんを、そしておもてなし課を、正しい方向へと導く羅針盤のような存在でした。彼が抱える、清遠さんや佐和さんとの複雑な過去と、秘めた想い。その背景を知ると、彼の言動の奥にある優しさや不器用さが見えてきて、ますます人間的な魅力を感じました。佐和さんへのプロポーズの場面なんて、もう、涙なしには読めませんでしたよ。
清遠和政さん。この方もまた、魅力的な人物でした。「パンダ誘致論」で県庁を追われた過去を持つ、ちょっと変わり者のおじさん、という第一印象ですが、その実、誰よりも高知の可能性を信じ、壮大な夢を描いていた人。彼が提唱する「高知まるごとレジャーランド構想」は、単なる思いつきではなく、高知の豊かな自然や文化に対する深い洞察に基づいたものでした。県内の人が当たり前すぎて気づかない魅力を掘り起こし、それらを繋ぎ合わせることで、高知全体を一つの大きな魅力的な場所にしようという発想は、本当にワクワクさせられましたね。彼が掛水くんと多紀ちゃんを連れて県内各地を巡る場面は、まるで高知の観光ガイドを読んでいるようで、私も一緒に旅をしている気分になりました。娘の佐和さんや、元義理の息子の吉門さんとの関係も、物語に深みを与えています。県庁に一度は裏切られながらも、高知への愛を失わず、再び立ち上がろうとする姿には、心を打たれました。
そして、清遠さんの娘であり、民宿きよとおを切り盛りする佐和さん。最初は県庁に対して強い憎しみを持っていて、掛水くんにも敵意むき出しでした。父親が県庁に翻弄された過去を知っているからこその、当然の反応だったのかもしれません。でも、物語が進むにつれて、彼女の心の中にも変化が訪れます。吉門さんへの長年の想い、父親への複雑な感情、そして、掛水くんたちのひたむきな姿に触れる中で、少しずつ心を解きほぐしていく。吉門さんと結ばれる場面は、本当に良かったね、と心から思いました。彼女もまた、過去のしがらみを乗り越えて、新しい一歩を踏み出した一人なんですね。
物語のテーマとして大きいのは、やはり「地方創生」や「地域活性化」ですよね。高知県という実在の場所を舞台に、観光客を呼び込むために何が必要なのか、どうすれば地域の魅力が伝わるのか、という課題に真正面から取り組んでいます。特に印象的だったのは、「不便を便利へ」という考え方です。アクセスが悪かったり、設備が整っていなかったりすることを、マイナスとして捉えるのではなく、むしろそれを「価値」として楽しんでもらおうという発想の転換。馬路村のエピソードなどが、まさにそれですよね。これは、観光に限らず、いろんな場面で応用できる考え方だなと感じました。無理に都会の真似をするのではなく、その土地ならではの個性や、ありのままの姿を魅力として打ち出していくことの大切さを教えられた気がします。
また、「公務員」と「民間」の意識の違いも、リアルに描かれていました。縦割り行政の弊害、前例踏襲主義、意思決定の遅さなど、「あるある」と感じる人も多いのではないでしょうか。でも、この物語は、単に公務員を批判するだけでは終わりません。掛水くんのように、現状を変えようと奮闘する人もいるし、最初は変化を嫌っていた他の職員たちも、掛水くんの熱意に影響され、次第に「自分たちの高知を良くしたい」という想いを共有していくようになります。組織の中で、どうやって壁を乗り越え、周りを巻き込んでいくか。お仕事小説としても、非常に読み応えがありました。
そして、忘れてはいけないのが「おもてなし」の心です。タイトルにもなっているこの言葉の意味を、物語を通して深く考えさせられました。単に施設をきれいにしたり、クーポンを配ったりするだけではない。本当に大切なのは、訪れる人の立場に立って物事を考え、心から歓迎する気持ちを持つことなんだと。多紀ちゃんが気づいた「トイレの重要性」なんかも、まさにその表れですよね。観光客が何に困り、何を求めているのか。その視点を持つことが、本当の意味でのおもてなしに繋がるのだと感じました。
舞台となった高知県の描写も、本当に素晴らしかったです。仁淀川の美しい流れ、四万十川の雄大さ、カツオのたたきをはじめとする美味しい食べ物、よさこい祭りの熱気。まるで、高知県の魅力を詰め込んだ宝石箱のように、次々と美しい風景や文化が目の前に広がっていくようでした。有川浩さん自身が高知県出身ということもあって、故郷への深い愛情が、文章の端々から伝わってきました。読んでいると、今すぐにでも飛行機に飛び乗って、高知を訪れたくなりますね。この小説を読んで、実際に高知旅行を決めた人も多いのではないでしょうか。
物語の結末も、希望に満ちていて、読後感がとても爽やかでした。清遠さんの構想は、掛水くんと多紀ちゃん、そしておもてなし課の仲間たちによって引き継がれ、吉門さんの協力も得て、着実に前進していきます。掛水くんと多紀ちゃん、吉門さんと佐和さん、それぞれの恋の行方も、温かい未来を感じさせるものでした。困難を乗り越え、成長した登場人物たちが、それぞれの場所で輝いていく姿を想像すると、なんだか嬉しくなりますね。
この小説は、地方が抱える課題に真摯に向き合いながらも、決して重苦しくはならず、人と人との繋がりや、前向きに頑張る人々の姿を、温かい眼差しで描いている作品だと感じました。有川浩さんならではの、読みやすく、心に響く文章で、一気に読むことができました。仕事で壁にぶつかっている人、何か新しいことを始めようとしている人、そしてもちろん、有川浩さんのファンや、心温まる物語が読みたい人には、ぜひ手に取ってみてほしい一冊です。読めばきっと、元気をもらえると思いますよ。
まとめ
この記事では、有川浩さんの小説「県庁おもてなし課」の物語の詳しい流れを、結末まで含めてお伝えし、さらに私の個人的な深い思いも語らせていただきました。高知県庁のおもてなし課を舞台に、主人公の掛水くんたちが、人気作家の吉門さんや元県庁職員の清遠さん、アルバイトの多紀ちゃんたちと共に、高知の観光を盛り上げようと奮闘する物語でしたね。
県庁特有の体質に悩みながらも、民間感覚を学び、周りを巻き込みながら成長していく掛水くんたちの姿は、とても応援したくなりました。また、「不便を便利へ」という発想の転換や、「おもてなしマインド」の大切さなど、地域活性化や仕事への向き合い方について、多くの気づきを与えてくれる作品でもありました。登場人物たちの人間関係や、有川浩さんらしいピュアな恋愛模様も、物語の大きな魅力です。
高知県の美しい自然や文化の描写も豊かで、読んでいるだけで旅情をかきたてられます。地方創生に関心のある方、お仕事小説が好きな方、心温まる人間ドラマに触れたい方、そしてもちろん、有川浩さんの作品が好きな方には、心からおすすめしたい一冊です。読後にはきっと、温かい気持ちと、少しの勇気をもらえるはずですよ。