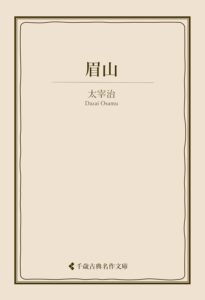 小説「眉山」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治の短編小説の中でも、読後に深く考えさせられる作品の一つだと私は思います。
小説「眉山」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治の短編小説の中でも、読後に深く考えさせられる作品の一つだと私は思います。
物語は戦後間もない新宿の飲み屋「若松屋」を舞台に、小説家の「僕」と、そこで働く女中のトシちゃんとの関わりを描いています。「僕」とその仲間たちは、無邪気で少しおっちょこちょいなトシちゃんを「眉山」とあだ名をつけ、日頃からからかったり、内心で見下したりしています。
しかし、物語の終盤で、トシちゃんが実は重い病気を患っていたことが明らかになります。彼女の奇妙に見えた行動の数々が、病気と、そして「僕」たち小説家への純粋な憧れから来ていたことを知り、「僕」は強い衝撃と自己嫌悪に襲われるのです。
この記事では、そんな「眉山」の物語の顛末と、私が感じたこと、考えたことを詳しくお伝えしたいと思います。読んだことがある方も、まだ読んだことがない方も、この作品が持つ切なさや、人間の心の複雑さに触れていただけたら嬉しいです。
小説「眉山」のあらすじ
舞台は、飲食店閉鎖の命令が出る前の、戦後間もない新宿。小説家の端くれである「僕」は、知人の姉が営む飲み屋「若松屋」に入り浸っていました。つけが利き、二階に泊まることもできたので、何かと都合が良かったのです。「僕」は画家の橋田新一郎や俳優の中村国男といった仲間たちと、よくこの店で飲んでいました。
若松屋には、トシちゃんという二十歳前後の女中さんがいました。彼女は幼い頃から何よりも小説が好きだと公言しており、「僕」たちが連れてくる仲間を皆、有名な小説家だと思い込んでいました。実際には画家や音楽家、俳優なのですが、トシちゃんは無邪気に尊敬の眼差しを向けてくるのです。
ある日、「僕」がピアニストの川上六郎氏を連れて行くと、トシちゃんは彼を明治時代の小説家「川上眉山」だと勘違いしてしまいます。「僕」が呆れて訂正しても、彼女は聞く耳を持ちません。それ以来、「僕」たちは陰でトシちゃんのことを「眉山」と呼んでからかうようになりました。
トシちゃんは、お世辞にも器量が良いとは言えず、少し騒々しいところがありました。階段をドタドタと駆け下りたり、トイレの戸を大きな音で閉めたり。「僕」たちの会話にも、よく知ったかぶりをして入ってこようとします。特にトイレの使い方がぞんざいで、「眉山の大海」と揶揄されるほど汚してしまうこともあり、「僕」たちは彼女の存在を正直、煙たく感じていました。味噌を踏んで部屋に入ってきた「ミソ踏み事件」など、困った出来事も起こります。
どれだけ仲間内で悪口を言ったり、時には直接からかったりしても、トシちゃんはいつもニコニコしているばかりでした。ある時、「僕」の悪口が載った文芸雑誌をトシちゃんが買ってきて、「僕」の名前を探しているのを見た時は、本気で腹が立ちました。自分の悪評を、この無知な女中に読まれてたまるか、と思ったのです。それでも、つけがきく便利さから、若松屋通いはやめられませんでした。
そんなある日、「僕」は飲み過ぎで体調を崩し、十日ほど寝込みます。回復して久しぶりに若松屋へ向かう途中、友人の橋田氏にばったり会いました。そして、橋田氏から衝撃の事実を知らされます。トシちゃんは、もう若松屋にはいない、と。実は彼女は重い腎臓結核を患っており、長くは生きられないため、実家に帰されたというのです。頻繁にトイレに行っていたのも、時折粗相をしてしまっていたのも、病気のせいでした。それでも、大好きな小説家の先生たち(と彼女が思い込んでいる「僕」たち)のそばに少しでも長くいたくて、ギリギリまで我慢していたのでした。「……いい子でしたがね」。「僕」は思わずそう口にしましたが、その言葉が自分の心からのものではないような気がして、ひどくうろたえます。トシちゃんが、どんなに遅い時間でも嫌な顔一つせず、病身を押して自分たちの世話をしてくれていたことを思い出し、「僕」は地団駄を踏みたいような後悔と自己嫌悪に苛まれ、その日を境に若松屋へ行くのをやめたのでした。
小説「眉山」の長文感想(ネタバレあり)
太宰治の「眉山」を読むと、いつも胸が締め付けられるような気持ちになります。そして同時に、自分自身の心の奥底にある、見たくない部分を突きつけられるような感覚に陥るのです。「僕」が最後に漏らした「……いい子でしたがね」という言葉。それは、トシちゃんへの純粋な追悼の念だったのでしょうか。それとも、もっと別の、複雑な感情が入り混じっていたのでしょうか。
この物語の中心にいるのは、女中のトシちゃんです。「僕」やその仲間たちからは、「眉山」とあだ名をつけられ、どこか見下され、厄介者扱いされています。彼女は確かに、世間知らずで、空気が読めないところがあり、行動も少しがさつに見えます。しかし、彼女の根底にあるのは、文学への強い憧れと、小説家(だと彼女が信じている)「僕」たちへの純粋な尊敬の念なのです。
彼女が、画家や音楽家を著名な小説家だと勘違いしてしまう場面。これは、彼女の無知さを示すと同時に、いかに彼女が「小説」という世界に焦がれているかを表しているように思います。教育を受ける機会に恵まれず、女中として働く身でありながら、彼女は必死に文学の世界に触れようとしていたのではないでしょうか。「川上眉山」という、今ではあまり知られていない明治の作家の名前を知っていたことからも、彼女の文学への関心が単なる付け焼き刃ではなかったことがうかがえます。
しかし、「僕」たちは、そんなトシちゃんの純粋な気持ちに気づこうともしません。それどころか、彼女の言動を嘲笑し、軽蔑します。階段をドタドタと駆け上がる音、トイレの戸を閉める音、そして何より「眉山の大海」とまで言われたトイレの使い方。これらはすべて、「僕」たちにとって不快なものでしかありませんでした。
特に印象的なのは、「僕」の悪口が書かれた雑誌をトシちゃんが読もうとする場面です。「僕」は激しい嫌悪感を抱き、彼女に読まれることを何よりも恐れます。これは、「僕」の自尊心の現れでしょう。自分が軽んじている相手に、自分の評価が低いことを知られたくない。その根底には、「自分は彼女よりも上の存在だ」という無意識の驕りがあったのではないでしょうか。
私たちは誰しも、程度の差こそあれ、自分と他者を比較し、優位に立ちたいという欲求を持っているのかもしれません。「話が合わない」「レベルが違う」と感じる相手を、心のどこかで見下してしまう。そして、そういう相手に限って、悪意なくこちらを慕ってくれたりすると、余計に罪悪感を覚えてしまう…。参考資料にあった感想のように、私も「眉山」を読むと、そうした自己嫌悪のループに陥ってしまうのです。
物語の転換点は、トシちゃんが重い腎臓結核を患っていたという事実が明かされる場面です。彼女の不可解な行動――頻繁なトイレ通いや粗相――は、すべて病気によるものでした。そして、「僕」たちが煙たがっていた騒々しい足音や、どんなに遅くても嫌な顔一つせずにお酒を運んできてくれた健気さは、病気の苦しみに耐えながらも、憧れの「先生」たちのそばにいたい、少しでも役に立ちたいという、彼女の切ない願いの表れだったのです。
この事実を知った時の「僕」の衝撃は、いかばかりだったでしょうか。自分たちが、いかに表面的な部分しか見ていなかったか。トシちゃんの純粋な好意を、無知や図々しさとしてしか捉えられず、どれだけ彼女を傷つけてきたか。その事実に打ちのめされたはずです。
そして、「僕」は思わず「……いい子でしたがね」と口走ります。この言葉の解釈は、読む人によって分かれるかもしれません。遅ればせながらトシちゃんの本当の姿に気づき、心から哀悼の意を示した言葉なのかもしれません。あるいは、参考資料の考察にあるように、トシちゃんがいなくなったことで生じるであろう、自分たちの不便さや寂しさを予感し、どこまでも自己中心的な感傷に浸っているだけなのかもしれません。
私は、おそらく後者の要素も含まれているのではないかと感じます。だからこそ、「僕」は「自分で自分の口を覆いたいような気持がした」のではないでしょうか。自分の言葉が、あまりにも薄っぺらく、自己欺瞞に満ちていると感じたからではないでしょうか。トシちゃんへの同情や後悔とともに、そんな自分自身への強烈な嫌悪感が、「僕」を襲ったのだと思います。
この作品が書かれたのは、第二次世界大戦が終わって間もない頃です。参考資料にもあるように、当時の日本は価値観が大きく揺らぎ、人々は混乱の中にいました。太宰治自身も、『トカトントン』などで戦後の虚無感を描こうとしています。「眉山」の冒頭で触れられている「飲食店閉鎖の命令」も、当時の厳しい食糧事情を物語っています。
そんな時代背景の中で、トシちゃんという存在は、何を象徴していたのでしょうか。ある考察では、身分や性別に関わらず誰もが文学を自由に楽しめる、新しい時代の女性像を示唆しているのではないか、と述べられています。確かに、女中という立場の女性が、これほどまでに小説に情熱を傾ける姿は、戦前の価値観からすれば異質だったかもしれません。
しかし私は、それ以上に、トシちゃんの存在は、時代や状況に関わらない、普遍的な人間の「純粋さ」や「真心」を象徴しているように感じます。そして、「僕」たちの態度は、そうした純粋さや真心を踏みにじってしまう、人間の「弱さ」や「愚かさ」を表しているのではないでしょうか。
私たちは、知らず知らずのうちに、先入観や偏見で人を判断してしまいがちです。相手の肩書きや見た目、話し方などで、勝手にその人の価値を決めつけ、理解しようと努めることを怠ってしまう。そして、後になってから、その人の本当の姿や、隠された苦しみ、秘められた優しさに気づき、後悔するのです。「眉山」の「僕」が経験したことは、決して他人事ではない、私たち自身の物語でもあるように思えてなりません。
太宰治は、自身のダメさや弱さを隠さずに作品に描き出す作家として知られています。「眉山」の「僕」にも、太宰自身の姿が投影されているのかもしれません。売れない小説家としての焦りや劣等感、他人を見下すことで保たれる脆い自尊心。そうした人間の弱さを、太宰は冷徹な目で見つめ、描き出します。しかし、そこには単なる自己憐憫や開き直りだけではない、深い反省と、人間存在への切ない眼差しが感じられるのです。
だからこそ、「眉山」は読者の心を強く打つのだと思います。トシちゃんの健気さと悲しい運命に涙し、「僕」の愚かさに憤りを感じながらも、その「僕」の姿に自分自身を重ね合わせ、胸が痛むのです。そして、読み終わった後には、「自分は大丈夫だろうか」「大切な人の真心を見誤ってはいないだろうか」と、深く自問させられるのです。
この物語の結末で、「僕」は若松屋に行くのをやめます。それは、トシちゃんへの罪滅ぼしのつもりだったのかもしれませんし、単に気まずさから逃げただけなのかもしれません。いずれにせよ、彼がトシちゃんの死(あるいは余命宣告)をきっかけに、何らかの変化を経験したことは確かでしょう。しかし、その変化が彼の本質的な部分にまで及んだかどうかは、定かではありません。人間は、そう簡単には変われないものです。だからこそ、この物語は、一過性の感傷に終わらせてはならない、というメッセージを私たちに投げかけているようにも思えます。
トシちゃんのような存在は、私たちの周りにもいるのかもしれません。少し不器用で、うまく自分を表現できなくても、心の中には豊かな感情や、純粋な思いやりを秘めている人。私たちが、日々の忙しさや、自分の物差しだけで人を判断する癖によって、見過ごしてしまっている大切なものが、きっとあるはずです。
「眉山」は、そんな当たり前の、しかし忘れがちなことを、静かに、しかし鋭く、私たちに教えてくれる作品です。短い物語の中に、人間の愚かさと愛おしさ、そして人生の哀しみが凝縮されています。何度読んでも、新たな発見と考えさせられる点がある、深い味わいを持つ小説だと、私は思います。
まとめ
太宰治の短編小説「眉山」は、戦後間もない新宿の飲み屋を舞台に、小説家の「僕」と女中のトシちゃんの交流を描いた物語です。ネタバレになりますが、当初「僕」たちはトシちゃんを無知で騒々しい存在として見下し、「眉山」とあだ名をつけてからかいます。
しかし、物語の終盤で、トシちゃんが重い腎臓結核を患っており、彼女の行動が病気と「僕」たちへの純粋な憧れから来ていたことが判明します。この事実に衝撃を受けた「僕」は、自己嫌悪と後悔の念に苛まれます。最後に漏らした「……いい子でしたがね」という言葉には、複雑な感情が込められているように感じられます。
この作品を読むと、人の表面的な部分だけで判断することの危うさや、先入観の恐ろしさを痛感させられます。トシちゃんの純粋さや健気さが胸を打つ一方で、「僕」の弱さや愚かさに、自分自身の姿を重ねてしまう読者も少なくないでしょう。
「眉山」は、短いながらも人間の心の機微、人生の哀しみ、そして他者への想像力の大切さを深く考えさせてくれる作品です。読後、きっとあなたの心にも静かな問いかけが残るはずです。ぜひ一度、手に取って読んでみていただきたい一編です。




























































