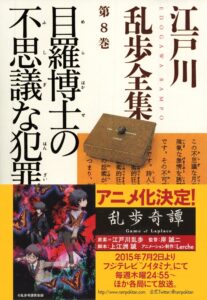 小説「目羅博士」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩が描く、都市の片隅に潜む奇妙な事件の物語です。
小説「目羅博士」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩が描く、都市の片隅に潜む奇妙な事件の物語です。
物語は、語り手である「私」が、ある男と出会うところから始まります。その男が語る体験談が、本作の中核を成しています。男の話は、一見すると突拍子もないようでいて、妙にリアリティを感じさせる部分があります。
それは、人間の持つ「模倣」という本能と、視覚的なトリック、そして都市が生み出す特異な空間が絡み合った、まさに乱歩ならではの世界観です。この記事では、その詳細なあらすじと、読後に感じた深い考察を、余すところなくお伝えしたいと思います。
これからお話しする内容には、物語の結末に触れる部分も含まれます。未読の方はご注意いただきつつ、すでに読まれた方は、ぜひご自身の解釈と照らし合わせながら読み進めてみてください。
小説「目羅博士」のあらすじ
物語の語り手「私」(江戸川乱歩自身を思わせる作家)は、ある日、動物園で奇妙な男に出会います。男は猿の「真似」をする習性について語り出し、「真似」という行為に潜む恐ろしさを説きます。猿が人間の真似をして自滅するという、寓話めいた話を引き合いに出しながら。男自身も鏡に映る自分の姿を「真似されている」と感じ、異常な恐怖を抱いていることを告白します。
日が暮れ、動物園を出た後、男は「私」が江戸川乱歩であることを見抜き、ファンだと明かします。そして、月光の下でこそ話すにふさわしい、自身の体験した奇怪な事件について語り始めると提案し、二人は不忍池の見える高台へと移動します。
男はかつて、東京・丸の内の高層ビルに挟まれた「恐怖の谷」と呼ばれる薄暗い路地に面したビルで、夜警として働いていました。そのビルの5階にある特定の部屋では、借り手が次々と首を吊って亡くなるという不可解な事件が続いていたのです。最初の犠牲者は香料ブローカー、二人目は陽気な性格の人物、どちらも自殺する動機は見当たりませんでした。
三人目の犠牲者は、噂を確かめようとした豪胆なビルの事務員でした。「私」は、前の住人の死を無意識に「模倣」してしまうのではないかと推測します。しかし男は、事件が起こるには「月光」という条件が必要だと見抜いていました。事務員が亡くなった夜は、まさに月が明るく照らす晩だったのです。
男は事務員の部屋に入り、向かいのビルにも同じように窓が開いていることに気づきます。そして、首を吊った事務員の姿と、向かいの部屋にいる「誰か」の影を目撃します。しかし、向かいの部屋は空室のはずでした。男は、月光が直接の原因ではなく、何者かが関与していると確信します。
男はその人影の正体を探し、ついに目羅眼科の医学博士である目羅博士に行き着きます。しかし、博士がなぜそのような事件に関わるのか、動機は不明のままでした。やがて、例の部屋に四人目の借り手がつきます。男は目羅博士の犯行を確信し、博士の動向を探ります。博士の事務所には、四人目の借り手と全く同じ服装をした蝋人形が置かれていました。男はついに、博士が使うトリックの核心に気づきます。月光が差し込む夜、窓の外を見ると、まるで巨大な鏡が現れたかのように錯覚するのです。そして、その「鏡」には、向かいのビルに吊るされた蝋人形(借り手そっくりの)が映り込み、あたかも自分自身が首を吊っているかのように見える。この光景を見た者は、「鏡の中の自分」を真似するように、自ら命を絶ってしまうのでした。男は四人目の借り手になりすまし、目羅博士のトリックを見破ります。そして、用意していた目羅博士そっくりの蝋人形を窓から突き落とすことで、博士自身に「模倣」させ、飛び降り自殺へと導くのでした。
小説「目羅博士」の長文感想(ネタバレあり)
江戸川乱歩の「目羅博士の不思議な犯罪」を読むと、いつも心がざわめきます。この物語には、都会の片隅に潜む闇と、人間の心理の深淵を覗き見るような、独特の魅力が詰まっていると感じるのです。
まず、この物語のテーマである「月光、鏡、模倣」という要素が、見事に組み合わさっている点に感嘆します。月光が作り出す非日常的な空間、鏡が映し出す虚像、そして人間(あるいは動物)が持つ模倣の本能。これらが連鎖し、恐ろしい結末へと繋がっていく構成は、実に巧みだと思います。
特に印象的なのは、冒頭で語られる猿の模倣の話です。旅人の仕草を真似て自滅する猿の話は、一見すると本筋とは関係ないように思えるかもしれません。しかし、このエピソードがあることで、「模倣」という行為に潜む危険性が読者の意識に強く刷り込まれ、後半で展開される目羅博士による犯罪の異様さと説得力を増しているように感じます。
物語の舞台となる「恐怖の谷」の描写も秀逸です。高いビルに挟まれた、日の当たらない薄暗い空間。そこは文明が生み出した、もう一つの自然の峡谷のようです。乱歩の筆致は、その場所の陰鬱さ、閉塞感をありありと描き出し、読者を物語の世界へと引き込みます。まるで自分もその谷間に迷い込んだかのような感覚に陥るのです。
連続する首吊り事件の謎が深まっていく過程も、引き込まれる要素の一つです。動機不明の死、現場に残された奇妙な共通点、そして「月光」というキーワード。読者は語り手の男と共に、事件の真相へと迫っていきます。このミステリアスな展開が、ページをめくる手を止めさせません。
そして、目羅博士の登場。彼の存在は、物語に更なる深みを与えています。なぜ彼はこのような手の込んだ犯罪を行うのか?その動機は最後まで明確には語られませんが、それゆえに彼の不気味さが際立ちます。彼の歪んだ好奇心や、人間心理を操ることへの倒錯した喜びが垣間見えるようです。
トリックの核心が明かされる場面は、本作のクライマックスと言えるでしょう。月光とガラス窓が生み出す巨大な「鏡」。そこに映し出される、自分そっくりの蝋人形の首吊り姿。この視覚的な幻惑によって、被害者は自らの死を「模倣」してしまう。このアイデアには、ただただ脱帽するほかありません。科学的な現象と人間の心理的な弱さを見事に結びつけた、独創的なトリックだと感じます。
結末で、男が目羅博士を同じ「模倣」の手口で破滅させる展開は、ある種のカタルシスを感じさせます。悪が悪自身の仕掛けた罠によって滅びるという構図は、物語として非常に美しい決着の付け方だと思います。しかし、同時に一抹の恐ろしさも残ります。
それは、最後に男が見せる表情が、どこか目羅博士に似ていた、という描写です。彼もまた、博士を「模倣」してしまったのではないか? 犯罪者を裁く過程で、彼自身もまた闇に染まってしまったのではないか? このような余韻を残す終わり方も、乱歩作品ならではの味わい深さと言えるでしょう。
個人的な話になりますが、私は都会の、特に古い雑居ビルが立ち並ぶ風景に惹かれる性質があります。乱歩の作品、特に初期のものは、そうした東京の風景と非常に親和性が高いと感じています。「目羅博士の不思議な犯罪」で描かれる「恐怖の谷」も、まさにそうした都市の隙間に潜む異界のような場所です。
乱歩を読むことは、私にとって、かつて憧れた「東京」という街の、光と影が交錯する姿を追体験するような行為でもあります。彼の描く都市は、単なる背景ではなく、物語の重要な登場人物のように感じられます。
また、乱歩の文章そのものにも、強い魅力を感じます。簡潔でありながら、情景や心理を的確に描き出す筆力は、時代を経ても色褪せません。特に「目羅博士の不思議な犯罪」のような短編では、その凝縮された表現力が際立っていると思います。
この作品は、怪奇小説であり、探偵小説の要素も持ち合わせていますが、その根底にあるのは、人間の心の不可思議さへの問いかけではないでしょうか。私たちは、いかに容易に外部からの影響を受け、時には自らを破滅に導くような行動をとってしまうのか。
日常の中に潜む、非日常への入り口。窓の外の風景が、月光によって一変し、恐ろしい幻惑の世界となる。そんな裂け目が、私たちのすぐそばにも存在するかもしれない。そう思わせる力が、この物語にはあります。
「目羅博士の不思議な犯罪」は、読後、しばらくの間、窓の外を眺めるのが少し怖くなるような、そんな類の物語です。しかし、その恐怖と共に、人間の心の奥底を覗き見たような、不思議な感覚も残ります。これこそが、江戸川乱歩作品の持つ、尽きない魅力なのだと改めて感じさせられました。
まとめ
この記事では、江戸川乱歩の名作短編「目羅博士」について、物語の詳しい筋道と、読み終えて感じた様々な思いを綴ってきました。ネタバレを含む形で、その奇妙で恐ろしい事件の全貌と、そこに隠されたテーマに迫ってみました。
物語は、都会のビル街に潜む「恐怖の谷」を舞台に、月光と鏡、そして人間の「模倣」という本能が絡み合って引き起こされる連続首吊り事件を描いています。語り手の男が目撃し、そして最後には自ら関与することになる事件の顛末は、読者に強烈な印象を残します。
目羅博士が仕掛けたトリックの独創性、そしてそれを暴き、同じ手口で博士を破滅させる男の対決は、物語の大きな見どころです。しかし、単なる猟奇的な事件としてだけではなく、人間の心理の脆さや、日常に潜む狂気を描き出している点に、本作の深みがあると感じます。
江戸川乱歩の描く世界観、特に都市の闇と人間の心の不思議に興味がある方には、ぜひ読んでいただきたい一作です。「目羅博士の不思議な犯罪」は、きっとあなたの心にも、忘れられない読書体験を刻むことでしょう。






































































