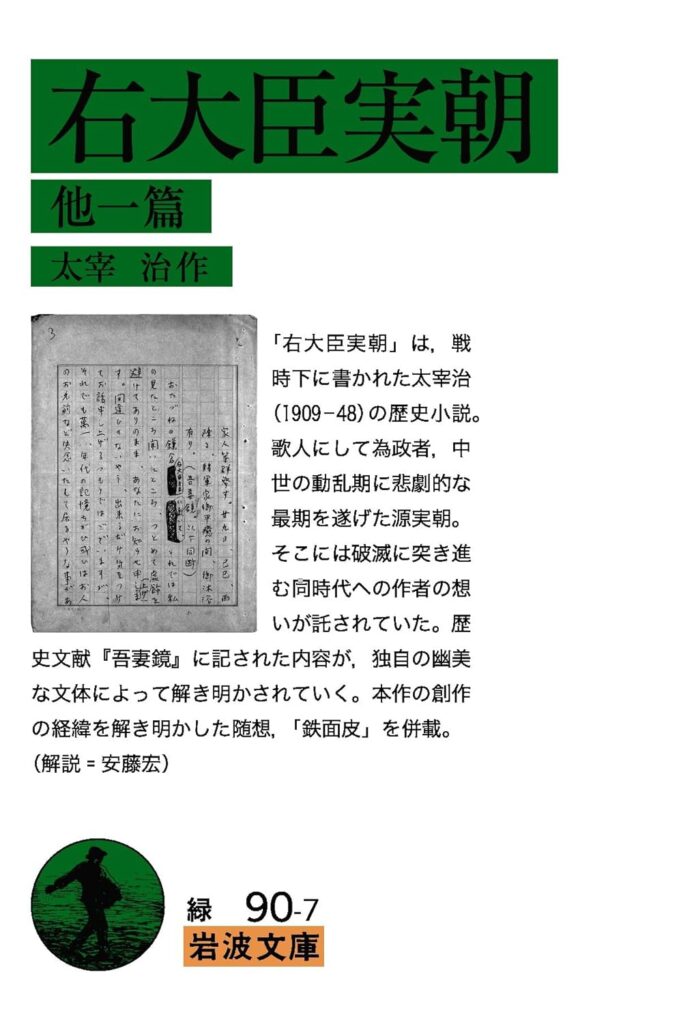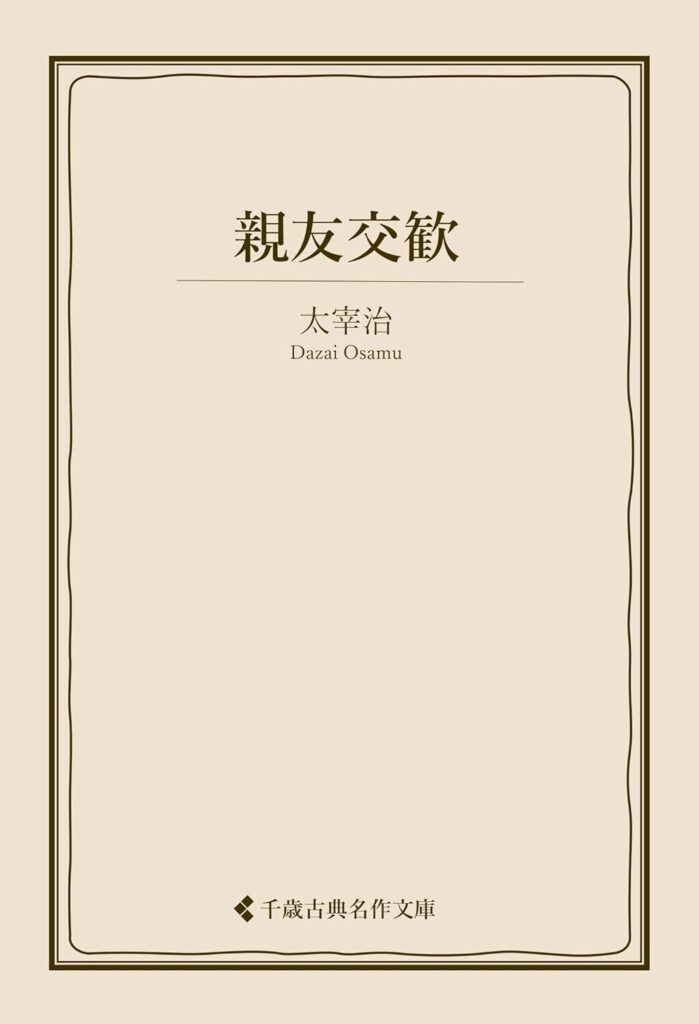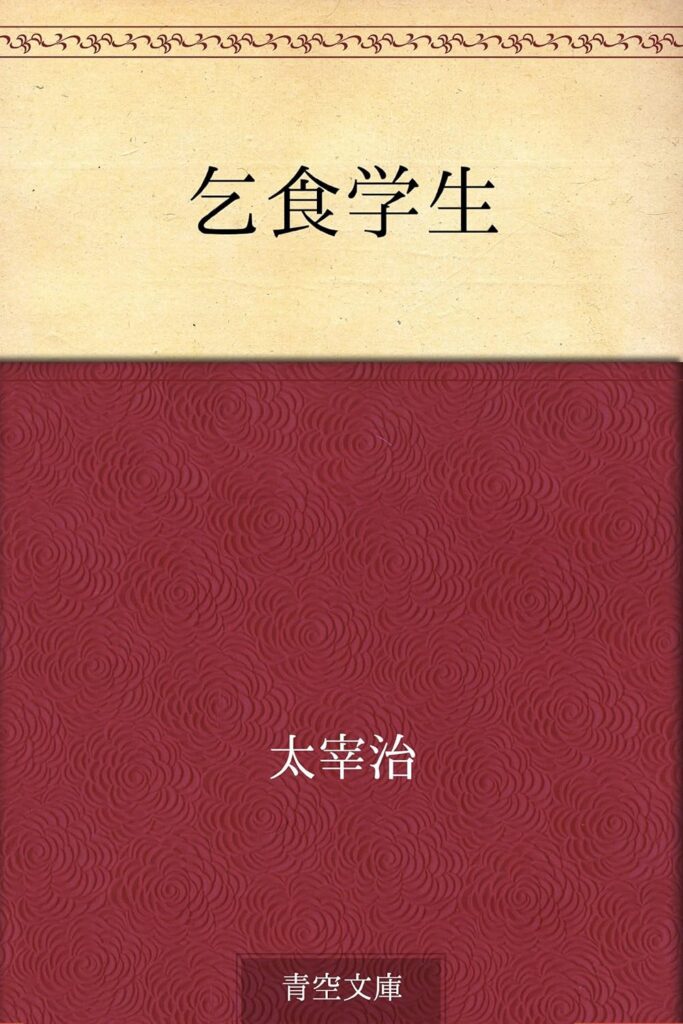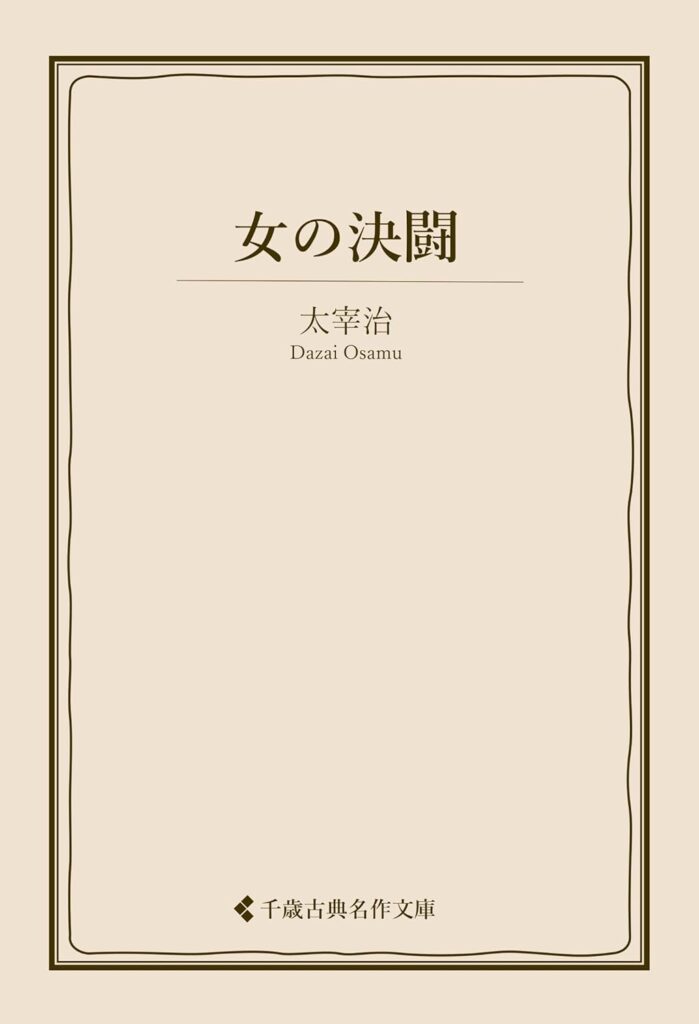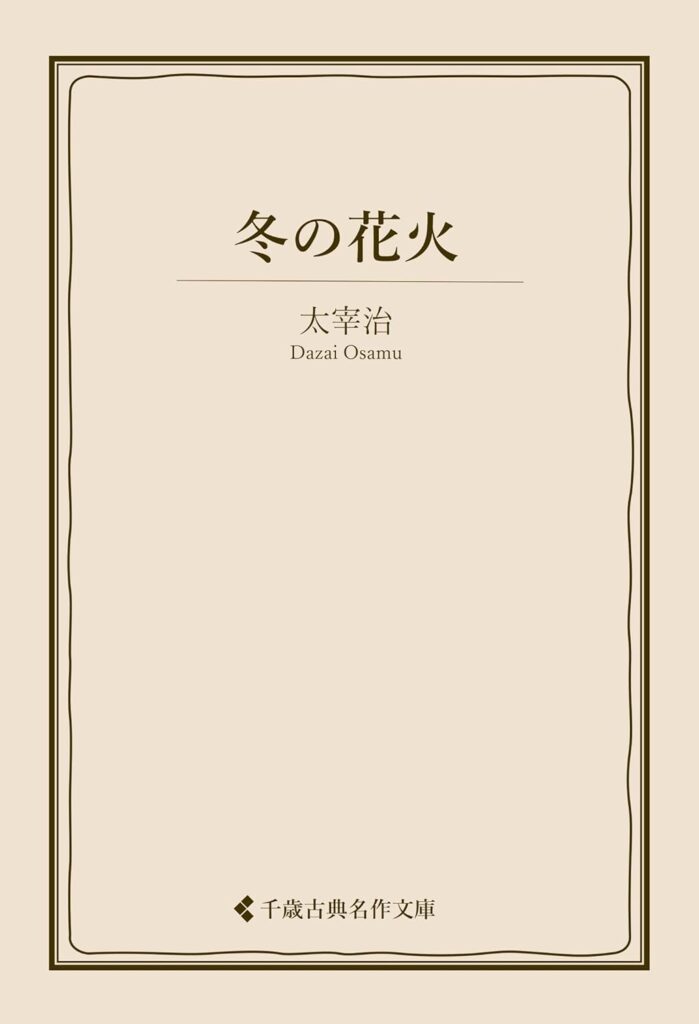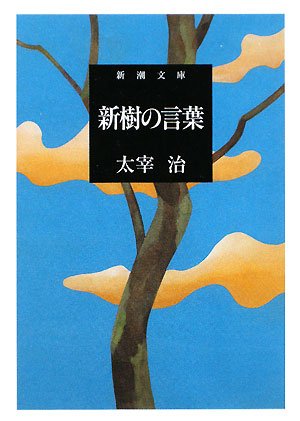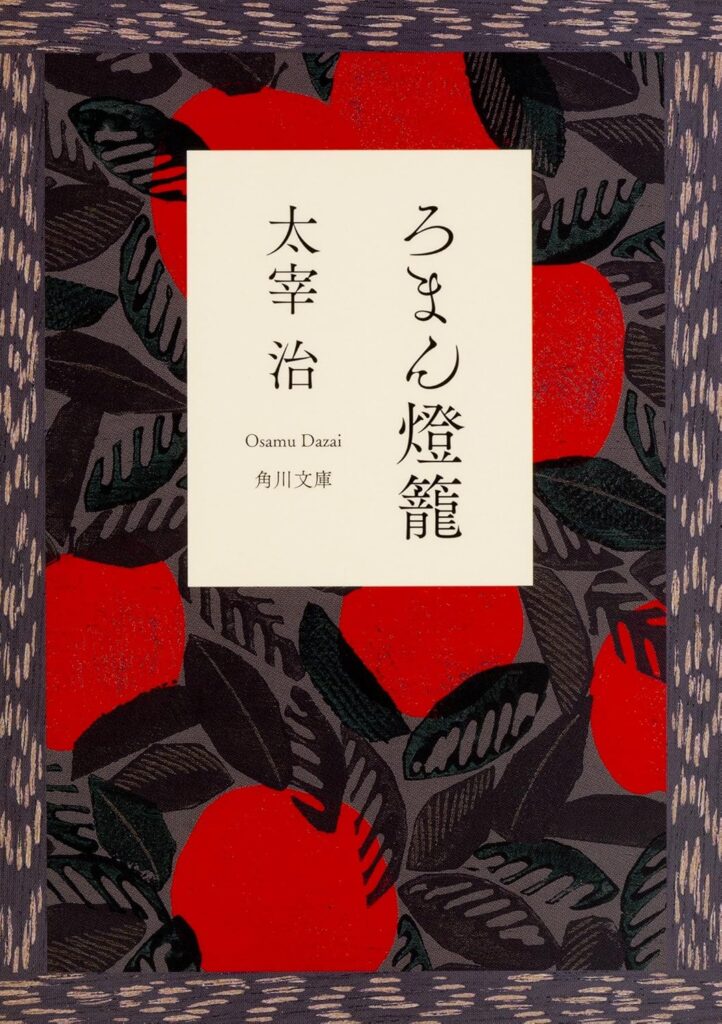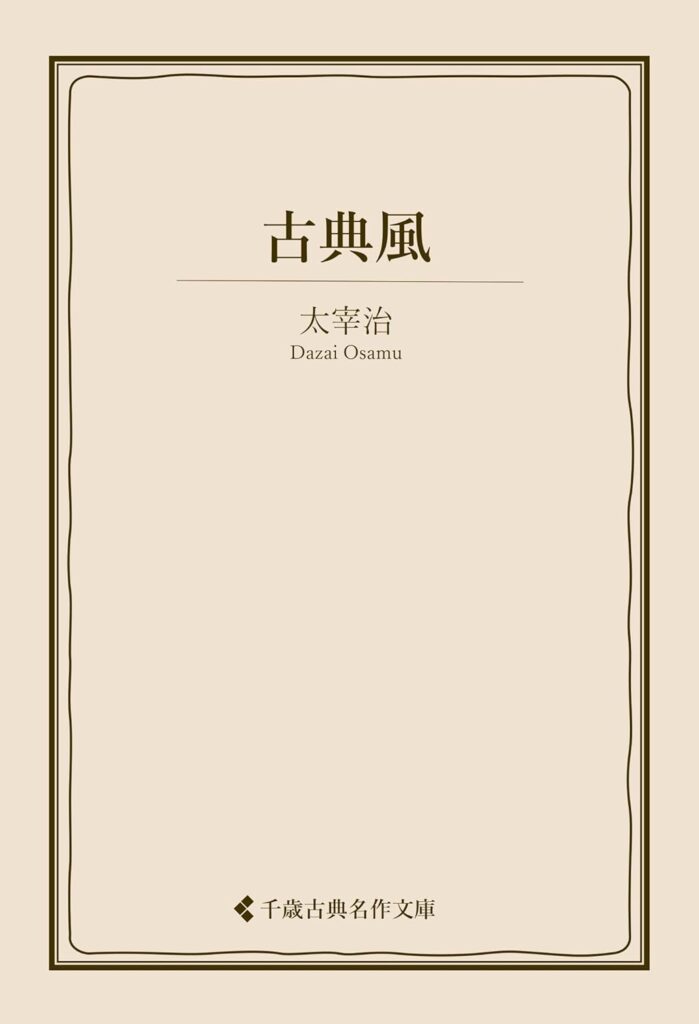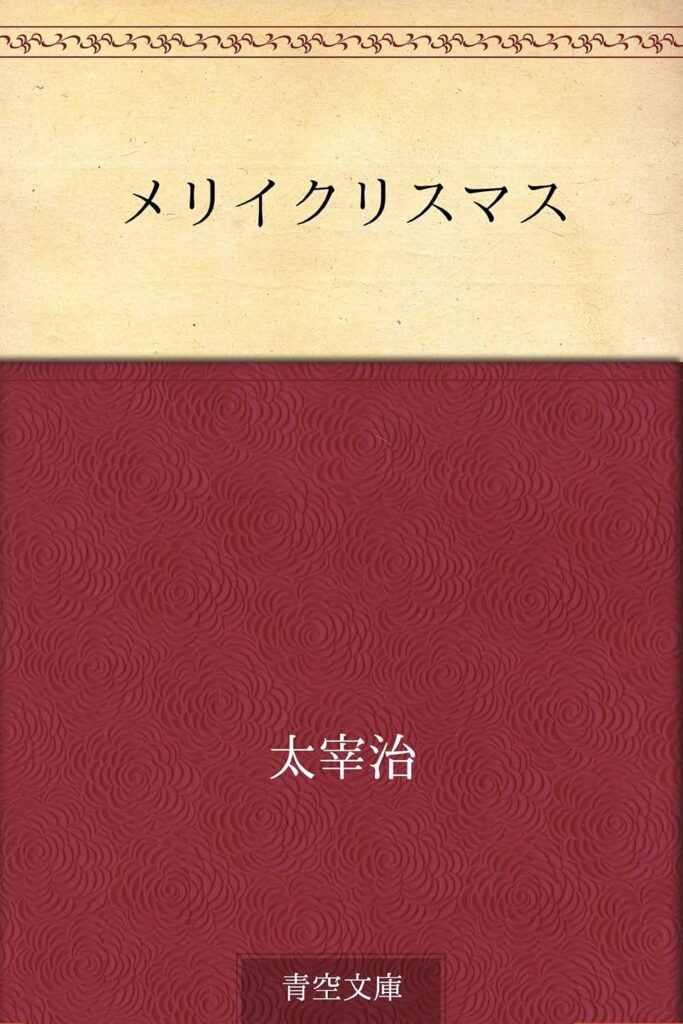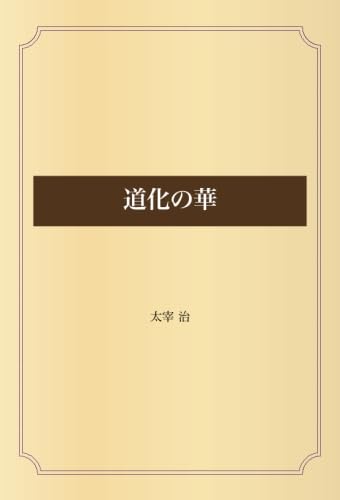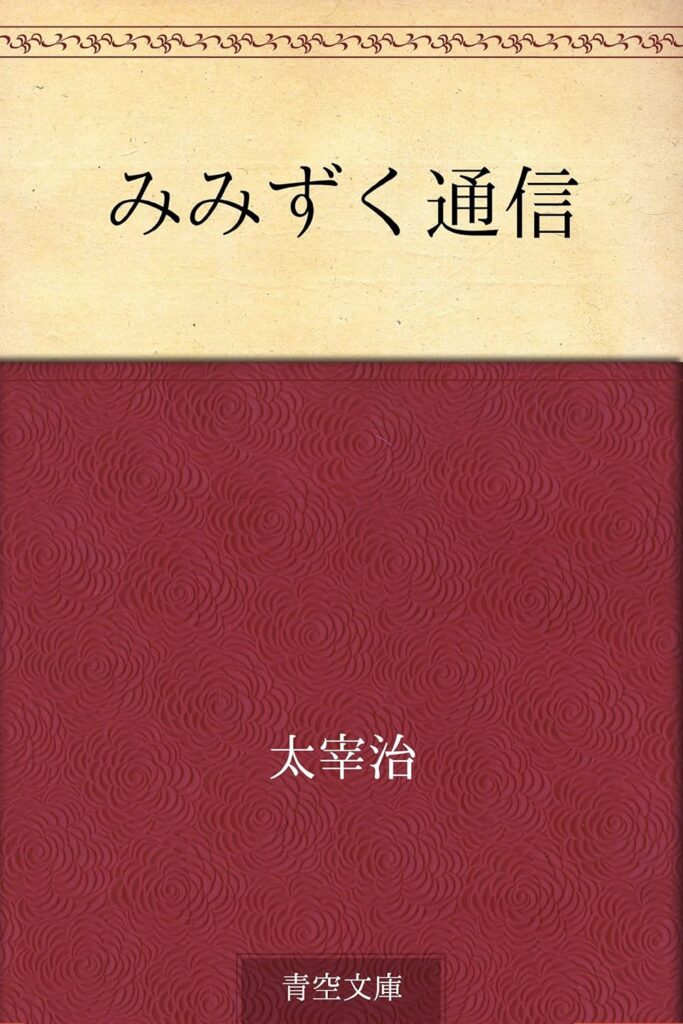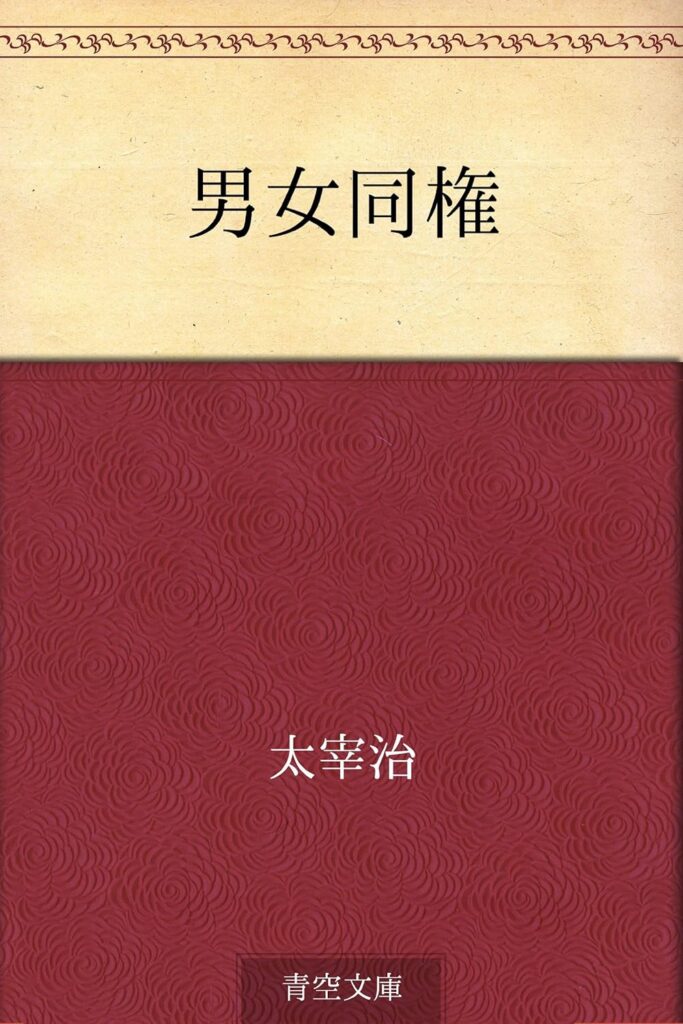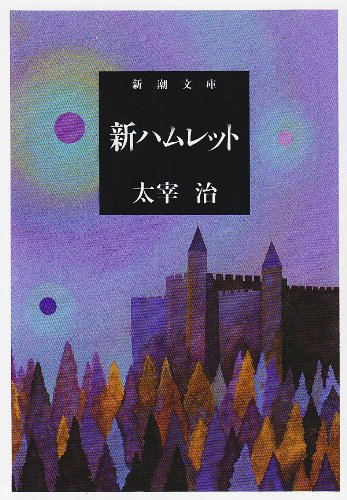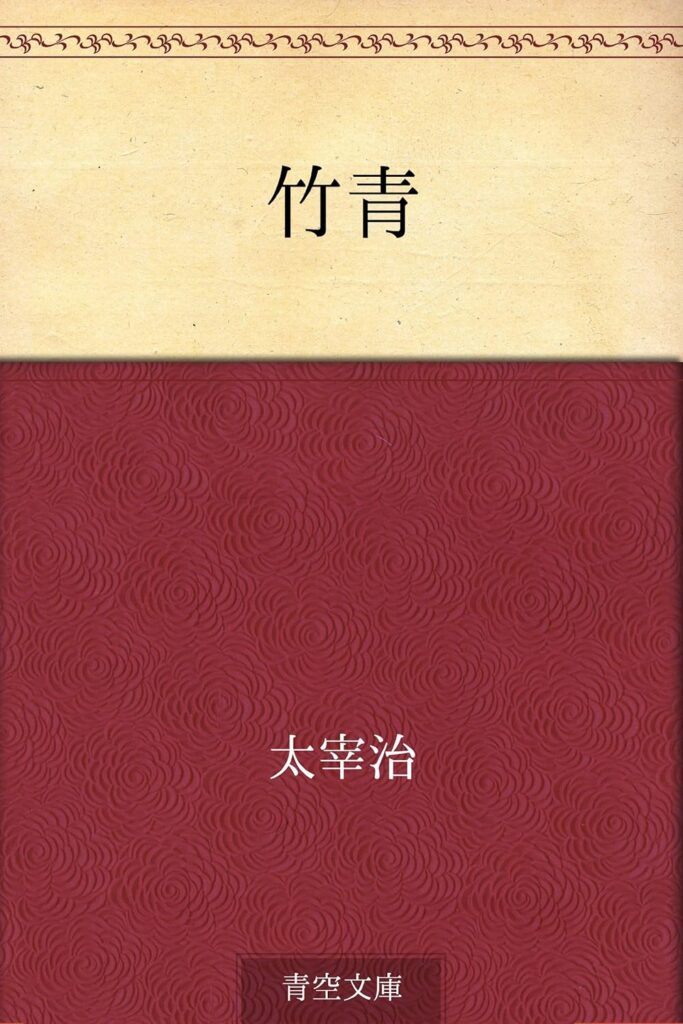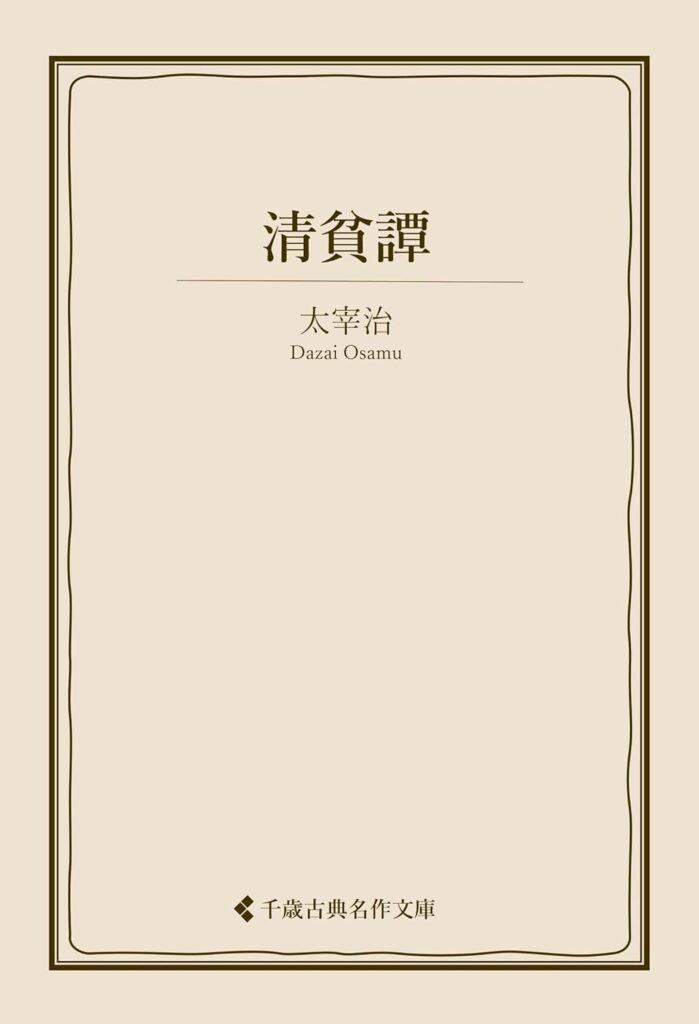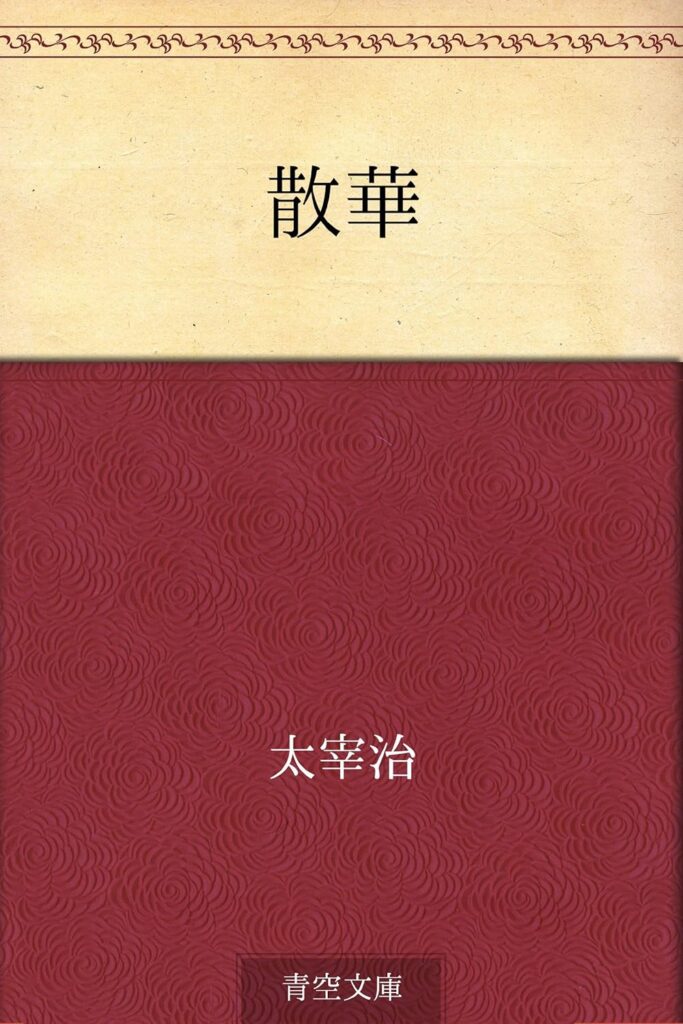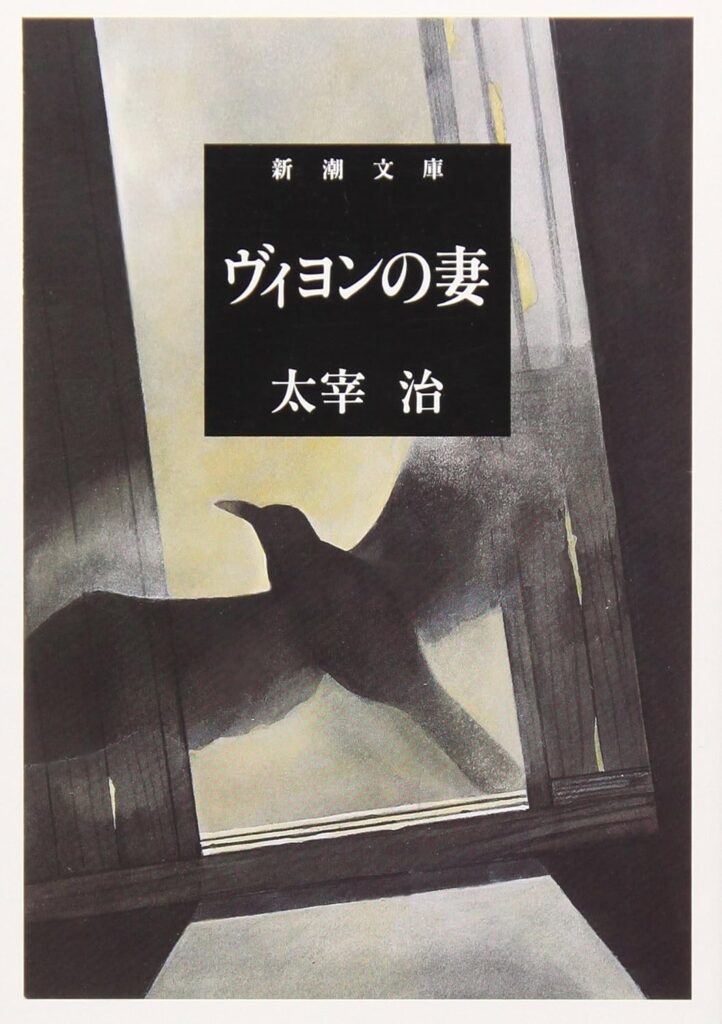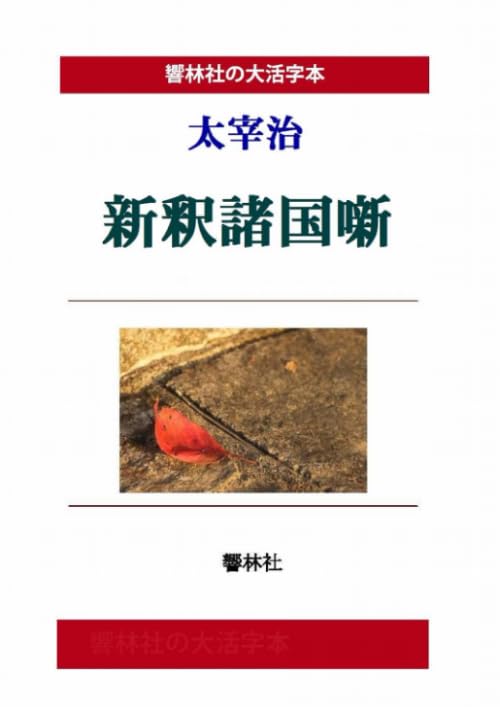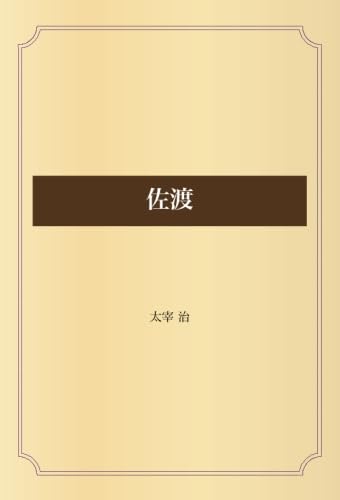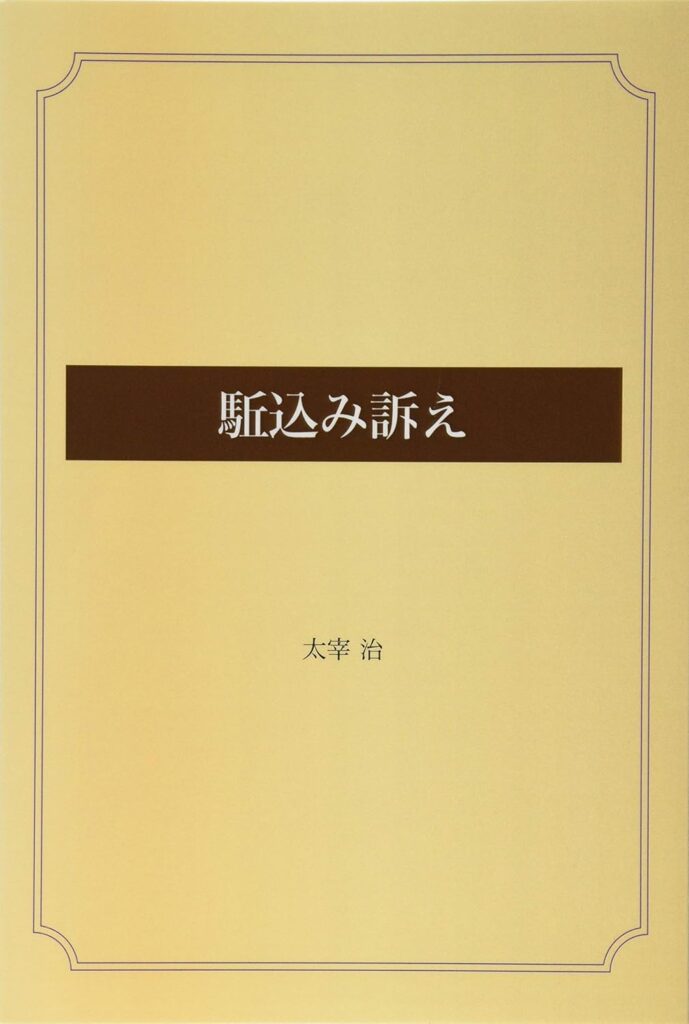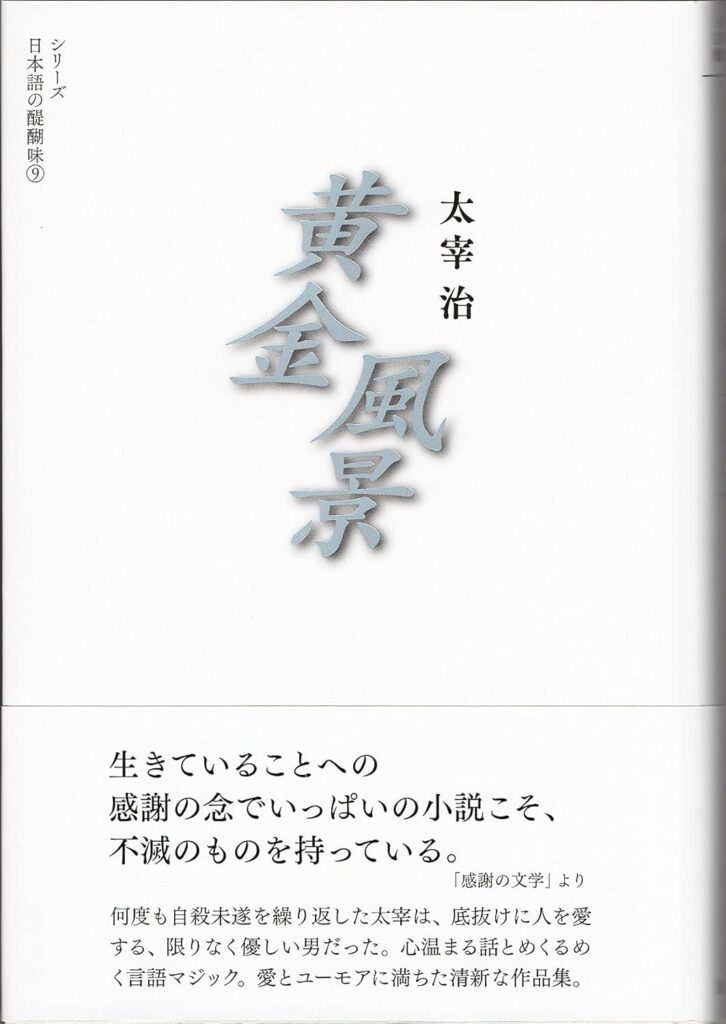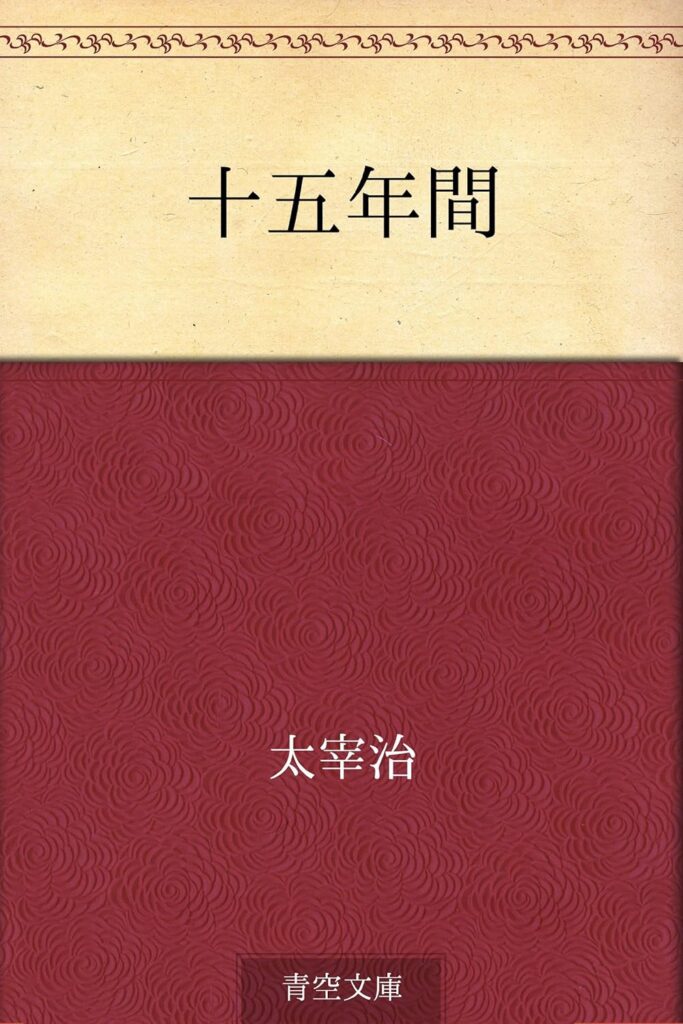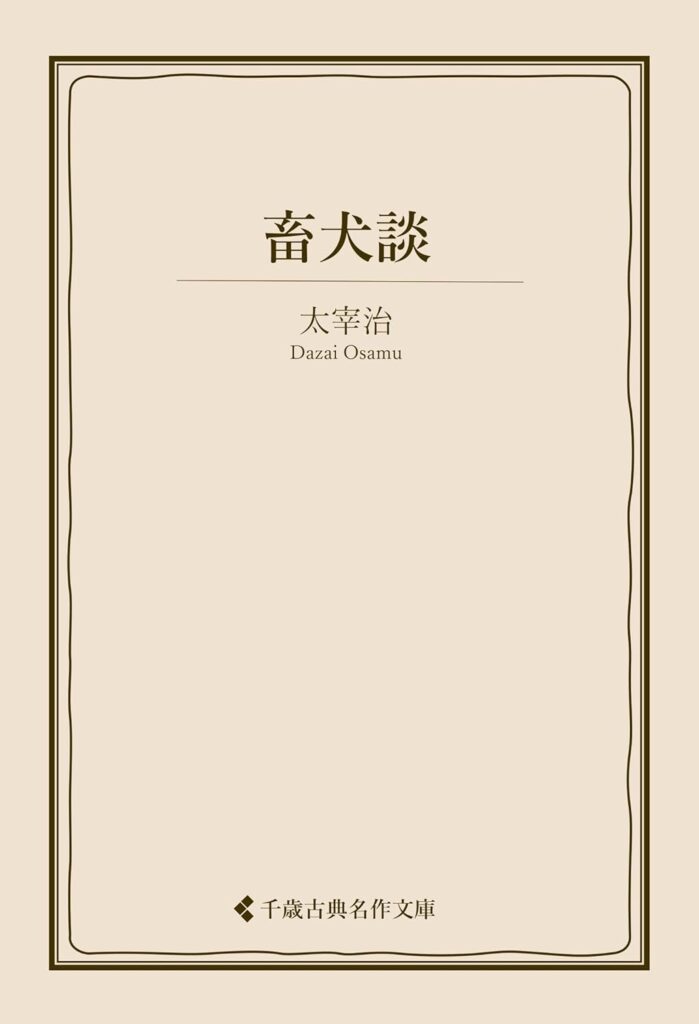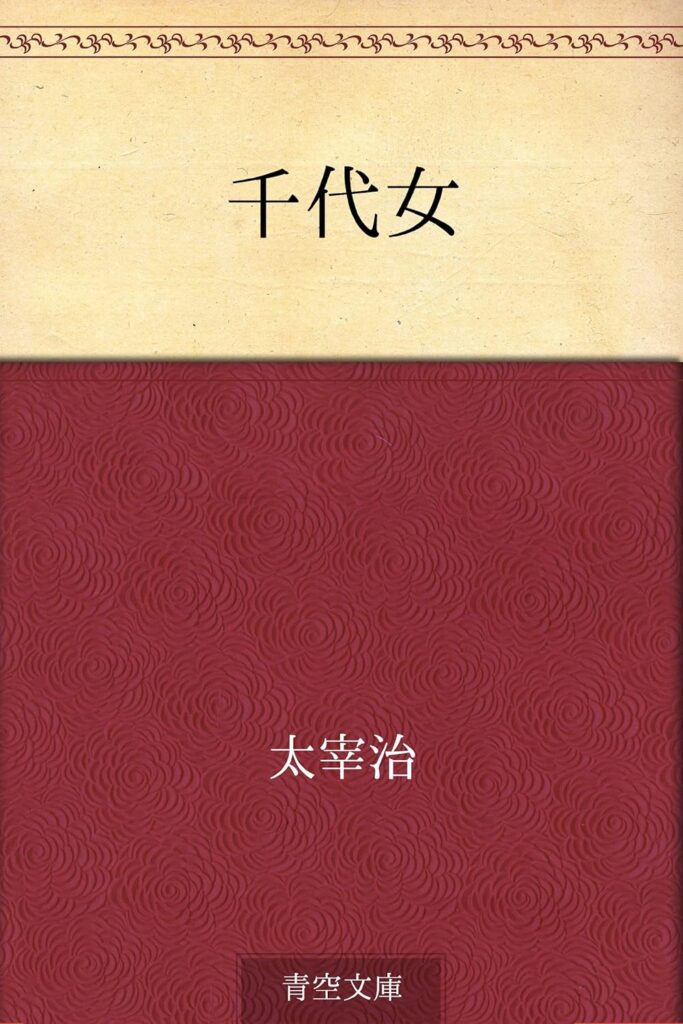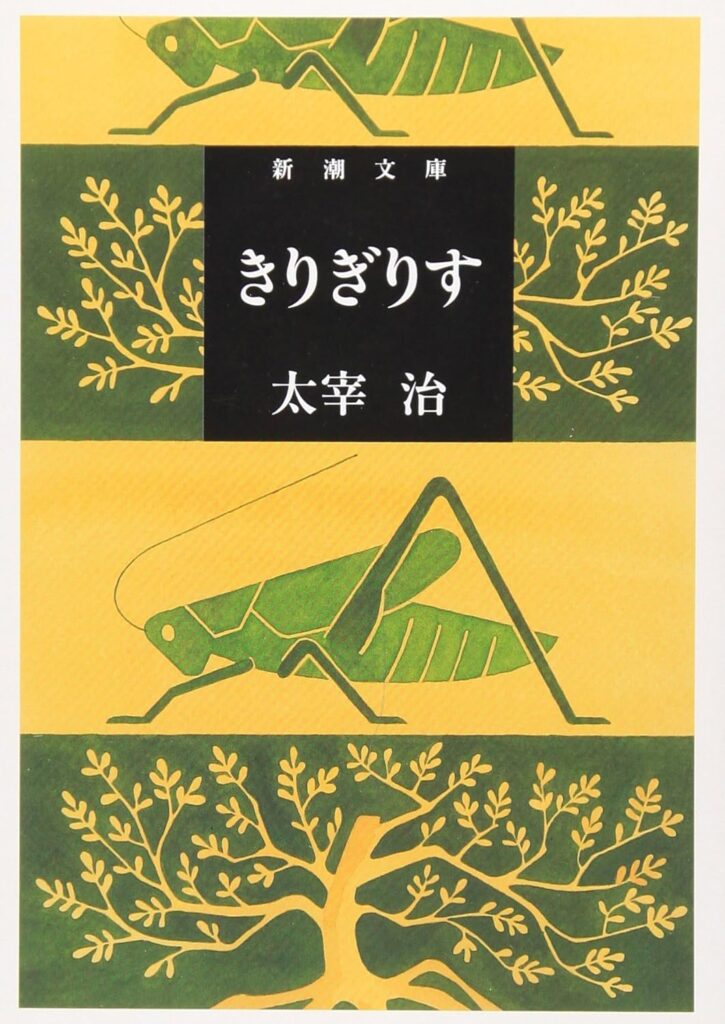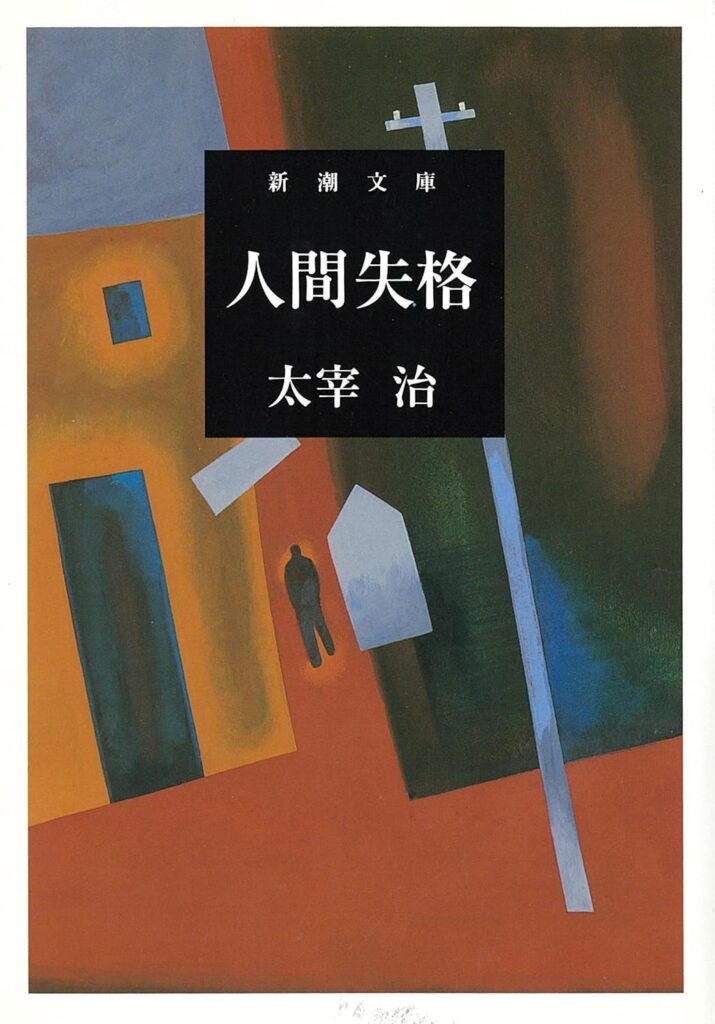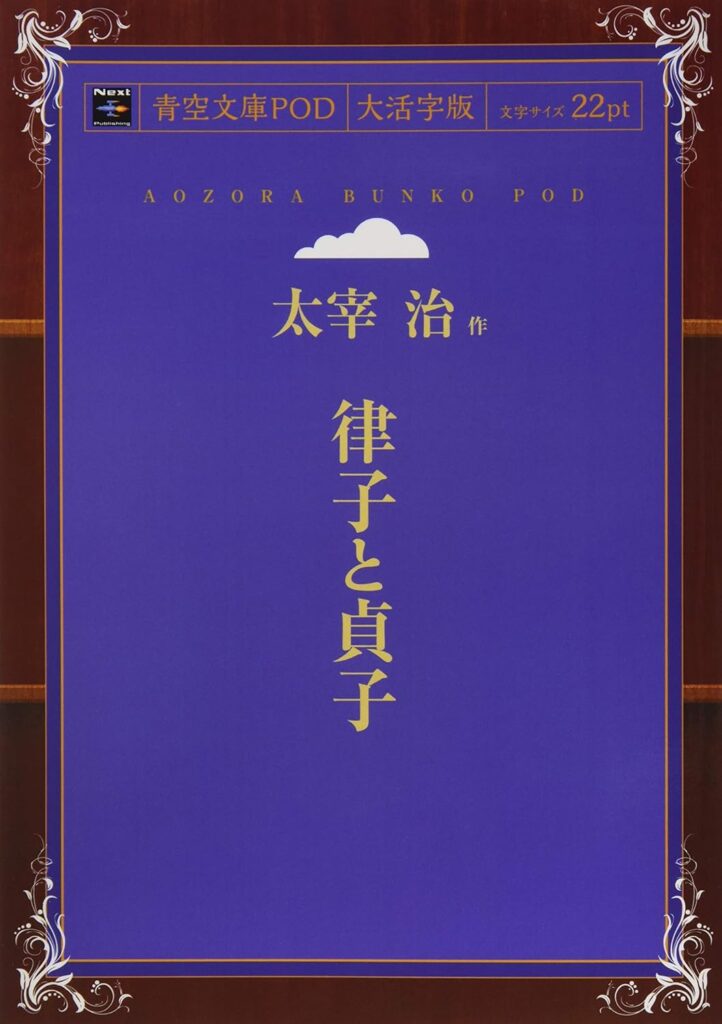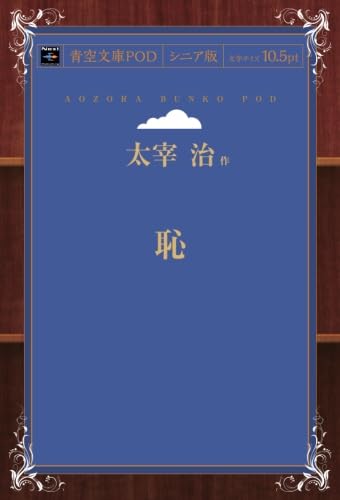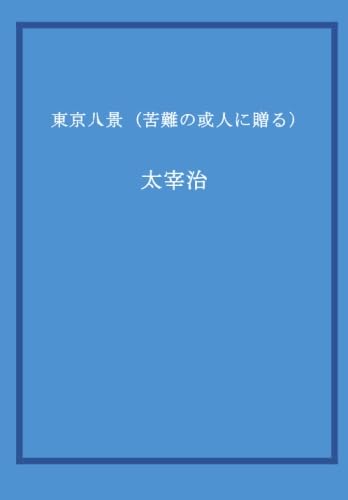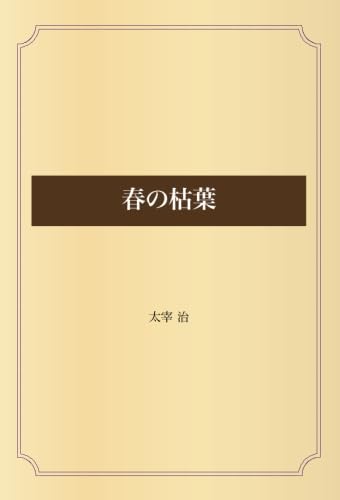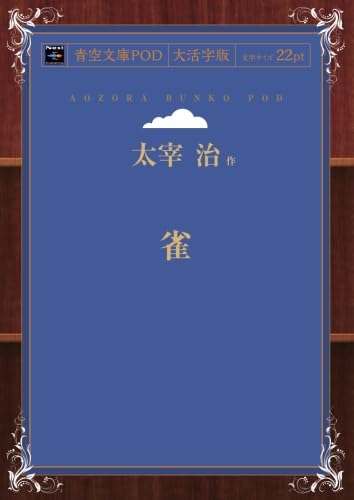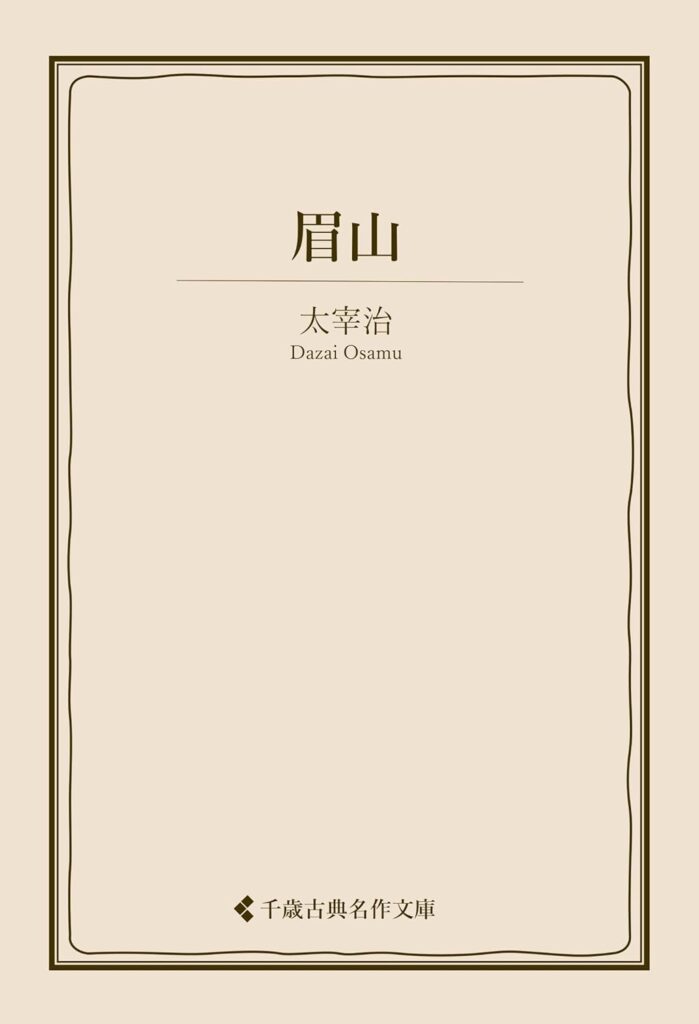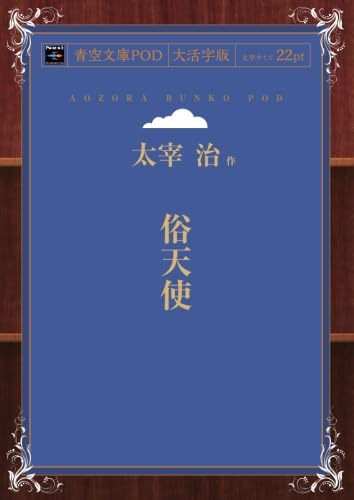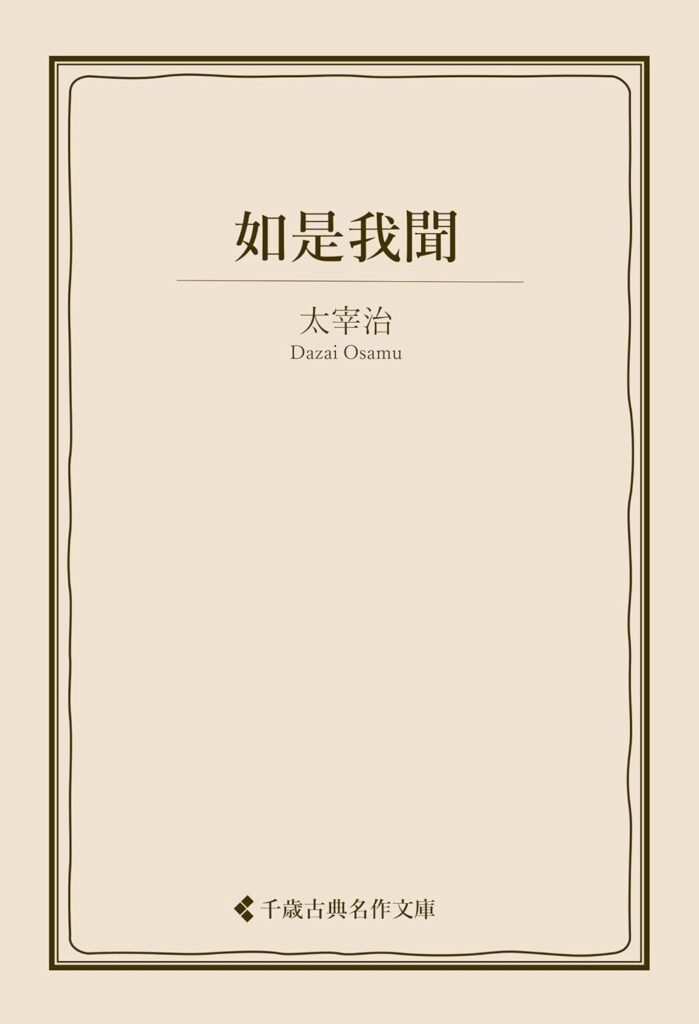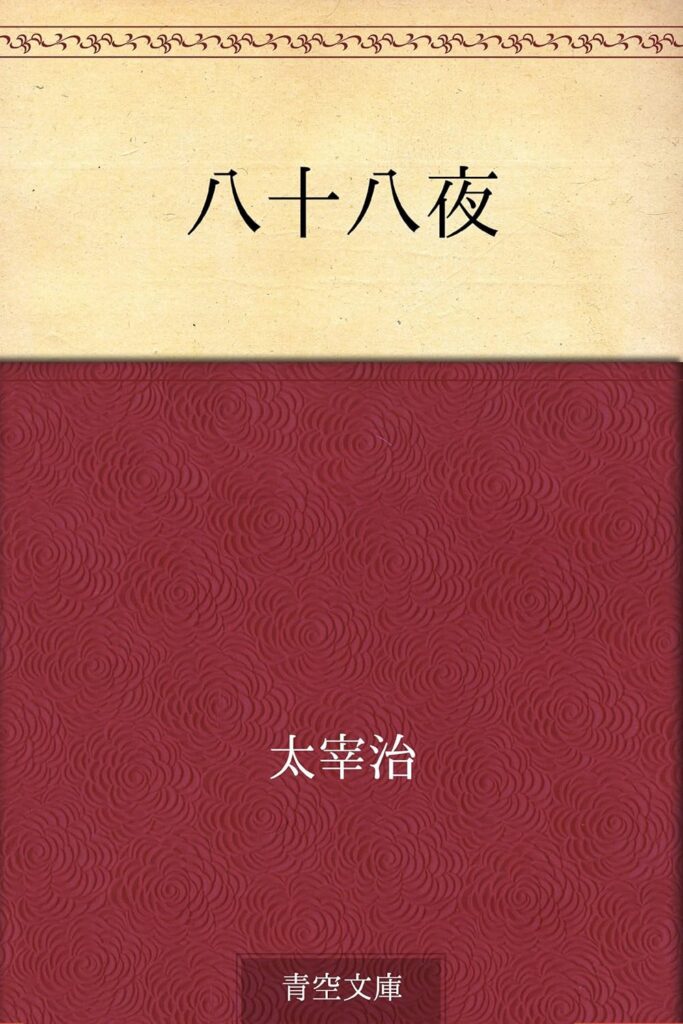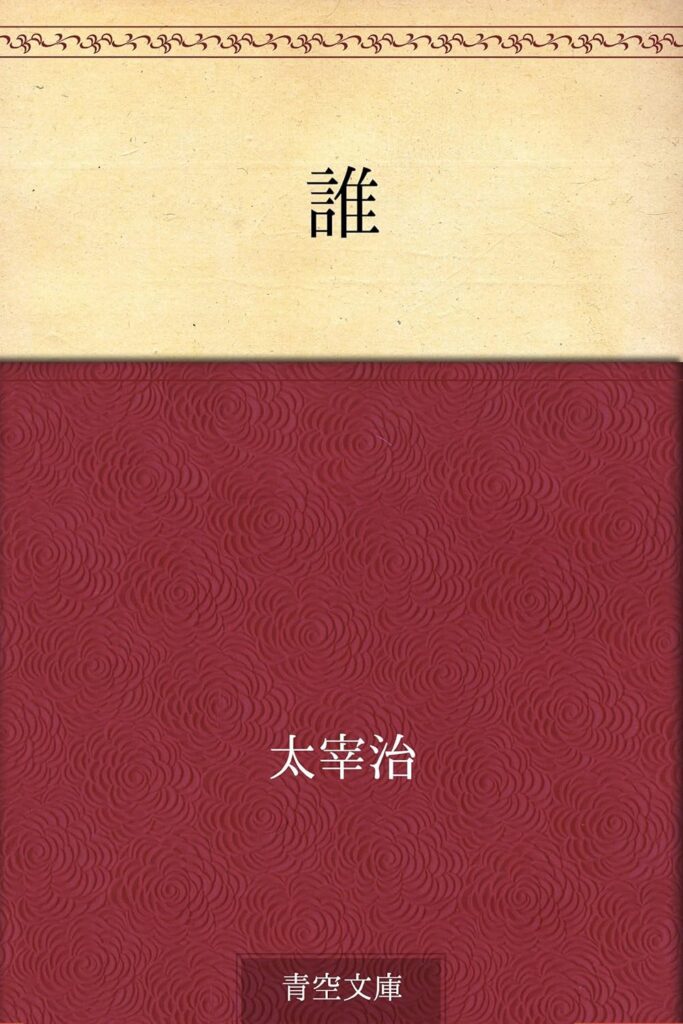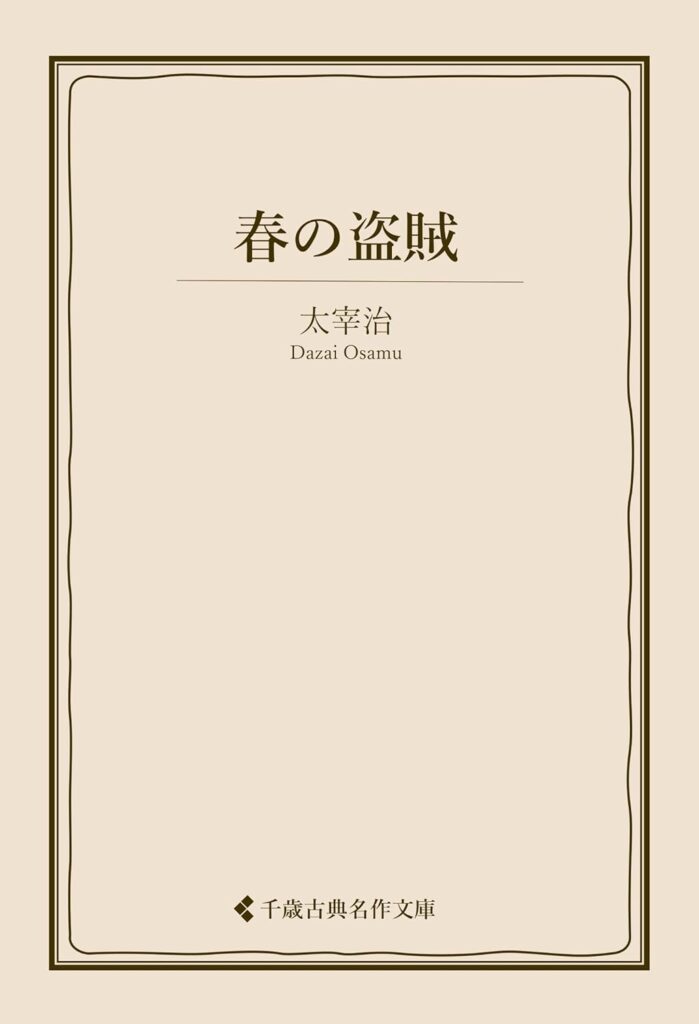小説「皮膚と心」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、太宰治が描く、ある夫婦の心の機微と、ささいな出来事がもたらす関係性の変化を捉えた物語です。読んでいると、登場人物たちの不安や喜びが、まるで自分のことのように感じられるかもしれません。
小説「皮膚と心」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、太宰治が描く、ある夫婦の心の機微と、ささいな出来事がもたらす関係性の変化を捉えた物語です。読んでいると、登場人物たちの不安や喜びが、まるで自分のことのように感じられるかもしれません。
特に、主人公である妻の心情描写は、非常に細やかで、読む人の心に深く響くものがあります。日常のささいなコンプレックスや、夫婦間の微妙な距離感、そして予期せぬ出来事をきっかけに溢れ出す感情。これらが、太宰治ならではの筆致で描かれています。
この記事では、物語の結末まで触れながら、その内容を詳しくお伝えします。さらに、作品を読んで私が感じたこと、考えたことを、たっぷりと書き綴ってみました。もしかしたら、あなたもこの夫婦の物語に、どこか共感する部分を見つけるかもしれません。
これから「皮膚と心」の世界に触れる方も、すでに読まれた方も、この記事を通して、作品の持つ奥深さや登場人物たちの心の動きを、改めて味わっていただけたら嬉しいです。それでは、物語の核心に迫っていきましょう。
小説「皮膚と心」のあらすじ
物語の主人公は、28歳の「私」。少し前に、お見合いで7歳年上の「あの人」(旦那さん)と結婚しました。旦那さんはデザイナーとして成功していますが、学歴がないことに引け目を感じています。一方の「私」も、早くに父を亡くし、裕福とは言えない家庭で育ち、自身の容姿にも自信が持てず、結婚を諦めかけていたところでした。お互いにどこか自信を持てない二人は、夫婦仲は悪くないものの、どこかよそよそしく、心の底から打ち解けられない日々を送っていました。
そんな「私」の唯一の自慢は、きめ細やかで白い肌でした。決して美人ではないけれど、この肌のおかげで少しはましに見える、そう信じていました。しかしある日、銭湯で体を拭いていると、右の乳房の下に小さな赤い斑点を見つけます。最初は気にしていませんでしたが、家に帰って鏡を見ると、少し広がっているように見えました。
心配になって旦那さんに報告すると、彼は仕事の手を止め、患部をじっと見つめ、「痒くはないか」と心配そうに尋ねます。「私」が痒みはないと答えると、薬箱から塗り薬を取り出し、「蕁麻疹なら痒いはずだが」と言いながら丁寧に塗ってくれました。「うつらないかしら」と不安がる「私」に、「気にしちゃいけねえ」と応える旦那さんの静かな優しさに、「私」は少し心が軽くなるのを感じます。
翌朝、鏡を見ると、赤いブツブツは顔にまで広がっていました。唯一の自慢だった肌が、見るも無残な状態になってしまったことに、「私」は絶望します。こんな姿では旦那さんに見捨てられる、生きている価値もない、と死さえ考えてしまうほどでした。「どうだ、よくなったか」と部屋に入ってきた旦那さんに、本当のことを隠そうとしますが、思わず「うちへ帰ります」という言葉が口をついて出てしまいます。
旦那さんは少し戸惑いながらも、「ちょっと見せな」と言います。「私」が体の斑点を見せ、「こんなところにグリグリができて」と言った途端、抑えていた涙が堰を切ったように溢れ出してしまいます。まるで少女のように泣きじゃくる「私」を見て、旦那さんは「よし!お医者へ連れて行ってやる」と、今まで聞いたことのない力強い声で言いました。
その日、旦那さんは仕事を休み、有名な皮膚科へ連れて行ってくれることになりました。人に肌を見られたくないから電車は嫌だと言う「私」に、「分かってるさ」と明るく答え、タクシーを呼んでくれます。道中、「私」は旦那さんの頼もしさや優しさを改めて感じ、これまで意識しなかった旦那さんの前の奥さんのことが急に憎らしく思えたり、同時に、今自分が旦那さんの妻であることに満たされた気持ちになったりするのでした。病院に着き、診察の結果、赤い斑点の原因は食中毒によるものだと判明します。簡単な注射を打ってもらい、医師から「すぐ治りますよ」と言われ、二人は病院を後にします。太陽の下で自分の手を見ると、もう治っているような気がして、「うれしいか?」と尋ねる旦那さんの声に、「私」は少し恥ずかしく思うのでした。
小説「皮膚と心」の長文感想(ネタバレあり)
太宰治の「皮膚と心」を読むと、まず心惹かれるのは、その驚くほどリアルな心理描写です。特に、主人公である「私」の心の揺れ動きは、読んでいるこちらまで不安になったり、安堵したり、まるでジェットコースターに乗っているかのような感覚を覚えます。物語は、彼女の身体に現れた些細な変化、つまり皮膚の異変から始まりますが、それはすぐに彼女の「心」の問題へと深く繋がっていきます。
「私」は、自分の容姿に強いコンプレックスを抱えています。美人ではない、若くもない、そんな風に自分を捉えています。その中で唯一の拠り所であり、ささやかな自信の源だったのが「肌の綺麗さ」でした。その大切な部分が、ある日突然、赤い斑点によって脅かされるのです。この衝撃は、単なる肌荒れというレベルを超えて、彼女の存在そのものを揺るがすほどの出来事となります。「地獄絵を見たような気がして、すっとあたりが暗くなりました」という描写は、彼女の絶望の深さを物語っています。
この絶望感は、彼女が元々持っていた「集合体恐怖症」とも関連しているように描かれています。「虫食った葉」や「蜂の巣」を嫌い、ふりがなさえも「シラミみたい」と気持ち悪がる彼女にとって、自身の肌に現れたブツブツは、生理的な嫌悪感と、自己肯定感の崩壊が同時に襲ってくる、二重の苦しみだったのではないでしょうか。唯一の自慢が、最も嫌悪するものの姿に変貌してしまったのですから、そのショックは計り知れません。
そして、この肌の異変は、夫婦関係にも微妙な影を落とします。お互いに自信がなく、どこか遠慮がちな関係だった二人。旦那さんは学歴コンプレックスと離婚歴を気に病み、「私」は自分の容姿や家柄に引け目を感じています。普段は、旦那さんの前の奥さんのことなど考えないように努めていた「私」ですが、肌のトラブルで精神的に不安定になると、抑え込んでいた感情が噴出します。「だまされた!結婚詐欺」といった激しい言葉が浮かび、旦那さんの過去の女性に対する嫉妬心が、初めて生々しく湧き上がってくるのです。
これは、自分の「女としての価値」が、肌の異変によって著しく損なわれたと感じたからでしょう。美しい肌という最後の砦を失い、他の女性(特に、おそらくは美しいであろう前の奥さん)と比較して、自分は劣っているのではないか、という不安と劣等感に苛まれた結果だと思います。普段は心の奥底にしまい込んでいた黒い感情が、皮膚のトラブルという触媒によって、一気に表面化してしまったかのようです。このあたりの、状況によって揺れ動く不安定な感情の描写は、本当に見事だと感じます。
しかし、物語の転機となるのは、この絶望と混乱の中で見せる旦那さんの姿です。「私」が涙ながらに「うちへ帰ります」と言った時、そして堰を切ったように泣き出してしまった時、旦那さんはうろたえながらも、決して彼女を突き放しませんでした。それどころか、「よし。泣くな!お医者へ連れていってやる」と、普段の彼からは想像もできないような、力強く、きっぱりとした声で宣言するのです。この一言が、二人の関係性を変える大きなきっかけとなります。
普段は自信なさげで、どこか頼りなく見えた旦那さんが、妻の危機に際して見せたこの「男らしさ」。それは、「私」にとって、驚きであり、大きな安心感をもたらしたはずです。「お医者を、男と思っちゃいけねえ」という言葉も、彼の不器用ながらの優しさと配慮が感じられ、心温まる場面です。診察を受けることを恥じらう妻の気持ちを汲み取り、少しでもその不安を取り除こうとする。この一連の旦那さんの行動を通して、「私」は彼の深い愛情を改めて実感したのではないでしょうか。
病院へ向かう道中、「私」の心境は目まぐるしく変化します。人に肌を見られたくないという羞恥心、旦那さんへの感謝と愛情、前の奥さんへの嫉妬、そして現在の幸福感。これらの感情が入り混じりながらも、確実に旦那さんへの信頼と愛情が深まっていく様子が伝わってきます。「年甲斐もなく少女に戻った気持ち」になり、「初めて自分が描いていた夫婦になれた気がした」と感じる場面は、読んでいるこちらも、なんだか嬉しく、くすぐったい気持ちになります。よそよそしかった二人の間に、確かな心の繋がりが生まれた瞬間です。
結局、原因はただの食中毒で、深刻な病気ではなかったことが判明します。あっけない結末ではありますが、この一連の出来事は、「私」にとっても、そしておそらく旦那さんにとっても、非常に大きな意味を持つものでした。皮膚のトラブルという身体的な問題が、最終的には二人の心の壁を取り払い、より深い精神的な結びつきをもたらしたのです。「皮膚」と「心」は、まさに表裏一体であり、互いに影響し合っているのだということを、この物語は示唆しているように思います。
太宰治が男性でありながら、これほどまでに女性の繊細な心理、特にコンプレックスや不安、嫉妬といった感情をリアルに描き出せることには、いつも驚かされます。参考にした文章にもありましたが、太宰自身も容姿、特に顔の吹き出物を気にしていたというエピソードは興味深いです。もしかしたら、彼自身のコンプレックスや繊細さが、登場人物、特に女性主人公の心理描写に深みを与えているのかもしれません。彼の描く女性像は、時にヒステリックに見えたり、自意識過剰に感じられたりすることもありますが、それは決して女性を戯画化しているのではなく、人間誰しもが持つ弱さや揺らぎを、女性というフィルターを通して克明に描いているからではないでしょうか。
また、この物語の夫婦は、現代で言うところの「自己肯定感の低い」二人と言えるかもしれません。お互いに相手を思いやる気持ちはあるのに、自分に自信がないために素直に甘えたり、愛情を表現したりすることができない。そのもどかしさが、読んでいて切なく感じられます。しかし、予期せぬトラブルという非日常的な出来事が、彼らの日常に変化をもたらし、 repressed されていた感情を解放するきっかけとなりました。これは、お見合い結婚という、恋愛感情が後から育まれる可能性のある関係性だからこそ、よりドラマチックに描かれたのかもしれません。
コンプレックスというテーマについても考えさせられます。旦那さんの学歴や離婚歴、そして「私」の容姿や家柄。これらは、彼らが強く気に病んでいることですが、相手はそれらをほとんど気にしていない、あるいは受け入れています。この事実は、物語の終盤で「私」が旦那さんの優しさに触れる中で、より明確になっていきます。私たちは往々にして、自分の欠点や弱みを過大評価し、他人も同じようにそれを見ていると思い込みがちです。しかし、実際には、自分が気にしているほど周りは気にしていない、ということは多いのかもしれません。この物語は、そんなコンプレックスとの向き合い方についても、そっとヒントを与えてくれているように感じます。
太宰治の文章は、時に句読点が少なく、思考の流れをそのまま書き出したような、独特のリズムを持っています。この作品でも、特に「私」の心情が揺れ動く場面では、その文体が効果的に機能しています。不安や混乱、めまぐるしく変わる感情が、途切れることのない文章の流れによって、より生々しく、ダイレクトに伝わってくるのです。この独特の文体も、「皮膚と心」の魅力の一つと言えるでしょう。
この作品は、単なる夫婦の物語というだけでなく、人間の弱さ、コンプレックス、そしてそれを乗り越えて生まれる愛情や絆を描いた、普遍的なテーマを持つ物語だと思います。肌のトラブルという、誰にでも起こりうる(そして多くの人が気にする)出来事をきっかけに、心の奥底に隠された感情や、人間関係の本質が浮かび上がってくる。その展開は、読んでいて非常に引き込まれますし、読み終わった後には、登場人物たちのささやかな幸せに、温かい気持ちになります。太宰治の作品に暗いイメージを持っている人もいるかもしれませんが、「皮膚と心」は、そんなイメージを覆すような、人間味あふれる優しい眼差しを感じられる作品ではないでしょうか。
まとめ
太宰治の小説「皮膚と心」は、ある夫婦の日常と、ささいな出来事がきっかけで起こる心の変化を描いた物語です。主人公の「私」が、唯一の自慢だった肌にできた赤い斑点に絶望するところから話は始まります。この皮膚のトラブルは、彼女のコンプレックスや、旦那さんとの間の微妙な距離感を浮き彫りにしていきます。
物語の核心は、この出来事を通して、普段は自信なさげな旦那さんが見せる意外な頼もしさと優しさ、そしてそれによって「私」の心が解き放たれ、二人の関係性が深まっていく過程にあります。肌の異変という身体的な問題が、結果的に夫婦の精神的な絆を強める触媒となるのです。太宰治特有の繊細な心理描写が光り、特に女性の心の揺れ動きがリアルに描かれています。
結局、斑点の原因は深刻なものではなく、物語は穏やかな結末を迎えます。しかし、この一連の出来事は、登場人物たちにとって大きな意味を持つものでした。コンプレックスとの向き合い方や、夫婦間のコミュニケーション、そして人間の弱さとそれを支える愛情について、深く考えさせられる作品です。
もし、太宰治の作品に少しでも興味があるなら、あるいは、人間の心の機微に触れる物語を読みたいと思っているなら、「皮膚と心」はぜひ手に取っていただきたい一冊です。読み終わった後、きっと温かい気持ちになれるはずですよ。