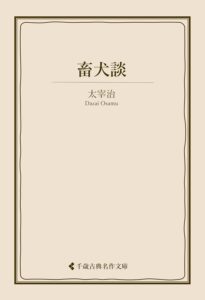 小説「畜犬談」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治というと、どうしても暗いイメージや破滅的な生き方を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、彼の作品の中には、思わずクスッと笑ってしまうような、おかしみに満ちたものも少なくないのです。
小説「畜犬談」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治というと、どうしても暗いイメージや破滅的な生き方を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、彼の作品の中には、思わずクスッと笑ってしまうような、おかしみに満ちたものも少なくないのです。
この「畜犬談」は、まさにそんな太宰治の別の一面を垣間見ることができる短編小説です。主人公の「私」は、とにかく犬が怖い。どれくらい怖いかというと、道を歩いていて犬に出会おうものなら、全身がこわばり、冷や汗が止まらなくなるほど。その恐怖心たるや、尋常ではありません。
そんな「私」が、犬を避けようと涙ぐましい努力をするのですが、なぜかことごとく裏目に出てしまい、逆に犬たちに好かれてしまうという、なんとも皮肉な物語が展開されます。この導入部だけでも、太宰治らしい独特の筆致と、人間のどうしようもない性(さが)のようなものが描かれていて、引き込まれてしまいます。
この記事では、そんな「畜犬談」の物語の詳しい流れ、結末に至るまでの展開を追いかけ、さらに私なりの深い読み解きや感じたことを詳しくお伝えしていこうと思います。太宰作品の入門としても、あるいは少し変わった読書体験を求めている方にも、おすすめできる一作ですよ。
小説「畜犬談」のあらすじ
物語の語り手である「私」は、極度の犬嫌いです。その原因は、友人が犬に噛まれて狂犬病の治療で大変な思いをした経験を間近で見たことにあります。「私」は犬を「猛獣」と断じ、いつか自分も噛まれるに違いないという確信に近い恐怖心を抱いています。街を歩くにも、犬との遭遇を避けるため、神経をすり減らす毎日を送っているのでした。
ある時、「私」は執筆に集中するため、山梨の町外れに部屋を借ります。しかし、その周辺は犬が多く、平穏な日々は望めそうにありません。「私」は犬に敵意がないことを示すため、奇妙な対策を講じます。犬に出会うと満面の笑みを浮かべ、夜道では無邪気な童謡を歌い、怪しまれないように髪を短く整え、威嚇していると誤解されかねないステッキすら捨ててしまうのです。
ところが、これらの涙ぐましい努力は完全に逆効果でした。犬たちは「私」の態度を好意の表れと勘違いし、むしろ積極的に近寄ってくるようになります。散歩に出れば、どこからともなく犬たちが現れ、尻尾を振ってぞろぞろと後をついてくる始末。「私」の犬への恐怖心は募るばかりです。
そんなある日、一匹の痩せた黒い子犬が「私」の家の玄関先に現れます。噛まれることを恐れた「私」は、またしても「軟弱外交」を展開。お菓子や水を与えて機嫌を取ろうとします。すると、その子犬はすっかり懐いてしまい、家に居着いてしまいます。「私」は渋々、その犬を「ポチ」と名付けて面倒を見ることにしたのでした。
ポチは「私」によく懐き、どこへ行くにもついて回ります。家の中を汚したり、洗濯物を噛みちぎったりと、やんちゃな面も見せますが、「私」は犬への恐怖心から強く叱ることもできません。そんな奇妙な同居生活が続く中、「私」は東京の三鷹に新しい家を見つけ、引っ越しを決意します。犬嫌いの「私」にとって、ポチと離れられることは大きな喜びでした。
しかし、引っ越しを間近に控えたある日、ポチはひどい皮膚病にかかり、悪臭を放つようになります。最初はポチを可愛がっていたはずの妻が、「ご近所に迷惑だから殺してください」と冷たく言い放ちます。あれほど犬を嫌っていた「私」ですが、いざ殺すとなると躊躇いを覚えます。しかし、ポチの状態は悪化する一方で、ついに「私」は毒殺を決意。薬を仕込んだ牛肉を用意し、最後の散歩へとポチを連れ出すのでした。
小説「畜犬談」の長文感想(ネタバレあり)
「畜犬談」、この作品を読むたびに、私は太宰治という作家の持つ、一筋縄ではいかない魅力に引き込まれてしまいます。冒頭の「私は、犬については自信がある。いつの日か、かならず喰いつかれるであろうという自信である。」という一文からして、もう尋常ではありませんよね。犬に噛まれることへの「自信」。この倒錯したような、しかし妙に真剣味のこもった告白に、まず心を掴まれます。
主人公の「私」が抱く犬への恐怖は、病的と言ってもいいほどです。友人の体験談がきっかけとはいえ、その恐怖心の描写は徹底しています。「諸君、犬は猛獣である。」と読者にまで呼びかける始末。この過剰さが、まず最初の笑いを誘うポイントでしょう。大の大人が、本気で犬におびえ、その対策に真剣に取り組む姿は、滑稽でありながら、どこか哀愁も漂わせています。
山梨での犬避け作戦は、その滑稽さの頂点かもしれません。満面の笑み、童謡、身だしなみへの配慮、ステッキの放棄。これらはすべて、犬に嫌われ、避けられるための努力のはずでした。しかし、結果は真逆。犬たちは彼を「優しい人」と認識し、むしろ慕ってくるようになる。この皮肉な展開は、人間の意図や努力が、必ずしも望んだ結果に結びつくわけではない、という人生の普遍的なおかしさを描いているようにも思えます。
そして現れるのが、黒い子犬、ポチです。ここでも「私」は、噛まれたくない一心で「軟弱外交」に徹します。お菓子を与え、水を与え、丁重にもてなす。その結果、ポチはまんまと居着いてしまう。嫌で嫌で仕方がないはずなのに、自らの行動が原因で、最も恐れる存在を身近に引き寄せてしまう。このあたりの展開は、本当に見事としか言いようがありません。
ポチとの同居生活の描写も、味わい深いです。「私」はポチを嫌っています。その理由は、単に犬が怖いからだけではありません。ポチの不格好さ(胴長短足で亀のようだと描写されています)を恥じ、散歩中に笑われることにプライドが傷つく。ポチが他の犬と喧嘩っ早いのも気に入らない。しかし、そんなポチが悪さをしても、強く叱れない。ここには、「私」の臆病さや見栄っ張りな性格がよく表れています。
さらに興味深いのは、「私」がポチの振る舞いの中に、自分自身の嫌な部分を見出すようになる点です。他の犬に吠えられても、喧嘩を避けて「私」におべっかを使うようになったポチを見て、「私」は「顔色を伺っている嫌な奴として飼い主である自分に似てきた」と感じ、ますます嫌悪感を募らせます。ポチは、いつしか「私」にとって、自身の弱さや卑屈さを映し出す鏡のような存在になっていくのです。これは、太宰作品にしばしば見られる自己嫌悪のテーマとも重なります。
物語が大きく動くのは、ポチの皮膚病と、妻からの「殺してください」という衝撃的な一言です。あれほど犬嫌いを公言していた「私」が、いざポチの死を具体的に突きつけられると、動揺し、躊躇する。「殺すのか」という彼の言葉には、単なる驚きだけでなく、どこかポチへの情のようなものが芽生え始めていたことをうかがわせます。しかし、状況は彼に決断を迫ります。
毒殺を決意し、薬を仕込んだ牛肉を持ってポチを散歩に連れ出す場面は、この物語のクライマックスの一つでしょう。死地に赴くとも知らず、喜び勇んでついてくるポチの無邪気さが、哀れを誘います。道中、赤犬に喧嘩を売られるポチ。以前なら蔑んでいたであろうその場面で、「私」は意外な行動に出ます。「赤犬は卑怯だ!思う存分やれ!」とポチをけしかけ、その戦いを固唾をのんで見守り、勝利を「よし!強いぞ。」と褒めるのです。
この瞬間、「私」の中で何かが変わったのではないでしょうか。犬嫌いの「私」ではなく、共に困難に立ち向かう(たとえ相手が犬であっても)共感者としての意識が芽生えたのかもしれません。あるいは、これからポチを殺そうとしている罪悪感が、一時的にポチへの強い肩入れという形で表れたのかもしれません。いずれにせよ、ここでの「私」とポチの間には、これまでとは質の違う結びつきが生まれているように感じられます。
そして、毒入りの牛肉をポチに与える場面。しかし、ポチは死ななかった。薬が効かなかったのか、量が足りなかったのか。理由は定かではありませんが、この「死ななかった」という事実が、「私」の心を決定的に変えることになります。死の淵から生還した(結果的にそうなった)ポチを見て、「私」は妻にこう宣言します。
「だめだよ。薬が効かないのだ。ゆるしてやろうよ。あいつには、罪がなかったんだぜ。芸術家は、もともと弱い者の味方だったはずなんだ」「弱者の友なんだ。芸術家にとって、これが出発で、また最高の目的なんだ。こんな単純なこと、僕は忘れていた。僕だけじゃない。みんなが、忘れているんだ。僕は、ポチを東京へ連れてゆこうと思うよ。」
この最後の独白は、「畜犬談」という作品を、単なる犬嫌いの男の滑稽譚から、より深いテーマ性を持つ物語へと昇華させています。「芸術家は弱い者の味方であるべきだ」という言葉。ここでいう「弱い者」とは、単に皮膚病でみすぼらしくなったポチだけを指すのではないでしょう。社会の中で虐げられたり、疎外されたりしている人々、貧しい人々、病を持つ人々、そういった存在すべてを包含しているように思えます。
「私」は、ポチを生かすことを決意すると同時に、芸術家としての自身の原点、あるいは使命のようなものに立ち返ろうとしているのです。それは、太宰治自身の文学に対する姿勢表明とも受け取れます。太宰の作品には、社会の片隅で生きる人々や、破滅的な生き方を選ばざるを得なかった人々への、温かいとは言えないまでも、どこか共感的な視線が感じられることが多くあります。この「畜犬談」の結びは、そうした太宰文学の根底にある思想を、比較的ストレートに表現しているのかもしれません。
もちろん、この結びを額面通りに受け取るべきか、という議論もあるでしょう。最後の妻の「浮かぬ顔」という描写は、どこか現実の厳しさや、理想だけではいかない日常を暗示しているようにも読めます。ポチを東京に連れて行ったとして、本当にうまくやっていけるのか。芸術家の理想と現実は、そう簡単には一致しないのかもしれません。それでも、「弱い者の味方」であろうと決意した「私」の姿は、どこか清々しく、読後にある種の希望のようなものを感じさせてくれます。
この作品の魅力は、そうしたテーマ性だけでなく、やはり太宰治ならではの文章表現にもあります。「私」のモノローグは、時に大げさで、時に自嘲的で、常に読者を引きつけるリズムと熱量を持っています。深刻な場面であっても、どこかおかしみがつきまとう。この絶妙なバランス感覚が、「畜犬談」を何度読んでも飽きさせない理由なのだと思います。
まとめ
「畜犬談」は、太宰治の作品の中でも、特に読みやすく、親しみやすい短編の一つと言えるでしょう。極度の犬嫌いである主人公「私」が、犬を避けようとすればするほど、逆に犬に好かれてしまうという皮肉な状況設定が、まず読者の興味を引きます。そのおかしみに満ちた展開は、太宰治の持つ軽妙な筆致と相まって、私たちを楽しませてくれます。
物語は、単なる滑稽譚にとどまりません。主人公が嫌々ながら飼うことになった犬「ポチ」との関係を通して、人間の持つ見栄や弱さ、自己嫌悪といった複雑な感情が巧みに描かれています。特に、ポチの中に自分自身の嫌な部分を見出してしまう描写は、深く考えさせられるものがあります。
そしてクライマックス、ポチの毒殺未遂とその後の心境の変化は、この物語にさらなる深みを与えています。「芸術家は弱い者の味方であるべきだ」という気づきは、太宰治自身の文学観の表明とも読め、読後に静かな感動や思索のきっかけを与えてくれるでしょう。笑いの中に、人間の哀しさや、それでも失われない希望のようなものが織り込まれた、味わい深い作品です。
太宰治の入門として、あるいは少し変わった角度から彼の文学に触れたい方にとって、「畜犬談」は非常におすすめできる一作です。ぜひ一度、この奇妙で、おかしくて、そして少しだけ切ない物語の世界に触れてみてください。きっと、太宰治の新たな魅力に気づくはずです。




























































