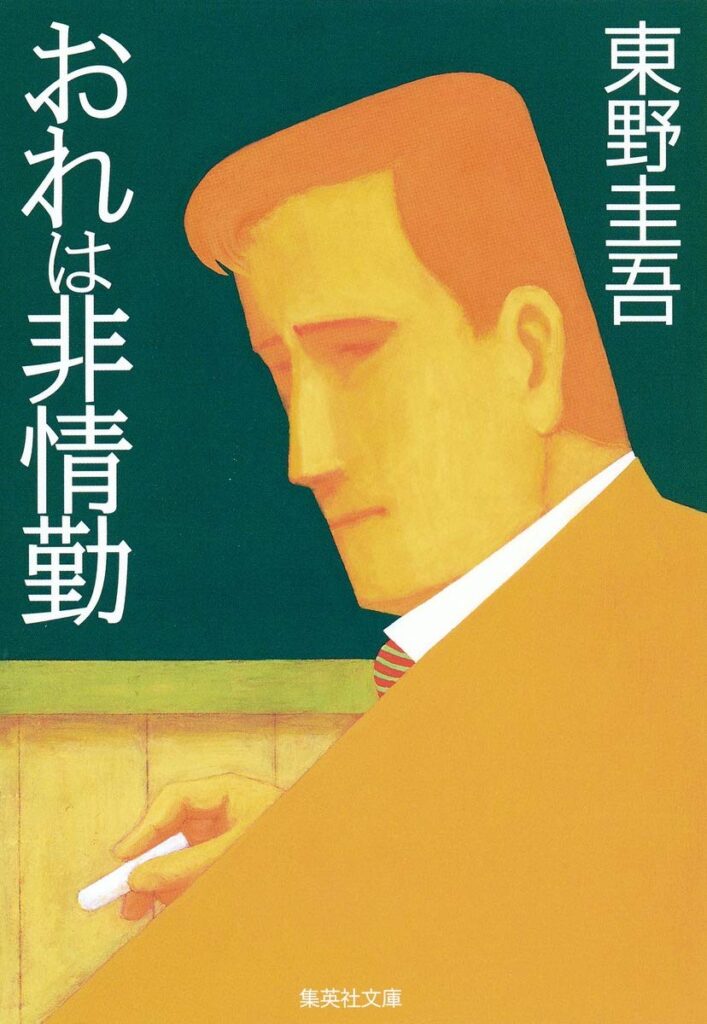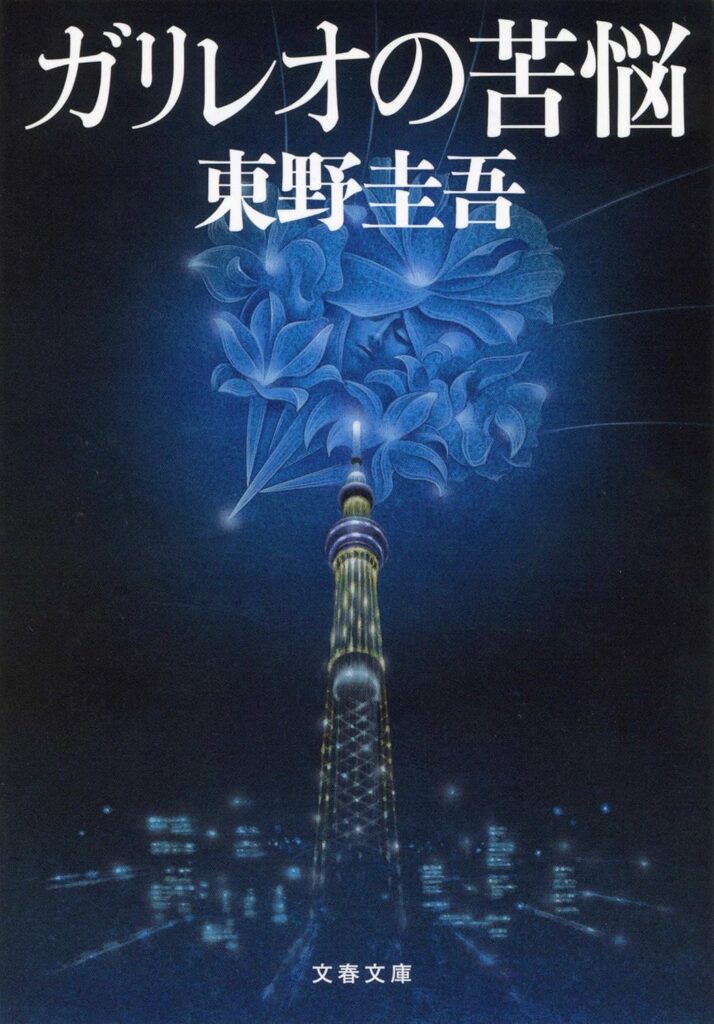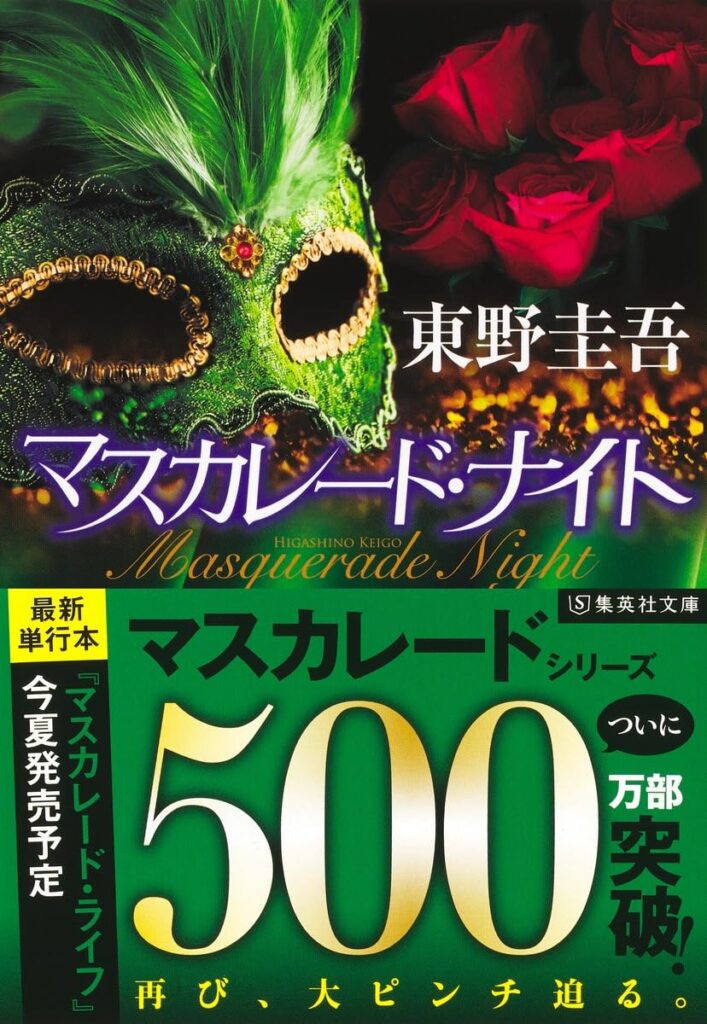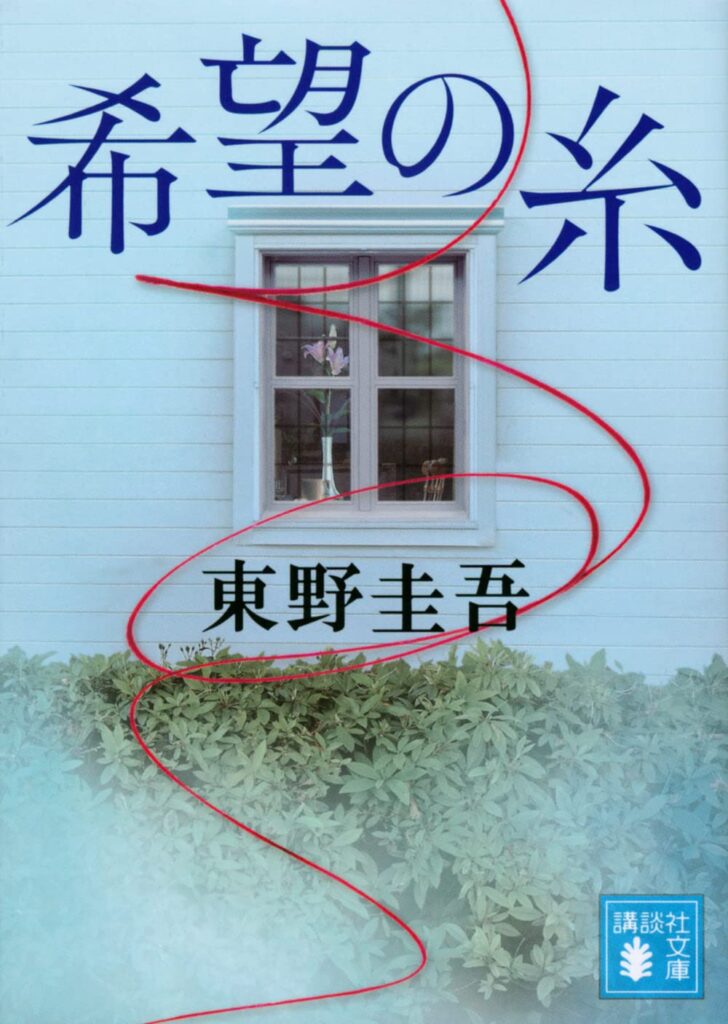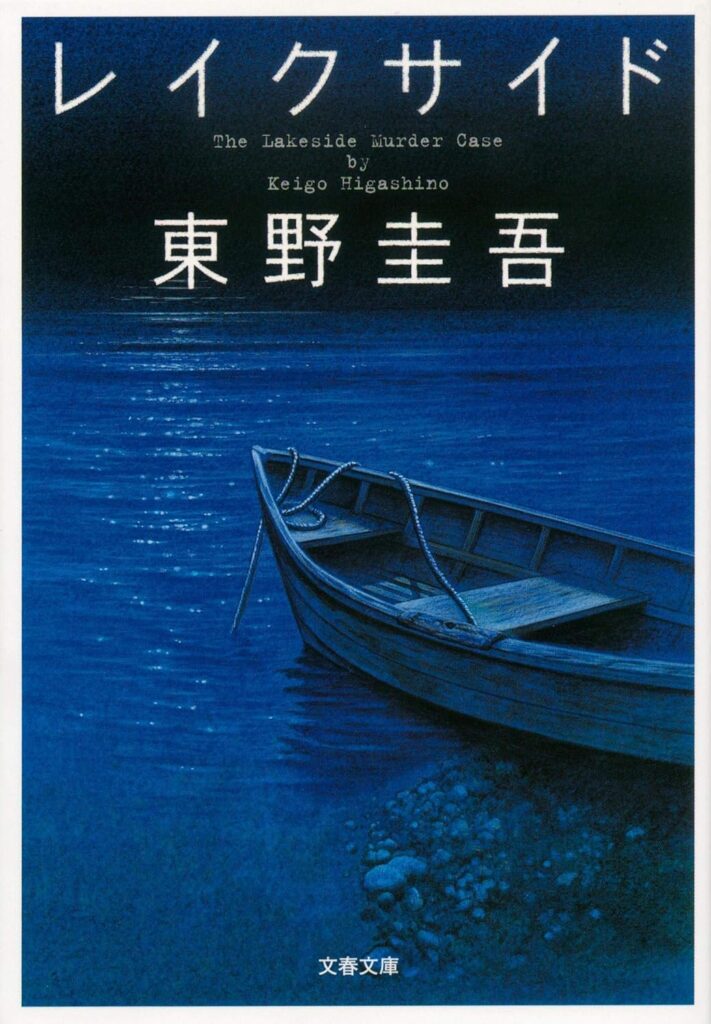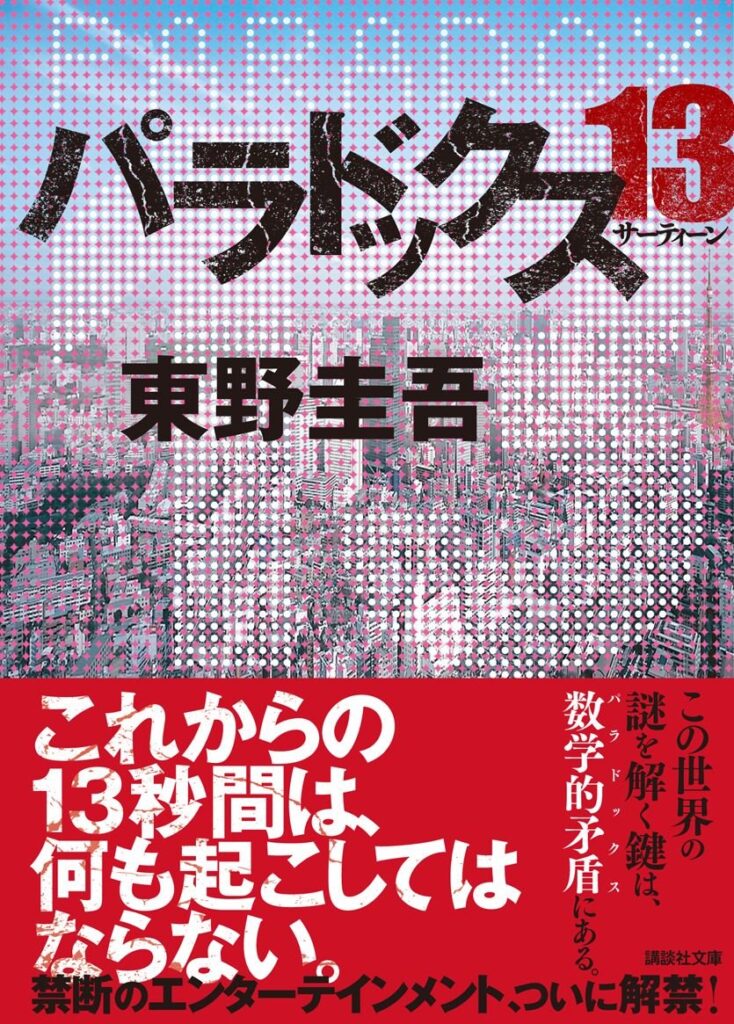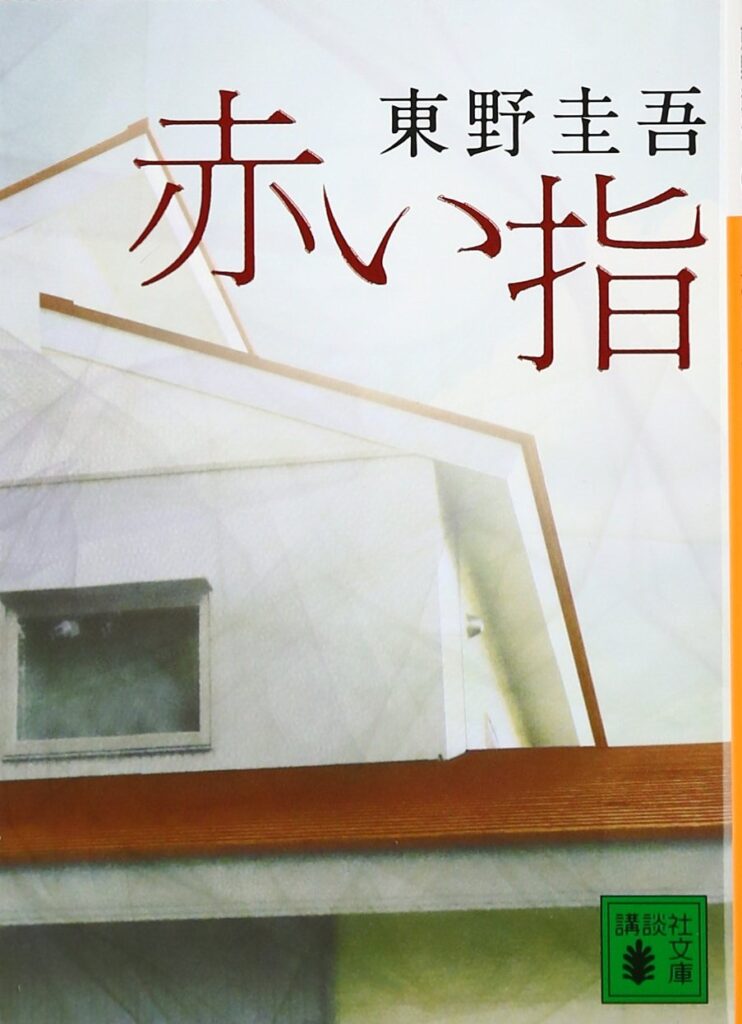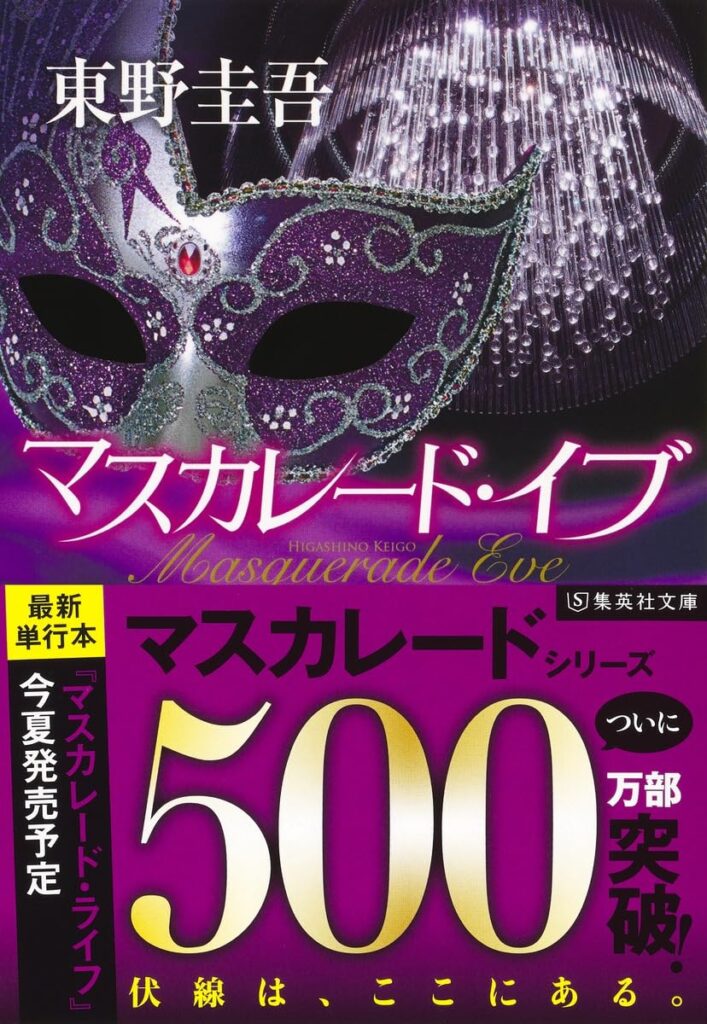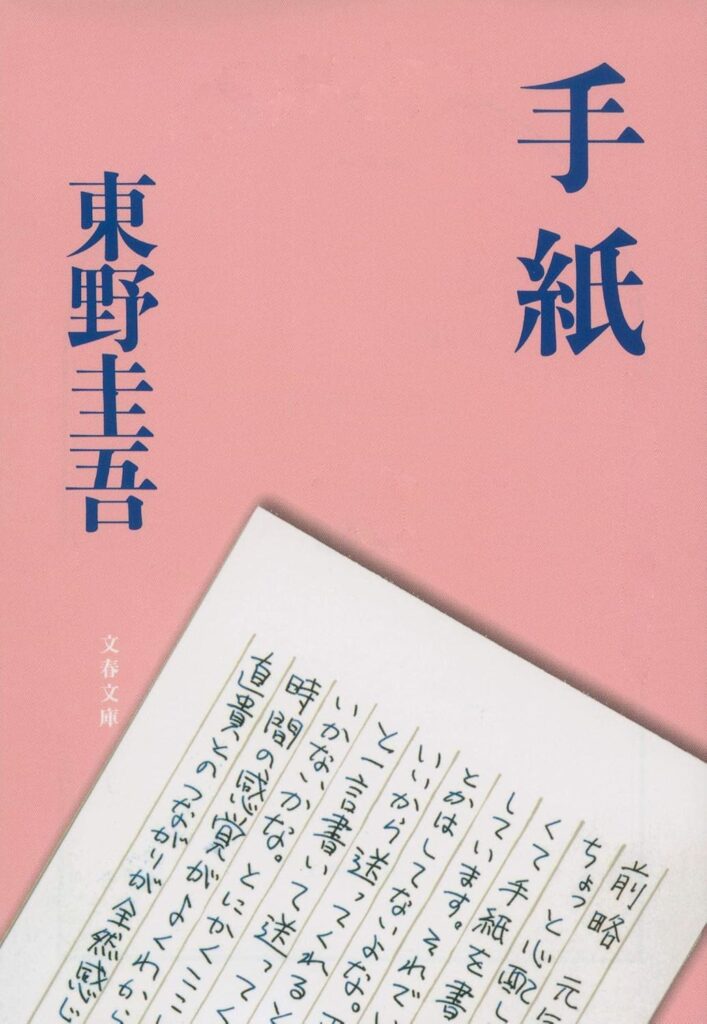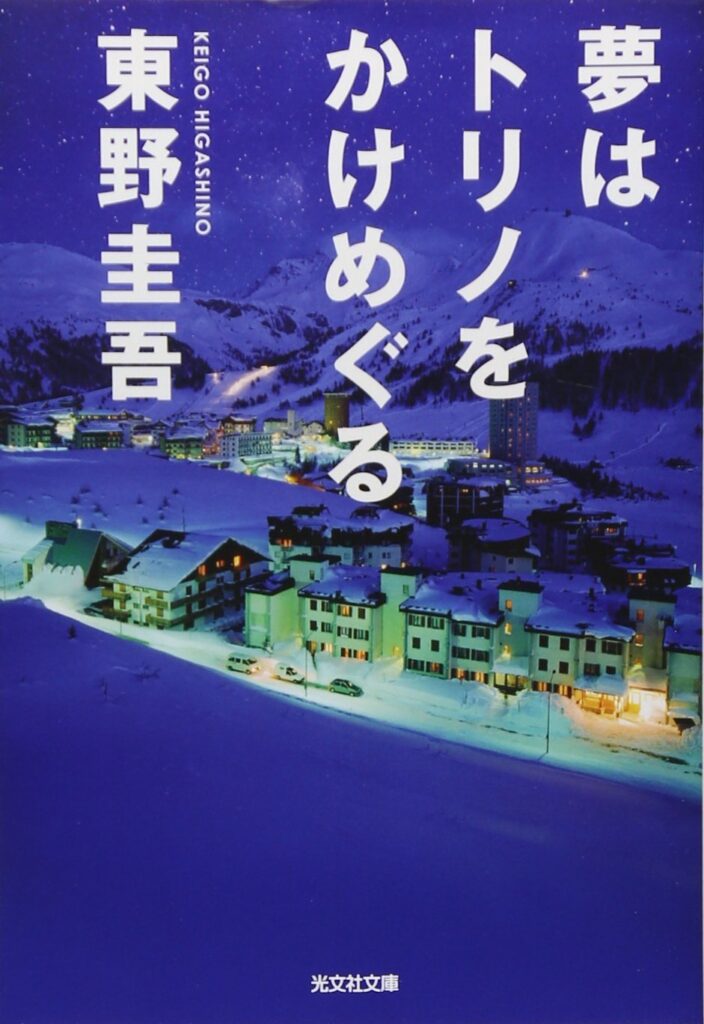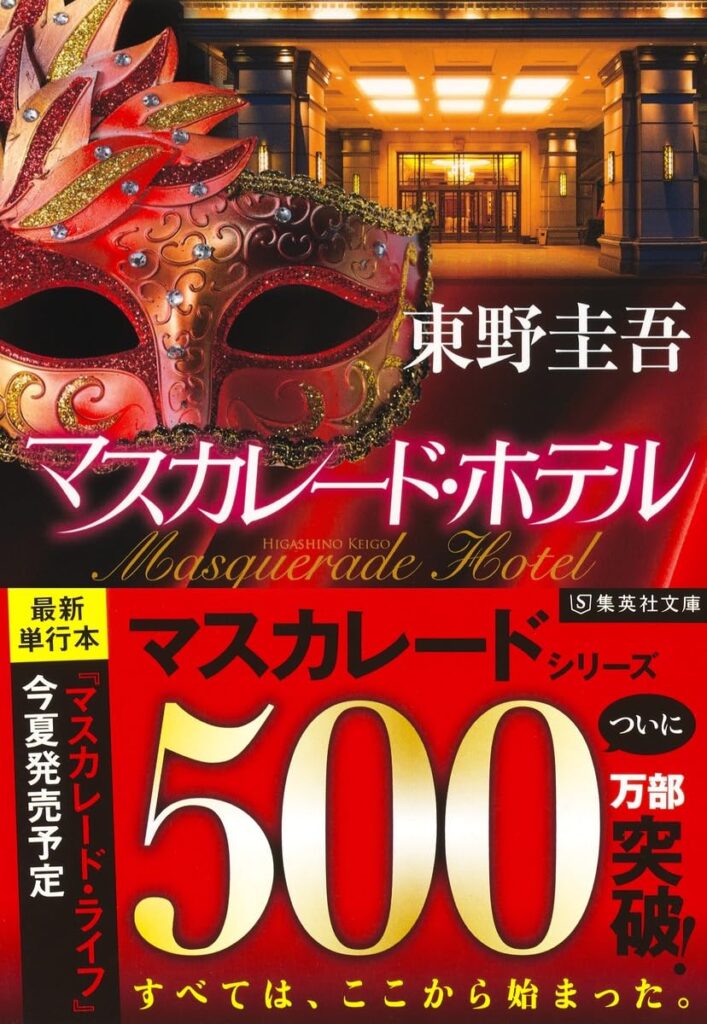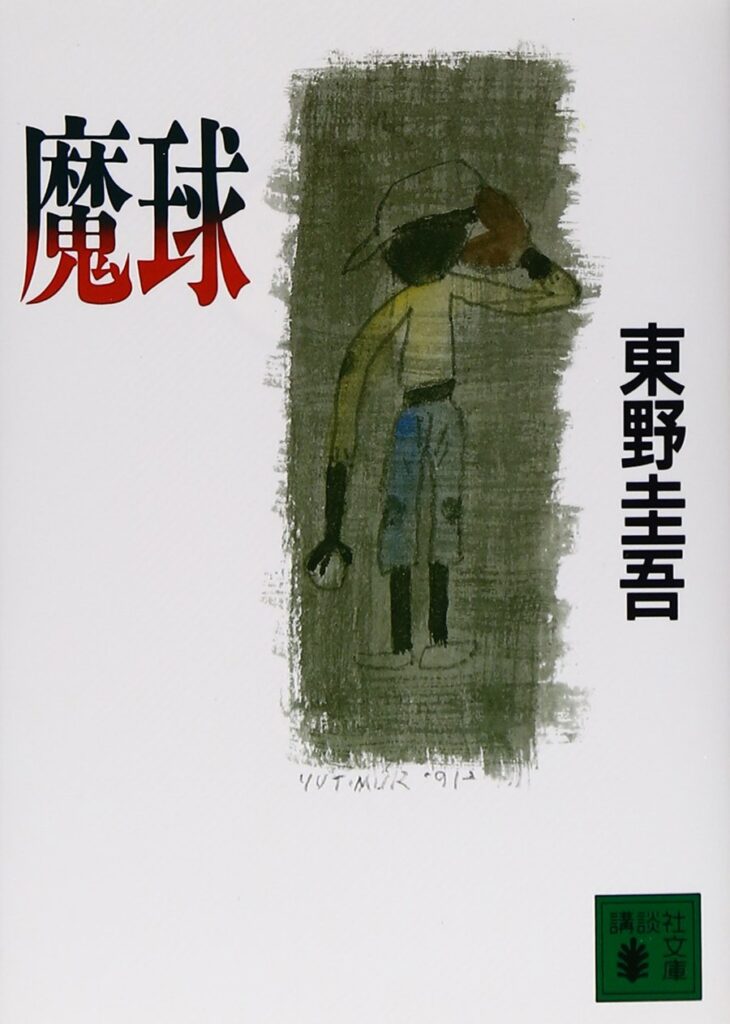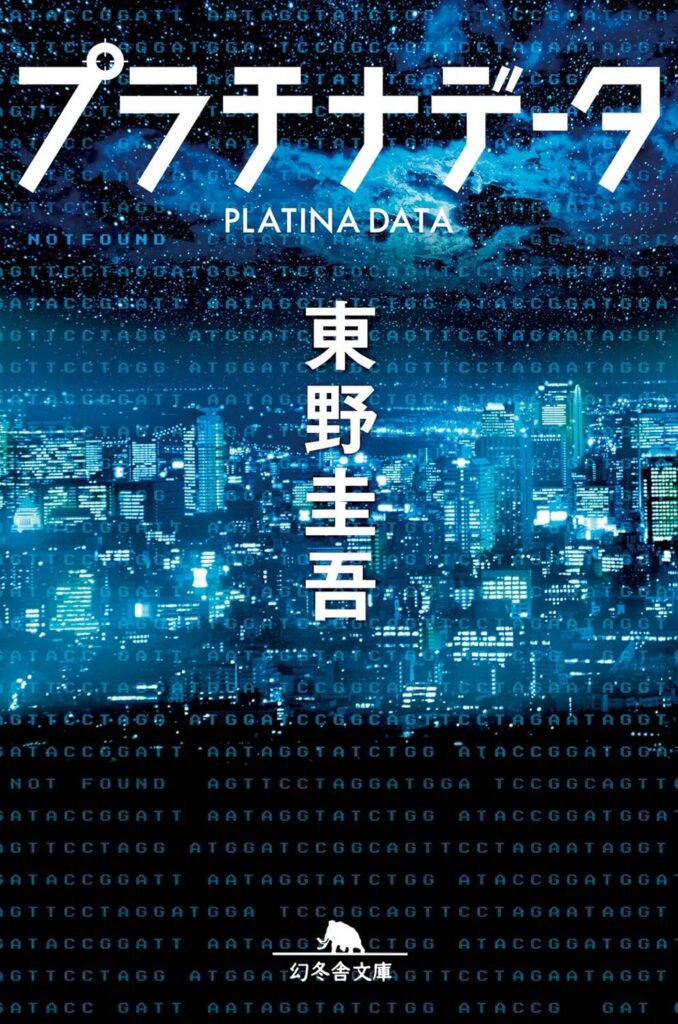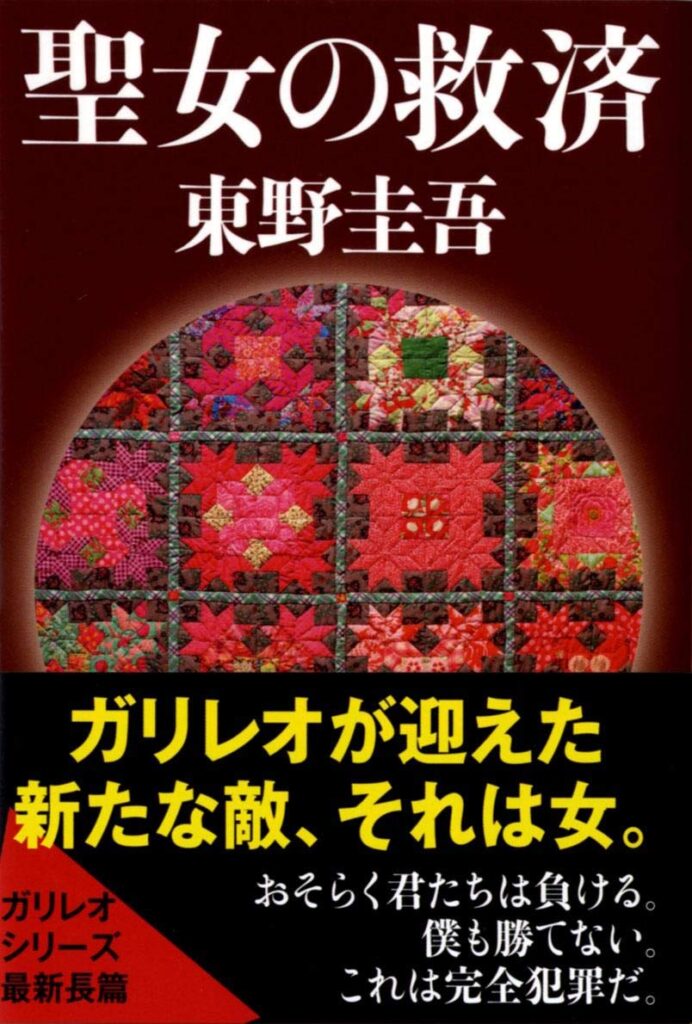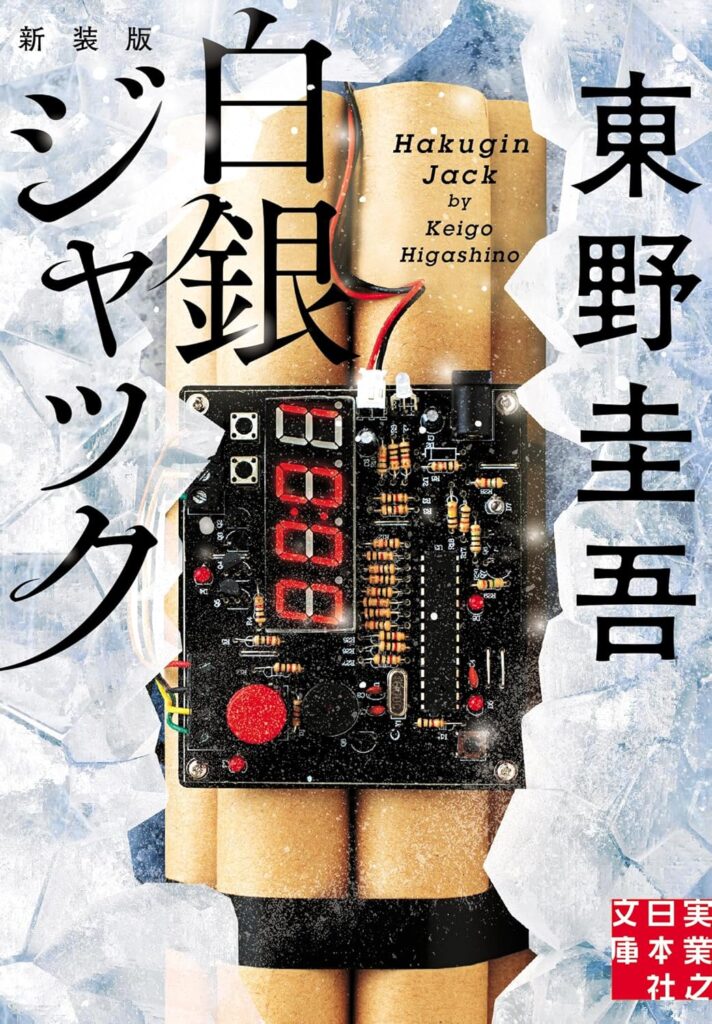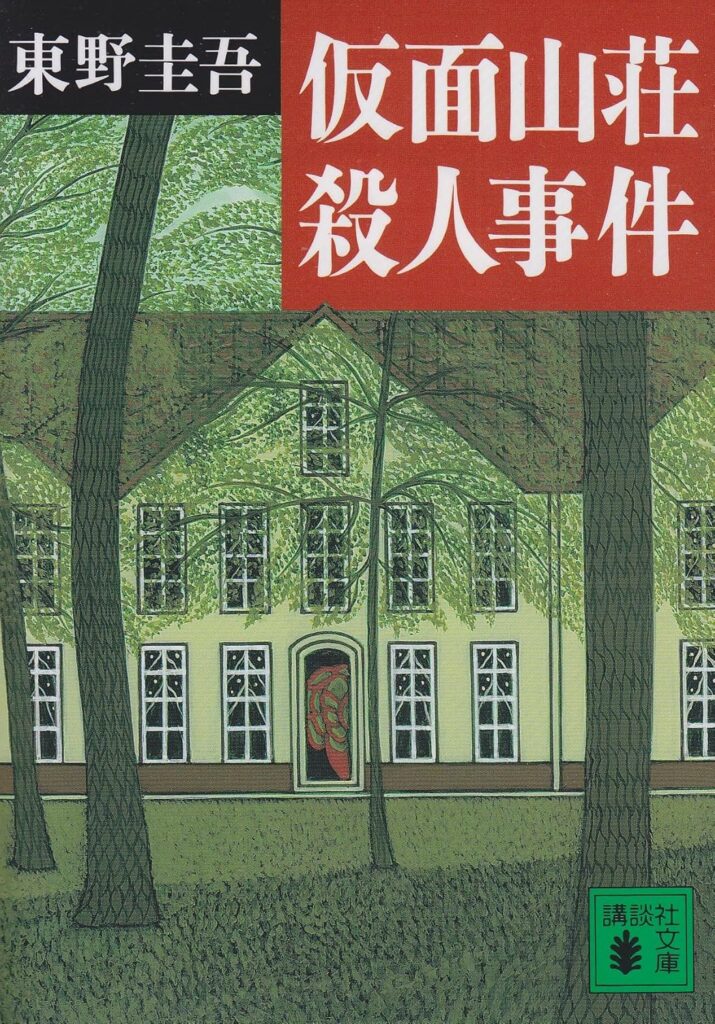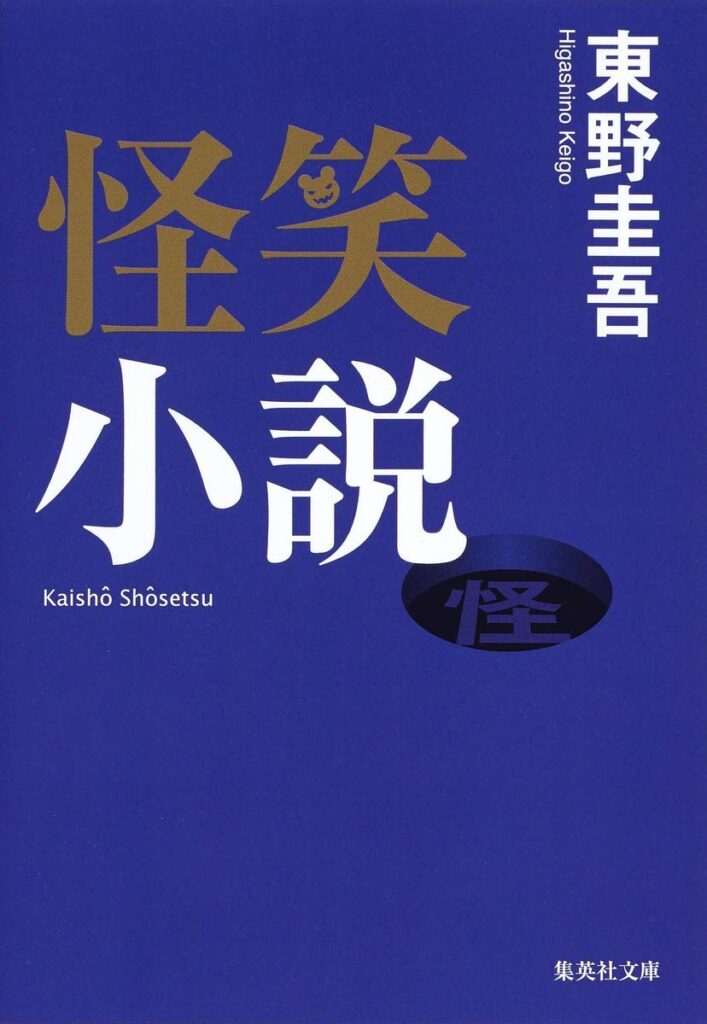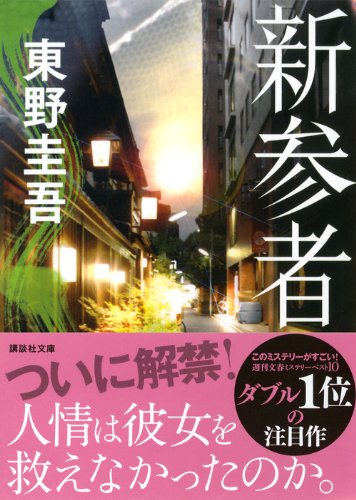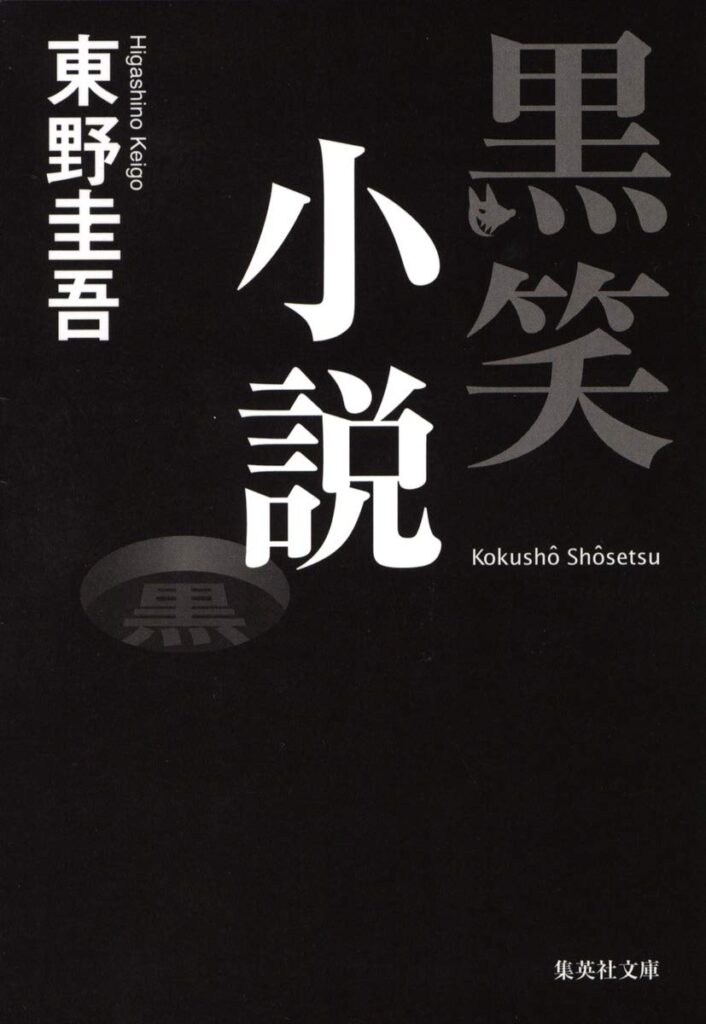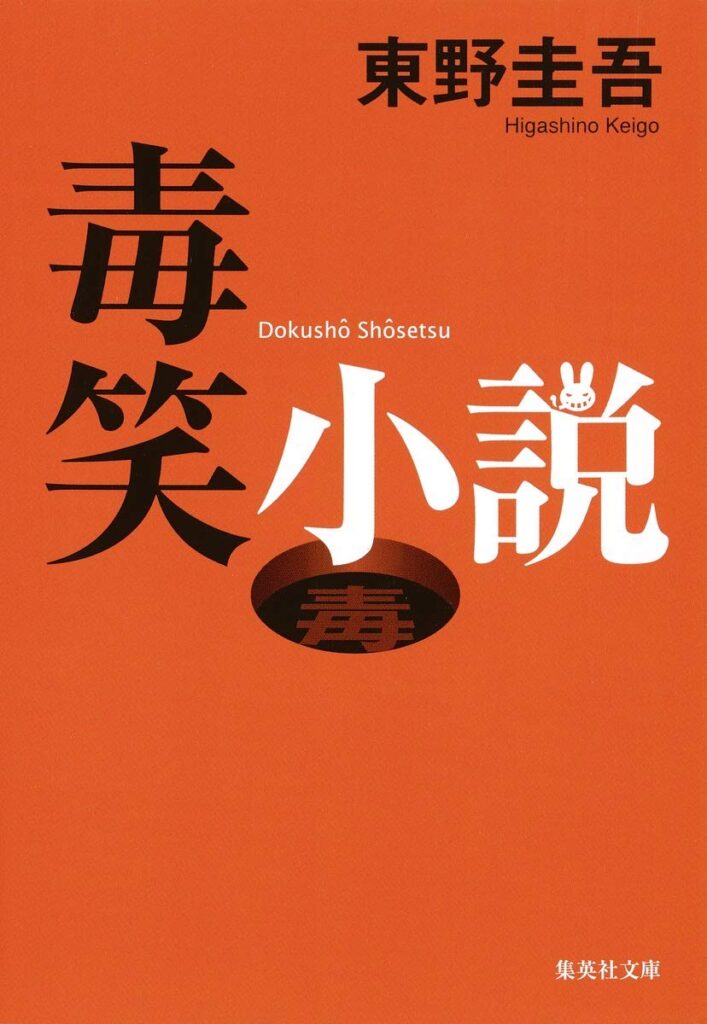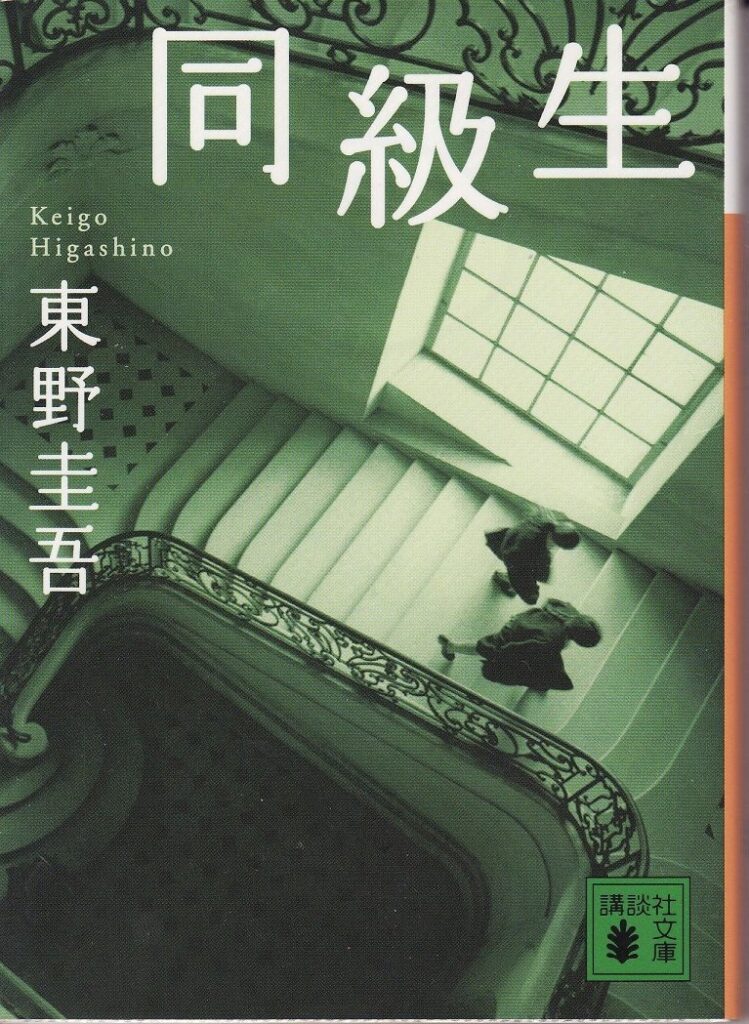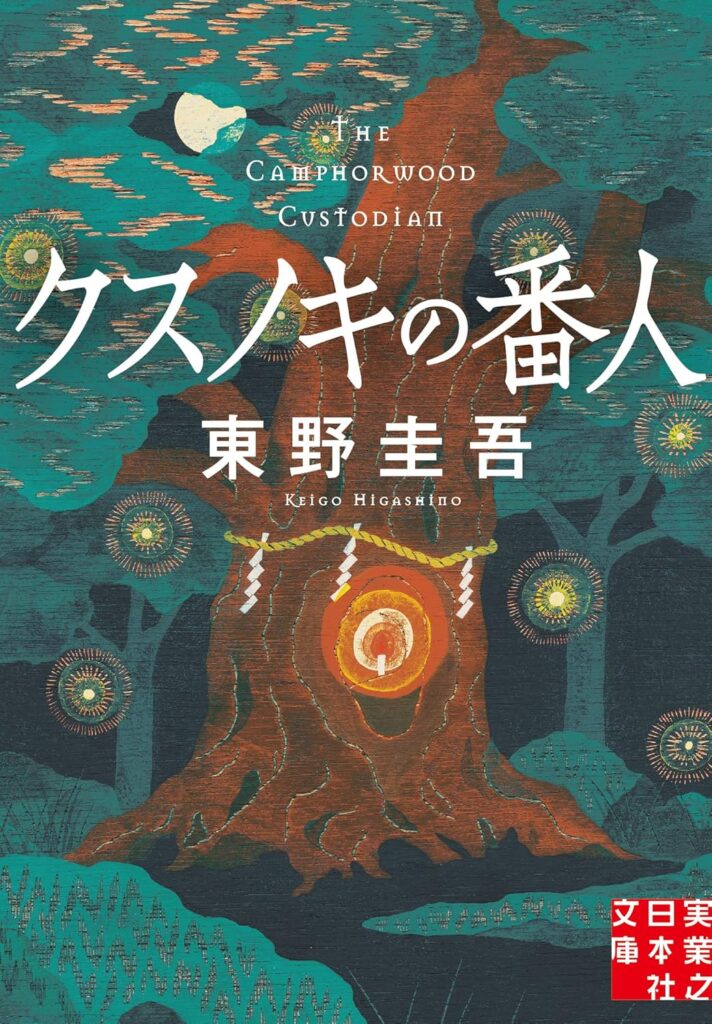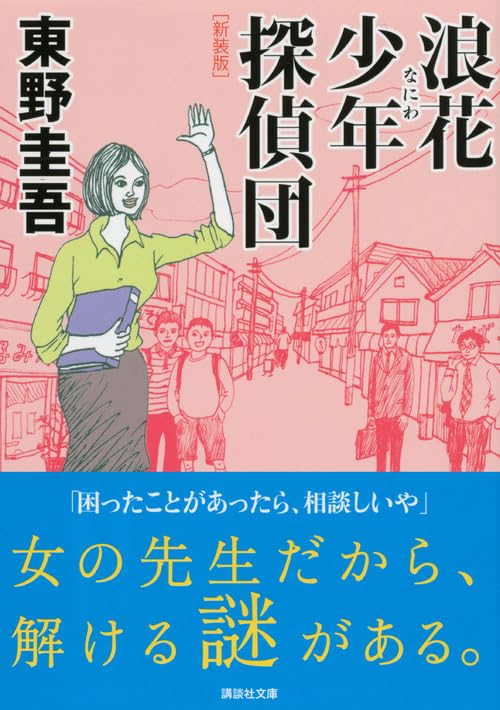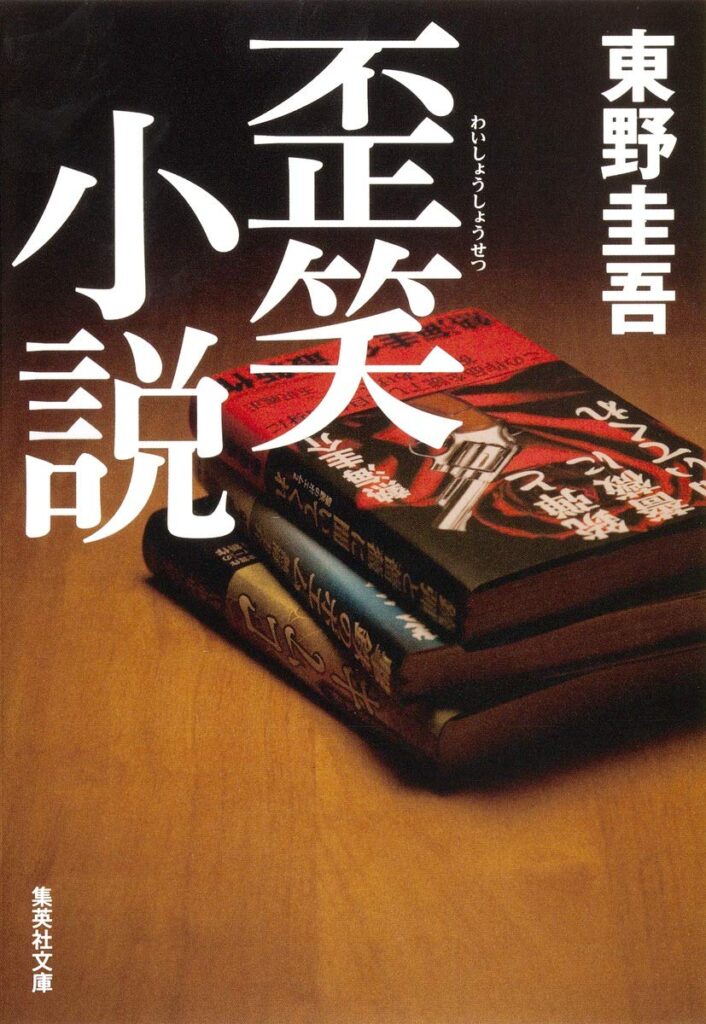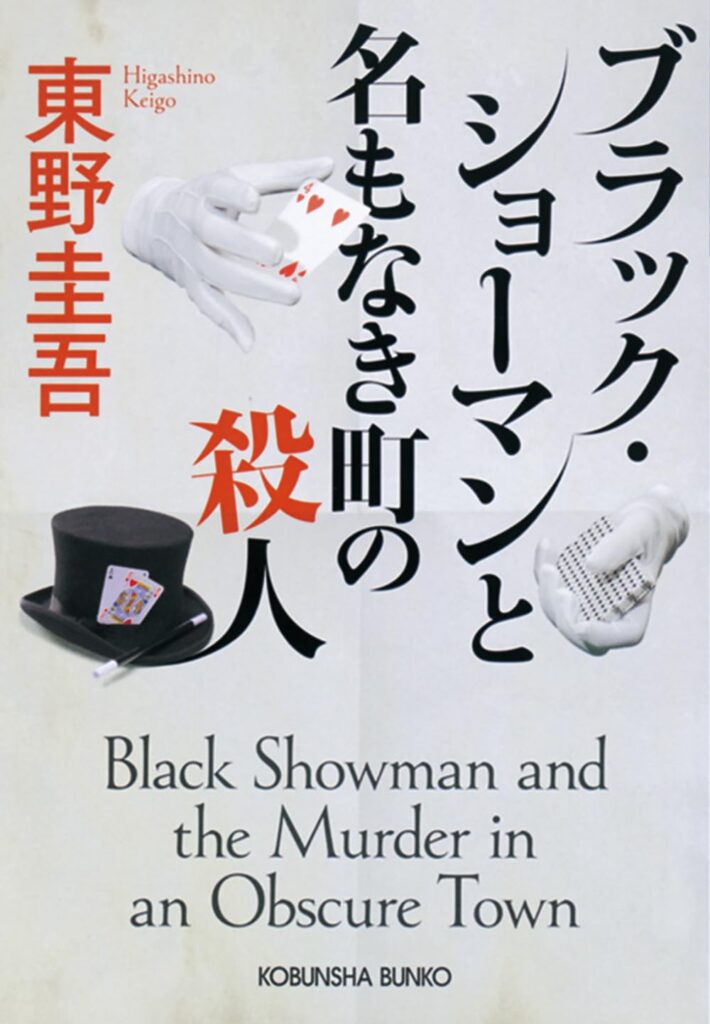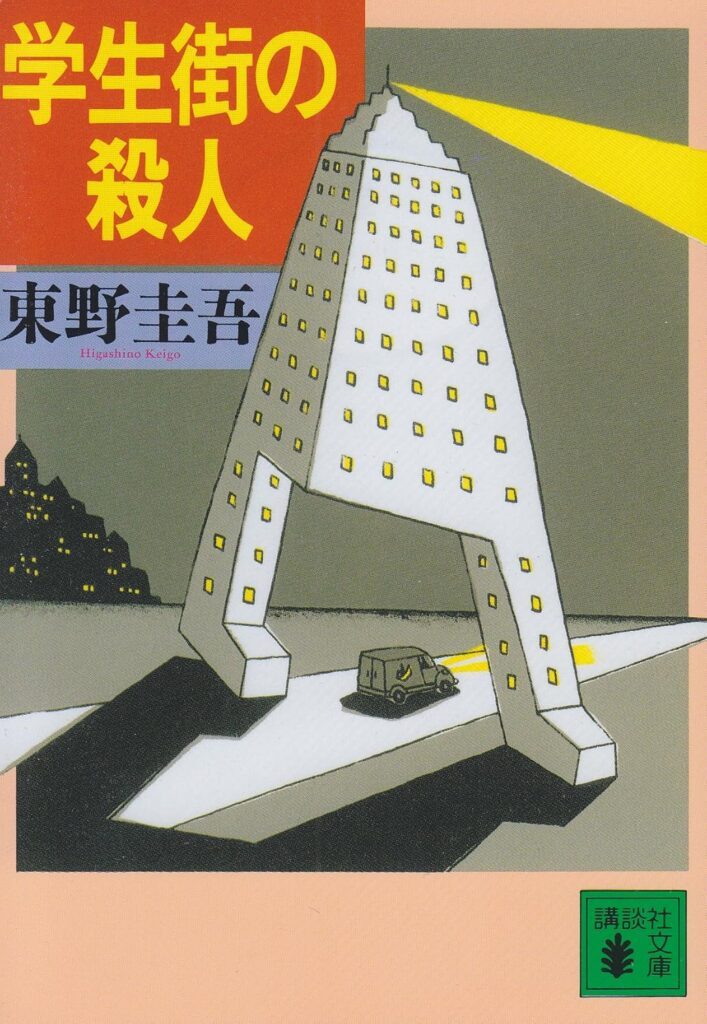小説「流星の絆」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。夜空を駆ける一筋の光に、人は何を願うのでしょう。儚い希望か、あるいは消えぬ復讐の誓いか。この物語は、そんな問いを投げかけるのかもしれません。幼き日に理不尽にも両親を奪われた三兄妹。彼らが背負った宿命は、あまりにも重く、そして暗い。
小説「流星の絆」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。夜空を駆ける一筋の光に、人は何を願うのでしょう。儚い希望か、あるいは消えぬ復讐の誓いか。この物語は、そんな問いを投げかけるのかもしれません。幼き日に理不尽にも両親を奪われた三兄妹。彼らが背負った宿命は、あまりにも重く、そして暗い。
彼らが選んだ道は、正義とは言い難いものでした。いや、むしろ社会の影に潜むような生き方。しかし、それもまた、奪われたものを取り戻すための、彼らなりの闘いだったのでしょう。世間の同情など求めず、ただ一点、真実だけを見据えて。その執念が、やがて思いもよらぬ人物へと繋がっていくのですから、運命とは皮肉なものです。
この記事では、そんな彼らの軌跡を、核心に触れながら辿ってみようと思います。甘っちょろい感傷は抜きにして、彼らが何を見て、何を感じ、そしてどのような結末を迎えたのか。少々長くなりますが、お付き合いいただけますかな。まあ、退屈はさせませんよ。少なくとも、ありきたりな勧善懲悪で終わらないことだけは、保証しましょう。
小説「流星の絆」のあらすじ
物語の幕開けは、14年前の夜。小学生の有明功一、泰輔、そして妹の静奈は、両親に隠れて家を抜け出し、ペルセウス座流星群を見に出かけます。しかし、期待した夜空のショーは雨に遮られ、彼らが家に戻った時、待っていたのは想像を絶する光景でした。洋食店「アリアケ」を営む父と母が、何者かによって惨殺されていたのです。兄妹の世界は、その夜、一変しました。
唯一の手がかりは、泰輔が裏口から逃げる犯人らしき男の後ろ姿を目撃したことだけ。しかし、幼い彼の証言は捜査の決め手とはならず、事件は迷宮入りとなります。両親を失い、天涯孤独となった三兄妹は、養護施設で肩を寄せ合いながら成長しますが、心には決して消えない傷と、犯人への憎しみを抱き続けていました。時間は流れ、彼らは社会へと巣立っていきます。
月日は流れ、大人になった兄妹。しかし、平穏な日々は訪れません。静奈が詐欺被害に遭ったことをきっかけに、長男の功一は、世の中の不条理に対する怒りを新たにし、ある決意を固めます。それは、彼ら自身が詐欺師となり、世にはびこる悪党から金を騙し取るというものでした。功一が計画を練り、泰輔が実行役、そして静奈がターゲットを誘惑する役。歪んだ形ではありますが、彼らは再び「家族」として結束します。
次なるターゲットとして狙いを定めたのは、大手洋食チェーン「とがみ亭」の御曹司、戸神行成。計画を進める中で、泰輔は衝撃的な事実に気づきます。行成の父、戸神政行の風貌が、14年前に目撃した犯人の男と酷似していたのです。「とがみ亭」の看板メニューであるハヤシライスが、父の店の味にそっくりであることも疑念を深めます。詐欺計画は、いつしか両親の仇を討つための復讐計画へと変貌を遂げていくのでした。彼らは、巧妙な罠を仕掛け、政行を追い詰めようと動き出します。
小説「流星の絆」の長文感想(ネタバレあり)
さて、東野圭吾氏の「流星の絆」ですか。多くの読者を惹きつけてやまないこの作品、私も手に取ってみましたよ。結論から申しますと、実に巧みな物語であることは認めざるを得ません。ミステリーとしての骨格をしっかりと保ちながら、家族の絆という、ともすれば陳腐になりがちなテーマを、どす黒い復讐劇と絡めて描き切っている。その手腕は、さすがと言ったところでしょう。
物語の導入部、幼い兄妹が両親の無残な死体を発見する場面。この衝撃的な出来事が、彼らの人生を決定的に捻じ曲げてしまう。ここまでは、まあ、よくある悲劇の設定かもしれません。しかし、彼らが単なる被害者として涙に暮れるのではなく、時を経て、自ら「加害者」の側に身を投じることを選ぶ。この屈折した展開が、物語に独特の陰影を与えていますね。静奈が詐欺に遭い、それを逆手に取って詐欺師稼業に手を染めるというのは、実に皮肉が効いています。失ったものを取り戻すために、他者から奪うことを選ぶ。彼らの正義は、社会の規範から大きく逸脱している。しかし、その歪んだ正義感こそが、彼らを強く結びつける絆となっているわけです。フン、美しいとは言えませんが、切実ではありますな。
詐欺のターゲットとして登場する戸神行成。この男の存在が、物語にさらなる複雑さをもたらします。典型的な「お坊ちゃん」かと思いきや、その誠実さ、人の好さ。静奈が彼に惹かれていくのは、計画の内とはいえ、ある意味当然の流れでしょう。そして、その父・政行が復讐のターゲットとして浮上する。父の店のレシピを盗み、殺害したのではないかという疑念。読者のミスリードを誘う、実に巧妙な仕掛けです。泰輔の目撃証言と、ハヤシライスの味という状況証拠。これらが揃えば、誰もが政行を犯人だと疑うでしょう。兄妹が証拠を捏造してまで彼を追い詰めようとする執念は、痛ましいほどです。
しかし、物語はそう単純には進まない。ここからが、東野作品の真骨頂といったところでしょうか。政行は確かに事件当夜、現場にいた。しかし、彼は犯人ではなかった。レシピを買う約束のために訪れたものの、惨状を目の当たりにし、保身のために逃げ出しただけだった。彼の告白によって、事態は一変します。そして、決定的な証拠となるはずだった「傘」。政行が持ち帰った傘と、現場に残された傘。ここに真犯人特定の鍵が隠されていたわけです。
功一が、事件を担当した刑事・柏原の些細な行動、傘の持ち方や傷に気づき、真相に辿り着くクライマックス。これは見事でした。14年間、兄妹に寄り添い、親身になっていたかに見えた刑事が、実は全ての元凶だった。息子の手術費用という、あまりにも人間的な、しかし許されざる動機。このどんでん返しは、読者の予想を裏切るに十分な衝撃を与えます。柏原が自らの罪を認め、功一の目の前で歩道橋から身を投げる結末は、救いようのない悲劇性を際立たせています。彼もまた、運命に翻弄された、弱い人間の一人に過ぎなかったのかもしれません。まるで操り人形のように、運命の糸に引かれていたのは、兄妹だけではなかったということです。
さて、事件は一応の解決を見ました。しかし、残された問題は、兄妹が犯してきた詐欺という罪です。彼らが自首を決意する場面。特に泰輔の「人から奪った金で幸せを掴むなんて、そんなのインチキなんだ!」という叫びは、柏原の犯行への怒りであると同時に、自らが行ってきたことへの深い悔恨の念が込められているのでしょう。彼らは、復讐を果たしたことで、ようやく自分たちの罪と向き合うことができた。これもまた、皮肉な到達点と言えるかもしれません。
ラスト、功一と泰輔が罪を償う一方で、静奈は戸神行成に未来を託される形になります。行成が、兄たちが騙し取ろうとしたダミーの指輪を「本物」として静奈に贈り、「僕も、あなたたちと絆で繋がれていたい」と告げるシーン。これは、いささか出来すぎていると感じなくもありません。あまりにも都合の良い救済に見えなくもない。しかし、これもまた、作者が提示する一つの「希望」の形なのでしょう。血の繋がりだけではない、困難を乗り越えた先に結ばれる新たな絆。まあ、感傷的ではありますが、読後感としては悪くないのかもしれません。
この物語を通じて描かれるのは、罪と罰、そして再生の可能性です。しかし、それは決して単純なものではない。兄妹が背負った罪は消えませんし、彼らが失った時間も戻らない。それでも、彼らは未来へ向かって歩き出す。その姿は、痛々しくも、どこか力強い。東野圭吾氏は、人間の持つ弱さ、醜さ、そして僅かな光を、巧みに描き出しています。甘ったるいヒューマンドラマに辟易している向きには、このビターな味わいは、むしろ心地よく感じられるのではないでしょうか。まあ、たまにはこういう物語に酔いしれるのも、悪くはありませんね。
まとめ
結局のところ、「流星の絆」とは何だったのか。それは、悲劇的な運命に翻弄されながらも、もがき、あがき、そして互いを支え合った三兄妹の記録、と言えるでしょう。彼らの選んだ道は、決して褒められたものではありません。むしろ、唾棄すべき犯罪行為に手を染めていた。しかし、その根底には、奪われたものへの執念と、唯一残された「絆」を守ろうとする必死さがあった。
真犯人が、最も身近にいた人物だったという結末は、皮肉としか言いようがありません。信じていたものに裏切られる絶望。しかし、それによって彼らは、自分たちが犯してきた罪と向き合う機会を得た。これもまた、運命の奇妙な采配というものでしょうか。復讐の連鎖を断ち切り、新たな一歩を踏み出す。その選択は、決して容易ではなかったはずです。
この物語は、読者に問いかけます。正義とは何か、絆とは何か、そして償いとは何か。単純な答えはありません。ただ、暗闇の中でもがきながら光を求める人間の姿が、そこには描かれている。感傷に浸るのは無粋ですが、彼らの行く末に、僅かながらも希望の光が見えることを願わずにはいられません。まあ、所詮はフィクション。ですが、心を揺さぶる何かがあることは、認めましょう。