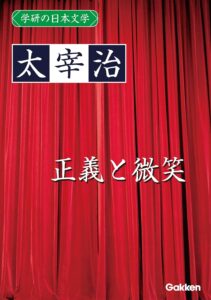 小説「正義と微笑」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治の作品というと、「人間失格」や「斜陽」のような、少し暗くて重たいイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんね。でも、この「正義と微笑」は、そういった作品とは少し趣が異なります。
小説「正義と微笑」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治の作品というと、「人間失格」や「斜陽」のような、少し暗くて重たいイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんね。でも、この「正義と微笑」は、そういった作品とは少し趣が異なります。
この物語は、16歳の少年、芹川進の日記形式で進んでいきます。思春期真っ只中の、多感で、ちょっと生意気で、でも純粋な彼の視点を通して、日々の出来事や心の揺れ動きが赤裸々に綴られていくんです。彼の目を通して見る世界は、時に青臭く、時に鋭く、読んでいるこちらもなんだか昔の自分を思い出して、くすぐったいような気持ちになるかもしれません。
この記事では、そんな「正義と微笑」の物語の筋道を追いながら、特に物語の核心、つまり結末に触れる部分も含めて詳しくご紹介します。進がどんな経験をして、何を感じ、どう変わっていくのか。そして、彼が見つけた「正義」と「微笑」とは何だったのか。そういった点に注目していただければと思います。
もちろん、物語の詳しい流れだけでなく、私がこの作品を読んで何を感じたのか、どんなところに心を動かされたのかといった、かなり個人的で詳細な思いもたっぷりとお話ししています。これから「正義と微笑」を読んでみようかなと思っている方、あるいは既に読んだけれど他の人の意見も聞いてみたいという方の、何かの参考になれば嬉しいです。
小説「正義と微笑」のあらすじ
物語は、主人公である16歳の旧制中学の生徒、芹川進が、日々の反省と青春の記録として日記を書き始めるところから始まります。彼はルソーの言葉に影響を受け、16歳から20歳までの間に人格が形成されると信じ、自身の思想を統一しようと試みます。日記には、学校生活、受験勉強、友人関係など、日常の出来事とともに、彼の内面の葛藤や世の中に対する考えが率直に綴られていきます。
進は感受性が強く、少しばかり自意識過剰なところもある少年です。学校の先生や級友に対して批判的な目を向けたり、自分の才能を信じて疑わなかったり。そんな彼がまず直面するのは、一高(第一高等学校)の受験です。「大いに勉強しよう」と意気込むものの、なかなか本腰を入れることができず、日々の生活の中で様々な出来事に心を揺さぶられます。
結局、進は受験に失敗してしまいます。自暴自棄になった彼は、心配してくれる兄を殴ってしまい、そのことに深く傷つき家出をします。この挫折は、彼にとって大きな転機となりました。第二志望の大学に入学はしたものの、そこでの生活にも馴染めず、彼は自分の本当にやりたいこと、つまり俳優になるという夢を追いかける決意を固めるのです。
俳優への道は決して平坦ではありませんでした。彼は劇団「鴎座」の入門試験を受けますが、試験官の横暴な態度に憤りを感じつつも、芝居への情熱を訴え、なんとか合格を掴み取ります。しかし、始まった俳優修業は、台詞覚えや雑用といった下積みの連続。理想と現実のギャップに苦しみながらも、進は必死に食らいついていきます。
その後、進は「春秋座」という別の劇団の研究生となります。そこでも、安い給金、厳しい稽古、先輩俳優との人間関係など、様々な困難が彼を待ち受けます。それでも進は、芝居に対する情熱を失うことなく、ひたむきに努力を続けます。時には仲間とぶつかり、時には恩師である斎藤先生に励まされながら、少しずつ役者として、そして一人の人間として成長していくのです。
物語は、進が厳しい下積み生活の中で、仲間たちと共に舞台を作り上げ、千秋楽を迎える場面で一つの区切りを迎えます。様々な苦労や葛藤を乗り越えた進が、最後に心からの「幸福」を感じる瞬間までが、彼の日記を通して生き生きと描かれています。単なる成功物語ではなく、悩み、もがきながらも自分の信じる道を進もうとする、一人の若者の等身大の成長記録と言えるでしょう。
小説「正義と微笑」の長文感想(ネタバレあり)
「正義と微笑」、太宰治の作品の中でも、特に若々しいエネルギーと、ある種の清々しさを感じさせる物語だと私は思います。もちろん、そこには太宰らしい苦悩や葛藤、そして社会への鋭い視線も織り込まれているのですが、主人公・芹川進の視点がとにかく瑞々しい。日記形式という手法が、彼の内面をダイレクトに伝えてくるからかもしれませんね。結末に至るまでの彼の心の軌跡を、少し詳しく辿ってみたいと思います。
物語の冒頭、16歳の進は、いかにも思春期の少年らしい、と言えるかもしれません。自意識が強く、少し斜に構えて世の中を見ているようなところがあります。ルソーにかぶれて「思想の統一」なんて言い出すあたり、微笑ましくもあり、青臭くもありますよね。学校の先生を内心で見下したり、自分の才能を過信したり。この時期の、根拠のない万能感と、それゆえの脆さのようなものが、実に巧みに描かれていると感じます。
彼の「正義」感も、まだ未熟で、自分本位な部分が見え隠れします。例えば、級友との関係や、受験勉強に対する姿勢にも、彼の潔癖さや理想主義が表れていますが、それは同時に、他者への不寛容さや現実逃避の裏返しでもあるように思えます。この頃の彼にとっての「微笑」は、どこか自分を守るための鎧のような、あるいは他者を見下すような、少し歪んだものだったのかもしれません。
そんな彼が、一高受験に失敗し、自暴自棄になって兄を殴ってしまう場面。ここは、彼の未熟さが引き起こした悲劇であり、同時に、彼が自分自身と向き合わざるを得なくなる最初の大きな転機だったのではないでしょうか。これまで自分の内面ばかりに目を向けていた彼が、自分の行動が他者(それも最も身近な存在である兄)を深く傷つけたという事実に直面する。この経験は、彼の心に大きな爪痕を残したはずです。
そして、俳優への道を志す決意。これは、単なる現実逃避ではなく、彼なりに見つけ出した、自分の情熱を傾けられる対象だったのだと思います。大学生活に意味を見いだせず、「ここは自分の居場所じゃない」と感じた彼が、芝居の世界に自分の「正義」、つまり生きる意味や価値を見出そうとした。それは、ある意味で純粋で、ひたむきな選択だったと言えるでしょう。
しかし、その道もまた、彼の理想通りには進みません。鴎座の入団試験での、試験官の横暴な態度。ここで進は、社会の理不尽さや権威主義といったものに直面します。彼は憤りを感じながらも、ぐっとこらえて自分の思いを訴える。この経験は、彼の「正義」感を少しだけ現実的なものへと変えていったのではないでしょうか。単に理想を叫ぶだけでなく、現実の中でどう自分の信念を貫くか、という課題にぶつかったわけです。
俳優としての修業の日々は、さらに過酷です。台本覚え、発声練習、そして雑用。憧れていた世界の現実は、地味で、時に屈辱的ですらあります。進は、持ち前のプライドを傷つけられ、何度もくじけそうになります。日記には、弱音や不満も率直に綴られています。しかし、それでも彼は逃げ出さない。芝居が好きだという気持ち、そして、自分で選んだ道だという覚悟が、彼を支えていたのでしょう。
この下積み時代を通して、進は少しずつ変わっていきます。以前のような、根拠のない自信や他者への批判的な態度は影を潜め、謙虚に学ぶ姿勢や、周囲の人々への感謝の気持ちが芽生えてくる。特に、兄との関係性の変化は印象的です。かつて殴ってしまった兄に対して、進は負い目を感じながらも、俳優としての自分の活動を報告し、アドバイスを求めたりする。兄もまた、弟の夢を理解し、静かに応援し続ける。二人の間には、言葉少なながらも深い信頼関係が築かれていきます。
姉の存在も、進にとっては心の支えだったでしょう。結婚して家を出た姉を気遣い、時には夫婦喧嘩の仲裁に入ったりもする。家族という、当たり前のようでいて、かけがえのない存在。進が厳しい俳優の世界で踏ん張れたのは、こうした家族の存在があったからかもしれません。彼の成長は、彼一人の力だけでなく、周囲の人々との関わりの中で育まれていったものなのです。
そして、恩師・斎藤先生との出会い。斎藤先生は、進の才能を見抜き、厳しくも温かい指導を与えます。彼の言葉は、進にとって道標となり、俳優としての心構えを教えてくれます。物語の後半で、進が久しぶりに斎藤先生を訪ねる場面があります。そこで先生は、進の成長を認めつつも、さらなる精進を促す。この師弟関係もまた、進の人間的な成長に大きな影響を与えたと言えるでしょう。
春秋座での日々は、まさに試練の連続です。薄給に苦しみ、先輩からのいじめのような仕打ちに耐え、それでも舞台に立ち続ける。仲間たちと協力して一つの作品を作り上げる中で、彼は、個人の才能だけでは成り立たない、集団で何かを成し遂げることの難しさと喜びを学びます。千秋楽を迎え、仲間たちと打ち上げをする場面。そこには、かつての青臭い自己中心的な少年の姿はもうありません。
そして、物語のラスト。進は日記にこう記します。「ああ、幸福だ。」と。この一言に、どれほどの重みが込められていることか。それは、単に舞台が成功したという喜びだけではないでしょう。受験に失敗し、挫折し、悩み、苦しみ、それでも自分の信じる道を選び、そこで必死にもがき、仲間や恩師、家族に支えられながら、ささやかながらも確かな達成感を得た。その過程全体が、彼にとっての「幸福」だったのではないでしょうか。
この物語における「正義」とは、もはや初期の彼が考えていたような、観念的で独りよがりなものではありません。自分の弱さや社会の理不尽さと向き合いながらも、誠実に、ひたむきに自分の信じる道(この場合は俳優としての道)を歩むこと。その姿勢そのものが、進にとっての「正義」となったのではないでしょうか。そして、「微笑」もまた、かつての自意識過剰なものではなく、苦労を知り、他者への感謝を知った上で浮かべることのできる、穏やかで、確かなものへと変化したように感じられます。
太宰治自身の経験が色濃く反映されていると言われるこの作品。彼もまた、文学の道を志し、多くの苦悩や葛藤を経験したことでしょう。だからこそ、進の心情描写はこれほどまでにリアルで、読む者の心を打つのかもしれません。青春時代の痛みや輝き、そして成長の軌跡。それは、時代を超えて多くの人々の共感を呼ぶ、普遍的なテーマなのだと思います。この物語を読むと、たとえ不器用でも、悩みながらでも、自分の信じる道を歩むことの尊さを改めて感じさせられます。進が見つけたささやかな「幸福」は、読後、温かい余韻として心に残るのです。
まとめ
太宰治の「正義と微笑」は、16歳の少年、芹川進が俳優という夢を見つけ、その実現のために奮闘する姿を、彼自身の日記を通して描いた成長物語です。物語の結末まで含めて考えると、単なる青春小説というだけでなく、人が生きていく上で直面するであろう普遍的な苦悩や喜びが詰まっている作品だと言えるでしょう。
当初は自意識過剰で青臭さの残る進が、受験の失敗、家族との衝突、そして俳優としての厳しい下積み生活といった様々な経験を通して、少しずつ変化していく過程が丁寧に描かれています。彼の「正義」感も、当初の独りよがりなものから、現実と向き合い、他者との関わりの中で培われる、より地に足の着いたものへと変わっていきます。
兄や姉、恩師である斎藤先生といった周囲の人々との関係性も、この物語の重要な要素です。彼らに支えられ、時にはぶつかり合いながら、進は人間的に成長していきます。そして、数々の困難を乗り越えた末に彼が感じる「ああ、幸福だ」という言葉には、深い実感がこもっており、読者の心に強く響きます。
この作品は、夢を追うことの厳しさと素晴らしさ、そして挫折や苦悩の中から立ち上がり、前を向いて進むことの大切さを教えてくれます。太宰治というと暗いイメージを持つ方もいるかもしれませんが、「正義と微笑」は、読後にどこか温かい気持ちと、ささやかな勇気を与えてくれるような、魅力的な作品だと思います。




























































