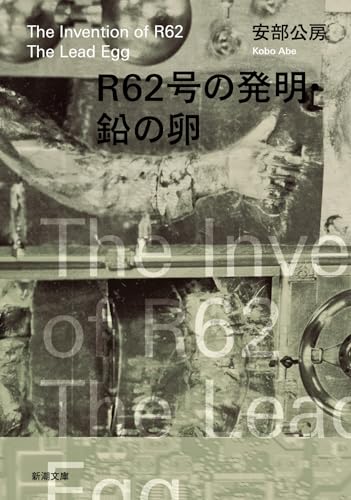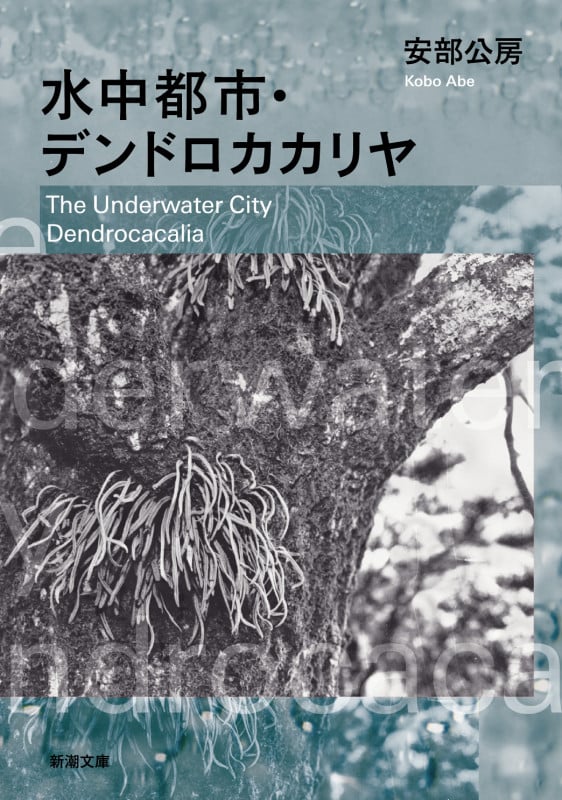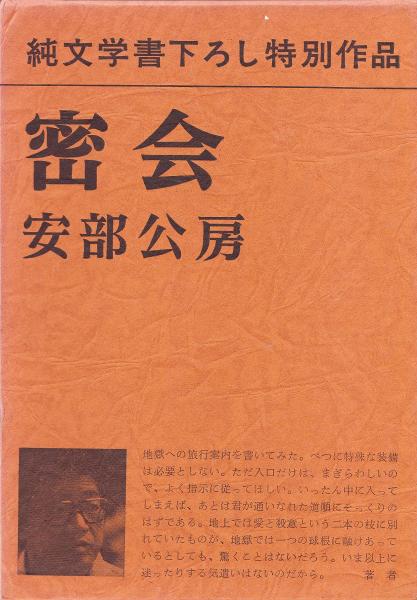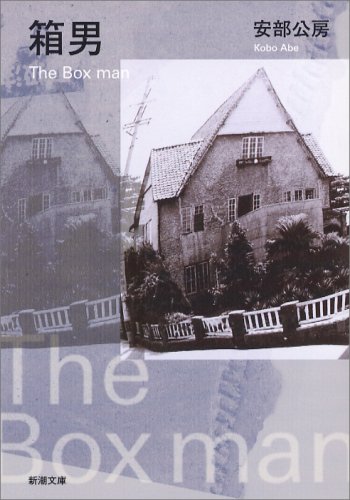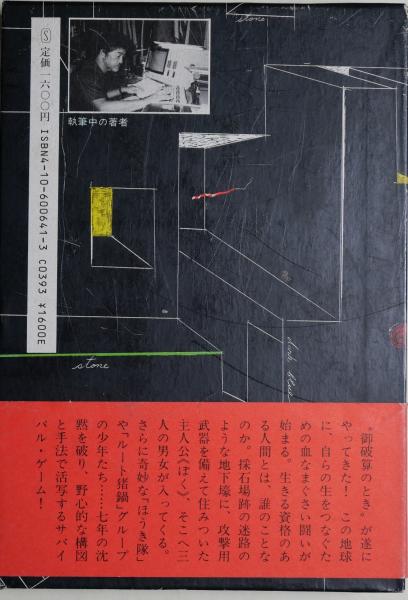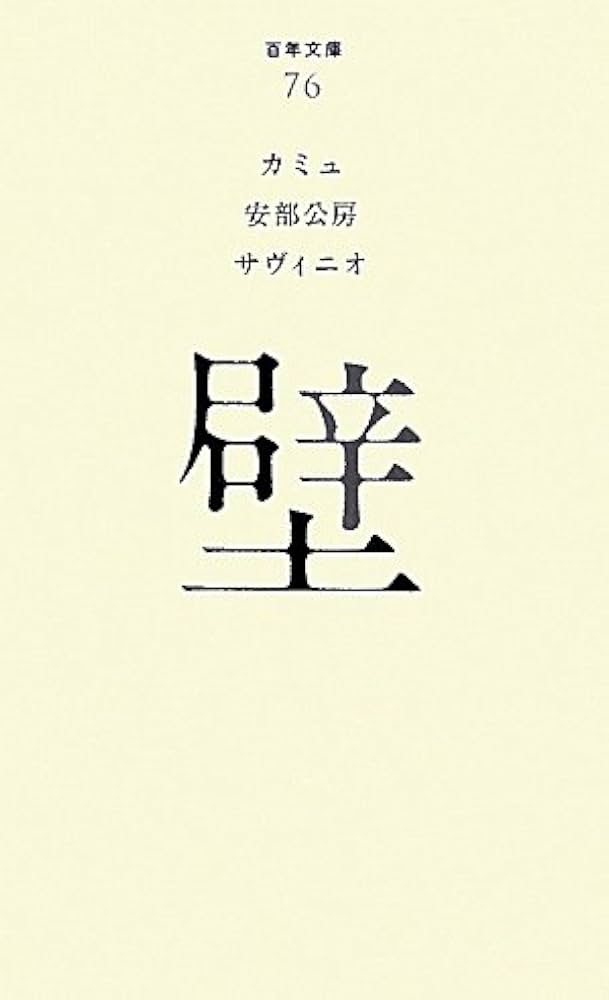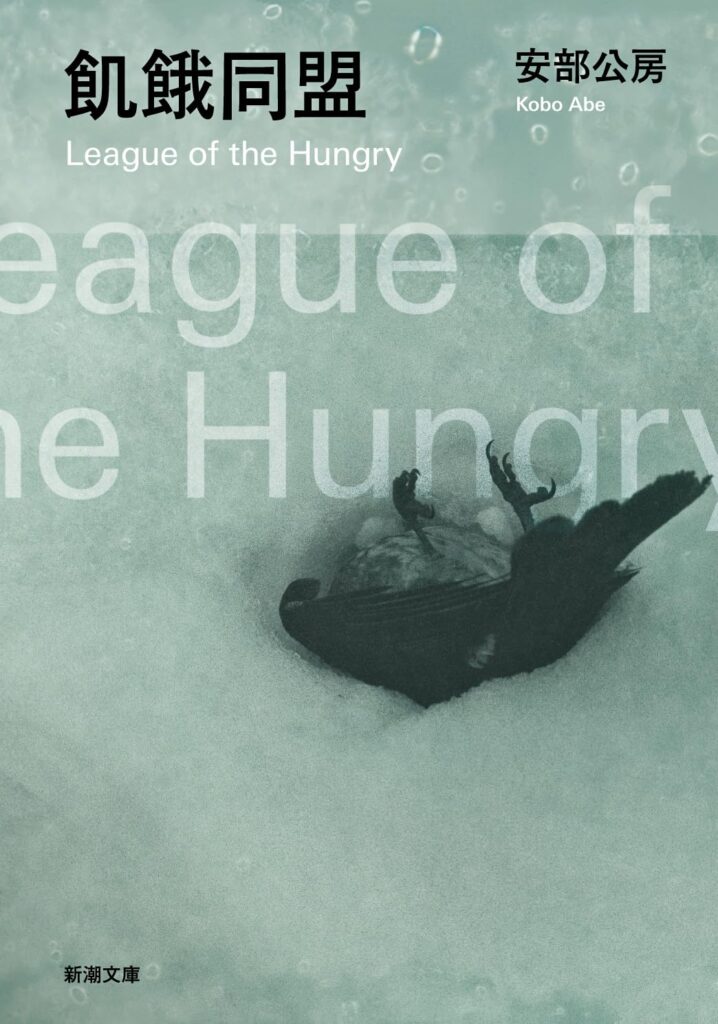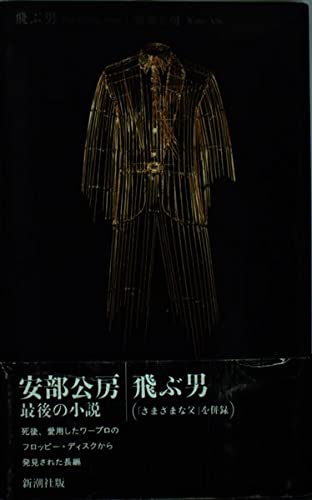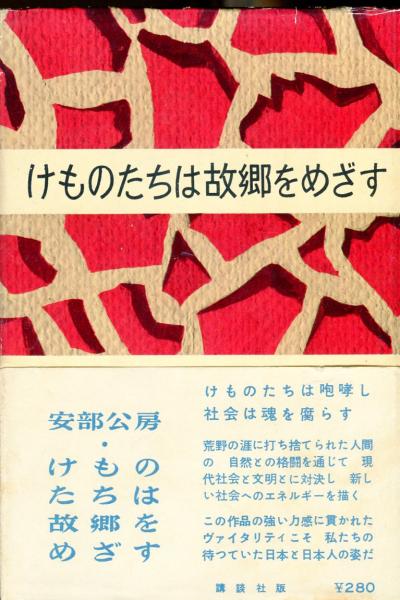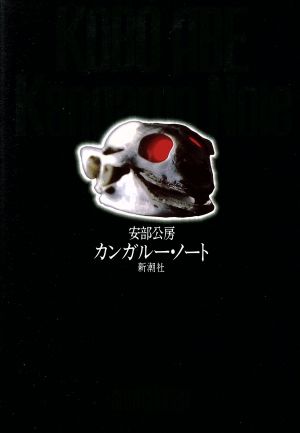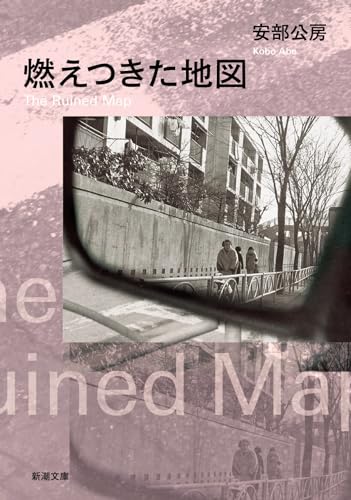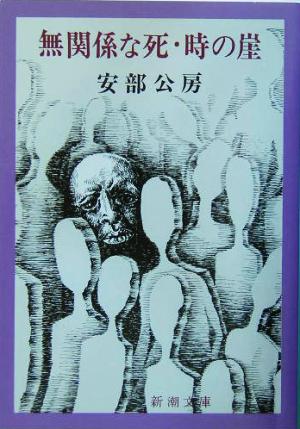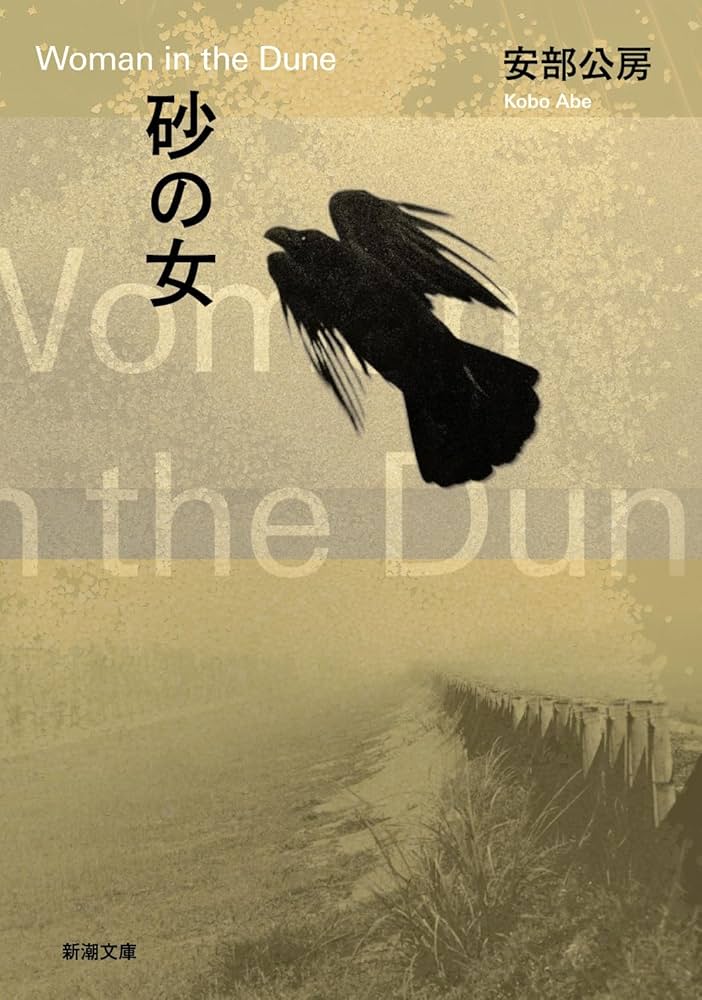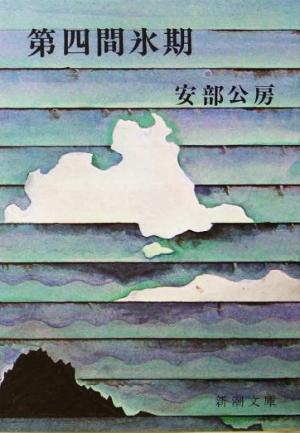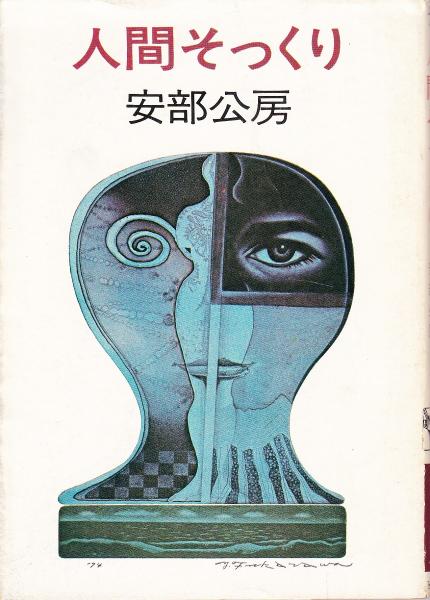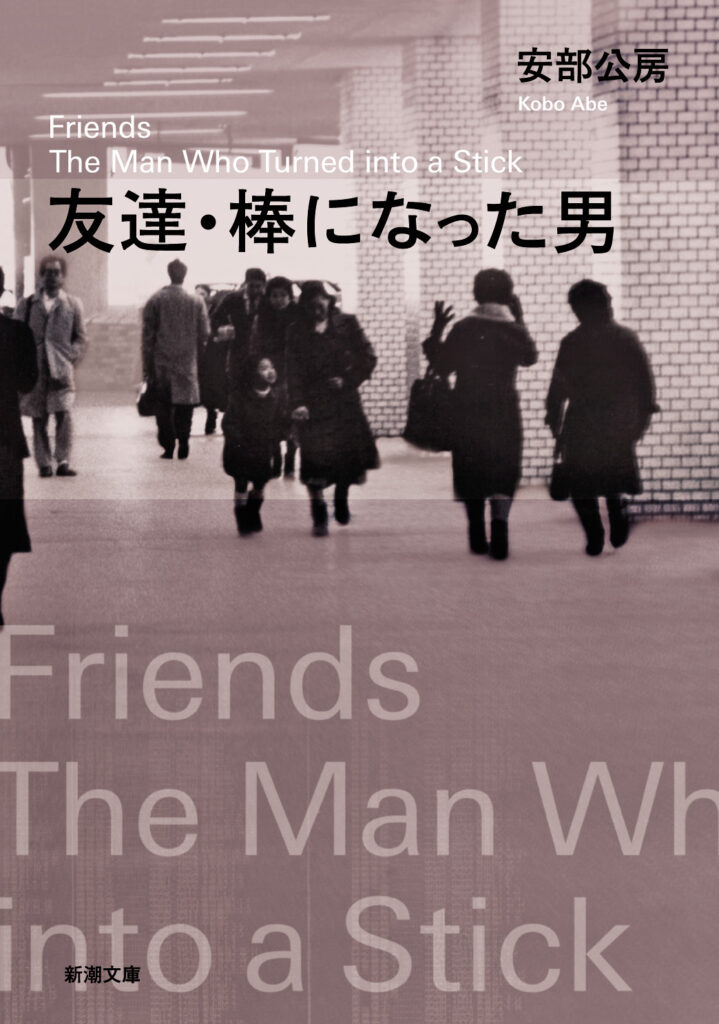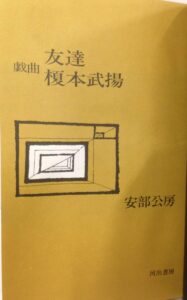 小説「榎本武揚」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「榎本武揚」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
安部公房が描く歴史上の人物、榎本武揚。彼は幕末の動乱期、幕臣として最後まで新政府軍に抵抗し、蝦夷の地に共和国まで樹立した人物です。しかし、降伏後は一転、敵であったはずの明治新政府で要職を歴任し、栄達を極めました。この劇的な転身ゆえに、彼は「変節漢」という評価を受けることも少なくありません。
この歴史の大きな謎に、安部公房は独自の視点から切り込んでいきます。本作は、単に史実をなぞる歴史小説とは一線を画します。虚実が入り混じる複雑な構造を用いて、榎本武揚という人間の行動の裏に隠された「論理」を暴き出そうとする、知的なスリルに満ちた物語なのです。
この記事では、まず「榎本武揚」の物語の骨格となるあらすじを紹介します。その後、物語の核心に迫る重大なネタバレを含んだ、詳細な感想を綴っていきます。安部公房が仕掛けた壮大な謎解きを、ぜひ一緒に体験していただければと思います。
「榎本武揚」のあらすじ
物語は、現代を生きる「私」が旅先の北海道・厚岸(あっけし)にある旅館に宿泊するところから始まります。そこで出会ったのは、福地と名乗るどこか影のある旅館の主人でした。彼はかつて憲兵だった過去を持ち、義理の弟を密告したという重い十字架を背負って生きていました。主人は、自らの裏切りにも似た行為と、世間から変節漢と罵られながらも新政府で大成した榎本武揚の生涯を重ね合わせ、榎本に強い関心を寄せていたのです。
一年後、「私」のもとに、突然姿を消した主人から一通の手紙と、『五人組結成の顛末』と題された古い記録が届きます。この古文書こそが、物語の核となる部分です。それは、新選組副長・土方歳三の近習であった浅井十三郎という人物が、戊辰戦争の終結と、その後の出来事を記した手記でした。
手記の中で浅井は、土方歳三が抱いたある強烈な疑念を語ります。北へ敗走を続ける旧幕府軍の戦いは、どうにも精彩を欠き、まるで誰かが意図的に敗北を演出しているかのようでした。土方は、海軍を率いる榎本武揚と陸軍を率いる大鳥圭介が、密かに通じ合って「八百長戦争」を仕組んでいるのではないかと直感します。
土方の壮絶な戦死の後、その疑念を確信に変えた浅井は、榎本こそが同志たちを裏切り、死に追いやった元凶だと断定します。彼は復讐を誓い、同じ志を持つ仲間と「五人組」を結成。箱館戦争に敗れて東京の牢獄に収監された榎本武揚を暗殺するため、自らも罪を犯して同じ牢獄へと入るのでした。はたして、彼らの復讐計画の行方とは。そして、榎本武揚が隠し続ける真実とは何なのでしょうか。
「榎本武揚」の長文感想(ネタバレあり)
ここから先は、「榎本武揚」の物語の核心に触れる部分、つまり結末までのネタバレをふんだんに含んだ感想となります。未読の方はご注意ください。この物語の本当の面白さは、衝撃のラストとその論理を知ってから、もう一度物語を振り返ることで倍増するように感じます。
まず申し上げておきたいのは、この「榎本武揚」という作品が、いわゆる歴史小説の枠組みを大きく超えている点です。安部公房の作品らしく、物語は入れ子構造になっています。現代の語り手「私」、旅館の主人・福地、そして福地が遺した古文書の書き手・浅井十三郎と、視点が複雑に交錯しながら、一つの巨大な謎へと収斂していく様は見事です。
物語の導入部で登場する旅館の主人・福地の存在が、非常に重要です。彼は、戦争中に義弟を密告したことで家族を失い、周囲から蔑まれながらも商才で成功を収めた人物。彼の人生は、まさに榎本武揚の毀誉褒貶に満ちた生涯とパラレルな関係にあります。彼が榎本に執着するのは、自らの「裏切り」とも言える行為を、榎本の行動に重ね合わせることで正当化したいという、痛切な自己弁護の欲求から来ているのです。
福地が「私」に託す古文書『五人組結成の顛末』は、一見すると客観的な記録の形をとっています。しかし、その書き手である浅井十三郎の視点は、主君・土方歳三への絶対的な忠誠心と、榎本への燃えるような憎悪に貫かれています。ここにもまた、強烈な主観のフィルターがかかっているわけです。安部公房は、歴史というものが、いかに個人の主観や都合によって解釈され、語り継がれていくかを、この二重の構造を通して巧みに示唆しています。
古文書が描く「八百長戦争」の疑惑は、この物語前半の大きな牽引力となります。土方歳三や浅井にとって、戦とは主君への忠義を尽くすための神聖な行為です。しかし、彼らが命を懸けるその戦いが、実は自分たちの指導者によって仕組まれた茶番だったとしたら。その絶望と怒りは計り知れません。土方が抱く違和感、そして彼の悲劇的な死は、旧時代の価値観(武士道)が、新しい時代の冷徹な論理の前に砕け散る瞬間を描いているように思えます。
浅井たち「五人組」が、榎本暗殺のために辰ノ口の牢獄に潜入するところから、物語はクライマックスへと向かっていきます。彼らが用意した時限爆弾や毒針といった暗殺計画は、ことごとく杜撰で失敗に終わります。このどこか間抜けな失敗の描写も、彼らの抱く旧来的な復讐の論理が、もはや通用しないことを暗示しているかのようです。
そして、ついに榎本本人と対峙する場面。ここが本作の白眉であり、全ての価値観が転倒する驚愕のシーンです。怒りに燃える五人組から「裏切り者」と罵られた榎本は、少しも動じません。それどころか、彼らの告発内容、つまり戊辰戦争が意図的に仕組まれた敗戦であったことを、あっさりと認めてしまうのです。このネタバレには、読んでいるこちらも度肝を抜かれます。
ここから、榎本の口を通して、彼の行動の真意が語られます。それは、浅井たちの復讐心など吹き飛んでしまうほど、壮大で、冷徹で、そして圧倒的な説得力を持つものでした。オランダ留学で国際法を学び、弱肉強食の国際情勢を目の当たりにした榎本は、日本が内戦を長引かせれば、欧米列強の介入を招き、植民地化される未来を正確に予測していたのです。
彼の忠誠の対象は、もはや滅びゆく徳川幕府ではありませんでした。彼が守ろうとしたのは、ただ一つ、「日本」という国家そのものだったのです。国家という全体を生かすためには、幕府という部分を、外科手術のように迅速に、そして管理された形で切り捨てる必要があった。彼が演出した「八百長戦争」は、内戦を早期に終結させ、列強の介入を防ぐための、苦渋に満ちた唯一の策だったのでした。
蝦夷共和国の建国すら、本気で独立を目指したのではなく、来るべき近代国家運営のための「リハーサル」であり、新時代を担う有為な人材を温存するための壮大な実験だったと彼は語ります。浅井たちの掲げる個人的な忠義や復讐心は、このグローバルな地政学的視点と国家存亡の論理の前では、あまりにも矮小で、無力でした。
この牢獄での対決は、まさに知の巨人による一方的な蹂躙です。浅井たちが持ち込んだ物理的な武器(爆弾や毒針)や道徳的な正義は、榎本が持つ「情報」と「論理」という、より強力な武器の前に完全に無力化されます。彼らは、自分たちの世界観そのものを根底から破壊され、知的にも精神的にも完膚なきまでに打ちのめされてしまうのです。
この圧倒的な弁明の後、彼らはもはや暗殺者ではなく、榎本の信奉者へと「転向」させられます。彼らの復讐劇は、一人の傑出した知性が描いた壮大な物語に吸収され、解消されてしまう。このどんでん返しこそが、この小説の最大の魅力であり、安部公房の真骨頂と言えるでしょう。
物語は、もう一つの結末を用意しています。榎本の演説を盗み聞きしていた36人の囚人たちです。彼らもまた榎本のビジョンに感化され、自分たちの手で理想の国を創ろうと集団で脱獄します。彼らは物語の冒頭の舞台である厚岸へと向かい、共和国建設を試みますが、その試みはあっけなく、そして惨めに失敗します。
この囚人たちのエピソードは、極めて重要な意味を持っています。彼らは榎本と同じ「理想」を掲げながら、それを実現する「能力」を持っていませんでした。この失敗談は、理念だけでは何も成し遂げられないという冷徹な事実を突きつけます。そして逆説的に、榎本という人物が、単なる理想家ではなく、目的のためには非情な手段さえ厭わない、恐ろしく有能な「実行者」であったことを際立たせるのです。
安部公房は、この作品を通して榎本武揚を「裏切り者」という汚名から解放し、全く新しい人物像として再構築しました。彼が描く榎本は、古い忠誠を捨て、より大きな忠誠を選んだ近代的テクノクラートであり、システムを巧みに操ることで未来を切り開いた、ある種の救世主です。その行動は、旧来の道徳観からは理解されず、孤独です。
この物語は、歴史とは何か、正義とは何か、そしてリーダーシップの本質とは何かを、私たちに鋭く問いかけてきます。単純な英雄譚や勧善懲悪では決して割り切れない、複雑で、不穏で、しかし強烈に知的好奇心を刺激する傑作。それが安部公房の「榎本武揚」なのです。この驚くべき物語の構造と、胸のすくような論理の展開を、ぜひご自身の目で確かめてみてください。
まとめ
安部公房の小説「榎本武揚」は、歴史上の謎多き人物を、独自の視点で解剖した知的な物語です。この記事では、まず物語の導入となるあらすじを紹介し、後半では結末までのネタバレを含む詳しい感想を述べさせていただきました。
本作の魅力は、単なる歴史の再現にとどまらない、虚実を織り交ぜた重層的な構造にあります。そしてクライマックスで明かされる、榎本武揚の「裏切り」の真相。彼の行動は、幕府への裏切りではなく、植民地化の危機から日本という国家を守るための、より高次の忠誠心の発露であったという驚くべきネタバレが待っています。
この小説を読むことで、榎本武揚という人物に対する評価は一変するかもしれません。彼は変節漢などではなく、旧時代の価値観を乗り越え、冷徹な論理と壮大なビジョンで国家の未来を切り開いた、近代的なリーダーとして描かれています。その姿は、現代に生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれるはずです。
歴史の謎解きと、安部公房ならではの緻密な物語の仕掛けが融合した「榎本武揚」。まだ読まれていない方は、ぜひこの機会に手に取ってみてはいかがでしょうか。きっと、忘れられない読書体験が待っていることでしょう。