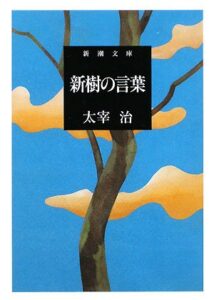 小説「新樹の言葉」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治といえば、どこか退廃的で暗いイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、この「新樹の言葉」という短編は、読後に爽やかな風が吹き抜けるような、不思議な明るさを持った作品なんです。
小説「新樹の言葉」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治といえば、どこか退廃的で暗いイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、この「新樹の言葉」という短編は、読後に爽やかな風が吹き抜けるような、不思議な明るさを持った作品なんです。
物語の中心となるのは、作家である「私」と、思いがけず再会した乳兄弟の幸吉とその妹。この出会いをきっかけに、「私」は自身の過去や感傷的な心と向き合い、そして乳兄弟のひたむきな生き方に心を打たれていきます。特に、過去の象徴ともいえる生家が焼失する場面での兄妹の態度は、強く印象に残ります。
この記事では、まず物語の詳しい流れを追いかけます。どのような経緯で乳兄弟と出会い、どんな交流があったのか、そして「私」の心境がどう変化していったのか、重要な出来事を含めてお伝えします。読んだことのない方はもちろん、すでに読んだことがある方も、新たな発見があるかもしれません。
そして後半では、この物語から私が感じ取ったこと、考えたことをじっくりと述べていきます。登場人物たちの心の動きや、作品全体に流れる空気感、太宰治がこの作品に込めたかもしれない想いなど、深く掘り下げてみたいと思います。少し長いかもしれませんが、お付き合いいただけると嬉しいです。
小説「新樹の言葉」のあらすじ
早春の頃、作家である「私」は仕事のため甲府に滞在していました。ある日、道を歩いていると、見知らぬ郵便配達の青年に声をかけられます。「青木大蔵さん、内藤幸吉さんを知っていますか。あなたは幸吉さんの兄さんです」と言われ、「私」は全く身に覚えがなく戸惑います。その場は曖昧に返事をして別れますが、不思議な気持ちが残りました。
その日の夕方、「私」が宿の部屋にいると、昼間の青年が言っていた内藤幸吉が訪ねてきました。話を聞くと、幸吉の母親は「おつる」という名で、「私」の乳母だった女性だということが判明します。「私」は生まれてすぐ、体が弱かった実母に代わって乳母のつるに預けられ、小学校に上がる頃まで育てられました。「私」にとってつるは実の母同然の存在であり、その息子である幸吉は、つまり乳兄弟にあたるのでした。思いがけない再会に、「私」は大きな喜びと興奮を覚えます。
「私」は幼い頃の記憶を辿ります。つるはいつも「私」の味方で、教育にも熱心でした。たくさんの本を読み聞かせ、大人の道徳を教えてくれた、愛情深い女性でした。しかし、「私」が小学校に上がる少し前、つるは甲州の甲斐絹問屋の番頭のもとへ嫁いでいきました。突然の別れで、ちゃんとしたお別れの言葉も言えなかったことが、「私」の心に悔いとして残っていました。小学校二、三年の頃に一度だけ、つるが男の子を連れて家を訪ねてきたことがありましたが、それが幸吉だったのでした。
その後、「私」は高校生の時に、つるが亡くなったことを聞かされます。つるの夫は独立して甲府で呉服屋を営んでいましたが、つるの死後、店は傾き、幸吉が中学校を卒業する直前に夫も亡くなったとのことでした。幸吉には妹がおり、両親を亡くしてからは兄妹二人で苦労を重ねてきたようです。昼間声をかけてきた郵便配達の青年は幸吉の友人で、幸吉から私の名前を聞かされており、郵便物の宛名を見てピンときたのでした。
「私」と幸吉は食事をするために宿を出ます。幸吉は「今日は絶対にここだ」と、古風で立派な料亭に「私」を案内します。驚いたことに、その料亭はかつて幸吉一家が暮らしていた呉服屋の建物だったのでした。感慨深い場所での食事でしたが、「私」は慣れない再会の興奮と酒の勢いでひどく酔ってしまい、感傷的な言葉を繰り返してしまいます。やがて幸吉の妹も合流しますが、「私」は自分が何を言ったか、何をしたか、ほとんど覚えていない有様でした。それでも幸吉兄妹は、そんな「私」を嫌な顔ひとつせず、優しく介抱してくれたのでした。妹の微笑は、どこか乳母つるの面影を感じさせ、夢のように美しく見えました。
翌日、二日酔いから覚めた「私」は、前夜の自分の醜態を恥じるとともに、幸吉兄妹の誠実さ、ひたむきさに心を打たれ、彼らのためにもう少ししっかりしなければ、と決意を新たにします。それから二日後、あの料亭で火事が起こります。「私」と幸吉兄妹は、かつての自分たちの家が燃えていく様子を静かに眺めていました。しかし、兄妹は過度に感傷に浸ることはなく、むしろその姿は凛として美しく見えました。その姿を見た「私」は、過去の感傷にばかり浸っている自分を愚かしく、恥ずかしく思うのでした。「君たちは、幸福だ。大勝利だ。そうして、もっと、もっと幸せになれる。」と心の中で呟きながら、彼らの未来を信じ、静かに力こぶを握るのでした。
小説「新樹の言葉」の長文感想(ネタバレあり)
太宰治の作品群の中で、「新樹の言葉」は、どこか特別な光を放っているように感じられます。もちろん、太宰特有の自己憐憫や弱さ、ダメ人間っぷりも顔を覗かせますが、それらを包み込むように、春の芽吹きを思わせるような清々しさ、未来へのほのかな希望が全体を覆っているのです。読後感がこれほど爽やかな太宰作品も珍しいのではないでしょうか。物語は、作家である「私」が、幼い頃自分を育ててくれた乳母の息子、つまり乳兄弟である幸吉と偶然再会するところから始まります。この出会いが、私の心を大きく揺さぶります。
主人公の「私」は、まさに太宰治自身を投影したかのような人物です。仕事で訪れた甲府の地で、感傷に浸ったり、酒に酔って醜態を晒したりと、その弱さや情けなさは、太宰作品でお馴染みの主人公像と重なります。特に、乳兄弟との再会に興奮し、過去の思い出に浸って涙ぐむ姿は、非常に人間臭く、共感を覚える部分でもあります。彼は、過去の美しい思い出、特に乳母つるへの強い思慕の念を抱き続けています。それは、彼にとって失われた楽園のようなものなのかもしれません。
その「私」の心の中で、乳母「つる」は非常に大きな存在として描かれています。実の母よりも長く一緒に暮らし、愛情を注いでくれた「育ての母」。彼女の存在は、「私」の人格形成に深く関わっていたことでしょう。彼女から教わったこと、読み聞かせてもらった物語、そして突然の別れ。それら全てが、「私」の中で美化され、聖域化されているかのようです。だからこそ、その息子である幸吉との再会は、「私」にとって単なる偶然ではなく、失われた過去との再接続のような、特別な意味を持ったのでしょう。つるの思い出は、私にとって温かくも切ない、心の拠り所なのです。
そして、その「つる」の息子である幸吉との再会シーンは、物語の大きな転換点となります。見知らぬ郵便配達員からの唐突な問いかけ、そして幸吉本人の訪問。最初は戸惑いながらも、乳兄弟という関係性が判明した瞬間の「私」の喜びようは、読んでいるこちらまで嬉しくなるほどです。「私」にとって、それは過去の美しい記憶が一気に蘇るような、感動的な出来事だったに違いありません。この予期せぬ出会いが、停滞していたかもしれない「私」の心に、新たな波紋を投げかけます。
幸吉と、そして後に登場するその妹。彼らは、「私」とは対照的な存在として描かれています。両親を早くに亡くし、おそらくは多くの苦労を重ねてきたであろう兄妹ですが、彼らからは悲壮感や過去への執着はあまり感じられません。むしろ、現実をしっかりと見据え、地に足をつけて生きている印象を受けます。特に、かつて自分たちが住んでいた家が料亭になり、さらにそれが火事で焼失するという出来事に対しても、彼らは過度な感傷を見せず、凛とした態度を崩しません。この強さ、潔さが、「私」の目には眩しく映ります。
料亭での場面は、この物語の中でも特に印象深いシーンの一つです。そこは、幸吉兄妹にとってはかつての「家」であり、多くの思い出が詰まった場所のはずです。そんな場所で、乳兄弟である「私」と再会し、酒を酌み交わす。幸吉がこの場所を選んだことには、特別な思いがあったのかもしれません。過去との対峙、あるいは過去への決別といった意味合いもあったのでしょうか。しかし、その感慨深い場面で、「私」は酔って感傷に溺れてしまいます。
この料亭での「私」の酔態は、彼の弱さや未熟さを象徴しているようです。過去の美しい思い出や乳母への思慕、そして現在の自分の不甲斐なさなどが入り混じり、感情が溢れ出してしまったのでしょう。しかし、そんな「私」を、幸吉兄妹は静かに、そして優しく受け止めます。彼らは、「私」の感傷的な言葉に同調するでもなく、かといって突き放すでもなく、ただそこにいてくれる。この兄妹の落ち着いた態度は、「私」の感傷癖をより際立たせると同時に、彼らの精神的な成熟を感じさせます。
幸吉の妹の存在も、物語に彩りを加えています。彼女の描写は多くありませんが、その微笑みが乳母つるに似ている、という記述は重要です。「私」にとって、彼女は過去の象徴であるつると、未来への希望をつなぐ存在のように見えたのかもしれません。兄妹が持つ、過去にとらわれずに前を向く力は、妹の存在によって、より柔らかく、温かいものとして伝わってきます。彼女の静かな佇まいは、兄である幸吉の強さとはまた違った種類の、しなやかな強さを感じさせます。
物語のクライマックスとも言えるのが、料亭の火事の場面です。かつて幸吉兄妹の家だった建物が、炎に包まれ焼失していく。これは、過去の物理的な象徴が完全に消え去ることを意味します。普通なら、ここで感傷に浸ってもおかしくない状況です。しかし、幸吉兄妹は違いました。彼らは燃え盛る炎を前にしても、動揺したり、嘆き悲しんだりすることなく、ただ静かに、凛としてその光景を見つめています。それは、過去への執着から解放され、未来へ向かって歩み出す決意の表れのようにも見えます。
この幸吉兄妹の姿は、「私」に大きな衝撃を与えます。過去の思い出に浸り、感傷に溺れがちな自分自身の姿を、彼らの潔い態度を通して見つめ直すことになるのです。「私」は、彼らの姿に「大勝利だ」と心の中で喝采を送ります。それは、過去の不幸や苦労に打ち勝ち、現在を力強く生きる兄妹への賛辞であり、同時に、自分自身の弱さに対する深い省察でもあります。この場面で、「私」は感傷主義からの脱却の必要性を痛感し、新たな一歩を踏み出す決意を固めたのではないでしょうか。
この物語が持つテーマの一つは、やはり「過去との向き合い方」でしょう。「私」のように過去の美しい記憶に浸り、感傷に溺れる生き方と、幸吉兄妹のように過去は過去として受け止め、現在と未来に目を向けて力強く生きる生き方。太宰治は、後者の生き方を肯定的に描いているように思えます。もちろん、過去を完全に切り捨てるのではなく、それを受け入れた上で、前へ進むことの大切さを示唆しているのではないでしょうか。感傷は時に美しいけれど、それに囚われすぎてはいけない、というメッセージが伝わってきます。
そしてもう一つ、この作品からは「再生と希望」というテーマも読み取れます。両親を失い、家も失った幸吉兄妹ですが、彼らは決して打ちひしがれてはいません。むしろ、その逆境を乗り越えたことで得た強さや潔さが、彼らを輝かせています。火事によって過去の象徴が消え去った後、彼らの未来には、きっと新たな希望が待っている。そんな予感を抱かせます。「私」もまた、彼らの姿に触発され、自己憐憫から抜け出し、「もう少し偉くなりたい」と前向きな気持ちを抱きます。これは、太宰作品には珍しい、明確な希望の描写と言えるでしょう。
太宰治の他の多くの作品、例えば「人間失格」や「斜陽」などに見られる破滅的な暗さやデカダンスとは、「新樹の言葉」は一線を画しています。もちろん、「私」のダメ人間っぷりには太宰らしさが表れていますが、作品全体を覆う空気は驚くほど明るく、肯定的です。これは、太宰治自身の人生のある時期の心境を反映しているのかもしれませんし、あるいは、彼が理想としたかった生き方の一つの形を描いたのかもしれません。自身の経験(乳母に育てられたことなど)を色濃く反映させつつも、それを感傷的な物語に終わらせず、未来への希望へと繋げている点に、この作品の独自性があると感じます。
「新樹の言葉」の魅力は、その文体にもあります。深刻になりがちなテーマを扱いながらも、筆致はどこか軽やかで、読みやすいのです。甲府の春先の風景描写や、登場人物たちの会話には、瑞々しさが感じられます。「私」の心情描写も、いつもの太宰作品のように粘着質になる一歩手前で踏みとどまり、どこか客観的な視点も保たれているように思います。この軽やかさが、作品全体の爽やかな読後感に繋がっているのでしょう。
この物語を読み終えたとき、心に残るのは、一種の清々しさです。過去の感傷に別れを告げ、前を向いて歩き出すことへの静かな決意。幸吉兄妹が見せた潔さ、そしてそれに心を動かされた「私」の姿。それは、現代を生きる私たちにとっても、決して他人事ではないメッセージを含んでいます。私たちは皆、多かれ少なかれ過去の出来事に影響を受けながら生きていますが、それに囚われすぎることなく、未来へ向かって歩み続けることの大切さを、この作品はそっと教えてくれるような気がします。太宰治の新たな一面に触れられる、貴重な一編だと思います。
まとめ
太宰治の短編小説「新樹の言葉」は、作家である「私」が、偶然にも幼い頃の乳母の息子、幸吉と再会する物語です。この出会いをきっかけに、「私」は自身の感傷的な心と向き合い、過去にとらわれずに力強く生きる幸吉兄妹の姿に心を打たれます。
物語のハイライトは、かつて幸吉兄妹の家だった料亭が火事で焼失する場面です。過去の象徴が消え去るのを目の当たりにしながらも、兄妹は悲嘆にくれることなく、凛とした態度を崩しません。その姿を見た「私」は、自らの感傷癖を恥じ、彼らの生き方を「大勝利だ」と心の中で称えます。
この作品は、太宰治の他の作品とは異なり、暗さや退廃的な雰囲気よりも、爽やかさや未来への希望を感じさせる点が特徴的です。過去との向き合い方、そして逆境を乗り越えて前向きに生きることの肯定が、軽やかな筆致で描かれています。
読後には、まるで春の新しい緑のような清々しさが残ります。太宰治の意外な一面に触れることができ、現代に生きる私たちにも、過去にとらわれず未来へ向かうことの大切さを教えてくれるような、心に残る一編です。ぜひ一度、手に取ってみてはいかがでしょうか。




























































