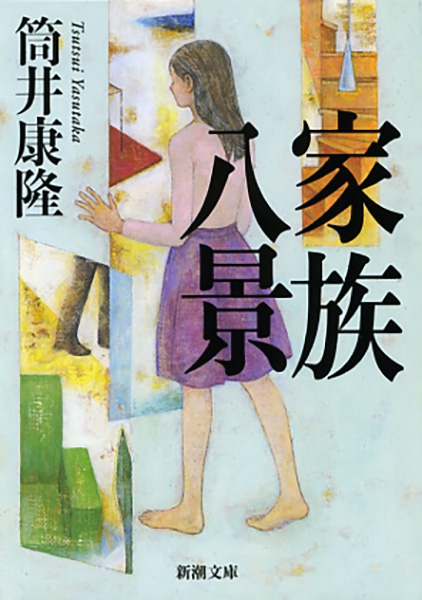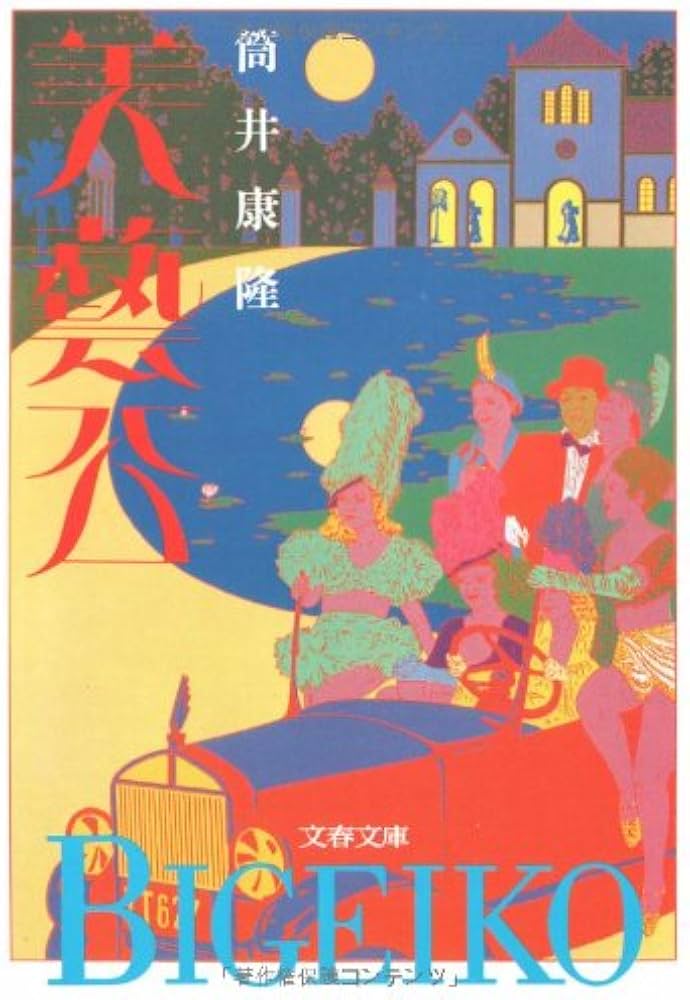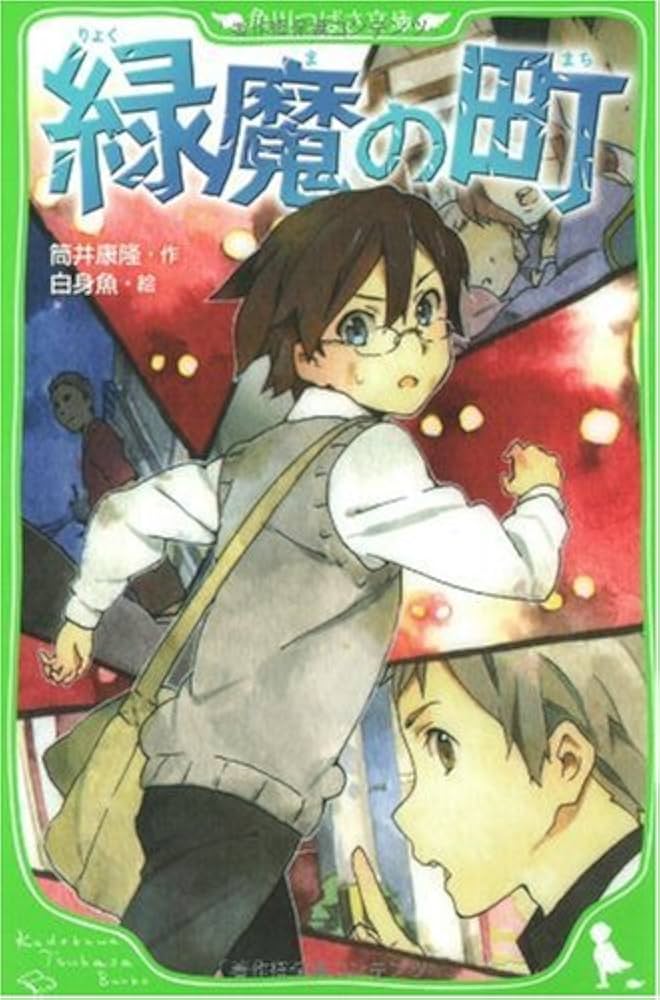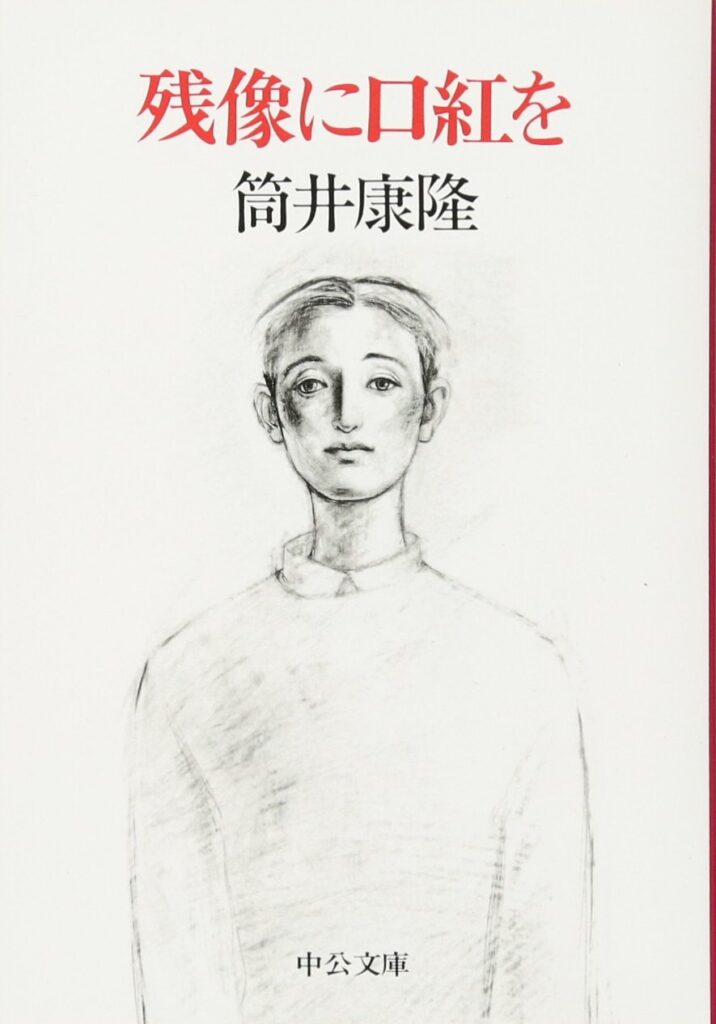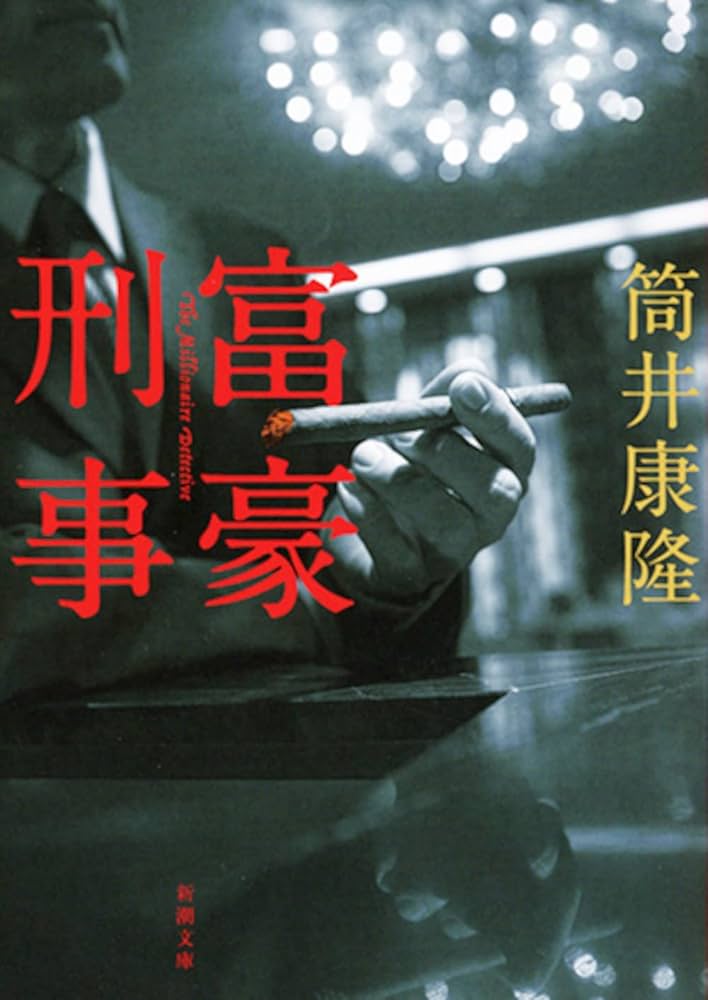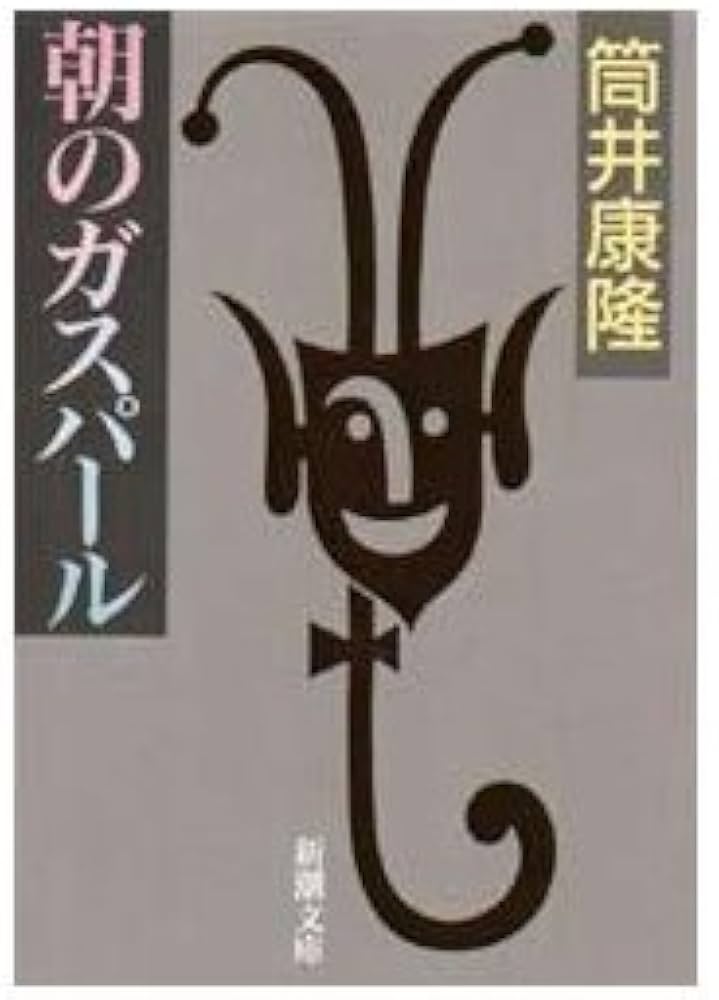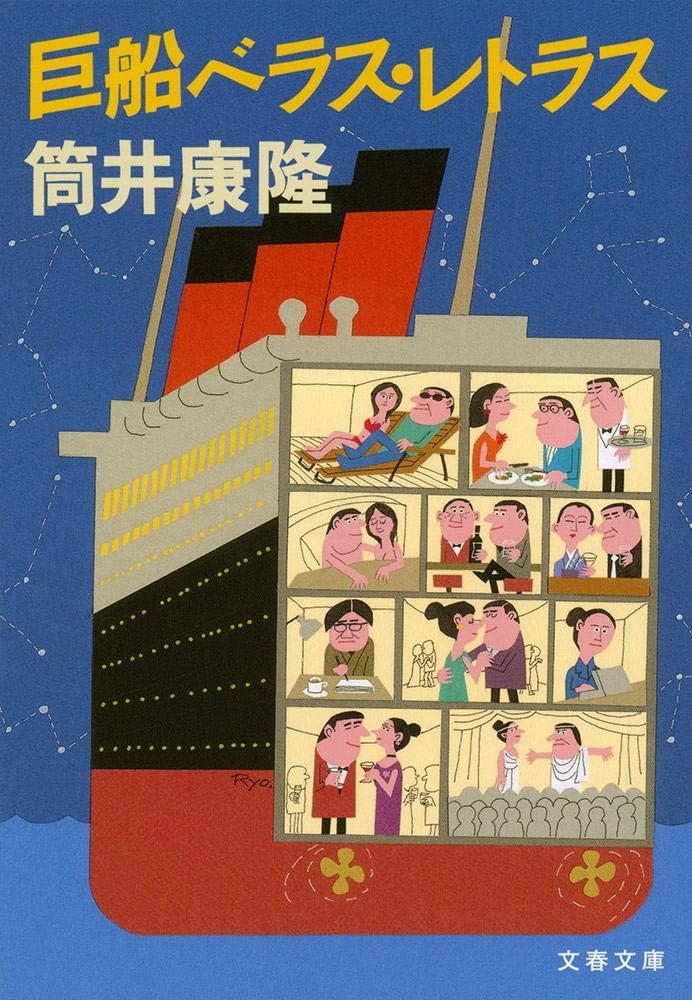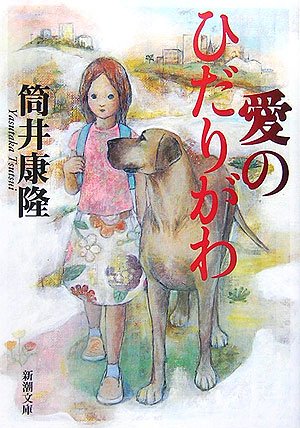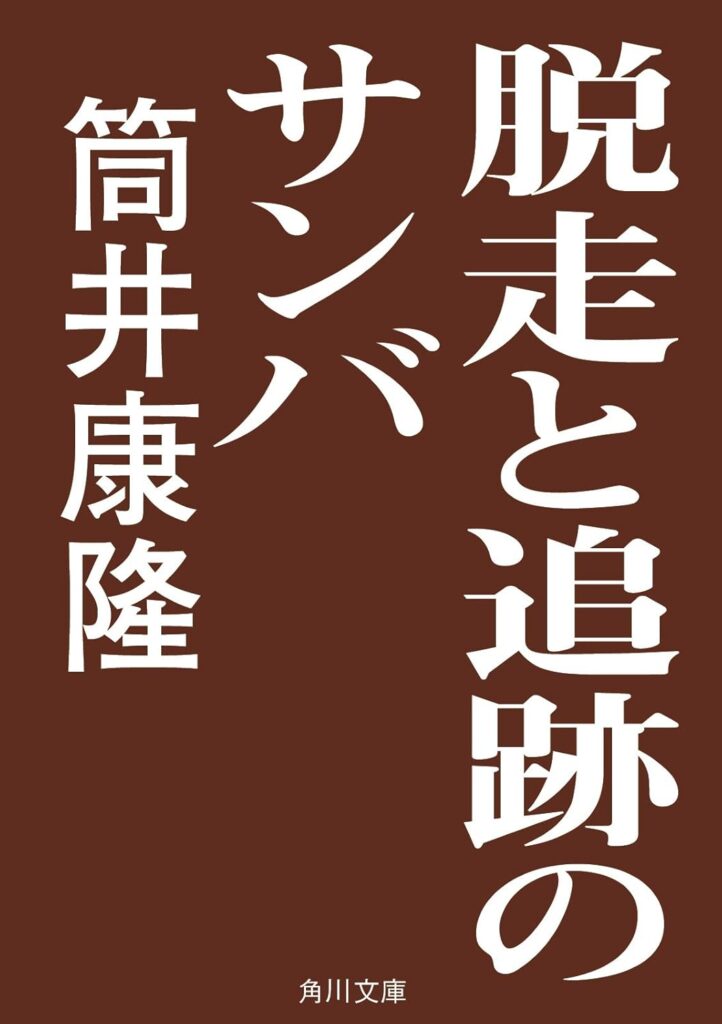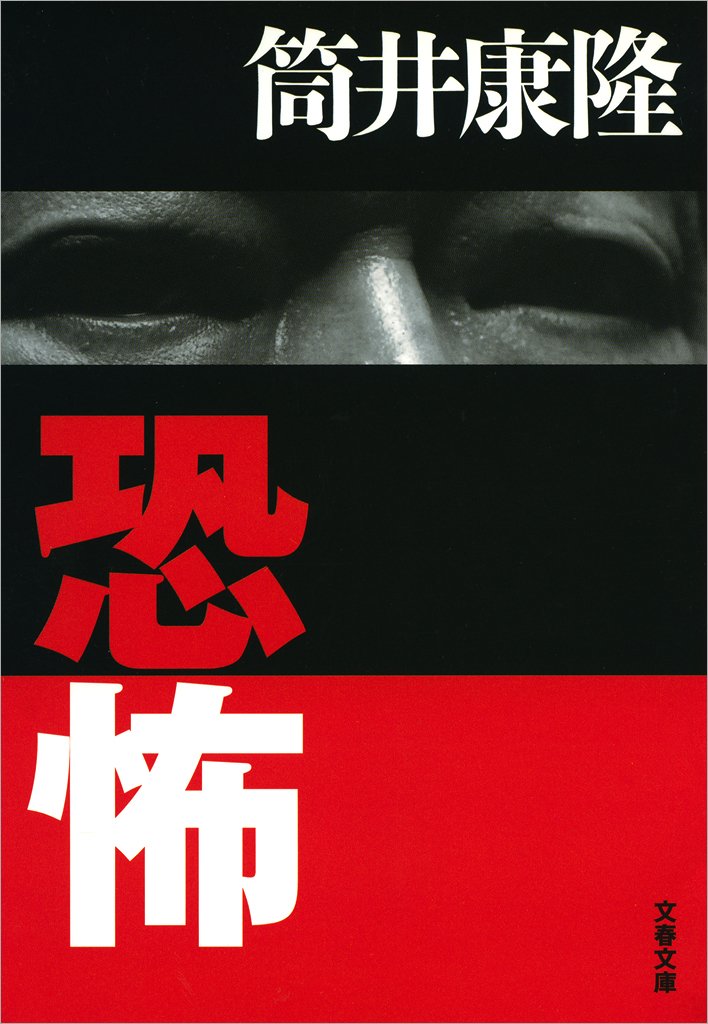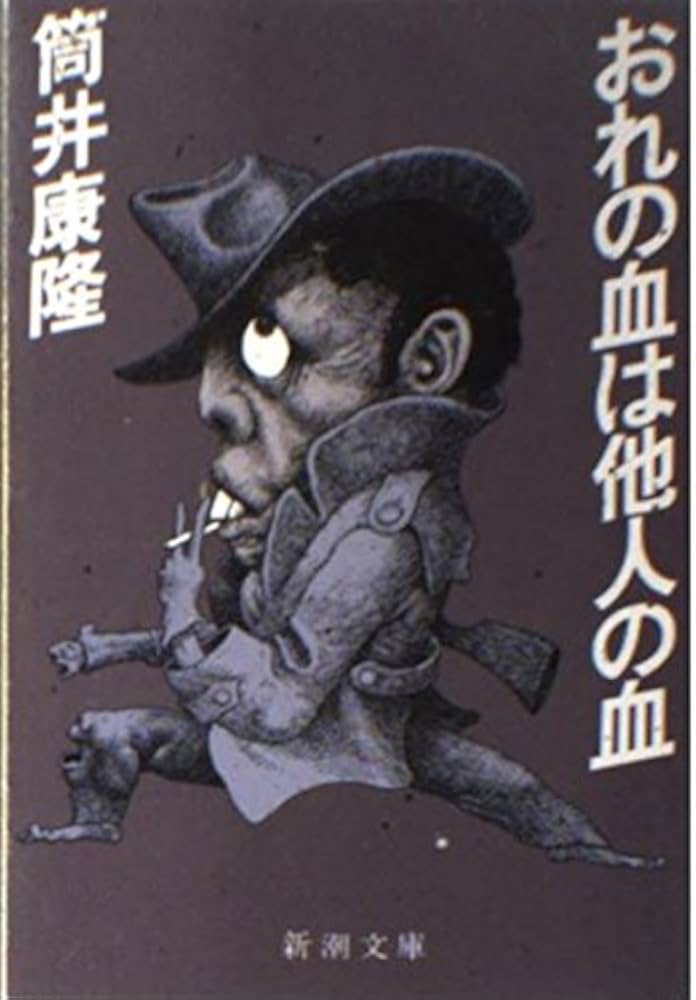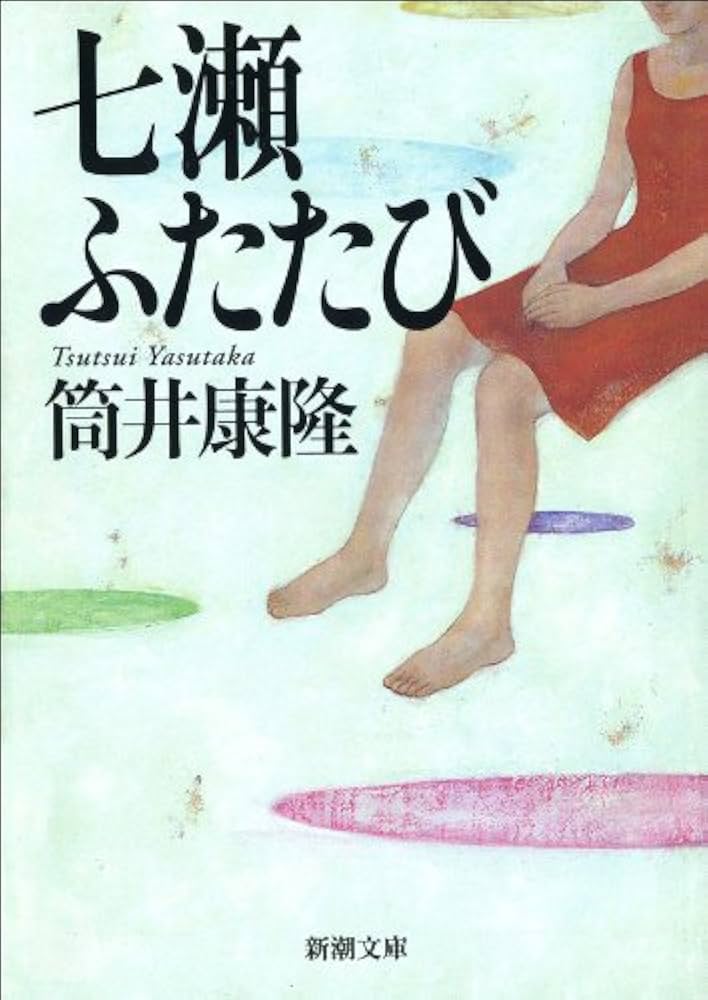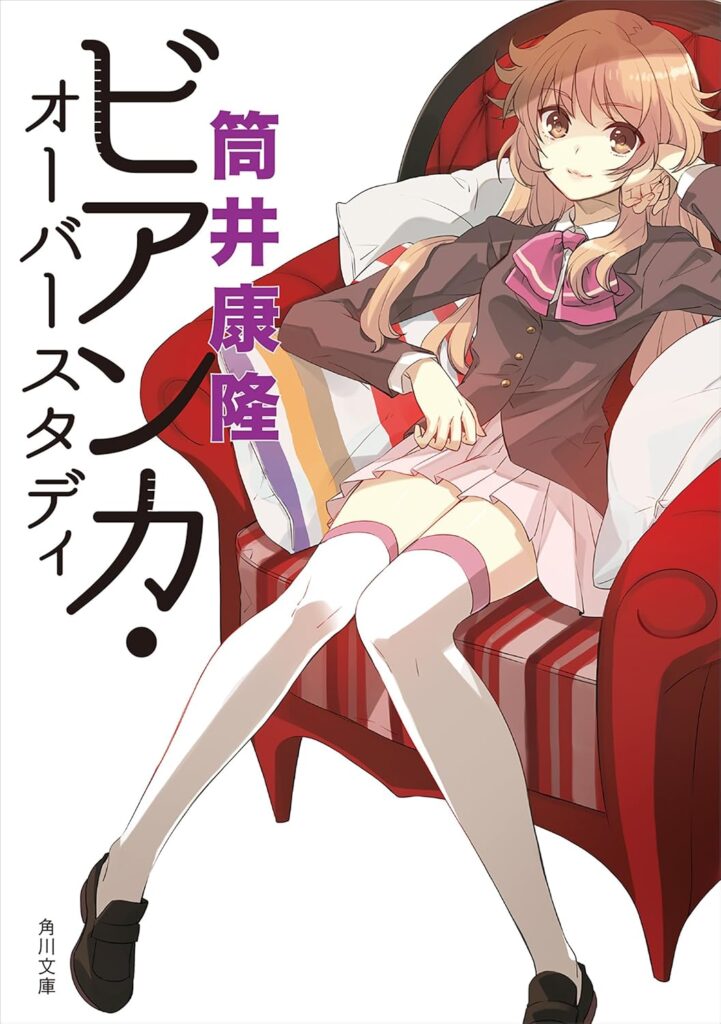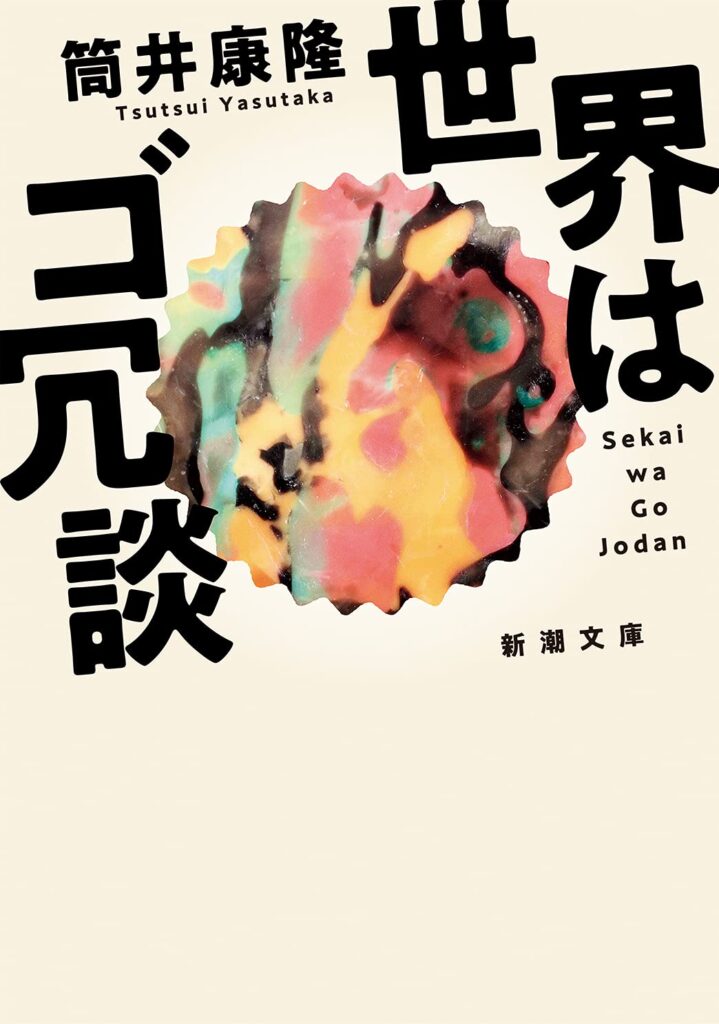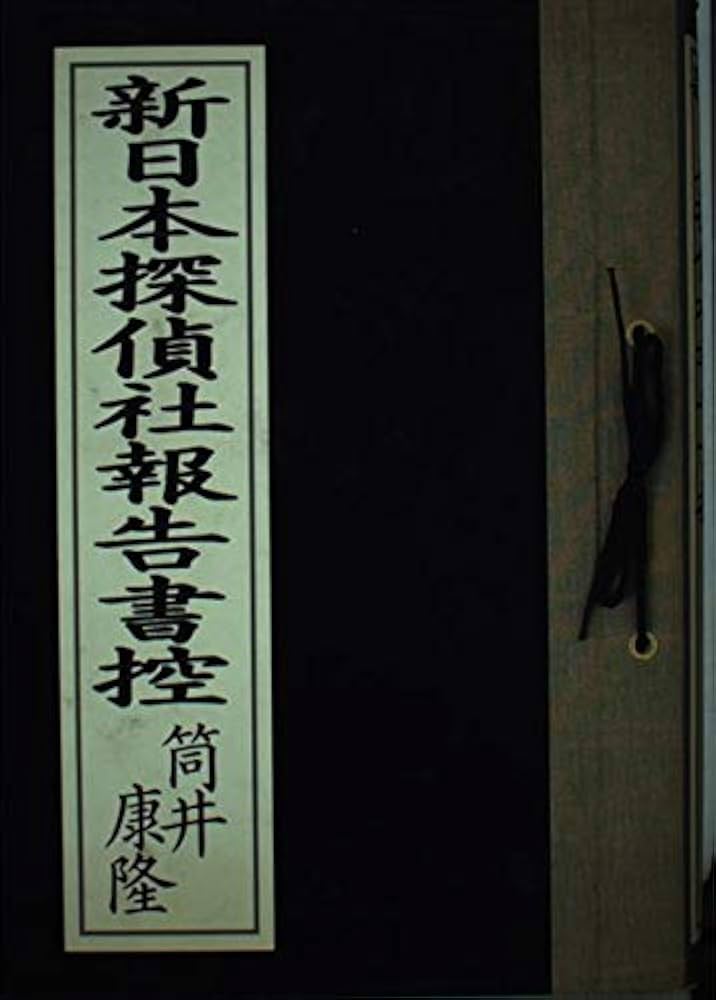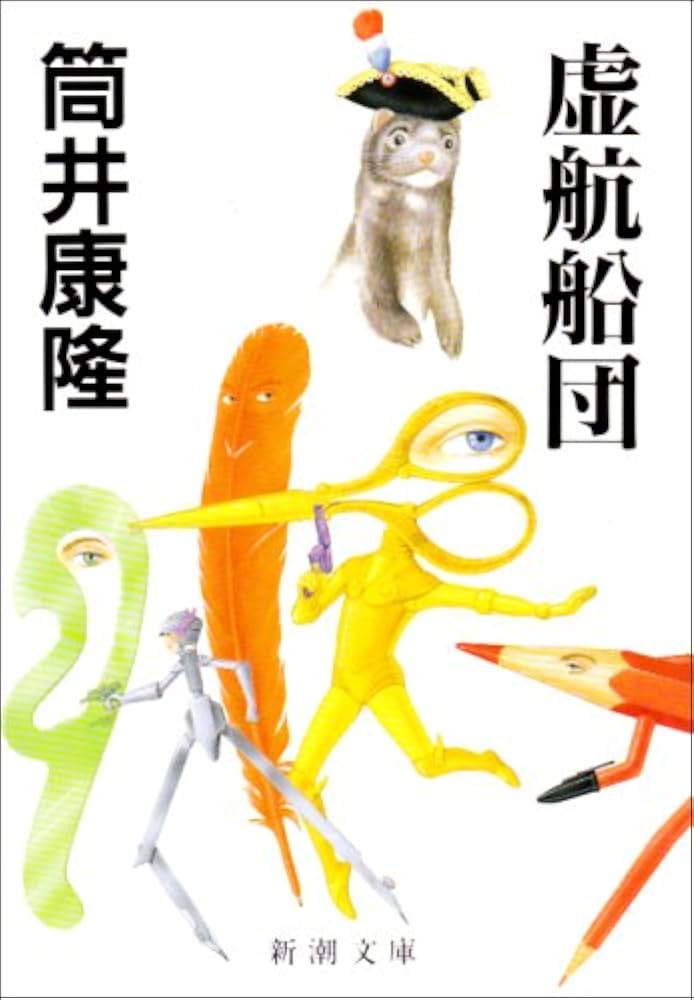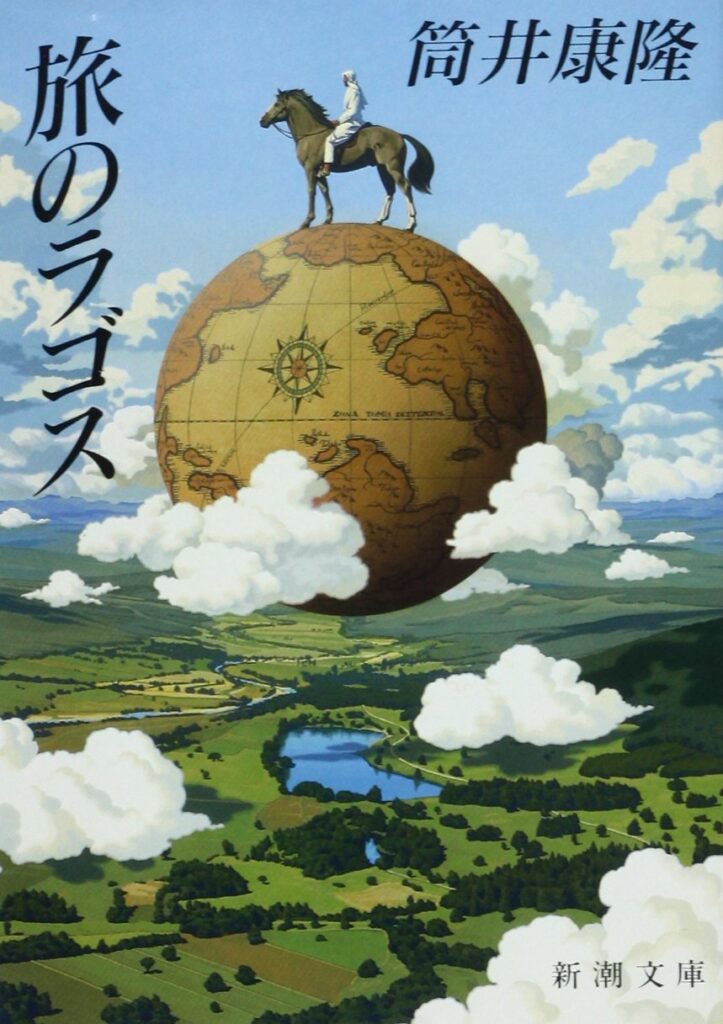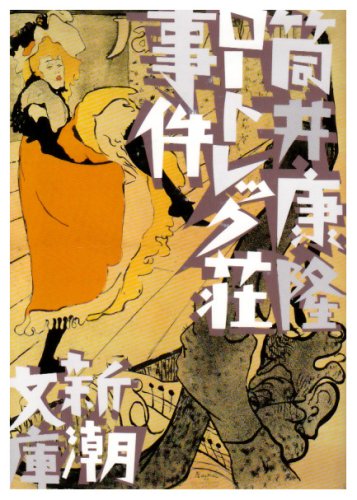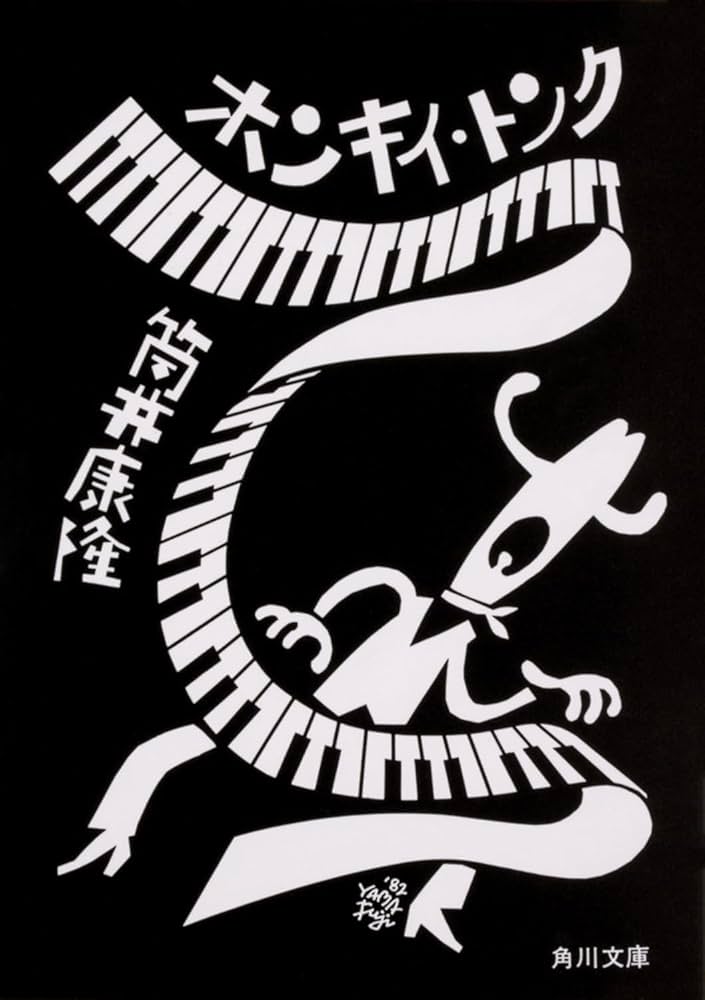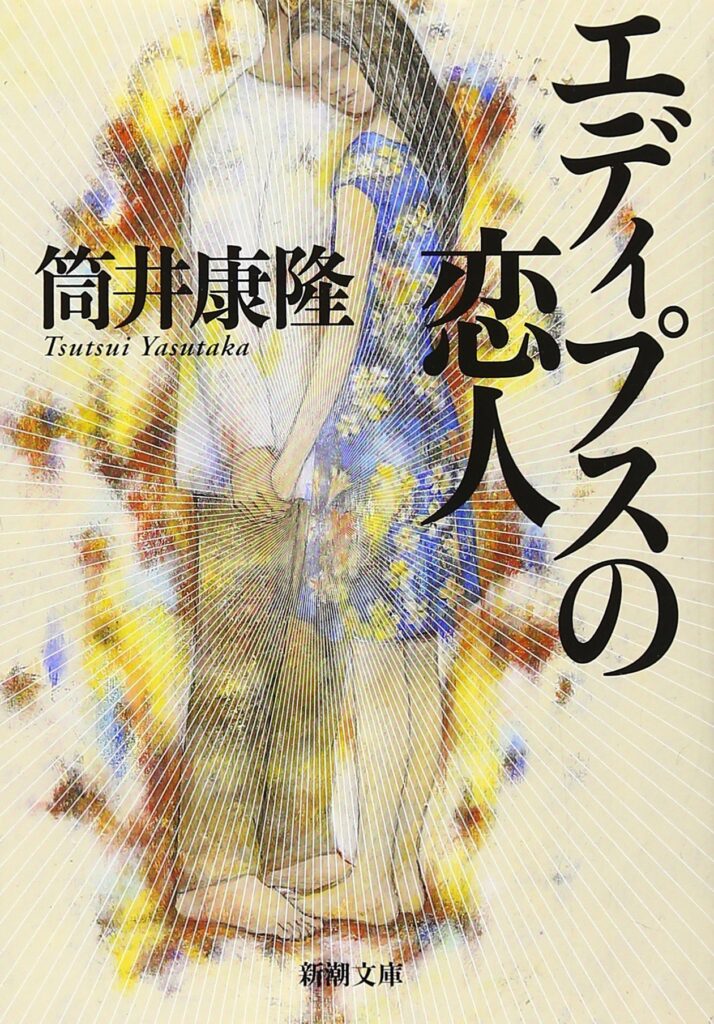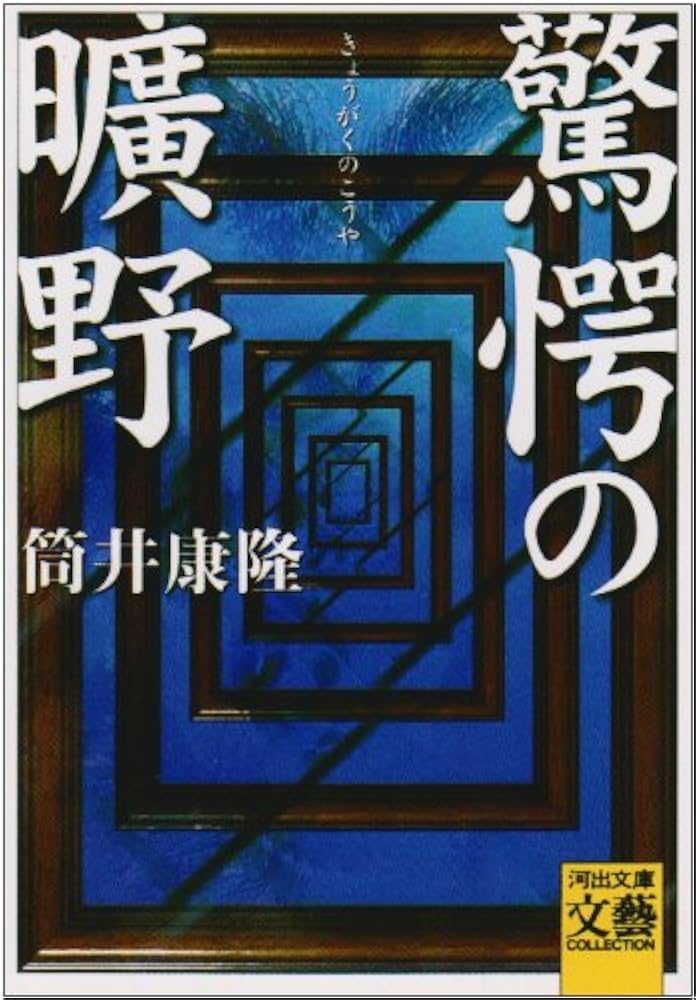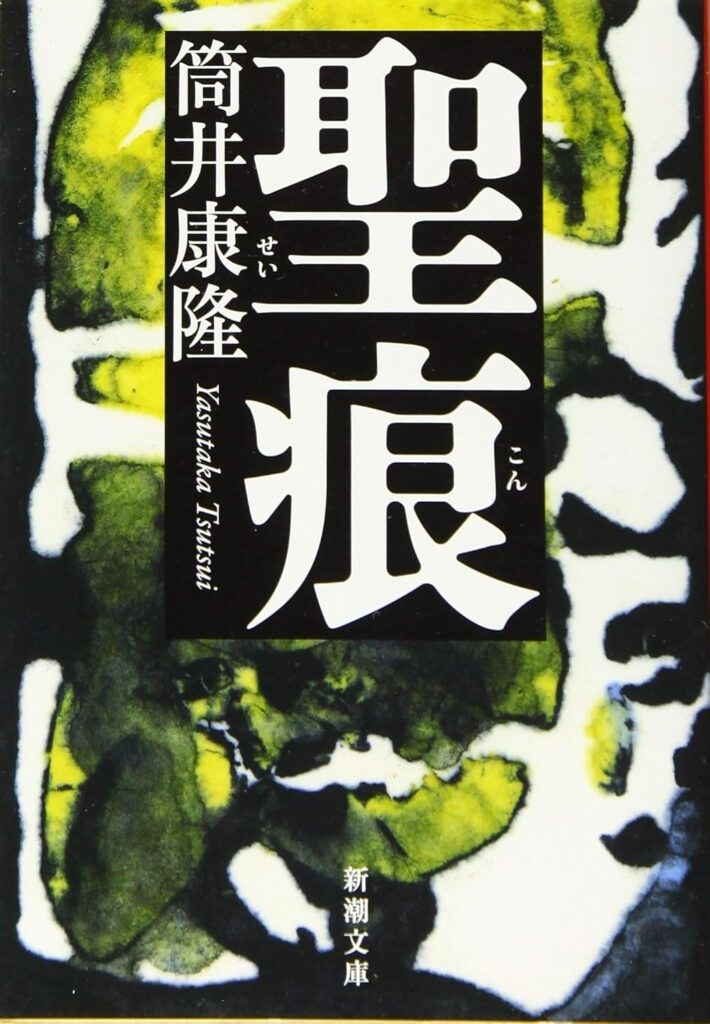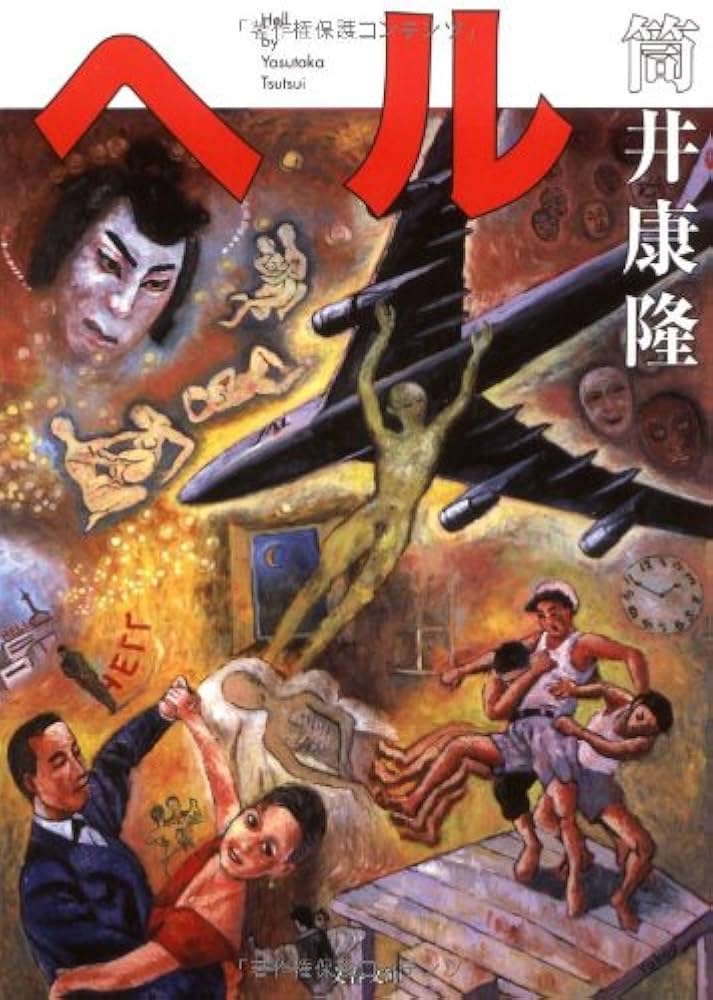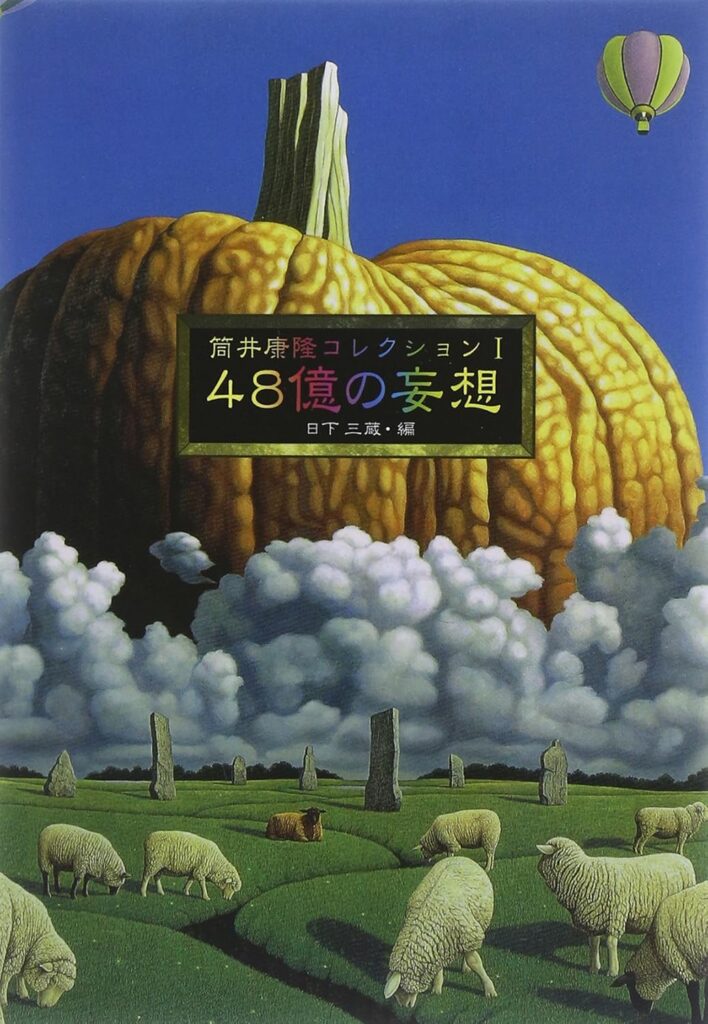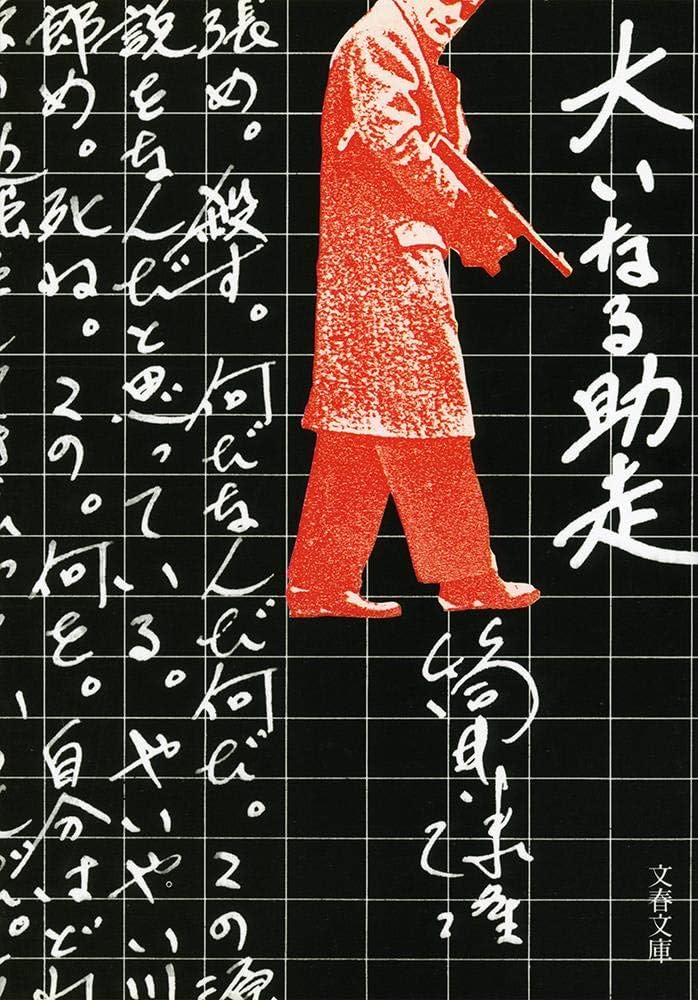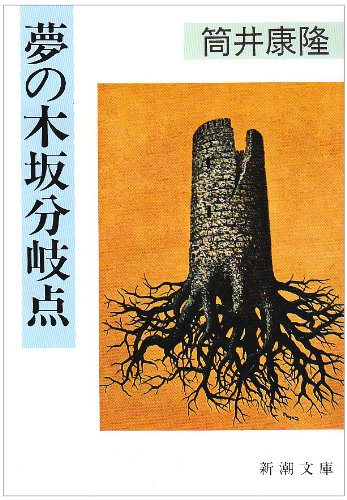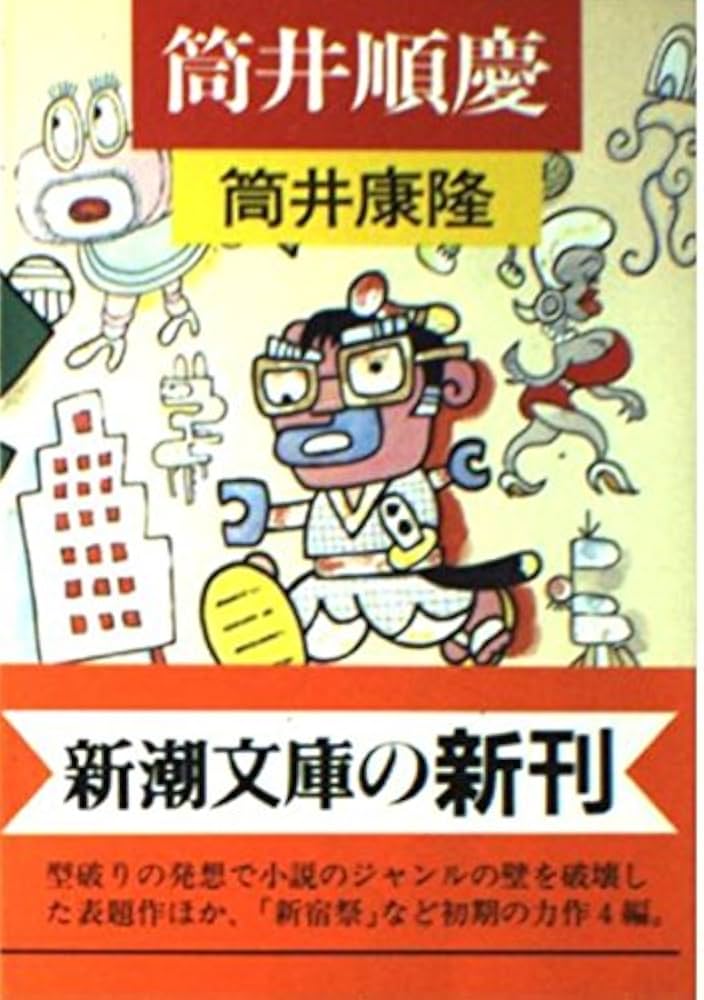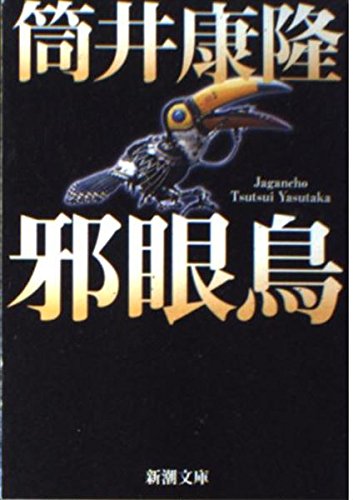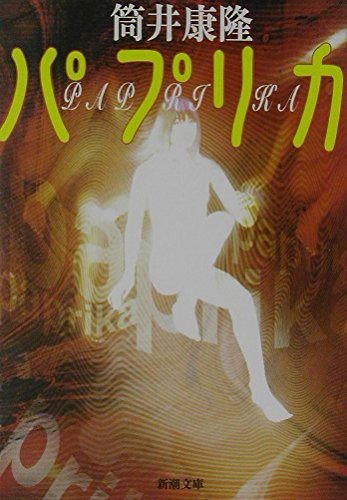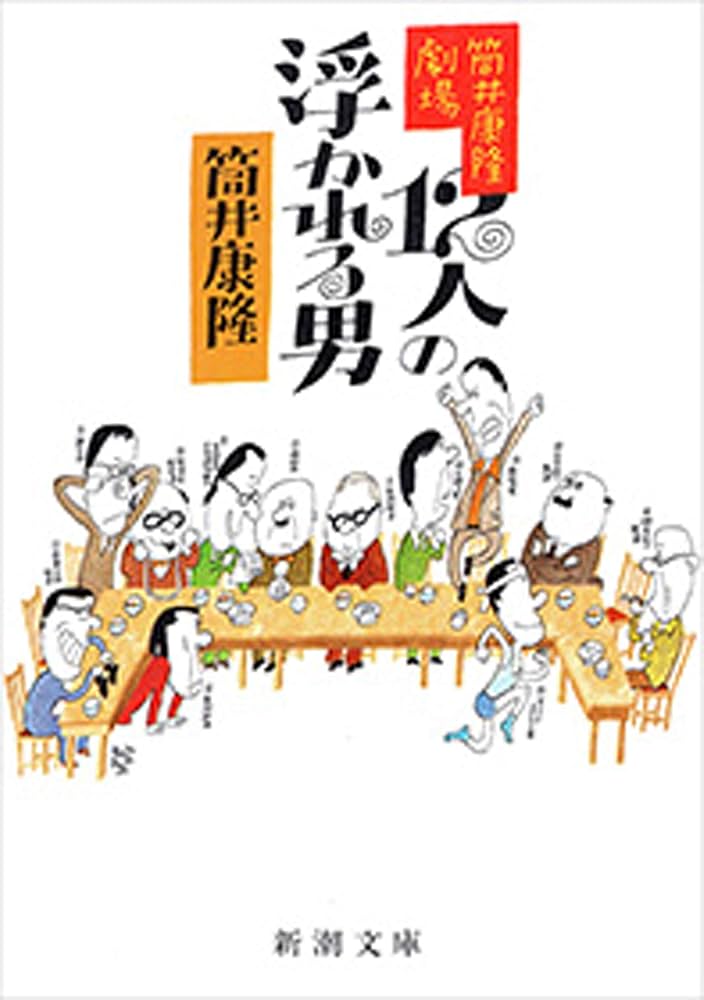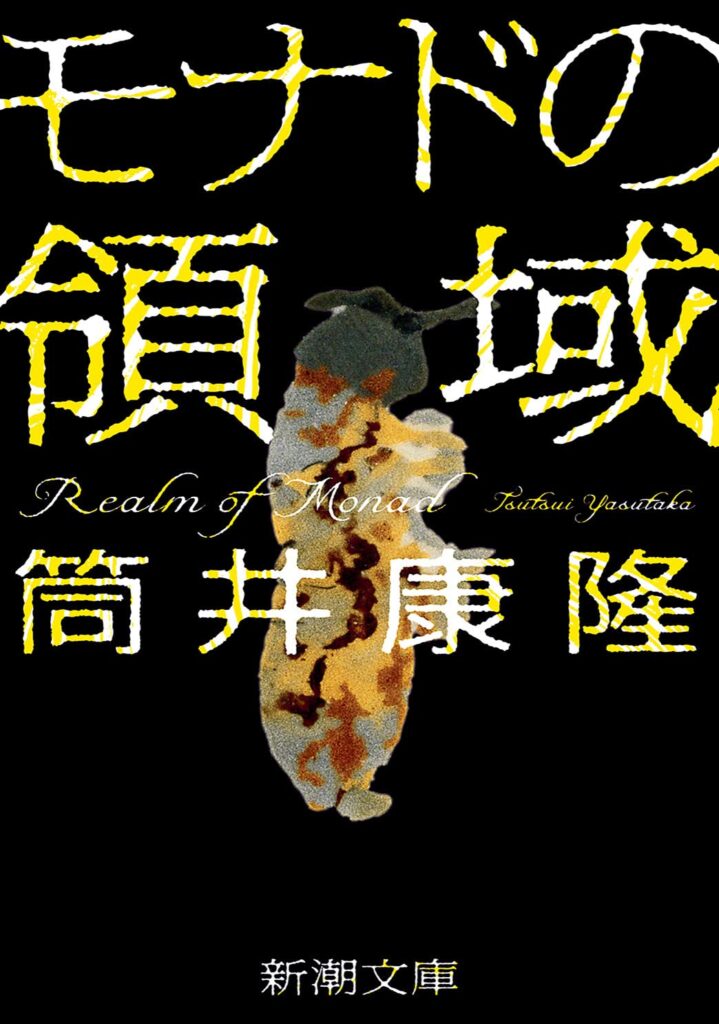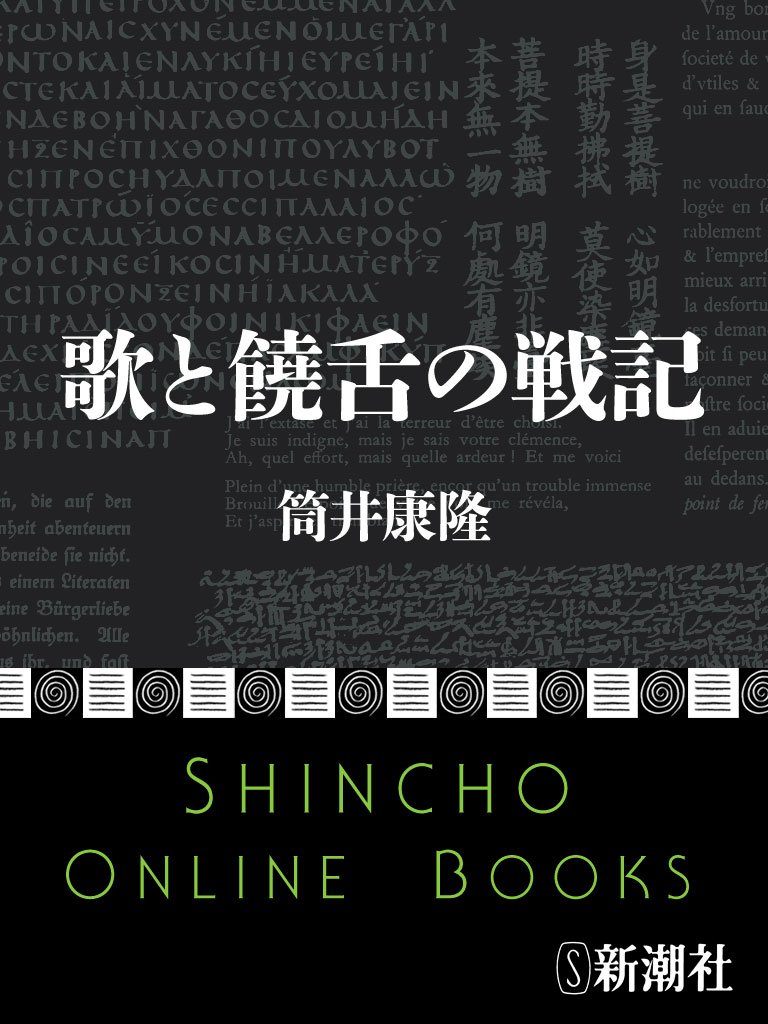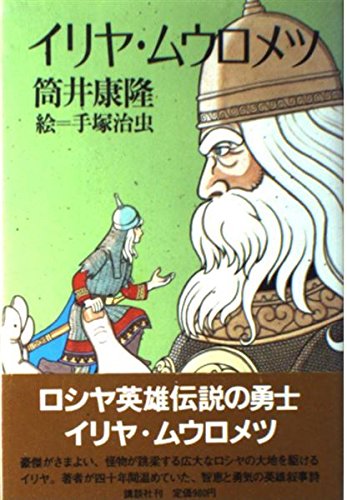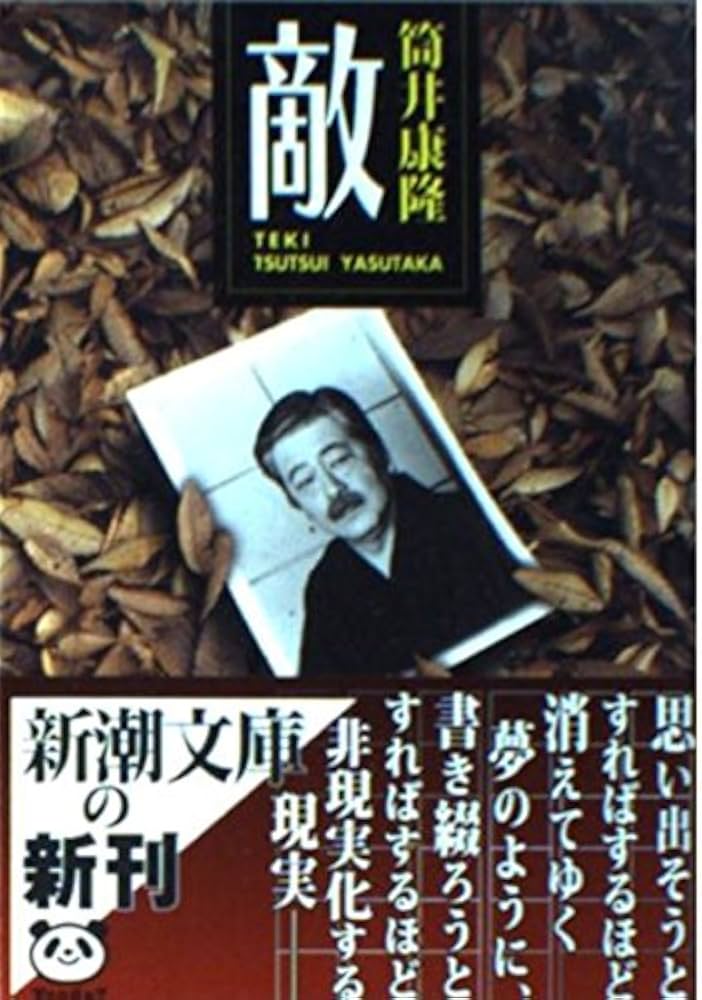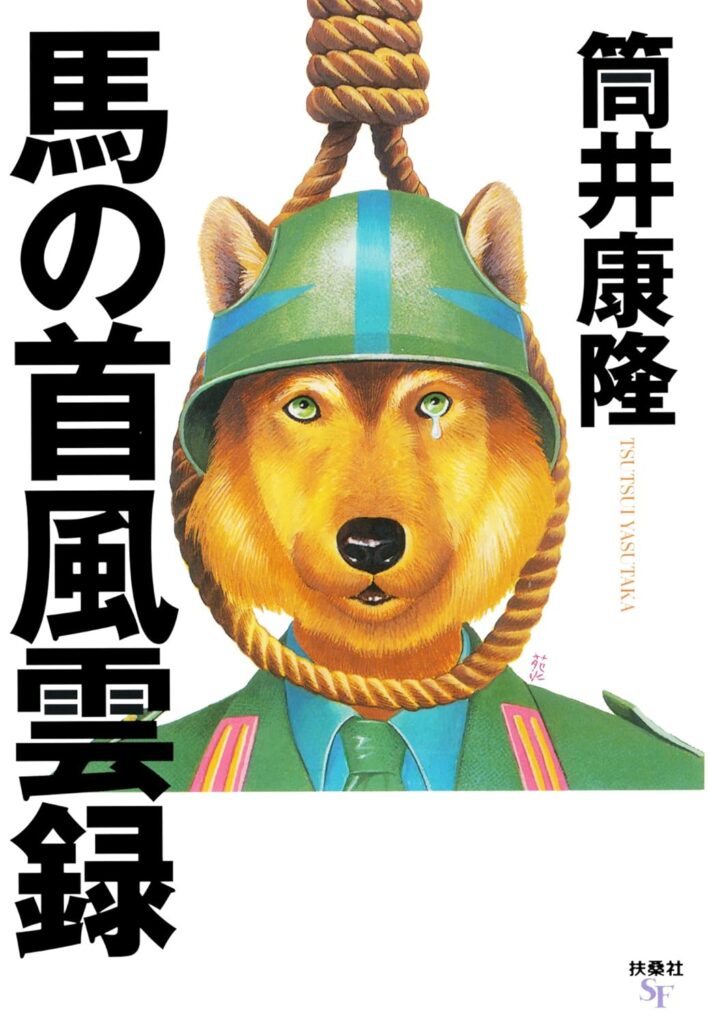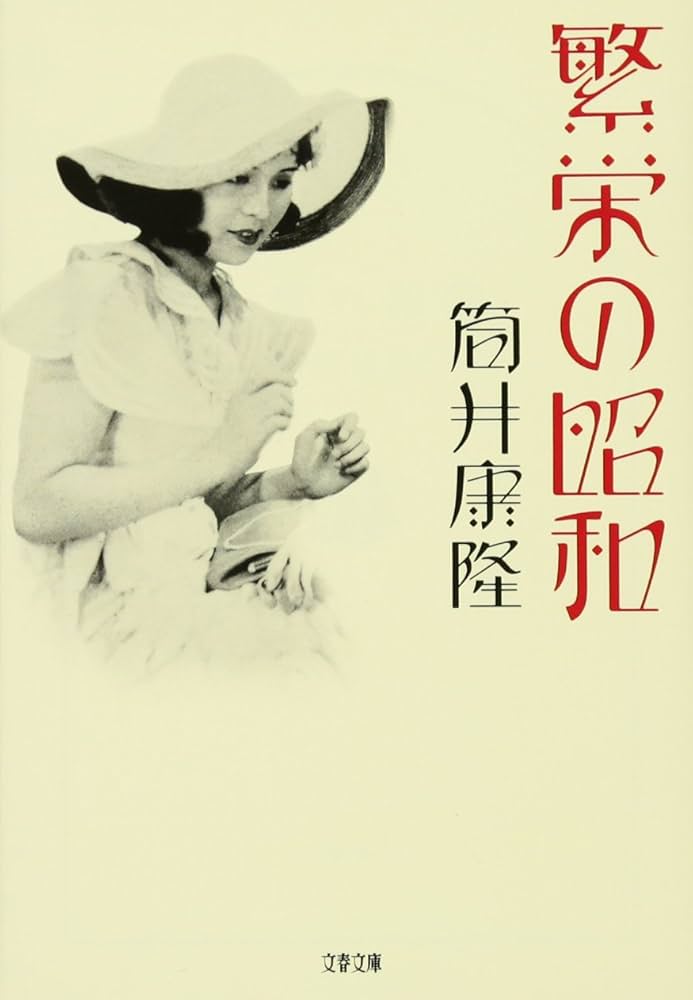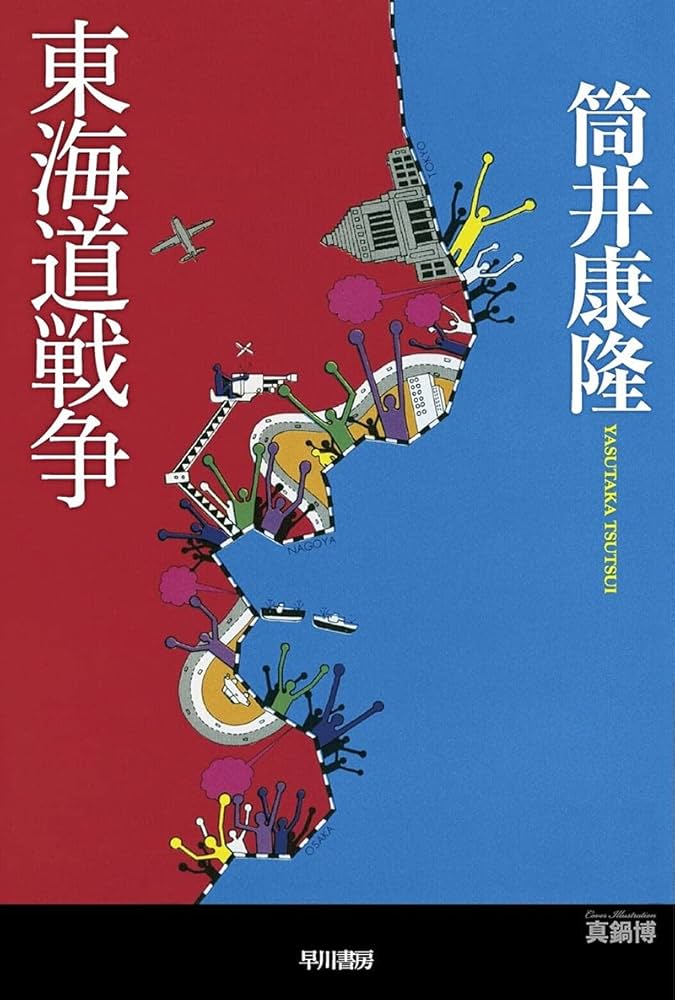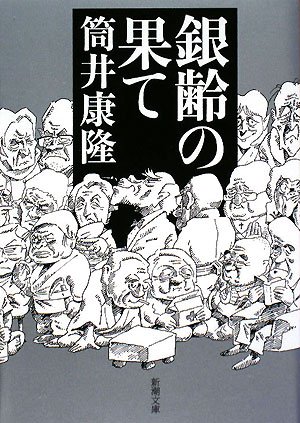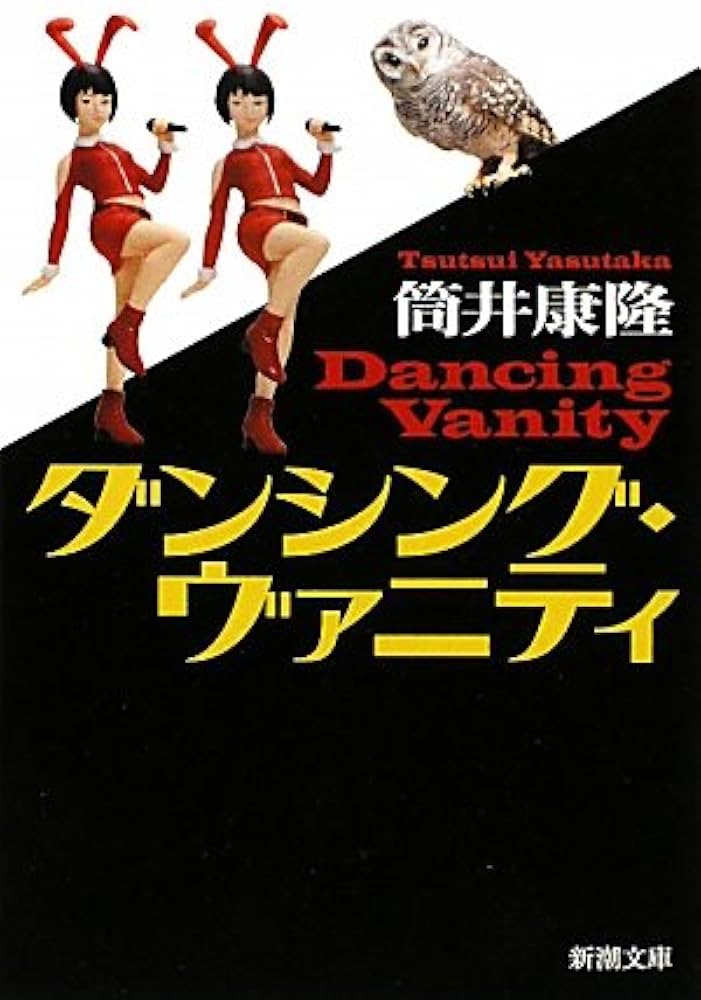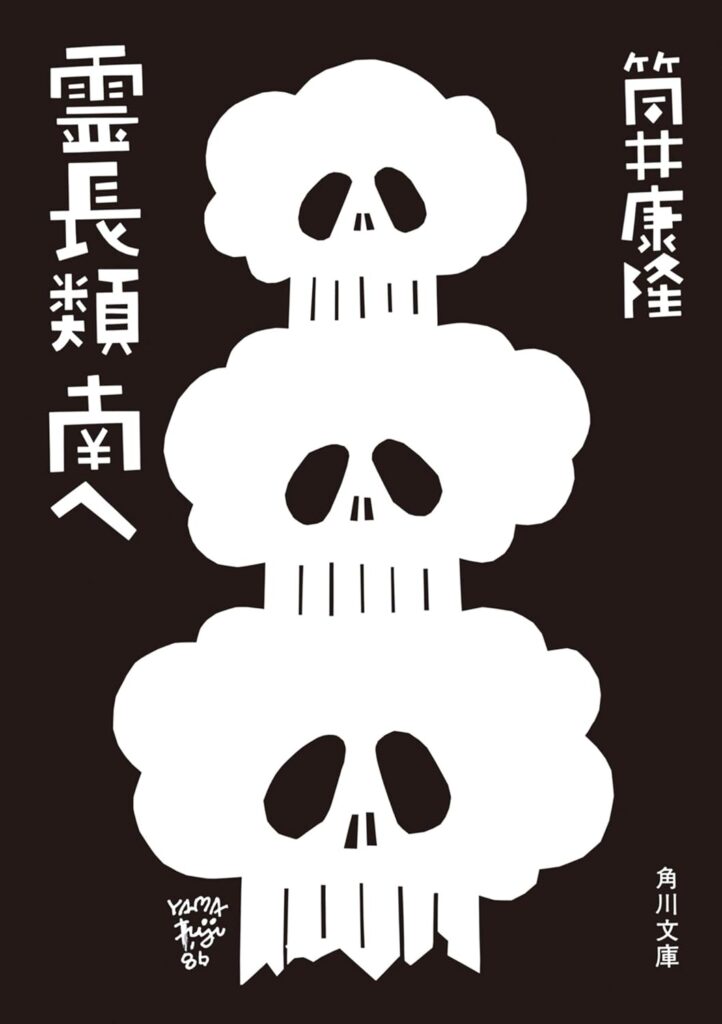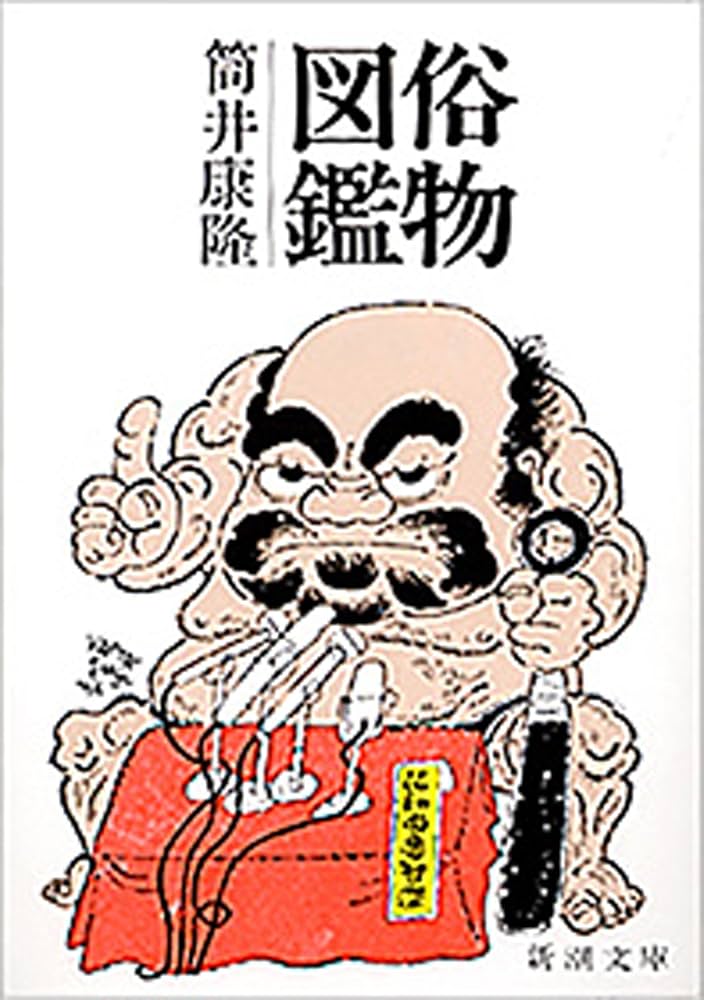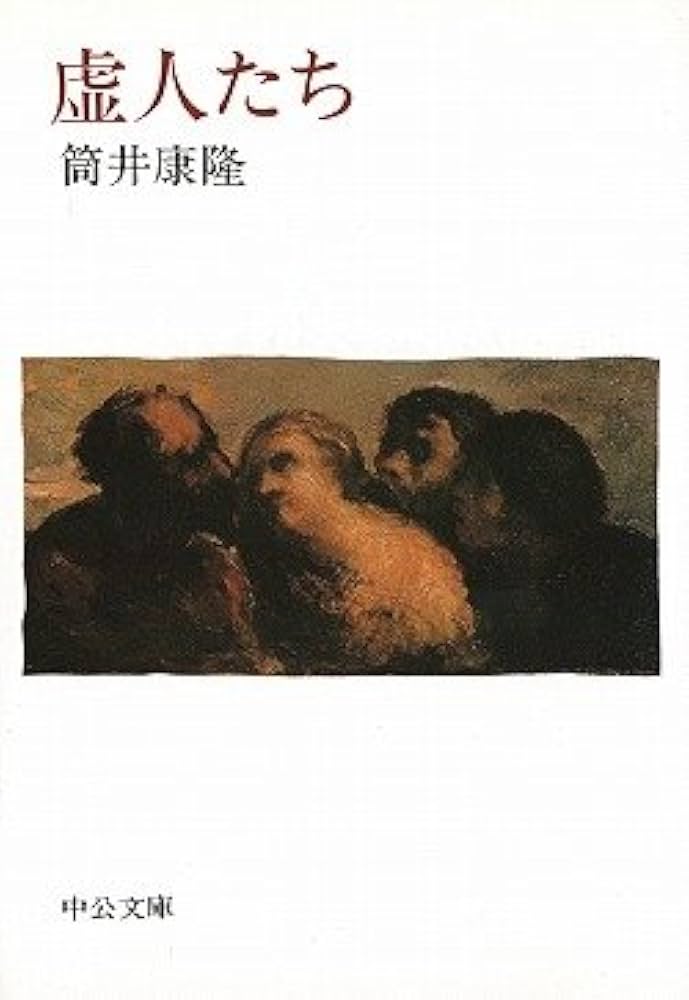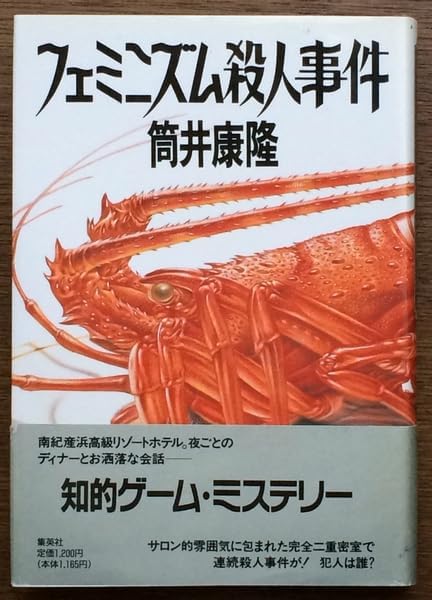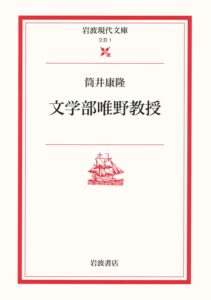 小説「文学部唯野教授」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「文学部唯野教授」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この作品は、大学という組織の奇妙な実態と、そこで繰り広げられる人間模様を痛烈に描き出した傑作です。一見すると難しそうな文学理論が、驚くほど分かりやすく、そして物語のスパイスとして絶妙に効いている点も見逃せません。
主人公である唯野教授の置かれた状況は、まさに綱渡りそのもの。彼の秘密がいつ白日の下に晒されるのか、読んでいるこちらもハラハラさせられます。彼の視点を通して語られる大学の日常は、滑稽でありながら、どこか私たちの身の回りにもありそうなリアリティを帯びています。
この記事では、物語の魅力的な筋立てから、物語の核心に触れる考察まで、深く掘り下げていきます。まだ読んだことのない方はもちろん、かつて読んだけれど内容を忘れてしまったという方も、ぜひこの機会に「文学部唯野教授」の世界に浸ってみてください。
小説「文学部唯野教授」のあらすじ
物語の主人公は、若くして早治大学文学部の教授となった唯野仁(ただの じん)。彼はその名の通り「ただの人」を装っていますが、実は大きな秘密を抱えています。それは、「野田耽二(のだ たんじ)」というペンネームで、新進気鋭の純文学作家として活動していることでした。このペンネームが本名のアナグラムになっているのも、作者の仕掛けた遊び心でしょう。
唯野が何よりも恐れているのは、この二重生活が学内の、特に恩師である蟻巣川教授に知られることでした。学者が専門外の活動で世間の注目を浴びることを極端に嫌う蟻巣川教授に秘密が発覚すれば、自身の学究生活は終わりだと考えていたのです。この恐怖が、彼の言動すべてを縛り付けていきます。
物語は、唯野が立智大学で行う文芸批評論の講義と、早治大学でのグロテスクとも言える日常が交互に描かれる形で進みます。講義では小難しい文学理論が分かりやすく語られ、それが彼の身に降りかかる出来事と皮肉な形で結びついていくのです。
教授会の形骸化した議論、同僚たちの足の引っ張り合い、そして友人からの厄介な頼みごと。唯野は、正体がバレるかもしれないという絶え間ない不安の中で、これらの複雑な人間関係を乗り切っていかなければなりませんでした。果たして彼は、平穏な(?)大学教授と、注目される小説家という二つの顔を両立させることができるのでしょうか。
小説「文学部唯野教授」の長文感想(ネタバレあり)
この物語を手にとってまず感じるのは、大学という組織の描写の生々しさではないでしょうか。私が学生だった頃に垣間見た、あるいは伝え聞いた教授たちの世界の裏側が、これでもかというほど赤裸々に、そしてコミカルに描かれています。それは単なる作り話ではなく、ある種の真実を捉えているように感じられてなりません。
主人公の唯野仁教授は、まさにこの奇妙な世界の渦中にいます。教授としての仮面と、小説家「野田耽二」としてのもう一つの顔。この危ういバランスの上に成り立つ彼の日常は、読んでいるこちらまで落ち着かない気持ちにさせます。彼の感じるプレッシャーや焦燥は、ページをめくるごとにひしひしと伝わってきました。
物語の大きな魅力の一つは、大学内部の権力闘争や人間関係の描写です。特に唯野の恩師である蟻巣川教授は、強烈な個性を持つ人物として描かれています。学者の本分から外れることを何よりも嫌い、その影響力は絶対的。唯野が彼に抱く恐怖は、この物語全体の緊張感を支える重要な柱となっています。
そして、この物語を唯一無二のものにしているのが、各章で展開される文学理論の講義です。印象批評からポスト構造主義まで、多岐にわたる理論が、これ以上ないほど平易な言葉で解説されます。大学の講義と聞くと退屈なイメージを持つかもしれませんが、唯野教授のそれは、知的好奇心を大いに刺激するエンターテインメントになっています。
さらに巧みなのは、その講義内容が、唯野自身の置かれた状況や物語の展開を皮肉に照らし出す鏡になっている点です。例えば、読者の役割を論じる「受容理論」を講義しているまさにその時、彼自身は自作の評価にやきもきしている。この構造によって、読者は単に物語を追うだけでなく、物語そのものを批評的に眺める視点を与えられるのです。
この作品は、アカデミズムへの痛烈な風刺に満ちています。教授会での進まない議論、学閥や個人的な感情が優先される人事、同僚たちの嫉妬や見栄の張り合い。これらは大げさに描かれているように見えながらも、閉鎖的な組織にありがちな病理を見事に突きつけています。
登場する教授たちも、一癖も二癖もある人物ばかりです。唯野の友人である蟇目助教授や、何かと噂の絶えない日根野教授など、強烈な個性を持つキャラクターたちが、物語に深みと彩りを加えています。彼らの巻き起こす騒動は、唯野の悩みをさらに深いものにしていくのです。
そんな混沌とした日常の中、唯野の分身である「野田耽二」の評価は、彼の意に反してどんどん高まっていきます。ついには、権威ある文学賞の候補にまでなってしまう。普通なら大喜びするところですが、唯野にとっては悪夢の始まりでした。受賞すれば、正体は必ず暴かれる。それは学究生活の終わりを意味します。
この状況の皮肉は強烈です。多くの作家が夢見る栄誉が、彼にとっては破滅への引き金でしかない。この葛藤を通して、世間的な成功とは何か、組織に属するとはどういうことか、という普遍的な問いが投げかけられているように感じました。唯野の苦悩は、決して他人事ではないのです。
そして、運命の時は訪れます。「野田耽二」は文学賞を受賞。マスコミはたちまちその正体を突き止め、唯野教授の名は世に知れ渡ることになります。彼が最も恐れていた事態が、最悪の形で現実のものとなった瞬間でした。この暴露の場面の描写は、息をのむほどの迫力があります。
案の定、恩師の蟻巣川教授は激怒します。唯野がこれまで築き上げてきたものが、ガラガラと崩れ落ちていく。このクライマックスがまた、見事に仕組まれているのです。唯野が立智大学で行う最後の講義、そのテーマは「ポスト構造主義」でした。
「ポスト構造主義」とは、物事の安定した意味や絶対的な権威を疑い、解体していく思想です。まさにその講義の最中に、唯野自身の社会的地位やアイデンティティが、マスコミや野次馬の前で公然と解体されていく。講義内容と現実がシンクロするこの場面は、この物語の白眉と言えるでしょう。
彼の二つの世界が衝突し、すべてが白日の下に晒された時、唯野はどうなるのか。彼の周りの人々はどう反応するのか。破滅の淵に立たされたかに見えた彼ですが、物語は意外な結末へと向かいます。この結末については、ぜひご自身の目で見届けていただきたいところです。
この物語を読み終えて強く感じるのは、これが単なる大学内部の出来事を描いた小説ではないということです。組織と個人、建前と本音、安定と自由といった、私たちが生きていく上で誰もが直面するテーマが、ここには詰まっています。唯野教授の奮闘は、滑稽でありながらも、どこか切実な共感を誘います。
また、作者自身が楽しんで書いていることが伝わってくるのも、この作品の魅力です。文学理論を巧みに物語に組み込み、登場人物の名前に遊び心を忍ばせる。読者を物語の世界に引き込みながら、同時に「これは作り話なのだ」と突き放すようなメタフィクションの構造は、実に鮮やかです。
発表から長い年月が経っているにもかかわらず、この物語が描き出す大学や組織の問題は、今もなお古びていません。むしろ、現代社会において、その射程はさらに広がっているとさえ言えるかもしれません。だからこそ、今、この「文学部唯野教授」を読む価値があるのだと感じます。
難解な文学理論への最高の入門書でありながら、一級のエンターテインメントでもある。そして、社会や人間を深く洞察した、骨太な物語でもある。これほど多層的な楽しみ方ができる作品は、そう多くはないでしょう。知的な刺激と笑い、そして少しの哀愁が、読後、心の中に深く残るはずです。
まとめ
小説「文学部唯野教授」は、大学という特殊な世界を舞台に、一人の男の二重生活の行方を描いた、知的で刺激的な作品です。難解に思われがちな文学理論を物語に溶け込ませる手腕は、見事としか言いようがありません。
主人公・唯野教授が抱える秘密のスリルと、彼を取り巻く個性的な教授たちが織りなす人間ドラマは、読者を飽きさせません。その描写は風刺に富んでいながら、組織に生きる人間の普遍的な苦悩や葛藤をも描き出しています。
物語の核心に触れる部分では、主人公のアイデンティティが崩壊していく様が、彼自身の講義内容と重なり合うという圧巻の展開が待っています。このメタフィクション的な仕掛けこそ、この物語を傑作たらしめている大きな要因でしょう。
まだこの名作に触れたことのない方はもちろん、再読を考えている方にも、新たな発見があるはずです。知的な興奮と物語の面白さが見事に融合した「文学部唯野教授」を、ぜひ手に取ってみてください。