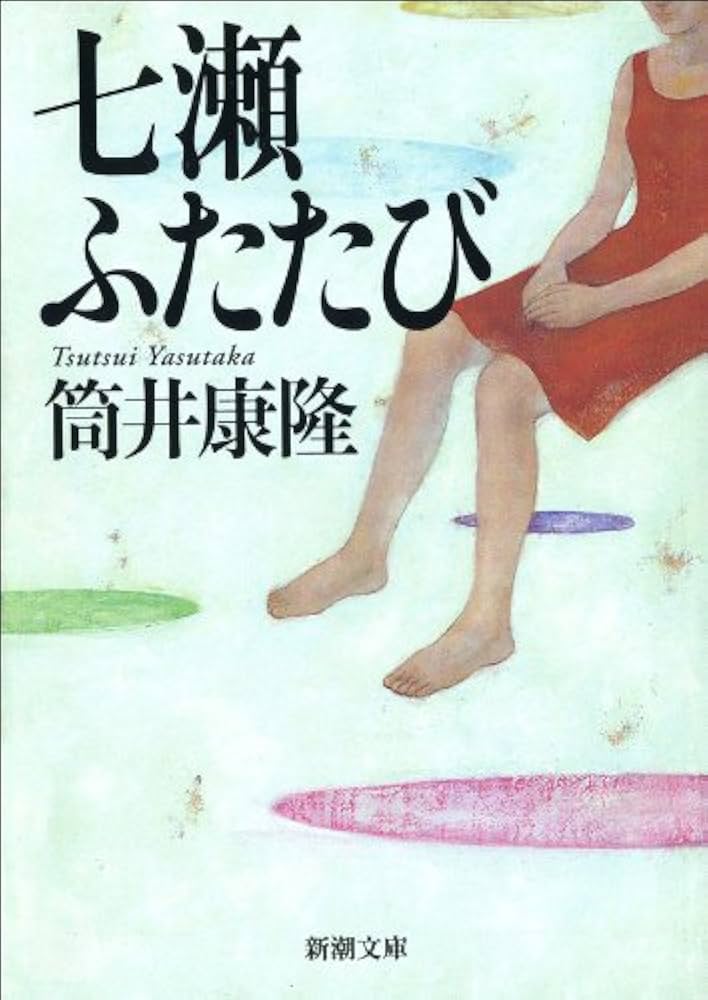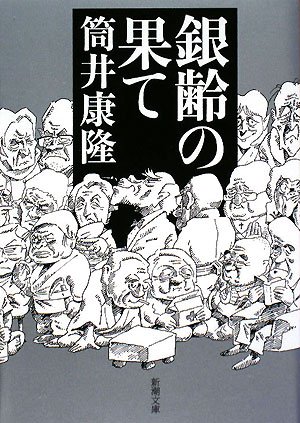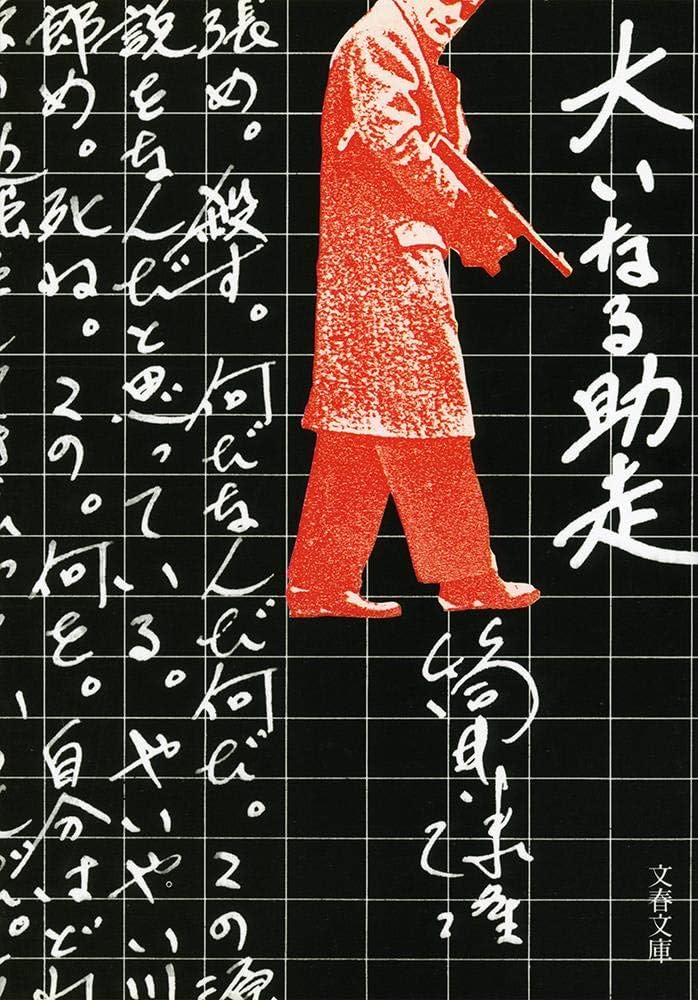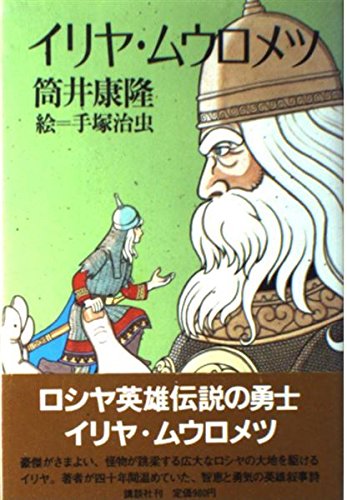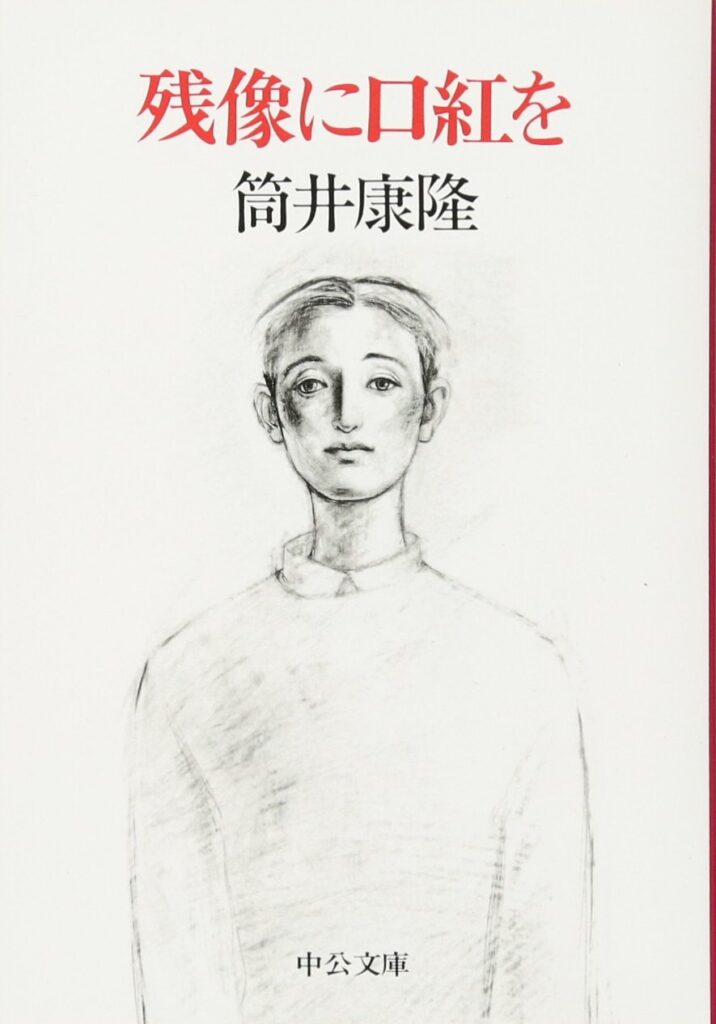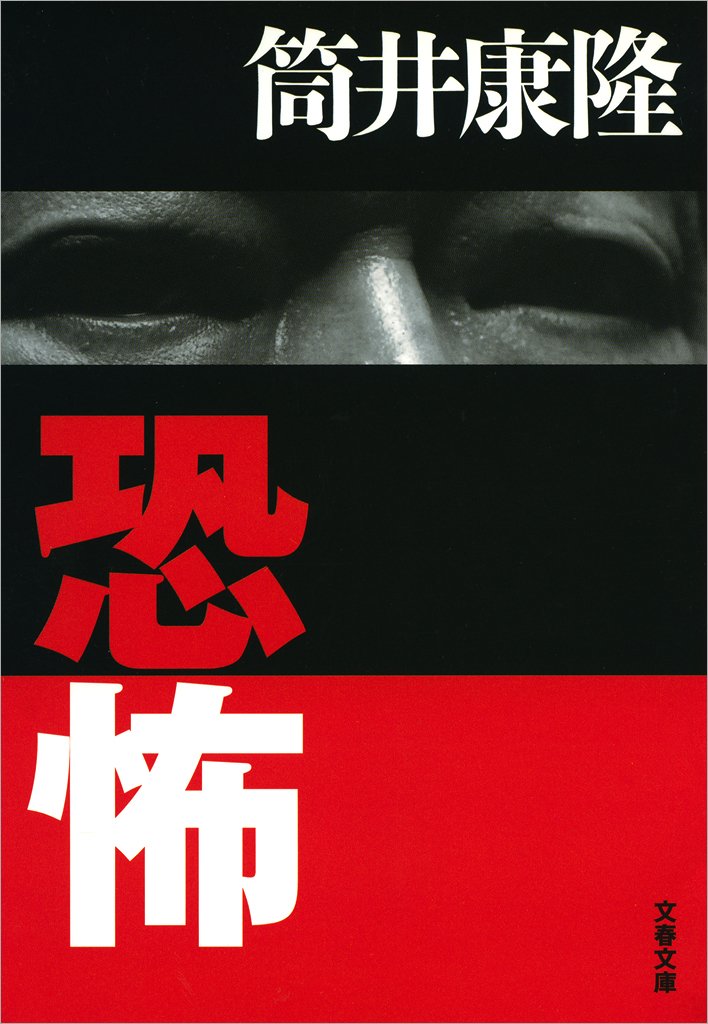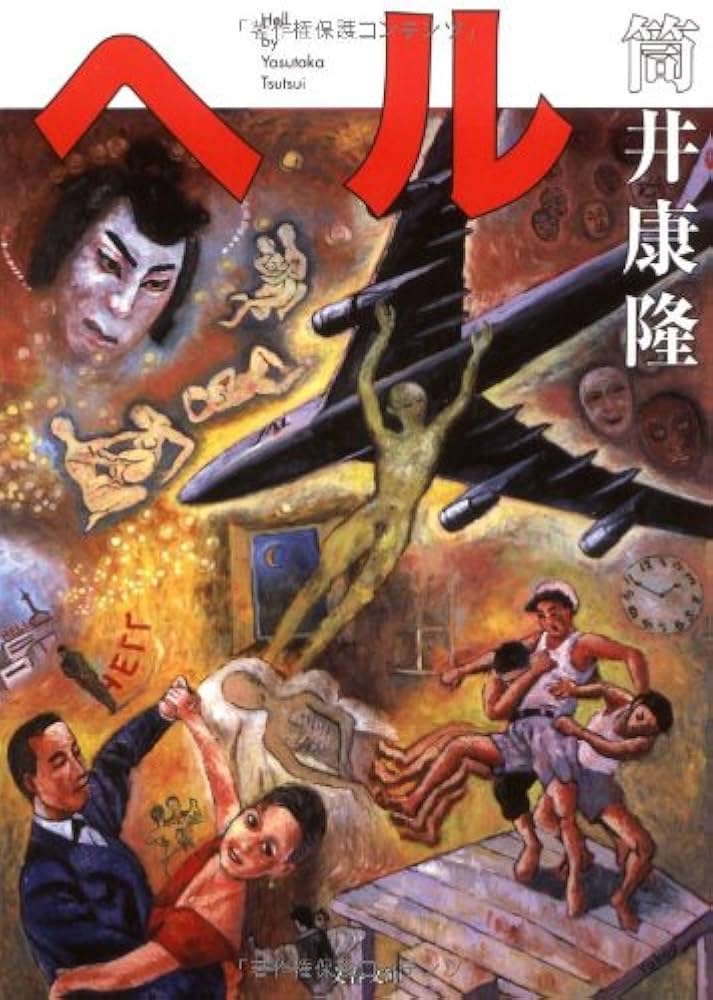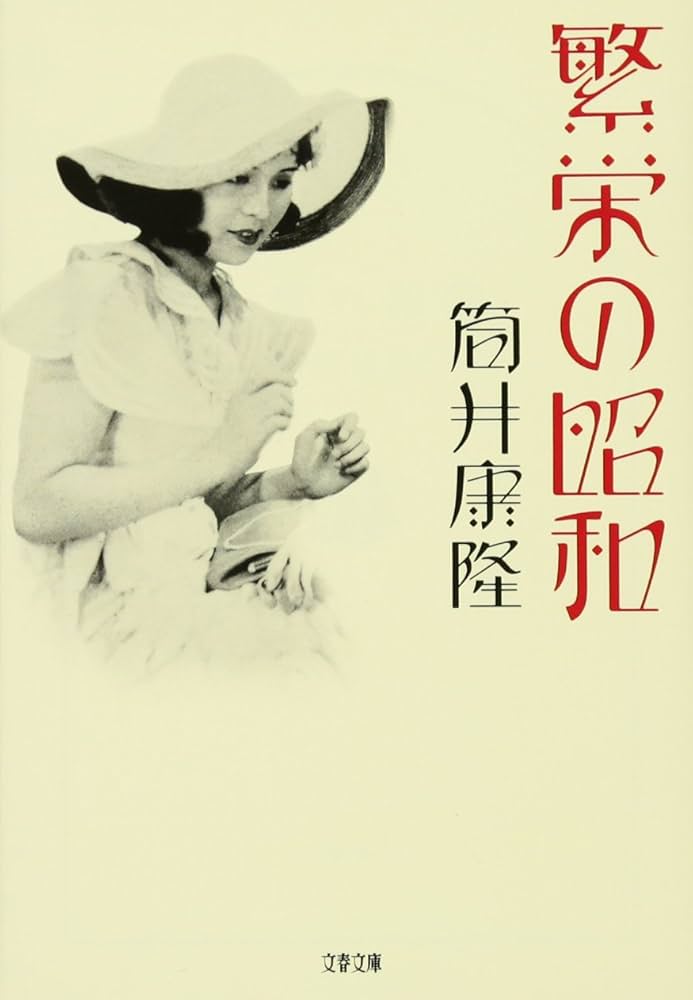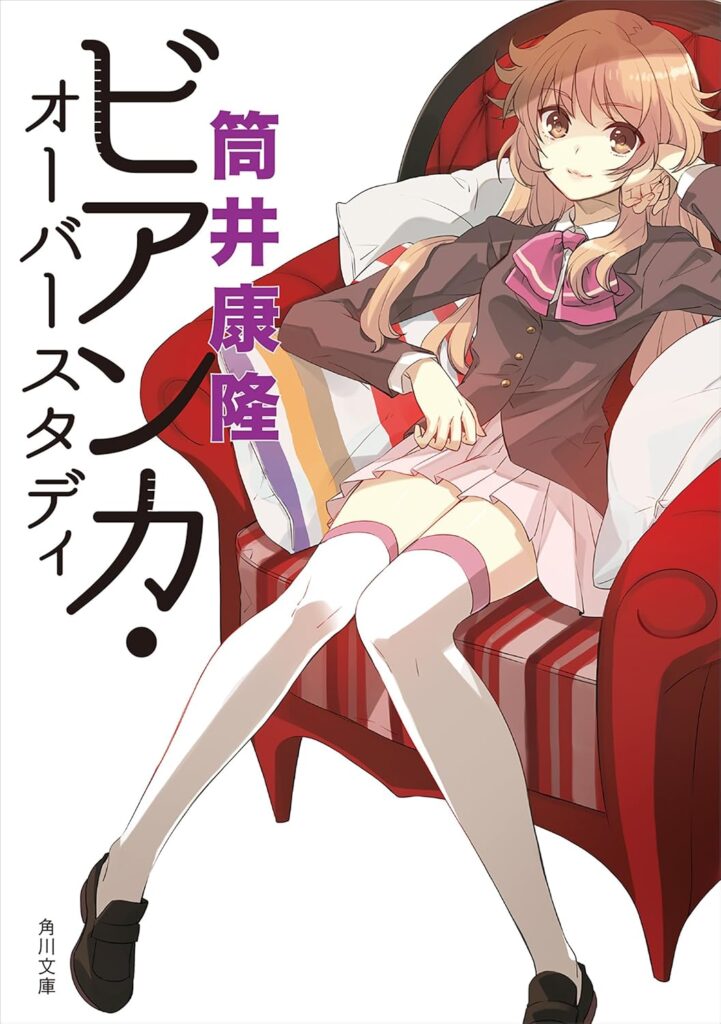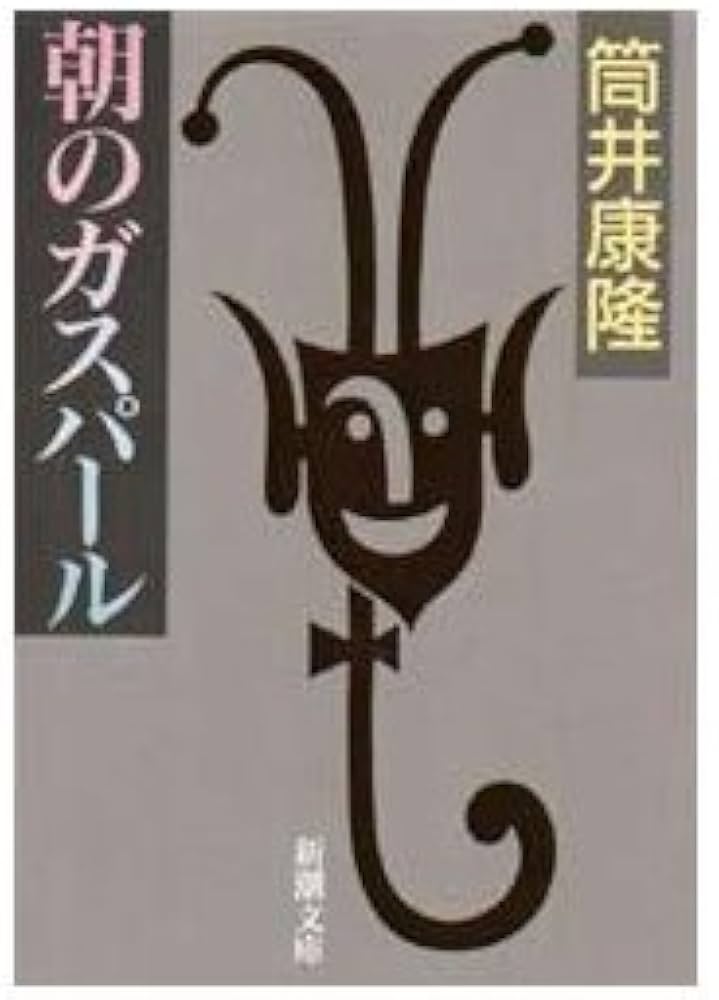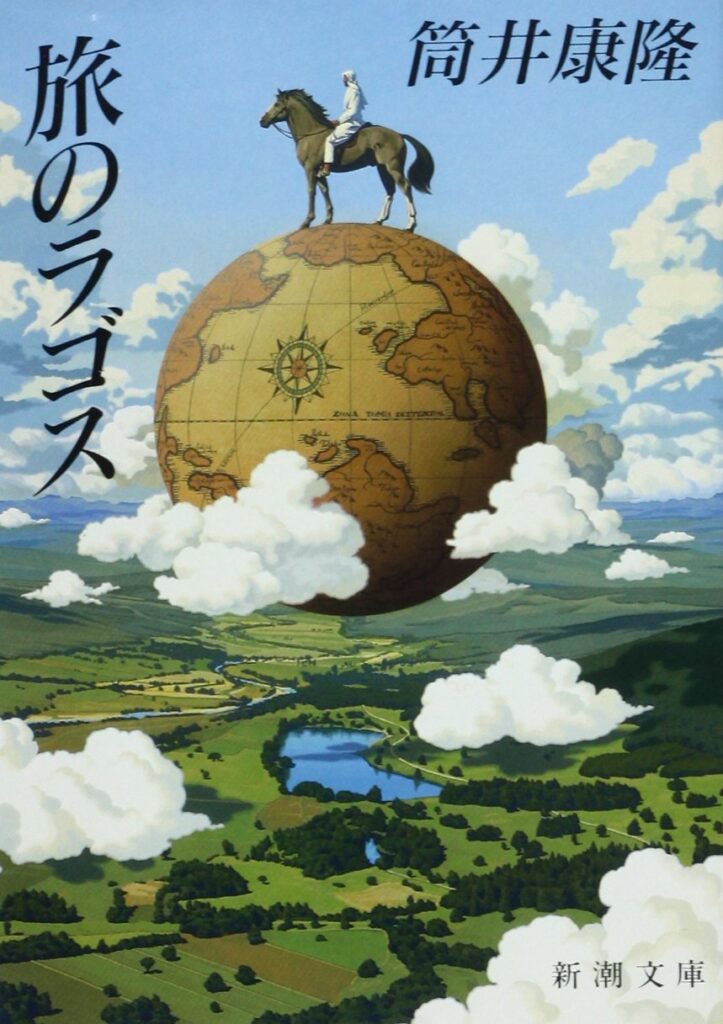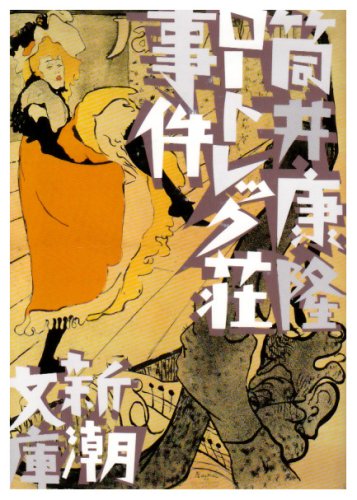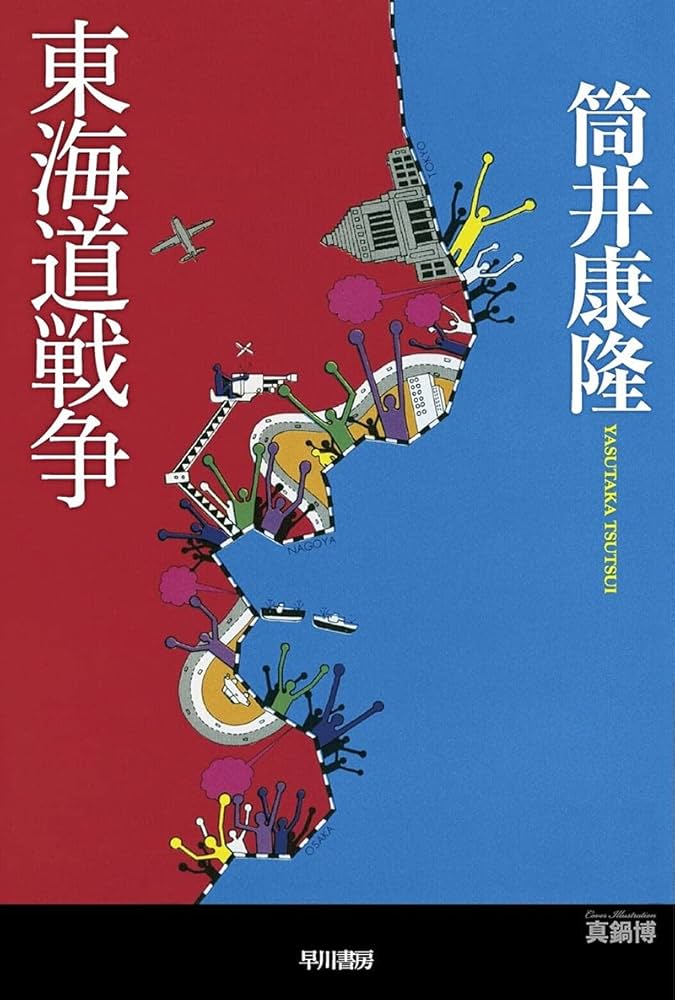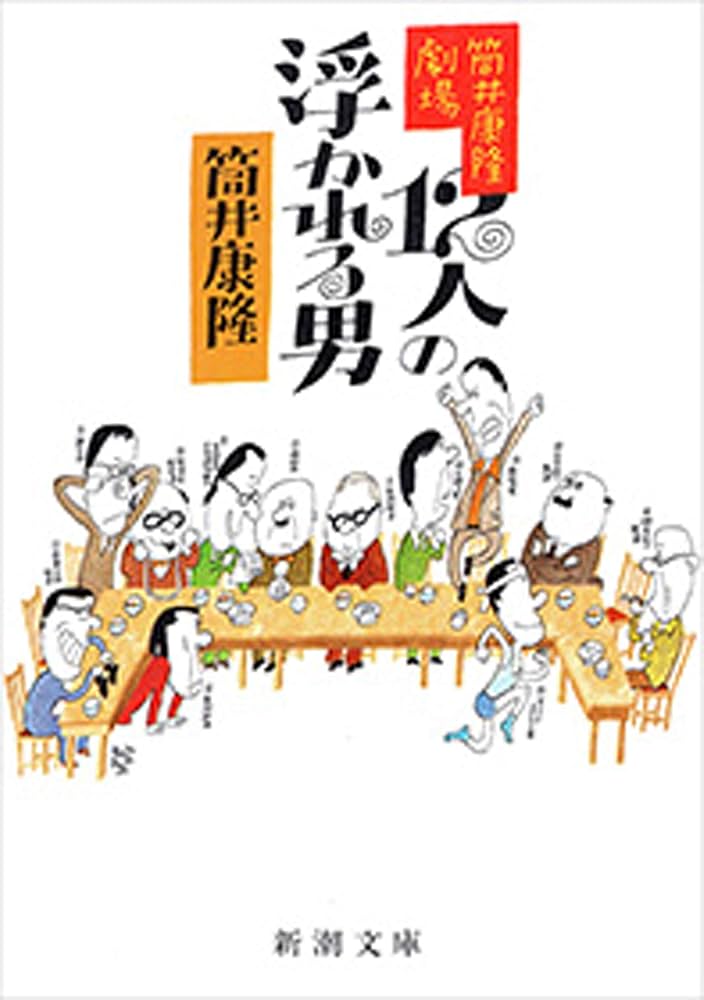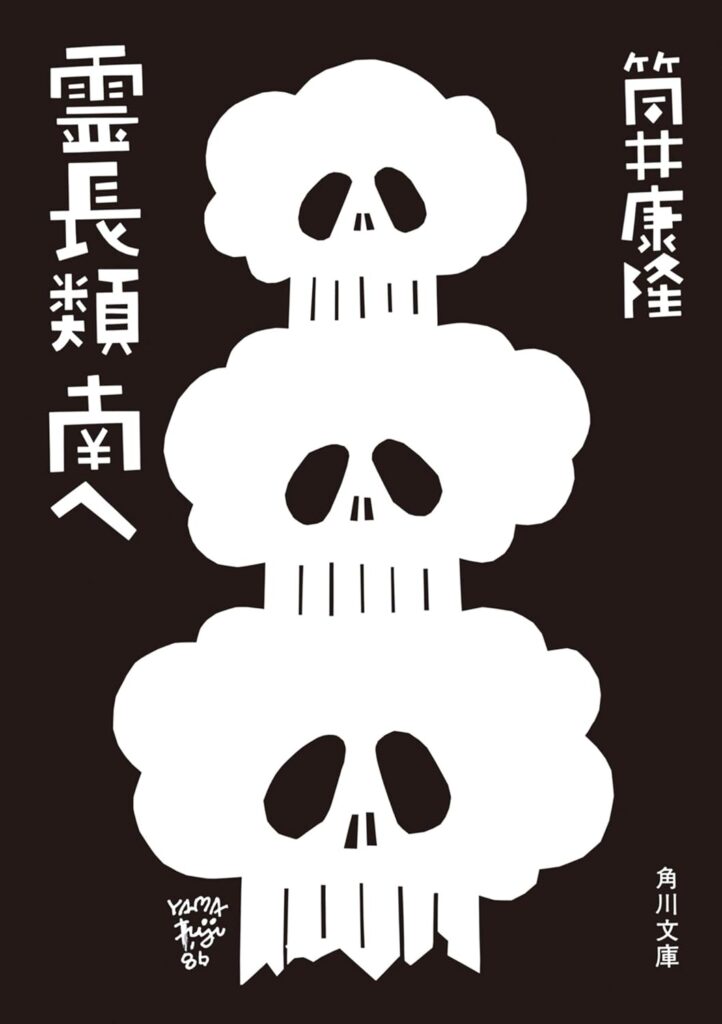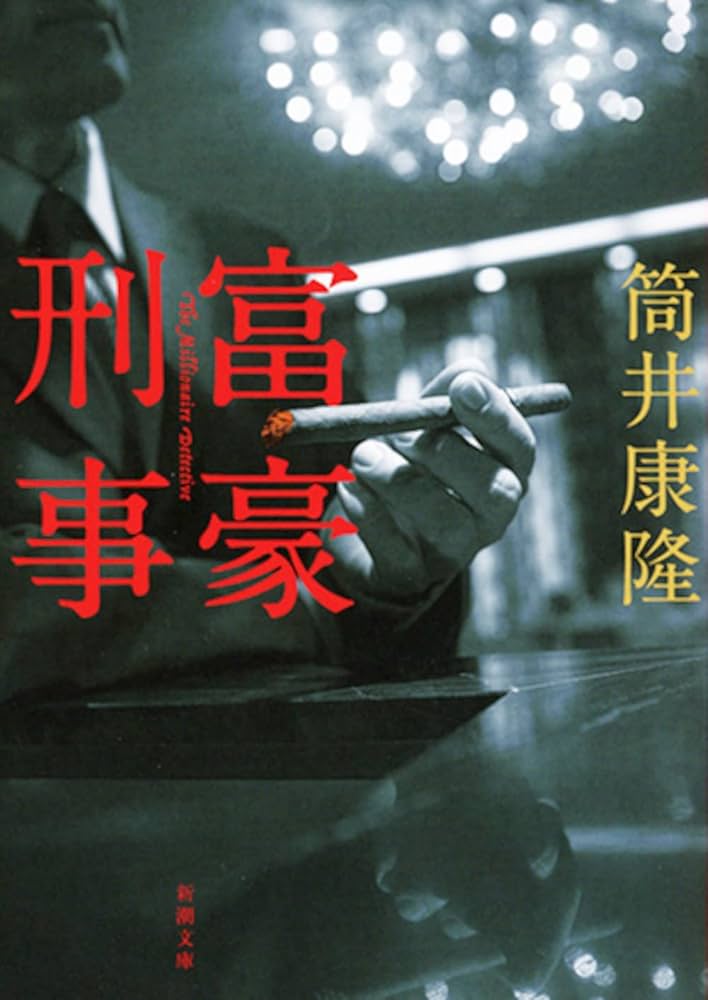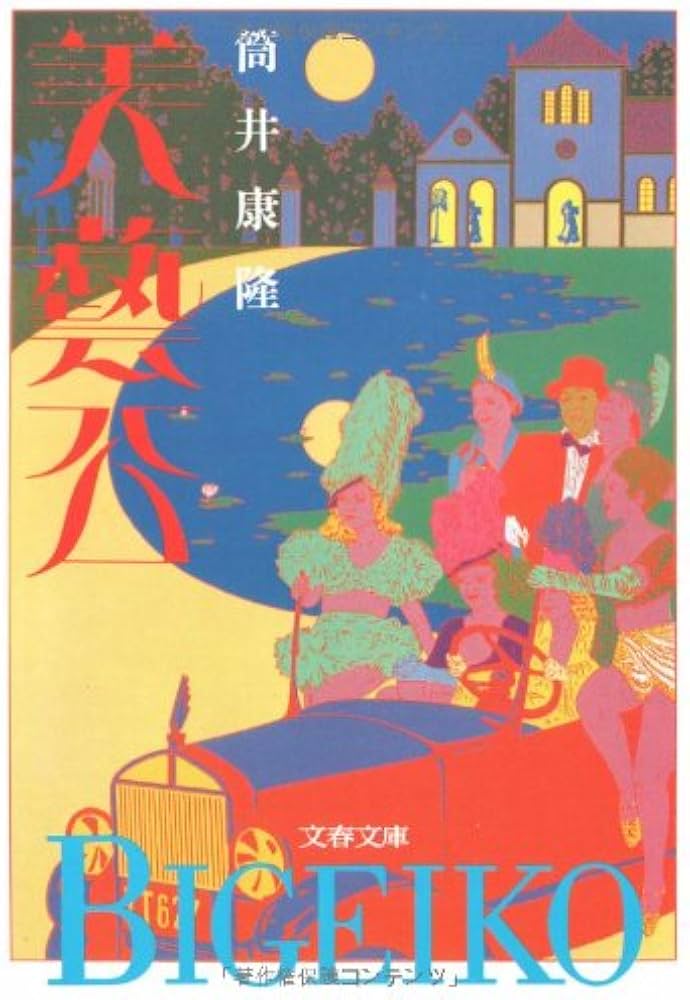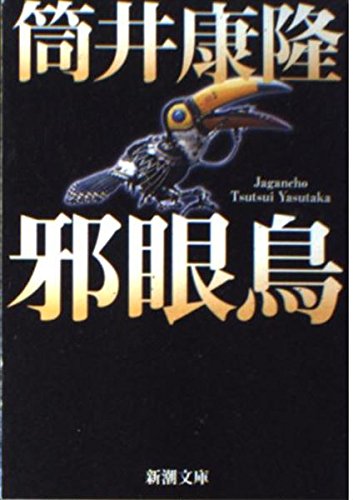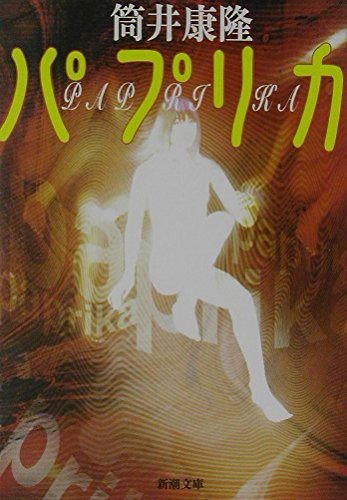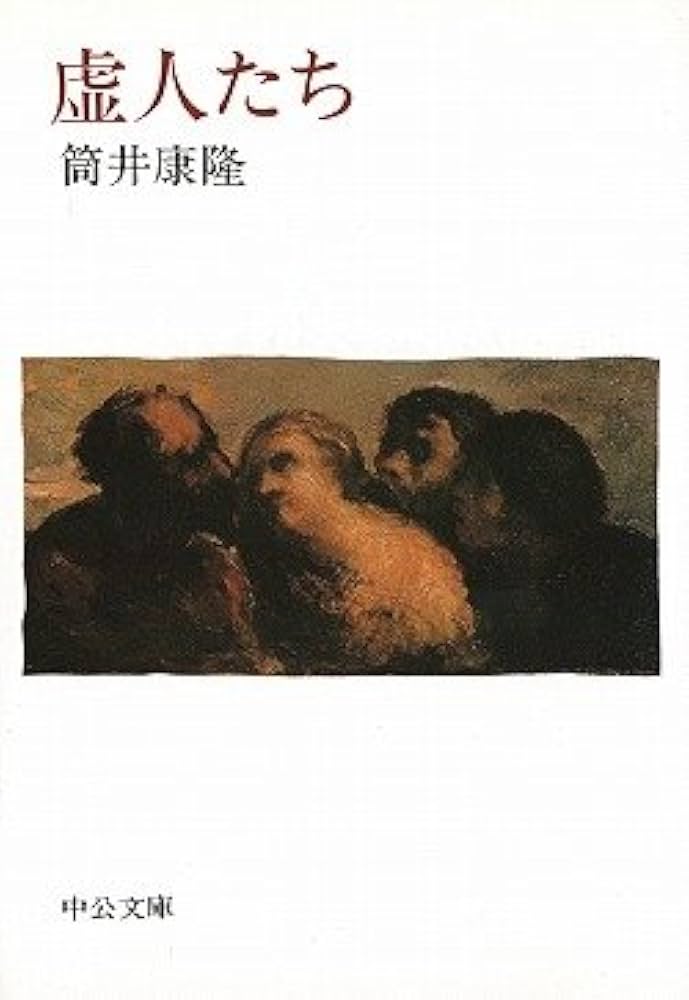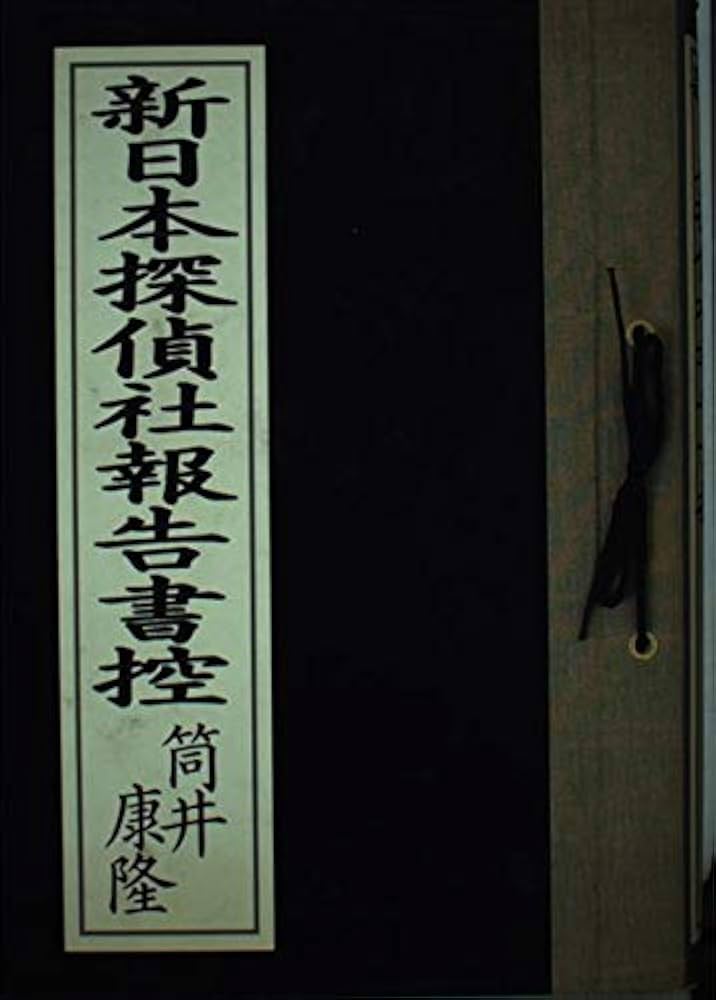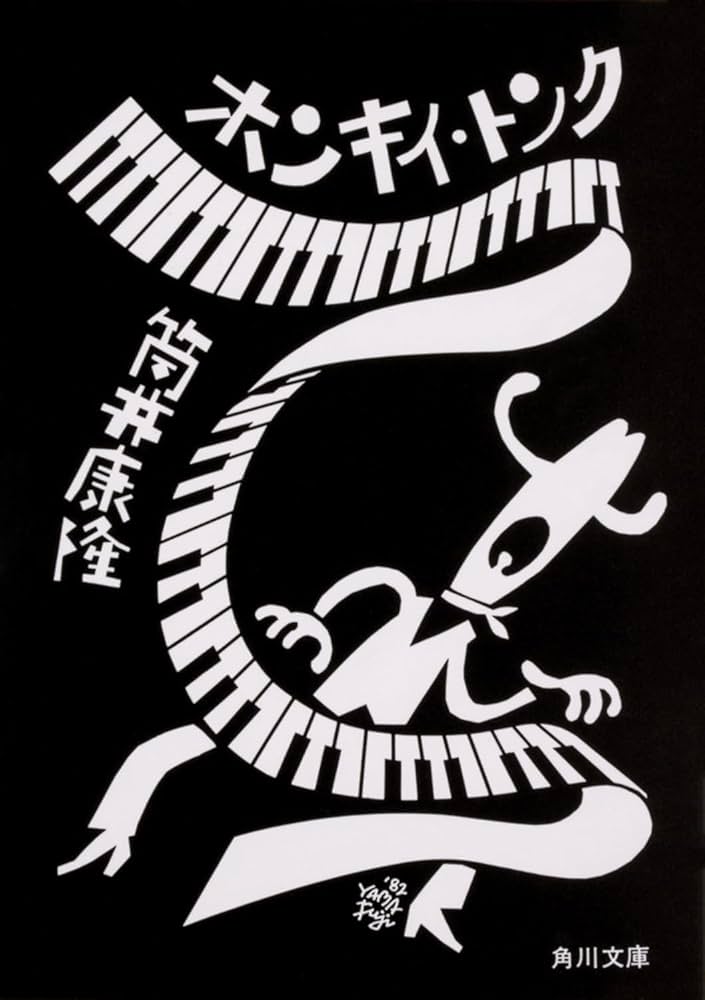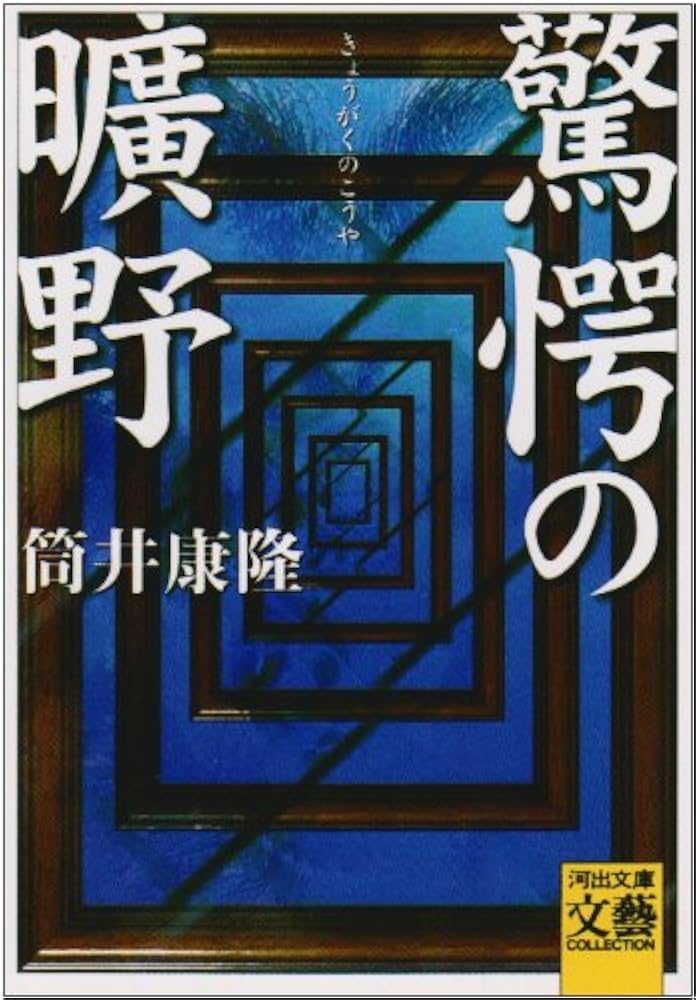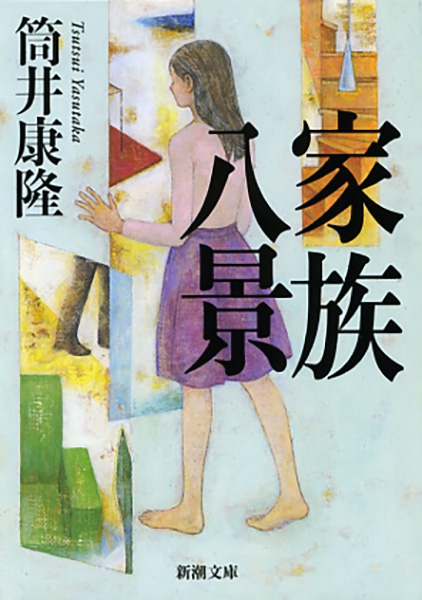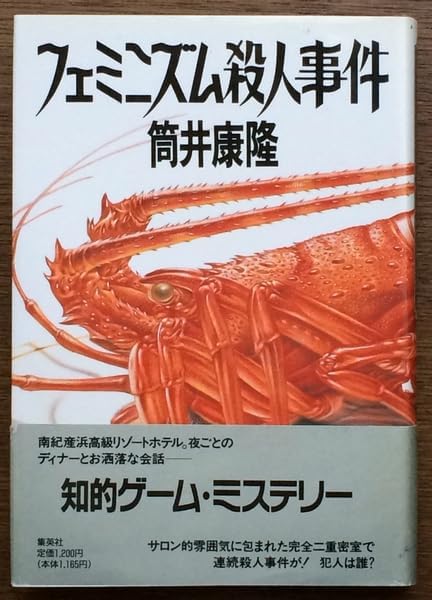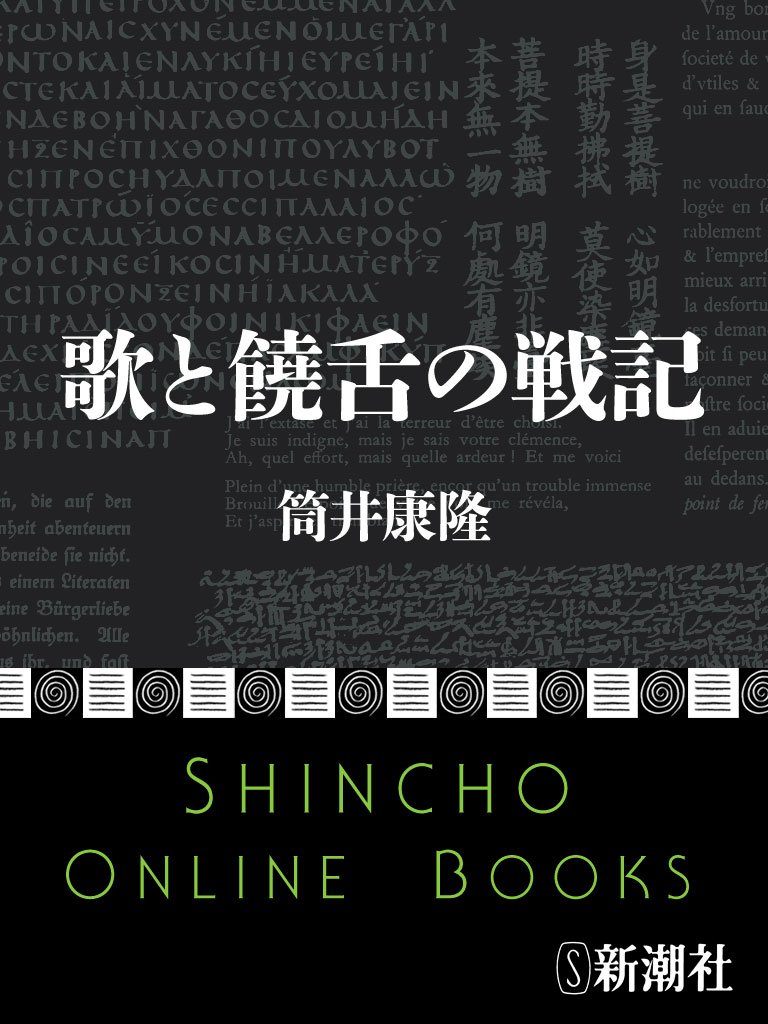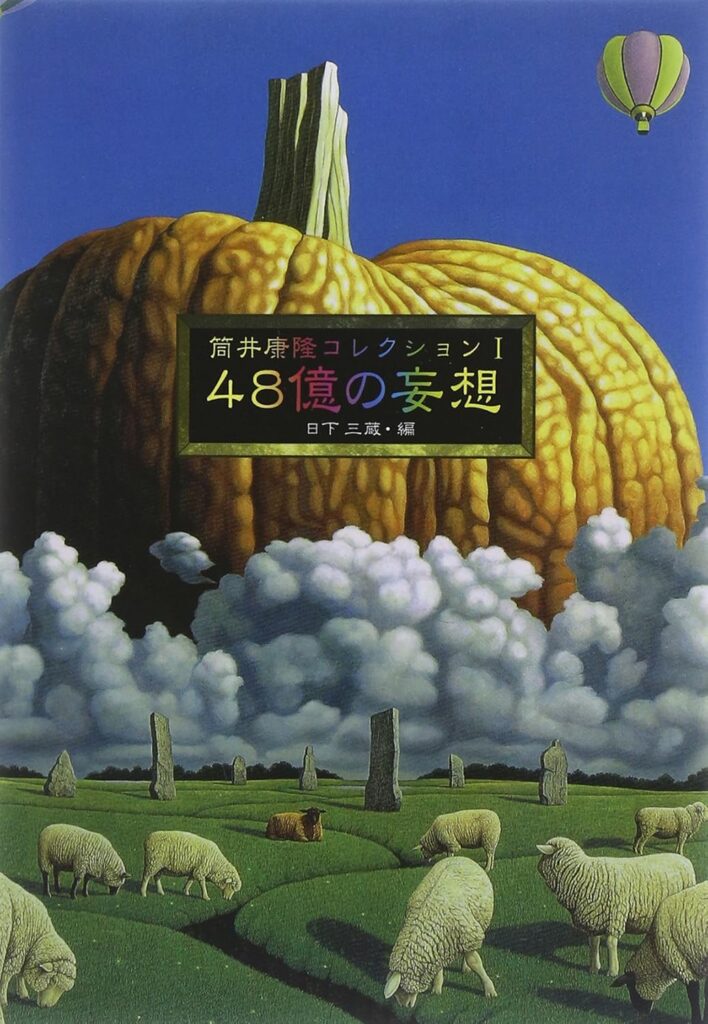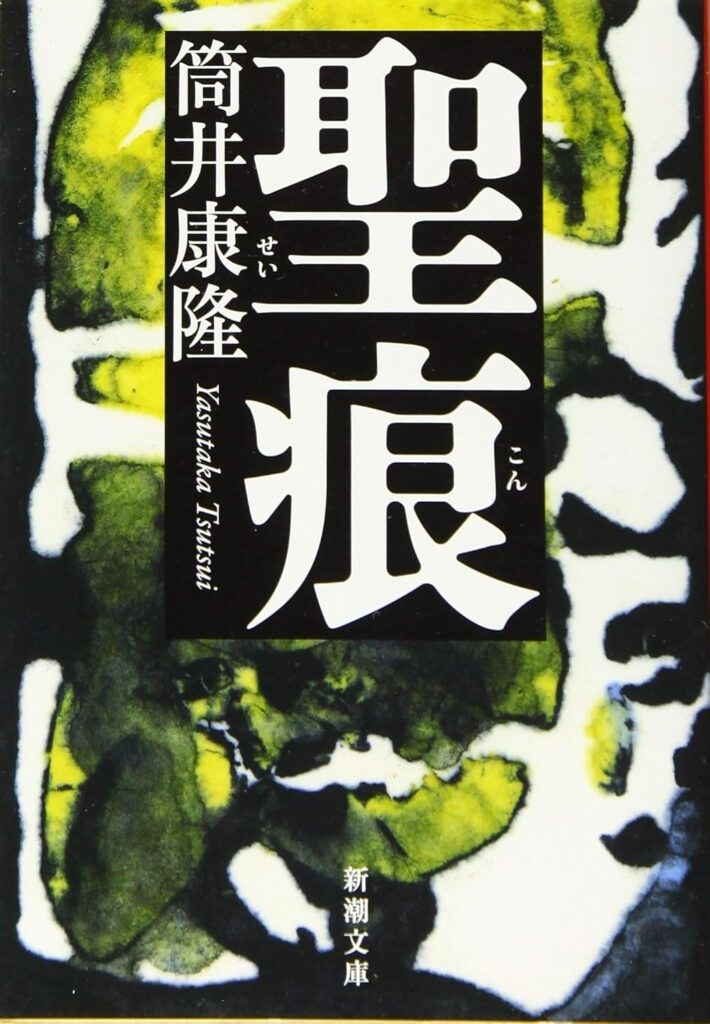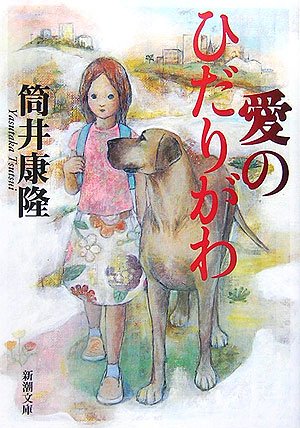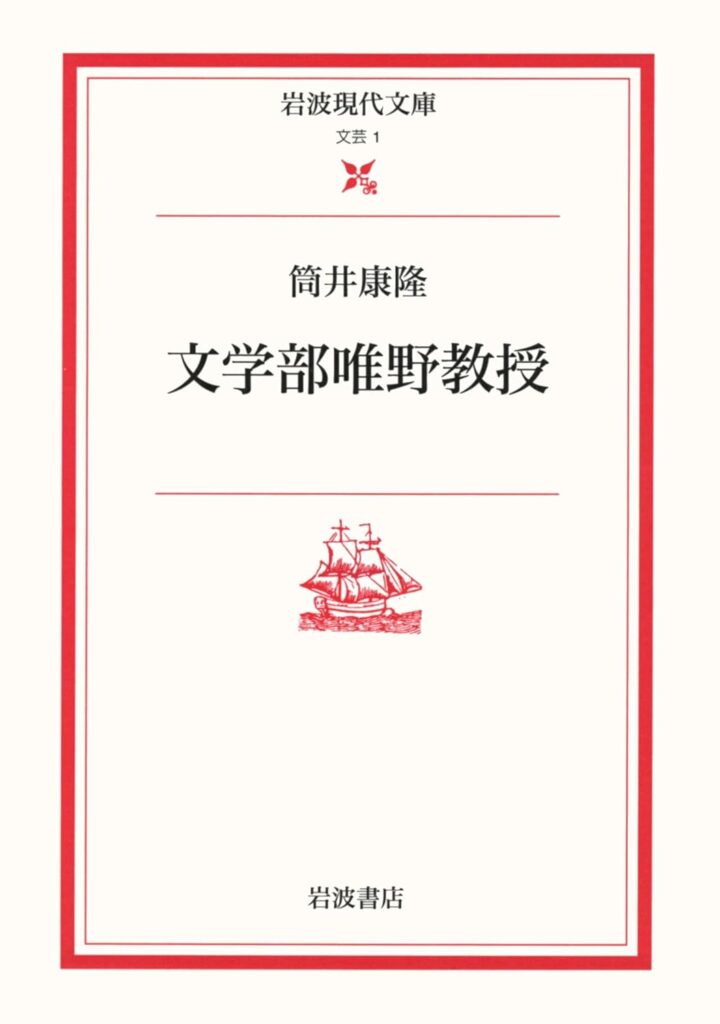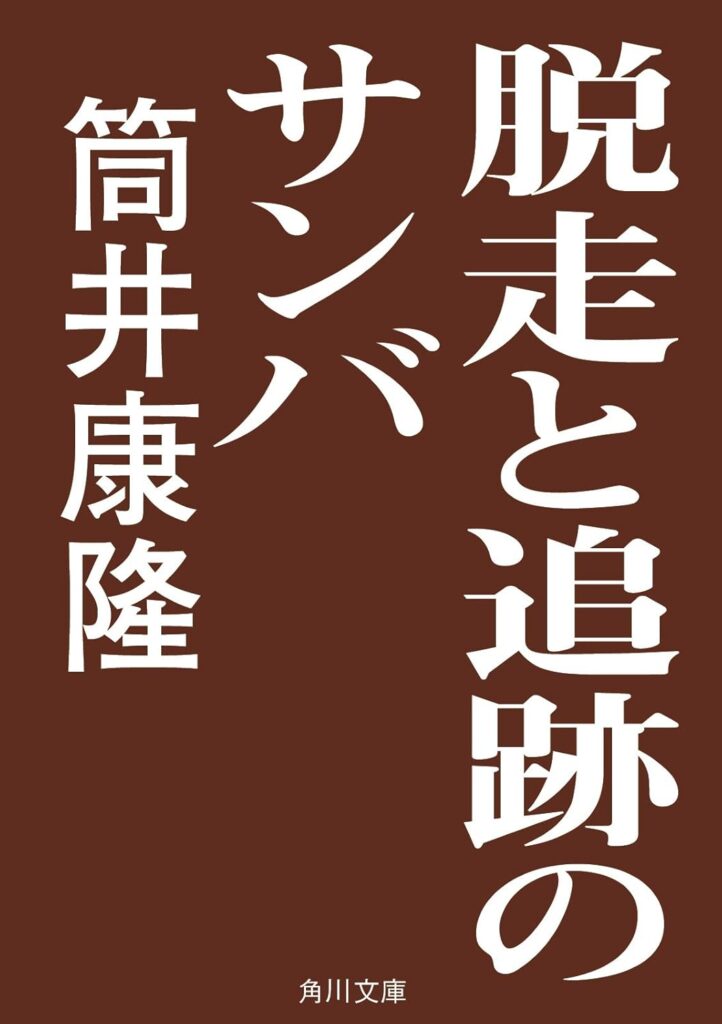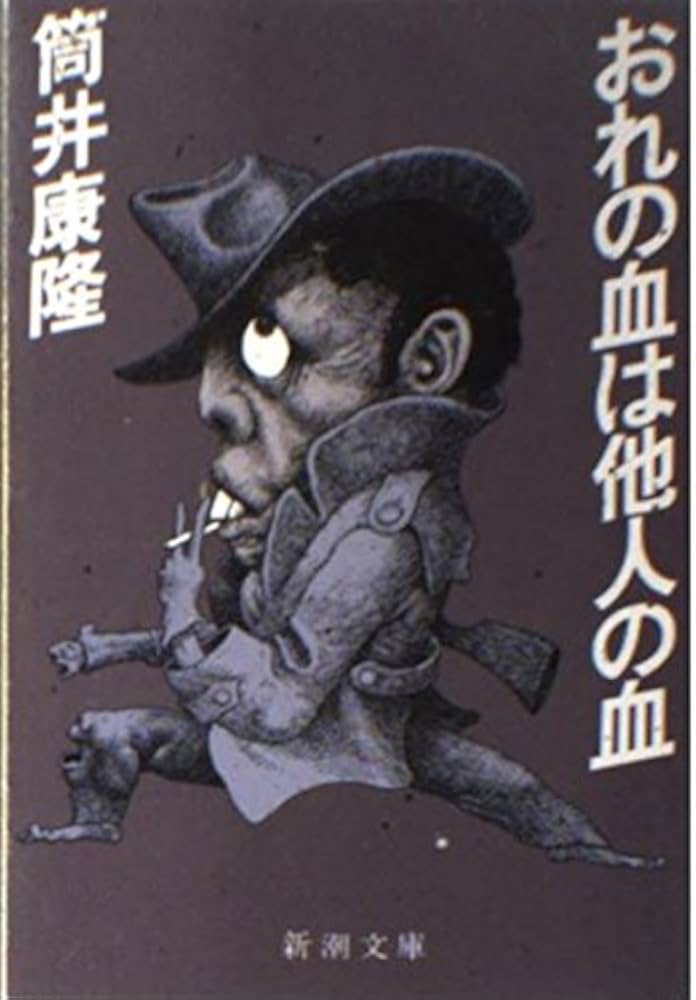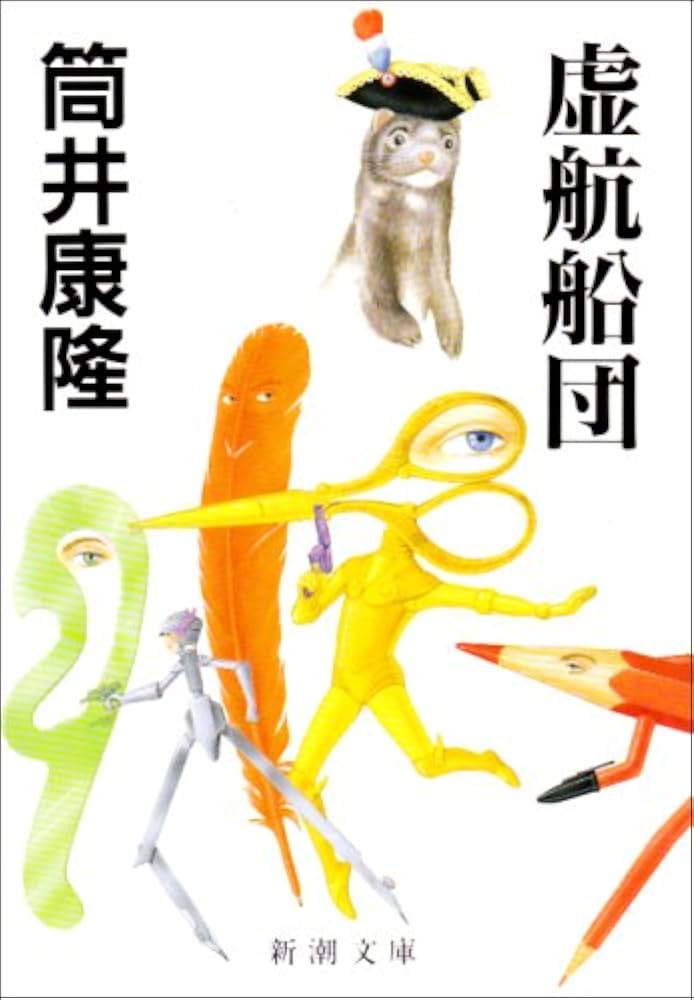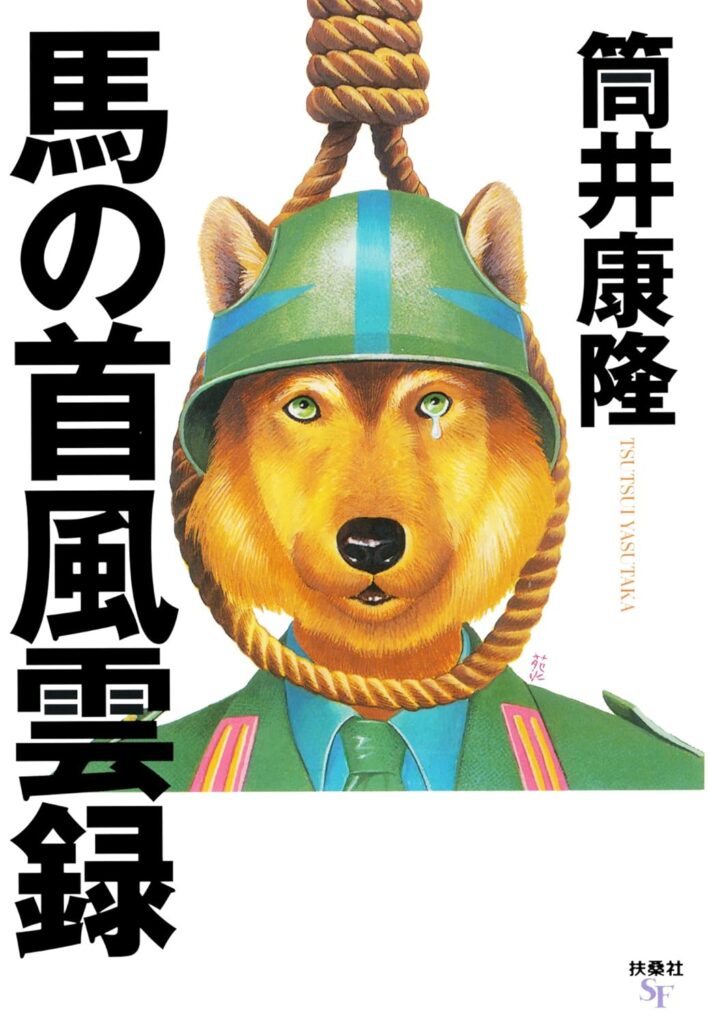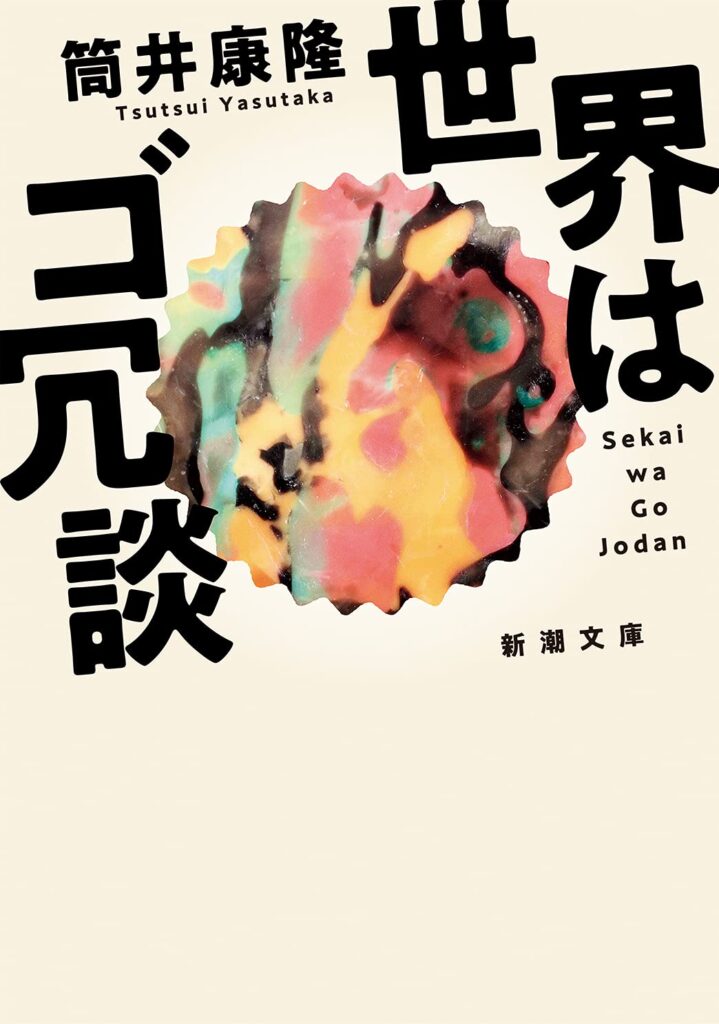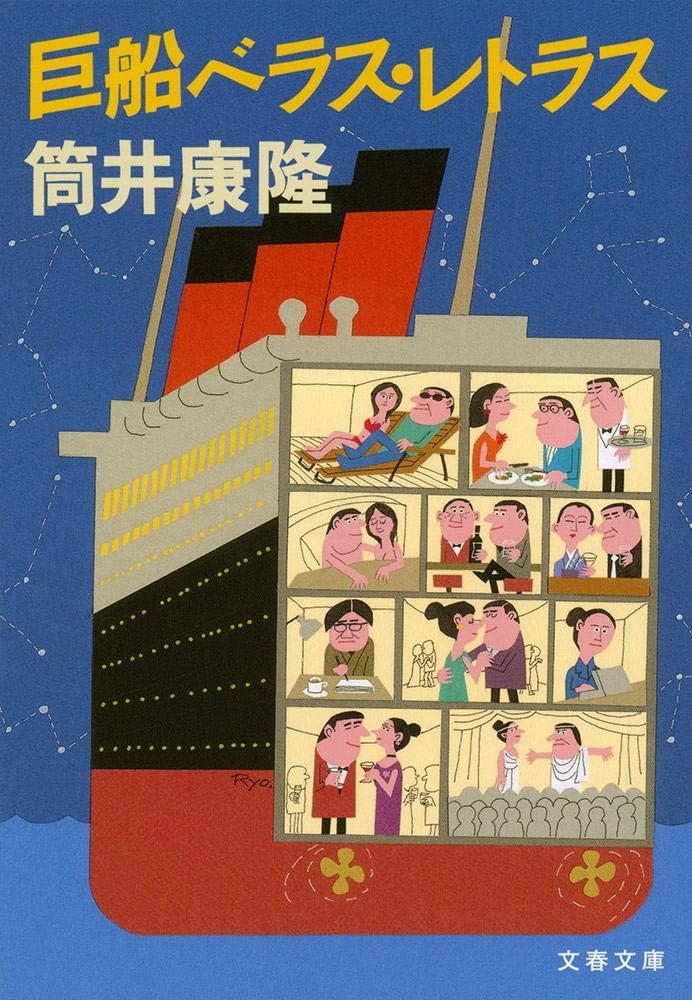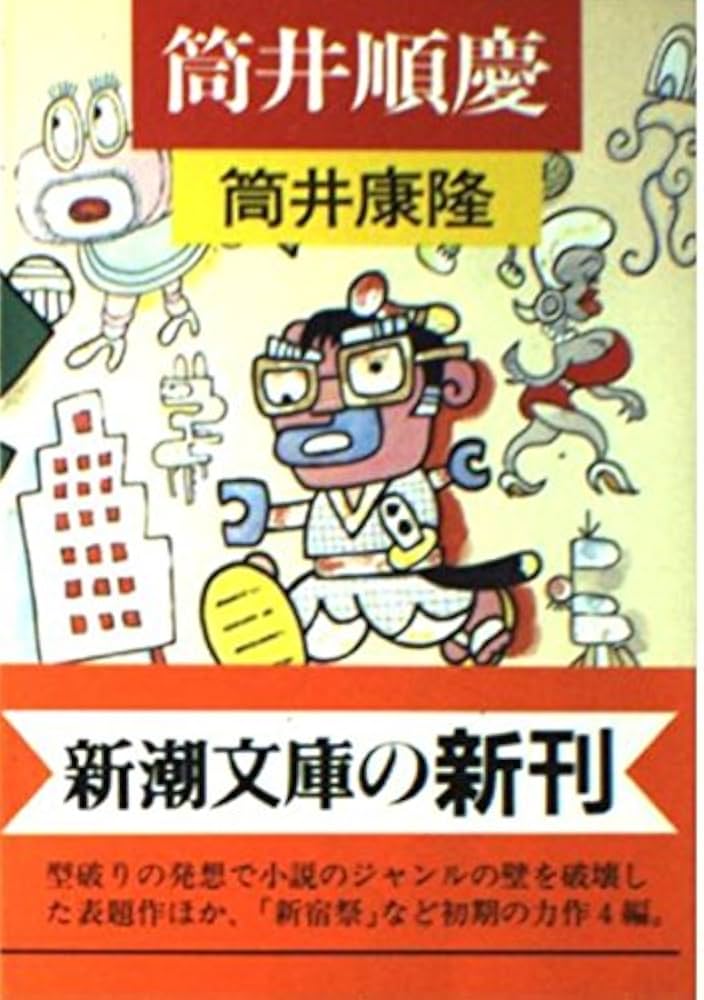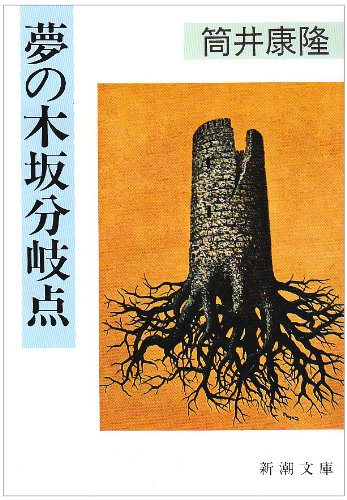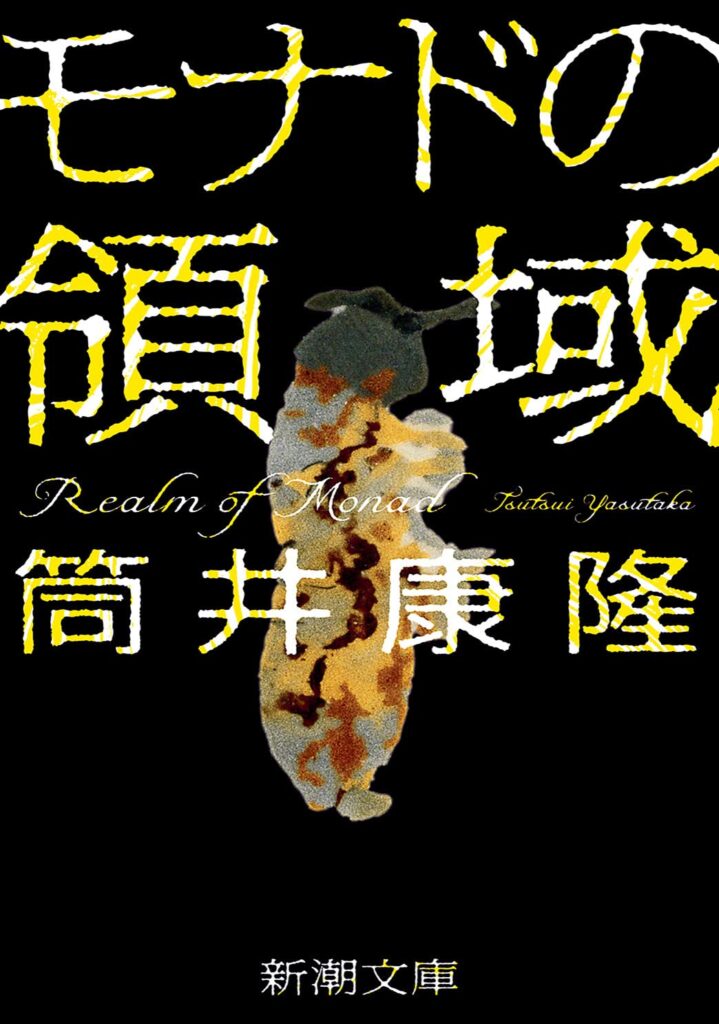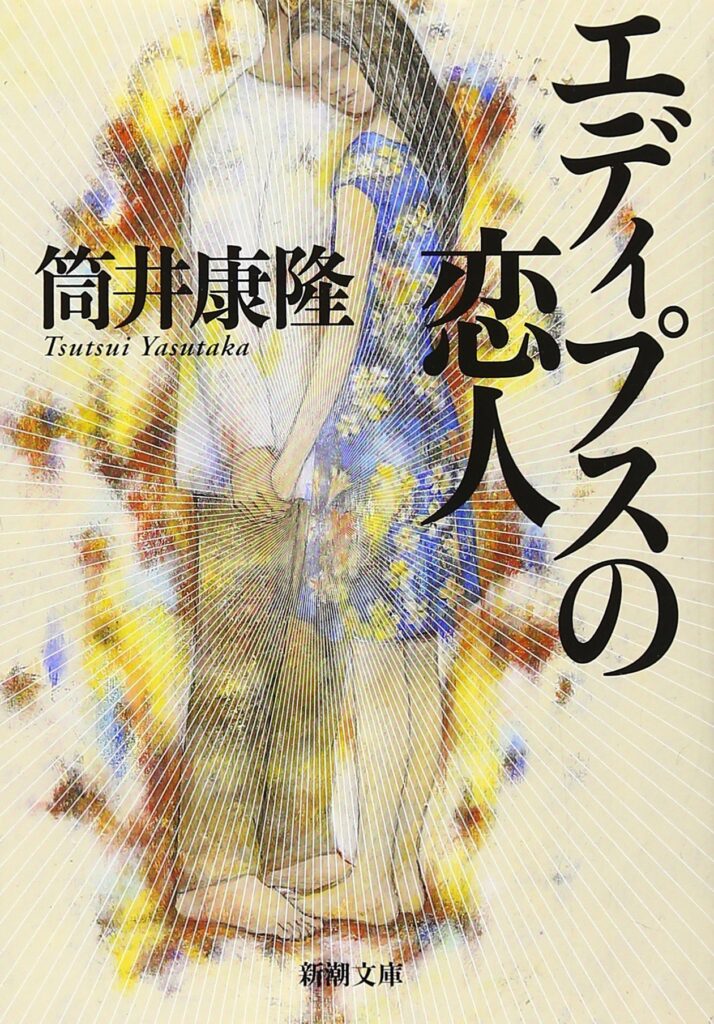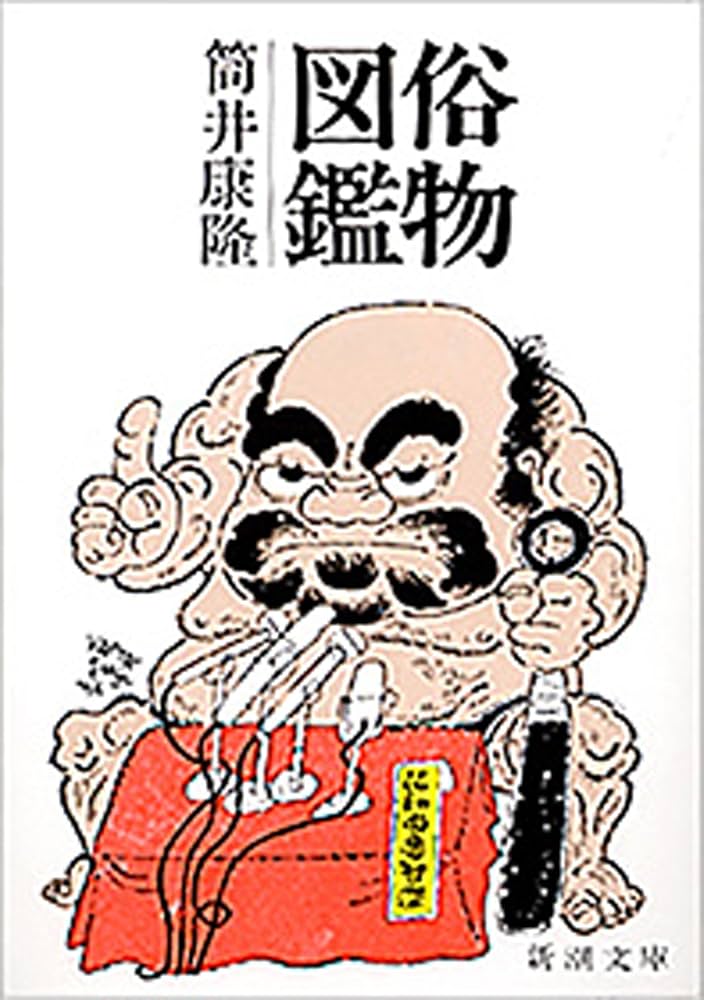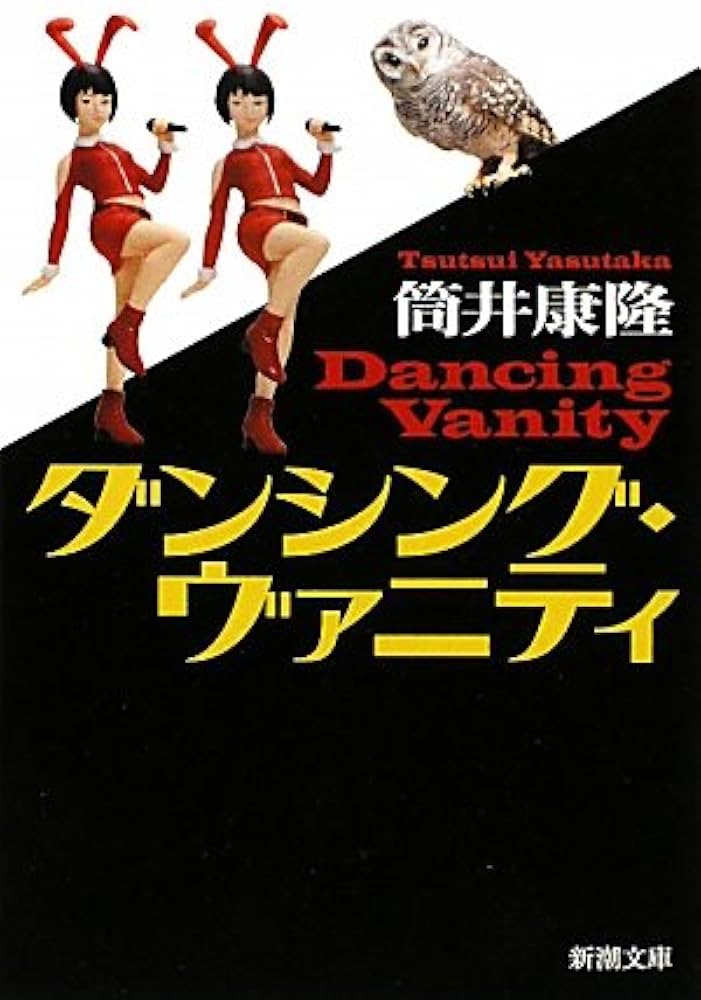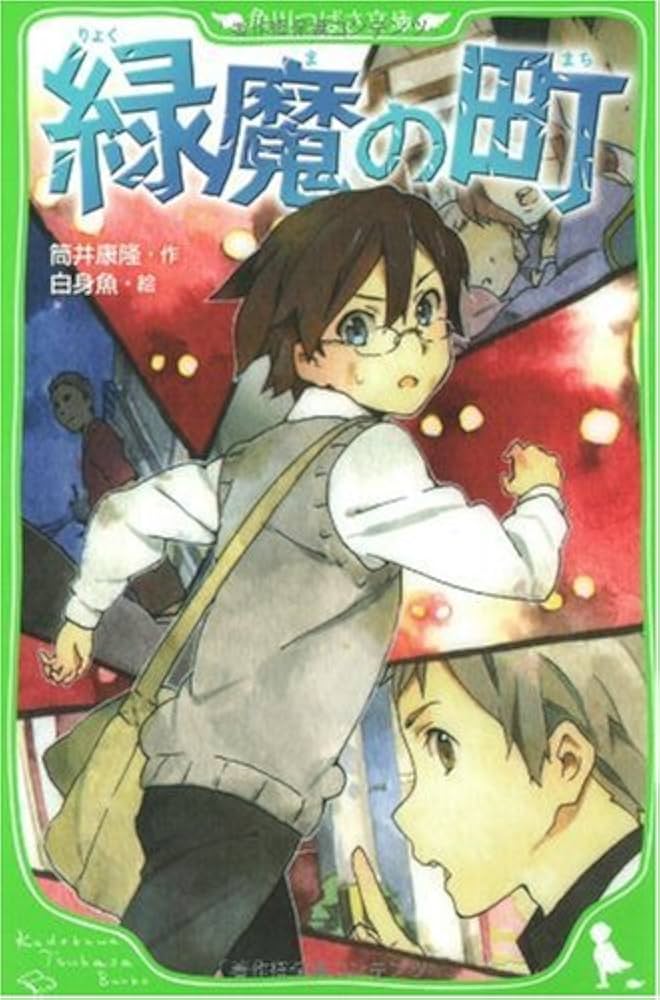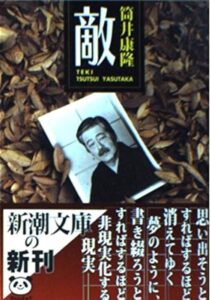 小説「敵」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「敵」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、静かで規則正しい老後を送る一人の元大学教授が、ある日突然、正体不明の「敵」の存在に脅かされていく様子を描いたものです。日常が静かに、しかし確実に崩壊していく過程は、読む者の心にじわじわとした恐怖を植え付けます。
主人公の緻密に管理された世界が、パソコンの画面に現れた不可解なメッセージをきっかけに、いかにして狂気と幻想に飲み込まれていくのか。その一部始終を、この記事では詳細に追いかけていきます。彼の内面で何が起こっているのか、そして「敵」とは一体何なのか、深く掘り下げてみたいと思います。
この記事を読めば、筒井康隆さんが描いた『敵』という作品の恐ろしさ、そしてその文学的な深みの一端に触れていただけることでしょう。物語の結末まで踏み込んでいきますので、これから読もうと思っている方はご注意ください。それでは、始めましょう。
小説「敵」のあらすじ
物語の主人公は、75歳の渡辺儀助という元大学教授です。彼は妻に先立たれ、都心から離れた古い日本家屋で、孤独ながらも極めて規則正しい毎日を送っていました。食事は自炊にこだわり、貯金の残高を常に意識し、自らの死期さえも計画するような、知性と自己規律の塊のような人物です。
そんな彼の周到に管理された日常は、ある日、書斎のパソコンに「敵がやって来る」という不吉なメッセージが表示されたことから、静かに綻び始めます。儀助は当初、それを迷惑メールか何かだろうと無視しようとしますが、その一文は彼の心に消しがたい不安の種を植え付けました。
このメッセージを境に、儀助の穏やかな生活は少しずつ崩壊していきます。不穏な物音、物の配置の僅かなズレ、そして何よりも彼自身の心に芽生える疑心暗鬼。彼の世界は、現実と悪夢、そして妄想の境界が曖昧になっていくのです。
仪助は自身の理性を頼りに、この見えざる「敵」の侵食に抵抗しようと試みます。しかし、「敵」の正体も目的もわからぬまま、彼の精神は徐々に追い詰められていきます。かつての教え子への淡い想いや、亡き妻の記憶も、この不可解な状況の中で奇妙な色合いを帯びていくのでした。
小説「敵」の長文感想(ネタバレあり)
渡辺儀助という人物の造形から、この物語は始まります。75歳の元大学教授で、専門はフランス近代演劇史。妻に先立たれてからは、祖父の代から受け継いだ旧い日本家屋で、孤独な日々を送っています。この設定だけで、彼の人物像が浮かび上がってくるようです。博識で理知的、しかしどこか世間から隔絶された生活を送っている、そんな老知識人の姿です。
彼の生活は、徹底した自己規律によって成り立っています。食事、特に蕎麦を茹でる際の独特な描写は、彼の生への執着と、抑圧された生命力のようなものを感じさせます。また、貯蓄が尽きる頃に自ら命を絶つと決めているという事実は、彼の死生観と、自らの人生を最後までコントロールしようとする強い意志の表れと言えるでしょう。この徹底した日常の描写が、後の崩壊をより際立たせるための重要な布石となっています。
彼の孤独は完全なものではなく、年下の友人との交流や、かつての教え子である鷹司靖子への秘めた好意も描かれます。この満たされない想いは、彼の人間的な側面を浮き彫りにします。彼の内面では、亡き妻の記憶や過去への回想、そして危機が訪れる前から妄想が渦巻いていたことも示唆されており、彼の理性の下には複雑な感情が眠っていることがわかります。
物語の歯車が大きく動き出すのは、パソコンの画面に「敵がやって来る」というメッセージが現れる場面です。古い日本家屋という伝統的な空間に、パソコン通信というデジタルな媒体から未知の脅威が侵入してくる。この対比が非常に印象的です。彼の確立された秩序ある世界に、制御不能な現代性が亀裂を入れる瞬間なのです。
このメッセージの恐ろしさは、その徹底した曖昧さにあります。「敵」が誰で、何で、いつ、なぜ来るのか、一切が不明です。この情報のない脅威は、儀助の、そして読者の不安を最大限に掻き立てます。定義されない恐怖ほど恐ろしいものはありません。それは、人が最も恐れるものを自由に投影できる、空っぽの器のようなものだからです。
メッセージの出現後、儀助の世界はゆっくりと、しかし確実に侵食されていきます。最初は些細な異変です。聞き慣れない物音、物の位置のズレ。しかし、それらは彼の心にパラノイアの種を蒔き、慣れ親しんだはずの自宅が、どこか異質で脅威的な空間に感じられるようになります。このじわじわと進む侵食の描写が、本作の心理的恐怖の核心部分と言えるでしょう。
そして、物語は儀助の内的世界へと深く潜っていきます。現実と夢、そして妄想の境界線が次第に曖昧になっていくのです。彼は悪夢にうなされ、その悪夢が覚醒時の知覚にまで影響を及ぼし始めます。作中では、儀助の状態は単なる認知症ではなく、「夢と妄想の人」なのだと示唆されています。これにより、物語は老人の衰えという単純な話ではなく、精神の崩壊や自己の喪失という、より根源的なテーマへと昇華されているのです。
彼の知覚は歪み、日常の何気ない出来事にも敵意を感じるようになります。彼の几帳面に整えられた世界が、彼を脅かすものへと変貌していく様子は、読んでいて胸が苦しくなるほどです。物語の文体も、当初の緻密な写実性から、次第に断片的で、どこかシュールなものへと変化していきます。これは、儀助自身の精神が断片化していく様を、文章そのもので表現しているかのようです。
物語が進行するにつれ、「敵」の存在はより支配的になり、儀助の精神は急速に崩壊の一途をたどります。彼の理性による抵抗は、もはや何の役にも立ちません。内なる世界と外の世界の境界が完全に取り払われ、彼の現実は狂気と幻覚に塗り替えられてしまいます。三人称で淡々と綴られていたはずの日常が、気づけば悪夢そのものになっているのです。
では、この「敵」とは一体何なのでしょうか。それは、儀助が抱えるあらゆる恐怖の集合体なのかもしれません。老いへの恐怖、無力になることへの恐怖、孤独への恐怖、そして死への恐怖。彼が秩序正しい生活によって必死に蓋をしていた、様々な不安が噴出した姿が「敵」なのではないでしょうか。
ある洞察によれば、「敵」は外から来るように見えて、実は内から生まれている、とされています。これは非常に重要な指摘だと感じます。「敵」は儀助の心の産物であり、彼の脆弱性や抑圧された欲望、そして生と死という根源的なコントロール不能性と彼を向き合わせるための触媒なのです。彼の統制された生活は、「敵」という混沌によって根底から覆されます。
悪化していく状況の中にあっても、儀助は最後まで自身の理性にすがり、戦おうとします。しかし、相手は実体を持たず、内面に巣食う不定形の存在です。この戦いに勝ち目がないことは、初めから運命づけられていたのかもしれません。彼の闘いは、理解を超えた力に直面した人間の普遍的な苦闘の縮図とも言えるでしょう。
作中にある「あなたは自分で自分を殺す人なのよ」という言葉は、この物語の核心を突いています。「敵」が主に内的なものであるならば、儀助は自分自身と戦っていることになります。それは、自らの心と身体の、避けられない変化との戦いです。この悲劇的な構図こそが、この物語に深い奥行きを与えているのです。
「敵」を多角的に捉えると、その恐ろしさがさらに増します。まず、「敵」は老いと心身の衰弱そのものとして解釈できます。できていたことができなくなり、持っていたものを奪っていく存在。それはまさしく、多くの人が恐れる「老い」の姿です。老いることに伴う肉体的、経済的な困窮、孤独、そして死への恐怖、それら全てが「敵」として儀助に襲いかかります。
同時に、「敵」は彼の内面化された不安や、精神の断片化のメタファーでもあります。彼の意識の深層に潜む、漠然とした恐怖が具現化したものです。彼が築き上げた理性の壁が崩れるとき、抑圧されていたものが歪んだ形で噴出する。その残酷なまでの描写に、私たちは戦慄を覚えるのです。
さらに、「敵」は形而上学的な、あるいは実存的な脅威としても捉えられます。秩序が失われ、非合理的な混沌が世界を支配するのではないかという根源的な恐怖です。儀助の知性は、この非合理的な「敵」を前にして無力です。理解しようとすればするほど、彼は苦悩の深みにはまっていく。彼の理性が、彼自身を苛む道具となってしまうのです。
物語の終盤、儀助は完全に「敵」に飲み込まれます。彼の理性の砦は陥落し、その意識は妄想と恐怖の世界に完全に屈服します。その壊れていく過程の描写は、圧巻の一言です。彼の内的世界の闘争が、いかに凄まじいものであったかを物語っています。
しかし、物語は儀助が「どうなったか」を明確には示しません。狂気に堕ちたのか、死んだのか、それとも「敵」という新たな現実に吸収されたのか。その結末は曖昧なまま、読者の解釈に委ねられています。この曖昧さこそが、この物語の余韻を深くしていると言えるでしょう。「敵」に飲み込まれた彼の最後の状態は、ある意味では、かつての理知的な自己が抱えていた不安から解放された姿なのかもしれません。しかし、そのために失った代償はあまりにも大きいのです。
まとめ
筒井康隆さんの小説『敵』は、一人の老知識人の日常が、正体不明の「敵」によって静かに、そして容赦なく崩壊していく様を描いた、強烈な作品でした。緻密に構築された秩序が、パソコンに表示されたたった一文のメッセージから脆くも崩れ去っていく過程は、読む者の心に深い不安を刻みつけます。
この物語における「敵」とは、単一の存在ではありません。それは老いそのものであり、主人公の内なる不安の表れであり、さらには存在を脅かす非合理的な力そのものでもあります。この多義性こそが、物語に底知れない深みを与えているのだと感じます。
主人公の儀助は、最後まで理性で抵抗しようとしますが、その知性こそが彼をより深い混乱へと導いてしまいます。そして訪れる結末は、彼の意識が完全に「敵」に支配されるという、ある種の破滅です。しかし、その状態は明確に描かれず、読後に重い問いを残します。
本作は、人間の精神がいかに脆いものであるか、そして私たちが拠り所としている日常や理性が、いかに薄氷の上にあるのかを突きつけてくるようです。読点を極力排した独特の文体が、主人公の混乱した内面を追体験させ、読者を物語の世界へ深く引き込みます。