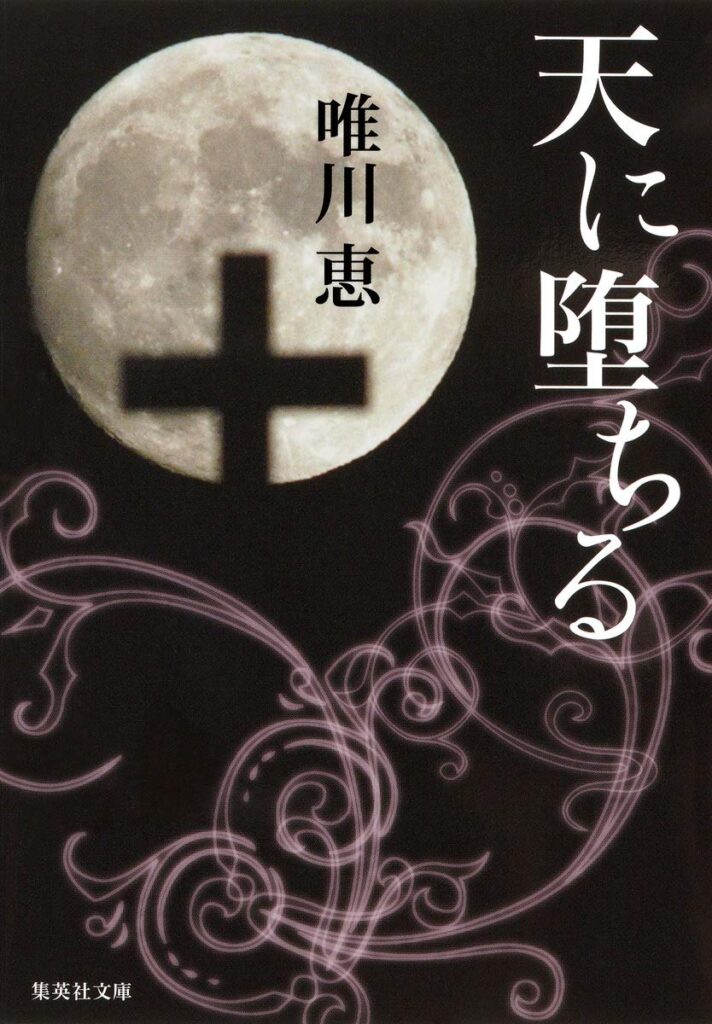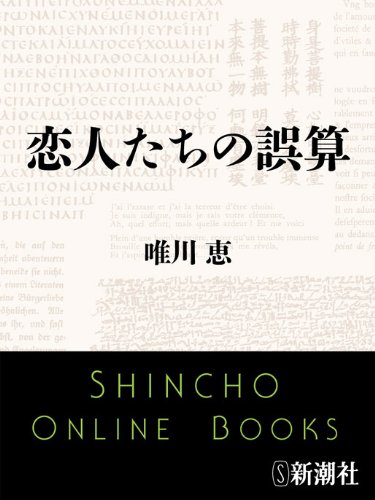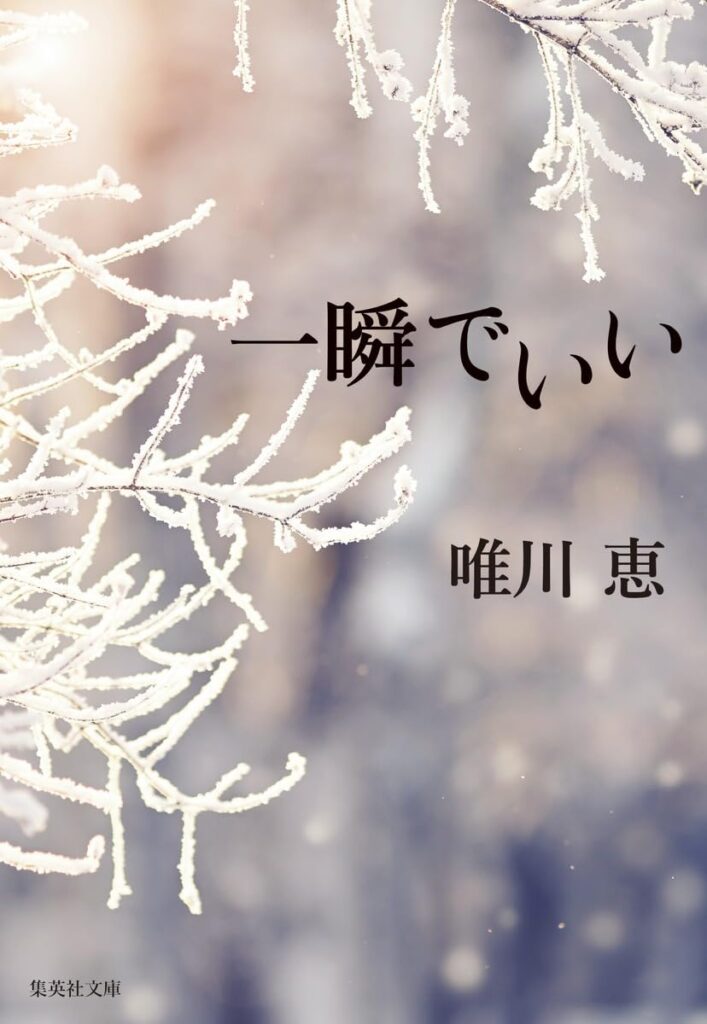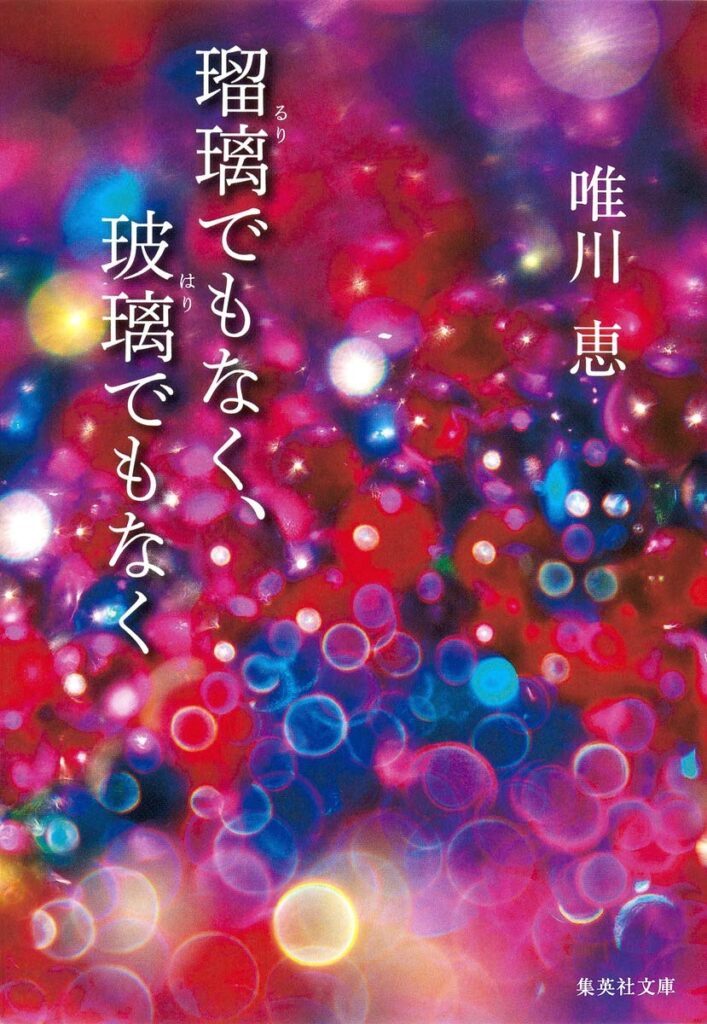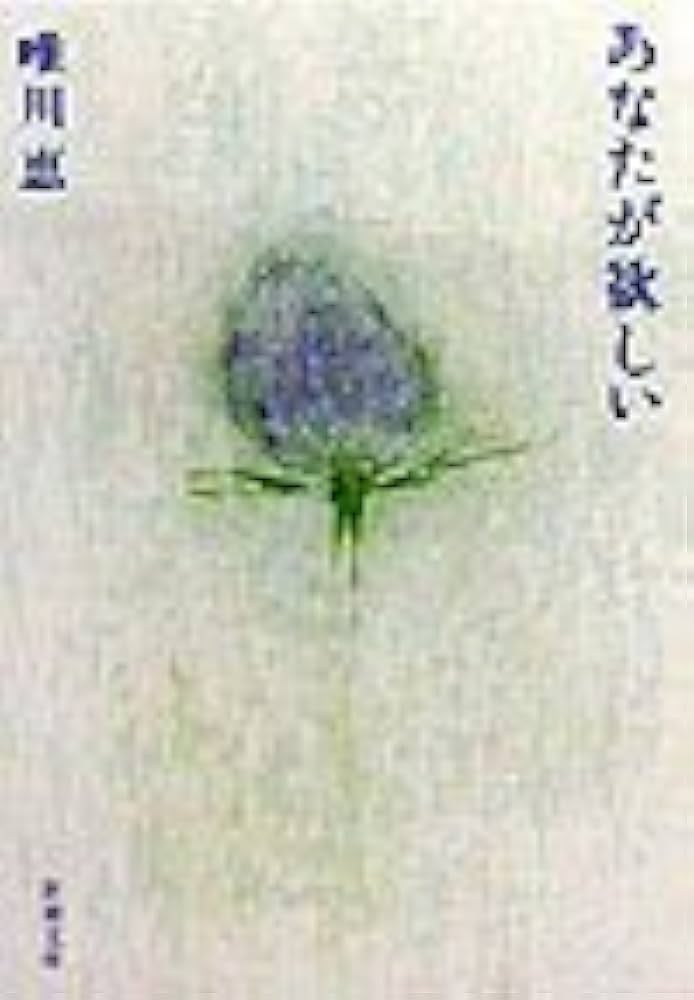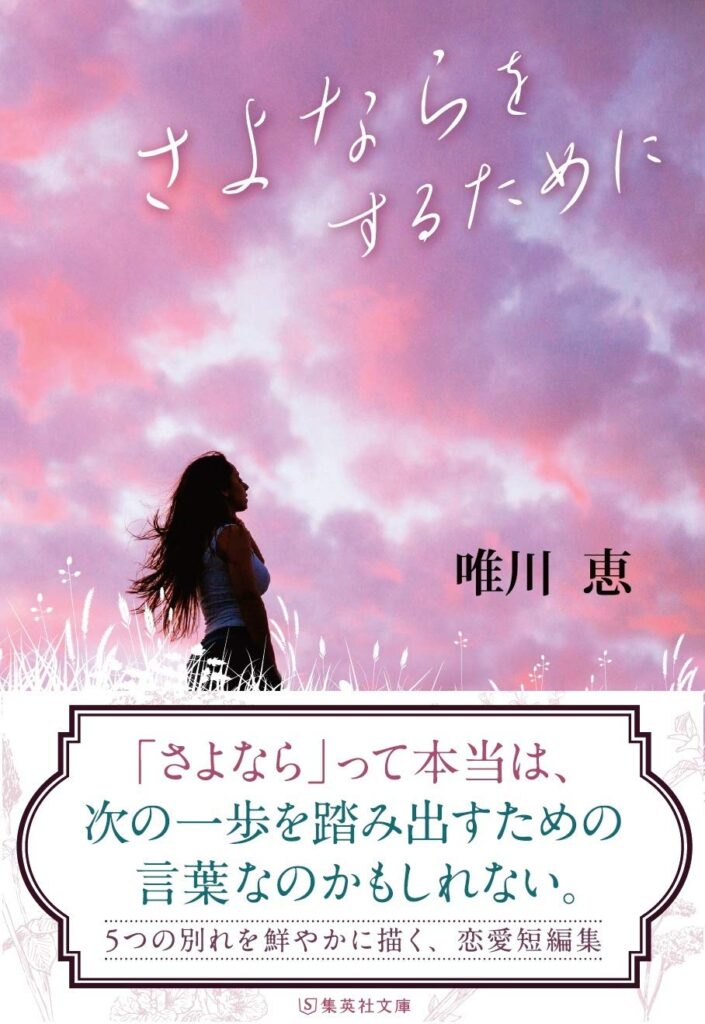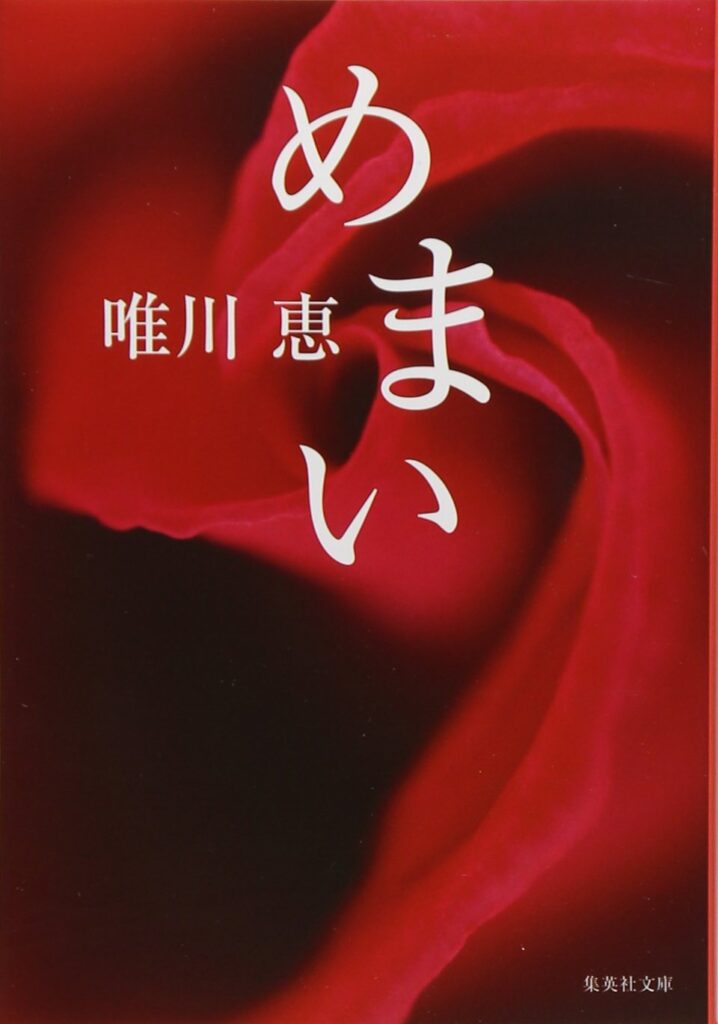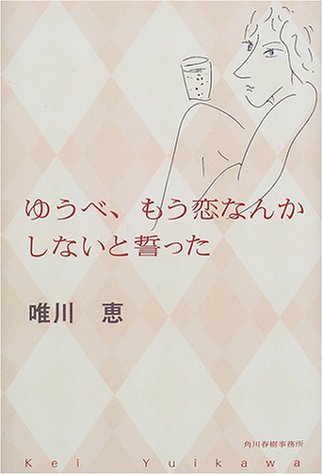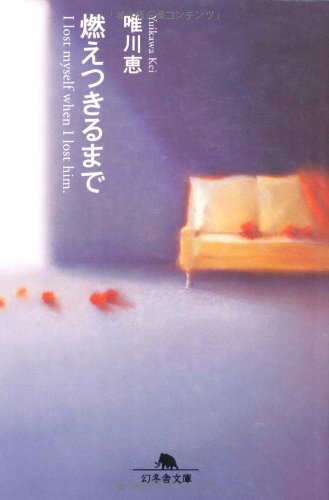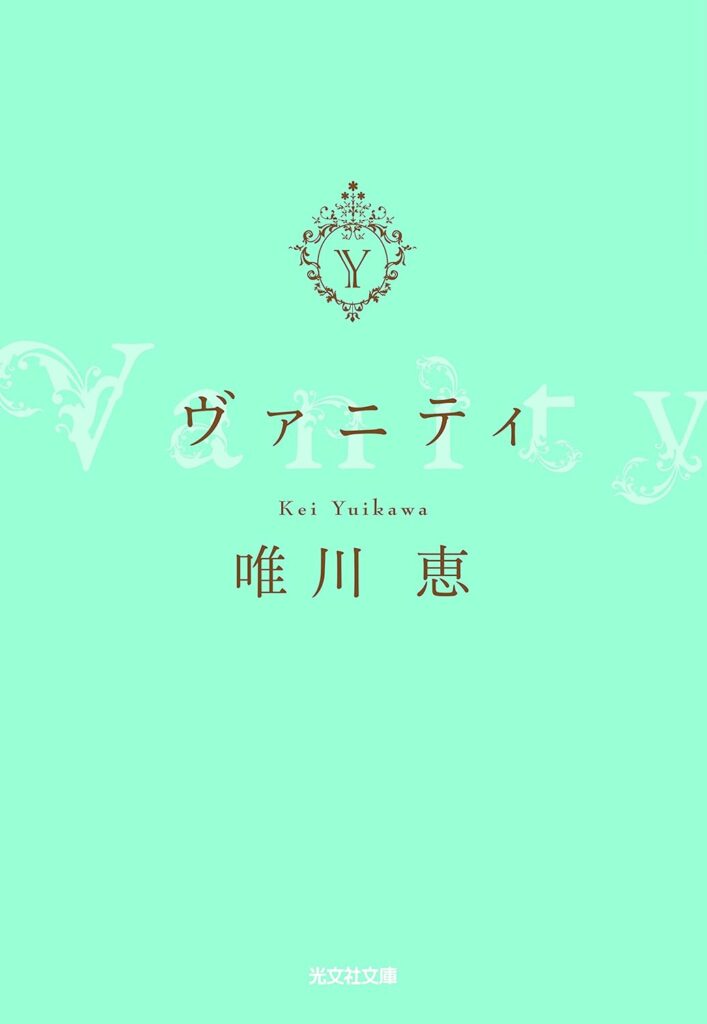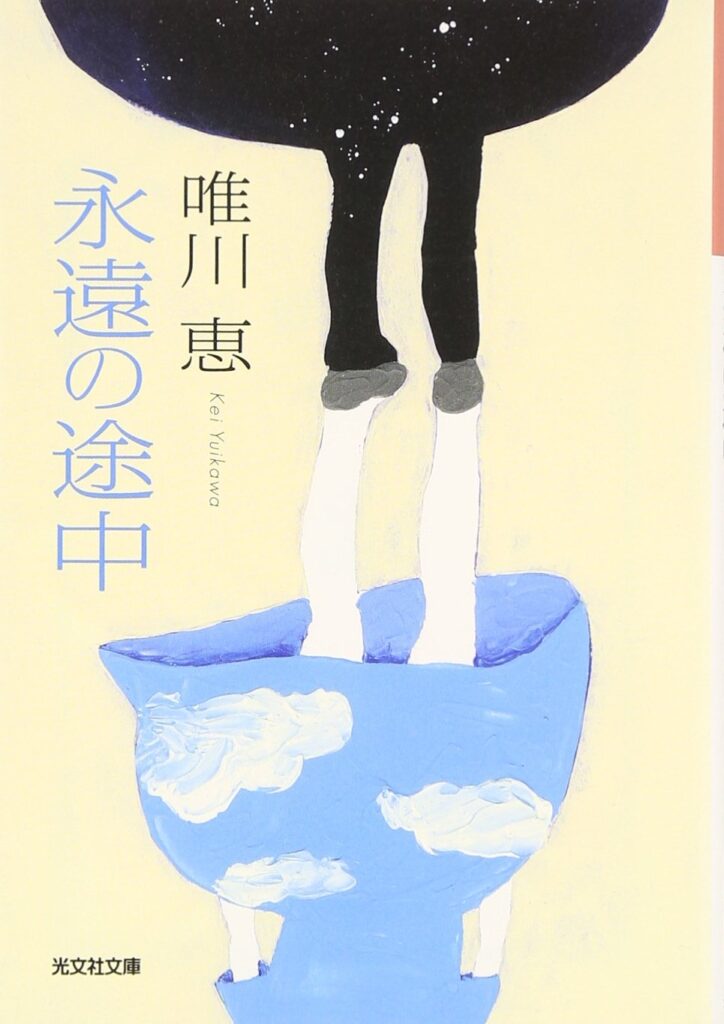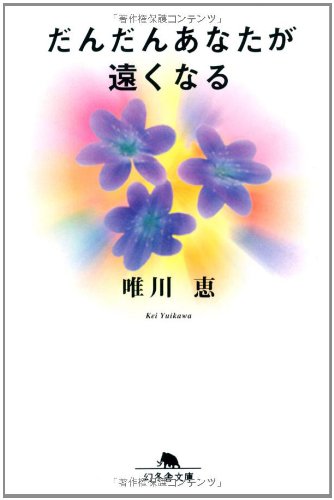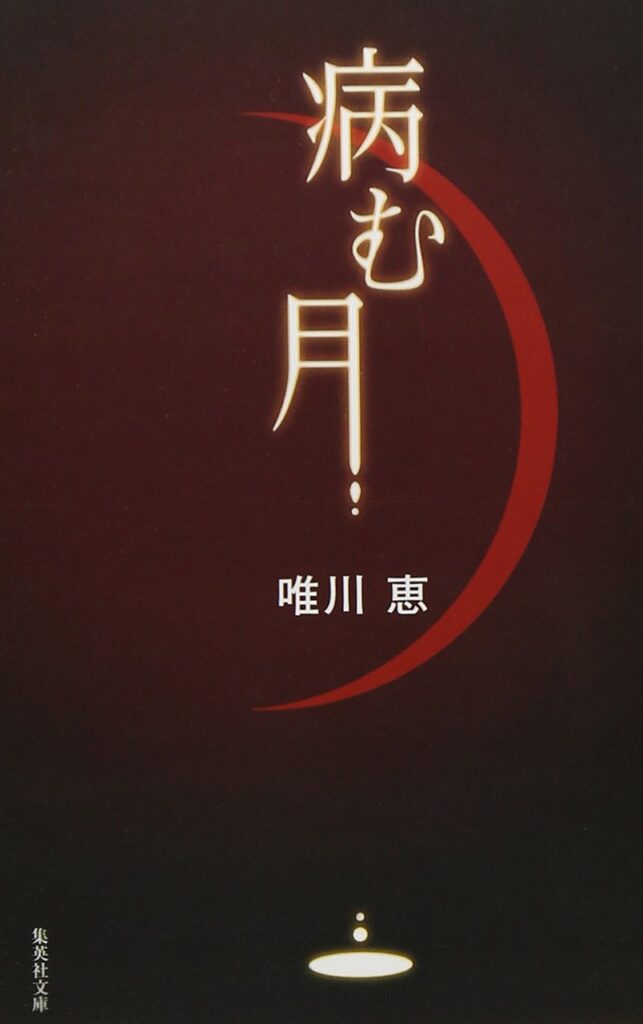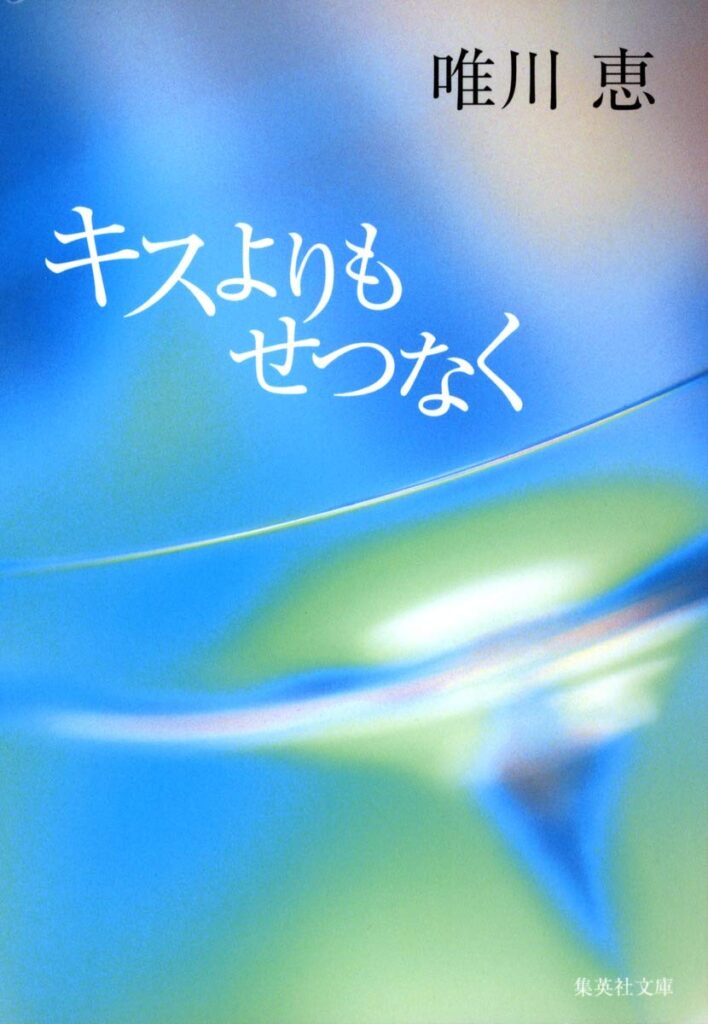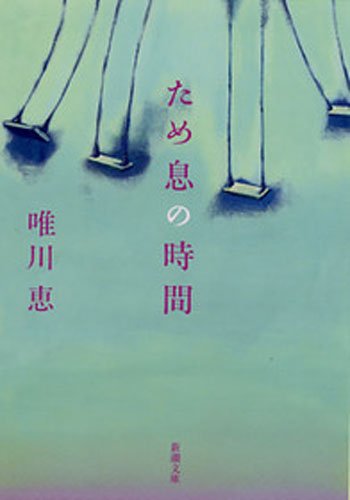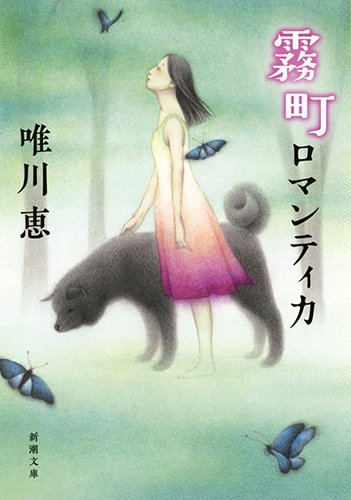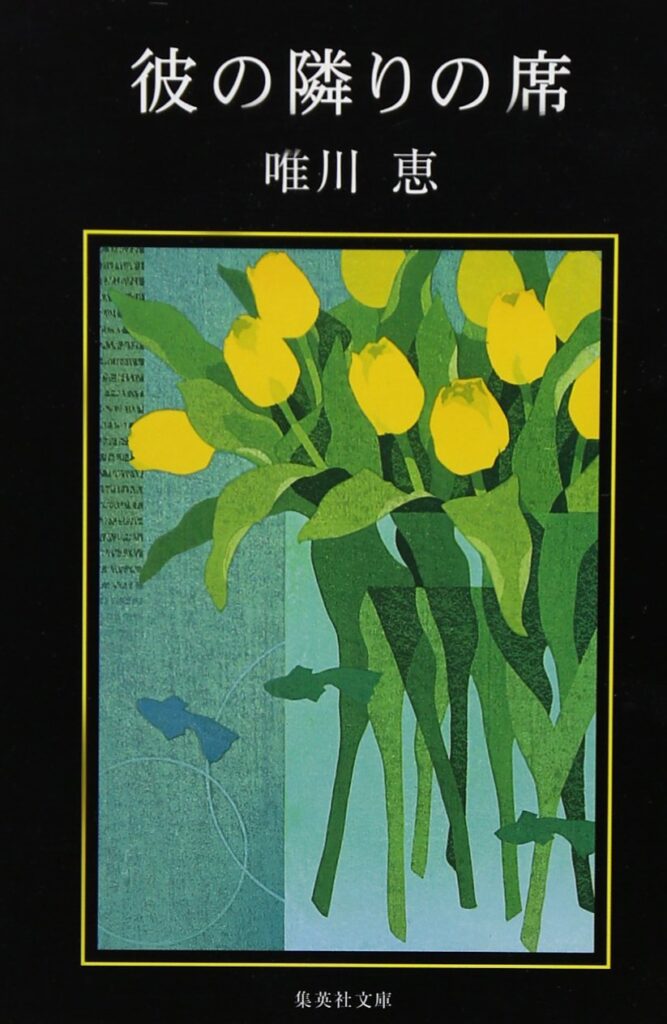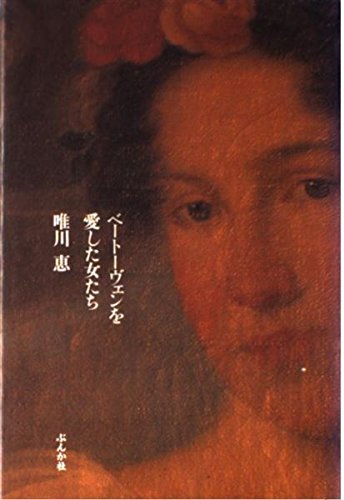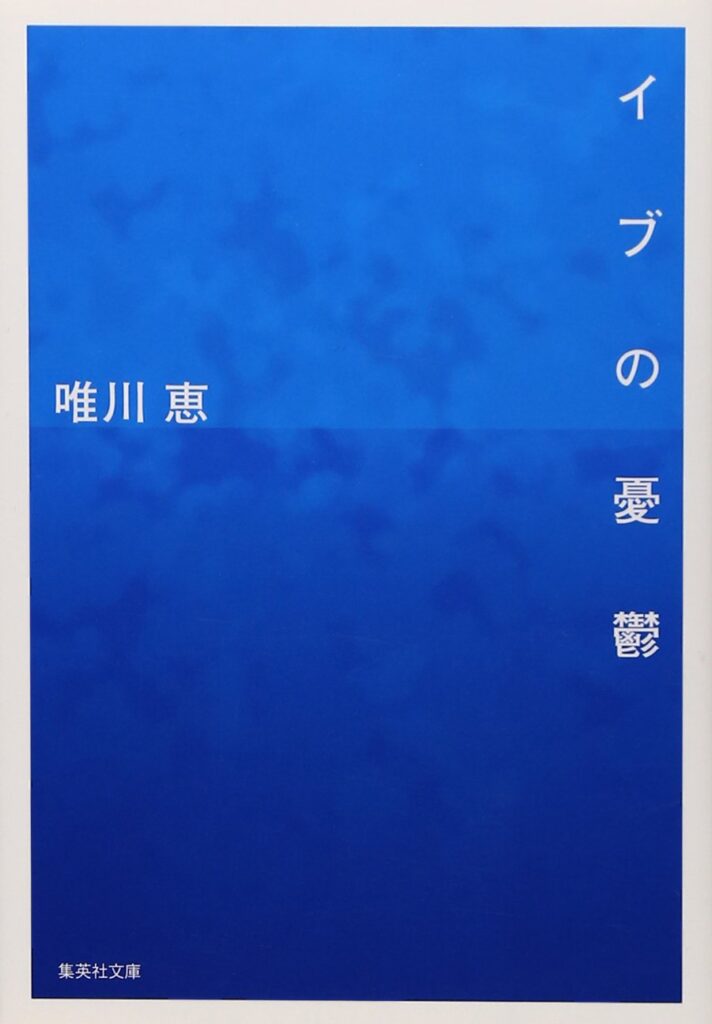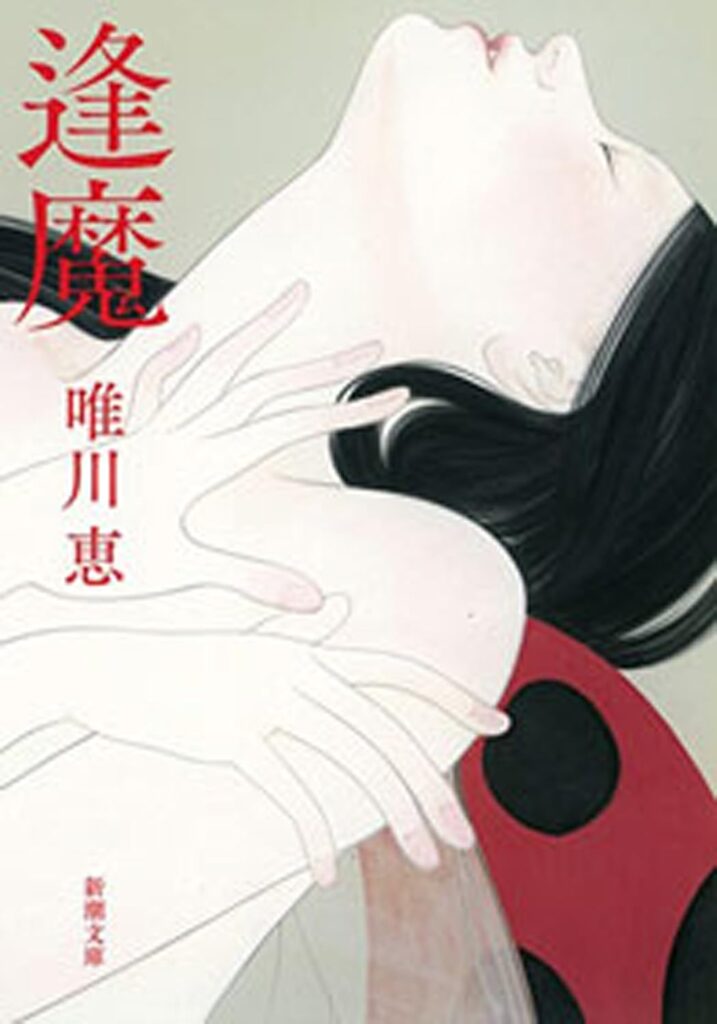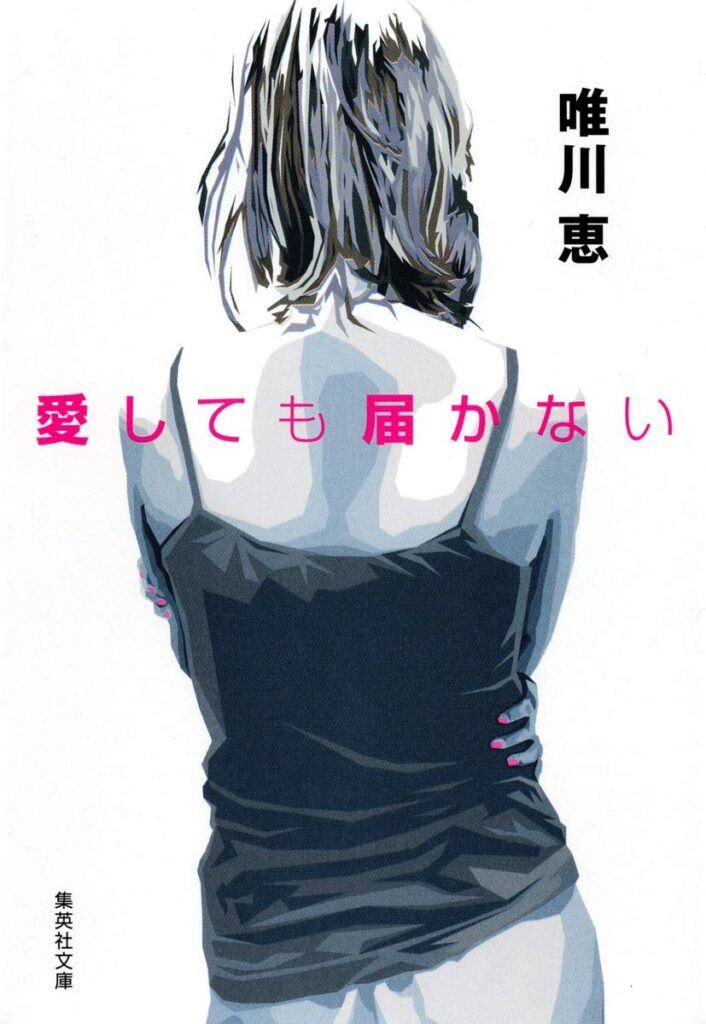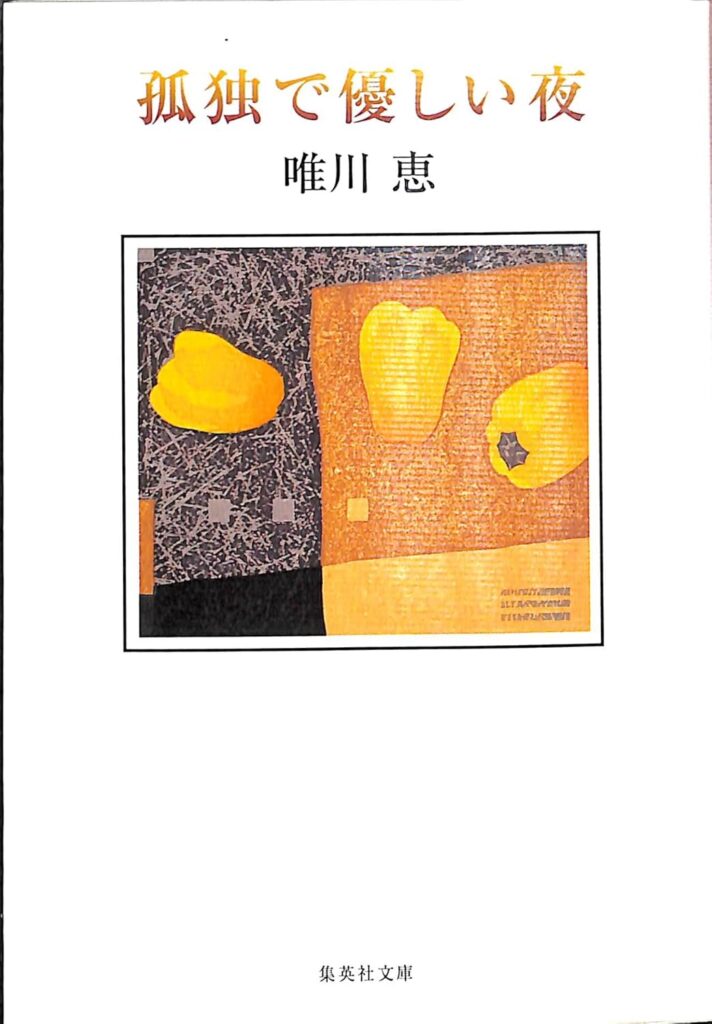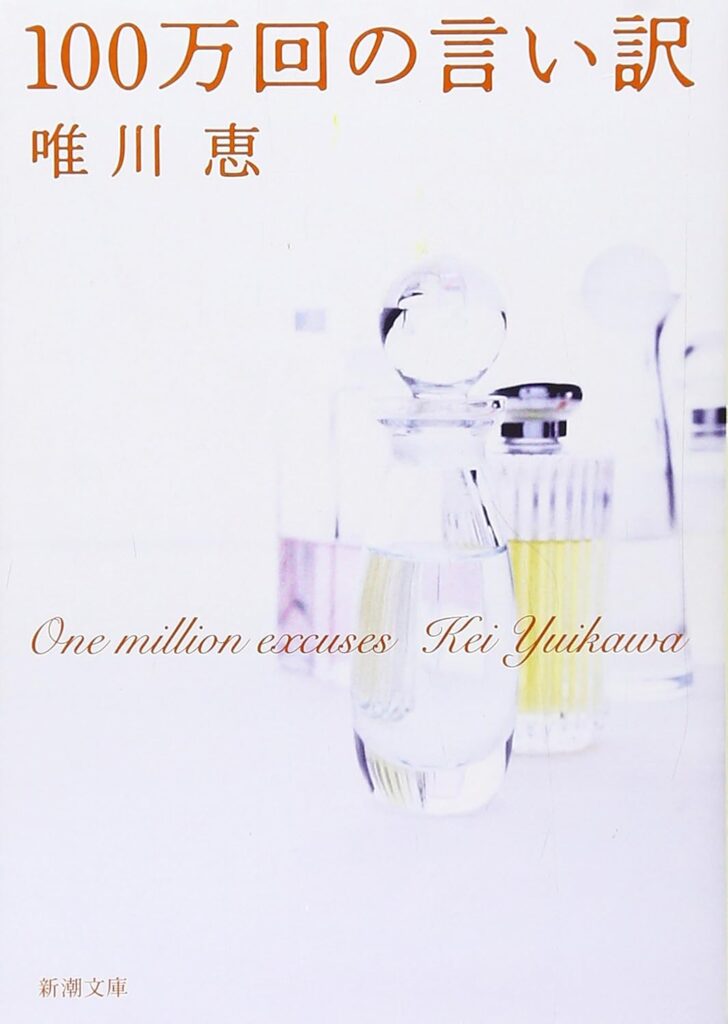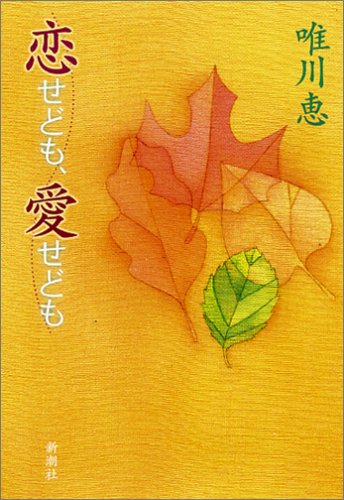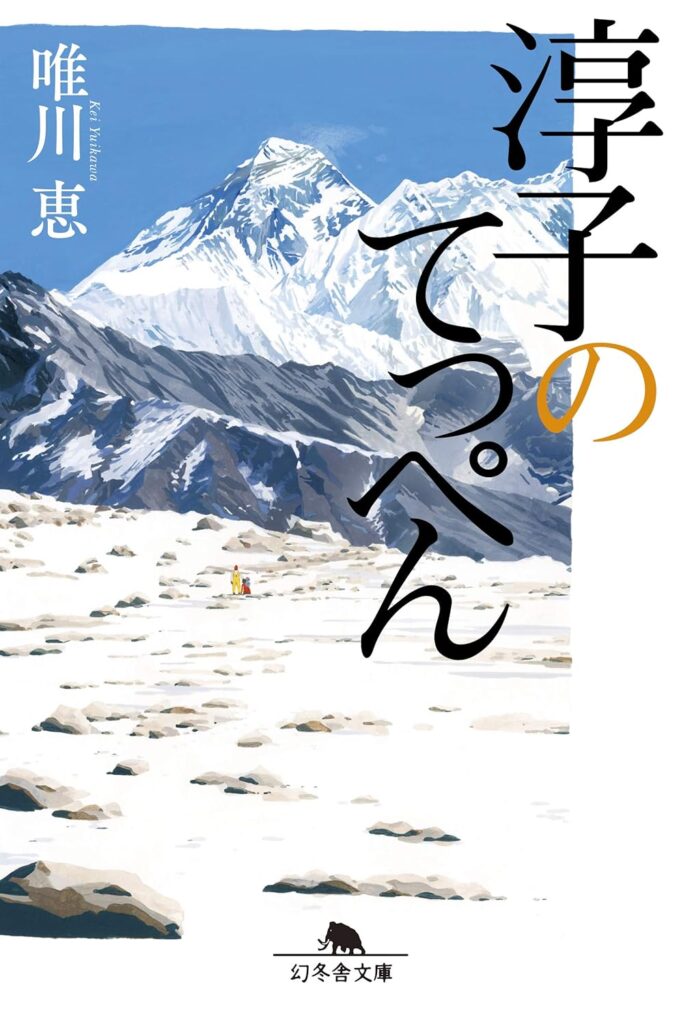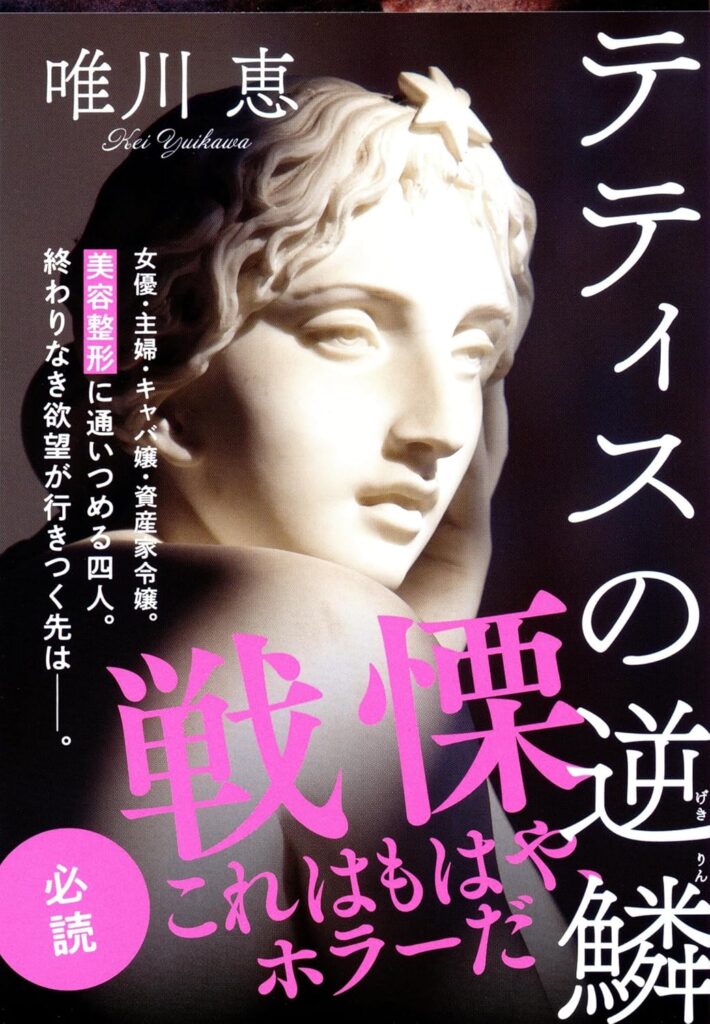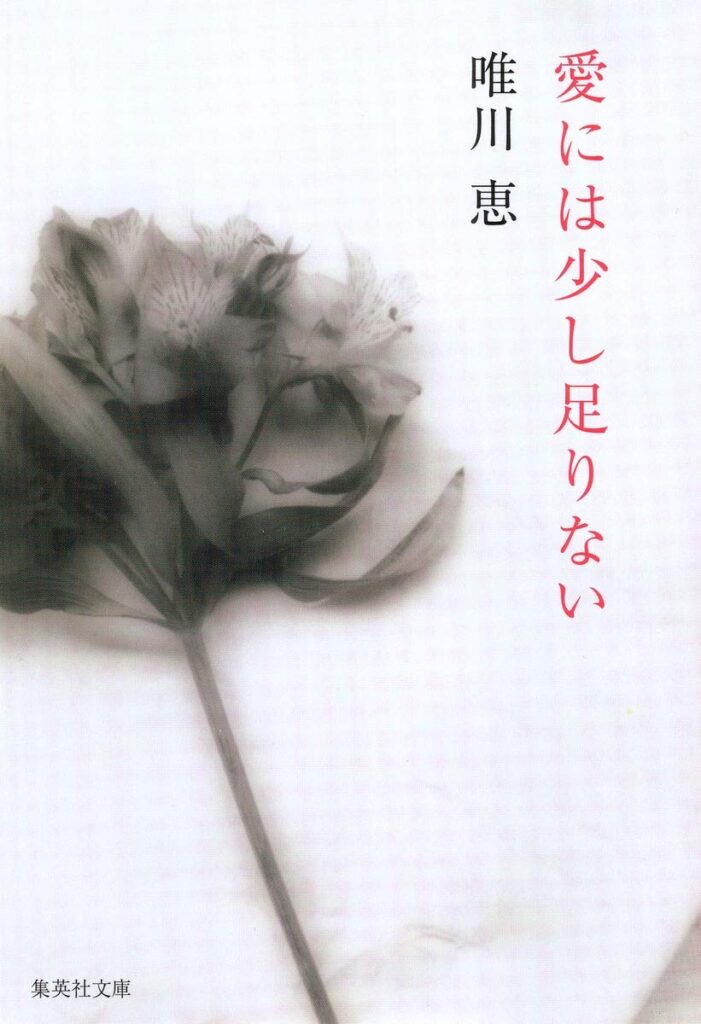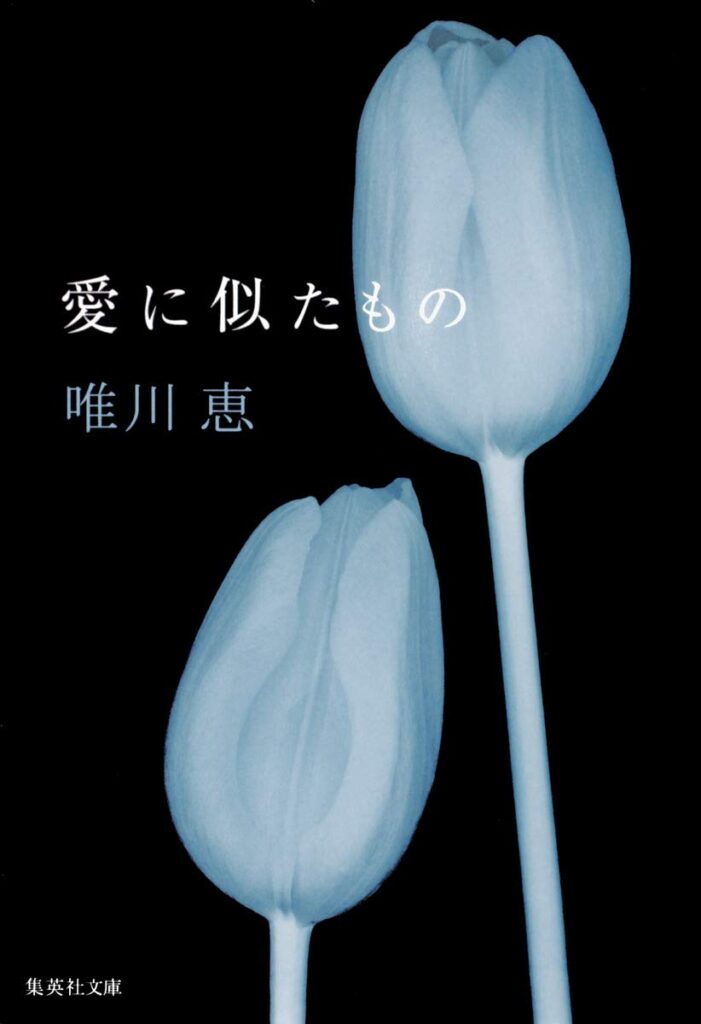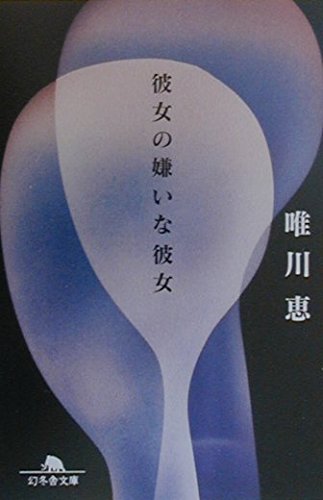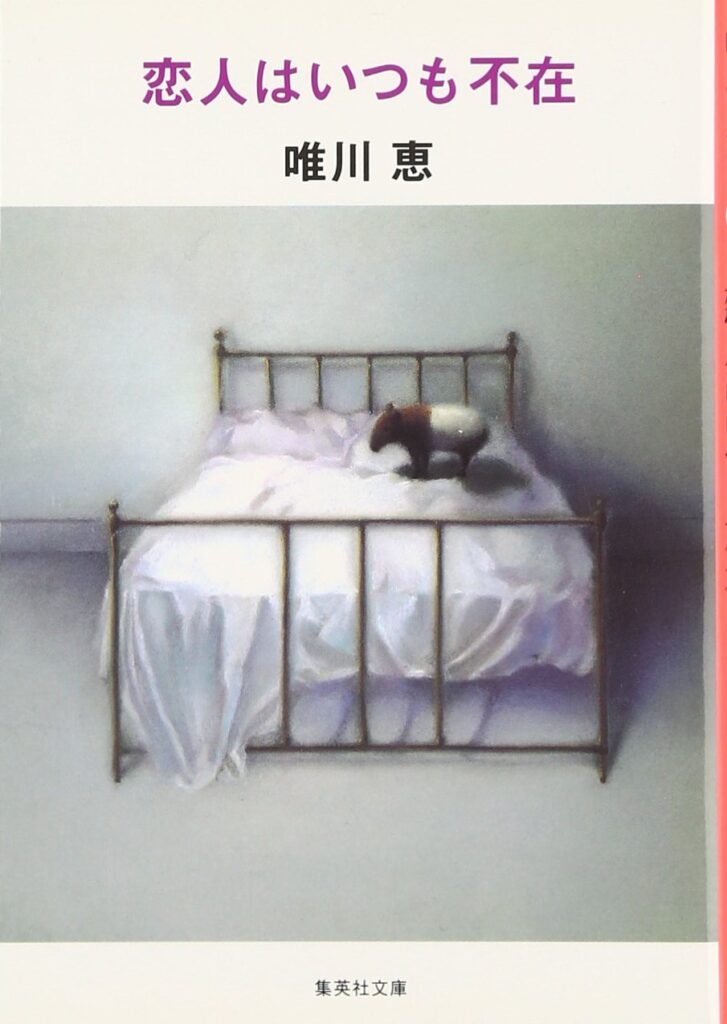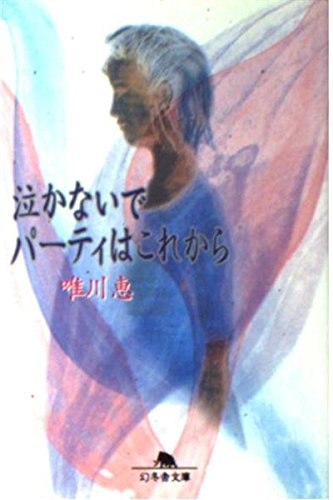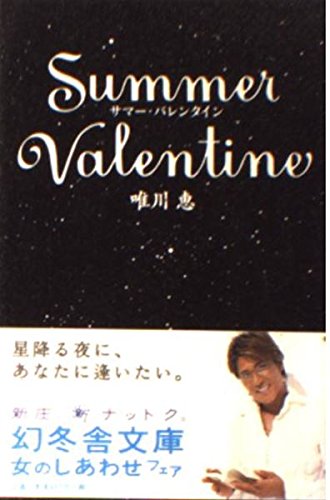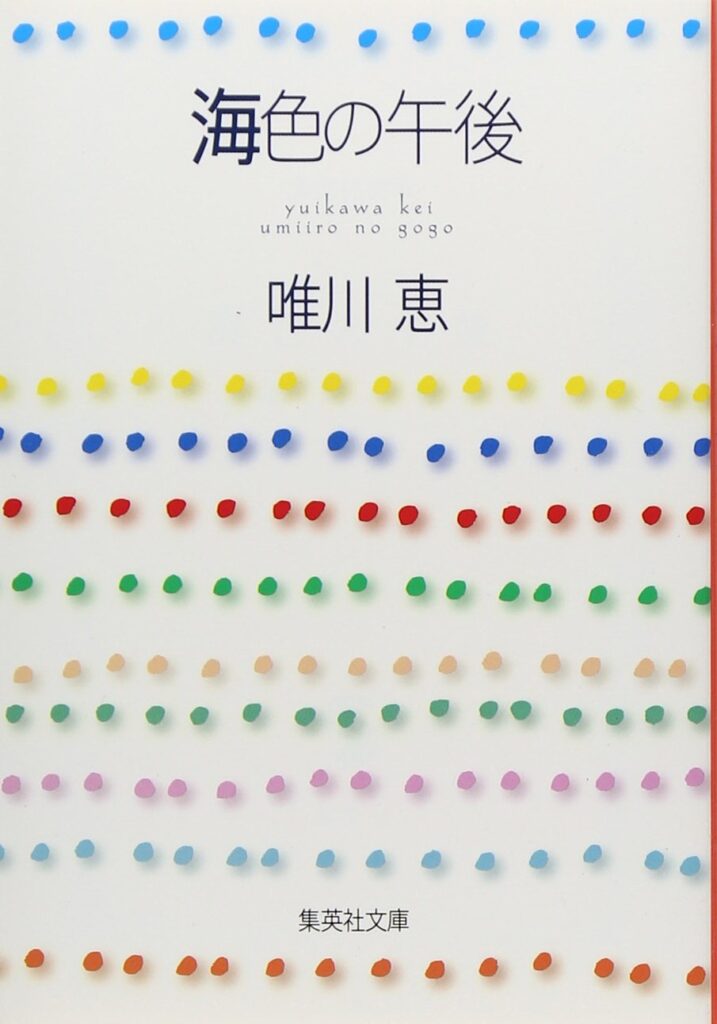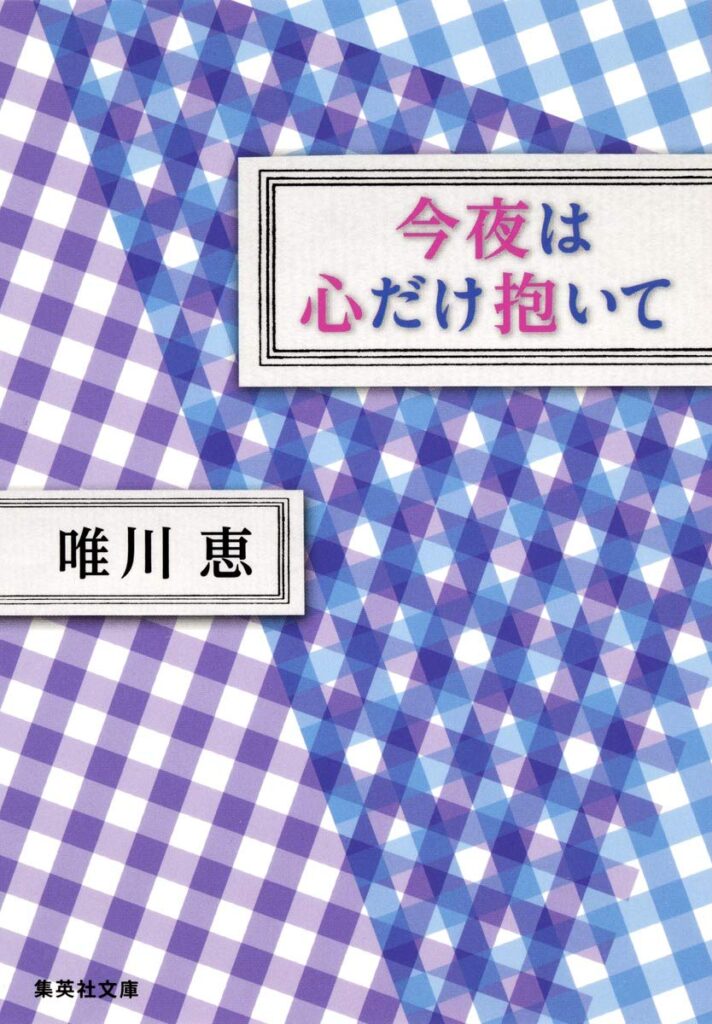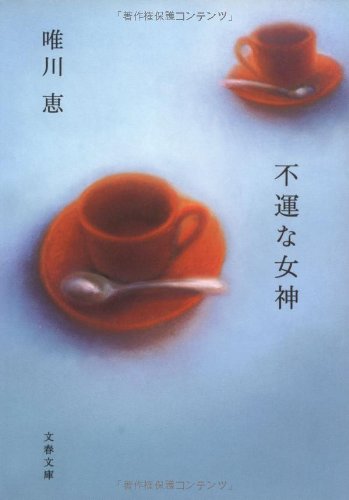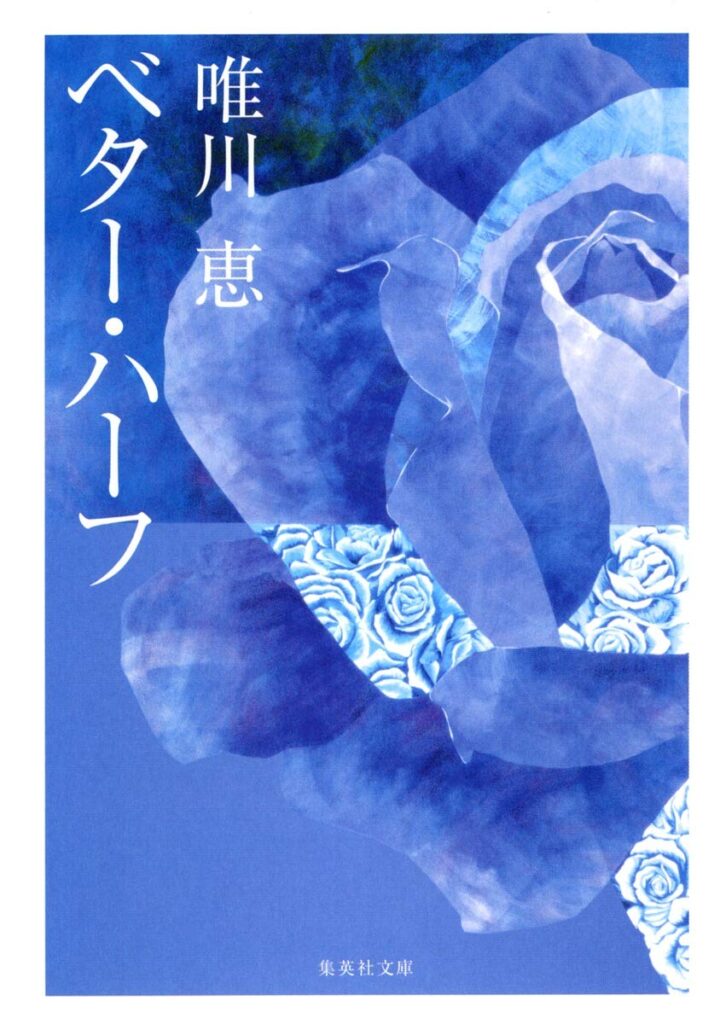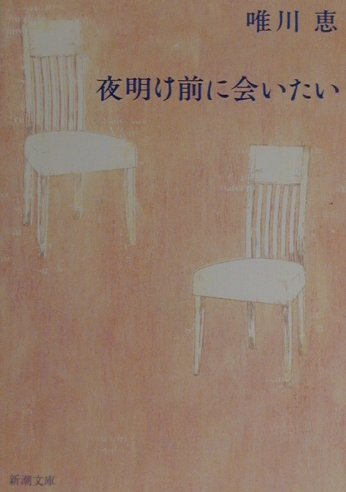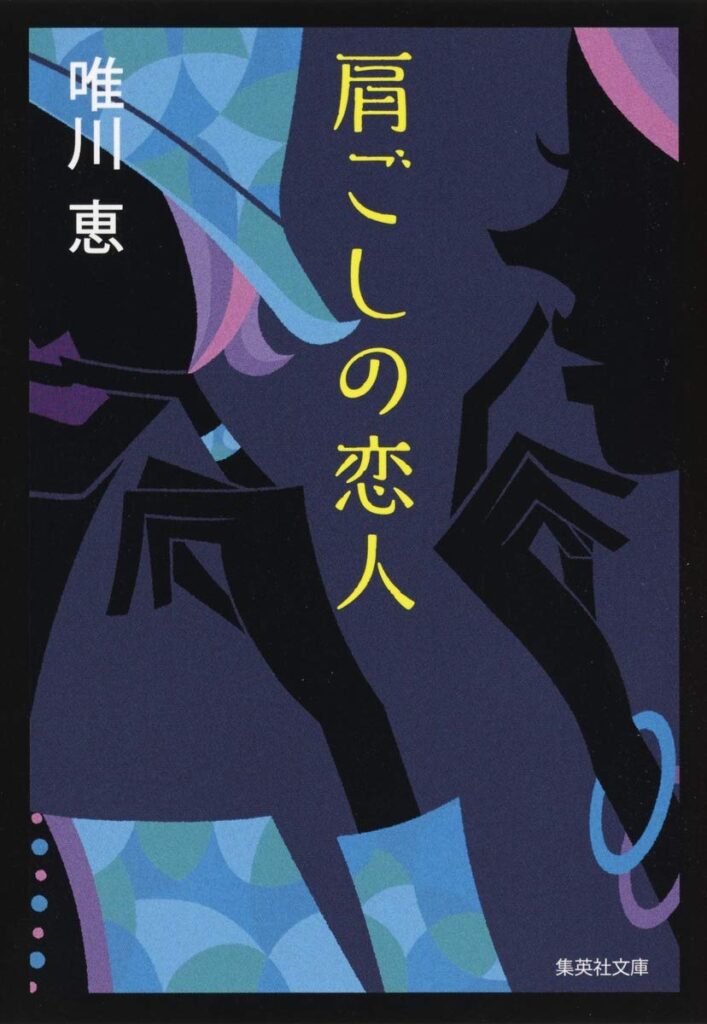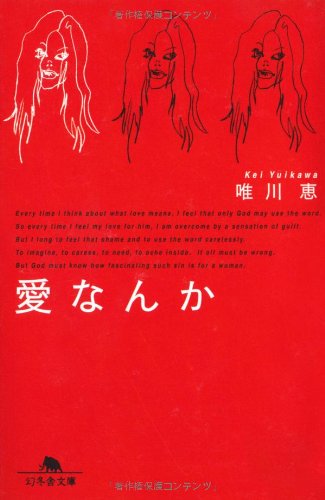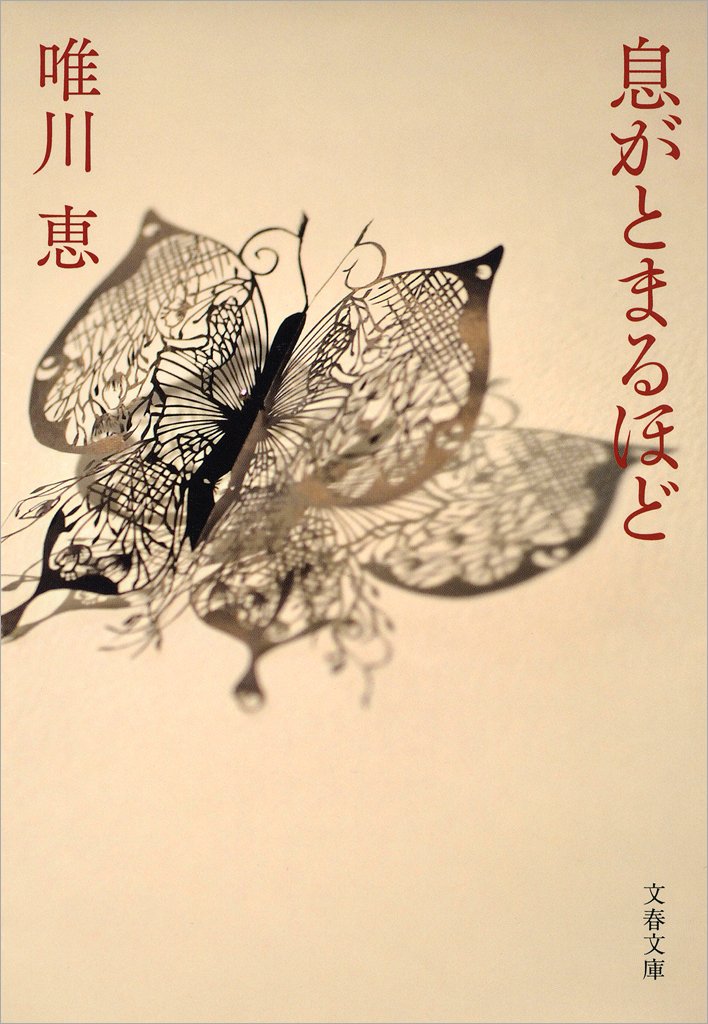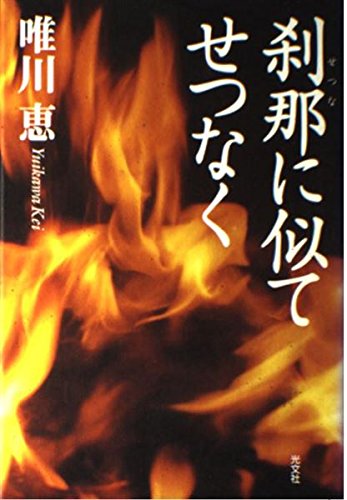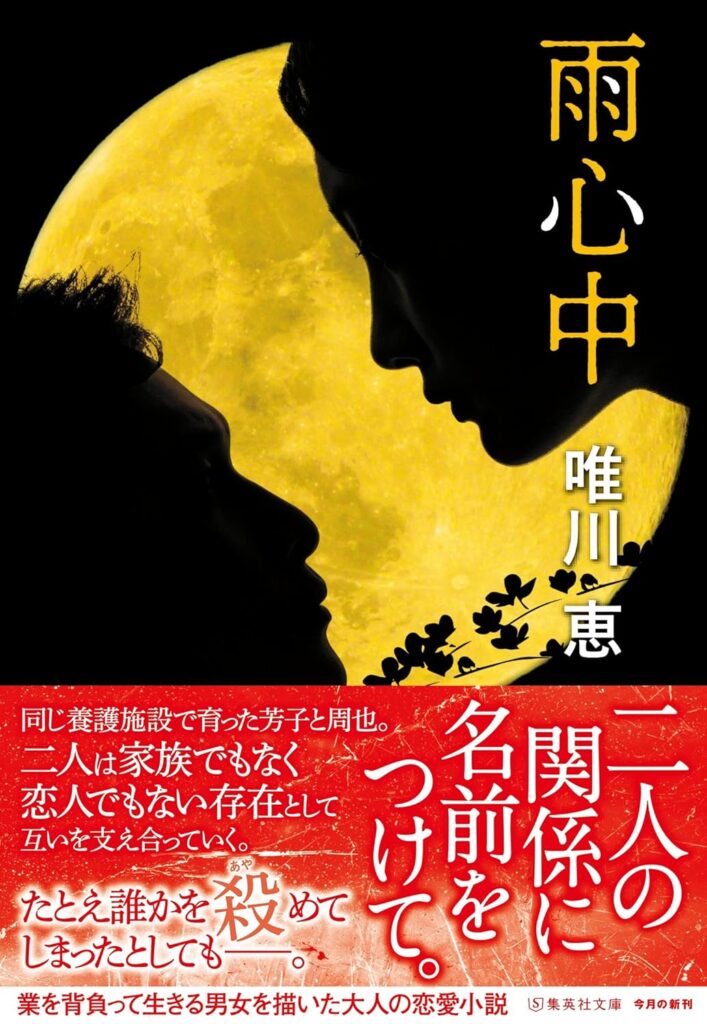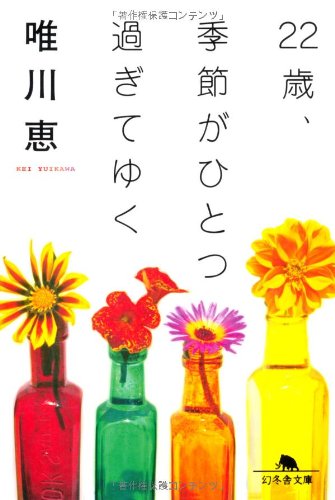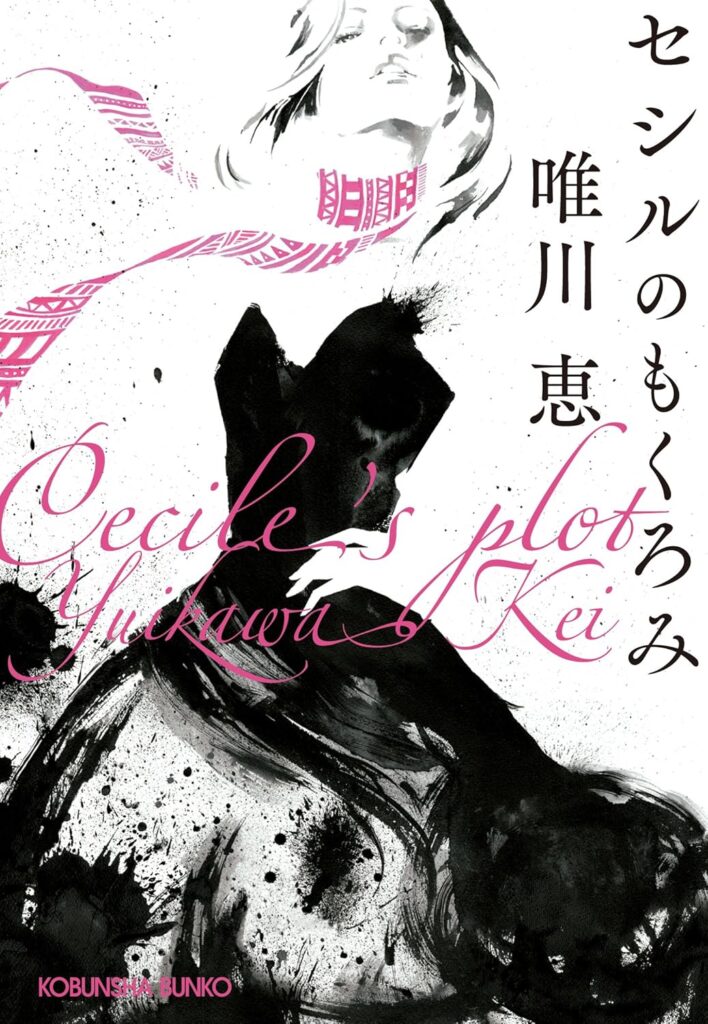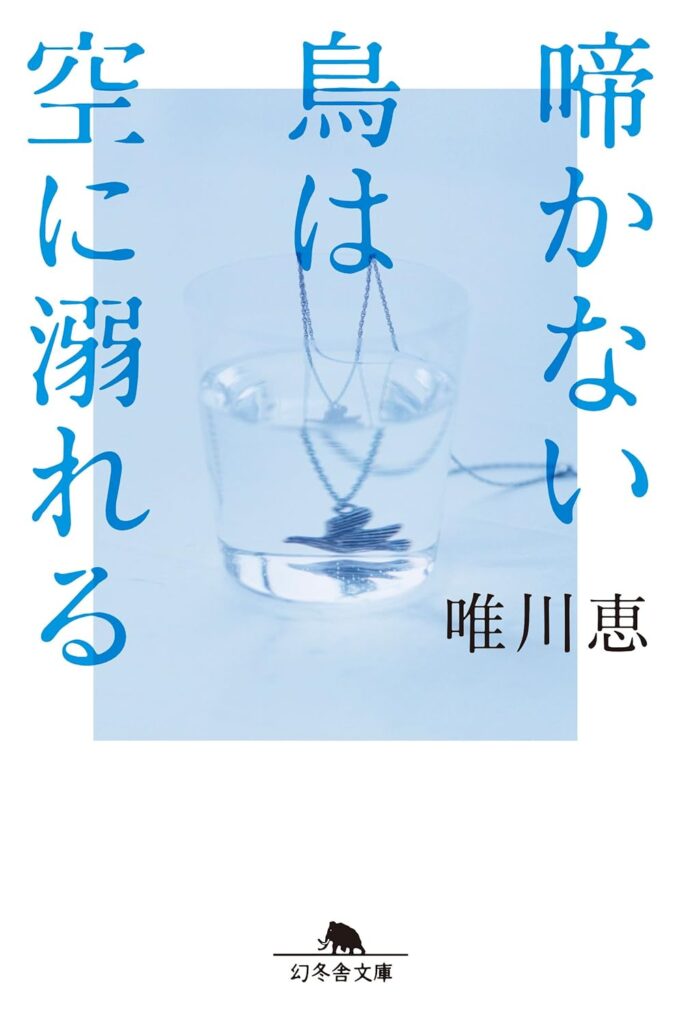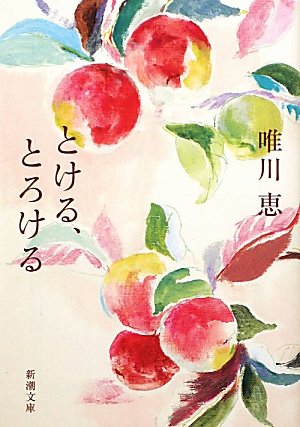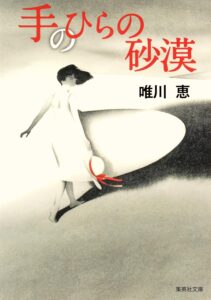 小説「手のひらの砂漠」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「手のひらの砂漠」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
恋愛小説の名手として知られる唯川恵さんが、ドメスティック・バイオレンスという非常に重いテーマに挑んだ本作。ページをめくる手が止まらない、強烈なサスペンスでありながら、人間の心の奥底にある脆さや強さを鋭く描き出しています。
この記事では、まず物語の骨子となる部分をご紹介します。どのような物語なのか、その入口をご案内いたしますね。そして、核心に触れる部分、つまり結末に至るまでの道のりを、私の思いを交えながら詳しく語っていきます。
物語の結末に関する記述を多く含みますので、まだ作品を読んでいない方はご注意ください。この物語が投げかける問いを、ぜひ一緒に深く考えていければと思います。
小説「手のひらの砂漠」のあらすじ
主人公の可穂子は、誰もが羨むようなエリートの夫・雄二と結婚し、専業主婦として平穏な日々を送っているように見えました。しかしその裏側で、彼女は雄二からの凄まじい暴力に耐える地獄のような毎日を送っていたのです。夫の暴力は日に日にエスカレートし、彼女の心と体を蝕んでいきます。
ある日、命の危険を感じた可穂子は、文字通り着の身着のままで家を飛び出します。警察に駆け込み、DV被害者を保護するシェルター、そして自立支援施設であるステップハウスへと身を寄せ、弁護士の助けを借りて離婚を成立させました。法的に夫との関係を断ち切り、ようやく手にしたはずの自由。
しかし、雄二の異常なまでの執着は、離婚という紙切れ一枚で消えることはありませんでした。可穂子が新しい生活を始めようとするたびに、まるで影のように雄二が現れ、彼女のささやかな希望を無慈悲に打ち砕いていくのです。逃げても逃げても追いかけてくる恐怖の中、可穂子は女性だけの農業共同体「えるあみファーム」にたどり着きます。
そこで束の間の安らぎと新たな出会いを見つける可穂子。ですが、雄二の執拗な追跡はそこにも忍び寄ります。公的な支援も法的な手続きも、狂気的な執着の前では無力なのでしょうか。逃げ場を失い、精神的に追い詰められた可穂子が、自らの手で安寧をつかむために下すことになる、ある決断とは一体何なのでしょうか。
小説「手のひらの砂漠」の長文感想(ネタバレあり)
この物語を読み終えたとき、心に残ったのはずっしりと重い感情と、一つの大きな問いでした。恋愛の機微を描くことに長けた唯川恵さんが、なぜこれほどまでに壮絶なDVというテーマを選んだのか。それは、本作が単なるサスペンスではなく、人間の尊厳と生存をかけた魂の物語だからに他ならないのだと、私は感じています。
物語の冒頭から、私たちは主人公・可穂子が置かれた息の詰まるような現実に引きずり込まれます。夫・雄二による暴力の描写は、目を背けたくなるほど生々しく、しかし決して目を離すことができません。それは読者に、これが決して他人事ではないのだという事実を突きつけてくるかのようです。
雄二という存在は、物語における恐怖の象徴です。社会的地位も高く、外面は完璧。しかしその内面は、理解不能なほどの支配欲と狂気に満ちています。彼の行動は常軌を逸しており、なぜそこまで可穂子に執着するのか、その動機は最後まで明確には語られません。その「わからなさ」こそが、彼の不気味さを際立たせ、読者に底知れぬ恐怖を植え付けます。
可穂子の逃亡は、DV被害者がたどる道のりを非常に現実的に描いています。警察、シェルター、ステップハウス。社会には確かに被害者を守るためのシステムが存在します。しかし、本作はそうしたセーフティネットでさえ、執拗な加害者の前では完璧ではないという厳しい現実を容赦なく見せてきます。
法的に離婚が成立した場面では、読者も可穂子と共に一瞬安堵のため息をつくでしょう。しかし、物語はそこからが本当の恐怖の始まりなのだと告げます。雄二のストーキングは、法的な関係の解消など意にも介しません。この展開は、DVが単なる夫婦間の問題ではなく、個人の尊厳をかけた終わりのない闘いであることを強く印象付けました。
そんな絶望の中で、一筋の光のように現れるのが、女性だけの農業共同体「えるあみファーム」です。男性のいないその場所は、傷ついた女性たちが互いの傷を舐めあい、癒やし、そして自立を目指す聖域のように描かれます。著者が描きたかったという「男のいない幸せ」の一つの形がここにありました。
ファームの主宰者である裕ママの存在も、物語に深い奥行きを与えています。彼女自身、ストーカーによって娘を亡くしたという癒えない悲しみを背負っている。だからこそ、彼女の言葉や行動には重みがあり、可穂子を、そして読者の心を打ちます。彼女の過去は、雄二の脅威が単なる嫌がらせではなく、死に直結する危険なものであることを予感させます。
ファームでの穏やかな生活の中で、可穂子に新たな恋の予感が芽生える場面は、この物語における数少ない救いの一つです。このまま幸せになってほしい、と誰もが願う瞬間でしょう。しかし、そのささやかな希望さえも、雄二は執拗に追い詰めて破壊しにきます。この繰り返しが、読者の心をじわじわと締め付けてくるのです。
雄二の追跡は物理的なものに留まりません。可穂子の人間関係を破壊し、彼女を社会的に孤立させようとします。その目的は、彼女を精神的に完全に支配し、絶望させることにあるのでしょう。希望が見えるたびに叩き落とされる展開は、本当に心が苦しくなります。
本作が特に巧みだと感じたのは、被害者の心理描写です。追い詰められる中で、可穂子は「自分が悪いのかもしれない」という思考に陥っていきます。これはDV被害者が抱える典型的な心理状態であり、その思考の罠の恐ろしさ、抜け出すことの困難さが痛いほど伝わってきました。
そして、可穂子は究極の思考へとたどり着きます。「自分が死ぬか、相手が死ぬか」。それ以外に、この苦しみから解放される道はないのではないか。平和な日常を生きる私たちにとっては過激に聞こえるかもしれませんが、物語を読み進めてきた読者には、彼女がそう思い詰めるまでの絶望が痛いほど理解できてしまうのです。
物語の大きな転換点となるのが、終盤で出会う一人の老婆です。彼女が可穂子に授ける「生の技法」。それは具体的なノウハウというよりも、生き抜くための心構え、一つの哲学のようなものでした。「逃げることは恥ではない、生の技法だ」という教えは、可穂子の心に深く突き刺さります。
この老婆との出会いを経て、可穂子は明らかに変わります。ただ怯え、逃げ続けるだけの被害者ではありません。自らの手で人生を取り戻すため、能動的に行動するサバイバーへと変貌を遂げるのです。彼女の中に、静かですが、燃えるような覚悟が生まれる瞬間でした。
そして物語は、避けることのできないクライマックス、可穂子と雄二の直接対決へと向かっていきます。著者が描きたかったという「殺すか殺されるか」という極限状況で「戦う」主人公の姿が、ここにありました。その場面の壮絶さは、息を飲むほどです。
結末を言えば、可穂子は雄二をその手で殺めます。正当防衛が成立するのか、法的にどう裁かれるのか、という視点もありますが、物語が読者に問いかけるのは、もっと根源的な部分です。彼女には、本当にそれ以外の選択肢がなかったのか。読んでいるこちらも、彼女の気持ちがわかると思ってしまうほど、追い詰められていたのです。
雄二という脅威が物理的に消え去った後、可穂子に訪れたのは、完全な解放感や幸福ではありませんでした。読後感として残るのは、むしろ「一抹の寂しさ」。手に入れた自由の代償はあまりにも大きく、彼女の心には消えない傷跡と、人を殺めたという重い事実が残り続けます。この単純なハッピーエンドではない終わり方が、物語に強い現実感を与えています。
そして、多くの読者が衝撃を受けたと語るエピローグ。唐突に登場する「伊原父娘」、そして「元さや家族」という謎めいた言葉。雄二はもういないはずなのに、「元さや」とは一体何を意味するのか。この結末は、さまざまな解釈を呼ぶでしょう。
私自身の解釈ですが、これは可穂子が過去から完全に自由になることはない、ということを示唆しているのではないでしょうか。雄二の影は、彼の死後も彼女の人生に何らかの形で影響を与え続ける。あるいは、彼女が築こうとする新しい家族の形が、また別の複雑さをはらむことになる。この謎めいた終わり方こそが、トラウマと共に生き続けるということの厳しさと、人生のままならなさを象徴しているように思えてなりませんでした。
まとめ
唯川恵さんの「手のひらの砂漠」は、DVという重く苦しいテーマを扱いながらも、読者をぐいぐいと引き込む力を持った傑作サスペンスです。主人公・可穂子が夫の暴力から逃れ、本当の自由を求めて戦う姿が描かれます。
この記事では、物語の序盤から結末に至るまでを、私の個人的な思いを交えながら詳しくご紹介してきました。彼女がたどる過酷な道のり、そして彼女が下した究極の選択。そこには、簡単には答えの出ない、深い問いが横たわっています。
物語は、衝撃的ともいえる結末を迎えます。しかし、それは決して後味の悪いものではなく、人間の強さと、生きていくことの複雑さを教えてくれるものでした。この物語は、読む人の心に深く長く残り続けるに違いありません。
もしあなたが、心を揺さぶるような、深く考えさせられる物語を求めているのなら、ぜひこの「手のひらの砂漠」を手に取ってみてください。可穂子の旅の終わりに何を見つけるのか、ぜひご自身の目で見届けてほしいと願います。