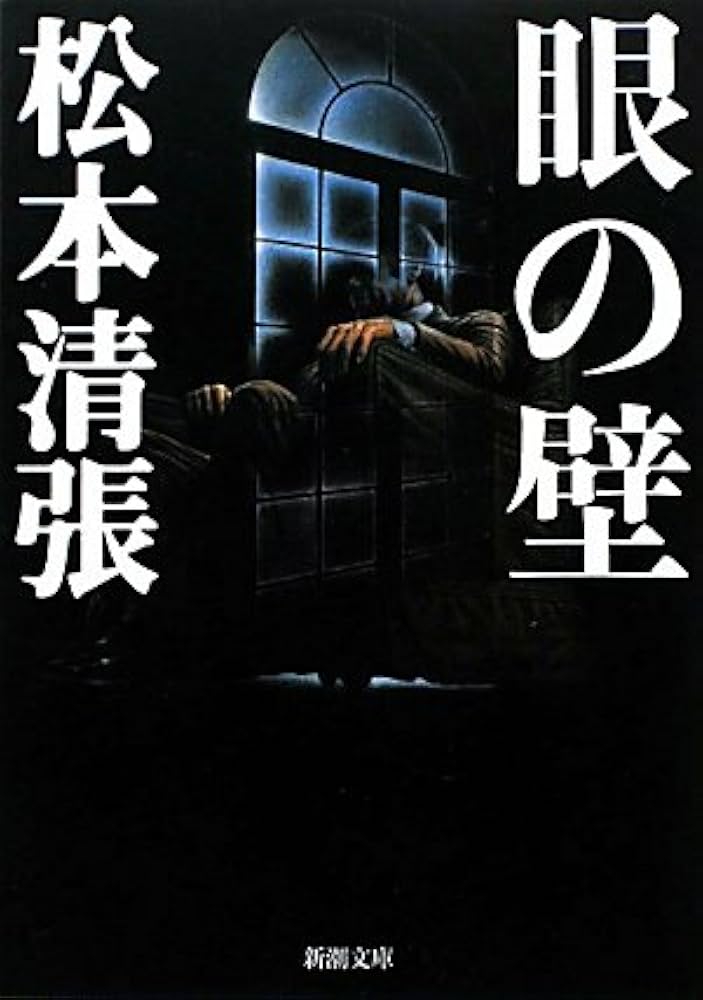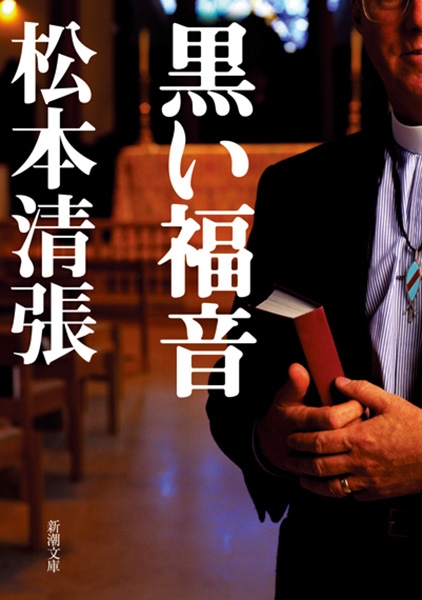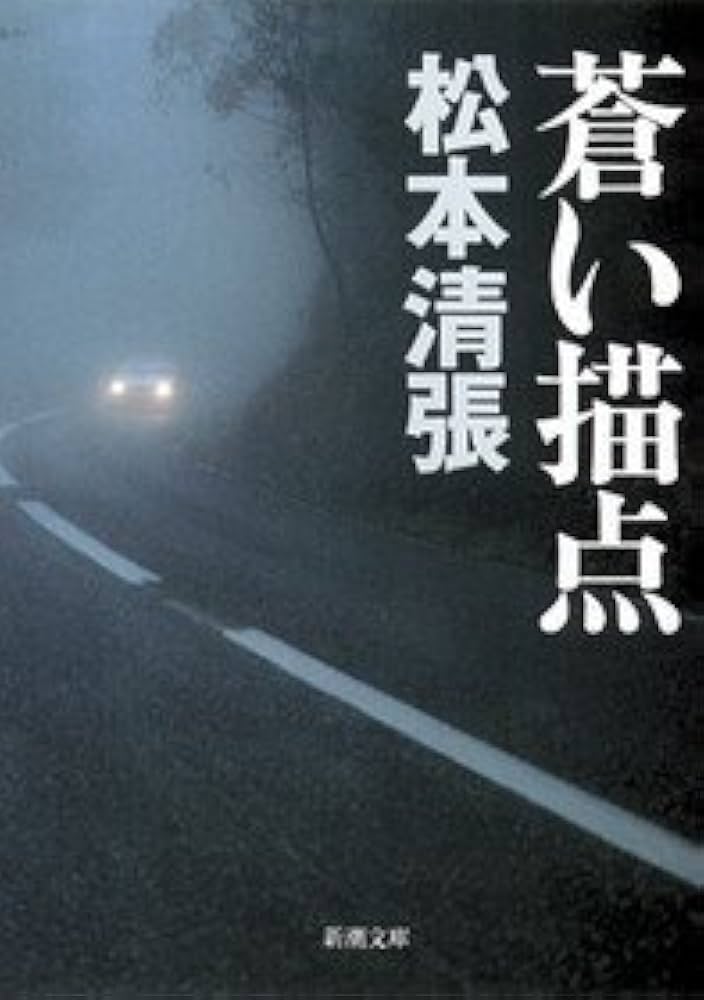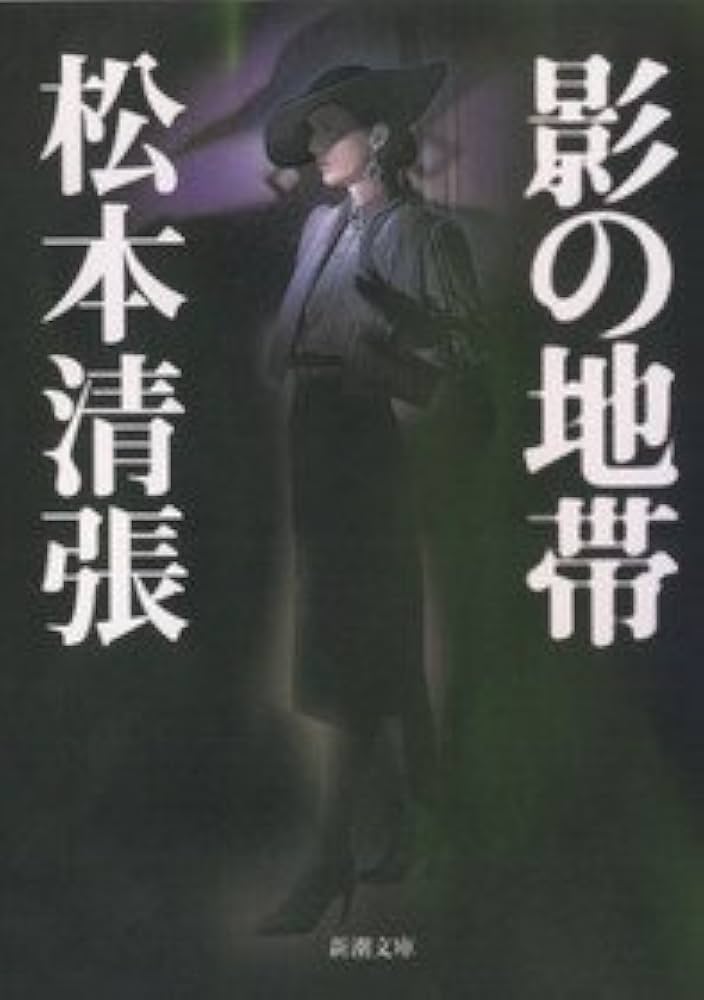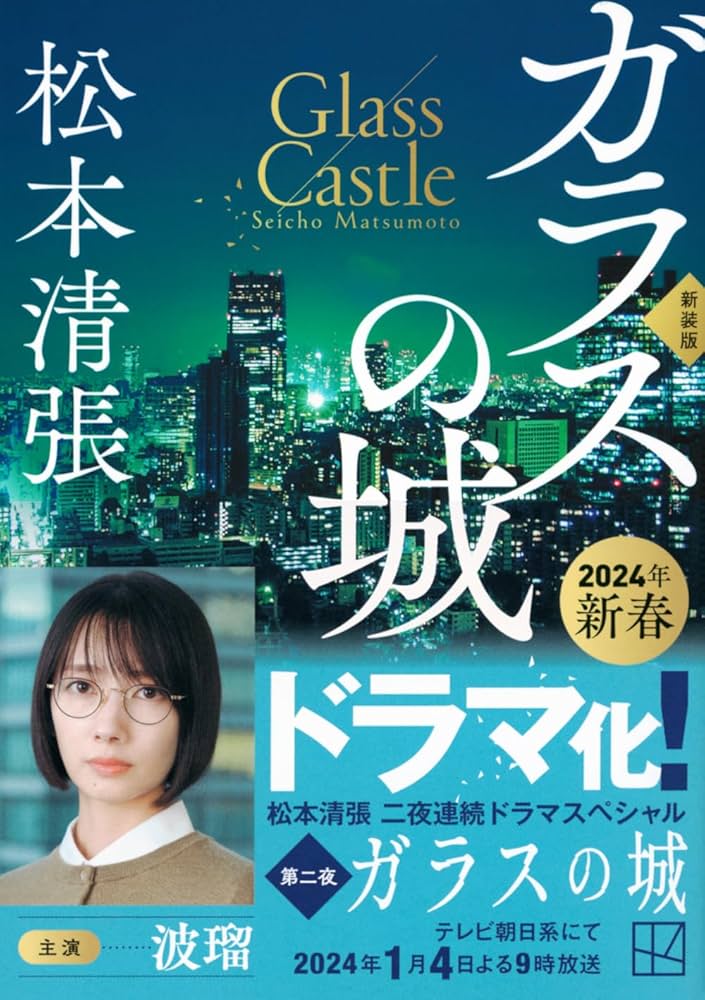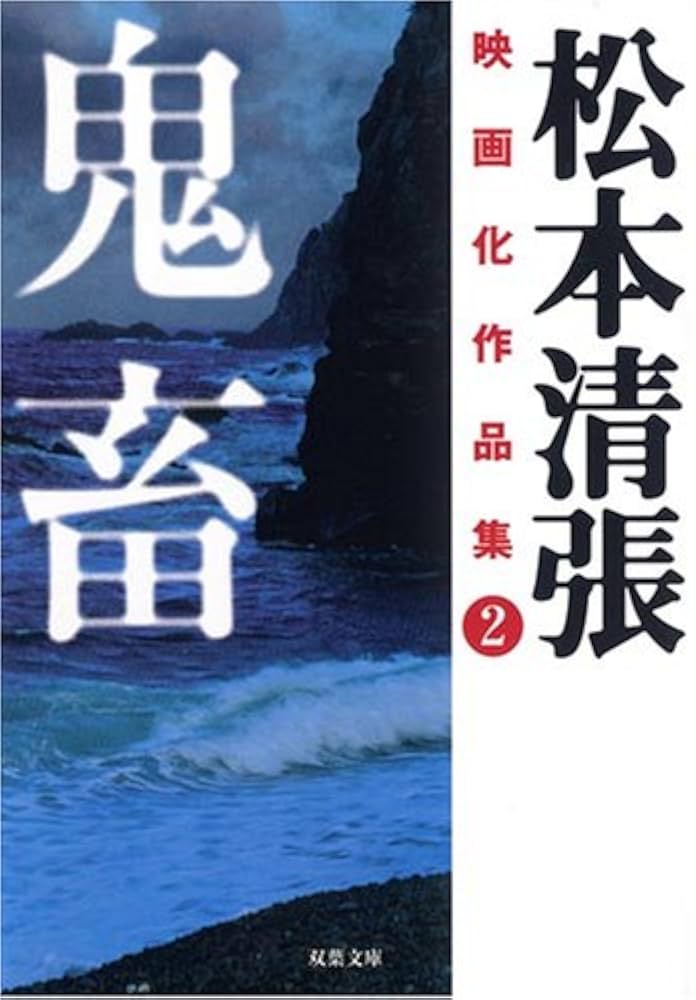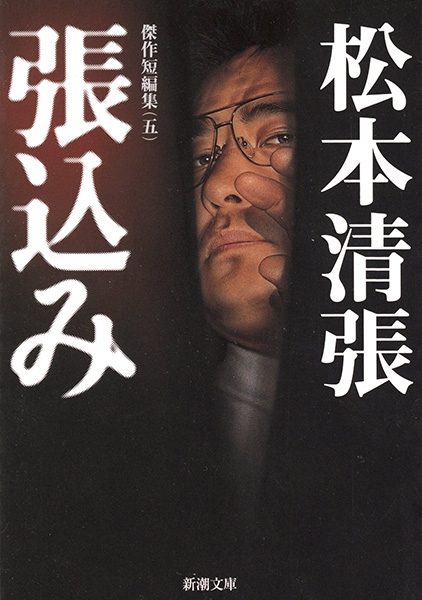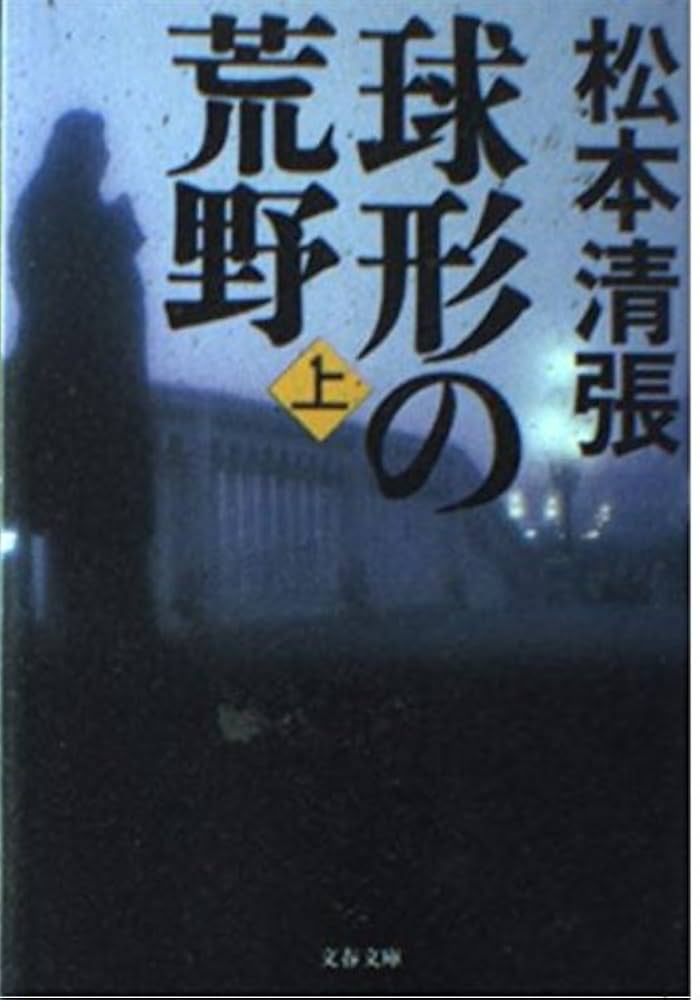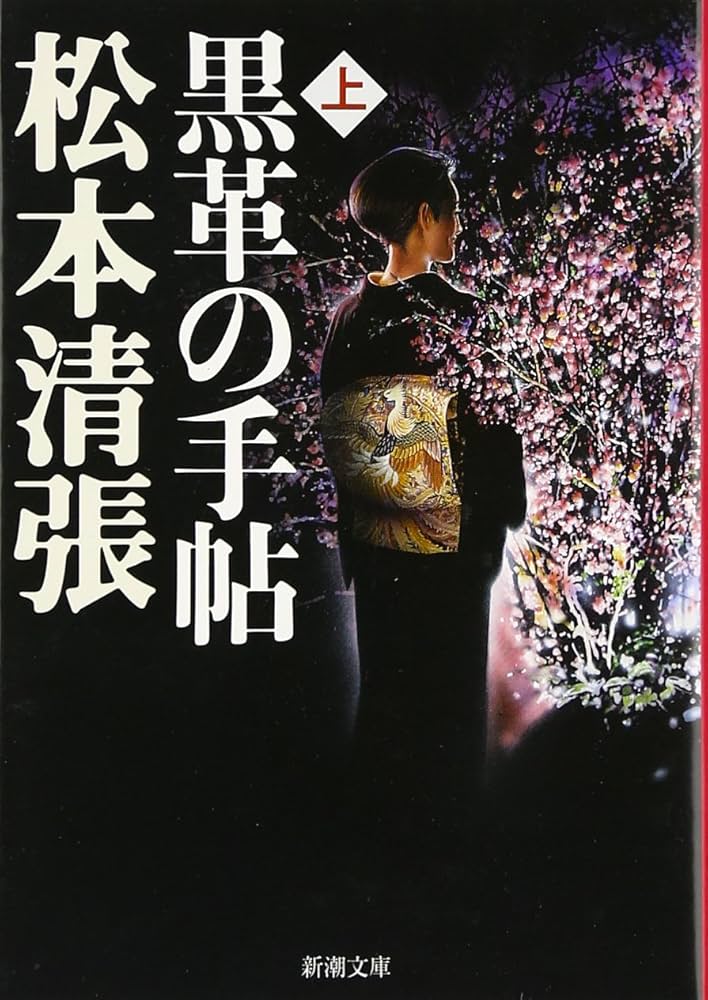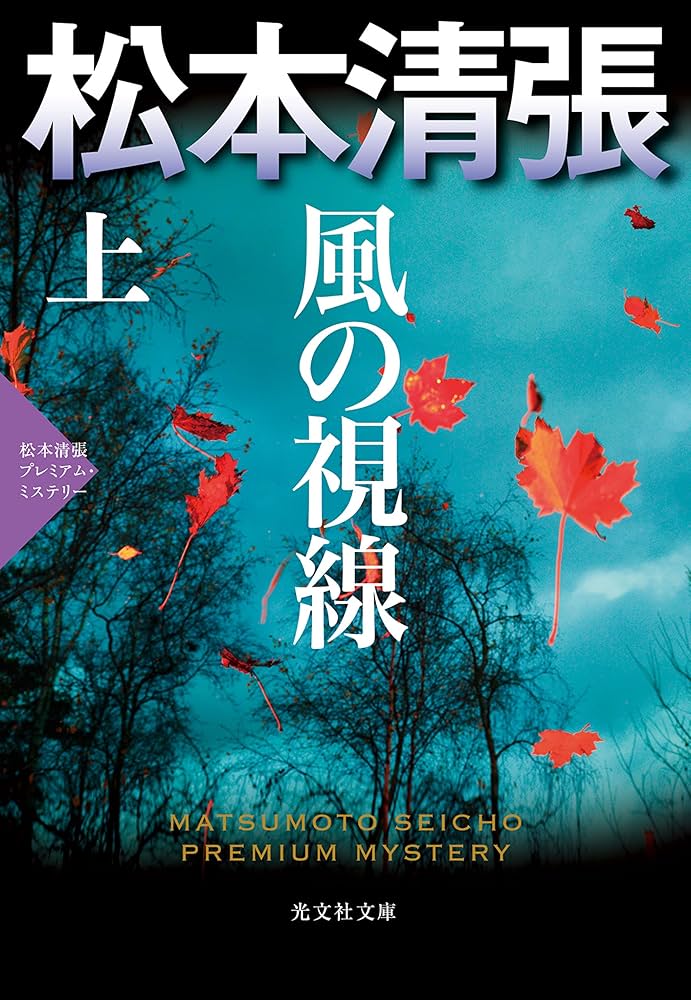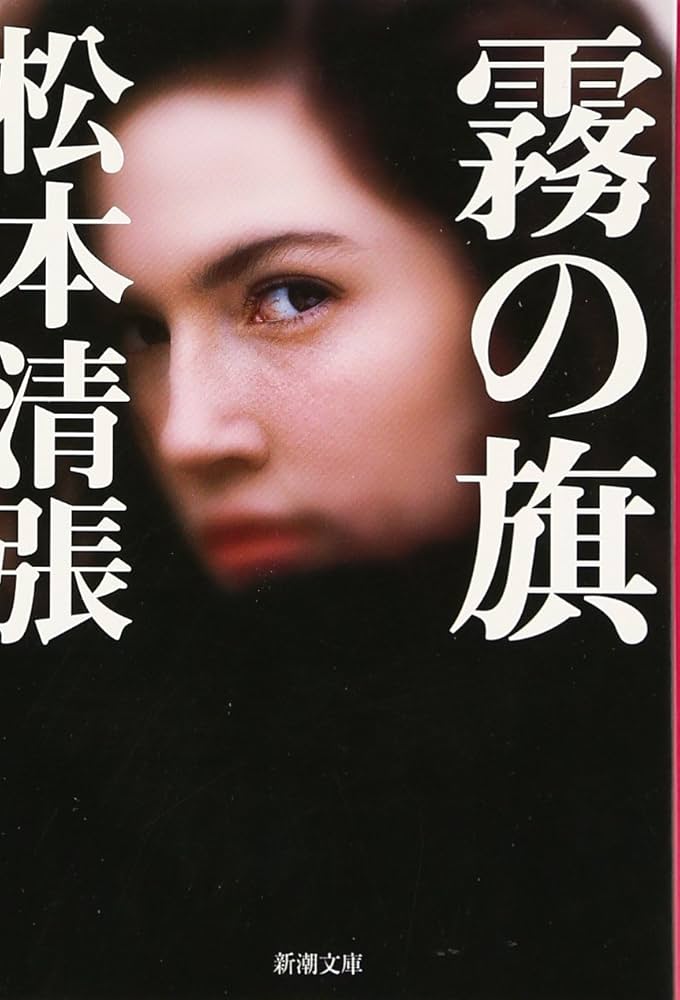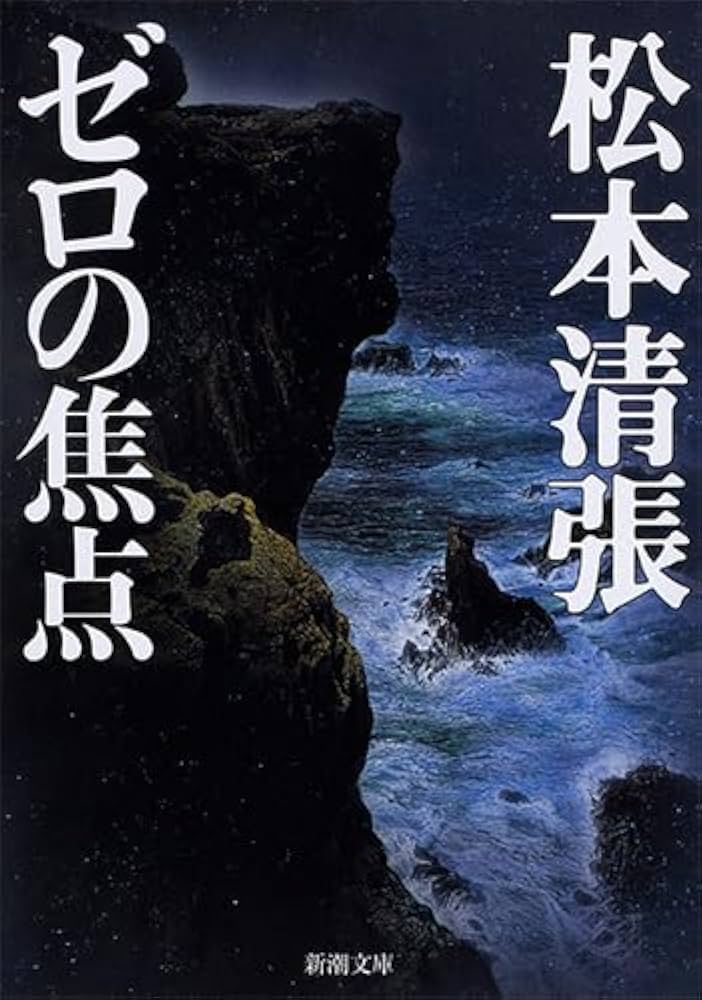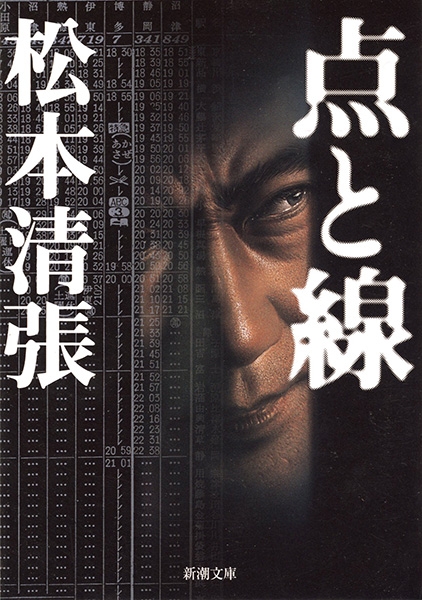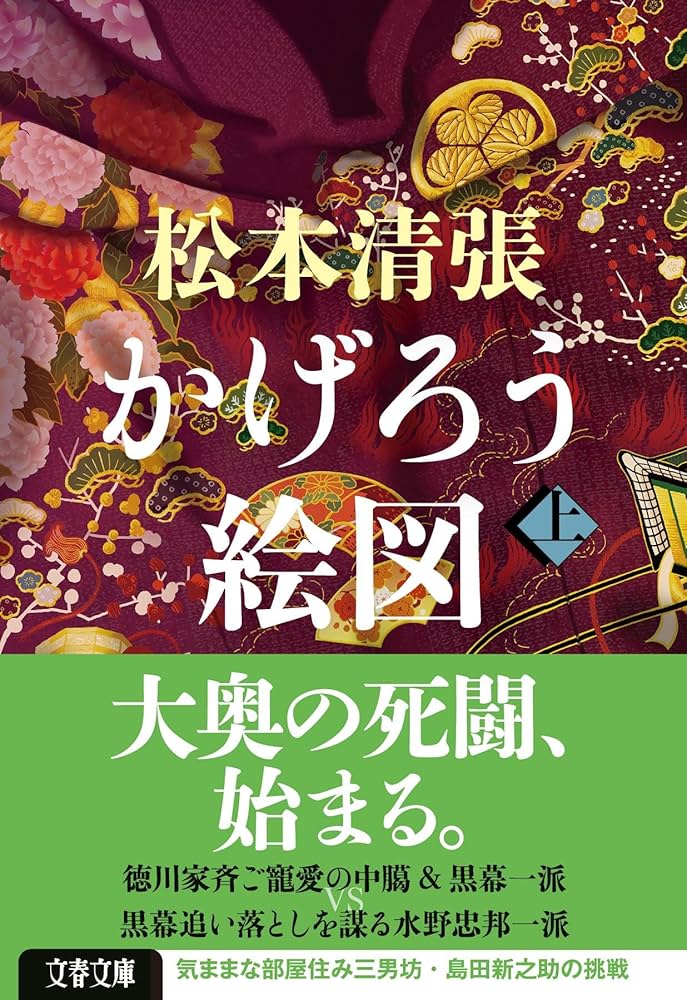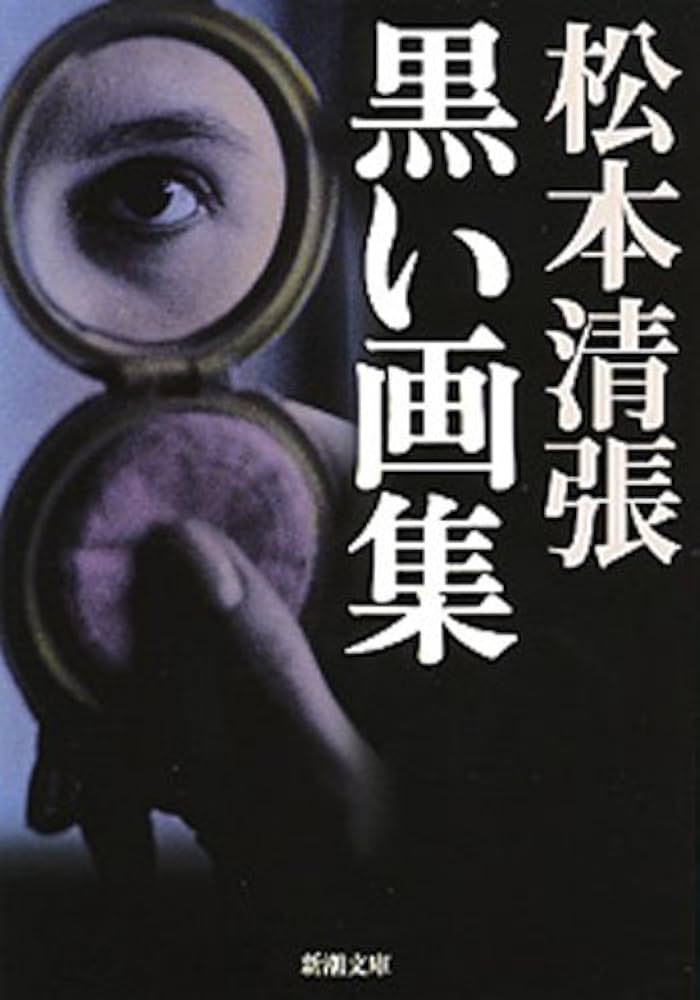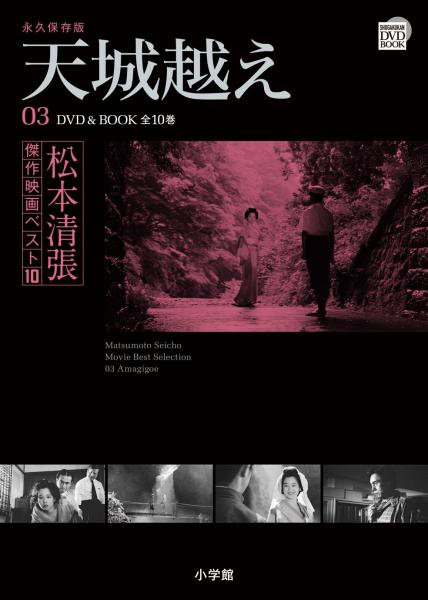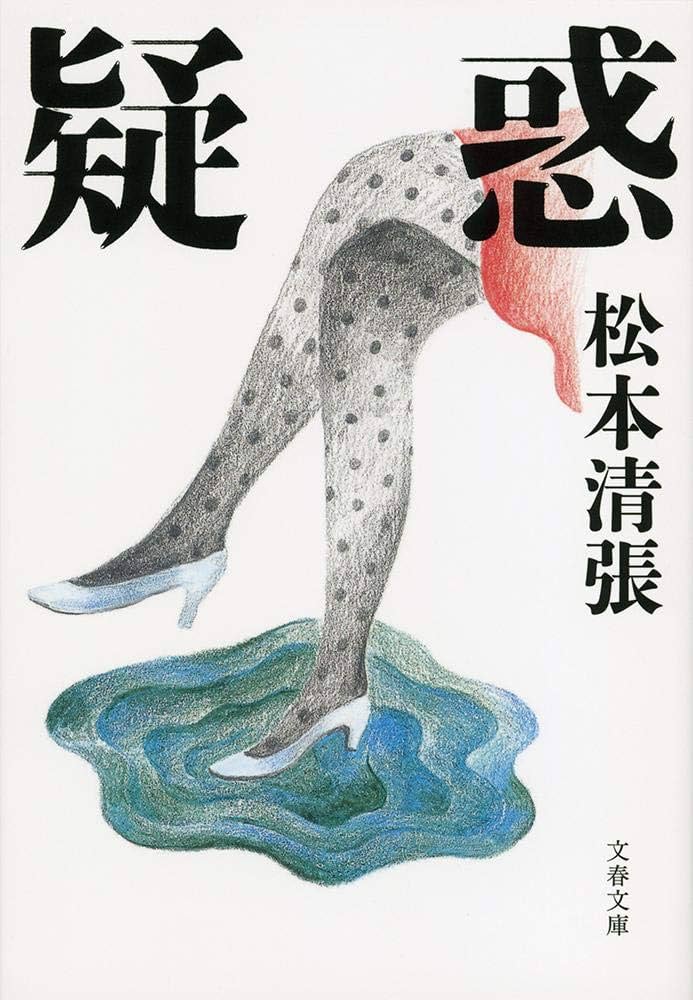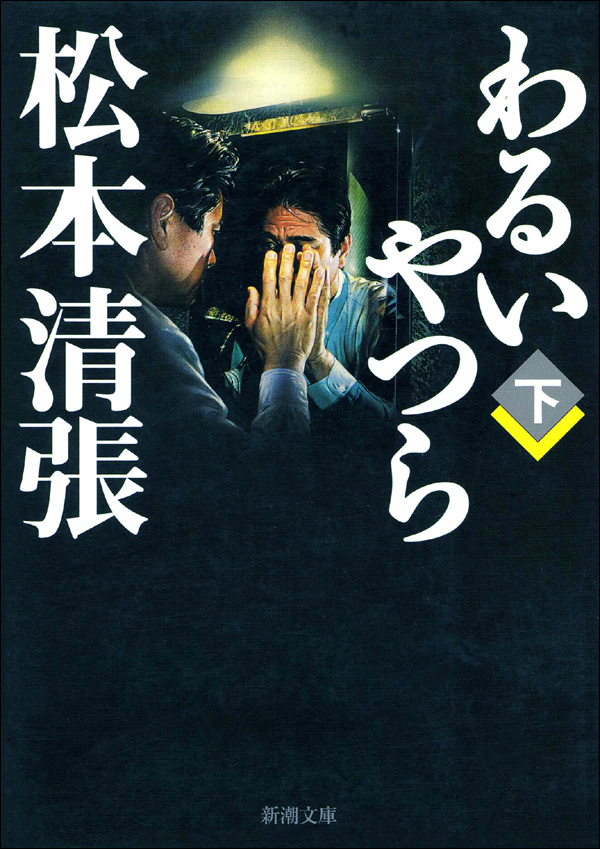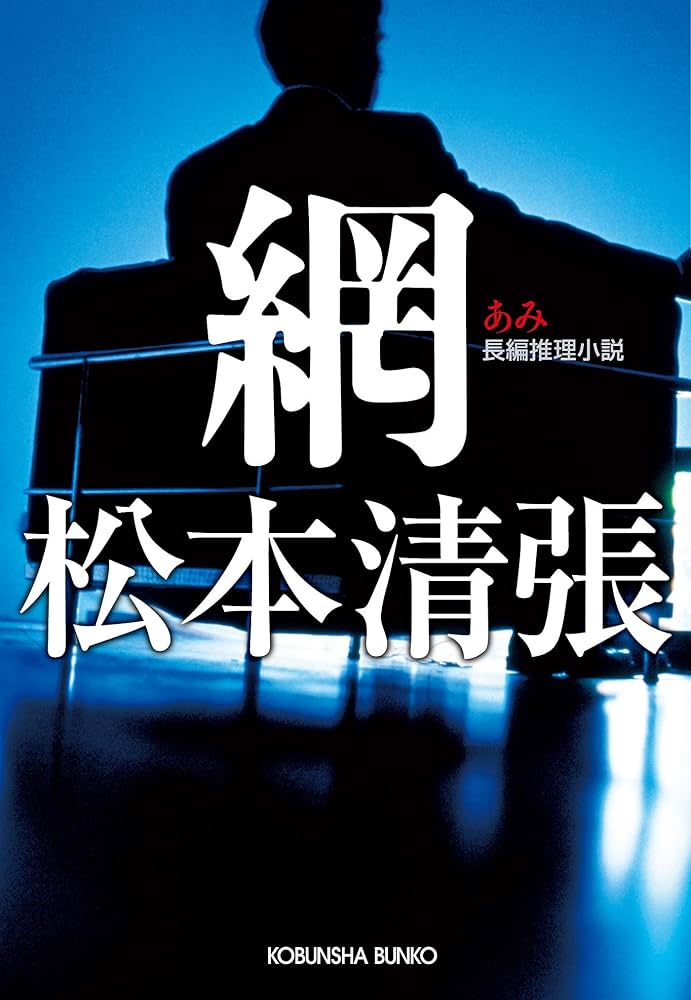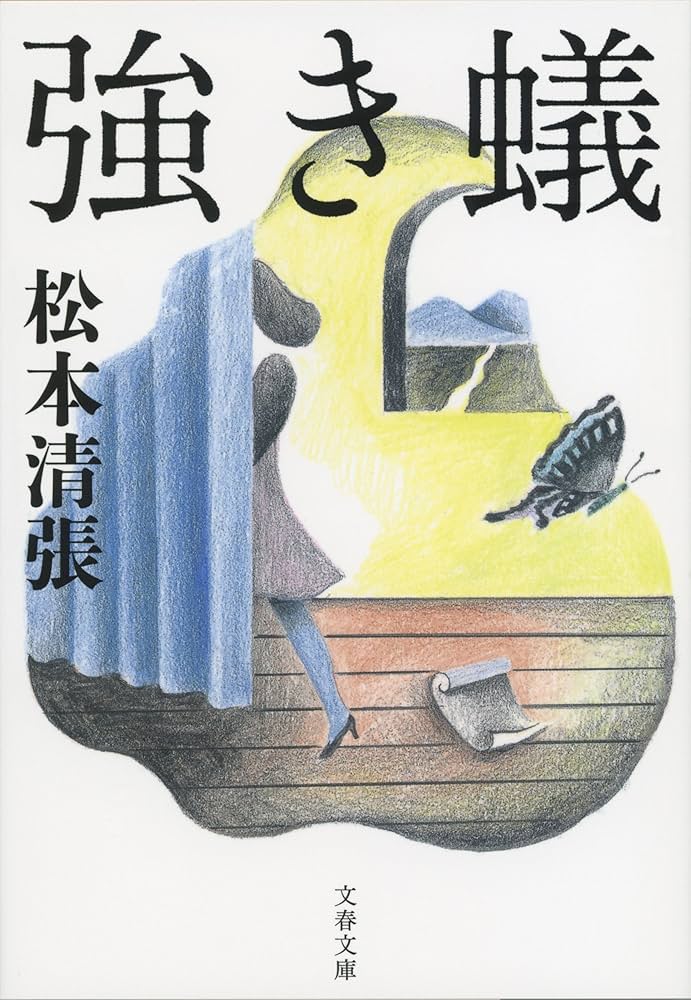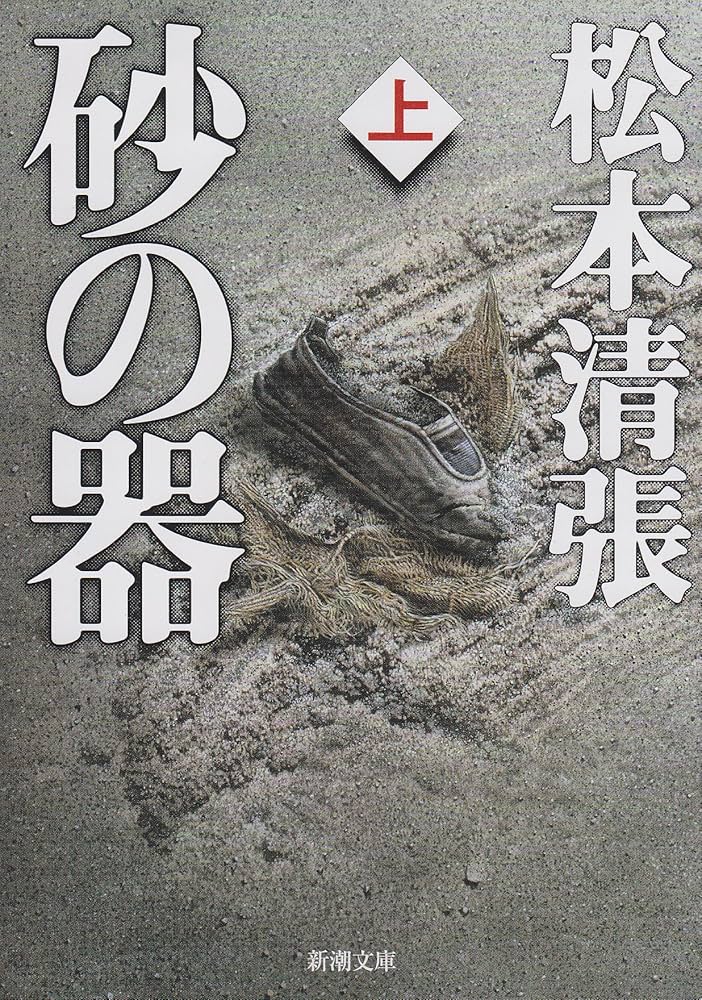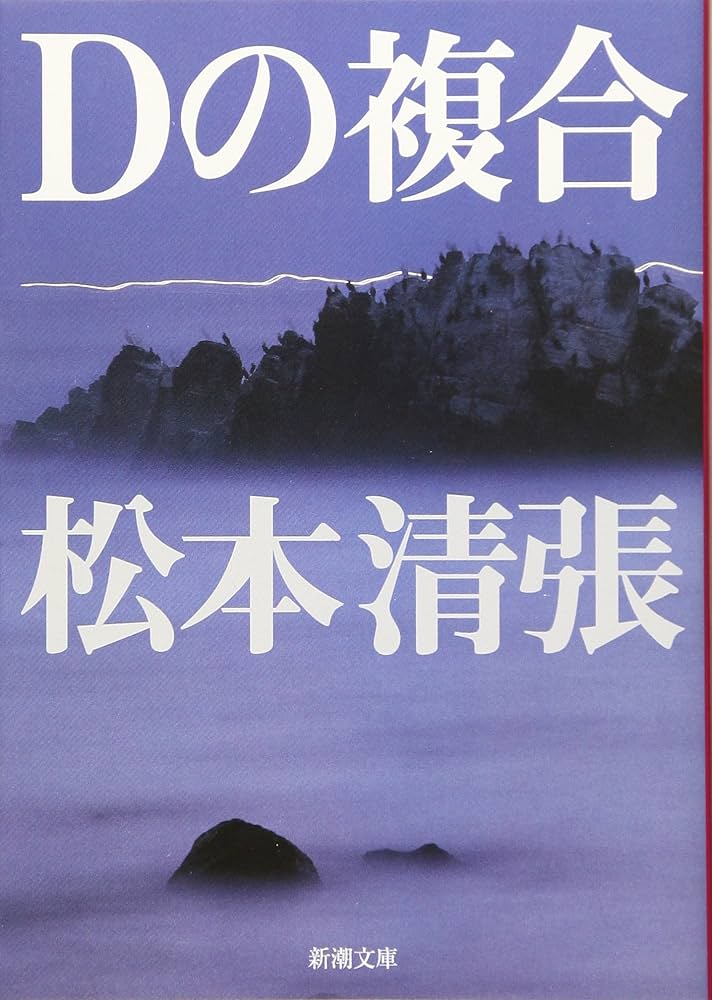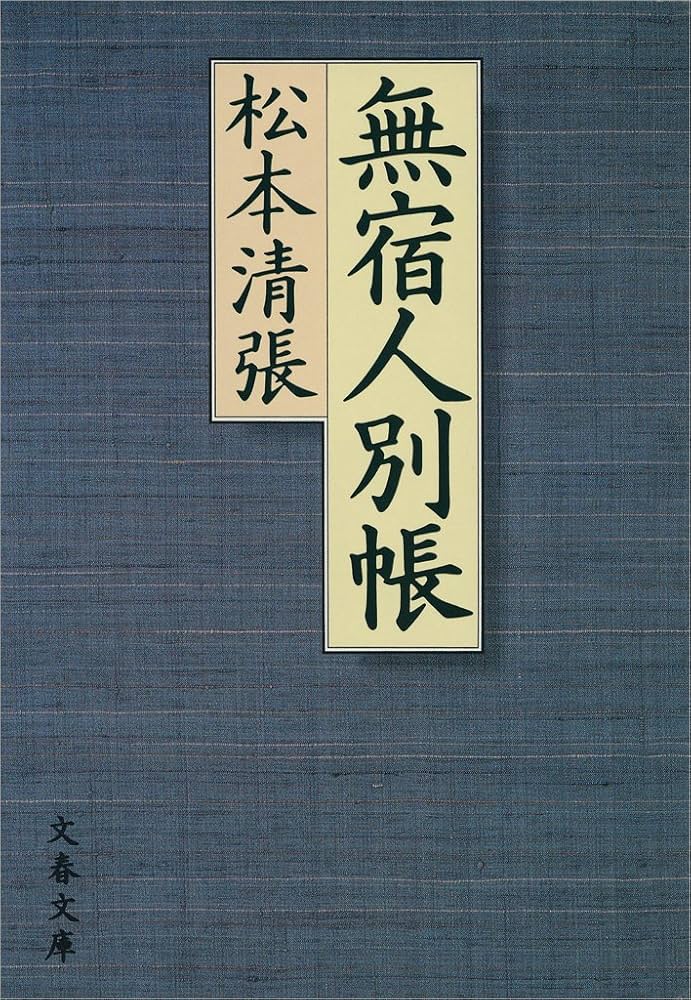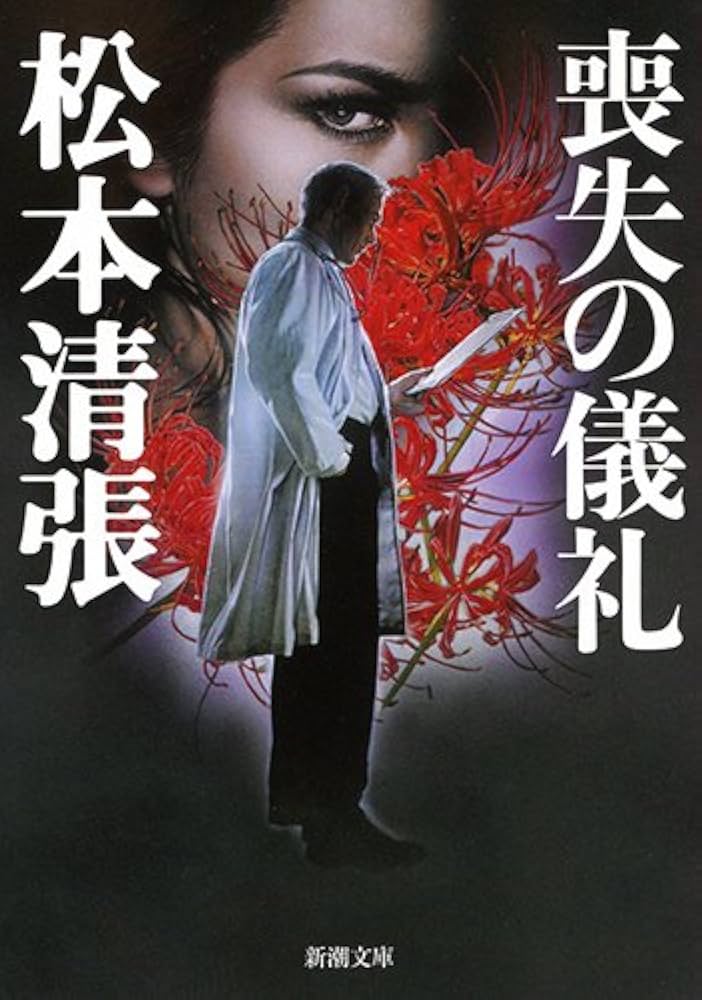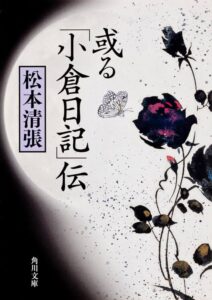 小説「或る小倉日記伝」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「或る小倉日記伝」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、松本清張が作家として世に出るきっかけとなった記念碑的な作品です。第28回芥川賞を受賞し、当時無名だった新聞記者を、一躍時代の寵児へと押し上げました。坂口安吾が「文章甚だ老練」と評したように、その完成度は新人離れしており、読む者を静かに、しかし強く引き込む力を持っています。
物語の中心にいるのは、田上耕作という一人の男。彼は生まれつき重い身体障害を背負いながらも、非常に明晰な頭脳を持っていました。その彼が、人生のすべてを懸けて挑んだのが、文豪・森鷗外が小倉に赴任していた時代の失われた日記を探し出し、復元するという壮大な試みでした。
本記事では、この田上耕作の孤高の生涯を追うことで、物語の詳細な姿を明らかにしていきます。彼の人生は、私たちに「生きることの意味」そのものを問いかけてきます。社会の片隅で、ただひたすらに一つのことを追い求めた男の執念の記録。その結末に待ち受ける衝撃的な事実まで、深く掘り下げていきましょう。
「或る小倉日記伝」のあらすじ
主人公の田上耕作は、生まれつきの神経系の病により、手足が不自由で、言葉もはっきりと話せませんでした。その不自由な身体とは対照的に知性は極めて高く、旧制中学校を優秀な成績で卒業します。しかし、障害が壁となり、社会に出て働くことは叶いませんでした。彼は、未亡人となった母ふじの愛情に支えられ、静かに暮らしていました。
そんな耕作の人生に転機が訪れます。数少ない友人の一人である江南(えなみ)に勧められて読んだ森鷗外の小説『独身』の中に、自分が幼い頃に聞いていた「伝便(でんびん)」という郵便配達人が鳴らす鈴の音の描写を見つけたのです。この発見は、孤独だった彼の人生と、偉大な文豪の世界とを繋ぐ、運命的な架け橋となりました。
この出来事をきっかけに、耕作は鷗外に強く惹かれていきます。そして、鷗外が軍医として小倉にいた三年間の日記が失われ、その詳細が不明であることを知ります。この文学史上の「空白」を埋めること。それが、耕作が自身の人生を懸けるべき、壮大な目標となったのです。
地元の名士である白川院長の蔵書整理の仕事を得た耕作は、わずかな収入と膨大な資料に触れる機会を手にします。彼はそこから、鷗外が小倉時代に関わった人々を一人ひとり訪ね歩くという、地道で果てしない調査の旅へと分け入っていくのでした。その先に何が待っているのか、この時点では誰も知る由もありません。
「或る小倉日記伝」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の核心に触れるネタバレを含んだ、私の深い感想をお話しさせてください。この作品が問いかけるのは、一人の人間の生涯の価値とは、一体何によって測られるのかという、重く、そして普遍的なテーマです。
物語の主人公、田上耕作は、その肉体をいわば「檻」として生きていました。明治の終わりに生まれ、原因不明の障害によって、歩行も発語もままならない。常に人々から同情や好奇の視線に晒され、社会の輪の中に入ることができない。彼の人生は、出発点から大きなハンディキャップを背負っていました。
しかし、その不自由な身体に閉じ込められていたのは、驚くほど明晰で、鋭敏な精神でした。学業では常に優秀。この身体と精神の著しい不均衡こそが、田上耕作という人間の本質であり、彼の悲劇の源泉でもあったのです。彼の知性は、社会的な成功や活躍とは別の場所で、その輝きを放つことを宿命づけられていました。
彼の世界を支えていたのが、母ふじの存在です。夫に先立たれた後、再婚もせず、ただひたすらに息子のために人生を捧げた母。二人の関係は、深く、そして閉鎖的でした。互いだけを頼りに、寄り添いあって生きる姿は、美しくも、どこか痛々しさを感じさせます。この母子の関係性が、耕作の後の人生を決定づけていくことになります。
耕作が森鷗外の世界に引き込まれるきっかけは、実に詩的です。友人・江南に勧められた鷗外の小説で、彼は幼少期に聞いた「伝便」の鈴の音の描写に出会います。それは、彼の孤独な子ども時代の記憶と、文豪の作品世界が奇跡的に交差した瞬間でした。この「ちりんちりん」という物悲しい音は、彼の無名な人生が、偉大な文学史と無関係ではないのだという、天啓のような響きを持っていたに違いありません。
そして彼は、鷗外の「小倉日記」が失われていることを知ります。偉大な人物の生涯に残された「空白」。この空白を埋めるという行為に、彼は自らの人生の意味を見出します。それは、彼自身の満たされない人生の空白を埋める作業でもあったのでしょう。ここから、彼の執念に満ちた探求が始まります。
耕作の研究は、想像を絶する困難を伴いました。まず、彼の身体そのものが大きな障害でした。そして、彼が調査で出会う人々が向ける、無理解と偏見の眼差し。安国寺の住職が、彼の障害をただ薄笑いを浮かべて眺める場面は、読んでいて胸が詰まります。彼は、情報を得る以前に、まず人間としての尊厳を踏みにじられるという経験を、幾度となく繰り返さなければなりませんでした。
そんな彼の人生にも、ささやかな光が差す瞬間がありました。白川院長の病院で出会った看護婦、山田てる子への淡い恋心です。母ふじも、息子の将来を彼女に託したいと願います。しかし、結婚の話が持ち上がると、彼女は冷たくそれを拒絶します。この出来事は、耕作にとって決定的でした。世の常の幸福への道を完全に断たれた彼は、より深く、研究という孤高の世界へと沈潜していくのです。
もちろん、彼の探求は常に情熱に満ちていたわけではありません。自分のやっていることは本当に意味があるのか、ただの幻を追っているだけではないのか。そんな疑念と絶望が、何度も彼を襲います。髪をかきむしるほどの苦悩。それは、彼がこの研究に、いかに自分の全存在を賭けていたかの裏返しでもありました。
やがて、時代の大きなうねりが、彼のささやかな研究を飲み込んでいきます。第二次世界大戦です。戦争は人々の心から余裕を奪い、過去を振り返ることを許しませんでした。耕作の個人的な探求は、国家という巨大な現実の前では、あまりにも無力でした。
そして戦後、さらなる苦難が彼を襲います。劣悪な食糧事情と生活環境が、彼の弱った身体をさらに蝕んでいくのです。神経の症状は悪化し、ついに彼は完全に寝たきりとなってしまいます。彼のライフワークであった「小倉日記」の復元は、ここにきて完全に中断を余儀なくされました。
忠実な友人である江南と、老いた母ふじによる看病の日々。病床にあってもなお、彼の意識ははっきりとしていました。いつか元気になって、風呂敷いっぱいに集めた調査資料を整理する日を夢見ていました。その夢が叶わないことを知りながらも、彼は最後まで希望を捨てませんでした。
そして、最期の時が訪れます。1950年の冬。弱り果てた耕作は、朦朧とする意識の中で、ふと何かに耳を澄ませるような仕草を見せます。そして、ほとんど声にならない声で、はっきりと一言、「伝便…」と呟いたのです。彼の人生の探求の始まりを告げた、あの懐かしい鈴の音。それを幻聴として聞きながら、彼は静かに息を引き取りました。
物語は、ここで終わっても、一つの感動的な悲劇として完結していたかもしれません。しかし、松本清張は、この後に冷徹で、あまりにも皮肉な「追記」を用意していました。ここからが、この作品の真骨頂であり、読者の心を揺さぶり続ける部分です。ネタバレになりますが、この結末こそがすべてなのです。
耕作の死から、わずか数ヶ月後。森鷗外の息子が、実家の物置にあった箪笥の中から、完全な状態の「小倉日記」を発見します。日記は失われてなどいなかった。ただ、忘れられていただけだったのです。耕作が人生のすべてを捧げて追い求めたものは、彼が知らない場所で、ひっそりと存在していました。
そして、物語はあの有名な一文で締めくくられます。「田上耕作が、この事実を知らずに死んだのは、不幸か幸福か分らない。」この問いかけこそ、松本清張が私たち読者一人ひとりに突きつけた、この物語の核心です。彼の人生は、徒労だったのでしょうか。それとも、意味のあるものだったのでしょうか。
表面的に見れば、これほどの不幸はありません。彼の人生を懸けた大事業は、客観的に見れば全くの無駄骨でした。彼の苦闘、彼の情熱、彼のすべてが、意味のないものになってしまった。しかし、本当にそうでしょうか。私は、彼が事実を知らずに死んだことは、「幸福」だったのだと信じたいのです。なぜなら、彼の人生の価値は、日記の発見という「結果」にあったのではないからです。彼の人生の価値は、日記を追い求めた「過程」そのものにあったのですから。
もし、耕作が生きて日記の発見を知ったらどうなっていたでしょう。彼のアイデンティティは崩壊し、人生そのものが否定されたと感じたかもしれません。彼が築き上げてきた内面的な充足感は、無慈悲な客観的事実によって木っ端微塵に破壊されていたでしょう。彼の死は、その意味で、彼自身の物語を永遠に守ったのです。彼の人生は、彼の心の中において、尊く、意味に満ちた探求として完結しました。この物語は、人生の価値を、目に見える成果や他者からの評価で測ろうとする私たちの価値観を、根底から揺さぶってきます。耕作の人生は、結果だけを見れば「徒労」です。しかし、その「徒労」こそが、彼の困難な人生に光を与え、彼を生かしていたのです。
まとめ
松本清張の「或る小倉日記伝」は、一人の男の壮絶な人生を通して、私たちに「価値」とは何かを問いかける不朽の名作です。身体の障害という宿命を背負いながら、一つの目標に全生涯を捧げた田上耕作の姿は、読む者の胸を強く打ちます。
物語の結末は、あまりにも衝撃的で皮肉に満ちています。耕作が人生を懸けて追い求めた「小倉日記」は、彼が知らない場所で完全な形で存在していたのです。彼の探求は、客観的には全くの「徒労」でした。この事実を知らずに世を去った彼を、作者は「不幸か幸福か分らない」と評します。
しかし、この物語を深く読むと、彼の人生が決して無駄ではなかったことが分かります。彼にとって重要だったのは、日記を見つけるという「結果」ではなく、それを追い求める「過程」そのものでした。その情熱こそが、彼の人生に意味と尊厳を与えていたのです。事実を知らないまま死んだことは、彼の人生の価値を守った、最後の救いだったのかもしれません。
この作品は、成果主義や効率が重視される現代社会に生きる私たちに、静かな、しかし重い問いを投げかけます。人生の本当の豊かさは、一体どこにあるのか。この深遠なテーマを考えさせてくれる、必読の物語であると私は感じています。