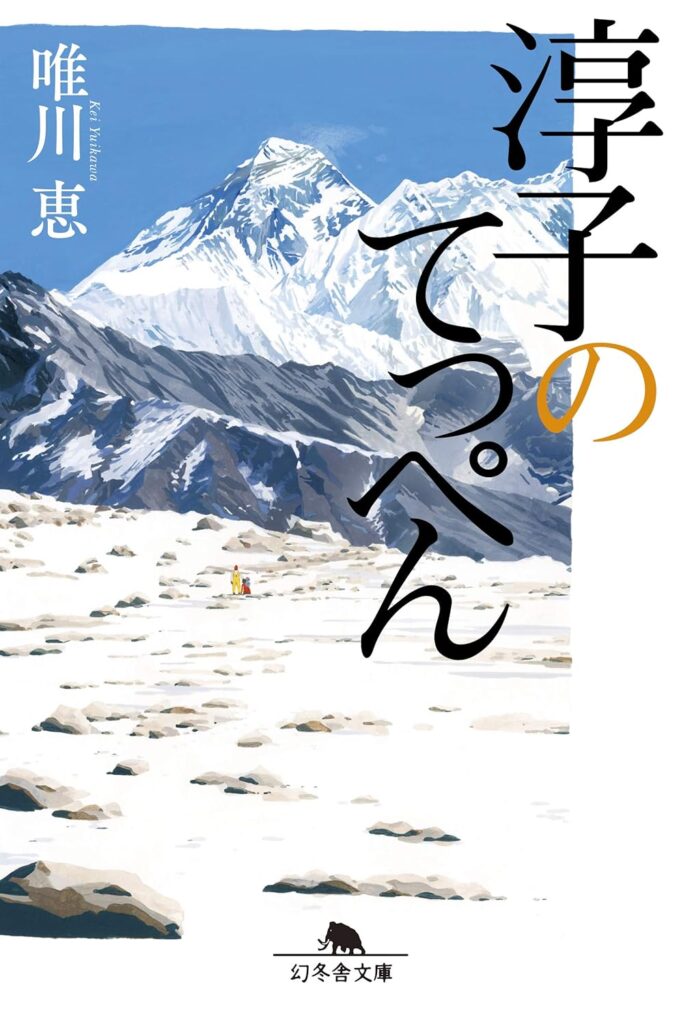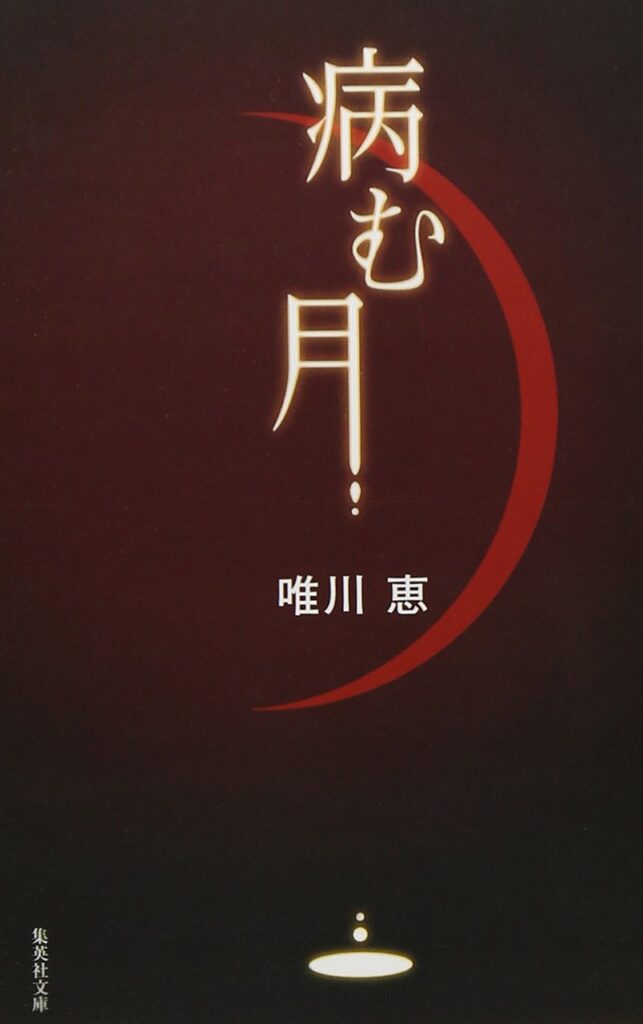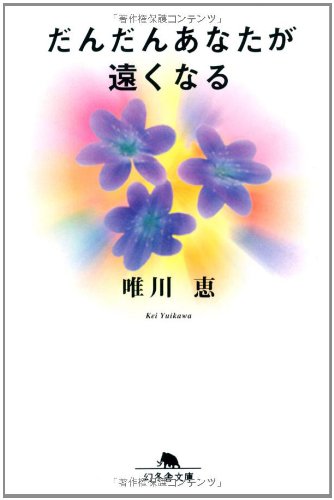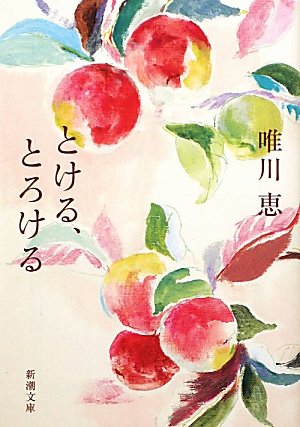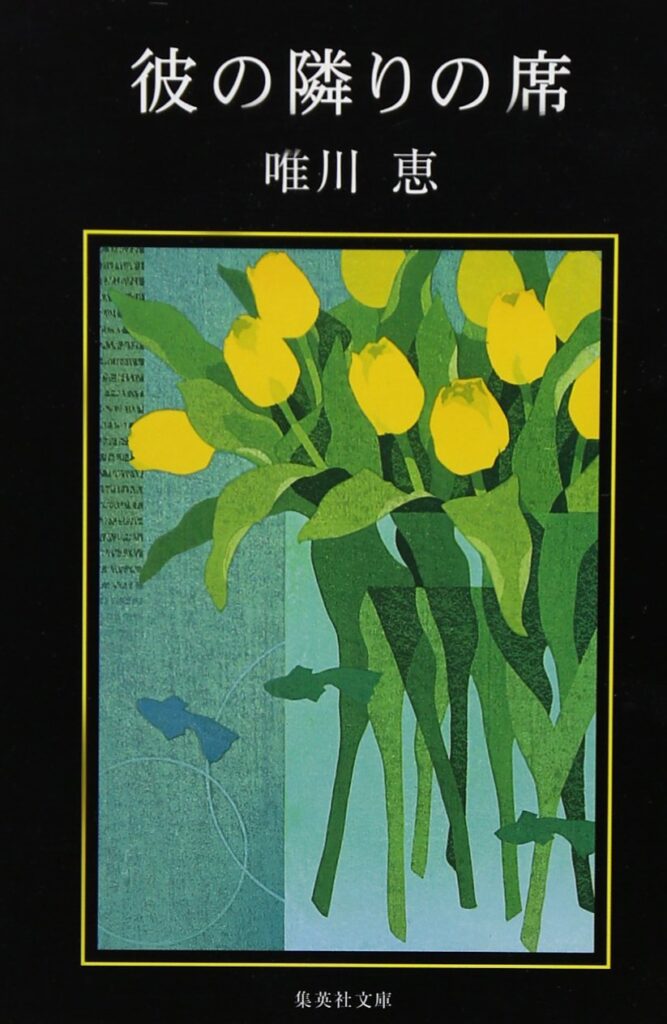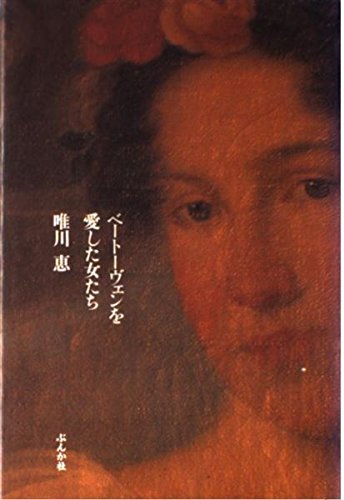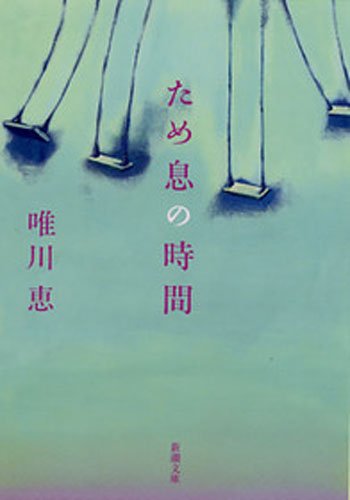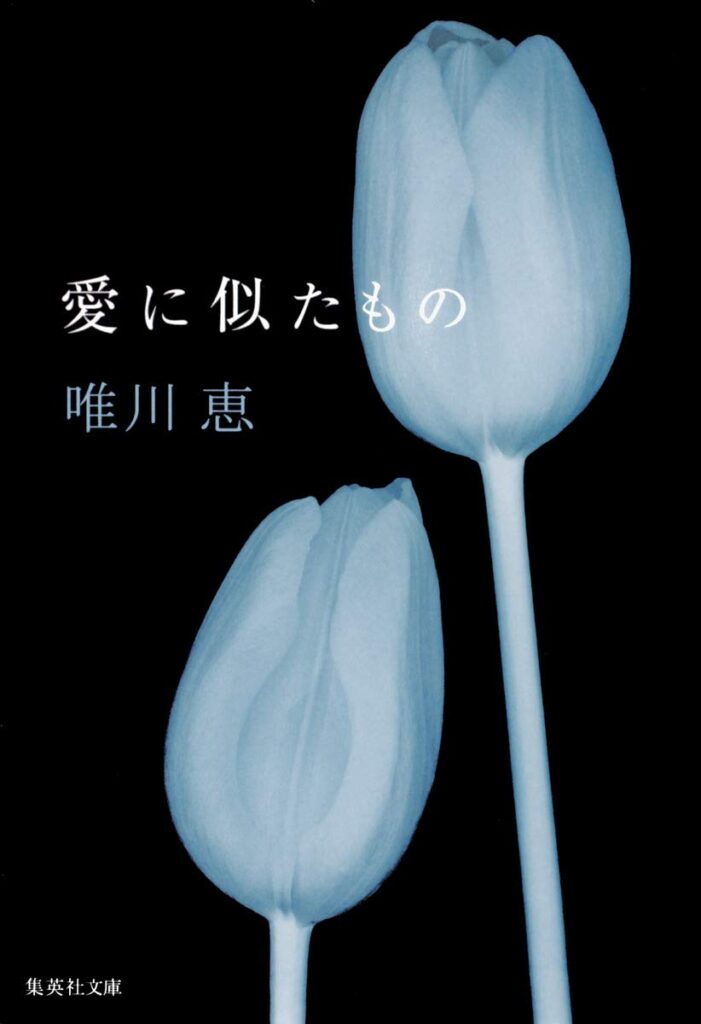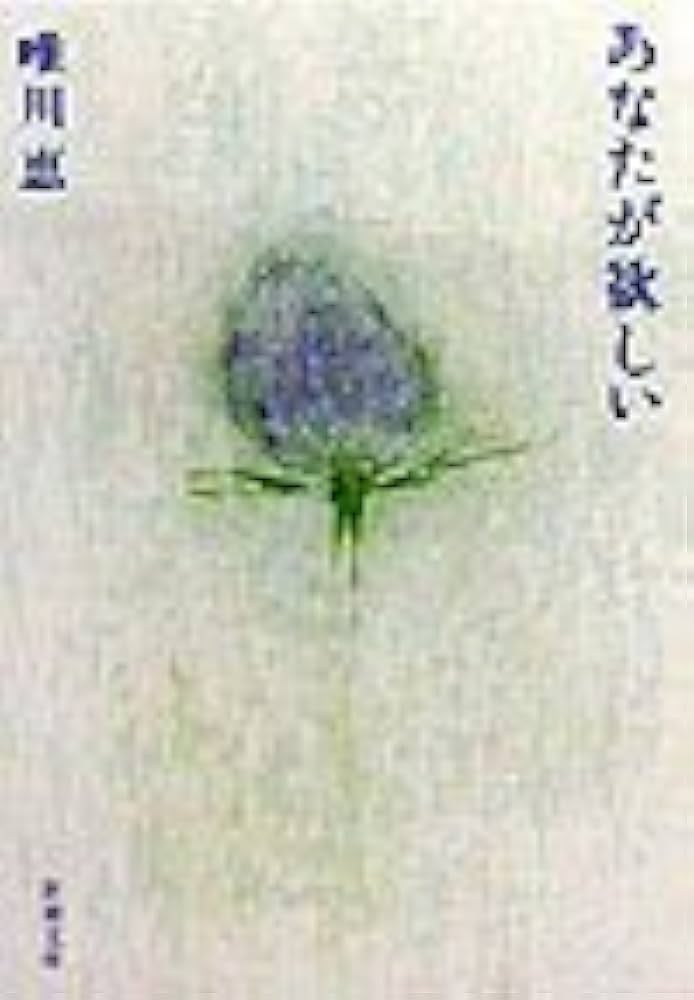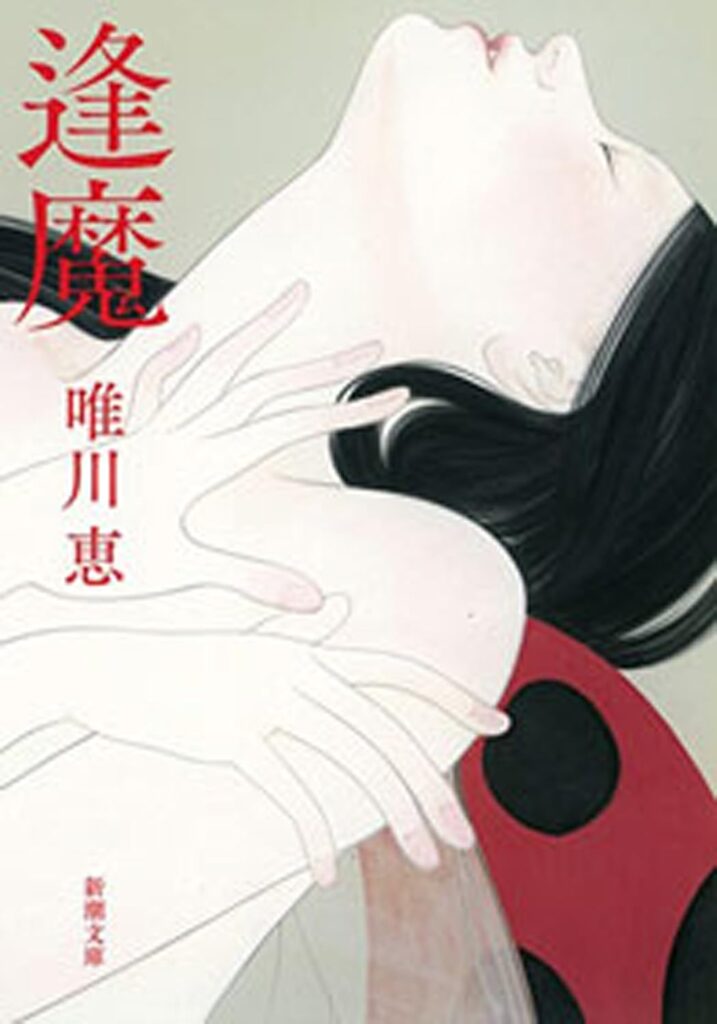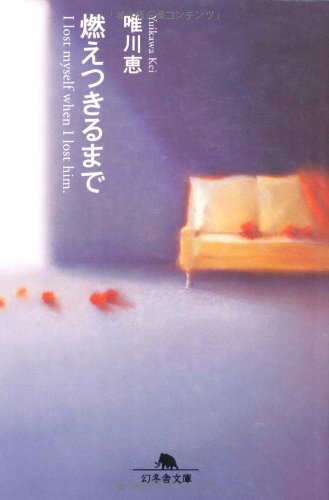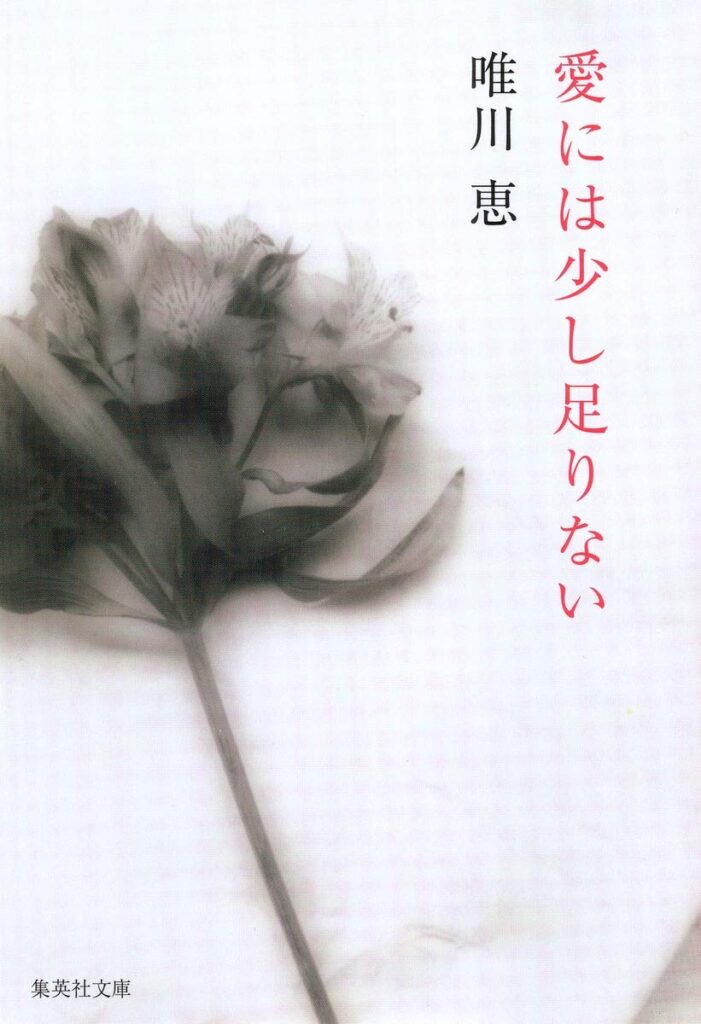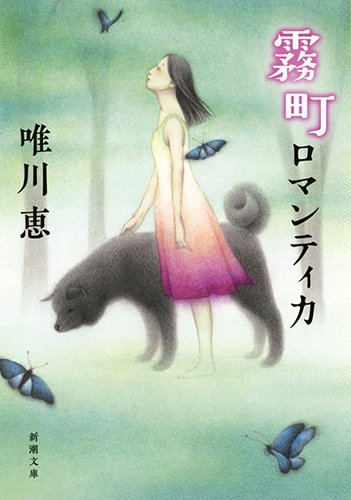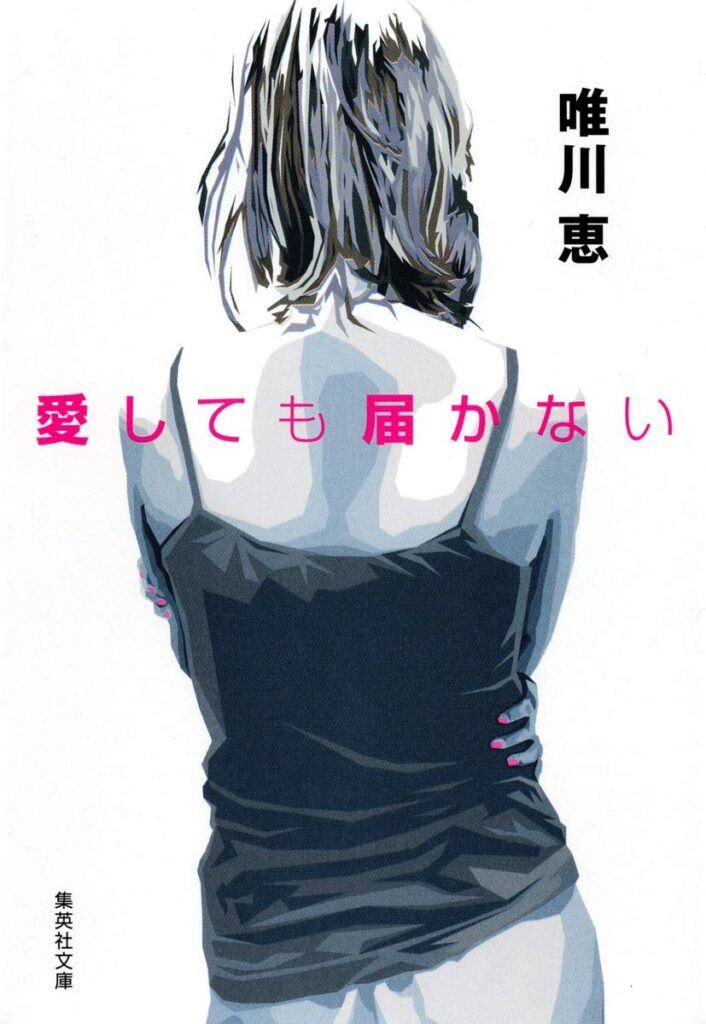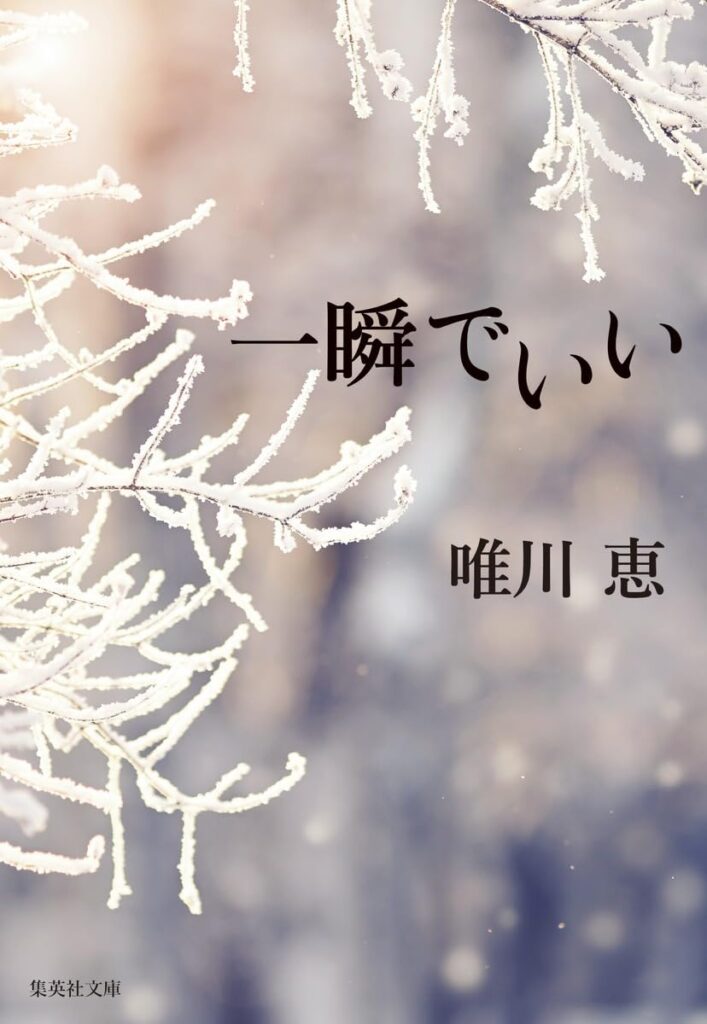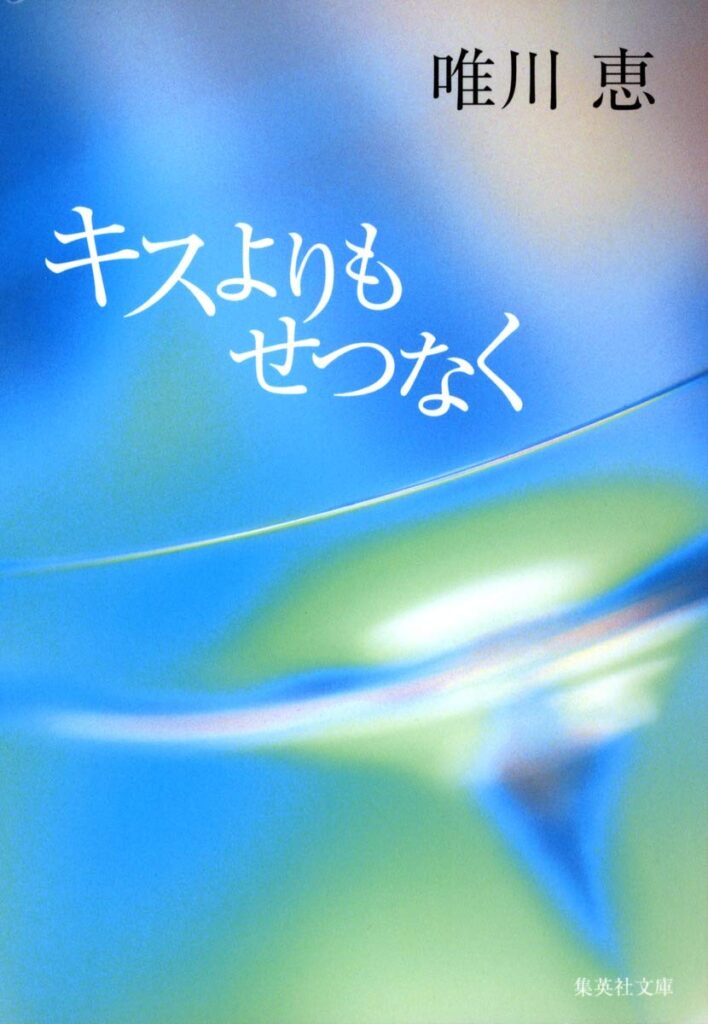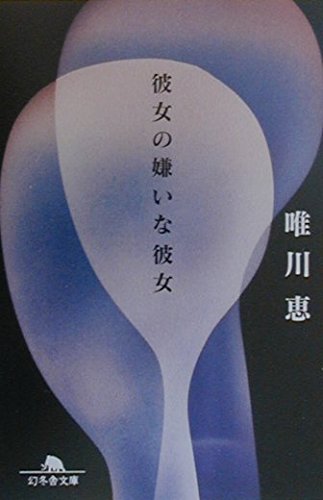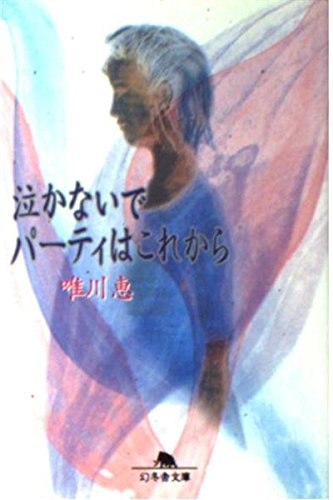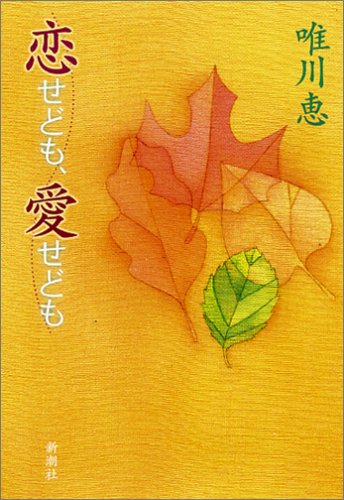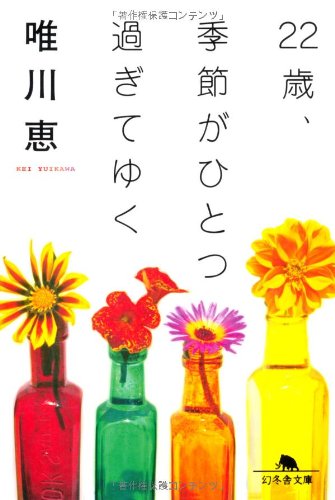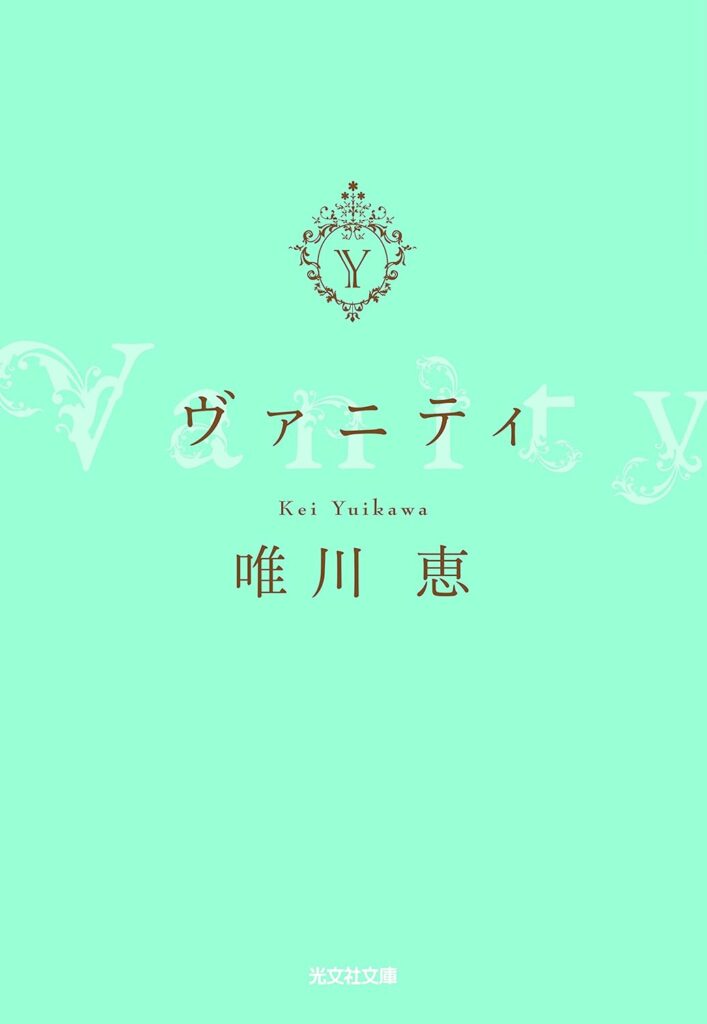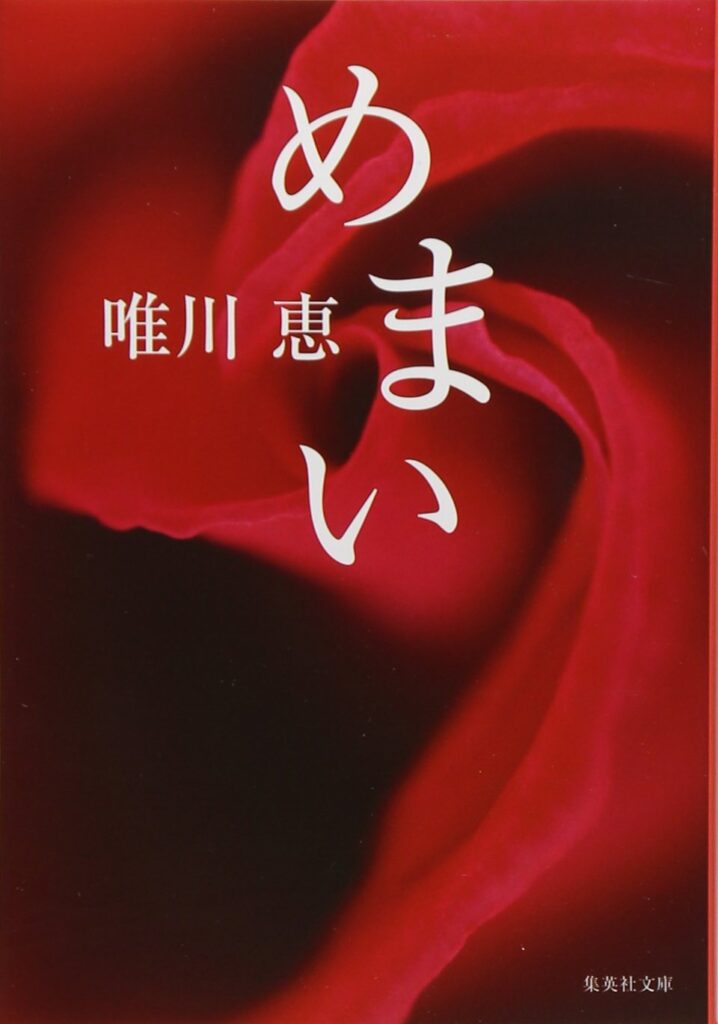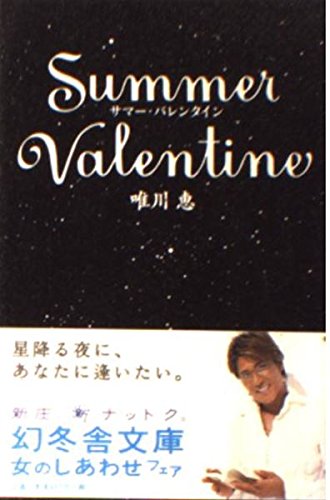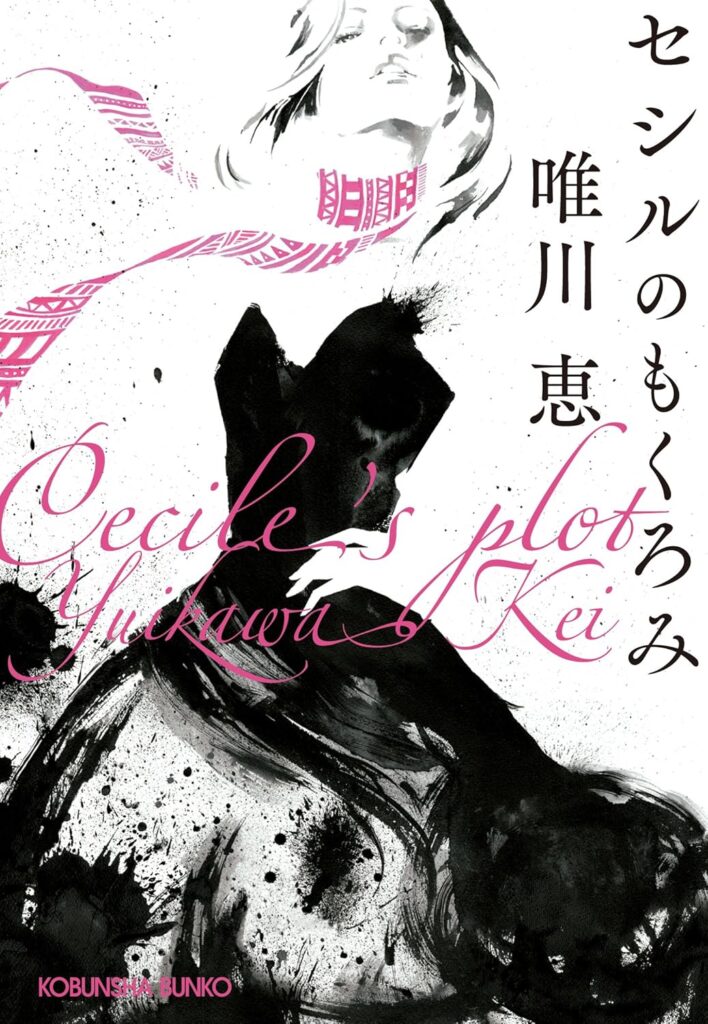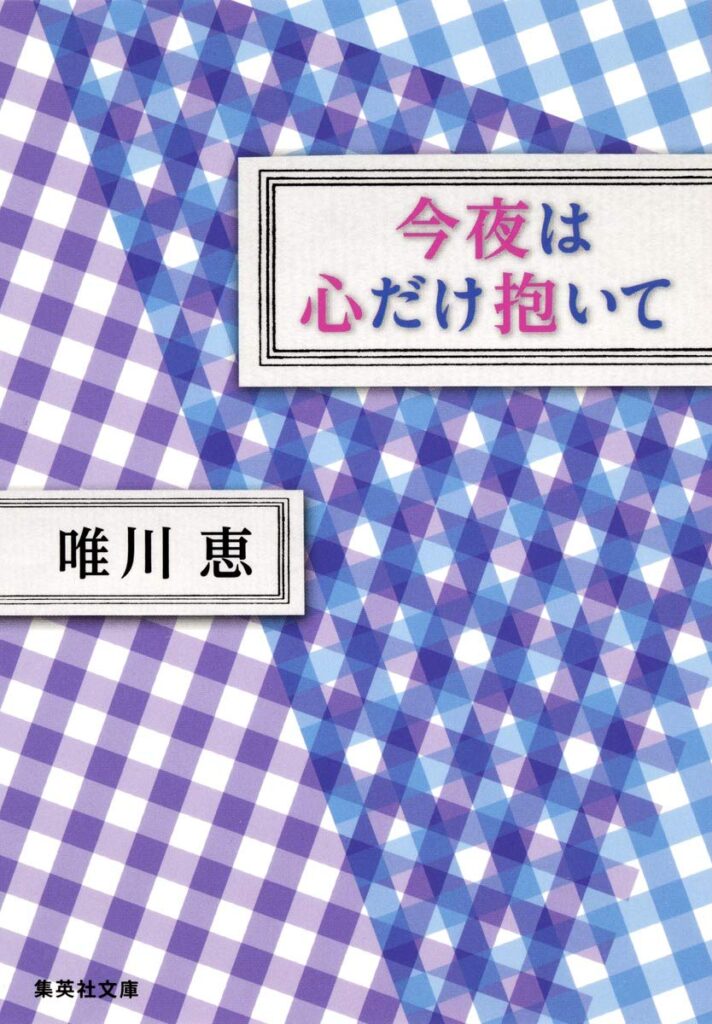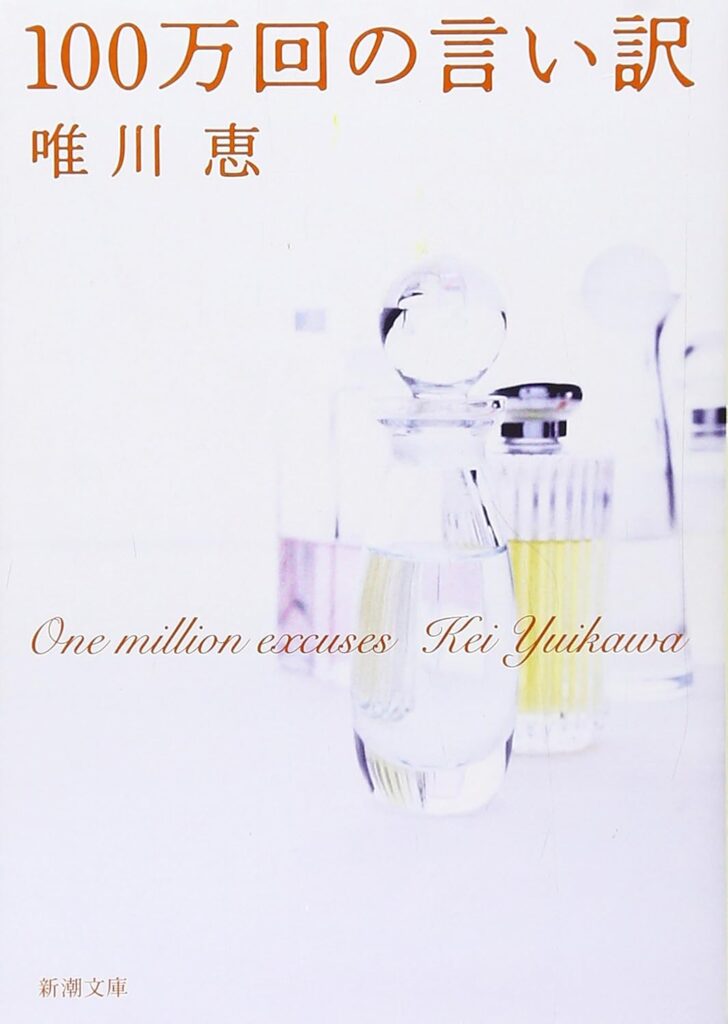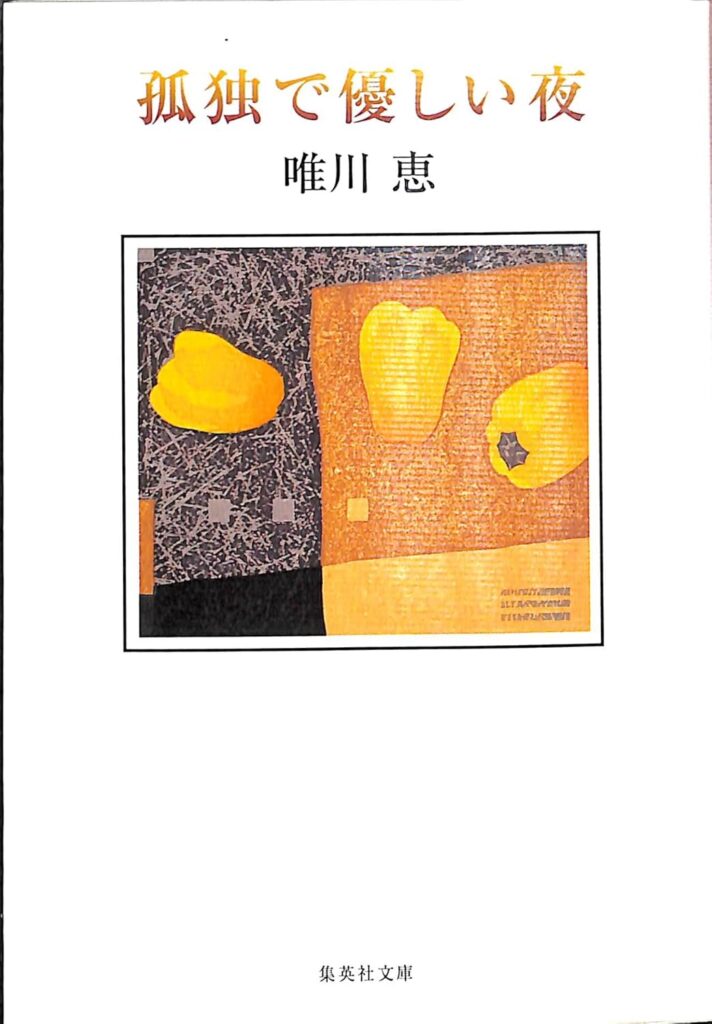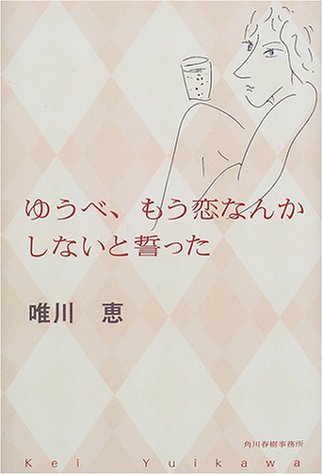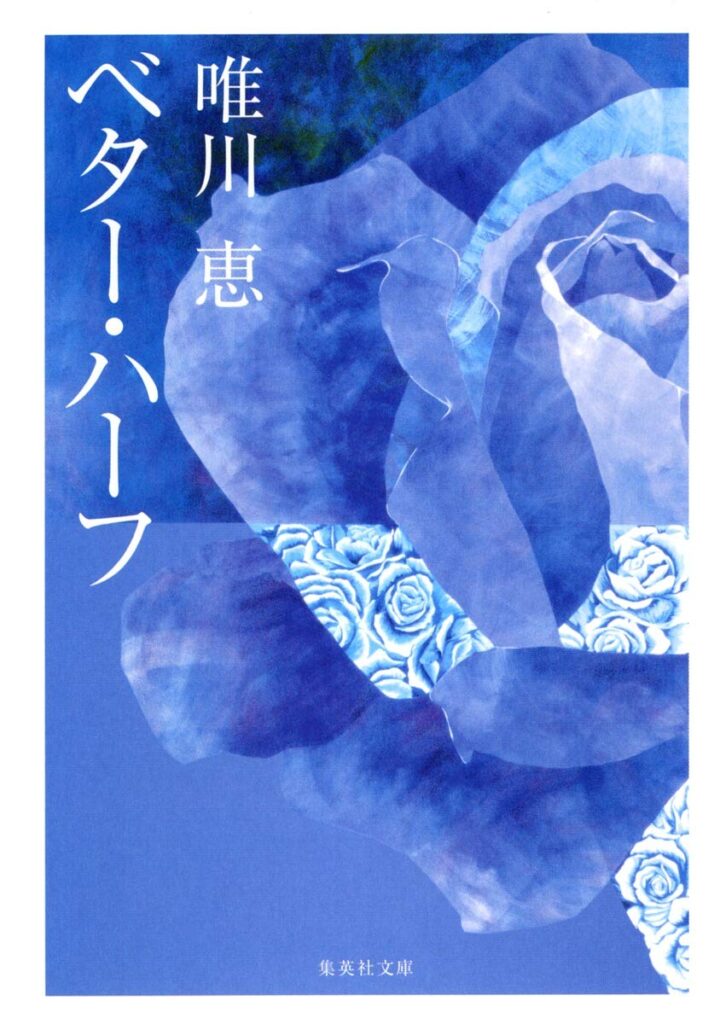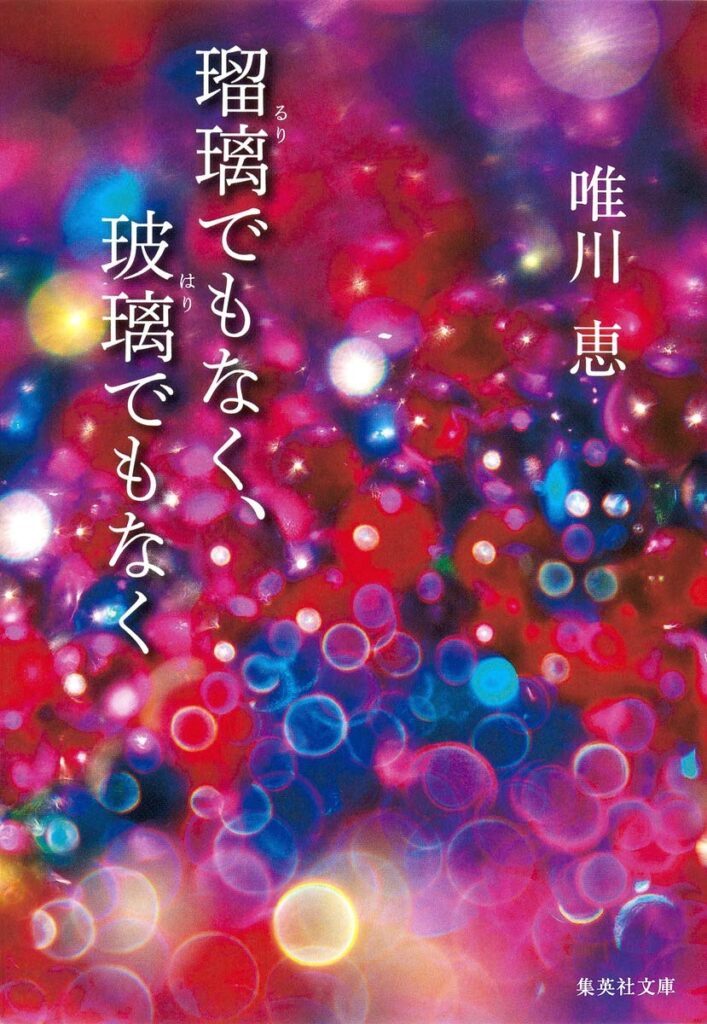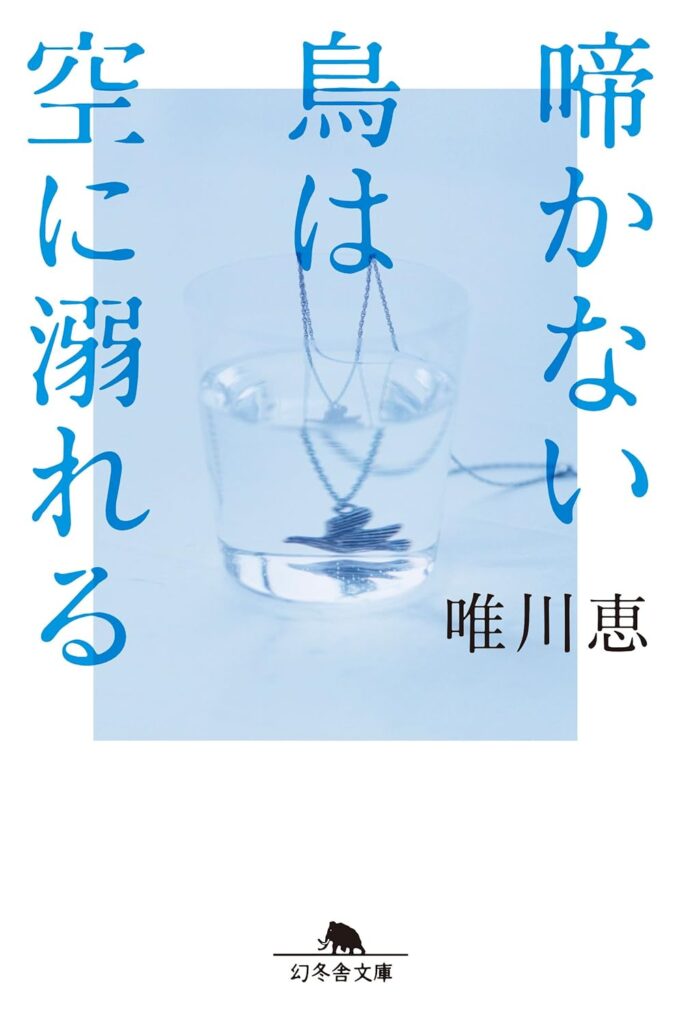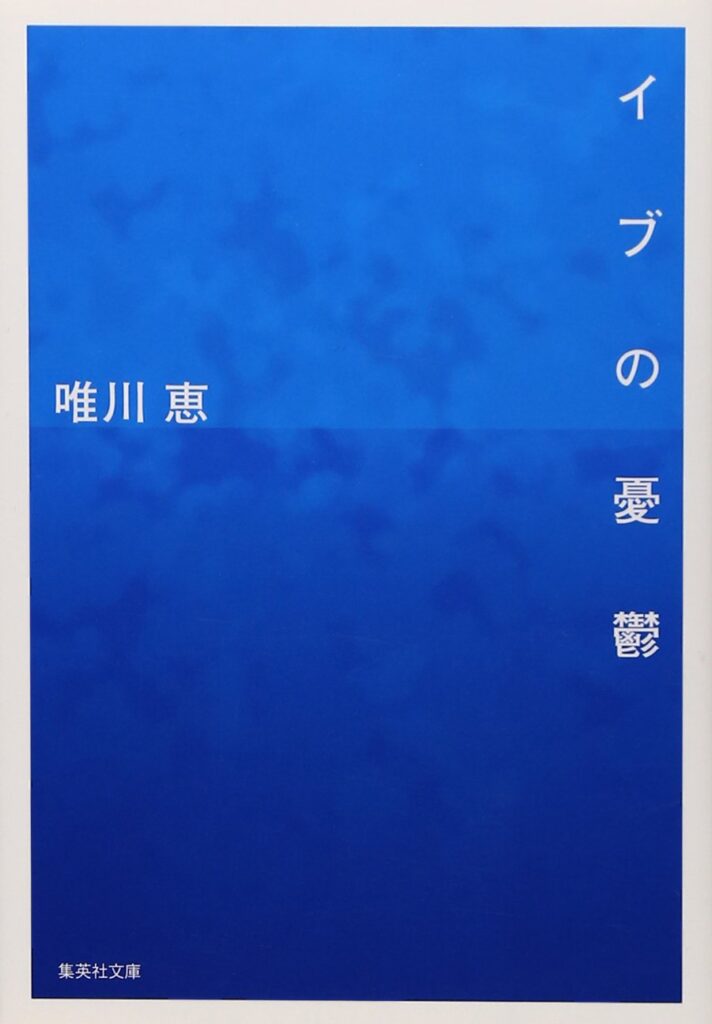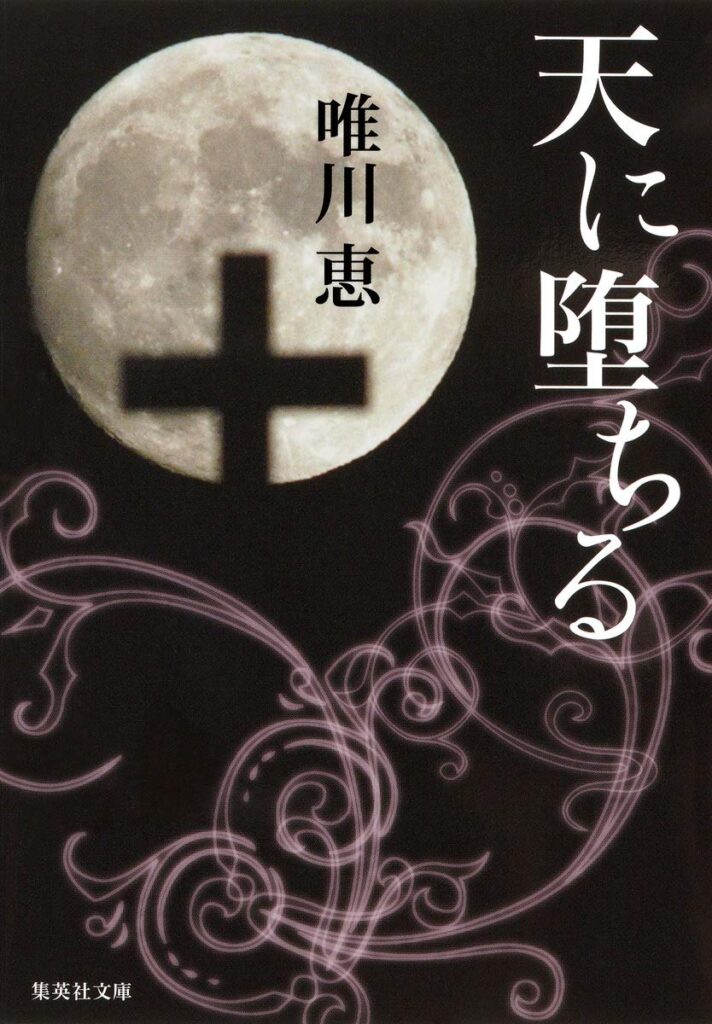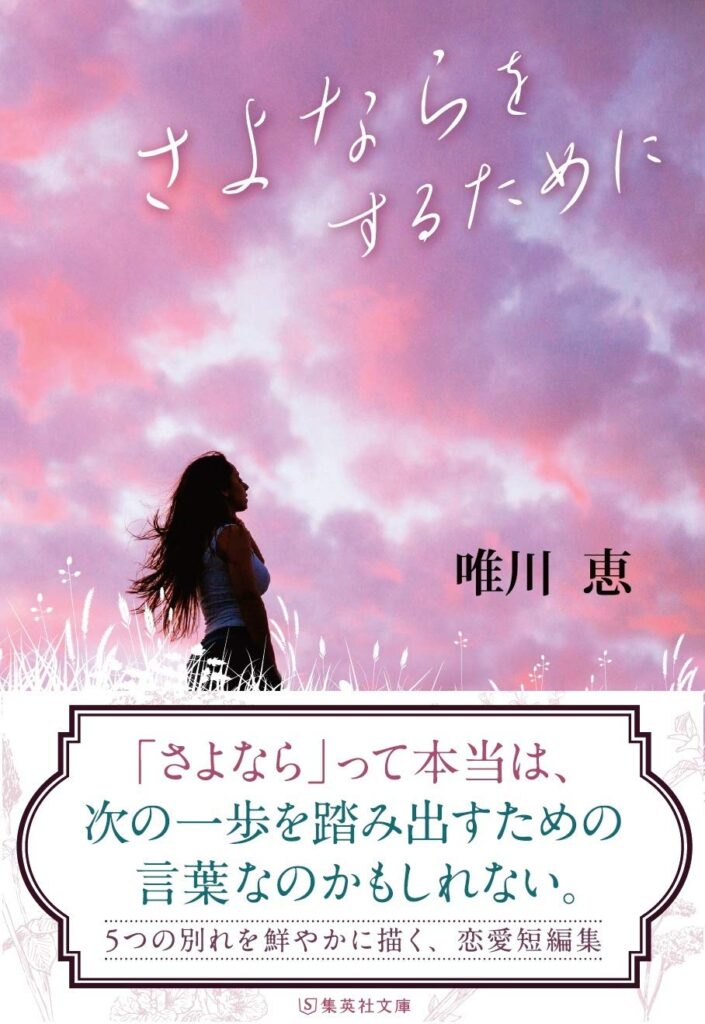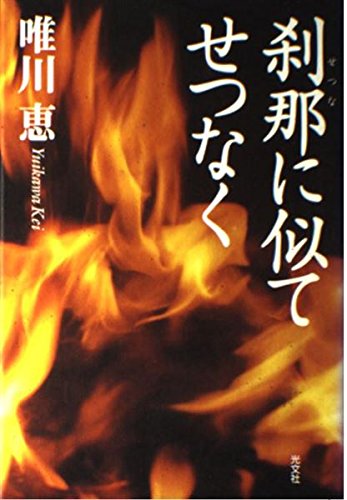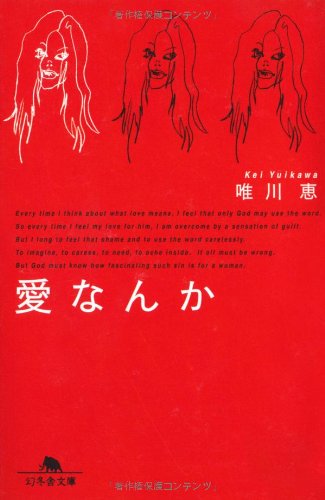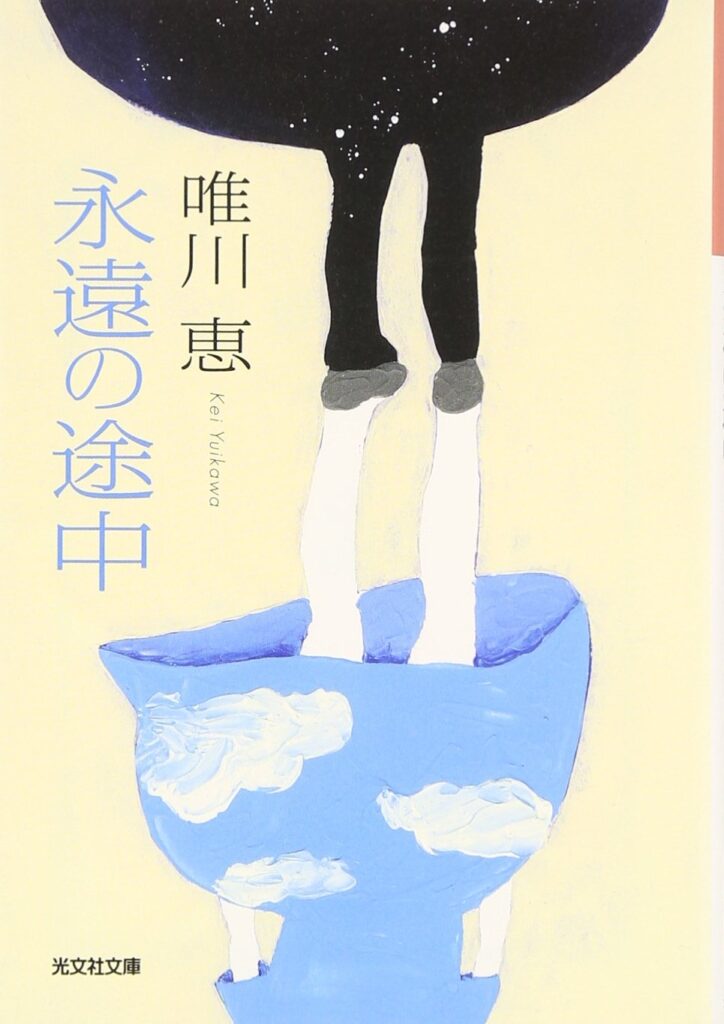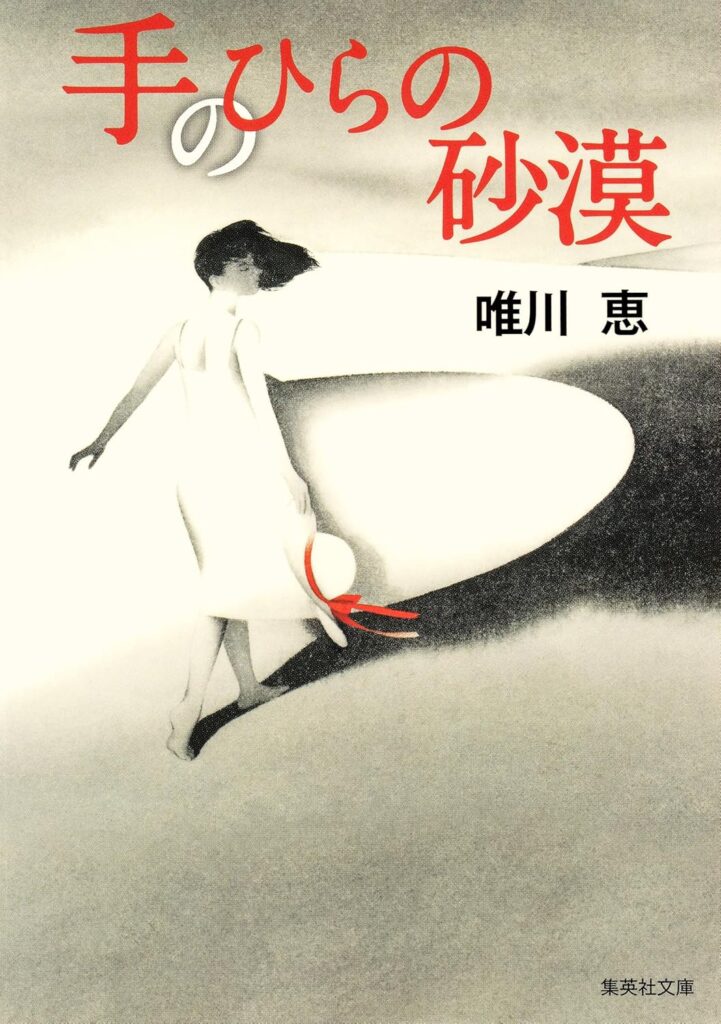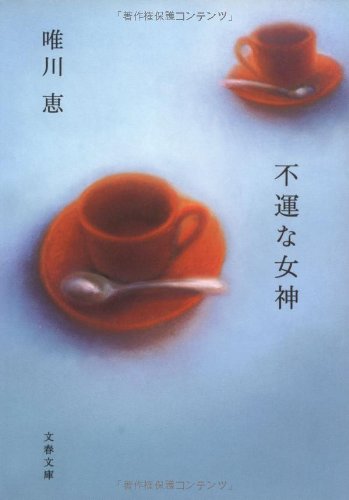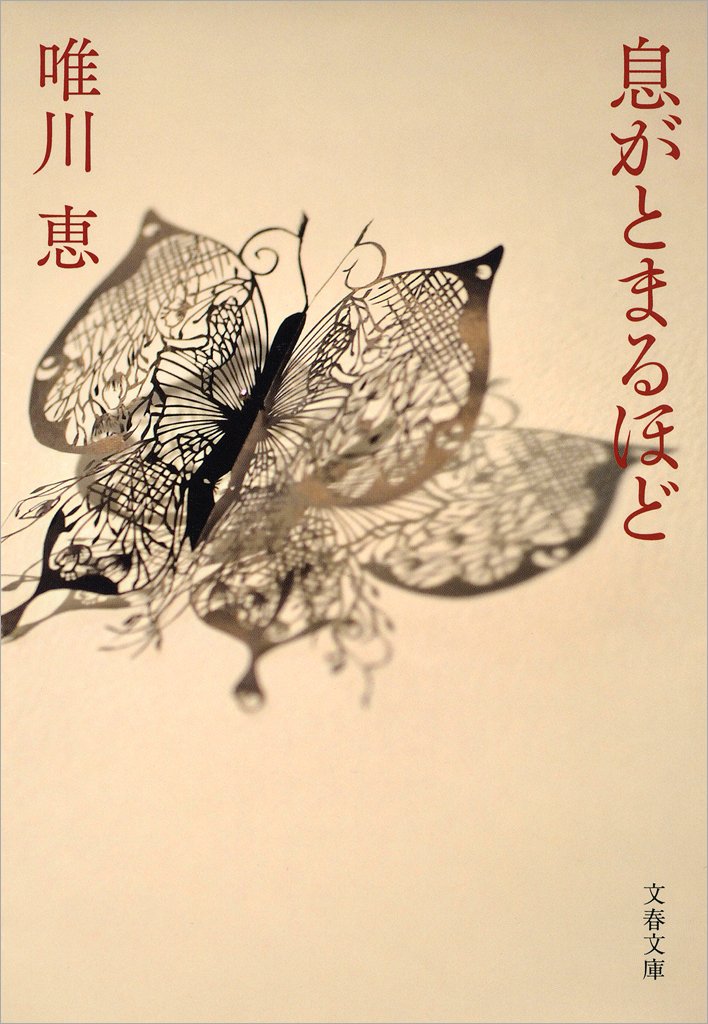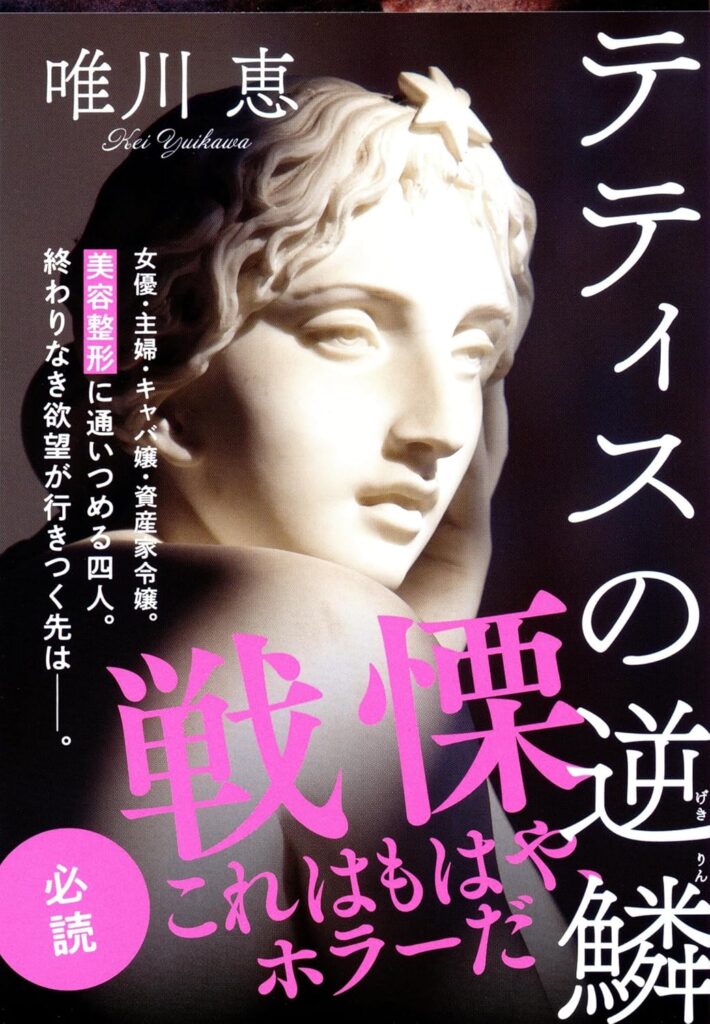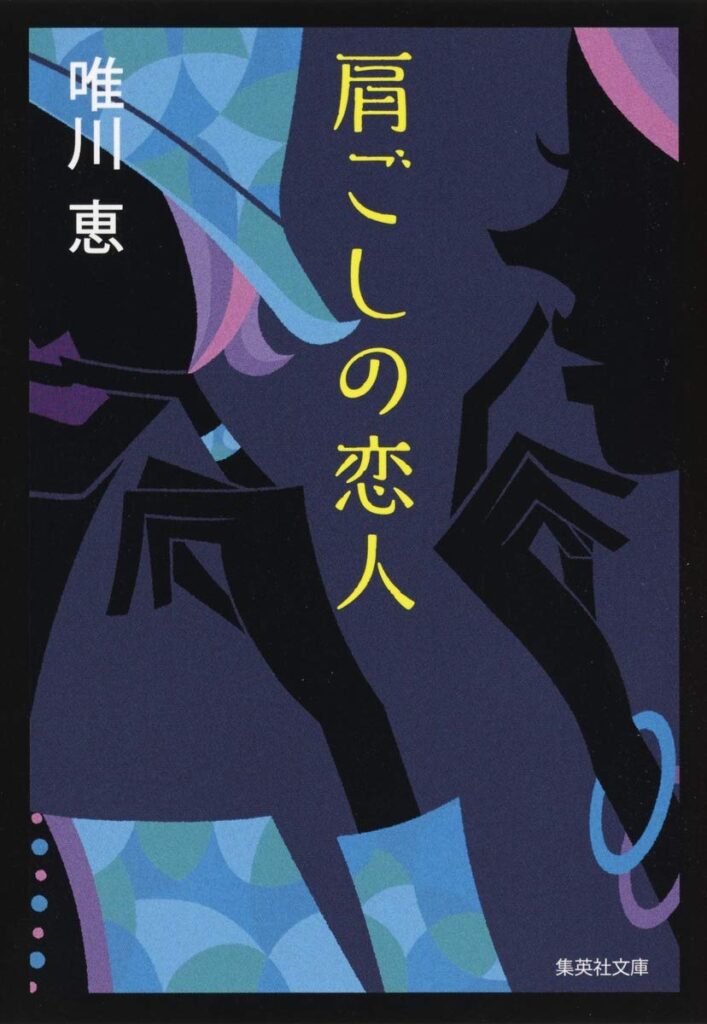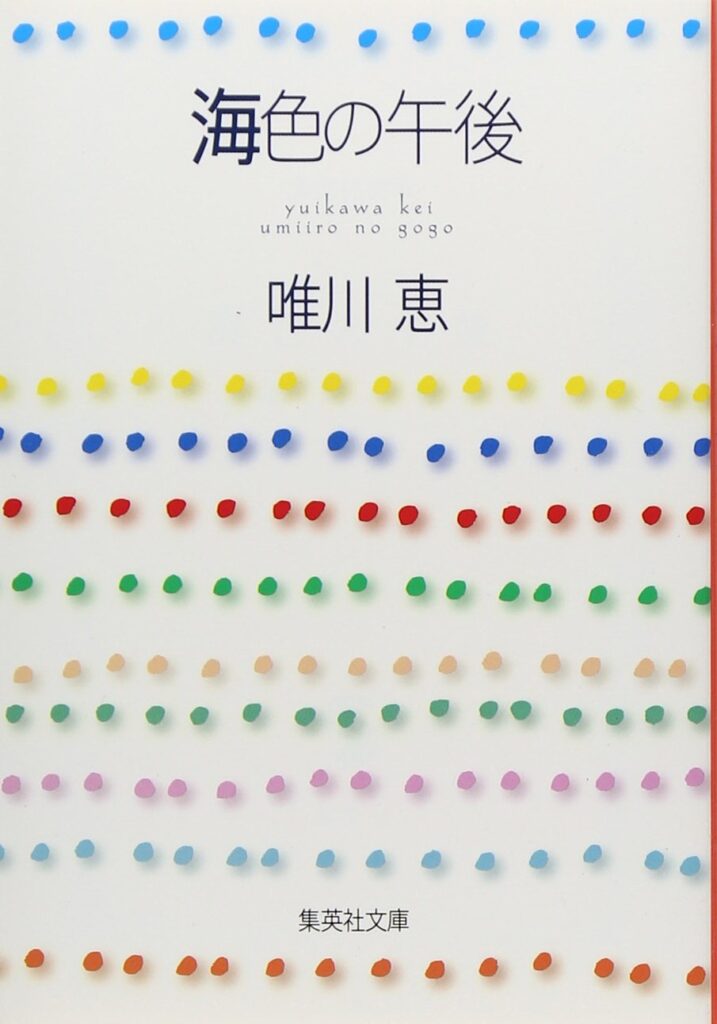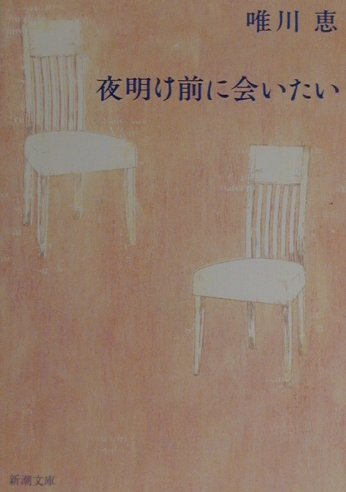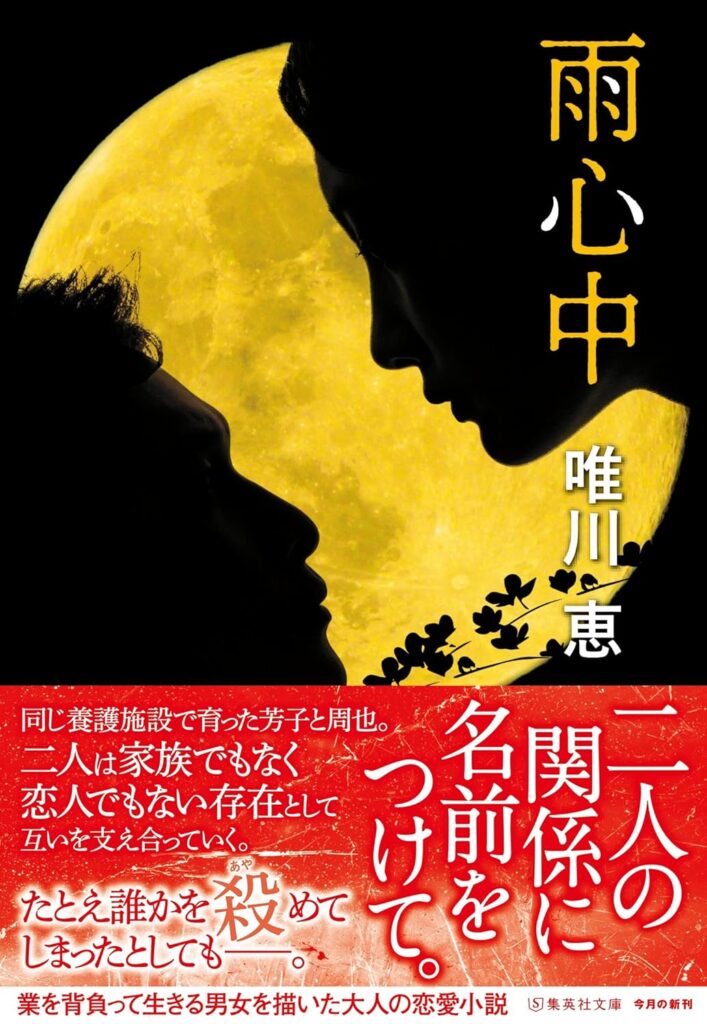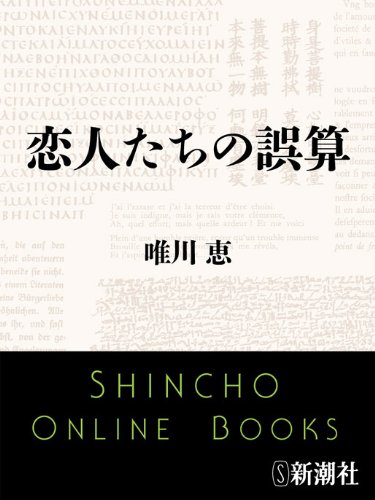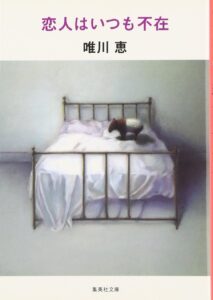 小説「恋人はいつも不在」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「恋人はいつも不在」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
唯川恵さんの作品は、男女の心の機微を丁寧に描き出すことで知られていますが、この「恋人はいつも不在」もまた、読む人の心に深く響く物語となっています。恋人との関係に悩んだり、自分の生き方について考えたりしたことがある方なら、きっと登場人物の誰かに共感できる部分があるのではないでしょうか。
物語は、どこにでもいそうな一組のカップル、奈月と時男の関係を中心に展開していきます。付き合いが長くなるにつれて生じる、言葉にならないすれ違いや、心の距離。それは特別なことではなく、多くの人が経験するかもしれない感情の揺らぎかもしれません。しかし、彼らはその中で何を感じ、どのような選択をしていくのでしょうか。
この記事では、そんな「恋人はいつも不在」の物語の核心に触れながら、その魅力をじっくりと語っていきたいと考えています。物語の結末にも触れていきますので、まだお読みでない方で、内容を知りたくないという場合はご注意くださいね。それでは、一緒に物語の世界へ入っていきましょう。
小説「恋人はいつも不在」のあらすじ
事務員として働く奈月とサラリーマンの時男は、交際して3年になる恋人同士です。しかし、いつの頃からか二人の間には見えない溝ができ始め、お互いの心は少しずつ離れていってしまっているのを感じていました。「話したいことがあるのに、相手がいない」「しんどい理由をいちいち説明するのが面倒」そんな思いが、二人のコミュニケーションをますます希薄なものにしていきます。奈月も時男も、言葉にして相手に伝えることをためらい、心の中で不満や疑問を募らせていくのです。
そんなある日、時男は会社に行けなくなってしまいます。勤めて3年目、上司との関係が大きなストレスとなり、彼の心は限界を迎えていたのでした。時を同じくして、時男は学生時代の同級生である協介と偶然再会します。協介は海外でボランティア活動をしており、彼の生き方に触れた時男は、自分も現状を打破するために海外ボランティアに行くことを決意します。意外なことに、時男の出社拒否の原因であったはずの上司が、会社に籍を置いたままボランティアに参加できる制度を時男に示し、彼の背中を押す形となりました。
一方、奈月もまた、自身の生活に変化を求めていました。ある会社の会議で、思わず製品について意見を言ってしまったことがきっかけで、仕事に対する新たな達成感と目的意識に目覚めます。そして、以前から興味のあった服飾デザインを学ぶため、夜間の専門学校に通い始めることを決意するのでした。奈月の両親は離婚し、母はパッチワーク教室を始めるなど、奈月の周囲の環境もまた、変化の時を迎えていました。
二人の関係に影を落とすかのように、時男の元恋人である小夜子が現れます。派手な雰囲気を持つ小夜子に、時男は再び心惹かれていくのを感じます。小夜子の存在は奈月を不安にさせ、焦燥感を募らせます。そして、小夜子はある衝撃的な告白をするのですが、その内容は奈月と時男の関係を揺るがすものでした。
奈月と時男、それぞれが新たな目標を見つけ、歩みを進めようとする中で、二人の歯車はますます噛み合わなくなっていきます。時男が小夜子に心を寄せ、奈月の前にはかつて自分に好意を寄せていた協介が再び現れるなど、それぞれの心は別の方向へと向かい始めます。彼らはすれ違いを重ねながら、関係の「新しい局面」へと否応なく進んでいくのでした。
最終的に、奈月と時男はそれぞれの道を選ぶことになります。恋愛関係を修復するのではなく、別々の未来へ向かって歩み出すことを決意するのです。それは決して悲しい結末ではなく、それぞれが自分自身の人生に誠実に向き合い、新たな一歩を踏み出すための、希望に満ちた選択として描かれています。
小説「恋人はいつも不在」の長文感想(ネタバレあり)
この「恋人はいつも不在」という作品、読み終えた後に心に残るのは、切なさや寂しさだけではない、不思議な清々しさでした。恋人同士の心が離れていく過程は、読んでいて胸が締め付けられるような場面も多いのですが、最終的に二人が下す決断と、そこから先の未来に光を感じさせてくれる物語だと感じました。
まず、主人公である奈月と時男の関係性について触れないわけにはいきません。交際3年という、安定しているようでいて、実は一番危うい時期なのかもしれませんね。お互いの存在が当たり前になり、新鮮さが薄れていく中で、コミュニケーションの重要性を改めて考えさせられました。「話したいのにいない」「説明するのがおっくう」という描写は、経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。小さな不満や誤解が積み重なり、気づいた時には大きな溝になっている…そんなリアルな恋愛の断面図を見ているようでした。
特に印象的だったのは、奈月と時男、双方の視点から物語が語られる点です。同じ出来事でも、奈月が感じていることと時男が考えていることが全く違っていたりして、「ああ、だからすれ違ってしまうんだな」と納得させられる場面がたくさんありました。どちらか一方だけが悪いのではなく、お互いの思いやりや言葉が少しずつ足りなくなっていった結果なのでしょう。恋愛において、一方的に誰かを断罪することの難しさを、この作品は巧みに描いていると思います。
時男が経験する「出社拒否」も、現代社会において決して他人事ではない問題だと感じました。上司との関係が原因ということでしたが、彼の内面的な葛藤や、将来への不安がひしひしと伝わってきました。そんな時男にとって、協介との再会は大きな転機となります。ボランティアという新しい道を見つけ、一歩を踏み出そうとする姿には勇気づけられます。そして、意外だったのが、彼を追い詰めたはずの上司が救いの手を差し伸べるという展開です。この上司、作中では「ヒキガエル」なんて呼ばれていて、最初はなんてひどい人なんだろうと思ったのですが、彼なりの考えや、ある種の不器用な情があったのかもしれないと考えさせられました。人間の多面性を感じさせる描写でしたね。
一方の奈月も、時男との関係に悩みながらも、自分自身の足で人生を切り開いていこうとします。それまで受け身だった彼女が、会議で勇気を出して意見を述べたことをきっかけに、仕事への情熱に目覚め、服飾デザインの道へ進む決意をする。この変化は、読んでいてとても応援したくなりました。彼女の母親が離婚を経てパッチワーク教室を始めるエピソードも、女性の自立や再出発というテーマと重なり、奈月の成長を後押ししているように感じました。自分のやりたいことを見つけ、それに向かって努力する姿は、誰にとっても輝いて見えるものですね。
そして、物語に大きな波紋を投じるのが、時男の元恋人・小夜子の登場です。彼女の存在は、奈月と時男の間に既にあった亀裂を、より明確なものにしてしまいます。時男が小夜子に惹かれていく様子は、奈月の立場からすると非常につらく、読んでいて胸が痛みました。小夜子自身もまた、何かを抱えているような影を感じさせる女性として描かれており、彼女の「突然のカミングアウト」は、物語の大きなターニングポイントの一つと言えるでしょう。このカミングアウトの内容については、はっきりとは書かれていない部分もありますが、それがかえって読者の想像力を掻き立て、様々な解釈を可能にしているのかもしれません。
小夜子の出現は、二人の関係がもはや修復困難な段階に来ていることを示す出来事ではありますが、彼女だけが破局の原因ではないと私は思います。むしろ、それ以前から積み重なっていた問題点が、彼女の登場によって一気に表面化したのではないでしょうか。時男が小夜子に安らぎや刺激を求めたのだとしたら、それは奈月との関係において満たされない何かがあったからなのかもしれません。
奈月の前にも、かつて自分に想いを寄せていた協介が再び現れます。協介の存在は、時男との関係で傷ついた奈月にとって、新たな可能性を感じさせるものだったでしょう。時男が小夜子に、奈月が協介に、それぞれ心が揺れ動く様子は、お互いの心が既に別の方向を向き始めていることの証のようにも見えました。このあたりの心の動きは、非常に繊細に描かれていて、唯川さんの筆致の巧みさを感じずにはいられません。
物語が進むにつれて、奈月と時男は、それぞれが自分自身の人生と真剣に向き合い始めます。奈月は服飾の勉強に没頭し、確かな手応えを感じていきます。時男もまた、ボランティアという新たな道で自分を見つめ直し、少しずつ前進していきます。二人がそれぞれの場所で成長していく姿は、頼もしくもあり、同時に、もう二人の道が交わることはないのかもしれないという予感を抱かせます。
そして、物語は「えーーーっとびっくりする展開があった」と評されるような、ある種のクライマックスを迎えます。これは小夜子のカミングアウトもそうですが、それ以外にも、奈月と時男が最終的な決断を下すに至るまでの、様々な出来事の積み重ねを指しているのかもしれません。隠されていた思いや、見て見ぬふりをしてきた現実と向き合わざるを得なくなった時、彼らはどのような選択をするのか。読者は固唾を飲んで見守ることになります。
私がこの作品を読んで特に素晴らしいと感じたのは、登場人物一人ひとりがとても丁寧に描かれている点です。奈月や時男はもちろんのこと、彼らの両親、時男の上司、協介、そして小夜子。それぞれが抱える思いや背景があり、単純な善悪では割り切れない人間らしさが感じられました。誰の視点に立っても、その人の気持ちが理解できるような気がしてくるのです。これこそが、物語に深みを与えている要因なのでしょう。
そして、最も心に残ったのは、やはりその結末です。奈月と時男は、最終的に別々の道を歩むことを選択します。恋愛物語の多くは、困難を乗り越えて二人が結ばれる、というハッピーエンドを期待しがちですが、この作品はそうではありません。しかし、不思議と悲壮感はなく、むしろ「爽やかだった」「きらきらしたラスト」と評されるように、希望に満ちた終わり方だと感じました。
二人が再び恋人同士になることだけが幸せの形ではない。お互いがそれぞれの目標を見つけ、自分自身の足で未来に向かって歩き出すこと、それもまた素晴らしい「ハッピーエンド」なのだと、この物語は教えてくれます。「自分に正直に生きることの大切さ」というメッセージが、静かに、しかし力強く伝わってきました。時には、無理に関係を続けようとするよりも、一度距離を置き、それぞれの道を進むことが、双方にとってより良い結果をもたらすこともあるのかもしれません。
この作品は、恋愛の終わりを描きながらも、それ以上に個人の「成長」というテーマを鮮やかに描き出していると思います。奈月も時男も、悩み、傷つきながらも、最終的には前を向いて歩き出します。その姿は、読んでいて本当に清々しい気持ちにさせてくれました。もしかしたら、恋人という関係は失ったかもしれませんが、彼らはそれ以上に大切な何かを見つけ、新しい人生の章をスタートさせたのではないでしょうか。そんな未来への期待感が、読後感を温かいものにしてくれます。
「恋人はいつも不在」というタイトルは、物理的な不在だけでなく、心の不在をも表しているのでしょう。すぐ隣にいても、心が通い合っていなければ、それは「不在」と同じなのかもしれません。この物語は、そんな恋人たちの心の機微、すれ違い、そしてそれぞれの再生を描いた、深く、そして優しい物語だと言えるでしょう。恋愛に悩んでいる人、新しい一歩を踏み出したいと思っている人に、ぜひ手に取ってみてほしい一冊です。きっと、何かを感じ取り、明日への力をもらえるはずです。
まとめ
小説「恋人はいつも不在」は、3年間付き合ったカップル、奈月と時男が直面する関係の終わりと、それぞれが新たな道を見つけて成長していく姿を描いた物語です。読んでいると、誰もが経験するかもしれない恋愛のすれ違いや、コミュニケーションの難しさに共感し、胸が締め付けられる場面も少なくありません。
しかし、この物語の魅力は、単に失恋の痛みを描くだけでなく、そこから立ち上がり、自分自身の力で未来を切り開いていく登場人物たちの強さにあります。奈月は仕事への情熱を見出し、服飾の道へ。時男は出社拒否という危機を乗り越え、ボランティア活動を通じて新たな自分を発見します。
最終的に二人は別々の道を歩むことになりますが、その結末は決して暗いものではなく、むしろ希望に満ちています。お互いが自分に正直に生きることを選び、それぞれの目標に向かって輝き始める姿は、読む人に勇気と清々しさを与えてくれるでしょう。
「恋人はいつも不在」は、恋愛の終わりと個人の再生というテーマを通じて、私たちに「自分らしく生きることの大切さ」を教えてくれる作品です。関係の形が変わっても、そこから得られるものがあり、新たな始まりがあることを感じさせてくれます。