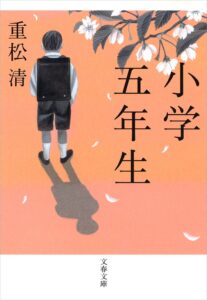 小説「小学五年生」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「小学五年生」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この作品は、直木賞作家である重松清さんによって紡がれた、17編の短編からなる物語集です。それぞれの物語で主人公となるのは、タイトルにもなっている「小学五年生」の男の子たち。彼らが過ごす日常の中で起こるささやかな出来事や、心の中に芽生える様々な感情が、丁寧に、そして深く描かれています。
誰もが通り過ぎてきたであろう、子供時代のあの独特な空気感。大人になる一歩手前、心と体が大きく変化する時期の、喜び、悲しみ、戸惑い、そしてちょっぴり背伸びしたくなる気持ち。そんな、懐かしくも切ない感情が、この本には詰まっているように感じます。読んでいるうちに、自分自身の遠い記憶がふと蘇ってくるかもしれません。
この記事では、それぞれの物語がどのような内容なのか、その概要(結末に触れる部分もあります)をお伝えするとともに、私自身がこの作品を読んで何を感じ、何を考えたのか、個人的な思い入れを込めて詳しく記していきたいと思います。少し長い文章になりますが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
小説「小学五年生」のあらすじ
重松清さんの『小学五年生』は、17の短い物語を集めた一冊です。共通しているのは、どの話も小学五年生の男の子が中心にいるということ。彼らが日々の中で経験すること、感じる心の揺れ動きが、一つ一つの物語の核となっています。
例えば、『葉桜』では、転校してしまった友達と春休みに再会する、少し切ないけれど温かい交流が描かれます。『おとうと』では、目の手術を控えた弟を思う、兄の複雑な心境と優しさが胸を打ちます。視力の弱い弟を普段は足手まといに感じてしまうこともあるけれど、手術を前にした特別な一日、兄としてできることをしようとする姿が印象的です。
また、『友だちの友だち』では、転校生との間に生まれたぎくしゃくした関係が、ある女性との出会いをきっかけに変化していく様子が描かれます。その女性は、二年前に同じ年の息子さんを事故で亡くしており、その息子さんが転校生の元親友だったという事実が、少年たちの関係に静かな影響を与えます。友情のもろさと、思いがけない繋がりから生まれる再生の物語と言えるでしょう。
『ケンタのたそがれ』は、父を亡くし、母も働きに出るようになった少年の、夏休みの孤独な一日を描いています。友達は皆、塾の夏期講習に行ってしまい、公園に行っても誰もいない。時間を持て余し、やり場のない寂しさを抱える少年の姿は、読む者の心に静かに響きます。家族や友人との関係性の変化が、子供の心に落とす影を丁寧に捉えています。
『バスに乗って』では、母親が入院してしまい、一人でバスに乗って見舞いに通う少年の不安な日々が描かれます。バスの運転手との関わりや、なかなか減らない回数券が象徴するように、母の回復を願う切実な気持ちと、先の見えない不安が伝わってきます。『どきどき』は、バレンタインデーを前に、初めて女子から年賀状をもらった少年の、そわそわした心情を描いた可愛らしい物語です。
これらの物語を通して、転校、家族関係の変化、友人との葛藤や友情、淡い恋心、そして身近な人の死といった、子供たちが直面する様々な出来事が描かれています。少年たちの視点から語られる世界は、時に瑞々しく、時にほろ苦く、読む人の心に深く染み入ります。全体として、誰もが子供時代に感じたかもしれない様々な感情や、記憶の片隅にある風景を呼び覚ますような、そんな物語が集められています。
小説「小学五年生」の長文感想(ネタバレあり)
重松清さんの『小学五年生』を読み終えて、しばらくの間、なんとも言えない余韻に浸っていました。本を閉じた後も、物語の中に登場した少年たちの顔や、彼らが過ごした風景が、頭の片隅からなかなか離れてくれませんでした。それは、どこか懐かしく、そして少し切ない、特別な読書体験だったように思います。
この作品集の素晴らしい点は、やはり小学五年生という、子供と大人の狭間にいる少年たちの心の動きを、驚くほど繊細に捉えているところだと感じます。彼らの目を通して見る世界は、純粋で、時に残酷で、そしてどうしようもなく愛おしい。一つ一つの短編が、まるで自分自身の遠い記憶の一部を切り取ってきたかのように、リアルな手触りをもって迫ってきます。
特に心に残っている物語はいくつかありますが、例えば『葉桜』。転校してしまった友達との再会は、嬉しいけれど、どこか以前とは違う空気も感じてしまう。それでも変わらない何かを信じたい、そんな少年たちの気持ちが痛いほど伝わってきました。時間は流れ、環境は変わるけれど、心の奥底で繋がっていたいと願う気持ちは、大人になった今でもよく理解できます。あの頃の友情の形は、今とは少し違っていたかもしれません。もっと不器用で、でももっと純粋だったような気がします。
『おとうと』も忘れられません。目の手術を控えた弟に対して、普段は照れくささや煩わしさも感じているであろう兄が、その日だけは精一杯の優しさを見せようとする姿。弟のために、見えるかどうかわからない海を見せに連れて行こうとする不器用な愛情に、胸が熱くなりました。不安な気持ちを隠しながら、必死でペダルを漕ぐ少年の背中が目に浮かぶようです。兄弟って、こういう複雑な感情の積み重ねなのかもしれないな、と感じました。
『友だちの友だち』では、友情の難しさと、人の死がもたらす思いがけない繋がりが描かれていて、深く考えさせられました。子供同士の関係は、些細なことで壊れてしまう脆さを持っているけれど、共通の痛みや経験を通して、また新しい形で結びつくこともある。亡くなった友人の母親との交流が、二人の少年の心を再び通わせるきっかけになるという展開は、静かな感動を呼びました。悲しみを通して人は成長する、という普遍的なテーマを感じさせる物語でした。
『カンダさん』は、憧れのお兄さんのような存在だったカレシとの突然の別れを描いていて、子供時代の「喪失」を象徴しているように思えました。楽しかった時間が永遠に続くわけではないこと、大切な人との別れは予期せず訪れることを、少年は身をもって知る。プラモデル作りの思い出とともに、ほろ苦い感情が残ります。あの頃、自分にとっての世界の中心だった人が、ある日突然いなくなってしまう感覚は、子供にとっては計り知れない衝撃だったはずです。
日常の中のふとした瞬間を切り取った『雨やどり』も印象的でした。同じバス停、同じ決闘の場、同じ歯医者。それぞれの場所にいる三人の少年が、突然の雨によって同じ時間を共有する。彼らの心の中には、おばあちゃんへの心配、友達との対立、気になる女の子への淡い気持ちといった、それぞれのドラマがある。雨が上がり、虹がかかるまでの短い時間に凝縮された、子供たちの世界の豊かさを感じました。
思春期特有の感情を描いた『もこちん』は、読んでいて少しドキドキしました。異性への意識、体や心の変化への戸惑い。少年たちの、ちょっとおませで、でもまだ幼い部分が垣間見える描写がリアルでした。「もこちん」というあだ名に込められた意味と、それを女子に問われる場面の気まずさは、誰もが経験したかもしれない(あるいは想像できる)思春期の一コマとして、妙に記憶に残ります。
『南小、フォーエバー』は、楽しみにしていた友達との再会の約束が、少し違う形で実現してしまう物語。新しい環境で新しい友達と楽しそうにしているかつての親友の姿に、少年は寂しさと戸惑いを覚えます。友情は変わらないと信じていたけれど、現実はそう単純ではない。子供ながらに感じる、人間関係の変化への切なさが描かれていました。約束が果たされないことへの失望感は、大人になっても経験することですが、子供にとってはより大きな出来事だったでしょう。
『プラネタリウム』には、少年期特有の甘酸っぱいときめきが詰まっていました。偶然隣り合わせになった女の子との、ぎこちないけれど心弾む交流。同じ誕生日だと知った時の高揚感。プラネタリウムの暗闇の中で、二人の間に流れる特別な空気感は、読んでいるこちらまで胸が高鳴るようでした。あの頃の、ちょっとした偶然に運命を感じてしまうような、純粋な気持ちを思い出させてくれました。
父の死という重いテーマを扱った『ケンタのたそがれ』は、静かな筆致ながら、少年の深い孤独感がひしひしと伝わってくる作品でした。夏休みの、太陽だけがやけに明るい一日。友達もいない、父親もいない、母親も仕事。ぽっかりと空いた時間と心の穴を、少年はどう埋めればいいのかわからない。そのやるせない気持ちが、痛いほど伝わってきました。子供が抱えるにはあまりにも大きな喪失感を、淡々と描くことで、かえってその深さが際立っていました。
『バスに乗って』もまた、家族の不在という不安を描いています。入院中の母親を案じながら、一人でバスに乗る少年の心細さ。ぶっきらぼうに見えた運転手の、思いがけない優しさに触れる場面は、救いでした。回数券が一枚、また一枚と減っていくことへの恐怖と、母の回復を願う切実な祈り。子供の視点から見た、大人の世界の理不尽さや、それでも存在する確かな温かさが描かれていました。
いじめという難しい問題を扱った『ライギョ』は、読んでいて胸が苦しくなりました。友達からの圧力に抗えず、いじめに加担してしまった少年の罪悪感と恐怖。本当はやりたくないのに、やってしまう。その弱さが、とても人間的で、だからこそ余計に辛く感じました。被害者であるタカギくんの、淡々とした態度の裏にあるかもしれない感情を想像すると、さらにやるせない気持ちになりました。子供の世界にも存在する、残酷な現実を突きつけられる物語でした。
『すねぼんさん』は、父の死後、母の実家へ引っ越すトラックの中で過ごす一夜を描いています。見慣れない大人たち、知らない土地への不安。そんな心細い少年の心を、不器用ながらも温かく包み込もうとする大人たちの存在が、救いのように感じられました。深夜のドライブインでの出来事は、少年にとって忘れられない記憶になったことでしょう。不安の中に差し込む、ささやかな光のような物語でした。
離婚という、子供には理解しきれない大人の事情に巻き込まれる『川湯にて』。母と二人、真冬の川辺で温泉を掘るという過酷な作業を通して、少年は母の強さと脆さ、そして自分自身の無力さを感じるのかもしれません。父への複雑な思いと、母を支えたいという気持ち。厳しい自然の中で、母子の関係性が静かに描かれていました。
家族間の微妙な空気を描いた『おこた』も印象的でした。離婚して実家に戻ってきた叔母と、それを快く思わない父。大人の複雑な感情や確執を、子供は敏感に感じ取ってしまう。お正月の、本来なら和やかであるはずの食卓に漂う緊張感が、リアルに伝わってきました。子供にはどうすることもできない、大人の世界の理不尽さを感じさせる物語でした。
『正』は、学級委員選挙という学校生活の一場面を通して、少年の自意識や承認欲求を描いています。選ばれたいけれど、面倒なことはしたくない。でも、選ばれないのは悔しい。そんな揺れ動く気持ちは、誰にでも覚えがあるのではないでしょうか。「真ん中よりちょっと上」でありたいという、微妙なプライドと不安が、コミカルでありながらも切実に描かれていました。
そして、バレンタインデーをめぐる『どきどき』。年賀状をくれた女の子からのチョコレートを、期待していないと言いながらも、心のどこかで待ち望んでしまう少年の姿が、微笑ましくも愛おしい。異性を意識し始めたばかりの、あの独特のそわそわした感じが、見事に表現されていました。「可能性」という言葉にすがりたくなる気持ち、よくわかります。
最後の『タオル』は、祖父の死を通して、知らなかった父の若い頃の姿や、漁師としての祖父の生き様を知る物語です。世代を超えて受け継がれていくもの、家族の歴史。お通夜という場で、少年は少しだけ大人に近づいたのかもしれません。シライさんという外部の人の視点を通して語られる家族の物語が、少年の心に新たな感慨をもたらしたことでしょう。
これらの物語を読んでいると、まるでタイムマシンのように、自分自身の小学五年生の頃へと連れていかれるような感覚になります。忘れていた友達の顔、通学路の風景、些細なことで笑ったり泣いたりしたこと。楽しかったことも、悲しかったことも、全部が今の自分につながっているのだと感じさせてくれます。
参考にした文章の筆者の方が、読み終えて昔の友人のことを思い出し、連絡先を探したというエピソードがありましたが、その気持ち、とてもよくわかります。私も、あの頃一緒に遊んだ仲間たちは今どうしているだろうか、と考えずにはいられませんでした。特に、小学四年生まで毎日のように一緒にいたのに、五年生になるタイミングでクラスが分かれたり、あるいは自分が引っ越したりして、疎遠になってしまった友達のことなどを思い出しました。あの頃、もっとたくさん話しておけばよかった、もっと一緒に色々なことをしてみたかった、という後悔にも似た気持ちが湧き上がってきます。
でも、この『小学五年生』という作品は、単に過去を懐かしむだけの物語ではないと思います。少年たちが直面する悩みや葛藤は、形を変えながらも、私たちが大人になってからも経験し続ける普遍的なテーマを含んでいます。友情、家族、別れ、喪失、そして自分自身との向き合い方。これらの物語を通して、私たちは子供時代の自分自身を再発見すると同時に、今の自分自身を見つめ直すきっかけを与えられるのかもしれません。
重松清さんの文章は、どこまでも優しく、登場人物たちへの温かい眼差しに満ちています。だからこそ、時に描かれる子供の世界の残酷さや切なさが、より一層胸に響くのかもしれません。読み終えた後には、温かい気持ちと、ほんの少しの切なさが残る。そんな、心に深く刻まれる読書体験でした。この本に出会えて本当に良かったと感じています。
まとめ
重松清さんの小説『小学五年生』は、17編の短編が収められた珠玉の作品集です。それぞれの物語で小学五年生の少年が主人公となり、彼らの日常の中で起こる出来事や、心の成長が瑞々しく描かれています。
物語の概要として触れたように、転校による別れと再会、家族(兄弟、親子、祖父母)との関係、友人との衝突や深まる絆、異性への淡い意識、そして身近な人の死といった、子供たちが経験する様々なテーマが扱われています。少年たちの視点を通して語られる世界は、時に切なく、時に温かく、読者の心を揺さぶります。
結末に触れる部分も含めて感想を述べましたが、この作品の魅力は、子供時代の普遍的な感情や記憶を呼び覚ます力にあると思います。読者は、物語の少年たちに自分自身のかつての姿を重ね合わせ、懐かしさや共感を覚えることでしょう。また、大人になった今だからこそ、少年たちの純粋さや健気さ、そして彼らを取り巻く大人たちの思いにも、深く共感できる部分があるはずです。
単なるノスタルジーに留まらず、人が生きていく上で向き合うことになる様々な感情や出来事を、子供たちの視点を通して深く描いた『小学五年生』。読後には、温かい気持ちと、どこか切ない余韻が残ります。忘れかけていた大切な何かを思い出させてくれるような、多くの人に手に取ってほしいと感じる一冊です。
































































