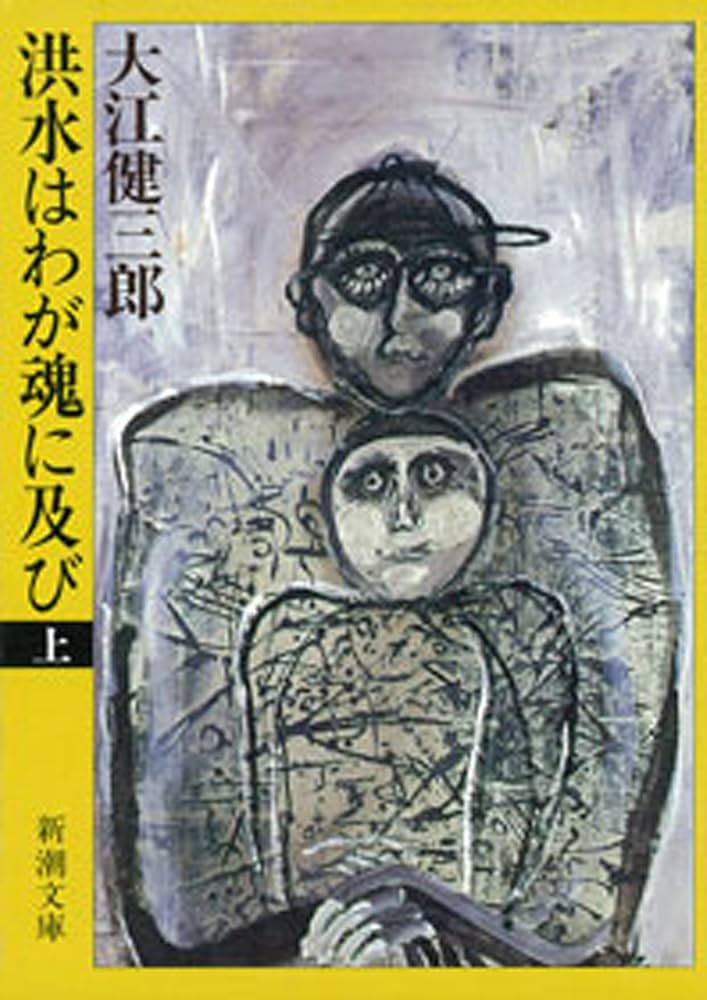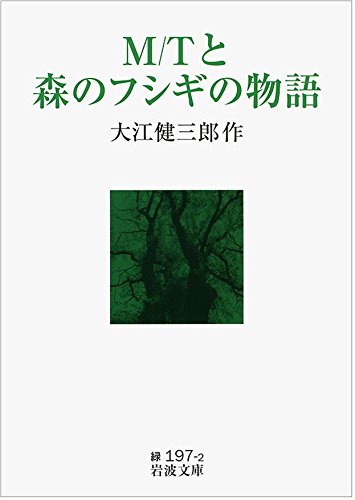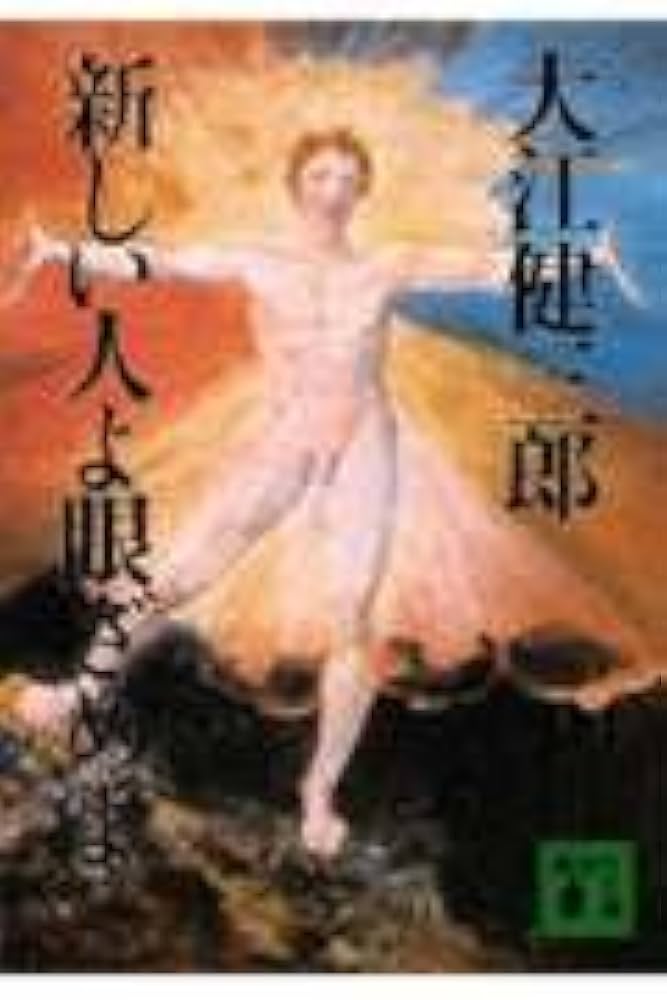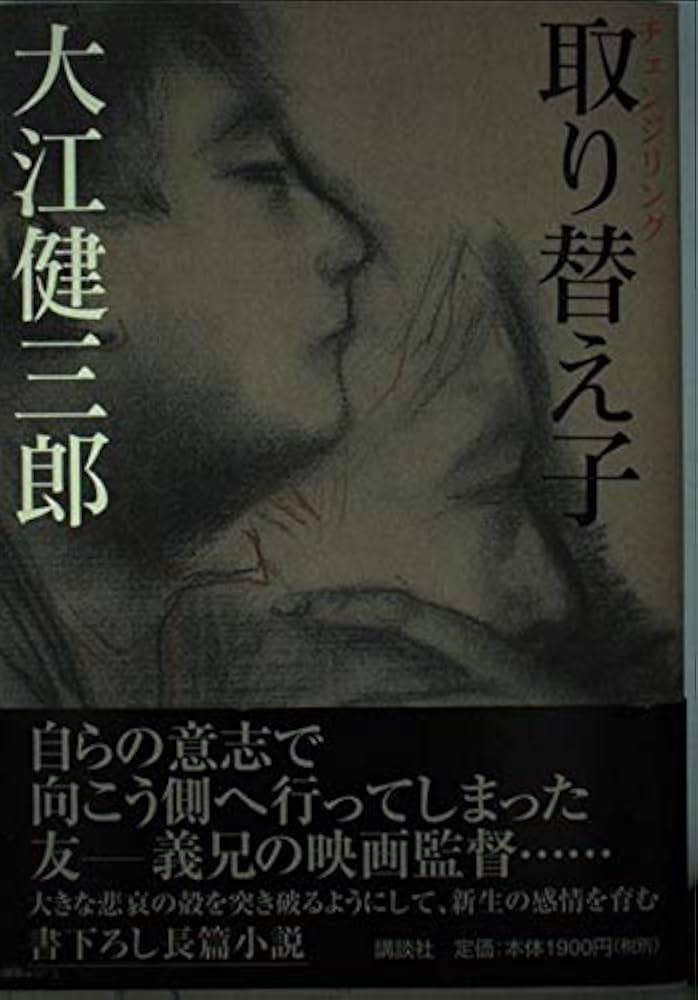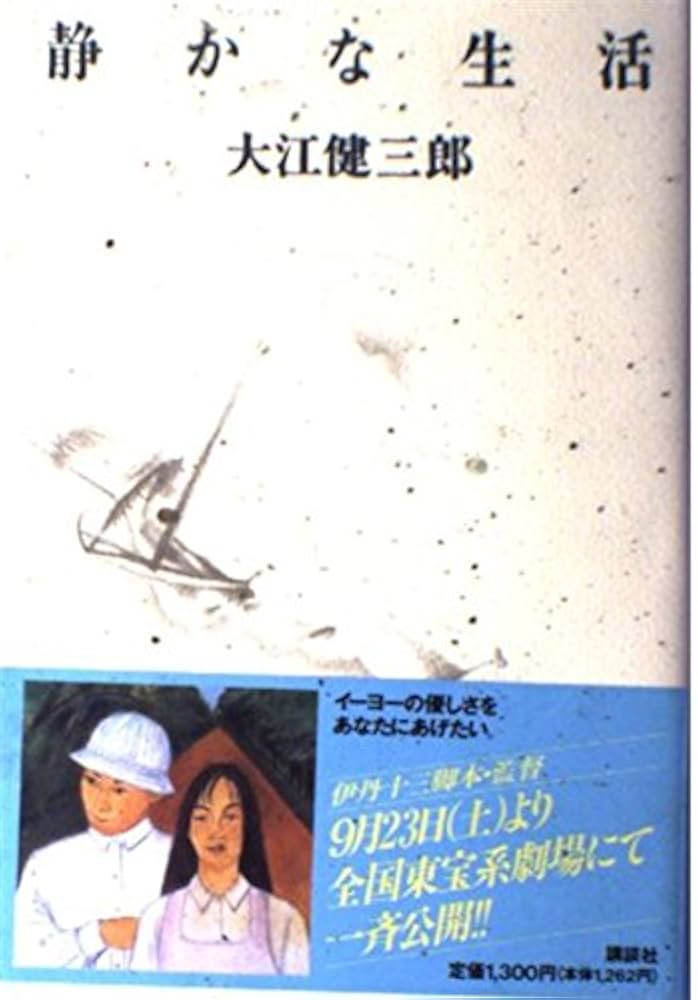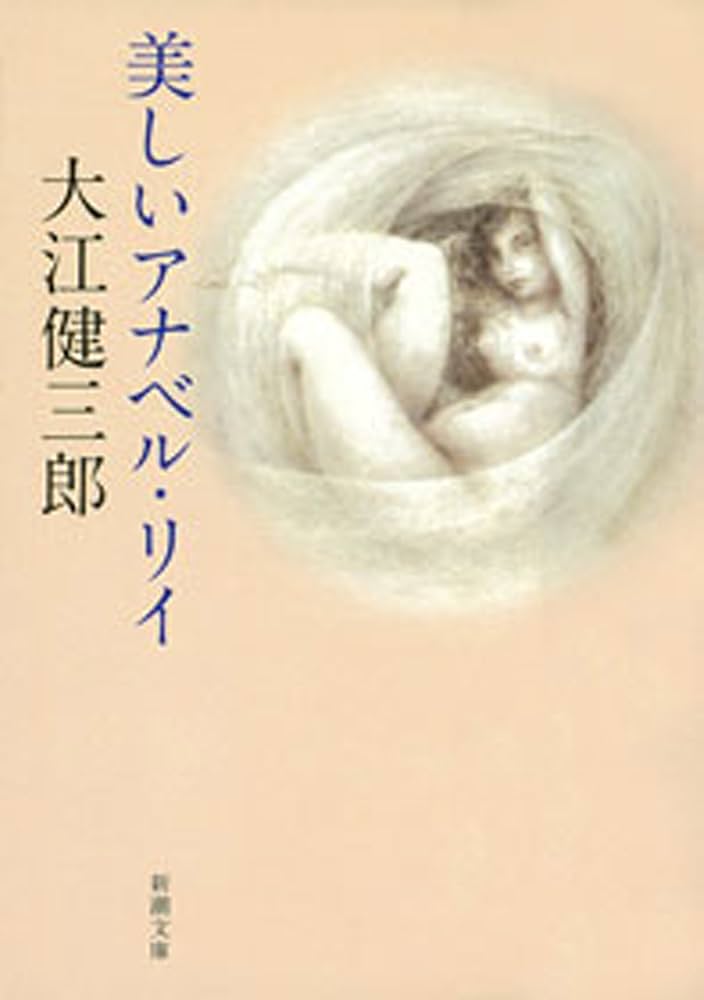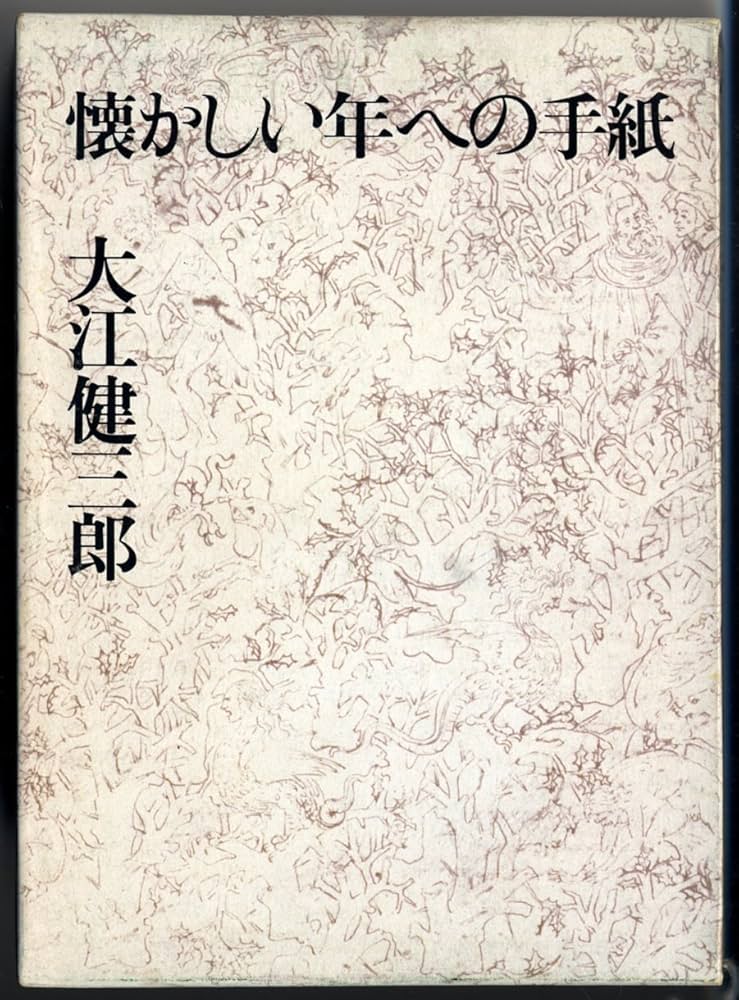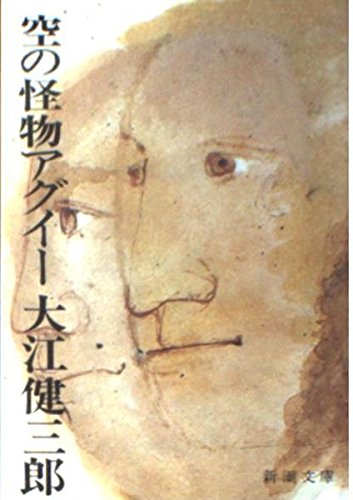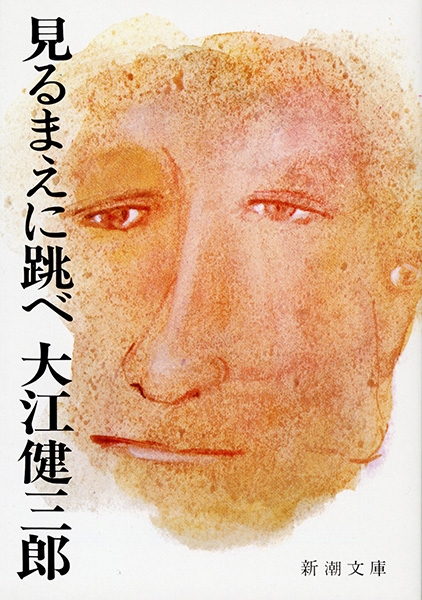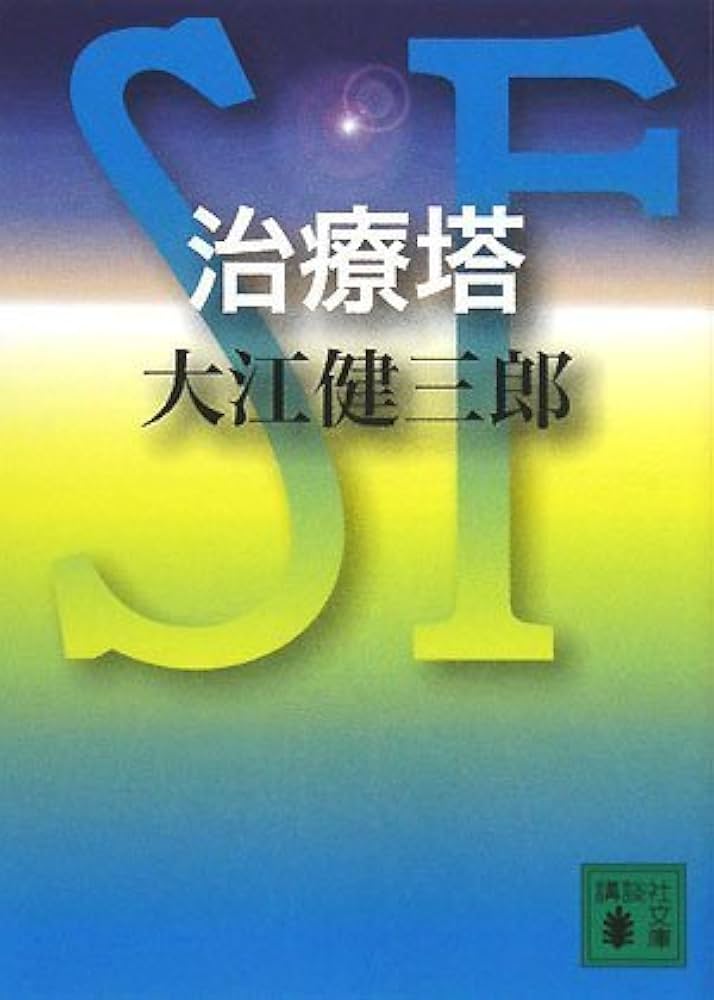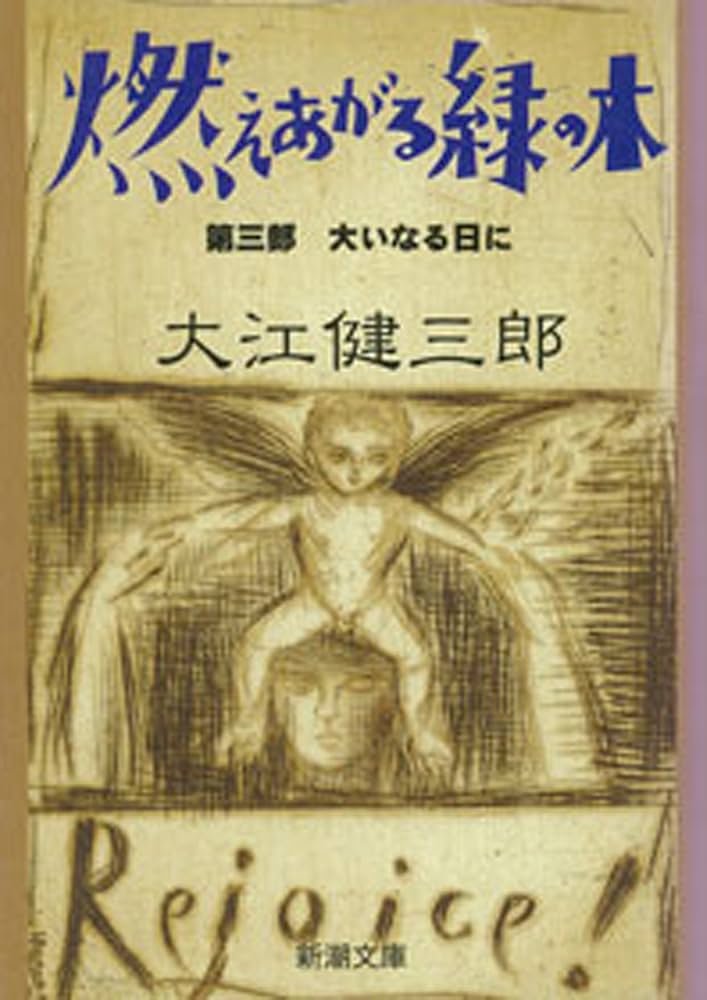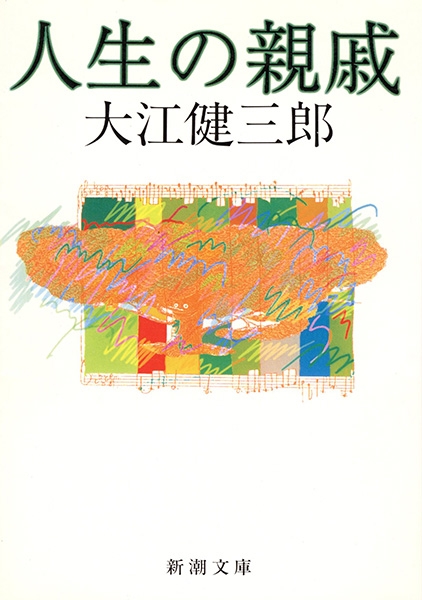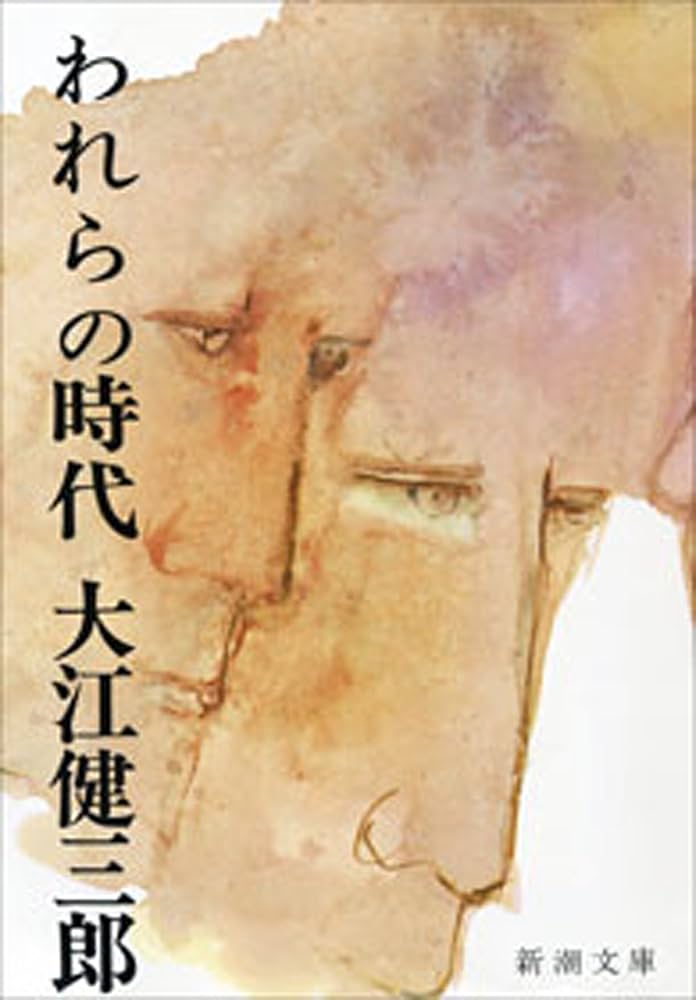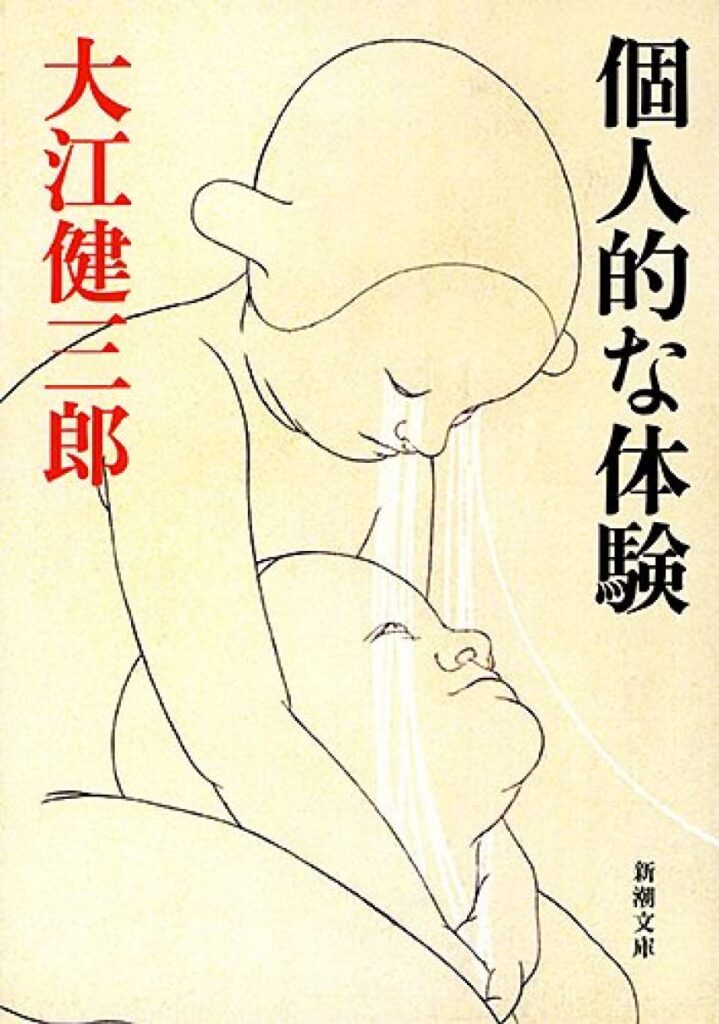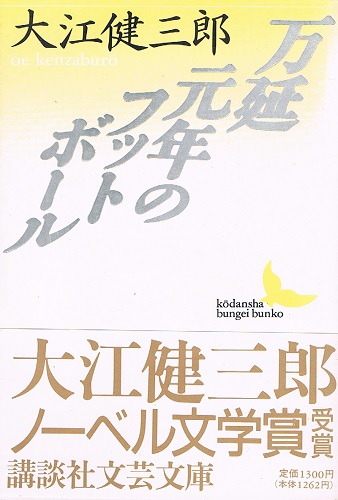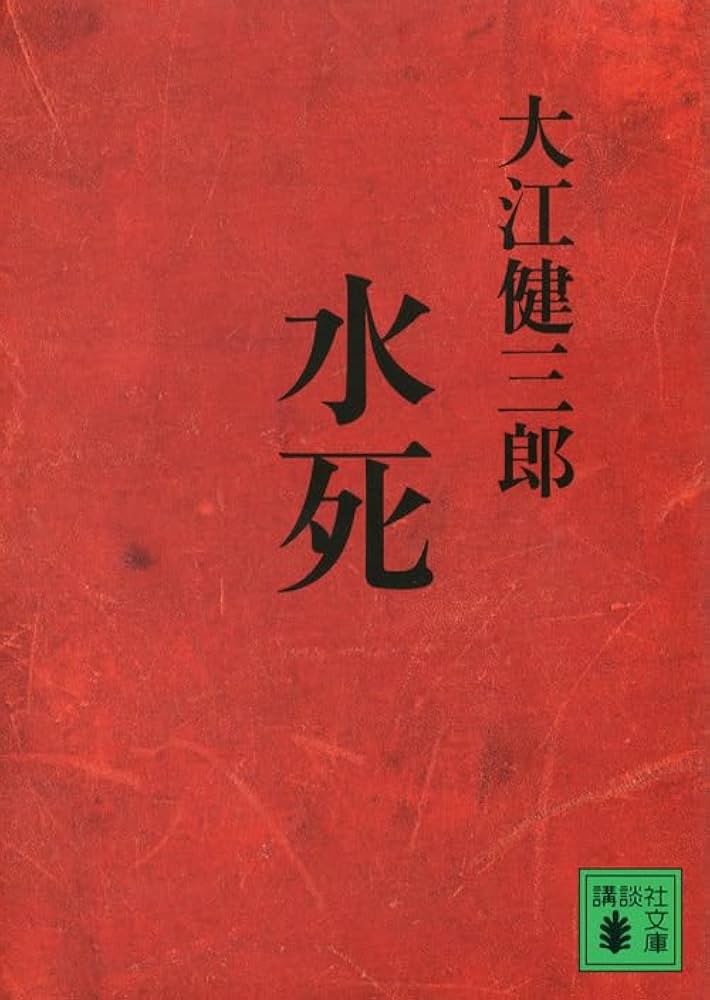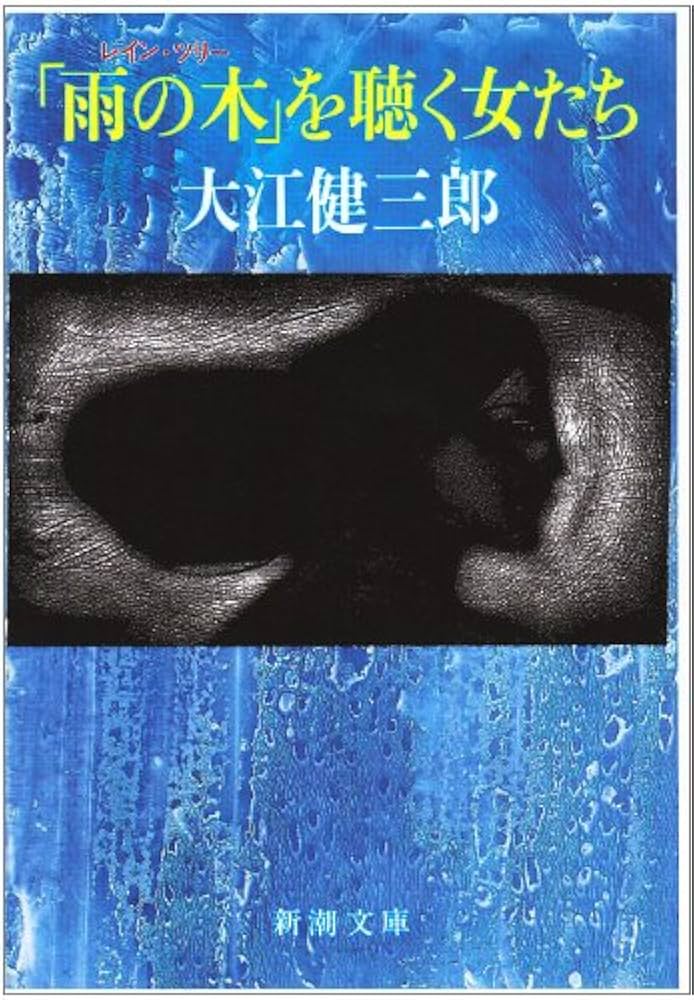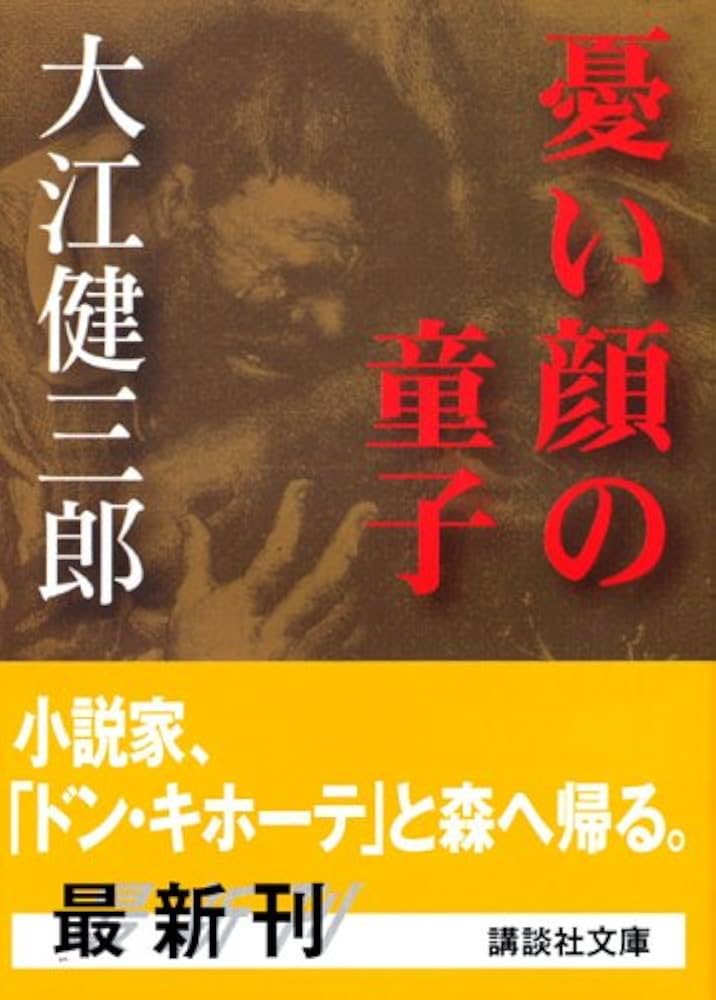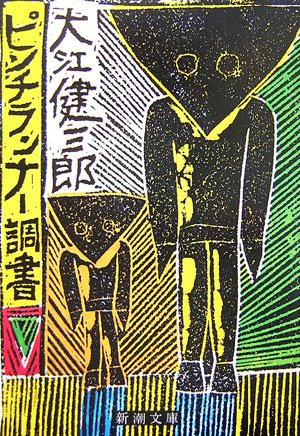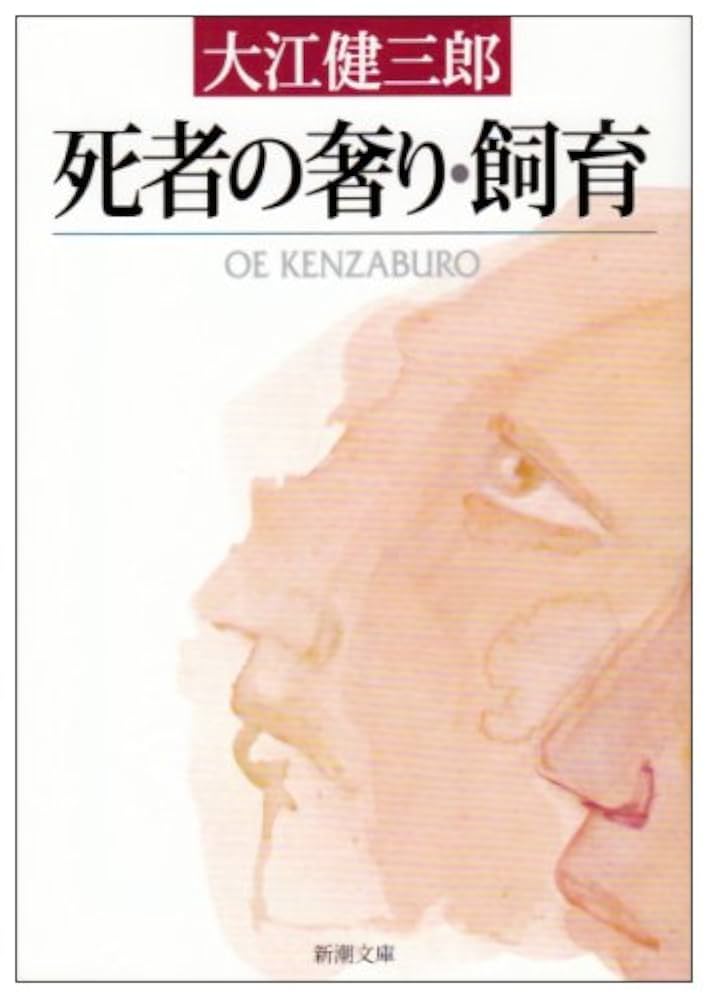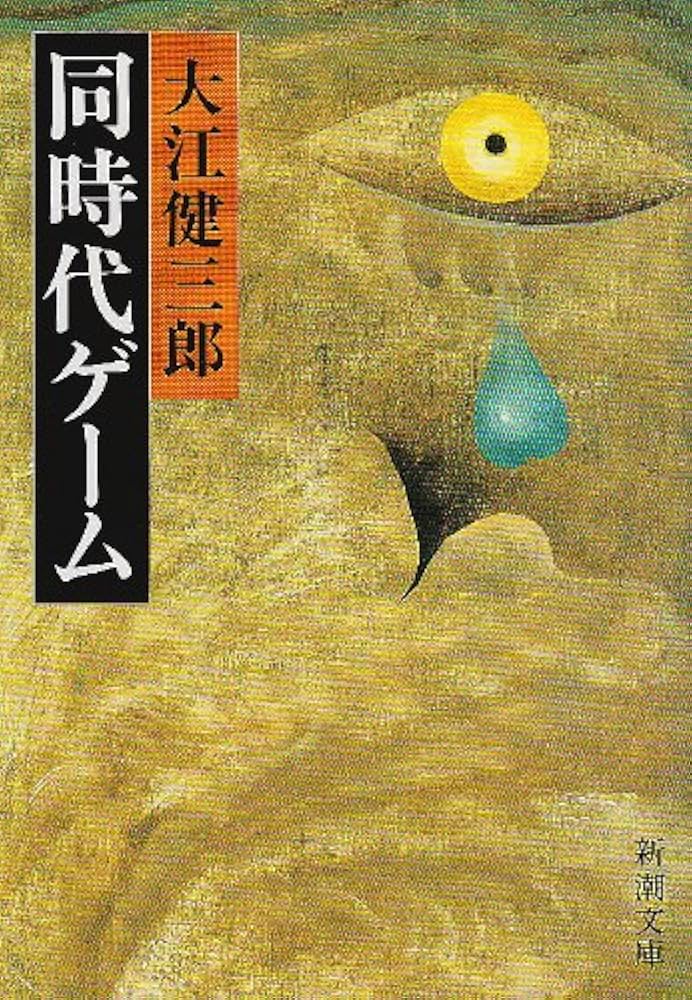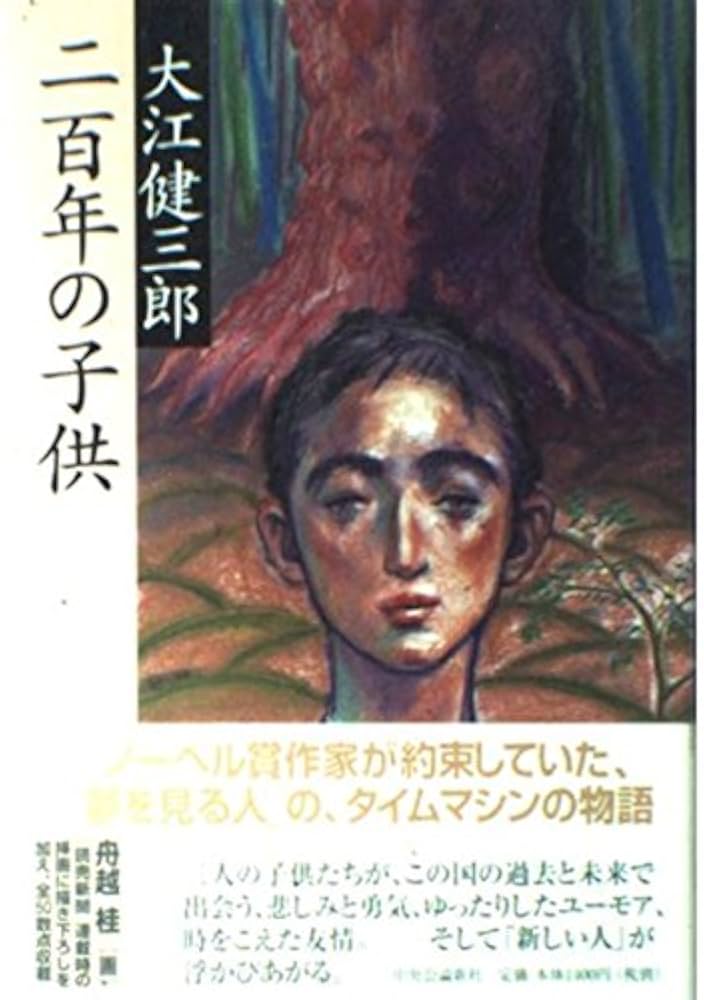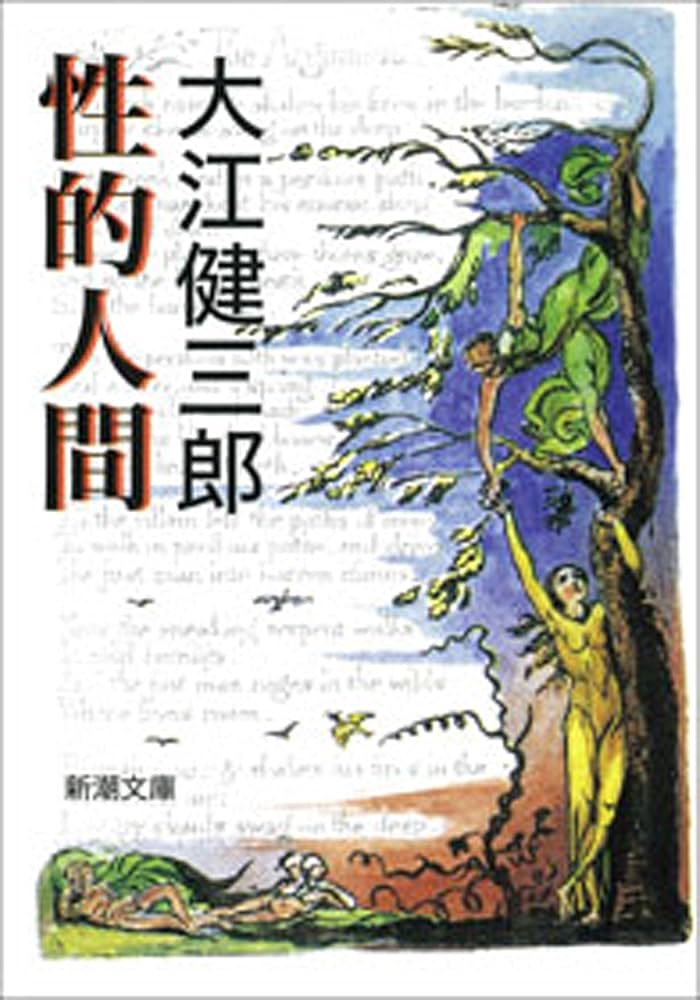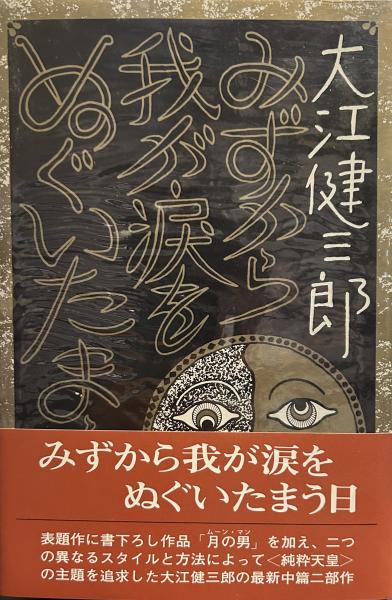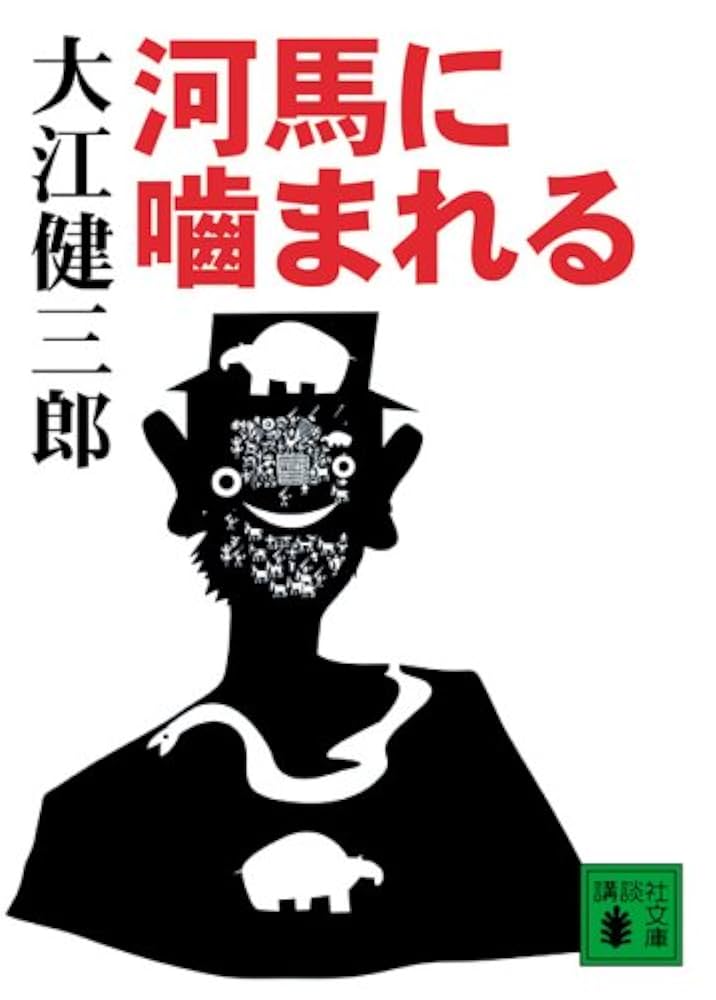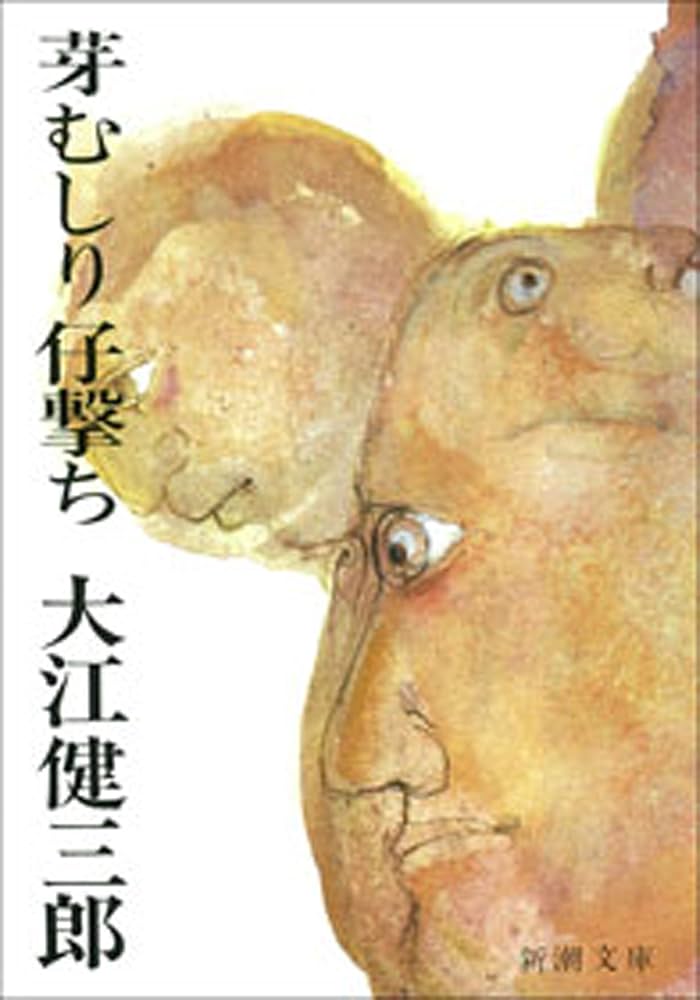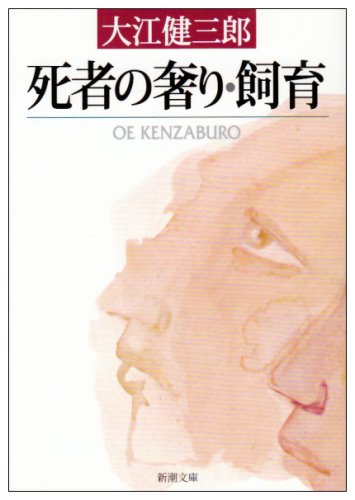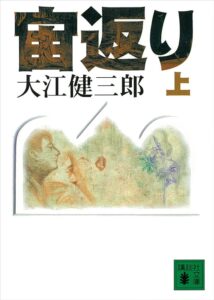 小説「宙返り」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。本作は、ノーベル文学賞作家である大江健三郎さんが、一度「最後の小説」と宣言した後に沈黙を破って発表した、まさに渾身の大作です。物語のスケールは非常に大きく、読者の魂を激しく揺さぶる力を持っています。
小説「宙返り」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。本作は、ノーベル文学賞作家である大江健三郎さんが、一度「最後の小説」と宣言した後に沈黙を破って発表した、まさに渾身の大作です。物語のスケールは非常に大きく、読者の魂を激しく揺さぶる力を持っています。
この物語は、かつて巨大な影響力を持ちながら、ある事件をきっかけに自らの教えを全否定するという前代未聞の「宙返り」を行った新興宗教団体が、10年の時を経て再起を図るところから始まります。『宙返り』という作品は、単なる教団の再生の物語ではありません。そこには、信仰とは何か、魂の救済は可能なのか、そして絶望の淵から人はどう立ち上がるのかという、普遍的で根源的な問いが投げかけられています。
この記事では、まず物語の骨格となるあらすじを追い、その後で物語の核心に触れるネタバレを含んだ深い感想を述べていきます。なぜ彼らは「宙返り」し、そして再び歩み始めたのか。その先に待ち受ける運命とはどのようなものだったのか。『宙返り』が描き出す、人間の魂の軌跡を一緒にたどっていきたいと思います。
大江健三郎さんの作品に初めて触れる方にも、長年の愛読者の方にも、『宙返り』という作品の持つ圧倒的な熱量と深い思索を感じていただけるはずです。複雑に絡み合う登場人物たちの運命と、その結末に待ち受ける衝撃を、ぜひ見届けてください。
「宙返り」のあらすじ
物語は、かつてカリスマ的な指導者として多くの信者を率いた「師匠」と、その言葉を翻訳し伝える「案内人」が、10年の沈黙を破り活動を再開するところから始まります。彼らの教団は10年前、内部の急進派による無差別テロ計画を阻止するため、「教えはすべて冗談だった」と宣言し、自らを全否定する「宙返り」を行いました。この衝撃的な事件の後、彼らは表舞台から姿を消していました。
アメリカで美術を教えていた初老の画家・木津は、癌の治療のため日本に帰国します。そこで彼は、少年時代に鮮烈な印象を受けた謎の多い美青年・育男と運命的な再会を果たします。時を同じくして再起を決意した「師匠」と「案内人」のもとへ、木津と育男、そして「師匠」の秘書である「踊り子」といった人々が、不思議な縁に導かれるように集まってきます。
しかし、彼らの再出発は苦難に満ちたものでした。活動再開を宣言した直後、かつての「宙返り」を裏切りと見なす元信者によって「案内人」が拉致され、命を落としてしまうのです。大きな柱を失った教団は、絶望の淵に立たされます。残された「師匠」は、信者たちを率いて新たな拠点を求め、四国の深い森の中にある谷間の村へと移住することを決意します。
外界から隔絶されたその村で、彼らは新しい共同体の生活を始めます。しかし、そこにはかつての急進派の残党や、複雑な思いを抱える信者たちも同行していました。画家の木津は、育男の危うい魅力に惹きつけられながら、この共同体の行く末を静かに見守ります。平穏に見えた村の生活の裏で、やがて彼らの信仰と魂を根底から揺るがす、ある計画が静かに進行していくのでした。
「宙返り」の長文感想(ネタバレあり)
大江健三郎さんの『宙返り』は、読後にただならぬ余韻を残す作品です。それは、物語が内包するテーマの重厚さと、登場人物たちがたどる壮絶な運命の故でしょう。この物語は、オウム真理教事件を色濃く反映しており、信仰が持つ救済の光と、それが転じた時の暴力的な闇という、極めて現代的な問題を正面から描いています。
物語の核となるのは、タイトルにもなっている「宙返り」という行為です。信者が計画した無差別テロを阻止するため、指導者である「師匠」と「案内人」は、テレビカメラの前で自らの教えの全てを「冗談だった」と否定します。この行為は、個人の命を思想よりも重んじるというヒューマニズムの発露であり、究極の自己否定です。しかし、一度全てを投げ打った者が、再び魂の救済を語り始めることの困難さは計り知れません。
再出発の矢先に「案内人」を失うという悲劇は、言葉による救済の限界を象徴しているかのようです。言葉を紡ぎ、指針を示してきた片翼を失った教団は、より根源的な祈りの形を求め、大江作品に繰り返し登場する象徴的な場所、四国の谷間の村へと向かいます。この森閑とした土地は、外界から隔絶された聖域であると同時に、人々の内なる狂気が増幅される舞台装置でもあります。
この物語の視点人物として重要な役割を果たすのが、画家の木津です。彼は死の病を抱えながらも、教団の外部からの観察者として、冷静に、そして時に情熱的に共同体の変化を見つめます。彼が強く惹かれる青年・育男は、過去に殺人を犯しながらも、神の声を聴いたとされる聖性と罪を併せ持つ存在です。木津が育男をモデルに絵を描く行為は、芸術によって魂の本質に迫ろうとする試みであり、物語に深い奥行きを与えています。
共同体の生活が続く中で、物語は静かに、しかし確実に破局へと向かっていきます。ここからは物語の核心に触れるネタバレになりますが、この作品の真価を語る上で避けては通れません。教団内の一部の信者グループ「静かな女たち」が、集団での自決を計画していることが明らかになるのです。彼女たちは、現世での救済に行き詰まり、死による魂の昇華を求めます。
この絶望的な計画を知った「師匠」の行動こそが、この『宙返り』という物語のクライマックスであり、二度目の「宙返り」と言えるでしょう。彼は、言葉で彼女たちを説得しようと試みますが、その決意が揺るがないことを悟ります。そして、「師匠」は自らの命を犠牲にして、彼女たちの集団自決を阻止するという究極の選択をします。
彼は建物に自ら火を放ち、炎の中で命を絶ちます。一度目は「言葉」によって教団の方向転換(宙返り)を行いテロを防ぎましたが、二度目は自らの「死」という行為そのものをもって、信者たちの死を阻んだのです。この自己犠牲は、指導者としての責任の取り方として、あまりにも壮絶であり、読む者の胸に重く突き刺さります。
「師匠」の死は、絶対的な指導者に依存する信仰の危うさと、その果てにある悲劇を浮き彫りにします。しかし、大江健三郎さんは物語をそこで終わらせませんでした。当初、「師匠」の死で物語を終える予定だったのを、生き延びた者たちの姿を描くために終章を書き加えたとされています。この終章こそが、『宙返り』に救いのかすかな光をもたらしています。
「師匠」の死に呼応するように、一時は奇跡的に消滅していた木津の癌も再発し、彼は静かに死を迎えます。カリスマを失った教団は、しかし崩壊しませんでした。残された人々は、深い悲しみと混乱の中から、自分たちの足で新たな道を探り始めます。そして、村の少年たちのリーダーであったギー少年が、次世代の希望として、教団の未来を担っていくことが示唆されて物語は幕を閉じます。
この結末は、特定の指導者に依存するのではなく、共同体の中で魂や意志が世代を超えて継承されていく可能性を示しています。それは、大江健三郎さんが繰り返し描いてきた再生のテーマでもあります。『宙返り』は、信仰の持つ危険性を描きながらも、人が祈ること、共同体の中で生きようとすること自体を否定してはいません。
この小説が発表されたのは1999年。世紀末の不安な空気の中で、多くの若者が魂の救いを求めてカルト集団に惹きつけられた時代でした。『宙返り』は、そうした時代背景を背負いながら、人間の魂がどこへ向かうべきなのかを問いかけます。
この物語は、分かりやすい答えを与えてはくれません。むしろ、いくつもの重い問いを読者に投げかけ、考え込ませます。師匠の自己犠牲は本当に正しかったのか。残された者たちは真の救いを見出すことができるのか。
『宙返り』は、そうした問いと共に、私たちの心に長く留まり続けるでしょう。それは、この物語が単なるフィクションではなく、現代を生きる私たち自身の魂の問題と深く結びついているからです。
特に、作中で描かれる登場人物たちの心理は、非常に複雑で多面的です。彼らは決して単純な善悪で割り切れる存在ではなく、誰もが内に矛盾や弱さ、そして破壊的な衝動を抱えています。その人間描写の深さこそ、大江文学の真骨頂と言えるでしょう。
また、文章の持つ独特の熱量と密度も特筆すべき点です。決して読みやすい文体とは言えないかもしれません。しかし、そのゴツゴツとした手触りの文章だからこそ、描かれる世界の深刻さや、登場人物たちの魂の叫びがダイレクトに伝わってきます。
『宙返り』という作品は、まさに読書という行為が一種の格闘であることを思い出させてくれます。読み進めるにはエネルギーが必要ですが、読了後には、その苦労に値するだけの深い思索と感動が待っています。
魂の救済という、あまりにも大きく、そして困難なテーマに、文学という手法で真っ向から挑んだ『宙返り』。この作品は、大江健三郎さんの作家としての誠実さと執念が結晶した、記念碑的な大作であると断言できます。ネタバレを知った上で再読することで、さらに多くの発見があるに違いありません。
まとめ:「宙返り」のあらすじ・ネタバレ・長文感想
この記事では、大江健三郎さんの長編小説『宙返り』について、物語のあらすじと、核心部分のネタバレを含む長文の感想を述べてきました。本作は、一度自らの教えを全否定した新興宗教団体が、10年の時を経て再生しようとするも、さらなる悲劇に見舞われるという壮大な物語です。
物語の序盤では、指導者である「師匠」と「案内人」の再出発と、そこに集う人々の人間模様が描かれます。しかし、「案内人」の死をきっかけに、教団は四国の森深くへと拠点を移し、物語はより深刻な局面へと向かっていきます。そこで待ち受けるのは、一部の信者による集団自決計画という、あまりにも衝撃的な展開でした。
感想の部分では、この物語のクライマックスである「師匠」の自己犠牲の意味について深く掘り下げました。言葉による「宙返り」の次に、自らの死という行為をもって信者を救おうとした「師匠」の選択は、信仰や救済とは何かを読者に鋭く問いかけます。ネタバレになりましたが、この結末こそが『宙返り』の魂と言えるでしょう。
指導者を失いながらも、残された人々が未来へと歩みだすラストシーンは、かすかな希望を感じさせます。魂の救済という困難なテーマに挑んだ『宙返り』は、読む者に深い思索を促す、忘れがたい読書体験を与えてくれるはずです。