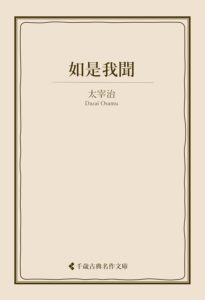 小説「如是我聞」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「如是我聞」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
太宰治が最晩年に発表した『如是我聞』は、痛烈な文壇批判が込められた随筆です。雑誌「新潮」に連載されましたが、太宰自身の死によって第四回で未完となってしまいました。その内容は、当時の文壇の重鎮や評論家、さらには彼らを盲信する読者に対する、容赦のない言葉で満ちています。
一見すると、個人的な恨みつらみや悪口のようにも読めてしまうかもしれません。特に、名指しで批判されている志賀直哉との確執はよく知られています。しかし、太宰自身はこの文章を単なる八つ当たりではなく、「小論」であると述べています。そこには、彼の文学に対する真摯な、そして切実な思いが込められているのです。
この記事では、『如是我聞』で太宰が何を訴えようとしていたのか、その核心に迫ってみたいと思います。単なるスキャンダラスな暴露話としてではなく、太宰治という作家の文学観、そして人間観を深く理解するための一助となれば幸いです。作品の核心に触れる部分もありますので、その点をご理解の上、読み進めていただければと思います。
小説「如是我聞」のあらすじ
『如是我聞』は、太宰治が1948年に発表した、彼の最後の随筆作品となります。その題名は「かくのごとく、我聞けり」という意味の仏教用語から取られており、お釈迦様の教えを弟子が伝える際の決まり文句です。これは、太宰がこれから語ることが、自身の揺るぎない信念に基づくものであるという宣言のようにも受け取れます。
作品の冒頭で太宰は、「攻撃すべきは、あの者たちの神だ」と記します。個人への攻撃ではなく、相手が信奉する価値観、その「神」を撃つべきだと。これは、彼がこれから展開する批判が、単なる感情的なものではなく、思想や文学観に基づいたものであることを示唆しています。
太宰の批判の矛先は、主に「文壇の老大家」と呼ばれる人々、彼らを無批判に称賛する学者や読者、そして旧弊を打破する勇気のない若手作家たちに向けられます。彼は、これらの人々が持つ権威主義的な態度や、上から目線での物言いを痛烈に批判し、「民主革命」の必要性を訴えます。「人間は人間に服従しない」という民主主義の根本精神に立ち返るべきだと主張するのです。
特に槍玉に挙げられるのが、志賀直哉をはじめとする「老大家」です。太宰は彼らの作品や言動を具体的に取り上げ、その欺瞞性を暴こうとします。例えば、彼らが自身の強さを誇示し、弱さを軽蔑する一方で、内面の軽薄さや醜さを巧みに隠蔽していると指摘します。また、過去の過ちを認めずに権威の座に居座り続けようとする姿勢も、厳しく批判されます。
太宰は、ある老大家の小説の一節を引用し、「この作品には、この少年工に対するシンパシーが少しも現われていない」と断じます。表面的な描写はあっても、描かれる対象への真の共感、共に苦しむような気持ちが欠けていると批判するのです。これは、太宰が考える文学の核心に触れる部分であり、彼が自身の文学で何を追求しようとしていたのかを理解する上で非常に重要です。
結局、『如是我聞』は、太宰が理想とする文学のあり方を、既存の文壇へのアンチテーゼとして提示しようとした試みであったと言えるでしょう。それは、権威や体面ではなく、人間の弱さや苦悩に寄り添い、真の「共感(シンパシー)」をもって描く文学への強い希求でした。しかし、その思いをすべて吐き出す前に、太宰はこの世を去り、作品は未完のまま残されることになったのです。
小説「如是我聞」の長文感想(ネタバレあり)
太宰治の『如是我聞』を読むと、彼の魂の叫びのようなものが聞こえてくる気がします。単なる文壇ゴシップとして片付けるには、あまりにも切実で、痛々しいほどのエネルギーに満ちています。ここには、太宰が命を懸けて守ろうとした文学の姿、そして彼自身の生き様が色濃く反映されているように感じられます。
太宰がこれほどまでに激しく「老大家」たちを批判する背景には、彼が理想とする小説家像との決定的な断絶があったのでしょう。彼は、老大家たちが「自分の強さを誇り、自分の中の軽薄な部分を認めようとせず、強さを美徳と考え、上に立とうとする」存在だと断じます。強い者が弱者を導く、といったような、ある種のヒエラルキーを肯定するような態度に、太宰は我慢ならなかったのだと思います。
では、太宰が目指した小説家像とはどのようなものだったのでしょうか。老大家の姿を反転させてみると、それは「自分の弱さを大切にし、自分の中の軽薄な部分を認め、弱さを美しいと思い、上から目線にならないようにする小説家」となります。これはまさに、太宰自身の作品世界に通底するテーマではないでしょうか。『人間失格』や『斜陽』といった作品で描かれる主人公たちの姿は、決して強く、立派な人間ではありません。むしろ、弱さや欠点を抱え、社会の中でうまく生きられない人々です。
太宰は、そのような「弱さ」にこそ、人間の真実があると信じていたのではないでしょうか。そして、その弱さに寄り添い、共感することこそが、文学が果たすべき役割だと考えていたのでしょう。彼が老大家の作品を評して「シンパシーが無い」と厳しく批判するのは、まさにこの点に起因します。「シンパシー(sympathy)」の語源が「共に(syn)苦しむ(pathos)」ことにあるように、太宰は、描く対象と同じ地平に立ち、その痛みや苦しみを共有しようとしました。
彼は「愛撫するかも知れぬが、愛さない」という言葉で、シンパシーの欠如した態度を表現します。これは、相手の立場に立たずに、一方的に情けをかけるような行為を指しているのでしょう。例えば、志賀直哉の『小僧の神様』では、貴族院の男が鮨を食べられない小僧に鮨をおごりますが、それはあくまで「上から」の施しであり、小僧の孤独や屈辱感を共有するものではありません。太宰にとって、それは真の「愛」ではなかったのです。
この「共に苦しむ」という姿勢を考える上で、参考文章で紹介されていた漫画『ブルーピリオド』のエピソードは非常に示唆的です。「溺れている時の息苦しさとか海の暗さは溺れた人同士でしか共有できへんねん。その人と話したかったら八虎も飛び込むしかないんやで」という言葉は、太宰の文学観を的確に言い表しているように思います。安全な場所から救命道具を投げるのではなく、自らも冷たい海に飛び込み、相手と同じ苦しみを体験しようとすること。それが太宰の考える「共感」であり、彼の文学の根幹をなすものだったのではないでしょうか。
太宰は、自身の作品『斜陽』を読んだ宮様の感想として、「身につまされるから」という言葉を紹介し、「それで、いいじゃないか」と肯定します。読者が作品に触れて、教訓を得たり、襟を正したりするのではなく、「わかる」「自分のことだ」と感じること。それこそが、太宰が文学に求めた最も大切な価値だったのかもしれません。上から教え諭すのではなく、読者と同じ目線に立ち、その孤独や不安に寄り添うこと。それが、苦しい時代を生きる人々にとって、何よりの慰めになると信じていたのでしょう。
しかし、このような「弱さへの共感」を徹底しようとすることは、作家自身にとって大きな負担を強いることにもなります。『如是我聞』の中で、太宰は繰り返し「自分の作品に文句を言わないでほしい」と訴えています。彼は、他者からの批判に対して非常に脆く、傷つきやすい側面を持っていました。これは、彼が常に「上」に立つのではなく、弱い者と同じ地平に身を置いていたことの裏返しなのかもしれません。絶対的な自信を持つことができず、他者の評価に一喜一憂してしまう。
また、他者の苦しみに深く共感することは、自身の精神をも蝕んでいく可能性があります。共に苦しむということは、相手の痛みを自分の痛みとして引き受けることでもあります。太宰の作品に漂う切迫感や、時折見せる自虐的な態度は、このような共感の苦しみと無縁ではないように思えます。
平林たい子は、太宰の死後に寄せた追悼文『脆弱な花』の中で、太宰の文学を「薄い脆い電球」に喩えました。それは、決して煌々とした強い光ではなく、儚く、壊れやすい、しかし確かに存在する光です。この表現は、『如是我聞』で示された太宰の文学観、そして彼自身の姿を見事に捉えていると感じます。
人間は誰しも、弱く、脆い存在です。それでも、かすかな光を頼りに生きていかなければなりません。太宰は、その人間の弱さ、脆さの中に美しさを見出し、同じように弱く脆い存在として、読者の隣に立とうとしたのではないでしょうか。上から手を差し伸べるのではなく、隣で共に震え、痛みを分かち合おうとする。それが太宰の「心づくし」であり、彼の文学が今なお多くの人々の心を捉えて離さない理由なのかもしれません。
『如是我聞』は、太宰治という作家の、文学に対する純粋で、不器用で、そしてあまりにも痛切な遺言であると言えるでしょう。その激しい言葉の奥にある、彼の深い苦悩と、人間への尽きせぬ愛情に思いを馳せる時、私たちは改めて太宰文学の核心に触れることができるのかもしれません。この作品を読むことは、決して楽しい経験ではないかもしれませんが、太宰治という稀有な作家を理解する上で、避けては通れない道程なのだと思います。
まとめ
太宰治の『如是我聞』は、彼の最晩年の、そして未完の随筆として知られています。一読すると、当時の文壇に対する激しい怒りや悪口が並んでいるように見え、特に志賀直哉への批判が目立ちます。しかし、これを単なる個人的な攻撃と捉えるのは早計かもしれません。
太宰自身が「小論」と位置付けているように、ここには彼の文学に対する真剣な考え方が表明されています。彼は、権威を振りかざし、上から目線で人々を断じるような文学を嫌い、人間の弱さや苦しみに寄り添い、深く「共感(シンパシー)」することこそが文学の本質だと考えていた節があります。
参考文章でも触れられていた平林たい子の「脆弱な花」という追悼文は、太宰の文学の本質をよく表しています。彼の文学は、強い光ではなく、儚く脆い電球のような光かもしれません。しかし、そのかすかな光は、同じように弱く脆い人間の心に寄り添い、慰めを与えてくれます。共に悩み、苦しむ姿勢こそが、太宰文学の核心なのでしょう。
『如是我聞』を読むことは、太宰治の文学観、そして彼の苦悩に満ちた魂に触れる経験となるはずです。激しい言葉の裏にある、彼の深い人間愛と文学への情熱を感じ取っていただければと思います。




























































