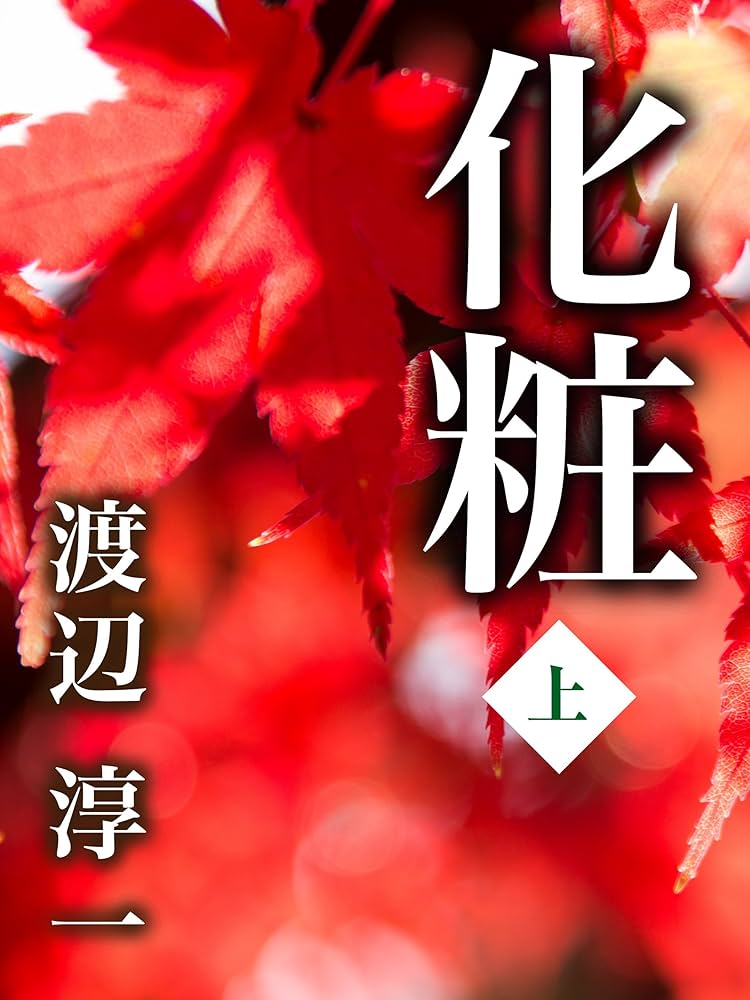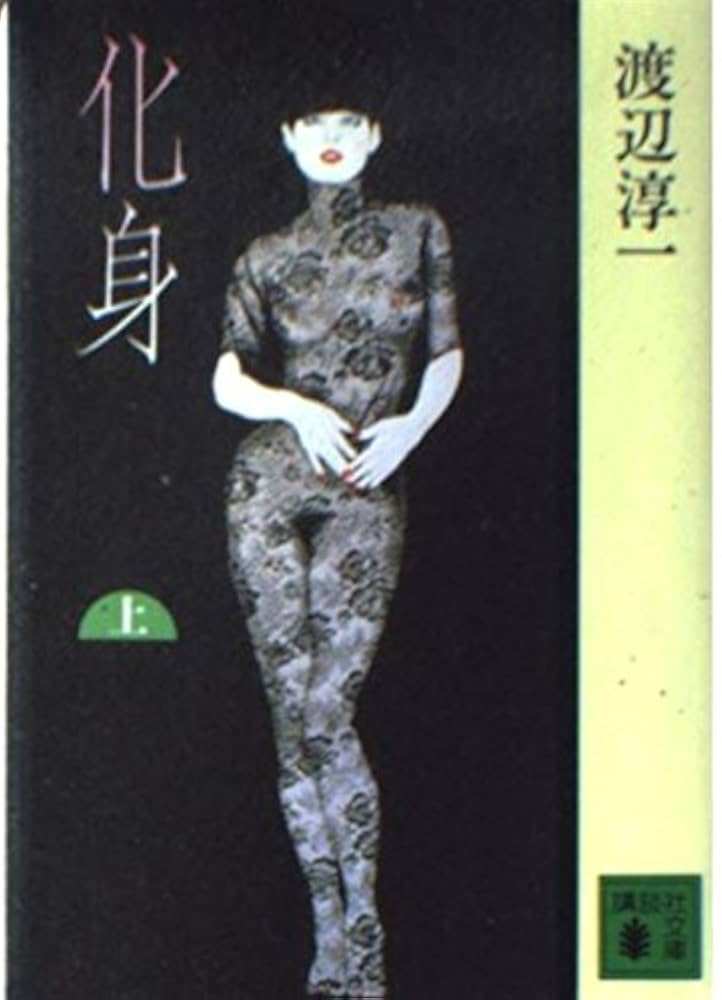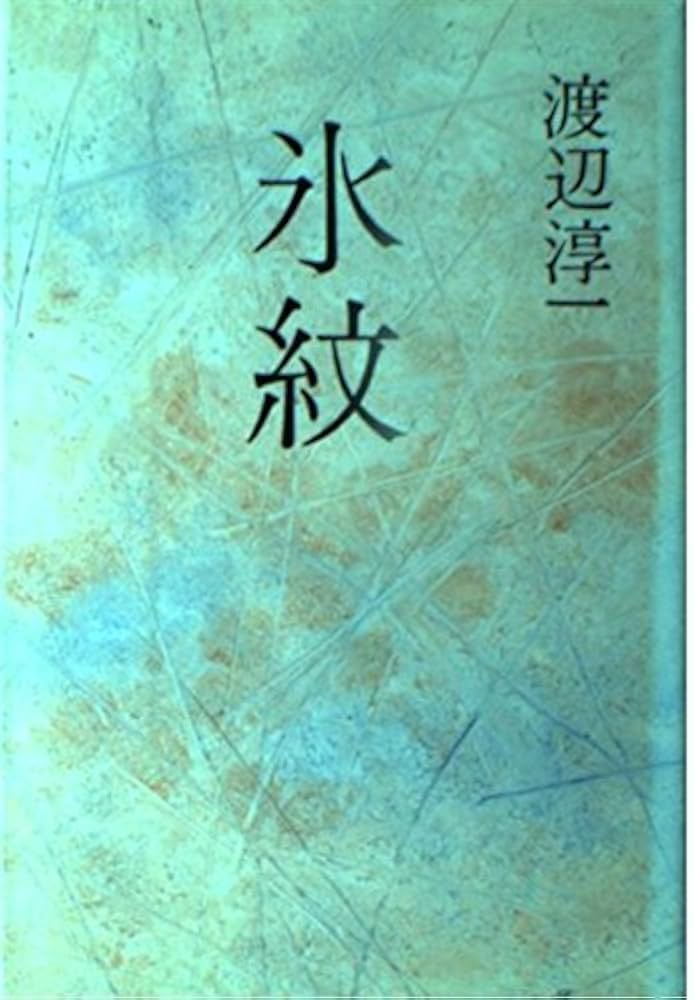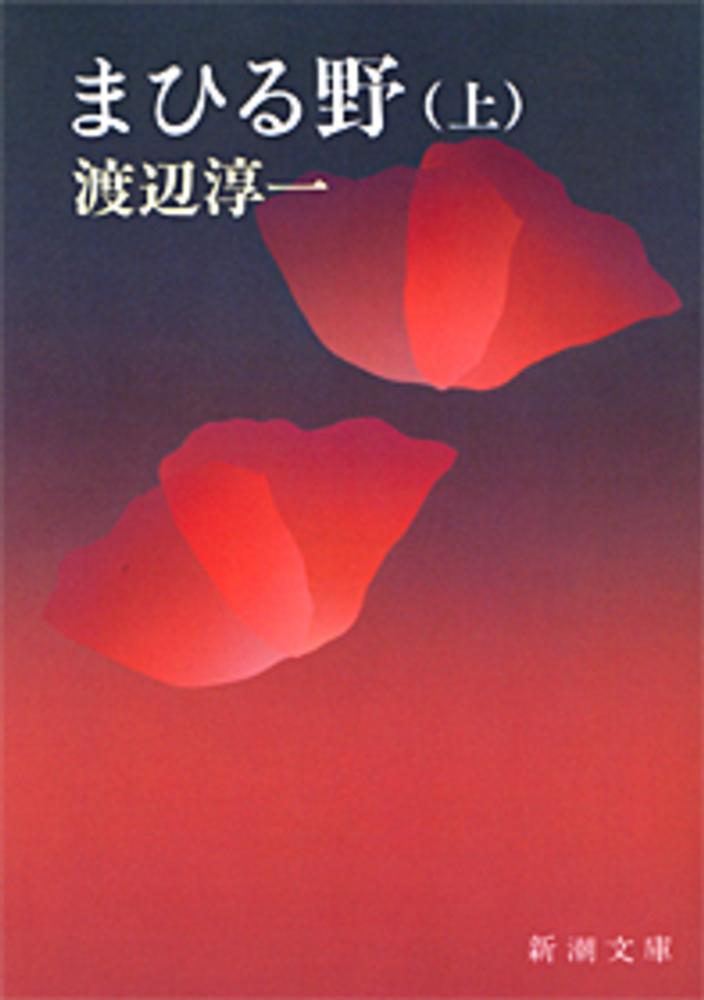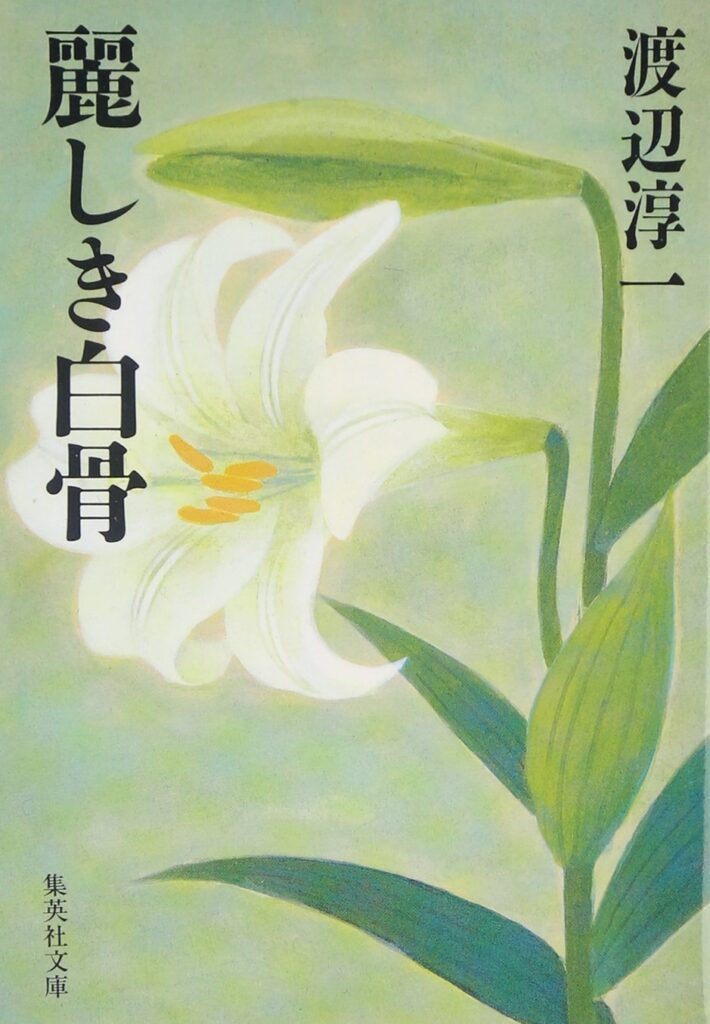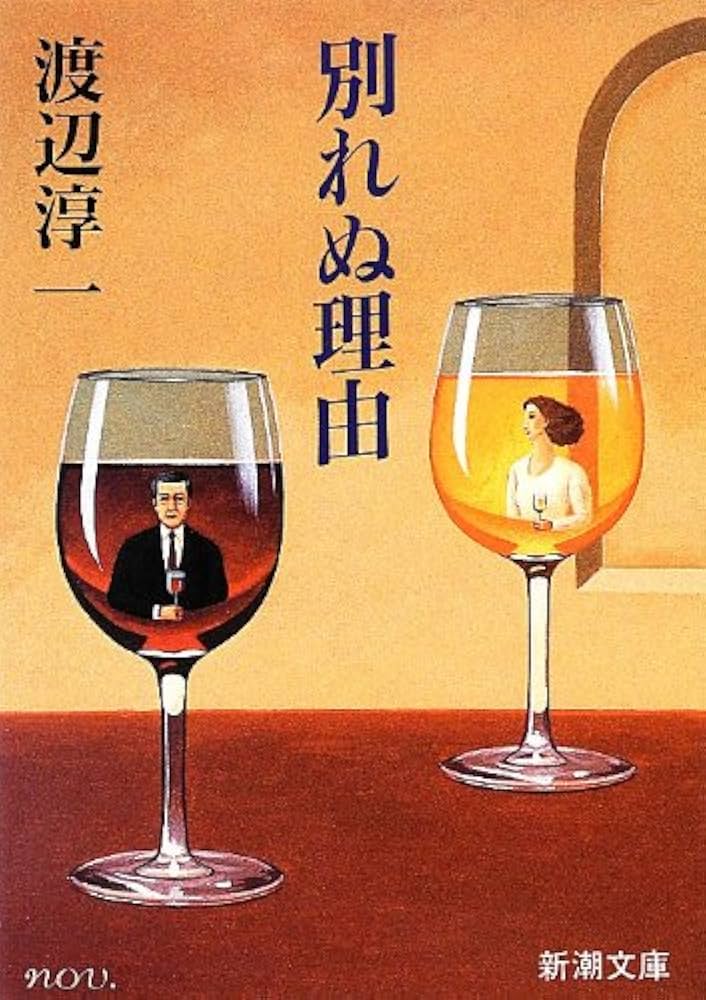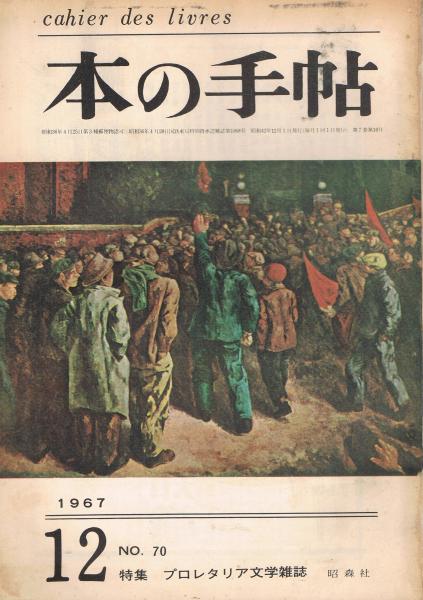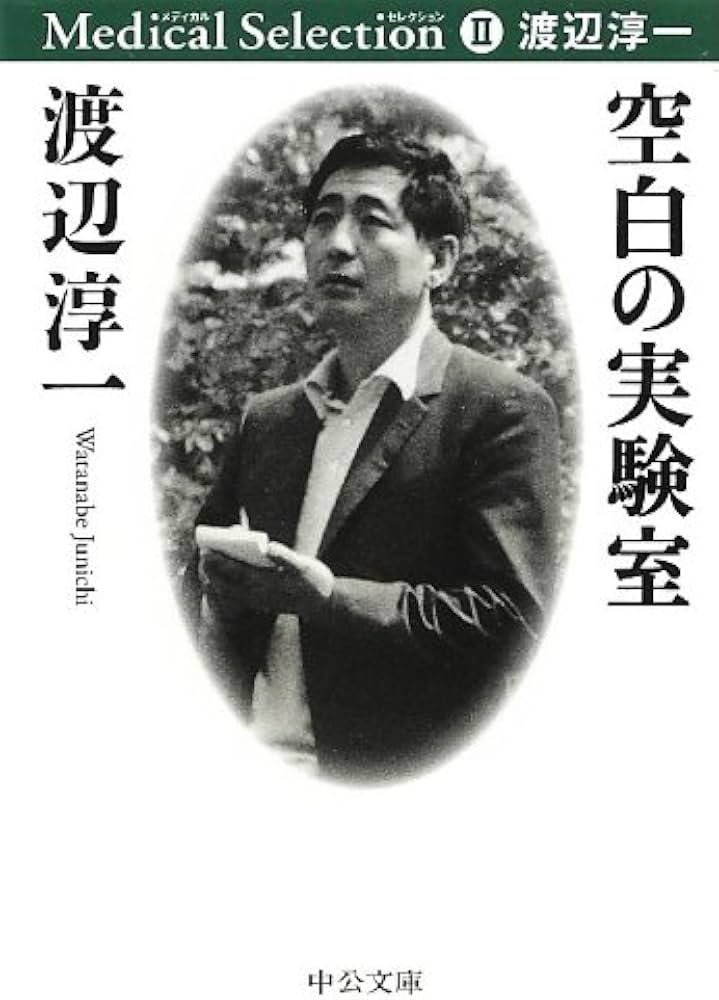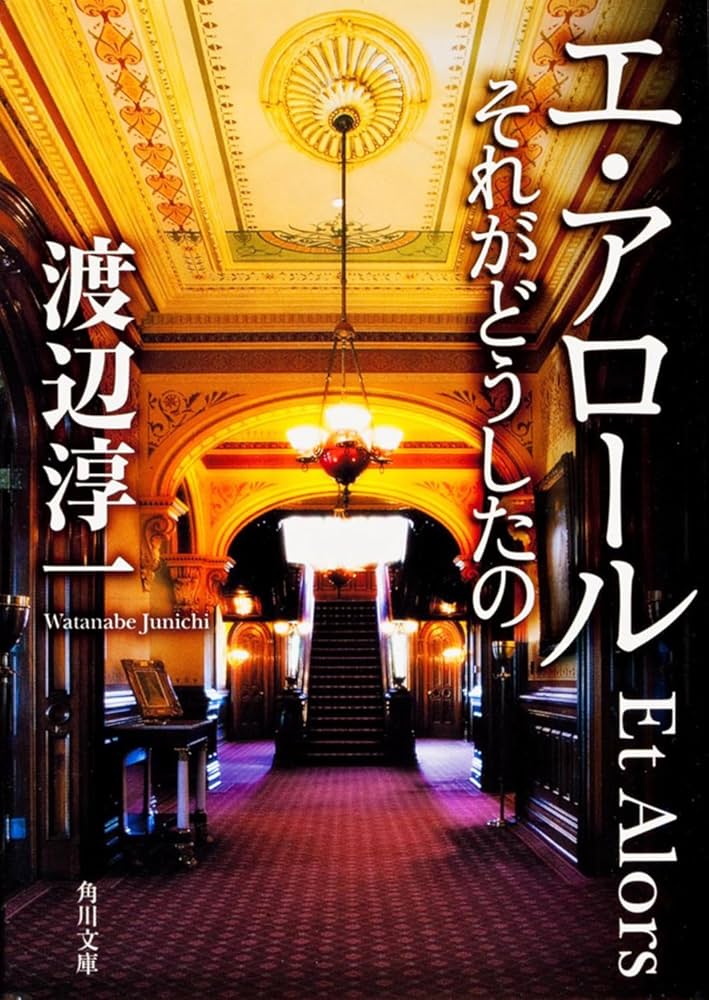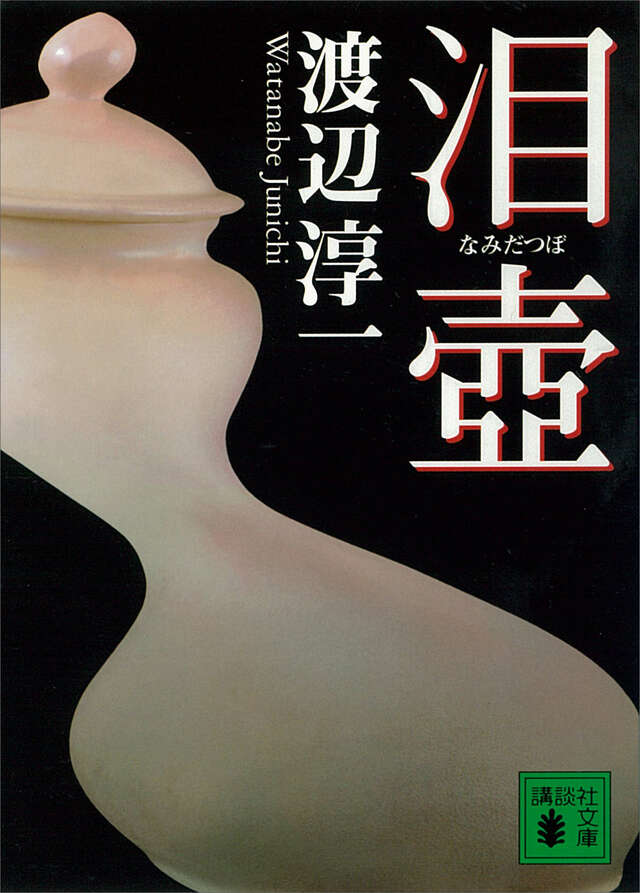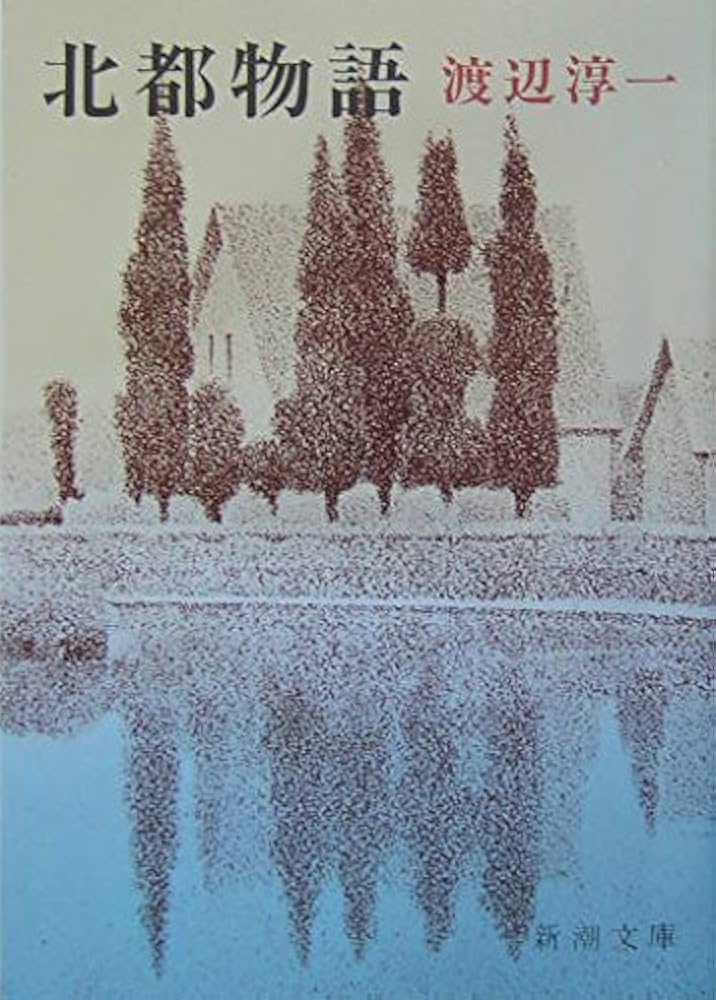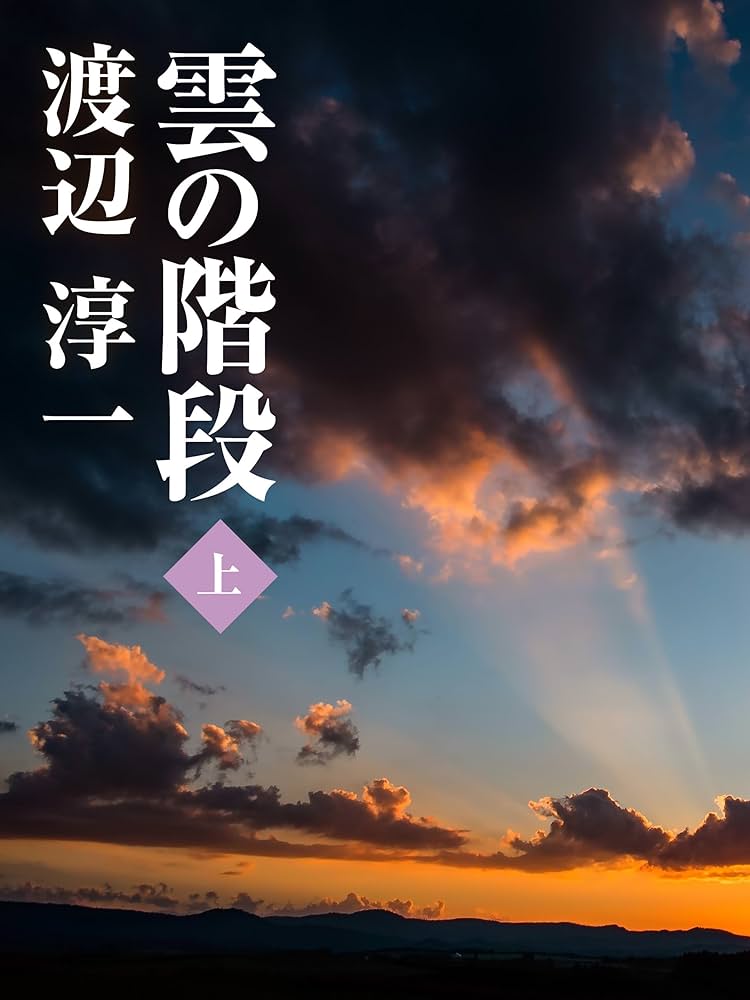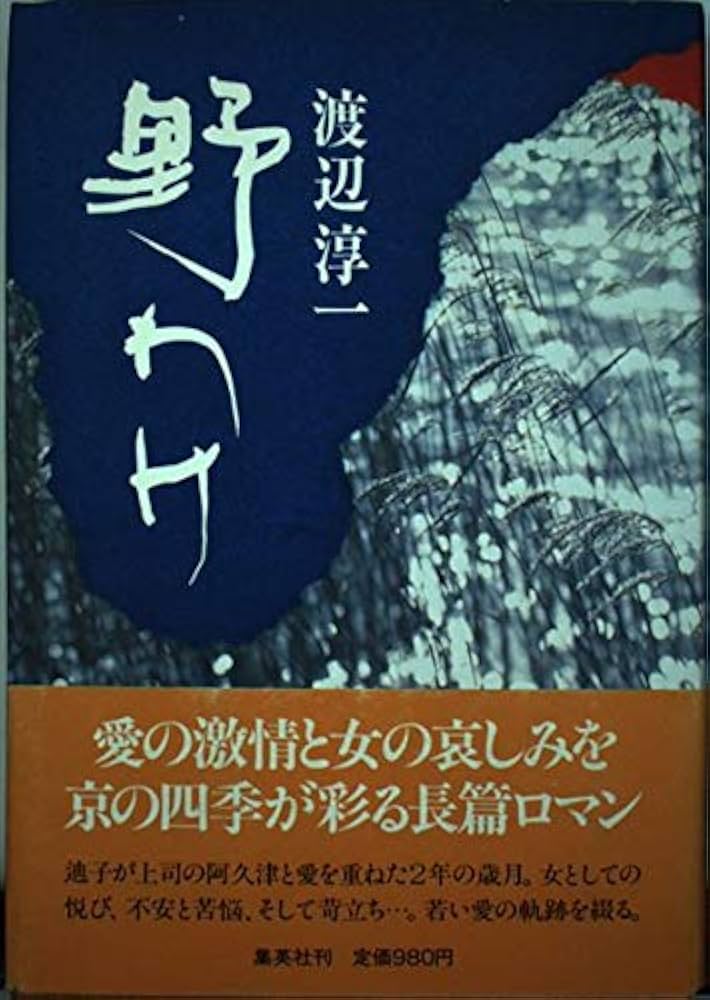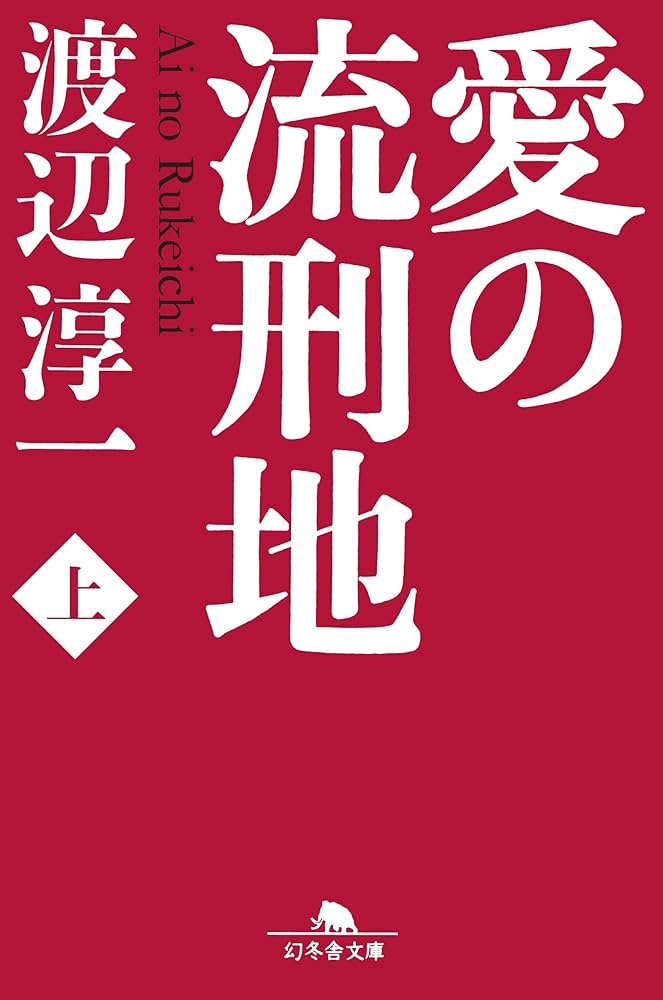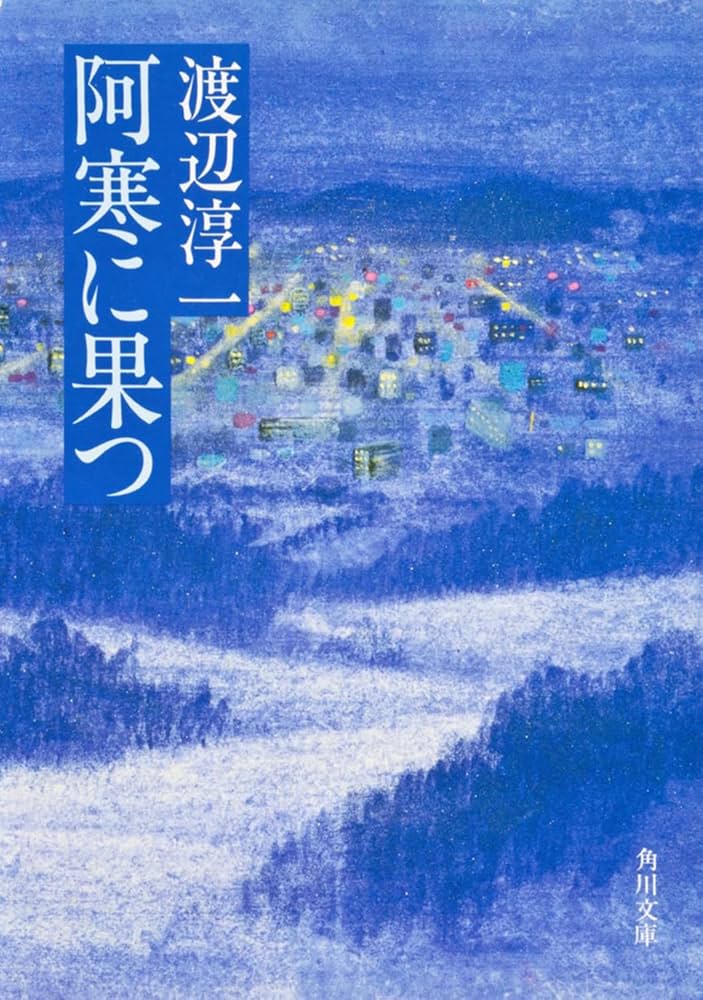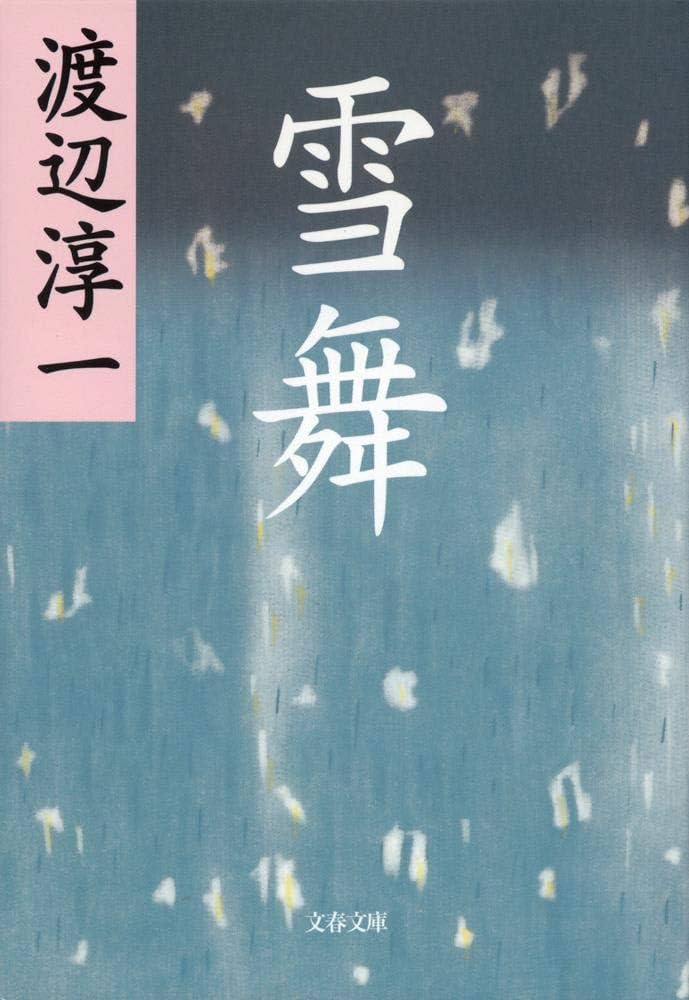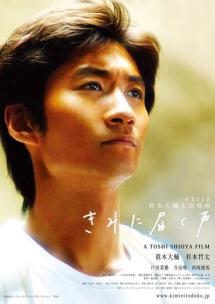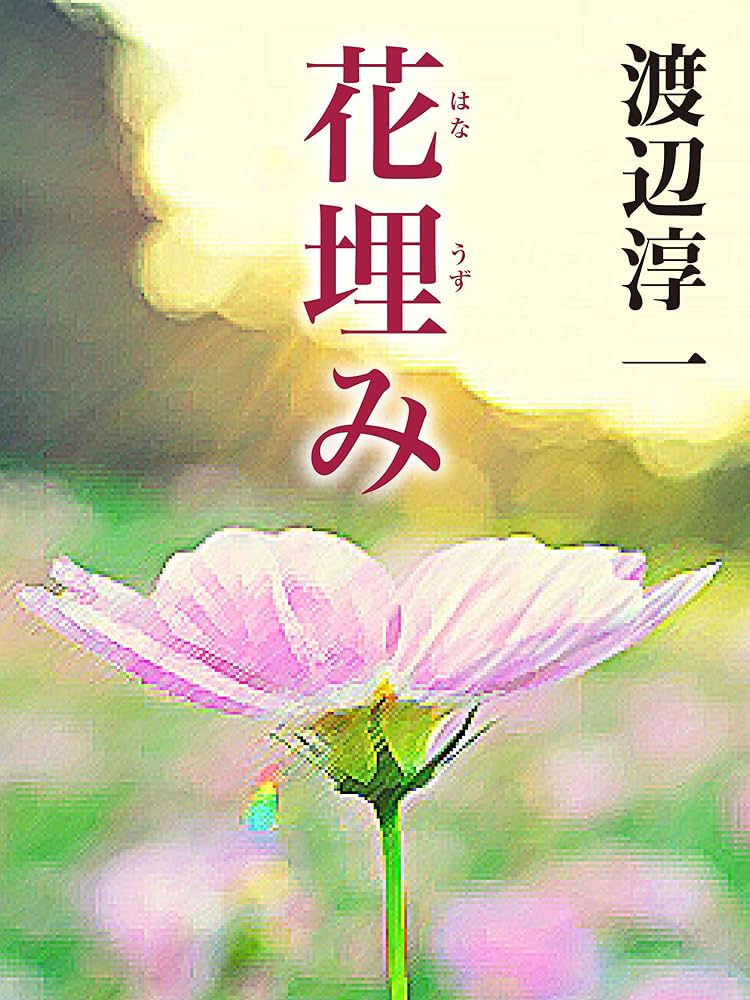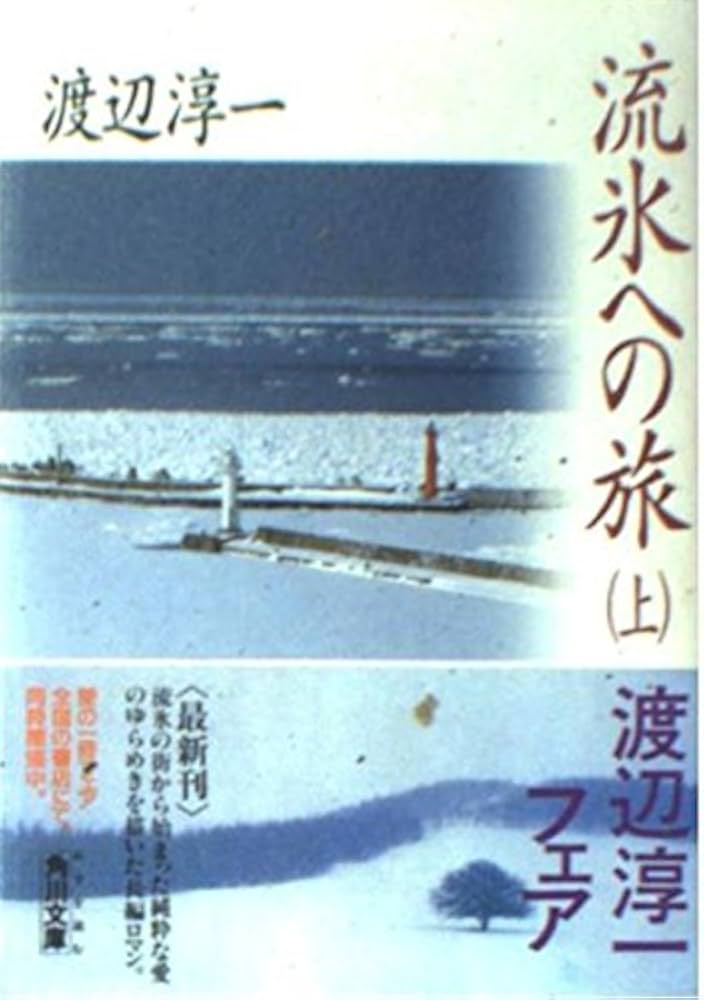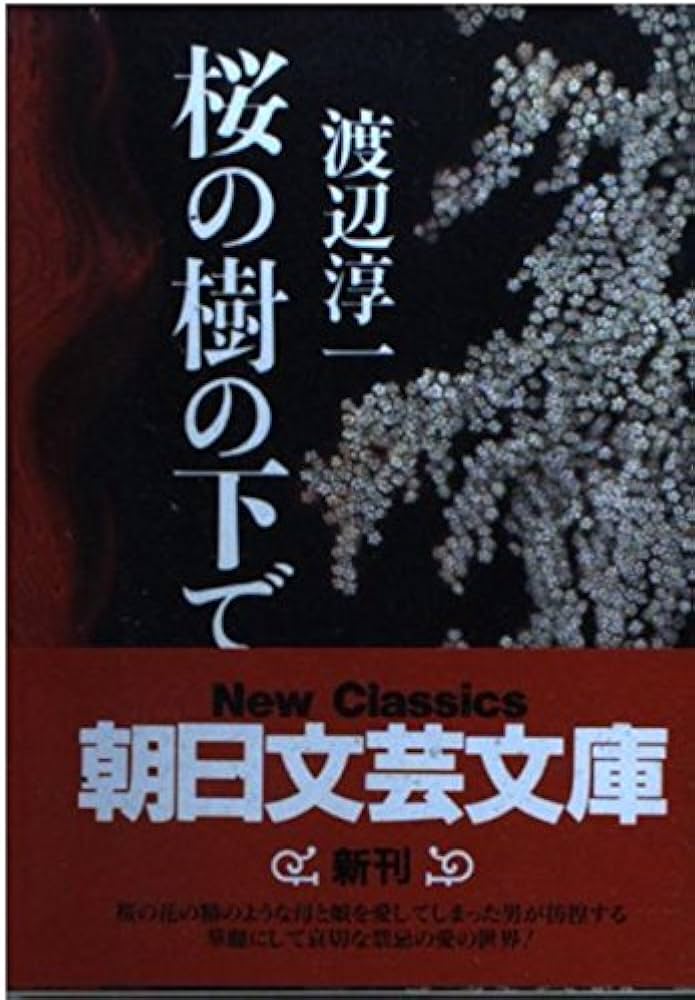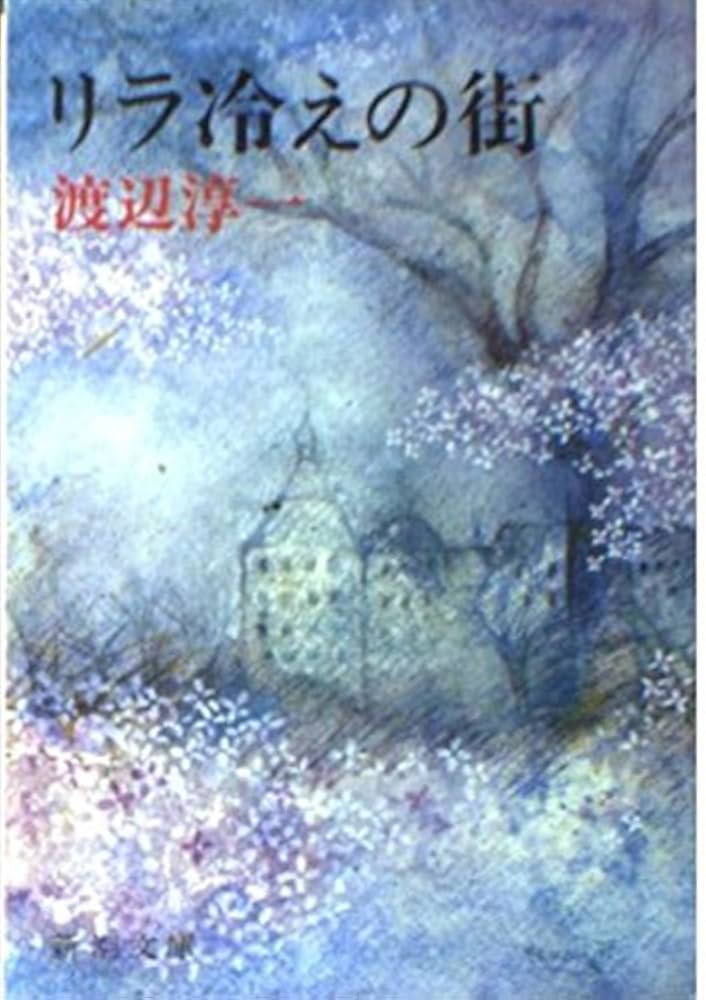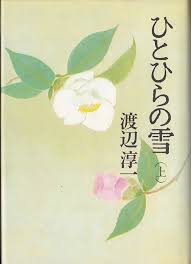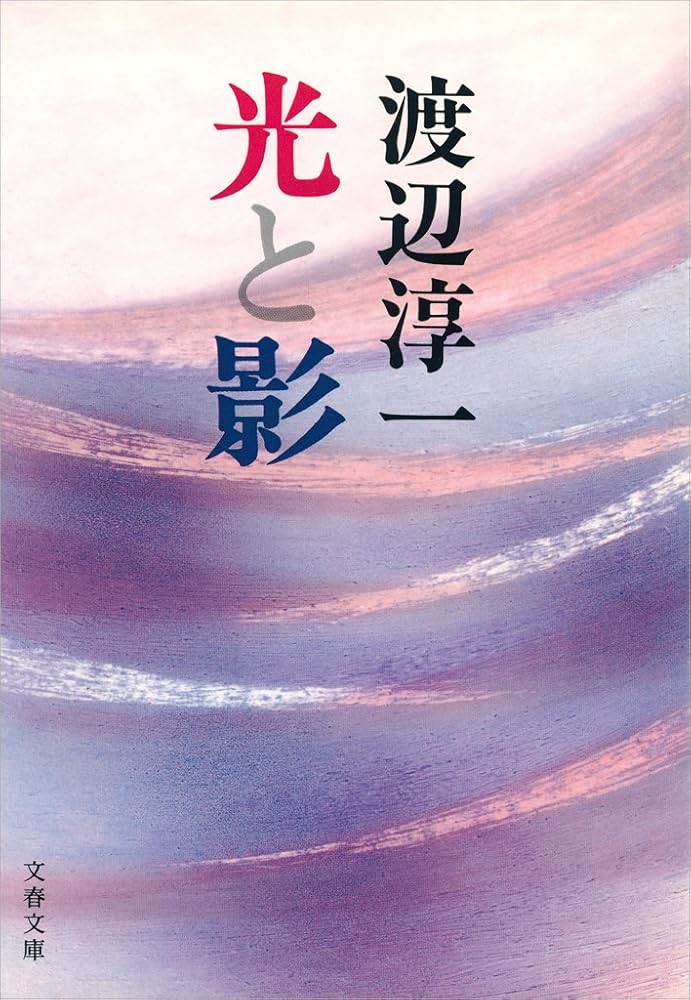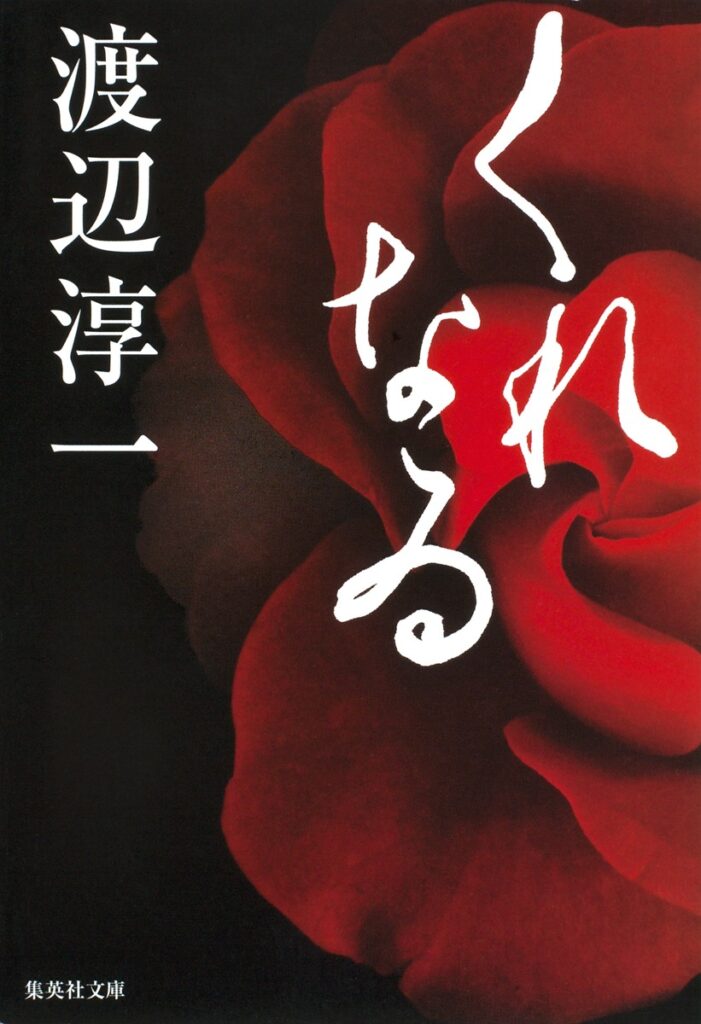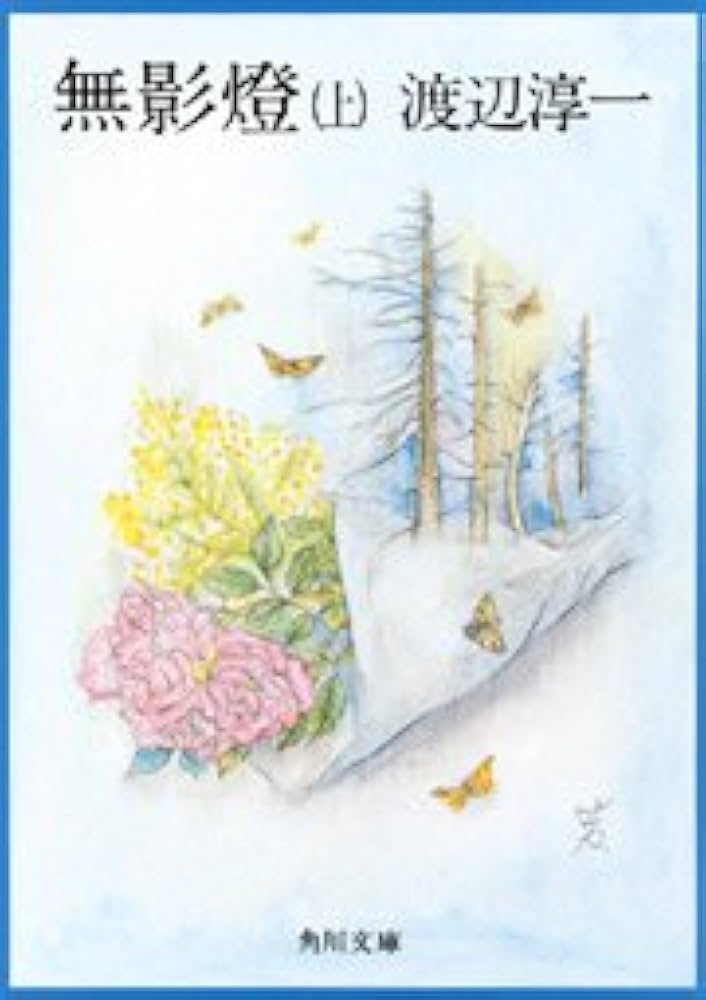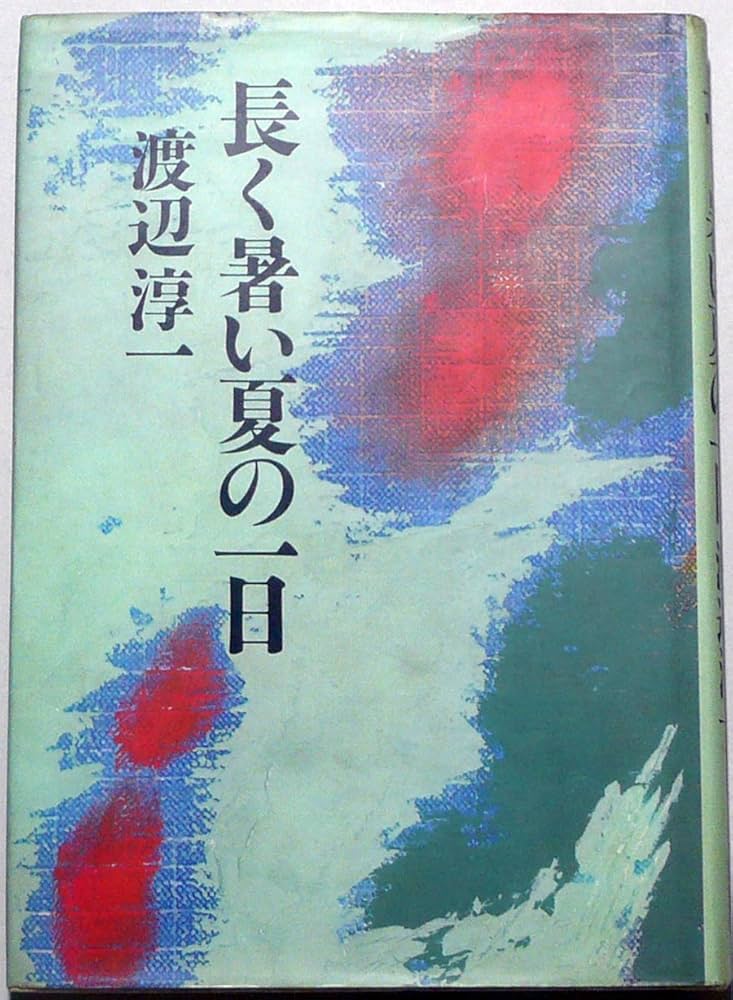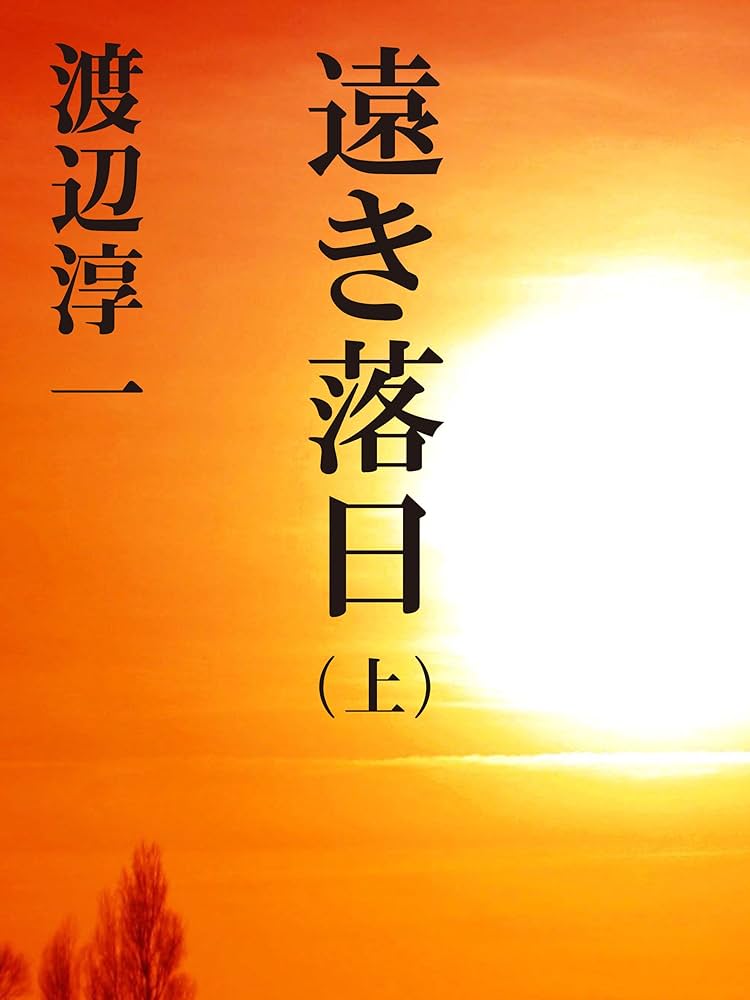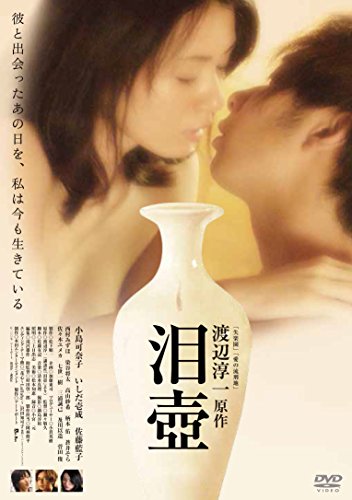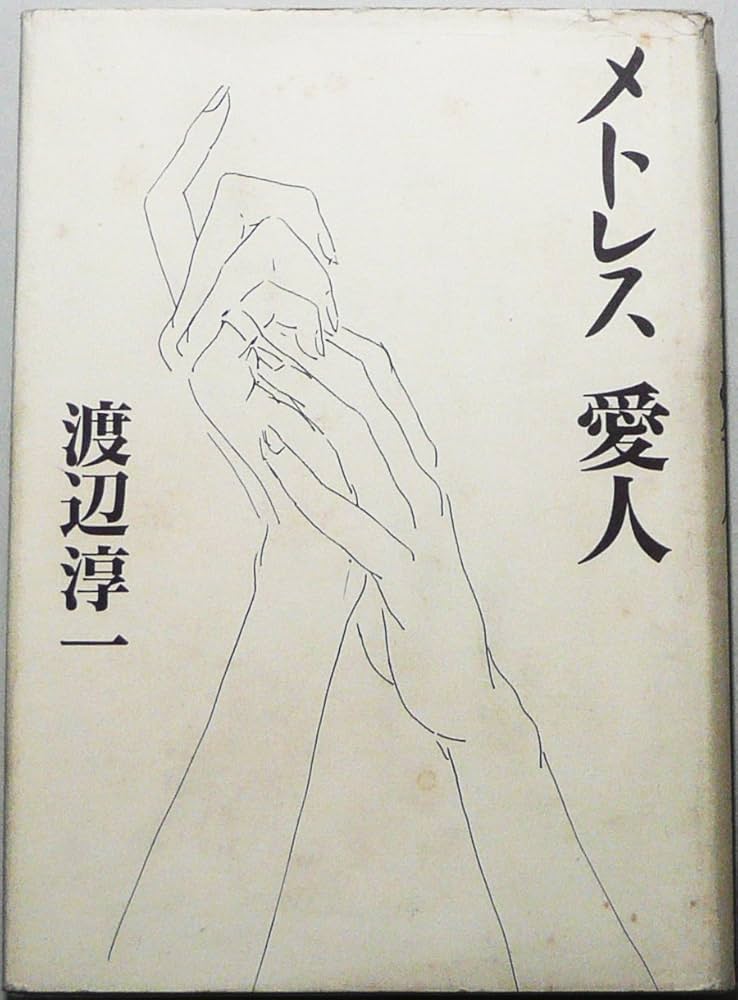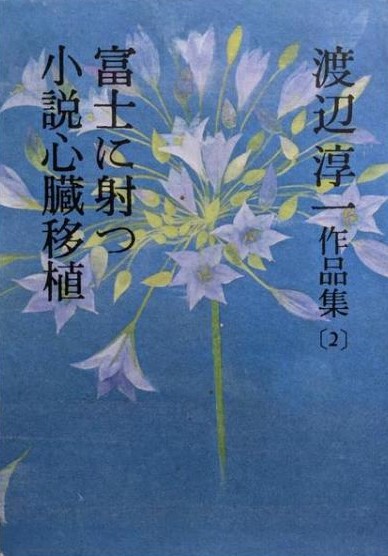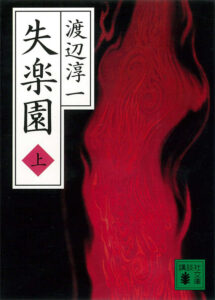 小説「失楽園」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「失楽園」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
渡辺淳一氏によって紡がれたこの物語は、1990年代の日本に大きな衝撃を与え、社会現象にまでなりました。単なる不倫小説という言葉では到底括ることのできない、人間の愛と性の根源、そして生と死の境界線にまで踏み込んだ作品です。一度読み始めれば、その濃密な世界観に引き込まれ、最後まで目が離せなくなるでしょう。
この記事では、まず物語の筋道を追いかけ、登場人物たちがどのような運命を辿るのかを見ていきます。その後、物語の核心に触れる考察を、私の思いを交えながら詳しくお話しさせていただきます。特に後半では、物語の結末に深く言及しますので、まだ結末を知りたくないという方はご注意ください。
なぜ二人は、社会的な地位も家庭もすべてを捨ててまで、愛の道を選んだのでしょうか。そして、その道の果てに何を見出したのでしょうか。この物語が、刊行から長い年月を経てもなお、多くの人々の心を捉えて離さない理由を、一緒に探っていきたいと思います。
小説「失楽園」のあらすじ
出版社の編集者として働いていた久木祥一郎は、50代を迎え、仕事への情熱も家庭の安らぎも失い、空虚な日々を送っていました。妻の文枝との関係は冷え切り、会話も途絶えがち。そんな彼の前に現れたのが、書道講師の松原凛子でした。彼女もまた、医師である夫・晴彦との間に深い溝を感じ、満たされない心を抱えていました。
知人の紹介で出会った二人は、互いの心の渇きを潤すかのように、瞬く間に惹かれ合います。鎌倉のホテルでの密会から始まった二人の関係は、次第に熱を帯びていきます。世間の目を忍ぶ逢瀬は、背徳的でありながらも、彼らにとっては何ものにも代えがたい、生きている実感を取り戻すための時間となっていきました。
やがて久木は、二人だけの世界を築くために都内にマンションを借ります。そこは、社会のしがらみから解放された、二人だけの「楽園」でした。しかし、その禁断の愛が深まれば深まるほど、彼らの周囲の世界は静かに、しかし確実に崩壊を始めます。二人の関係は家族の知るところとなり、彼らは徐々に社会的な居場所を失っていくのです。
すべてを失う覚悟で愛に生きることを選んだ久木と凛子。しかし、その選択は彼らを周囲から完全に孤立させていきます。社会的な制裁、家族との断絶。逃げ場を失い、二人だけの世界に閉じこめられていく中で、彼らが迎える運命とはどのようなものだったのでしょうか。物語は、愛の純粋さと狂気が交錯する、衝撃的な領域へと読者を導いていきます。
小説「失楽園」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、小説「失楽園」の結末に触れながら、私がこの物語を読んで感じたこと、考えたことを詳しくお話しさせていただきます。この作品が問いかけるテーマは非常に深く、読む者の心に重い問いを投げかけてきます。
まず、主人公である久木祥一郎という男性について触れないわけにはいきません。彼は50代前半、かつては仕事のできる編集者でしたが、今は閑職に追いやられています。家庭では妻との関係も冷え切り、娘は独立。一見、何不自由ない生活に見えますが、その内実は生きる目的を見失った深い空虚感に支配されています。彼が感じていたのは、いわば「緩やかな死」とでも呼ぶべき状態だったのではないでしょうか。
一方の松原凛子は38歳の書道講師。貞淑で落ち着いた佇まいから「楷書の君」と呼ばれていますが、その仮面の下では、満たされない想いが渦巻いていました。医師の夫は冷淡で、彼女の心と体は「持て余されて」いる状態。彼女の中には、日常からの逸脱への強い憧れと、愛と死を結びつける独特の感性が秘められていました。
この二人の出会いは、偶然のようでいて、実は必然だったのかもしれません。互いが抱える欠落を、相手の中に見出したのです。久木は失いかけた男としての自信を、凛子は与えられることのなかった情熱的な愛を。二人の関係は、それぞれの虚無から逃れるための、唯一の救済策として始まったように私には思えます。
物語の中で、二人の関係は急速に深化していきます。単なる密会から、久木が渋谷にマンションを借りることで、彼らの関係は一過性のものではなく、恒久的な二人だけの「聖域」を創造する段階へと移行します。この部屋は、社会から隔絶されたエデンの園であり、彼らの愛を育むための閉鎖された世界でした。
この物語の核心部分を占めるのが、非常に濃密に描かれる性愛の場面です。これは単なる官能的な描写に留まりません。作者はしばしば、久木を「男」、凛子を「女」と記します。これにより、二人の行為は個人的な情事を超え、もっと根源的で普遍的な男女のドラマへと昇華されているのです。
凛子にとって、この関係は自己発見と解放の旅でした。これまで抑圧してきた自らの肉体の可能性に目覚め、快楽の探求者へと変貌していきます。久木もまた、彼女との交わりを通して、失われた若さと生命力を取り戻そうとします。しかし、関係が深まるにつれ、二人の力関係は少しずつ変化していくのが興味深い点です。
当初は経験豊富な久木が主導権を握っていましたが、凛子は次第に能動的になり、倒錯的ともいえる行為を求めるようになります。彼女はもはや、愛の受動的な享受者ではありません。二人だけの世界の、積極的な創造主となっていくのです。物語を仕掛けたのは久木でしたが、いつしか彼は、凛子という存在が放つ強烈な引力から逃れられなくなっていきます。
二人の関係が後戻りできない領域に入ったことを象徴するのが、凛子の継父の通夜の夜の密会です。喪服のまま家族のもとを抜け出し、久木と会うという行為は、社会的・道徳的な規範からの完全な決別を意味します。この背徳感こそが、皮肉にも二人の絆をさらに強固なものにしていくのです。この時点で、彼らはもう、元の世界に帰る橋を自ら焼き払ってしまいました。
当然ながら、その代償は大きなものでした。久木の妻・文枝は、ヒステリックになることなく、静かに、しかしきっぱりと離婚を突きつけます。彼女の冷静さは、情熱に溺れる二人との対比を際立たせ、彼らのいる世界がいかに常軌を逸しているかを浮き彫りにします。
一方で、凛子の夫・晴彦の反応は、陰湿で計算されたものでした。彼は復讐のためにあえて離婚に応じず、匿名の告発状を久木の会社に送りつけます。この行為が、久木の社会的な生命にとどめを刺しました。会社を辞職せざるを得なくなった久木は、自らの社会的地位と過去の人生との繋がりを、完全に断ち切ることになります。
家族からも、社会からも追放された二人。特に、凛子の母親までもが彼女を「ふしだらな女」と断罪し、絶縁を言い渡す場面は痛烈です。こうして、二人は完全に孤立無援となり、互いしかいない世界へと追い込まれていきました。晴彦の残酷な復讐がなければ、あるいは違う結末があったのかもしれないと思うと、人間の悪意の恐ろしさを感じずにはいられません。
追い詰められた二人の心は、次第に「死」へと傾倒していきます。特に凛子は、かつて情死を遂げた有島武郎や、愛憎の果てに相手を殺めた阿部定の事件に強い関心を寄せます。彼女にとって、これらの事件は単なるスキャンダルではなく、愛の理想形でした。愛が最も美しく燃え上がる瞬間に、その時を永遠にするために死を選ぶ。その考えは、徐々に久木の心をも侵食していきます。
すべてを失った久木にとって、もはや生き続けることに意味は見出せません。孤独な老後を送るより、愛する凛子と共に最高の瞬間に死を迎える方が、よほど幸福な終焉に思えたのでしょう。彼はついに、凛子の死の哲学を受け入れます。そして、計画を実行するために、知人の研究室から青酸カリを盗み出すのです。この行為は、彼らがもはや引き返すことのできない、最後の決意を固めた瞬間でした。
最後の舞台として彼らが選んだのは、軽井沢の別荘でした。そこは、有島武郎が情死を遂げた場所であり、二人にとって特別な意味を持つ場所です。最後のドライブの途中、凛子が口にする「ワンウェイチケットね。パラダイスにいきましょう」というセリフが、強く印象に残ります。彼らにとって、死は逃避ではなく、自らが定義した楽園への旅立ちだったのです。
そして、物語は衝撃的なクライマックスを迎えます。別荘の一室で、二人は最後の時間を過ごします。高級ワインに青酸カリを混ぜ、それを口移しで分か-ち合い、抱き合ったまま絶命する。それは、究極の愛の儀式でした。死の瞬間、彼らは互いの名前を絶叫します。匿名的な「男」と「女」であった彼らが、個としての存在を叫び、一つになる瞬間です。
この小説が本当に恐ろしいのは、その結末の描写です。翌日発見された二人の遺体は、性的に結合したまま、死後硬直によって固く結びついていました。まさに「結合死体」。生前の彼らの願いが、死によって物理的に実現されたのです。このグロテスクでありながらも、ある種の純粋さを感じさせる光景は、読者に強烈な印象を焼き付けます。
最終章が、警察医による「死体検案調書」という無機質な形式で締めくくられる点も、本作の巧みさです。それまでの情熱的な物語が、法医学という冷徹な科学の言葉で解剖される。この温度差が、二人の愛の異様さと、その壮絶な結末をより一層際立たせているのです。彼らが残した「2人を必ず一緒に葬ってください」という遺書が、彼らの最後の願いのすべてを物語っていました。
結局のところ、「失楽園」とは何だったのでしょうか。それは、社会の規範や常識といったものから逸脱し、自分たちだけの絶対的な愛を追求した物語です。そして、その絶対的な愛は、この社会においては「死」によってしか完成し得なかった。その悲劇性こそが、この物語の核心なのだと私は思います。二人の行為は自己破壊的であり、決して肯定されるべきものではないかもしれません。しかし、そこに込められた純粋なまでの情熱と、究極の自己決定の姿は、私たちの心を強く揺さぶるのです。
まとめ
渡辺淳一氏の小説「失楽園」は、刊行から時を経ても色褪せることのない、人間の愛と死を巡る究極の物語です。妻子ある男性と、夫ある女性がすべてを捨てて愛に溺れていく過程は、読む者に強烈な問いを投げかけます。
二人が追い求めたのは、日常の退屈や社会のしがらみから解放された、絶対的な愛の世界でした。しかし、その純粋すぎる情熱は、彼らを現実世界から完全に孤立させていきます。周囲からの断罪と拒絶の中で、彼らが選んだのは、愛の絶頂で共に死ぬという道でした。
この物語の結末は衝撃的であり、多くの議論を呼びました。しかし、それは単なるスキャンダラスな結末ではありません。社会の中で生きる意味を見失った人間が、愛という一点において自己の存在を証明しようとした、悲しくも純粋な魂の軌跡を描いています。
「失楽園」が描く愛の形は、決して誰もが共感できるものではないかもしれません。それでもなお、この物語が私たちの心を捉えて離さないのは、誰もが心のどこかで、日常を超えた強烈な何かを求める気持ちを秘めているからではないでしょうか。