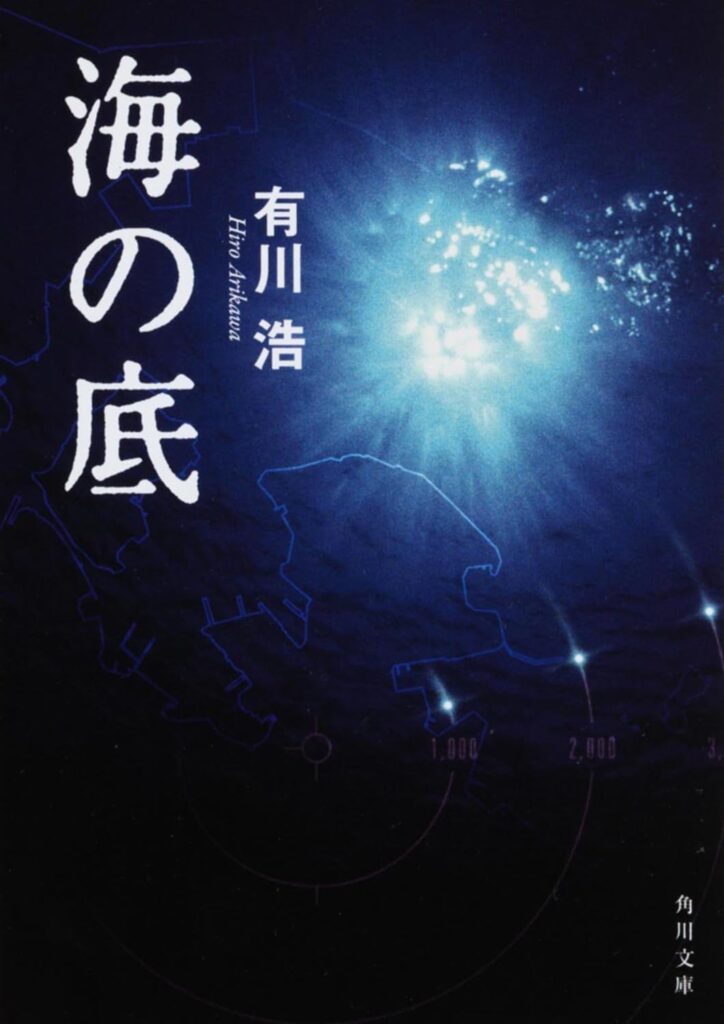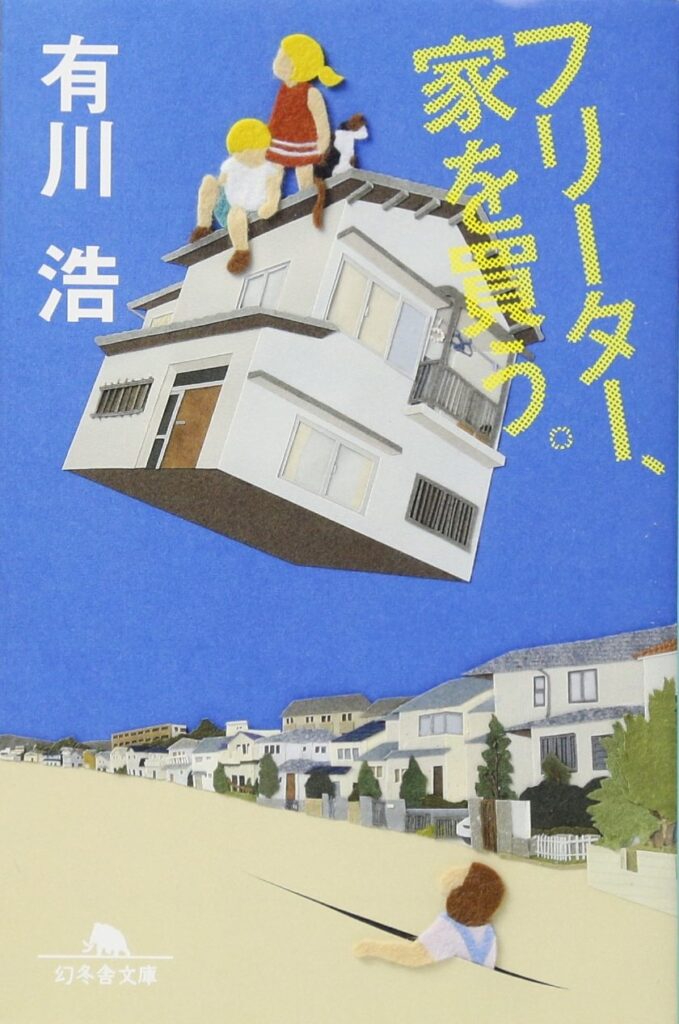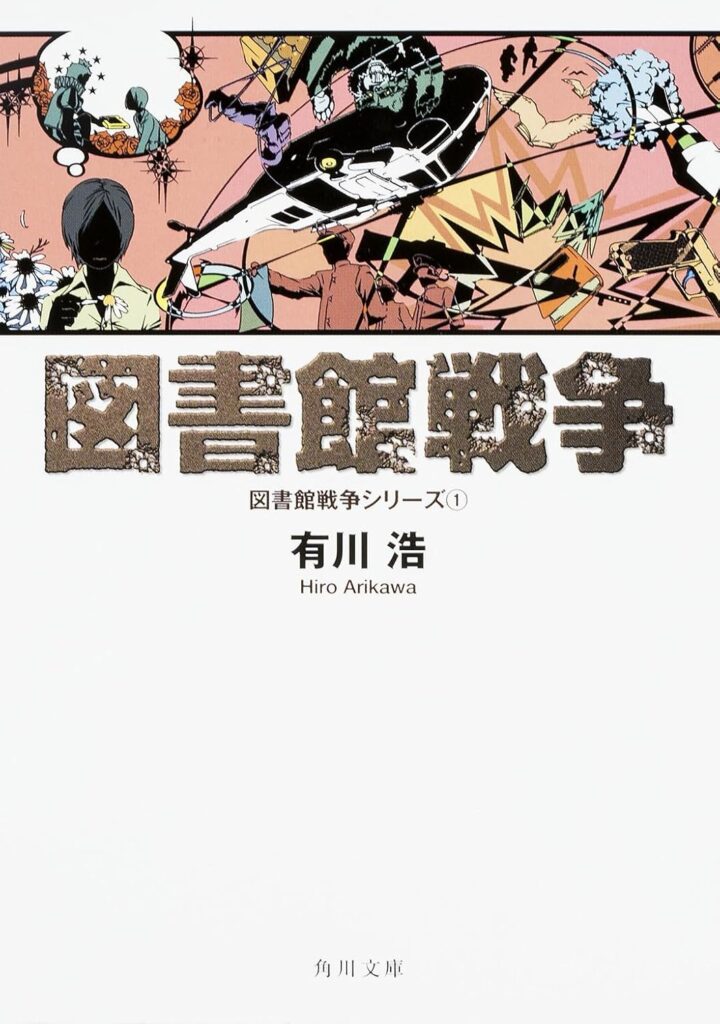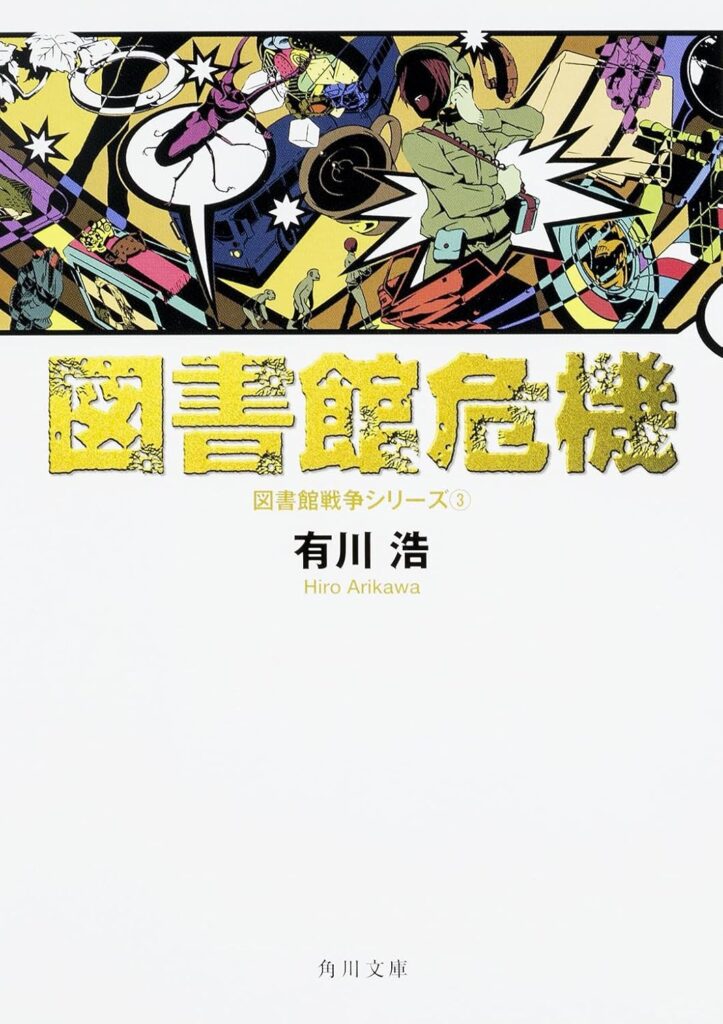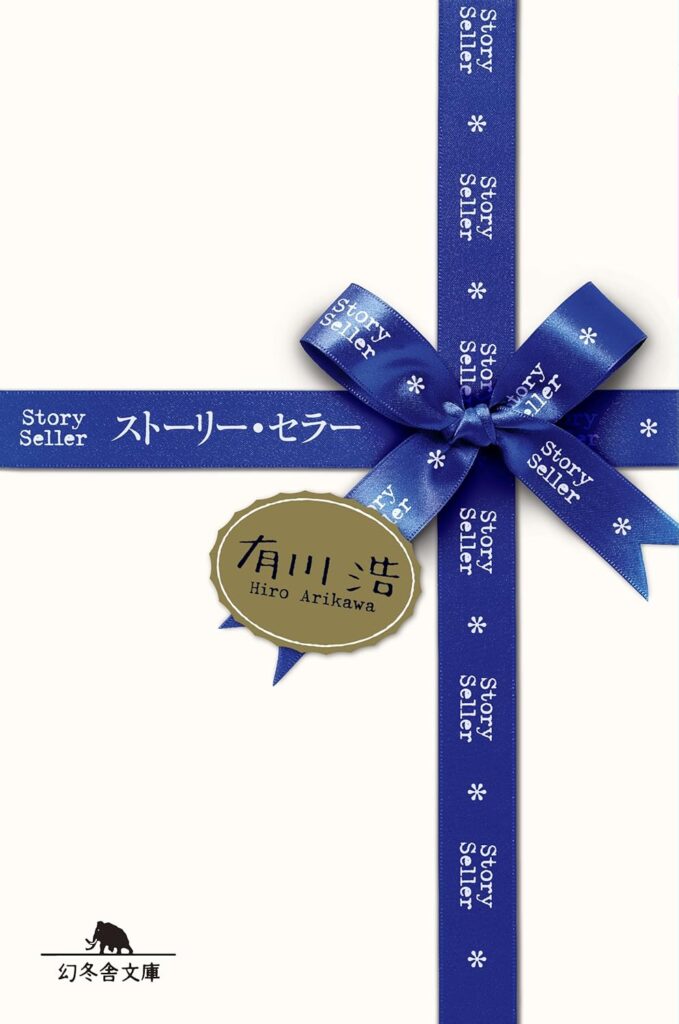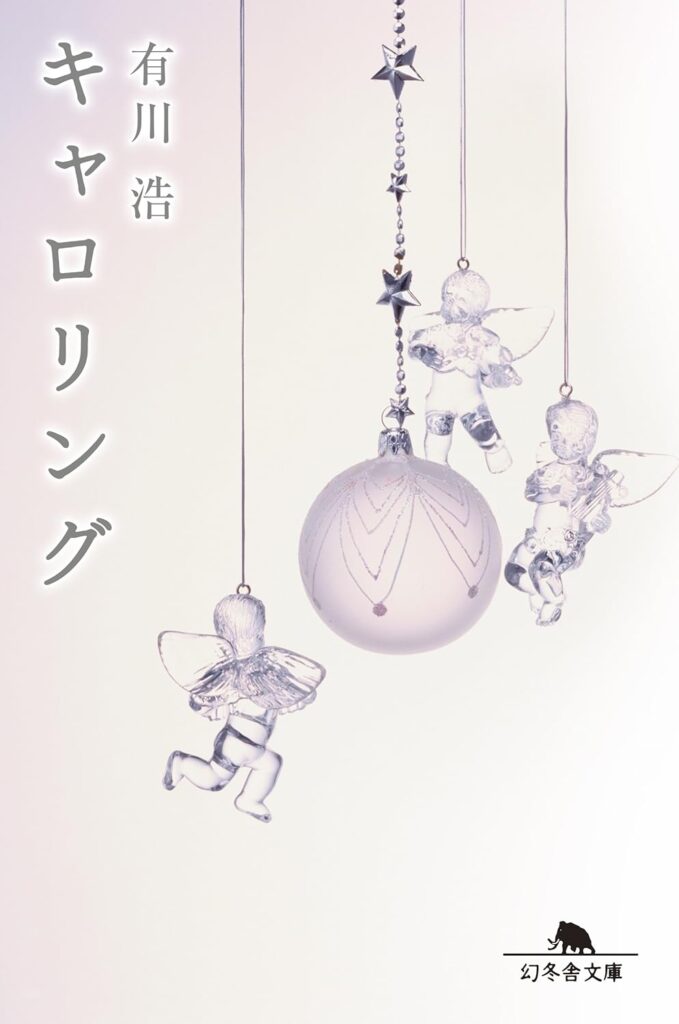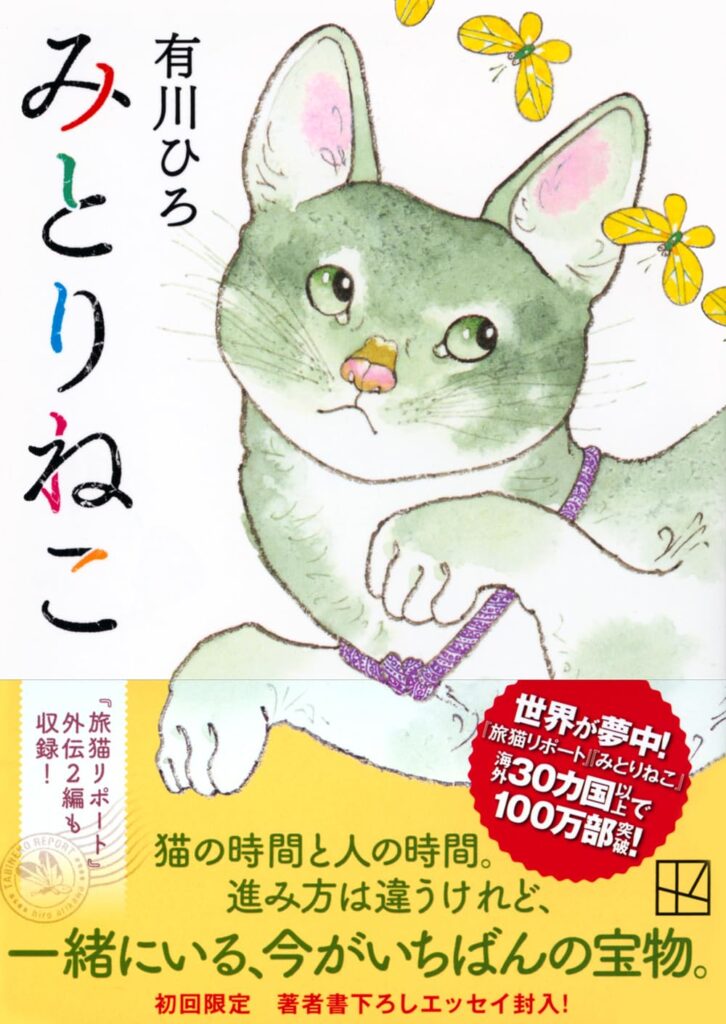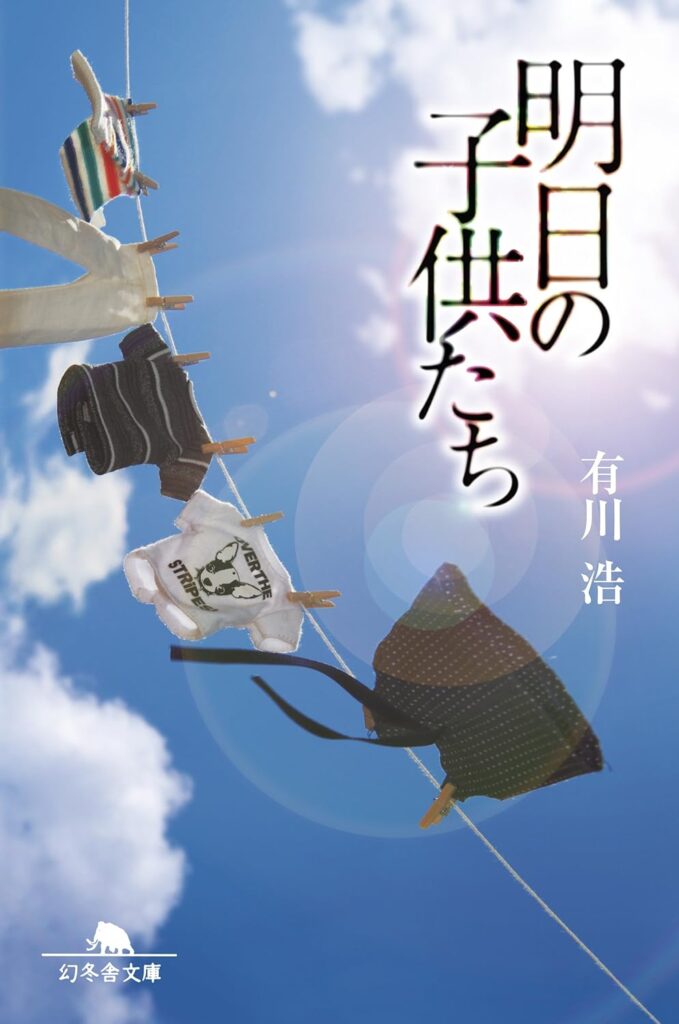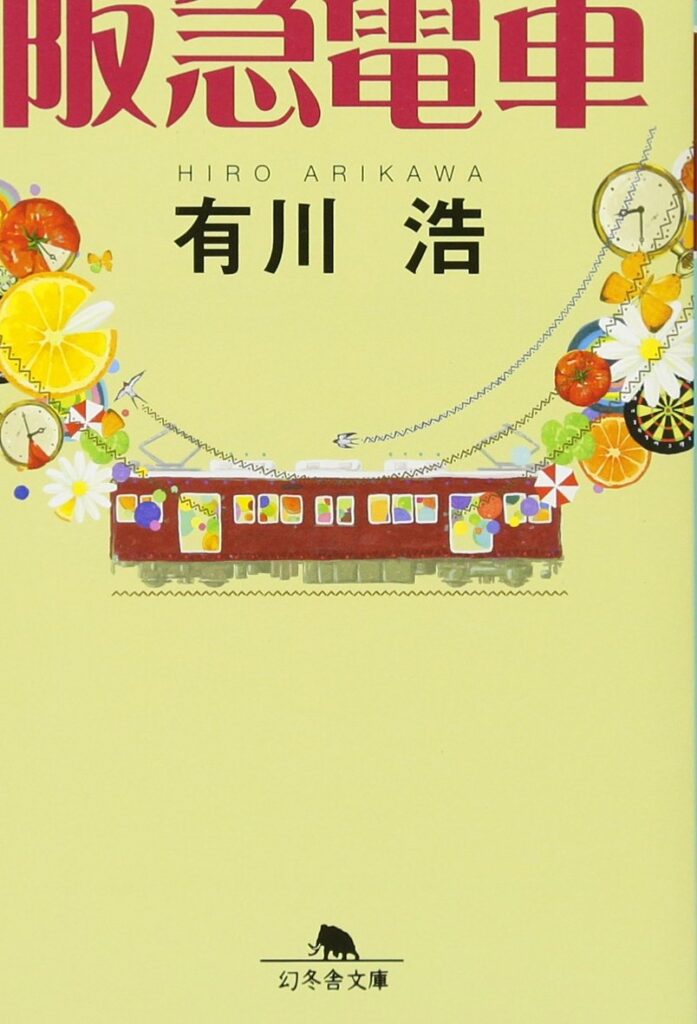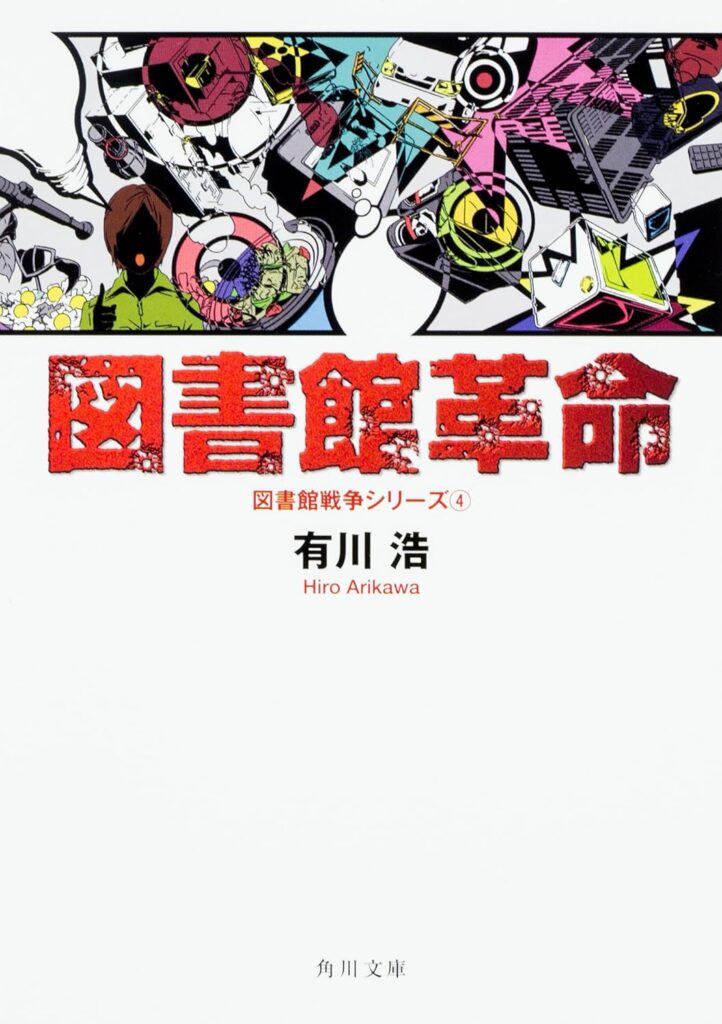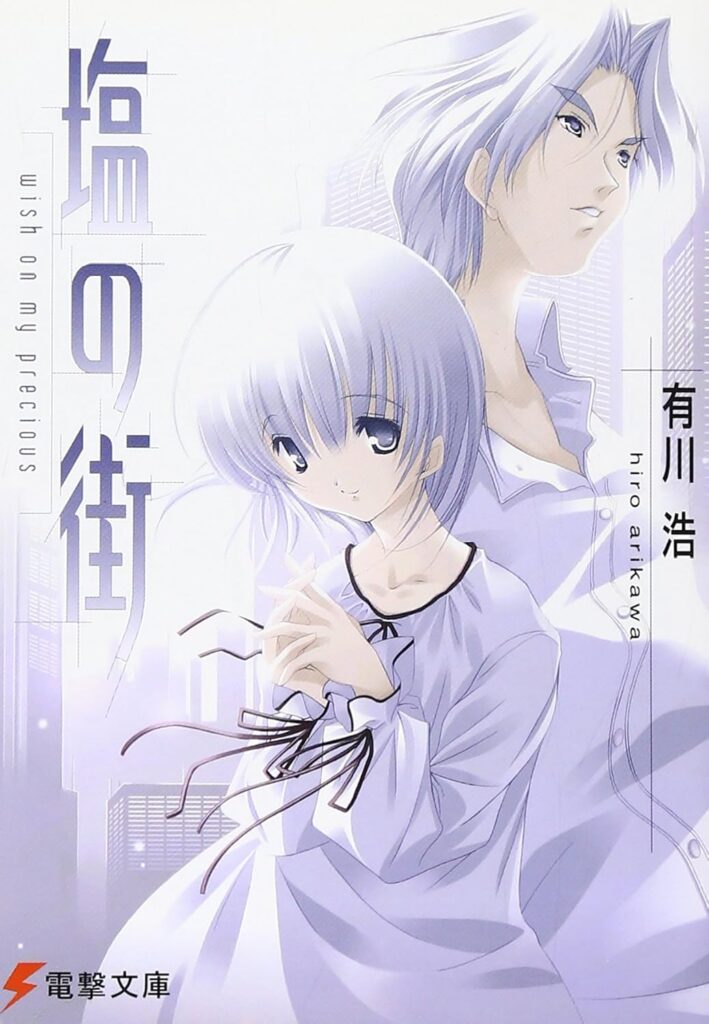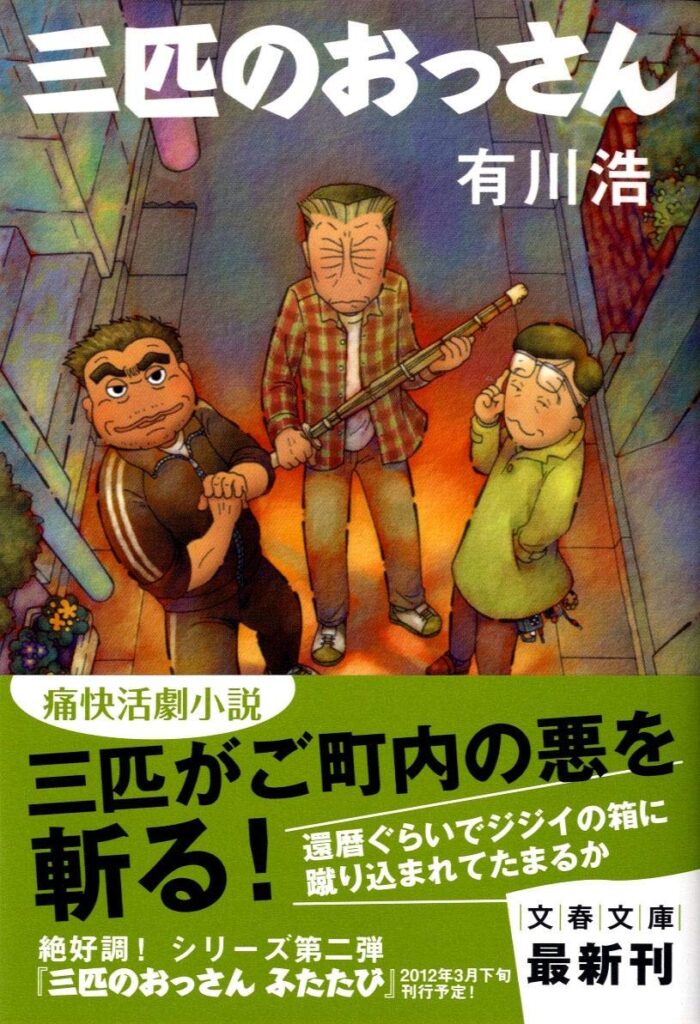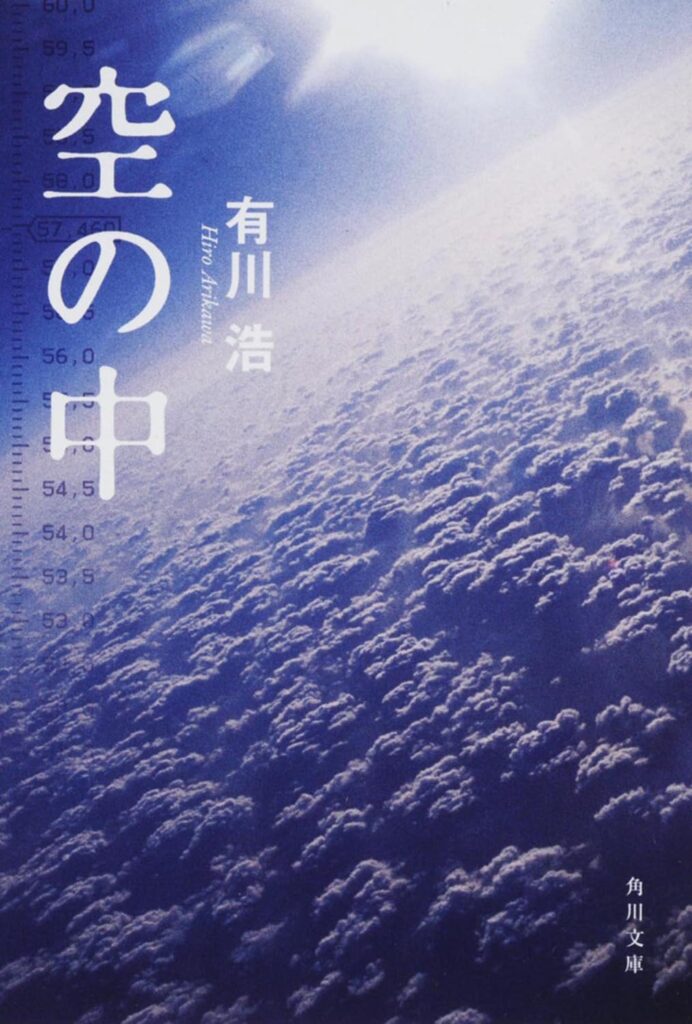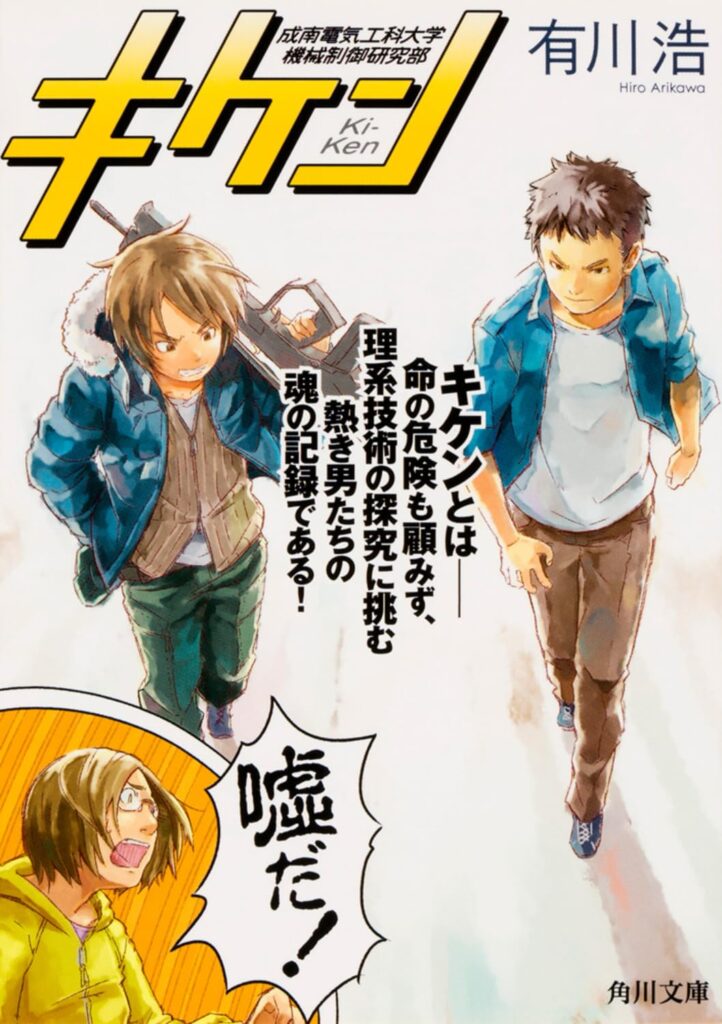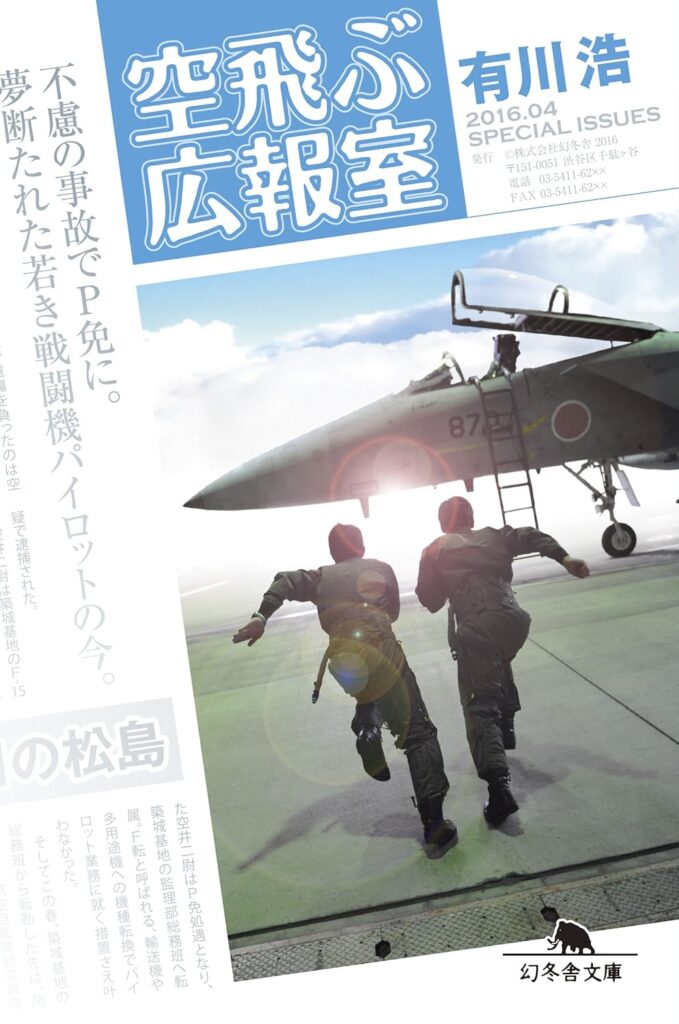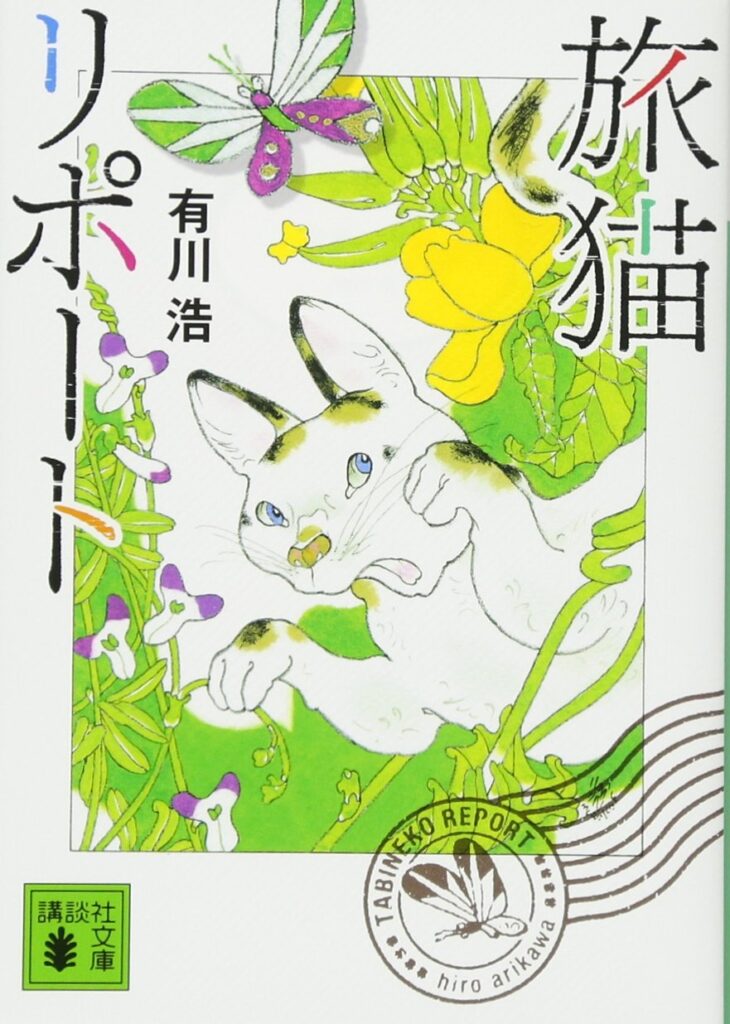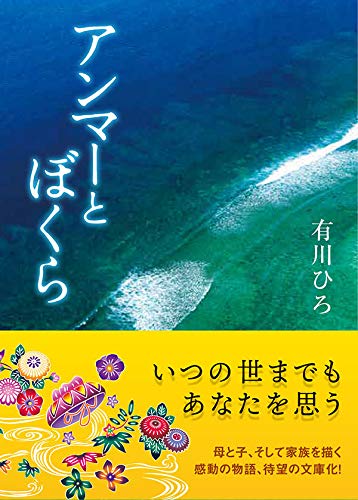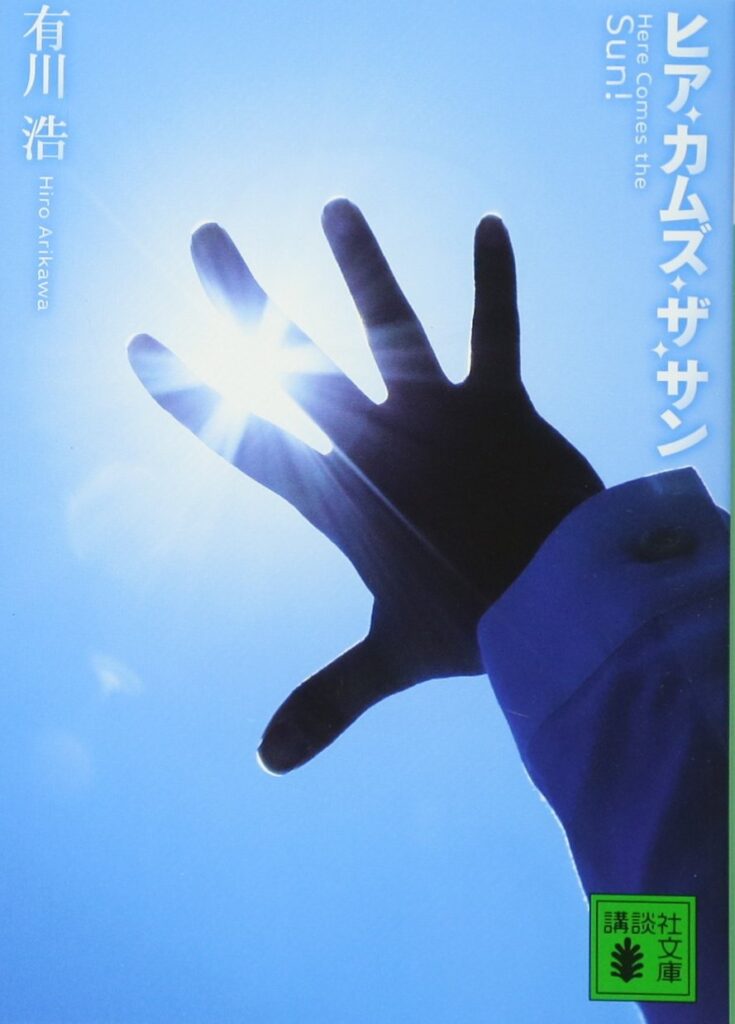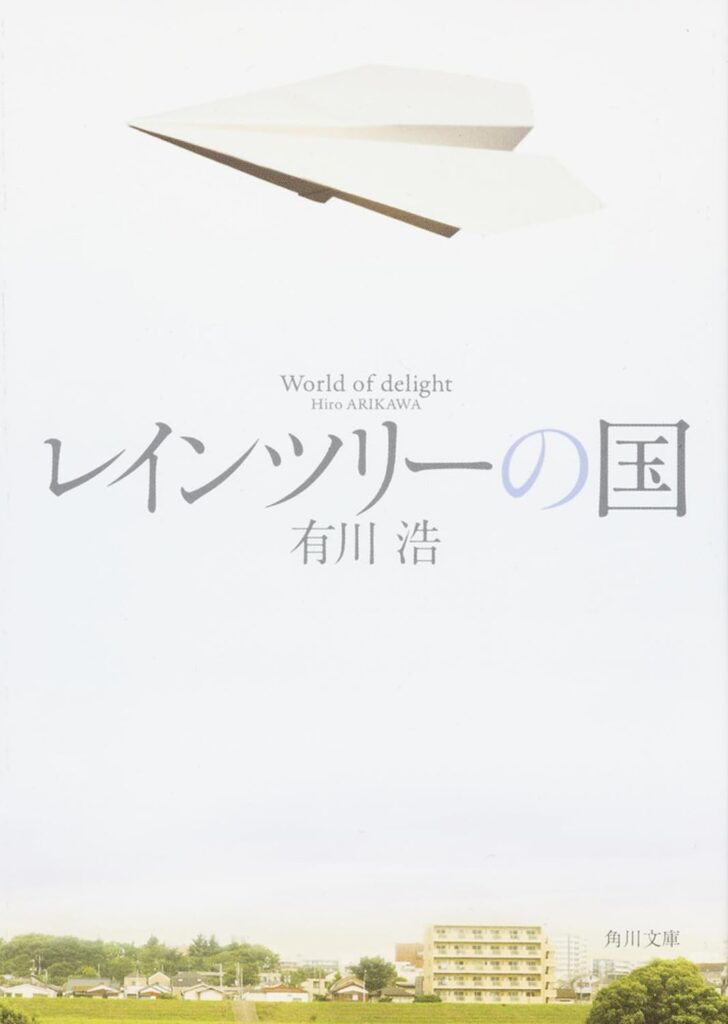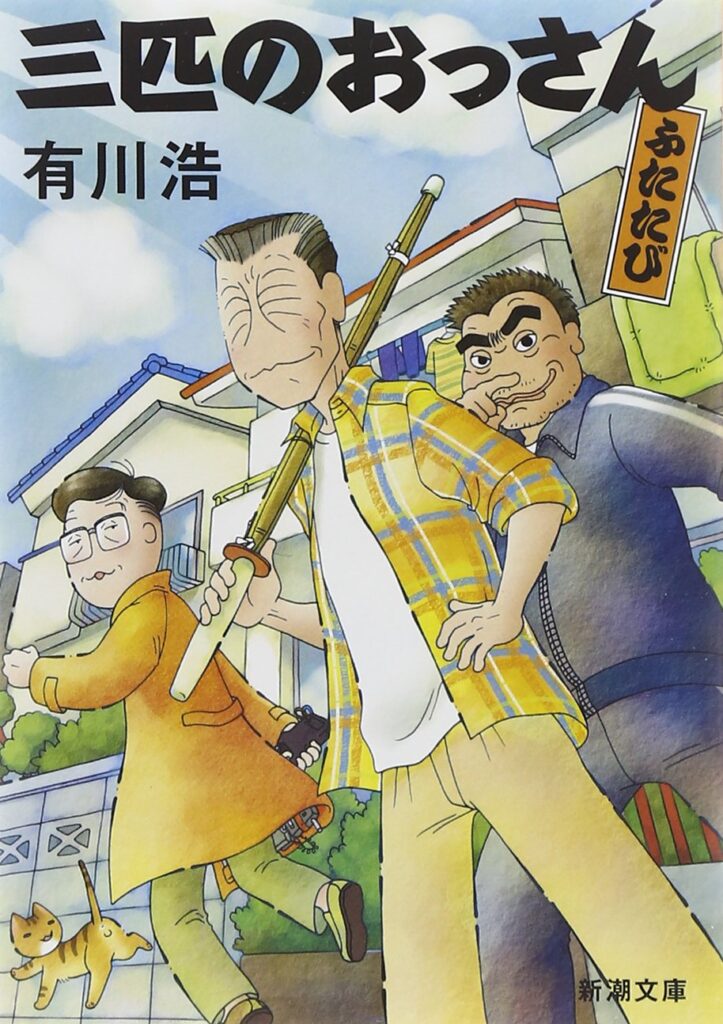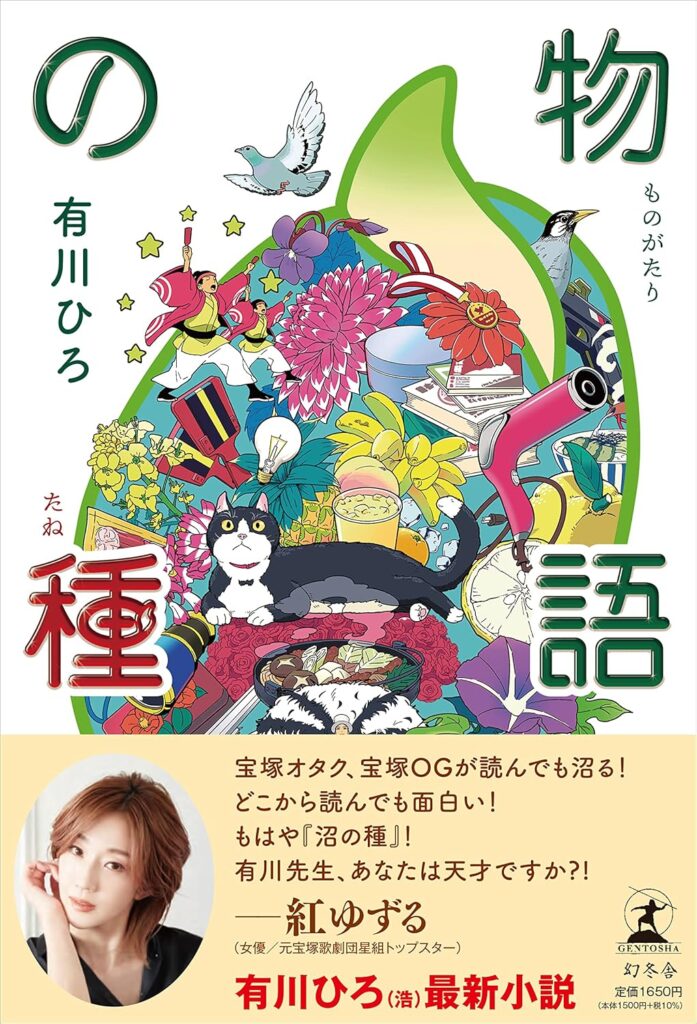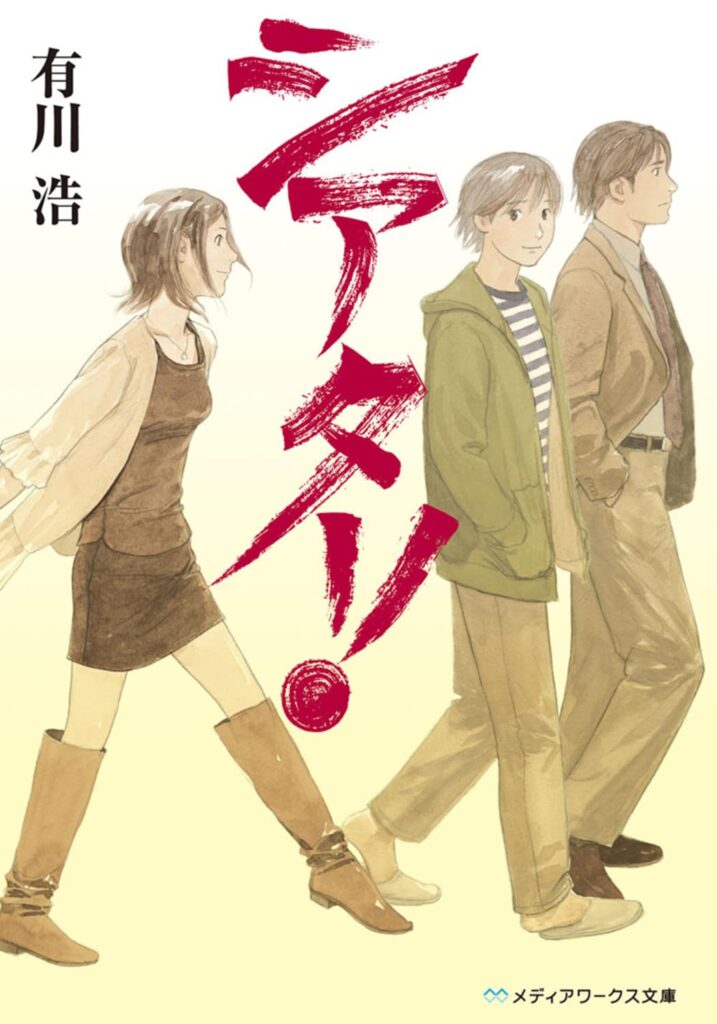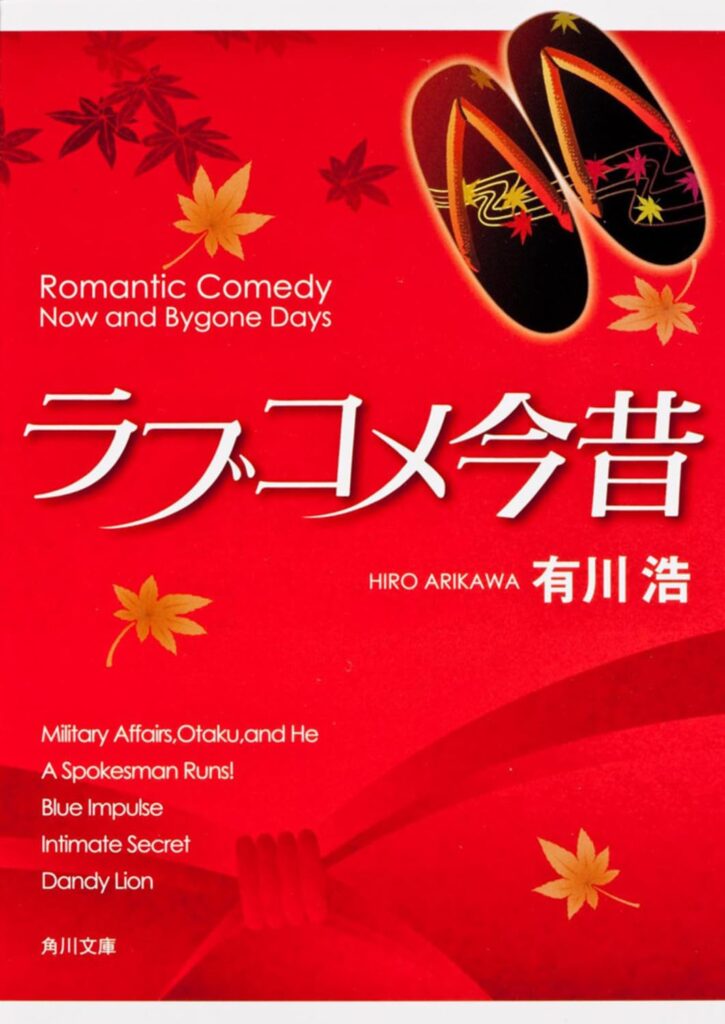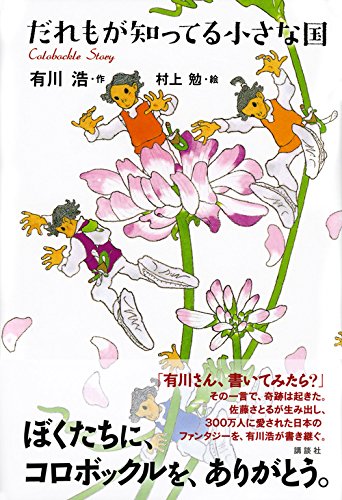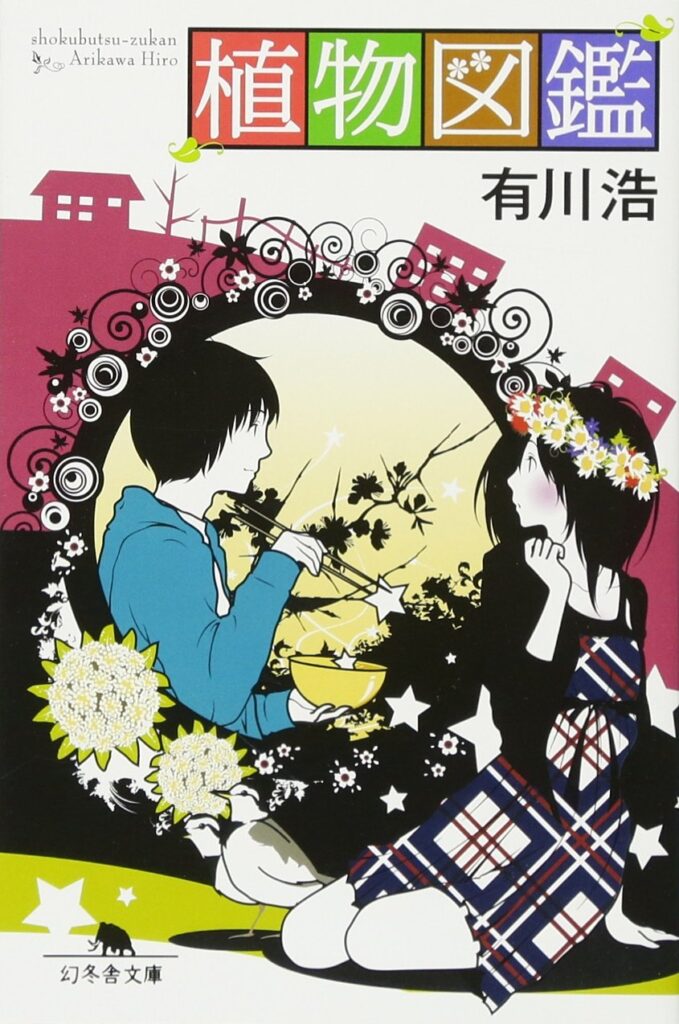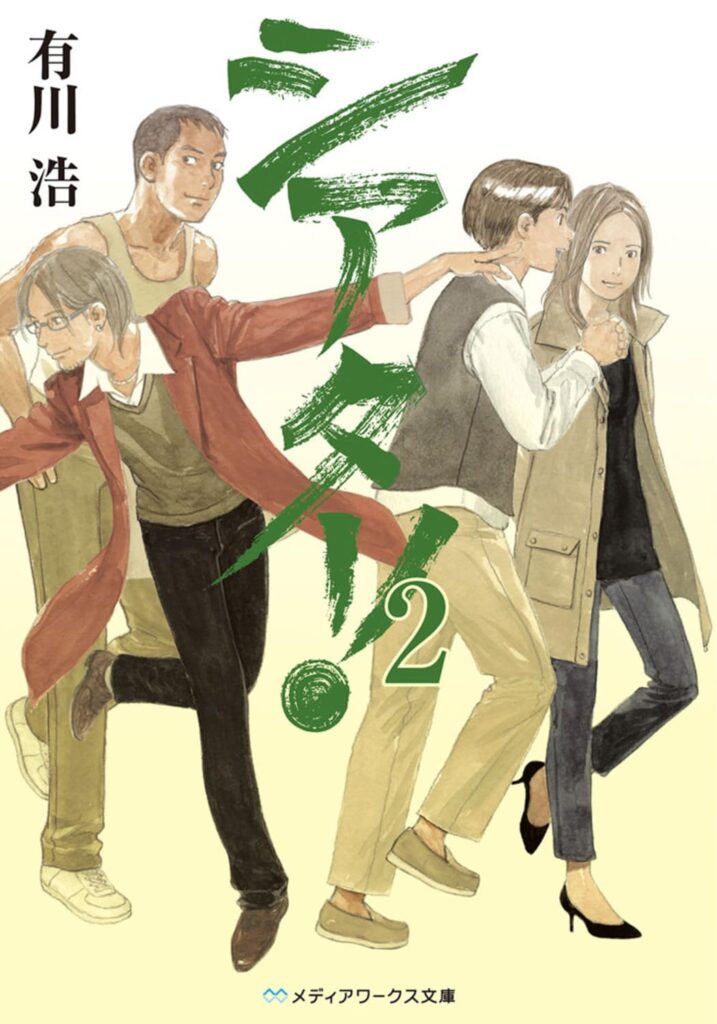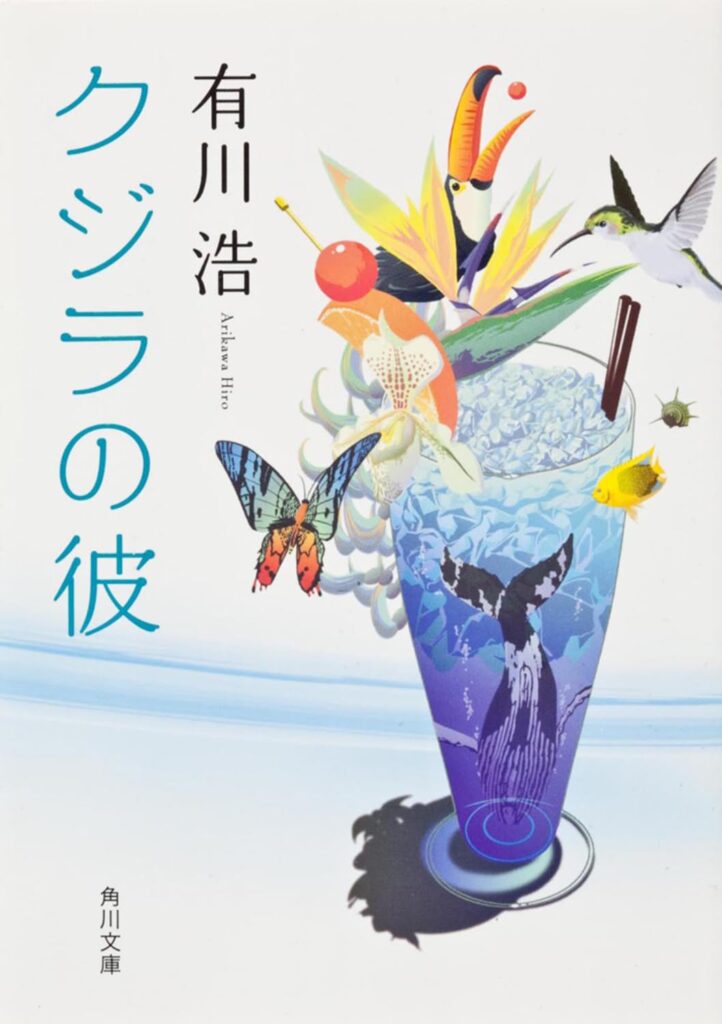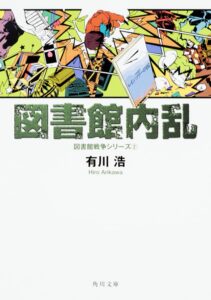 小説「図書館内乱」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、多くの読者を魅了した「図書館戦争」シリーズの第二弾にあたります。前作で描かれた、本を守るための戦いと、主人公・笠原郁の成長物語がさらに深掘りされる内容となっています。郁と教官である堂上篤との、もどかしくも応援したくなる関係性にも、新たな展開が待っていますよ。
小説「図書館内乱」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、多くの読者を魅了した「図書館戦争」シリーズの第二弾にあたります。前作で描かれた、本を守るための戦いと、主人公・笠原郁の成長物語がさらに深掘りされる内容となっています。郁と教官である堂上篤との、もどかしくも応援したくなる関係性にも、新たな展開が待っていますよ。
物語の中心となるのは、郁をはじめとする図書隊員たちの日常と、彼らが直面する様々な「内乱」です。それは、メディア良化委員会との物理的な戦闘だけではありません。郁の個人的な問題である両親との関係、同僚である小牧幹久の恋愛にまつわる表現の自由の問題、そして図書隊内部にも存在する考え方の対立など、様々な波乱が巻き起こります。これらの出来事を通して、キャラクターたちの内面や人間関係がより豊かに描かれていきます。
この記事では、まず「図書館内乱」の物語の筋道を詳しくお伝えし、その後で、物語の核心部分にも触れながら、私の感じたことや考えたことをたっぷりと語っていきます。特に、キャラクターたちの魅力や、心を揺さぶられた場面、作品全体から受け取ったメッセージについて、熱を込めてお話しできればと思っています。シリーズファンの方はもちろん、これから読んでみようかなと考えている方にも、作品の雰囲気や読みどころが伝われば嬉しいです。
小説「図書館内乱」のあらすじ
舞台は、公序良俗を乱す表現を取り締まる「メディア良化法」が施行され、武力行使も辞さない「メディア良化委員会」と、本の自由を守るために組織された「図書隊」が対立する近未来の日本です。主人公の笠原郁は、高校時代に自分を守ってくれた図書隊員に憧れ、自身も図書隊に入隊しました。関東図書基地の図書特殊部隊(ライブラリー・タスクフォース)に配属され、厳しい訓練と実戦に明け暮れる日々を送っています。
今作「図書館内乱」では、郁の個人的な問題が大きくクローズアップされます。図書隊員であることを両親に隠していた郁ですが、母親が基地の近くまでやってくるという緊急事態が発生。上官である堂上や同僚たちの協力を得て、「両親撹乱作戦」を決行します。また、真面目な同僚・手塚光の兄であり、図書隊の在り方に疑問を呈する手塚慧が登場し、郁や図書隊に波紋を投げかけます。彼は、現在の図書隊の活動を「自由のための戦い」ではなく、単なる武力闘争だと批判するのです。
さらに、郁の良き相談相手である堂上班の先輩・小牧幹久にも危機が訪れます。彼が病気の少女・中澤毬江におすすめした本が、メディア良化委員会によって「障害者への配慮を欠く」として検閲の対象となり、小牧自身が拘束されてしまう事態に発展します。この出来事は、図書隊内部でも「表現の自由」や「お勧め」の是非について、大きな議論を巻き起こします。郁や堂上たちは、小牧を救い出すために奔走することになります。
物語の終盤では、郁が過去に自分を助けてくれた「王子様」の正体がついに明らかになります。それは、郁にとってあまりにも予想外で、そして運命的な瞬間でした。一連の出来事を通して、郁は図書隊員として、一人の人間として、大きな成長を遂げていきます。仲間との絆、守るべきものへの信念、そして堂上への複雑な想いを胸に、郁は次なる戦いへと歩みを進めていくのでした。
小説「図書館内乱」の長文感想(ネタバレあり)
「図書館戦争」シリーズ第二弾、「図書館内乱」。前作で心を鷲掴みにされた私は、期待に胸を膨らませてページをめくりました。そして、その期待は裏切られるどころか、はるかに上回る感動と興奮を与えてくれたのです。前作が郁と堂上、そして図書隊という組織の紹介編だとすれば、今作は個々のキャラクターの内面と関係性を深く掘り下げ、物語世界にさらなる奥行きを与えた作品だと言えるでしょう。まさに「内乱」というタイトルが示す通り、外部との衝突だけでなく、登場人物たちの心の中や、組織内部での葛藤、価値観のぶつかり合いが濃密に描かれていました。
まず、主人公の笠原郁。相変わらずの猪突猛進ぶりと、考えるより先に体が動いてしまう危なっかしさは健在ですが、今作では彼女の精神的な成長が随所に感じられました。「両親撹乱作戦」では、図書隊員であることを隠す後ろめたさと、それでも自分の選んだ道を肯定したいという思いの間で揺れ動きます。家族に心配をかけたくない一心での行動でしたが、結果的に堂上たち同僚を巻き込み、迷惑をかけてしまう。しかし、その経験を通して、彼女は自分の仕事に対する誇りと責任感を再確認します。特に、母親との対峙シーンで見せた、たどたどしくも懸命に自分の言葉で図書隊の意義を語る姿には、胸が熱くなりました。まだまだ未熟ではあるけれど、確実に前進している郁の姿に、読んでいるこちらも勇気づけられる思いがしました。
そして、忘れてはならないのが、郁と堂上教官の関係性の進展です。前作から続く、もどかしくて甘酸っぱい空気感はそのままに、今作では二人の距離がぐっと縮まる瞬間がいくつもありました。郁が査問委員会にかけられそうになった時、堂上が「あり得ませんッ!」と感情を爆発させるシーン。普段の冷静沈着な彼からは想像もつかないほどの激昂ぶりは、郁への深い信頼と、守りたいという強い意志の表れでしょう。読んでいるこちらも、思わず「よく言った!」と快哉を叫びたくなりました。そして、ついに郁が「王子様」の正体に気づく場面。まさか、あのような形で、しかも手塚慧によって明かされるとは! 郁の驚きと混乱、そして込み上げてくるであろう様々な感情を想像すると、胸が締め付けられるようでした。この事実が、今後の二人の関係にどのような影響を与えていくのか、目が離せません。堂上の方も、郁に対する自身の特別な感情に気づき始めているような描写があり、読者のやきもきは最高潮に達します。この二人の不器用な恋の行方は、シリーズを通して最大の関心事の一つですね。
今作でスポットライトが当てられたのは、郁と堂上だけではありません。他の図書隊メンバーたちの魅力も存分に描かれていました。特に印象的だったのは、小牧幹久のエピソードです。「恋の障害」と題されたこの章では、普段は穏やかで理知的な小牧の、内に秘めた情熱と信念の強さが明らかになります。彼が紹介した本『レインツリーの国』が、いわれのない理由で検閲対象となり、自身が拘束されるという理不尽な状況。この『レインツリーの国』が、後にスピンオフ作品として実際に刊行されるというのも、有川作品ならではの遊び心と仕掛けですよね。小牧は、たとえ自分が不利な立場に置かれようとも、「表現の自由」と「本を読む自由」を守るために毅然と立ち向かいます。「お勧めは肯定的な手法だ」と語る彼の言葉は、検閲という行為の本質的な問題点を鋭く突いています。そして、彼を支える中澤毬江との関係も、切なくも心温まるものでした。毬江のために、そしてまだ見ぬ多くの読者のために戦う小牧の姿は、まさに図書隊員の鑑と言えるでしょう。彼の冷静さの中に燃える炎のような意志に、私は深く感動しました。
情報屋として活躍する柴崎麻子も、今作でさらにその存在感を増しました。「美女の微笑み」の章では、彼女の有能さと、同僚である郁への深い友情が描かれています。一見、打算的で掴みどころがないように見える柴崎ですが、その実、誰よりも仲間思いで、強い信念を持っていることがわかります。郁が困っている時にはさりげなく手を差し伸べ、時には厳しい言葉で叱咤激励する。彼女の存在は、まっすぐすぎる郁にとって、なくてはならないバランサーであり、最高の友人です。彼女がどのようにしてその情報収集能力を身につけたのか、過去に何があったのか、まだまだ謎めいた部分も多く、今後の展開でさらに彼女の人物像が掘り下げられることを期待しています。手塚との間に漂う微妙な空気も気になるところです。
そして、今作の「内乱」を象徴する存在とも言えるのが、手塚光の兄・手塚慧の登場です。「兄と弟」「図書館の明日はどっちだ」の章で、彼は図書隊、特にタスクフォースの在り方に対して、真っ向から異を唱えます。彼の主張は、一見すると正論のようにも聞こえます。「自由を守るためとはいえ、武力闘争に明け暮れる現状は健全ではないのではないか」「もっと知的に、法的に戦うべきではないか」。彼の言葉は、郁や堂上たちだけでなく、読者にも「自由とは何か」「守るべきものとは何か」という問いを突きつけます。しかし、彼のやり方はあまりにも冷徹で、人の感情を考慮しない部分があります。郁が彼に言い放った「読みたいのは今なんだもの。何十年か後の自由のために今ある自由を捨てろとか言えない」という言葉は、まさにこの物語の核心を突くものだと感じました。未来のために現在を犠牲にすることを是とする考え方と、今ここにある自由を大切にしたいという郁の切実な思い。どちらが絶対的に正しいとは言えないかもしれませんが、郁の言葉には、彼女自身の経験に裏打ちされた強い説得力がありました。手塚慧という存在は、物語に深みと複雑さを与える重要な役割を担っています。彼の登場によって、図書隊が抱える問題や矛盾点が浮き彫りになり、物語はより一層緊張感を増しました。
物語全体の構成も、実に見事でした。郁の両親の問題、小牧の検閲問題、手塚兄弟の確執、そして郁と堂上の関係の変化といった複数のエピソードが、時にコミカルに、時にシリアスに、緩急自在に展開されていきます。それぞれの章が独立した物語として楽しめるだけでなく、それらが複雑に絡み合いながら、クライマックスに向けて大きな流れを形成していく。有川さんのストーリーテリングの巧みさには、改めて感嘆させられます。特に、会話劇の面白さは健在で、キャラクターたちの生き生きとしたやり取りに、何度も笑わされ、そして胸を打たれました。彼らの絆は、嵐の中でもしっかりと根を張る大樹のようでした。
また、この作品は単なるエンターテイメントとしてだけでなく、「表現の自由」「知る権利」「検閲」といった社会的なテーマについても深く考えさせてくれます。メディア良化法という架空の設定を通して、私たちが当たり前のように享受している「本を読む自由」がいかに脆く、尊いものであるかを改めて認識させられました。小牧のエピソードで描かれたように、ある特定の価値観や「配慮」の名の下に、表現が安易に制限されてしまう危険性は、決してフィクションの世界だけの話ではないのかもしれません。郁が言ったように、「捨てる権利も捨てない権利もあって、選ぶのはみんな自由」。この言葉の重みを、深く噛みしめました。
「図書館内乱」は、前作からの期待を裏切らない、いや、それ以上の満足感を与えてくれる素晴らしい続編でした。キャラクターたちの魅力はさらに深まり、物語はより複雑で読み応えのあるものへと進化しています。笑いあり、涙あり、胸キュンあり、そして社会的なメッセージ性もあり。エンターテイメントとしての面白さと、考えさせられるテーマ性が絶妙なバランスで融合した、まさに傑作だと思います。ラストの衝撃的な展開もあり、次作「図書館危機」への期待は否応なく高まります。この濃密な読書体験は、しばらく私の心から離れそうにありません。
まとめ
小説「図書館内乱」は、「図書館戦争」シリーズの魅力をさらに深めた、読み応え十分な第二弾でした。主人公・笠原郁の成長はもちろんのこと、堂上教官とのじれったい関係にも大きな進展が見られ、読者はますます二人の行方から目が離せなくなります。前作以上に、郁を取り巻く仲間たちの個性や内面が丁寧に描かれているのが、本作の大きな特徴と言えるでしょう。
特に、小牧教官が直面する検閲問題のエピソードは、「表現の自由とは何か」「本を読むことの意味」を深く問いかけてきます。また、新たに登場する手塚慧は、図書隊の活動意義に疑問を投げかけ、物語に緊張感と複雑さをもたらしました。これらの出来事を通して、キャラクターたちはそれぞれの信念に基づき、悩み、葛藤し、そして絆を深めていきます。笑いと涙、ドキドキする展開、そして社会派なテーマが見事に織り交ぜられています。
単なる続編に留まらず、物語世界とキャラクターの奥行きを格段に広げた「図書館内乱」。アクション、ラブコメ、そして「自由」をめぐる熱いドラマが凝縮されたこの一冊は、シリーズファンはもちろん、多くの読者の心を掴む力を持っています。ラストの展開も衝撃的で、次作への期待感を最高潮に高めてくれること間違いなし。ぜひ手に取って、この濃密な物語世界に浸ってみてください。