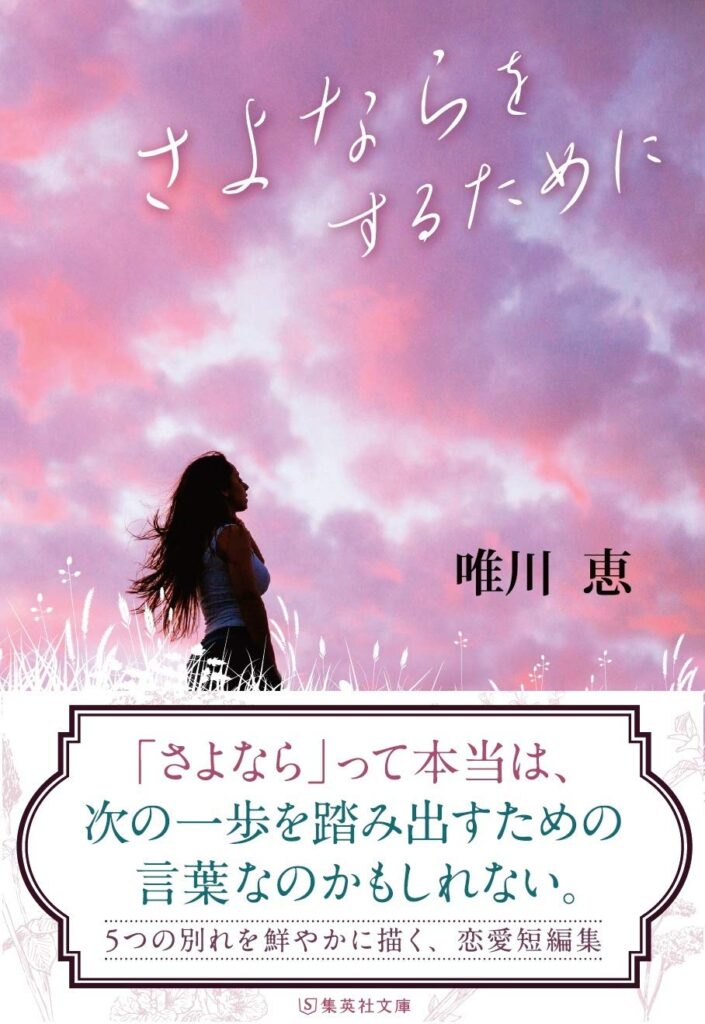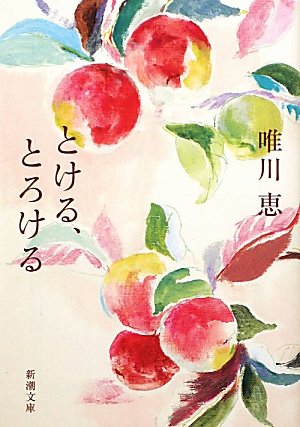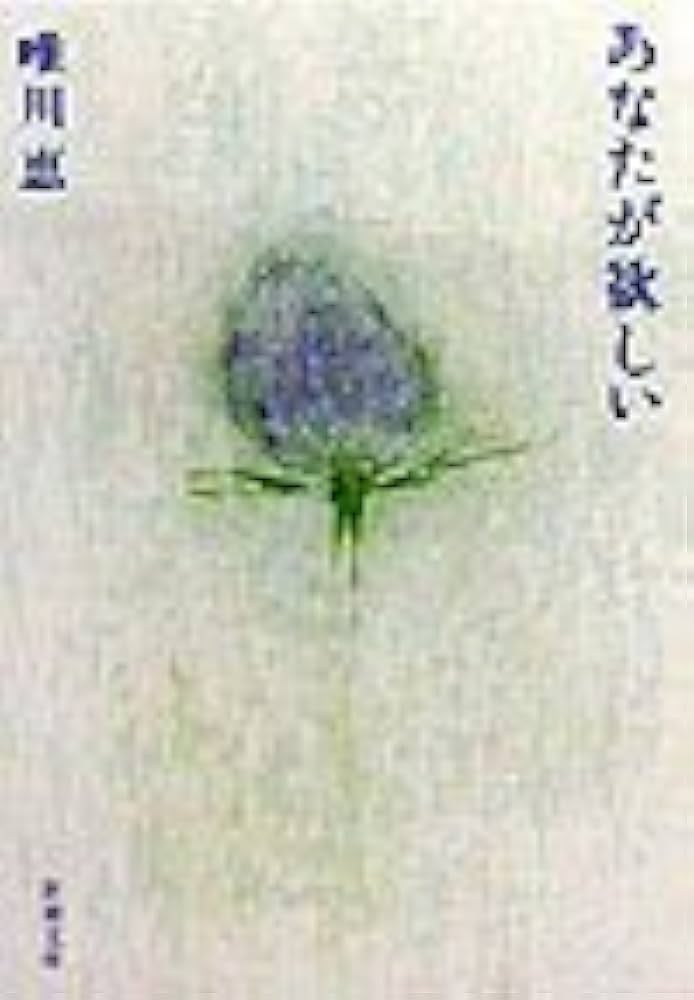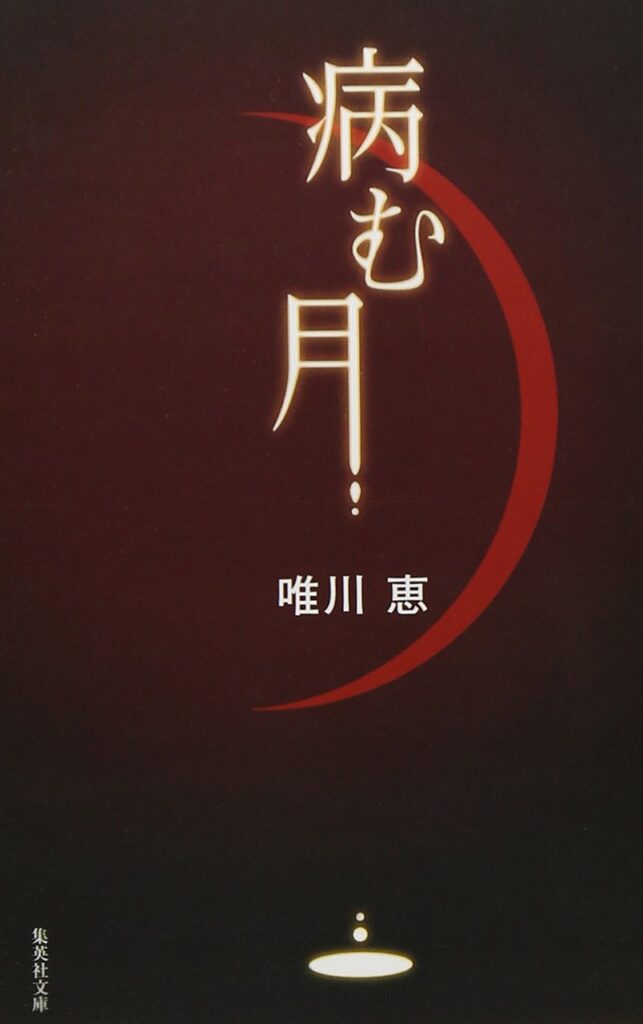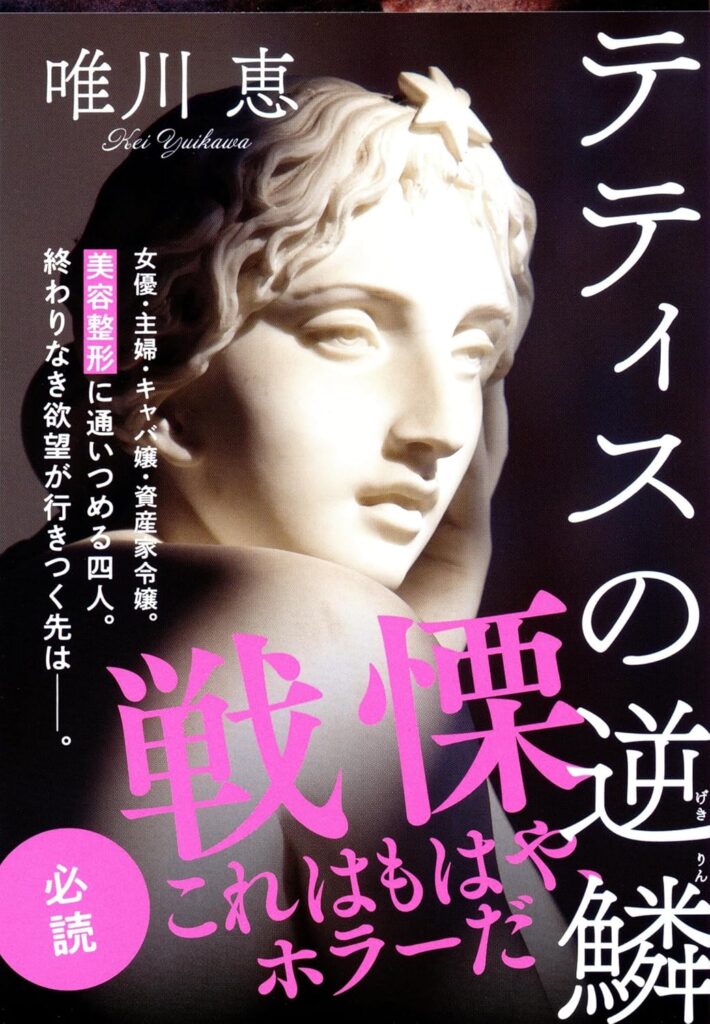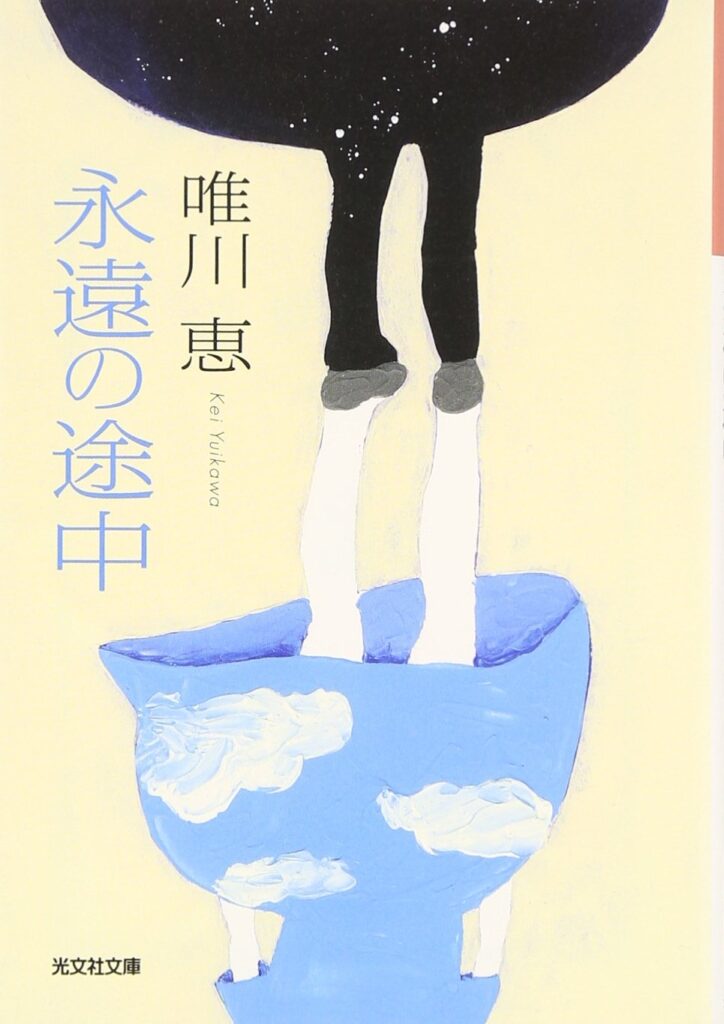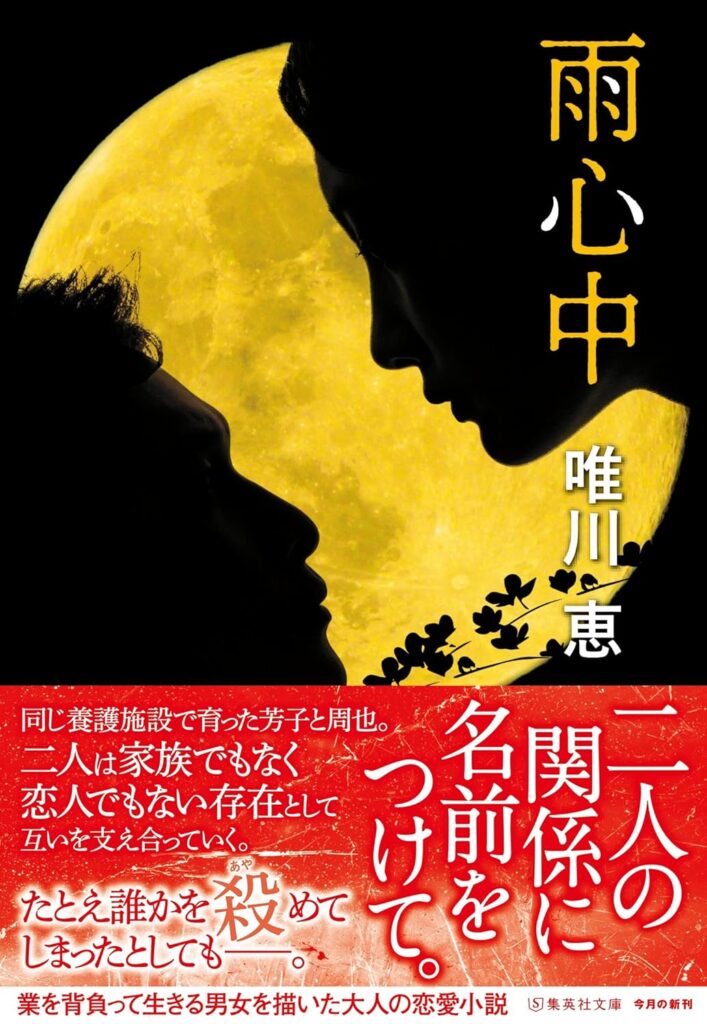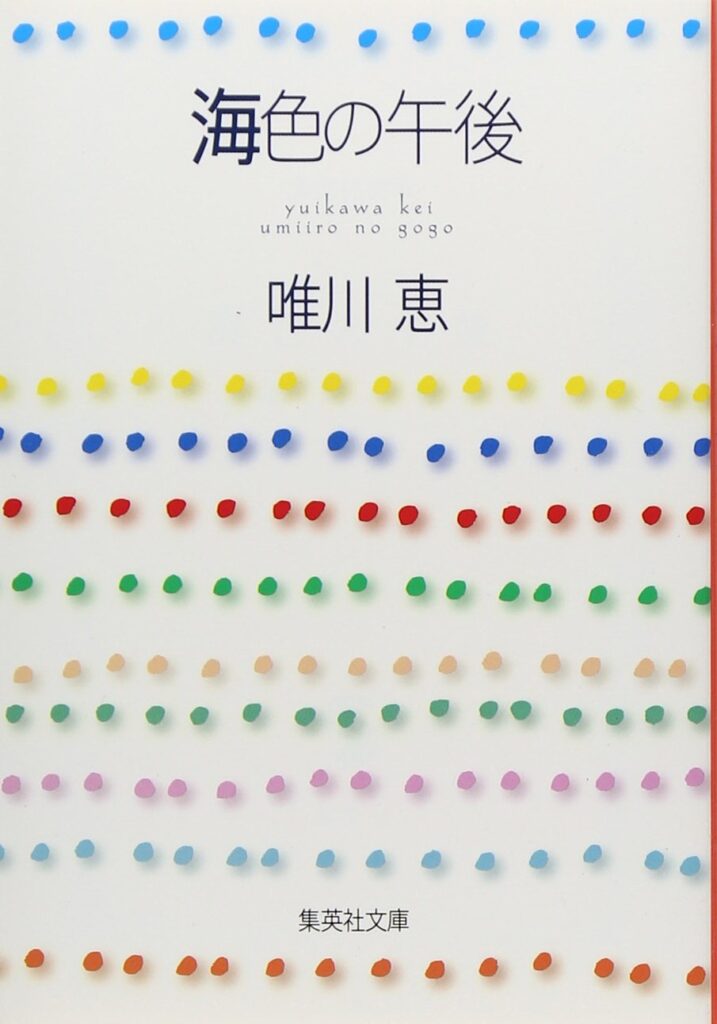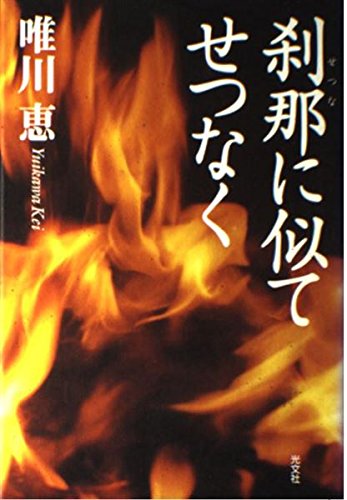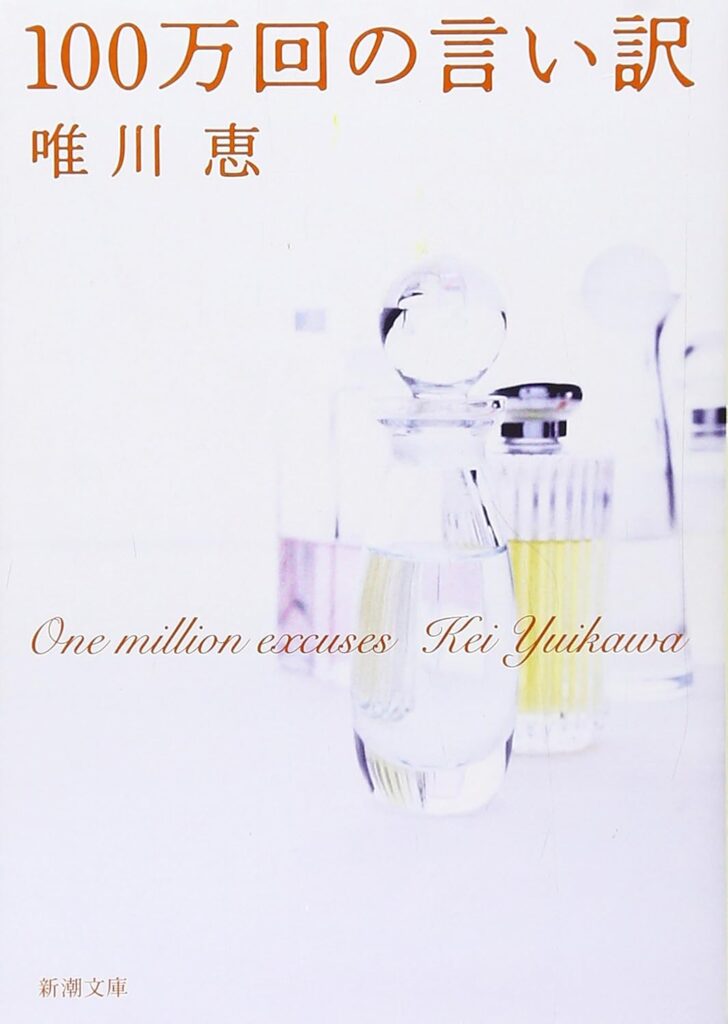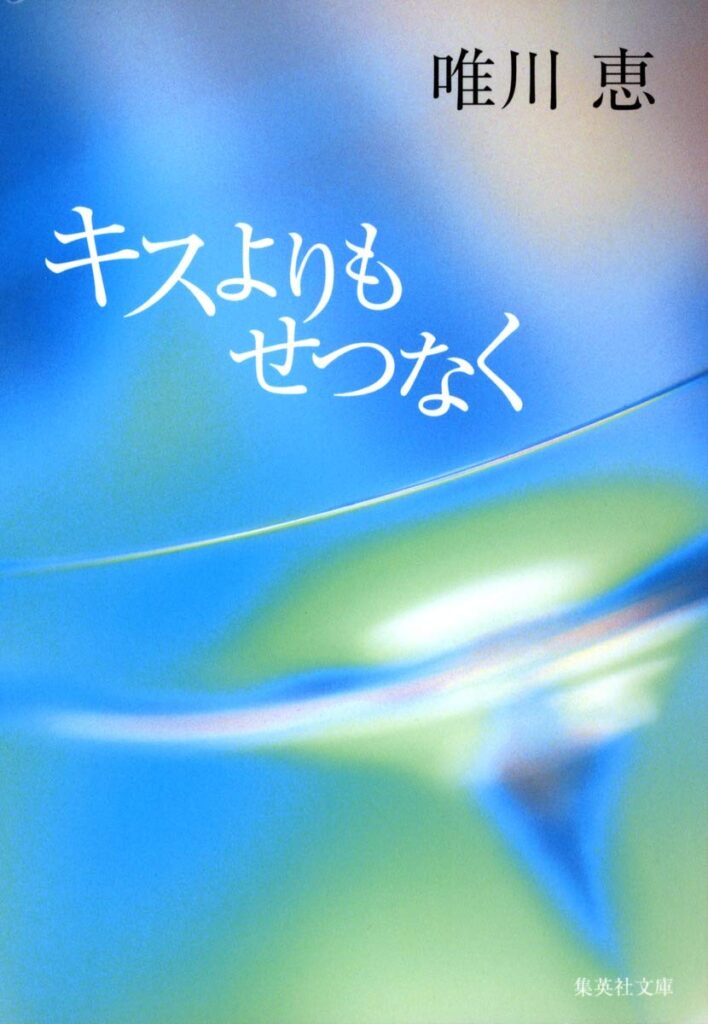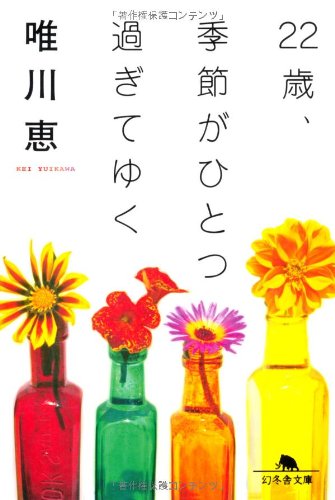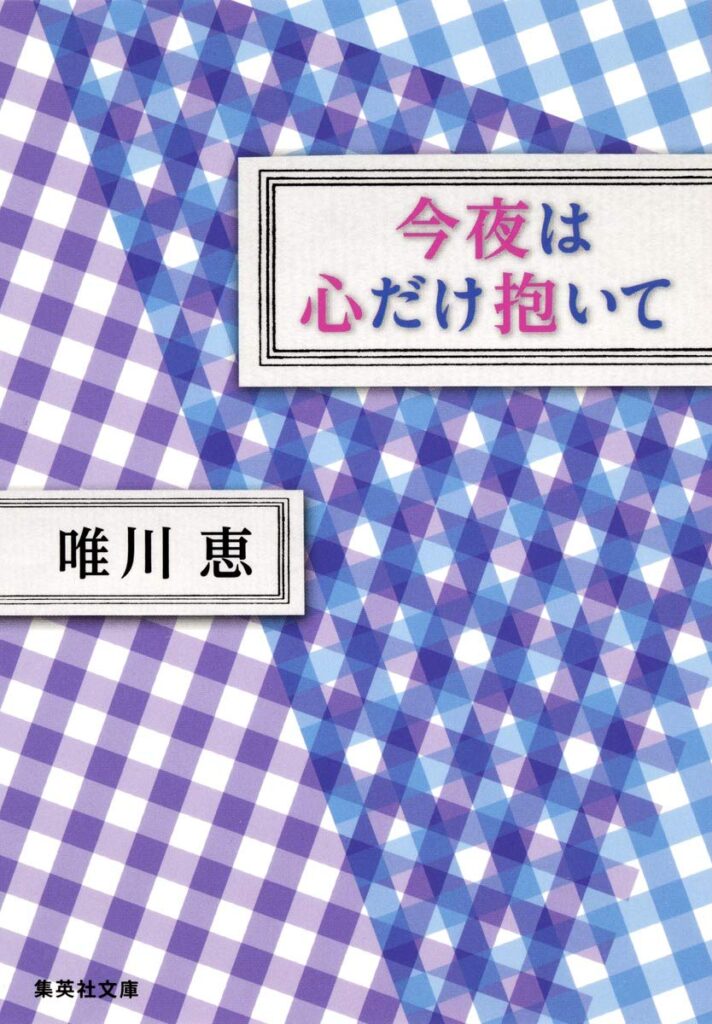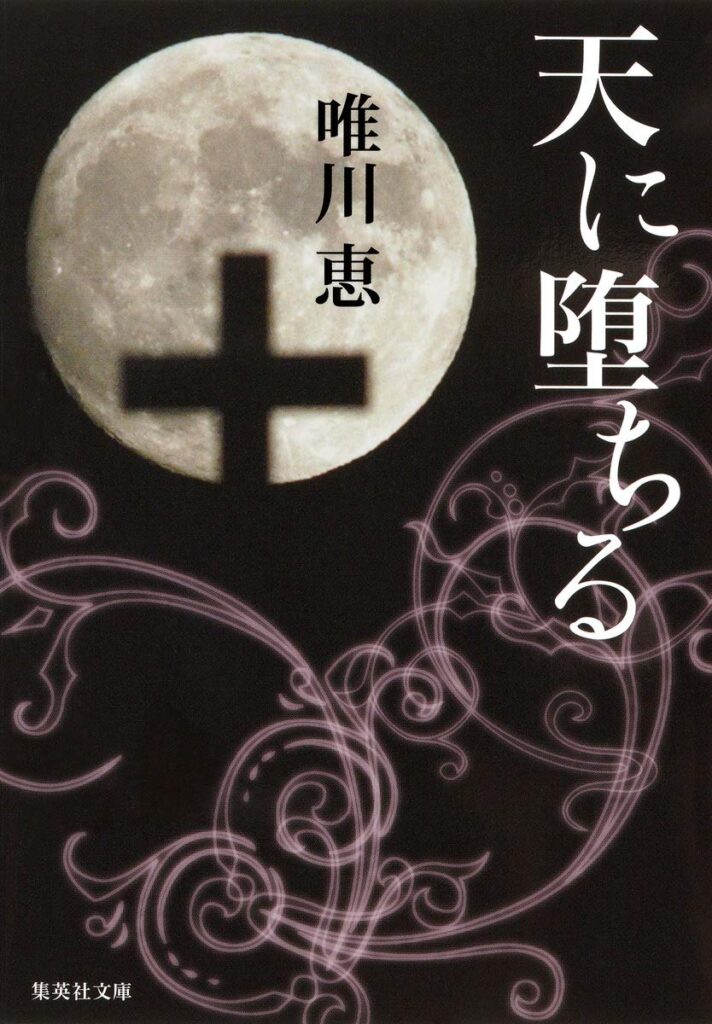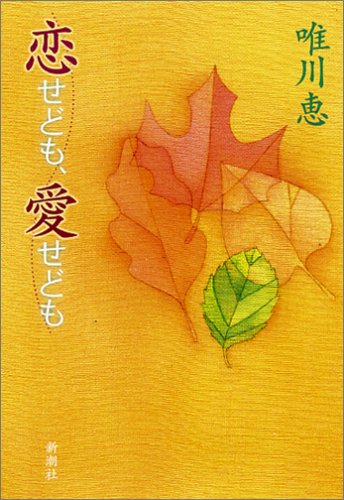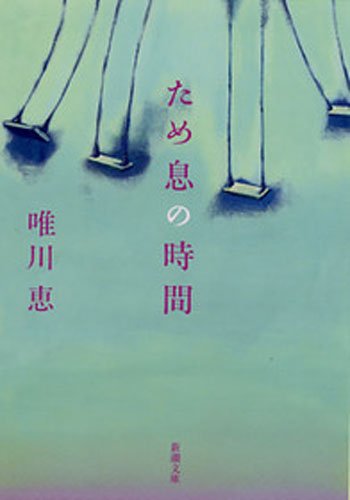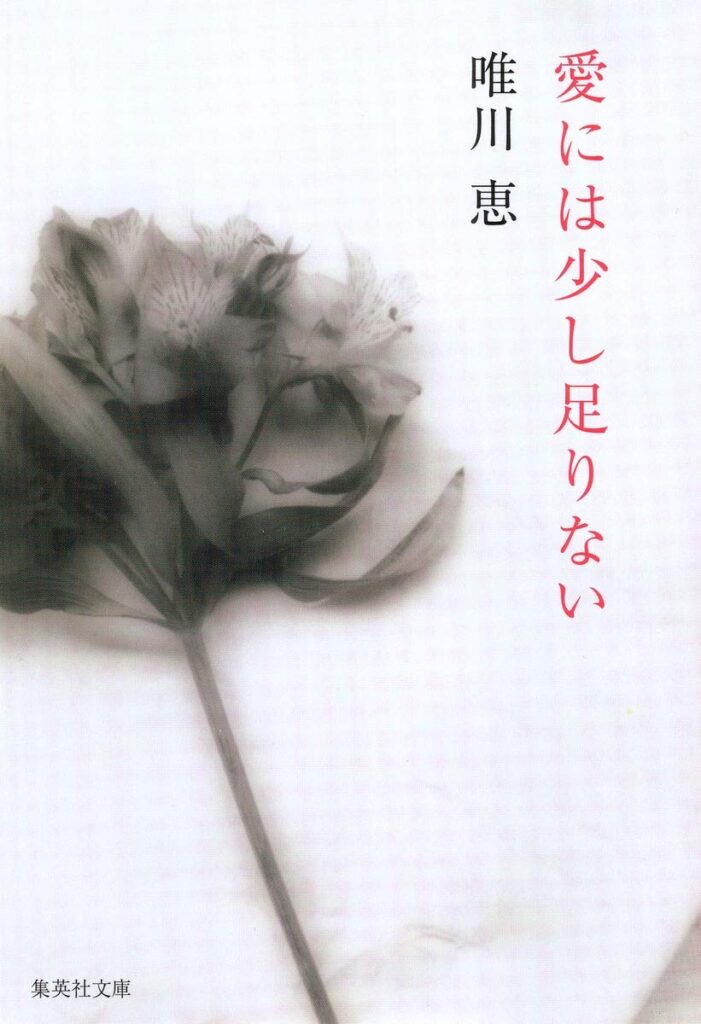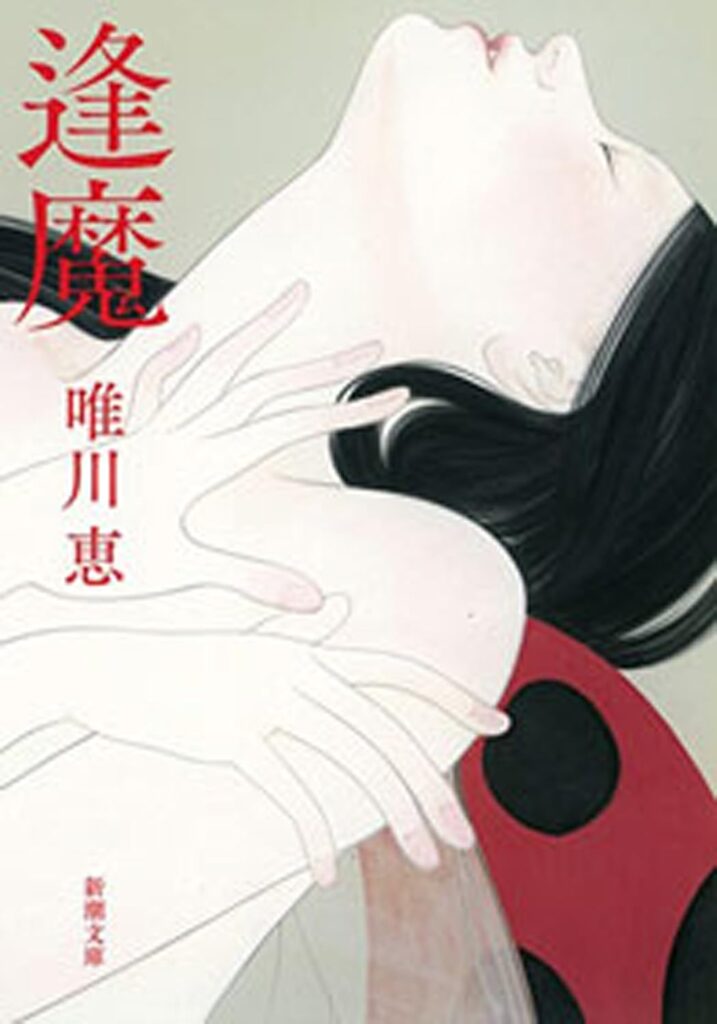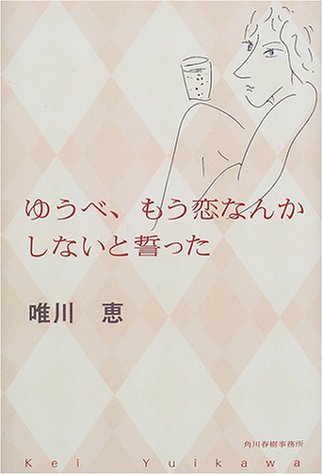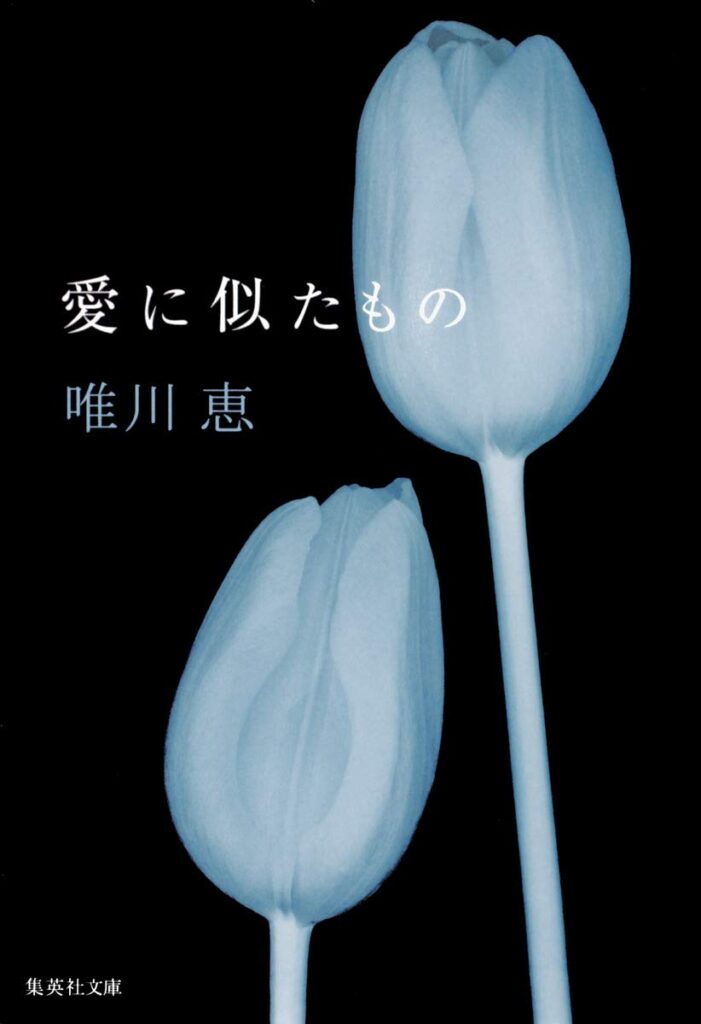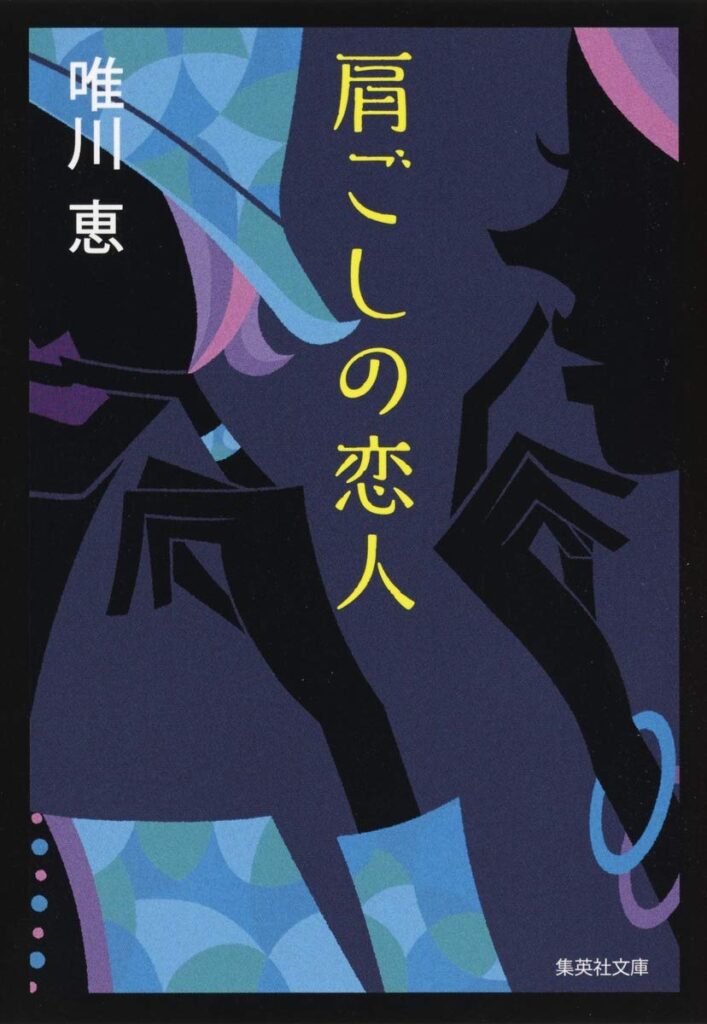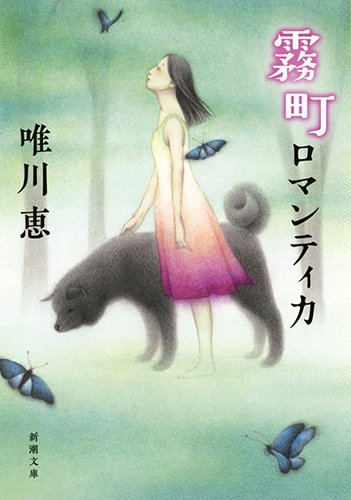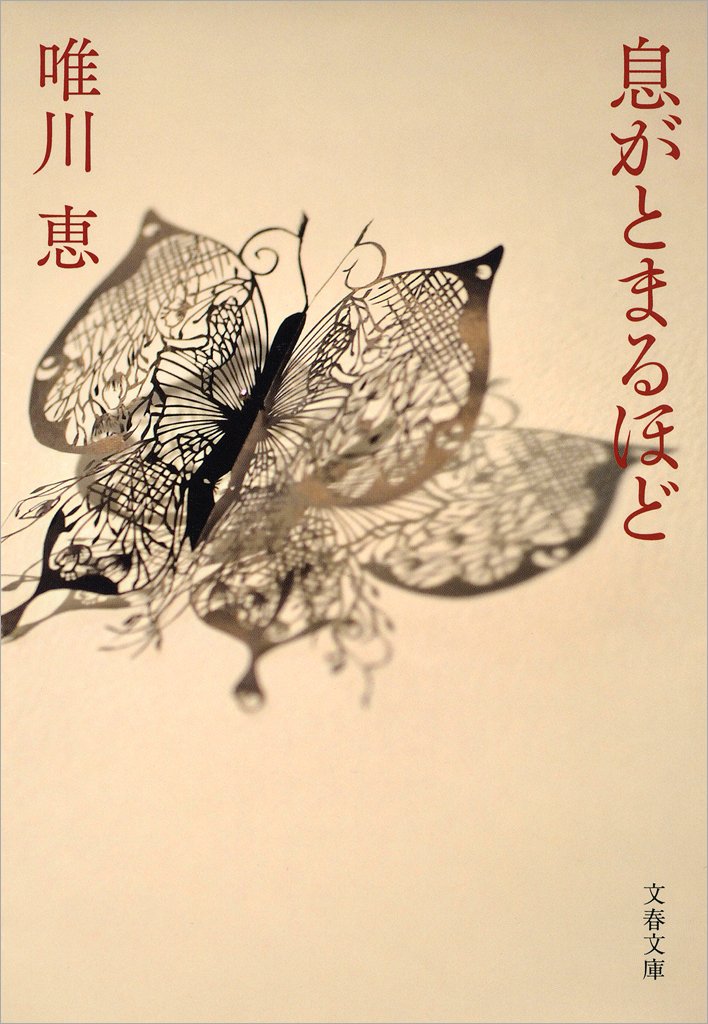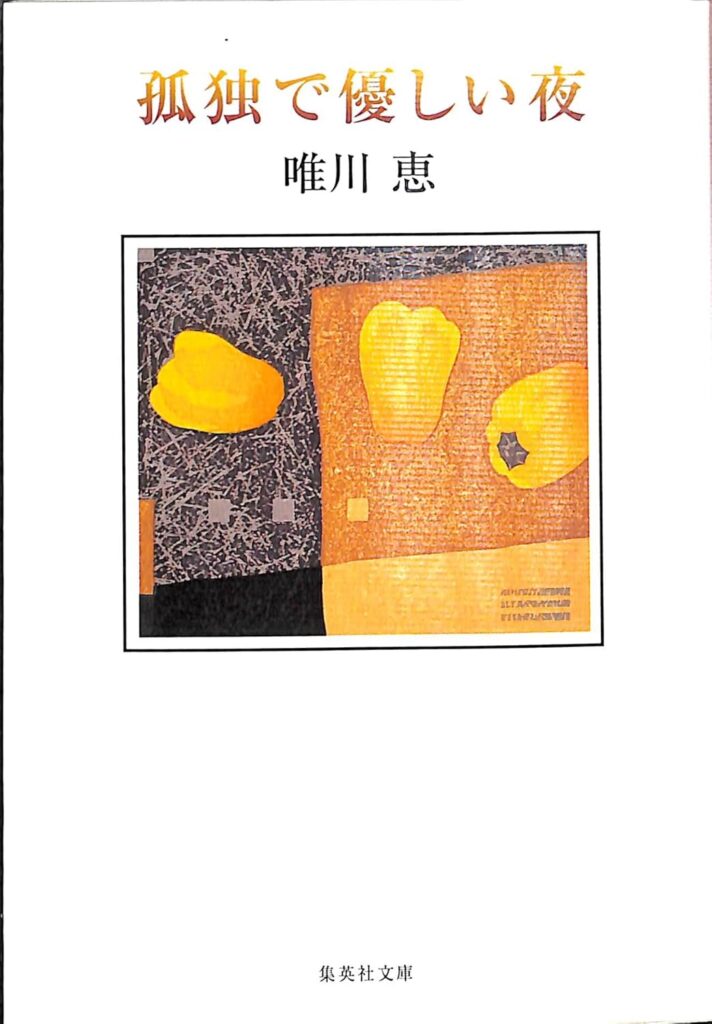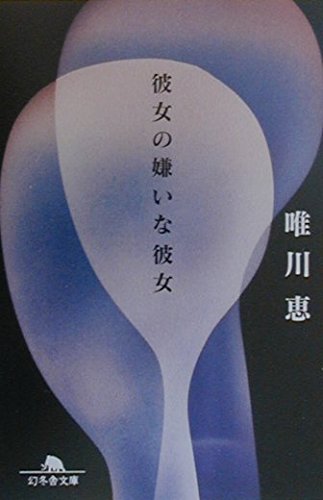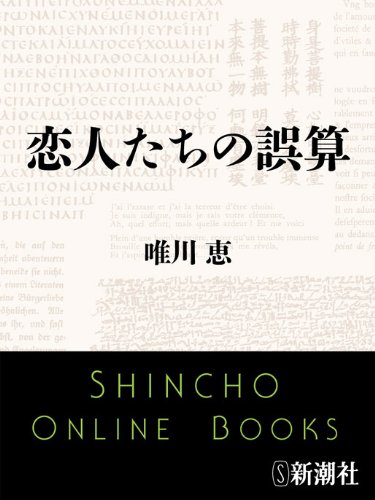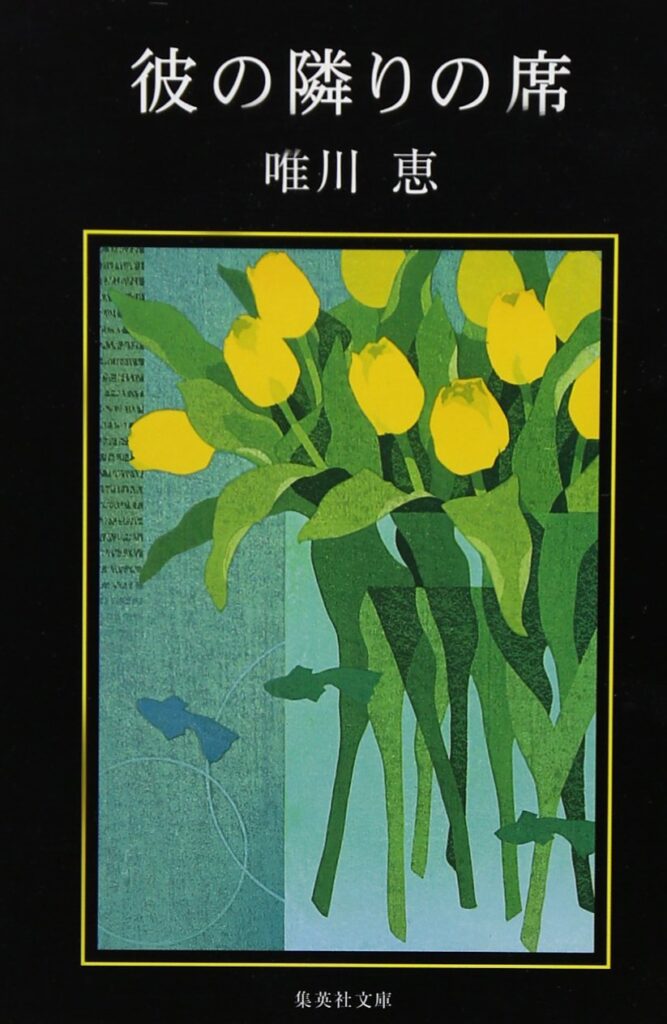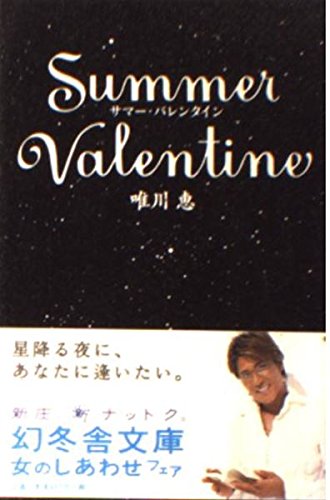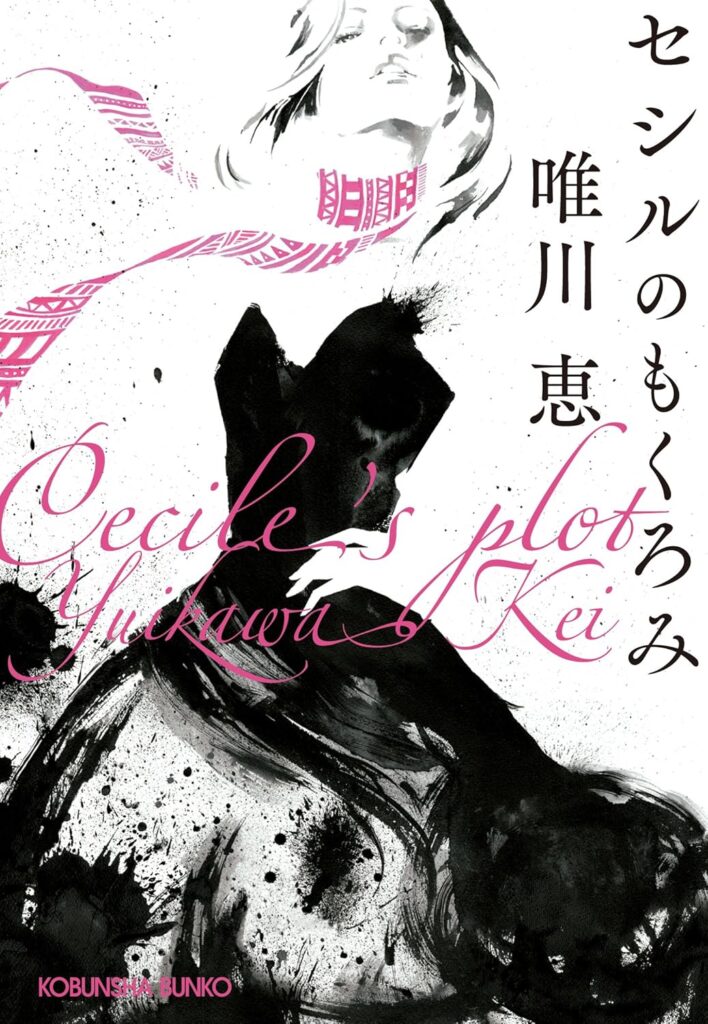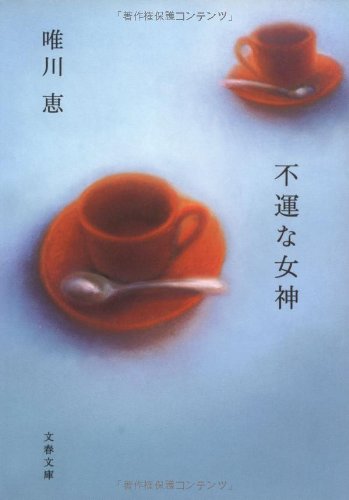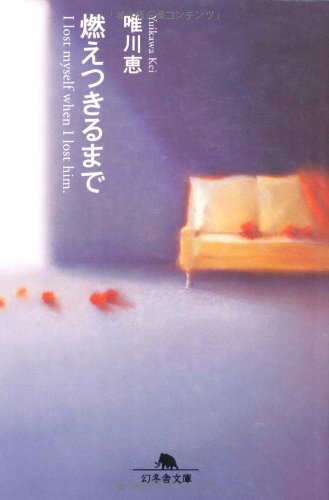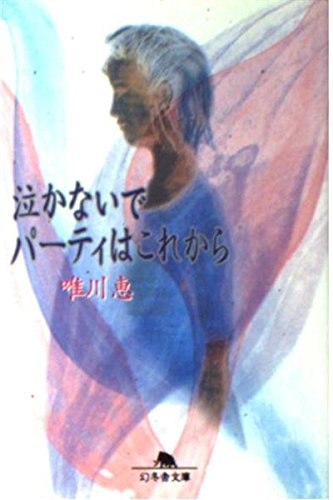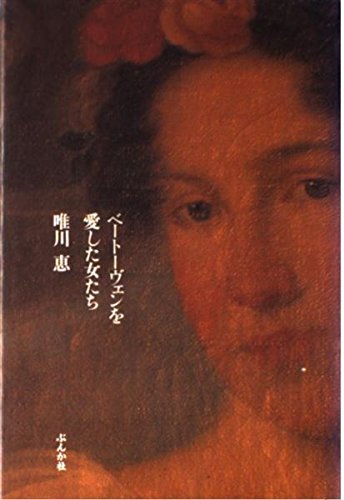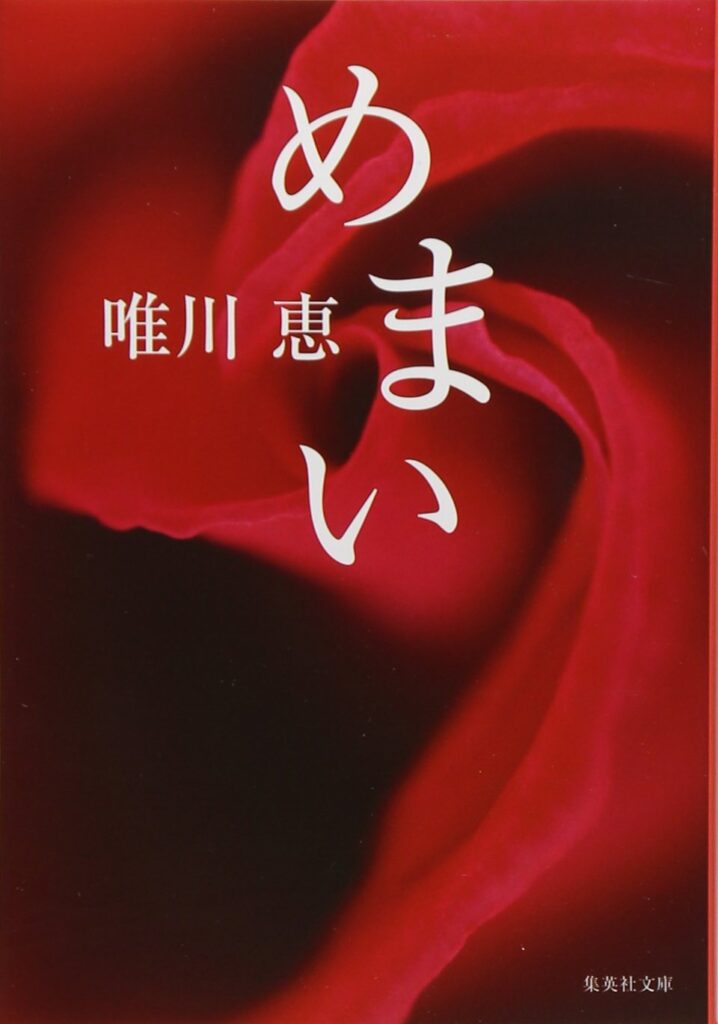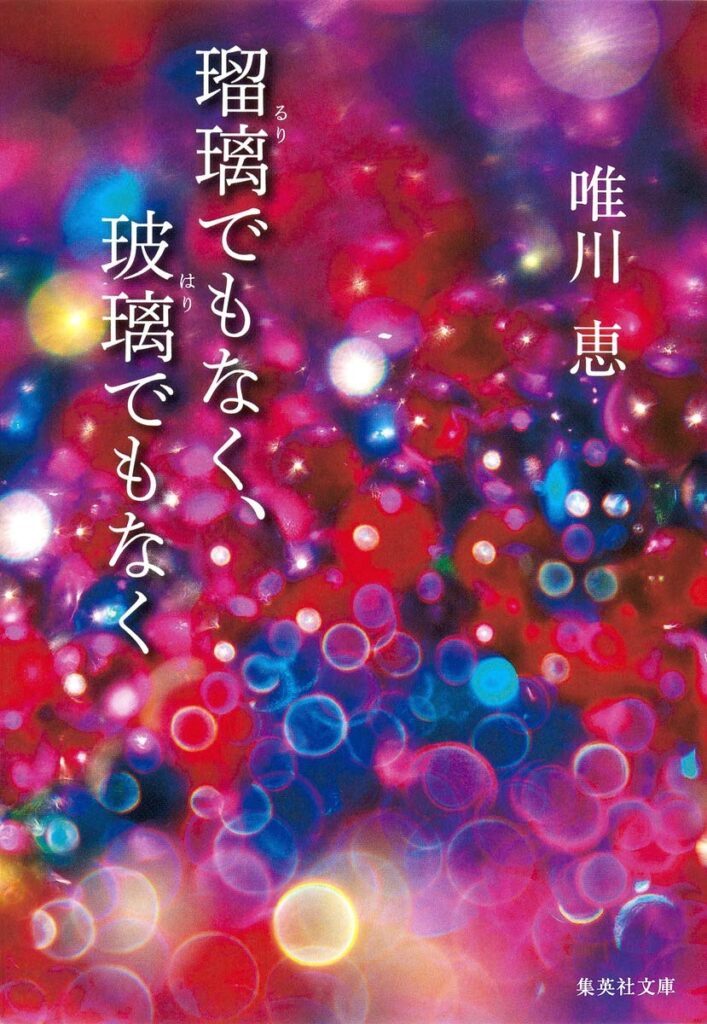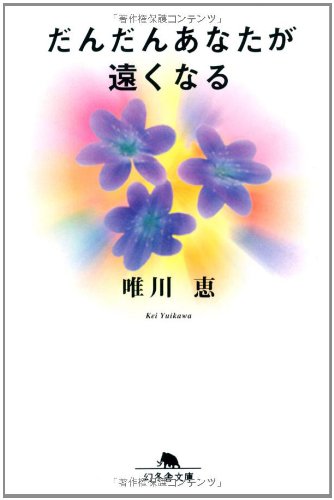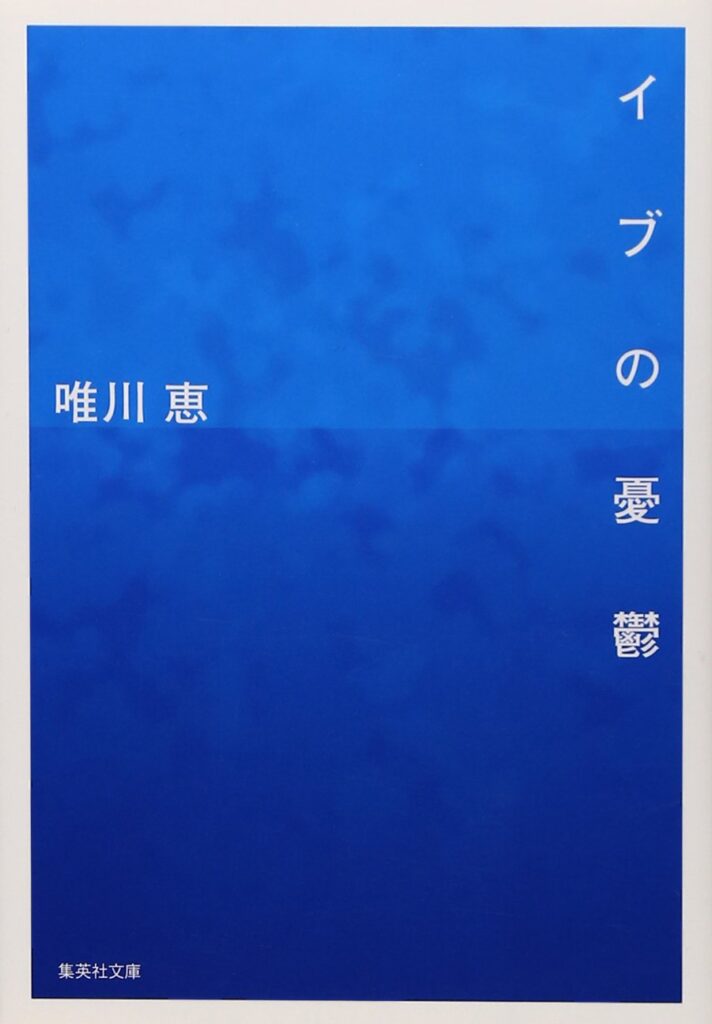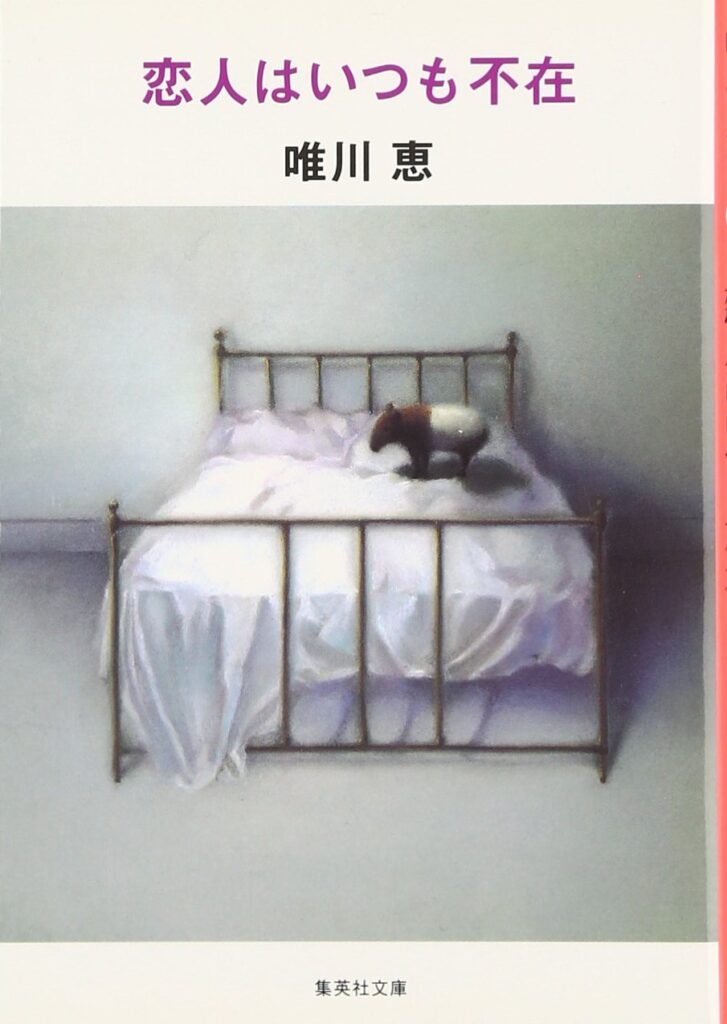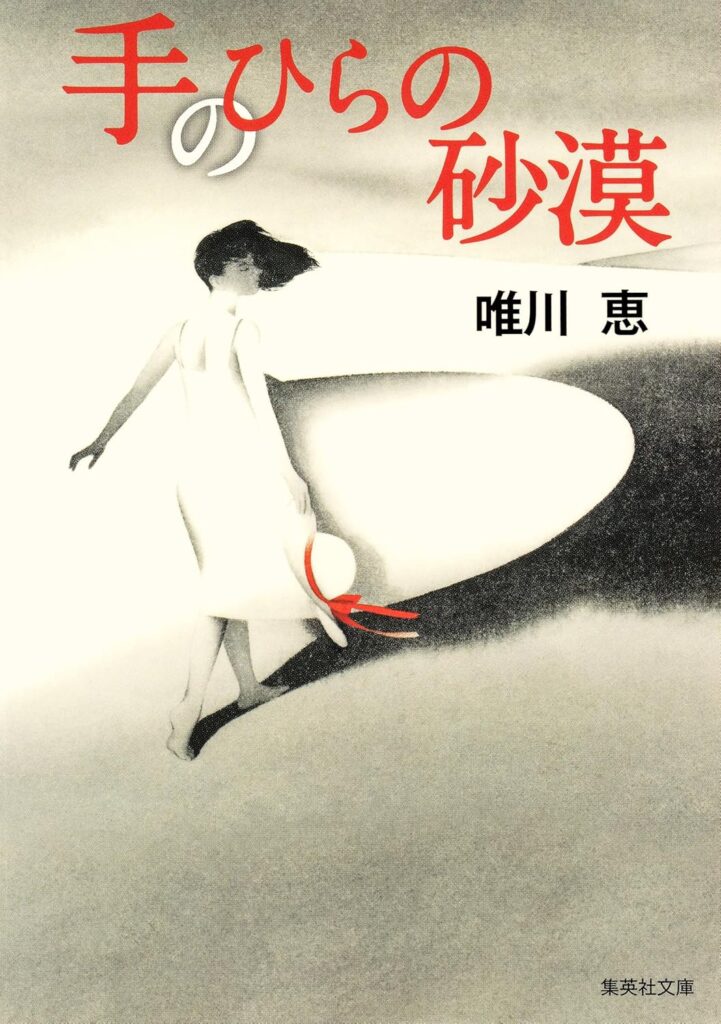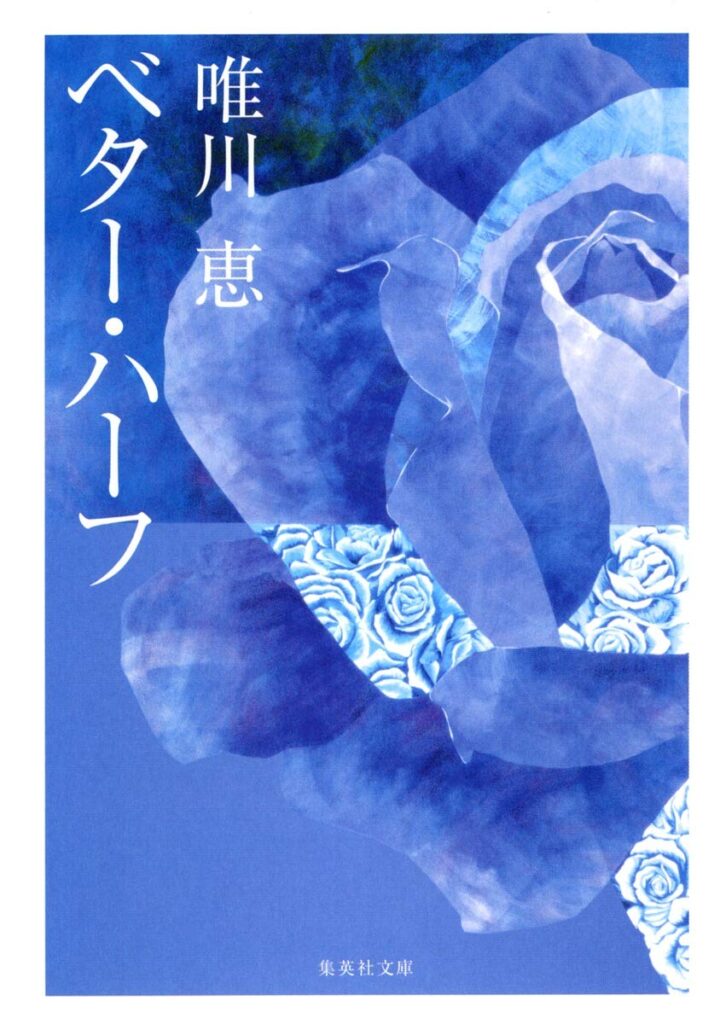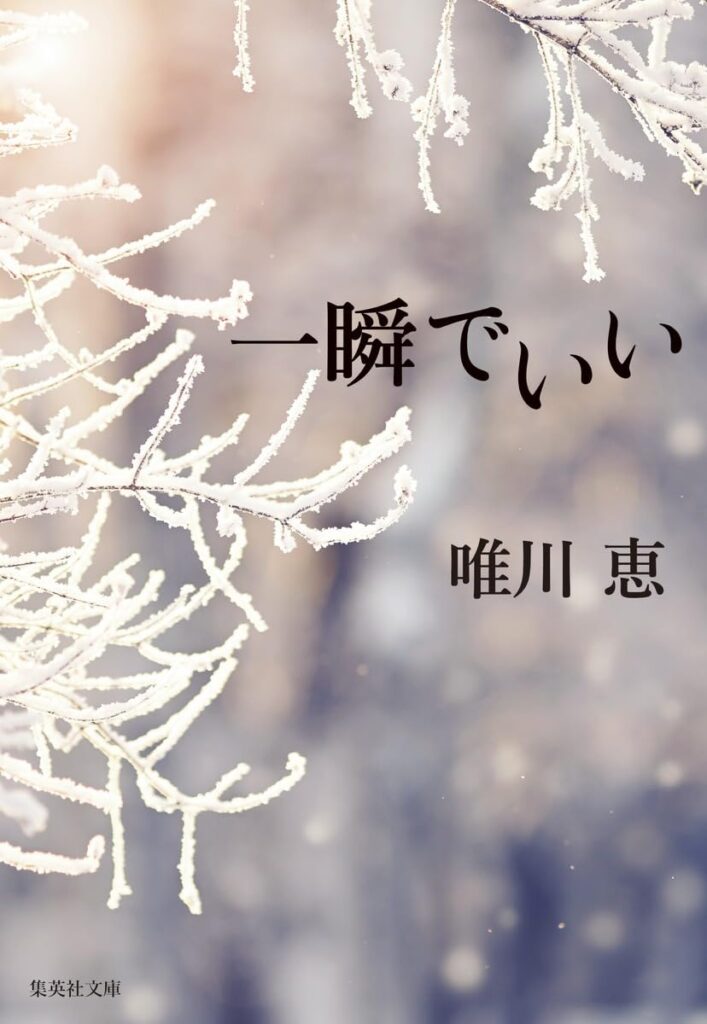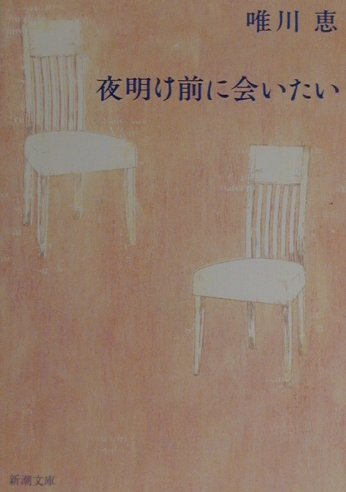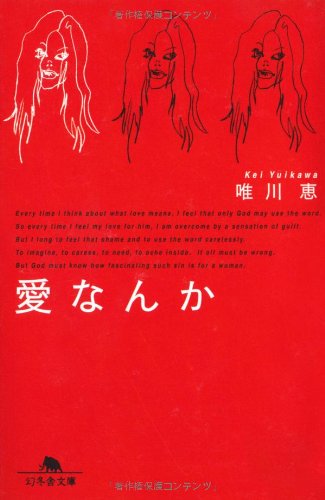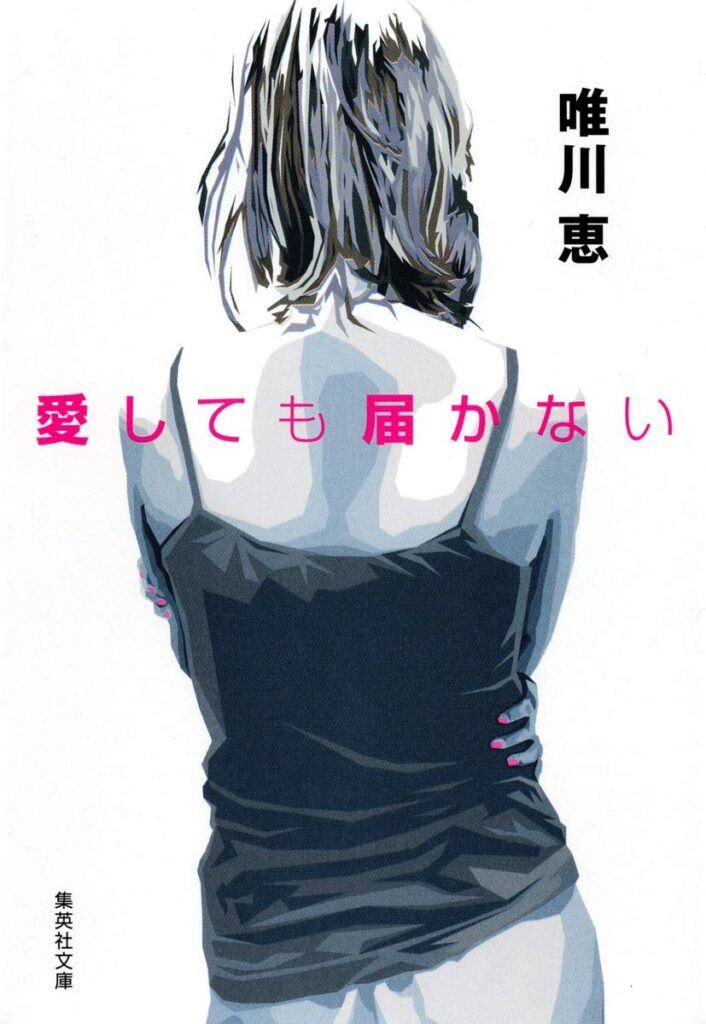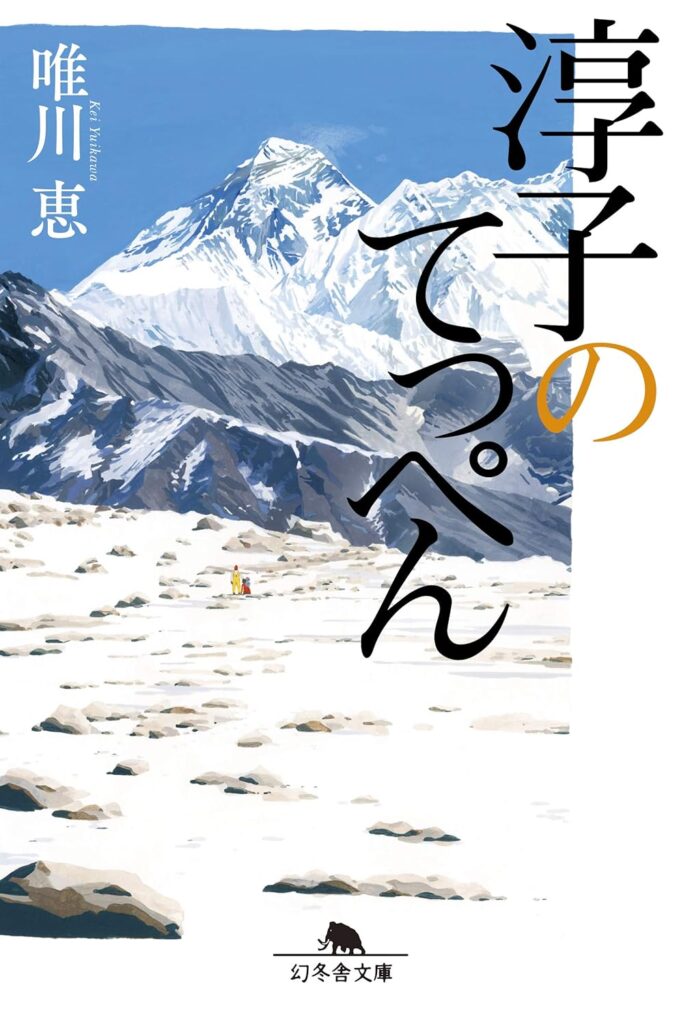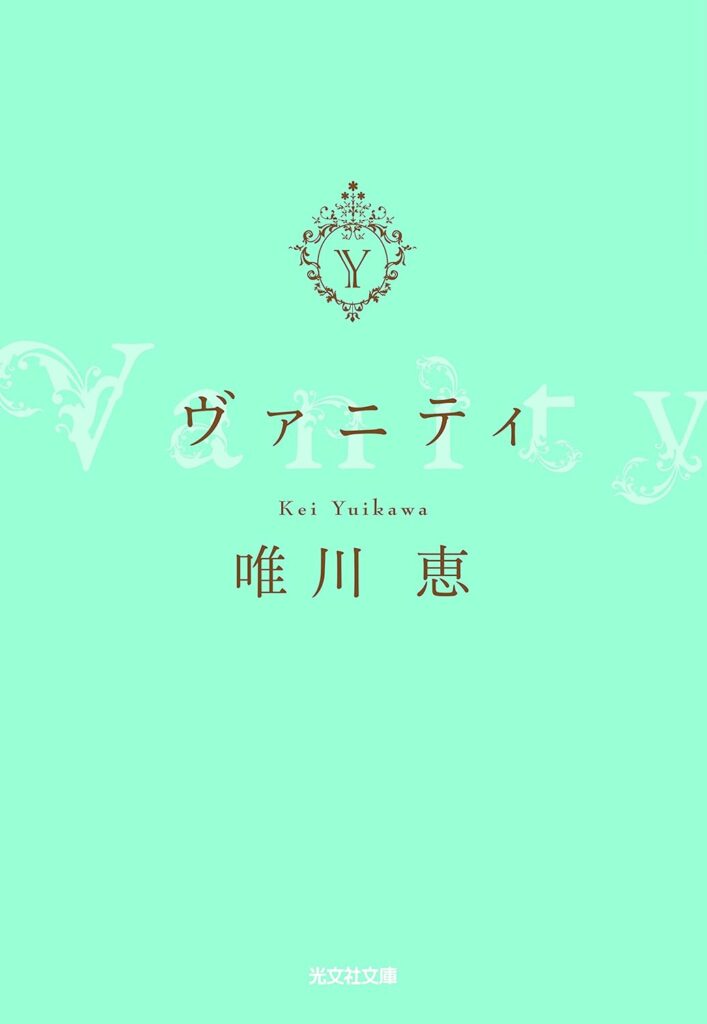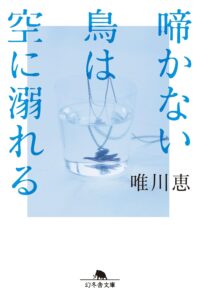 小説「啼かない鳥は空に溺れる」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「啼かない鳥は空に溺れる」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、読む者の心を深くえぐるような力を持っています。読み進めるうちに、登場人物たちが抱える心の闇、特に母と娘という関係性に潜む根深い呪縛に、息苦しささえ覚えるかもしれません。それはまるで、質の高い心理サスペンスを読んでいるかのような感覚です。
表面的な幸せの裏に隠された歪み、愛情という名の下に行われる支配。唯川恵さんが描き出す世界は、あまりにもリアルで、時に目を背けたくなります。しかし、その描写の巧みさゆえに、ページをめくる手が止まらなくなるのです。
この記事では、まず物語の導入部分となる概要を紹介し、その後、結末までを含んだ詳細な心の動きや物語の解釈を、たっぷりと語っていきたいと思います。この物語が投げかける問いに、一緒に向き合っていただけると嬉しいです。
小説「啼かない鳥は空に溺れる」のあらすじ
物語は、対照的な二人の女性、千遥(ちはる)と亜沙子(あさこ)を軸に進んでいきます。32歳の千遥は、愛人の援助で一見華やかな生活を送っていますが、その心は常に母親の影に支配されていました。幼い頃から続く母親からの精神的な虐待は、彼女の自己肯定感を奪い、買い物依存症という形で心の隙間を埋めさせています。
一方、27歳の亜沙子は、未亡人である母・紀枝と二人で暮らしています。父を早くに亡くし、母と支え合って生きてきたその関係は、傍目には理想的な母娘に見えます。しかし、その愛情は次第に亜沙子を縛り付ける息苦しい鎖となり、彼女の自立を阻んでいました。
そんな二人の人生が、それぞれ「婚約」という転機を迎えることで、静かに、しかし確実に軋みを上げていきます。千遥は、母親に認めさせるため、公認会計士となった年下の恋人・功太郎との結婚を目指します。亜沙子は、母親が勧めるままに、田畑という男との婚約を受け入れます。
この結婚という選択が、彼女たちを母親の呪縛から解き放つ希望となるのか、それとも更なる絶望へと突き落とすのか。二人の運命が交錯することなく、それぞれの家庭という密室で、物語は静かな狂気をはらみながら展開していくのです。
小説「啼かない鳥は空に溺れる」の長文感想(ネタバレあり)
この物語を読み終えたとき、心に残るのは爽快感ではなく、ずっしりと重たい鉛のような感情でした。これは単なる母娘の物語ではありません。人間の心の奥底に潜む闇、愛と支配の境界線を描ききった、一種の心理ホラーと言っても過言ではないでしょう。登場人物たちの息遣いや悲鳴が聞こえてくるような感覚に、何度も鳥肌が立ちました。
物語の主軸の一人、千遥。彼女の人生は、まさに母親という名の分厚い雲に覆われています。愛人の存在によってセレブのような生活を繕いながらも、その内面は驚くほどに脆く、常に母親の顔色を窺っています。彼女の行動原理は、ただ一つ。「母親に認められたい」。その一心に尽きるのではないでしょうか。
千遥の母親の言動は、読んでいて怒りを通り越して恐怖を覚えるほどです。それは、娘の人格を否定し、価値を貶め、精神的に支配し続ける、容赦のない言葉の暴力です。成人してなお、母を前にすると萎縮してしまう千遥の姿は、幼い頃からどれほど深く、癒えない傷を負わされてきたかを物語っています。この支配は、千遥の人生のあらゆる側面に影を落としています。
特に、彼女が抱える買い物依存症や、作中で語られる死産だった妹「ミハル」の存在は、その傷の深さを象徴しているように感じました。満たされない心を物で埋めようとする行為、そして、母親が理想としたかもしれない「完璧な子供」としてのミハルの影。生きている自分は常に欠陥品であると、無意識に思い込まされている。その構図はあまりにも残酷です。
もう一人の主人公、亜沙子は、千遥とはまた違った形で母親の呪縛に囚われています。彼女と母・紀枝の関係は、一見すると愛情深く、理想的にさえ見えます。週末のランチを共に楽しむなど、仲の良い母娘そのものです。しかし、この親密さこそが、亜C沙子の首を真綿で締めるように、ゆっくりと彼女の自由を奪っていくのです。
亜沙子の母・紀枝の支配は、千遥の母のような直接的な暴力とは異なります。愛情や心配、時には仮病といった巧妙な手段を用いて、娘を自分の手元に縛り付けようとします。娘のブログを勝手に飾り立てて「幸せな母娘」を演出し、自己の価値を確認する姿には、歪んだ自己愛が見え隠れします。この「愛」という名の支配は、目に見えない分、より根が深く、抜け出すのが困難なのかもしれません。
この二人の母親像は実に対照的です。片や、激しい言葉で娘を支配する独裁者のような母。片や、優しい仮面の下で娘を精神的に束縛する母。しかし、その方法は違えど、娘の人生を自分の所有物とみなし、その成長と自立を阻んでいるという点では同質です。どちらも「毒母」という言葉では足りないほどの、強烈な毒性を持っています。
物語が大きく動くきっかけ、それは「結婚」です。千遥にとって、恋人である功太郎が公認会計士という難関資格に合格したことは、一筋の光でした。「この相手なら、母を満足させられるかもしれない」。彼女のこの願いは、愛というよりも、母親からの承認を得るための最後の切り札に近いものだったのでしょう。
功太郎という青年は、野心家でありながら、どこか押しに弱い部分も感じさせます。彼が千遥の希望の星となる一方で、その関係がいかに脆い基盤の上に成り立っているかを予感させました。千遥の根深い問題は、結婚相手のスペックで解決できるほど単純なものではないからです。
一方の亜沙子にとっての結婚は、主体的な選択ではありません。「母がいいという相手だし、とくに嫌なところもないし」。この言葉に、彼女の母親への完全な服従が見て取れます。自分の意志で人生を切り開くことを、いつの間にか諦めてしまっているのです。
母親が紹介した婚約者の田畑。彼は「おとなしい男」と表現されますが、その実態は物語が進むにつれて明らかになります。彼の存在は、母親の判断がいかに娘の幸福ではなく、自分の都合を優先しているかの証明であり、亜沙子を待ち受ける恐怖の序章に過ぎませんでした。
物語の終盤、千遥はついに限界を迎え、母親に対して積年の感情を爆発させます。しかし、その対決が彼女を解放することはありませんでした。功太郎との結婚は破綻し、希望の光は消え失せます。この崩壊は、彼女が母親の呪縛から逃れることの絶望的な困難さを突きつけます。
そして、千遥が迎える結末は、この物語が「ホラー」であると確信させるものでした。彼女は、あれほど憎んだ母親の介護者として、再びその支配下に戻ってしまうのです。そして、おそらくは穏やかな表情さえ見せ始めた娘に対し、母親が最期に放つ「泣けば… 許されると… 思うな」という言葉。この一言が持つ破壊力は凄まじく、読者の心に冷たい爪痕を残します。それは、死してなお続く呪縛の宣告でした。
亜沙子の物語もまた、衝撃的な展開を迎えます。婚約者・田畑が持つ、児童ポルノという到底受け入れがたい秘密を知ってしまうのです。このおぞましい事実が、彼女を母親の言いなりだった自分から目覚めさせるきっかけとなります。婚約を破棄しようとする亜沙子に対し、母・紀枝が見せる反応は狂気そのものでした。
仮病を使い、自殺まで仄めかして娘を引き留めようとする母親。娘の幸福よりも、自分の元から離れていくことへの恐怖が勝るのです。この母親の執着を目の当たりにし、亜沙子はついに「母を棄てて逃げる」という選択をします。一見すると、彼女は呪縛から逃れ、自由を手にしたかのように思えます。
しかし、物語は亜沙子に単純なハッピーエンドを与えはしません。彼女がその後、千遥の元婚約者であった功太郎に接近していく様子には、どこか危うさが漂います。母親から受けた影響なのか、彼女自身の中にもまた、他者をコントロールしようとするような歪みが生まれてしまったのではないか。そう感じさせる、不穏な余韻が残ります。
この小説のタイトル「啼かない鳥は空に溺れる」は、まさに二人の主人公の姿そのものを表しているのでしょう。自分の心を殺し、苦しみを声に出すこと(啼くこと)ができない鳥は、自由の象徴であるはずの空で、息ができずに溺れてしまう。母親が作り出した歪んだ空の下で、彼女たちはもがき、沈んでいくのです。
この物語は、千遥と亜沙子という二人の女性の視点から、母と娘という関係の極限を描ききっています。彼女たちの運命は交わることなく、それぞれが密室の中で苦しみ続けます。その対照的な結末は、毒親が残す傷跡からの回復がいかに困難であるかを、私たちに容赦なく見せつけるのです。これは、読む人によっては、自身の経験と重なり、深い痛みを感じるかもしれません。しかし同時に、「この苦しみは自分だけではなかった」という、ある種の救いを感じる人もいるのではないでしょうか。美化されがちな母娘の絆の裏に潜む、暗く、複雑な真実を抉り出した傑作だと思います。
まとめ
唯川恵さんの「啼かない鳥は空に溺れる」は、母と娘の関係性に潜む「呪縛」と「依存」という重いテーマを、息をのむような筆致で描ききった作品でした。二人の主人公、千遥と亜沙子が、それぞれの母親から受ける異なる形の精神的支配に苦しむ姿は、読んでいて胸が締め付けられます。
物語は、彼女たちが迎える衝撃的な結末まで、一切の救いや甘えを許しません。特に、絶望的な状況に囚われ続ける千遥の運命と、母親の呪縛から逃れたかに見えて、その先に危うさを感じさせる亜沙子の未来は、深く心に残ります。
この物語の読後感は、決して明るいものではないかもしれません。しかし、家族という最も身近な存在が時に牙をむくという現実、そして愛情という名の支配がもたらす悲劇を、これほどまでにリアルに描いた作品は稀有だといえます。
人間の心の深淵を覗き込むような、強烈な読書体験を求める方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。きっと、忘れられない物語になるはずです。