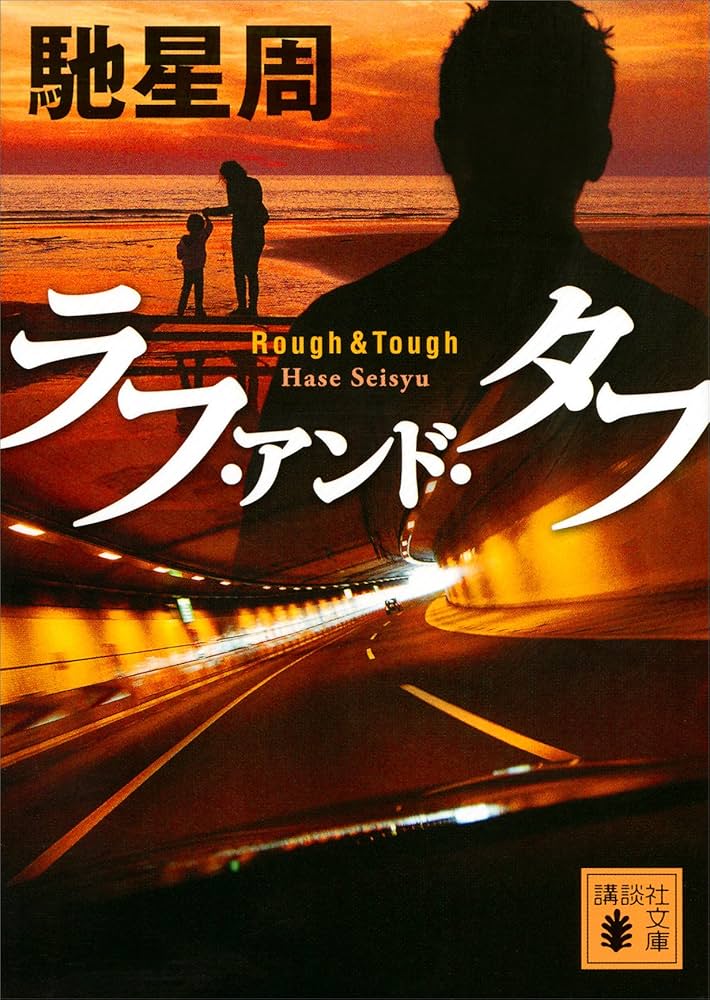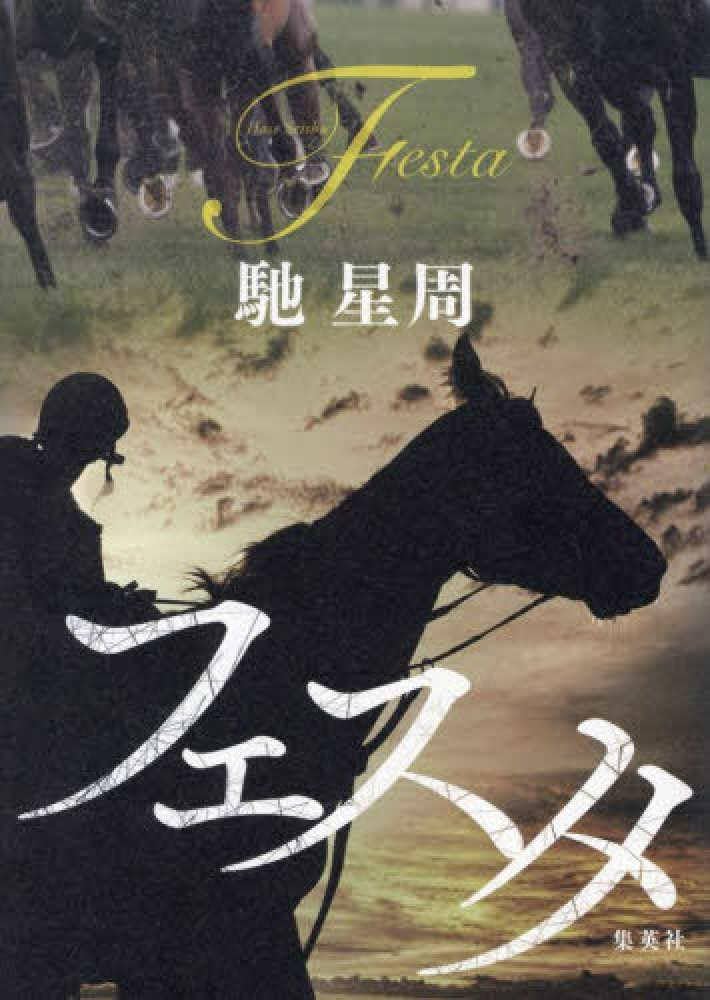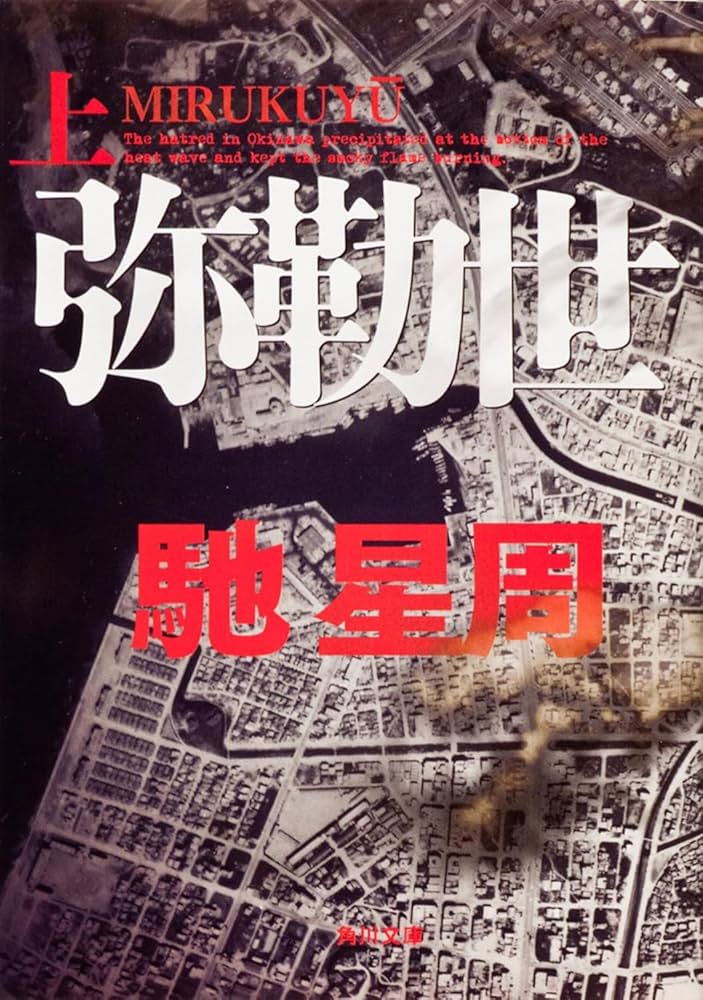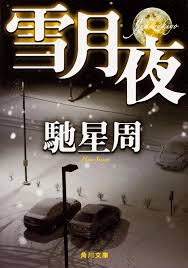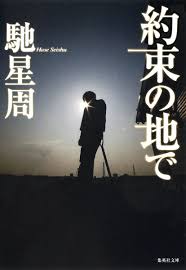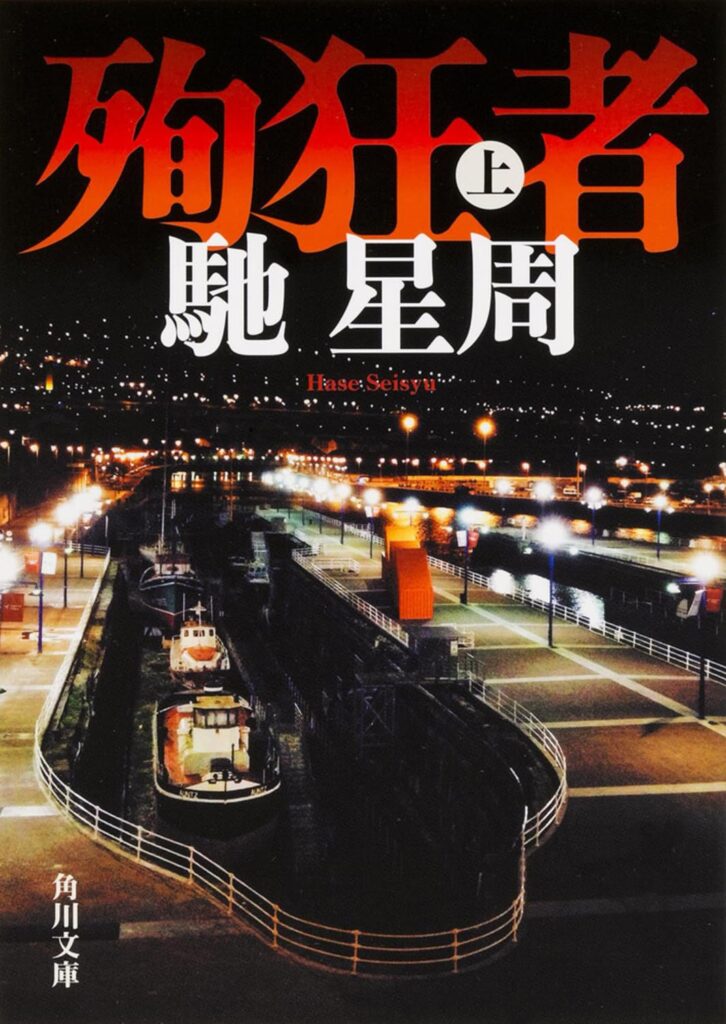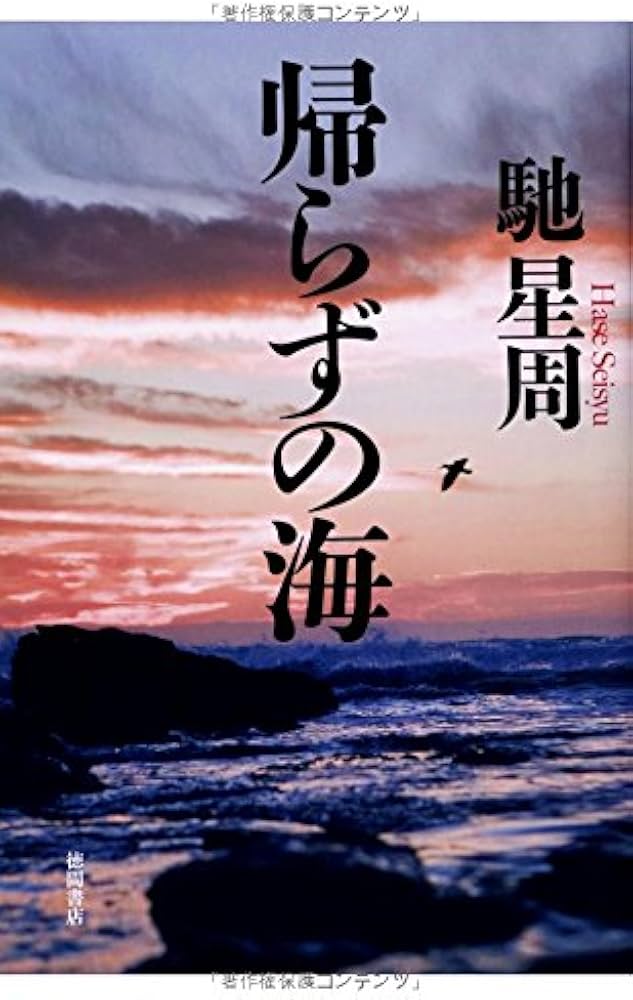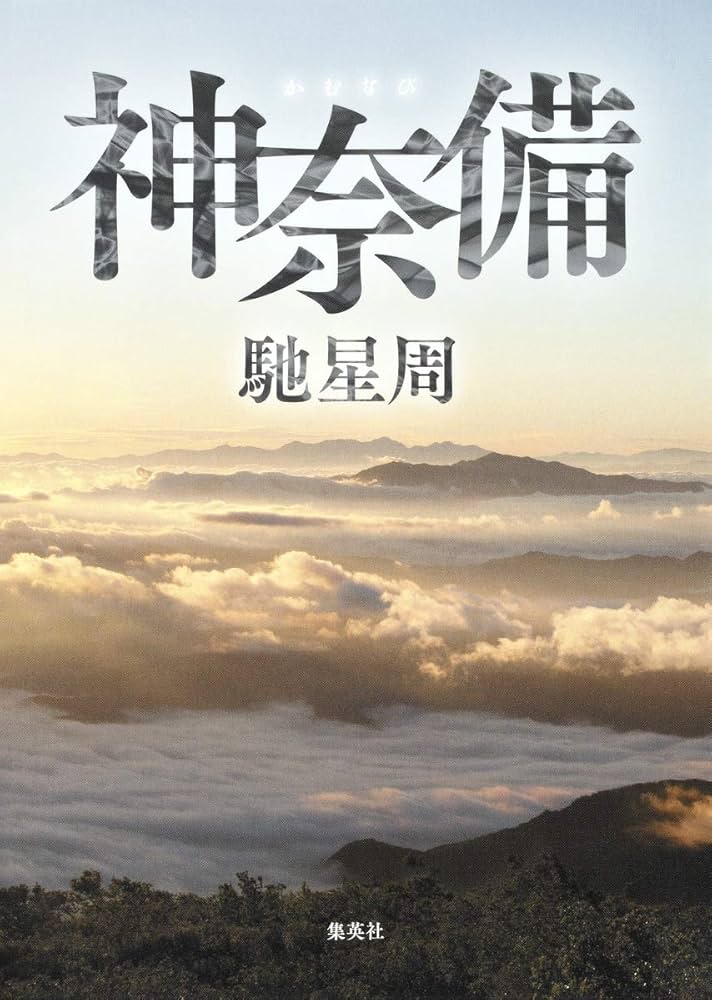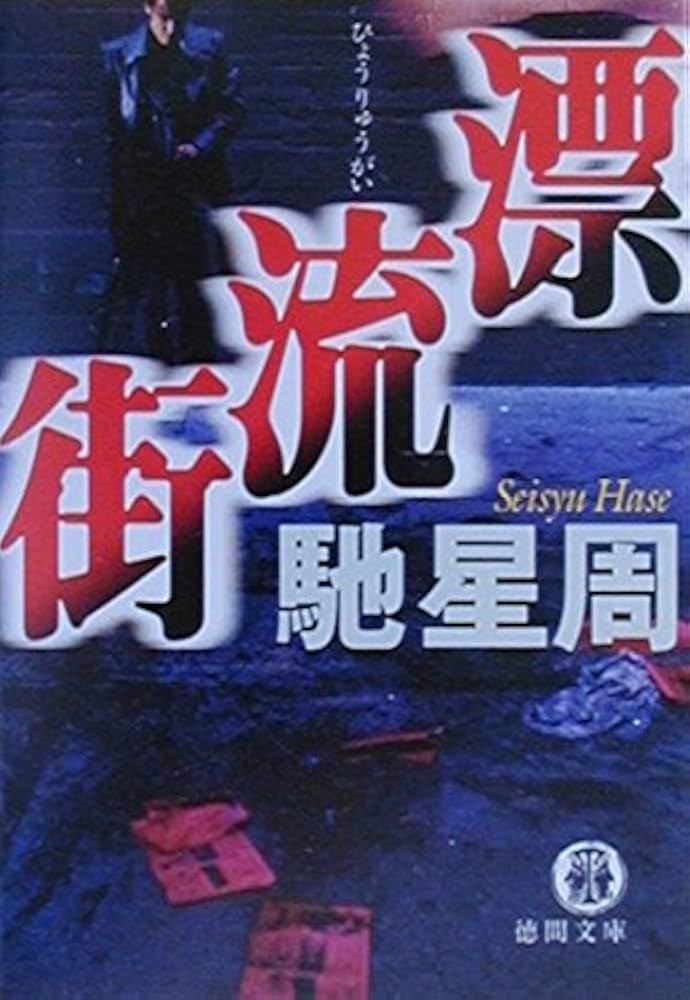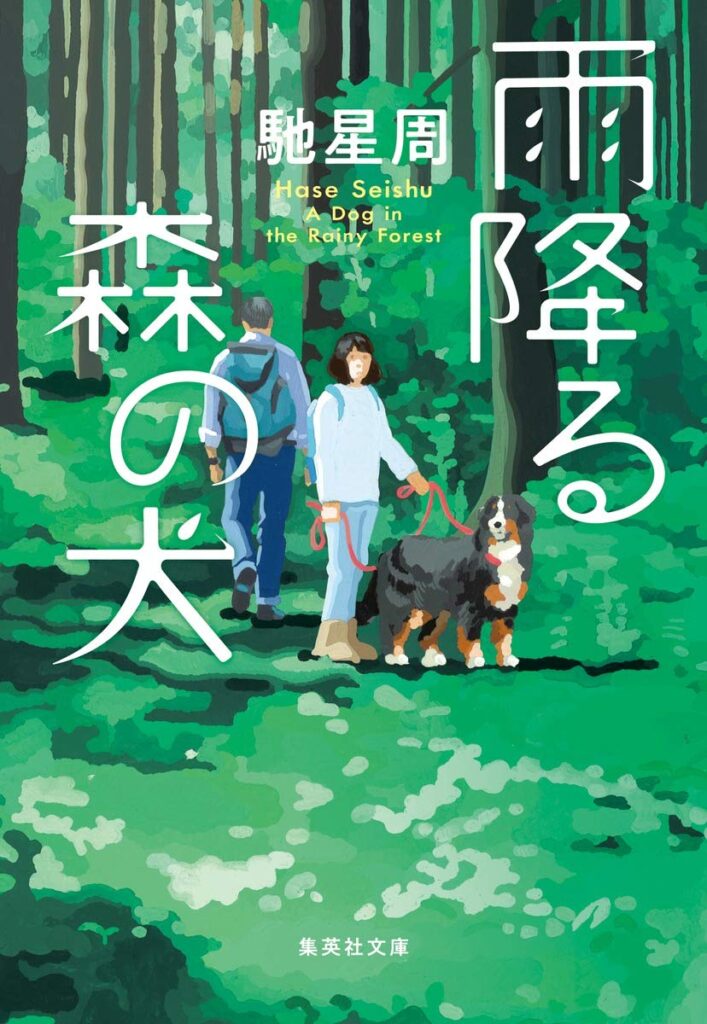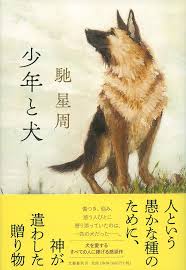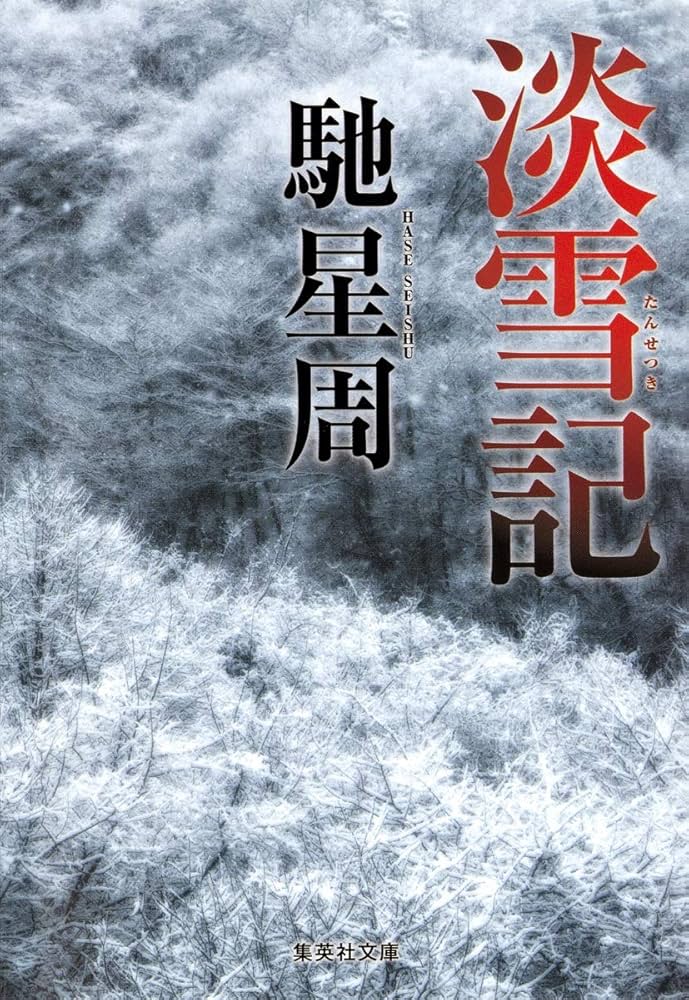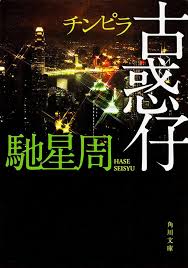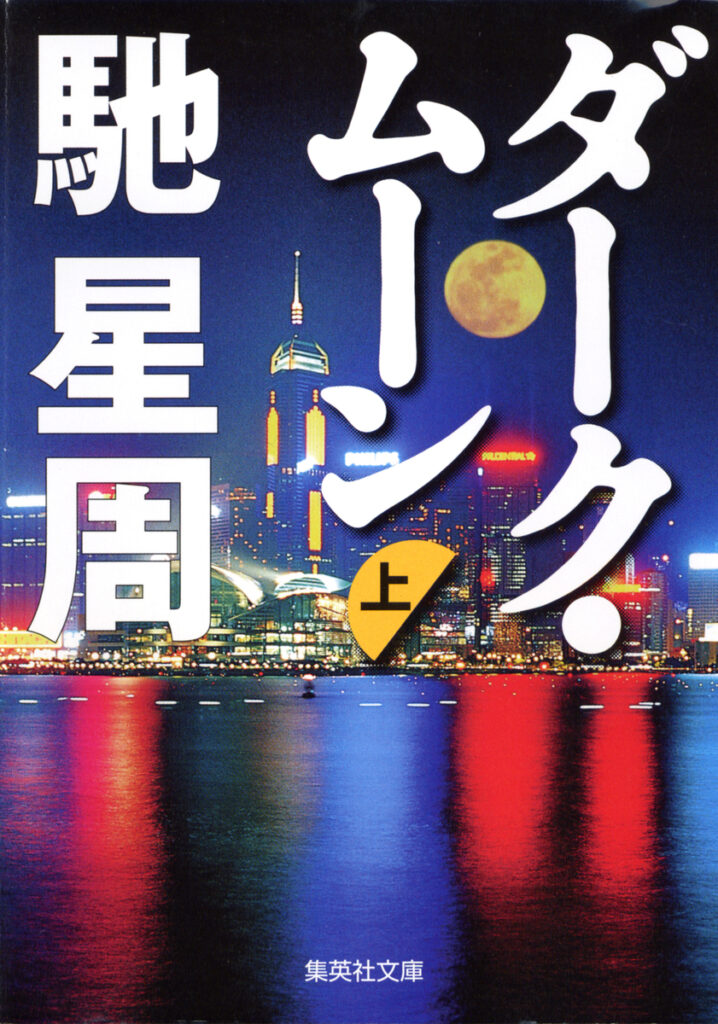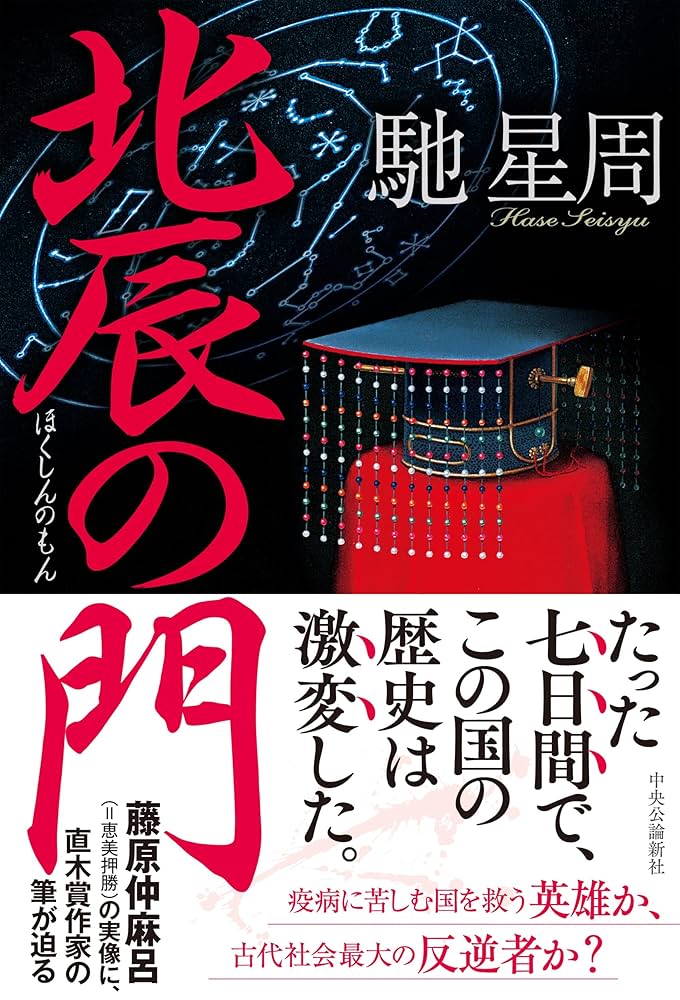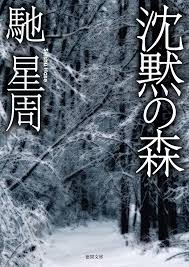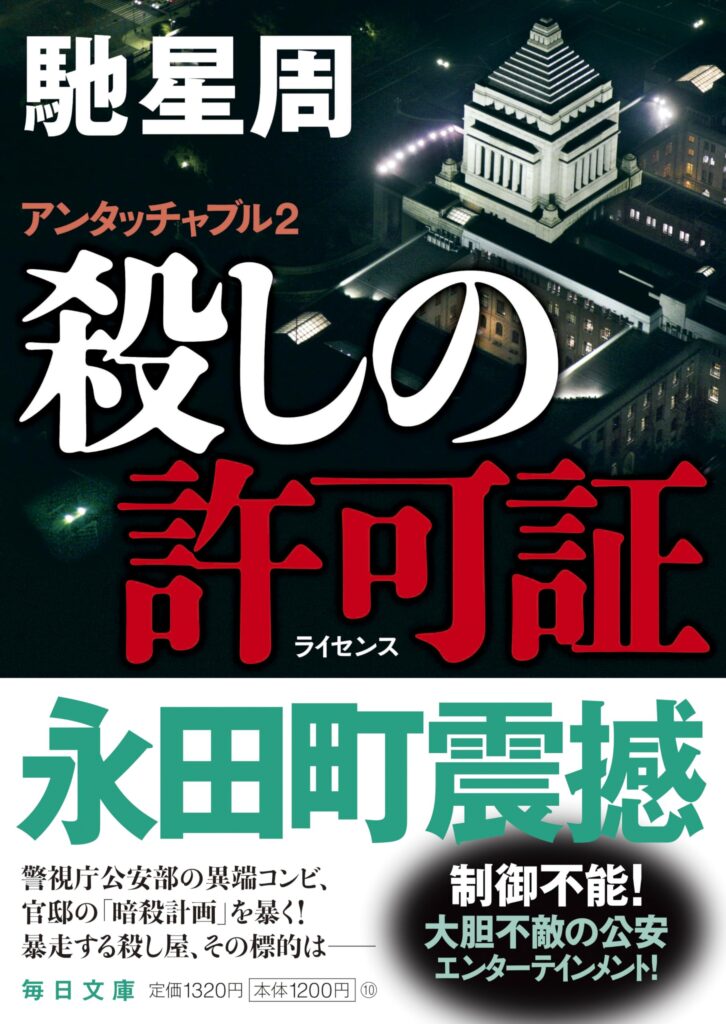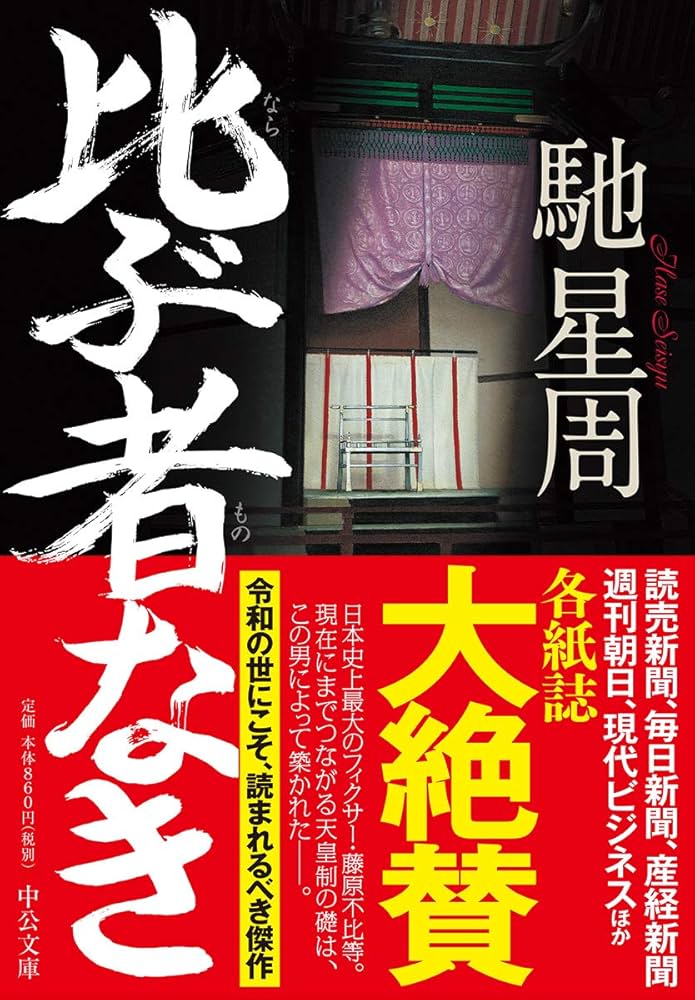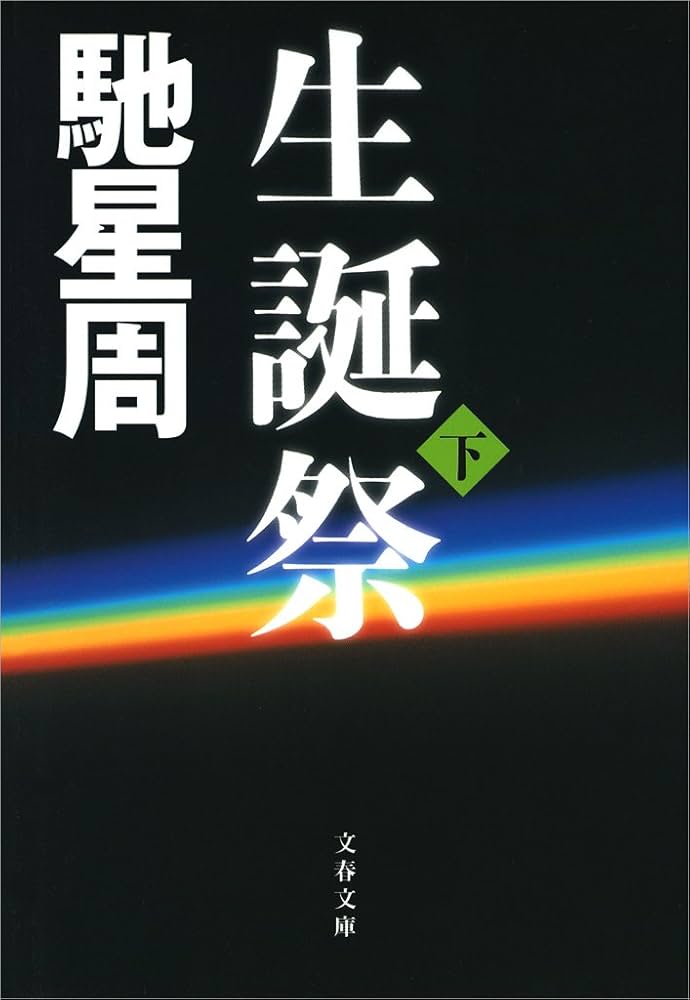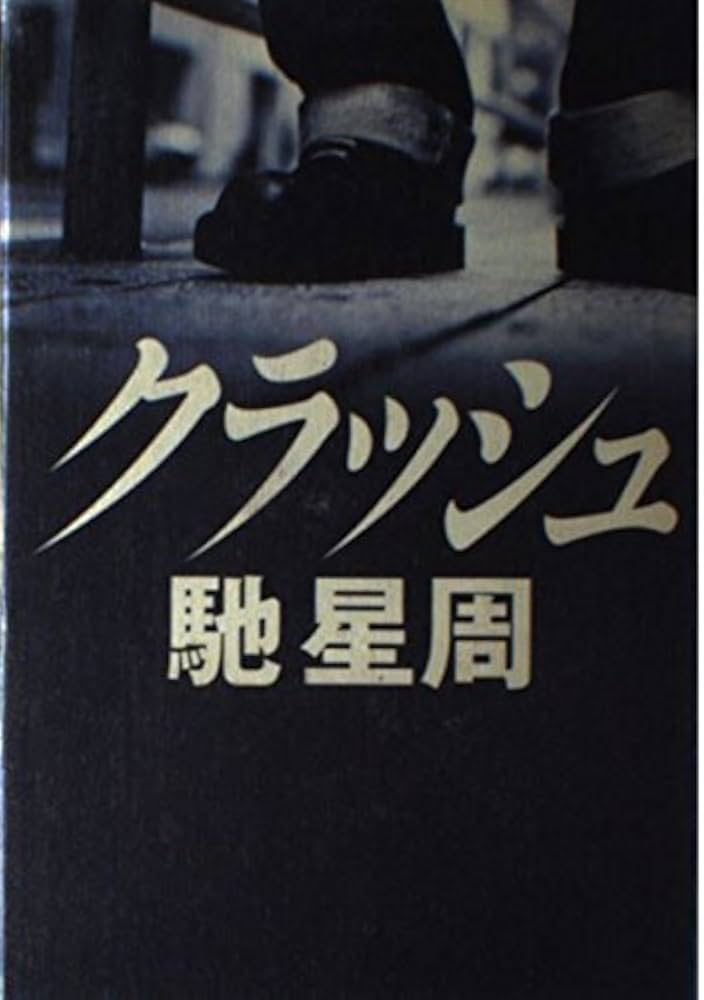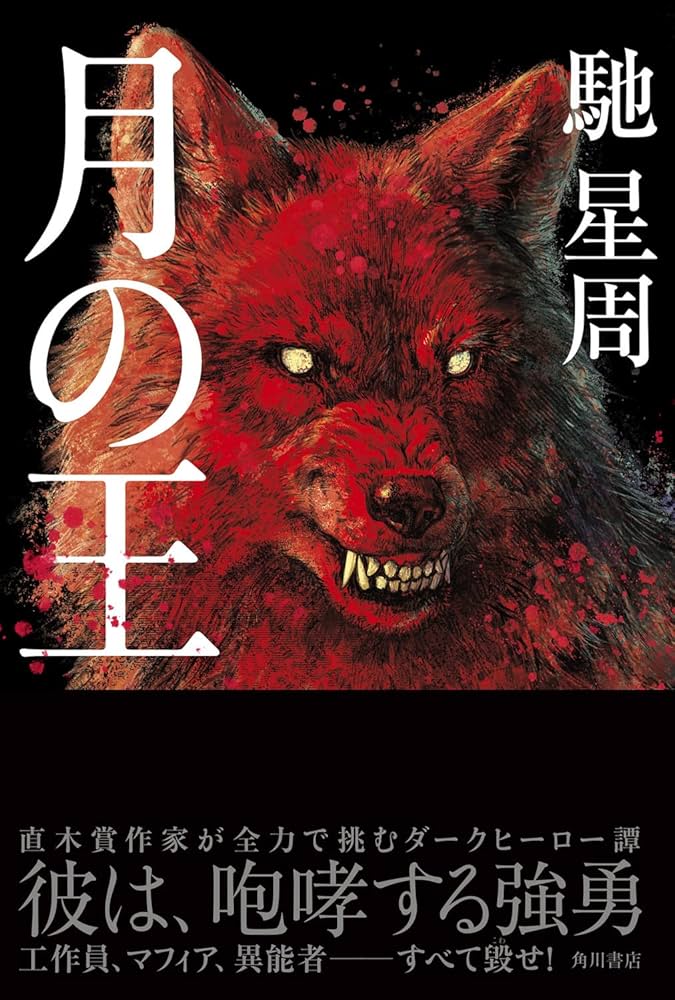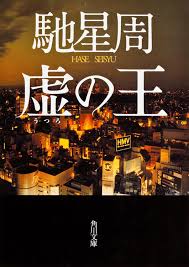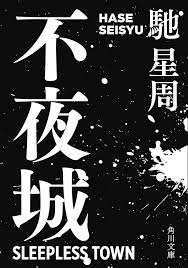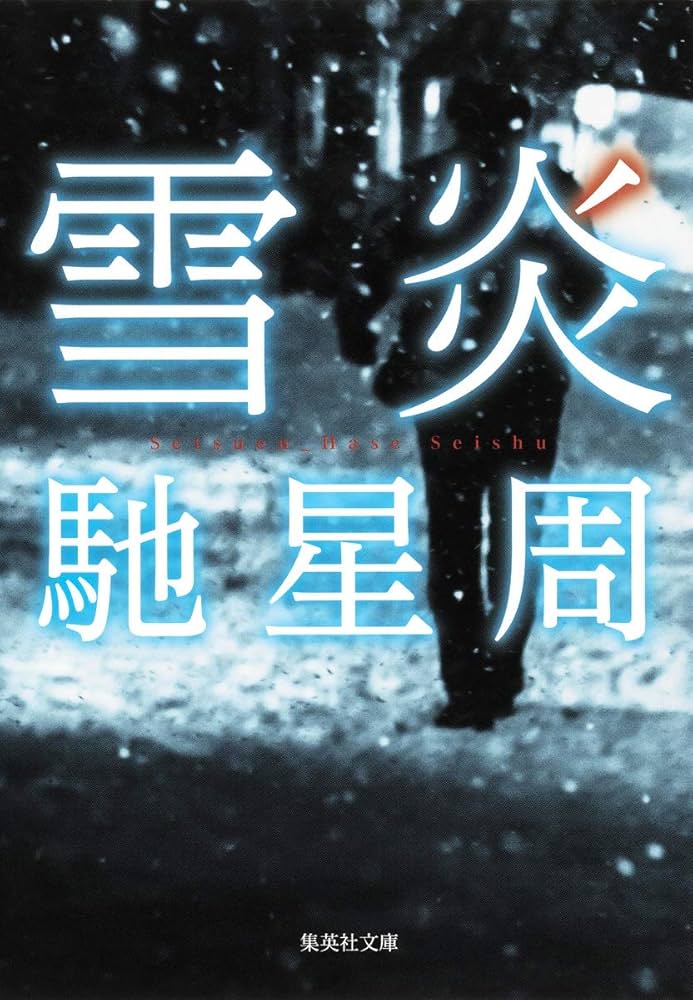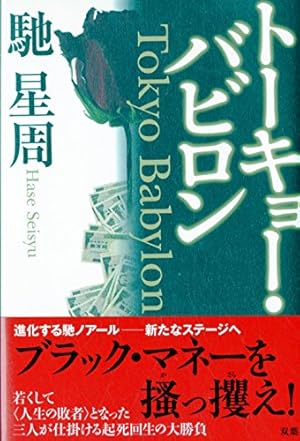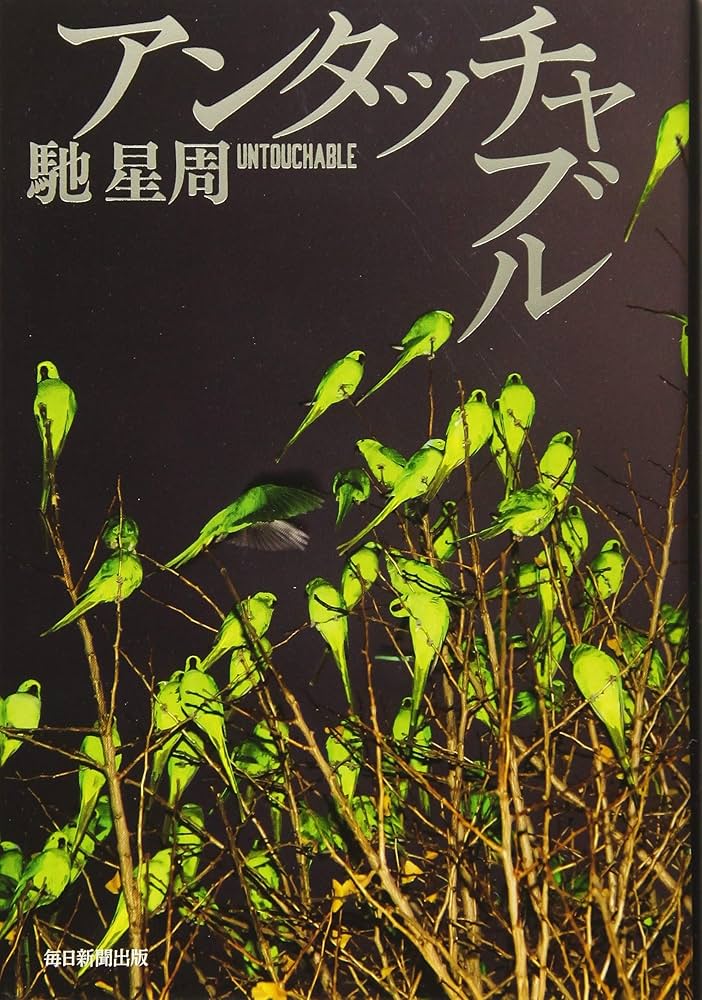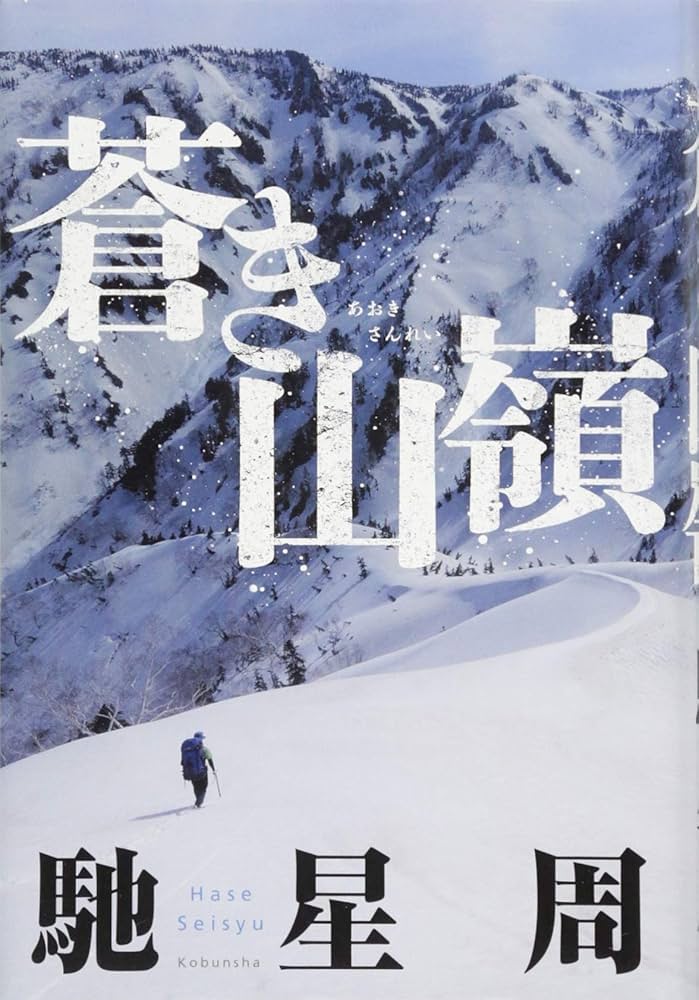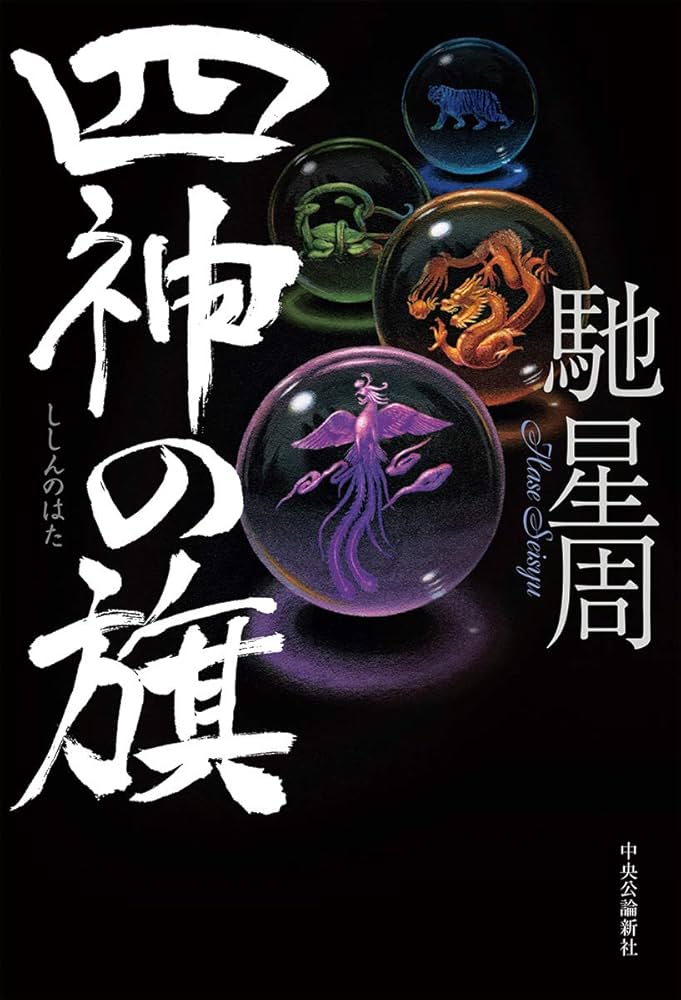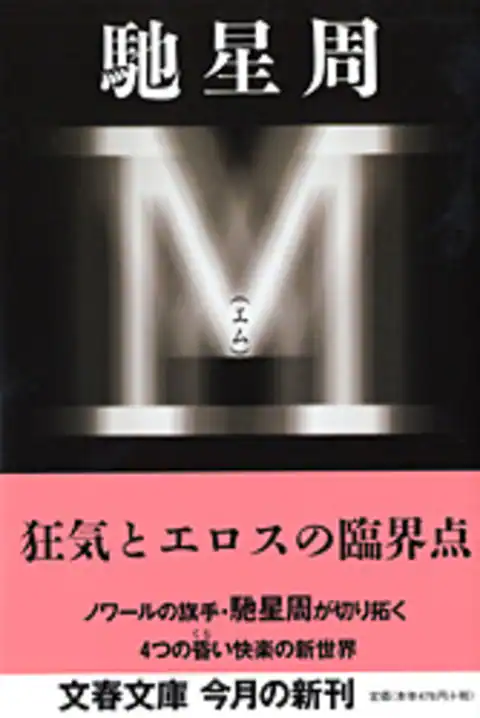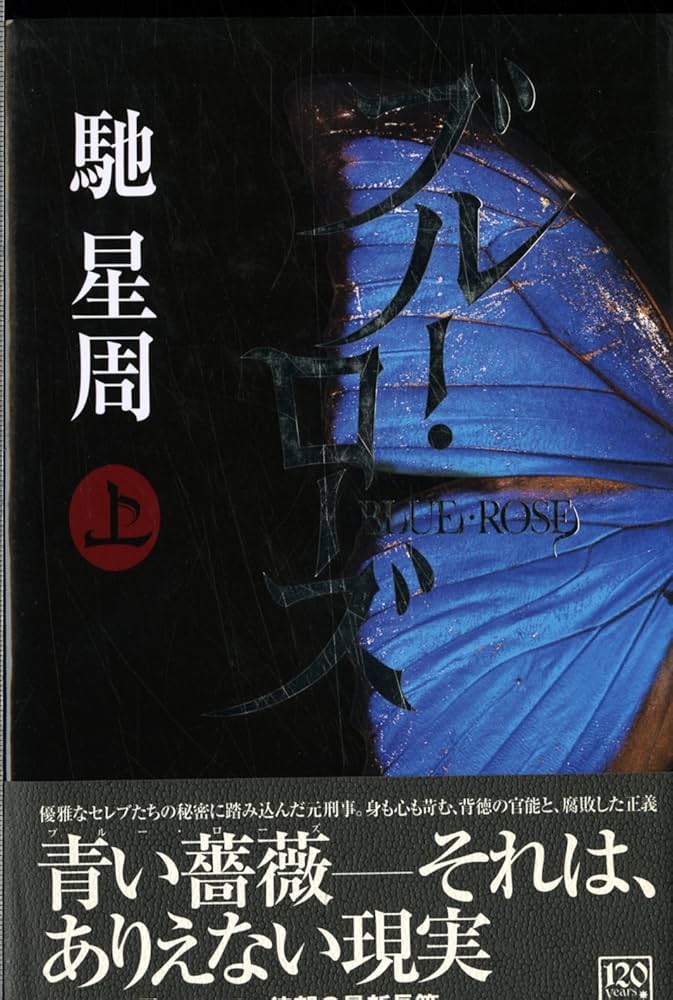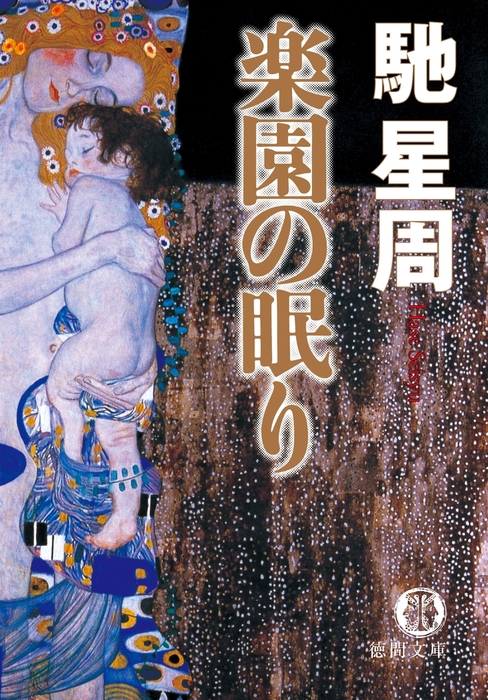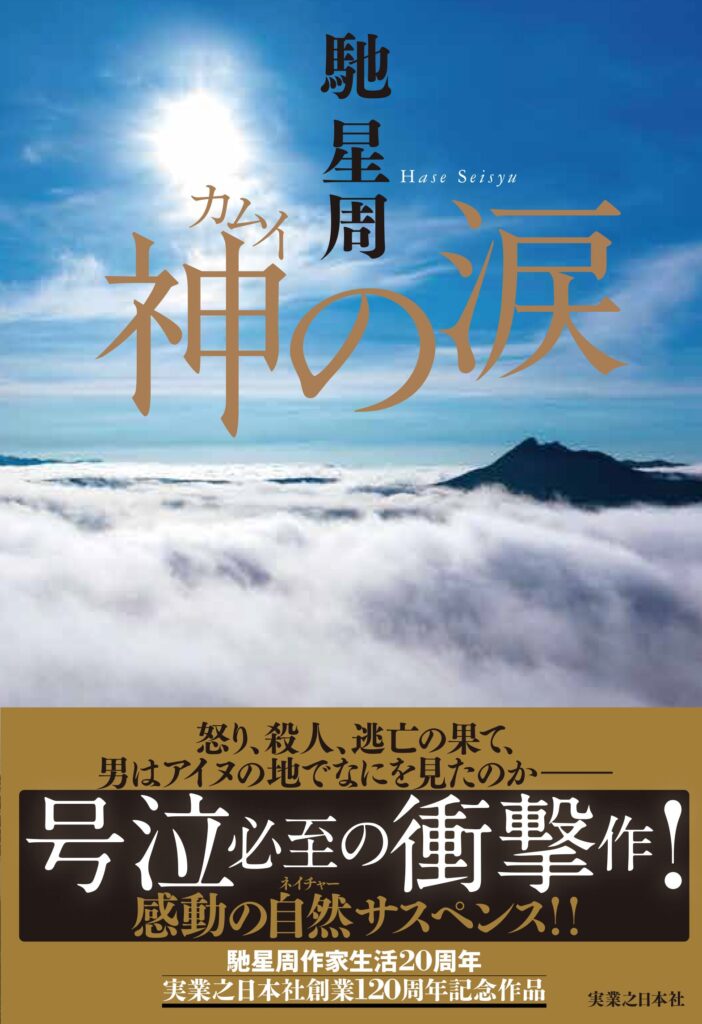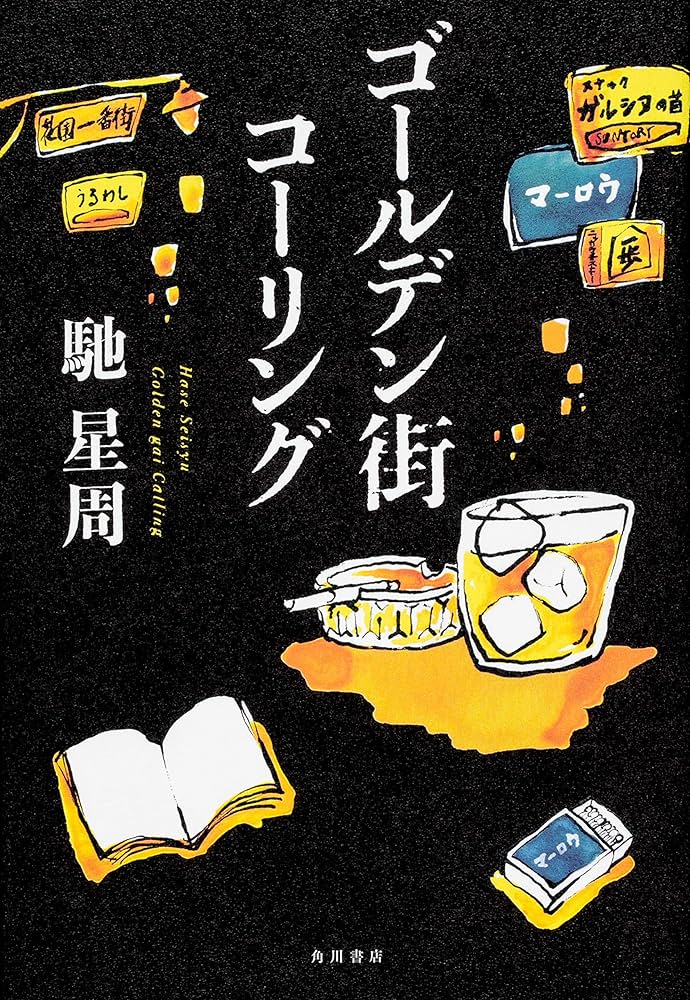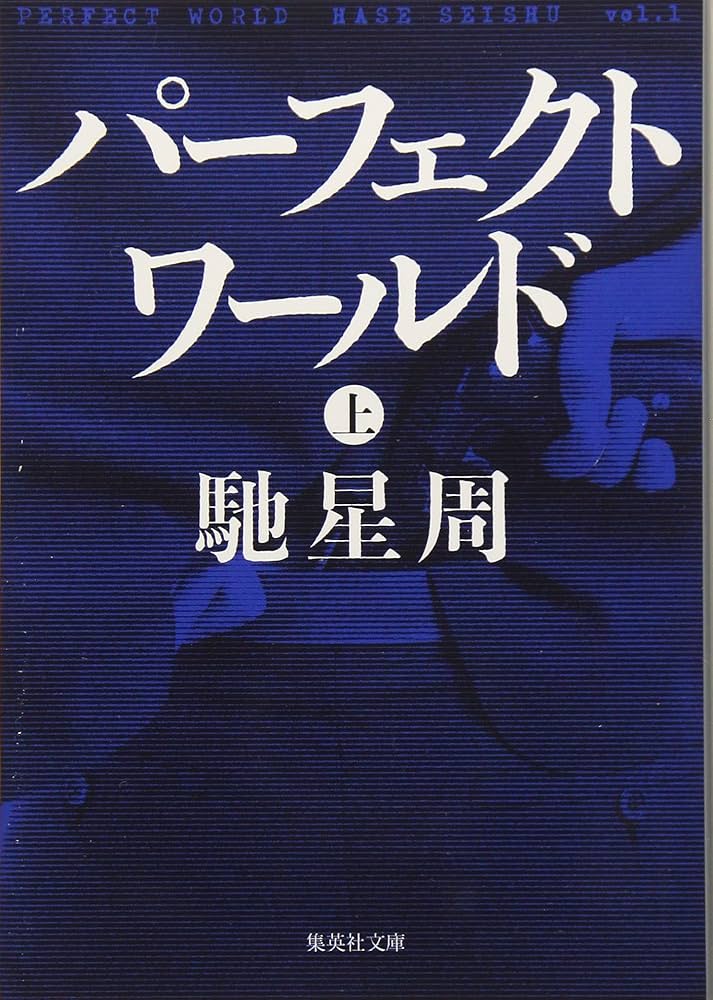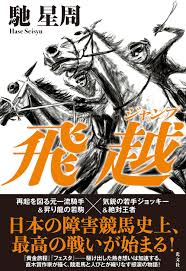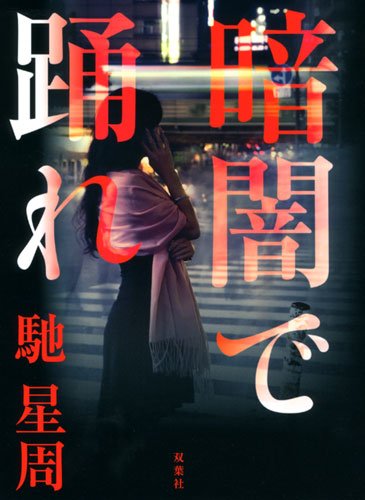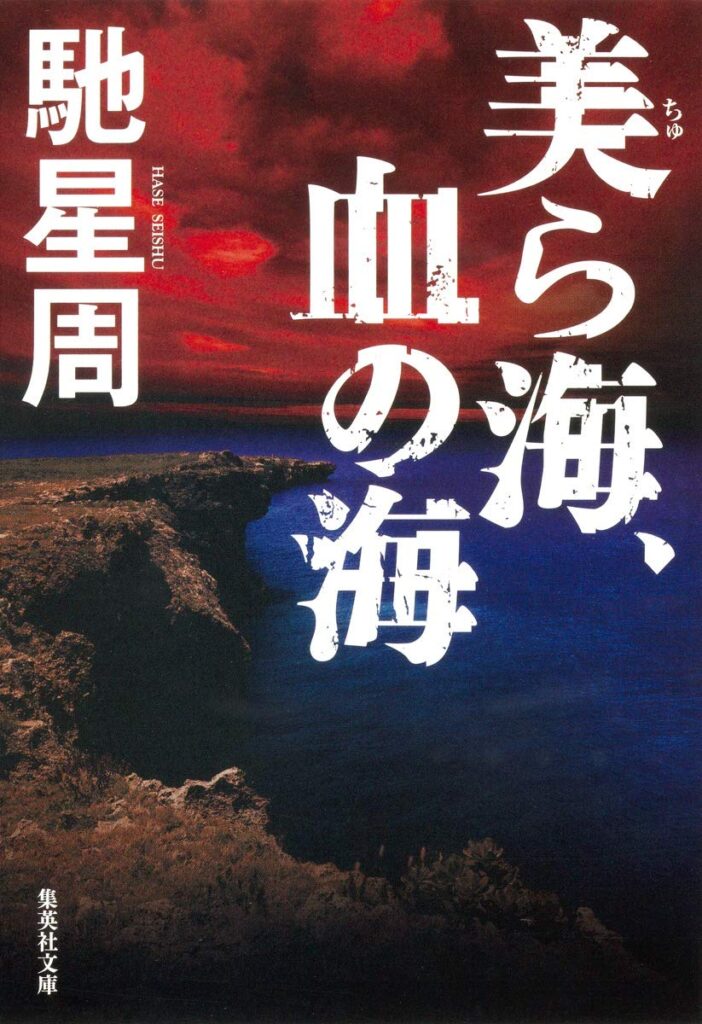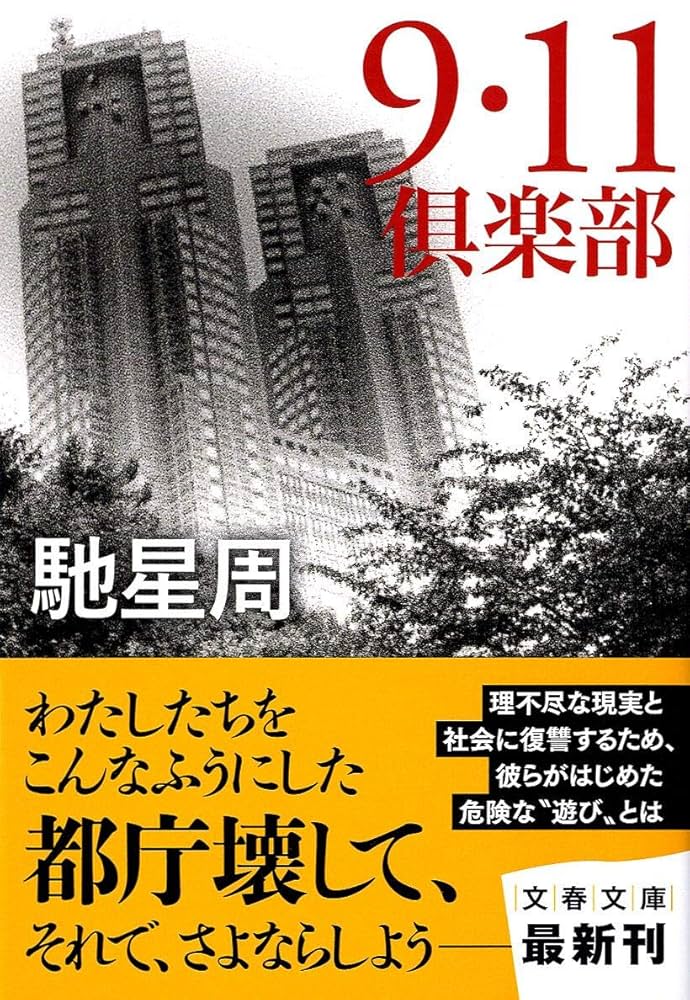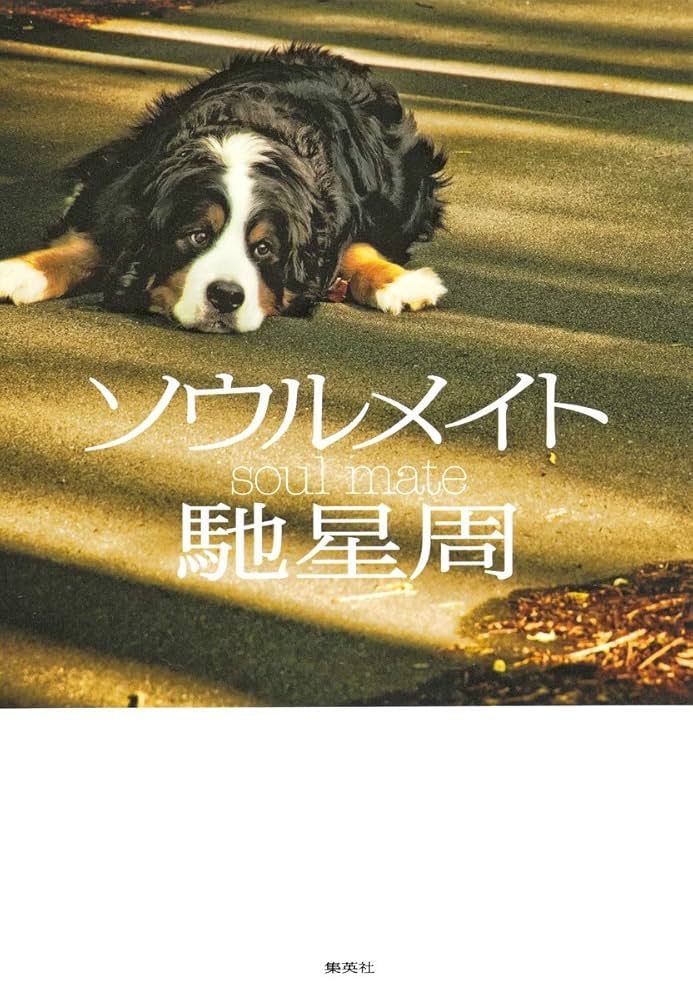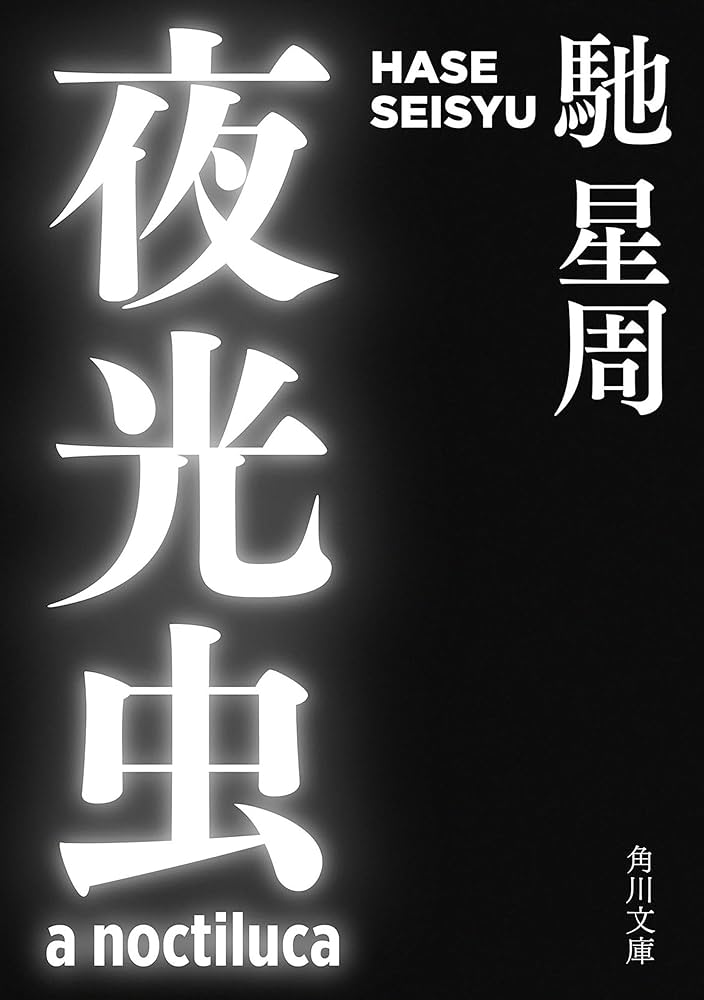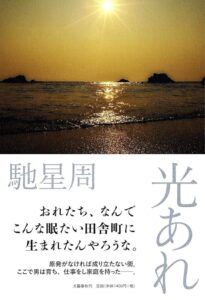 小説「光あれ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「光あれ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
馳星周さんといえば、裏社会の抗争や暴力的な男たちを描くノワール小説の旗手として知られています。しかし、この「光あれ」は、これまでの作品とは少し趣が異なります。描かれるのは、地方都市の閉塞感の中で、どうしようもなく堕ちていく一人の男の半生です。
本作の舞台は、福井県敦賀市。原子力発電所に経済を依存する、いわゆる「原発の町」です。この物語が東日本大震災よりも前に書かれたという事実は、作品を読む上で非常に重要な意味を持ちます。作中に漂う漠然とした不安や、見て見ぬふりをしながら生きる人々の姿は、期せずして未来を予見していたかのようで、読む者の胸に深く突き刺さります。
この記事では、まず物語の概要を追い、その後で主人公・相原徹という男の人生を深く掘り下げながら、物語の核心に迫る考察をお届けします。彼の人生を通して、絶望の淵に射し込む一条の光とは何なのか、一緒に考えていければと思います。どうぞ、最後までお付き合いください。
「光あれ」のあらすじ
福井県の原子力発電所がある町、敦賀。この町で生まれ育った相原徹は、特に大きな夢もなく、閉塞感に満ちた日々を送っていました。学生時代には、チェルノブイリ原発事故をきっかけに、大人たちが原発を巡って対立する姿を目の当たりにし、町の特殊な空気を肌で感じて育ちます。
高校を卒業した徹は、故郷を離れることもなく、地元の原子力発電所で働き始めます。やがて結婚し、娘も生まれ、一見すると平凡で安定した生活を手に入れたかのように見えました。しかし、彼の内面は常に満たされない思いと苛立ちで渦巻いており、その捌け口を刹那的な快楽に求めるようになります。
40歳を目前にしたある時、恩師の死をきっかけに旧友たちと再会したことから、彼の人生の歯車は大きく狂い始めます。友人の妻との許されない関係に陥り、その果てに悲劇的な結末を招いてしまうのです。この出来事が引き金となり、彼の家庭は崩壊。すべてを失い、町を彷徨うことになります。
絶望のどん底で、徹は自らの過去と向き合わざるを得なくなります。彼が犯してきた過ち、傷つけてきた人々、そして、それでも手放すことのできない唯一の絆。自らの罪を背負い、彼が最後に見出すものとは一体何なのでしょうか。物語は、彼の選択に一条の光が射すのかを問いかけながら、静かに幕へと向かっていきます。
「光あれ」の長文感想(ネタバレあり)
馳星周さんの作品というと、どうしても暴力と裏社会のイメージが強いのですが、この「光あれ」はそうした既存の枠組みから大きくはみ出した、静かで、しかし、だからこそ深く心をえぐるような物語でした。派手な銃撃戦も、裏切りに次ぐ裏切りの抗争もありません。ここにあるのは、日本のどこにでもありそうな地方都市の息苦しさと、そこでゆっくりと人生を沈ませていく一人の男の姿です。
物語の舞台となる福井県敦賀市は、原子力発電所と共に歩んできた町です。原発が雇用を生み、経済を潤す一方で、常に目に見えない不安が漂っている。この設定が、物語全体に重く垂れ込める閉塞感の源泉となっています。登場人物たちは、原発の是非を声高に叫ぶわけではありません。むしろ、その恩恵を受けながら、心のどこかで「何か」をやり過ごしながら生きている。そのリアルな描写が、胸に迫ります。
さらに驚くべきは、この作品が2011年の東日本大震災と福島第一原発事故のはるか以前に発表されているという事実です。作中には、原発の安全性について「絶対はあらへんよ」と語る場面が登場します。発表当時にこの台詞を読んだ人と、3.11を経験した私たちが読むのとでは、その言葉の重みが全く違って感じられるでしょう。意図せずして時代の予言書となった本作は、私たち日本人が抱えていた、あるいは今も抱えているであろう問題点を鋭く突きつけてきます。
本作は5つの短編からなる連作形式で、時系列が前後しています。最初は40歳手前の主人公・相原徹の現在の危機から始まり、物語は彼の過去へと遡り、そしてまた現在へと戻ってきます。この構成が非常に巧みで、徹という人間の人生が、過去の失敗や後悔に常に縛られ、現在を侵食されている様を、読者も追体験することになるのです。抜け出すことのできない町の閉塞感が、物語の構造そのものによって表現されているように感じました。
主人公の相原徹は、一言でいえば、どうしようもない男です。ある書評では「疫病神」とまで表現されていましたが、まさにその通りで、彼に関わる人間は次々と不幸になっていきます。彼の行動原理は自己憐憫と責任転嫁。何かがうまくいかないと、すぐに環境や他人のせいにする。そのくせ、歪んだプライドだけは一人前に持っている。読んでいて何度も「しっかりしろ!」と声をかけたくなりました。
彼の人間性は、少年時代からすでにその萌芽が見られます。中学時代、チェルノブイリの事故が遠い国の出来事として報じられる中、彼は純粋なサッカー少年でした。しかし、淡い初恋は惨めな形で終わり、この経験が後の彼の女性に対する歪んだ接し方を予兆させます。大人たちの原発を巡る対立は、彼の心に漠然とした不安の種を植え付けました。
高校生になっても、徹に明確な将来の目標はありません。友人たちとつるみ、目的のない日々を過ごす中で、募っていくのは諦めと苛立ち。その鬱屈した感情の捌け口を、彼は安易な性の快楽に求め始めます。ここから、彼の感情的な空虚を肉体的な関係で埋めようとする、破滅的なパターンが確立されていくのです。
結局、徹は故郷を離れることもなく、地元の原発で働き始めます。結婚し、娘を授かり、表面的には「普通」の人生を歩み始めます。町の景気が原発とバブルで一時的に潤い、そして衰退していくのと歩調を合わせるかのように、徹自身の人生もまた、内側から静かに蝕まれていきました。この、個人の人生と町の浮沈が見事にシンクロしていく描写は、実に見事でした。
そして、物語は徹の人生が破綻する現在へと至ります。友人の事故死、そして、その友人の妻との不倫。この関係が最悪の結末を迎えた時、彼は自分が他者の人生を破壊する存在であることを決定的に思い知らされます。もちろん、その時点でも彼は自分のせいだとは考えません。しかし、この不貞が妻に知られることで、彼のささやかな家庭は完全に崩壊します。
徹という男のどうしようもなさが最も表れているのは、家庭が崩壊した直後の行動でしょう。反省や後悔ではなく、彼が向かったのは昔の女の元でした。安易な慰めと逃げ場所に、またしても女性を利用するのです。この行動は、彼が救済からはほど遠い場所にいることを、読者に容赦なく突きつけます。彼は常に、問題の根本から目を逸らし、刹那的な快楽や安らぎに逃げ込むことしかできないのです。
この徹の「甘え」の構造は、敦賀という町が原発に依存する構造と酷似しています。徹は、自分の不幸を他責にすることで、自らの問題と向き合うことから逃げ続けます。それと同じように、町もまた、長期的なリスクから目を逸らし、原発がもたらす目先の経済的恩恵に依存している。「他に選択肢がなかった」という論理で、その依存を正当化するのです。徹個人の道徳的な破綻は、そのまま町全体の精神的な妥協の縮図となっているように思えました。
彼の人生の被害者は、数多く登場します。まずは、名前すら与えられていない妻と娘。妻は徹の裏切りに気づき、最終的に彼を切り捨てる決断をします。当然の帰結でしょう。娘は、父親の罪の象徴であると同時に、徹に残された唯一の救済の可能性でもあります。彼女の存在が、この物語にかすかな光をもたらすことになります。
そして、徹が逃げ場所として利用してきた数々の女性たち。自殺してしまった友人の妻、水商売の女性、そして昔の恋人。彼女たちとの関係はすべて、徹が成熟した責任ある関係を築けないことの証明に他なりません。彼は愛からは逃げ、欲望の対象としてしか女性を見ることができない。その姿は痛々しく、そして哀れですらあります。
昌也、圭輔、浩子、美紀といった友人たちもまた、徹の周りで不幸になっていきます。事故で死んだり、あるいは町の停滞した空気に引きずり込まれるように人生の輝きを失っていったり。彼らの存在は、徹という「疫病神」が放つ負の影響力を、より一層際立たせる役割を担っています。
物語の終盤、すべてを失った徹は、娘と痛々しい対話を交わします。そして、和解のしるしとして「キティちゃんの腕時計」を買うことを約束します。これは、彼が初めて、他者との繋がりを取り戻そうとした、不器用で、しかし切実な意志の表れと言えるのかもしれません。そして彼は、「自分の犯した罪で壊した家族との生活を選び直す」という決意を固めるのです。
では、本作のタイトルである「光あれ」とは、何を意味するのでしょうか。この結末を、手放しでハッピーエンドと呼ぶことは難しいでしょう。家を追い出された直後に他の女の元へ走るような男が、そう簡単に変われるとは思えません。彼が見た「光」は、完全な闇からの一瞬の解放に過ぎず、またすぐに夜が訪れる、そんな幻だったのかもしれない。そう解釈することも可能です。
しかし、それでも私は、ここにわずかな希望を見出したいと感じました。作者が、徹のような救いようのない男にさえ、最後に「家族と向き合う」という選択肢を与えたこと。これこそが、この物語の核心ではないでしょうか。光は、誰かに与えられるものではなく、暗闇の中でもがき、苦しみながら、自らそちらを向くことで初めて感じられるものなのかもしれません。
「光あれ」は、安易な答えや救済を読者に与えてはくれません。ただ、どうしようもない人間の、どうしようもない人生を通して、それでも人は変われる可能性があるのだと、最もか弱く、最も脆い可能性を提示してくれているように思います。絶望の淵に立った人間が、それでも光の方を向くことを選べるかもしれない。その静かな祈りのような響きが、読後、長く心に残る作品でした。
まとめ
馳星周さんの「光あれ」は、従来の作品群とは一線を画す、静かで内省的な物語です。原子力発電所に揺れる地方都市を舞台に、一人の男が堕ちていく半生を通して、人間の弱さや依存、そして再生の可能性を描き出しています。
主人公・相原徹のどうしようもない生き様は、読んでいて苛立ちを覚えるほどですが、その姿は、私たちが目を背けがちな現実や、自分自身の内なる弱さと重なる部分があるかもしれません。彼の人生が町の衰退と同期していく様は、個人の物語を超えた社会的な寓話としても読み解くことができます。
物語の結末は、決して安易なハッピーエンドではありません。しかし、絶望のどん底で示されるかすかな希望の兆しは、かえって深く心に響きます。救済は約束されていませんが、光の方を向く「選択」の尊さを教えてくれます。
重厚で読み応えのある作品を求めている方、人間の心の深淵を覗き込むような物語が好きな方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。読後、きっと「光」という言葉の意味を、改めて考えさせられることになるでしょう。