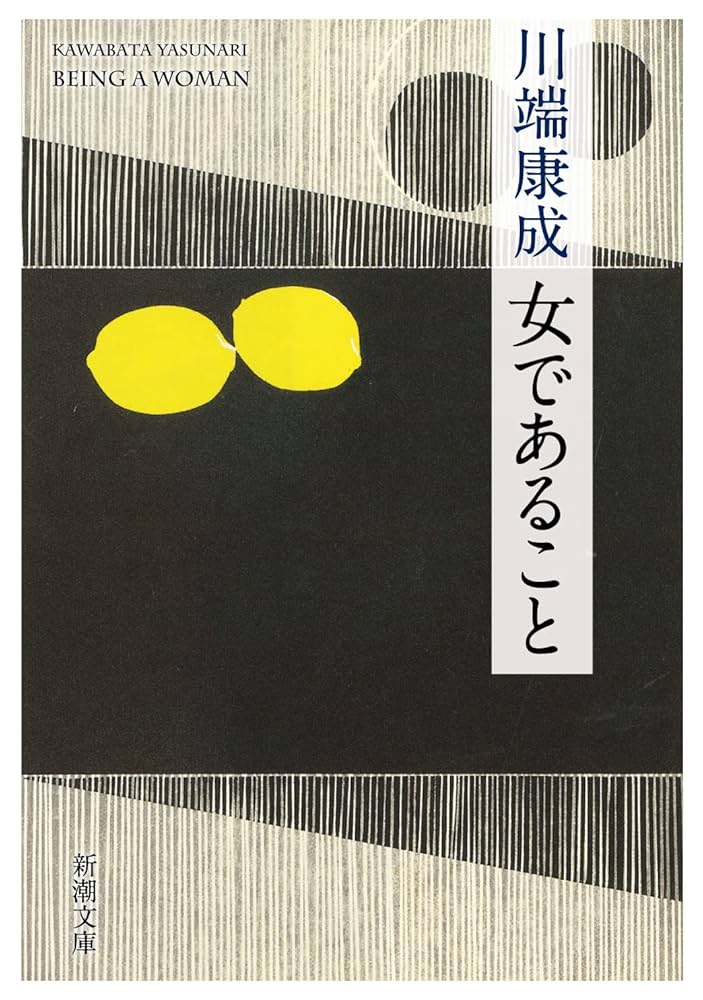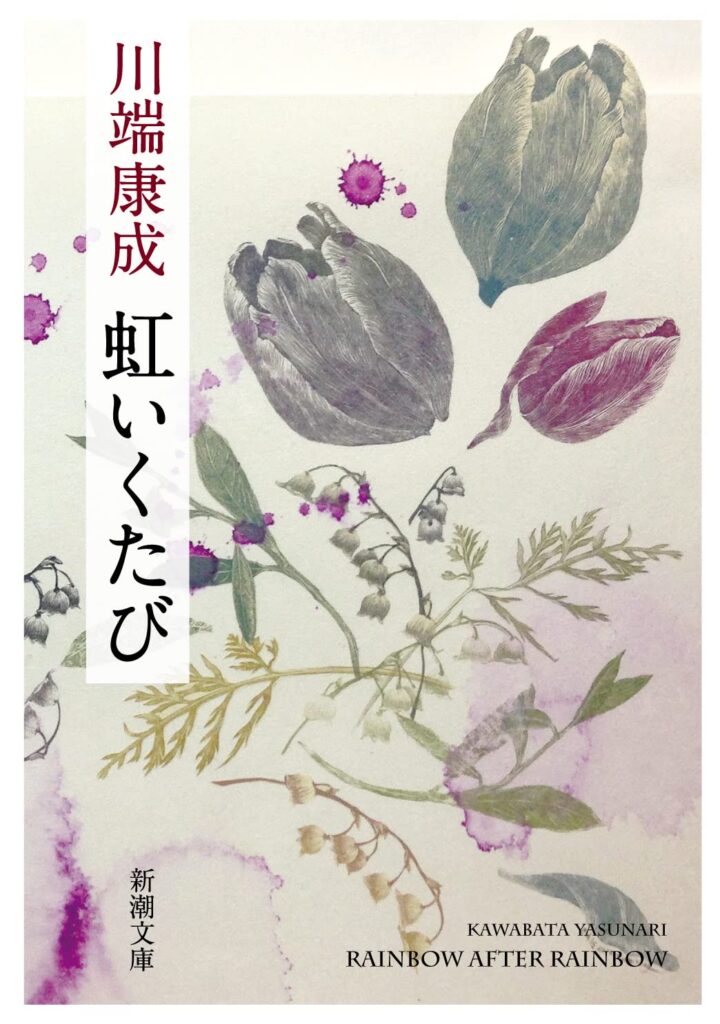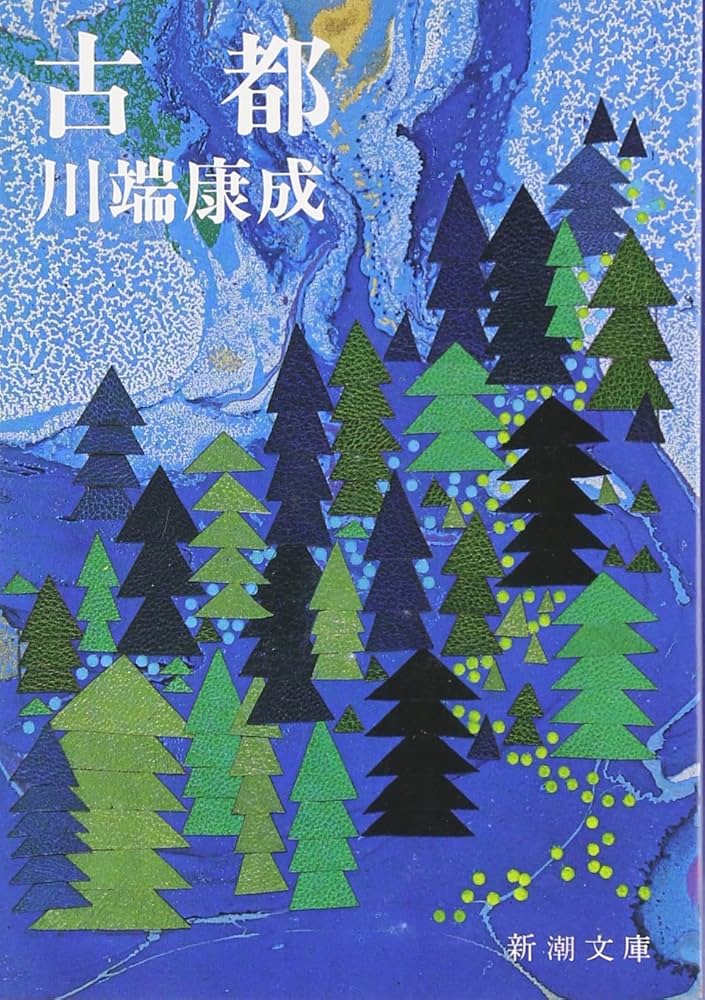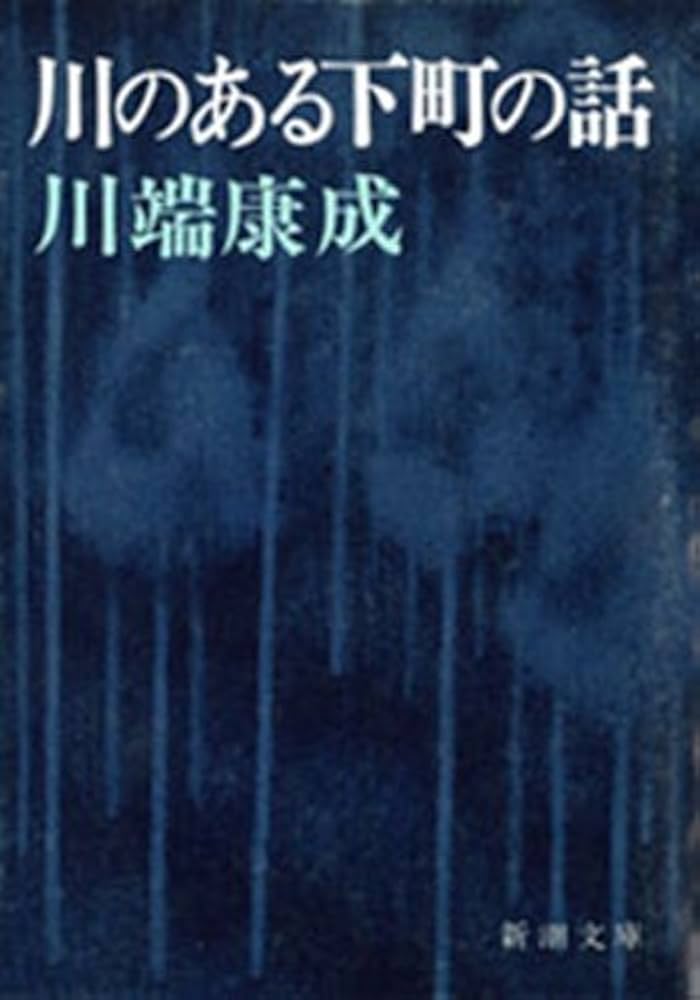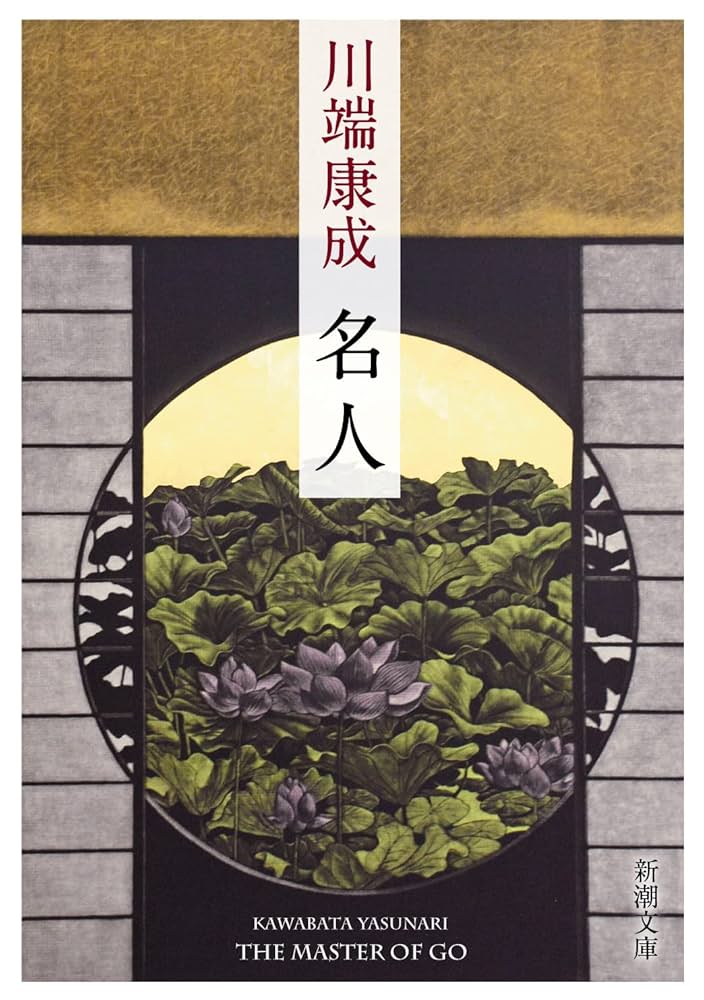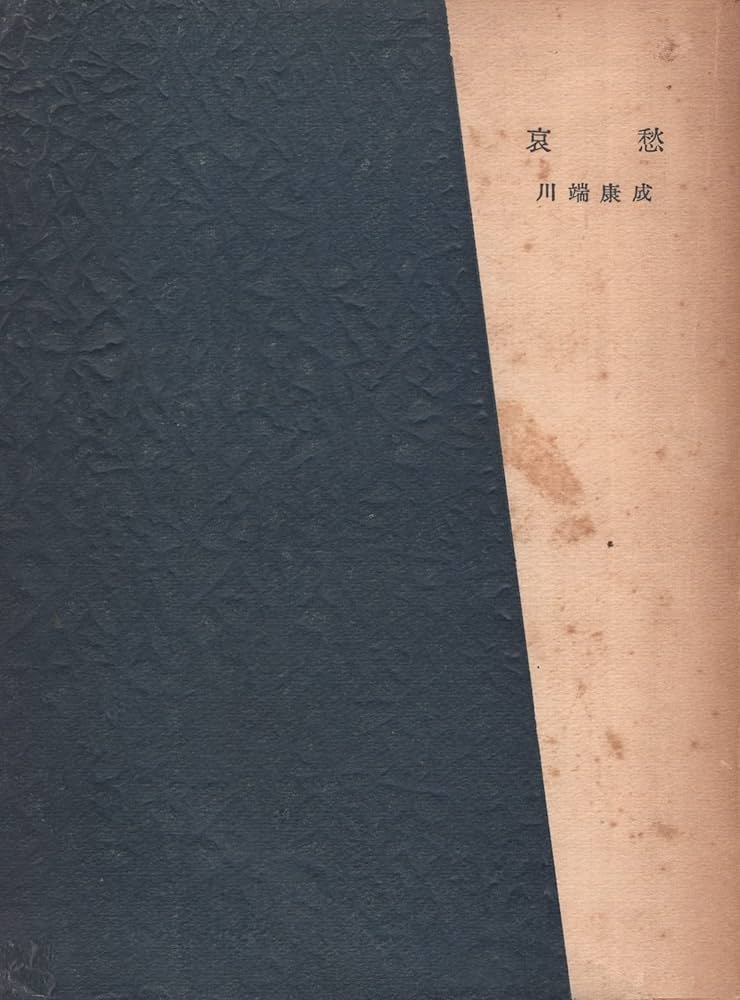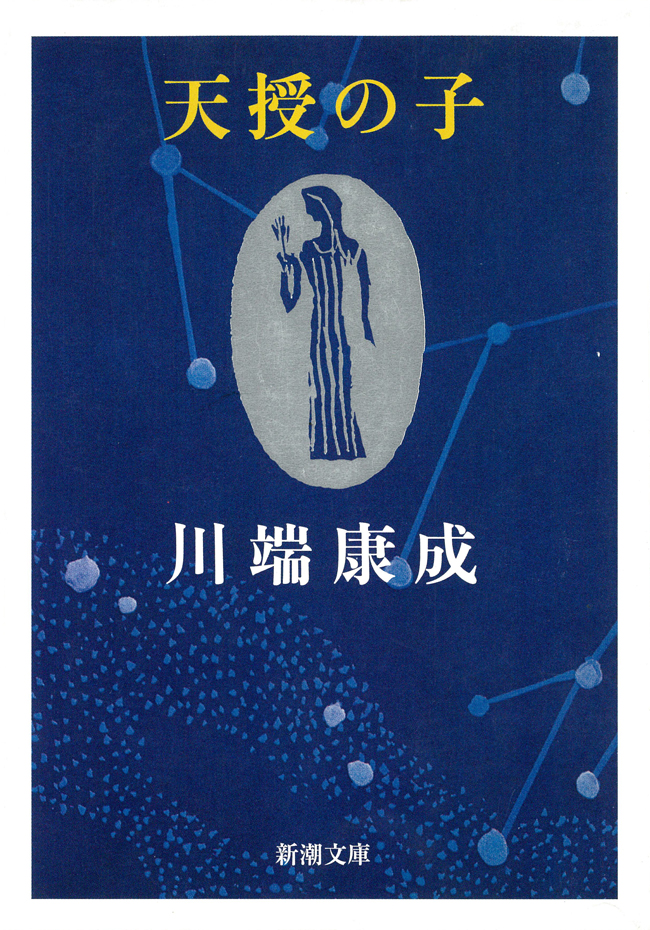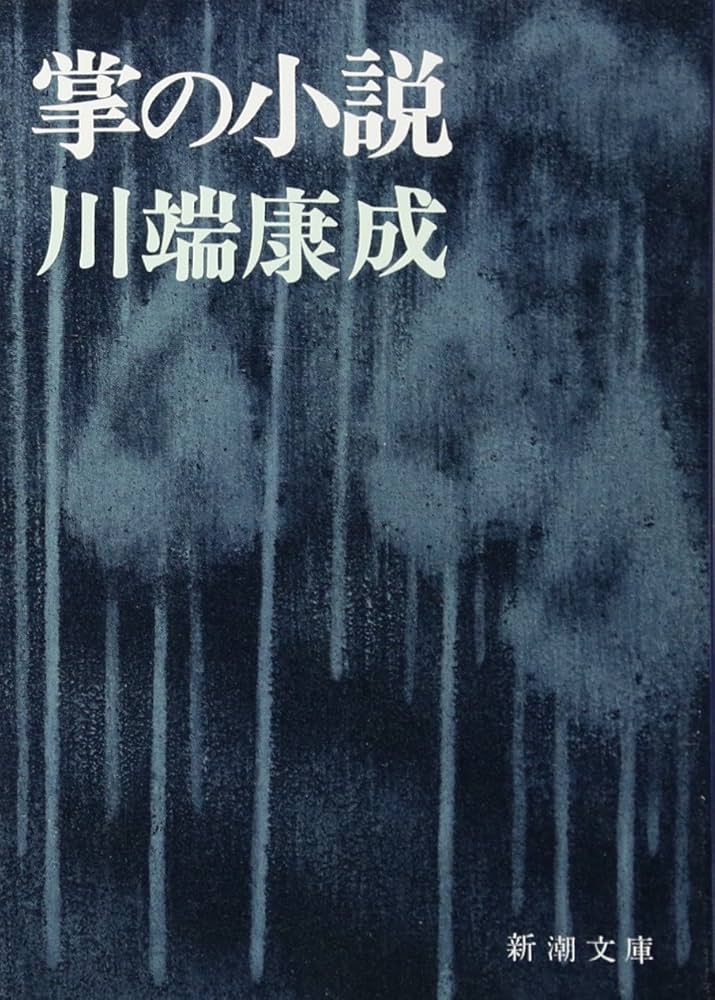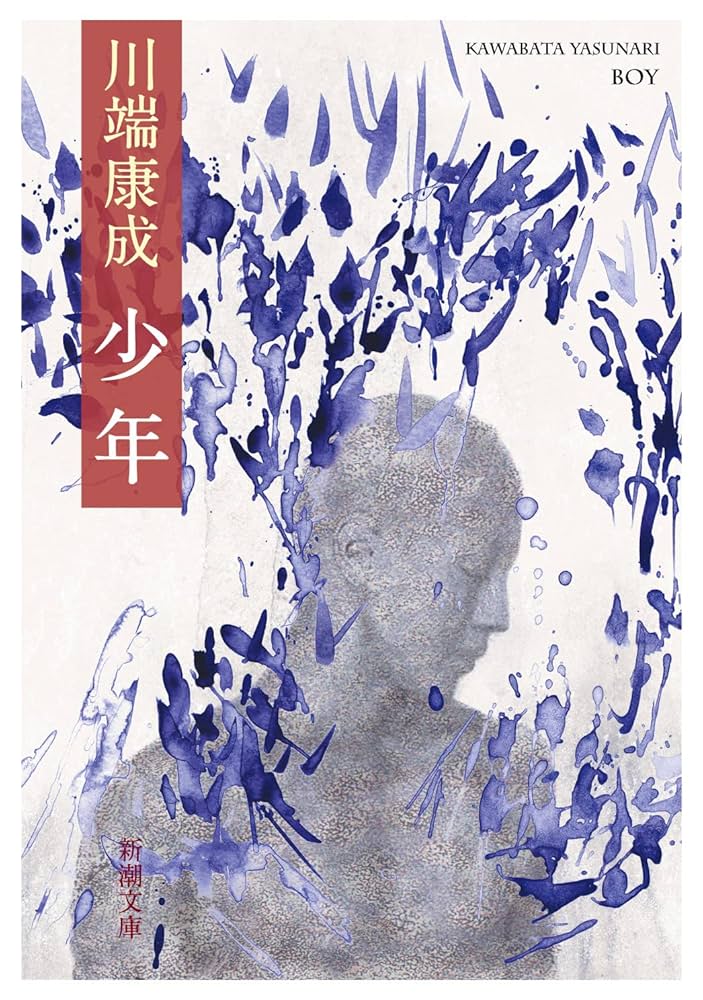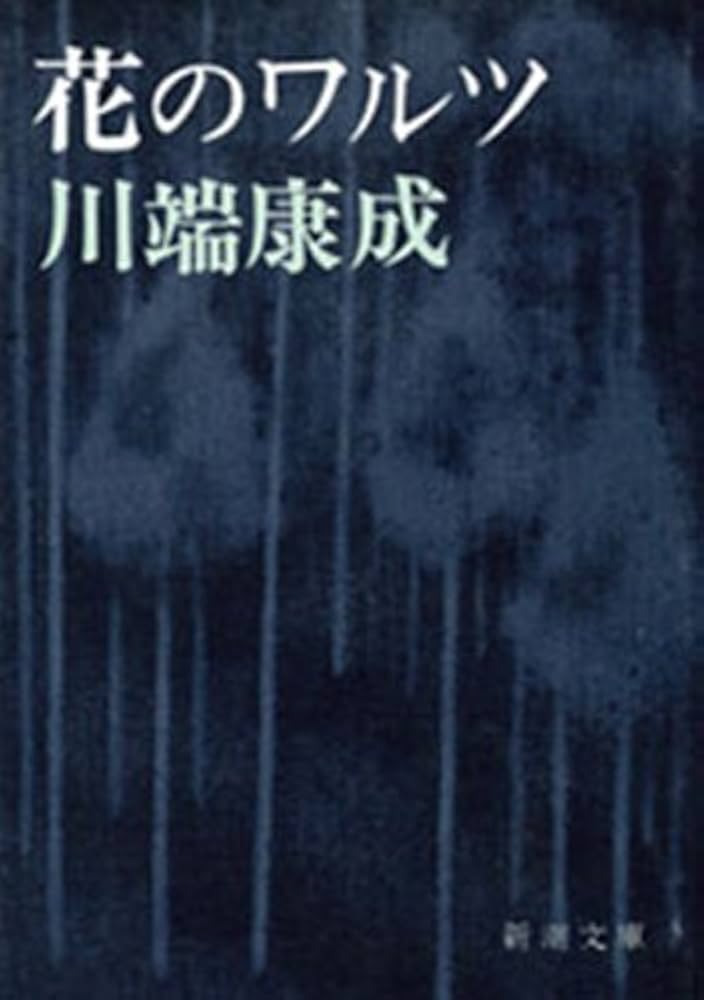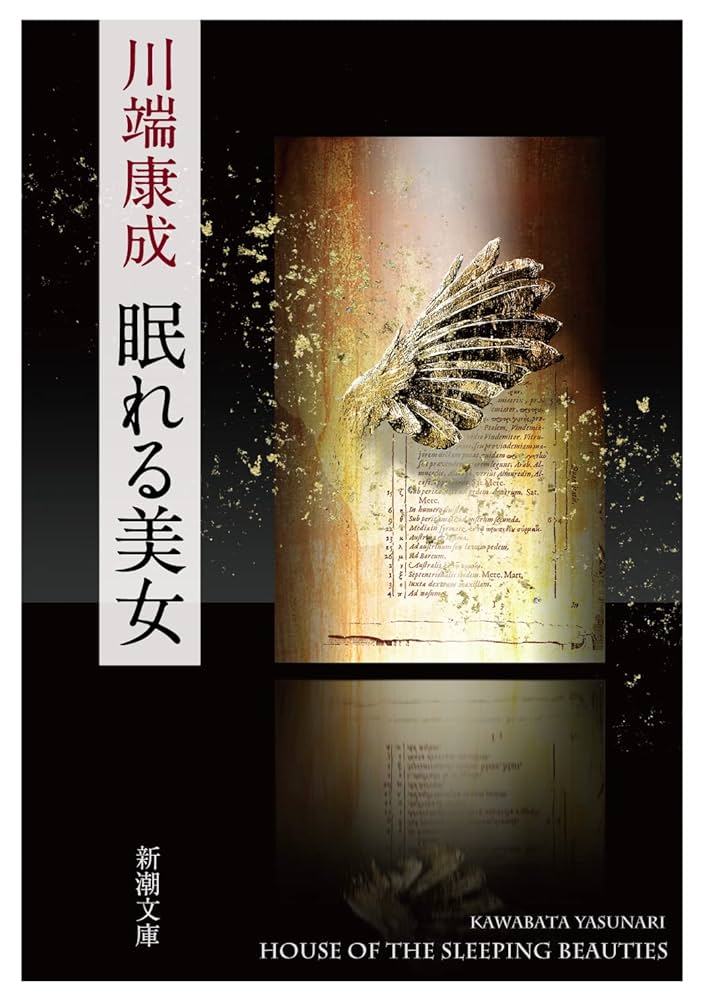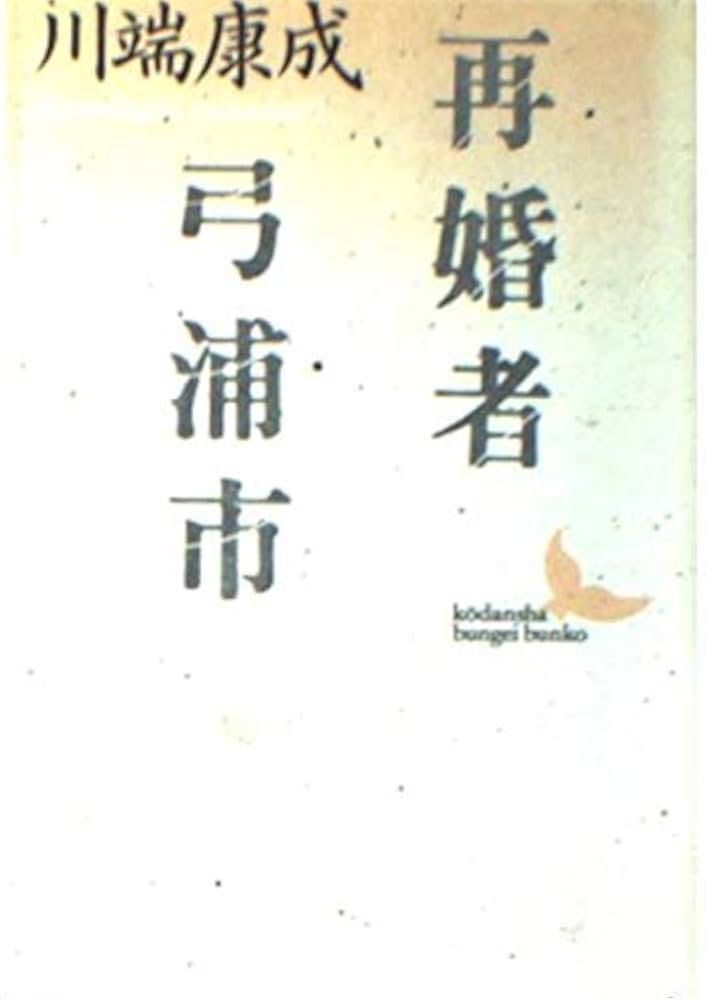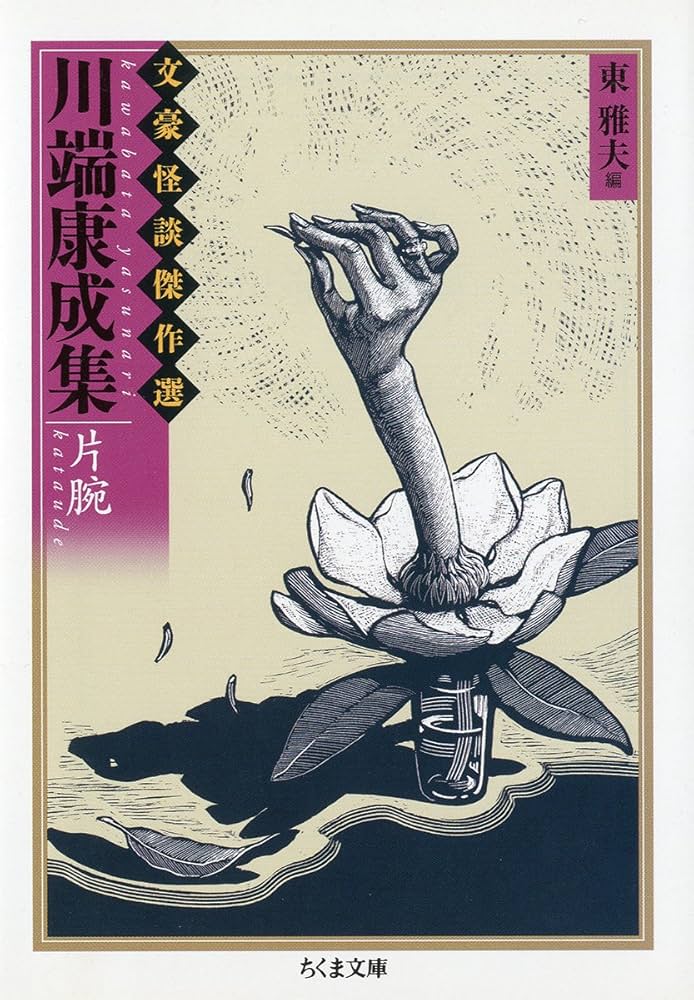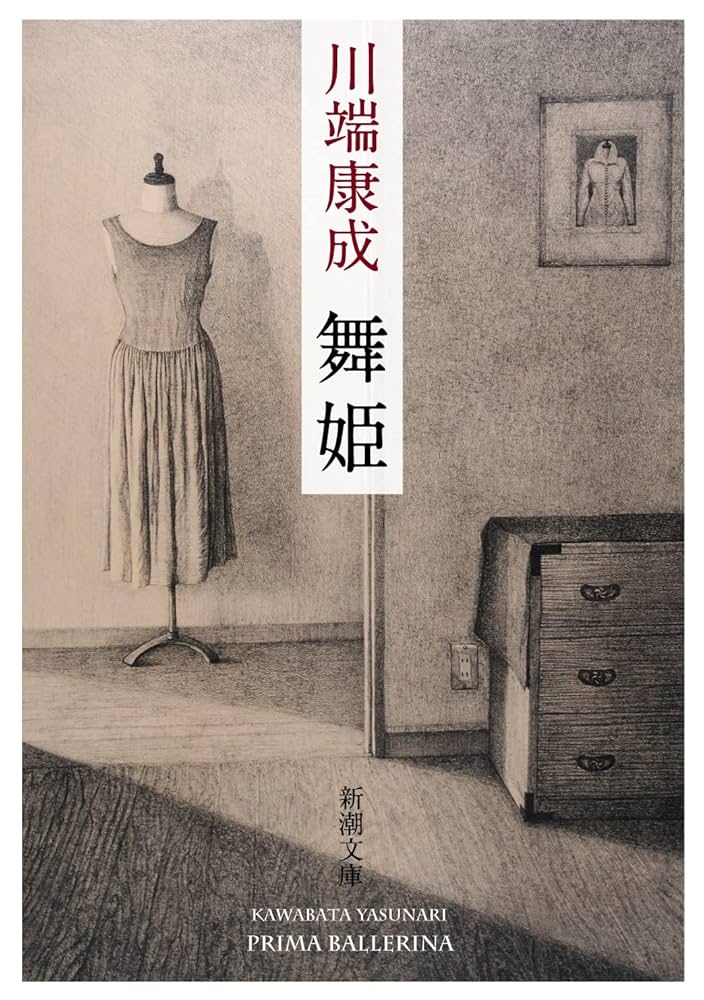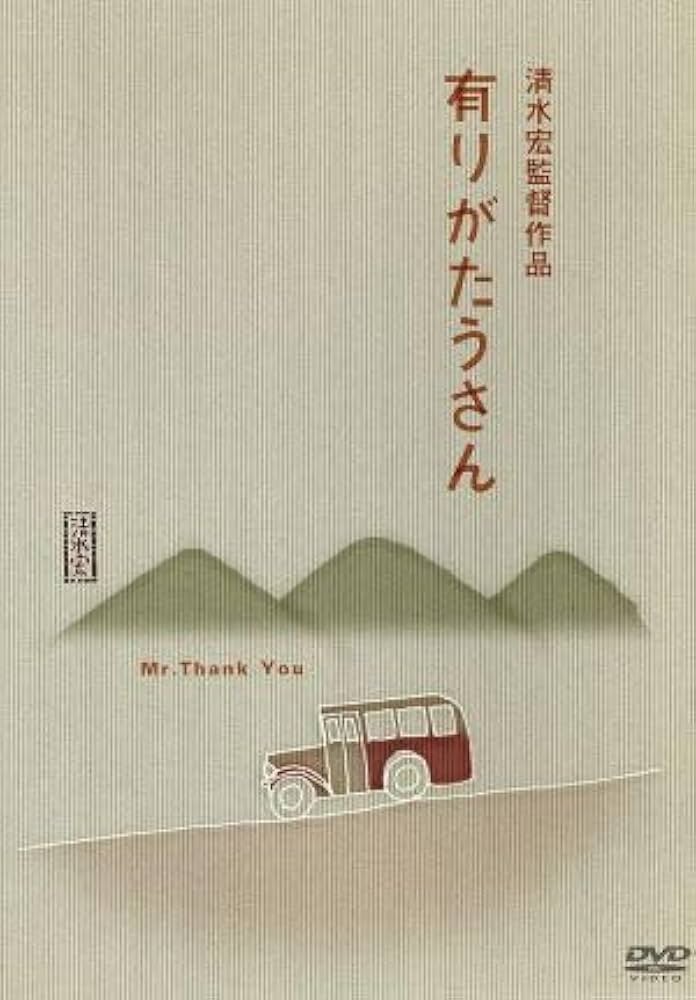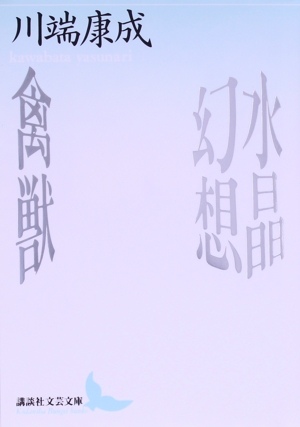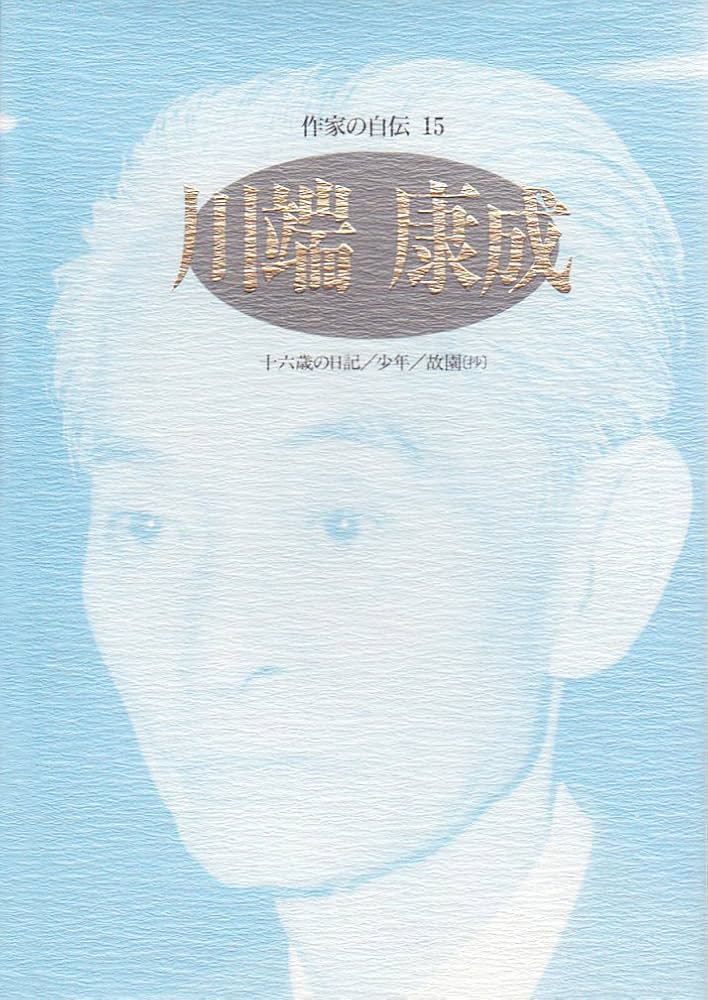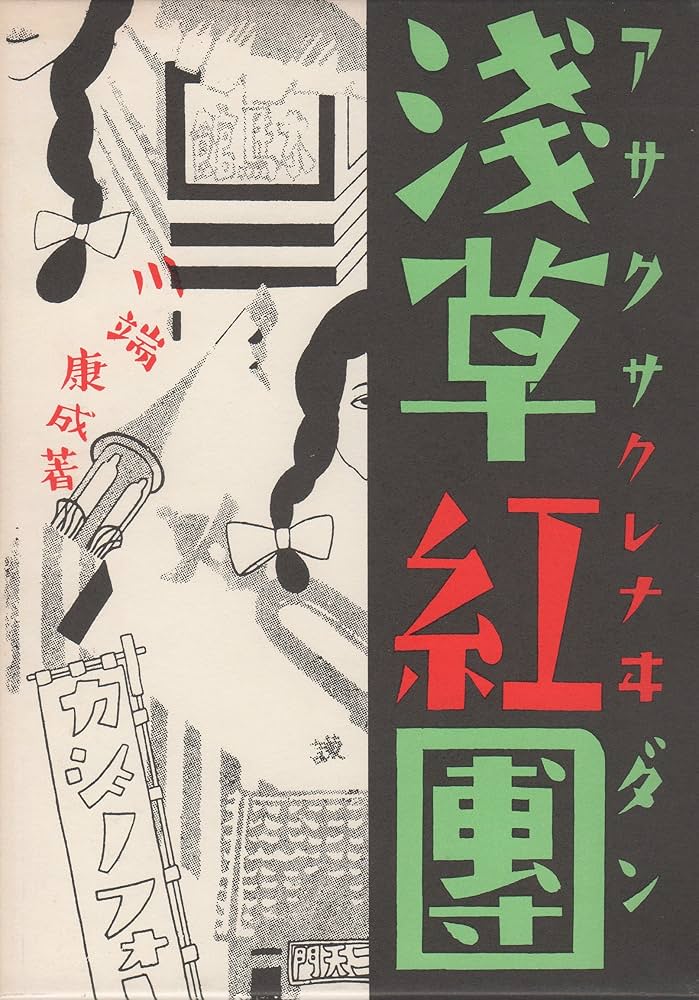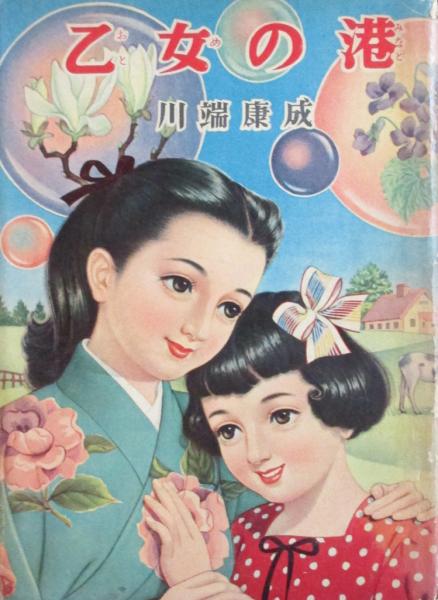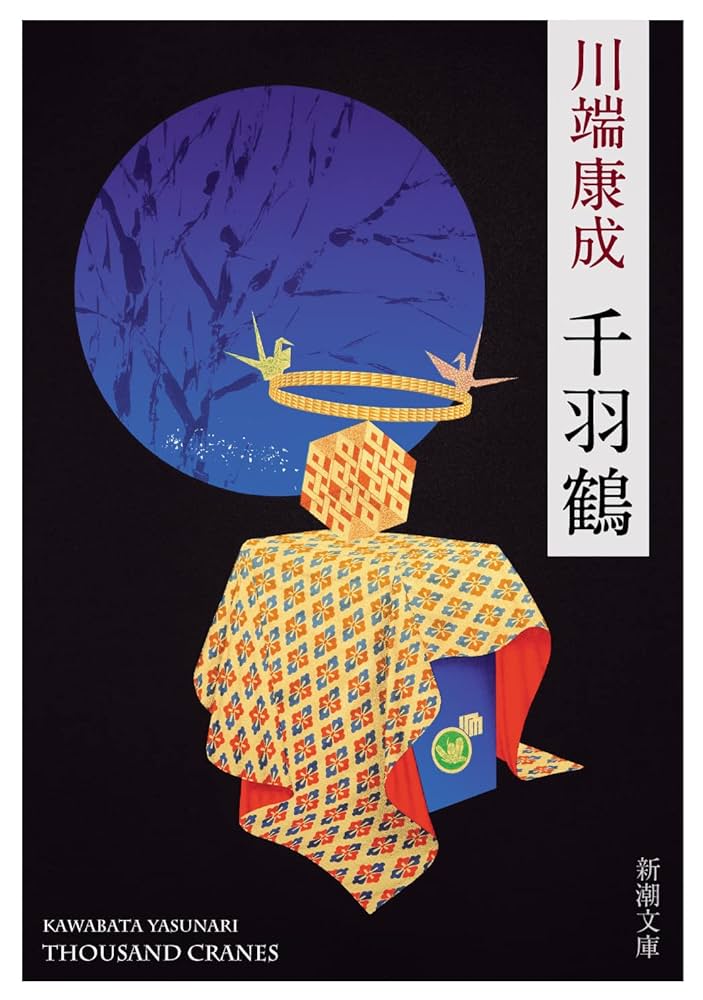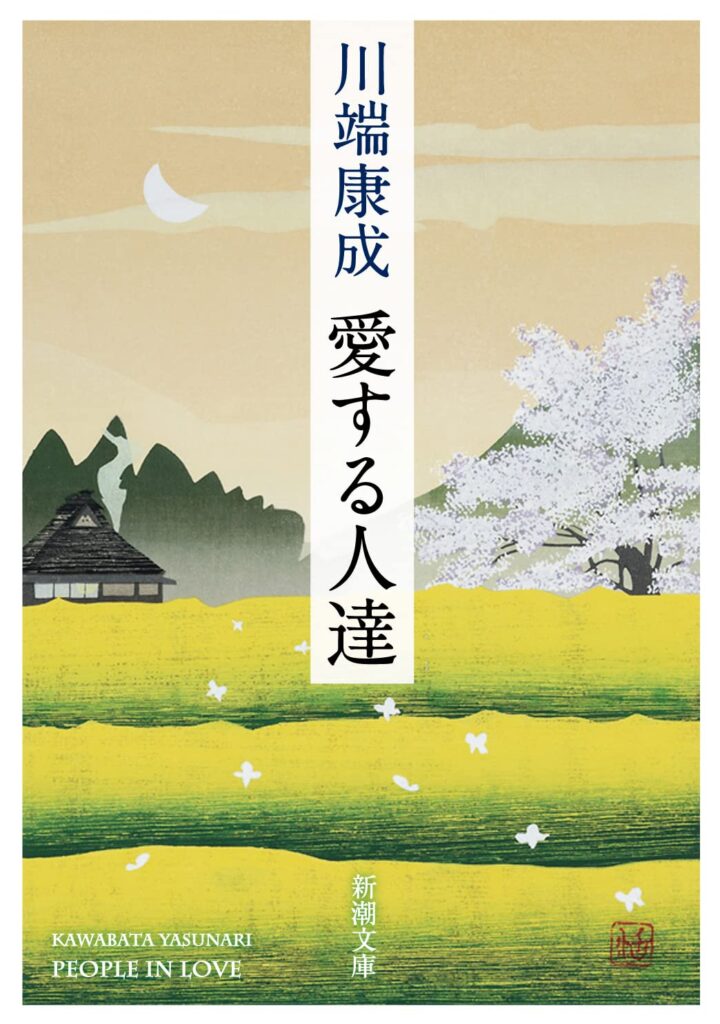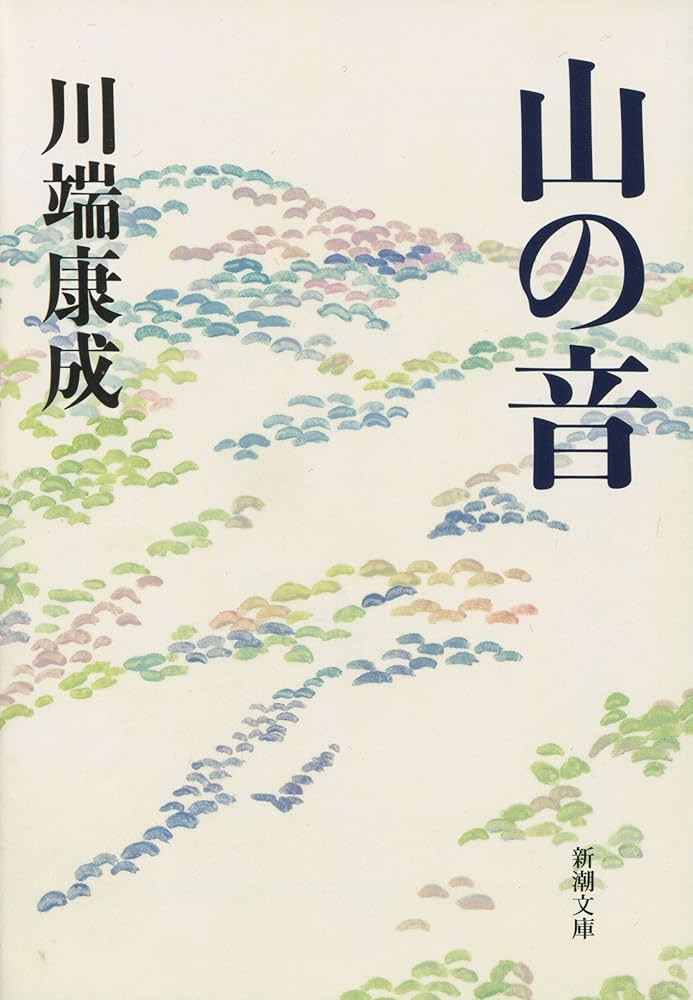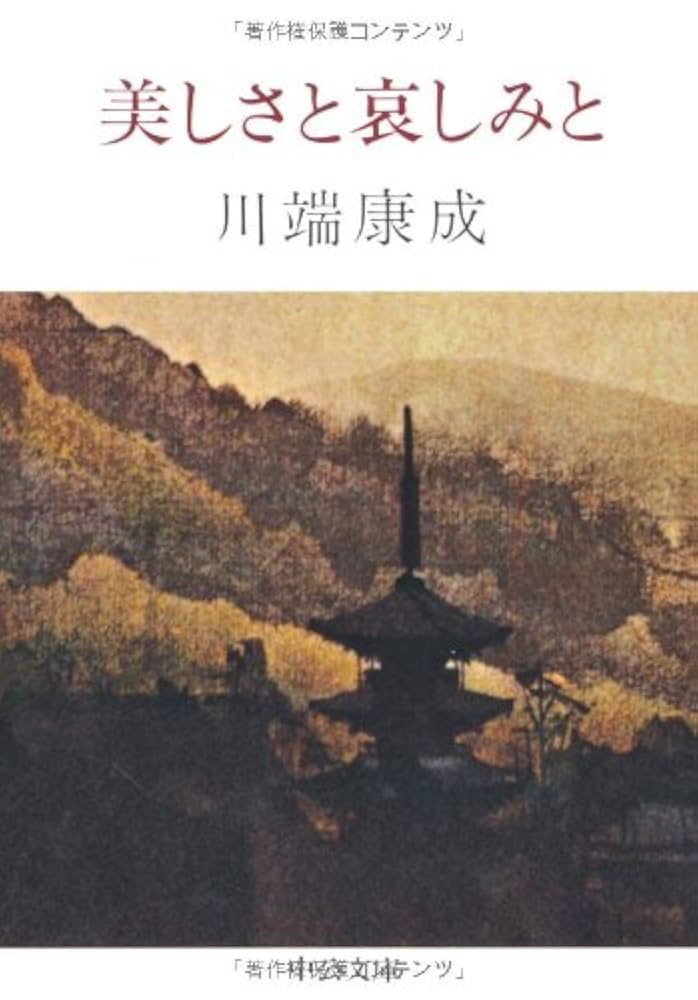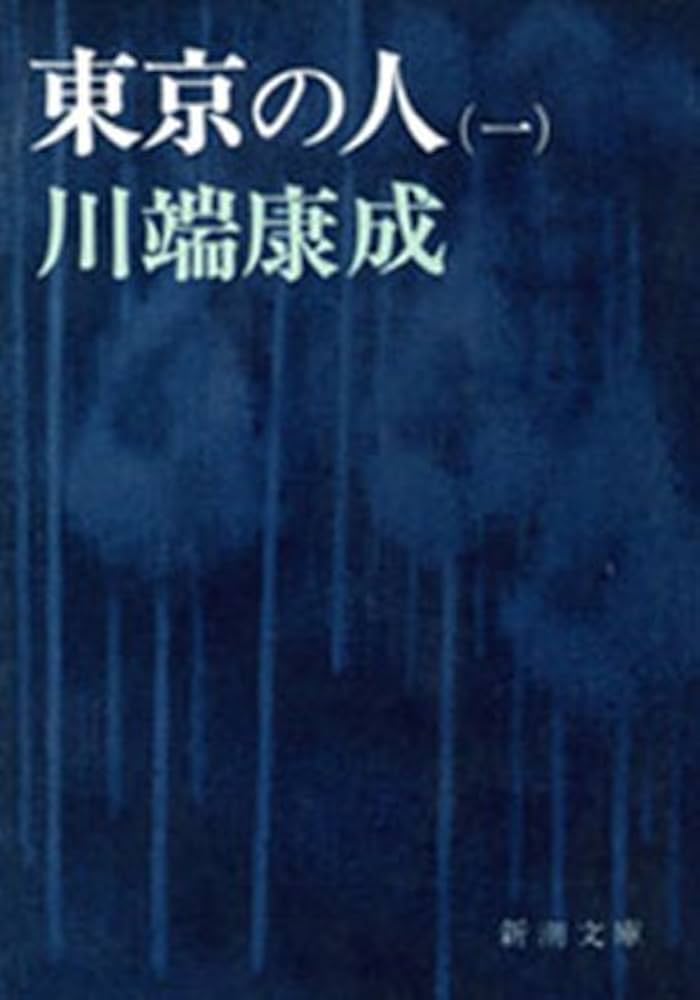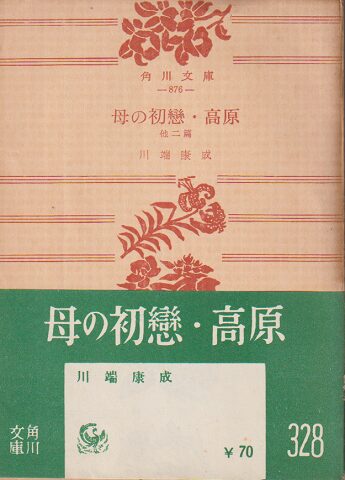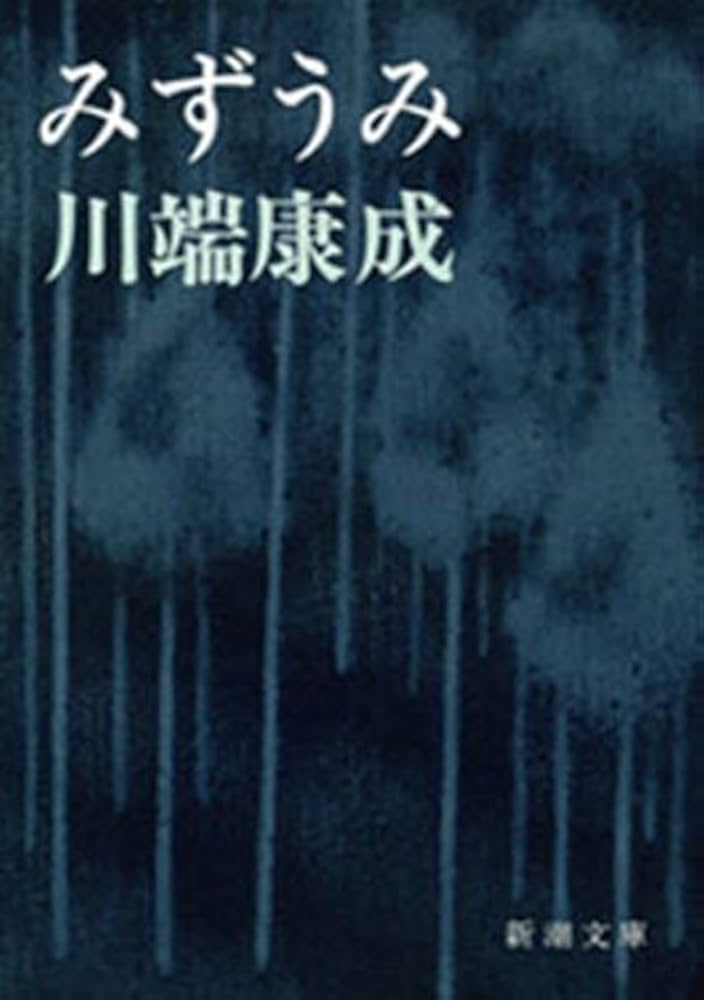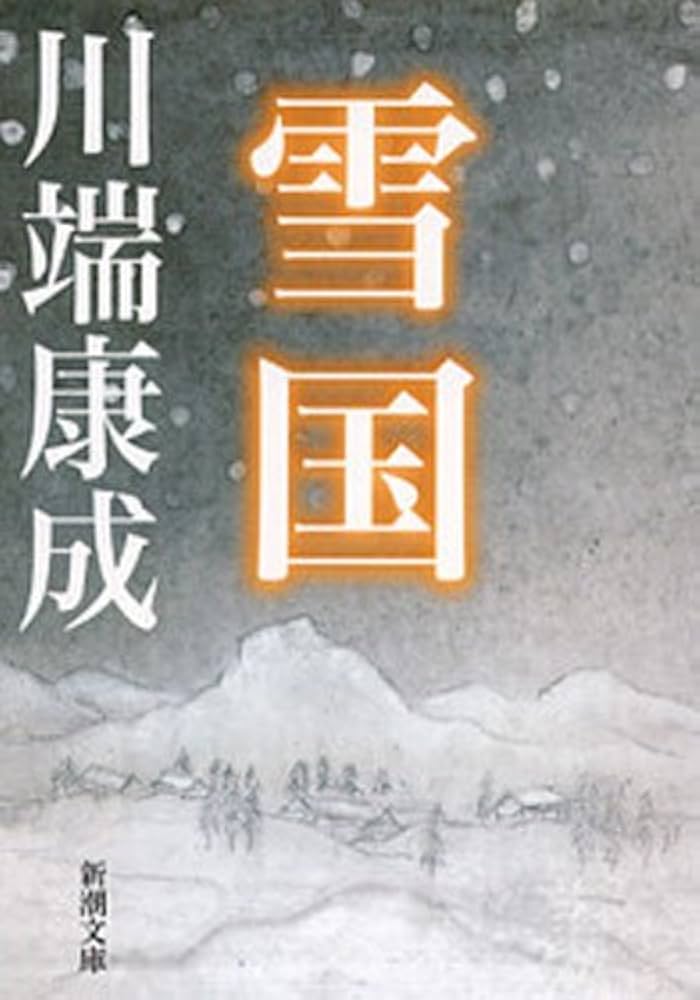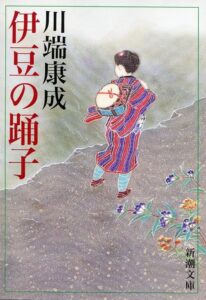 小説「伊豆の踊子」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「伊豆の踊子」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
川端康成の不朽の名作として知られる「伊豆の踊子」は、多くの人が一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。学生時代の淡い恋物語、旅先での美しい出会い、そんな爽やかなイメージを持たれている方も多いかもしれません。確かにその側面もありますが、この物語の本当の深さは、それだけにとどまらないのです。
この物語の核心にあるのは、一人の青年が抱える深い孤独と、そこからの解放の物語です。主人公が旅芸人の一座、特に幼い踊子との出会いを通して、いかにして凝り固まった心を解きほぐし、新しい自分へと生まれ変わっていくのか。その過程が、伊豆の美しい自然を背景に、繊細な筆致で描かれています。
この記事では、まず物語の骨子となるあらすじを紹介し、その後で、物語の核心に触れるネタバレを含む、私の個人的な深い読み解きと感想を綴っていきます。この物語がなぜこれほどまでに人の心を打ち、時代を超えて読み継がれるのか、その魅力の源泉に迫ってみたいと思います。
「伊豆の踊子」のあらすじ
物語は、二十歳の旧制高校生である「私」が、ある種の憂鬱な気分から逃れるように伊豆へ一人旅に出るところから始まります。彼は自らの性格を「孤児根性」で歪んでいると感じており、その息苦しさから解放されたい一心で、あてのない旅を続けていました。
道中、彼は湯ヶ島の宿などで見かけた旅芸人の一座に心を惹かれ、彼らを追いかけるように天城峠を越えます。峠の茶屋で雨宿りをしている一座に追いついた「私」は、そこで十七歳ほどに見えた踊子の美しい姿と、その純粋な親切心に触れ、彼らと道中を共にすることを決意します。
身分違いの一行との旅は、「私」にとって新鮮な驚きの連続でした。蔑まれることもある旅芸人たちの素朴で温かい人柄に触れるうち、彼の閉ざされた心は少しずつ開かれていきます。特に、踊子が彼のことを「いい人ね」と話しているのを聞いた時、「私」の心には大きな変化が訪れます。
しかし、旅には必ず終わりがやってきます。一座との距離が縮まり、踊子への清らかな愛情が芽生える一方で、旅の終着点である下田は刻一刻と近づいていました。彼らの短い旅路は、どのような結末を迎えるのでしょうか。そして、この出会いと別れは、「私」の心に何を残すのでしょうか。
「伊豆の踊子」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の核心部分のネタバレに触れながら、私の感想を詳しくお話しさせていただきます。この物語の本当の素晴らしさは、青年が抱える内面的な苦悩の描写と、それが癒やされていく過程の繊細さにあると、私は感じています。
まず、この物語は単なる紀行文や恋愛小説ではない、という点に触れさせてください。これは、一人の青年が「孤児根性」という名の重い荷物を背負い、そこから解放されるまでの魂の救済の物語なのです。主人公の「私」は、自分がエリート学生であるという自覚とは裏腹に、心の中では自分を歪んだ存在だと規定し、息苦しいほどの憂鬱を感じています。
この「孤児根性」という言葉には、作者自身の孤独な生い立ちが色濃く反映されていると言われています。他人の好意を素直に受け取れず、自分と他者との間に壁を作ってしまう。そんな苦しみから逃れるための旅が、この「伊豆の踊子」の出発点なのです。ですから、彼の旅は楽しい観光ではなく、むしろ必死の巡礼に近いものだったのではないでしょうか。
そして物語は、彼が天城峠で激しい雨に追われる場面から始まります。この雨は、まるで運命が彼を特定の場所へと導いているかのような、強い意志を持った存在として描かれています。彼自身も、ただ歩いていたわけではなく、以前見かけた旅芸人一座に再会したいという「一つの期待」を胸に、彼らを追いかけていました。この、偶然を装った必然の出会いこそが、彼の浄化の旅の始まりを告げる合図だったのです。
峠の茶屋での出会いの場面は、本当に見事です。そこは、物語のテーマが凝縮された小宇宙のような空間だと感じました。古風で凛とした美しさを持つ踊子。彼女は、息を切らして入ってきた「私」に、言葉もなく座布団を直し、そっと煙草盆を寄せてくれます。この計算のない、純粋な親切心が、まず彼の心を打ちます。
その一方で、茶屋の隅には、まるで「水死人のように」生気のない老人がうずくまっています。この老人の姿は、死や衰退のイメージを強く感じさせ、主人公が抱える病的な憂鬱を象徴しているかのようです。作者は意図的に、生命力にあふれる踊子と、死の匂いを漂わせる老人を、この狭い茶屋の中に配置したのです。
この対比は、主人公がまさに「生」と「死」の岐路に立たされていることを示唆しているように思えてなりません。彼の心は老人が象徴する暗い世界に支配されています。しかし、踊子の無垢な振る舞いは、彼を光の差す「生」の側へと引き寄せる最初のきっかけとなります。この茶屋の場面は、彼の心がどちらへ向かうのかを暗示する、実に巧みな舞台装置だと感じました。
一座との同行を決意した「私」は、当時の常識からすれば、大きな一歩を踏み出したと言えます。エリート学生が、社会の底辺と見なされていた旅芸人(当時は「河原乞食」などというひどい呼ばれ方もされていました)と行動を共にする。これは、彼が自らを縛っていた身分や体面といった価値観を、自ら捨て去ろうとする意志の表れだったのでしょう。
旅をするうち、「私」は彼らが自分の噂話をしているのを耳にします。しかし、それを不快に思うどころか、むしろ親しい気持ちにさえなっている自分に気づきます。これは、彼の心の壁が少しずつ溶け始めている証拠です。そして、彼は決定的な言葉を聞くことになります。踊子が、何の飾り気もなく「いい人ね」と言うのを。
この一言が、彼にどれほどの衝撃を与えたことか。自分で自分のことを「歪んでいる」と信じ込んできた彼にとって、他者から、しかも何の裏表もない人々から「いい人」だと認められることは、まさに青天の霹靂だったはずです。その言葉は、彼の心に「ぽたりと清々しく落ちかかった」と表現されています。このネタバレは物語の核心の一つですが、この瞬間の感動は格別です。彼は初めて、自分自身を肯定する光を見出したのです。
物語が大きく動くのが、湯ヶ野の共同浴場での場面です。ここが、この物語の最大の転換点であり、最も象徴的なシーンだと私は思います。この場面に至るまで、「私」は踊子に対してある種の不安を抱いていました。夜、宴席に呼ばれた彼女の太鼓の音を聞きながら、彼女が客に汚されているのではないかという、醜い猜疑心に囚われてしまうのです。
この疑いは、彼の「歪んだ心」が作り出した幻影に他なりません。彼は、大人びた化粧をした踊子を、旅芸人という色眼鏡を通して見てしまい、自分の汚れた世界観を彼女に押し付けていたのです。彼の眼差しは、彼自身の心の汚れによって曇っていた、と言えるでしょう。この部分の心理描写は、読んでいて胸が苦しくなるほどです。
しかし翌朝、その歪んだ認識は、衝撃的な形で打ち砕かれます。川向こうの共同浴場から、突然、裸のままの踊子が飛び出してくるのです。彼女は「私」の姿を見つけ、喜びのあまり、自分が裸であることも忘れて、手を振って何かを叫んでいます。その「若桐のように足のよく伸びた白い裸身」を見た瞬間、「私」の心の中のすべてが洗い流されます。「子供なんだ」。その絶対的な真実が、彼の心を占めるのです。この強烈なネタバレシーンこそ、物語の浄化作用の頂点です。彼の汚れた思考は、彼女の輝くような無垢さによって、完全に洗い流されたのでした。
共同浴場での一件の後、「私」と一座の関係は、明らかに変わります。よそよそしさが消え、まるで家族のような穏やかな空気が流れるようになります。彼は栄吉と碁を打ち、その横で踊子は頬が触れそうなほど顔を寄せて盤面をのぞき込む。かつて彼を苦しめた性的不安から解放された今、その無防備な近さが、心地よい信頼の証となります。
彼はまた、一座のために物語を朗読して聞かせたりもします。それは、彼が一時的ではあっても、保護者のような役割を担い、彼らの輪の中に深く溶け込んでいく過程を描いています。孤独だった彼が、つかの間の「所属」という温かさを手に入れた瞬間です。
そして、踊子の彼への気持ちも、言葉ではなく、ささやかな行動で示されます。彼女が彼のすぐ隣に座る、ただそれだけのことに、無垢な愛情がこもっているのが伝わってきます。彼の方も、彼女が持っている桃色の櫛を旅の記念に欲しいと思うなど、初々しい恋心にも似た愛着を抱き始めています。彼はもう、旅芸人を観察する傍観者ではありません。彼女とのつながりを心から大切に思う、一人の当事者へと変わっていったのです。
別れの港と涙の意味
旅の終わりは、下田の港で訪れます。最後の夜、映画に誘うという約束も、母親に反対されて果たせませんでした。一人で映画を観た帰り道、「私」は言いようのない寂しさに涙をこぼします。どれだけ親しくなっても、越えられない身分の違いや運命という現実を、彼は痛感したのです。旅という非日常が終わる時、彼らの関係もまた終わりを告げようとしていました。
翌朝の船着場での別れの場面は、言葉がないからこそ、より一層胸に迫ります。踊子はただ、うずくまって彼を待っている。話しかけても、こくりと頷くだけ。船が離れると、やがて白いものを振り始めます。その声にならない叫びのような最後の別れは、あまりにも切なく、美しいです。ここもまた、涙なしには読めないネタバレ場面です。
しかし、物語はここで終わりません。船上で、「私」は堰を切ったように泣き続けます。その涙は、単なる別れの悲しみだけではありませんでした。見知らぬ少年に「ご不幸でも?」と声をかけられ、彼は素直に「人に別れて来たんです」と答える。かつての彼なら、他人の前で涙を見せることなど、ましてや素直に理由を話すことなどできなかったでしょう。彼の涙は、彼を縛り付けていた「孤児根性」という名の殻が、完全に溶けて流れ落ちていく浄化の涙だったのです。そして最後に彼は「後には何も残らないような甘い快さ」を感じます。これは、苦悩から解放され、空っぽになった心が、これから何でも受け入れられるという、真の自由を手に入れた瞬間の感覚だったのだと、私は解釈しています。
まとめ
「伊豆の踊子」は、一見すると清らかな旅情と淡い恋を描いた物語に見えます。しかし、その奥深くには、一人の青年が自己嫌悪と孤独という重い病から解放され、魂の再生を遂げるまでを描いた、普遍的なテーマが流れています。
主人公の「私」は、旅芸人の一座、とりわけ踊子の薫が持つ、けがれのない純粋さに触れることで、自らを縛り付けていた「孤児根性」という名の殻を破ります。彼の歪んだ心は、彼女の無垢な存在そのものによって洗い清められ、他者からの好意を素直に受け入れ、また他者へ慈悲を与えることのできる人へと変わっていくのです。
物語の結末で彼が流す涙は、単なる別れの悲しみではありません。それは、長年背負ってきた心の重荷をすべて洗い流し、新しい自分として生まれ変わるための、カタルシスの涙だったと言えるでしょう。
読後には、切ないけれども、どこか温かく、心が澄み渡るような不思議な感覚が残ります。まだ読んだことのない方はもちろん、昔読んだという方も、ぜひもう一度この浄化の物語に触れてみてはいかがでしょうか。きっと新たな発見があるはずです。