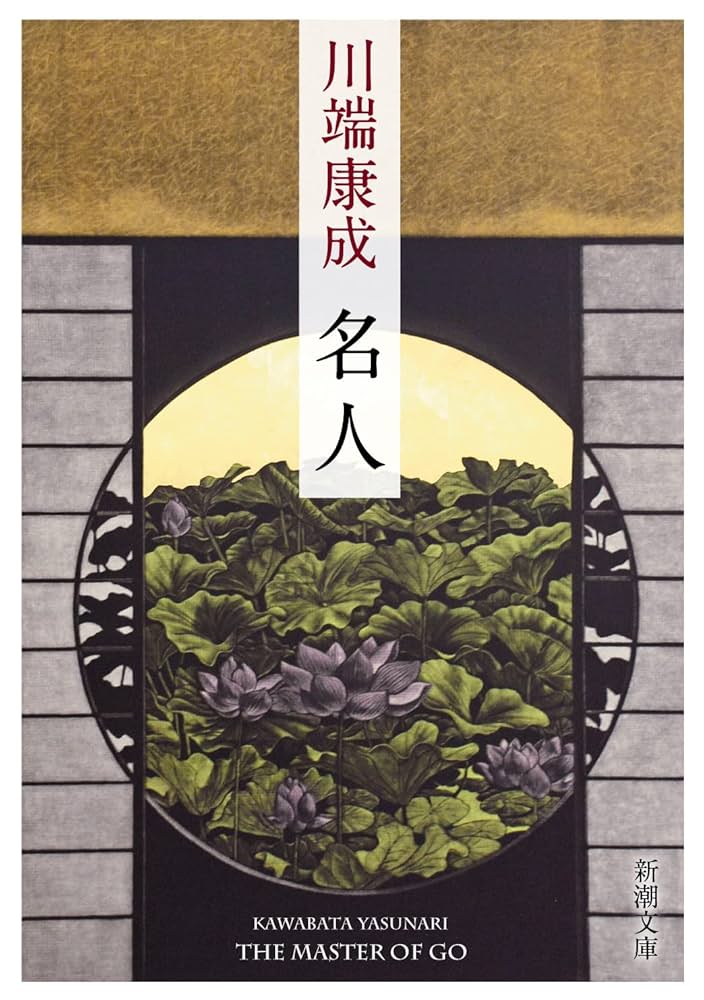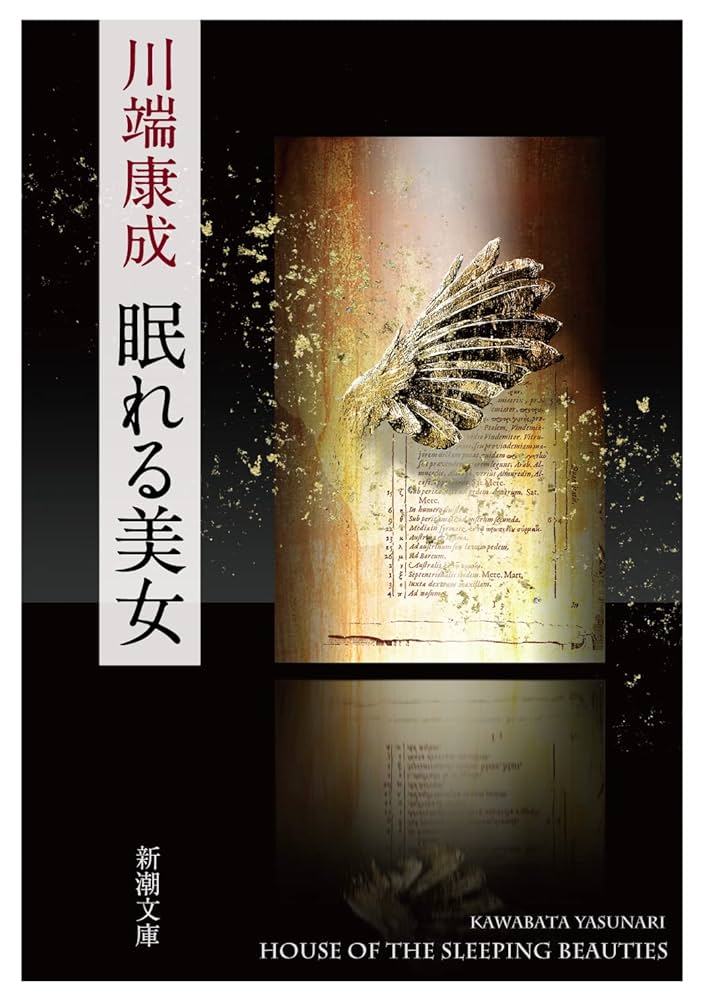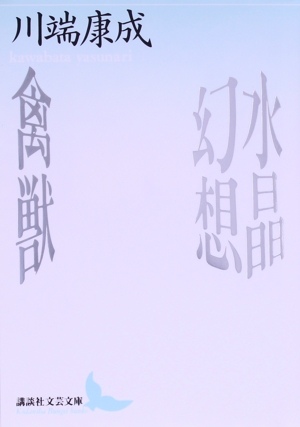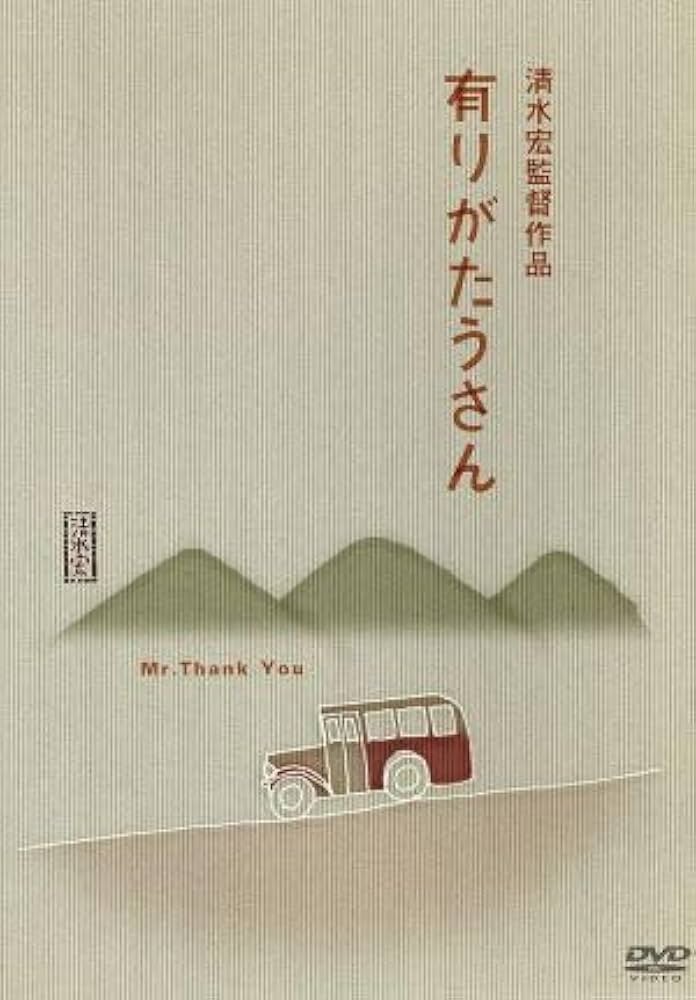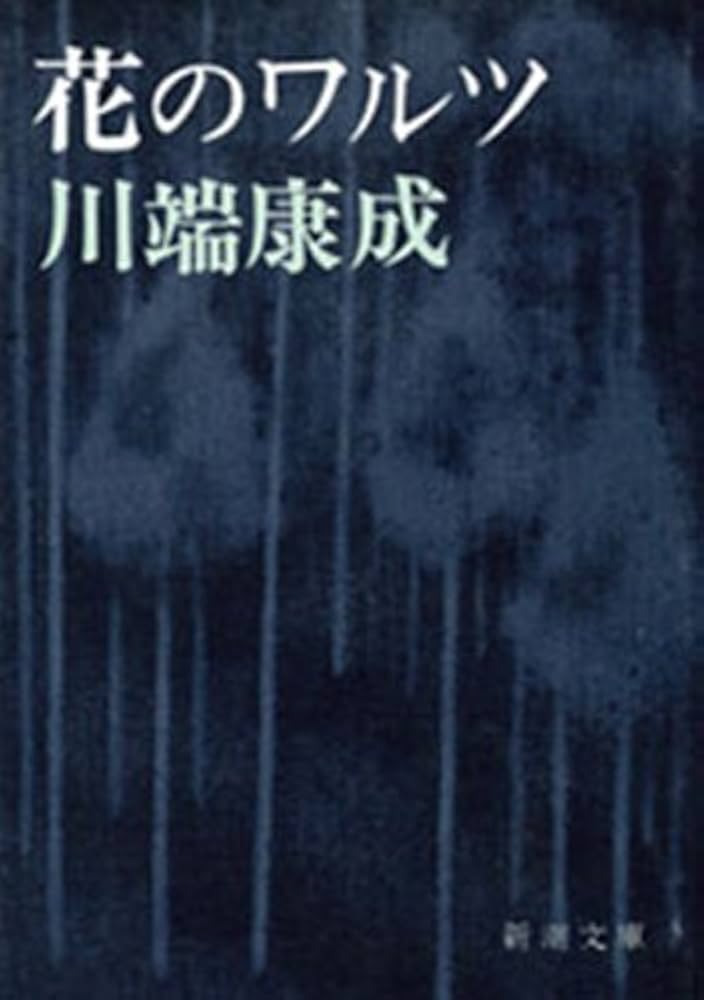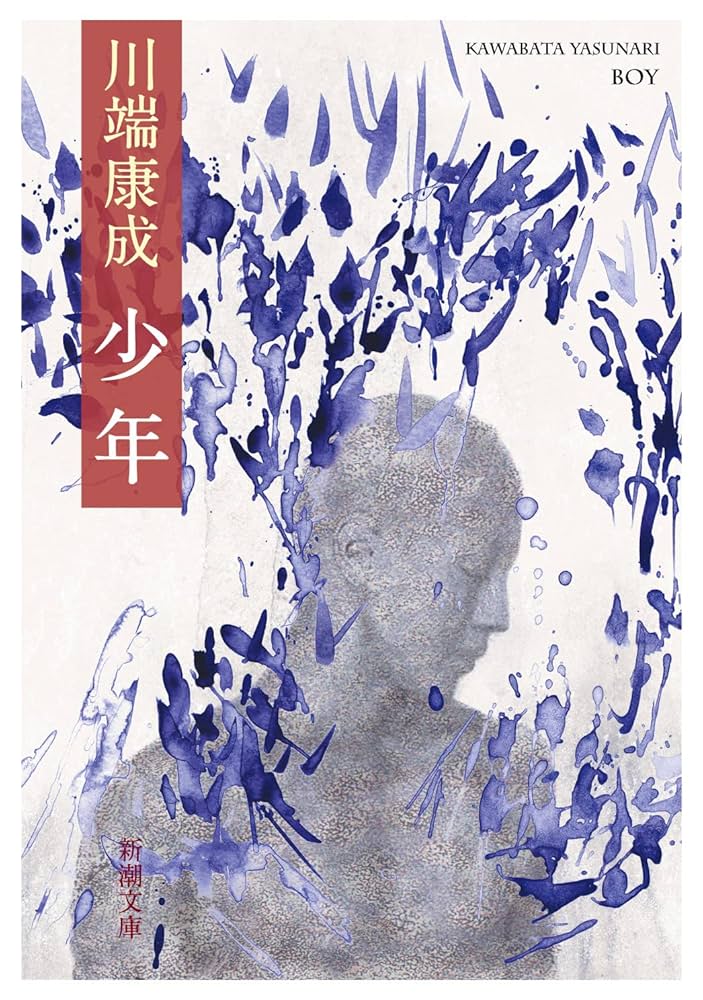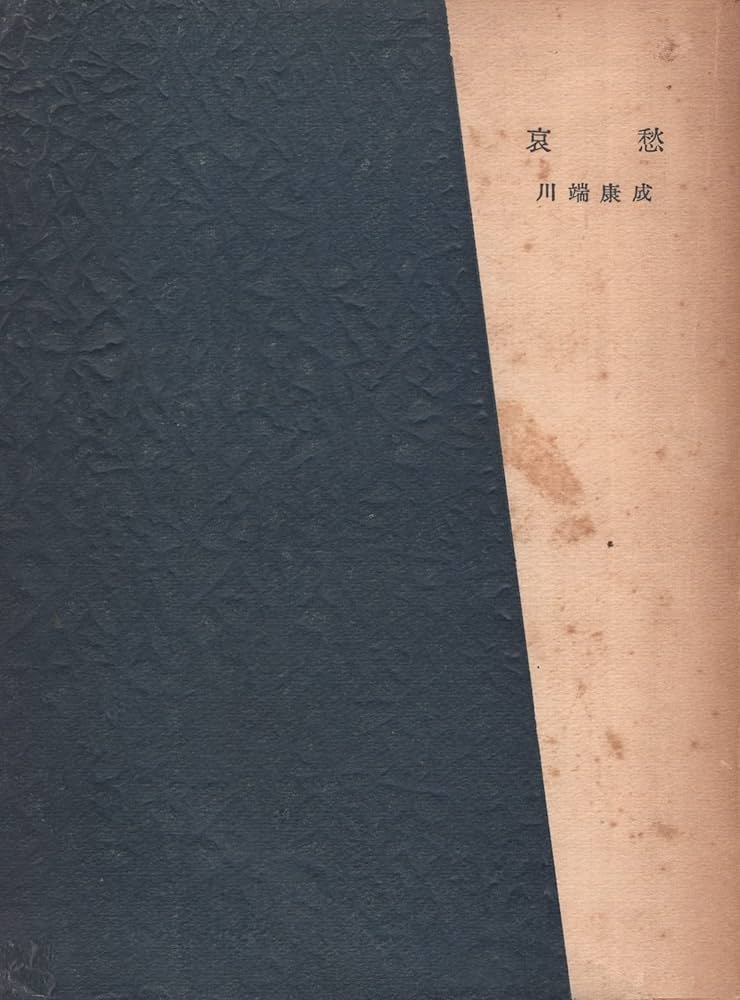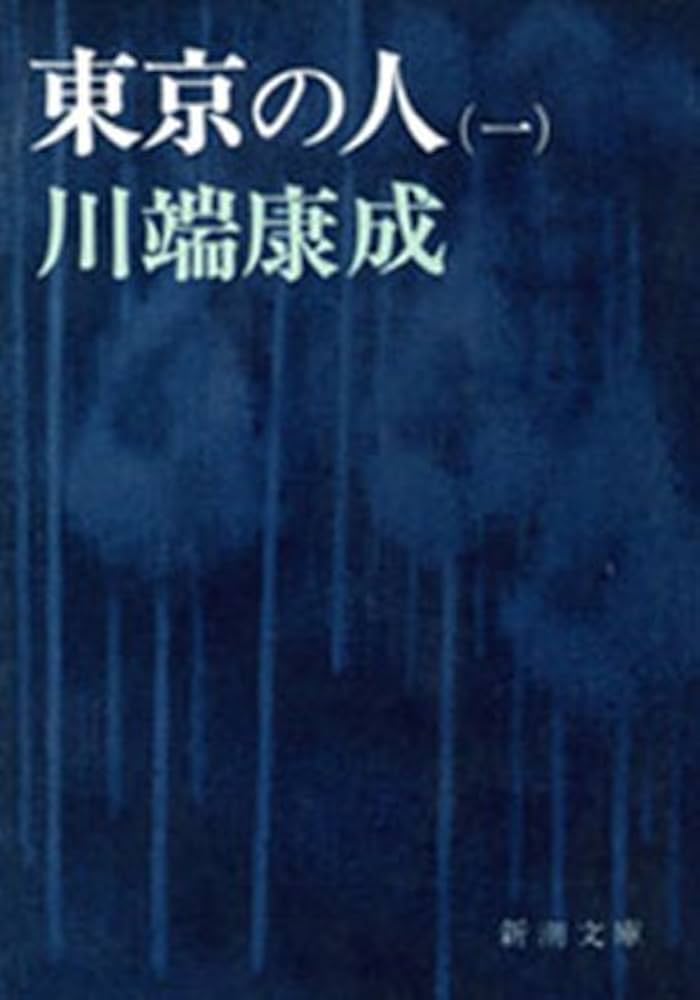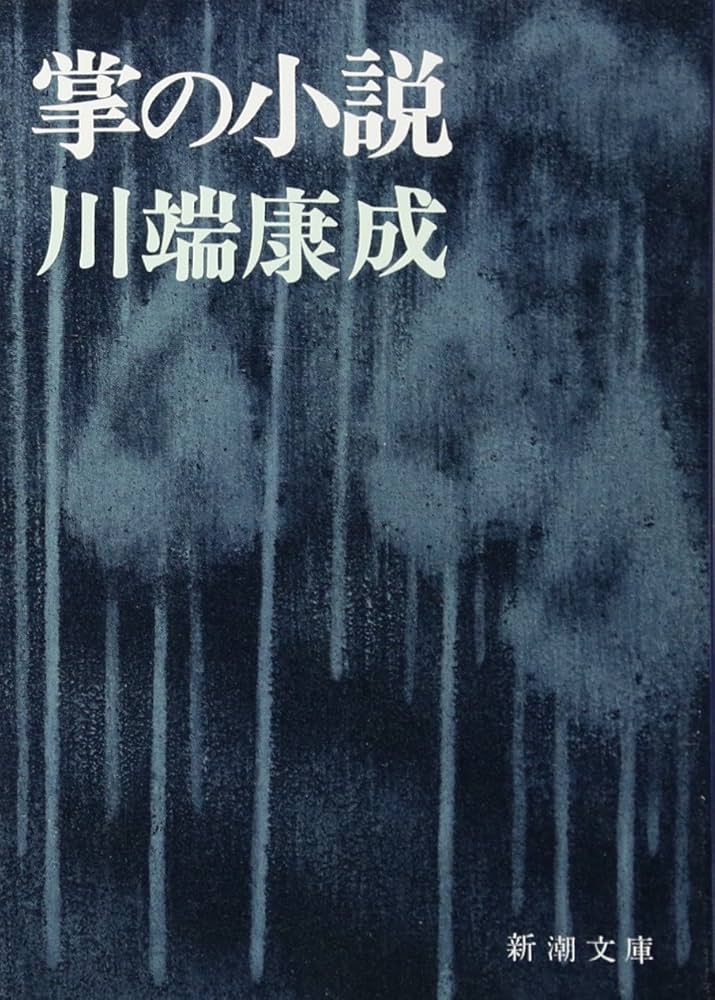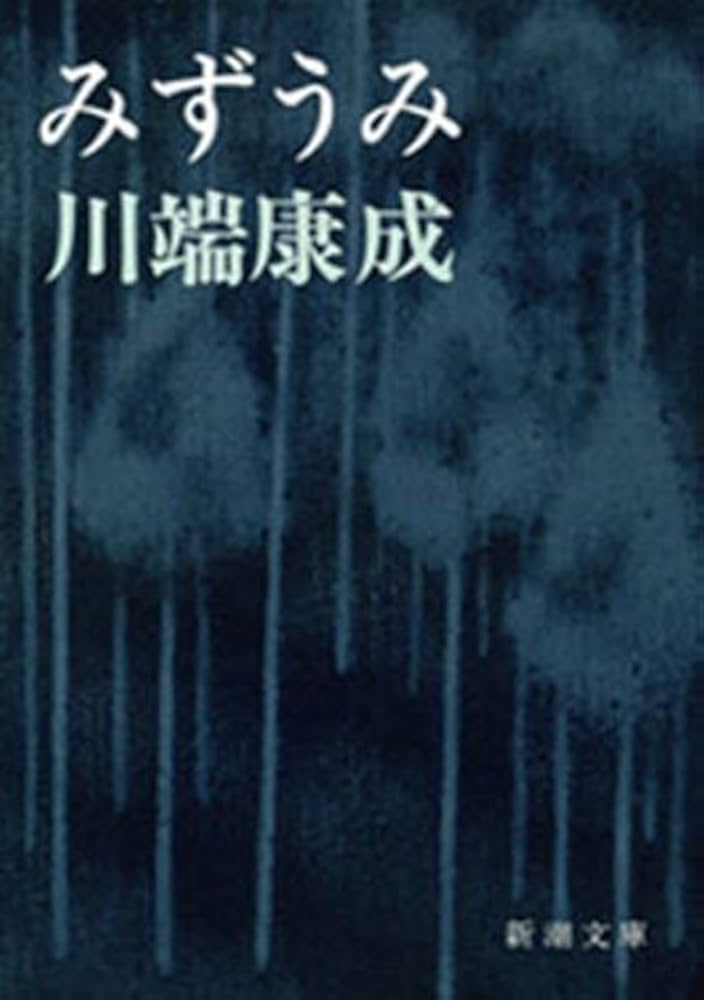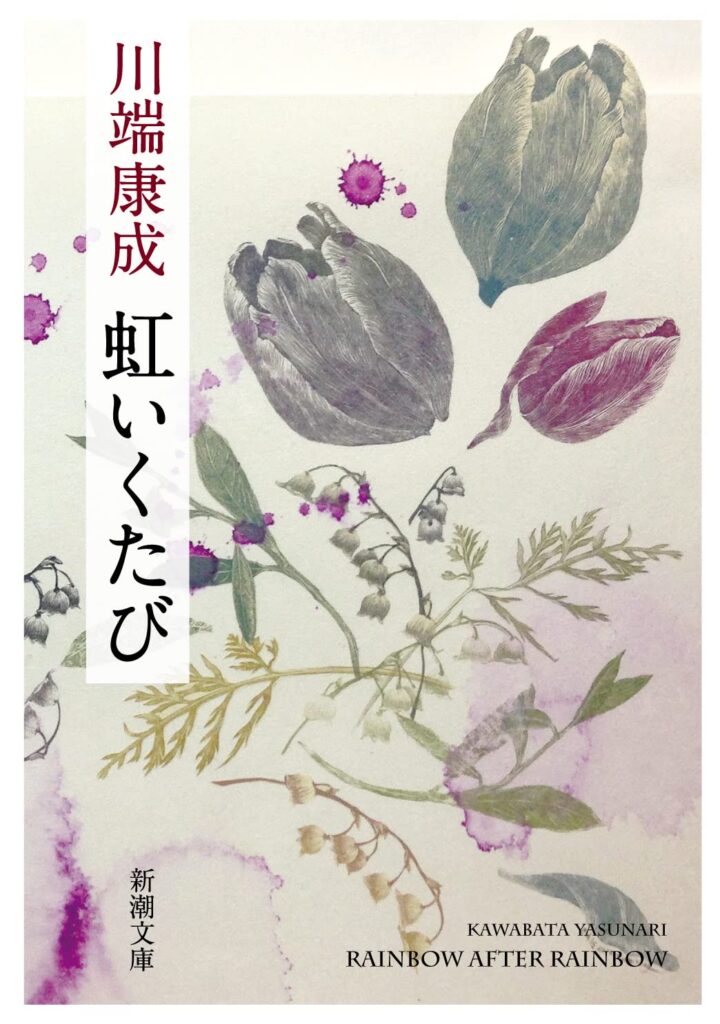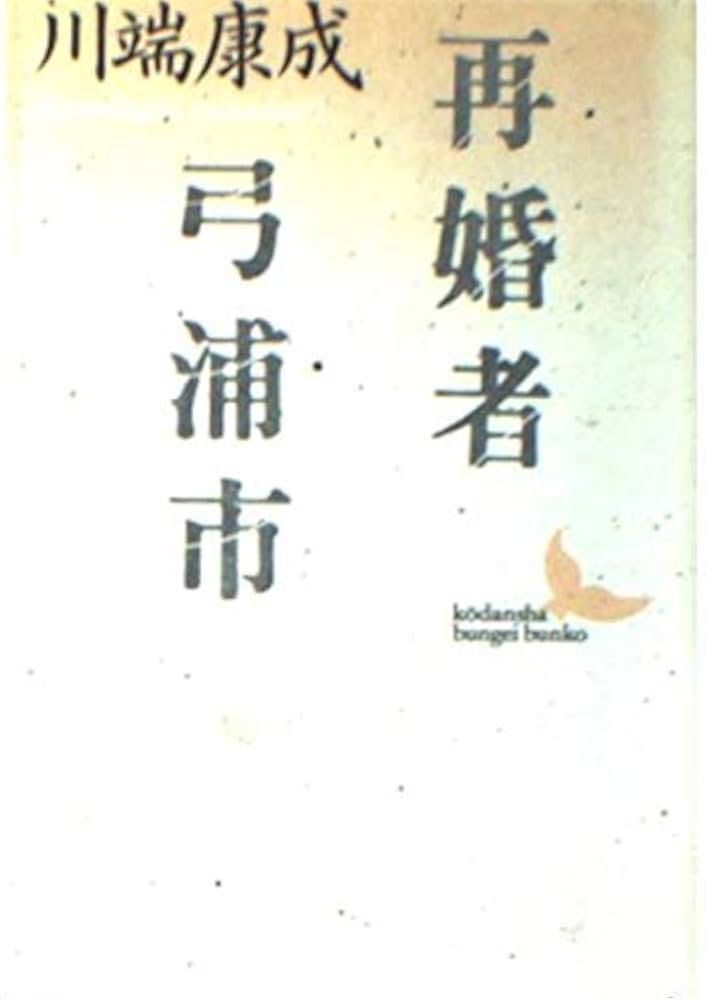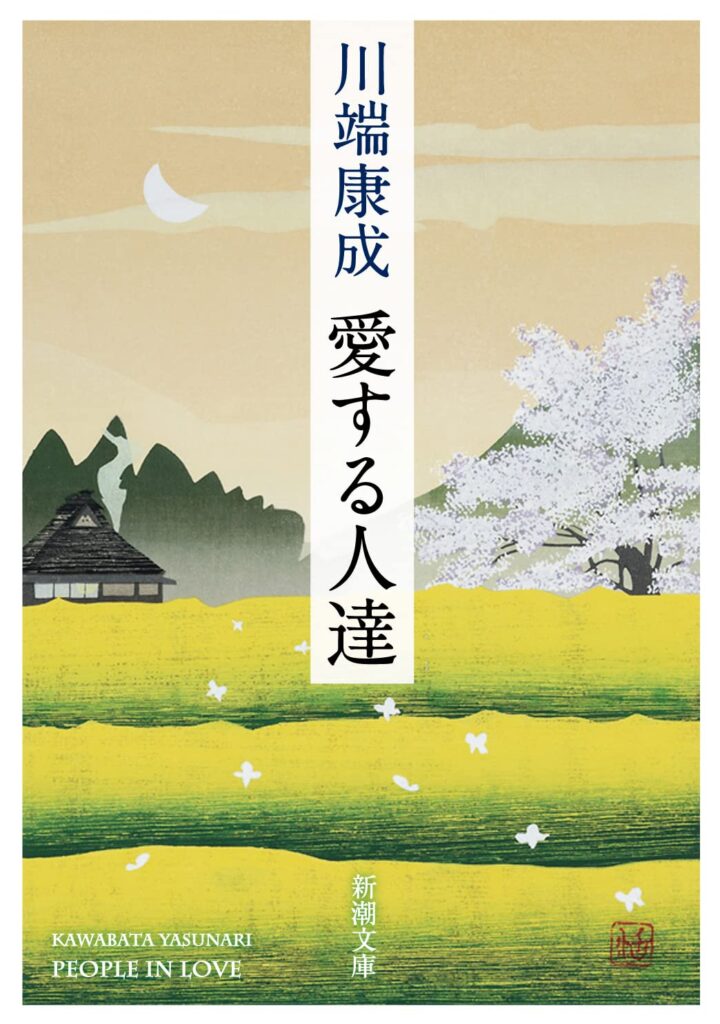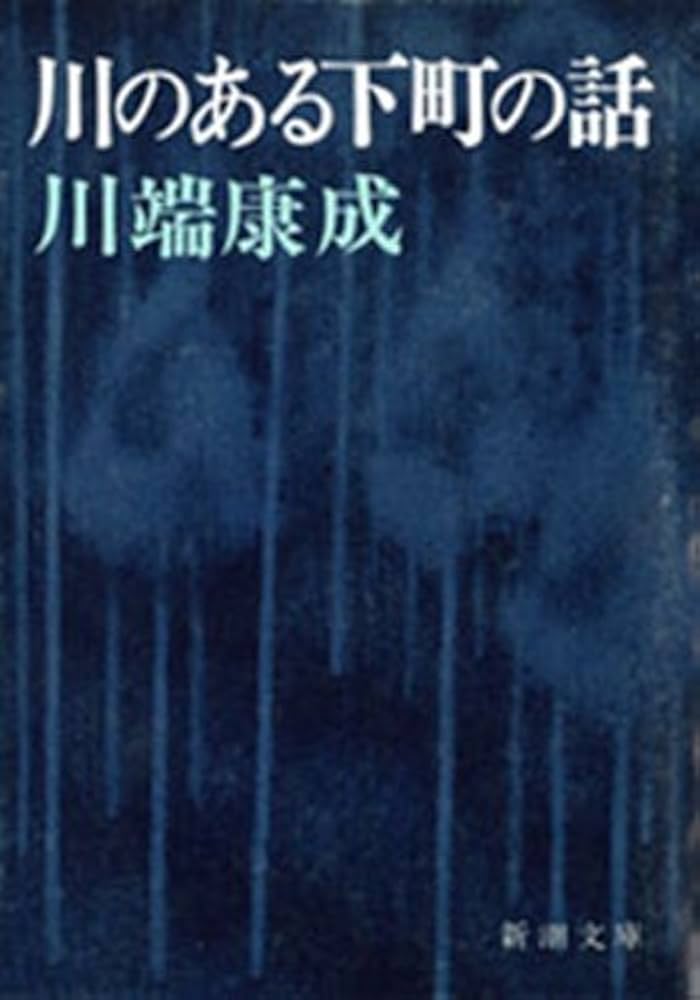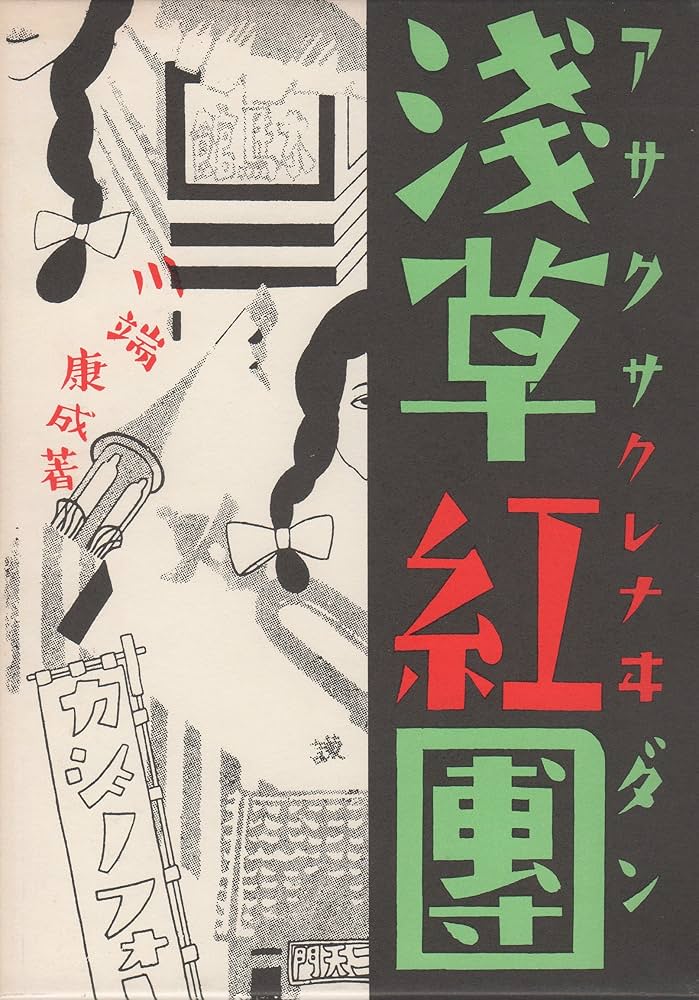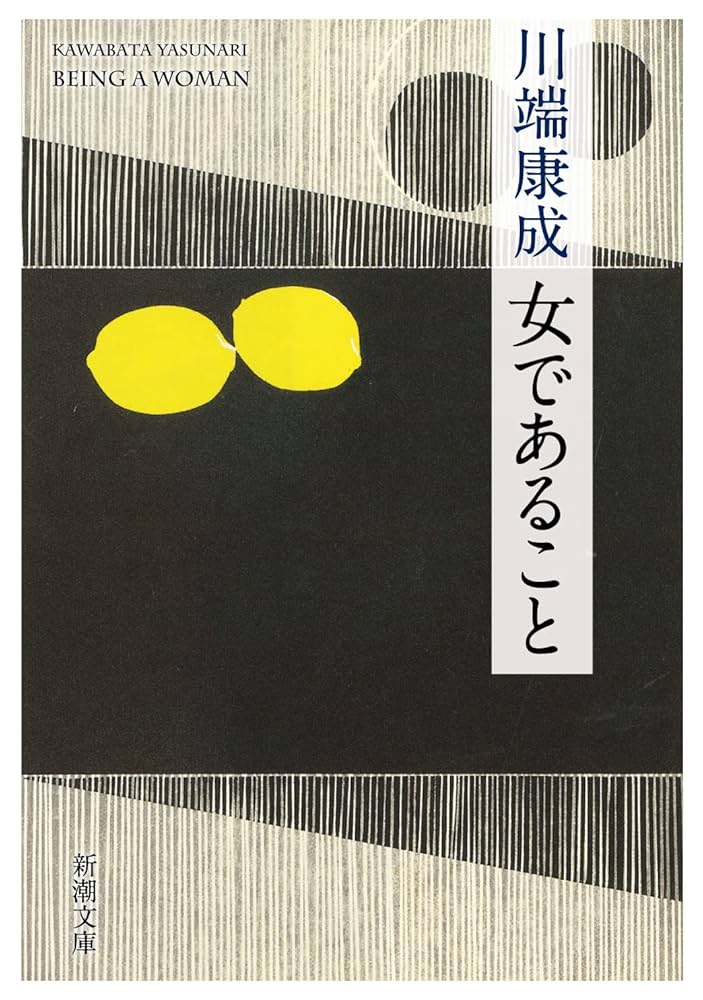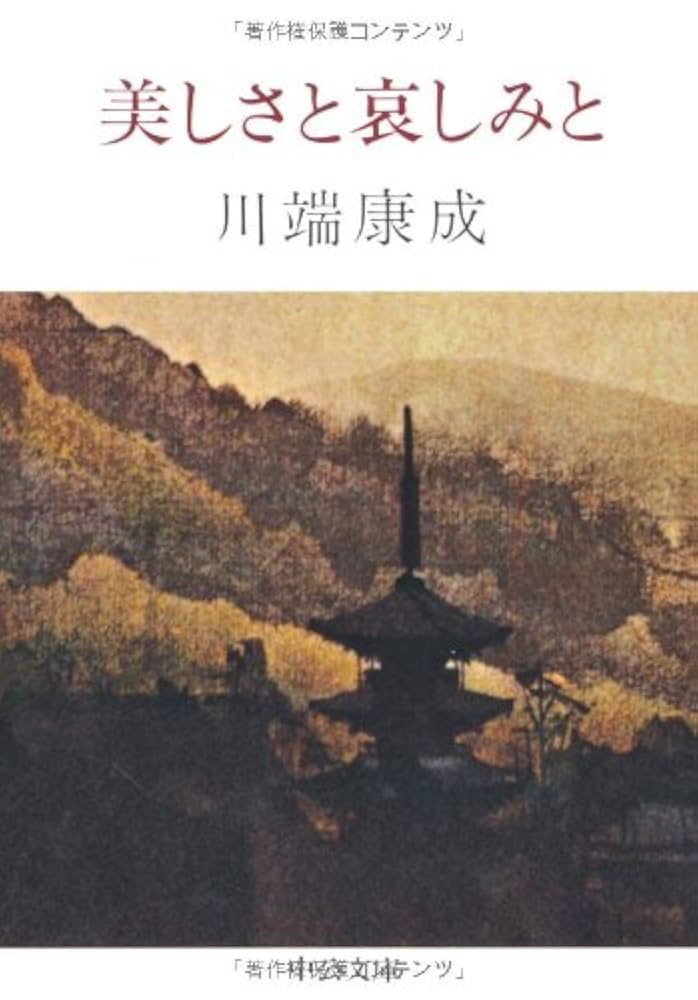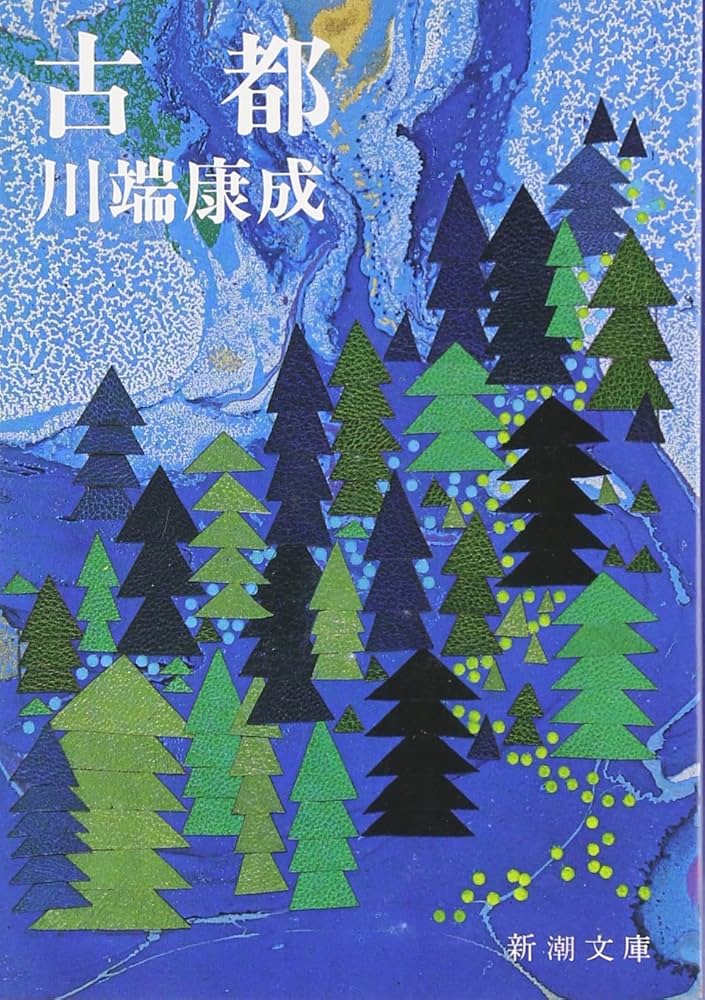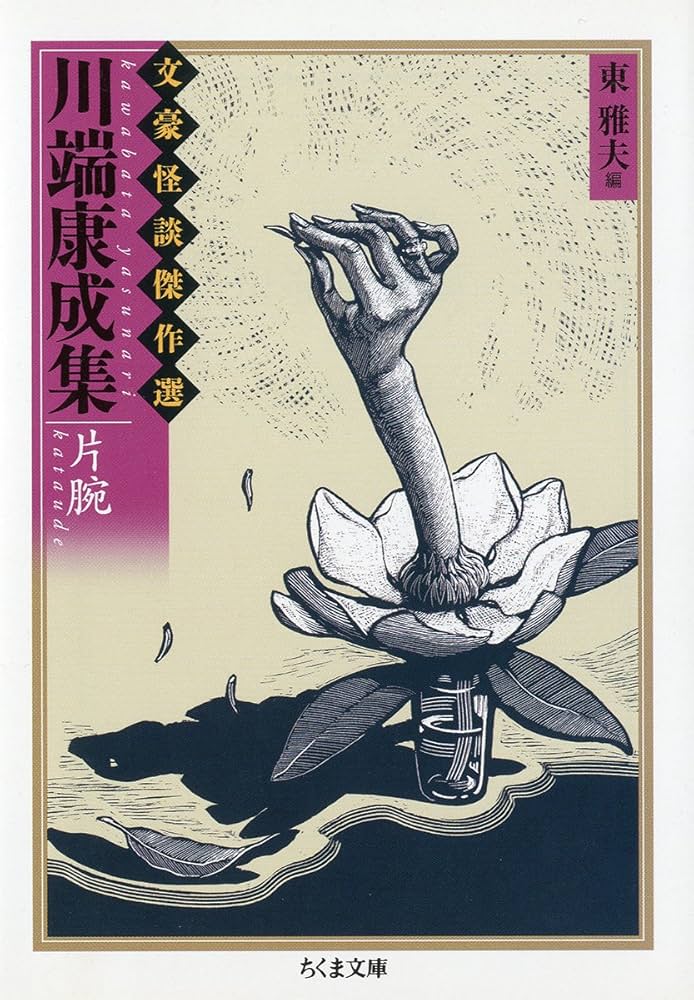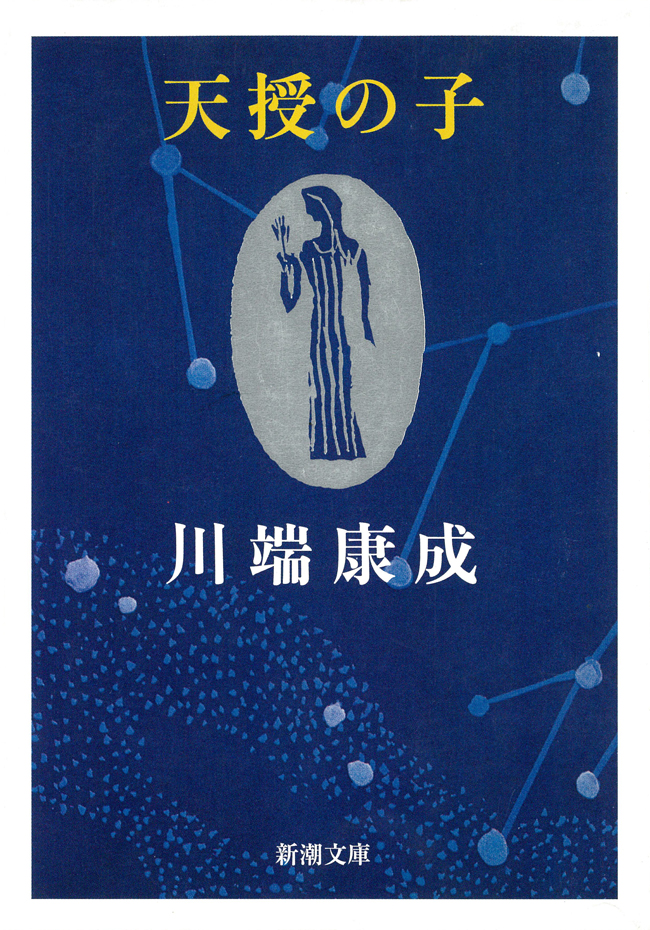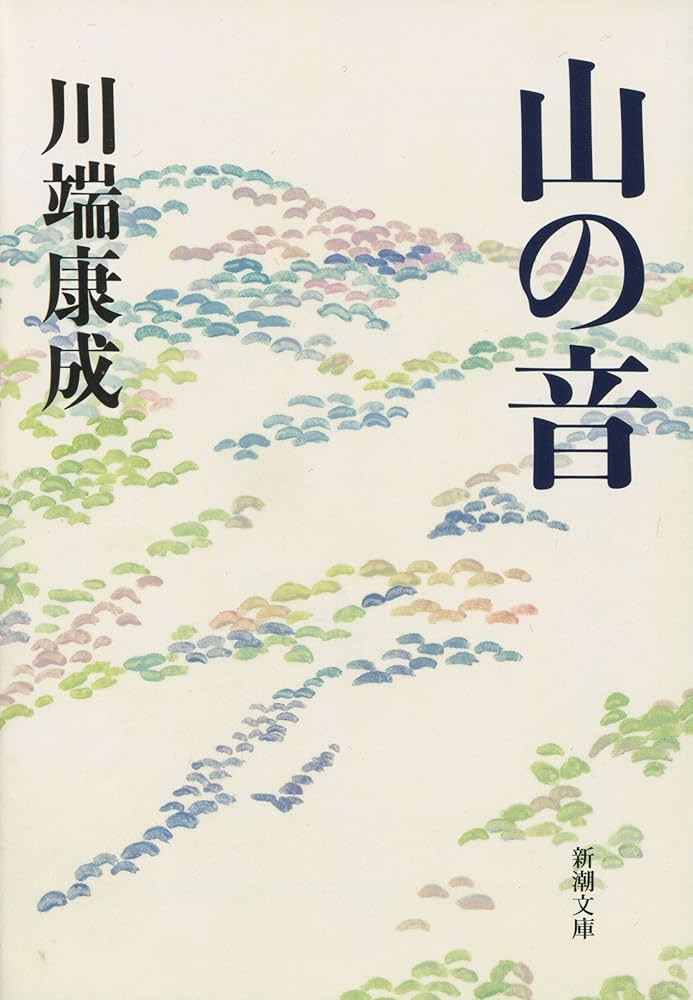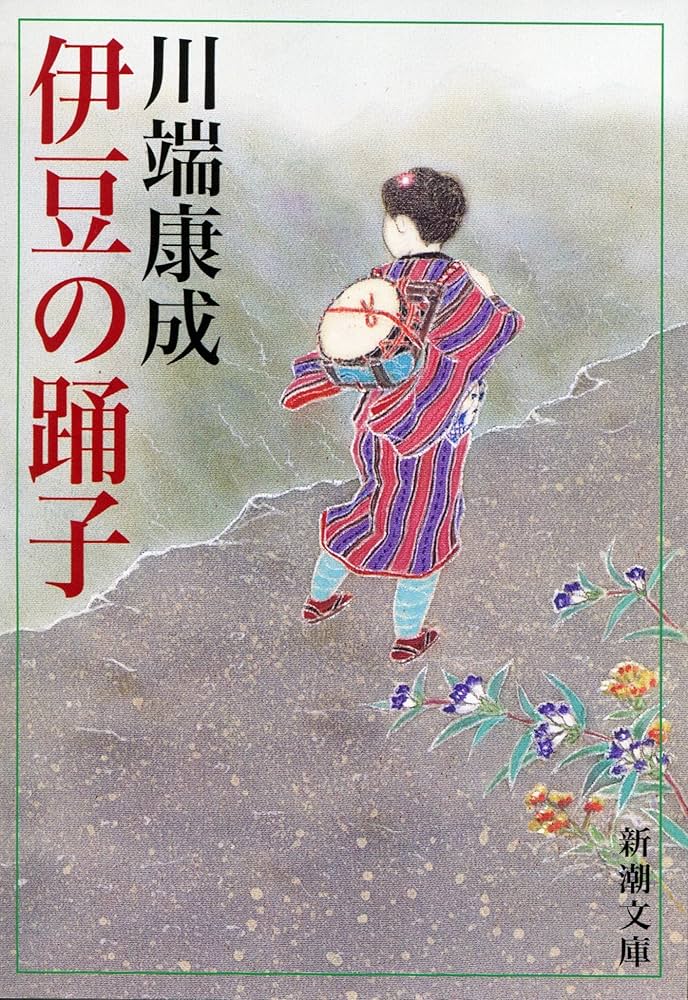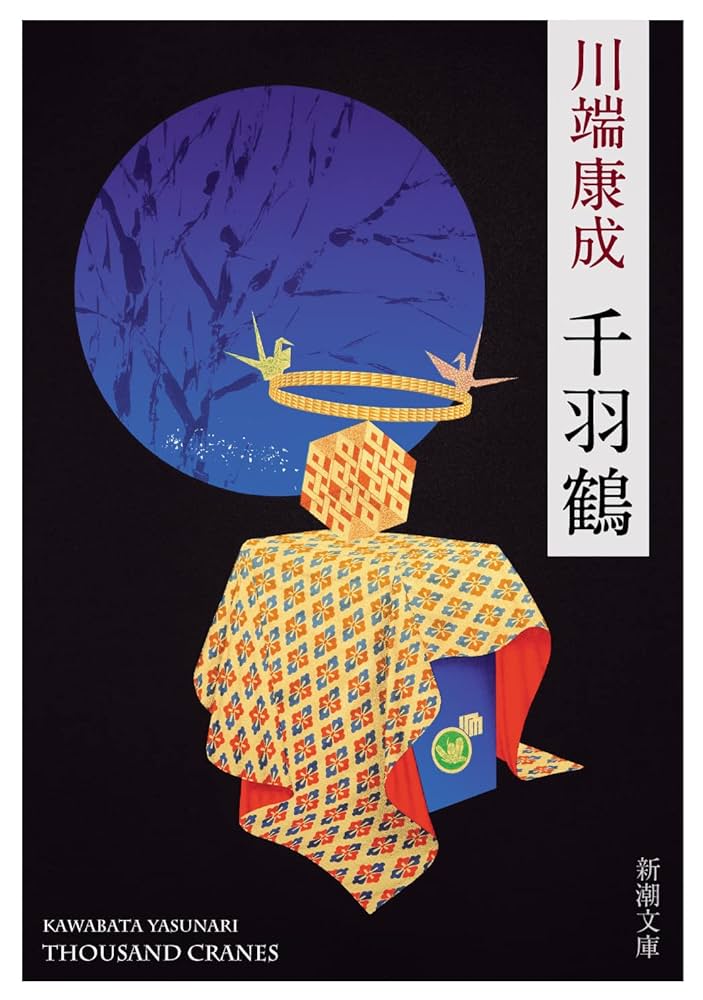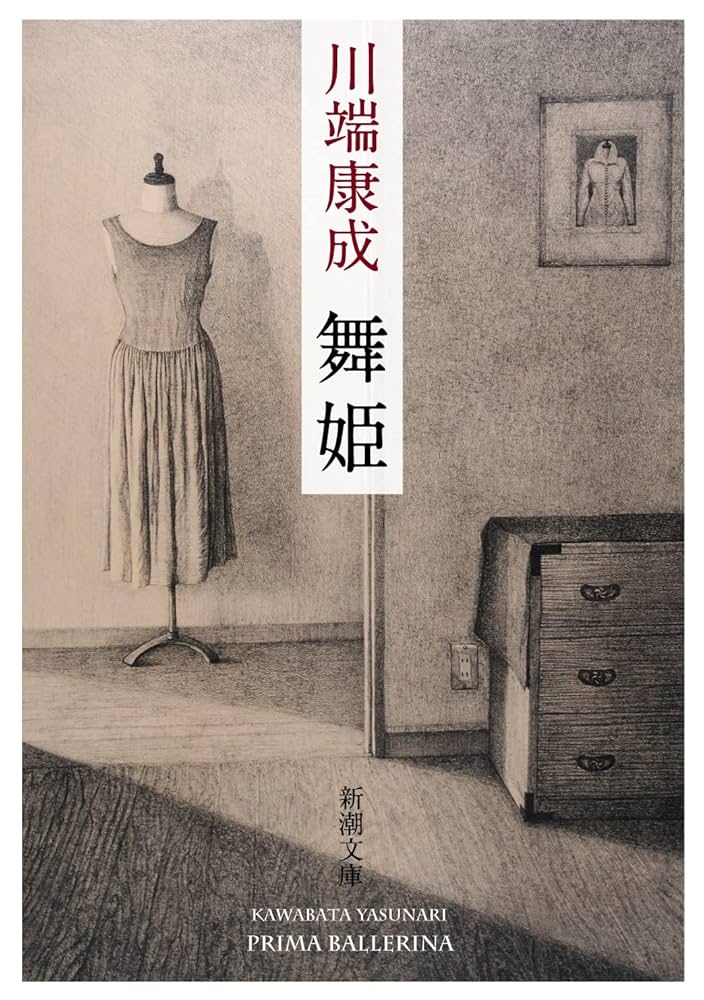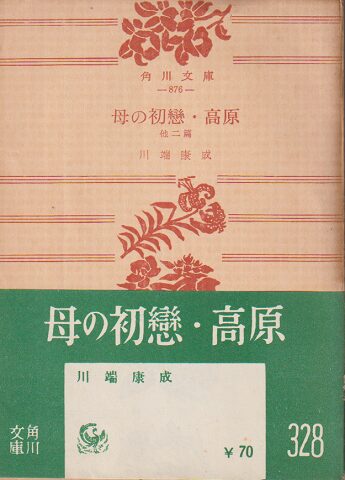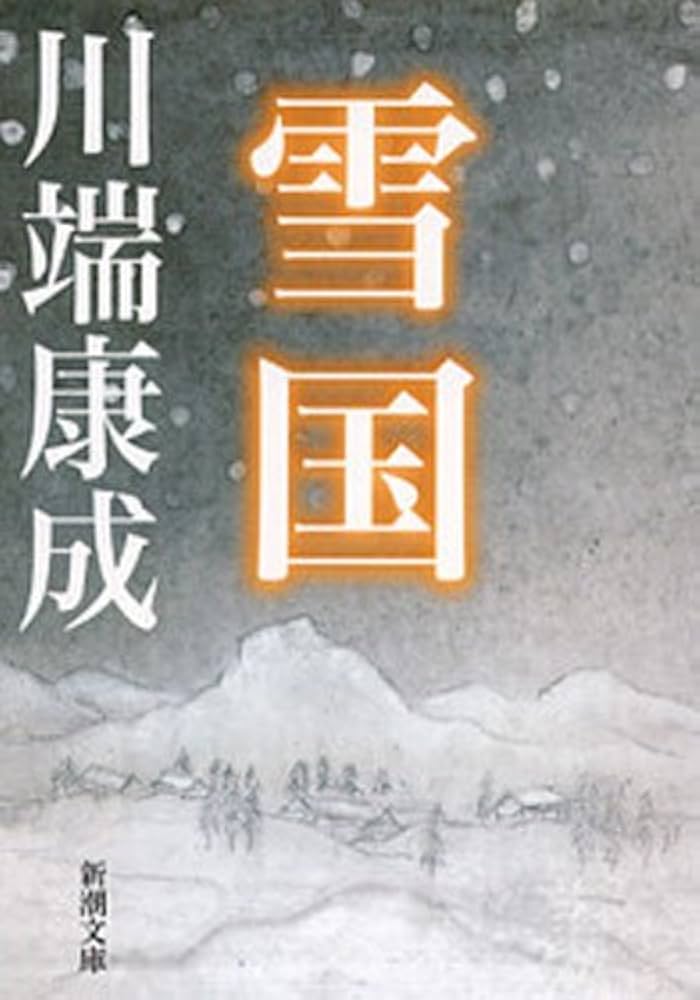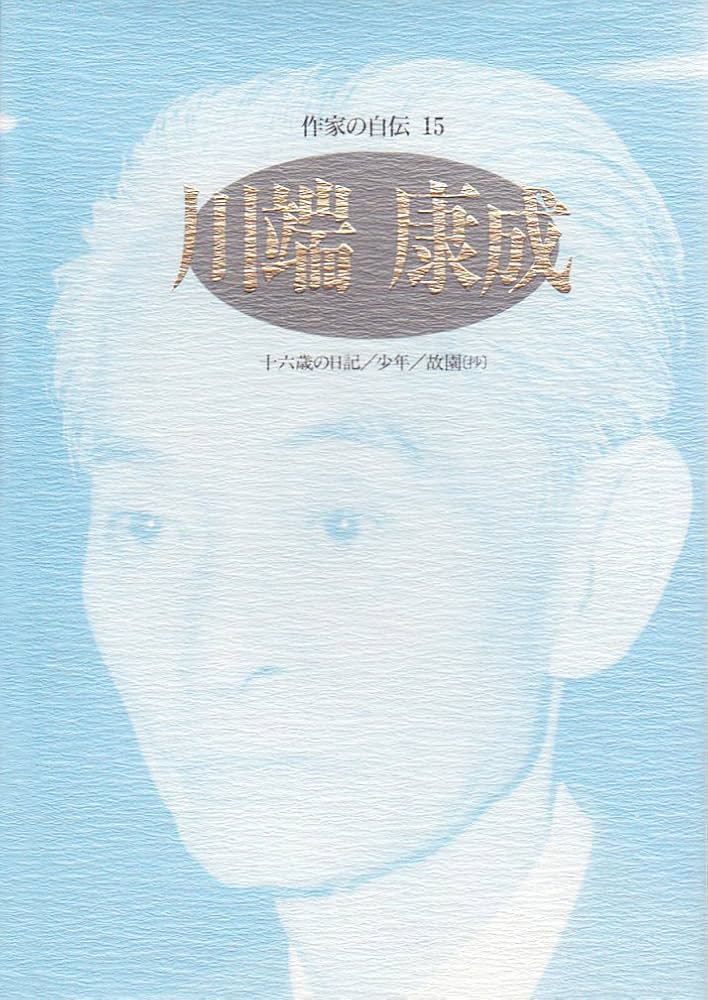小説「乙女の港」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「乙女の港」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
川端康成と中原淳一という、昭和の二人の巨匠がタッグを組んだ伝説の少女小説。それが、この『乙女の港』です。横浜のミッションスクールを舞台に、少女たちの瑞々しい、そして時に切ない感情の交錯を描いた物語は、発表から長い年月を経た今でも、私たちの心を強く揺さぶります。
この記事では、まず物語の骨格となるあらすじを、核心には触れすぎない範囲でご紹介します。どのような登場人物がいて、どのような出来事が彼女たちを待ち受けているのか。物語の世界への入り口として、お役立ていただければ幸いです。
そして後半では、物語の結末まで含んだ、ネタバレありの詳しい感想を綴っていきます。登場人物たちの心の奥底や、物語に込められた深いテーマについて、私なりの解釈を交えながらじっくりと語り尽くしました。一度読んだことがある方も、これから読もうか迷っている方も、ぜひお付き合いください。
「乙女の港」のあらすじ
物語は、主人公の三千子が横浜のお嬢様学校に入学するところから始まります。まだ学校の慣習に慣れない彼女のもとに、ある日、二人の上級生から相次いで手紙が届きます。一人は、校内で「マリア様」と慕われるほど気高く美しい最上級生の八木洋子。もう一人は、活発で情熱的な四年生の克子でした。
同級生から、それは「エス」という、上級生と下級生が姉妹のような特別な関係を結ぶための誘いだと教えられます。当時の女学校ではごく自然に行われていたこの習わしに、三千子は戸惑いながらも、次第に聖母のような洋子に心惹かれていくのでした。多くの生徒たちの憧れの的である洋子から「妹」として選ばれた三千子の学園生活は、輝かしいものになるはずでした。
しかし、三千子を諦めきれない克子の存在が、やがて三人の関係に複雑な影を落とし始めます。洋子を慕う気持ちと、克子の強烈な魅力との間で、三千子の心は激しく揺れ動きます。女学校という閉ざされた世界の中で、少女たちの純粋な思慕は、いつしか嫉妬と対立の渦を生み出していくのです。
夏休み、避暑地の軽井沢で偶然克子と再会したことで、物語は大きな転機を迎えます。洋子への罪悪感を抱きながらも、克子と過ごす時間に心を奪われていく三千子。果たして、この三人の少女たちの関係はどこへ向かうのでしょうか。秋の運動会で、彼女たちの感情はついに頂点に達します。
「乙女の港」の長文感想(ネタバレあり)
この『乙女の港』という物語は、単に美しい少女たちの友情物語、という言葉だけでは到底片付けられない深みを持っています。ここからは結末を含むネタバレに触れながら、この作品が放つ不朽の魅力について、たっぷりと語っていきたいと思います。少女たちの心の機微に、深く潜っていきましょう。
まず語らなければならないのは、この物語の根幹をなす「エス」という文化の存在です。これは上級生(お姉さま)と下級生(妹)が特別な絆を結ぶという、当時の女学校に見られた独特の習慣。現代の私たちから見れば少し不思議な制度ですが、異性との交流が厳しく制限されていた時代、少女たちの有り余る情熱や思慕の念が、同性へと向けられるのはごく自然なことだったのかもしれません。この「エス」が、単なる友情以上の、ほとんど恋に近いほどの熱量を帯びていたからこそ、『乙女の港』のドラマは生まれました。
そのドラマの中心にいるのが、主人公の三千子です。彼女の純真無垢さ、何も知らなかったがゆえの素直な心は、物語を動かす最大の原動力となります。彼女がただそこにいるだけで、周囲の少女たちの心にさざ波が立ち、やがて大きな渦となっていく。彼女は、二人の上級生の心を映し出す、澄み切った鏡のような存在だったと言えるでしょう。
その三千子が最初に心を捧げたのが、八木洋子です。成績優秀、容姿端麗、裕福な家庭に育ち、物腰は優雅で気高い。校内では「八木マリア様」とまで呼ばれる、まさに理想のお姉さま像を体現した人物です。しかし、物語を読み進めると、彼女がただの完璧なお嬢様ではないことがわかります。その輝きの裏には、病気の母を知らずに育ったという癒えない悲しみと孤独が影を落としているのです。この影こそが、彼女の人間的な深みと、後に見せる驚くべき強さの源泉となっていきます。
洋子と鮮やかな対比をなすのが、もう一人の上級生、克子です。貿易商の娘で、スポーツ万能、快活で社交的。その性格は情熱的で、一度欲しいと決めたものは決して諦めない、強い独占欲を秘めています。彼女の三千子へのアプローチは、洋子の詩的で静かなそれとは正反対の、直接的で力強いものでした。伝統的なやまとなでしこを思わせる洋子に対し、克子は近代的で自己主張の強い「モダンガール」の象徴とも言える存在です。
三千子が洋子を選んだことで、物語は静かに動き出します。しかし、それは平穏な日々の始まりではありませんでした。女学校という閉ざされた「港」は、一度感情がこじれると、逃げ場のない息苦しい空間へと変わります。洋子と三千子の関係を快く思わない者たち、そして敗北を認められない克子の存在が、悪意ある噂という形で二人の仲に亀裂を入れようとします。このあたりの、少女たちの世界の濃密さと、時に見せる残酷な一面の描写は、実に見事です。
物語の大きな転換点となるのが、夏の軽井沢です。学校という窮屈な枠組みから解放された避暑地で、三千子は偶然にも克子と再会します。ここで克子は、持ち前の行動力と魅力で三千子の心を掴んでいきます。二人で自転車に乗ったり、熱を出した三千子を甲斐甲斐しく看病したり。洋子との精神的な交流とは違う、身体性を伴った活動的な時間は、三千子にとって抗いがたい魅力でした。ここでの克子の描写は本当に生き生きとしていて、読んでいるこちらも彼女に惹きつけられてしまいます。
そして三千子の心は、洋子への忠誠と、新たに芽生えた克子への強い魅力との間で引き裂かれます。この内面の葛藤は、軽井沢の教会での告白シーンで頂点に達します。牧師の前で「あたしは悪い子ですわ。お姉さまを裏切りそうですわ」と涙ながらに懺悔する三千子。この場面は、彼女の感情がもはや単なる友情の揺らぎではなく、相手を裏切ることへの罪悪感を伴う、排他的な「恋」の領域に踏み込んでいることを明確に示しています。このネタバレは、物語の核心に触れる重要なポイントです。
夏休みが終わり、舞台は再び横浜の女学校へ。軽井沢での出来事は、三人の関係をより一層緊張させます。克子と洋子の対立は学園全体を巻き込むほどになり、その緊張は秋の運動会でついに爆発します。この運動会のシーンは、物語全体のクライマックスと言っていいでしょう。
リレーの最中、勝利への執念に燃える克子が転倒し、大怪我を負ってしまいます。この瞬間、物語は劇的に動きます。騒然とする周囲をよそに、冷静に行動したのは、他ならぬ洋子でした。彼女は的確な応急処置を施し、何よりも、動揺する三千子に対して、ライバルであるはずの克子に付き添うよう毅然と命じるのです。これは、個人的な感情を超えた、まさに「マリア様」の名にふさわしい、無私の行動でした。
この洋子の気高い行動に触れ、克子の頑なだった心は完全に打ち砕かれます。自分を憎んでいたはずの相手から示された深い思いやり。病院のベッドで、彼女はこれまでの自分の嫉妬深さや自己中心的な態度を涙ながらに三千子に告白し、謝罪します。この克子の懺悔は、読んでいて胸が詰まる名場面です。そして、洋子もまた、三千子を独占したいと願った自分の心を見つめ直し、この対立の一端は自分にもあったと省みるのです。
こうして、少女たちは傷つけ合い、苦しんだ末に、真の和解へとたどり着きます。克子の転倒という物理的な痛みは、三人の心を蝕んでいた感情的な傷を癒すための、いわば尊い犠牲だったのかもしれません。この結末に至るまでの過程で、洋子の「善」は、ただ受け身で優しいだけのものではなく、他者を救済する力強い徳性であることが証明されるのです。彼女は克子を打ち負かすのではなく、赦し、救うことによって、この恋の争いに勝利したと言えるでしょう。
物語は、しかし、これで終わりません。和解の後、静かに進行していた洋子の家庭の悲劇が明らかになります。父親の事業が破綻し、一家は没落。洋子は学業を諦めざるを得なくなります。この過酷な運命を、彼女はこれまでと同じように、静かな強さで受け止めます。このネタバレは、彼女たちの愛を次の段階へ昇華させるための、重要な布石となっています。
そして、物語のテーマが最終的に結晶するのが、クリスマスの夜のシーンです。洋子は三千子を教会へ誘います。そこで三千子が見たのは、貧しい子供たちの姿でした。洋子は三千子に語りかけます。本当のクリスマスとは、自分の持っているものを、恵まれない人々と分かち合う喜びを知ることなのだと。この言葉は、物語全体を貫く核心的なメッセージです。
あれほどまでに少女たちを苦しめた、排他的で独占欲に満ちた「エス」という一対一の「恋」。それは、この洋子の教えによって、より高次の、すべての人に向けられる無私で普遍的な「博愛」の精神へと見事に昇華されていくのです。少女たちの激しい恋愛感情の葛藤は、自己犠牲や慈愛といった、より成熟した倫理観の中に見事な着地点を見出します。この解決の仕方は、本当に見事というほかありません。
物語は、洋子の卒業という、避けられない別れで幕を閉じます。もちろん三千子は悲しみますが、そこには不思議なほどの清々しさが漂っています。二人の絆は、決して消えることはありません。洋子が去った後、今度は三千子が上級生となり、新たな後輩たちを迎える日が来る。彼女たちが苦悩の末に掴んだ愛と成長の物語は、個人的な思い出に終わることなく、この女学校の美しい伝統として、次の世代へと受け継がれていくことが示唆されます。
かくして、『乙女の港』は、単なるハッピーエンドでもバッドエンドでもない、甘く切ない、そして気高い余韻を残して終わります。少女たちの繊細な感情が一時的に停泊した「港」。そこから彼女たちは、より広い世界へと旅立っていくのです。しかし、そこで育まれた絆の記憶は、永遠に彼女たちの心に残り、未来を照らす灯台の光となることでしょう。この百合の香りが漂うような読後感こそ、『乙女の港』が時代を超えて愛され続ける理由なのだと、私は強く感じています。
まとめ
川端康成の『乙女の港』は、横浜の女学校を舞台にした、少女たちの繊細で美しい物語です。上級生と下級生が特別な関係を結ぶ「エス」という文化を中心に、三人の少女、三千子、洋子、克子の間で繰り広げられる思慕と嫉妬、そして和解と成長が描かれています。
物語のあらすじは、純真な三千子が高潔な洋子と情熱的な克子という二人の上級生の間で心を揺らすというもの。その葛藤は、やがて学園全体を巻き込むほどの対立へと発展していきます。しかし、ある事件をきっかけに、彼女たちは互いの過ちを認め合い、真の友情を育んでいきます。結末のネタバレになりますが、排他的な恋心は、より普遍的な博愛の精神へと昇華されるのです。
この物語の魅力は、美しい文章で綴られる少女たちの心理描写の巧みさはもちろん、その結末にあります。単なる恋愛沙汰に終わらせず、苦悩を通して人間的に成長し、より高次の愛に目覚めていく姿は、読む者に深い感動を与えます。
発表から長い時を経ても色褪せない、少女小説の金字塔。まだ読んだことのない方はもちろん、かつて夢中になった方も、この機会に再び「乙女の港」を訪れてみてはいかがでしょうか。きっと、懐かしくも新しい発見があるはずです。