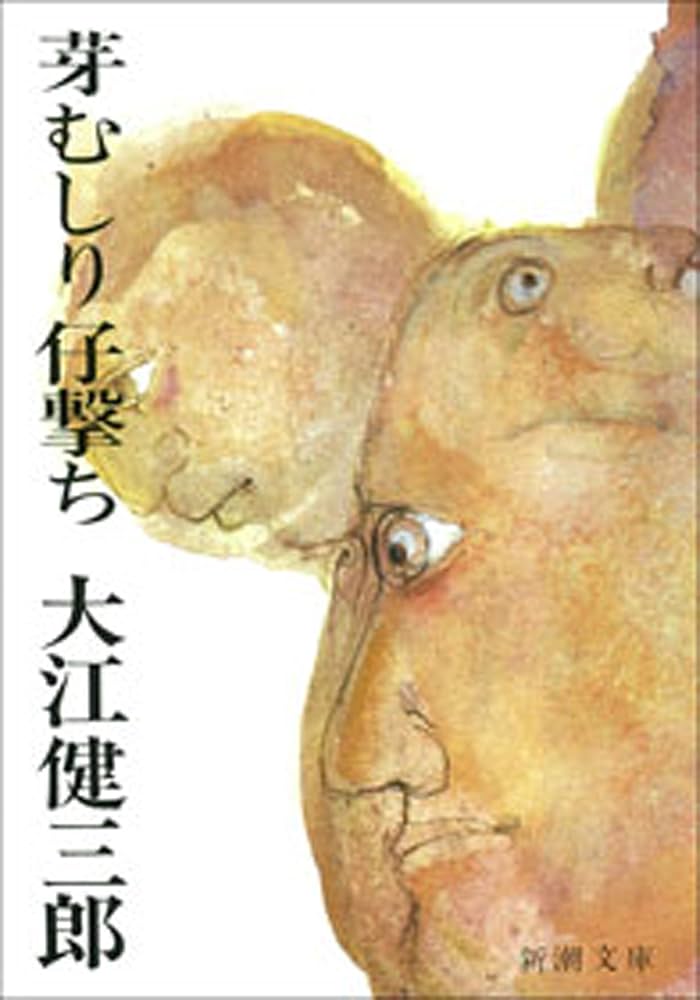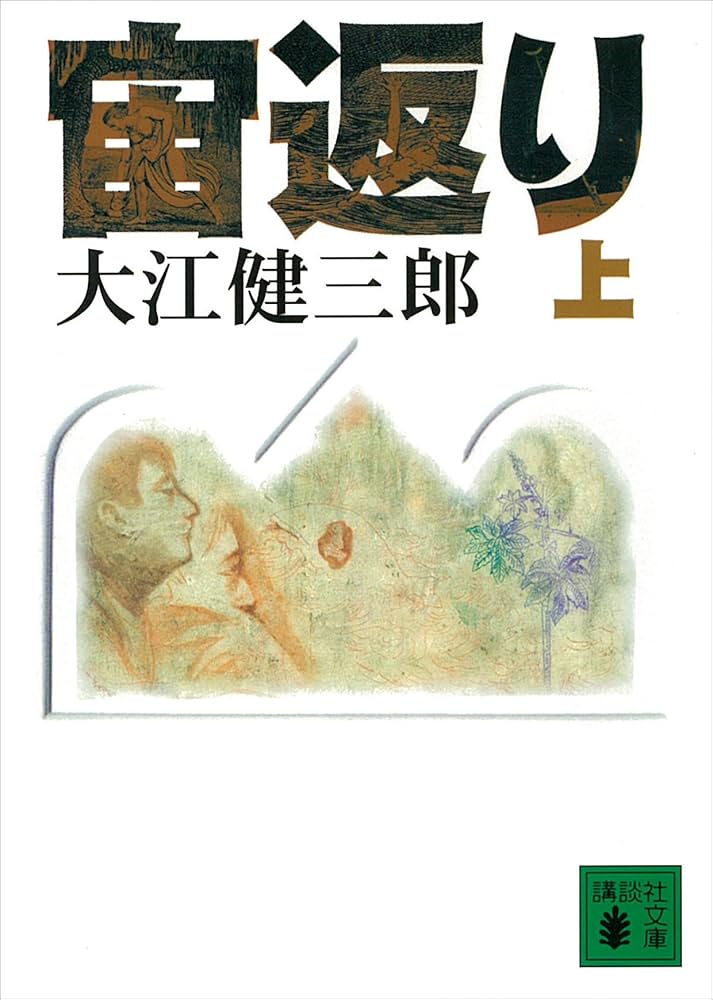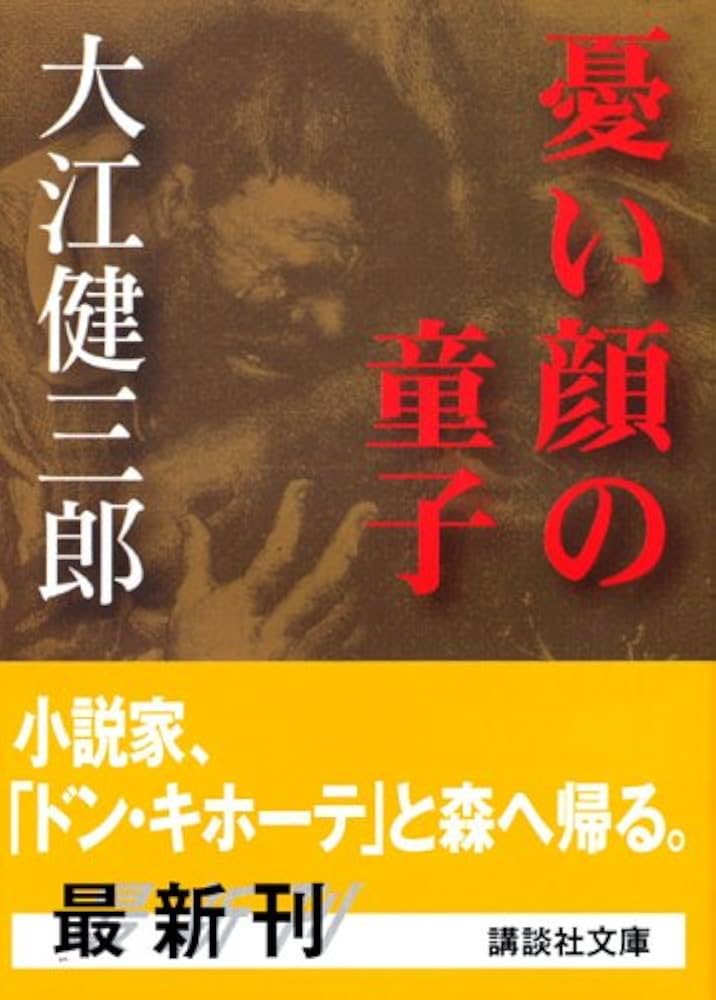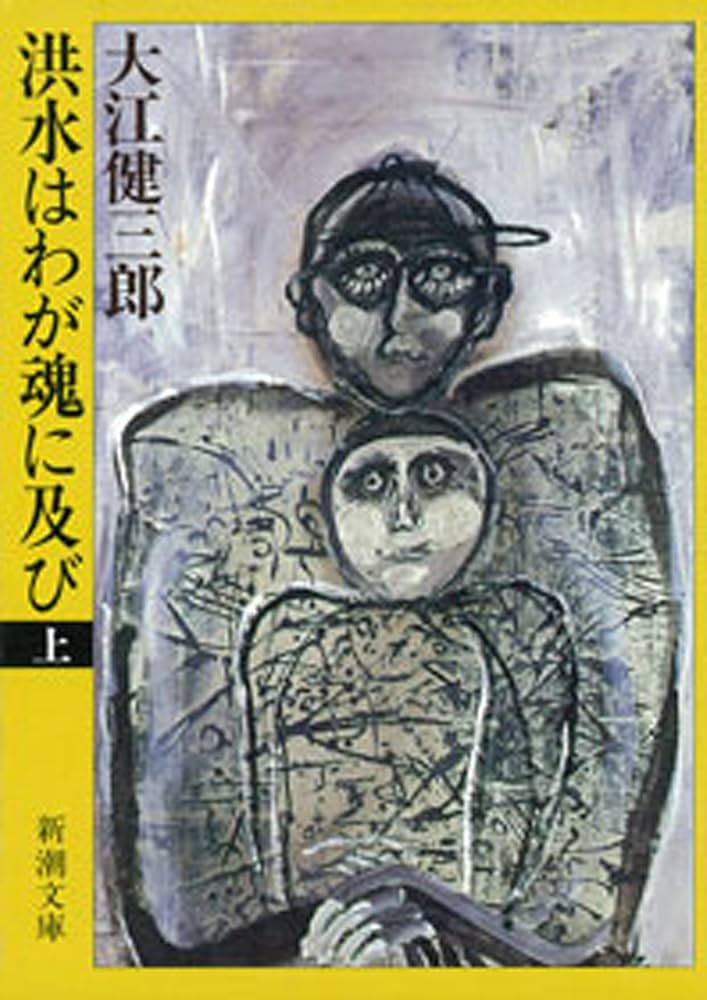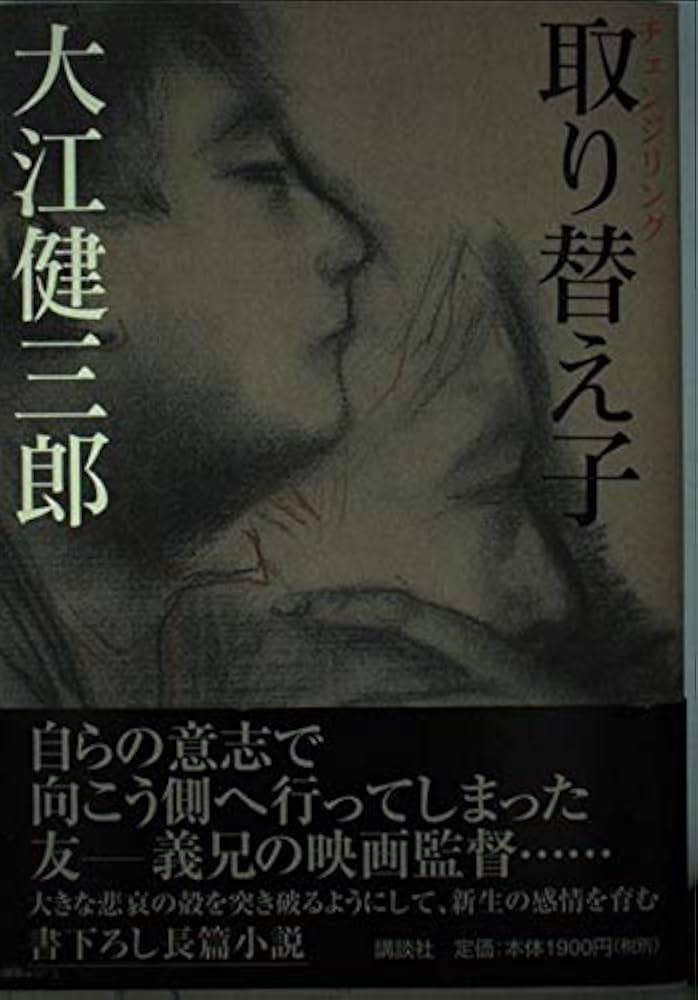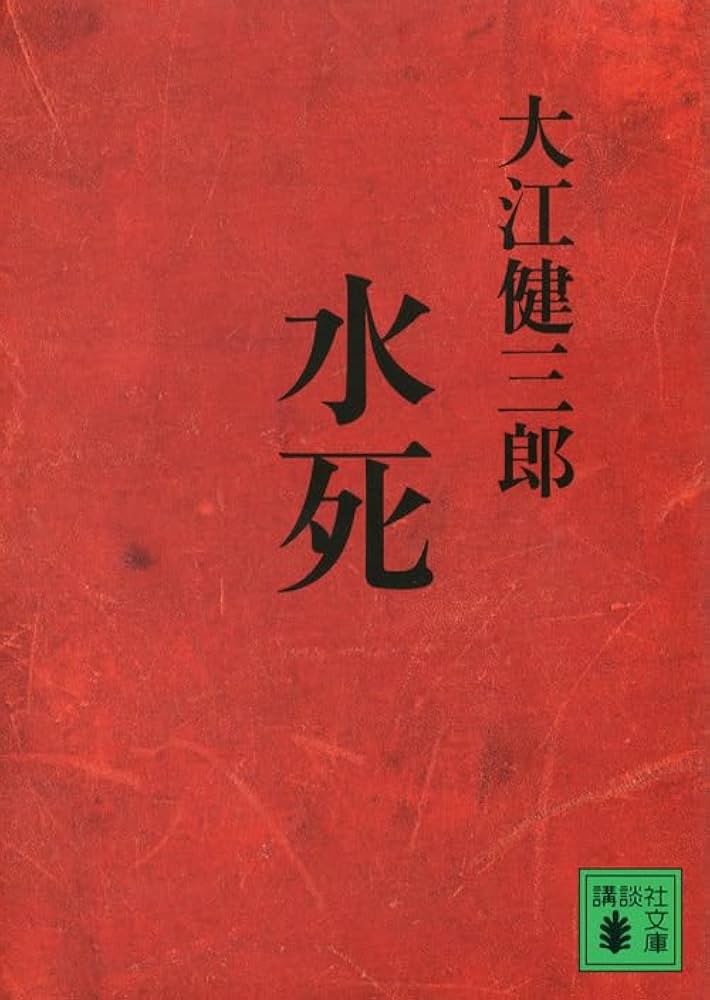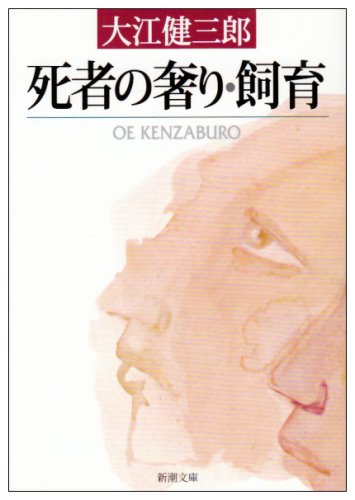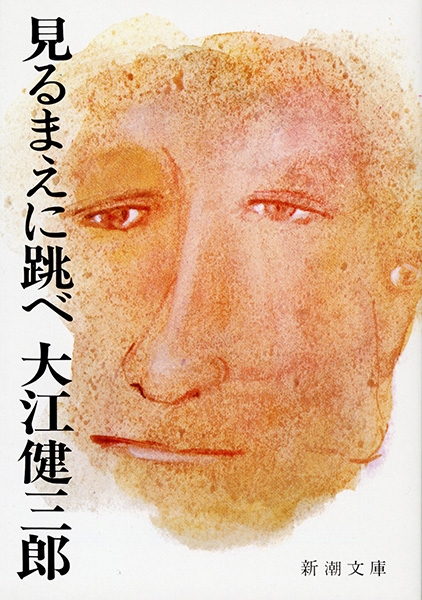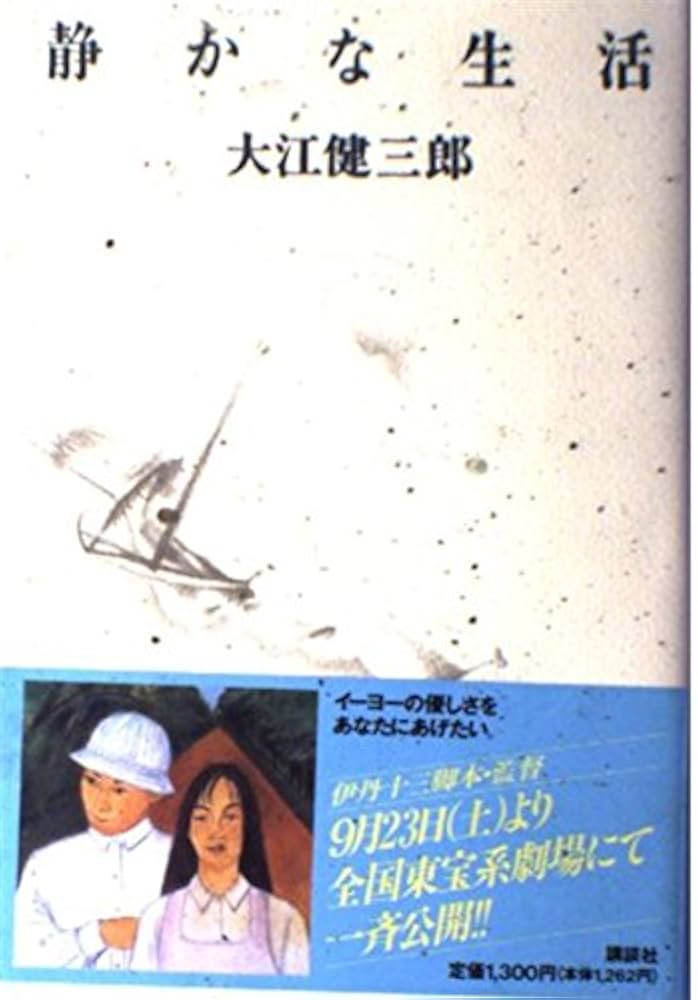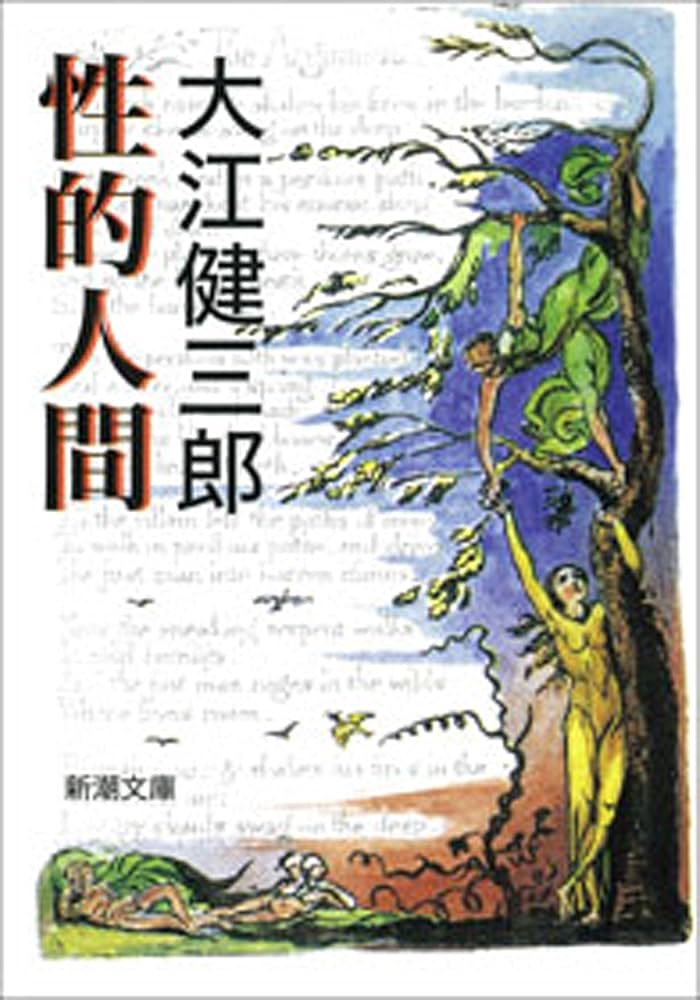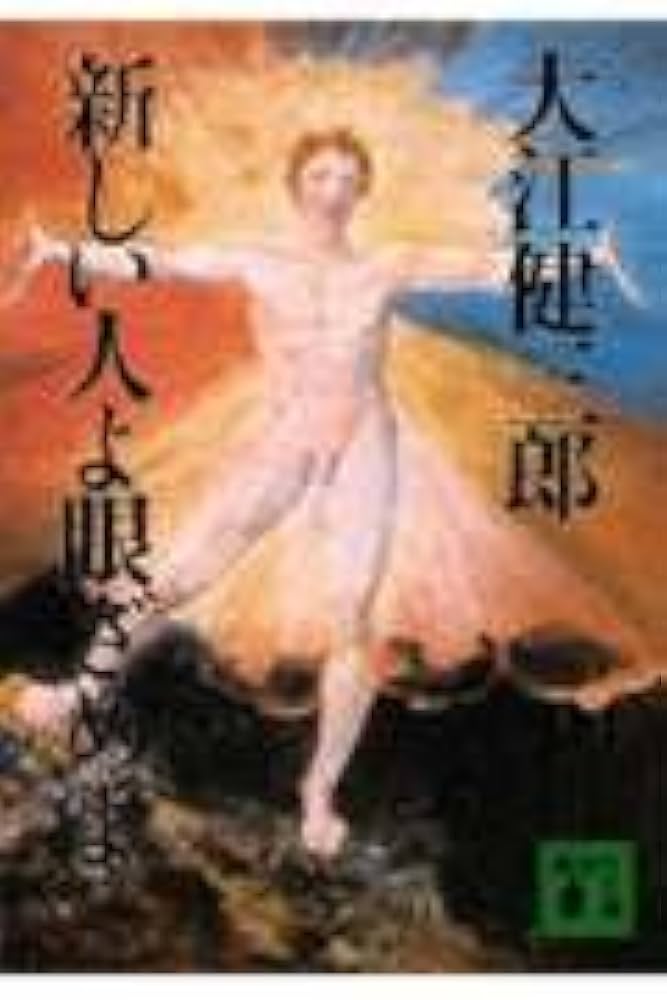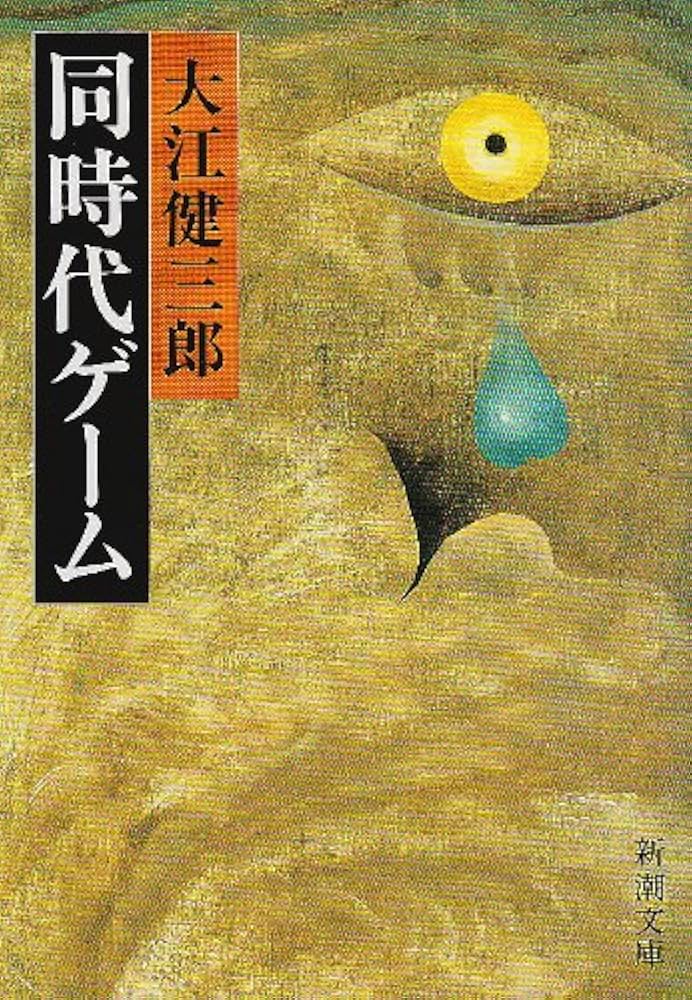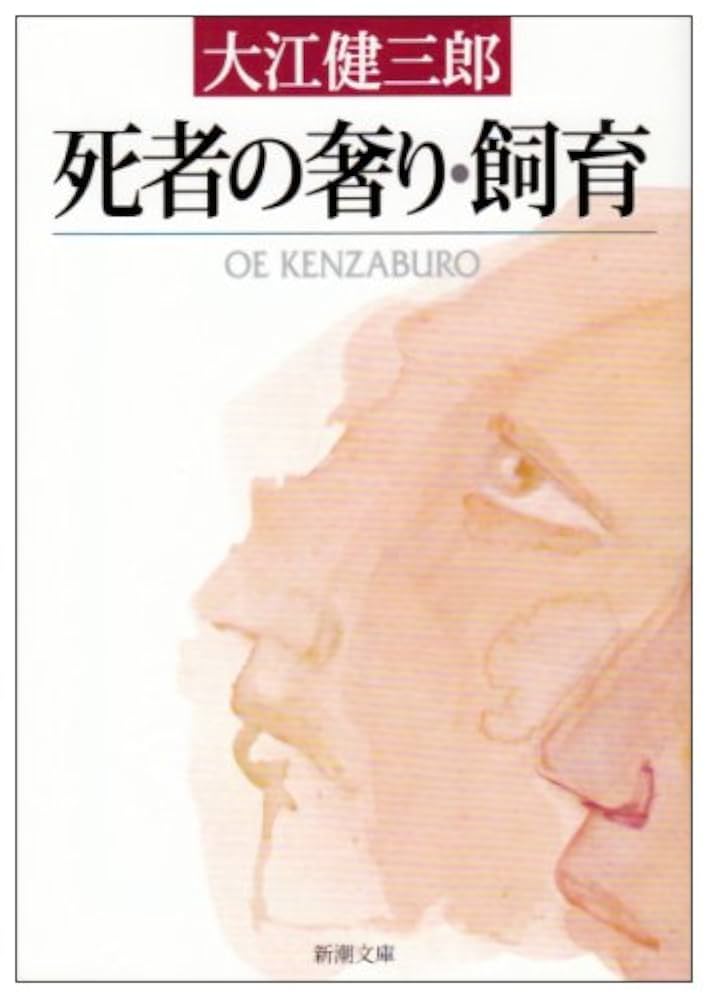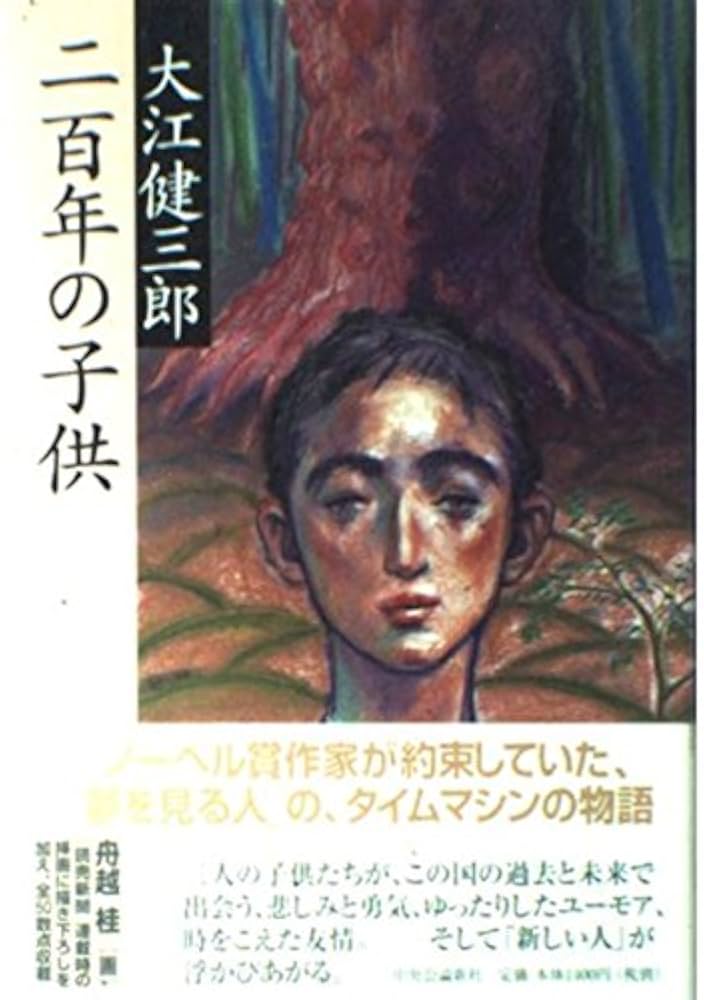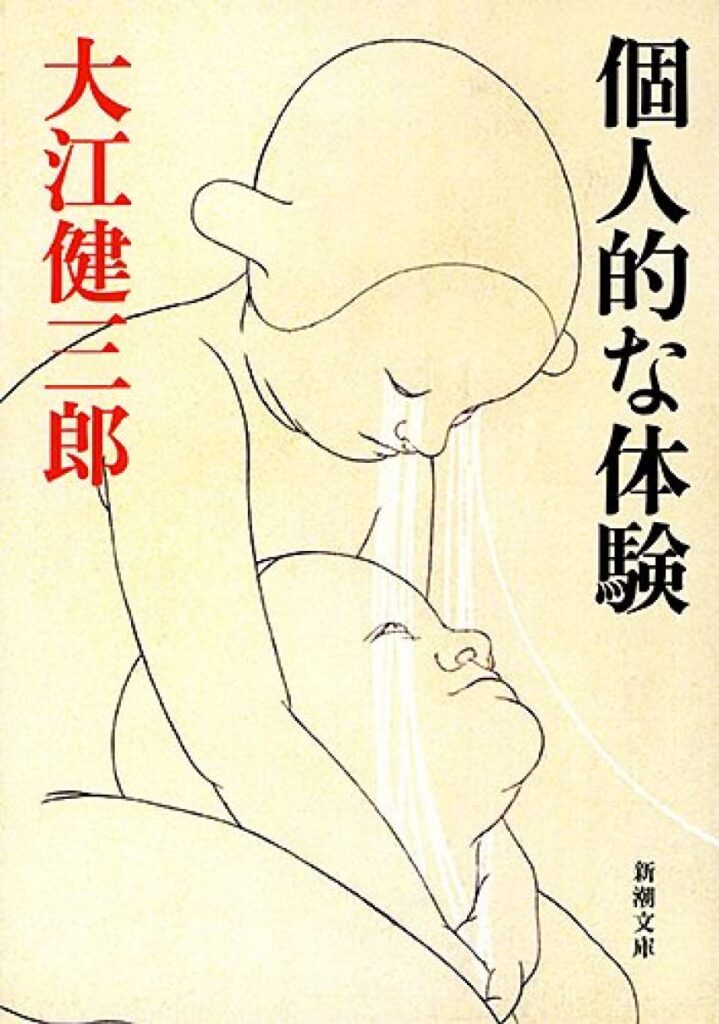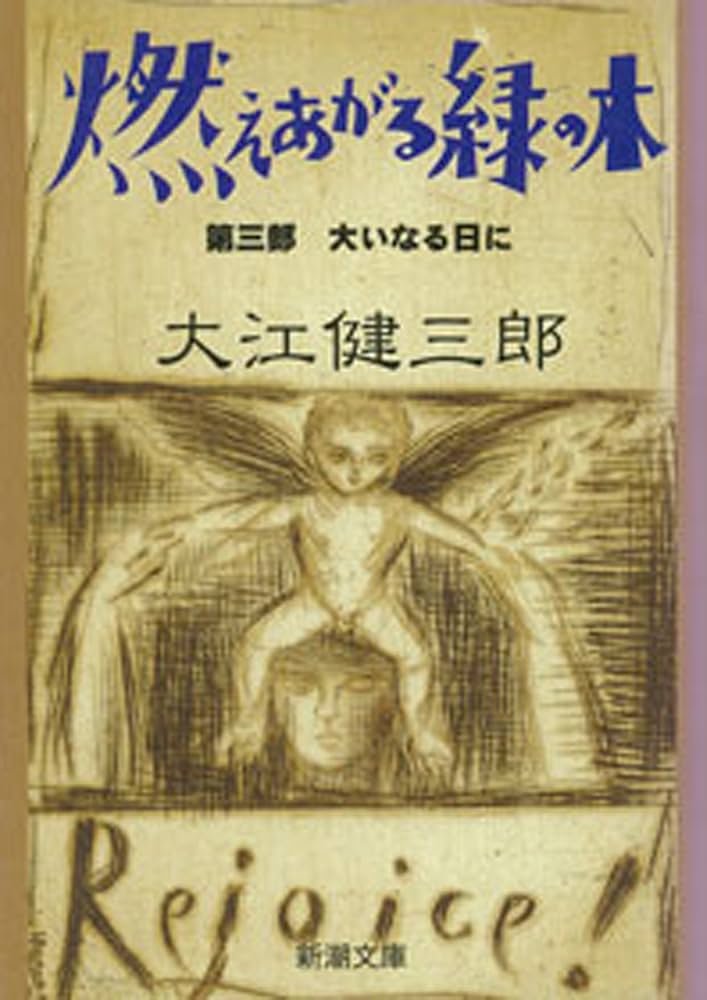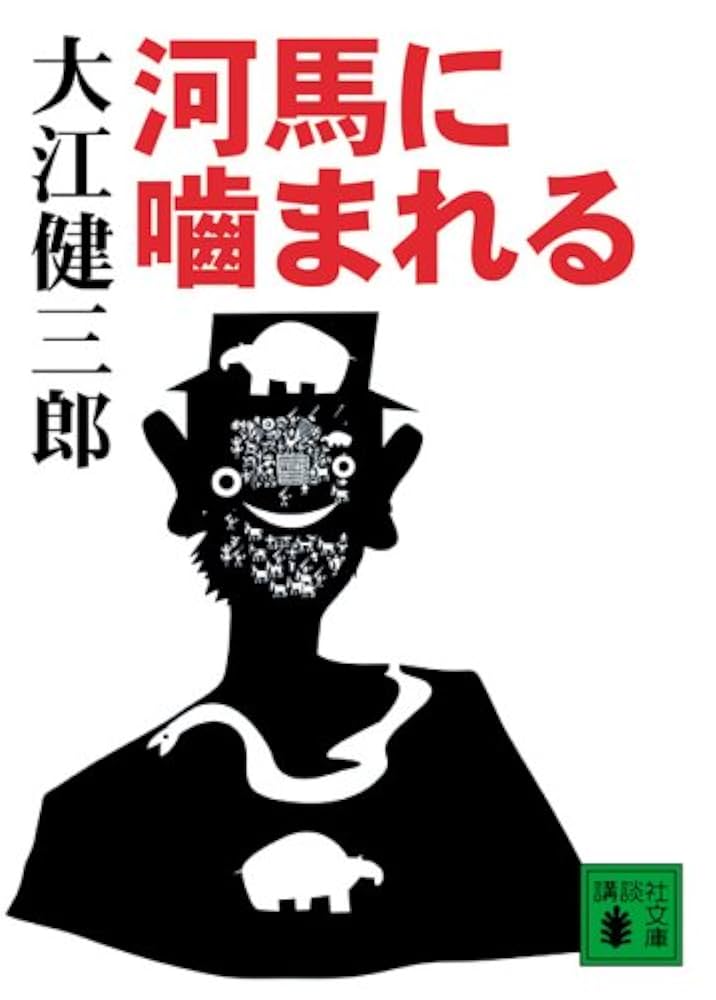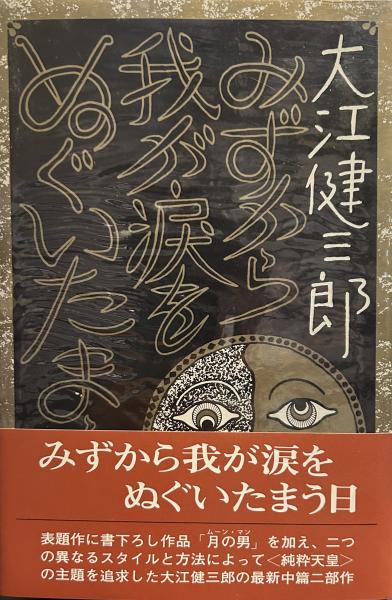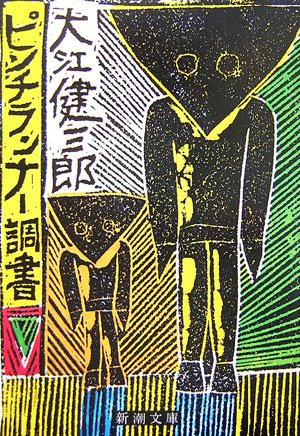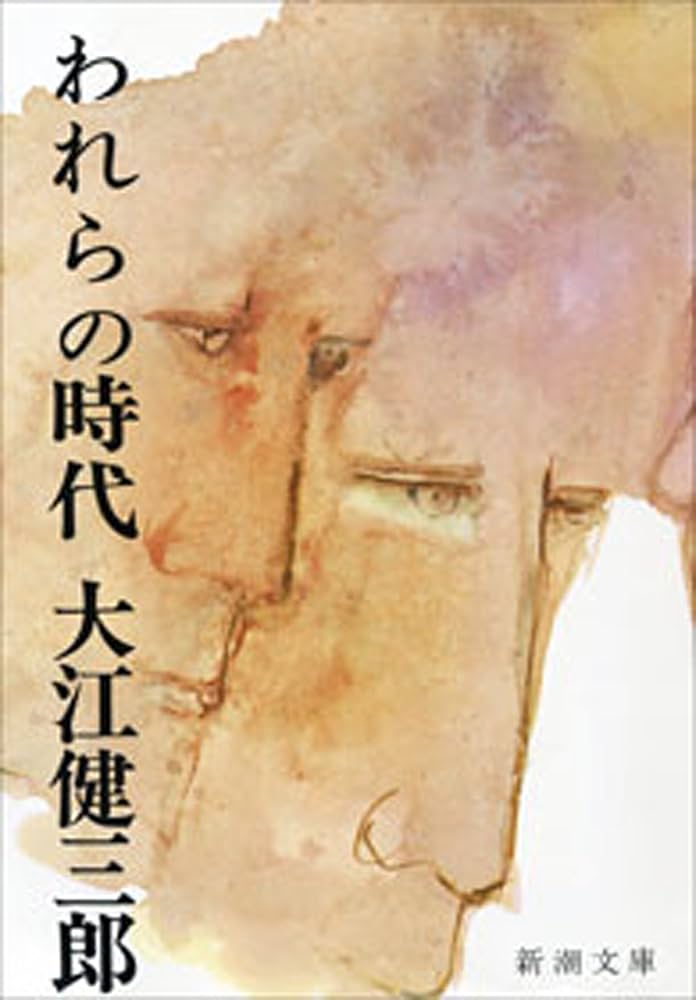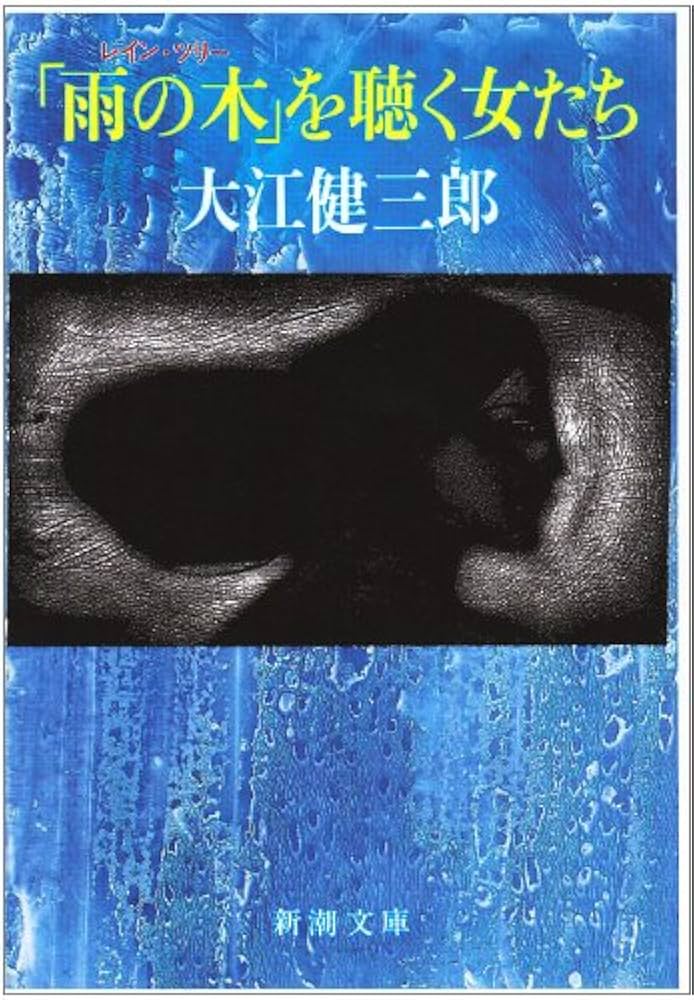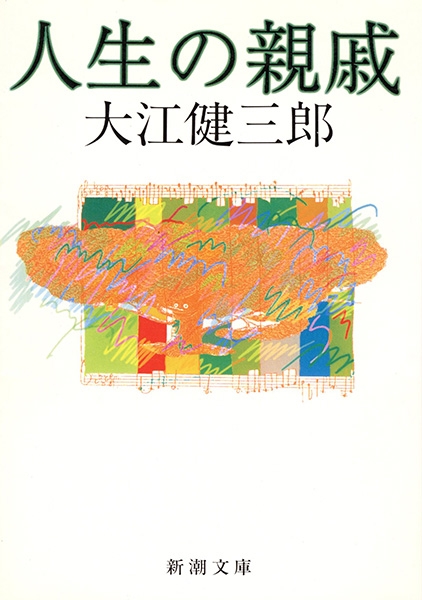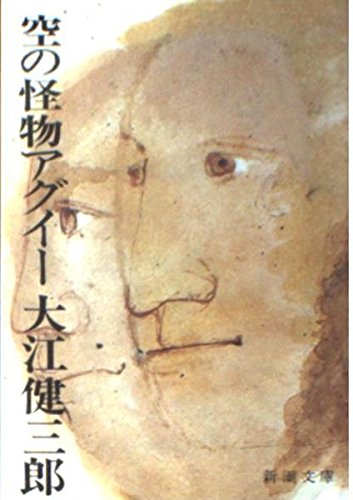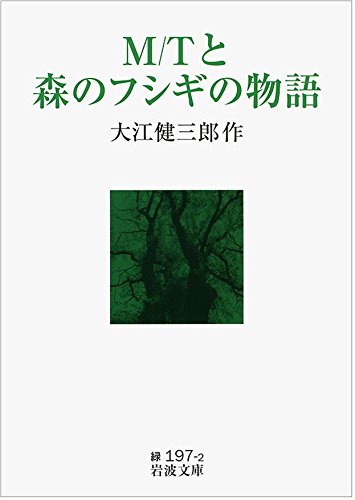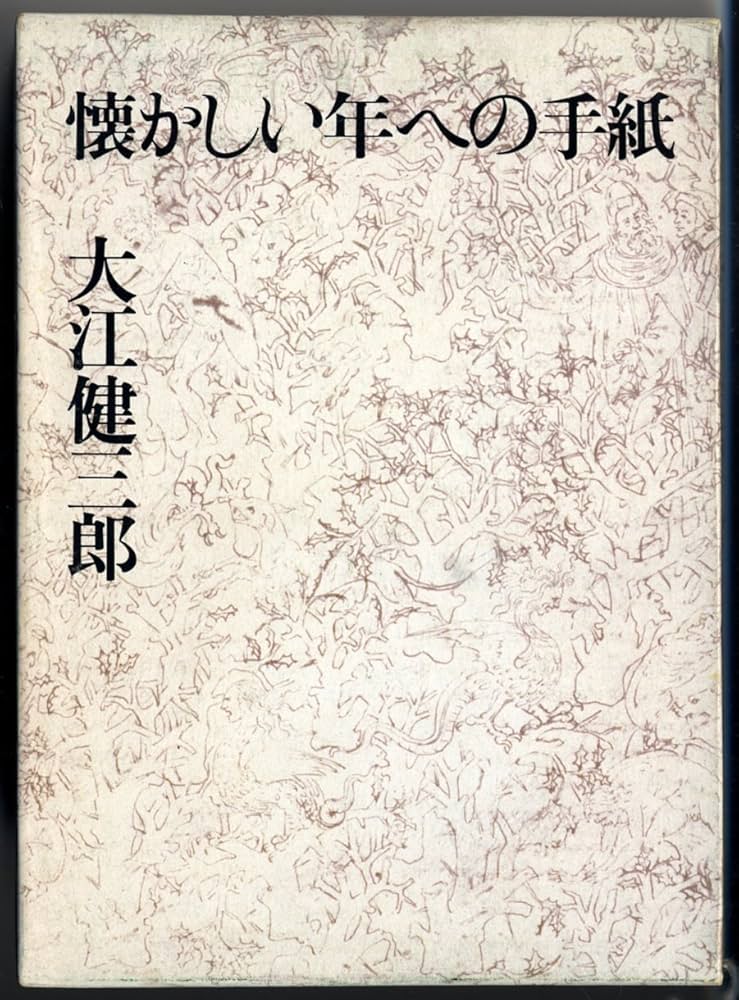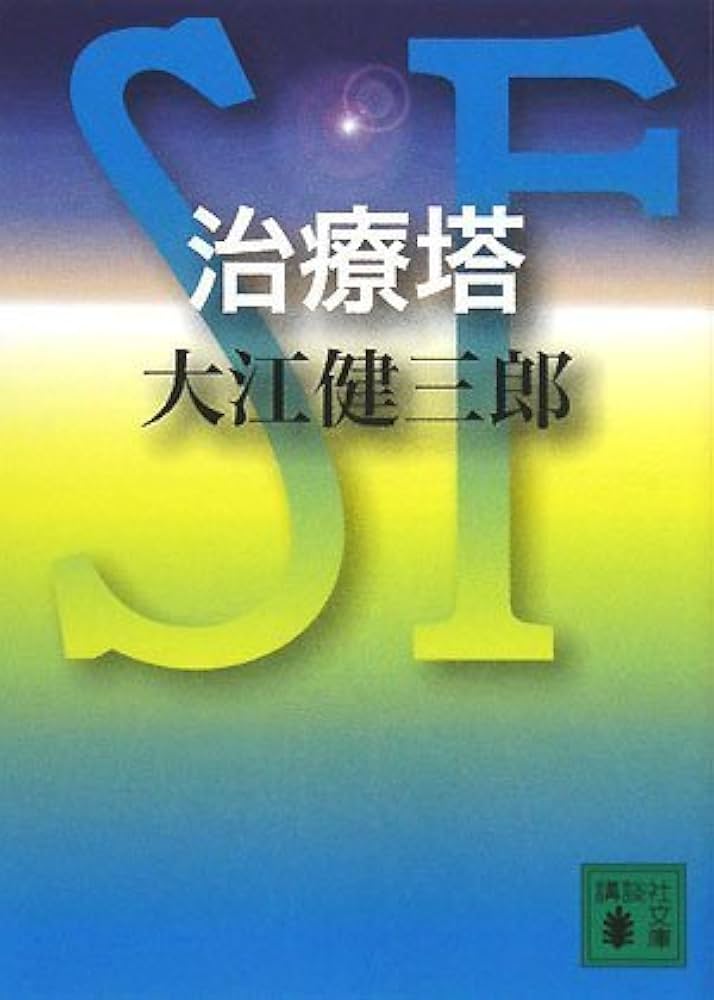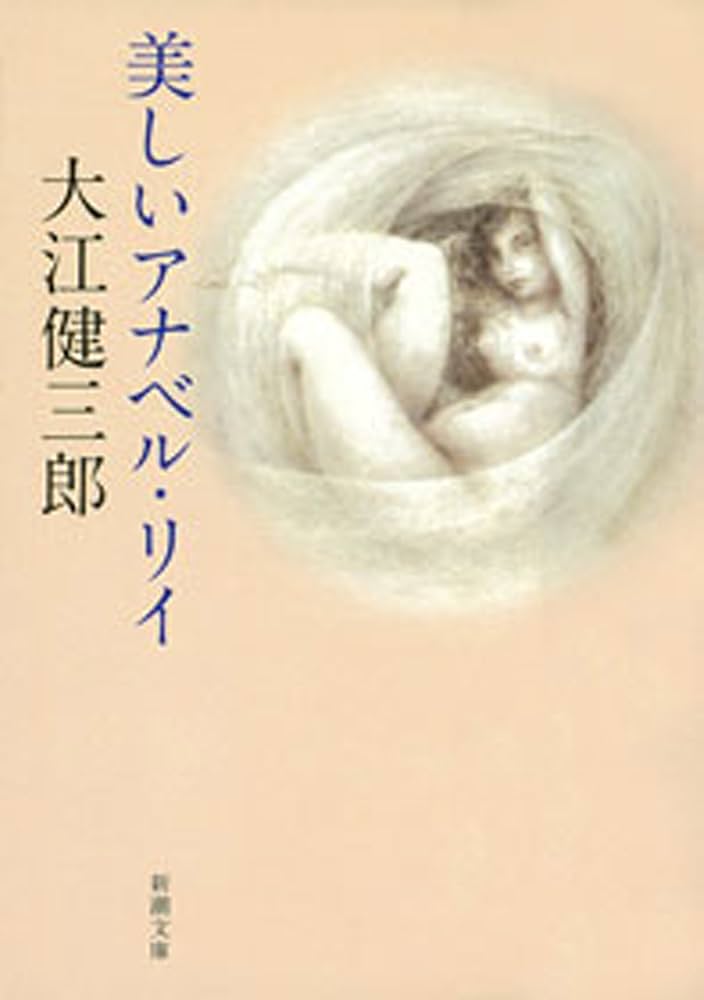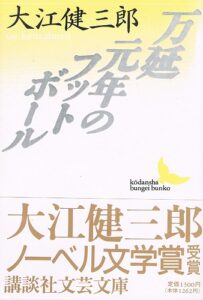 小説「万延元年のフットボール」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、1967年に発表された大江健三郎の代表作であり、ノーベル文学賞受賞の際にも主要な作品として挙げられました。発表から半世紀以上が経過した現在でも、その圧倒的な物語の力は色褪せることがありません。むしろ、現代社会が抱える問題と共鳴する部分が多く、今だからこそ読むべき作品だと言えるでしょう。
小説「万延元年のフットボール」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、1967年に発表された大江健三郎の代表作であり、ノーベル文学賞受賞の際にも主要な作品として挙げられました。発表から半世紀以上が経過した現在でも、その圧倒的な物語の力は色褪せることがありません。むしろ、現代社会が抱える問題と共鳴する部分が多く、今だからこそ読むべき作品だと言えるでしょう。
物語の舞台は、1860年の「万延元年」と、その百年後である1960年という二つの時代が交錯する四国の谷間の村です。主人公の兄弟が背負う一族の歴史と、それぞれの内なる地獄が、村を巻き込んだ壮大な悲劇へと発展していきます。この重厚なテーマ性こそが、「万延元年のフットボール」が多くの読者を惹きつけてやまない理由の一つです。
この記事では、まず物語の骨子となるあらすじを追いかけます。その後、物語の核心に触れるネタバレを含んだ深い感想を詳しく述べていきます。難解とされる「万延元年のフットボール」ですが、その複雑に絡み合った人間関係や歴史の謎を解き明かしながら読み進めることで、きっと忘れられない読書体験が得られるはずです。
これから「万延元年のフットボール」を読もうと考えている方はもちろん、かつて読んだけれど挫折してしまったという方にも、この物語の持つ力強さと感動を再発見していただけるよう、丁寧に解説していきます。
「万延元年のフットボール」のあらすじ
語り手である根所蜜三郎は、東京で英語講師として暮らす27歳の男性です。彼の日常は深い絶望に覆われていました。知的障害を持つ息子を施設に預け、そのことが原因で妻の菜採子はアルコールに溺れる日々を送っています。さらに、唯一無二の親友が、性器にきゅうりを詰めて首を吊るという奇怪な自殺を遂げたことで、蜜三郎は生きる希望を完全に見失っていました。
そんな八方塞がりの彼の前に、60年安保闘争に挫折しアメリカへ渡っていた弟の鷹四が突然帰国します。行動的な鷹四は、蜜三郎夫婦に対し、故郷である四国の谷間にある倉屋敷を売り払い、新しい生活を始めようと持ちかけます。倉屋敷は、村の経済を牛耳る「スーパー・マーケットの天皇」と呼ばれる在日朝鮮人の実業家が高値での買い取りを申し出ていたのです。
現状を打破したい一心で、蜜三郎夫婦は鷹四の提案を受け入れ、故郷の村へと向かいます。しかし、その村は兄弟の一族にまつわる暗い歴史と伝説に支配された土地でした。百年前に起きた「万延元年の一揆」で、彼らの曽祖父の弟が仲間を裏切ったという「恥」の記憶が、今なお村に色濃く影を落としていたのです。
蜜三郎は過去の歴史を静観しようとしますが、対照的に鷹四は、一揆の指導者であった曽祖父の弟に自らを重ね、その汚名を現代に蘇らせることで過去を乗り越えようと画策します。彼は村の若者たちを集めて「フットボール・チーム」を組織し、日当を払って訓練を始めます。それは単なるスポーツではなく、村の支配者「スーパー・マーケットの天皇」に対する暴動、すなわち「万延元年の一揆」の再現に向けた不穏な企てだったのです。
「万延元年のフットボール」の長文感想(ネタバレあり)
この物語は、息苦しいほどの絶望から始まります。語り手の蜜三郎が抱える閉塞感は、読んでいるこちらの胸をも締め付けます。しかし、読み終えた時に心に残るのは、その地獄の底から見出す、かすかな光と再生への強い意志です。まさに「万延元年のフットボール」は、人間の魂の深淵を覗き込み、その複雑さと力強さを描き切った、類い稀なる傑作と言えるでしょう。
物語は蜜三郎と鷹四という対照的な兄弟を軸に進みます。内向的で、過去から目を背け、ひたすら「穴」の中に閉じこもろうとする兄・蜜三郎。一方、行動的で、過去の歴史を現代に再現することで乗り越えようとする弟・鷹四。この二人の関係性は、静と動、あるいは絶望と希望の対立として描かれているように見えます。
しかし、物語を読み進めるにつれて、その単純な二項対立では捉えきれない、人間の心の複雑さが明らかになっていきます。特に鷹四の行動原理は、物語の核心に触れる重要なネタバレ要素を含んでいます。彼の起こす暴動は、単なる村への反乱や歴史の再現ごっこではありませんでした。それは、彼自身が背負った、誰にも打ち明けられない罪に対する、壮大な自己破壊と処罰への渇望だったのです。
この物語の重要なテーマの一つに「歴史」があります。兄弟の故郷の村は、「万延元年の一揆」という百年前の出来事にいまだ縛られています。一揆を率いた曽祖父の弟は、仲間を裏切って逃げたとされ、一族の汚点として語り継がれてきました。蜜三郎はこの歴史を客観的な事実として受け止めようとしますが、鷹四は伝説の中にこそ真実があると信じ、自らがその歴史を生き直そうとします。
鷹四が組織した「フットボール」は、村の若者たちを熱狂させ、「スーパー・マーケットの天皇」の店を襲撃し、略奪するという暴動にまで発展します。一時的に村の英雄となった鷹四ですが、その支配は長くは続きません。暴動の最中に起きた少女の強姦殺害事件をきっかけに、彼は一転して村人たちから糾弾され、追いつめられていきます。この展開は、熱狂の危うさと、集団心理の恐ろしさを見事に描き出しています。
そして物語は、衝撃的なクライマックスを迎えます。血まみれで帰ってきた鷹四は、蜜三郎に驚くべき真実を告白します。ここからが、この物語の最も重いネタバレになります。鷹四はかつて、知的障害のあった妹と近親相姦の関係にあり、彼女を妊娠させ、絶望のあまり自殺に追い込んでしまったという過去を背負っていたのです。
彼のこれまでの行動はすべて、この拭い去れない罪悪感から来ていました。彼は自らを「処罰されるべき人間」と規定し、この暴動を、自分が断罪されるための舞台装置として計画したのです。さらに、蜜三郎の妻・菜採子が身ごもっている子供が、実は鷹四の子であることも示唆されます。この二重三重の裏切りと罪の告白は、読者に強烈な衝撃を与えずにはおきません。
しかし、蜜三郎は弟の悲痛な告白を「本当のこと」として受け入れることができません。彼は、鷹四もまた、裏切り者とされた曽祖父の弟のように、卑劣な嘘をついて生き延びようとしているのだと突き放します。兄からの完全な拒絶に絶望した鷹四は、猟銃で自らの頭を撃ち抜き、壮絶な最期を遂げます。彼が遺した「オレハ本当ノ事ヲ言ツタ」という血のメモが、あまりにも悲痛です。
鷹四の死後、物語は再生へと向かいます。取り壊される倉屋敷の床下から秘密の地下蔵が見つかり、そこには「万延元年の一揆」の真実を記した古文書が残されていました。曽祖父の弟は仲間を裏切ったのではなく、一揆の失敗後も地下に潜伏し、明治時代に再び起こった暴動を指導して死んでいたのです。彼は裏切り者ではなく、真の英雄でした。
この歴史の真実の発見は、鷹四を最後まで信じきれなかった蜜三郎に大きな衝撃を与えます。「自分の内部の地獄に耐えている人間」への想像力が欠如していたことを深く恥じた彼は、弟の覚悟をようやく理解するのです。「万延元年のフットボール」が描き出すのは、個人の罪と、それが歴史や血縁とどう関わっていくかという壮大な問いかけです。
蜜三郎は、妻が身ごもった鷹四の子を、そして施設に預けていた自身の障害を持つ息子と共に育てていくことを決意します。それは、弟の「本当のこと」を受け入れ、彼の地獄を引き継いで生きていくという、あまりにも重い決断です。彼は過去を直視し、それを受け入れることで、ようやく自らの「穴」から這い出し、新しい一歩を踏み出すのです。
アフリカへ旅立つことを決めた蜜三郎の姿は、絶望の淵からの再生を見事に象徴しています。彼は、弟の死と歴史の真実を経て、ようやく自分自身の物語を生き始めることができたのです。この感動的な結末は、「万延元年のフットボール」が単なる暗い物語ではなく、人間の再生と希望を描いた物語であることを示しています。
物語全体を覆うのは、濃密な文体と、悪夢のような出来事の連続です。しかし、その息苦しさの中から立ち上がってくるのは、人間の業の深さと、それでもなお生きようとする生命の力強さです。性の問題や暴力も生々しく描かれますが、それらは決して表面的なものではなく、登場人物たちの内なる闇を抉り出すために不可欠な要素となっています。
「万延元年のフットボール」は、読者に安易な答えを与えてはくれません。むしろ、数多くの問いを投げかけてきます。家族とは何か、罪とは何か、歴史と個人はどう向き合うべきか。これらの問いと向き合うことこそが、この作品を読むということなのかもしれません。
鷹四の行動は、1960年の安保闘争における挫折と無関係ではないでしょう。政治の季節に傷ついた若者の絶望が、個人的な罪と結びつき、破滅的な行動へと向かわせたとも解釈できます。そうした時代背景を考えることも、この物語を深く理解する上で重要です。
この物語には、明確な悪役はいません。「スーパー・マーケットの天皇」でさえ、村に経済的な豊かさをもたらした側面があります。それぞれの登場人物が、それぞれの正義と絶望を抱えながら、必死に生きているのです。その複雑な人間模様が、「万延元年のフットボール」に圧倒的なリアリティと深みを与えています。
読後、心に残るのは、鷹四が求めた「本当のこと」とは何だったのか、そして蜜三郎が選んだ再生の道は正しかったのかという、重い問いです。この問いを持ち続けることこそが、大江健三郎がこの傑作に込めたメッセージなのかもしれません。一度読んだだけでは消化しきれない、何度でも読み返したくなる、まさに文学の力を感じさせる一作です。
まとめ:「万延元年のフットボール」のあらすじ・ネタバレ・長文感想
この記事では、大江健三郎の不朽の名作「万延元年のフットボール」について、あらすじの紹介から、物語の核心に触れるネタバレを含んだ長文の感想までを綴ってきました。絶望の淵にいた主人公・蜜三郎が、弟・鷹四との再会をきっかけに、一族の歴史と自らの過去に向き合っていく様を描いたこの物語は、読む者の魂を激しく揺さぶります。
物語の序盤は、登場人物たちが抱える苦悩や閉塞感が重くのしかかります。しかし、弟・鷹四が故郷の村で引き起こす「万延元年の一揆」の再現は、物語を予測不能な悲劇へと導くと同時に、stagnantな状況を根底から覆す力を持っています。
鷹四の衝撃的な自殺と、その後に明らかになる歴史の真実は、主人公・蜜三郎に再生への道を示します。弟の罪と希望を背負い、障害を持つ息子と共に新しい人生を歩み出すことを決意するラストシーンは、深い感動を呼び起こします。
「万延元年のフットボール」は、人間の罪と罰、歴史との対峙、そして絶望からの再生という普遍的なテーマを、圧倒的な筆力で描き切った傑作です。この記事が、これから作品を手に取る方、あるいは再読する方にとって、その深い世界を旅するためのささやかな案内となれば幸いです。