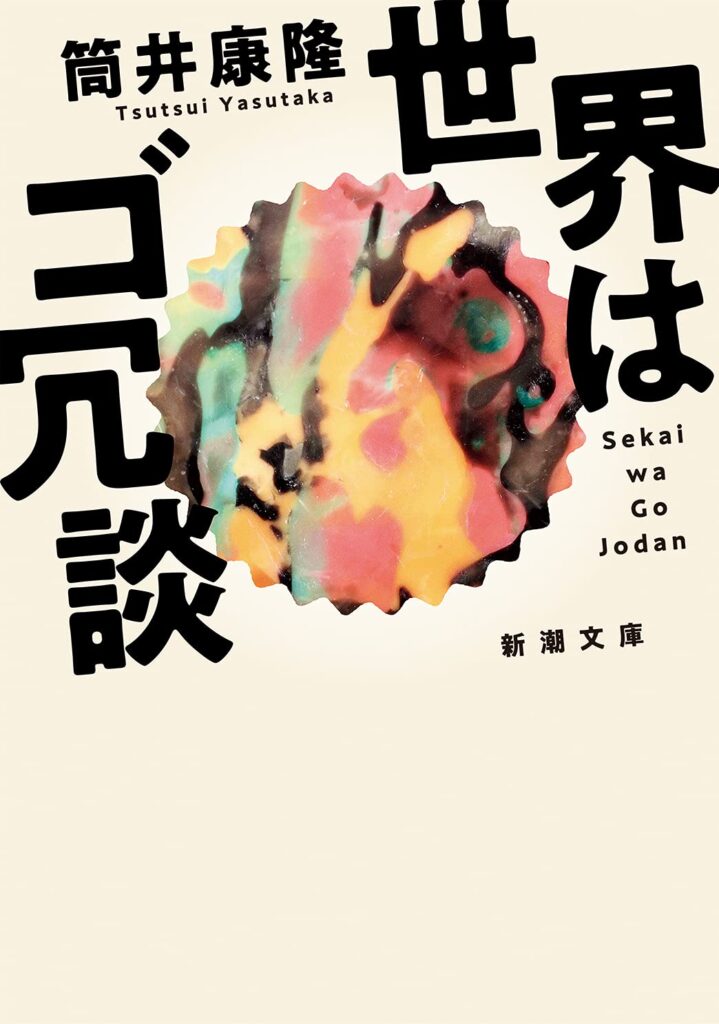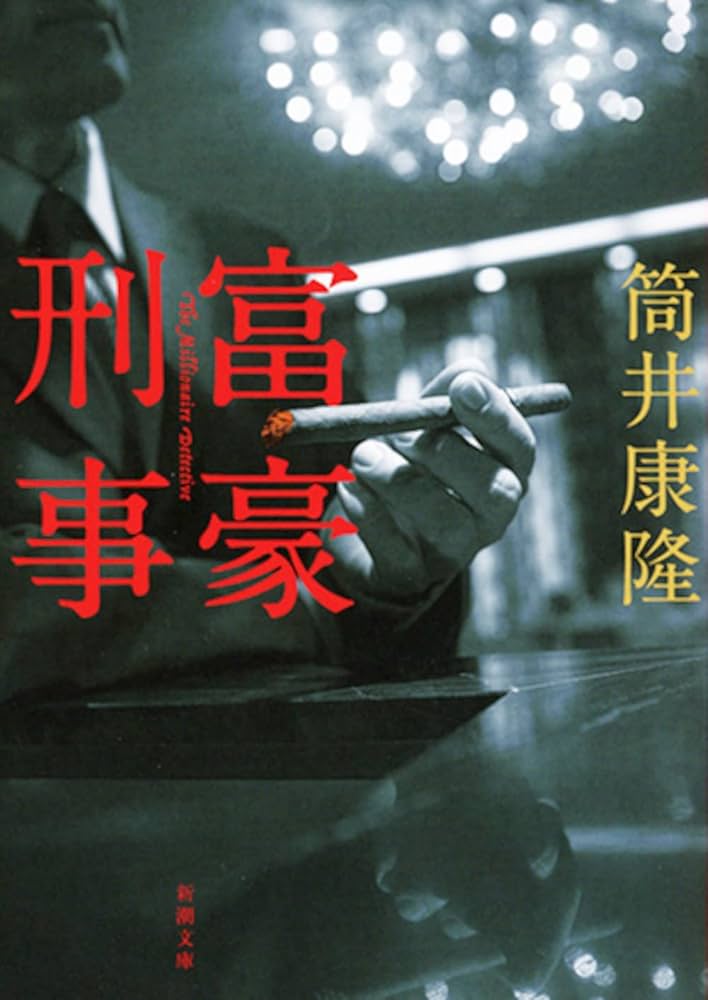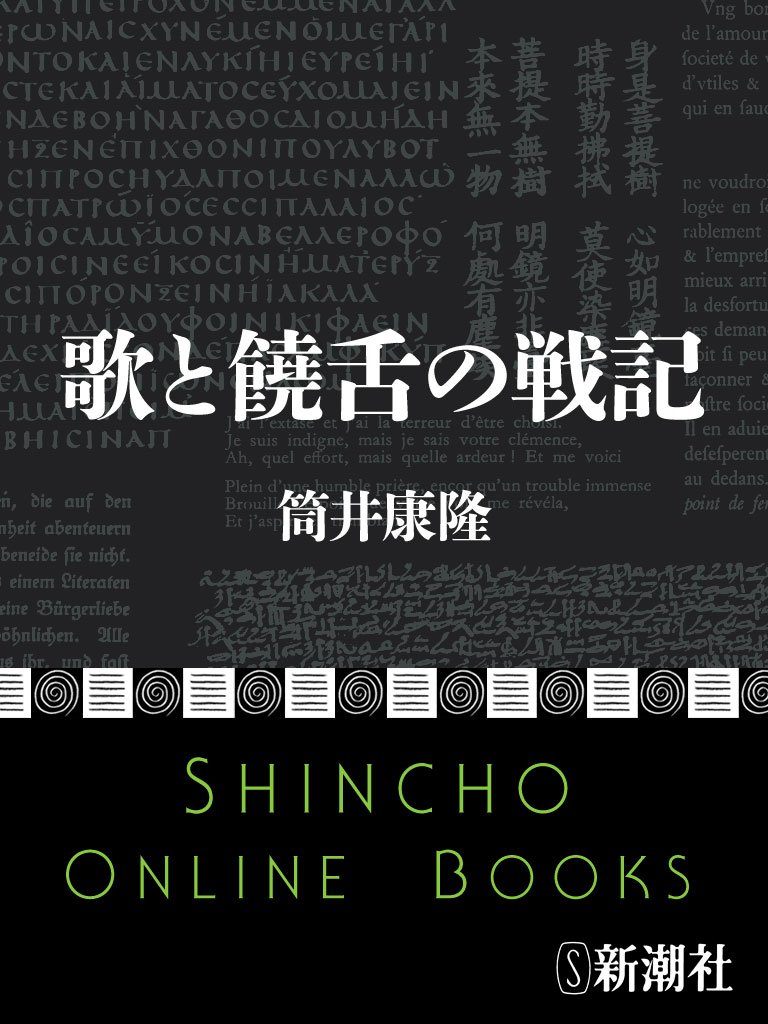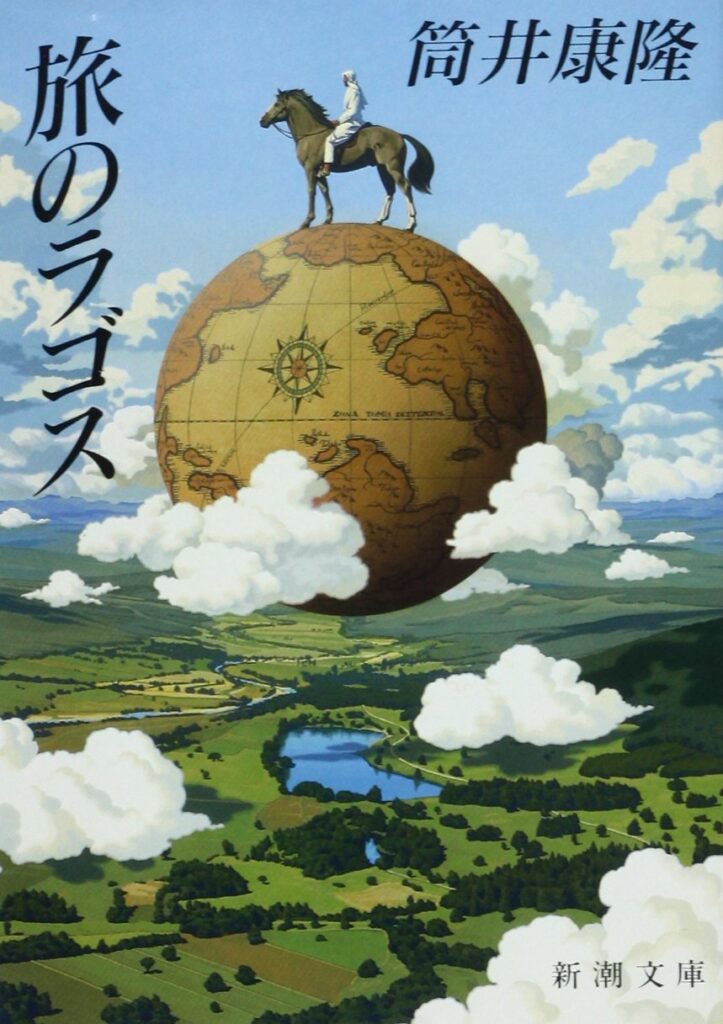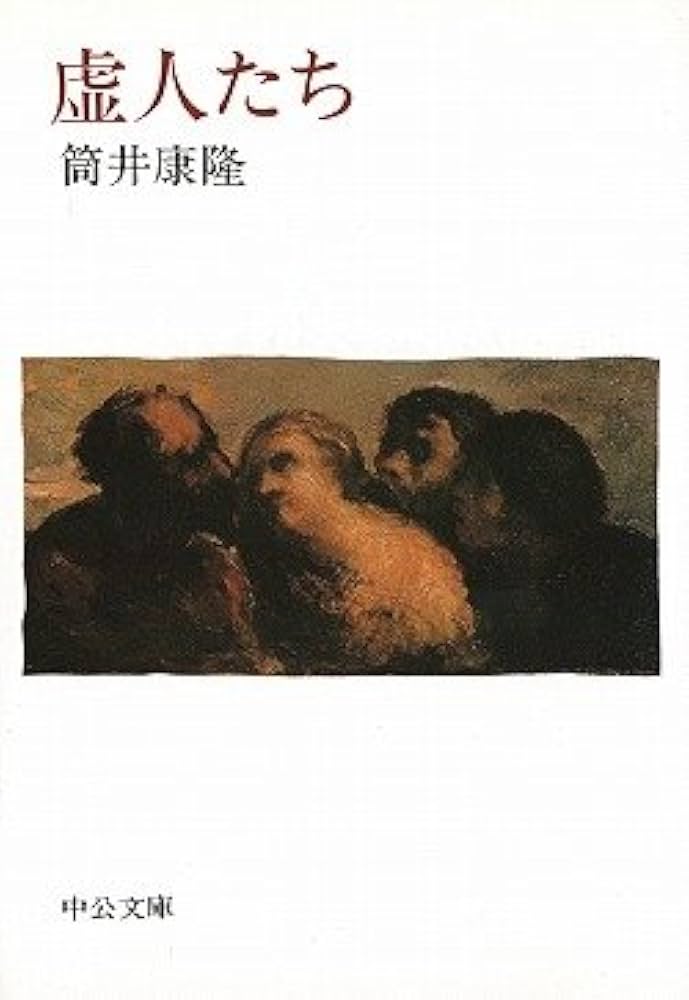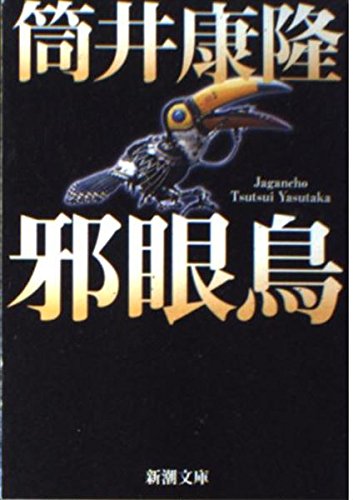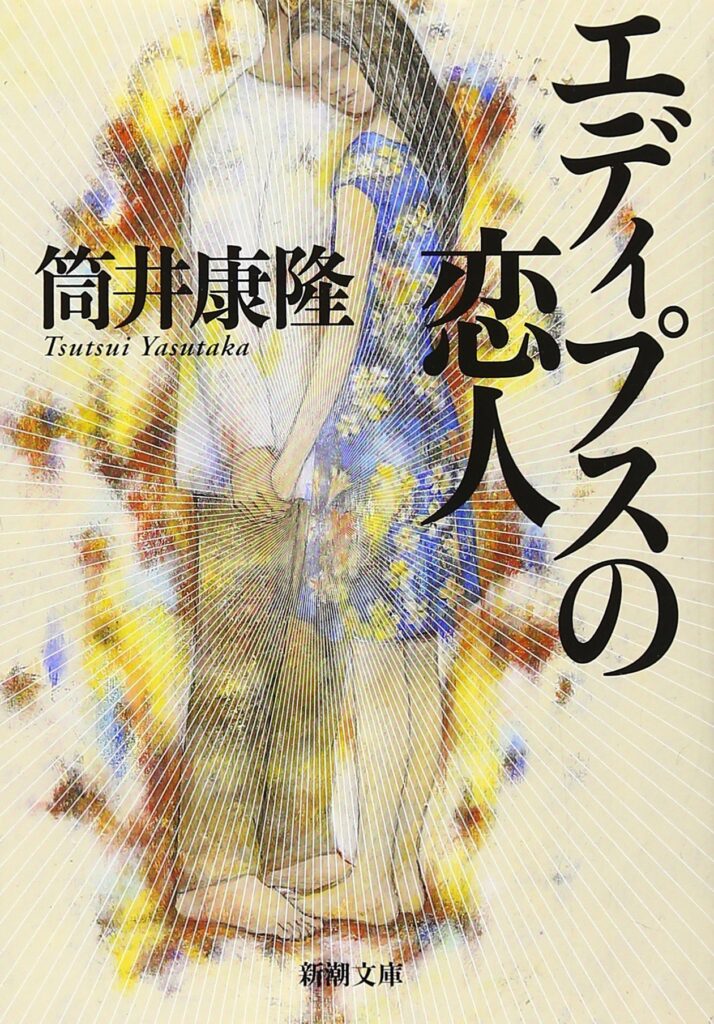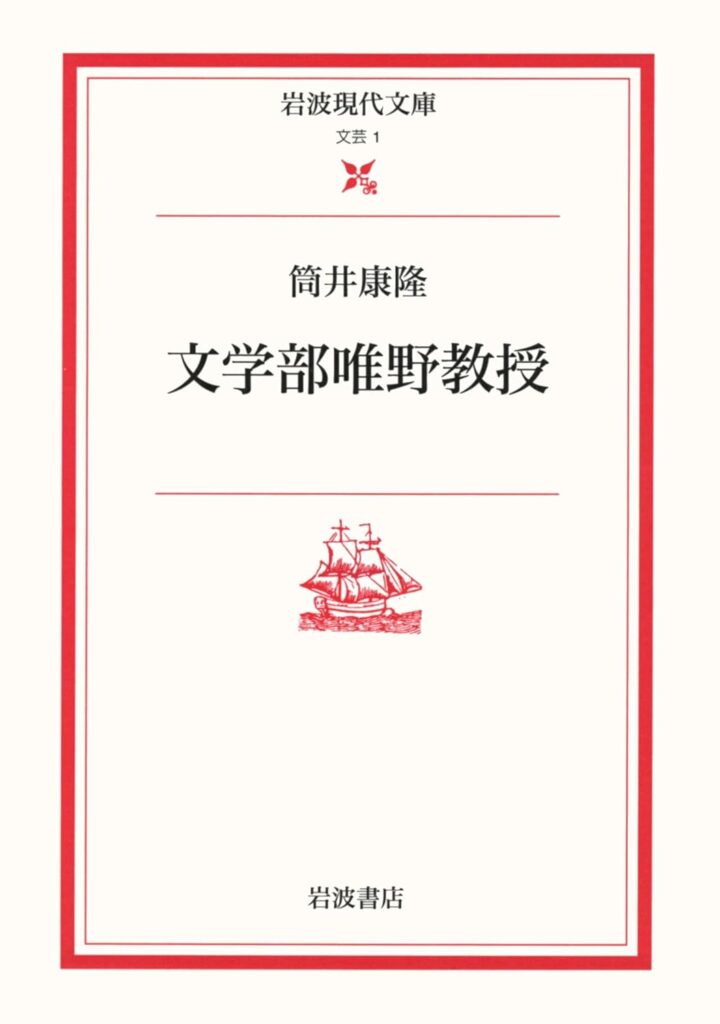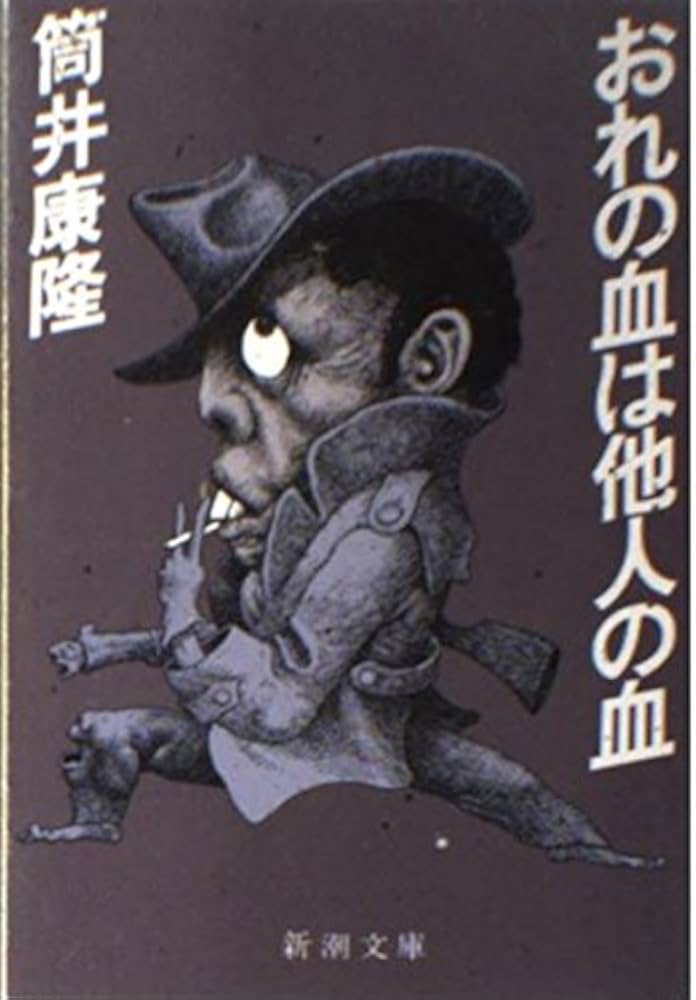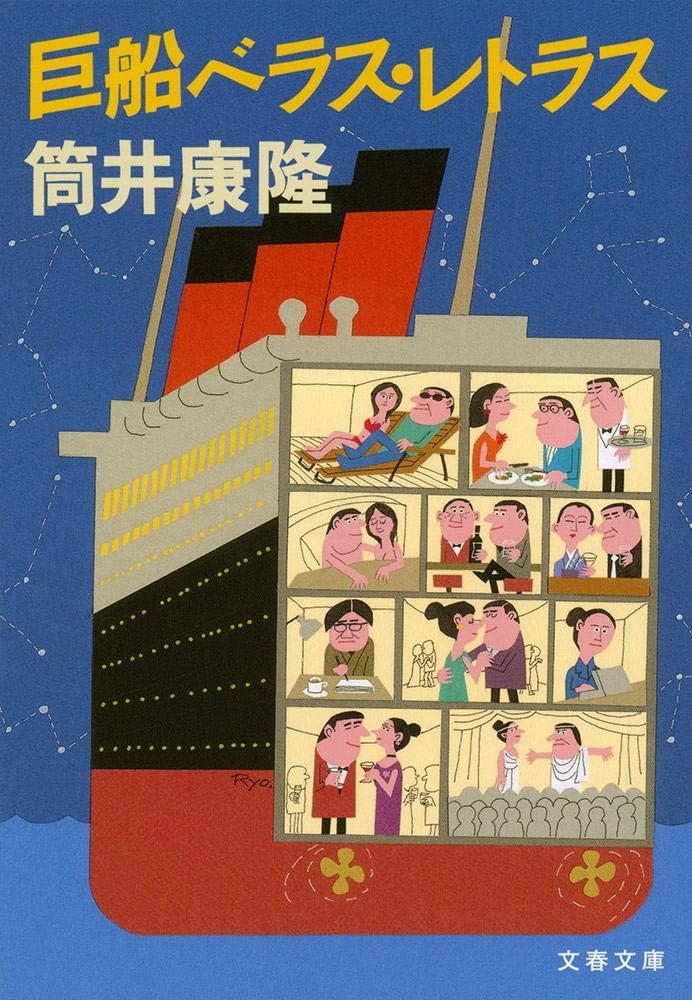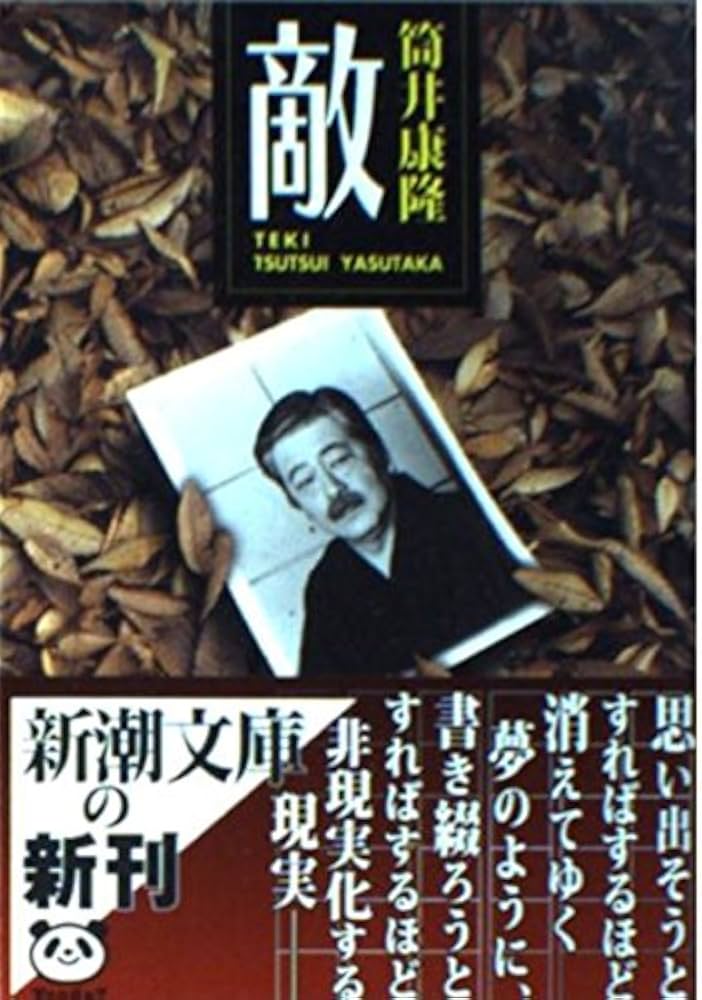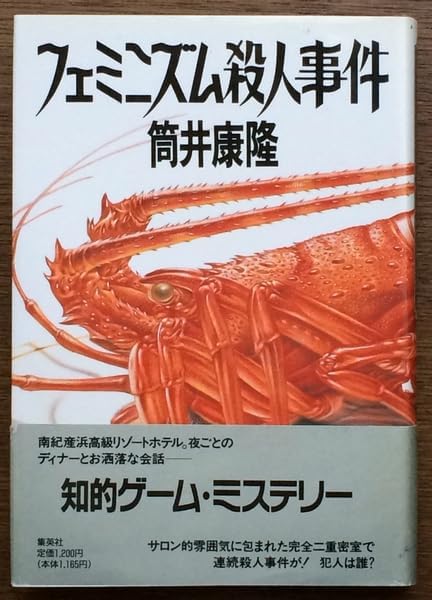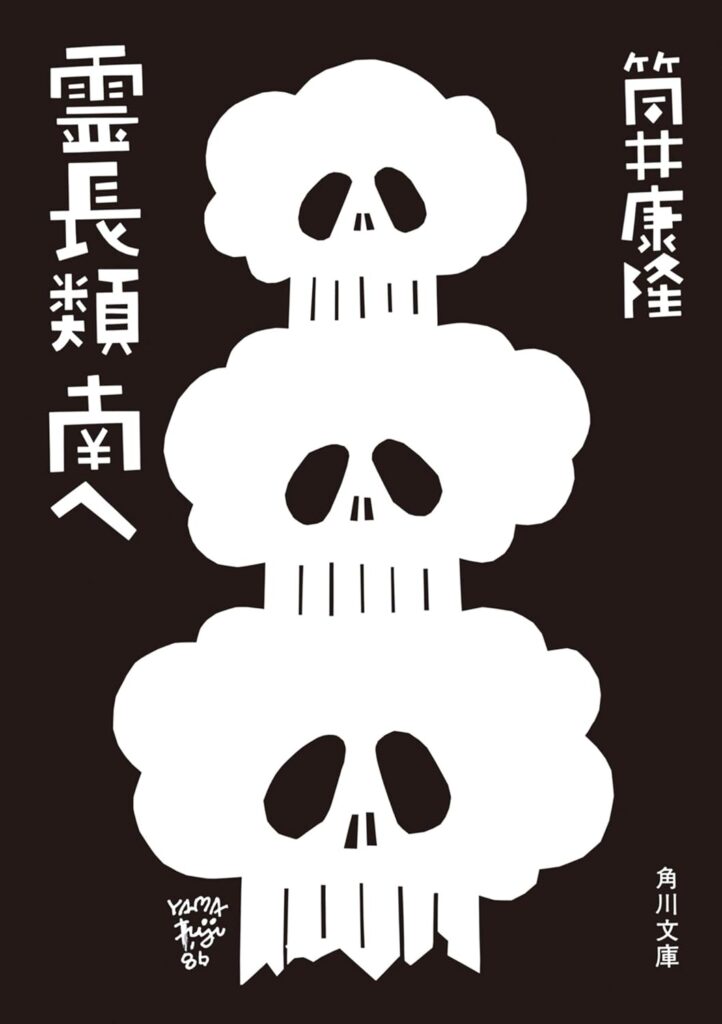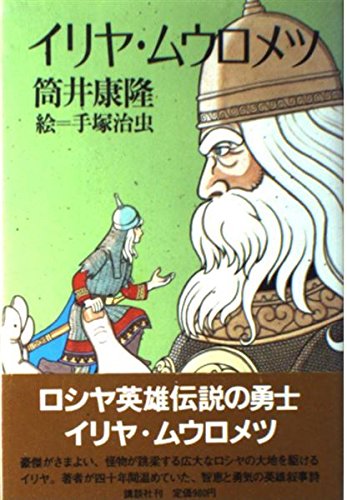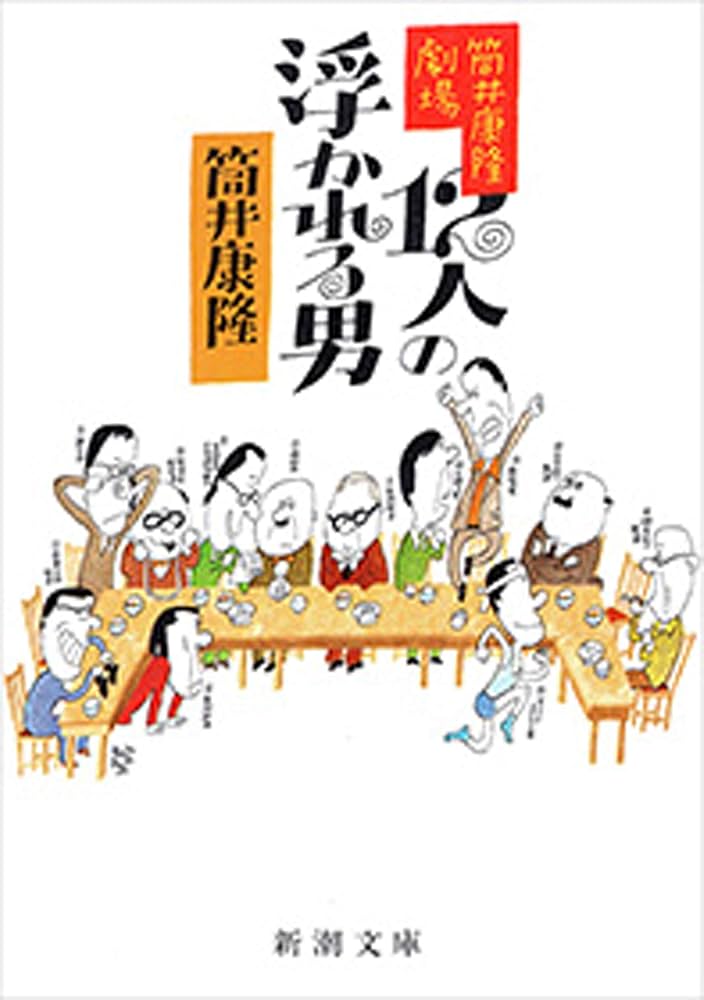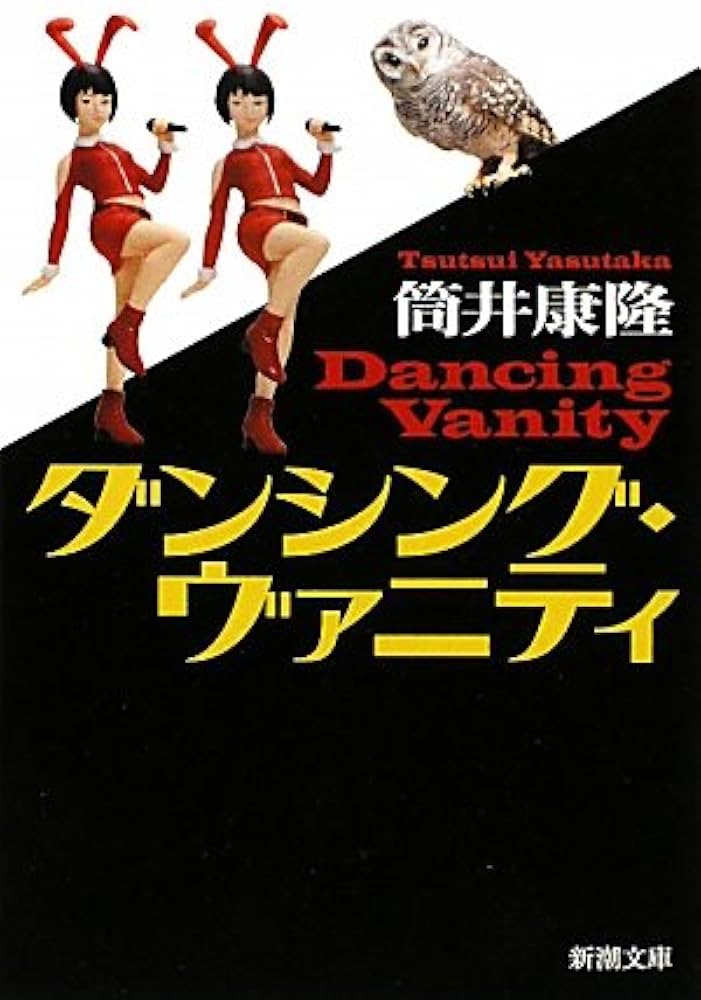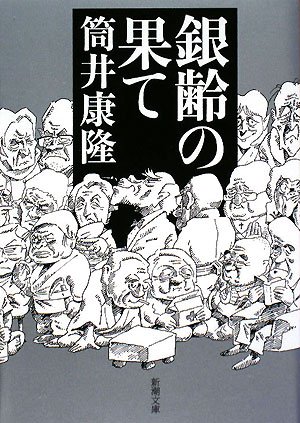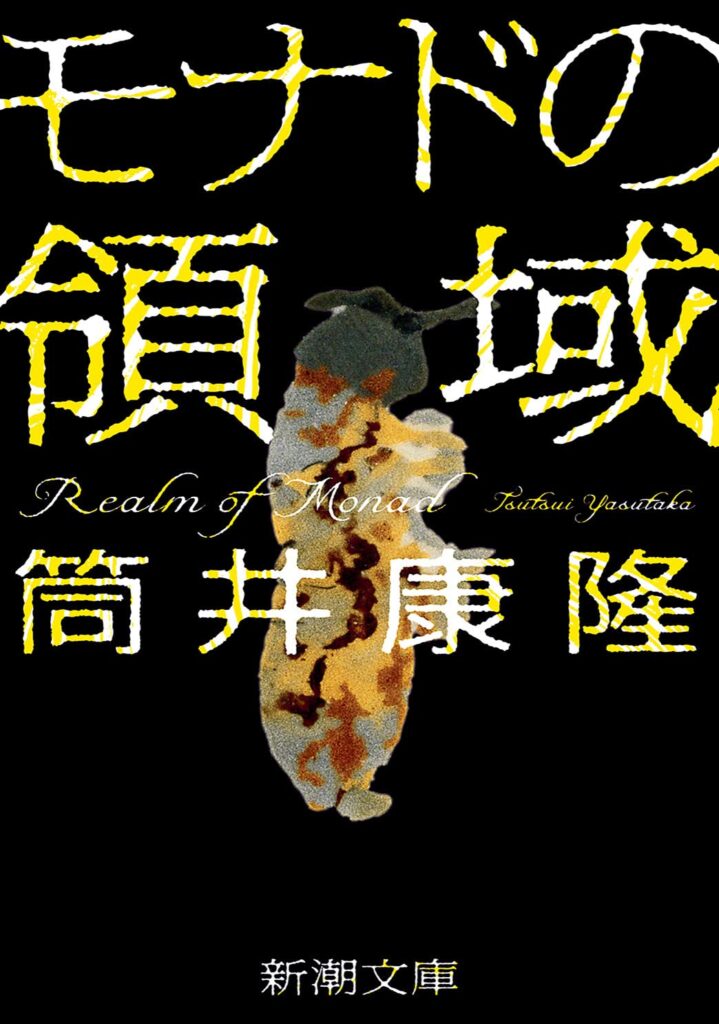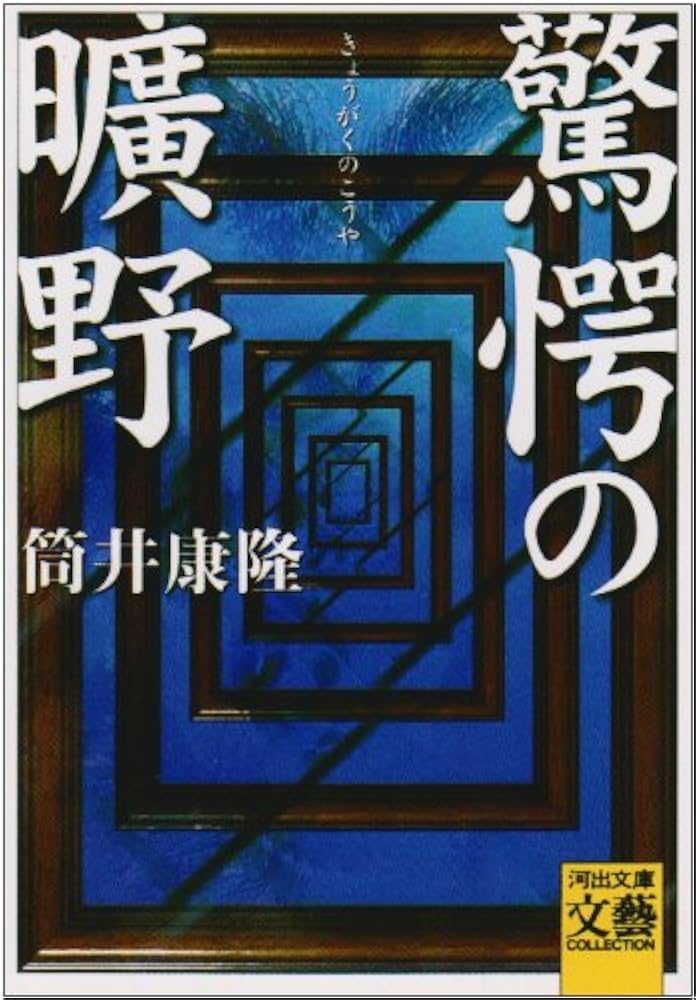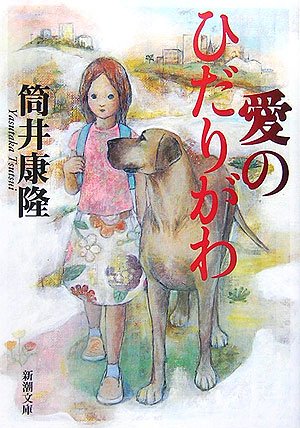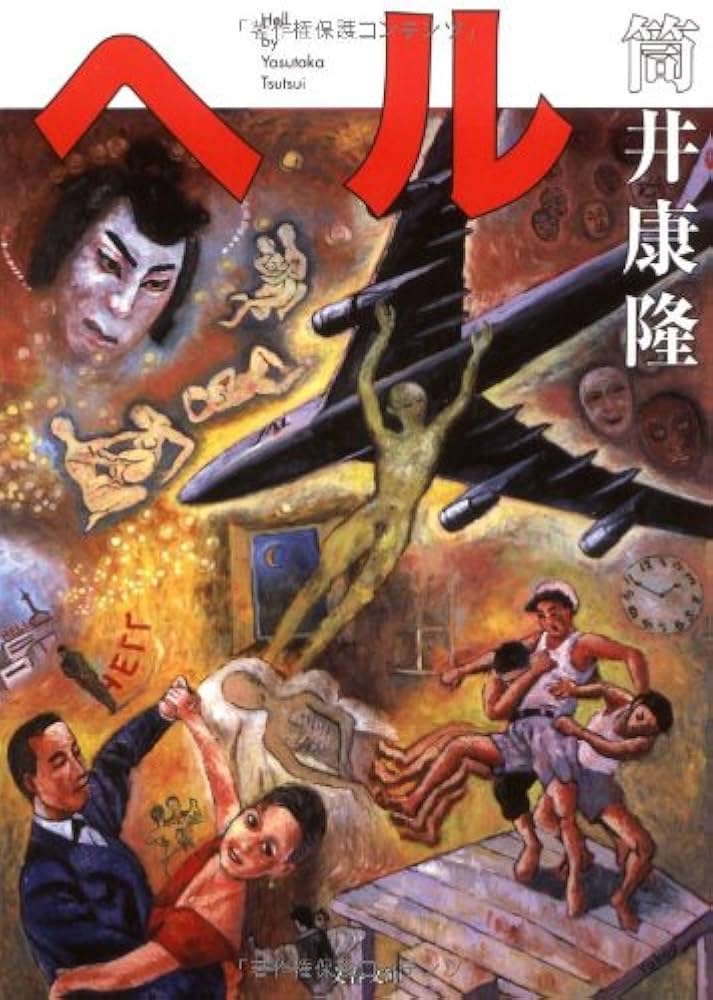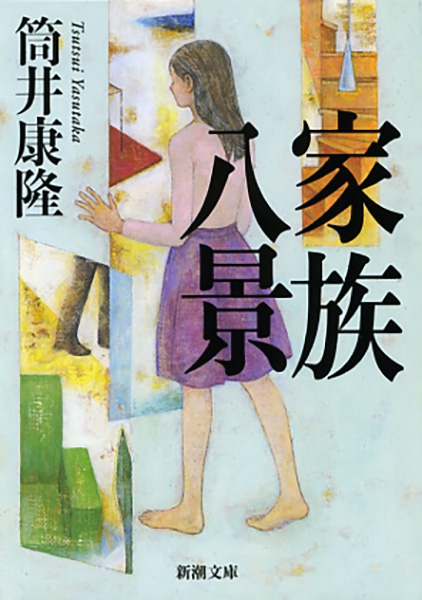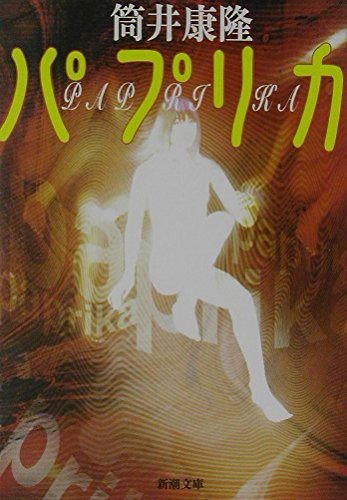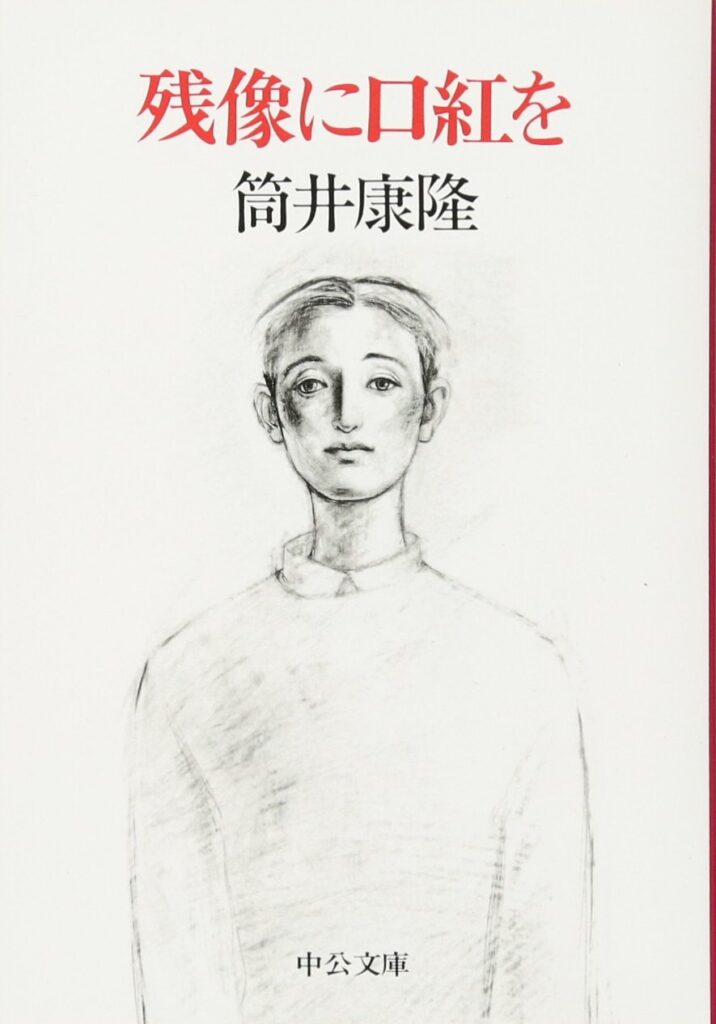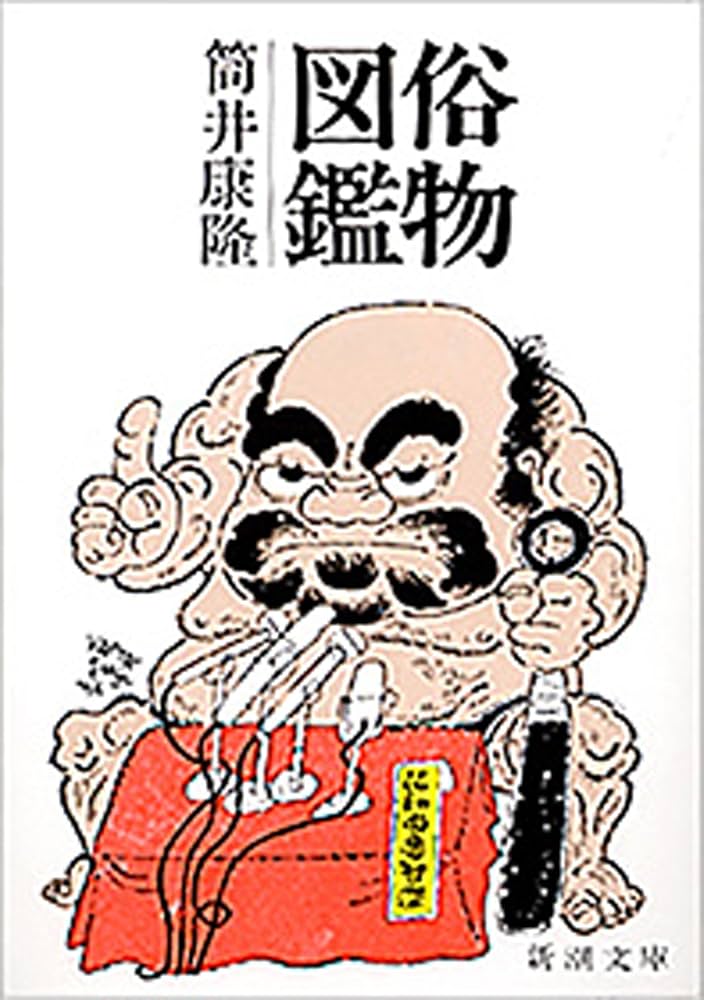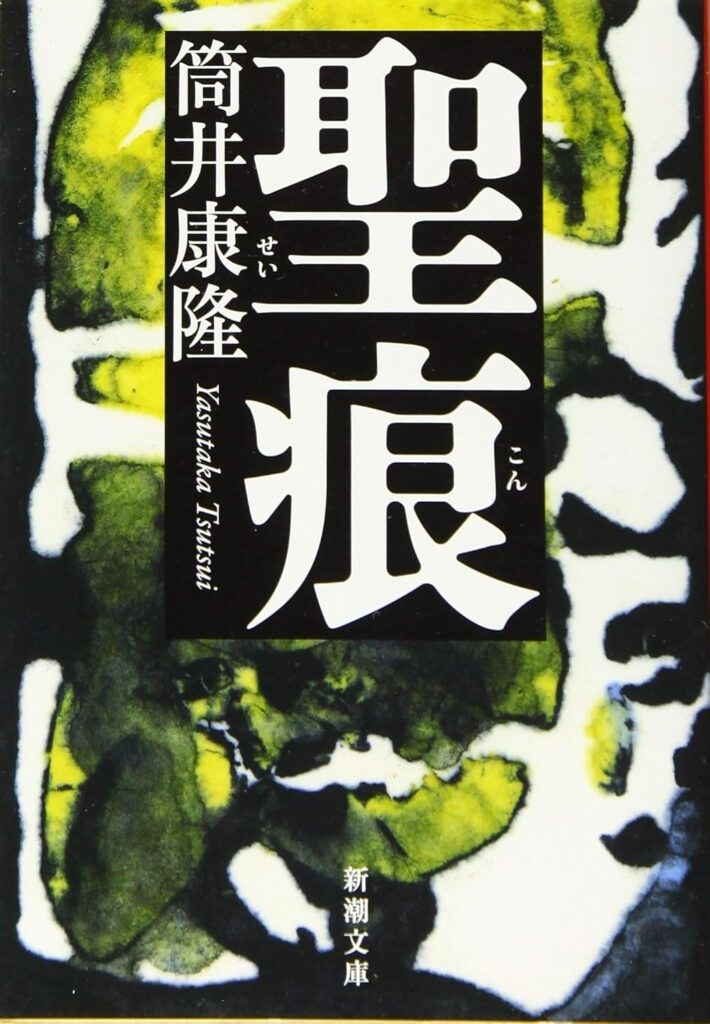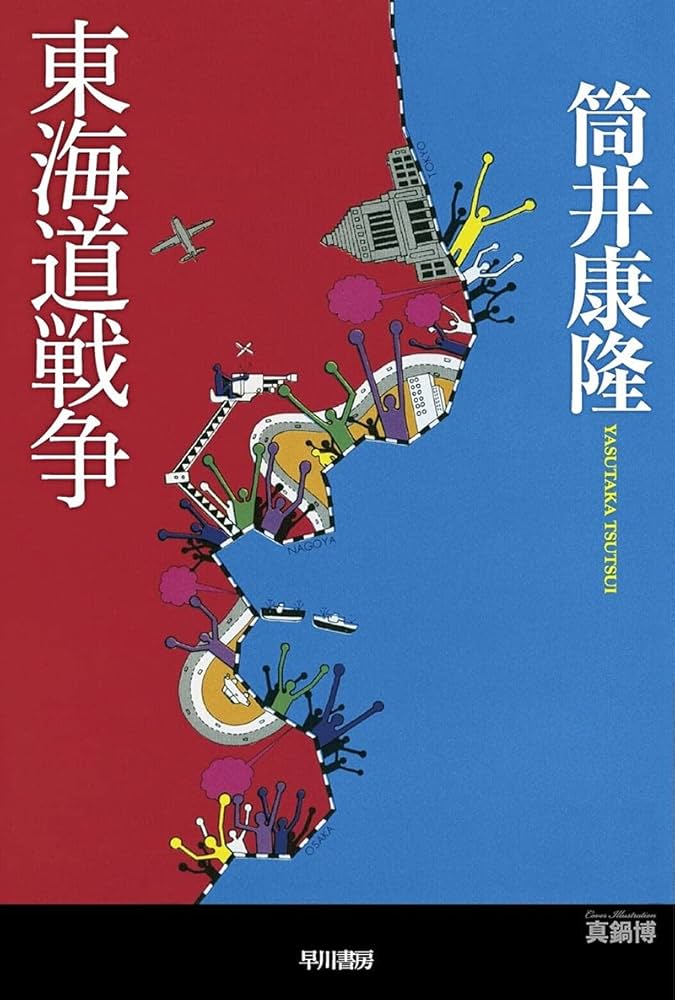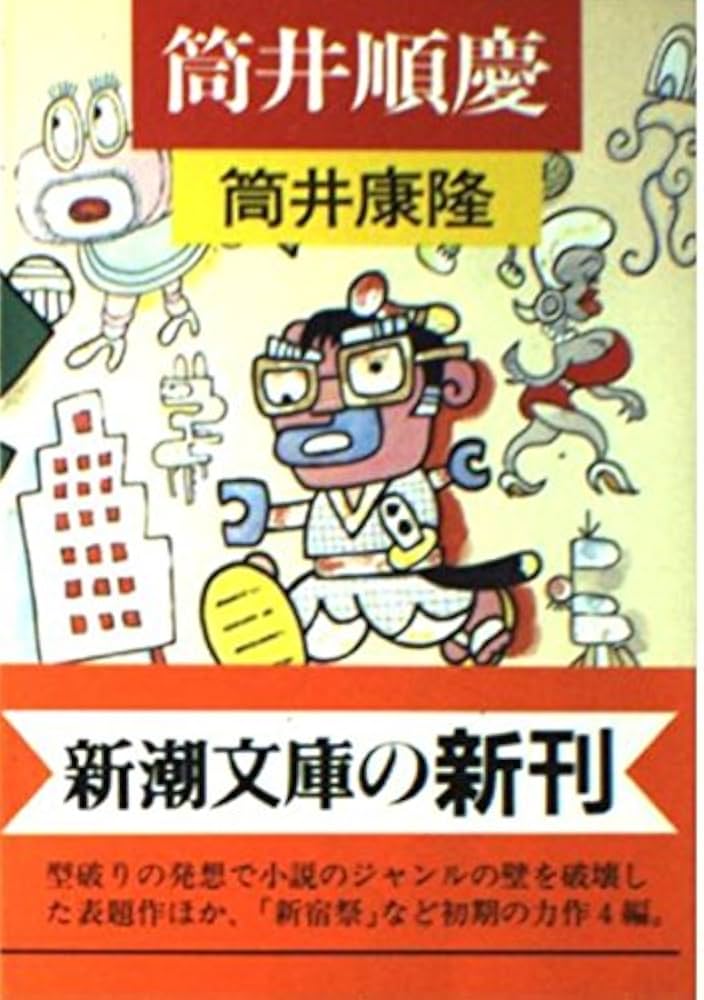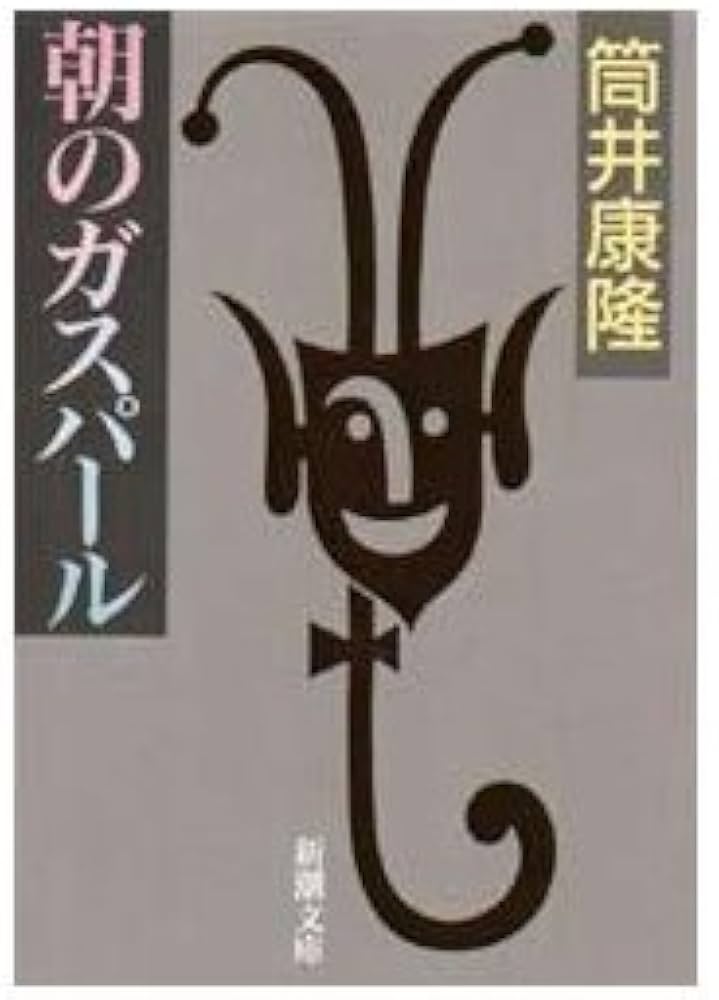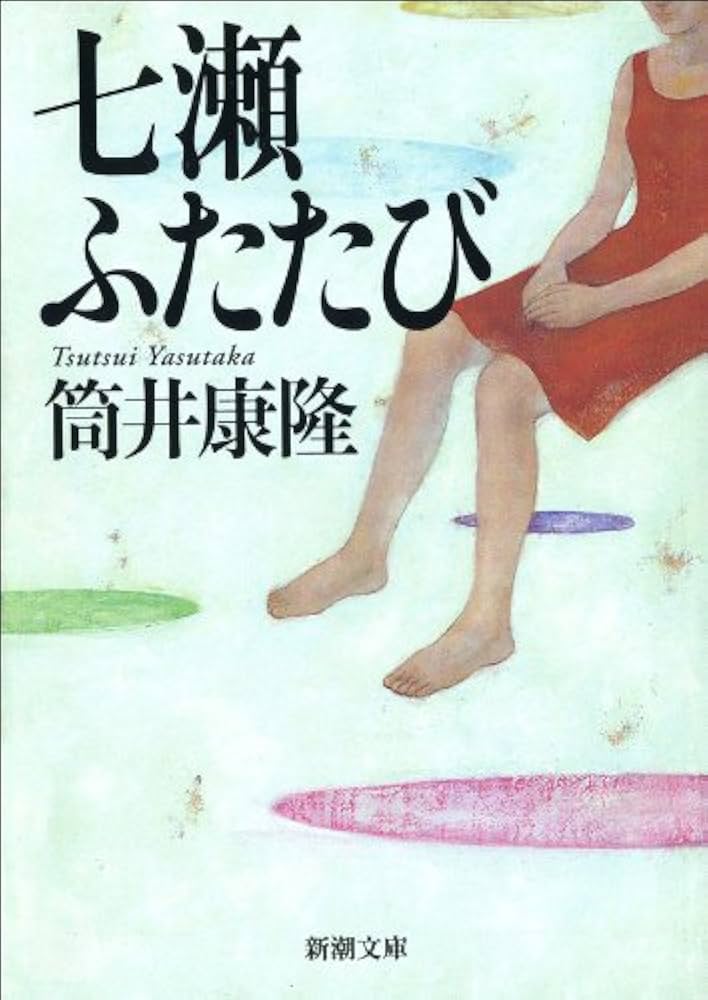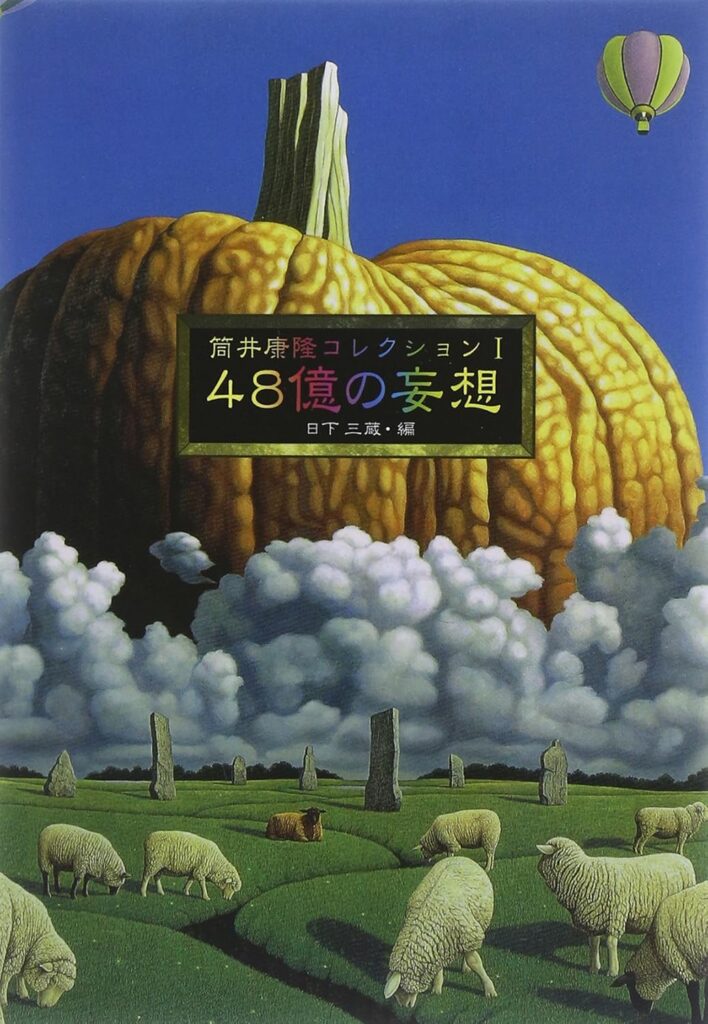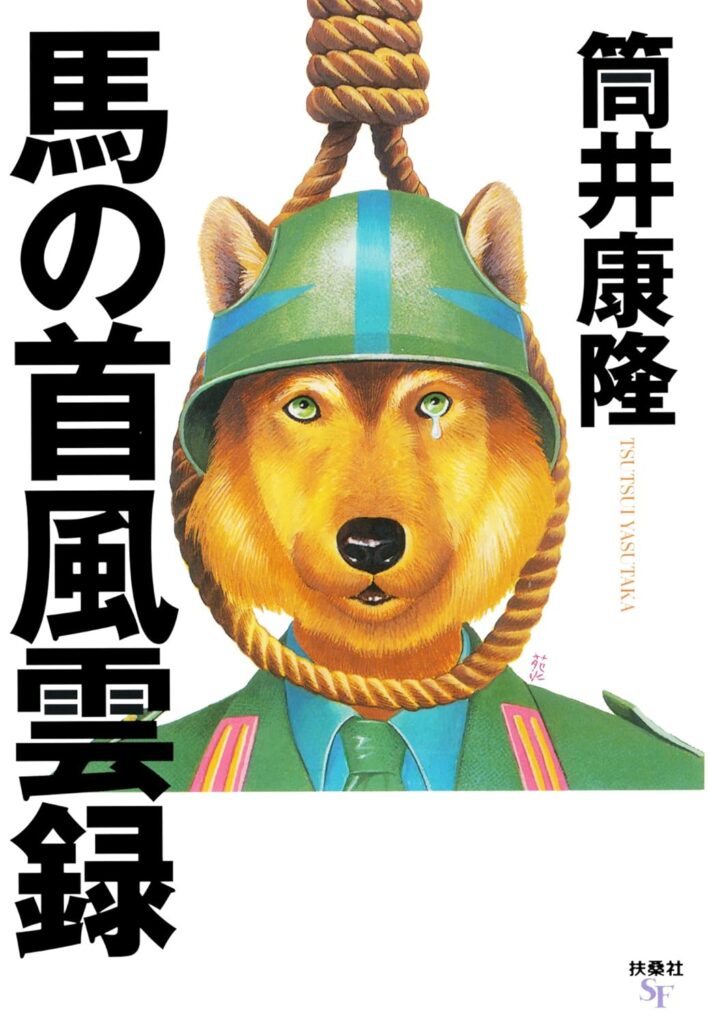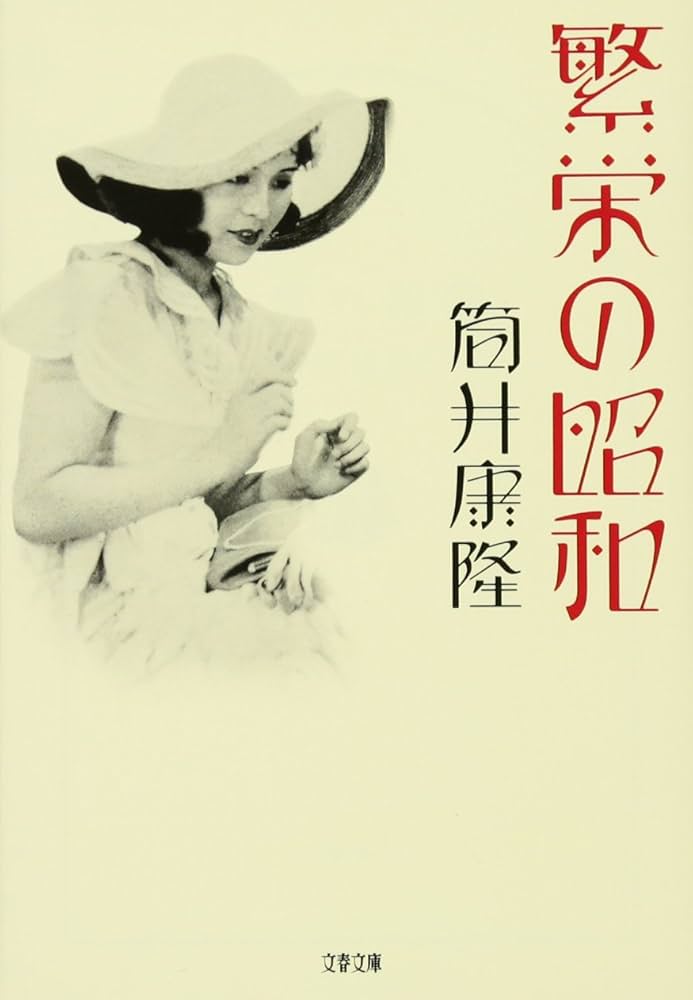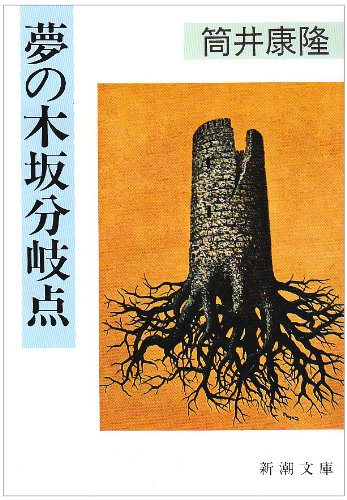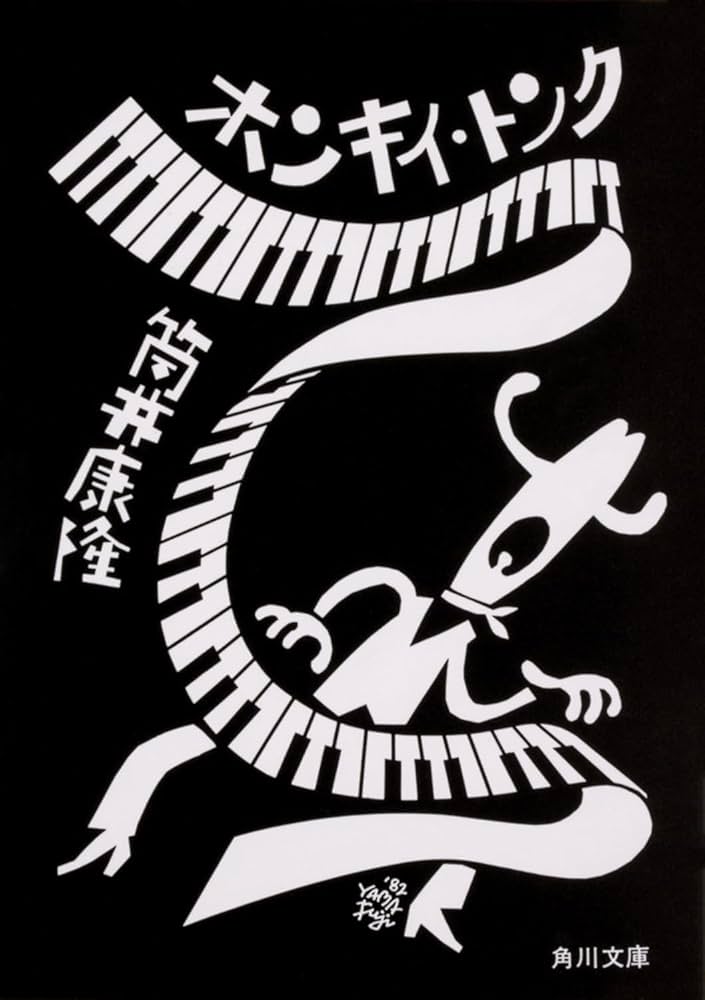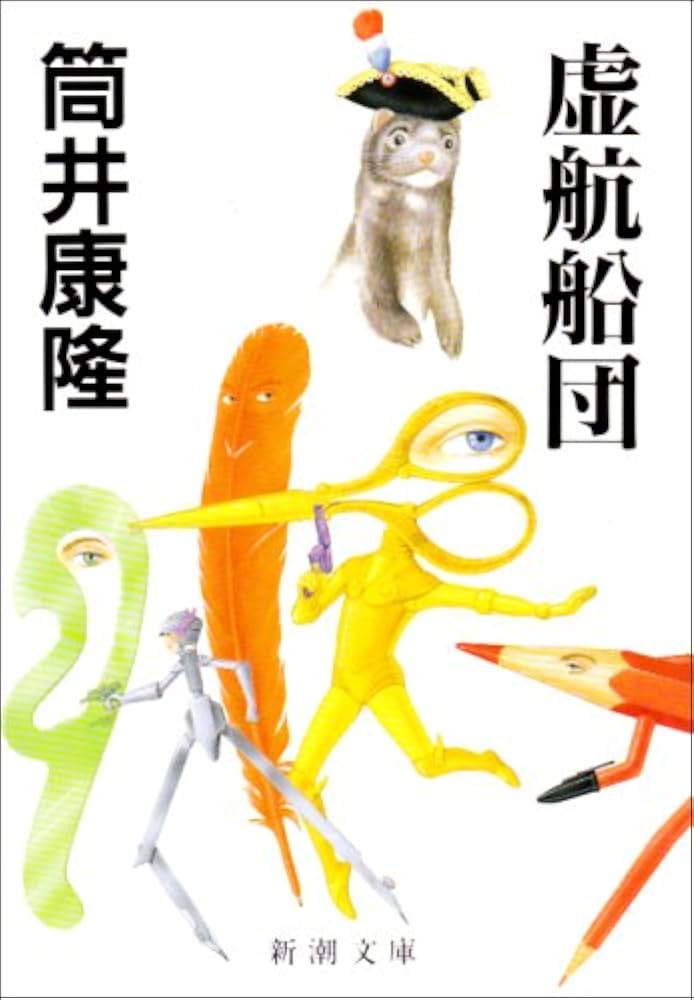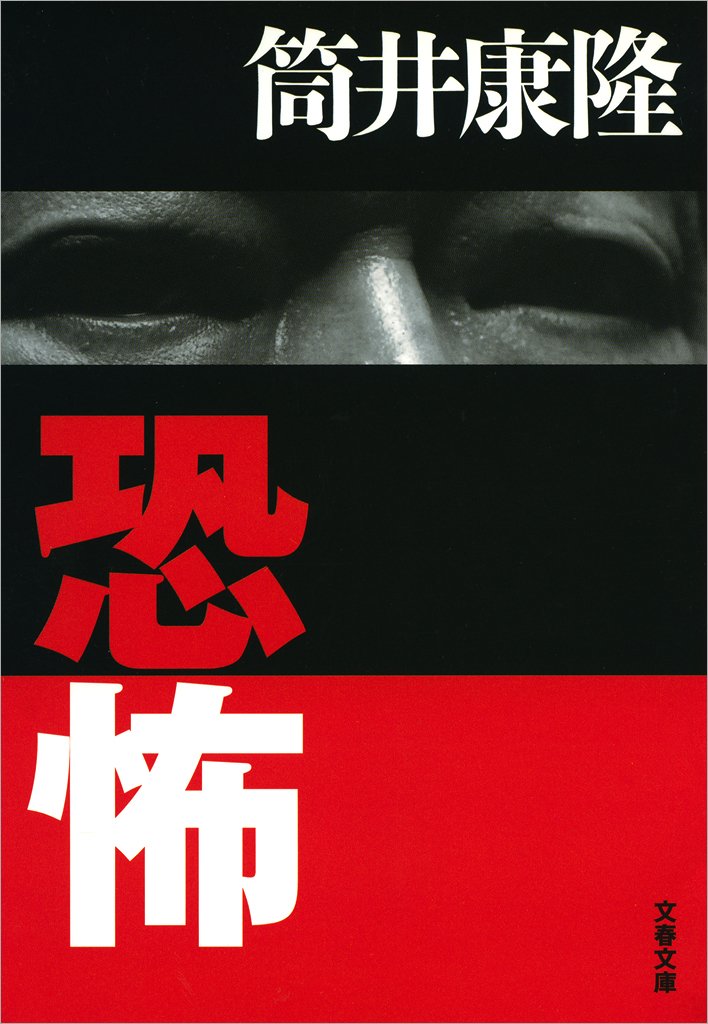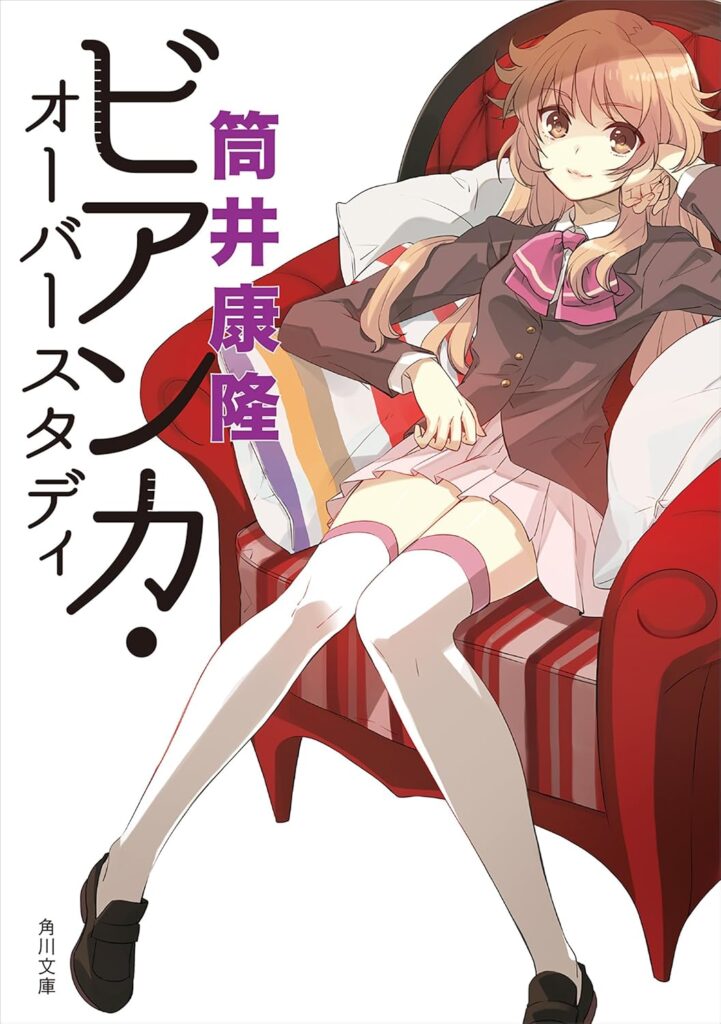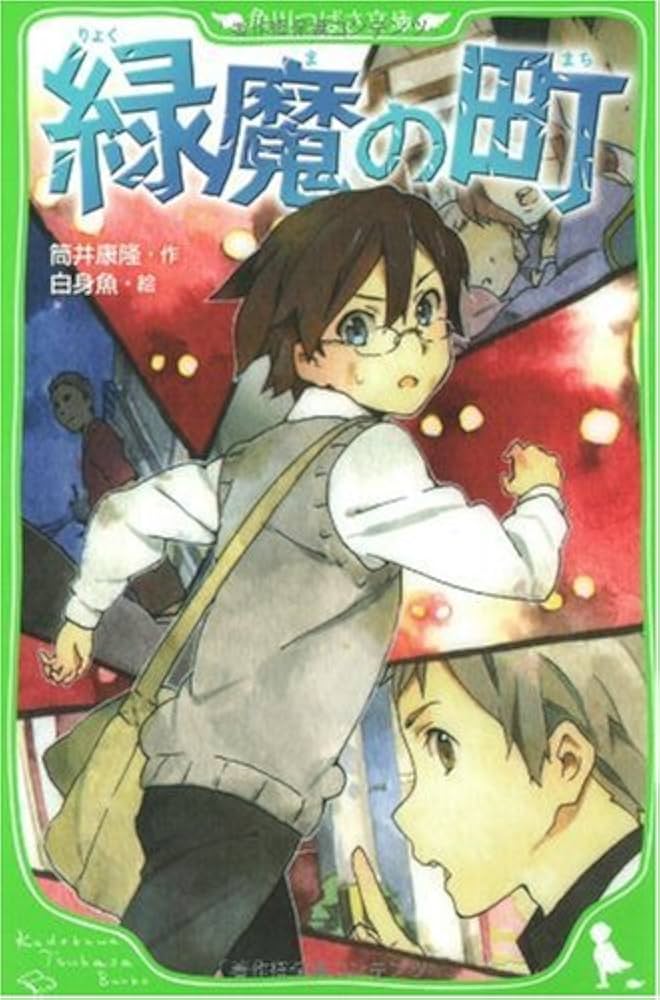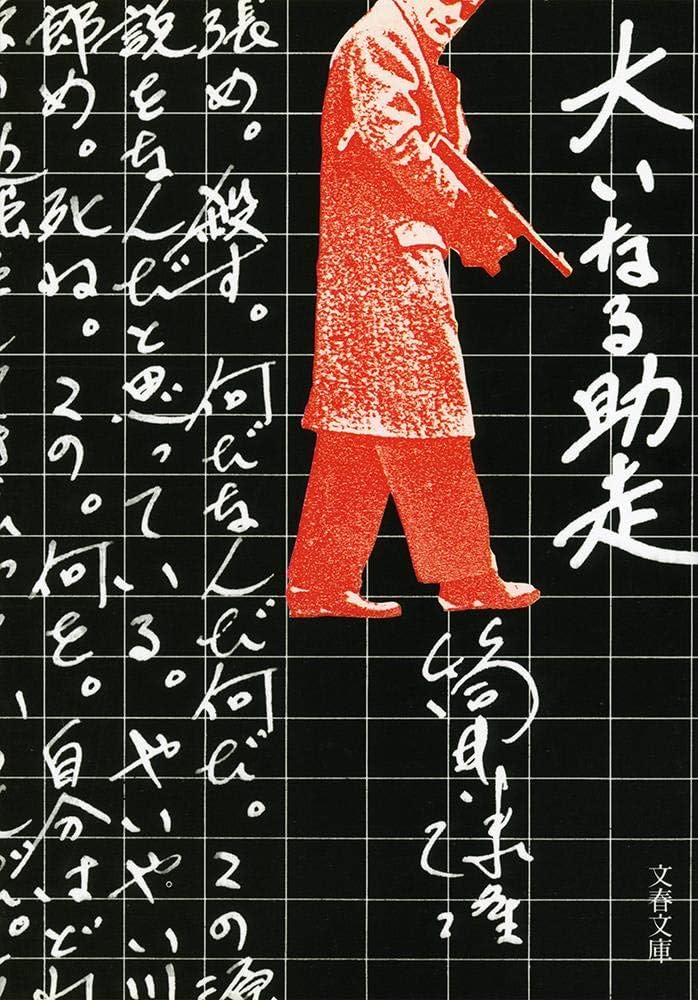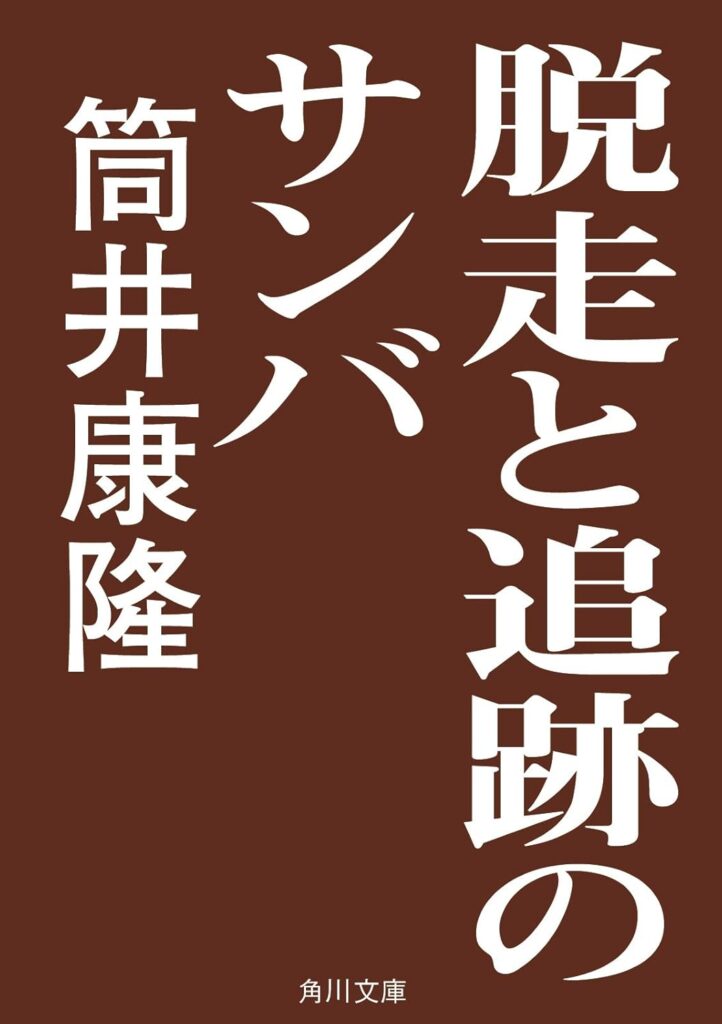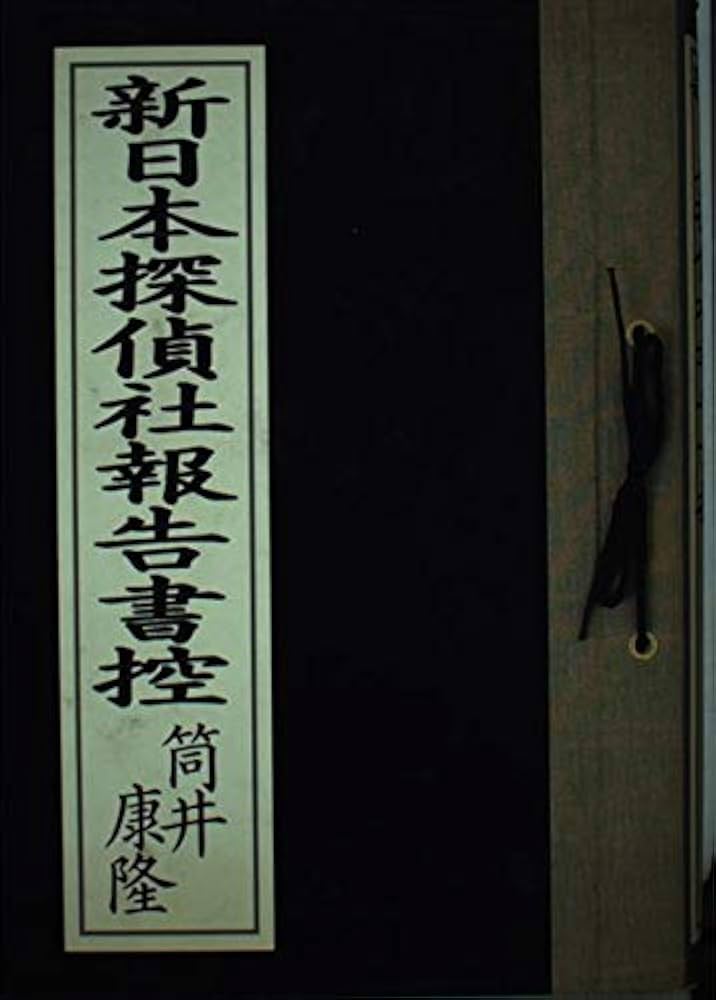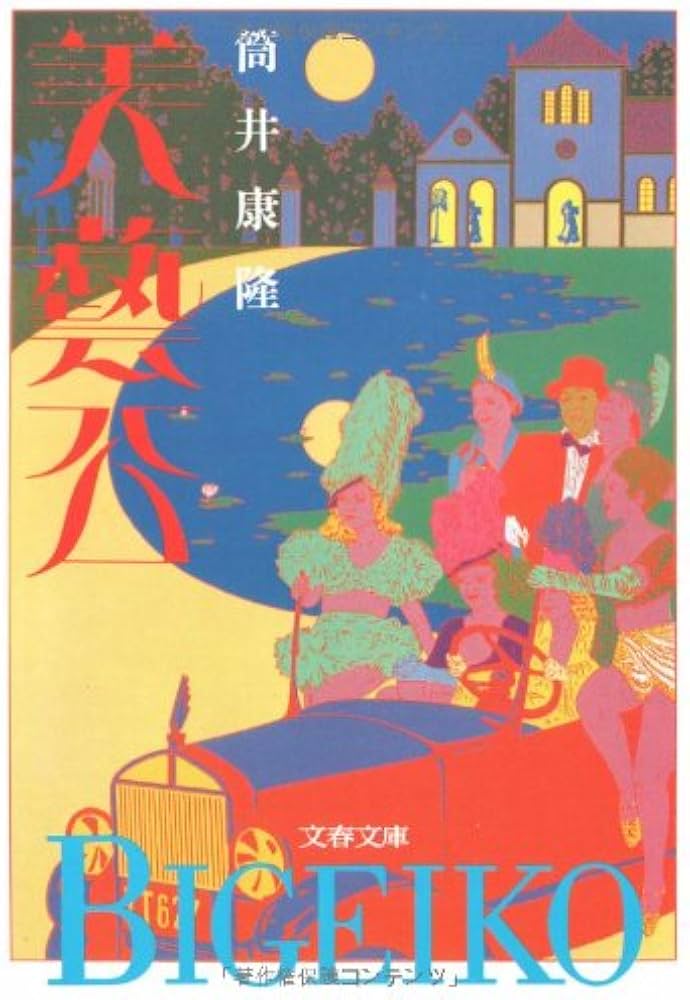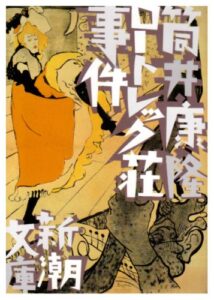 小説「ロートレック荘事件」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「ロートレック荘事件」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、ただのミステリではありません。読み終えた時、あなたはきっと「騙された!」と快哉を叫ぶか、あるいはそのあまりに悲しい結末に言葉を失うかのどちらかでしょう。私たちが普段、小説を読む際に無意識に抱いている「お約束」を根底から覆してくる、とんでもない仕掛けが施されているのです。
この記事では、まず物語の導入部と事件の発生までを、核心には触れずにご案内します。どのような謎が提示され、読者を迷宮に誘うのか。その雰囲気だけでも味わってみてください。華麗なる西洋館で繰り広げられる、美しくも残酷な事件の幕開けです。
そして、その先にはこの物語の真髄、大胆不敵な仕掛けのすべてと、登場人物たちが織りなす悲劇の全貌を、余すところなく書き記した私の思いの丈を綴っています。もしあなたが、この作品が突きつける挑戦を受けて立つ覚悟がおありなら、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは、ロートレックの絵画が彩る館で起きた、忘れられない事件の世界へご案内しましょう。
小説「ロートレック荘事件」のあらすじ
物語の舞台は、郊外に静かにたたずむ西洋風の館「ロートレック荘」。館の主である木内文麿氏が蒐集した画家ロートレックの作品が数多く飾られていることから、その名で呼ばれています。夏の終わり、主人の招待を受け、将来を嘱望された若者たちと美しい娘たちが、優雅なバカンスを過ごすためにこの館に集いました。
語り手は「おれ」と名乗る人物。彼は従兄弟の重樹とともにこの館を訪れます。一見、華やかで楽しげな雰囲気のなか、参加者たちの間では、誰が誰と結ばれるのかといった、恋の駆け引きも繰り広げられていました。美しい女性たちの中から、「おれ」は未来の花嫁を選ぶことを期待されています。
しかし、その平和な時間は突如として破られます。二発の銃声が響き渡り、最初の殺人事件が発生するのです。犠牲者は「おれ」の花嫁候補の一人であった牧野寛子。彼女の部屋にはロートレックのポスターが飾られており、その絵と死の状況には不気味な関連性が見られました。警察の捜査が開始され、館が厳重な監視下に置かれるも、犯人はそれを嘲笑うかのように、第二、第三の殺人を重ねていきます。
閉ざされた館の中で、誰もが疑心暗鬼に陥ります。外部からの侵入は不可能。犯人はこの中にいる——。生存者たちは、見えない犯人の影に怯えながら、絶望的な状況に追い込まれていきます。一体誰が、何のために、この惨劇を引き起こしているのでしょうか。そして「おれ」は、この連続殺人事件の謎を解き明かすことができるのでしょうか。物語は、読者の予想を根底から覆す、驚愕の真相へと突き進んでいくのです。
小説「ロートレック荘事件」の長文感想(ネタバレあり)
この「ロートレック荘事件」という物語を読み終えた時、私が感じたのは、謎が解けた爽快感よりも、むしろ頭を殴られたような強い衝撃と、胸にずっしりと残る深い悲しみでした。正直に告白しますと、私は作者である筒井康隆氏に、見事に、そして完膚なきまでに騙されてしまったのです。
この物語の核心にあるのは、フーダニット(誰が犯人か)という謎ではありません。もちろんそれも要素の一つではありますが、本当の恐ろしさは、ハウダニット(どうやって殺したか)でも、ホワイダニット(なぜ殺したか)でもない。物語の語り、その根幹を揺るがす「誰が語っているのか」という部分に、前代未聞の仕掛けが隠されていたのですから。
物語は一貫して「おれ」という一人称で語られます。私たちは自然と、この「おれ」という語り手を一人の人間だと信じて読み進めます。しかし、それこそが作者の仕掛けた壮大な罠でした。実はこの「おれ」は、浜口修と浜口重樹という二人の従兄弟が、章ごとに入れ替わりながら担当していたのです。いわゆる「二人一役」というトリックです。
この事実に気づかずに最後まで読み進めた読者は、最終章で作者自身によって行われる「種明かし」で、自分がどれほど深く物語の術中にはまっていたかを知ることになります。会話文において、誰が発言したのかを意図的に明記しない「言い落とし」という手法が、実に巧みに使われています。私たちは無意識のうちに、すべての会話を「おれ」(=単独の人物)と他の登場人物とのやりとりだと誤認させられていたのです。
さらに巧妙なのは、館の見取り図に隠されたヒントです。修と重樹が使う部屋には「浜口重樹」と書かれています。これを見て、誰もが「浜口重樹という人物の部屋」だと信じてしまいます。しかし、よく見ると他の部屋の住人は名字か名前のどちらか一方しか書かれていません。つまり、この部屋は「浜口(修)」と「(浜口)重樹」の二人部屋であることを、あの見取り図は示唆していたのです。後からこの事実に気づいた時の、あの悔しさと感嘆が入り混じった感覚は、今でも忘れられません。
この仕掛けは、ただ奇抜なだけではありません。物語の悲劇性を、より深く、より残酷なものにするために、完璧に機能しています。章によって語り手が入れ替わっているにもかかわらず、文体は一貫しています。読者は語り手の交代に気づくことなく、物語に没入していきます。このミスリードこそが、最後の悲劇を、どうしようもなく痛ましいものにしているのです。
そして明かされる犯人は、この二人一役の語り手の片割れ、浜口重樹でした。彼が連続殺人に手を染めた動機は、彼の人生そのものに深く根差した、壮絶な劣等感にありました。少年時代の事故が原因で下半身の成長が止まってしまった彼は、その身体的な欠陥に対して、深刻なコンプレックスを抱き続けてきたのです。
彼の犯行は、健常者である従兄弟の修や、館に集った「美貌の娘たち」に対する、歪んだ嫉妬と復讐心の発露でした。自分には決して手に入らないであろう幸福や美しさの象徴を、破壊していく。その行為は、彼の歪んでしまった精神が上げる、悲痛な叫びのようにも感じられます。
特に、それぞれの殺害現場に飾られたロートレックの絵画と、死の状況を関連付けるという演出は、彼の倒錯した美意識と、自らの犯行を一つの「作品」として完成させようとする計画性を物語っています。それは、自らが社会の周縁にいると感じる彼の、絶望的な自己表現だったのかもしれません。
しかし、この物語の本当の悲劇は、犯人の動機そのものよりも、その先にある、あまりにも残酷な「すれ違い」にあります。三人目の犠牲者となった木内典子。彼女が本当に愛していたのは、誰もが魅力的だと認める浜口修ではなく、コンプレックスに苛まれる浜口重樹、その人だったのです。
重樹は、典子のその純粋な想いに、最後まで気づくことができませんでした。自身の劣等感に目が眩み、彼女もまた他の女性たちと同じように修に惹かれているのだと、固く信じ込んでいたのです。その結果、自分を唯一愛してくれたかもしれない女性を、自らの手で殺めてしまうという、取り返しのつかない過ちを犯してしまいました。
物語の終盤、投獄された重樹のもとに、典子の母親から彼女の日記が届けられます。そのページをめくり、初めて典子の真情を知った時の彼の絶望は、いかばかりだったでしょうか。救われる可能性があった唯一の光を、自ら消してしまったという事実。この救いのない結末がもたらす読後感の重苦しさこそが、「ロートレック荘事件」という作品を忘れがたいものにしています。
この物語は、小説という形式そのものを問い直す、メタフィクション的な構造を持っている点でも特筆すべきでしょう。最終章の一つ手前、第十七章「解」において、作者である筒井康隆氏自身が物語に登場し、これまでに仕掛けたトリックのすべてを、ページ数まで引用しながら懇切丁寧に解説し始めるのです。
この突然の作者の介入は、読者を物語の世界から一気に引き剥がし、「これは作り物なのだ」という現実を突きつけます。それまで自分が必死に追いかけてきた謎や登場人物たちの感情が、すべて作者の手のひらの上で計算され尽くしたものであったことを、まざまざと見せつけられるのです。この構造は、読者が無意識に抱く「作者は誠実な語り手である」という信頼関係を、意図的に裏切るものです。
この「騙された」という感覚は、不快なものではなく、むしろ知的な興奮を伴うものでした。自分がどれだけ陳腐な思い込みに囚われて小説を読んでいたのかを自覚させられ、読書という行為そのものへの認識を新たにさせられたような気分です。これこそが、筒井康隆という作家の真骨頂なのかもしれません。
本作が発表された当時、ミステリ界では「新本格」というムーブメントが盛り上がりを見せ、叙述トリックを用いた作品も数多く登場していました。しかし、この「ロートレック荘事件」は、その潮流とは少し異なる場所で、独自の輝きを放っていたように思います。トリックの斬新さもさることながら、そのトリックが、人間のどうしようもない悲劇性を描き出すために、これ以上ないほど効果的に使われているからです。
この作品が投げかけるのは、劣等感という感情が人間をいかに破壊しうるか、という普遍的なテーマです。そして、言葉というものが、いかに簡単に真実を覆い隠し、誤解を生み出してしまうかという、コミュニケーションの根源的な危うさでもあります。重樹と典子の悲劇は、まさにその象徴と言えるでしょう。
もし、あなたがこれから「ロートレック荘事件」を手に取るのであれば、どうか先入観を捨てて、ただ物語の波に身を任せてみてください。そして、最後に待ち受ける衝撃と悲しみを、全身で受け止めてほしいと思います。それはきっと、あなたの読書人生において、決して忘れることのできない強烈な体験となるはずです。この物語は、単なるミステリの傑作という枠には収まらない、人間の業と哀しみを描ききった、壮絶な文学作品なのですから。
まとめ
この記事では、筒井康隆氏の傑作「ロートレック荘事件」について、その物語の骨子から、核心であるトリック、そして胸を打つ悲劇的な結末までを詳しく語ってきました。この作品の魅力は、一筋縄ではいかない複雑な構造にあります。
まず、読者の思い込みを巧みに利用した「二人一役」という叙述の仕掛けは、ミステリというジャンルの可能性を押し広げた、見事な発明と言えるでしょう。このトリックによって、読者は物語の終盤で強烈な知的興奮を味わうことになります。
しかし、本作の真価は、その奇抜な仕掛けだけに留まりません。物語の根底には、人間の劣等感や嫉妬、そしてコミュニケーションのすれ違いが引き起こす、どうしようもなく悲しいドラマが横たわっています。トリックの解明と悲劇の真相が分かちがたく結びついている点に、本作の奥深さがあるのです。
これから読まれる方も、すでに読まれた方も、この記事を通じて「ロートレック荘事件」という物語の持つ多層的な魅力を再発見していただけたなら幸いです。それは、あなたにとって忘れられない一冊になることを、私は確信しています。