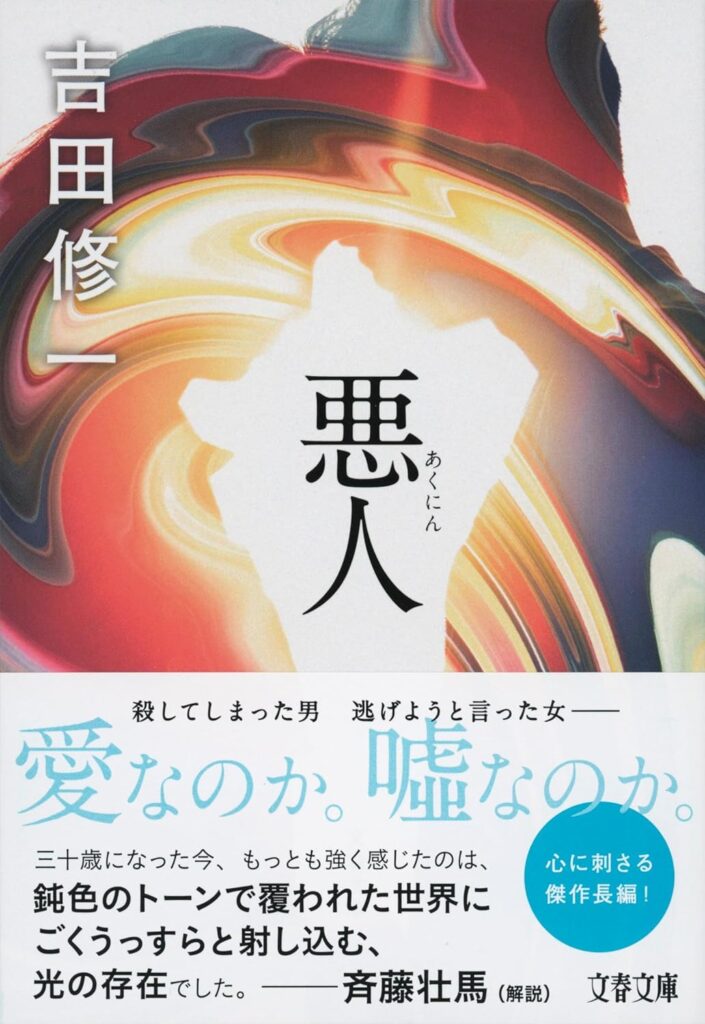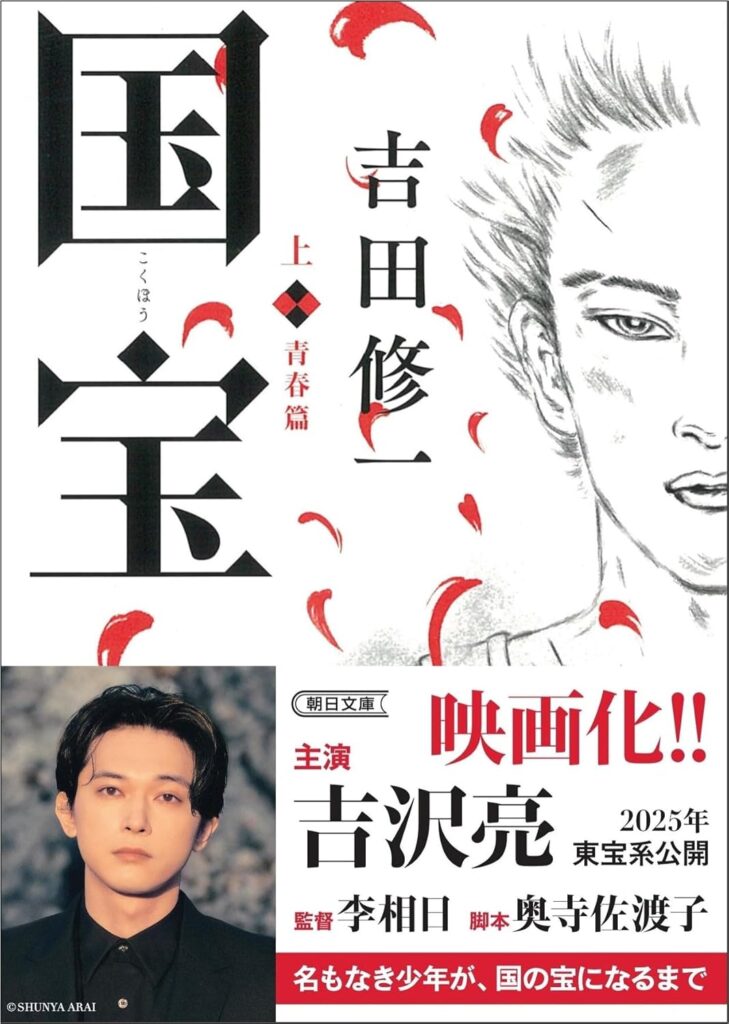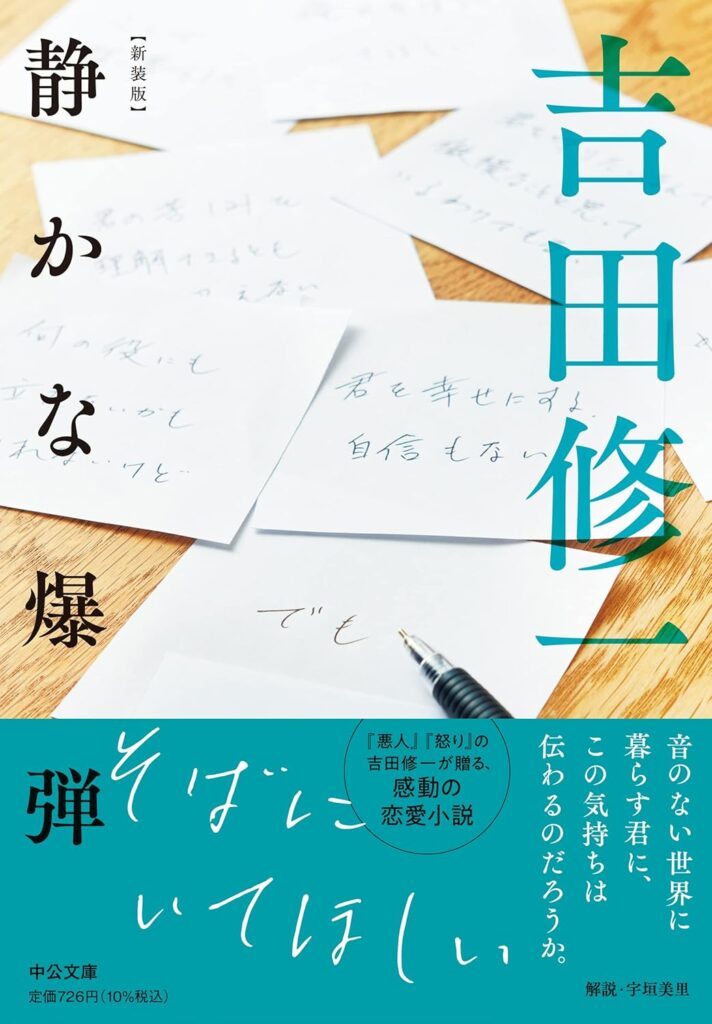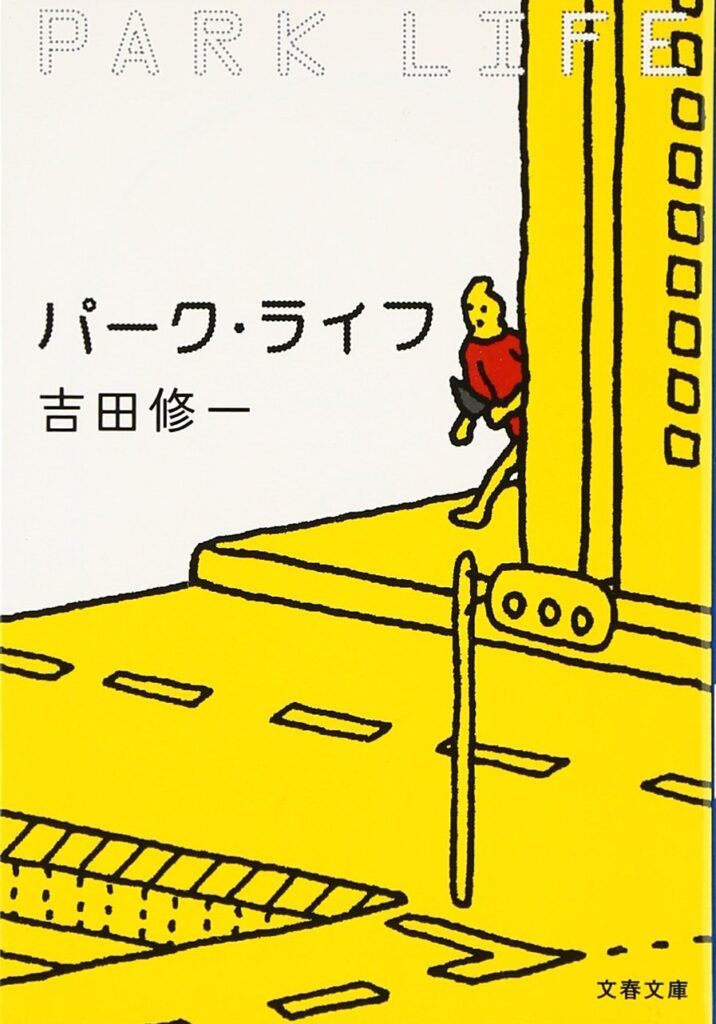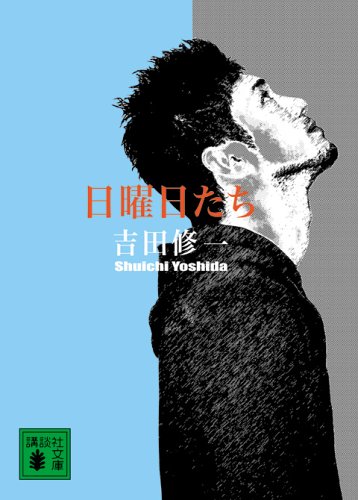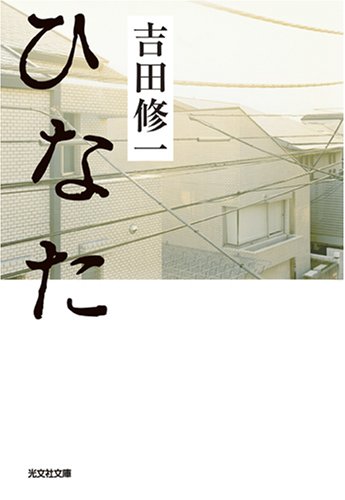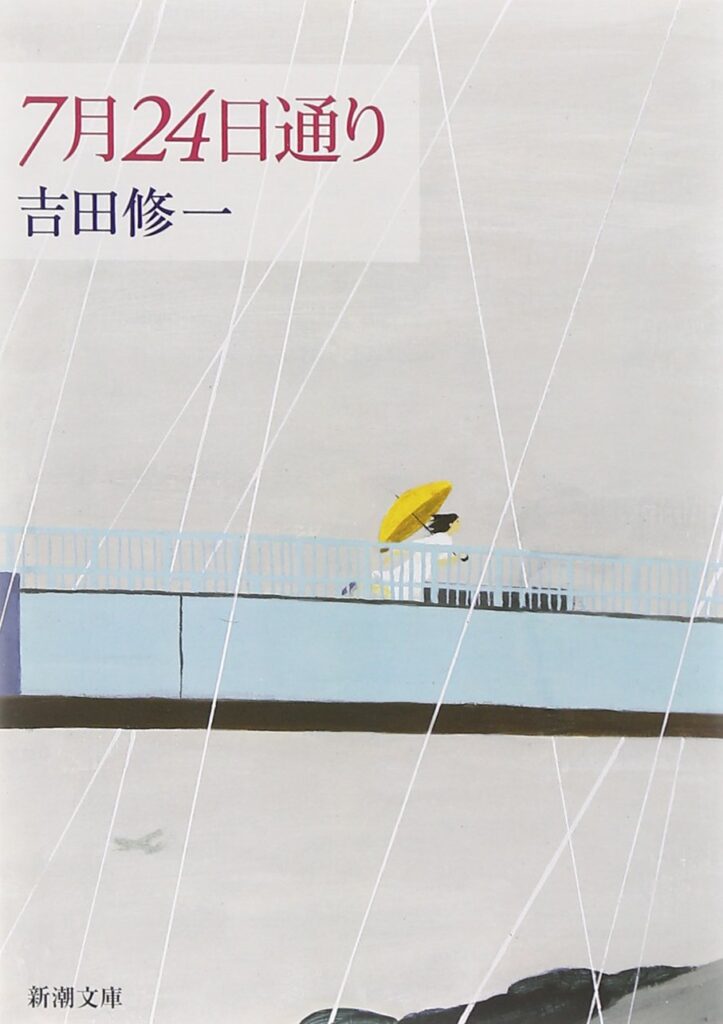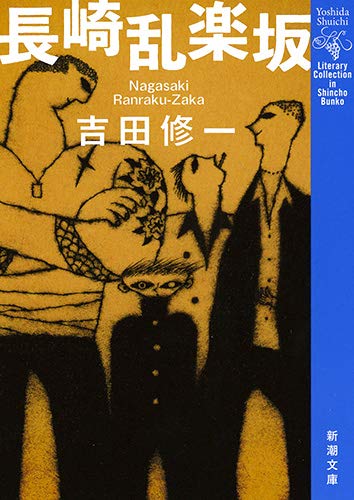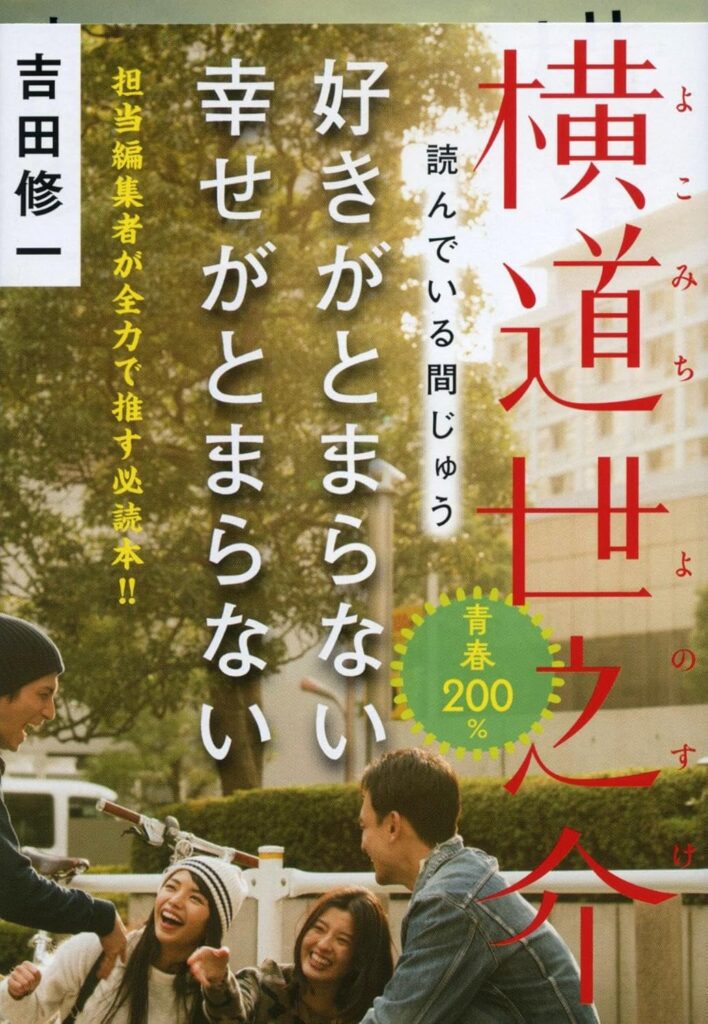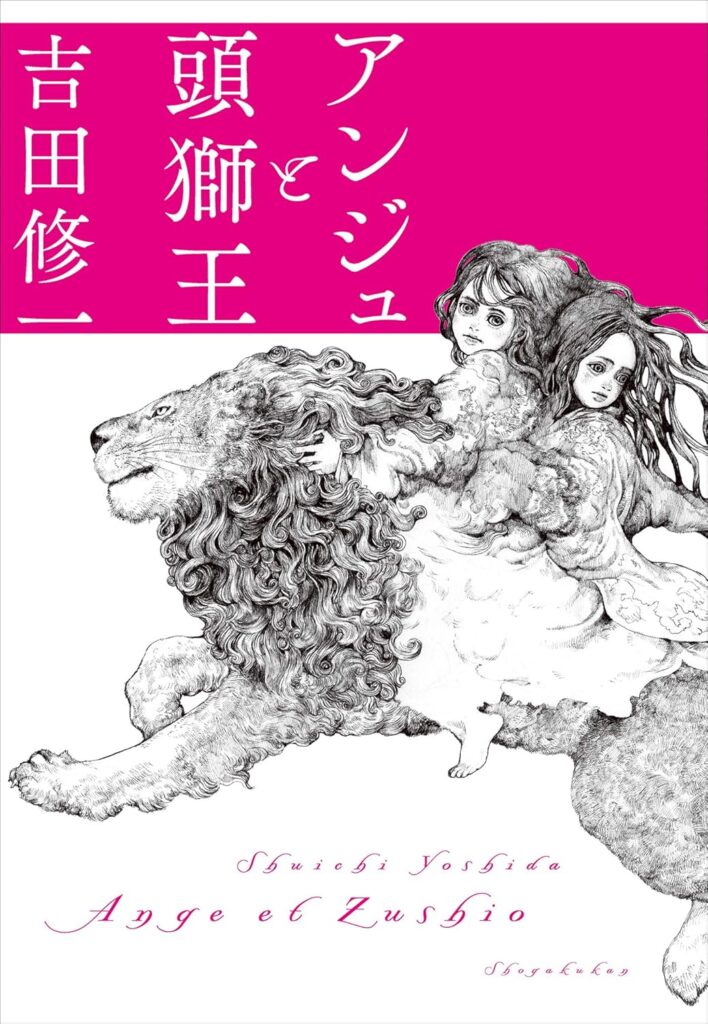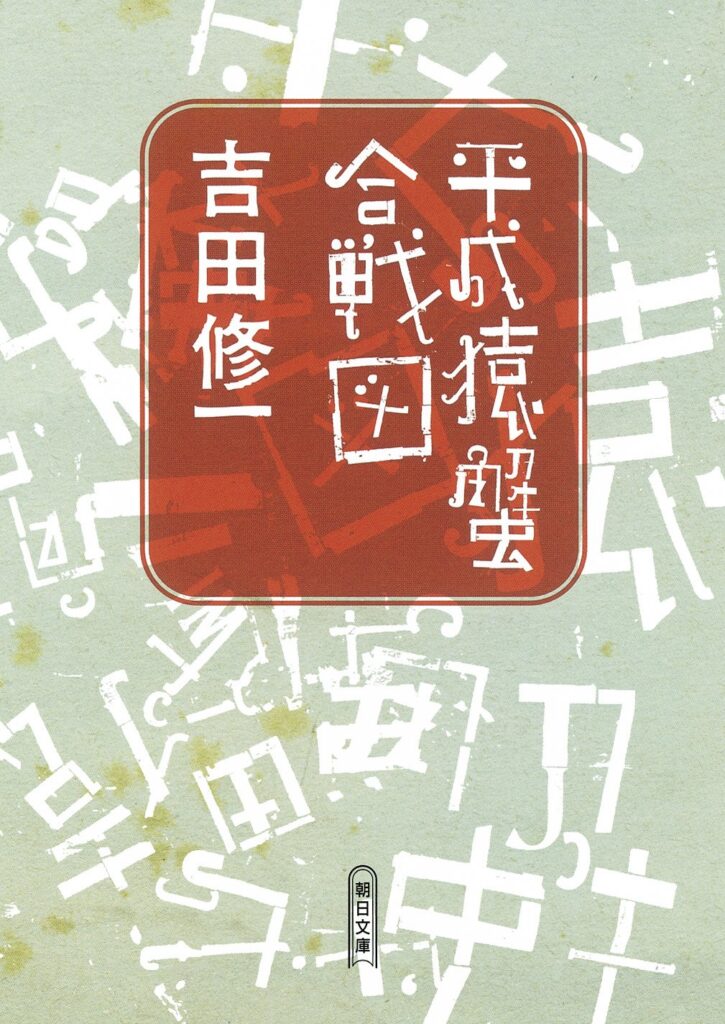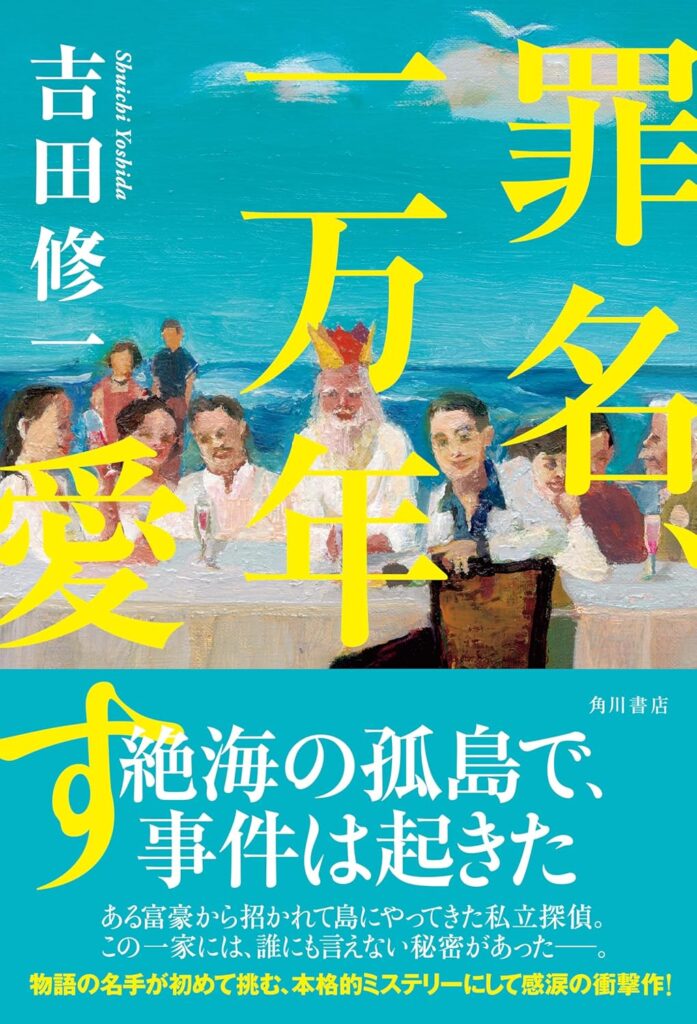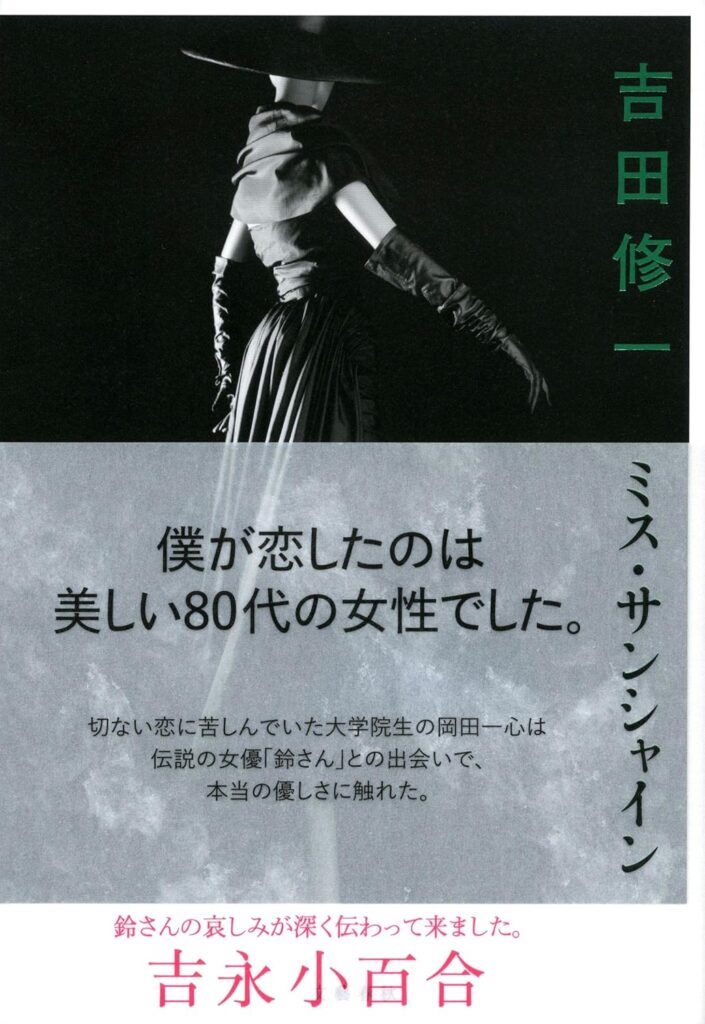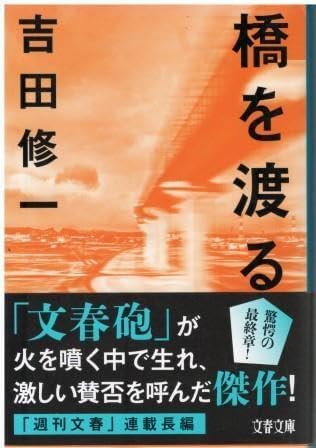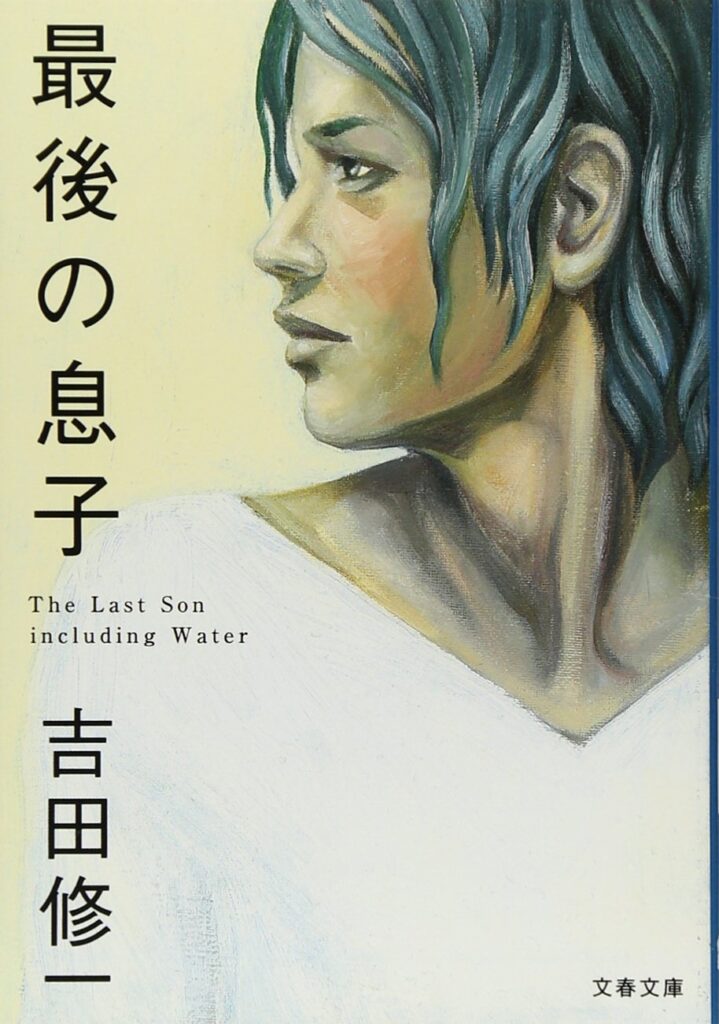小説「ランドマーク」のあらすじを物語の核心に触れつつご紹介します。長文の作品考察も書いていますのでどうぞ。吉田修一さんが紡ぎ出す物語は、いつも私たちに何かズシリと重い問いを投げかけてくるように感じます。この「ランドマーク」という作品も、その例に漏れません。
小説「ランドマーク」のあらすじを物語の核心に触れつつご紹介します。長文の作品考察も書いていますのでどうぞ。吉田修一さんが紡ぎ出す物語は、いつも私たちに何かズシリと重い問いを投げかけてくるように感じます。この「ランドマーク」という作品も、その例に漏れません。
物語の舞台は、開発が進む街にそびえ立とうとする巨大な螺旋状のビル。その建設に関わる二人の男の人生が、まるでその奇妙な建造物そのもののように、複雑に絡み合い、そして静かに軋んでいく様子が描かれます。読み進めるうちに、彼らの日常に潜む微細な狂気や、言葉にならない渇望のようなものが、じわりじわりと伝わってくるのです。
この作品の特筆すべき点は、その構成にあると言えるでしょう。章が通常とは逆に進んでいく趣向は、まるで何かの終わりへと向かうカウントダウンのようで、読者の心に独特の緊張感をもたらします。そして、二人の主人公の視点が交互に描かれることで、物語は多層的な深みを増していきます。
この記事では、そんな「ランドマーク」の世界観に深く分け入り、物語の細部や登場人物たちの心の機微、そして作品全体が問いかけるものについて、じっくりと考えてみたいと思います。この物語があなたにとって、どのような「目印」となるのか、一緒に探求していきましょう。
小説「ランドマーク」のあらすじ
「ランドマーク」は、関東近郊の都市、大宮に建設される地上35階建ての「O-miya スパイラル」という奇抜なデザインの超高層ビルを軸に、二人の男の人生が描かれていきます。一人は、この野心的なビルの設計を手掛けた建築士、犬飼洋一。彼は洗練された都会生活を送る一方で、妻がありながら職場の部下と関係を持つなど、どこか満たされない渇望を抱えています。
もう一人の主人公は、清水隼人。九州から上京し、このスパイラルビルの建設現場で働く鉄筋工の若者です。彼は、他の作業員たちとは一線を画すように、ある秘密の行動を続けます。それは、通販で購入した金属製の貞操帯を常に身に着け、その鍵を建設中のビルの各階のコンクリートに一つずつ埋めていくという、常軌を逸した行為でした。
物語は、章番号が10から1へとカウントダウンするように進んでいきます。それぞれの章は、エリートである犬飼の日常と、肉体労働者である隼人の日常が交互に描かれる構成になっています。犬飼は、自らが設計したビルが現実のものとなっていく様に複雑な思いを抱き、そのねじれた構造は彼の心象風景とも重なるかのようです。彼の私生活もまた、微妙なバランスの上で成り立っています。
一方の隼人は、過酷な労働環境の中で、貞操帯という異物を身に着けることで、自らにある種の負荷をかけ、存在の確かさを求めようとしているかのようです。彼の奇妙な儀式は、誰にも知られることなく続けられ、完成に近づくビルの中に、彼の秘密が塗り込められていきます。彼の行動の真意は、物語の中で明確には語られません。
犬飼と隼人。社会的立場も生活も全く異なる二人ですが、彼らは同じ一つの「ランドマーク」となるべき建造物を通して、間接的に繋がっています。設計者と建設者、創造する者とされる者。彼らの人生は、ビルが天へと伸びていくのとは対照的に、どこか不安定な方向へと静かに歪んでいくような様相を呈します。
そして物語は、ビルが完成に近づき、カウントダウンが終わりに近づくにつれて、不穏な空気を一層濃くしていきます。積み上げられた日常のわずかな亀裂、言葉にならない苛立ち、そして内なる狂気。それらが臨界点に達したとき、何が起こるのか。明確な破局が描かれるわけではありませんが、読者には強烈な「予感」が残される形で、物語は静かに幕を閉じます。
小説「ランドマーク」の長文感想(ネタバレあり)
吉田修一さんの手による「ランドマーク」を読み終えたとき、心に残るのは、すっきりとした解決や明確な答えではなく、むしろ問いそのものでした。まるで、巨大な建造物の前に一人佇み、その存在意義や、それを取り巻く人々の営みについて、静かに思いを馳せているような感覚。この物語は、私たち自身の日常や、現代社会が抱える見えない歪みについて、深く考えさせられる力を持っています。
まず、この作品の構造自体が非常に象徴的であると感じました。物語が「Number 10」から始まり、「Number 1」で終わるというカウントダウン形式。これは単なる趣向ではなく、物語全体に緊張感と、ある種の終末的な予兆を与えています。まるで、ゆっくりと時限爆弾の針が進むのを見守るような、あるいは、巨大な塔が完成に近づくにつれて、その影が濃くなっていくのを感じるような。読者は、何かが起こるかもしれないという漠然とした不安を抱えながら、ページをめくることになります。
そして、各章が設計士である犬飼のパートと、鉄筋工である隼人のパートに分かれている点。これは、社会における異なる階層、あるいは異なる価値観を持つ二つの世界を対比的に描き出すと同時に、その二つが「O-miya スパイラル」という一つの目標、一つの建造物を介して、否応なく結びついていることを示唆しています。彼らの人生は直接的には交わらないかもしれませんが、同じ一つの「ランドマーク」の建設という行為を通して、互いに影響を与え合っているかのようです。この構造は、まるでDNAの二重螺旋のように、絡み合いながら一つの大きな物語を形成していくかのようにも見えます。
犬飼洋一という人物。彼は、誰もが羨むような成功した建築家であり、美しい妻を持ち、都心の一等地に住む、いわば「勝ち組」の象徴のような存在です。しかし、彼の内面は決して満たされてはいません。職場の若い女性との不倫関係は、彼の心の空虚さや、日常からの逃避願望の表れなのかもしれません。彼が設計したスパイラルビルは、その名の通り、ねじれ、歪んでいます。それは、彼の心のありよう、あるいは彼が生きる現代社会の歪みを体現しているかのようです。彼がビルを見上げる時、そこに何を見ているのか。自らの野心、創造の喜び、それとも、その巨大さがもたらす得体の知れないプレッシャーでしょうか。
一方、清水隼人の存在は、この物語に強烈な異物感と謎をもたらします。彼が自らに課した「貞操帯の着用」という行為。これは一体何を意味するのでしょうか。社会への反発? 自己への懲罰? あるいは、希薄な現実の中で、自らの肉体的な存在を確かめるための儀式なのでしょうか。彼は、貞操帯の鍵を、建設中のビルのコンクリートに埋めていきます。まるで、自らの秘密や、言葉にならない思いを、巨大な建造物の一部として封じ込めていくかのように。この行為は、誰にも理解されることなく、ただ黙々と続けられます。彼の孤独と、内なる叫びが、この奇行を通して静かに伝わってくるようです。
隼人の行動は、現代社会における個人の疎外感や、承認欲求の歪んだ発露として解釈することもできるかもしれません。彼は、巨大な組織の中で、名もなき労働者として鉄筋を組み上げる日々を送っています。その中で、彼が「貞操帯」という異常なアイテムを身に着けることは、彼なりの抵抗であり、自分という存在を刻みつけるための行為だったのかもしれません。しかし、その行為は誰にも気づかれず、彼の孤独を深めるばかりです。
この二人の主人公、犬飼と隼人は、物語の中で一度も直接的な言葉を交わしません。彼らは、同じビルを見上げ、同じ建設現場に関わりながらも、決して交わることのない平行線の上を歩んでいるかのようです。この「交わらなさ」こそが、現代社会における人間関係の希薄さや、見えない壁の存在を象徴しているのかもしれません。私たちは、同じ空間にいながら、実は互いに深く理解し合うことなく、それぞれの孤独を抱えて生きているのではないか。そんな問いを突きつけられるようです。
そして、物語の中心にそびえ立つ「O-miya スパイラル」。このビルは、単なる背景ではなく、第三の主人公とでも言うべき存在感を放っています。そのねじれた外観は、美しさと同時に、どこか不穏な印象を与えます。完成すれば街の「ランドマーク」となるはずのこのビルが、実は人々の心の歪みや、社会の不安定さを内包しているかのようです。建設が進むにつれて、ビルが天に向かって伸びていく一方で、登場人物たちの日常は少しずつ軋み、歪んでいく。この対比が、物語に不気味な緊張感を与えています。
吉田修一さんの筆致は、どこまでも冷静で、淡々としています。登場人物たちの内面を克明に描き出しながらも、決して感情的に彼らを断罪したり、擁護したりすることはありません。ただ、そこにある現実を、あるがままに提示していく。だからこそ、読者は自ら考え、感じ取ることを促されるのです。特に、隼人が貞操帯を装着する場面や、それを隠そうとする心理描写は、非常に生々しく、読者の心に深く刻まれます。
物語の結末は、明確なカタルシスや解決が用意されているわけではありません。むしろ、「そこで終わるのか」という、ある種の宙吊り感、あるいは予感のようなものを残して幕を閉じます。ビルは完成に近づき、カウントダウンは終わろうとしている。しかし、登場人物たちが抱える問題や、彼らの内なる狂気が完全に解消されたわけではない。むしろ、これから何かが起こるのではないか、という不穏な空気を残したままなのです。この「寸止め」とも言える終わり方は、読者に強烈な印象を残し、物語について長く考えさせる効果を持っていると感じます。
この「ランドマーク」という作品が問いかけるものは何でしょうか。それは、現代社会における成功とは何か、真の充足とは何か、ということかもしれません。あるいは、日常の中に潜む狂気や、人間が抱える孤独の深さについてかもしれません。犬飼は社会的成功の只中にいながら虚無感を抱え、隼人は社会の底辺で奇行に走ることでしか自己を表現できない。彼らの姿は、現代を生きる私たちの姿と、どこかで重なる部分があるのではないでしょうか。
また、この物語は「見ること」「見られること」というテーマも内包しているように感じます。犬飼は設計者としてビルを「見る」立場であり、また、彼の不倫は隠された「見られる」ことへの恐れを伴います。隼人は、貞操帯という秘密を抱え、他者から「見られる」ことを極度に警戒しつつも、心のどこかでは誰かに気づいてほしいという矛盾した感情を抱えているのかもしれません。そして、ランドマークとなるビルは、完成すれば多くの人々から「見られる」存在となります。その視線の中で、彼らの歪みはどのように映るのでしょうか。
私は、この物語を読み終えて、隼人の貞操帯の鍵が埋められたビルが、まるで巨大な墓標のようにも感じられました。彼が葬り去りたかったのは何だったのか。あるいは、彼がそこに永遠に刻み込みたかったのは何だったのか。その答えは、読者一人ひとりの解釈に委ねられているのでしょう。
この作品は、決して読者に優しい物語ではありません。しかし、その突き放すような筆致の中に、人間の本質に迫ろうとする真摯な眼差しを感じます。そして、読み返すたびに新たな発見があり、異なる解釈が生まれるような、奥深い作品であると言えるでしょう。
最後に、この物語が示す「ランドマーク」とは、物理的な建造物だけを指すのではないように思います。それは、人生における重要な出来事や、心の転換点、あるいは、自分自身を見失わないための「目印」なのかもしれません。そして、その「目印」すらも、時には歪み、不安定なものであるという現実を、この物語は静かに教えてくれるのです。
まとめ
吉田修一さんの小説「ランドマーク」は、大宮に建設される螺旋状の超高層ビルを舞台に、設計士の犬飼と鉄筋工の隼人という二人の男の人生が、カウントダウン形式で描かれる物語です。彼らの日常に潜む歪みや孤独、そして内なる狂気が、ビル建設の進行とともに静かに浮かび上がってきます。
犬飼はエリートでありながら満たされず、隼人は貞操帯を身に着けるという奇行に走る。直接交わることのない二人の人生が、一つの「ランドマーク」を通して間接的に結びつき、現代社会の抱える問題や人間の複雑な心理を浮き彫りにしていきます。物語は明確な結末を提示せず、読者に深い余韻と考察の余地を残します。
この作品を読むことで、私たちは日常に隠された亀裂や、言葉にならない人間の感情の深淵に触れることになるでしょう。そして、何が真の「目印」となり得るのか、自問せずにはいられなくなるはずです。
もし、あなたが現代社会の深層や人間の心の不可解さに興味があるのなら、この「ランドマーク」という作品は、きっと忘れられない読書体験となるでしょう。一度手に取って、その独特の世界に迷い込んでみてはいかがでしょうか。


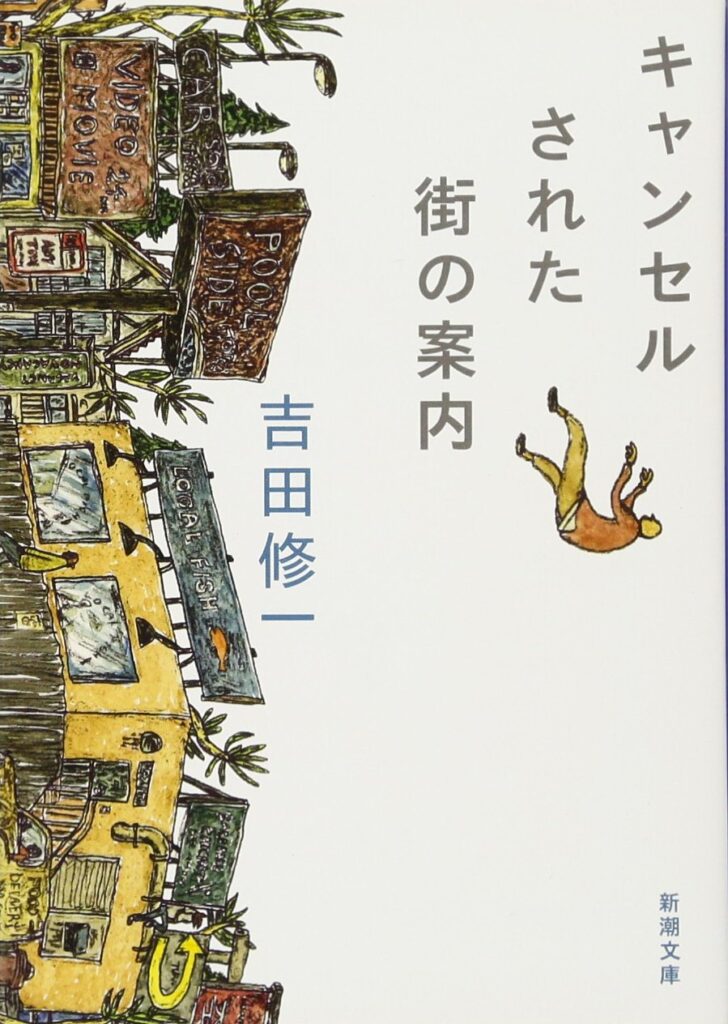
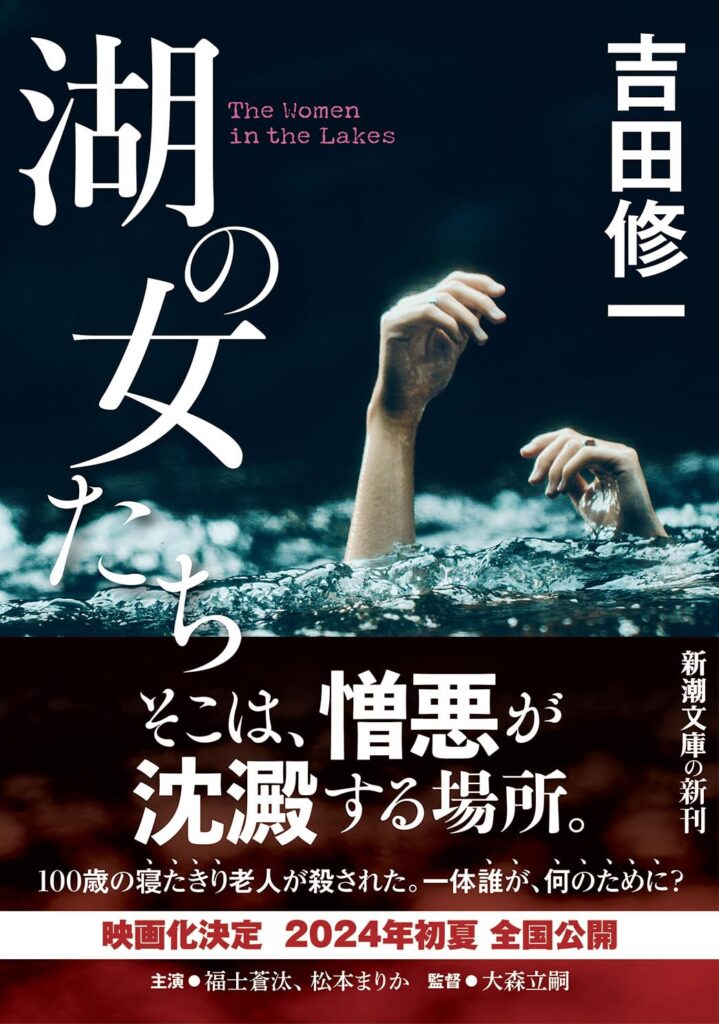
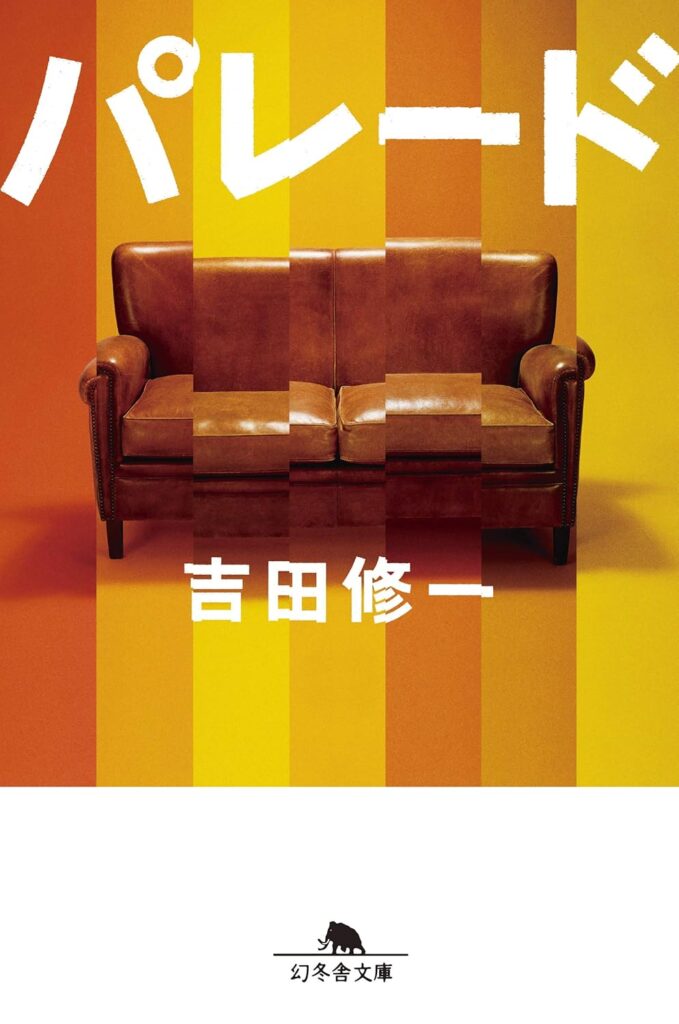
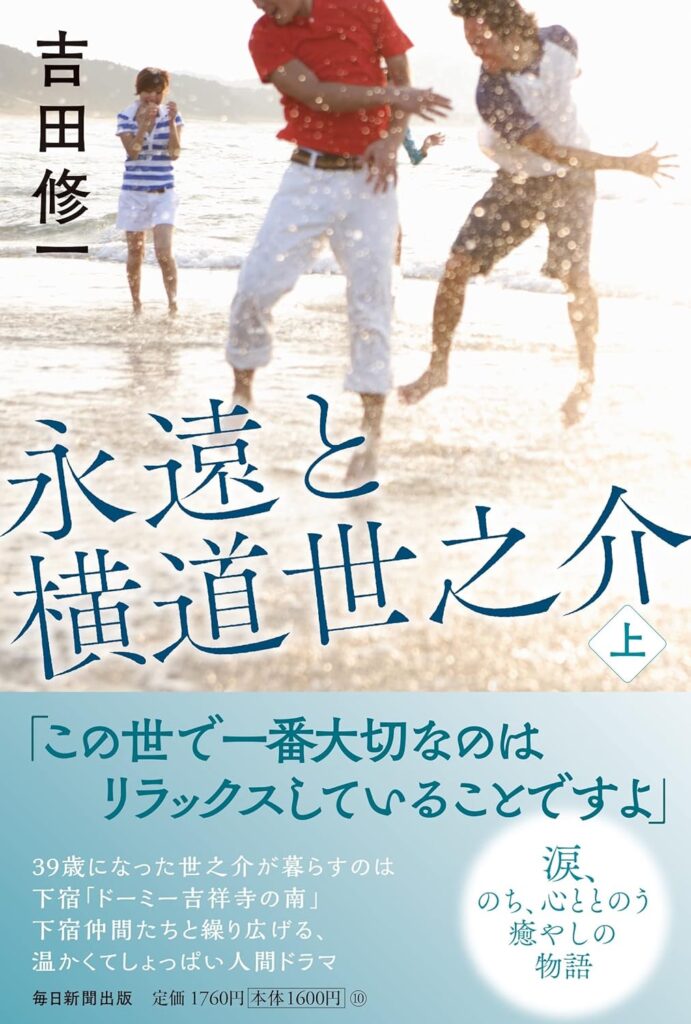
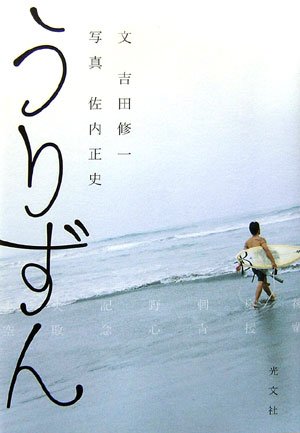
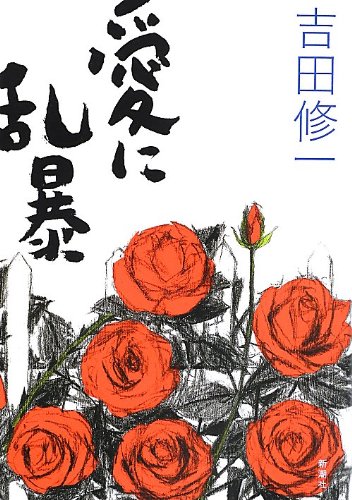
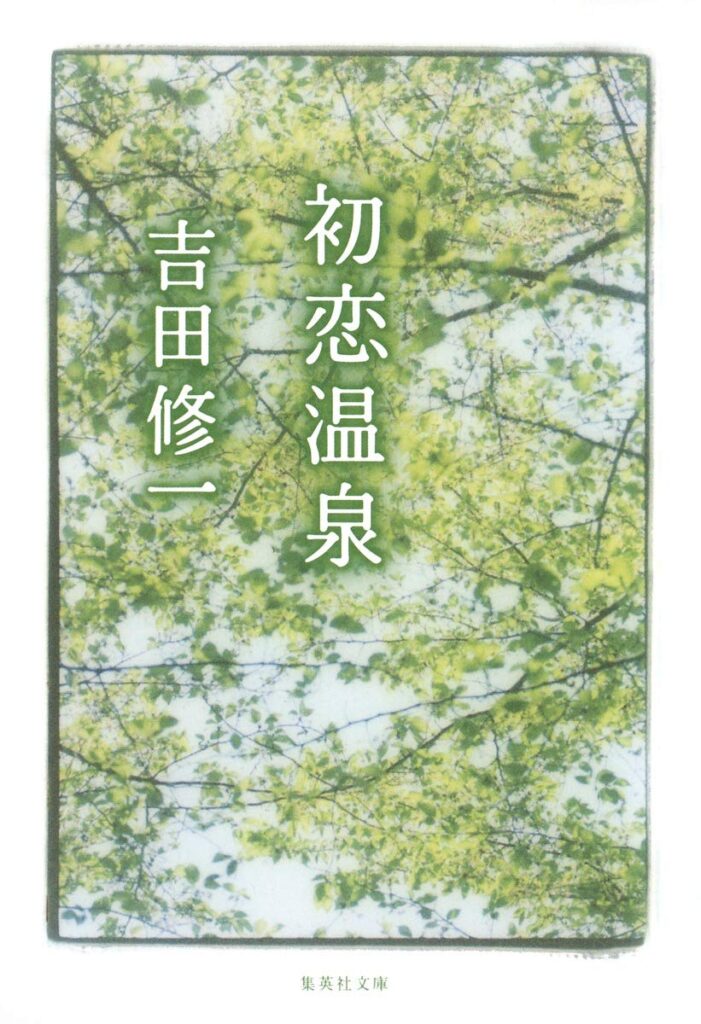
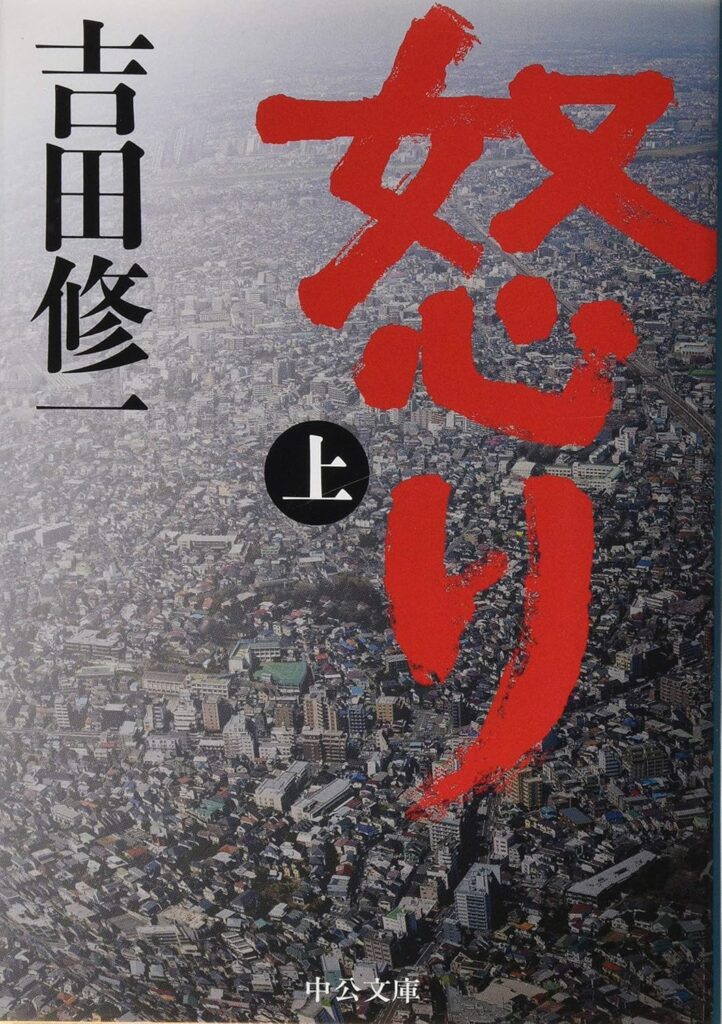
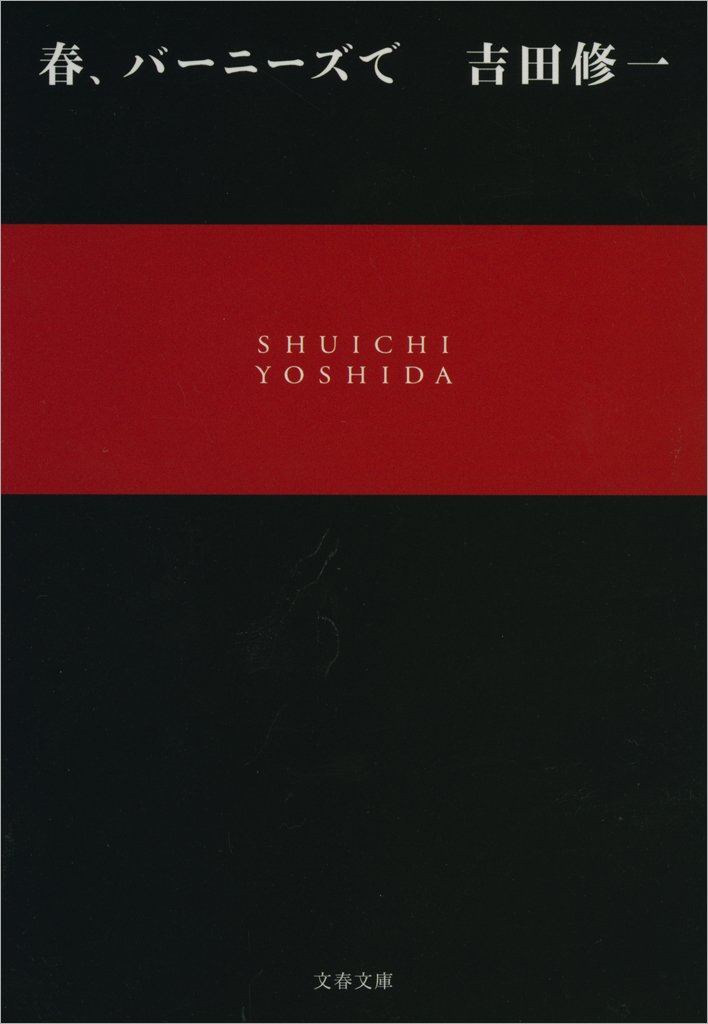
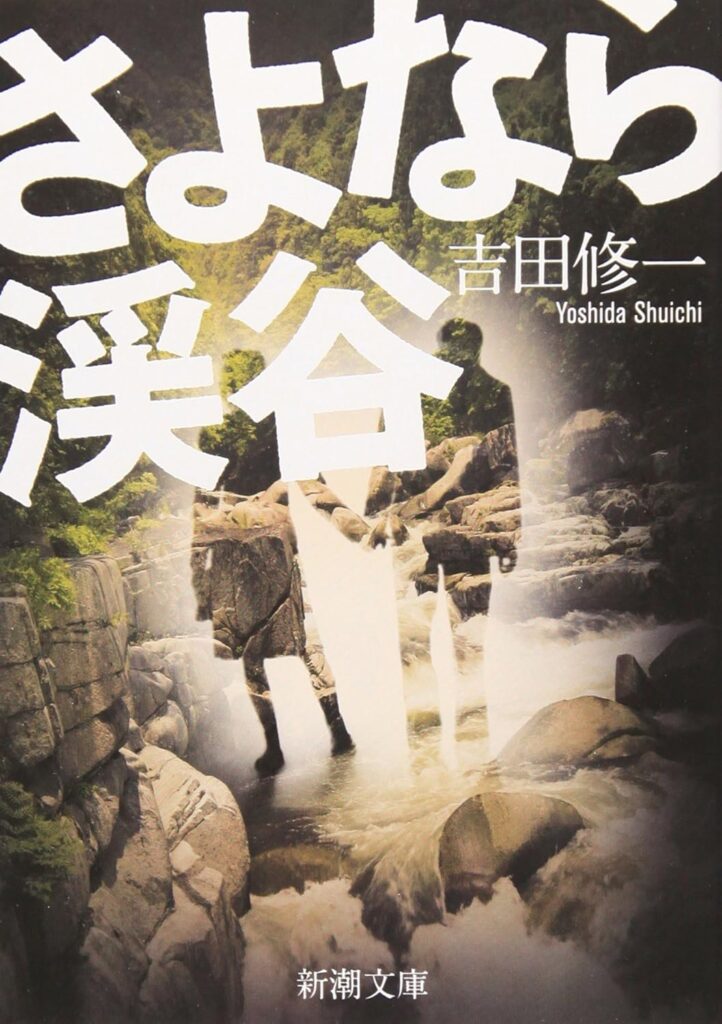
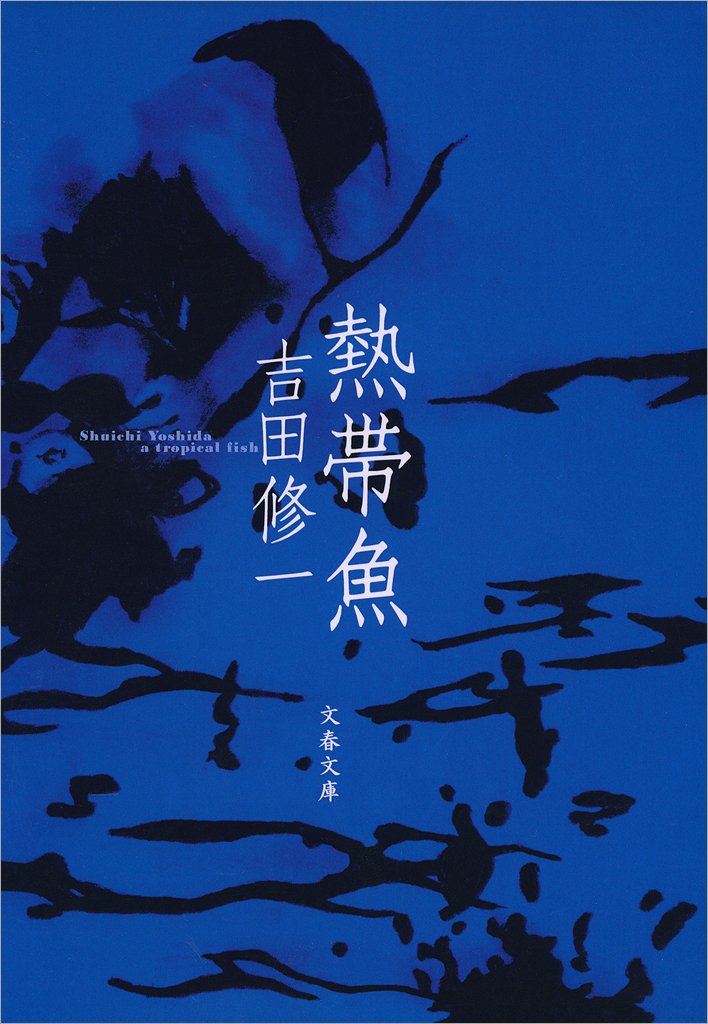
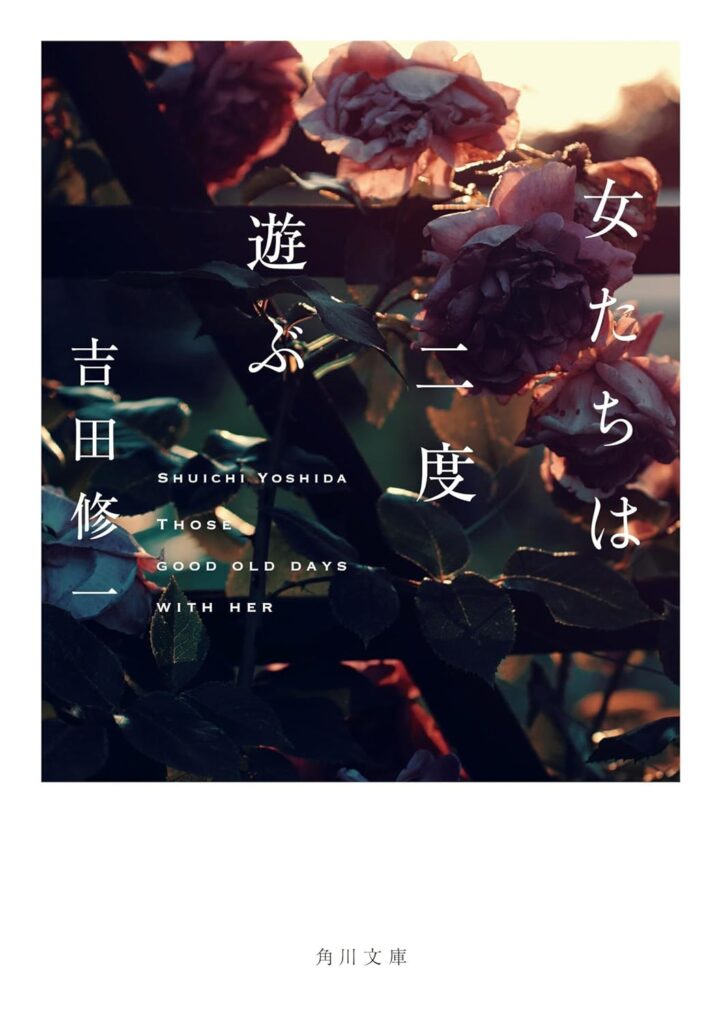
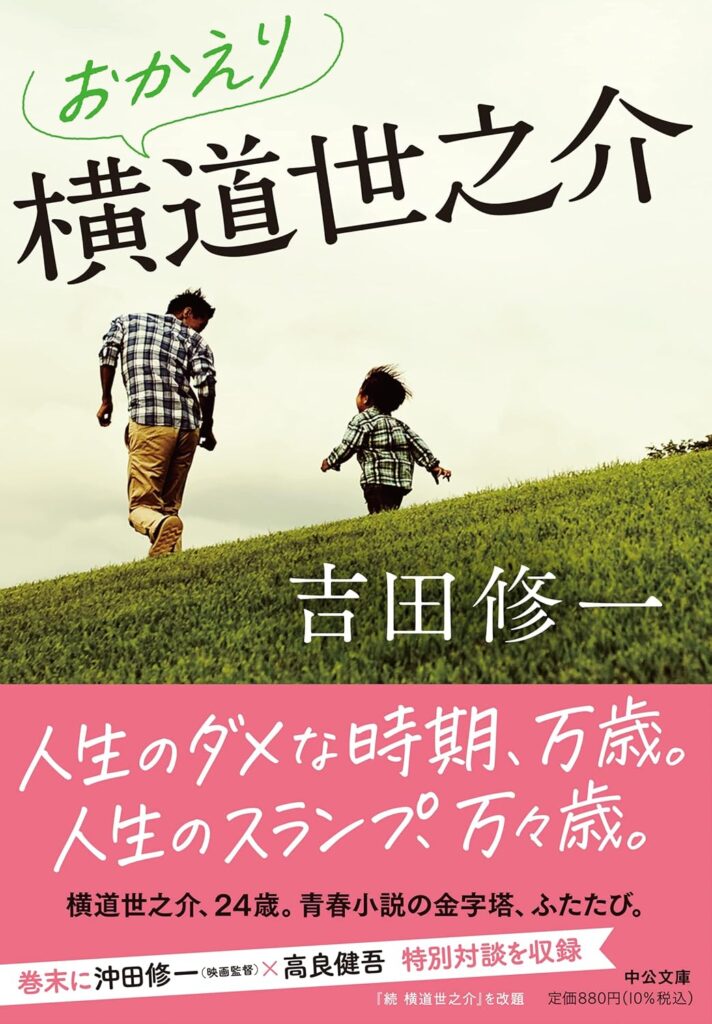
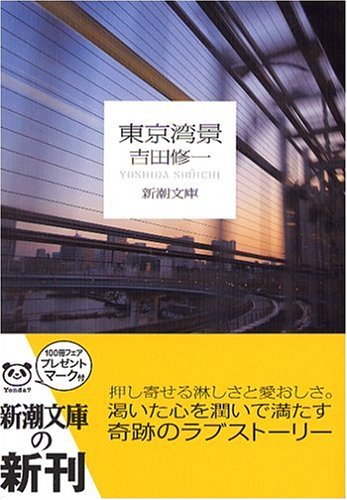
-728x1024.jpg)