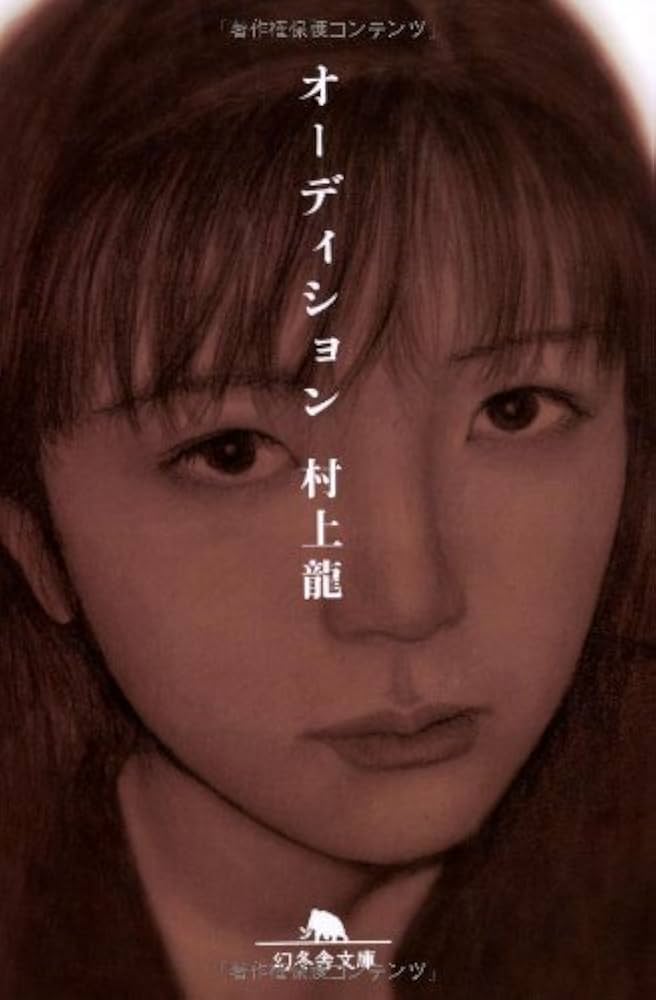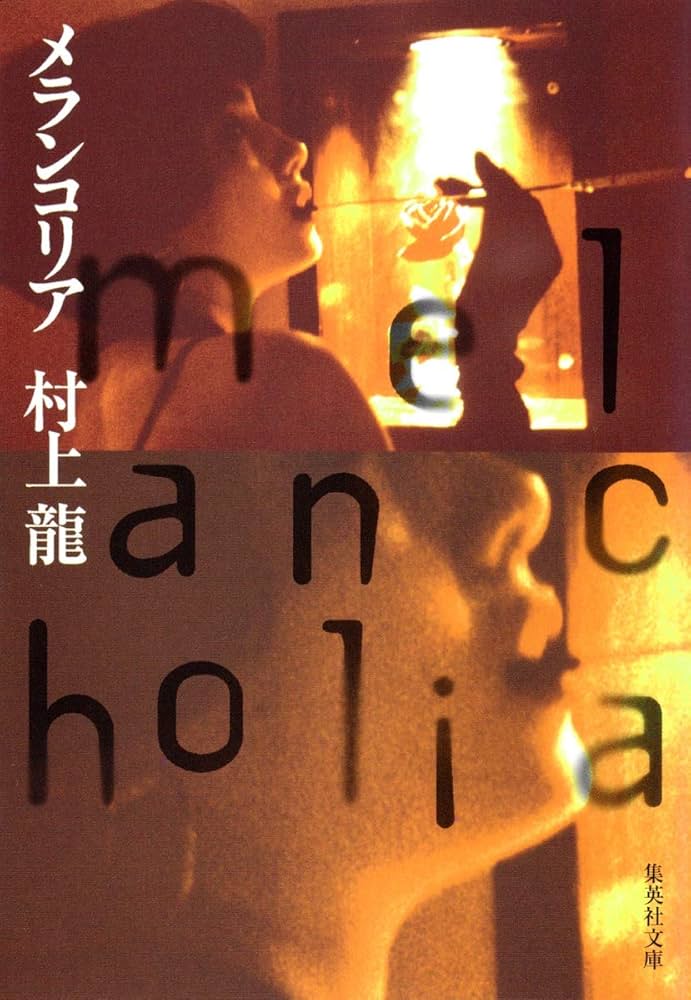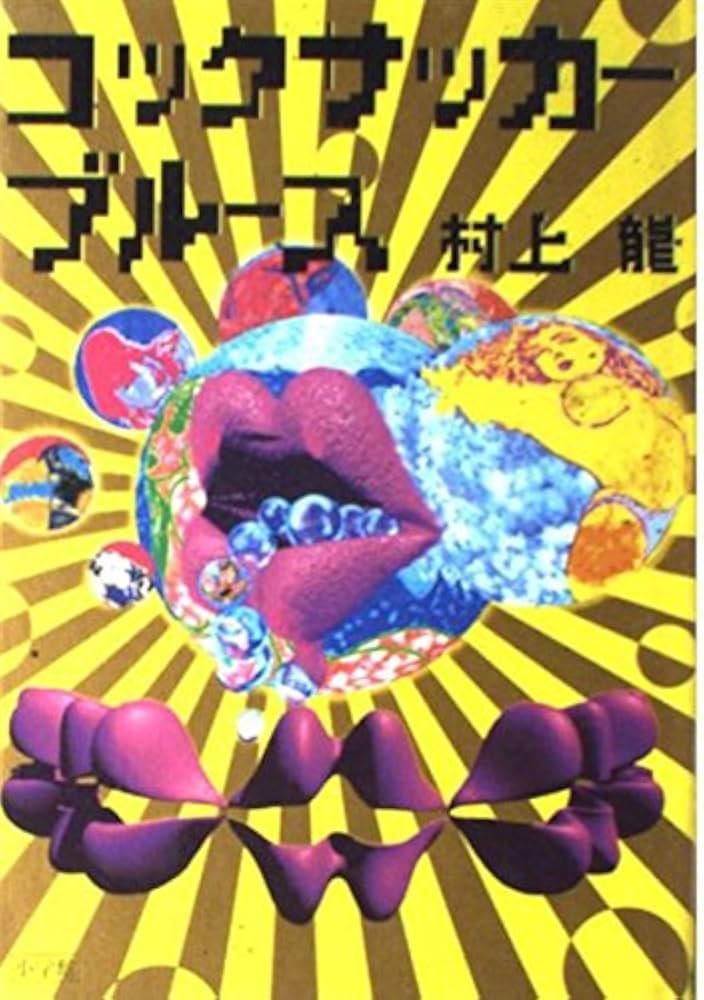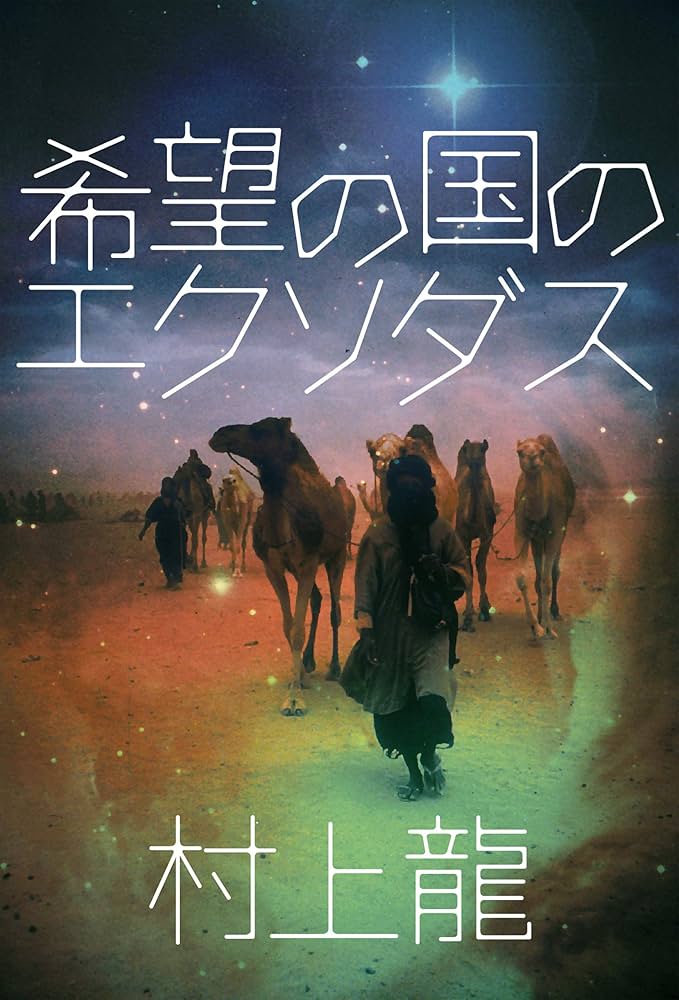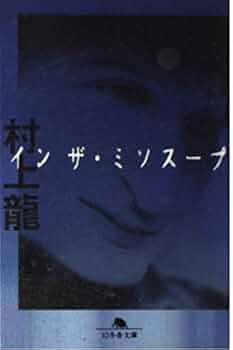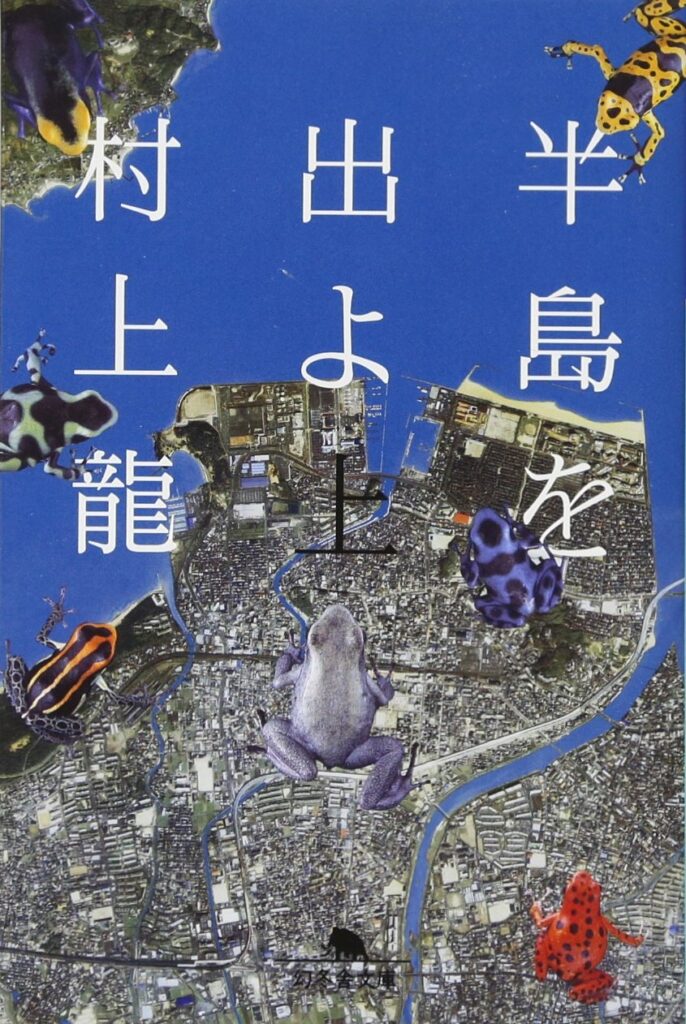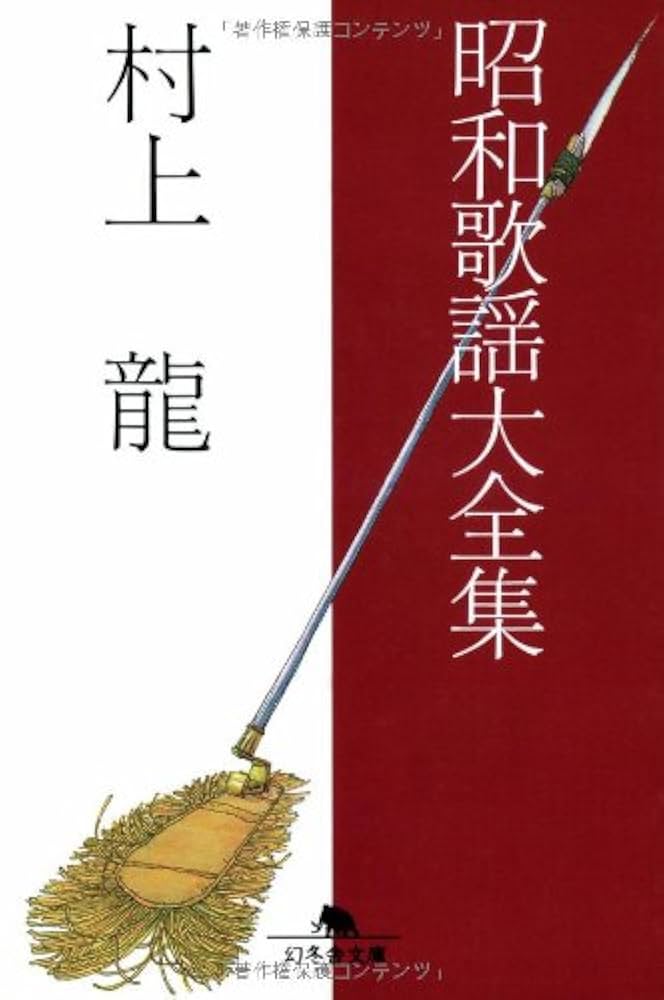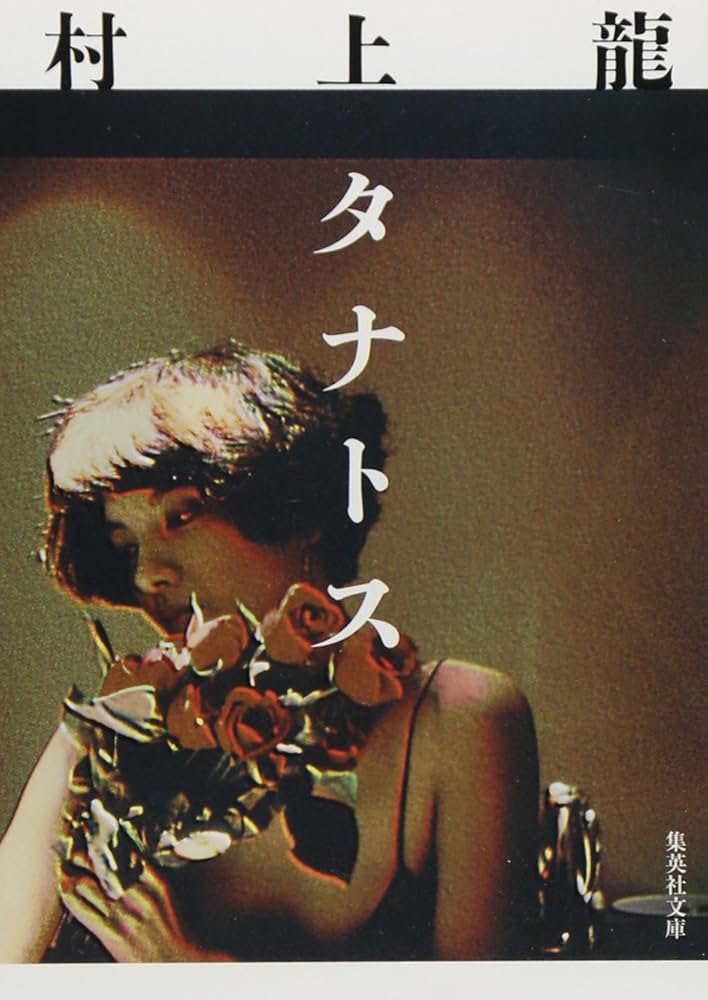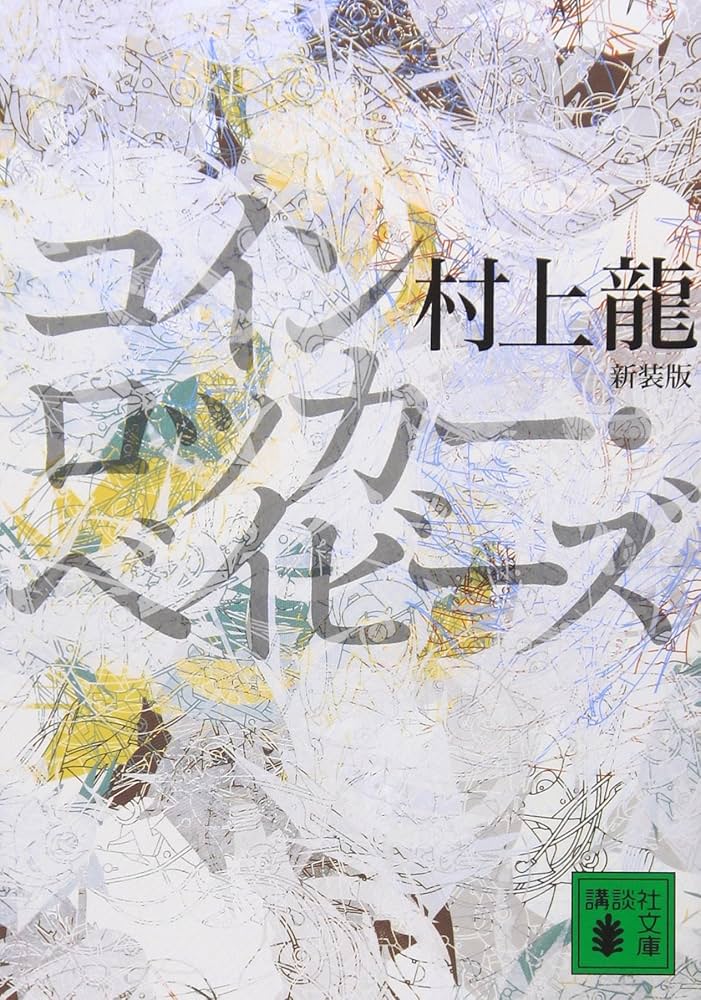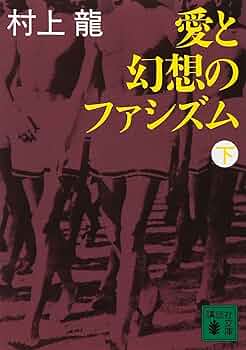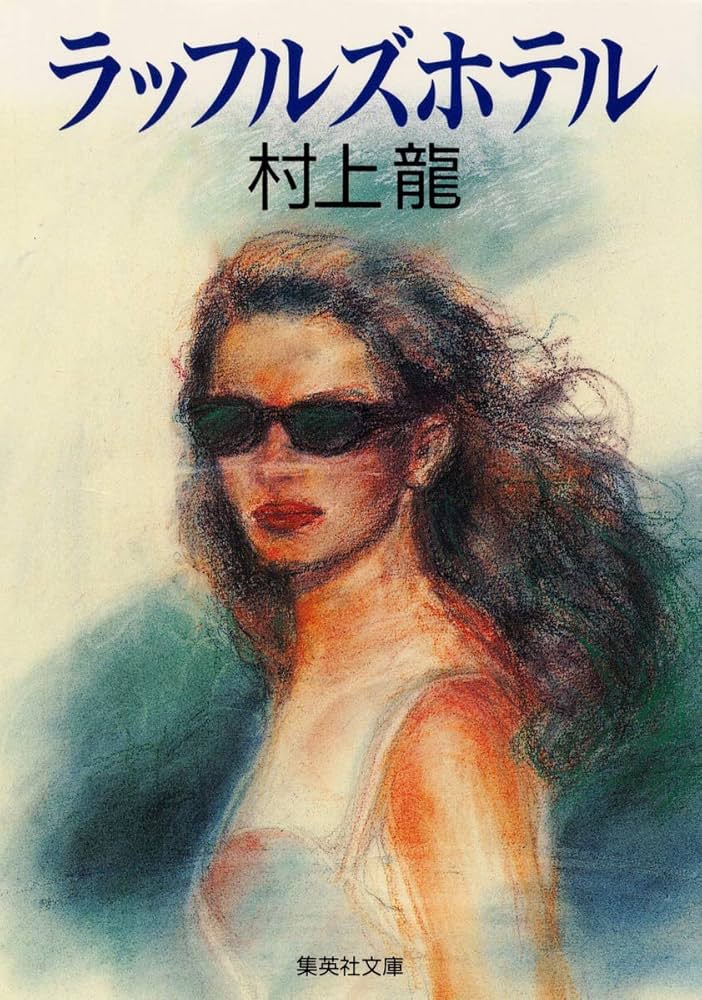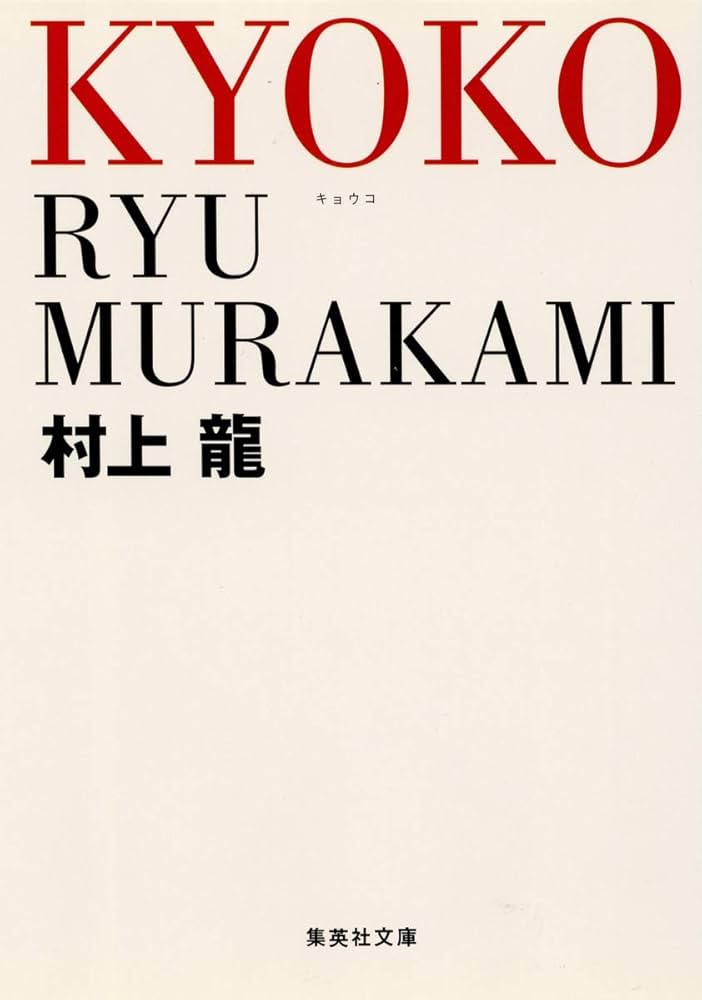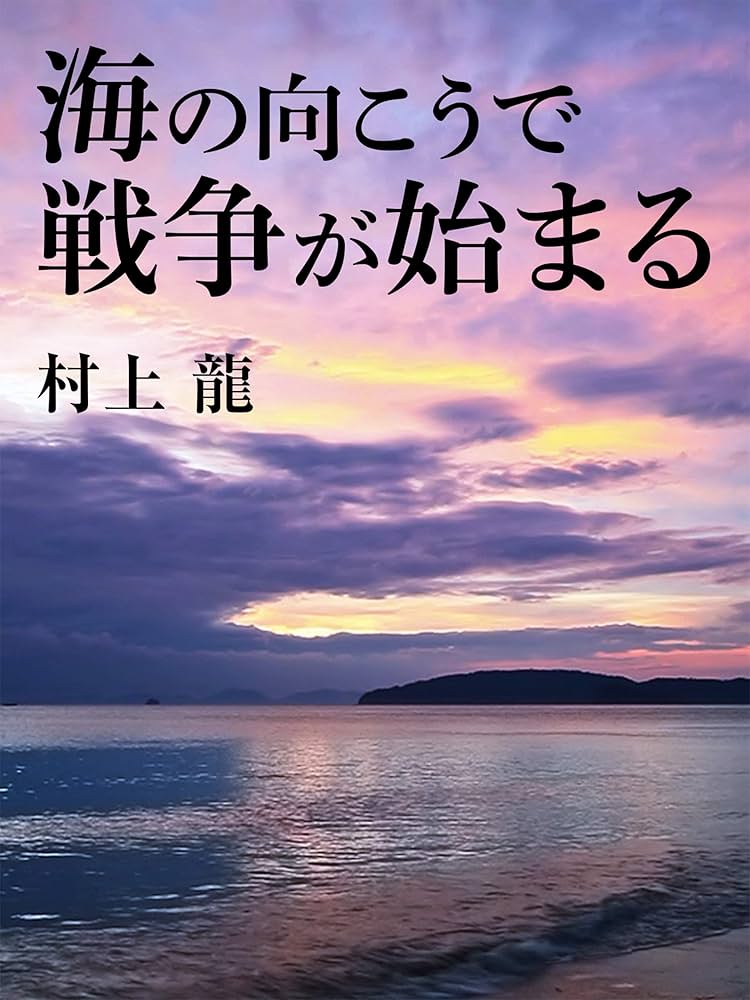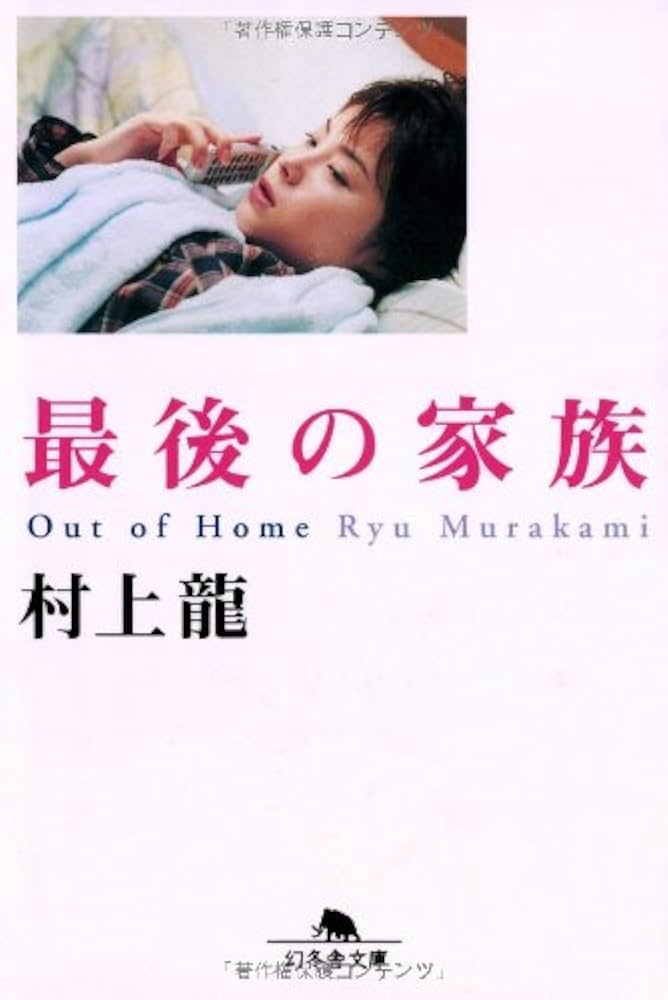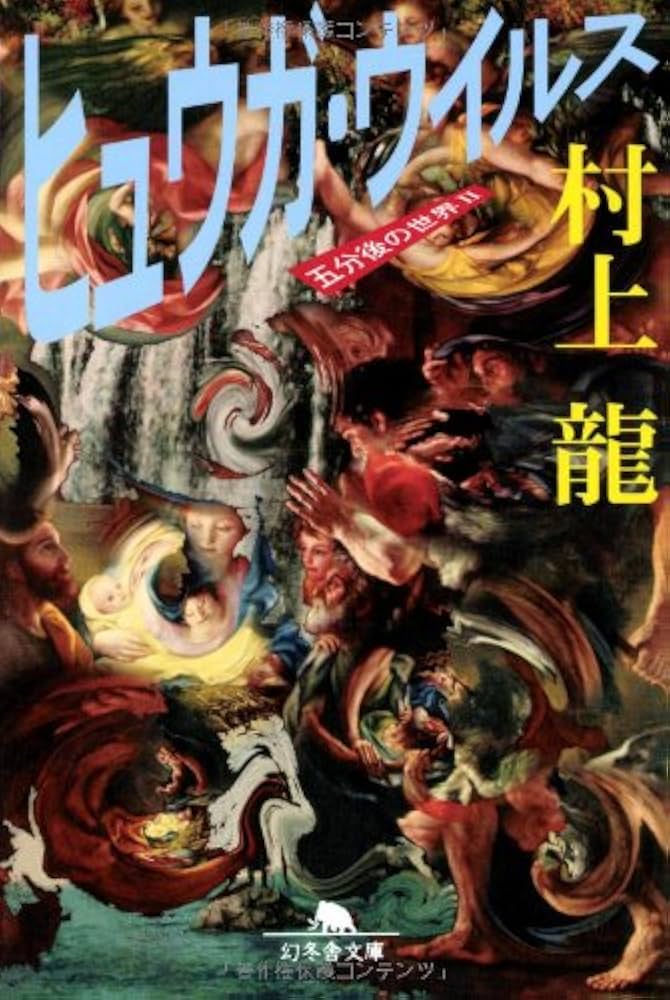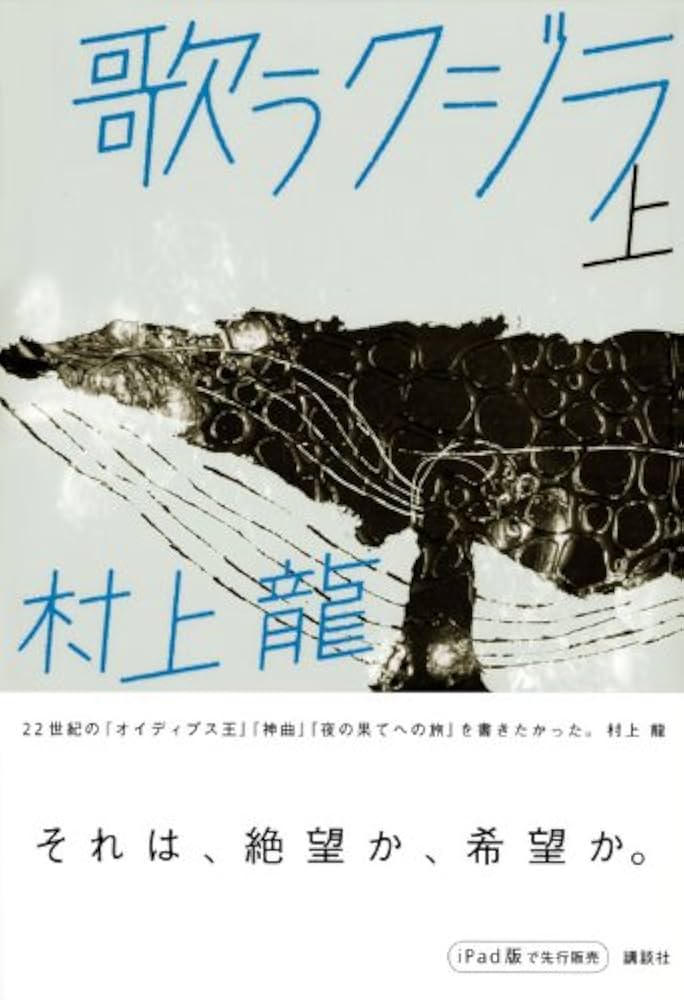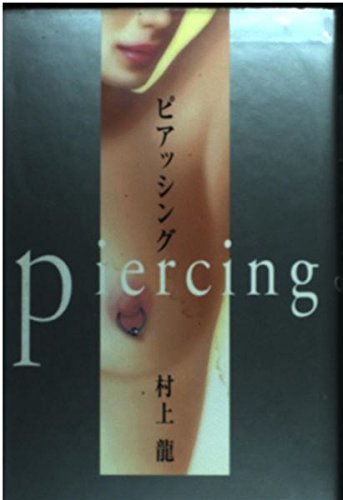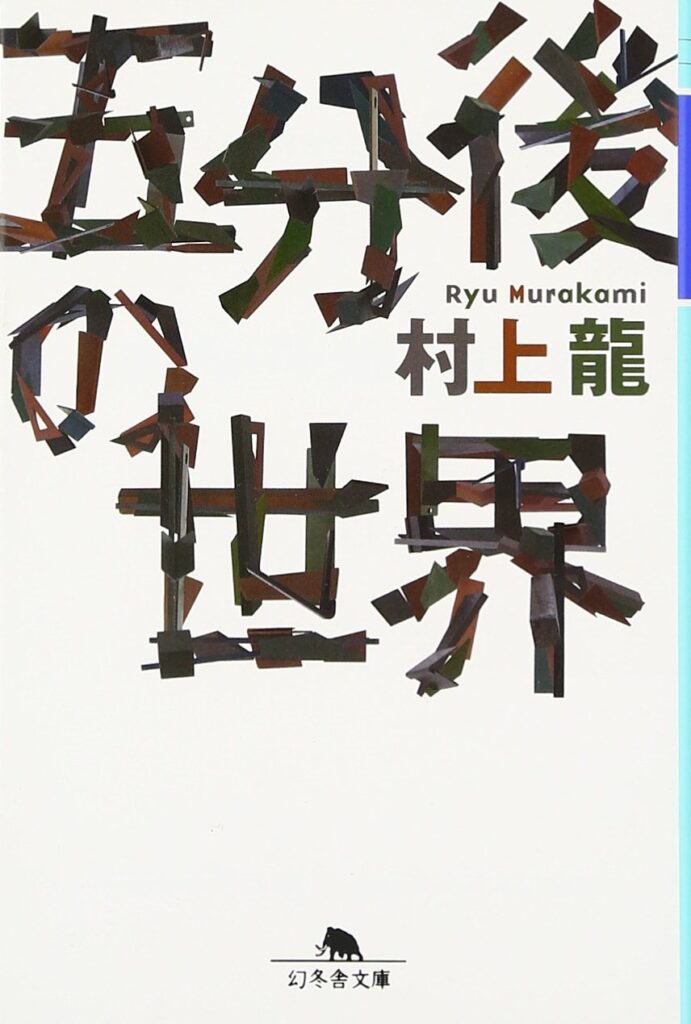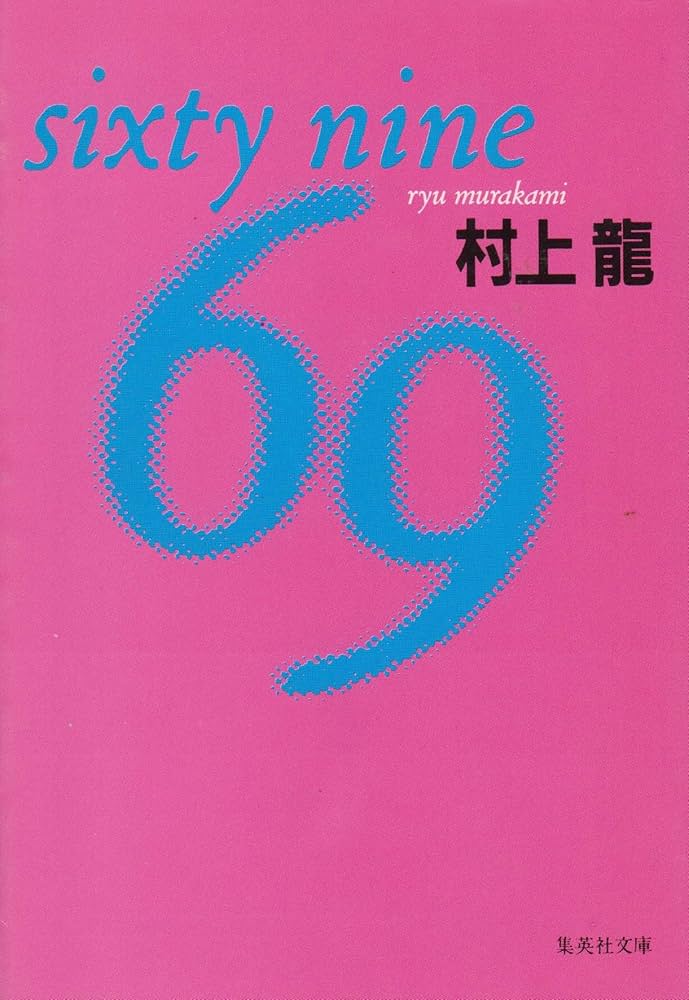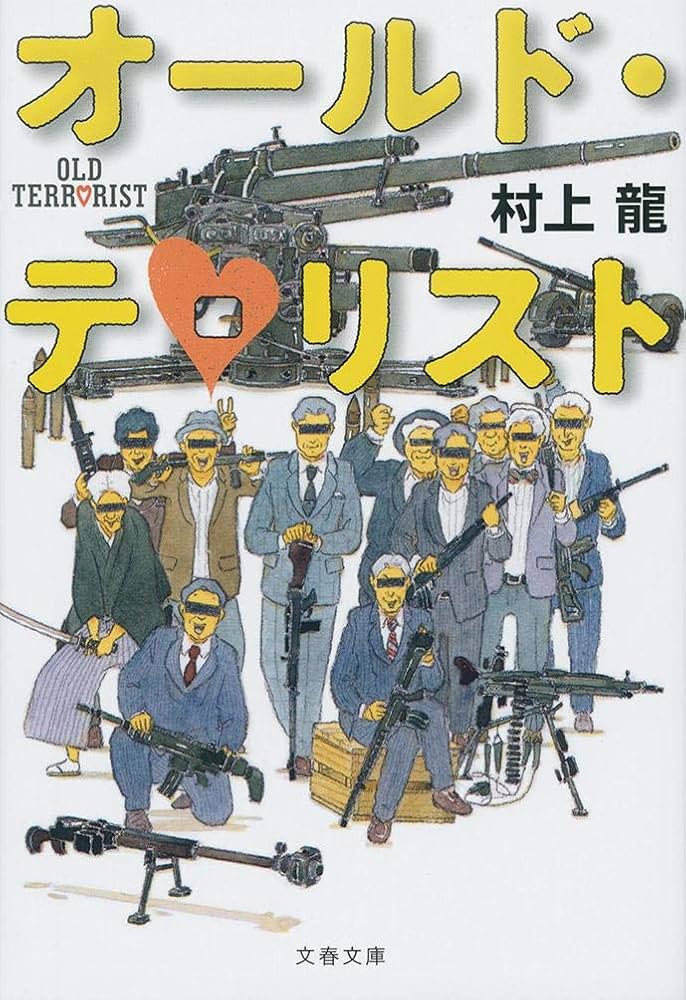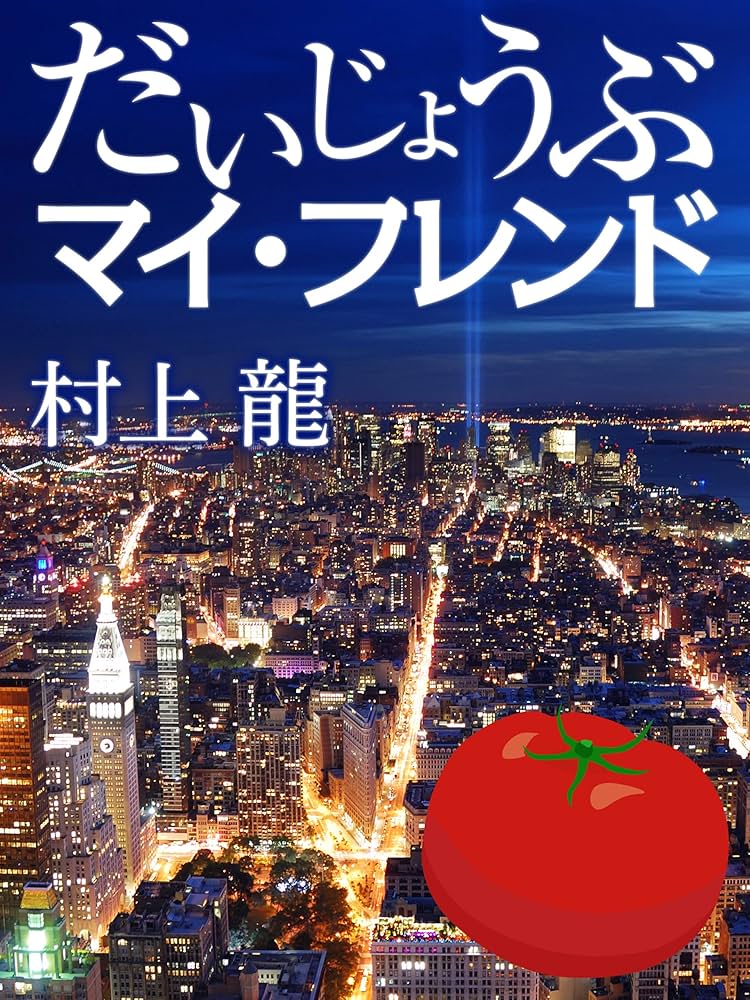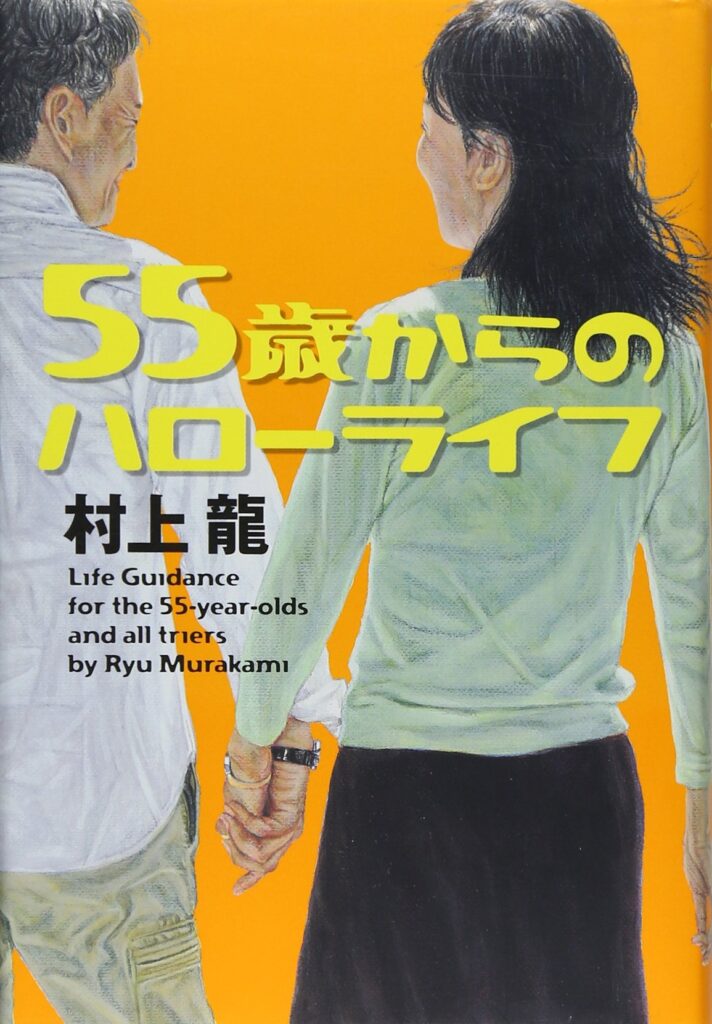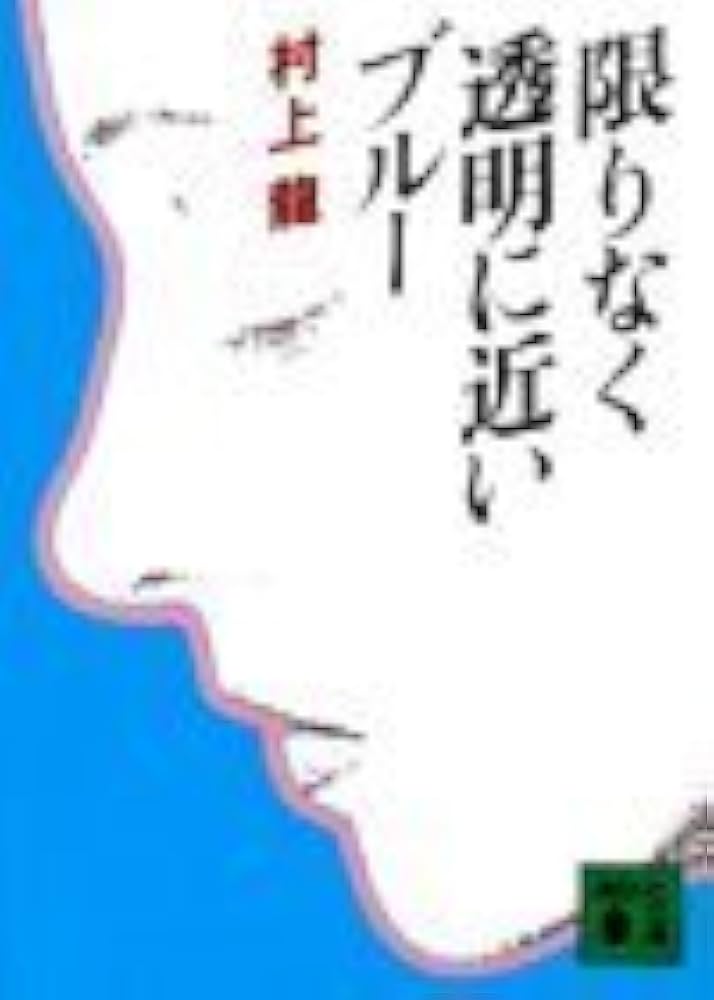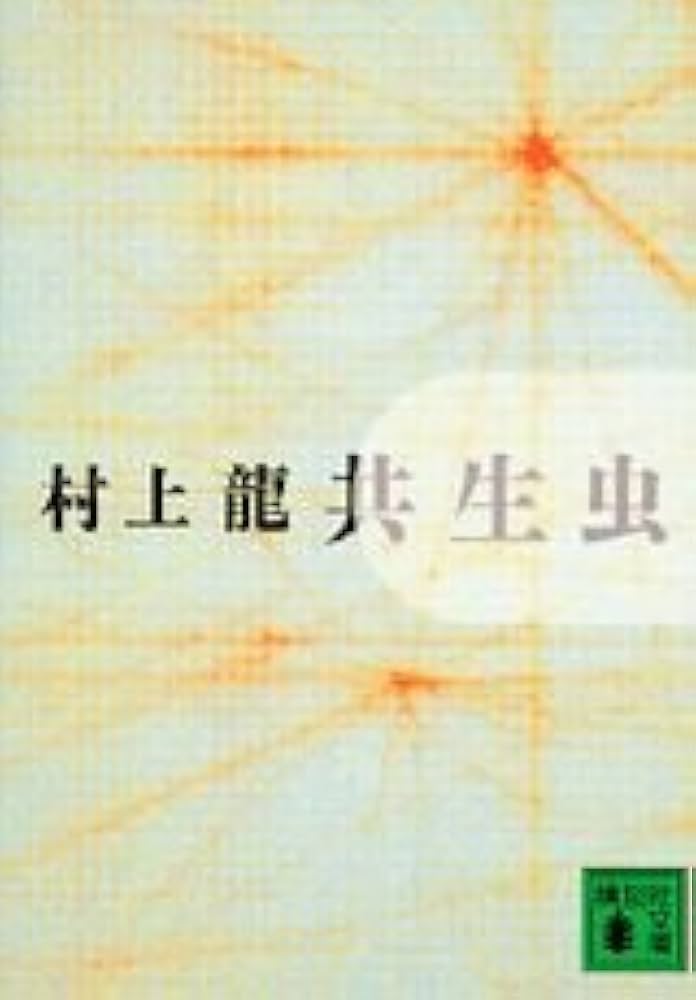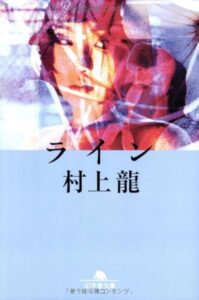 小説「ライン」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「ライン」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、デジタル時代が本格的に幕を開ける直前、1998年の東京が舞台です。ここで描かれる都市は、単なる背景ではありません。それ自体が、人々の孤独や疎外感を増幅させる巨大なネットワークとして機能する、一個の登場人物のような存在なのです。
本作を読み解く上で最も重要なのが、タイトルにもなっている「ライン」という言葉。これは物理的な電話線を指すと同時に、目には見えない人間関係の繋がりそのものを象徴しています。登場人物たちは、この「ライン」に繋がりながらも、真の意味で他者と交わることができず、深刻な断絶の中にいます。
この記事では、まず物語の骨格となるあらすじを紹介し、その後、核心に触れるネタバレを交えながら、この作品がどれほど深く、そして予見的であったかを、私の視点からじっくりと語っていきたいと思います。
「ライン」のあらすじ
物語は、一見、華やかな成功を収めているキャリアウーマンが、恋人を衝動的に殺害するところから始まります。この一つの暴力的な行為が、まるで水面に投げ込まれた石のように波紋を広げ、それまでかろうじて保たれていた日常の均衡を次々と崩壊させていくのです。これが、この壮大な群像劇の幕開けとなります。
次に登場するのは、IQ170という驚異的な知能を持つウェイター。彼はこの事件に偶然関わることになり、その知性で出来事を冷静に分析しようと試みます。しかし、世界の混沌とした非合理性の前では、彼の知性もまた無力であり、意図せずして次の悲劇への橋渡し役となってしまいます。彼の存在は、理性で世界をコントロールしようとする現代人の傲慢さの象徴とも言えるかもしれません。
その連鎖は、男の暴力から逃れられないトラウマを抱えた看護婦、そして性と暴力が倒錯した世界に生きるSM嬢へと繋がっていきます。彼女たちの物語は、暴力が一過性の事件ではなく、ある人々にとっては逃れようのない日常そのものであるという、社会の構造的な病理を浮き彫りにします。この小説のあらすじは、まさに絶望のリレーなのです。
最終的に18人もの登場人物が、この暴力と孤独の「ライン」の上で交錯していきます。彼らは物理的にすれ違い、影響を与え合いますが、互いを真に理解し合う「交信」は決して行われません。ある人物の絶望が、次の人物の絶望の引き金となる。この物語は、その痛ましい連鎖を冷徹な視点で描ききっています。
「ライン」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の核心に触れるネタバレを含んだ、私個人の深い感想をお話しさせていただきます。この『ライン』という作品は、単なる物語の枠を超えて、現代社会が抱える病理そのものを解剖して見せた、驚くべき一冊だと感じています。
まず、この物語の構造自体が、村上龍さんの強いメッセージになっている点に触れなければなりません。本作は、個々のエピソードが連鎖反応を起こしながら進む群像劇です。ある一人の絶望が、ウイルスのように目に見えない「ライン」を通じて他者へと伝染していく。この描き方は、個人の悲劇を「特殊な個人の問題」として片付ける現代社会への、痛烈な批判ではないでしょうか。
登場人物たちは、誰もが何かしらの「病的な性質」を抱えています。キャリアウーマンのプライドとトラウマ、ウェイターの知性ゆえの傲慢と孤立、看護婦の被虐性。これらの「病み」が相互に作用し合うことで、悲劇の連鎖は断ち切られることなく続いていきます。彼らは物理的には「交差」するものの、心は決して「交信」しない。この断絶こそが、物語の根幹をなすテーマなのです。
この構造は、現実社会で起こる悲劇的な事件を思い起こさせます。しばしば、事件は犯人の個人的な問題として処理されがちですが、村上龍さんは、その背景にある社会全体の不調を、この連鎖的な物語を通じて描き出しているように思えます。暴力は個人的なものではなく、システム的なものである、と。プロットそのものが、社会的伝染というテーマを体現しているのです。
そして、この物語の中心にいる最も謎めいた存在が「ユウコ」です。彼女は電話の「ライン」を流れる電気信号そのものを、痛みを伴う感覚として知覚できる特殊な能力を持っています。彼女は、この壊れた世界で起こる悲劇のすべてを見通すことができる、まるで全知の神のような存在です。
しかし、ここからが本作の恐ろしいところなのですが、ユウコはその力を使って何かしようとはしません。ネタバレになりますが、彼女はただひたすら、人々の苦悩が発するノイズを受信するアンテナであり続けるのです。完全な情報にアクセスできても、行動や救済には結びつかない。このユウコの受動性は、情報過多な現代に生きる私たちの無力さを象G徴しているかのようです。
ユウコの苦悩の核心は、「人間は他人によって自分を確認している」という本作の命題にあります。私たちは他者との関わり、つまり摩擦や抵抗を通じて「自分」という輪郭を認識します。しかしユウコは、他者の「データ」にはアクセスできても、その「存在」に触れることができません。結果、彼女は「自分を確認できない」という、究極の実存的孤独に陥っているのです。
一部では、このユウコの闇は作者自身のものだという解釈もあります。すべてを見通しながらも介入しないスタンスは、対象から距離を保ち、冷徹な観察眼を維持する作家の創造プロセスそのもののメタファーかもしれません。村上龍さんの他の作品にも通じる、臨床的な文体や登場人物との距離感は、このユウコのあり方と深く共鳴しているように感じられます。
ユウコという存在は、情報が飽和し、テクノロジーによって感覚が再配線された結果、人間的なレベルで世界と関われなくなった、新しい人間の姿を体現しているのではないでしょうか。彼女はネットワークと融合し、完全な情報を持ちながら、主体性を完全に失っている。これは、グローバルな情報フローを前にした現代人の無力感と、不気味なほど響き合います。
さて、この物語に蔓延する「暴力」について考えてみましょう。作中の暴力は、コミュニケーションの最終手段として描かれているように私には思えます。言葉による意思疎通が完全に壊れてしまった世界で、殴る、傷つけるといった物理的な行為だけが、他者に対して自分の存在を証明する最後の試みとなるのです。「暴力であれ、セックスであれ、…人には他人が必要である」という作中の洞察は、このテーマを鋭く突いています。
同様に、本作におけるセックスもまた、親密さの行為ではありません。それは繋がりを求める、もう一つの失敗した戦略として描かれます。感情の欠落した、取引としての関係。彼らは精神的な断絶を肉体で埋め合わせようとしますが、それは決して叶わない。関係性が必然的に「傷」を生むという考え方が、ここで重要になります。登場人物たちは、その「傷」こそが他者と関わった唯一の証であるかのように、それを求めているようにさえ見えるのです。
この小説が描き出す孤独は、決して一様ではありません。知性ゆえの孤立、トラウマによる孤立、そしてユウコのような実存的な孤立。まるで、現代に生きる孤独の多様な形態をカタログ化したかのようです。公式の作品紹介にもある「プライドとトラウマ」という言葉は、登場人物たちの行動を理解する鍵です。彼らの行動は、脆いプライドを守るための防衛反応か、過去のトラウマの再演なのです。
この物語は、失敗したコミュニケーションの階層を示しているとも言えます。最も高度な「言語」が敗北し、次に「セックス」や「商業的取引」に頼る。それすらも失敗したとき、最後に残るのが最も原始的な「暴力」です。この壊れた世界では、暴力こそが「傷」という否定しようのない物理的な結果を生み出す、最も「誠実」なコミュニケーションなのかもしれない、とまで考えさせられます。これは、この作品の非常にショッキングなネタバレの一つです。
このような重いテーマを支えているのが、村上龍さん独特の文体です。彼は意図的に登場人物の「内面を描写するのを避けている」ように見えます。これにより、私たちは登場人物の思考を直接知ることができず、外部の観察者の立場に置かれます。この手法は、登場人物たちが互いを理解できない状況を、私たち読者にも追体験させる効果があるのです。
彼の文章を読むには「体力が必要だ」と言われることがありますが、まさにその通りです。彼の文章は、読者に生理的な反応を引き起こすように書かれているように感じます。特に危機的な状況で用いられる、息継ぎもさせないような長い文章は、読者の内側に直接、不安と切迫感を植え付けます。これは感情移入ではなく、身体レベルでの没入感です。
混沌とした主題を描きながらも、彼の言葉選びは驚くほど精緻で力強い。「どっちでもいい」というような曖昧な表現を決して使いません。すべての単語が、特定の、そしてしばしば残酷な効果を生み出すために、厳密に選ばれている。この、混沌を精密に描写するという矛盾したスタイルこそが、村上龍文学の凄みなのではないでしょうか。
最後に、この『ライン』という小説が持つ、現代的な重要性について触れておきたいと思います。この作品は1998年に書かれましたが、まるで21世紀の私たちの社会を予言していたかのようです。見えない「ライン」の上で孤独な個人が暴走し、その影響が連鎖していく構図は、匿名のSNS空間で過激な思想が伝播していく現代の状況と、不気味なほど重なります。
本作の根源的なテーマは「孤独」です。テクノロジーの形は変わっても、本物の繋がりを求める人間の根源的な欲求と、それが満たされないときに生まれる孤独は、決して変わらない。インターネットは私たちを孤独から解放してくれたのでしょうか。この小説は、その問いに明確な「ノー」を突きつけます。接続手段が増えることが、繋がりの質の向上を意味しないという厳しい現実を、私たちは知っています。
『ライン』が今なお強烈な力を持つのは、それが希薄なコミュニケーションが支配する世界で、何か「リアル」なものを求める人間の、痛ましいほどの衝動を一切の妥協なく描き切っているからでしょう。その「リアル」なものとは、たとえそれが「傷」であり、暴力の瞬間であったとしても、です。『ライン』は、私たちが抱える繋がりへの渇望の暗い底を直視させる、必読の書であり続けます。
まとめ
村上龍さんの『ライン』は、1998年の東京を舞台に、18人の孤独な魂が織りなす断絶と暴力の連鎖を描いた、壮絶な物語です。物語のあらすじは、一人の女性の殺人事件をきっかけに、ドミノ倒しのように悲劇が広がっていくというものです。
本作は、単なる群像劇ではありません。物理的には繋がっていながら、心は決して交わらない現代人の孤独、そしてコミュニケーションの完全な失敗というテーマを、核心的なネタバレを含む展開の中で冷徹に描き出しています。特に、すべてを見通す力を持つ「ユウコ」の存在は、情報過多社会の絶望を象徴しています。
この感想で述べたように、本作はインターネット以前の時代に書かれたにもかかわらず、SNSが普及した現代の社会問題を驚くほど正確に予見していました。暴力やセックスが、歪んだコミュニケーションの手段として描かれる様は、読む者に強烈な衝撃と問いを投げかけます。
『ライン』は、テクノロジーがどれだけ進化しても、人間の根源的な孤独は消えないという、冷厳な真実を突きつける傑作です。その読書体験は決して快適なものではありませんが、現代を生きる私たちにとって、避けては通れない重要な示唆に満ちています。