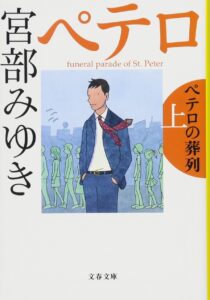 小説「ペテロの葬列」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品は数多く読んでいますが、この「ペテロの葬列」は杉村三郎シリーズの中でも、特に読後に重たいものが残る、深く考えさせられる一冊だと感じています。単なるミステリーという枠には収まらない、人間の心の闇や社会の歪みに鋭く切り込んだ物語です。
小説「ペテロの葬列」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品は数多く読んでいますが、この「ペテロの葬列」は杉村三郎シリーズの中でも、特に読後に重たいものが残る、深く考えさせられる一冊だと感じています。単なるミステリーという枠には収まらない、人間の心の闇や社会の歪みに鋭く切り込んだ物語です。
物語は、平凡なサラリーマンである杉村三郎が、ある日突然バスジャック事件に巻き込まれるところから始まります。この非日常的な事件をきっかけに、杉村の日常は静かに、しかし確実に変容していくことになります。事件そのものの解決だけでなく、事件に関わった人々の人生、そして杉村自身の夫婦関係にも大きな波紋が広がっていくのです。
この記事では、そんな「ペテロの葬列」の物語の核心に触れつつ、その詳細な流れと、私がこの作品を読んで何を感じ、考えたのかを、ネタバレを交えながら詳しくお話ししたいと思います。読後感が爽やかとは言えない作品ですが、人間の複雑さや社会のあり方を深く見つめたい方には、ぜひ手に取っていただきたい物語です。どうぞ、最後までお付き合いくださいませ。
小説「ペテロの葬列」のあらすじ
今多コンツェルン会長・今多嘉親の娘婿であり、グループ広報室に勤める杉村三郎は、ある日、拳銃を持った老人によるバスジャック事件に遭遇します。「むか〜し、悪いことをした」と語る犯人の老人は、しかし、具体的な要求をするわけでもなく、乗客たちに奇妙な慰謝料を配り始めます。緊張と混乱の中、事件は唐突な幕切れを迎えますが、杉村の心には多くの疑問が残りました。なぜ老人はバスジャックなど起こしたのか。なぜ慰謝料を配ったのか。
事件後、杉村は同じバスに乗り合わせていた人々――元美容部員の柴野和子、実家の金属加工工場を手伝う青年・坂本啓、元エステ経営者の田中雄一郎、そして派遣社員の迫田美和子らと関わりを持つようになります。彼らもまた、事件によって心に傷を負い、あるいは日常に変化が生じていました。特に、老人が配った慰謝料の出所を探る中で、杉村は「日商フロンティア協会」という謎めいた団体と、その代表である御厨(みくりや)という人物に行き当たります。
調査を進める杉村は、バスジャック犯の老人が過去に関わったとされる巨大な詐欺事件の存在を知ります。それは、多くの人々を不幸に陥れた悪質なものでした。そして、バスジャック事件や慰謝料は、その詐欺事件と深く結びついていたことが明らかになっていきます。さらに、バスに同乗していた坂本や田中も、単なる被害者ではなく、この詐欺事件に何らかの形で関わっていた過去を持つことが示唆されるのです。
事件の真相に迫るにつれ、杉村は人間の持つ悪意や欲望、そして弱さに直面します。登場人物たちが抱える秘密や葛藤が次々と明らかになり、物語は複雑な様相を呈していきます。バスジャック事件は単なる序章に過ぎず、その背後には根深い人間の業と、巧妙に仕組まれた復讐劇が隠されていたのでした。杉村自身も、この事件を通して、これまで築き上げてきた自身の家族関係、特に妻・菜穂子との関係性を見つめ直さざるを得なくなります。
小説「ペテロの葬列」の長文感想(ネタバレあり)
宮部みゆきさんの「ペテロの葬列」を読み終えたとき、ずしりと重い感情が胸の中に沈殿しました。これは、単なる事件解決のカタルシスを味わう物語ではありません。むしろ、事件を通して浮き彫りになる人間のエゴイズム、価値観の衝突、そして関係性の脆さといった、目を背けたくなるような現実を突きつけられる作品です。読後感が良いとはお世辞にも言えませんが、それ故に強く心に残り、様々なことを考えさせられました。まさに、読者の心を映す鏡のような作品と言えるかもしれません。読む人によって、どの登場人物に感情移入し、誰の行動を許せないと感じるかが、大きく分かれるのではないでしょうか。
物語の中心人物である杉村三郎は、一見すると温厚で思慮深い「いいひと」です。彼は、バスジャックという異常事態に巻き込まれても、冷静さを失わず、他者の立場や感情を理解しようと努めます。しかし、読み進めるうちに、その「いいひと」ぶりが、かえって事態を複雑にし、周囲の人々、特に妻である菜穂子を深く傷つけていく側面が見えてきます。
杉村は、相手を否定せず、受け入れようとする姿勢を持っています。これは美徳のようにも思えますが、一方で、彼自身の主体性の希薄さの表れとも取れます。困難な状況に陥ったとき、彼は相手に負担をかけるよりも、自分が耐えることを選びがちです。これは、自己犠牲的な優しさとも言えますが、同時に、他者と対等な関係を築く上での障壁にもなり得ます。特に、妻である菜穂子との関係において、この傾向は顕著です。
杉村は、義父である今多嘉親という強大な存在に、知らず知らずのうちに強く影響されています。彼は菜穂子を「守るべき存在」と捉え、困難から遠ざけようとしますが、それは対等なパートナーシップとは言えません。問題が起きたとき、杉村が真に頼り、意見を求めるのは、妻ではなく義父なのです。例えば、現在の職場を辞めようと決意した際、彼は菜穂子に相談することなく、まず義父に辞表を提出しようとします。これは、結婚の条件の一つであった就職という約束事を、一方的に反故にしようとする行為であり、菜穂子の立場からすれば、深い不安と不信感を抱かせるものでしょう。杉村は、菜穂子を庇護すべき「娘」のように扱い、夫として対等に向き合うことを避けていたのかもしれません。タイトルにある「ペテロ」は、キリストに従いながらも、最後には彼を裏切ってしまう弟子を指しますが、杉村もまた、偉大な義父という存在に心酔し、依存するあまり、最も大切なはずの妻との関係を見失ってしまった「ペテロ」だったのではないでしょうか。彼が離婚を受け入れたのも、自身の非を認めたからというよりは、「妻が望むなら」と自己犠牲的に受け入れた結果のように感じられます。
一方、妻の菜穂子は、多くの読者から厳しい目が向けられるキャラクターだと思います。夫が大変な目に遭っている最中に不倫に走り、それをある種開き直ったかのように告白する姿は、確かに身勝手に映ります。しかし、彼女の背景を考えると、一方的に断罪するのも難しいと感じます。菜穂子は、財界の大物の私生児として生まれ、特殊な環境で育ちました。彼女自身が、ある意味で「不倫」の産物なのです。そのため、一般的な倫理観よりも、個人の感情や愛情を優先する価値観を持っている可能性があります。彼女にとって、不倫は許されざる罪というよりは、満たされない愛情を埋めるための手段であったのかもしれません。
もちろん、彼女の行動が杉村を深く傷つけたことは事実です。しかし、彼女なりに罪悪感を感じ、謝罪しようとしている描写もあります。ただ、その価値観のズレゆえに、その謝罪が杉村や読者には届きにくいのです。彼女は、経済的な不自由を知らずに育ちました。杉村との結婚生活においても、庶民的な感覚を理解することは難しかったでしょう。杉村が「守ろう」とすればするほど、彼女は自分が対等なパートナーとして扱われていないと感じ、孤独感を深めていったのかもしれません。橋本との関係は、経済的な見返りを求めない(ように見える)相手との、ある種の逃避だったとも考えられます。それは、かつて杉村と出会った頃のような、純粋な関係への渇望だったのかもしれません。彼女の世間知らずさや身勝手さは擁護できませんが、その背景にある孤独や、杉村との関係性の歪みが、彼女をそのような行動に駆り立てた一因であることも否定できないように思います。
そして、私がこの物語で最も強い嫌悪感を抱いたのは、田中雄一郎です。彼は、バスジャックの被害者でありながら、後に事件の真相に関わる重要な人物として再登場します。彼の言動の端々に見える自己中心性、他者への配慮の欠如、そして尊大な態度は、読んでいて非常に不快でした。彼は、自分の都合やプライドを何よりも優先し、他人が自分にかける迷惑は許さず、自分が他人にかける迷惑は当然のことのように考えます。他人の呼び方もぞんざいで、相手への敬意が全く感じられません。「世界の中心は自分」という価値観が、彼の行動原理の根底にあるように見えます。バスジャック犯の老人や、詐欺事件の首謀者である御厨も許しがたい悪ですが、田中のように、日常の中に潜む身近な悪意、他者を尊重しない態度は、また別の種類の醜悪さを感じさせます。
この「ペテロの葬列」という物語は、登場人物の誰一人として、単純な善人や悪人として描かれていません。誰もが自分なりの正義や価値観に基づいて行動し、その結果、意図せずとも誰かを傷つけ、あるいは罪を犯してしまいます。そして、驚くほど多くの人物が、他者の罪には敏感でありながら、自身の過ちには鈍感です。作者は、特定の人物を断罪することなく、ただ淡々と彼らの行動と思考を描写していきます。だからこそ、読者は登場人物たちの誰に共感し、誰に反発するのかを、自分自身の価値観に照らし合わせて考えざるを得ません。
バスジャック事件を発端とする一連の出来事は、詐欺という大きな犯罪に繋がっていきますが、物語が本当に描いているのは、その事件の顛末だけではありません。むしろ、事件に関わる中で露呈する、人々の心の弱さ、身勝手さ、そして関係性の崩壊です。杉村と菜穂子の夫婦関係の破綻は、その象徴的な出来事と言えるでしょう。平凡だけれども幸せだと思っていた日常が、いかに脆い基盤の上に成り立っていたのかを、読者は杉村と共に痛感することになります。
宮部みゆきさんの筆致は、登場人物たちの内面を深く、そして丁寧に描き出します。特に、杉村の葛藤や、菜穂子の複雑な心情、あるいは田中や坂本といった人物たちの抱える闇が、リアルに伝わってきます。それは時に、読んでいて苦しくなるほどですが、だからこそ、この物語は強い印象を残すのだと思います。社会の片隅で起こるかもしれない、しかし決して他人事ではない人間のドラマが、ここにはあります。
読後、爽快感や希望といった感情は、正直なところ、あまり残りません。むしろ、人間の持つ業の深さや、救いのなさのようなものを感じてしまうかもしれません。それでも、私はこの「ペテロの葬列」を読んで良かったと思っています。それは、目を背けたくなるような人間の暗部や、複雑な関係性を深く見つめることで、かえって自分自身や社会について考えるきっかけを与えてくれるからです。誰かを簡単に「悪」と断罪することの危うさ、そして、自分自身の中にも潜んでいるかもしれない弱さや身勝手さに、気づかされるのです。
杉村三郎シリーズは、他にも「誰か Somebody」「名もなき毒」と続いていますが、「ペテロの葬列」はその中でも特に、主人公・杉村三郎自身の人生に深く切り込み、彼の人間性を揺るがす大きな転換点を描いた作品として、異彩を放っていると感じます。もし、あなたが単なる謎解きだけでなく、人間の心の深淵を覗き込むような、重厚な物語を求めているのであれば、この作品は間違いなく読む価値のある一冊です。ただし、読後しばらくは、その重たい余韻を引きずることになるかもしれませんが。
まとめ
宮部みゆきさんの小説「ペテロの葬列」は、杉村三郎がバスジャック事件に巻き込まれることから始まる物語です。しかし、単なるミステリーに留まらず、事件を通して明らかになる登場人物たちの過去の罪や秘密、そして現代社会に潜む詐欺事件の闇へと深く切り込んでいきます。読み進めるほどに、人間の持つエゴイズムや弱さ、価値観の衝突といった、重く、考えさせられるテーマが浮かび上がってきます。
この物語の大きな特徴は、読後感が決して爽やかではないことです。登場人物の多くが、自分に正直に行動した結果、誰かを傷つけたり、取り返しのつかない過ちを犯したりします。特に、主人公・杉村と妻・菜穂子の関係性の変化と破綻は、物語の核心の一つであり、読者に夫婦とは、家族とは何かを問いかけます。誰が正しく、誰が間違っているのか、簡単に断罪できない複雑さが、この作品の魅力であり、同時に重さの要因でもあります。
「ペテロの葬列」は、読む人によって受け止め方が大きく異なる作品でしょう。登場人物たちの誰に共感し、誰に嫌悪感を抱くかは、読者自身の価値観を反映するかもしれません。読んですっきりするタイプの物語ではありませんが、人間の複雑さや社会の暗部について深く考えたい方、心にずしりと響くような重厚な読書体験を求めている方には、強くおすすめしたい一冊です。杉村三郎という一人の男の人生を通して、私たちは多くのことを学ぶことができるはずです。































































