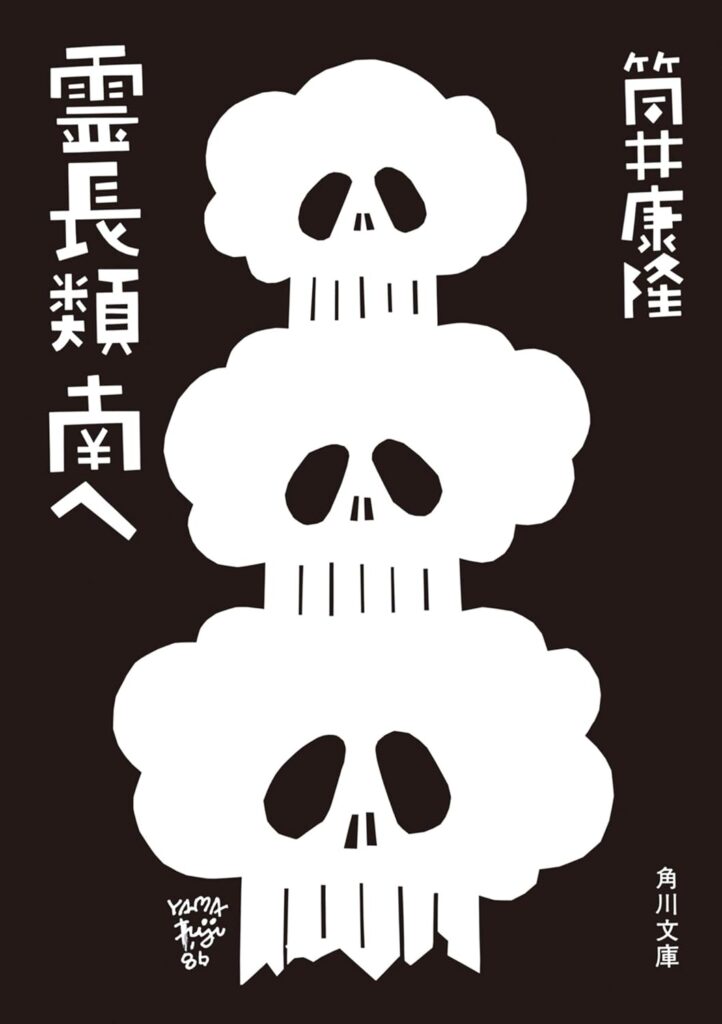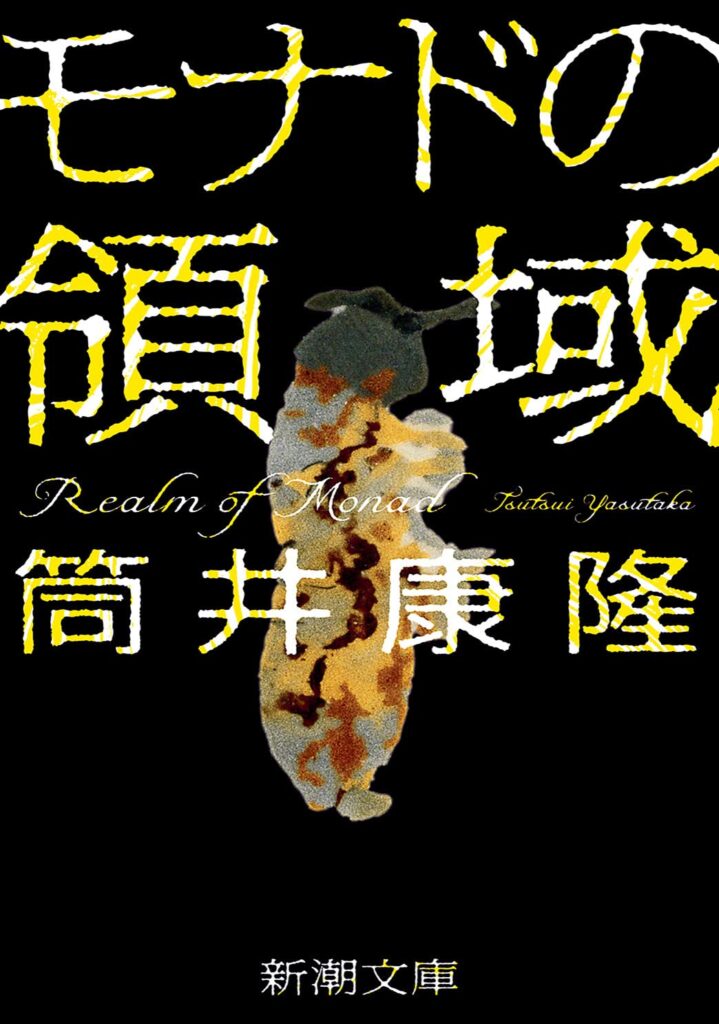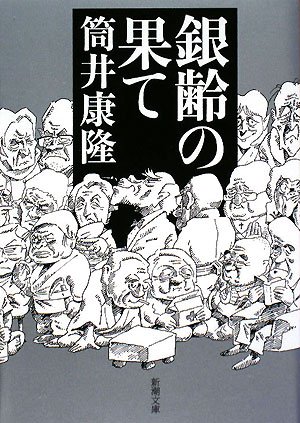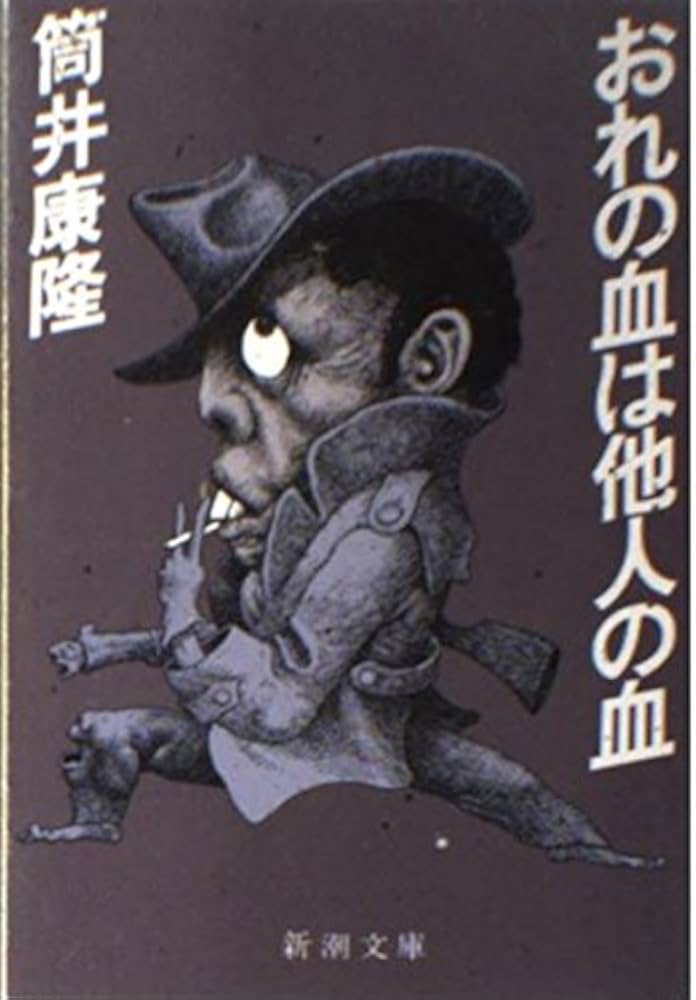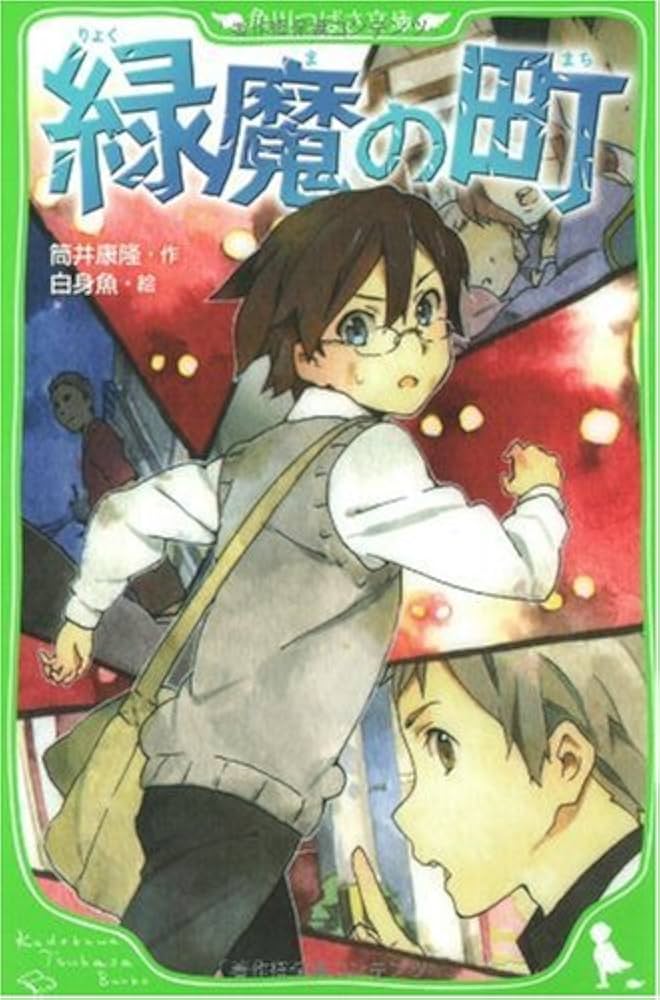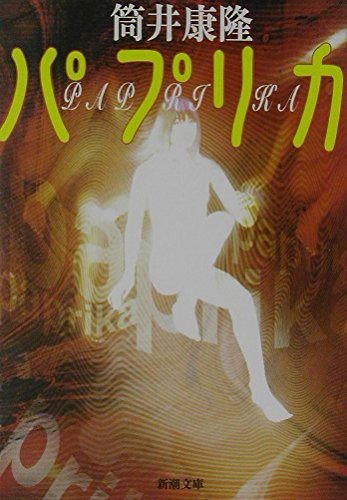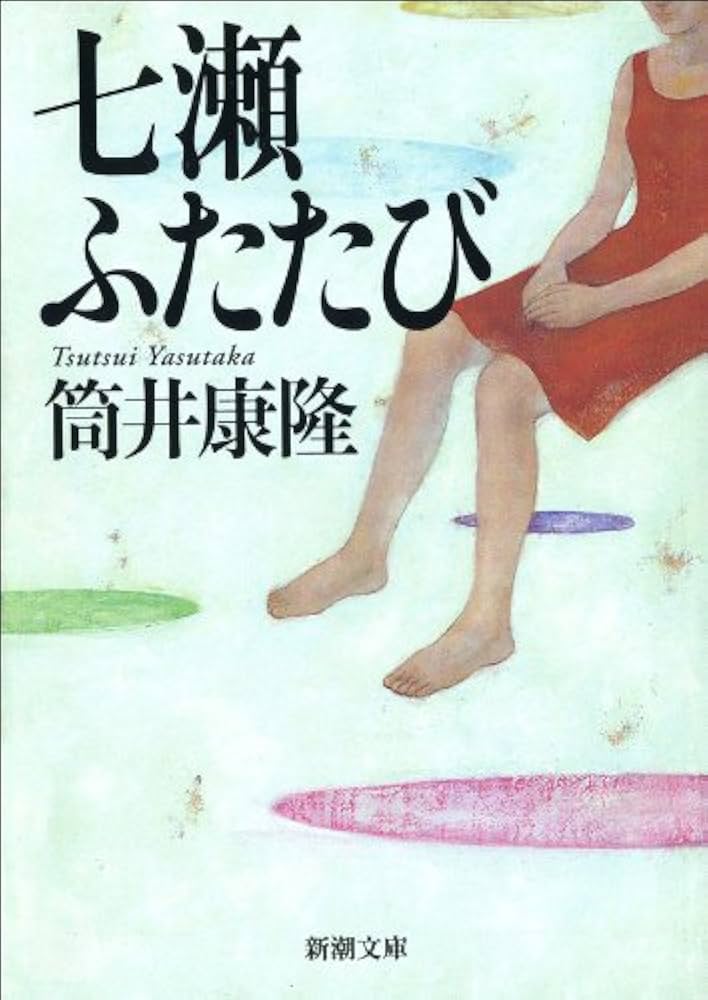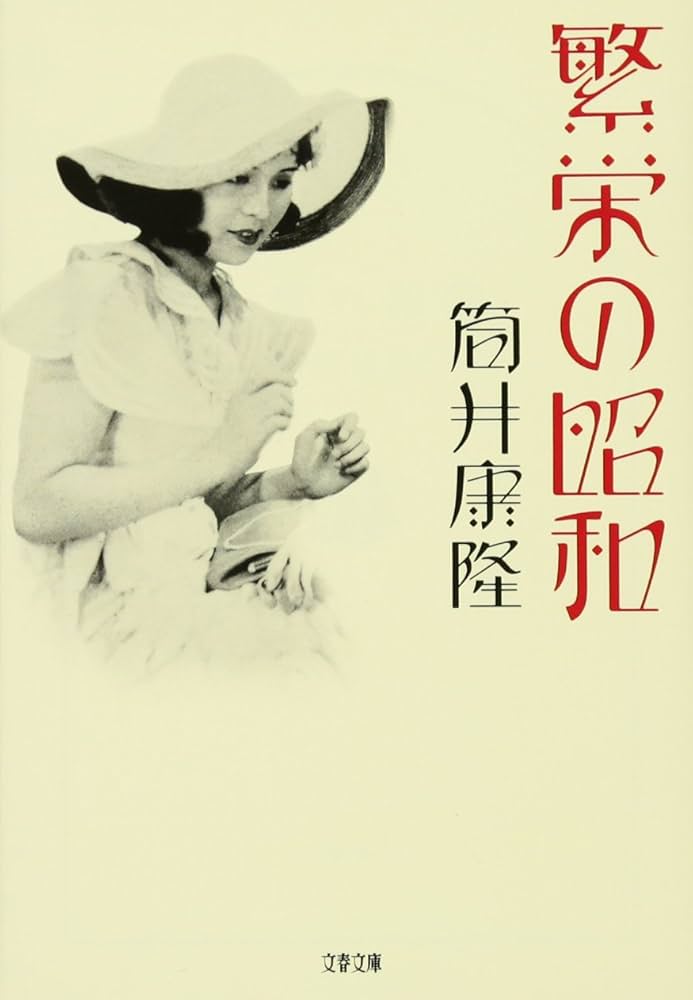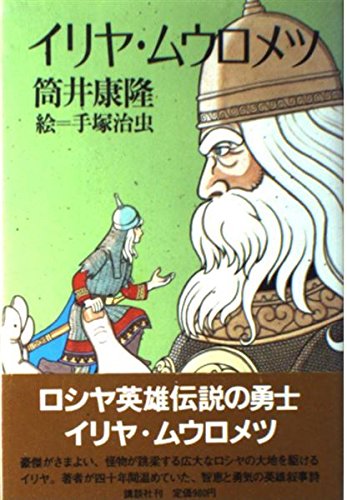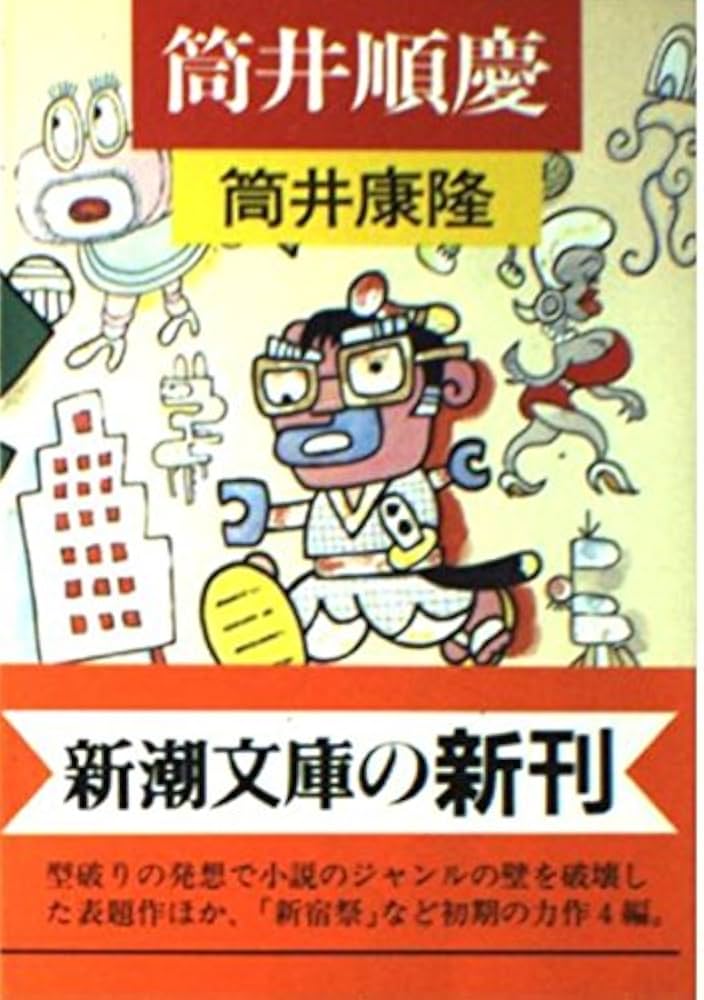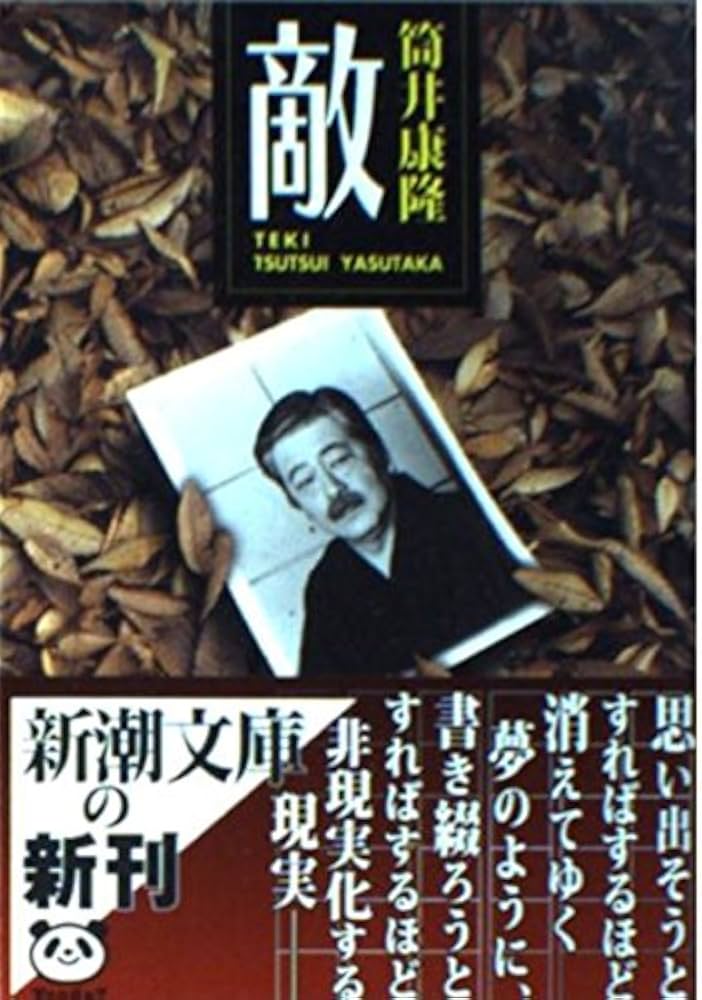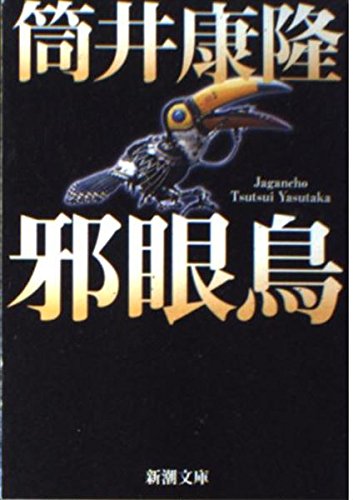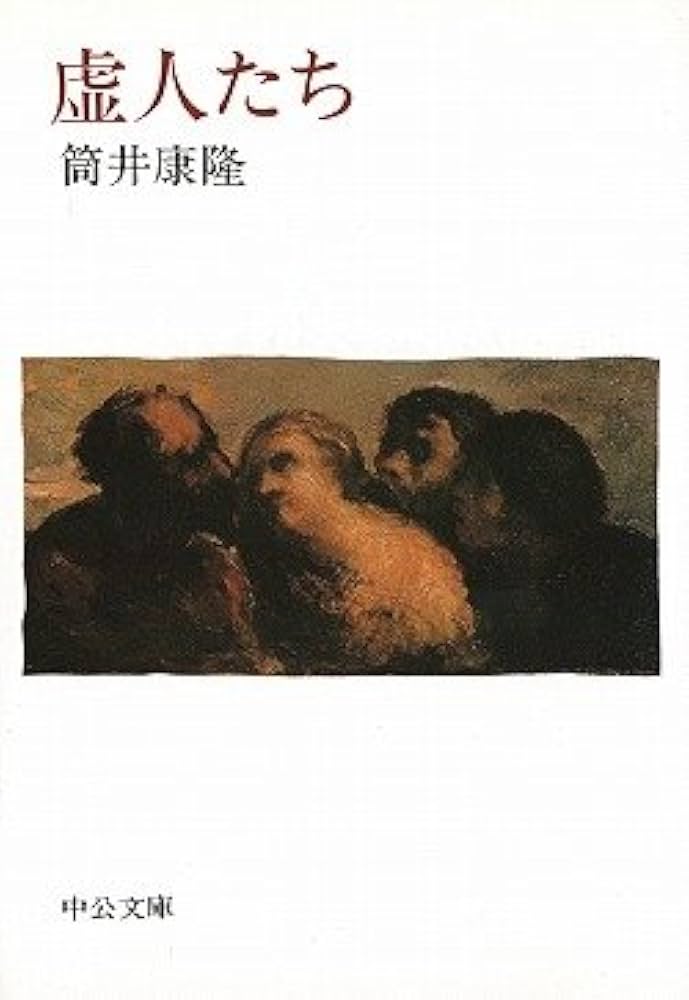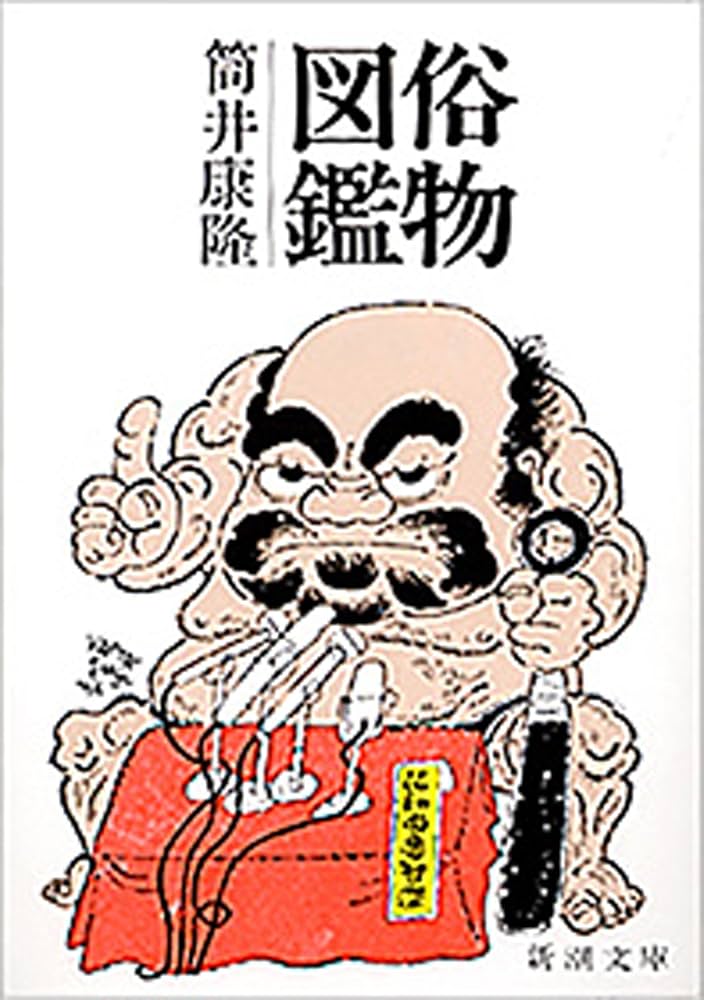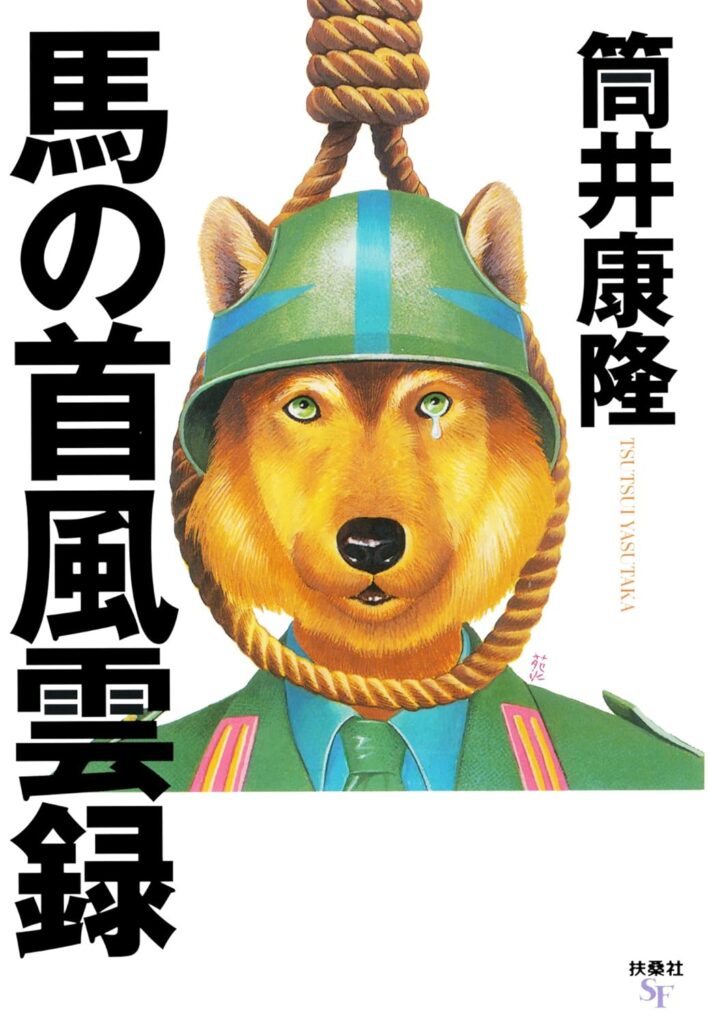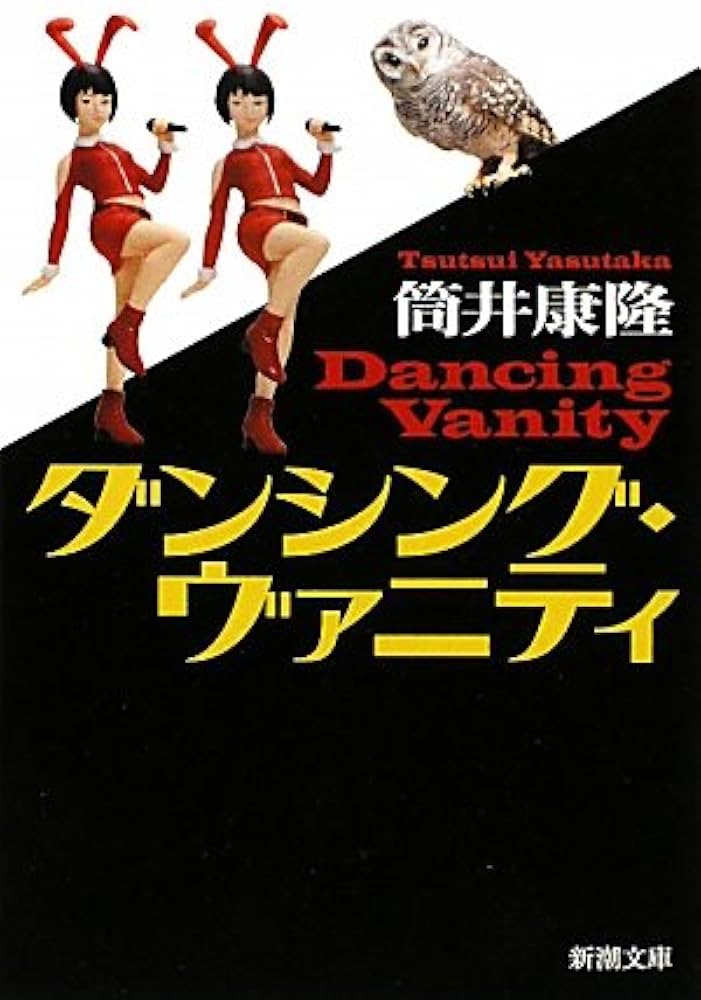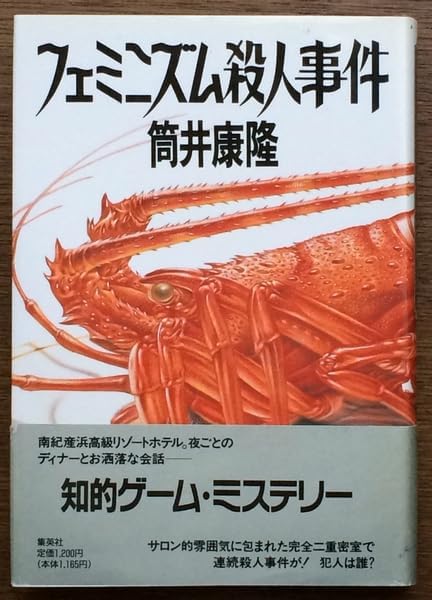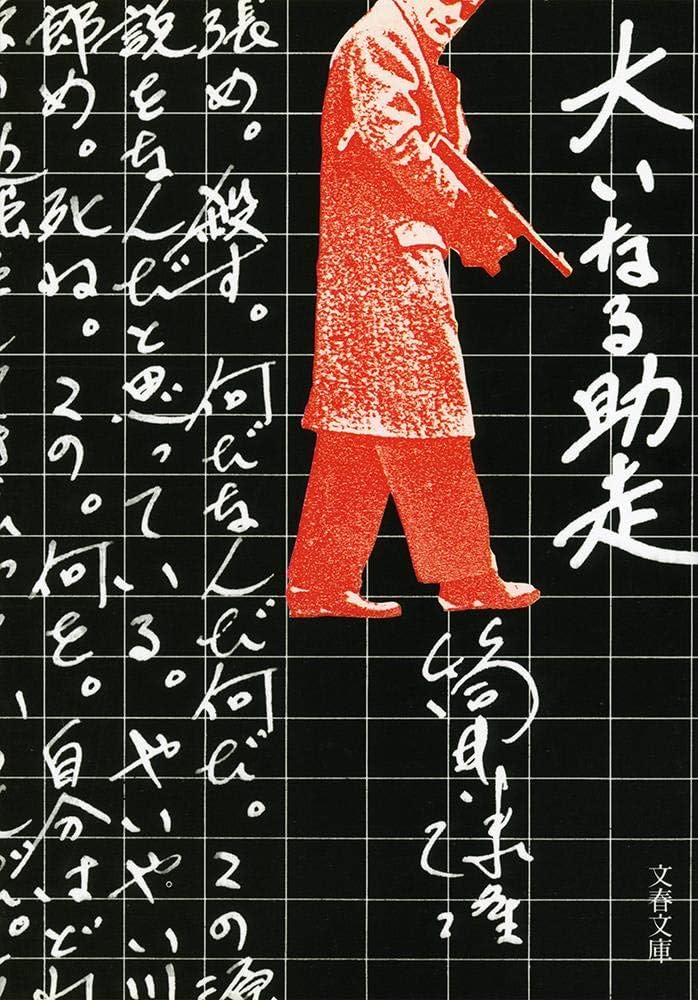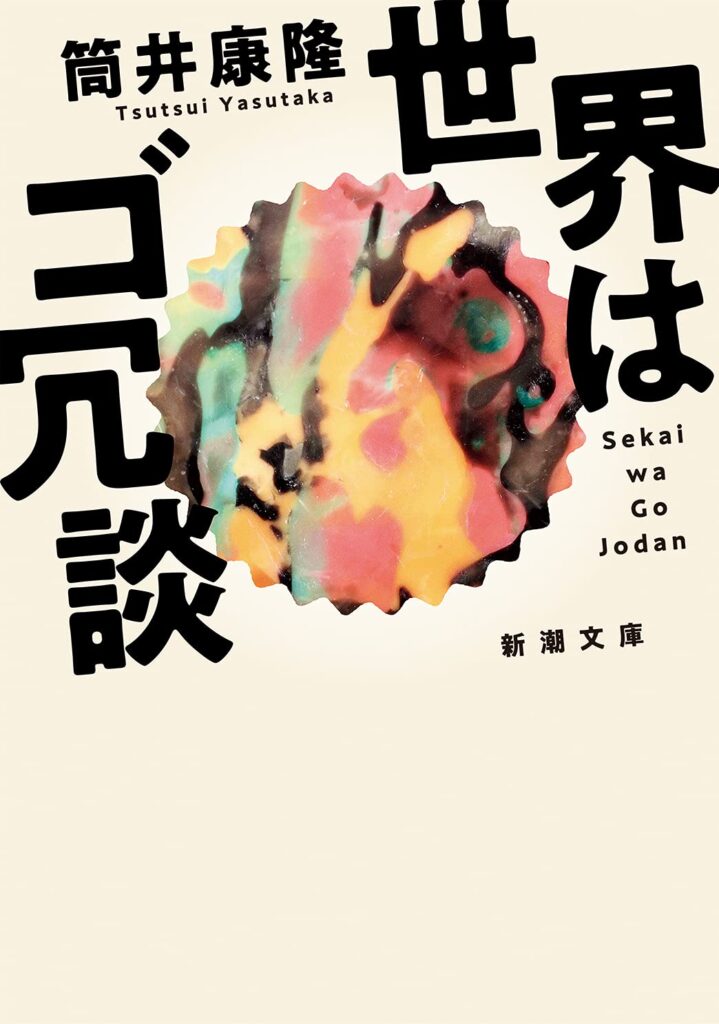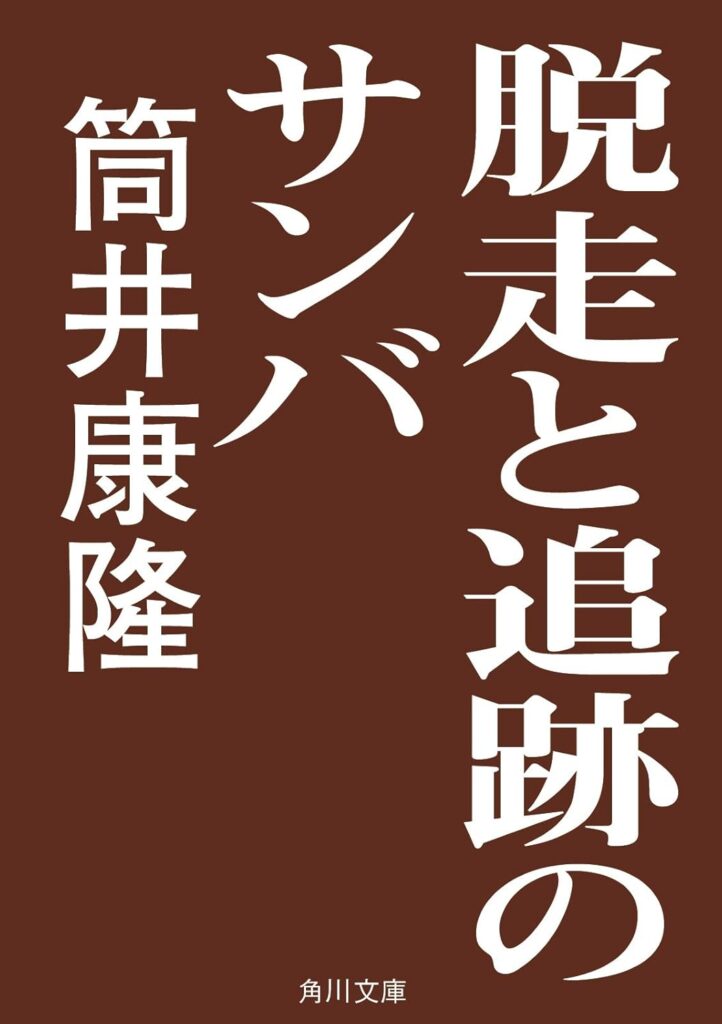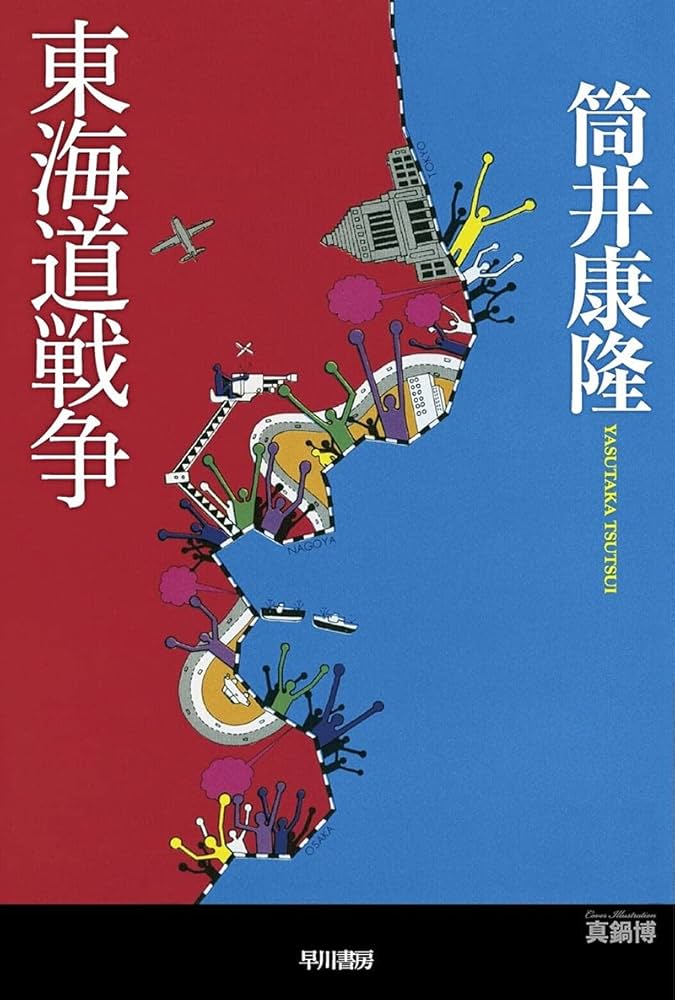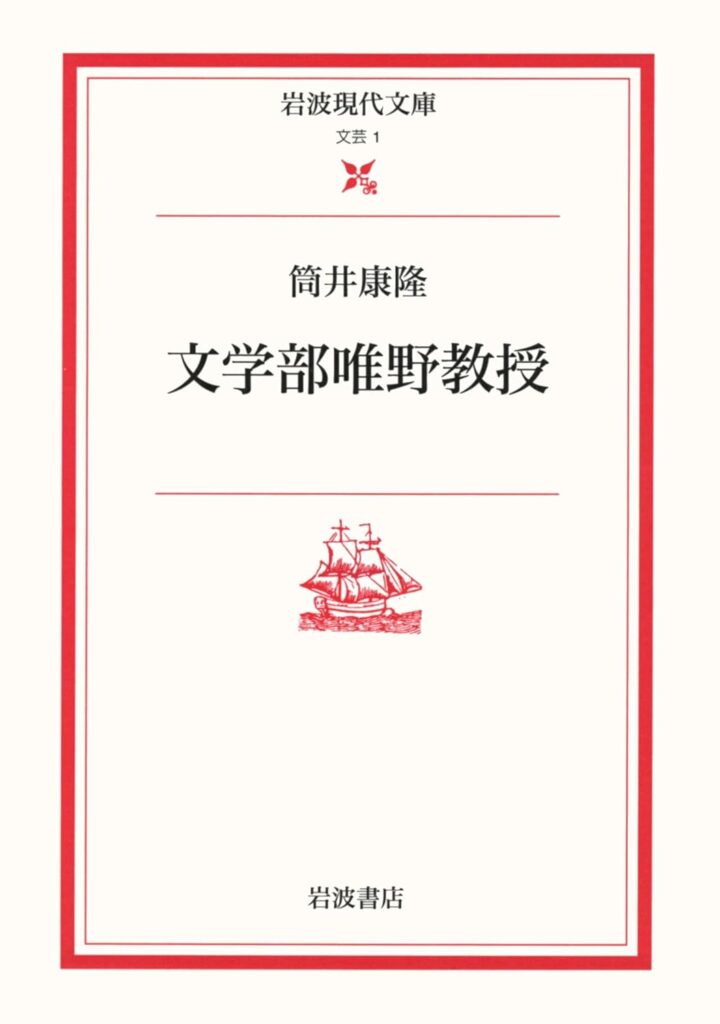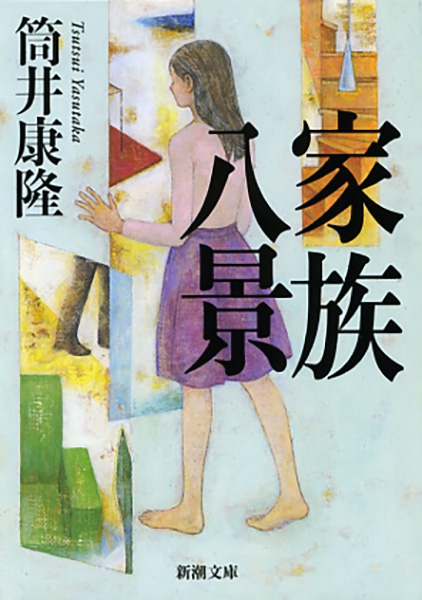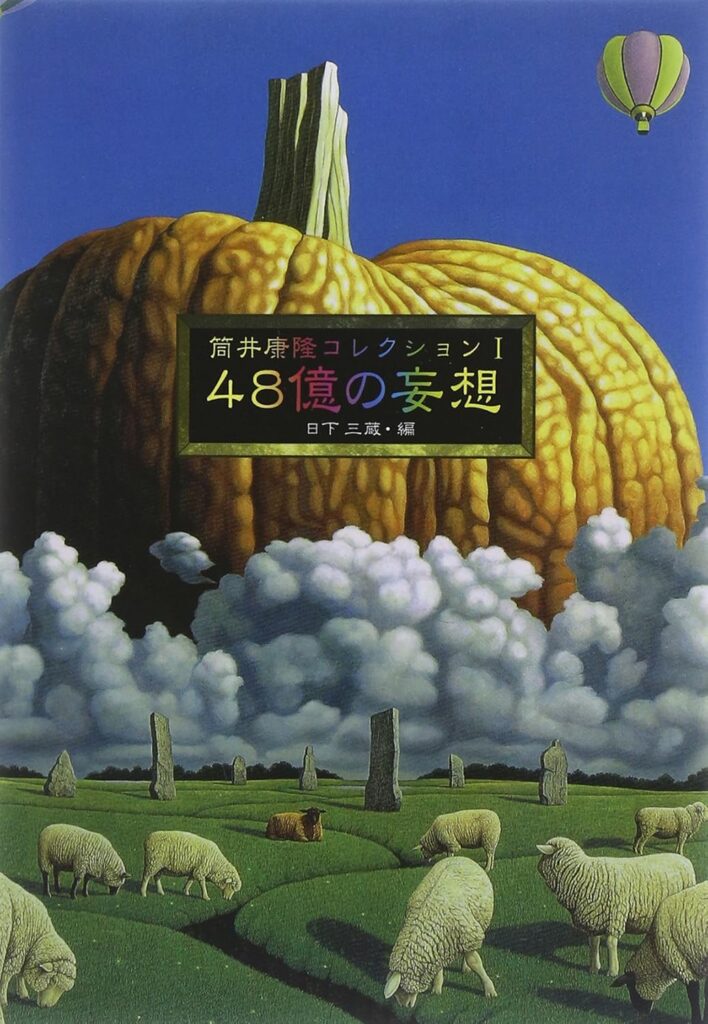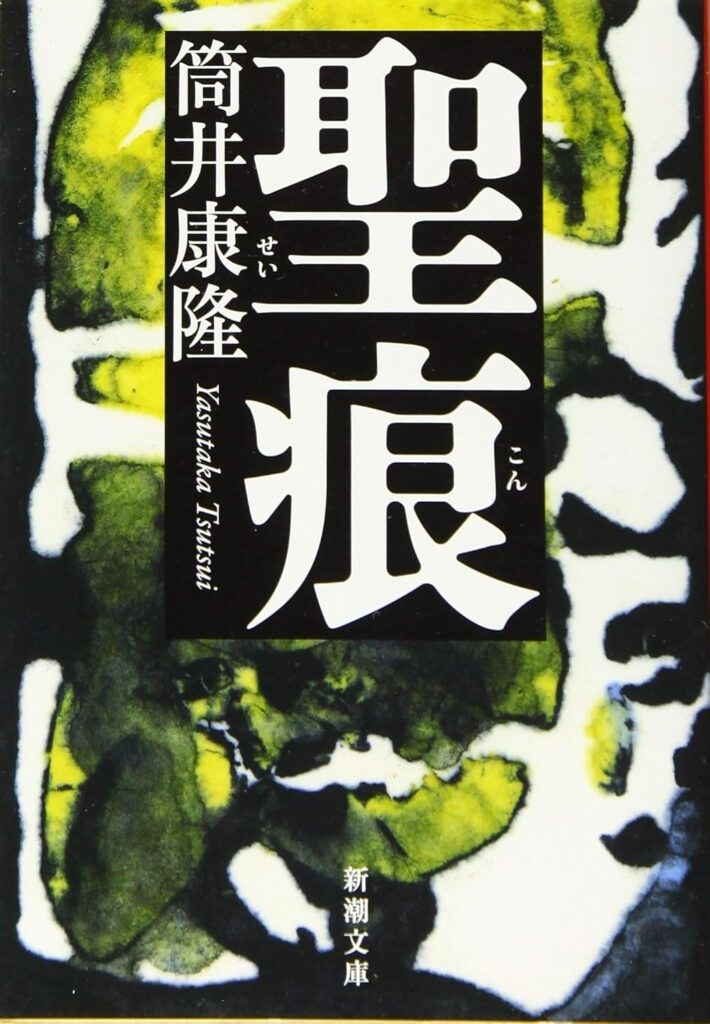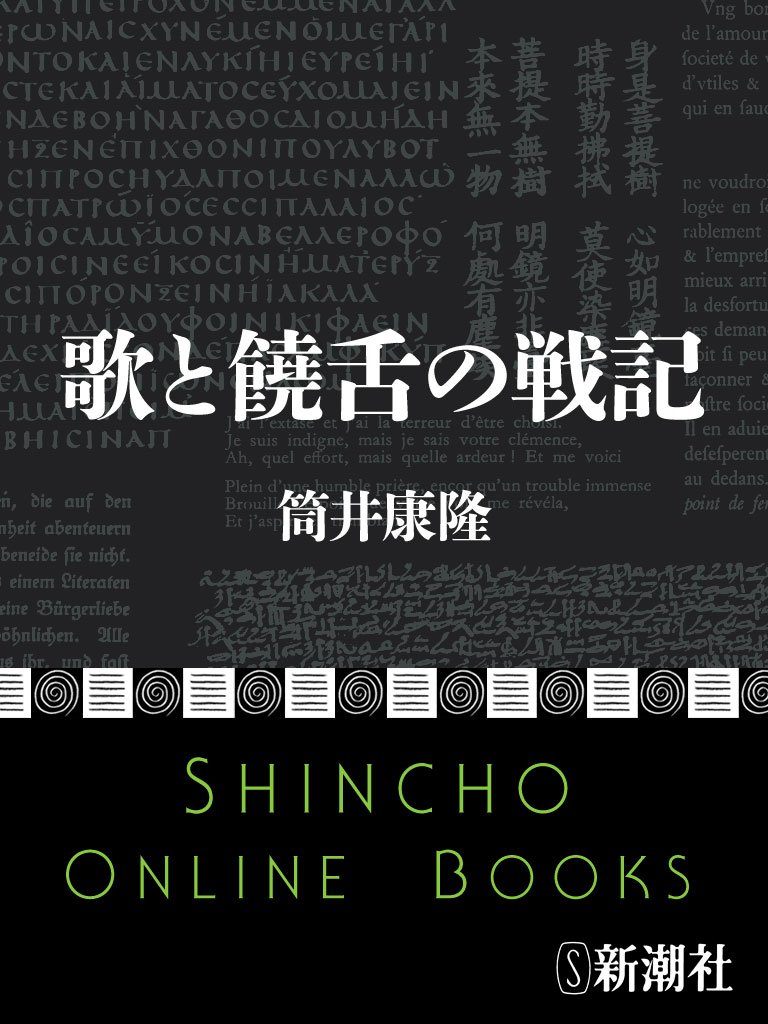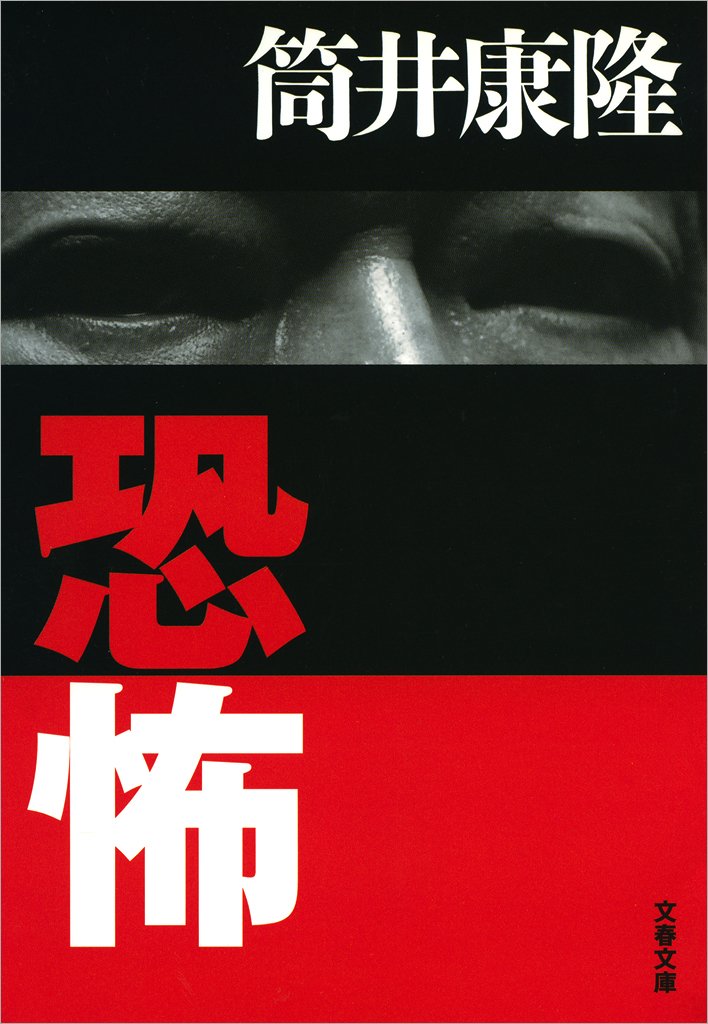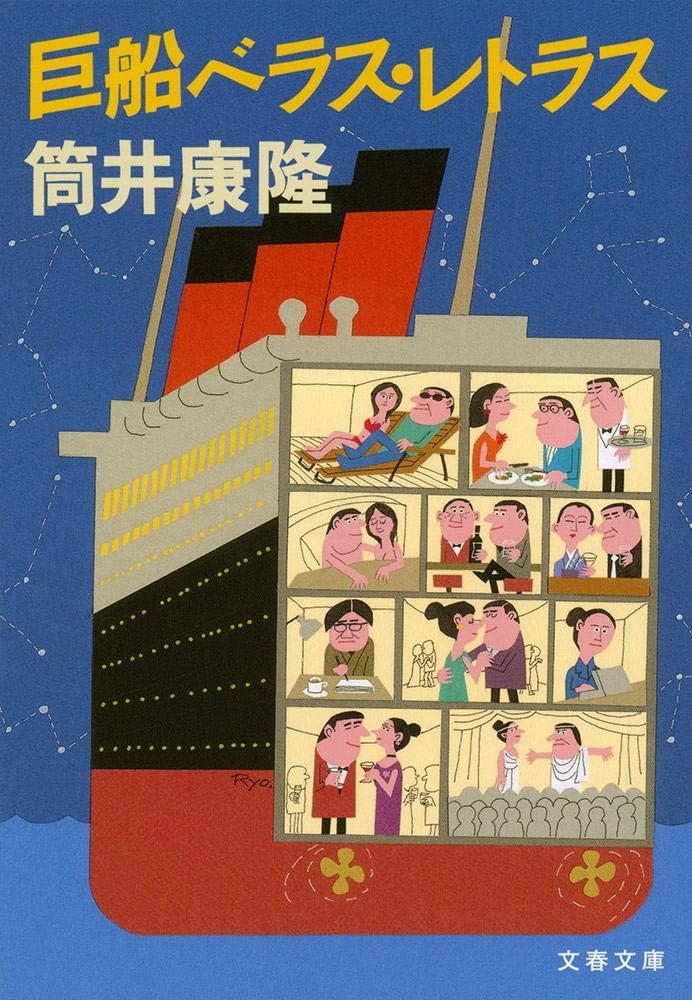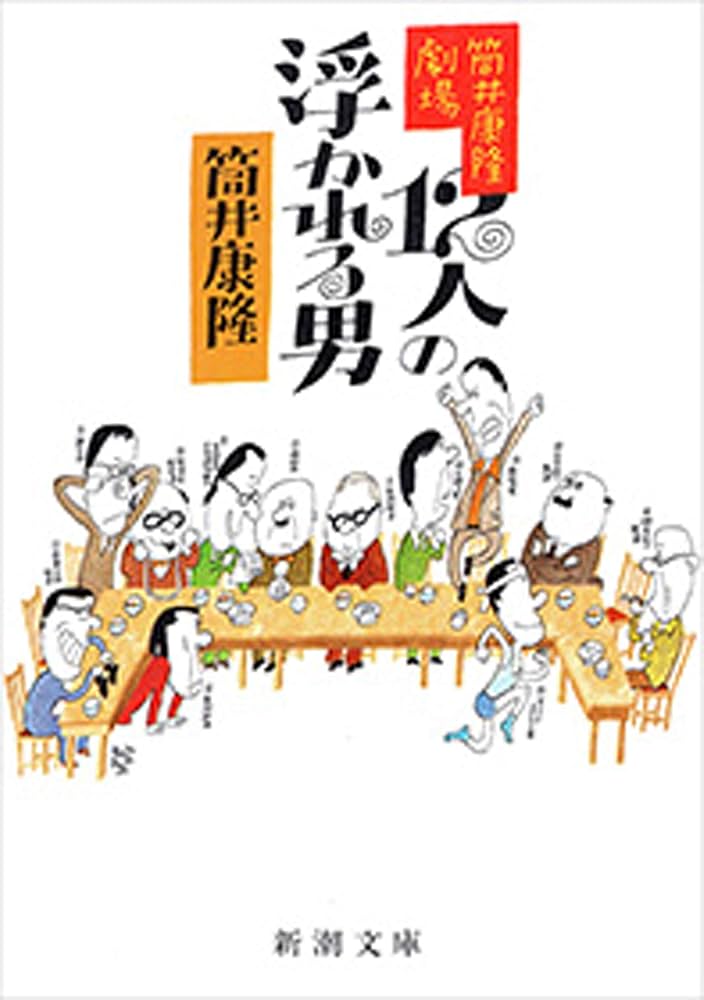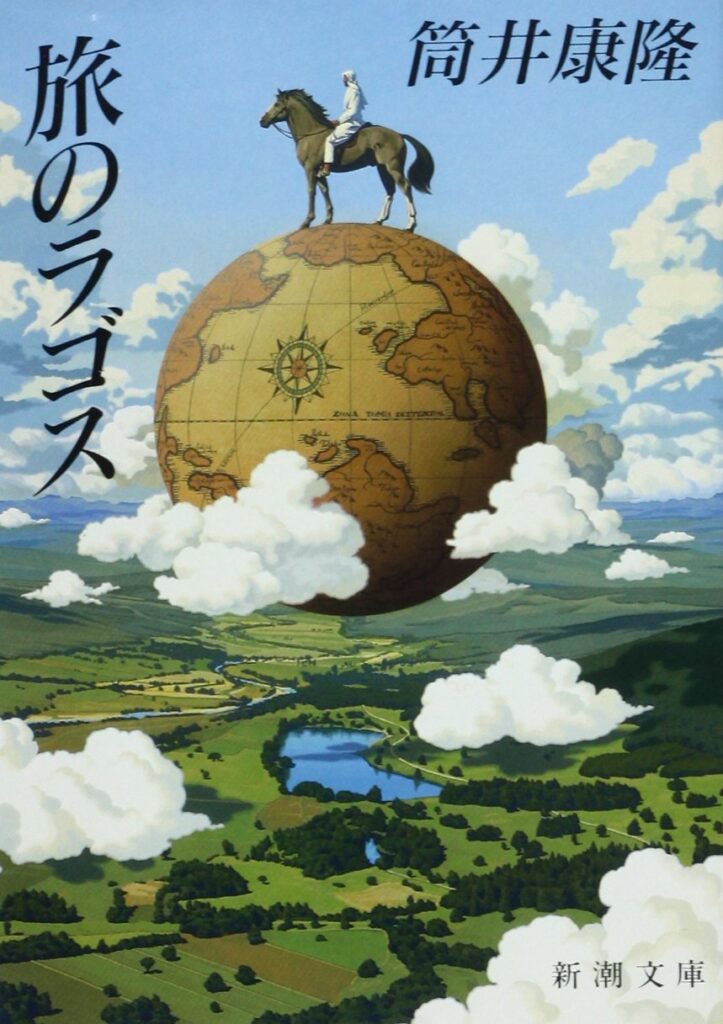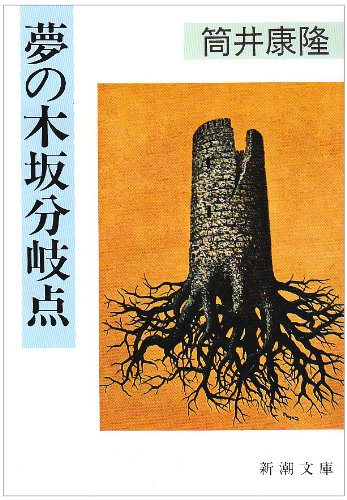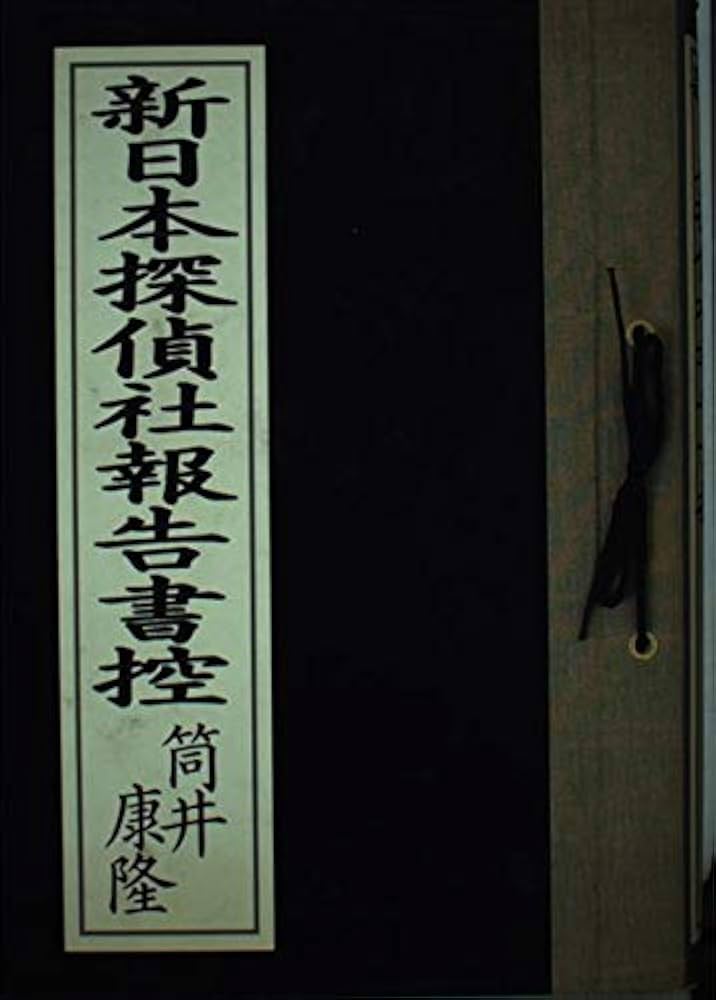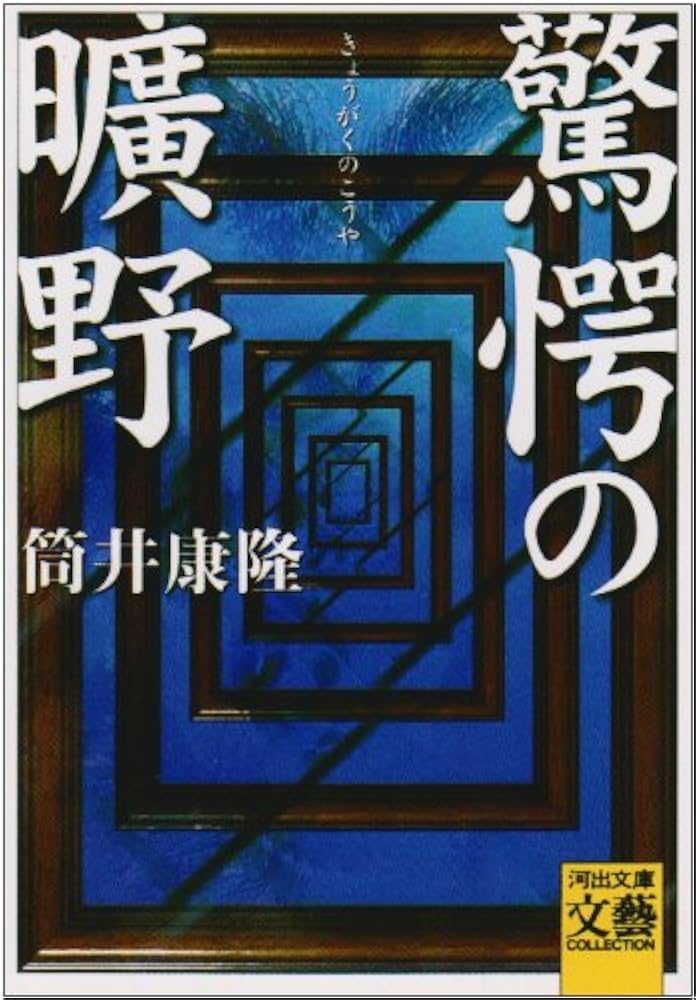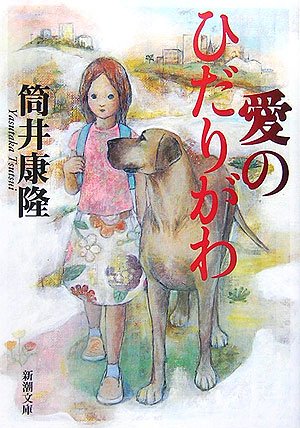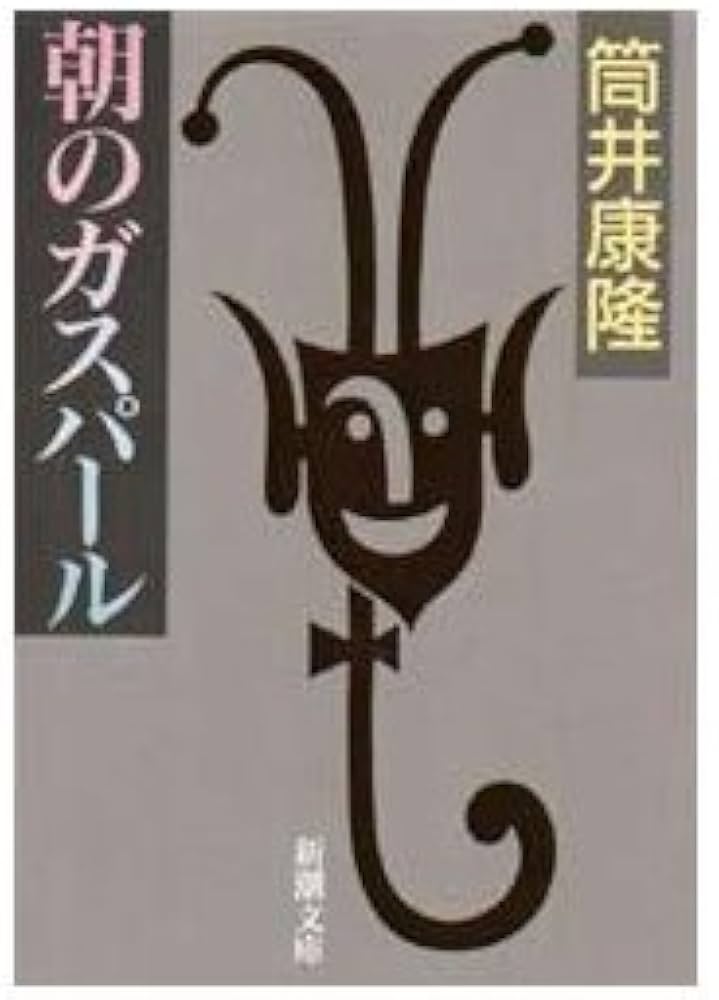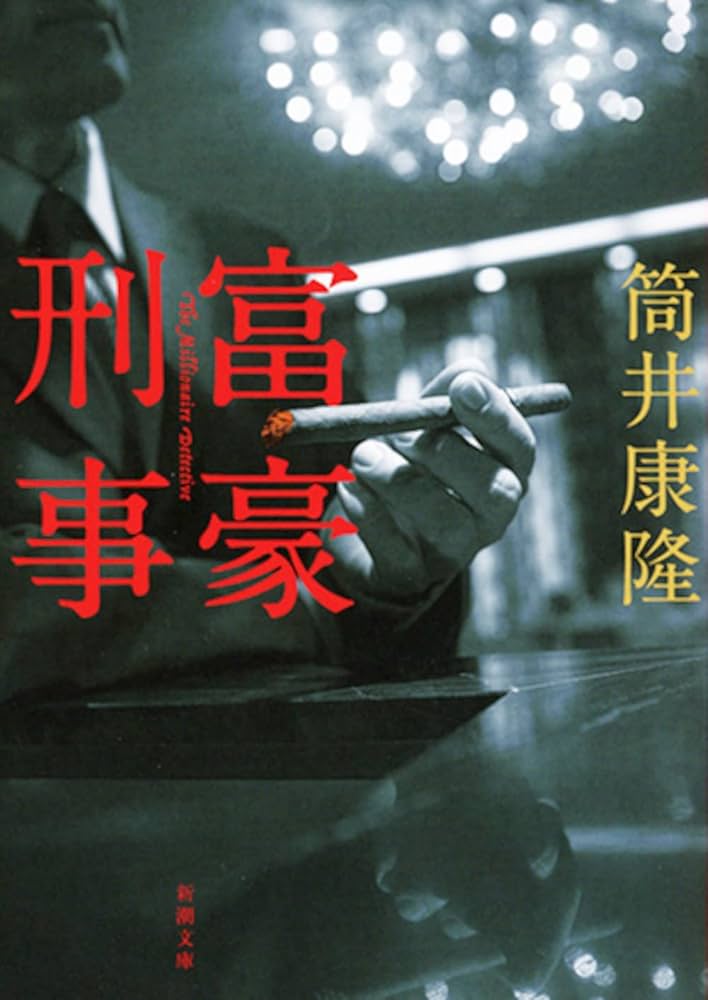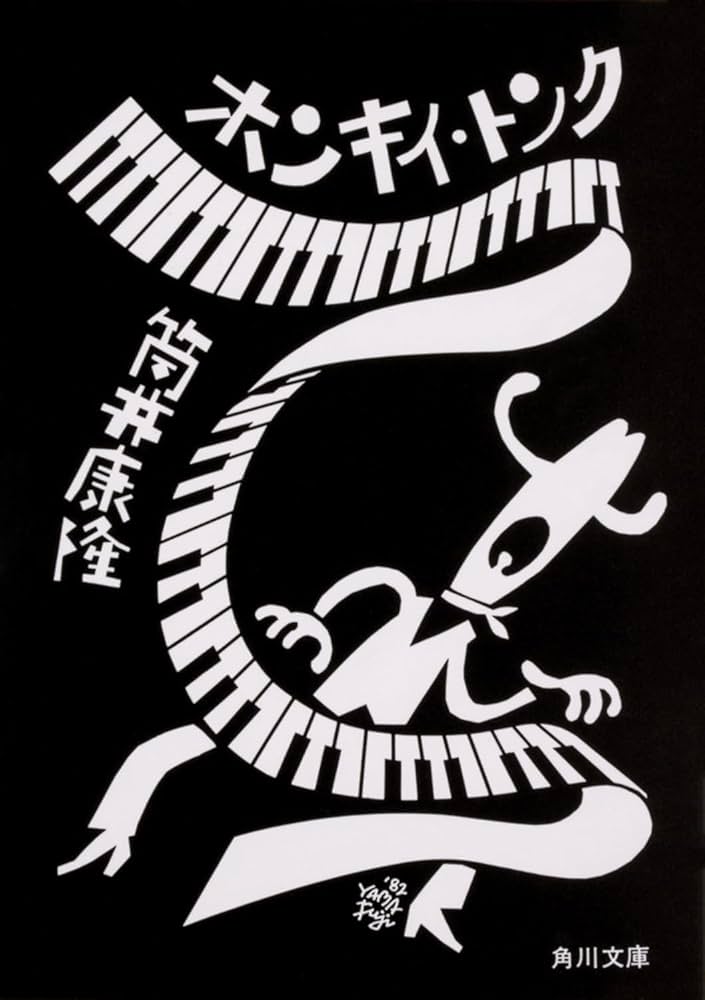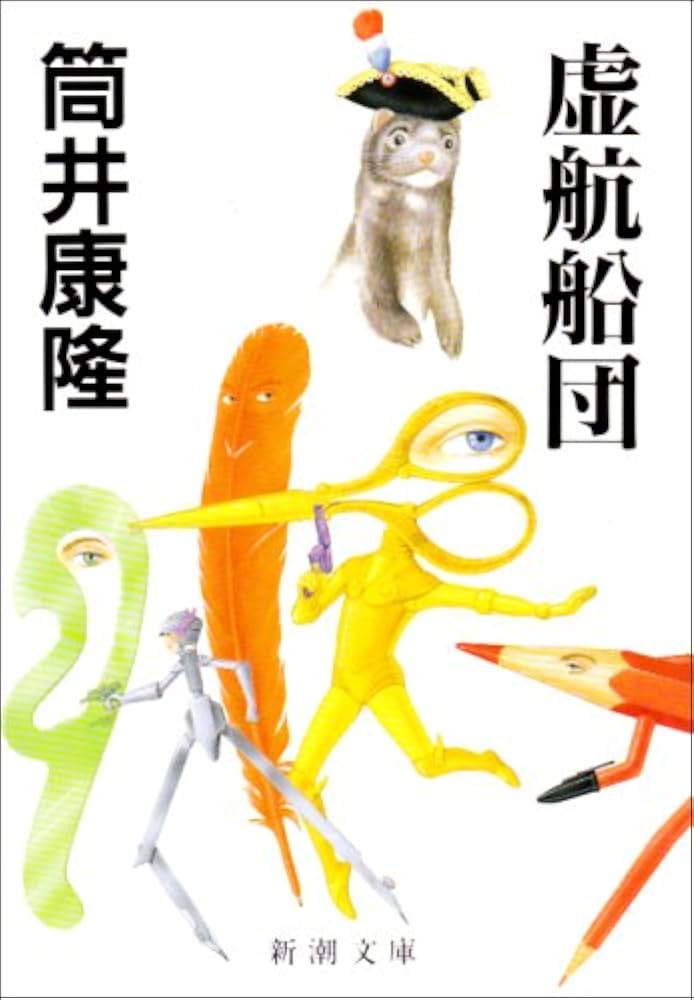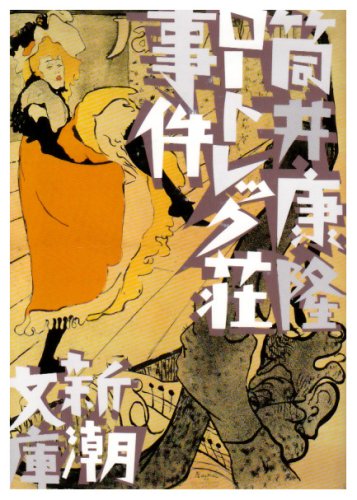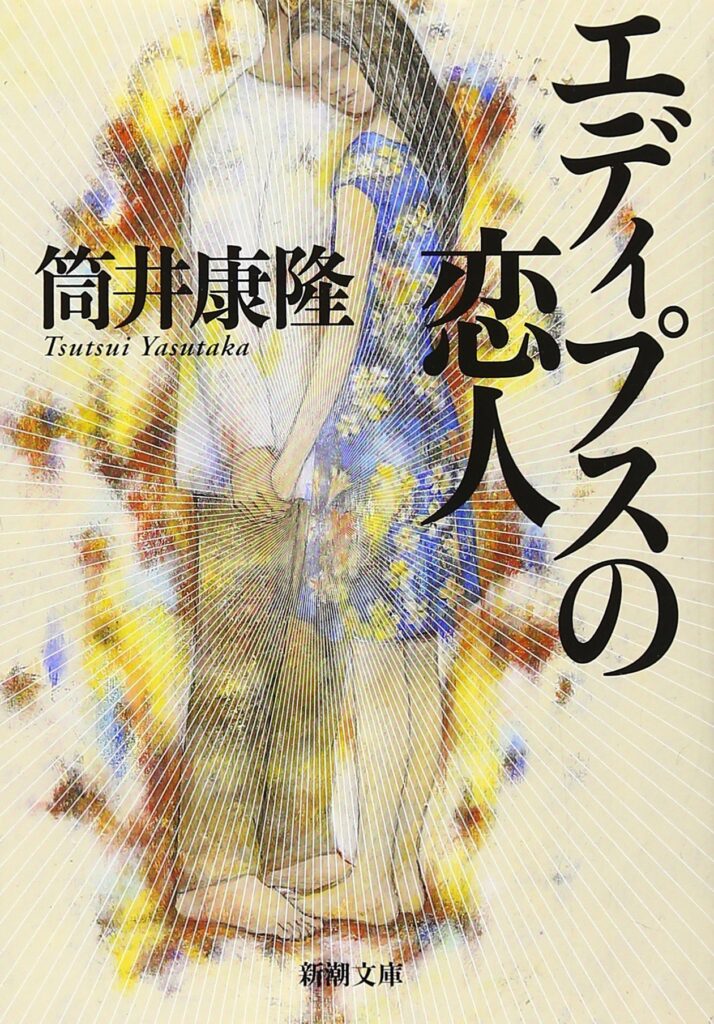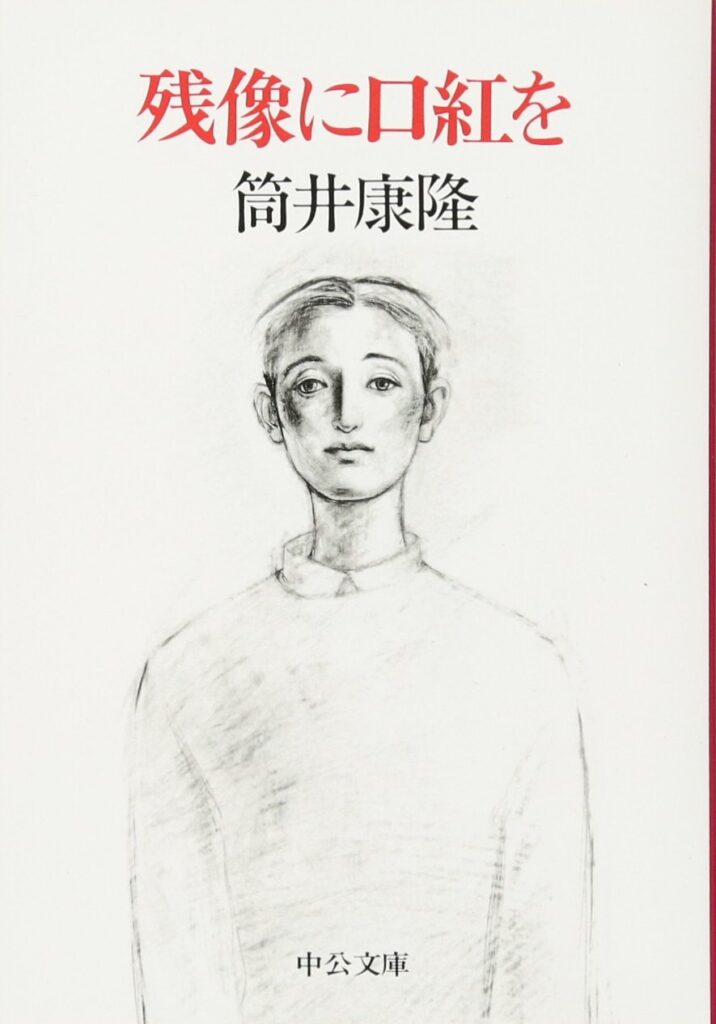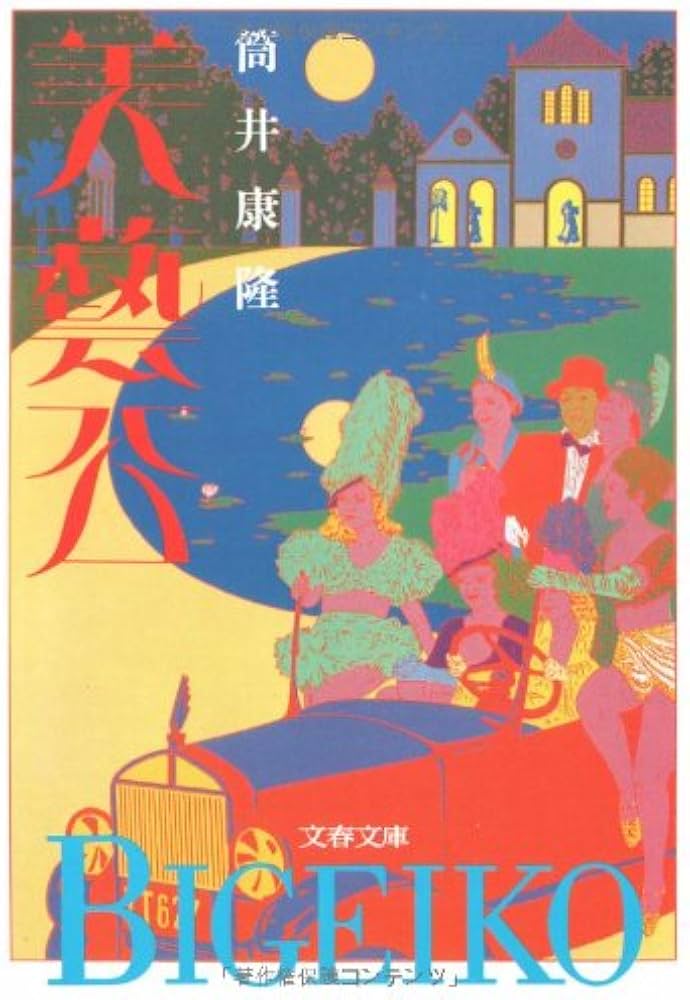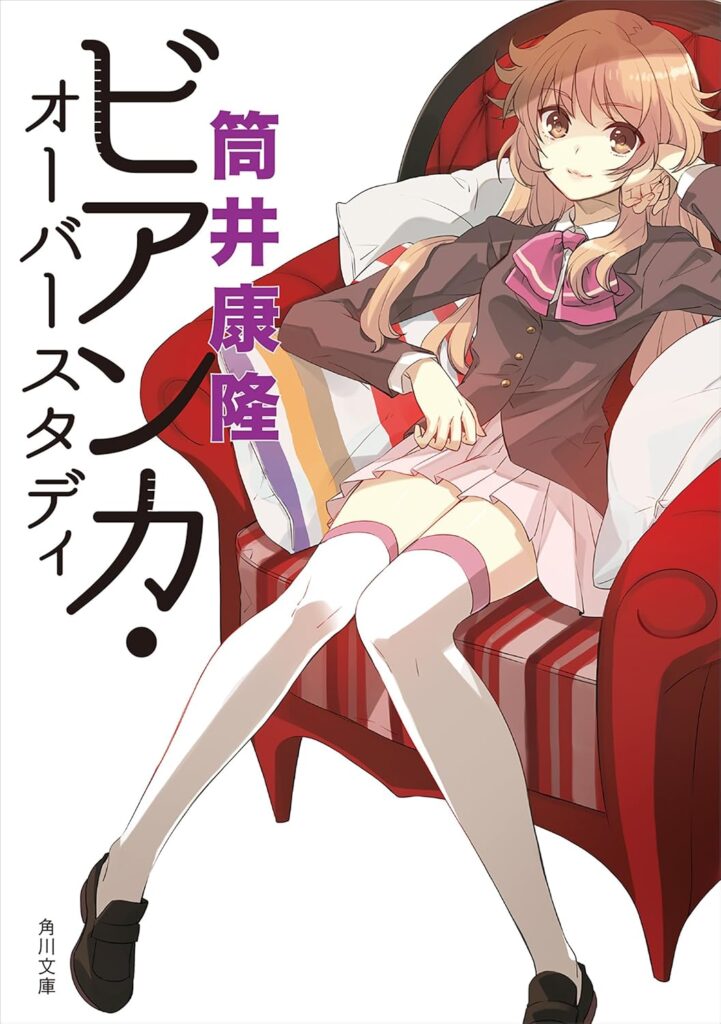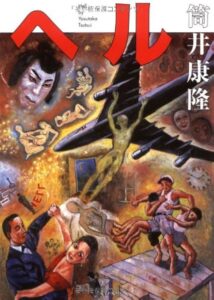 小説「ヘル」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「ヘル」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
筒井康隆氏が放ったこの作品は、私たちの「地獄」という概念を根底から揺さぶる、恐ろしくも魅力的な物語です。飛行機墜落の瞬間、あるいは交通事故の直後、意識が途切れたはずの登場人物たちが次に目覚めるのは、炎も責め苦もない、しかしどこまでも不条理で混沌とした世界「ヘル」でした。
そこは生前の記憶や人間関係、そして未練や後悔が渦巻く、奇妙な死後の領域。この記事では、そんな不可解な世界「ヘル」の物語の筋道と、その核心に迫る考察を、結末まで含めて詳しく語っていきます。一度読んだら忘れられない、その強烈な読書体験の源泉は何なのか。
この物語は、単なるエンターテインメントの枠を超え、読む者の意識そのものを変容させてしまう力を持っています。読み終えた後、あなたの見る世界は以前と同じではないかもしれません。そんな危険な魅力に満ちた一冊の深淵を、これから一緒に覗いていきましょう。
小説「ヘル」のあらすじ
物語は、57歳の男「武」が交通事故に遭い、意識を取り戻す場面から始まります。彼が目覚めたのは、見慣れないバー。しかし、そこで彼は驚くべきことに気づきます。生涯頼りにしてきた松葉杖なしで、自分の足で立っているのです。しかし、その喜びも束の間、彼は自分がいる場所が「ヘル」と呼ばれる死後の世界であることを知らされます。
「ヘル」には、武の他にも多くの知人たちがいました。5年前に飛行機事故で亡くなった女性・泉。ヤクザの抗争で命を落とした幼馴染の勇三。ホームレスとして凍え死んだはずが、なぜか生前のビジネスマンの姿で現れる佐々木。彼らは皆、それぞれの「死」を経て、この不可解な世界に集っていたのです。
この世界には独特のルールがありました。地上の10年間が、ここではわずか3日間に相当するというのです。さらに、そこにいる者は自らの過去と未来のすべてを見通すことができます。生前の後悔、自分を陥れた者たちのその後、そして変えることのできない未来。その全知は、救いではなく、終わりのない苦しみをもたらします。
生者と死者の境界さえ曖昧になり、時空を超えて絡み合う人間模様。登場人物たちは、絶え間ない追っ手に追われながら、それぞれのトラウマが具現化したかのような悪夢的状況に苛まれます。果たしてこの「ヘル」とは何なのか。そして、彼らに逃れる術はあるのでしょうか。物語は予測不能な混沌の中、誰もが予想しなかった結末へと突き進んでいきます。
小説「ヘル」の長文感想(ネタバレあり)
筒井康隆氏の『ヘル』を読み終えた時、私が感じたのは恐怖や驚きという単純な感情ではなく、むしろ脳髄を直接かき混ぜられたような、一種の酩酊感にも似た混乱でした。物語の冒頭、阿鼻叫喚の事故現場から一転、「スン」と静まり返る描写。この瞬間に、私たちは日常の物理法則が通用しない、全く新しい論理で動く世界へと突き落とされるのです。
そこは「ヘル」と名付けられてはいますが、私たちが想像するような業火に焼かれ、鬼に責められる場所ではありません。むしろ、生前の日常がグロテスクに歪んで連続しているような、悪夢的なリアリティに満ちた空間。この作品が描き出すのは、死後の罰ではなく、生きることそのものが内包する不条理の延長線なのかもしれません。
物語の中心人物である武は、「ヘル」で長年の身体的障害から解放されます。一見すると奇跡のようですが、これは作者が仕掛けた巧妙で皮肉な罠なのでしょう。肉体が癒されても、彼の魂は未解決の葛藤や人間関係のしがらみから逃れられず、むしろより深い精神的な混乱へと陥っていきます。物理的な救済が、存在論的な苦しみを少しも和らげない。この一点だけでも、この物語が描く「ヘル」の容赦のなさが伝わってきます。
そして、この世界には武だけでなく、彼の人生に関わった死者たちが次々と現れます。飛行機事故で死んだ泉、抗争で死んだヤクザの勇三、凍死した元ビジネスマンの佐々木。彼らの存在は、「死」が人間関係を清算してくれるわけではないという、残酷な事実を突きつけます。むしろ、生前の関係性やトラウマはそのまま持ち越され、この混沌の領域でさらに複雑に絡み合っていくのです。
特に印象的なのは、佐々木がホームレスとしてではなく、かつてのビジネスマンの姿で現れる点です。これは、「ヘル」が個人のアイデンティティや記憶を恣意的に選択し、再構築する場所であることを示唆しています。最も執着していた、あるいは最も未練を残した時代の姿で、人はこの世界を彷徨うのかもしれません。
この物語の根幹をなすルールの一つが、特異な時間感覚です。「ヘル」での3日間が地上での10年に相当し、過去と未来のすべてを見通せる。この能力は、一見すると神の視点のようですが、実際には登場人物たちを苛む最大の拷問となります。自分を殺した相手が地上で平然と暮らし、愛した妻が不義を続けている。そのすべてを知りながら、何一つ干渉できない無力感。これこそが、この「ヘル」における精神的な責め苦の正体なのでしょう。
また、「ヘル」は地上の現実と地続きでありながら、決定的に「破綻した世界」として描かれます。生前の欲望や憎しみは消えるどころか、むしろ剥き出しの形で「甦り」ます。ある場面では「ヘルに行くと恨みが消える」と語られる一方で、幼馴染への怨みを募らせる人物もいる。この矛盾は、「ヘル」が一様な法則で支配された空間ではなく、個々の魂の状態によってそのありようが変化する、極めて主観的な世界であることを物語っています。
その混沌をさらに加速させるのが、生者と死者、そして夢と現実の境界が完全に溶解していく描写です。「ヘルは夢につながっている」と明言される通り、物語は登場人物たちの意識の流れを追うように、論理を無視して飛躍します。読んでいる私たちも、いつしか登場人物たちと共にその存在論的な迷宮に迷い込み、何が現実で何が幻覚なのか、その区別がつかなくなっていくのです。この感覚こそ、筒井康隆氏が狙った読書体験そのものなのではないでしょうか。
この「ヘル」には、一つの明確な入場条件があります。それは、「年老いて死んだ者は受け入れられない」というルールです。認知症を患い、穏やかに(しかし意識は混濁したまま)生を終えようとしている武のもう一人の幼馴染・信照は、この世界に入ることができません。この除外規定は、「ヘル」が「未完の人生」を送った者たちのための場所であることを強く示唆しています。事故や殺人、あるいは若すぎる死。強烈な未練や執着を残して人生を中断された魂だけが、この混沌の精算所に招かれるのです。
物語は、特定の主人公の視点に留まらず、30人もの登場人物が織りなす群像劇として展開していきます。それぞれの人物が、生前の職業やトラウマを反映した、オーダーメイドの「地獄」を体験するのです。例えば、歌舞伎役者であった市川紺蔵は、舞台に上がることができず、永遠に奈落の迷路をさまよい続けます。これは彼の生前の嫉妬や舞台への執着が、そのまま悪夢として具現化した姿です。
また、女優のまゆみと作家の鳥飼が、パパラッチから逃れるために飛び乗ったエレベーターが「地下666階」まで落ちていく場面も強烈です。「666」という古典的な悪魔の数字を用いながらも、その原因が「パパラッチ」という現代的な苦悩にあるのが、いかにも筒井康拓らしい仕掛けと言えます。彼らの苦しみは、神による罰ではなく、あくまで彼ら自身の内面から生じているのです。
こうした個別のエピソード群は、「ヘル」が画一的な地獄ではなく、個々の精神世界が投影された鏡のような空間であることを浮き彫りにします。誰もが自分だけの悪夢から逃れることができない。そして、「追っ手はどこまでもやって来る」という絶え間ない脅威が、その閉塞感をさらに強固なものにしています。
そして、この物語を唯一無二の存在たらしめている最大の要因が、後半から現れる文体の劇的な変化です。突如として、すべての地の文と会話が、流れるような「七五調」のリズムを帯び始めるのです。この文体変化は、単なる実験的な試みに留まりません。
このリズミカルな文体は、物語に異様な「グルーヴ」を生み出し、読者を否応なく引きずり込んでいきます。意味を理解しようとする理性を、心地よくも狂気的なリズムが麻痺させていく。物語の内容が混沌を極めていくのと並行して、文章そのものが音楽的な高揚感を帯びていくのです。この形式と内容の見事な融合こそ、筒井康隆氏の真骨頂でしょう。アニメーション監督の今敏氏がこの手法に影響を受けたと公言していることからも、この言語実験がいかに革新的であったかがわかります。
この七五調のリズムは、まるで儀式的な詠唱のようでもあり、逃れられない苦しみの連鎖を刻む脈動のようでもあります。それは登場人物たちが理性を失い、より根源的な存在へと変容していく様を、文章の構造そのもので表現しているかのようです。読書という行為が、いつしかトランス状態に近い没入体験へと変わっていく。この感覚は、他のどんな小説でも味わうことのできない、本作ならではのものです。
物語は、しかし、この混沌の正体を最後まで明かしません。「結局ヘルの正体がわからないままクローズする」のです。それは浄化のための煉獄だったのか、それとも単なる無意味な混沌の反復だったのか。作者は安易な答えを用意せず、解釈のすべてを読者に委ねます。この突き放したような態度こそが、この物語の深みをさらに増しているように感じます。
クライマックスで描かれるのは、驚くべき光景です。「惚け爺に先導された」死者たちの一団が、「ヘルよりもさらに遠い場所をめざして」旅立っていくのです。あれほど逃れられないと思われた「ヘル」が、最終的な終着点ではなかった。この結末は、かすかな希望のようにも、あるいはさらなる未知の苦しみへの旅立ちのようにも見え、深い余韻を残します。
この最後の場面に漂う「哀切なノスタルジー」という感覚は、非常に重要です。たとえ「ヘル」を超えて次の段階へ進むとしても、そこで経験した苦悩や執着が完全に消え去るわけではない。それらをすべて抱えたまま、それでもなお先へと進んでいかなくてはならない。その姿は、まるで私たち自身の人生の営みを象徴しているかのようで、胸を締め付けられるような感慨を覚えずにはいられませんでした。この物語は、生と死を明確に分断されたものではなく、混沌とした一つの連続体として描ききった、壮大な文学的達成なのだと私は確信しています。
まとめ
筒井康隆氏の小説『ヘル』は、死後の世界を描きながらも、その実、私たちの生そのものの不条理を鋭くえぐり出す作品でした。物語の舞台となる「ヘル」は、伝統的な地獄のイメージを覆し、生前の記憶や執着が渦巻く混沌とした領域として描かれます。
そこでは、登場人物たちがそれぞれのトラウマを悪夢のように追体験し、終わりなき苦悩に苛まれます。しかし、物語の白眉は、後半からすべての文章が七五調のリズムを刻み始めるという、その大胆な言語実験にあります。この文体がもたらす圧倒的なグルーヴ感は、読者を物語の狂気と一体化させるでしょう。
結局のところ、「ヘル」の正体は明かされることなく、物語は登場人物たちの新たな旅立ちで幕を閉じます。明確な答えがないからこそ、読後も私たちの心に深く残り続け、生とは、死とは何かを問いかけてくるのです。
本作は、ただ物語を読むという行為を超えた、一つの強烈な「体験」そのものです。日常的な感覚を揺さぶられたい、文学の持つ極限の可能性に触れてみたいと願うすべての人にとって、忘れがたい一冊となることは間違いありません。