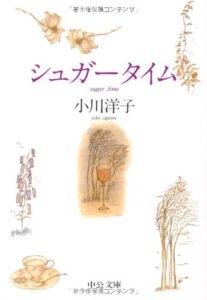
小説『シュガータイム』のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小川洋子さんが1991年に発表された長編作品『シュガータイム』は、青春の終わりと、日常に潜む「異質」なものを繊細な筆致で描いた一作です。芥川賞受賞作『妊娠カレンダー』に続く長編として、その独特の世界観は多くの読者を魅了してきました。主人公「わたし」(かおる)の身に起こる奇妙な出来事を軸に、人間関係や内面の変化が静かに紡がれていきます。
本作は、表面的な「失恋の物語」というだけでは語り尽くせない奥深さを持っています。甘く、もろく、しかしかけがえのない青春の日々。その透明な時間の中で、彼女が経験する食欲の異常、血の繋がらない弟との関係、そして恋人との別れが、次第に彼女を大人へと導いていきます。小川洋子さん特有の静謐で美しい文章は、読者を物語の世界へと深く誘い込み、登場人物たちの感情の揺らぎを鮮やかに映し出します。
物語全体に流れるのは、どこか懐かしく、そして少し切ない「シュガータイム」の感覚です。それは、大人になる前の、ある種の猶予期間における独特な感情の機微を捉えています。何が「普通」で、何が「異常」なのか。その境界線が曖昧になる中で、主人公は自身の心と向き合い、静かに成長していきます。
この作品は、単なる物語としてだけでなく、読者自身の青春時代や、日常に潜むささやかな「奇妙さ」について考えさせられる機会を与えてくれるでしょう。ぜひ、本作を手に取り、小川洋子さんが織りなす精緻な物語の世界に触れてみてください。
『シュガータイム』のあらすじ
主人公「わたし」(かおる)は女子大学生です。ある日突然、止めどない異常な食欲に襲われ、食べたものを克明に記録する奇妙な日記をつけ始めます。元々痩せ気味だったにもかかわらず、この強烈な食欲に支配されるようになった「わたし」は、その原因を、アルバイト先のホテルで食べた大量のアイスクリーム「ロイヤル」と、8歳から身長が伸びない奇病を抱える義理の弟・航平が、彼女の住むアパートの隣に引っ越してきたことの二つだと推測します。
「わたし」の食欲は「暴力的」と形容されるほど強烈で、一度始まると際限なく続いていきます。日記には、「四月二十二日(火) フレンチトースト四切れ(シナモンをかけすぎた)」のように、食べたものの種類と量が詳細に綴られていきます。深夜にパウンドケーキを焼くシーンなど、食べ物の描写は非常に緻密かつ鮮烈に描かれ、読者の食欲を刺激する一方で、どこか不穏な雰囲気を漂わせます。
「わたし」には、金属研究者の恋人・吉田さんがいます。彼は「性欲の無い彼」「不能症」と描写され、二人の関係には性的な行為がないことが示唆されています。彼らは社会が定める「普通」のカップル像から逸脱していますが、当人たちはそのことに不便や不満を感じていません。親友の真由子は、そんな「わたし」の日常を支え、彼女の抱える奇妙な状況にも淡々と寄り添い、話を聞いてくれる存在です。真由子は「シュガータイム」という言葉を「砂糖菓子みたいにもろいから余計にいとおしくて、でも独り占めにしすぎると胸が苦しくなる」ものと説明します。
「わたし」は、自身の異常な食欲、弟の奇病、恋人の不能症といった「普通ではないこと」を、驚くほど淡々と受け入れています。周囲の人間がこれらの「異常」について口出しするのを疎ましく感じる一方で、彼女自身はそれらを不便と感じていません。物語は、こうした日常に紛れ込む「異常」な存在たちとの関わりを通して、「わたし」の心境が静かに変化していく様子を描きます。
『シュガータイム』の長文感想(ネタバレあり)
小川洋子さんの『シュガータイム』は、読み終えた後も静かな余韻が残る、まことに忘れがたい作品でした。この物語は、単なる青春の終焉を描くだけでなく、人間の内面に潜む漠然とした不安や空虚感、そして「異質」なものをいかに受け入れ、自己の一部としていくかという深遠なテーマを、実に繊細な筆致で描き切っています。
まず心を奪われるのは、主人公「わたし」の異常な食欲に関する描写です。それは単なる生理的な欲求を超え、まるで自律した生命体のように「わたし」を支配します。「暴力的」とまで形容されるその食欲は、満たされない精神状態や、青春期特有の不安定さのメタファーとして機能しているように感じられました。食べたものを克明に記録する「奇妙な日記」は、本能的な衝動を理性で制御しようとする「わたし」の試み、あるいは内面の混乱を客観視しようとする彼女の努力の表れなのでしょう。
作品に登場する食べ物の描写は、時に読者の食欲を刺激するほどリアルでありながら、同時にどこか不穏な雰囲気を漂わせます。特に印象的なのは、深夜に「わたし」が一人でパウンドケーキを焼くシーンです。砂糖がバターに溶け込み、泡立て器を回す右腕が身体から切り離されたように軽やかに回転する様子は、決して美味しそうではなく、むしろグロテスクとすら言えるかもしれません。しかし、その詳細な描写には、孤独な春の夜の台所で静かに焼きあがっていくパウンドケーキの、ある種の詩情すら感じられました。このグロテスクな美しさは、「わたし」の内面に存在する「奇妙さ」や「満たされなさ」が、孤独な行為を通じてある種の昇華された「美」として表現される過程を示唆しているかのようです。
そして、物語が進むにつれて、この異常な食欲が「当たり前」のように描かれ、物語の中心から外れていく点も非常に興味深く感じました。これは、小川洋子さんの作品に共通する特徴で、「異常なもの」や「奇妙なもの」が日常の中に静かに存在し、それがやがて「普通」として受容されていく過程が描かれます。食欲が物語の主軸から外れていくのは、「わたし」がその「異常」を自らの日常の一部として完全に受け入れ、もはや特別視しなくなった心理変化の表れであり、これこそが小川作品の「幻想とリアルの境界を曖昧にする」手腕の核心であると言えるでしょう。食べる行為自体が、空虚感を埋めるものから、自己と向き合い、内面を整理する儀式へと変容していく過程が示唆されます。
「わたし」の周りに存在する「異常」な存在たちもまた、この物語の重要な要素です。血の繋がらない弟・航平は、8歳から身長が伸びないという奇病を抱えています。しかし、「わたし」は彼の状況を気にせず、むしろ周囲の口出しを疎ましく感じています。航平は「わたし」にとって癒しとなり、失恋後の感情を処理する助けとなります。彼の「まばたきの表現」は「とても美しく儚く、時間の流れがゆっくりとした静けさ」を感じさせ、彼は「わたし」の「真の魂の双子」である可能性さえ示唆されています。この示唆は、血縁を超えた魂の共鳴、あるいは社会の枠組みを超えた深い絆の存在を読者に訴えかけます。
恋人である金属研究者の吉田さんもまた、「性欲の無い彼」「不能症」と描写され、社会が定める「普通」のカップル像から逸脱しています。しかし、彼らはそのことに不便や不満を感じていません。精神科医が吉田を「不能」と診断する場面は、社会が「普通」という画一的な枠組みで人間を裁くことへの批判を強く感じさせました。登場人物たちがそれぞれ「どこか欠けていて」「不完全」「異常」とされながらも、主人公がそれらを淡々と受け入れている点は、非常に印象的です。
親友の真由子もまた、欠かせない存在です。彼女は「わたし」の日常を支え、「わたし」の抱える奇妙な状況にも淡々と寄り添い、話を聞いてくれます。「シュガータイム」という言葉の意味を「砂糖菓子みたいにもろいから余計にいとおしくて、でも独り占めにしすぎると胸が苦しくなる」ものと説明する真由子の言葉は、この物語の核心的なテーマを代弁しています。社会が規定する「普通」や「完全さ」の枠から外れた存在たちが、いかにして自己を肯定し、それぞれの「普通」を見出すか。この作品は、その過程を静かに、しかし力強く描いていると感じました。
物語の決定的な転換点となるのは、恋人・吉田さんからの別れの手紙です。「わたし」は、いつも完璧に整頓され、数限りない種類の商品が揃うスーパーマーケット「サンシャインマーケット」で、静かな深夜にこの手紙を開封します。この場所が「わたし」にとって秩序と安寧の象徴のような場所であったという対比が、物語に深い奥行きを与えています。サンシャインマーケットの「完璧さ」は、青春期における秩序や安定、あるいは未熟な自己が求める理想的な世界像を象徴していたのでしょう。しかし、その完璧な空間で読まれる吉田からの手紙は、シベリアの研究所や魂の伴侶といった現実離れした内容でありながら、「わたし」の日常に決定的な亀裂を入れます。
手紙の中で吉田さんは、「わたし」ではない別の女性と「お互いに含まれ合う」「決定的な存在」として出会い、「魂の伴侶」だと感じたことを告げます。彼はこの深く、言葉では伝えきれない感情を、直接ではなく手紙という形で「わたし」に伝え、別れを告げたのです。この手紙は「残酷で美しくて無駄がなく神聖で、こんな別れがあるのか、とはじめて知った感情だった」と表現され、その独特の性質が「わたし」に新たな感情の揺れをもたらします。
この幻想的で決定的な別れのシーンは、「主人公の青春が決定的に終わる瞬間」として描かれます。この対比は、青春という「完璧」に見えるモラトリアムの期間が、予期せぬ「非現実的」な出来事によって脆くも崩れ去り、現実の厳しさや不確かさに直面する瞬間を劇的に際立たせています。手紙の「残酷な美しさ」は、失恋という痛みを伴う経験が、同時に主人公の内面に新たな感情や認識をもたらす、一種の通過儀礼であることを示唆しています。この瞬間をもって、「わたし」の青春は決定的に終わりを告げ、新たな段階へと移行するのです。
吉田さんが「オーロラのように『わたし』の前から消えて行く」と表現されるように、その喪失の感覚は強調されます。しかし、この失恋は「わたし」の人生における大きな転換点となり、決して悲劇的な終わりとして描かれるわけではありません。
吉田さんからの手紙を読み、失恋という大きな喪失を経験した「わたし」に、内面的な変化が訪れます。彼女は、血の繋がらない弟・航平と食事会を開催します。この食事は「微笑みと満足に彩られた平和な食事だった」と描写され、航平との優しい時間を過ごすことで、「わたし」の心は哀しみを受け入れることができたと描かれます。そしてそれが、「ブラックホール化した食欲の終焉を意味していた」と表現されるのです。これは、食欲が満たされない心の状態の表れであったならば、航平との絆を通じて得られた精神的な充足が、その食欲を鎮めたことを示唆しています。
航平との食事会の後、「わたし」はこれまで過食で食べたものを克明に記録してきた「日記」を断裁します。この行為は、過去の自分、あるいは「異常な食欲」に支配されていた時期との決定的な決別を象徴しています。日記の断裁は、空虚感を埋めるために食べ続けた日々からの解放であり、精神的な充足を得て、自己を再構築する過程の表れであると言えます。同時に、彼女が自身の「異常さ」を完全に受容し、それをもはや特別視しない境地に至ったことを示しているように感じられました。
物語のタイトルである「シュガータイム」は、まさにこの青春の時間を象徴しています。それは「砂糖菓子みたいにもろいから余計にいとおしくて、でも独り占めにしすぎると胸が苦しくなる」時間。甘く、儚く、かけがえのない、しかし永遠には続かない青春のモラトリアム期間を指し、その時期が終わりを告げることの寂寥感と、同時に訪れる解放感を表現しています。「わたし」が「最後の春が始まる」と無意識に考えることで、このモラトリアムの時期が終わりを告げ、完全に大人へと移行する最終的な猶予期間が示唆されます。
日記の断裁と航平との食事を通じて、「何か」が変わり、「青春の『シュガータイム』が過ぎてゆくことを感じて物語は終わる」のです。失恋という大きな喪失を経験しながらも、「わたし」はそれをゆるやかに受け止め、静かに時間が流れていくのを感じます。物語は「終わりが始まり」であることを示唆し、悲しみを乗り越え、新たな自己を見出し、人生が静かに、しかし確かに続いていく「わたし」の未来を穏やかに描き出して幕を閉じます。
小川洋子さんの静謐な文章で描かれる時間の流れは、人生における変化や喪失もまた自然なプロセスの一部であり、それらを受け入れることの重要性を静かに、しかし力強く伝えていると感じました。登場人物たちの「欠損」や「異常」を否定するのではなく、むしろそれらを受け入れることで、他者との真の繋がりや自己の充足を見出すという、小川洋子作品に通底する重要なテーマが、この『シュガータイム』には深く刻まれているように思います。静かで、しかし確かな感動を呼ぶ、まさに珠玉の一作でした。
まとめ
小川洋子さんの長編作品『シュガータイム』は、主人公「わたし」の経験を通して、青春の終わりと日常に潜む「異質」なものの受容を描いた、非常に奥深い物語です。異常な食欲に支配される日々、血の繋がらない弟・航平との独特な絆、そして恋人・吉田さんとの別れを通じて、「わたし」の心境は静かに、しかし確実に変化していきます。
物語全体を彩るのは、甘く、もろく、しかしかけがえのない青春の時間「シュガータイム」の感覚です。これは、大人になる前のモラトリアム期間における感情の揺らぎと、それが終わりを告げることの寂寥感、そして新たな自己への解放感を表現しています。特に、異常な食欲を克明に記録した日記を断裁するシーンは、過去の自分との決別と、精神的な充足を得て自己を再構築する「わたし」の象徴的な行為として描かれています。
「普通」とは何か、「異常」とは何か。その境界線が曖昧になる中で、登場人物たちはそれぞれの「欠損」や「異質さ」を抱えながらも、それを否定せず、自己の一部として受け入れていきます。それは、社会が規定する枠組みを超え、真の自己肯定と他者との繋がりを見出す過程でもあります。吉田さんからの別れの手紙が、「わたし」の青春に決定的な終止符を打ちながらも、それが新たな始まりへと繋がる通過儀礼として描かれている点も印象的でした。
小川洋子さん特有の静謐で美しい文章は、読者を物語の世界へと深く誘い込み、登場人物たちの内面を鮮やかに映し出します。失恋という喪失を乗り越え、静かに人生が続いていく「わたし」の姿は、読者に確かな感動と、変化を受け入れることの重要性を教えてくれます。この作品は、何度読み返しても新たな発見がある、まさに文学の喜びが詰まった一冊と言えるでしょう。



































