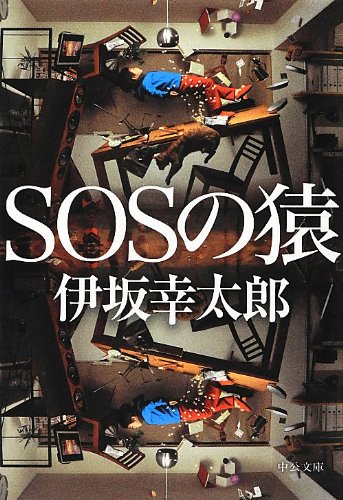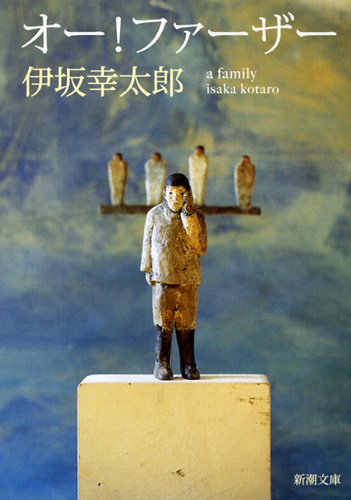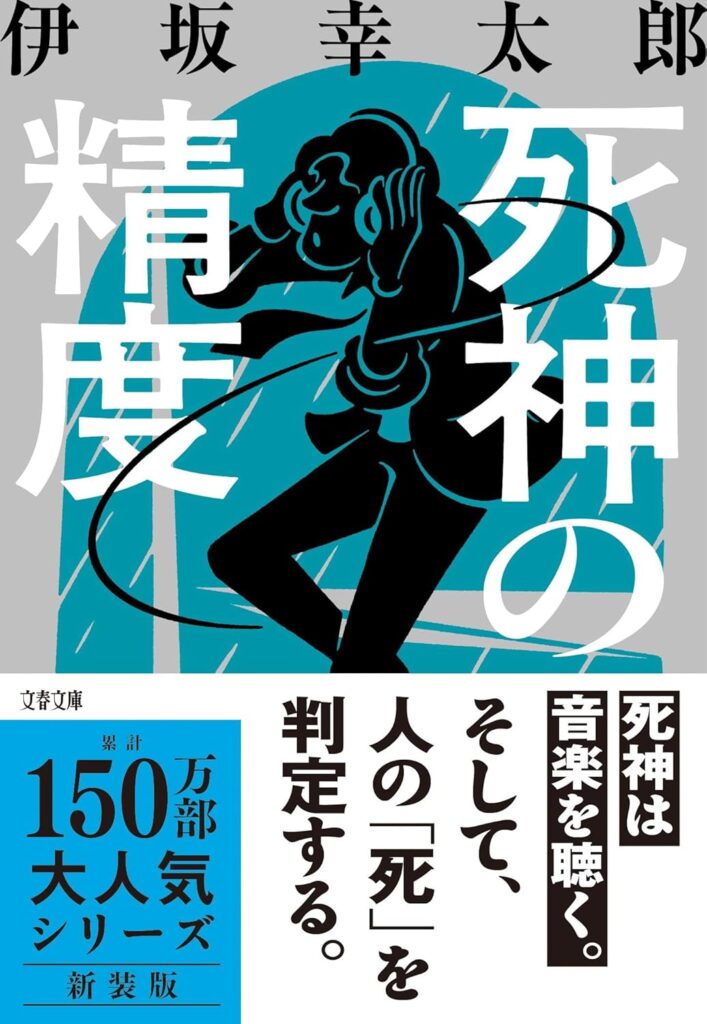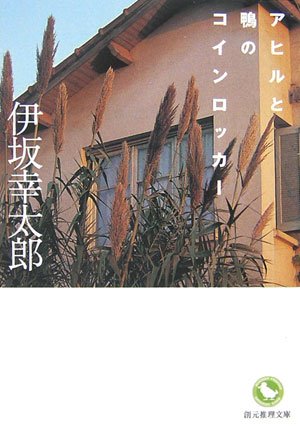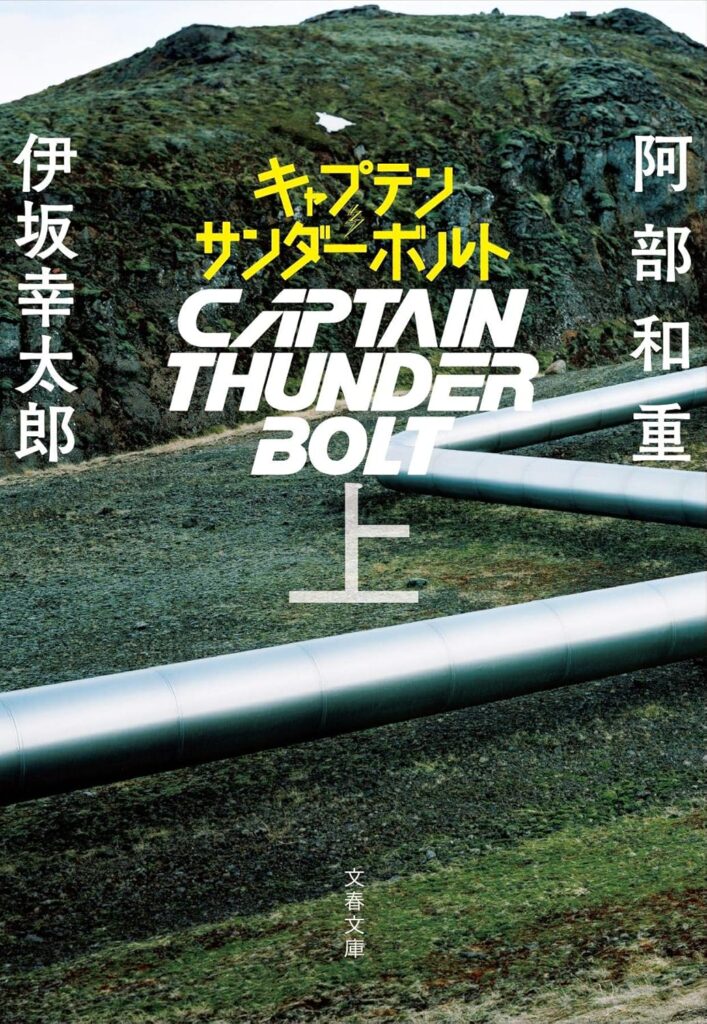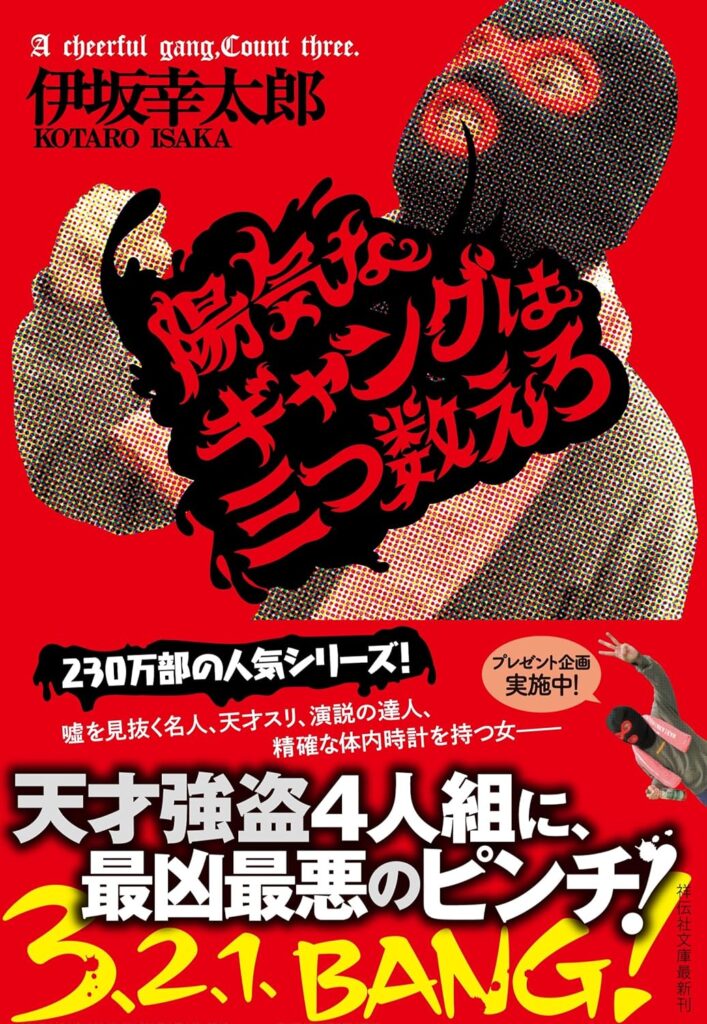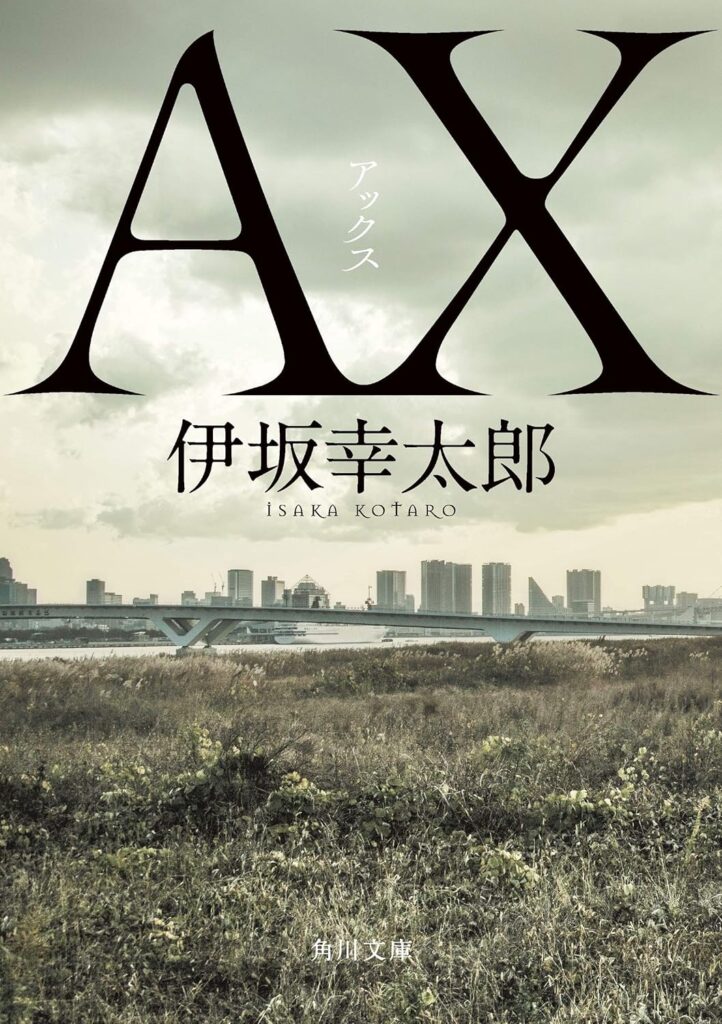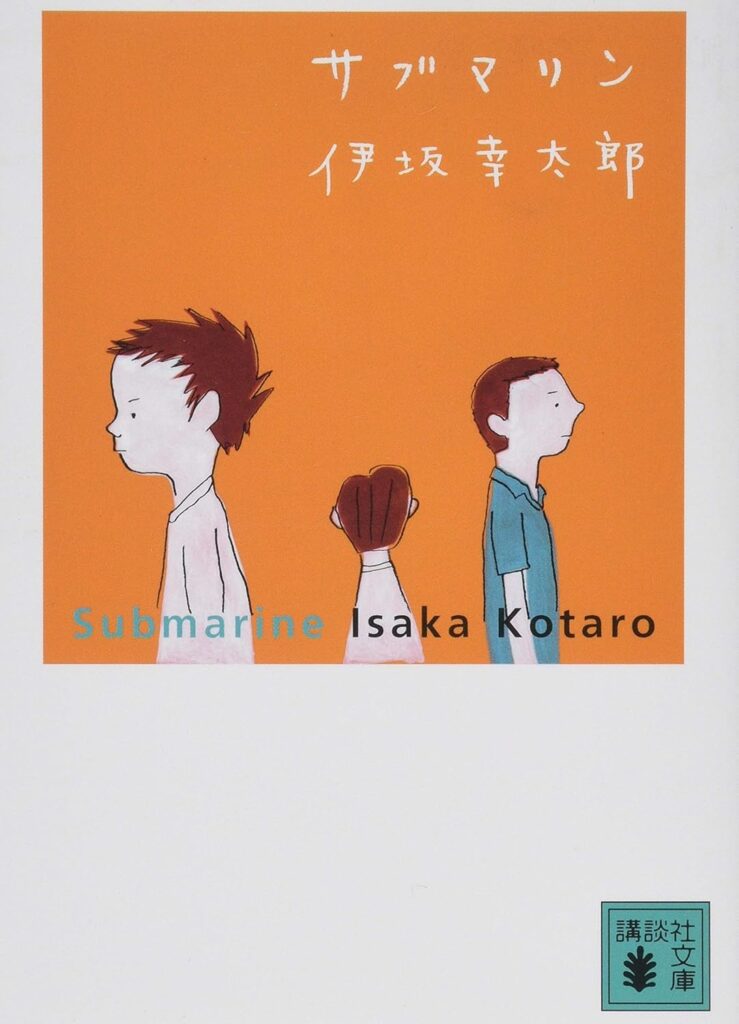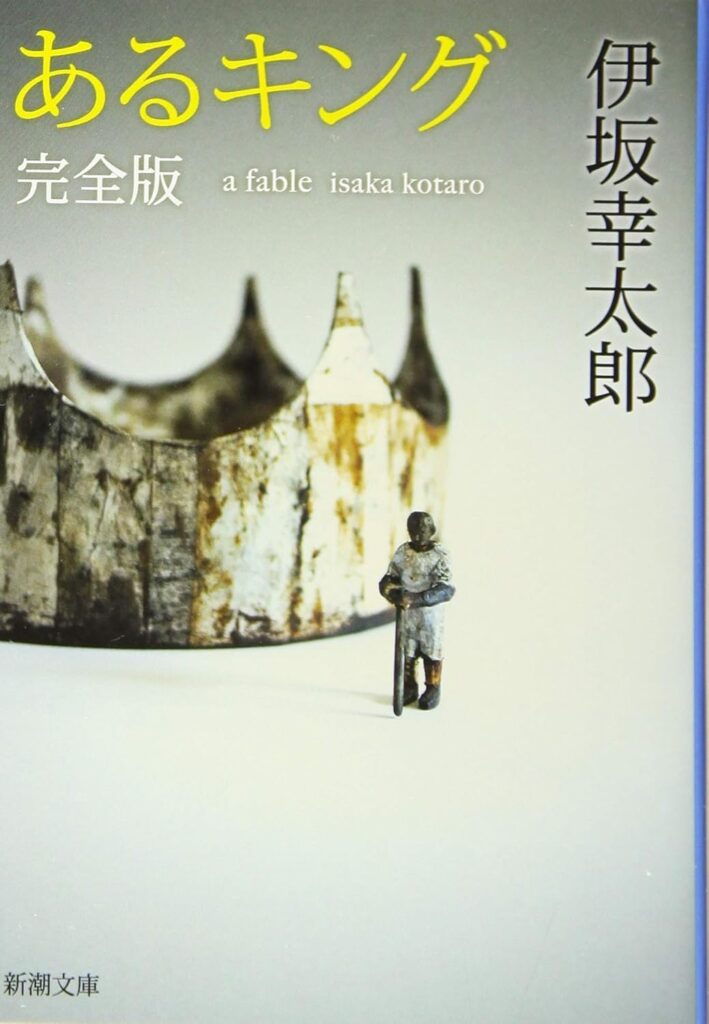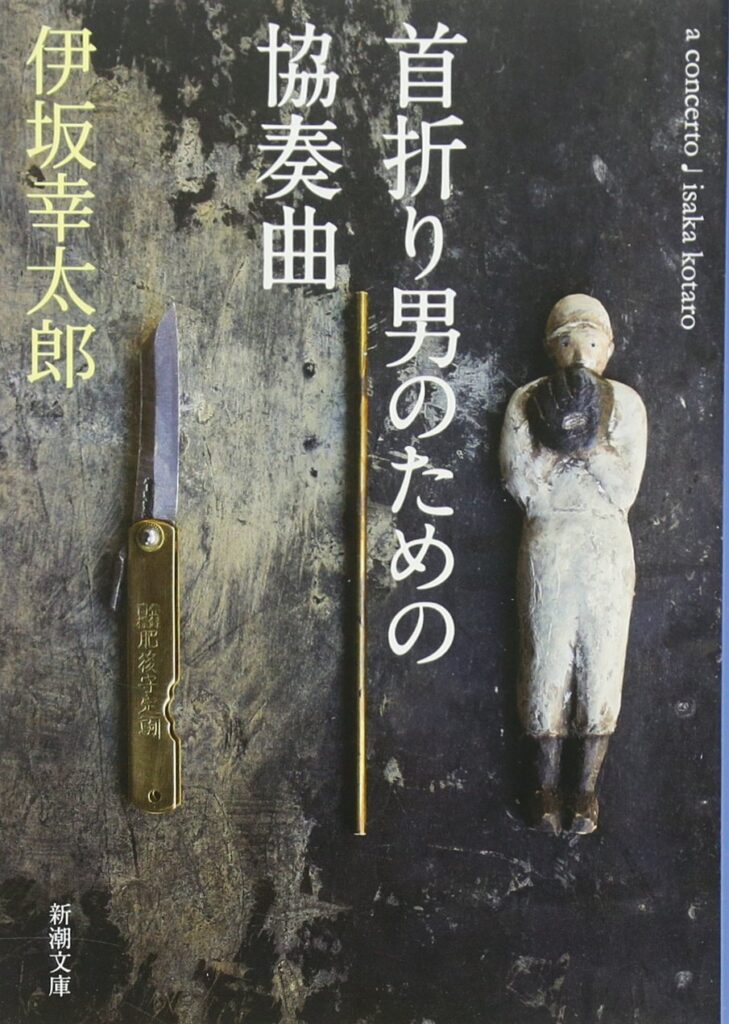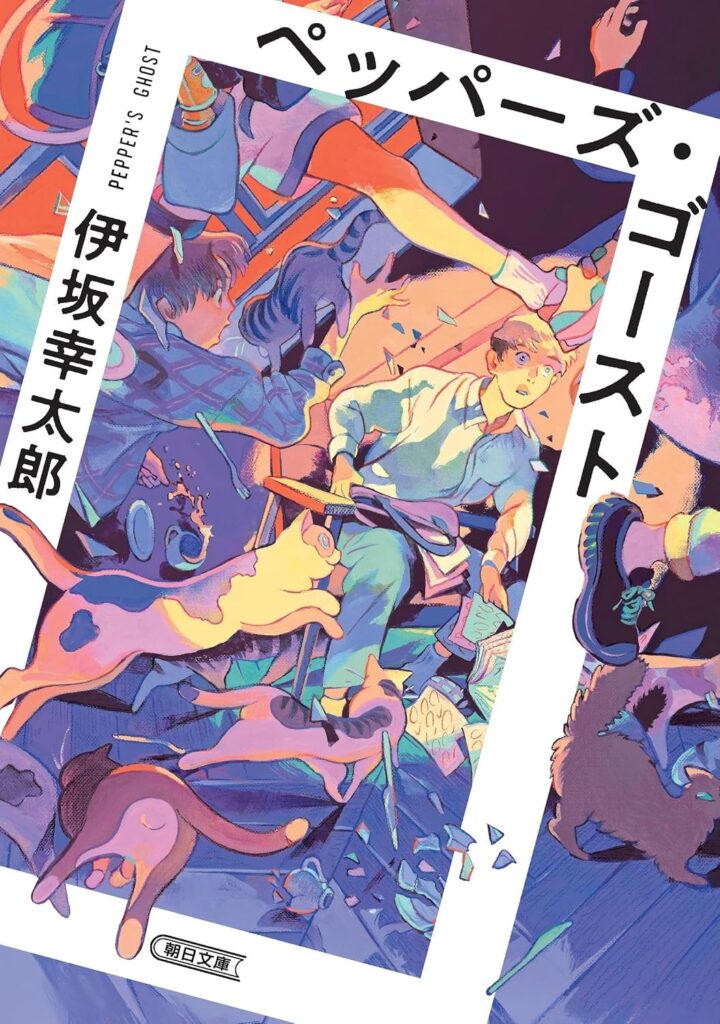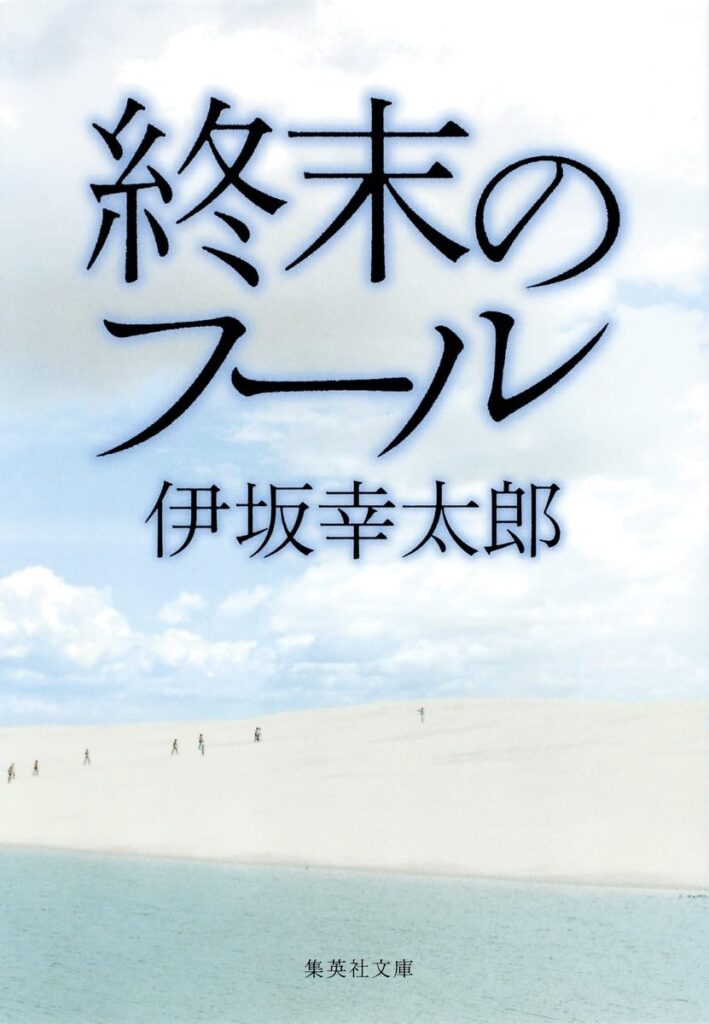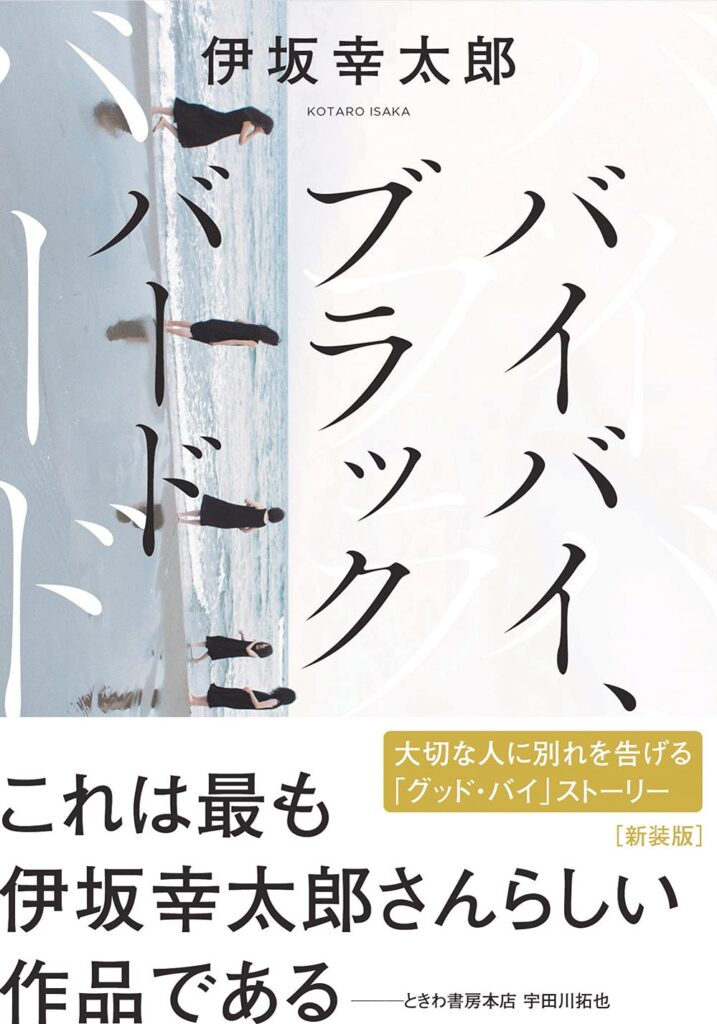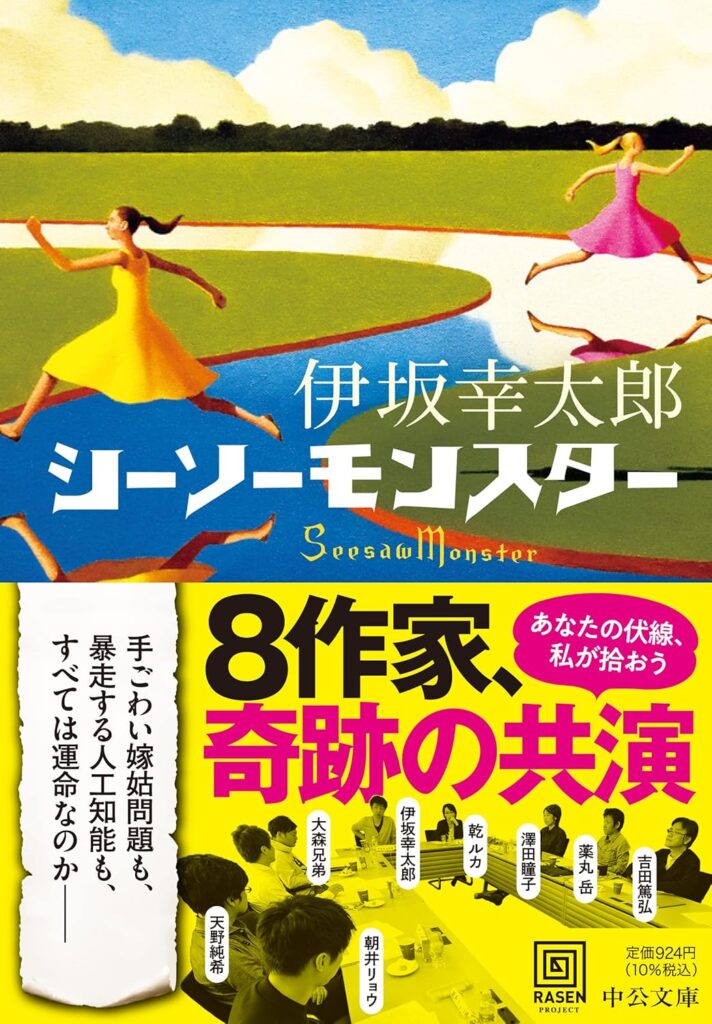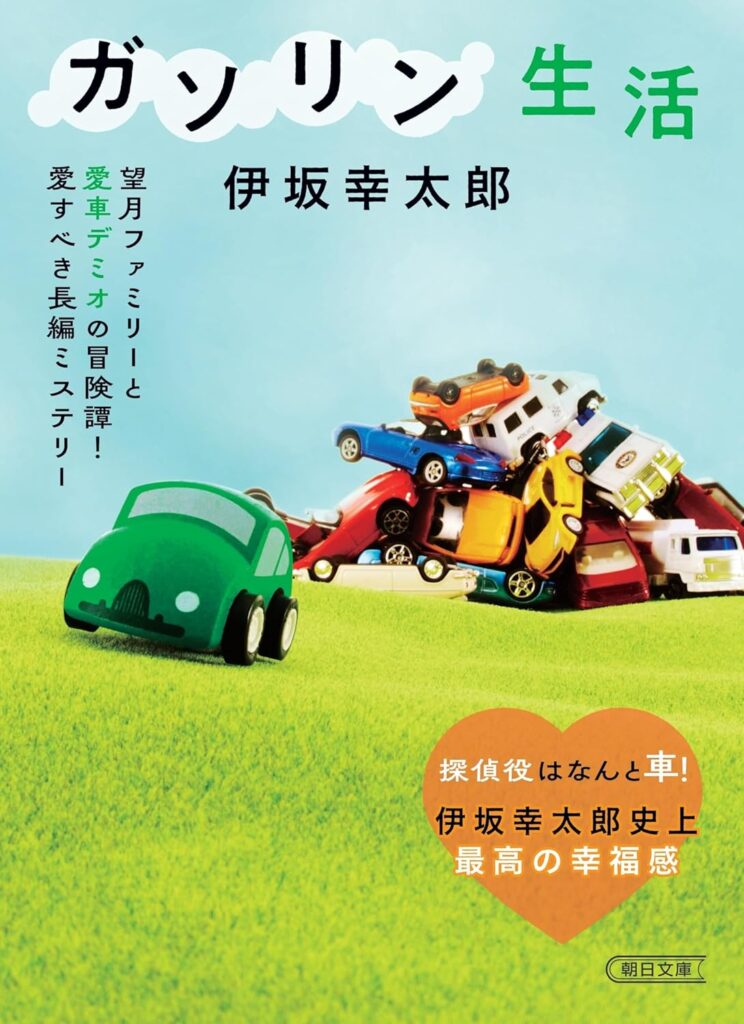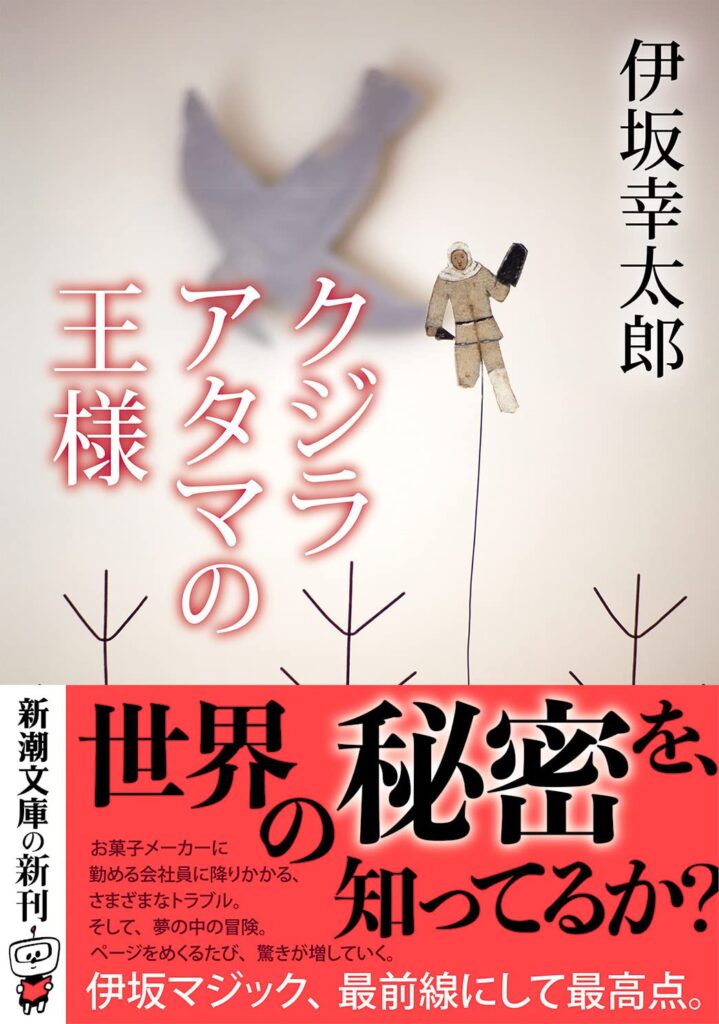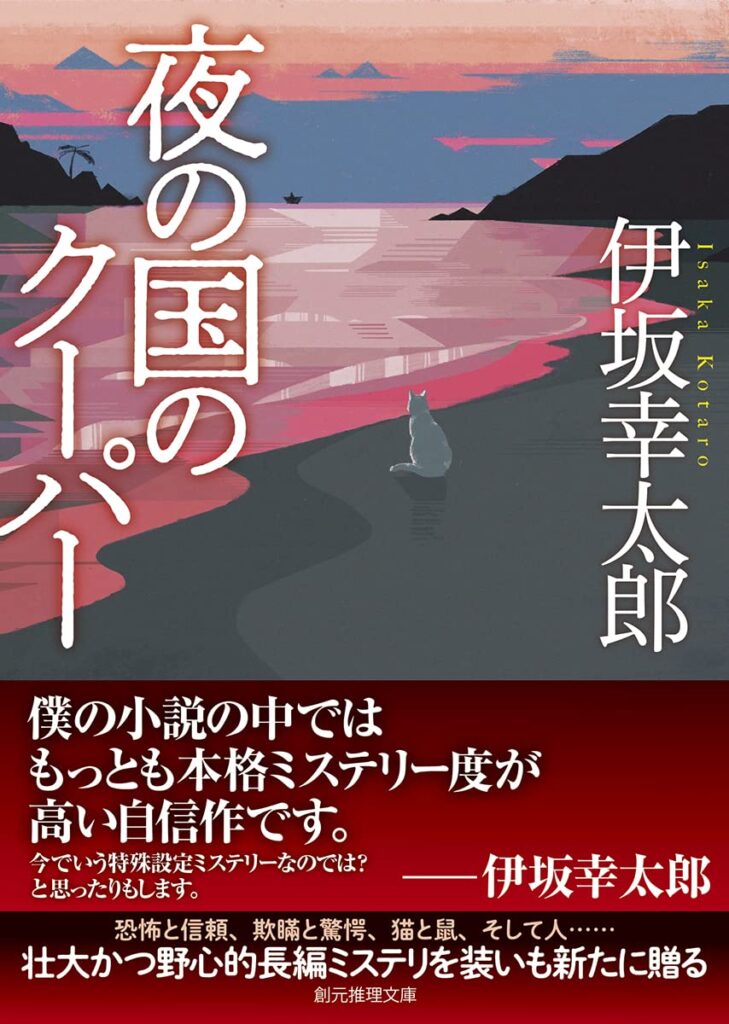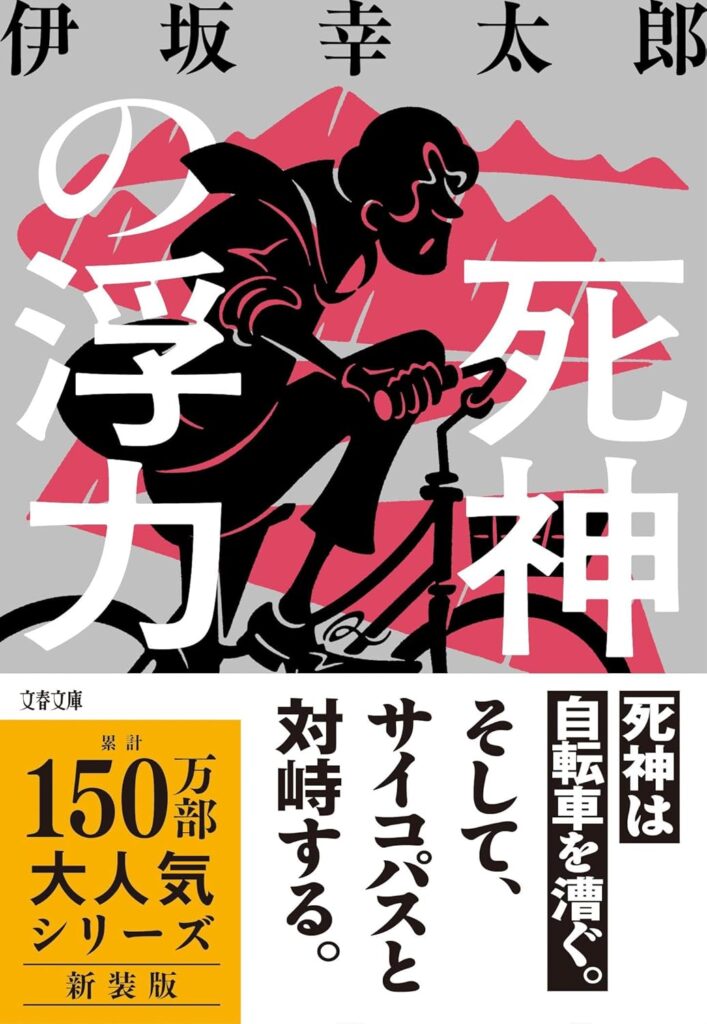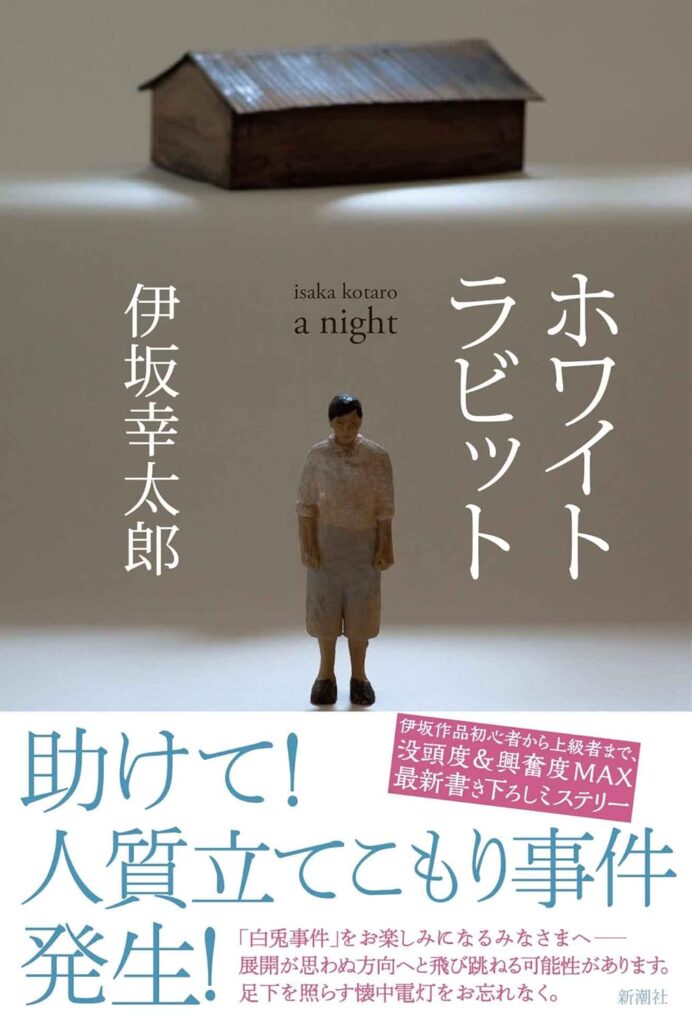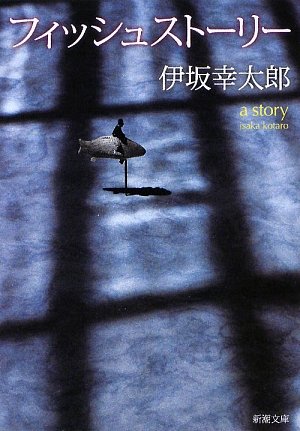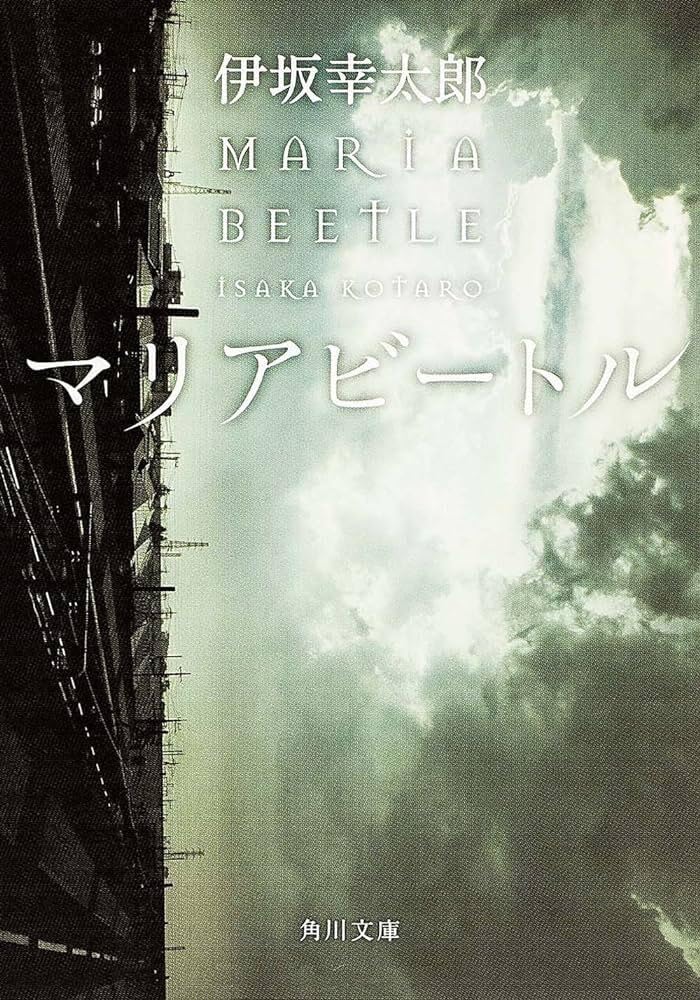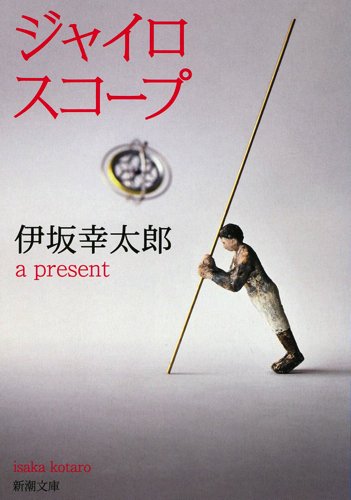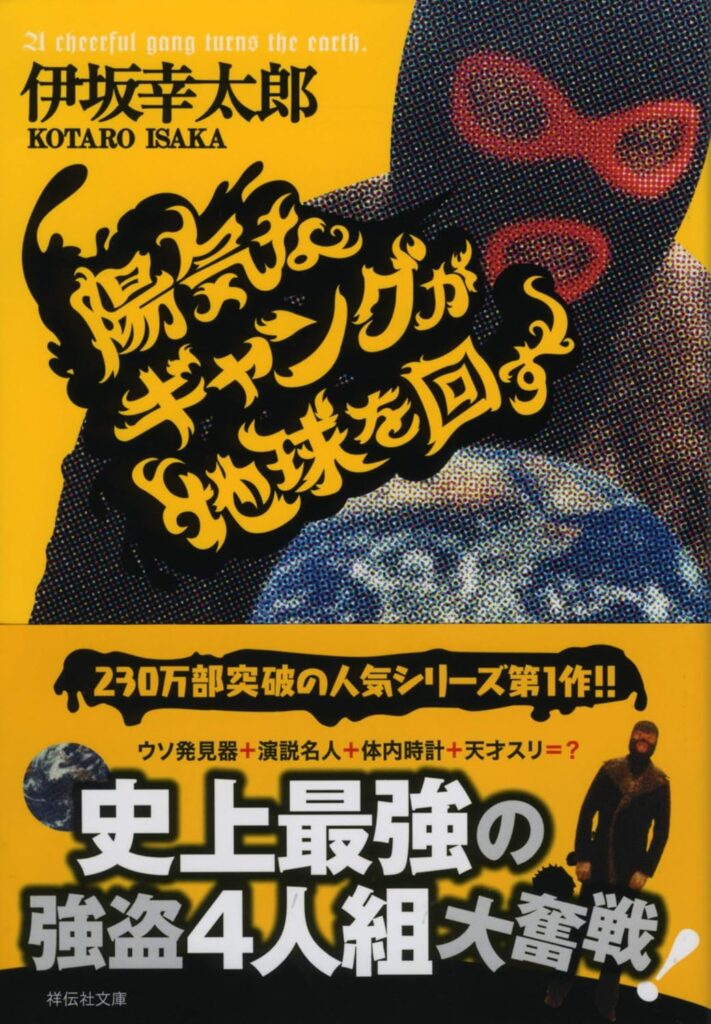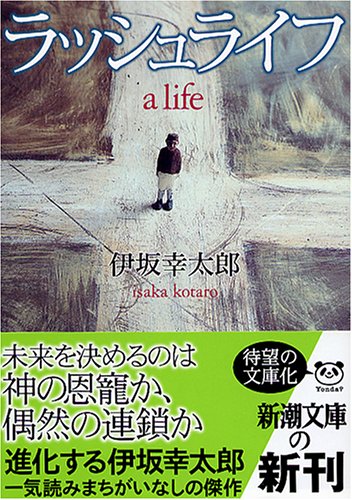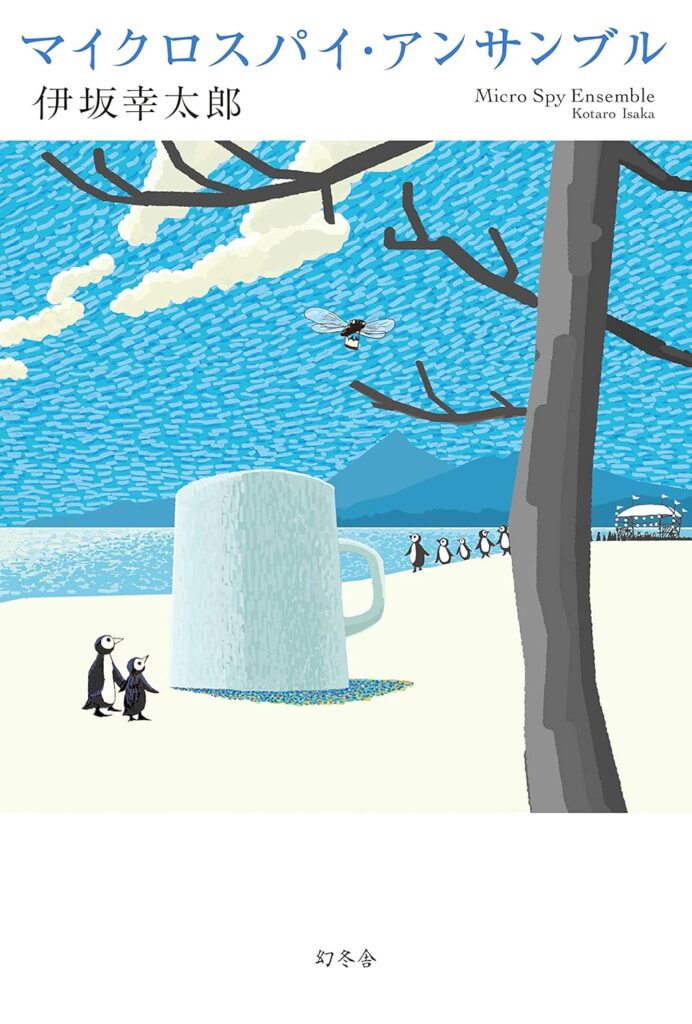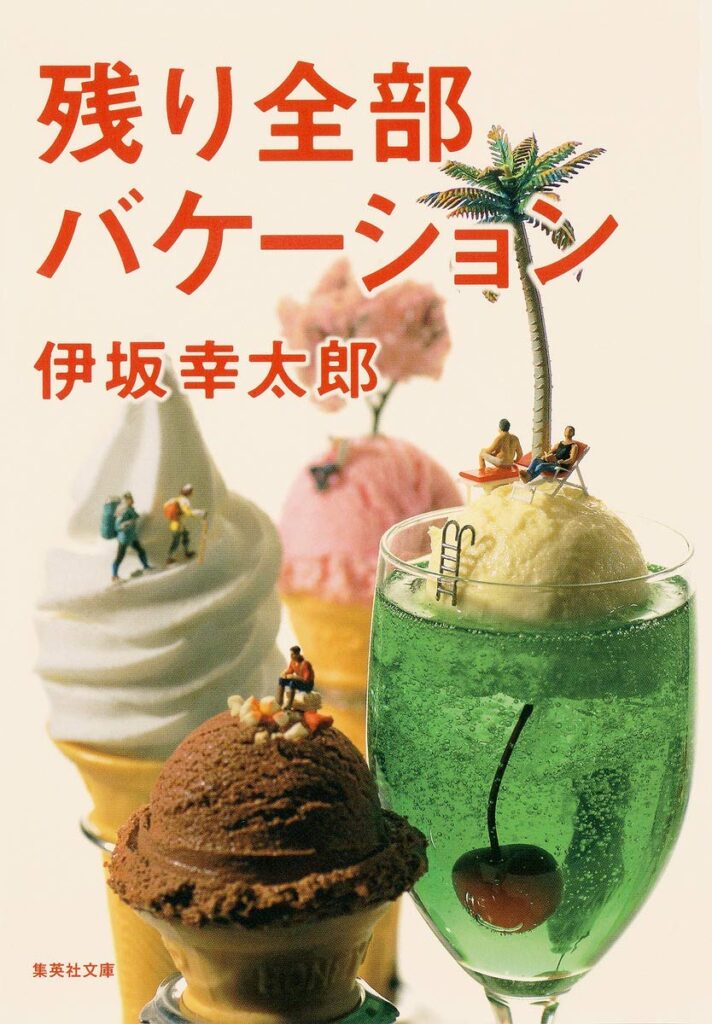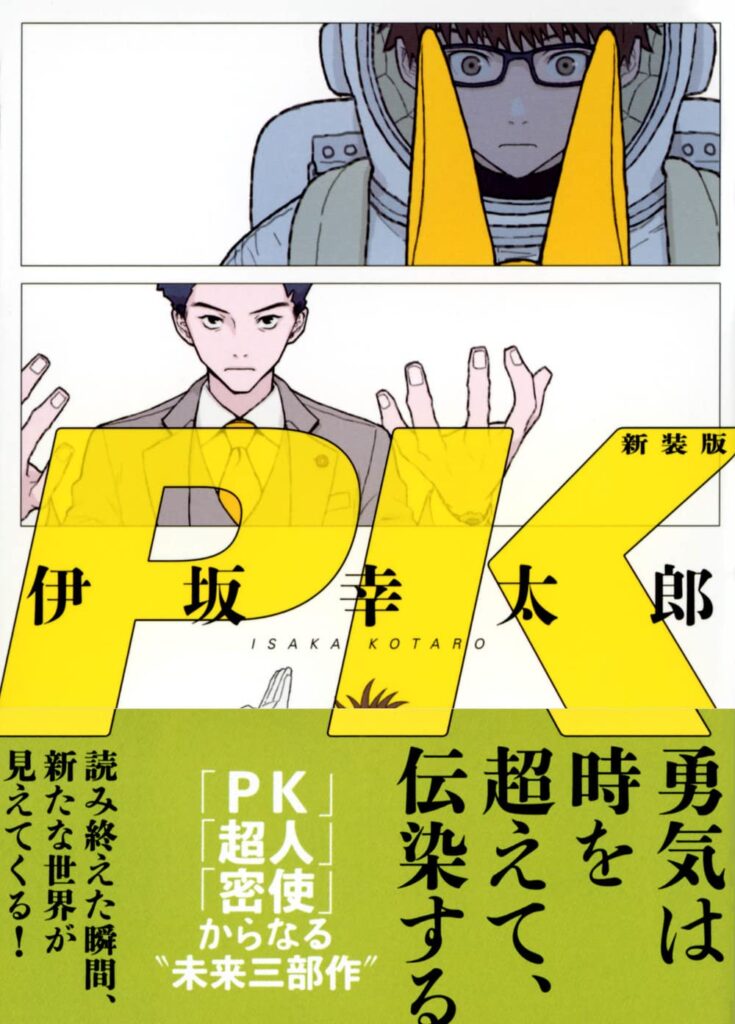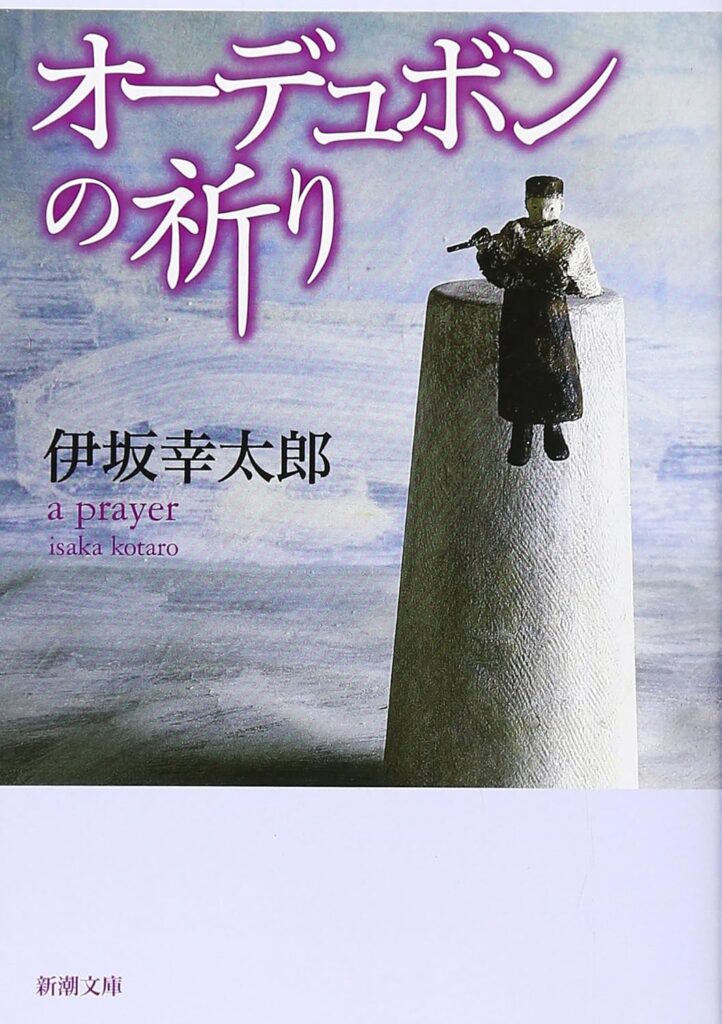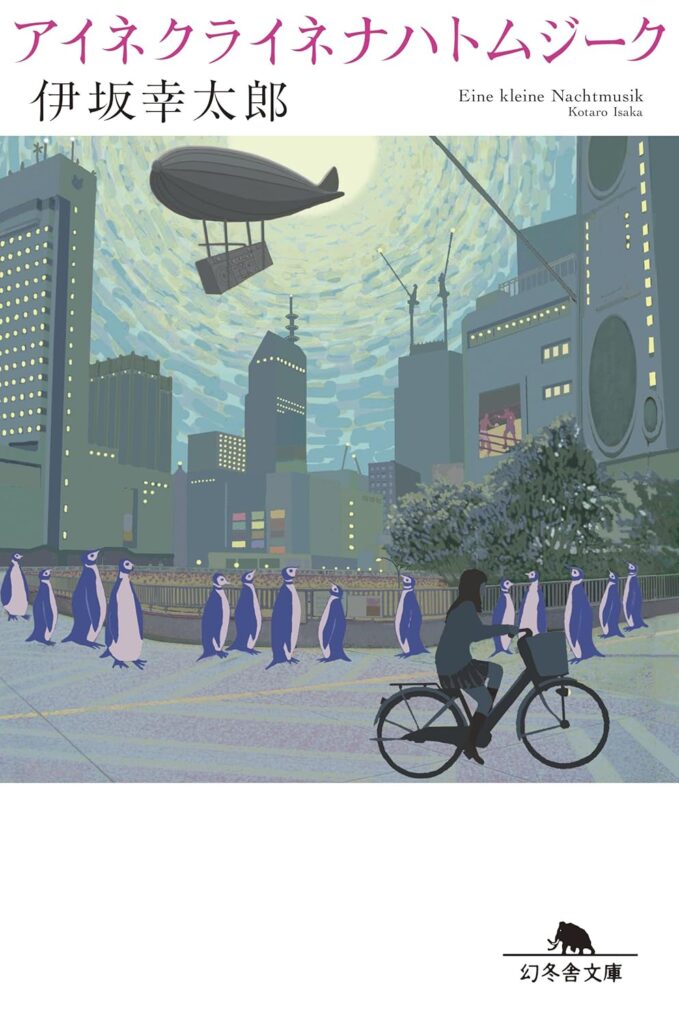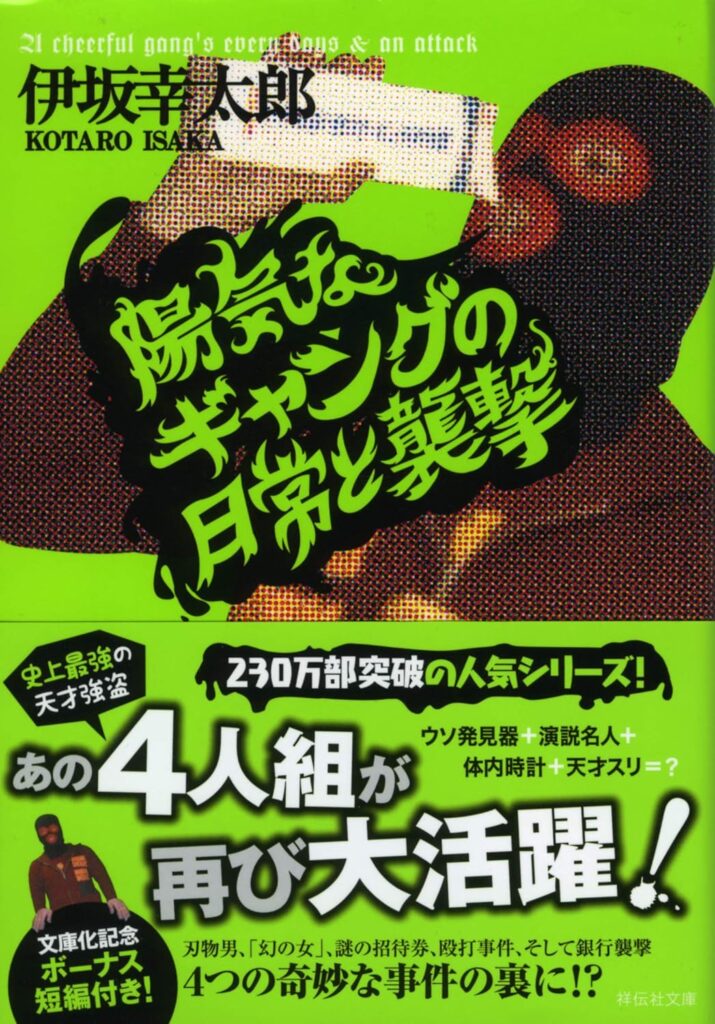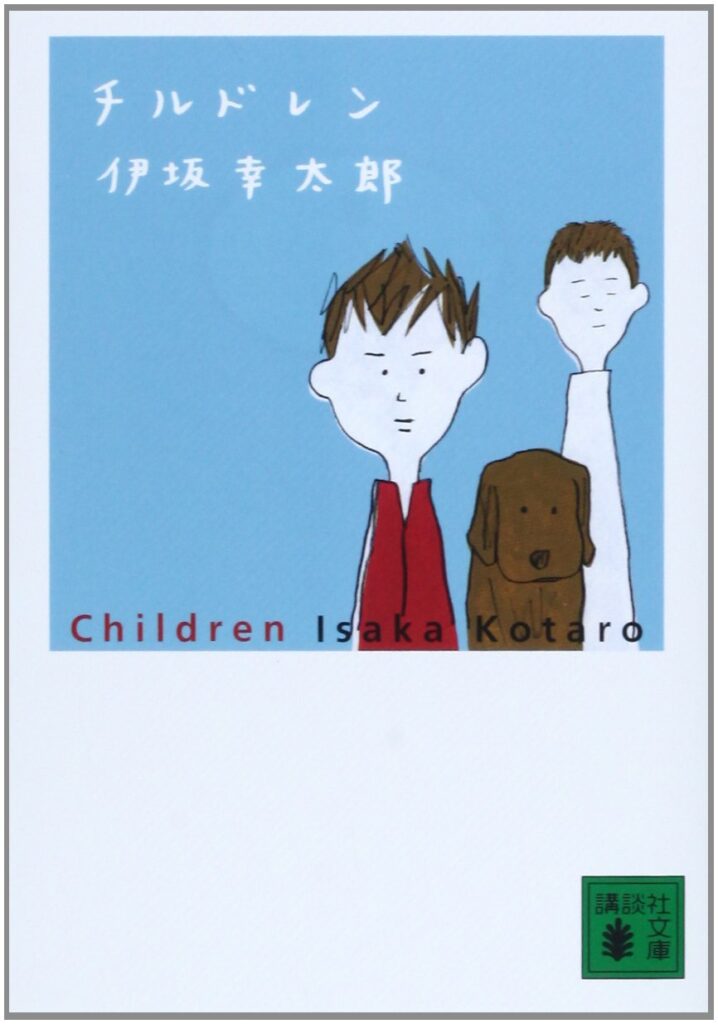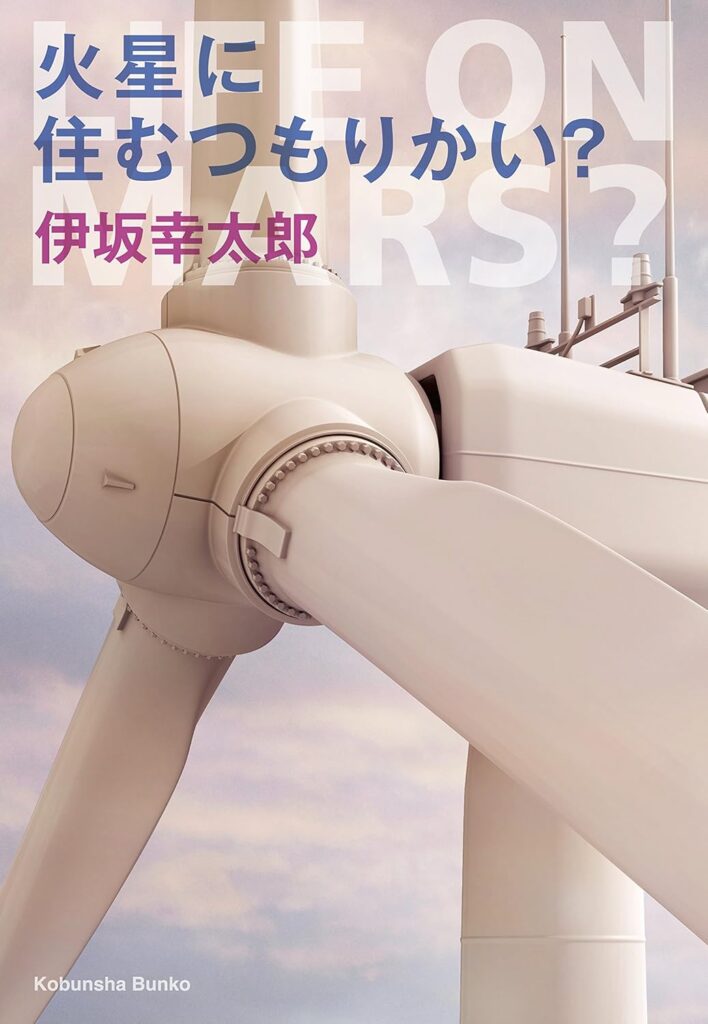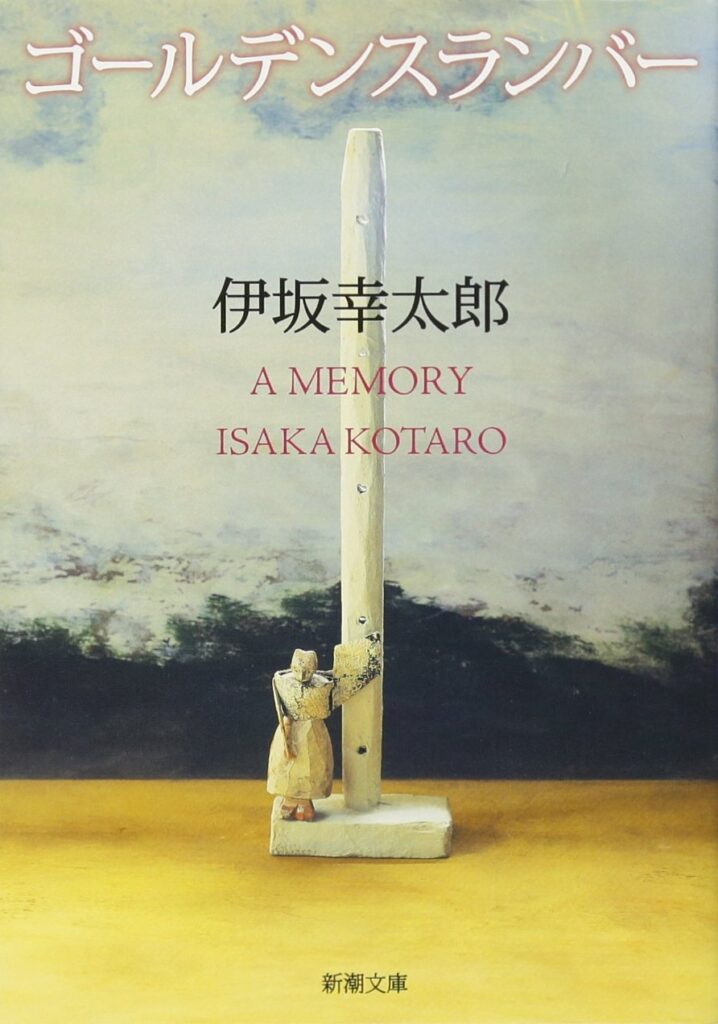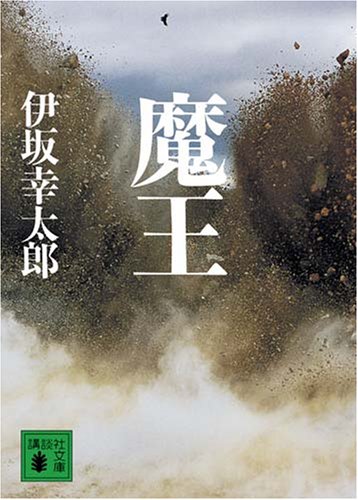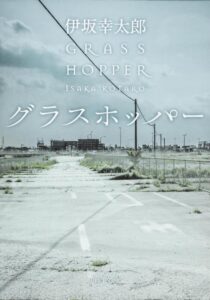 小説「グラスホッパー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「グラスホッパー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
伊坂幸太郎さんの手によるこの物語は、読む者の心を掴んで離さない魅力を持っています。平凡な日常を送っていたはずの男が、愛する人を失ったことをきっかけに、裏社会の渦へと巻き込まれていく様は、息もつかせぬ展開の連続です。
物語には、元教師の鈴木のほかに、人の心を操り自死へと導く力を持つ鯨や、若く腕の立つ殺し屋である蝉といった、個性的で忘れがたい面々が登場します。彼らの思惑が複雑に絡み合い、予測不能な出来事が次々と起こります。この記事では、物語の詳しい流れと結末に触れながら、その世界観や登場人物たちの生き様について、感じたことを詳しくお話ししていきます。
この物語が持つ独特の雰囲気や、登場人物たちが抱える葛藤、そして散りばめられた伏線が見事に回収されていく様を、ネタバレを含めてじっくりと解説します。読み終えた後に、きっとあなたも誰かとこの物語について語り合いたくなるはずです。それでは、一緒に「グラスホッパー」の世界へ足を踏み入れてみましょう。
小説「グラスホッパー」のあらすじ
物語は、元中学校教師の鈴木が、ハロウィンの夜に起きた轢き逃げ事故で最愛の妻を亡くすところから始まります。深い悲しみと怒りに駆られた鈴木は、犯人への復讐を決意。犯人が裏社会の組織「フロイライン」に関わる寺原という男の息子であることを突き止め、組織への潜入を図ります。しかし、フロイラインは表向きの顔とは裏腹に、危険な取引を行う闇の企業でした。鈴木はそこで、先輩社員の比与子から厳しい試練を与えられ、疑いの目を向けられながらも、復讐の機会をうかがいます。
ある時、鈴木は比与子の命令で拉致された若い男女を殺すよう迫られます。追い詰められた鈴木でしたが、その場に現れた寺原の息子が、何者かに突き飛ばされて車に轢かれるという衝撃的な事件が発生します。鈴木は、息子を突き飛ばした犯人、通称「押し屋」を追跡。その過程で、自殺専門の殺し屋「鯨」の存在を知ります。鯨は、人の心を絶望で満たし自ら死を選ばせる特殊な力を持っており、事件を目撃していました。鈴木は押し屋の居場所を突き止めますが、フロイラインのやり方を知る彼は、無実の人を巻き込む可能性を恐れ、すぐには報告しませんでした。
一方、ナイフ使いの殺し屋「蝉」は、雇い主の岩西から、寺原長男の事件を受けて業界が騒がしくなっていること、そして「鯨」を始末する依頼が入ったことを聞かされます。しかし、蝉が遅刻した間に、依頼人である政治家の梶は鯨によって自殺に追い込まれていました。失敗を取り戻したい蝉は、寺原長男を轢いた「押し屋」の情報を掴み、その始末に向かいます。その頃、鈴木は押し屋「槿」に家庭教師として接近し、その正体を探ろうとしていました。槿の家族との交流の中で、鈴木の心は揺れ動きますが、復讐の意志は変わりません。
やがて、それぞれの追跡と策略が交錯します。鈴木は比与子の罠にかかり拉致されますが、そこへ蝉が現れ、鈴木を助けます。しかし、脱出を図る鈴木と蝉を、鯨が待ち伏せていました。鯨は蝉を殺害。その後、槿に助けられた鈴木は、槿とその家族が「劇団」と呼ばれるプロの偽装集団であり、すべてが仕組まれていたことを知ります。鯨は槿の家に現れますが、幻覚に苛まれ、最後は自らが交通事故に遭い命を落とします。多くの死を経て、復讐の連鎖から解放された鈴木は、妻の指輪を見つけ出し、過去を乗り越えて新たな人生を歩み始めることを決意するのでした。
小説「グラスホッパー」の長文感想(ネタバレあり)
伊坂幸太郎さんの「グラスホッパー」を読み終えた時、まず感じたのは、ジェットコースターのような疾走感と、張り詰めた空気感でした。物語は、愛する妻を理不尽な形で失った男・鈴木の復讐譚として幕を開けますが、読み進めるうちに、単なる復讐劇ではない、もっと深く、そして複雑な人間模様が描かれていることに気づかされます。
物語の中心人物である鈴木は、元々はごく普通の、むしろ少し気弱な中学校教師です。そんな彼が、妻の死をきっかけに、裏社会という未知の世界へ足を踏み入れていく。その過程で描かれる彼の葛藤や恐怖、そして心の変化が、非常に丁寧に描写されていると感じました。フロイラインという怪しげな会社に潜入し、比与子のような得体の知れない人物たちと渡り合う中で、鈴木は決して「強い人間」に変貌するわけではありません。むしろ、彼は最後まで恐怖や迷いを抱えながら、それでも目的のために必死に行動します。この等身大の主人公像が、読者である私たちが物語に感情移入しやすくなる大きな要因ではないでしょうか。
特に印象的だったのは、鈴木が「押し屋」である槿とその家族と接触する場面です。槿の家で、家庭教師として振る舞いながら彼の正体を探ろうとする鈴木。しかし、そこには偽りではあっても、穏やかな家庭の風景が広がっています。息子の健太郎とサッカーをするシーンや、妻のすみれの手料理を囲む場面では、鈴木の中に眠っていた、失われた日常への郷愁のような感情が垣間見えます。復讐という暗い目的を抱えながらも、人の温かさに触れてしまう。この矛盾した状況が、鈴木の人間性をより深く描き出しているように思えました。そして、後にこの家族が「劇団」と呼ばれるプロの偽装集団であったことが明かされる展開には、本当に驚かされました。鈴木が感じていた温かささえも計算されたものであったかもしれない、という事実に、一種の物悲しさを感じずにはいられません。
そして、この物語を彩るもう二人の重要な登場人物が、殺し屋の「鯨」と「蝉」です。
鯨は、巨漢で寡黙な男ですが、その内面には深い孤独と、死への独特な哲学を抱えています。彼の持つ「相手を絶望させ、自殺に追い込む」という能力は、物理的な暴力とは異なる、精神的な恐ろしさを持っています。彼が仕事の依頼を受ける中で垣間見える人間たちの弱さや醜さ、そして彼自身が抱える幻覚(亡霊)との対話は、物語に哲学的な深みを与えています。鯨がなぜこのような能力を持ち、なぜ自殺幇助という仕事をしているのか、その背景は多く語られませんが、彼の存在は「生と死」というテーマを読者に問いかけてくるようです。彼が最期に、自らが引き起こしてきた死の連鎖に巻き込まれるかのように、交通事故で呆気なく命を落とす場面は、因果応報という言葉を思い起こさせると同時に、彼の抱えていた苦悩からの解放のようにも見え、複雑な気持ちになりました。
一方の蝉は、若く、ナイフ使いの殺し屋です。彼は一見すると軽薄で、仕事に対してもどこか投げやりな態度を見せることがあります。雇い主である岩西との軽妙な、それでいてどこか乾いたやり取りは、物語の緊張感を和らげるアクセントにもなっています。しかし、その裏にはプロとしての矜持と、岩西への複雑な感情が見え隠れします。蝉が水戸での一家惨殺を「軽い気持ちで」行ったと語る場面は、彼の非情さを際立たせますが、同時に、彼がそのような生き方しかできない、ある種の哀しみのようなものも感じさせます。特に、岩西との関係性は、派生作品である「Waltz」を読むとより深く理解できる部分ですが、この「グラスホッパー」単体でも、二人の間にある種の信頼やつながりのようなものが描かれていると感じます。それだけに、蝉が鯨にあっけなく殺されてしまう展開は衝撃的でした。裏社会の非情さ、そして命の儚さを象徴するような出来事だったと言えるでしょう。
この物語の魅力は、鈴木、鯨、蝉という三者の視点が切り替わりながら進んでいく構成にもあります。それぞれの目的、それぞれの事情が交錯し、一つの事件(寺原長男の事故)を軸に、運命が複雑に絡み合っていく。まるで操り人形が複雑な糸で結ばれているかのように、彼らは互いに影響を与え合い、予期せぬ方向へと物語は転がっていきます。読者は、それぞれの視点から断片的な情報を得ることで、徐々に全体像を掴んでいくことになりますが、最後まで全貌が見えないもどかしさ、そしてそれが明らかになった時の驚きが、この作品の大きな推進力となっています。
伊坂作品に特徴的な、会話の中に散りばめられたウィットや、ちょっとした豆知識、そして伏線の巧みさも健在です。岩西が口にするジャック・クリスピンの言葉や、鈴木が思い出す妻との会話など、何気ないやり取りが後の展開に繋がっていたり、物語のテーマを暗示していたりします。特に、槿の家での会話や、フロイラインでの出来事など、後から振り返ると「ああ、あれはそういう意味だったのか」と気づかされる仕掛けが多く、再読することで新たな発見がある作品だと感じました。
終盤の展開は、まさに怒涛という言葉がふさわしいです。鈴木が拉致され、蝉が助けに入り、そこに鯨が現れる。槿一家の正体が明かされ、スズメバチと呼ばれる別の殺し屋の存在が示唆され、寺原の死が告げられる。そして、鯨と鈴木の最後の対峙。目まぐるしく状況が変わる中で、多くの登場人物が命を落としていきます。この容赦のない展開は、裏社会の厳しさを描くと同時に、どこか寓話的な雰囲気も漂わせています。「未来は神様のレシピで決まる」という作中の言葉のように、人間の意志を超えた大きな力によって、物事が動いているような感覚さえ覚えます。
そして、物語の終わり。多くの死を経て、鈴木は生き残ります。復讐の対象であった寺原も、彼を裏切った比与子も、そして彼を翻弄した殺し屋たちも、皆いなくなりました。彼の復讐は、彼自身の手で果たされたわけではありません。しかし、彼は妻の形見である指輪を見つけ出し、過去と決別するかのように、新しい一歩を踏み出すことを決意します。この結末は、決して単純なハッピーエンドではありませんが、それでも微かな希望を感じさせるものでした。深い傷を負いながらも、生きていくことを選んだ鈴木の姿に、人間の持つ再生力のようなものを感じ取ることができました。
「グラスホッパー」は、殺し屋たちが登場するエンターテインメント性の高い作品でありながら、その根底には「生きること」「死ぬこと」「運命」「偶然」といった普遍的なテーマが流れているように思います。登場人物たちは、それぞれの理由で人を殺め、あるいは死に直面しますが、その姿を通して、私たちは自らの生や、日常の脆さについて考えさせられます。読み終えた後には、爽快感とともに、どこか切なく、そして深い余韻が残る。そんな不思議な魅力を持った一作でした。
まとめ
伊坂幸太郎さんの小説「グラスホッパー」は、妻を殺された元教師・鈴木の復讐劇を軸に、自殺専門の殺し屋・鯨、ナイフ使いの殺し屋・蝉といった個性的な登場人物たちの運命が交錯する物語です。裏社会の非情さや、予測不能な出来事の連続に、ページをめくる手が止まらなくなるでしょう。物語の詳しい流れや結末にも触れていますので、内容を深く知りたい方にもおすすめです。
鈴木の葛藤、鯨の持つ異質な能力と哲学、蝉の抱えるプロ意識と孤独感など、登場人物たちの内面が丁寧に描かれており、それぞれに感情移入してしまいます。彼らがどのように関わり合い、どのような結末を迎えるのか、その過程には多くの驚きが待っています。散りばめられた伏線が見事に回収されていく終盤の展開は、圧巻の一言です。
この物語は、単なるサスペンスやアクションに留まらず、「生と死」「運命」「偶然」といったテーマについても考えさせてくれます。読み終えた後には、物語の疾走感とともに、登場人物たちの生き様や、彼らが投げかける問いかけが心に残るはずです。手に汗握る展開と、深い余韻を味わいたい方に、ぜひ読んでいただきたい一冊です。