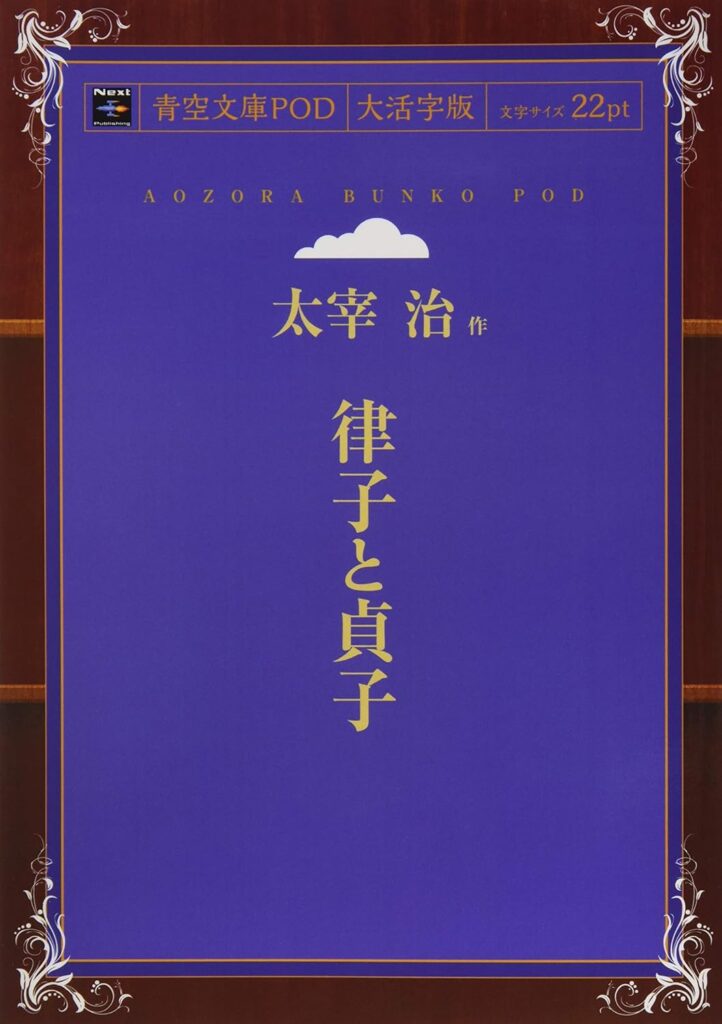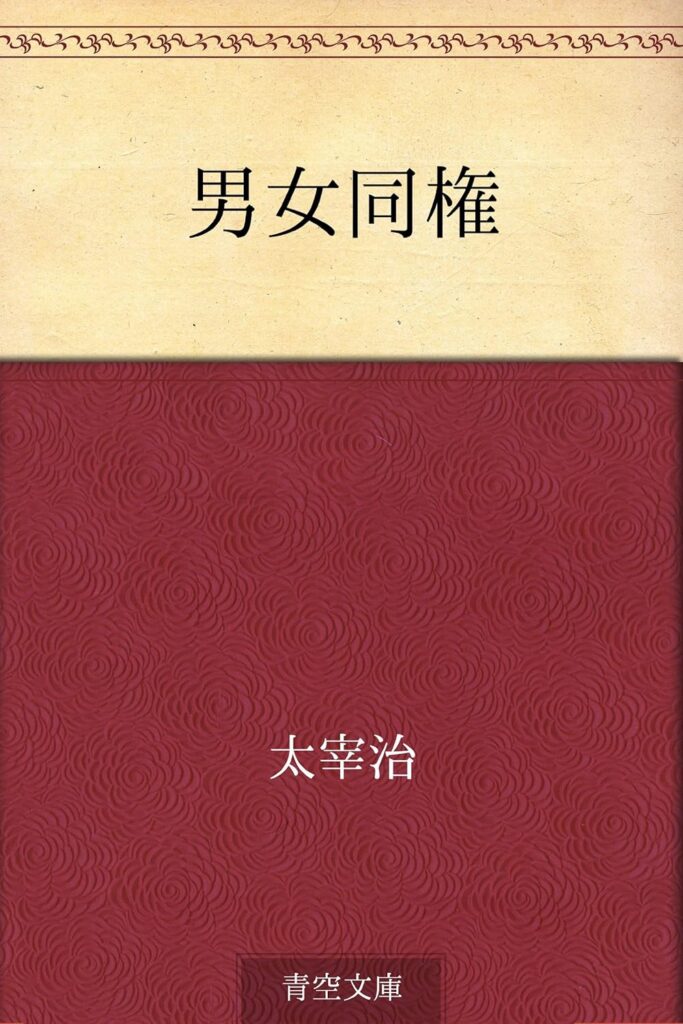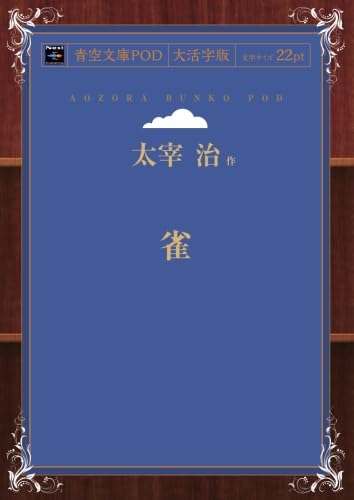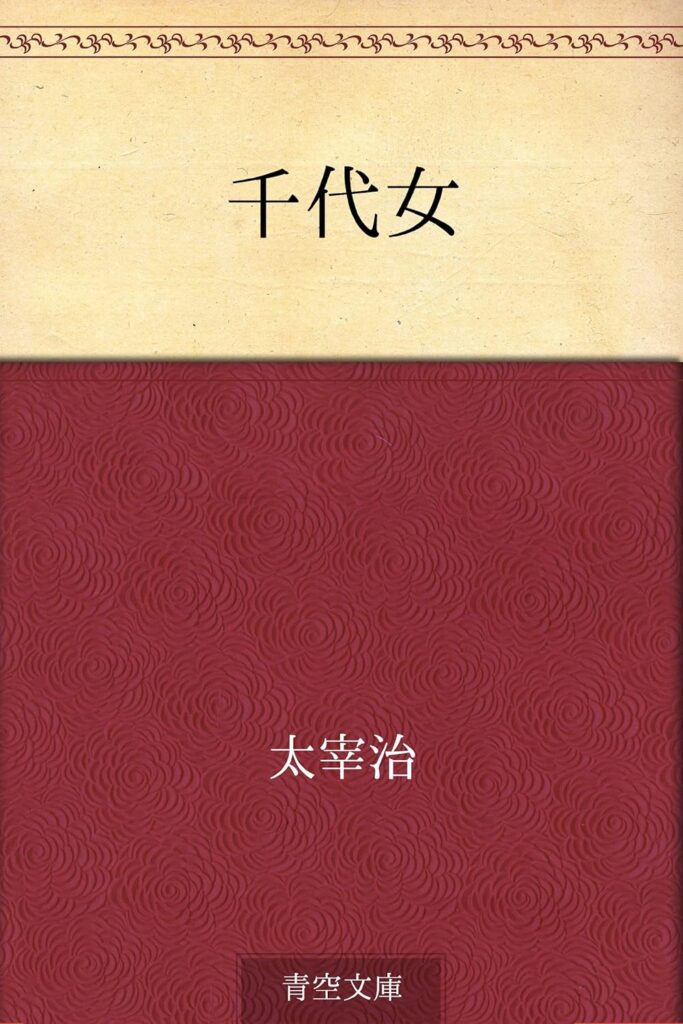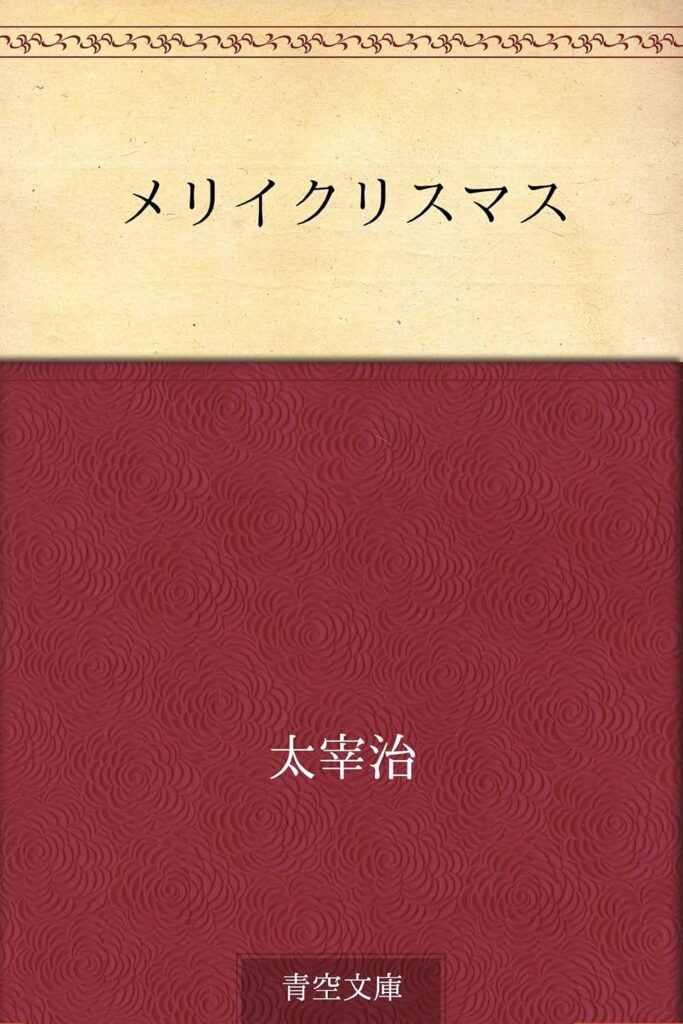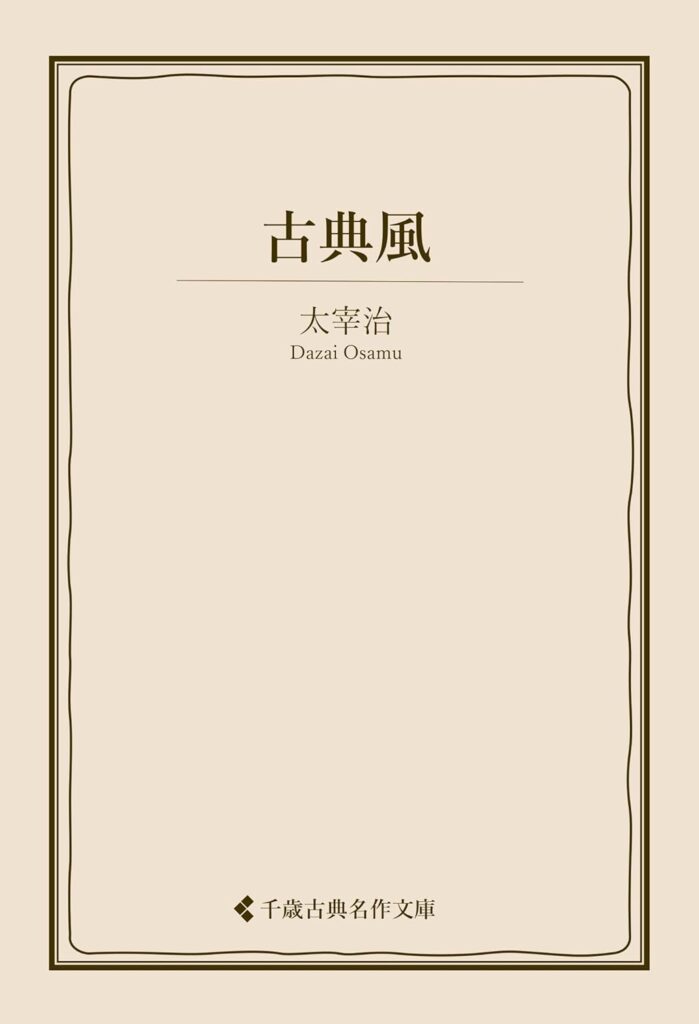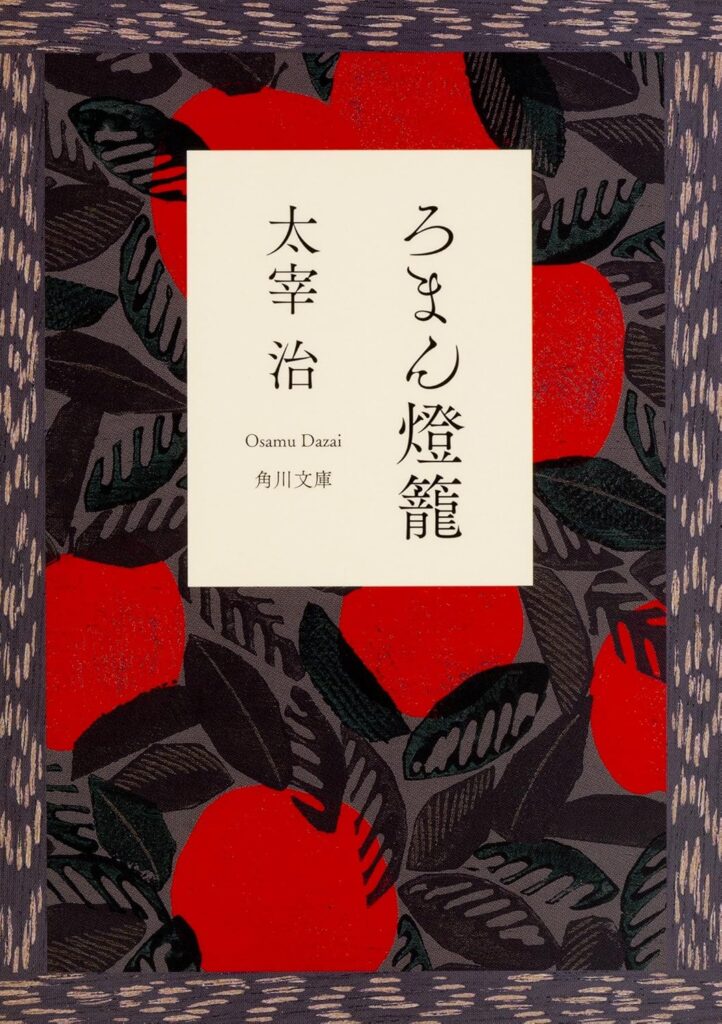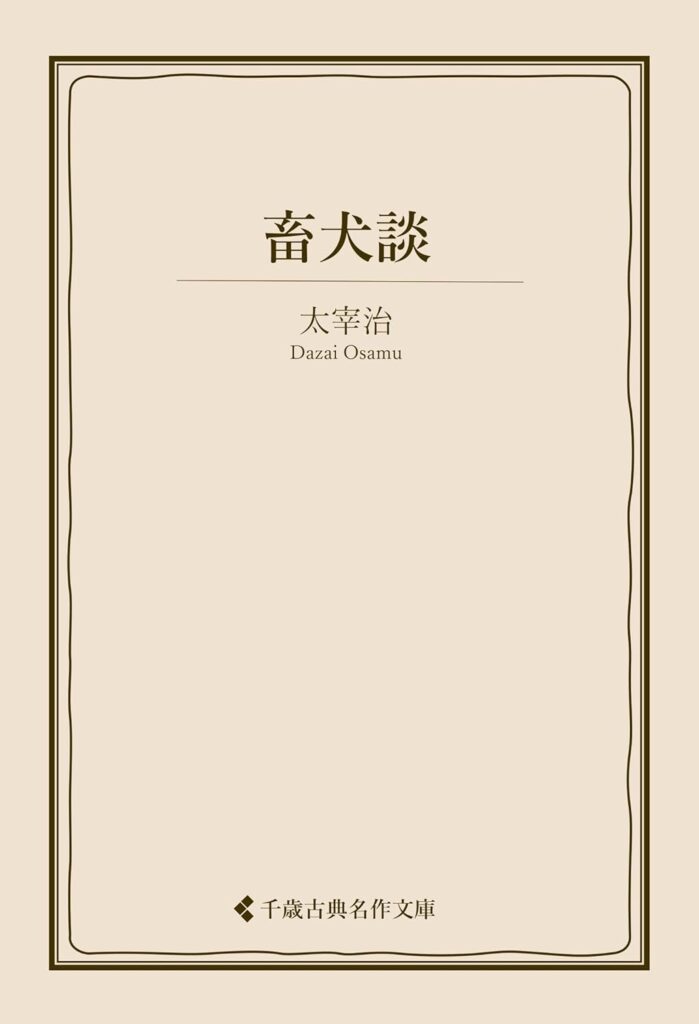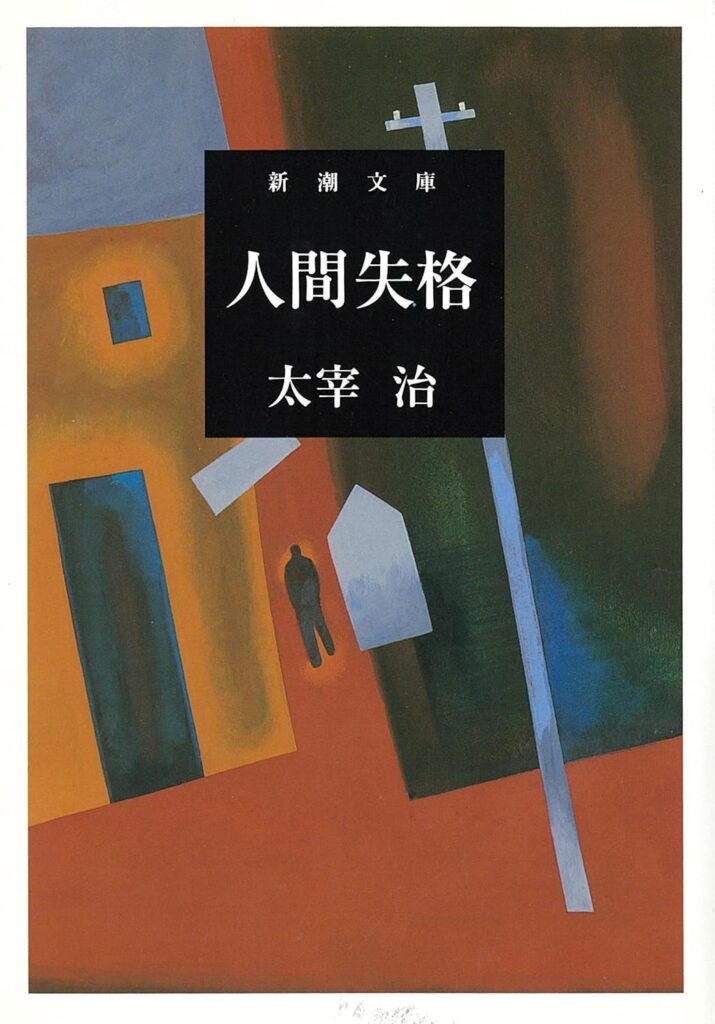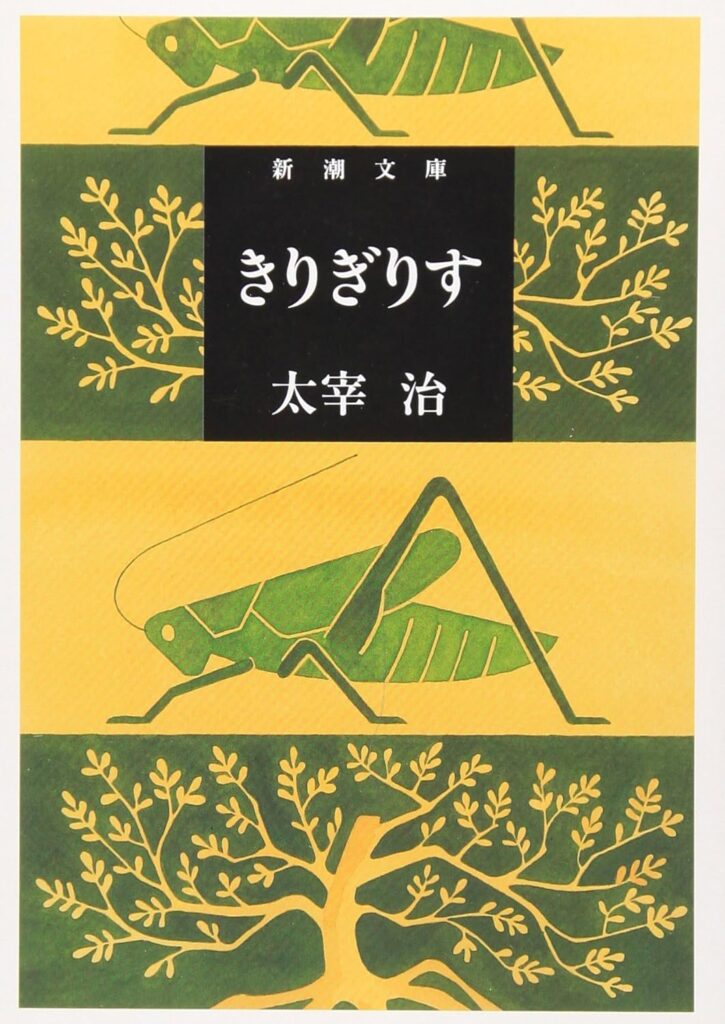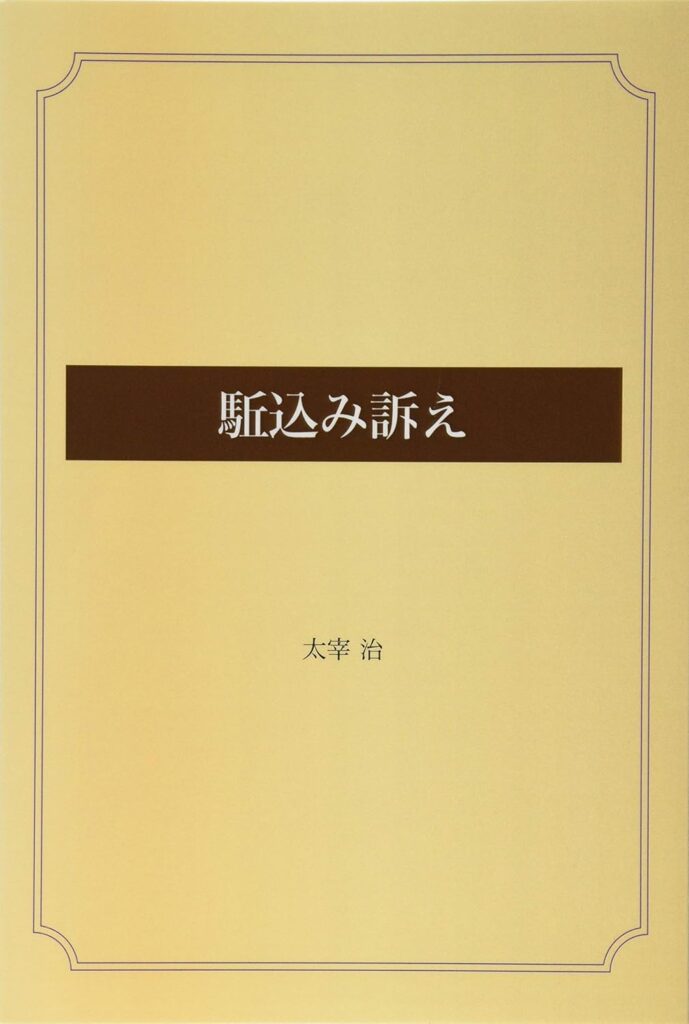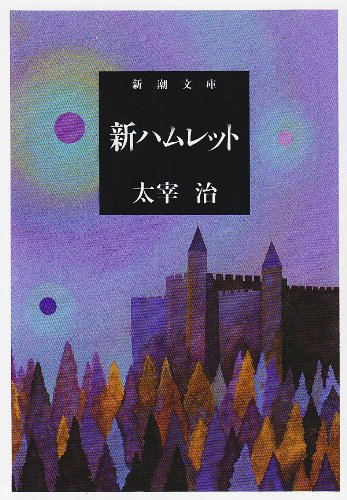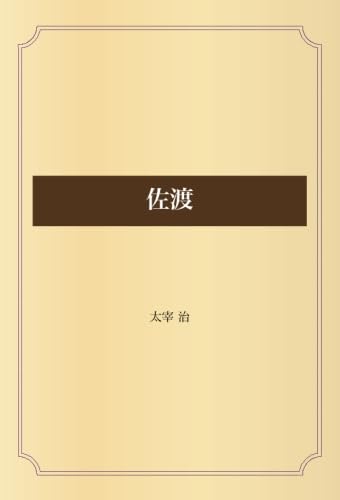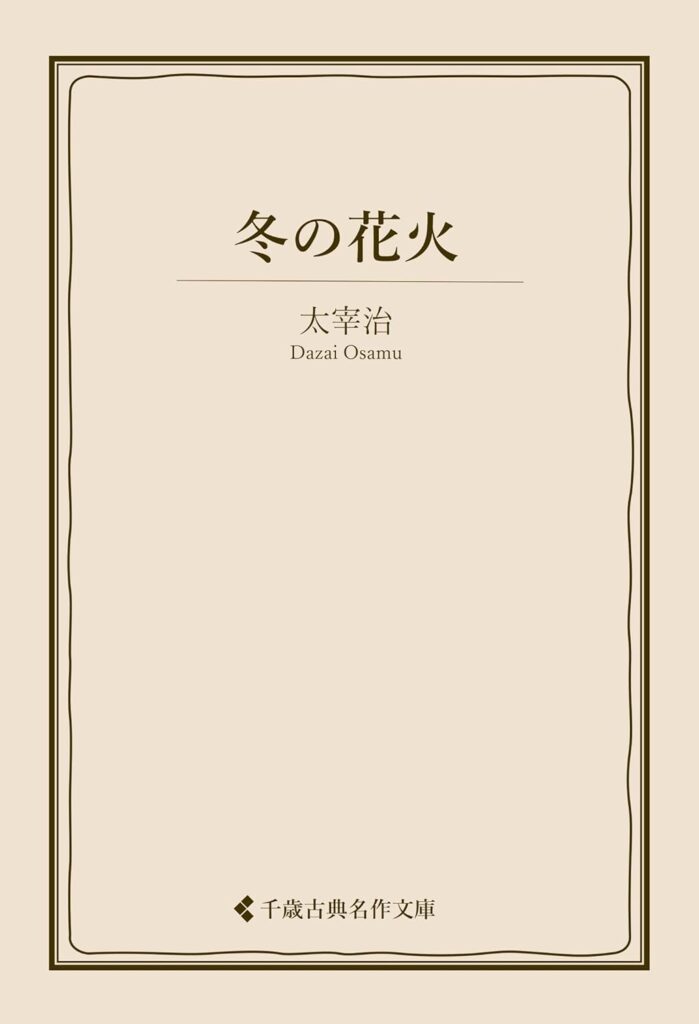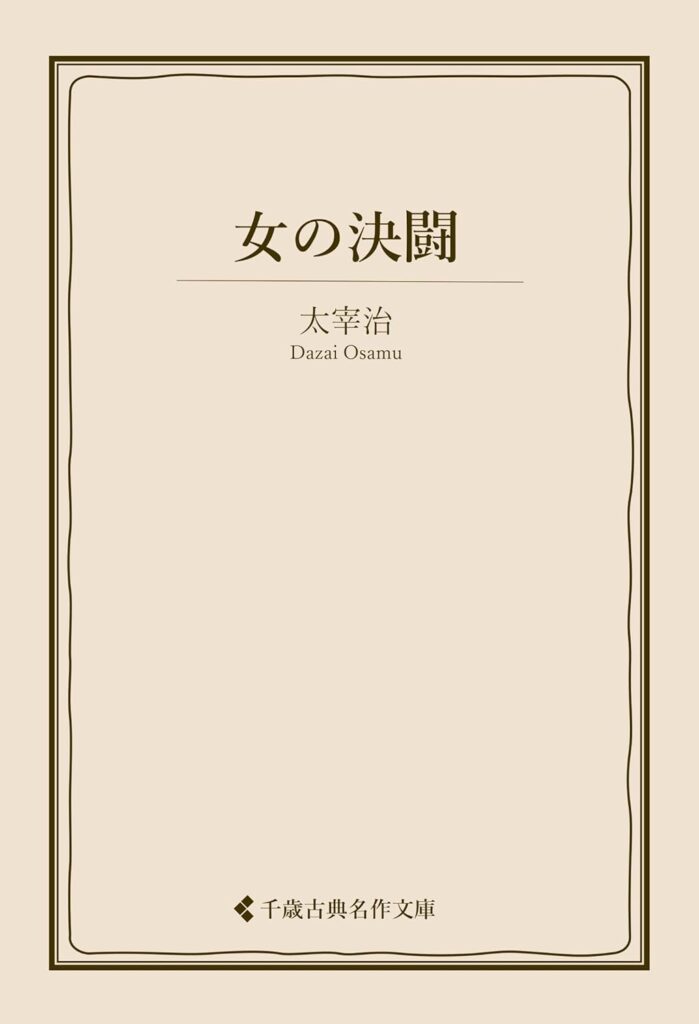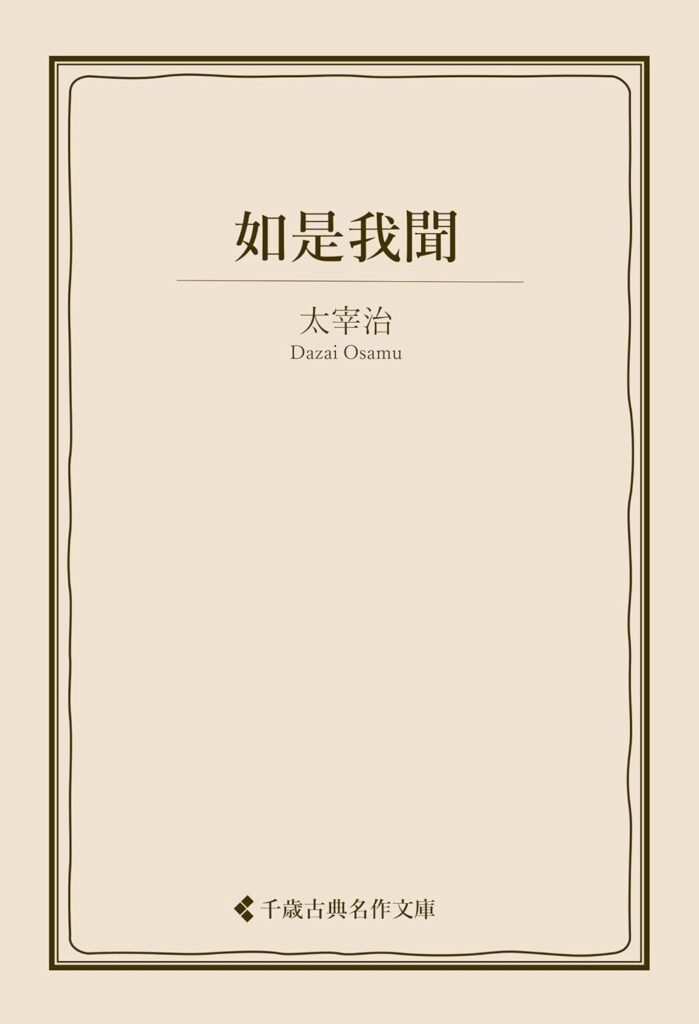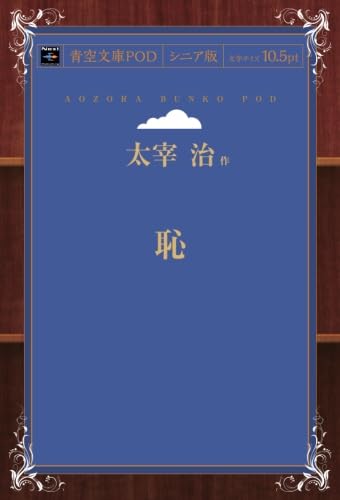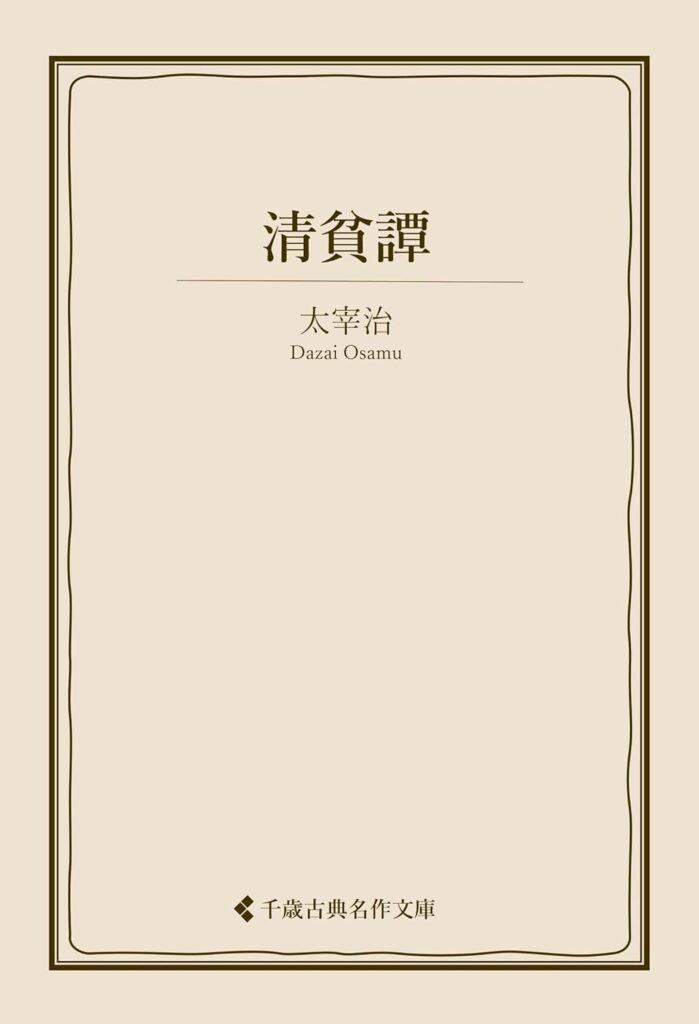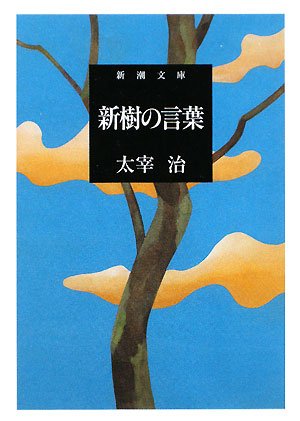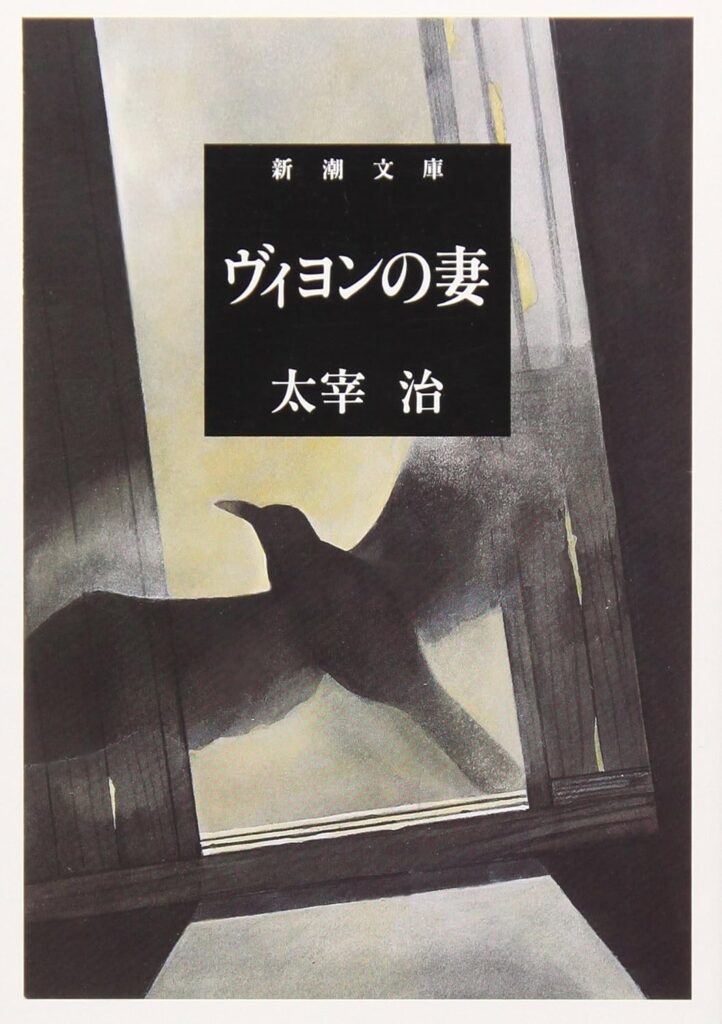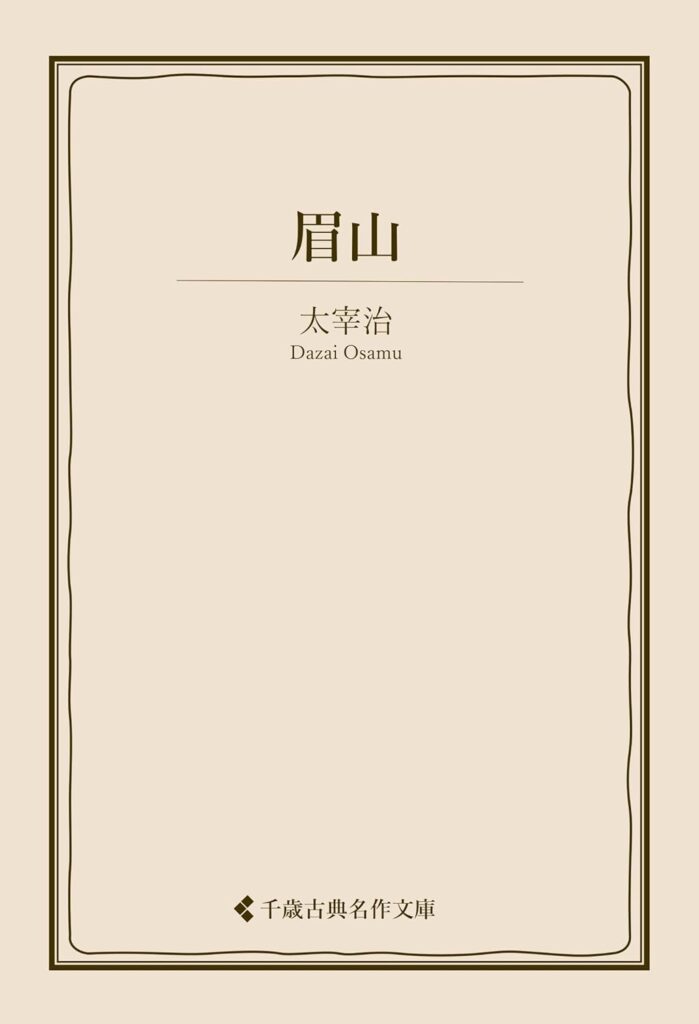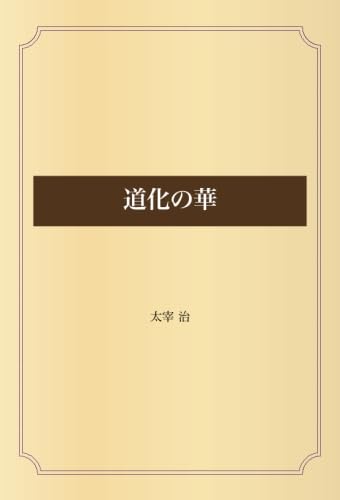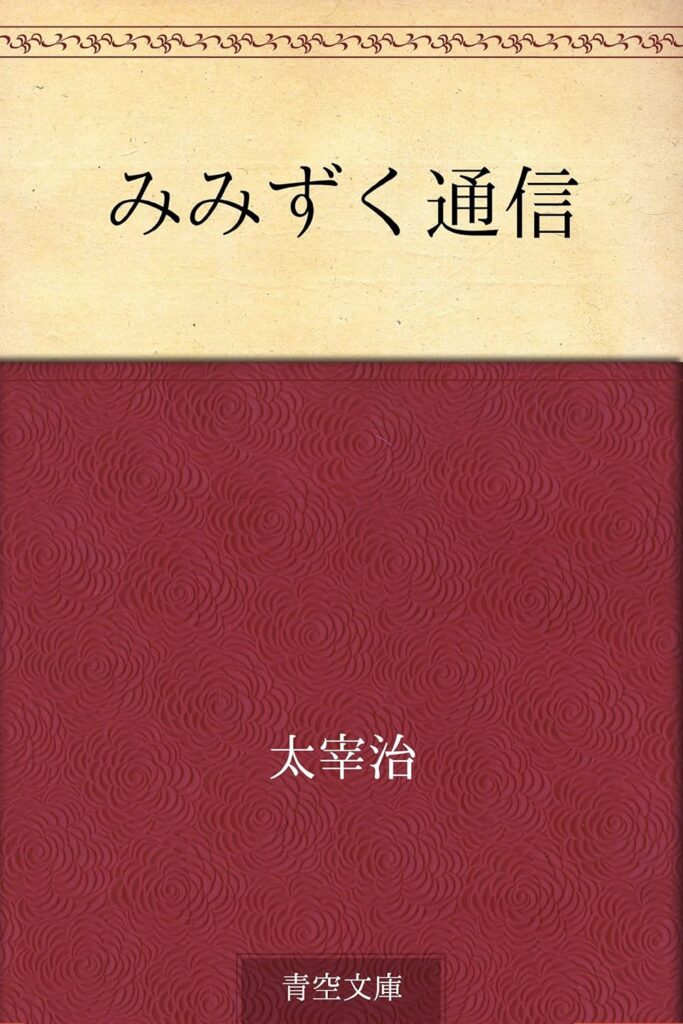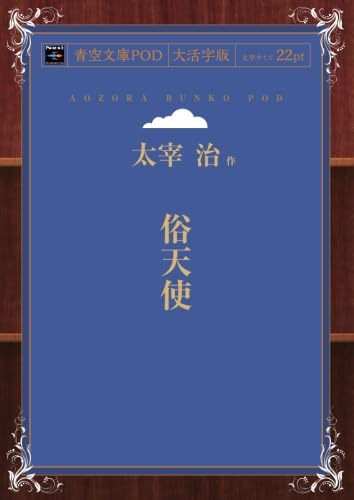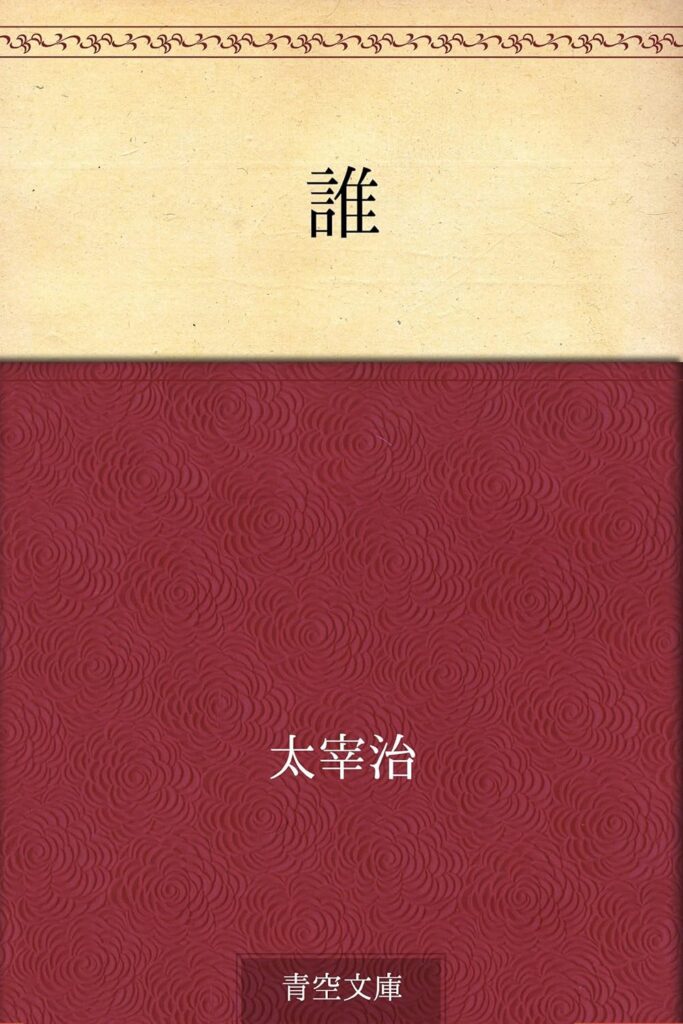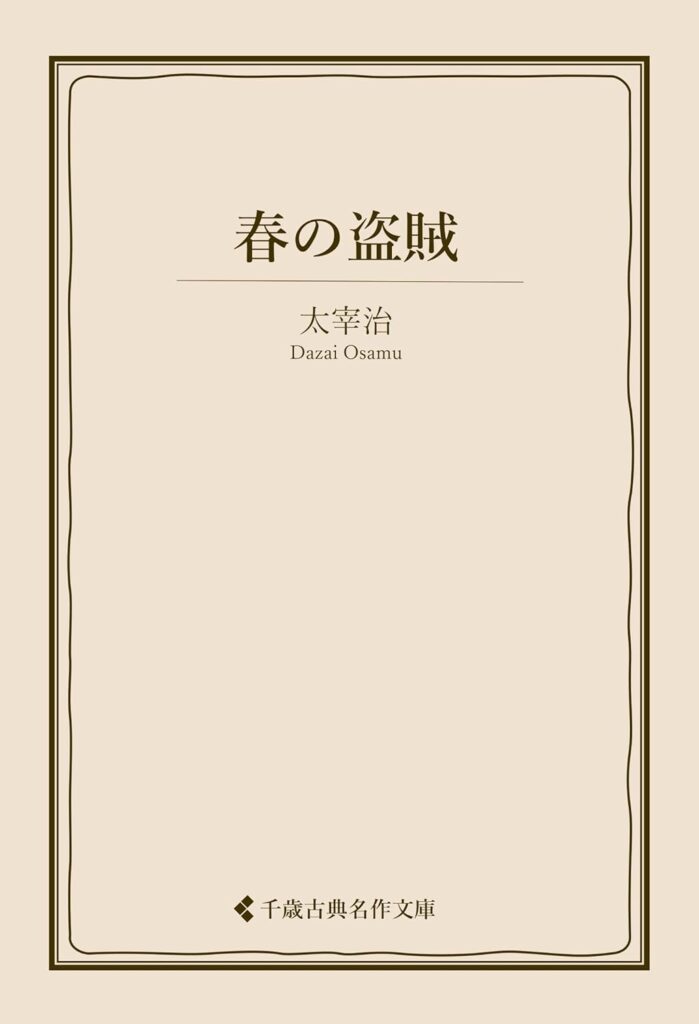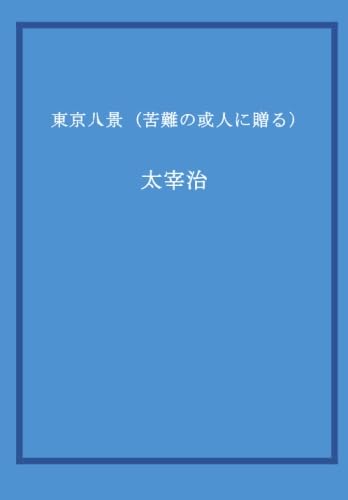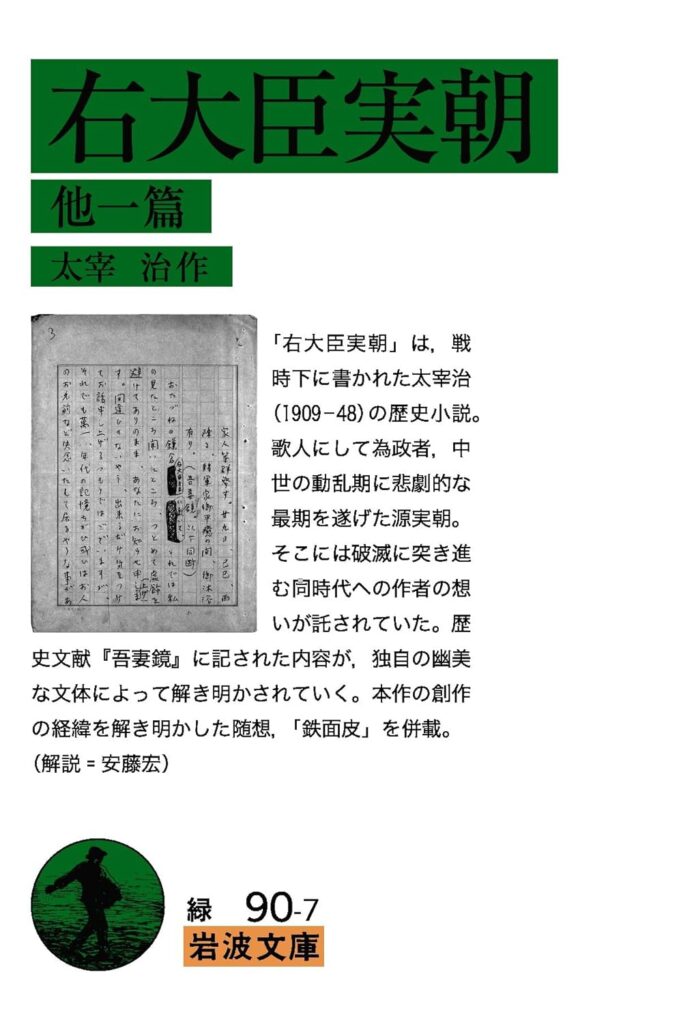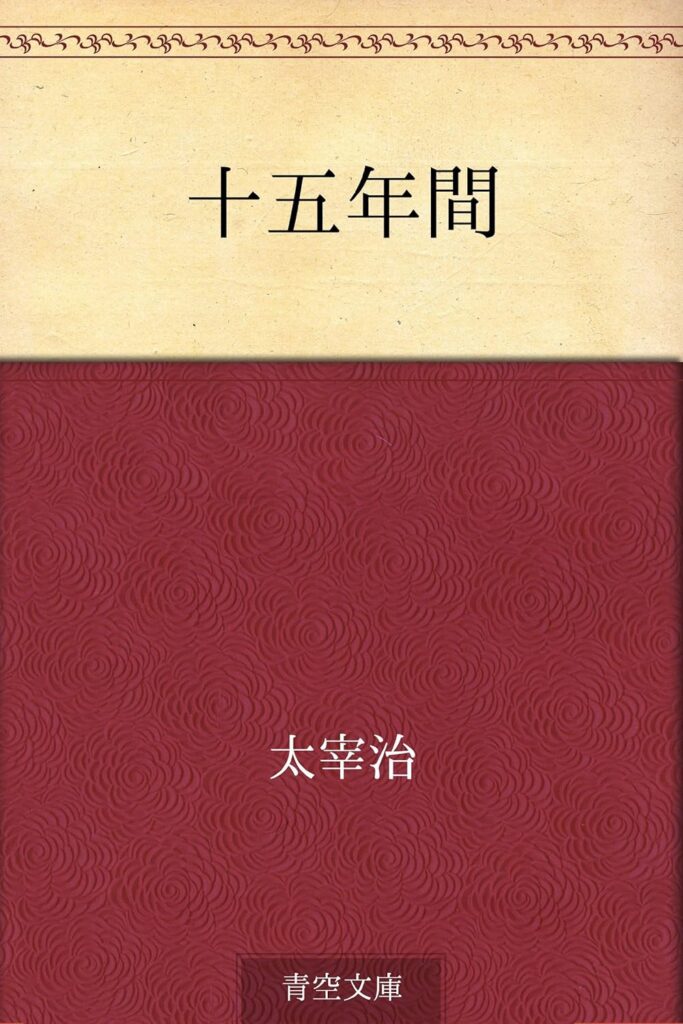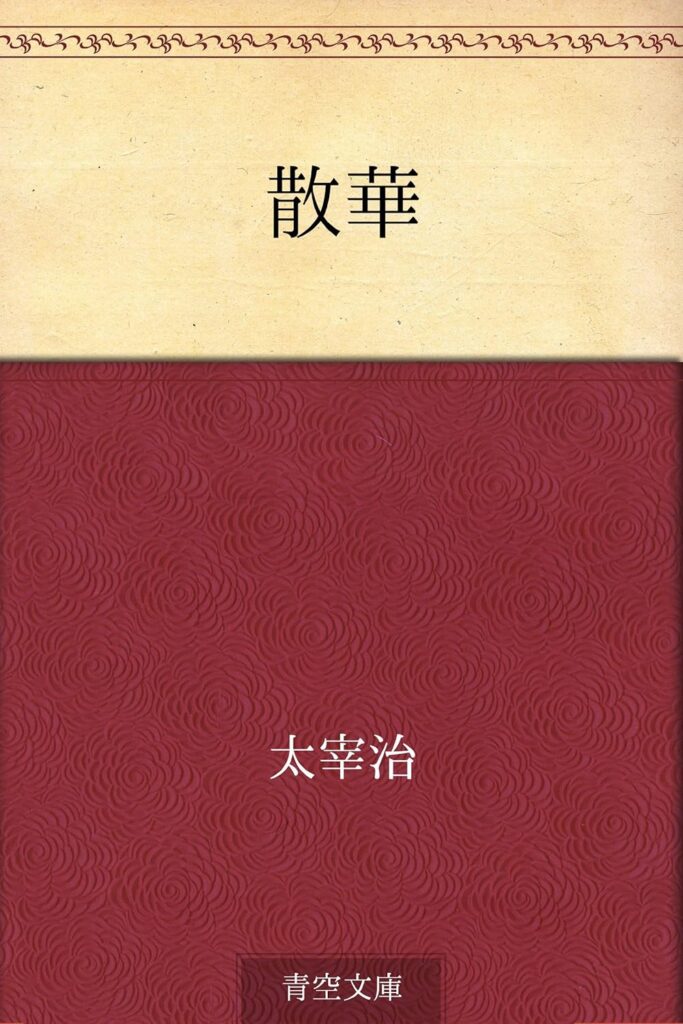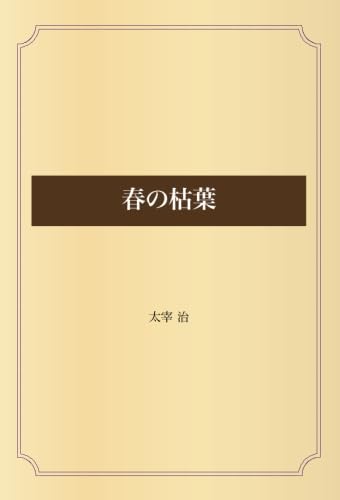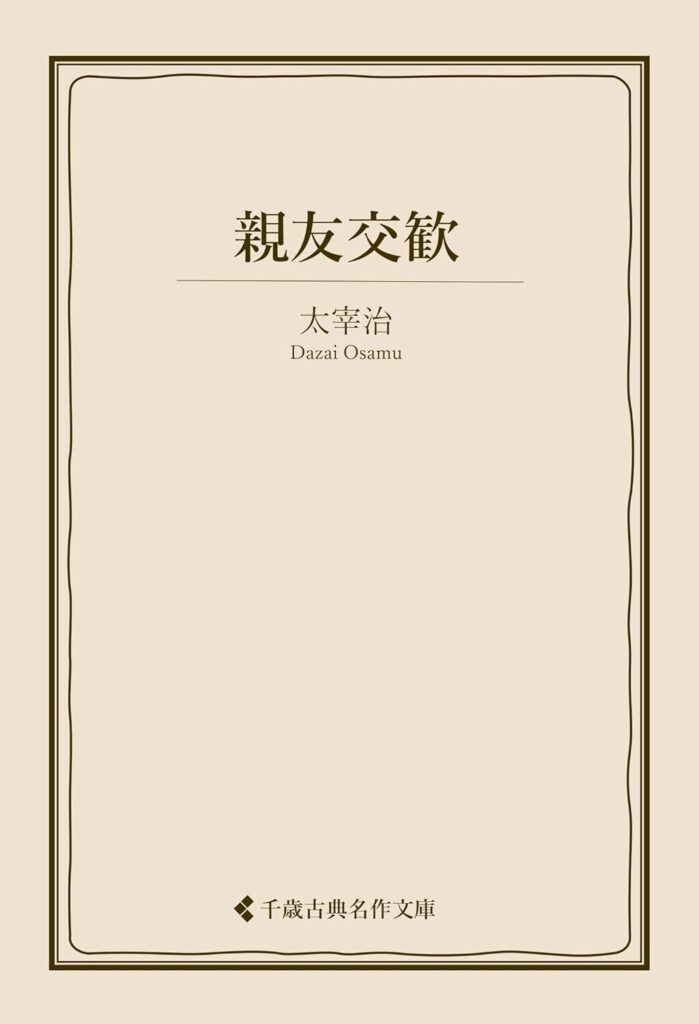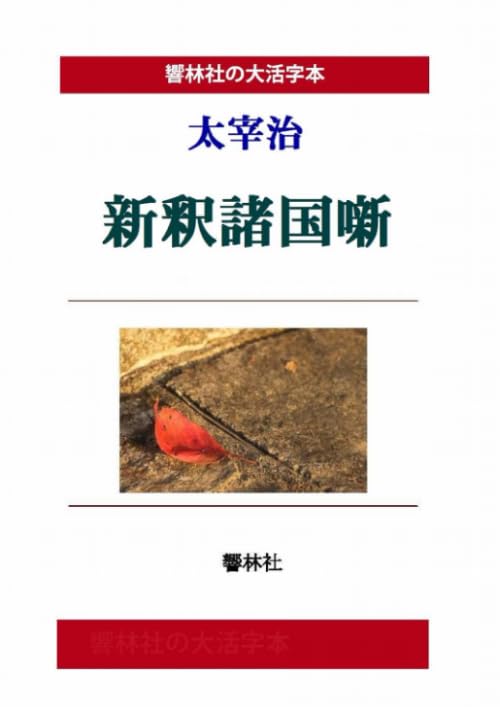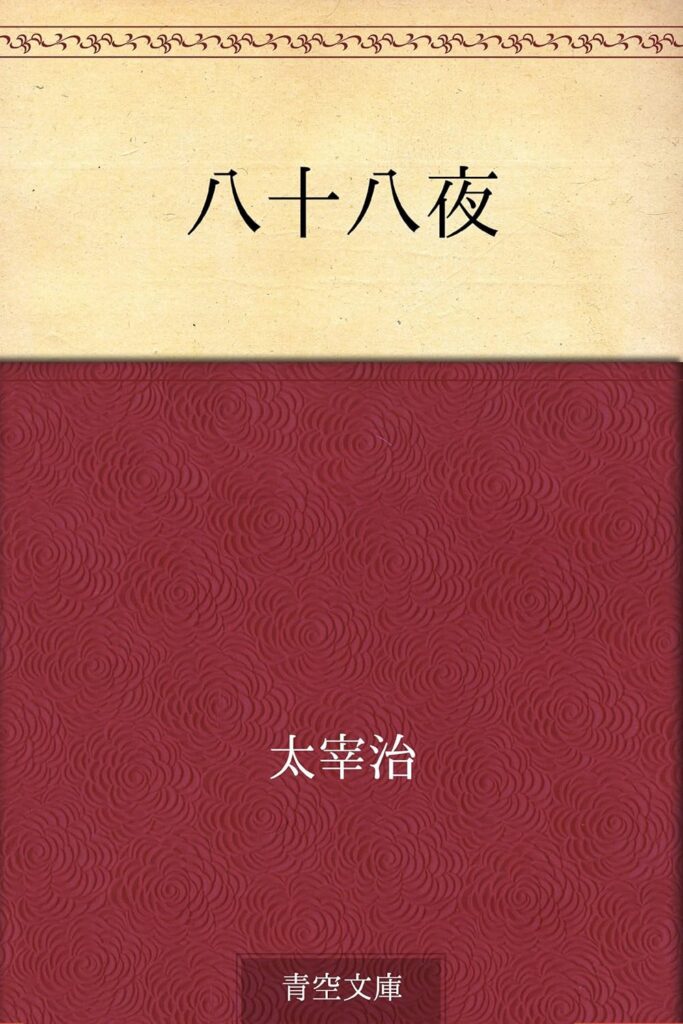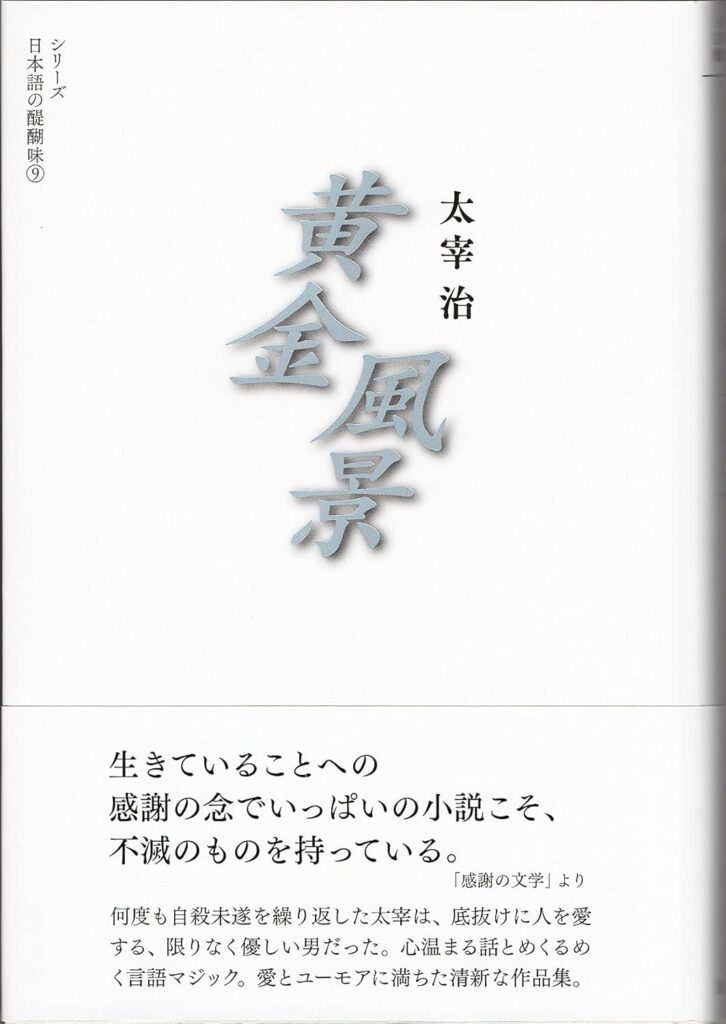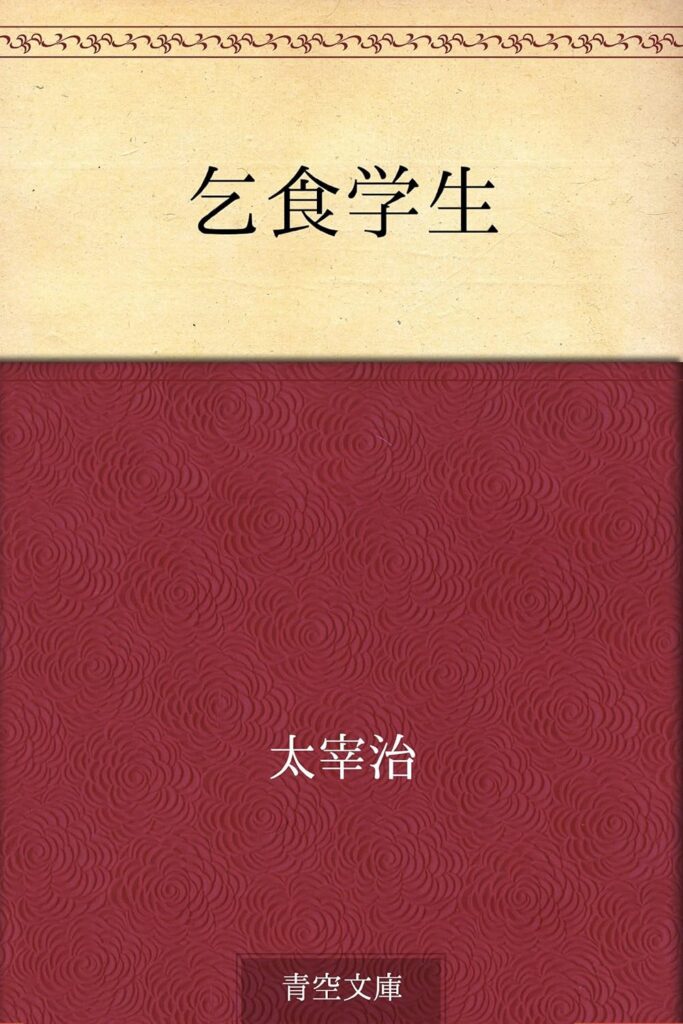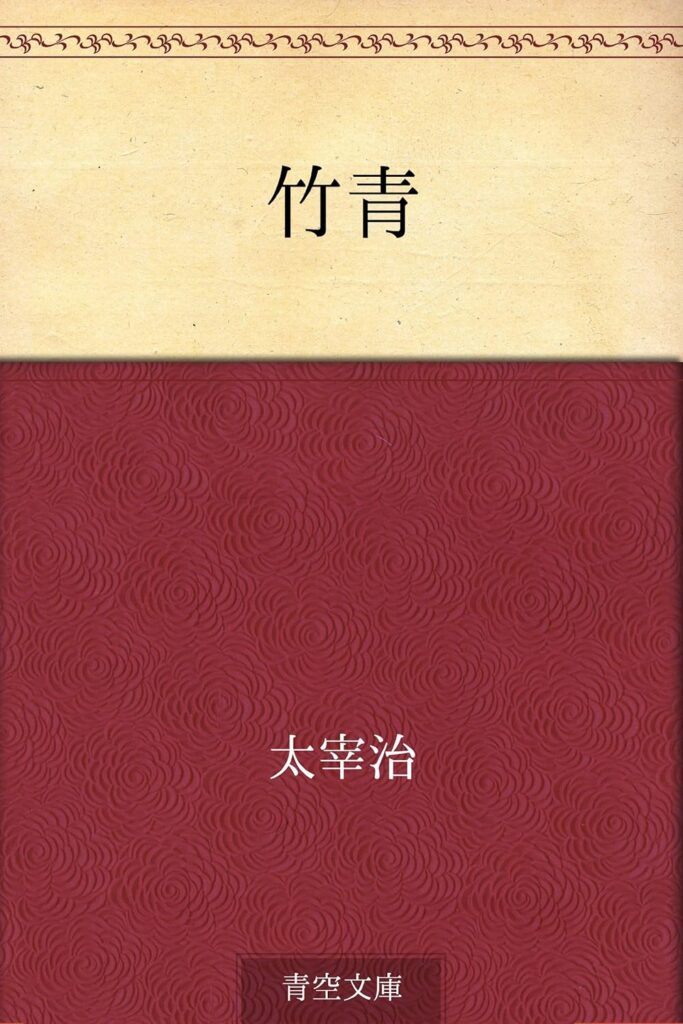小説「グッド・バイ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「グッド・バイ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
太宰治の最晩年の作品であり、残念ながら未完に終わったこの物語。もし完成していたら、彼の代表作の一つとして、「人間失格」や「斜陽」と並び称されていたかもしれません。それほど、この作品には独特の魅力と、太宰文学のエッセンスが凝縮されているように感じられます。
物語は、多くの愛人を抱える編集者の田島が、心機一転、まっとうな生活を送るために愛人たちとの関係を清算しようと決意するところから始まります。その方法として、絶世の美女を偽の妻として紹介するという、なんとも奇妙な計画を立てるのですが、この設定からして、すでに波乱の予感がします。
この記事では、「グッド・バイ」がどのような物語なのか、その顛末(と言っても未完ですが)を含めて詳しくお伝えします。さらに、物語を読んだ私の個人的な思いや考察も、かなり長くなりますが、詳しく書いてみました。未完だからこそ広がる想像の世界にも触れていますので、ぜひ最後までお付き合いください。
小説「グッド・バイ」のあらすじ
雑誌「オベリスク」の編集長という表の顔を持つ田島周二は、その裏で闇商売に手を染め、稼いだお金で十人近くの愛人を囲っていました。三十四歳、なかなかの男前で、女性関係も派手そのもの。しかし、終戦から三年が経ち、疎開先に残してきた妻と娘を呼び寄せ、真っ当な生活を築き直したいという気持ちが芽生え始めます。
そのためには、まず愛人たちと綺麗に別れなければなりません。どうしたものかと悩んでいた矢先、知り合いの文士から奇抜なアドバイスを受けます。「とびきりの美人に奥さん役を演じてもらい、その女性を連れて別れ話をすれば、相手も諦めるだろう」と。藁にもすがる思いの田島は、この作戦に乗ることに決めました。
問題は、その「絶世の美女」役を誰に頼むかです。なかなか適任者が見つからず途方に暮れていた田島は、新宿の闇市で偶然、かつぎ屋の永井キヌ子という女性と再会します。普段はもんぺ姿で鴉のような声を持つ彼女ですが、身なりを整えれば驚くほどの美人になる可能性を秘めていました。田島はこのキヌ子に白羽の矢を立てます。
田島はキヌ子を食事に誘い、例の計画を持ちかけます。キヌ子は、田島の頼りなさをなじりながらも、大食漢ぶりを発揮し、大量の料理を平らげた末、報酬を条件に協力を承諾します。ただし、訪問先では「話さないこと」「食べないこと」が条件でした。こうして、奇妙な二人組による「愛人清算作戦」が幕を開けるのです。
最初のターゲットは、日本橋のデパート内にある美容室で働く青木さん。未亡人である彼女は、田島からの経済的援助も受けていました。田島はキヌ子を伴って店を訪れ、「妻です」と紹介します。キヌ子の圧倒的な美しさと淑女然とした態度に、青木さんは打ちのめされ、涙ぐんでしまいます。田島はキヌ子の髪のセットを青木さんに頼むと、その場を離れ、戻ってきた際に青木さんの上着のポケットにお金(手切れ金)を忍ばせ、「グッド・バイ」と優しく、しかし哀しげに囁くのでした。別れのわびしさを感じながらも、作戦の第一段階は成功します。
しかし、デパートを出た後、キヌ子が高価な品物をためらいなく買い込み、田島に支払わせたことで、二人の間に亀裂が生じます。約束が違うと憤る田島に対し、キヌ子は「それなら協力しない」と強気な態度。腹を立てた田島は、キヌ子を色仕掛けで手なずけようと、彼女のアパートを訪ねるという、さらなる浅はかな計画を思いつきます。しかし、そこでもキヌ子の怪力によって手痛い反撃を受け、色男としてのプライドを打ち砕かれてしまいます。物語は、田島がキヌ子の怪力を別の形で利用しようと考え、次の愛人である洋画家の水原ケイ子のもとへ向かおうとするところで、突然終わりを告げます。
小説「グッド・バイ」の長文感想(ネタバレあり)
太宰治の未完の遺作、「グッド・バイ」。この作品を読むたびに、私は何とも言えない複雑な気持ちになります。軽快なタッチで描かれる物語の裏に、太宰自身の苦悩や願望が透けて見えるようで、読み終えた後(といっても未完ですが)も、様々な思いが頭の中を巡るのです。ここからは、結末にも触れながら、私の感じたこと、考えたことを詳しくお話しさせてください。
まず、主人公の田島周二という人物についてです。彼は雑誌編集長でありながら闇商売で儲け、十人もの愛人を囲うという、なかなかに破綻した生活を送っています。一見すると、どうしようもない色男、だらしない男と断じてしまいそうになります。しかし、物語を読み進めると、彼が単なる軽薄な男ではないことが分かってきます。
妻子を疎開先に残していること、そして愛人たちにもその事実を隠していないこと。これは、彼なりの誠実さの表れなのかもしれません。そして、終戦から三年が経ち、これまでの生活を清算して、家族と堅実な暮らしを始めようと決意する。この変化は、単なる気まぐれだったのでしょうか。それとも、心の底からの再生への願いだったのでしょうか。太宰自身も、破滅的な生活と再起への思いの間で揺れ動いた作家でしたから、田島の姿に自身を重ねていた部分は、少なかわらずあったのではないかと想像します。
彼の計画、「絶世の美女を偽の妻として連れて行き、愛人と別れる」というのも、実に彼らしいというか、どこか滑稽で、それでいて切実さが感じられます。真正面から別れを切り出す勇気がない、あるいは相手を傷つけたくないという思い(それは自己保身かもしれませんが)が、このような回りくどい方法を選ばせたのでしょう。最初の愛人、青木さんとの別れの場面では、お金を渡して「グッド・バイ」と囁く彼の姿に、一抹の哀愁すら感じます。決して、ただ遊び捨てているわけではない、という彼の複雑な心情が垣間見える瞬間です。
そして、この物語のもう一人の重要な登場人物が、永井キヌ子です。彼女の存在が、この物語を単なる「ダメ男の愛人清算劇」以上のものにしています。普段は薄汚れた格好で、鴉のような声、しかし身なりを整えれば誰もが振り返るほどの美貌と気品を兼ね備えている。このギャップが強烈です。さらに、見た目に反する怪力の持ち主であり、驚くほどの大食漢。常識の枠に収まらない、非常に魅力的なキャラクターだと思います。
キヌ子は、田島の計画に乗りながらも、彼に対して遠慮がありません。田島の優柔不断さや下心を鋭く見抜き、物怖じせずに指摘します。食事の場面での堂々とした食べっぷりや、デパートでのためらいない買い物、そして田島の色仕掛けを怪力で撃退する場面など、彼女の行動は痛快ですらあります。彼女は、田島にとって都合の良い「道具」では決してなく、むしろ彼を振り回し、ある意味で彼の本質を暴き出す存在として描かれています。
田島がキヌ子を手なずけようとして失敗する場面は、物語の転換点の一つと言えるでしょう。色男としての自信を打ち砕かれた田島は、キヌ子の怪力を別の形で利用しようと考えますが、この二人の関係性が今後どうなっていくのか、非常に気になるところで物語は終わってしまいます。キヌ子は田島を変えるきっかけを与える存在になったのでしょうか? それとも、結局は田島の計画の駒として利用されるだけだったのでしょうか? 未完であるがゆえに、想像は膨らむばかりです。
この作品の魅力は、こうした個性的な登場人物たちだけではありません。戦後間もない、まだ混乱と貧しさの残る時代を背景にしながらも、物語全体を覆う軽妙な空気感も特筆すべき点です。登場人物たちの会話はテンポが良く、どこか芝居がかっているようでもあり、読んでいると思わず笑みがこぼれる場面も少なくありません。特に田島とキヌ子のやり取りは、まるで漫才のようです。
しかし、その軽やかさの底には、やはり太宰治らしい人間の業や哀しみ、そして時代の空気が流れているように感じます。闇市でたくましく生きる人々、戦争未亡人の青木さんの生活、田島の抱える空虚感。それらが、決して重苦しくはならずに、しかし確かに描かれている。このバランス感覚が、太宰治の筆の冴えなのでしょう。
そして、やはり触れずにはいられないのが、「未完」であるという事実です。物語が佳境に入り、田島とキヌ子の関係、そして次の愛人との対決がまさに始まろうというところで、ぷっつりと途切れてしまう。これは、読者にとっては非常にもどかしいことであり、同時に、この作品に特別な魅力を与えている要因でもあります。
もし物語が続いていたら、どうなっていたのでしょうか。朝日新聞の文芸部長の証言によれば、最終的には田島自身が妻から「グッド・バイ」を告げられるという結末が構想されていたとも言われています。愛人たちとの別れは成功するものの、結局は自分自身が捨てられるという皮肉な結末。これは、いかにも太宰治が考えそうな展開かもしれません。田島の「改心」がいかに脆いものであったかを示す結末とも言えます。
しかし、未完だからこそ、私たちは自由にその先を想像することができます。キヌ子との間に恋愛感情が芽生える可能性は? 水原ケイ子とその兄との対決はどのような展開を迎えるのか? 残りの愛人たちとの別れはスムーズに進むのか? そして、最終的に田島は本当に家族のもとへ帰り、新しい生活を始めることができるのか? あるいは、全てが破綻し、元の木阿弥に戻ってしまうのか? 様々な可能性を思い描くことができるのは、未完の作品ならではの楽しみ方と言えるでしょう。
伊坂幸太郎さんがこの作品にオマージュを捧げた「バイバイ、ブラックバード」を執筆したり、ケラリーノ・サンドロヴィッチさんによって戯曲化・映画化(「グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇」)されたりしていることからも、「グッド・バイ」が持つ物語のポテンシャルの高さがうかがえます。多くのクリエイターが、この未完の物語の「続き」を自分なりに描きたいと感じるのでしょう。
太宰治は、「人間失格」という、自身の内面を深くえぐり出すような作品を書き上げた直後に、この「グッド・バイ」の執筆に取り掛かりました。それは、彼にとって一つの転換点だったのかもしれません。重苦しい自己内省の世界から、少し距離を置いた、軽やかで客観的な視点を取り戻そうとしていたのではないでしょうか。田島という、自分自身を投影しつつも、どこか突き放した距離感で描かれるキャラクターに、その試みが表れているように思います。
もし、この作品を完成させていたなら、太宰は新たな作風を獲得し、あるいは精神的な安定を取り戻すことができたのではないか…そんな詮無いことまで考えてしまいます。しかし、現実はそうなりませんでした。彼はこの作品を未完のまま残し、自ら命を絶ってしまった。その事実が、この軽妙な物語に、どうしようもない哀しみの影を落としていることも、また確かなのです。
「グッド・バイ」は、太宰治の文学の中でも異色の作品と言えるかもしれません。しかし、そこには紛れもなく、人間の弱さ、滑稽さ、そして再生への微かな希望(あるいはその挫折)が描かれています。未完であることを含めて、この作品は私たちに多くのことを問いかけ、想像力をかき立ててくれます。読むたびに新しい発見があり、田島やキヌ子のことが、まるで古い友人のように思えてくるのです。
まとめ
太宰治の未完の遺作「グッド・バイ」について、物語の概要と、ネタバレを含む形で私の思いや考察を綴ってきました。この作品は、多くの愛人を抱える主人公・田島が、心機一転を図り、奇妙な方法で愛人たちとの別れを進めようとする物語です。
相棒となるのは、普段の姿と美人になった時のギャップが激しい、怪力大食漢のキヌ子。この二人のちぐはぐなコンビが繰り広げる「愛人清算作戦」は、軽快な筆致で描かれ、思わず引き込まれます。戦後の混乱期という時代背景を感じさせつつも、物語全体は明るい雰囲気に包まれています。
しかし、物語が佳境に差し掛かったところで突然終わってしまう「未完」の作品であるため、その結末は読者の想像に委ねられています。もし続いていたらどうなったのか、太宰自身はどんな結末を考えていたのか、思いを巡らせるのもこの作品の楽しみ方の一つです。登場人物たちの魅力、テンポの良い会話、そして未完であるがゆえの余韻は、他の作品では味わえない独特の読書体験を与えてくれます。
太宰治の作品というと、暗く重いイメージを持つ方もいるかもしれませんが、「グッド・バイ」はそうしたイメージを良い意味で裏切ってくれる作品です。太宰文学の入門としても、あるいは彼の新たな一面を発見するためにも、ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。きっと、田島とキヌ子の奇妙な道行きに、あなたも心を奪われるはずです。