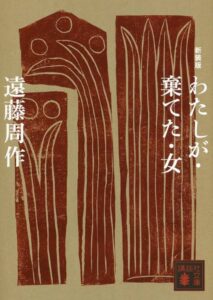 小説『わたしが・棄てた・女』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説『わたしが・棄てた・女』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
遠藤周作の代表作の一つである『わたしが・棄てた・女』は、発表から半世紀以上を経てもなお、多くの読者の心を揺さぶり続けています。人間関係の複雑さ、そして愛と裏切り、そして赦しという普遍的なテーマを深く掘り下げたこの作品は、読む者の心に問いかけます。
主人公の吉岡努が、若さゆえの傲慢さと自己中心的な行動によって、一人の女性、森田ミツを深く傷つけ、そして「棄てて」しまうところから物語は始まります。しかし、物語はそこで終わりません。吉岡の心に宿る後悔と、ミツの辿る過酷ながらも献身的な人生が、読者に深い感動と示唆を与えます。
これは単なる恋愛小説ではありません。人間の弱さ、罪、そしてそれらを乗り越えるための心の葛藤が、克明に描かれています。私たちは吉岡の視点から、いかに人間が他者を傷つけうるかを知り、同時にミツの存在を通して、いかに他者に尽くし、無償の愛を貫けるかを考えさせられます。
『わたしが・棄てた・女』のあらすじ
貧しい大学生の吉岡努は、雑誌の文通欄を通じて地方出身の森田ミツと知り合います。数回のデートの後、吉岡はミツを安旅館に連れ込み、強引に関係を持ちます。しかし、その純朴で垢抜けないミツの姿に、吉岡は魅力どころか嫌悪感さえ抱いてしまい、一方的に関係を断ち切ってしまいます。ミツは吉岡に深く惹かれていましたが、吉岡はそんな彼女の気持ちを顧みることなく、自らの欲望を満たした後は冷酷に離れていくのです。
大学を卒業し製薬会社に就職した吉岡は、出世のために社長の娘・三浦マリ子に近づきます。そんな中、吉岡はマリ子がかつてミツと同じ工場で働いていたことを知り、ミツの存在を再び意識し始めます。ある日、吉岡は同僚に誘われトルコ風呂に足を運び、そこでミツが身をやつして働いていた痕跡を発見します。さらに、物乞いに施しを与えたミツが受け取ったロザリオを、吉岡は偶然手にするのです。
街角でミツと再会した吉岡は、痩せ細ったミツがハンセン病の疑いで御殿場の療養所に入所しなければならないと告げられます。吉岡は動揺するものの、表面的な慰めの言葉をかけるだけで、自己保身のためにその場を去ってしまいます。ミツは絶望しながらも療養所へ向かうことになります。
療養所での生活に当初は抵抗を感じていたミツですが、次第に環境に慣れ、修道女や他の患者たちと心を通わせていきます。彼女は献身的に働き、食事の準備や配膳を手伝い、患者たちに寄り添います。しかし、幼い少年患者の死を前に、ミツは神の不在を嘆き、深い苦悩に襲われるのです。
『わたしが・棄てた・女』の長文感想(ネタバレあり)
遠藤周作の『わたしが・棄てた・女』を読み終えたとき、私は深い静寂と、同時に胸の奥をえぐられるような感覚に包まれました。この作品は、人間のエゴイズムと、それに抗うかのような無垢な愛の対比を、これでもかとばかりに私たちに突きつけます。
物語の中心にいるのは、大学生の吉岡努と、彼に「棄てられた」森田ミツです。吉岡は、自らの欲求に忠実で、ある意味で現代的な合理主義を体現しているかのようです。彼はミツを都合よく利用し、その純粋さ、あるいは「田舎臭さ」を疎ましく感じ、あっさりと切り捨てます。彼の行動は、多くの人が心の片隅に抱えているであろう、他者への無関心や、自己保身の願望を具現化したものではないでしょうか。彼を批判することは容易いですが、彼の中に自分自身の影を見ることに、私はある種の居心地の悪さを覚えました。
一方、ミツの存在は、吉岡の闇を照らす光そのものです。吉岡に裏切られ、貧困にあえぎ、さらにはハンセン病の誤診という過酷な運命に翻弄されながらも、彼女の心は濁ることがありませんでした。トルコ風呂で働き、それでも他者に施しを与えるその姿は、痛々しいほどに純粋で、読者の心を打ちます。彼女の存在は、人間の尊厳とは何か、そして真の強さとは何かを問いかけているように感じられます。
特に印象的だったのは、ミツが療養所での生活に順応していく過程です。絶望の淵に立たされながらも、彼女は他者のために尽くすことを選びます。幼い患者の死を前に、神への疑念を抱きながらも、それでもなお献身的に生きる彼女の姿は、まさしく聖女のようでした。神を信じるとは何か、信仰とは何かという問いが、彼女の行動を通して静かに、しかし力強く描かれています。彼女は、理不尽な苦難を受け入れながらも、決して希望を捨てず、他者への愛を貫いたのです。
誤診が判明し、東京に戻れることになったミツが、駅で偶然マリ子と再会する場面もまた、この物語の重要な転換点です。幸せそうなマリ子の姿を目の当たりにし、ミツは自分自身の「しみったれた人生」を痛感します。しかし、彼女は東京に戻り、吉岡との関係を取り戻す道を選びませんでした。代わりに、彼女は御殿場に残り、療養所の人々のために生きることを決意します。この決断は、彼女が自己の幸せよりも、他者への奉仕を選んだことの何よりの証であり、彼女の精神性の高さを物語っています。
吉岡がマリ子と結婚し、表面的な幸せを手に入れた後も、彼の心にはミツの影が常に付きまといます。年賀状を送り、その返事を待つ彼の姿は、彼がいかにミツの存在に囚われていたかを物語っています。ミツが事故死したという知らせを受け取った時の吉岡の虚無感と後悔は、読者である私にも痛いほど伝わってきました。彼は、ミツを「棄てた」ことで、自らの心の安寧もまた「棄てて」しまっていたのかもしれません。
ミツの最期の言葉、「さいなら、吉岡さん」は、彼女が最後まで吉岡を赦し、そして愛し続けていたことを示唆しています。この言葉は、吉岡にとって、そして読者にとっても、重く、そして深く心に響くものでした。吉岡は、ミツの死を通して、ようやく自分の罪と向き合うことになるのです。しかし、その気づきはあまりにも遅く、彼は永遠に償うことのできない「何か」を背負っていくことになります。
この作品は、キリスト教的な「罪と赦し」のテーマを深く扱っていますが、宗教に馴染みのない読者にとっても、普遍的な人間の葛藤として受け止められるでしょう。私たちは皆、吉岡のように他者を傷つけ、後悔することがあります。そして、ミツのように、苦しみの中で他者のために生きる道を選ぶこともまた、人間の可能性として存在します。
『わたしが・棄てた・女』は、吉岡の視点とミツの視点が交互に描かれることで、それぞれの内面がより深く理解できるようになっています。吉岡の打算的な思考とミツの純粋な献身が対照的に描かれることで、物語のテーマがより鮮明に浮かび上がります。著者がミツというキャラクターに深い愛情を注いでいたことが伝わってくる作品です。
ミツの存在は、吉岡の心に「良心」の種を蒔いたのかもしれません。彼女の死は、吉岡にとっての贖罪の始まりであり、彼が真に人間として成長するための、苦痛に満ちた一歩だったのではないでしょうか。この物語は、単なる悲劇で終わるのではなく、人間の心の奥底にある光と闇、そしてそこに宿る微かな希望を描き出しているのです。
この作品は、読むたびに新たな発見がある、まさに「名作」と呼ぶにふさわしいものです。人間の心の複雑さ、愛の形、そして自己犠牲の尊さについて、深く考えさせられる一冊でした。吉岡の、そしてミツの物語は、これからも多くの人々に読み継がれていくことでしょう。
まとめ
遠藤周作の『わたしが・棄てた・女』は、一人の男の身勝手な行動によって人生を狂わされた女性の物語を軸に、人間の罪と赦し、そして無償の愛の尊さを深く描いた作品です。主人公の吉岡努は、若さゆえの傲慢さから森田ミツを「棄て」、その後の人生で後悔と葛藤を抱え続けます。
一方、過酷な運命に翻弄されながらも、ミツは他者への献身的な愛を貫き、苦しみの中で人間としての真の強さを示します。彼女の純粋で自己犠牲的な生き方は、読む者に深い感動を与え、神への問いかけを通して普遍的な信仰の姿をも示しています。
この作品は、吉岡の自己中心的な視点と、ミツの無垢な視点を交互に描くことで、人間の心の光と闇、そしてそこに潜む葛藤を多角的に浮き彫りにしています。ミツの死は吉岡にとっての大きな転換点となり、彼が自らの罪と向き合い、人間として成長するきっかけを与えます。
『わたしが・棄てた・女』は、単なる恋愛物語に留まらず、人間の内面に深く切り込み、読む者に自らの人生や人間関係について深く考えさせる、時代を超えた普遍的なテーマを持つ傑作です。




























