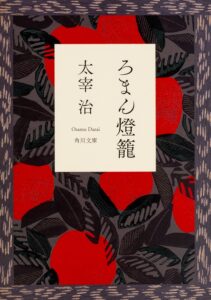 小説「ろまん燈籠」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治の作品の中でも、どこか温かく、家族の情景が浮かぶような本作は、戦時下に書かれたとは思えないほどの明るさも感じさせます。物語を紡ぐ楽しさと、そこに映し出される人間模様が魅力的な一編です。
小説「ろまん燈籠」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治の作品の中でも、どこか温かく、家族の情景が浮かぶような本作は、戦時下に書かれたとは思えないほどの明るさも感じさせます。物語を紡ぐ楽しさと、そこに映し出される人間模様が魅力的な一編です。
この記事では、まず「ろまん燈籠」がどのような物語なのか、その骨子となる部分、つまり物語の展開がわかるように説明します。結末に触れる内容も含まれますので、これから読む予定で結末を知りたくない方はご注意ください。物語の核心部分にも触れていきます。
そして、物語の詳細なあらすじをお伝えした後、私がこの作品を読んで何を感じ、どう考えたのか、詳しい思いを綴っていきます。登場人物たちの個性や、物語の構成、そして太宰治がこの作品に込めたであろうメッセージについて、深く掘り下げていくつもりです。
太宰作品というと、暗く重たいイメージを持つ方もいるかもしれませんが、「ろまん燈籠」は少し趣が異なります。家族が集い、一つの物語を作り上げていく過程は、創造の喜びと同時に、それぞれの内面を映し出す鏡のようでもあります。この記事を通して、その魅力を少しでもお伝えできれば幸いです。
小説「ろまん燈籠」のあらすじ
物語の中心となるのは、文学好きの五人兄妹、入江家の人々です。長兄を筆頭に、長女、次女、次男、そして末弟。彼らは退屈な日曜日など、時間を持て余すと、客間に集まっては一つの物語を共同で創り上げるという遊びに興じます。
この遊びは、まず一人が自由に人物を設定し、物語の口火を切ります。そして、次の者がその続きを考え、さらに次の者へとリレー形式で物語を紡いでいくのです。それぞれの性格や個性が物語の展開に色濃く反映され、時にちぐはぐになりながらも、一つの作品が生み出されていきます。
ある時、彼らはまたこの連作ゲームを始めます。末弟から始まった物語は、長女、そして次男へと受け継がれていきます。しかし、この物語作りは単なる遊びではありません。鉛筆を削ってばかりでなかなか筆が進まない末弟、自信満々に女心を描こうとする長女、霊感を求めピアノを叩く次女、立派な万年筆で書き始めるもすぐに詰まってしまう長兄。創作に取り組む姿は、そのまま彼らの人となりを表しています。
特に注目されるのが、帝大医学部に籍を置きながらも病弱で、皮肉屋な美形の次男です。彼は物語の構想に行き詰まり、布団の中で思案に暮れます。その傍らには、彼に密かな好意を寄せる、足の悪い十七歳の女中さとの姿があります。
次男は、物語の参考にするためと称して、さとに対して「もし僕がお前と結婚したら、どんな気がするか」と唐突な質問を投げかけます。純粋なさとは、主人の役に立とうと真剣に考え、「わたくしならば、死にます」と答えますが、次男は「つまらない」と一蹴します。このやり取りは、次男の創作への没頭ぶりと、さとの健気さ、そして二人の間の微妙な関係性を描き出しています。
最終的に、兄妹たちの手によって物語は完成します。それは、それぞれの個性がぶつかり合いながらも、一つの家族が共有する時間の中で生まれた、ユニークな創造物となるのです。この物語創作の過程を通して、入江家の日常、兄妹それぞれの思い、そして彼らを取り巻く人々の姿が生き生きと描かれています。
小説「ろまん燈籠」の長文感想(ネタバレあり)
太宰治の「ろまん燈籠」を読むと、いつも心が温かくなるような、不思議な感覚に包まれます。彼の多くの作品に見られる破滅的な影や、痛切な自己告白とは少し異なり、ここには家族という共同体が持つ、ある種の明るさや創造の喜びが描かれているように感じます。物語を「創る」という行為そのものが、この作品の核となっています。
物語の舞台となる入江家は、五人の兄妹が中心です。彼らが退屈しのぎに始める「連作物語」の遊びが、この短編の骨格を成しています。一人が物語を発案し、順番に続きを書いていく。この単純なルールの中で、兄妹それぞれの性格が見事に描き分けられている点には、いつもながら感心させられます。
長兄は、いかにも長男らしい威厳を見せようとするのか、立派な万年筆で書き始めるものの、冒頭一行で筆が止まってしまう。どこか頼りないけれど、憎めない存在です。長女は、自分が一番女心を理解していると自負し、自信たっぷりに筆を進めます。次女は感受性が豊かで、霊感を呼び込もうとピアノを弾いたりする。末弟はまだ幼さが残り、うまく書けずに半べそをかきながら鉛筆を削る。
そして、私がこの作品で特に惹かれるのが、次男の存在です。帝大医学部に在籍するも病弱で、美形だけれど皮肉屋でケチ。他の兄妹とは少し違った、複雑な内面を持っているように描かれています。好きな作家はゲエテだけれど、その精神性よりも地位や名誉に惹かれているのでは、と語り手(おそらく太宰自身)は指摘します。この屈折した感じが、いかにも太宰作品の登場人物らしいと感じます。
この次男が、創作に行き詰まった際に、女中のさとに問いかける場面は、作品の中でも特に印象深い箇所です。「僕がお前と結婚したら、どんな気がする?」このあまりにも唐突で、そしてある意味で残酷な質問。しかし次男は、あくまで小説の筋書きの参考として、悪気なく尋ねているのです。彼の頭の中は、創作のことでいっぱいで、さとの小さな胸がどれほど痛んだかには気づきません。
さとの応答がまた、胸を打ちます。「わたくしならば、死にます。」彼女なりに、主人の役に立とうと真剣に考え、絞り出した答えなのでしょう。しかし、次男は創作の材料として「つまらない」と一蹴します。このすれ違い、没頭する者とされる者の温度差が、リアルに描かれています。
しかし、さとはただ打ちひしがれるだけではありません。部屋を出て廊下を歩きながら、泣きたい気持ちになったけれど、別に悲しくもなかったので、今度は心から笑ってしまう。この描写が素晴らしい。彼女の健気さ、純粋さ、そしてどこか達観したような明るさが、この一文に凝縮されているように思います。彼女は決して悲劇のヒロインではなく、しっかりと自分の足で立っている(たとえ物理的な足は悪くても)人間として描かれています。
参考にした文章では、この「さと」が太宰の理想の女中像ではないかと考察されていましたが、私も同感です。沼津出身で、十三歳から入江家に奉公し、家族を神様のように敬い、婦人雑誌を読んで「女は操が第一」と信じ、懐剣代わりにペーパーナイフを隠し持つ。少し古風で、夢見がちだけれど、純粋で忠義心に厚い。特に、自分に一番似ていると感じる(であろう)俗物的な次男を、死ぬほど好いているという設定。これは太宰自身の願望の表れなのかもしれません。創作に没頭し、他者の気持ちに鈍感になりがちな自分(次男)を、それでも健気に、明るく慕ってくれる存在。そんな存在を、太宰は求めていたのかもしれない、と感じさせます。
兄妹たちが紡ぐ物語自体も、彼らの個性が反映されていて興味深いものです。物語がどのように展開し、どのような結末を迎えるのか。それは彼ら自身の合作であり、同時に彼らの関係性や家族の空気を映し出す鏡でもあります。たとえ出来上がった物語がちぐはぐなものであっても、その創作過程そのものが、入江家にとっては大切な時間なのでしょう。
この作品が書かれたのが、昭和16年から19年という戦時下であったことを考えると、その意義はさらに深まります。参考にした文章でも触れられていましたが、太宰は困難な時代にあっても、決して時流に迎合することなく、むしろ旺盛に、質の高い作品を書き続けました。それは彼にとって、書くことが生きることそのものであり、日常を守るための闘いであり、芸術的な抵抗でもあったのではないでしょうか。
「ろまん燈籠」に流れる、どこか牧歌的で、創造的な雰囲気は、戦争という非日常に対する、太宰なりの「日常という思想」の表明だったのかもしれません。家族が集い、物語を紡ぐ。そのささやかな営みの中にこそ、人間が人間らしく生きる証があるのだと、彼は言いたかったのではないでしょうか。
他の収録作、例えば「十二月八日」や「散華」が、より直接的に戦争の影を落としているのに対し、「ろまん燈籠」は、その喧騒から少し離れた場所で、家族の肖像と創作の喜びを描き出しています。しかし、その根底には、やはり困難な時代を生きる作家の強い意志と、日常への渇望が流れているように感じられてなりません。
この作品を読むたびに、登場人物たちの声が聞こえてくるようです。兄妹たちの賑やかな会話、次男の皮肉めいた呟き、そしてさとの控えめながらも芯のある言葉。彼らが織りなす人間模様は、時代を超えて私たちの心に響きます。それは、太宰治という作家が持つ、人間観察の鋭さと、物語を紡ぐことへの深い愛情の表れなのだと思います。
太宰治の作品というと、どうしても暗いイメージが先行しがちですが、「ろまん燈籠」は、そうした先入観を良い意味で裏切ってくれる作品です。もちろん、次男の屈折した性格や、さとの境遇など、単純な明るさだけではない要素も含まれていますが、全体を包む雰囲気は温かく、読後感も悪くありません。むしろ、創造する喜びや、家族という共同体の不思議な引力を感じさせてくれます。
この物語は、太宰自身の様々な側面が、五人の兄妹と、そして女中のさとに投影されているかのようです。創作の苦しみと喜び、他者との関係性の難しさ、日常の愛おしさ。それらが、連作物語という形式を通して、巧みに描き出されています。太宰文学の多様性を示す、重要な一編であると言えるでしょう。
まとめ
太宰治の「ろまん燈籠」は、文学好きな五人兄妹が共同で物語を創作するという、ユニークな設定の短編小説です。物語作りの過程を通して、兄妹それぞれの個性や、家族ならではの空気感が生き生きと描かれています。ネタバレになりますが、特に印象的なのは、皮肉屋で病弱な次男と、彼に好意を寄せる純粋な女中さとの関係性です。
あらすじとしては、退屈な時間を過ごす兄妹が連作物語を始め、それぞれの個性を反映させながら物語を紡いでいく様子が中心となります。創作に苦心する姿や、互いの考えがぶつかり合う様子は、微笑ましくもあり、また人間の本質を突いているようにも感じられます。結末として完成する物語は、彼らの共同作業の成果であり、家族の肖像画とも言えるでしょう。
この作品に対する私の感想は、戦時下という困難な時代に書かれたにも関わらず、創造の喜びや家族の温かさを感じさせる点に魅力を感じる、というものです。太宰作品にしばしば見られる暗さよりも、むしろ日常の営みを肯定しようとする意志が伝わってきます。女中さとの健気で明るいキャラクター描写も、作品に温かみを加えています。
「ろまん燈籠」は、太宰治の文学が持つ幅広さを示してくれる作品です。物語を創ることの意味、家族という共同体、そして困難な時代における日常の尊さについて考えさせられます。太宰文学の入門としても、また違った一面を知るためにも、おすすめしたい一編です。




























































