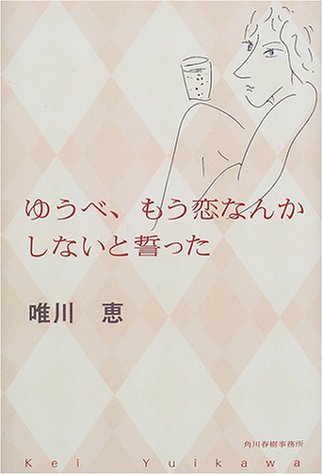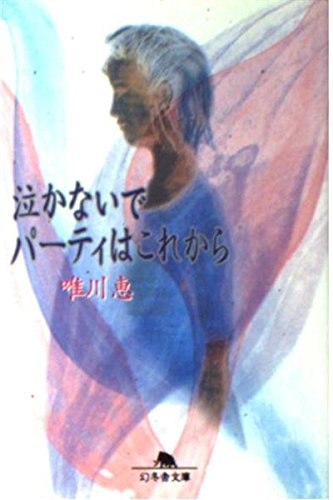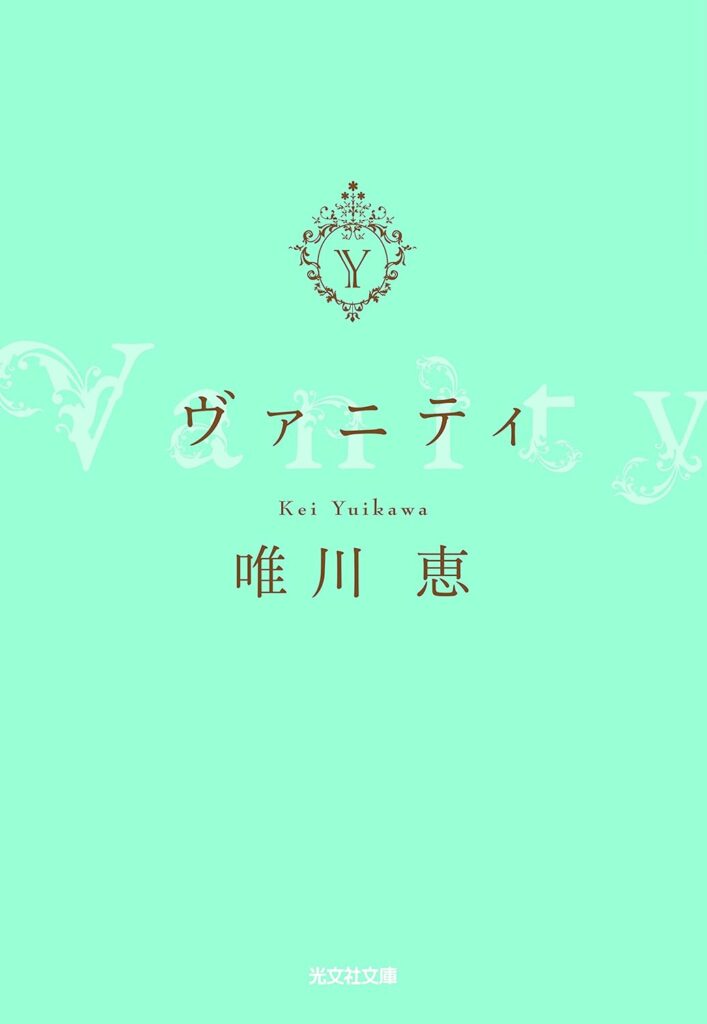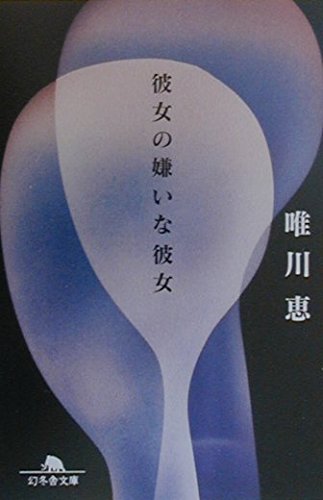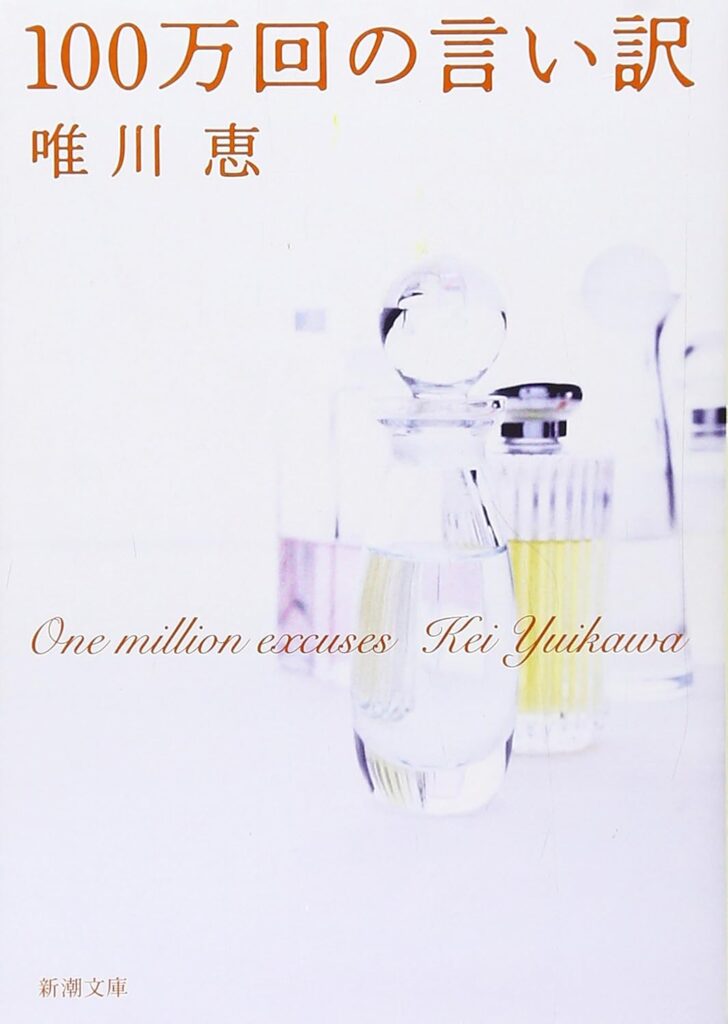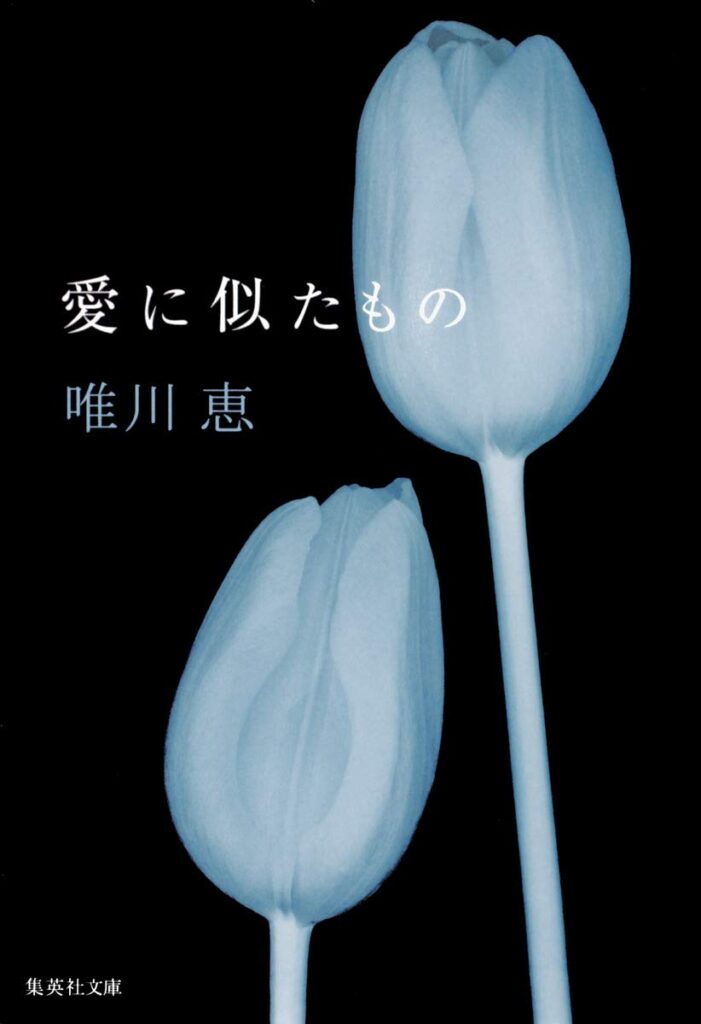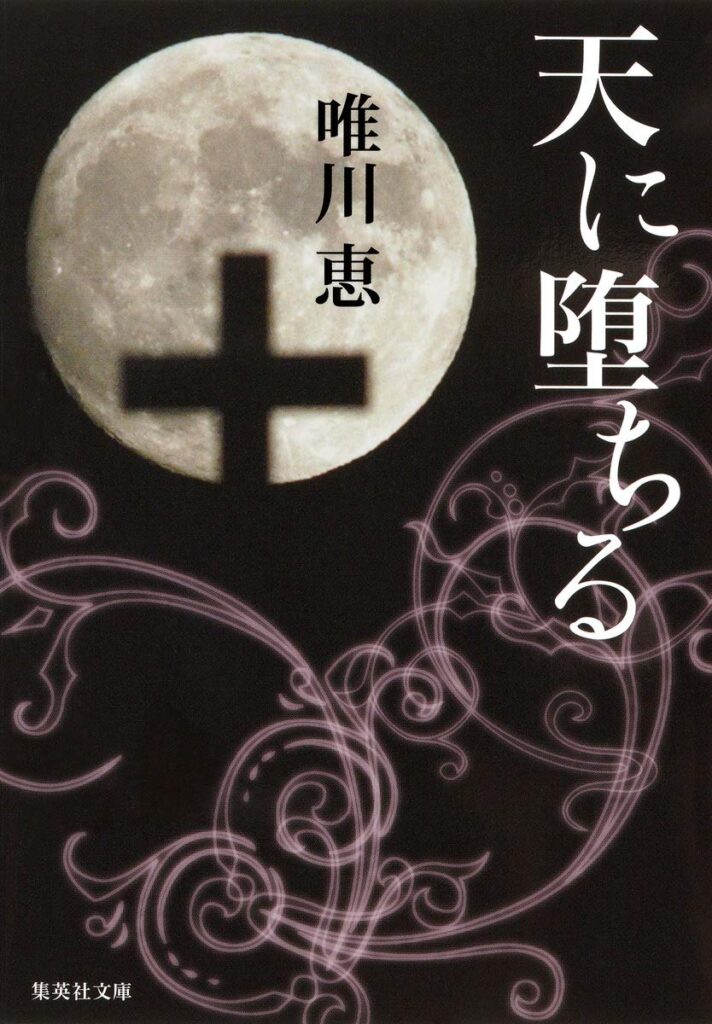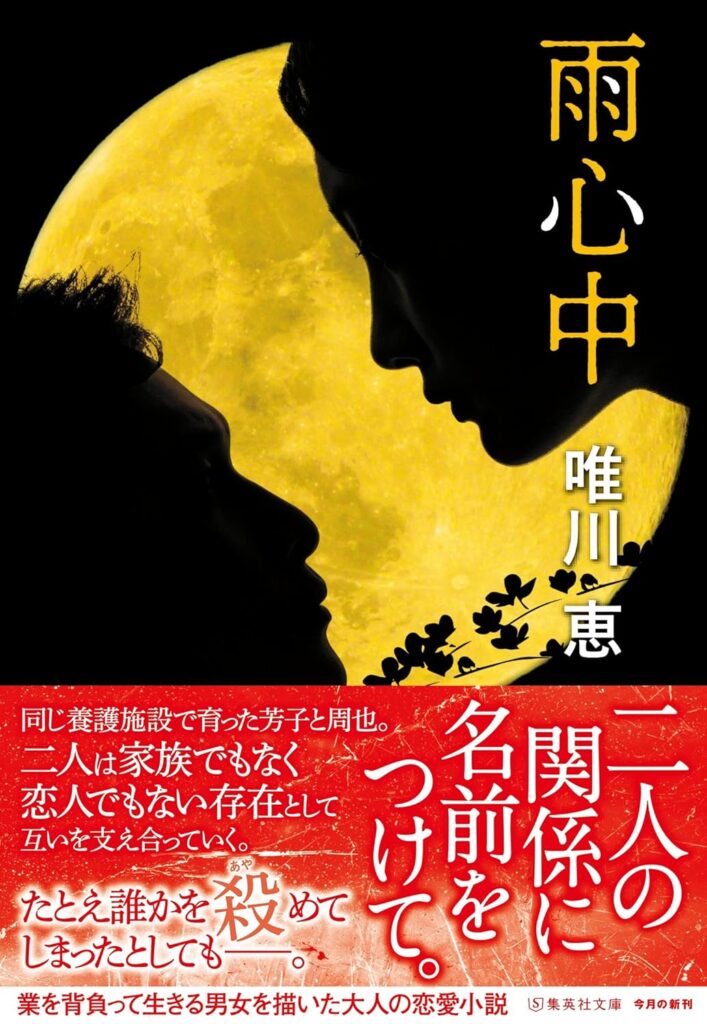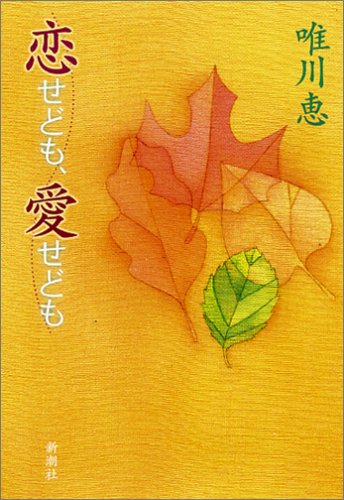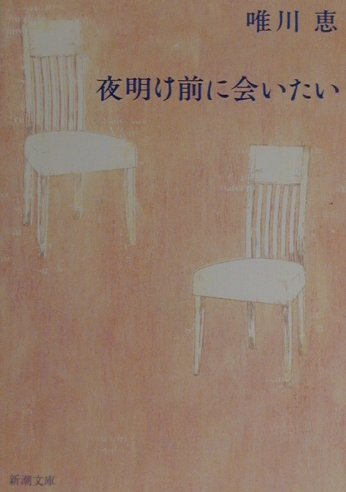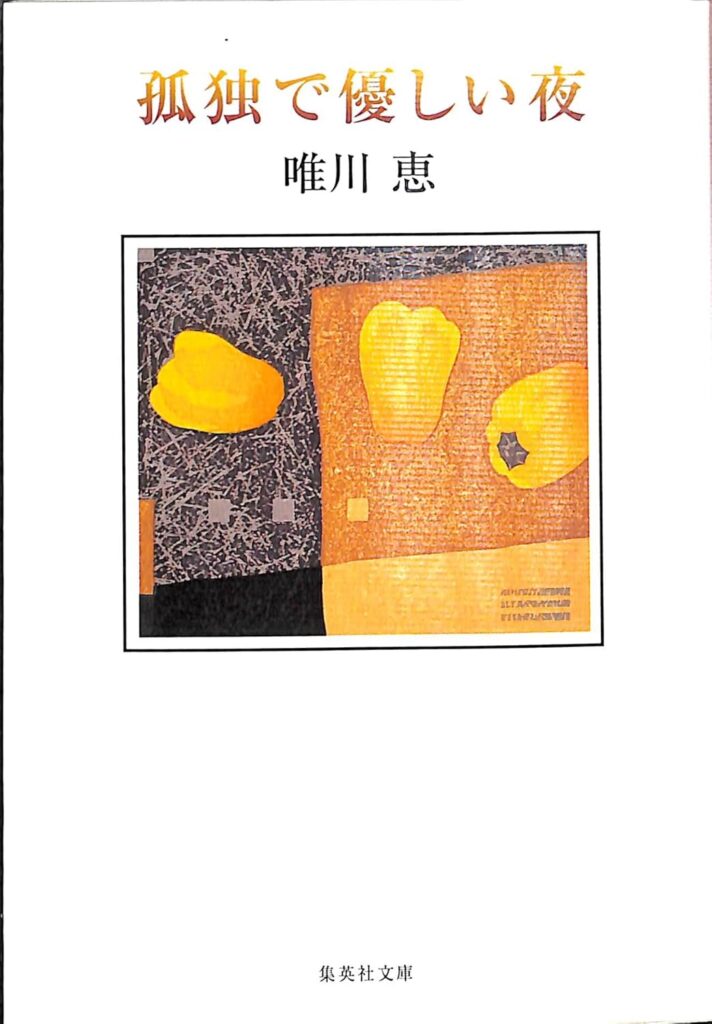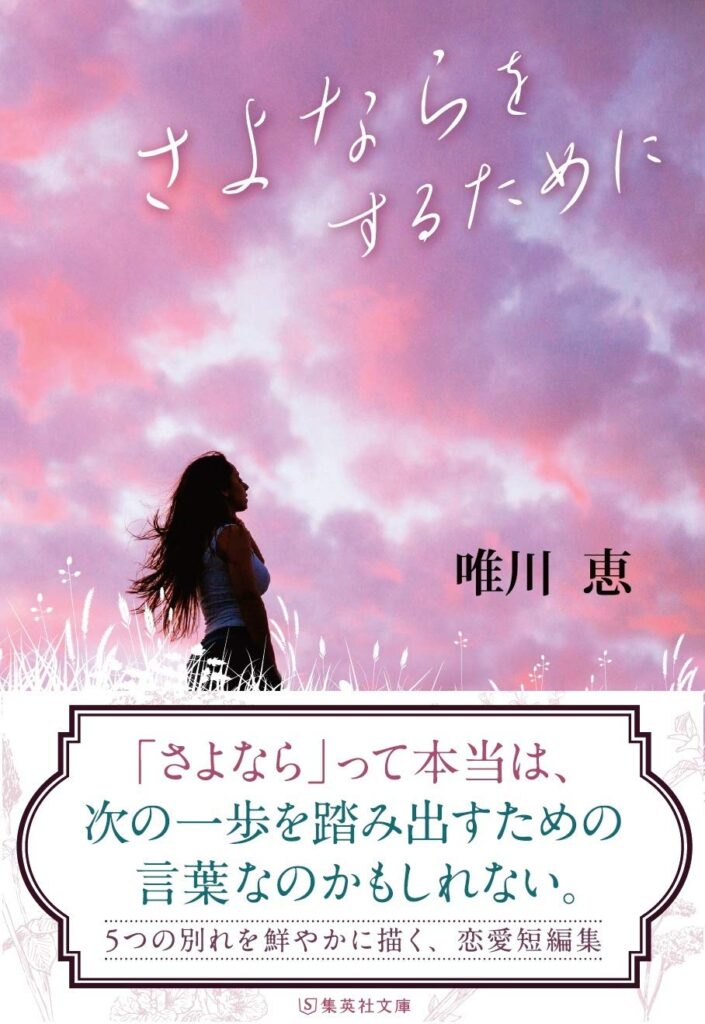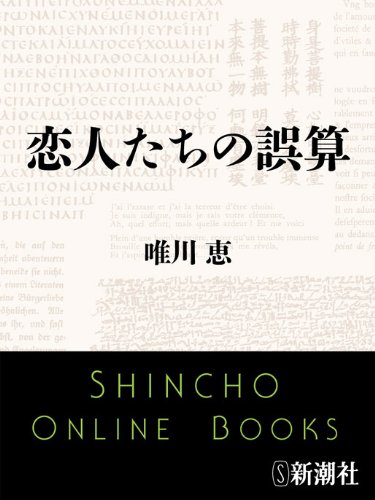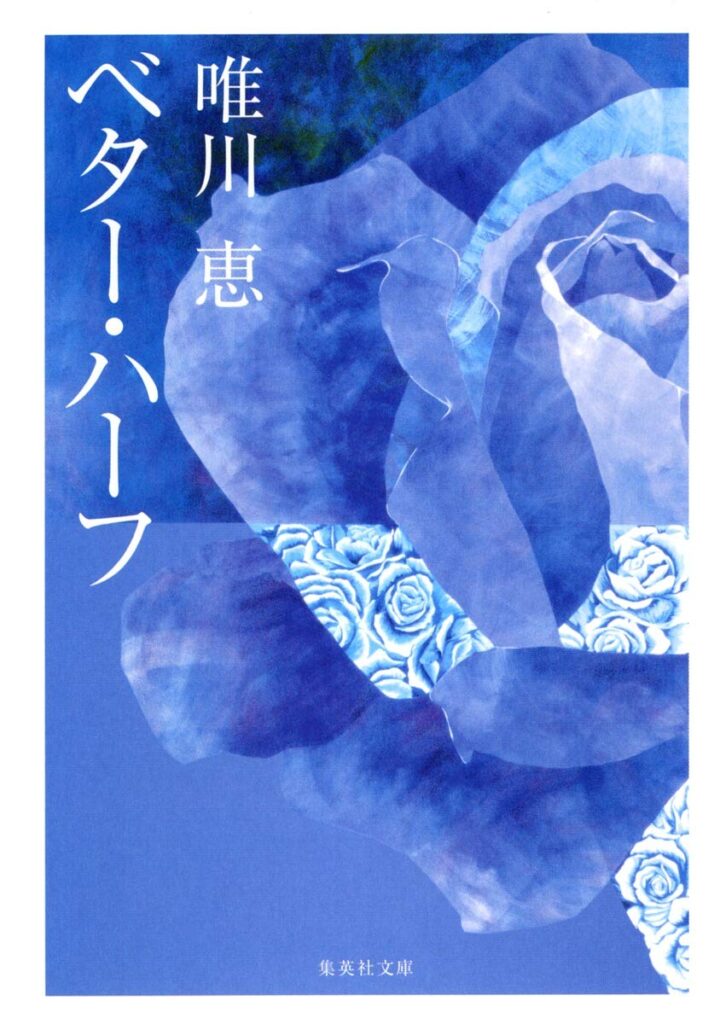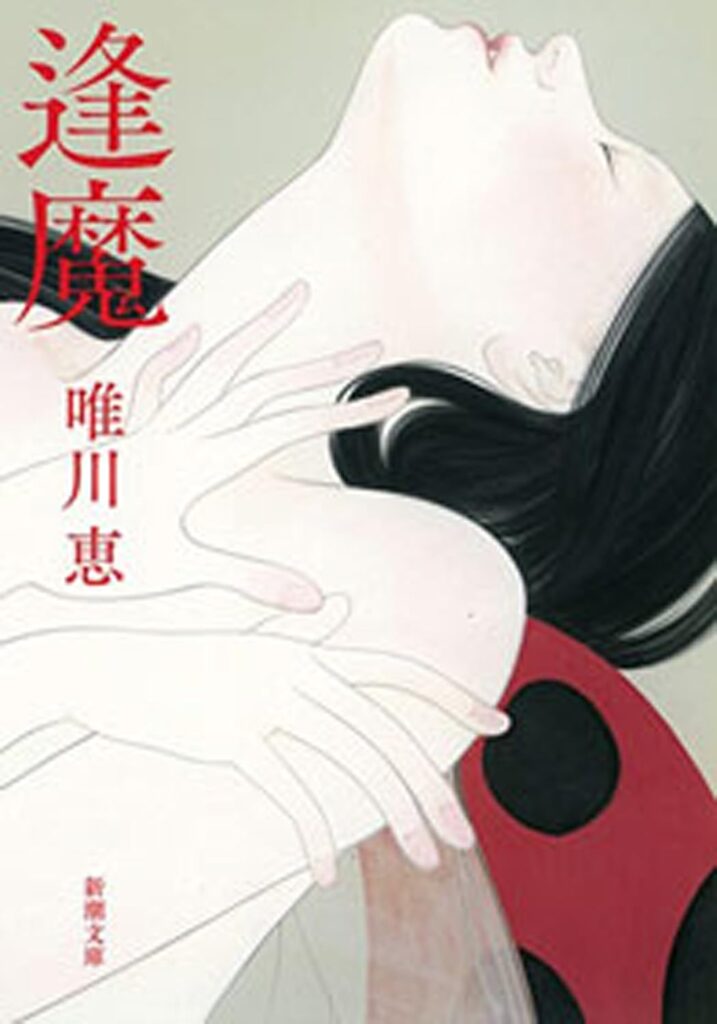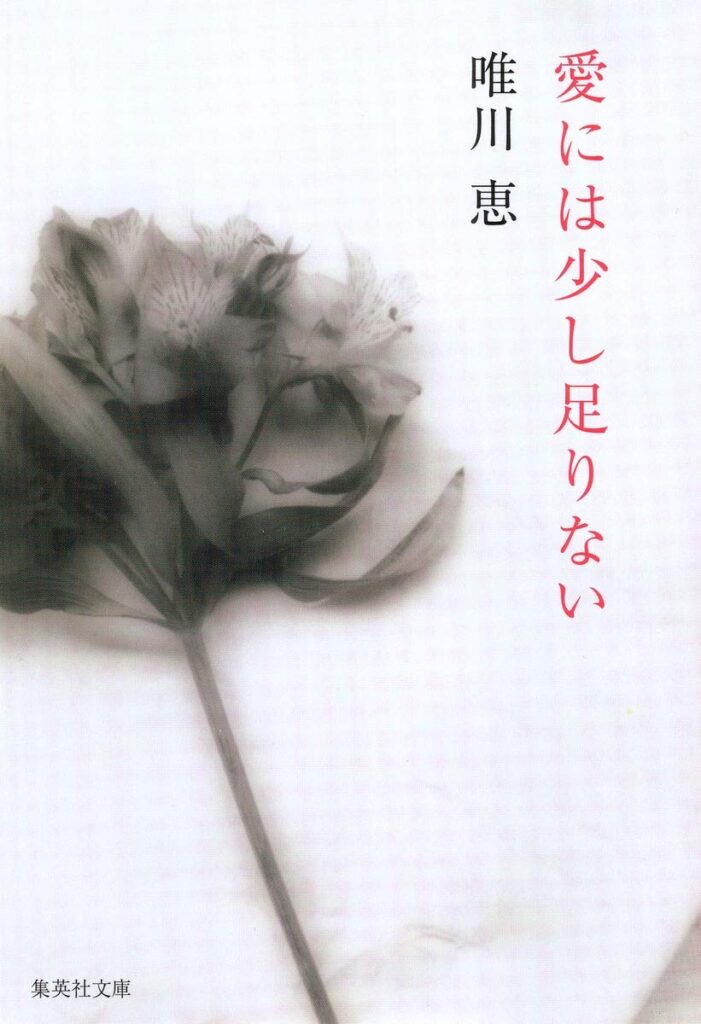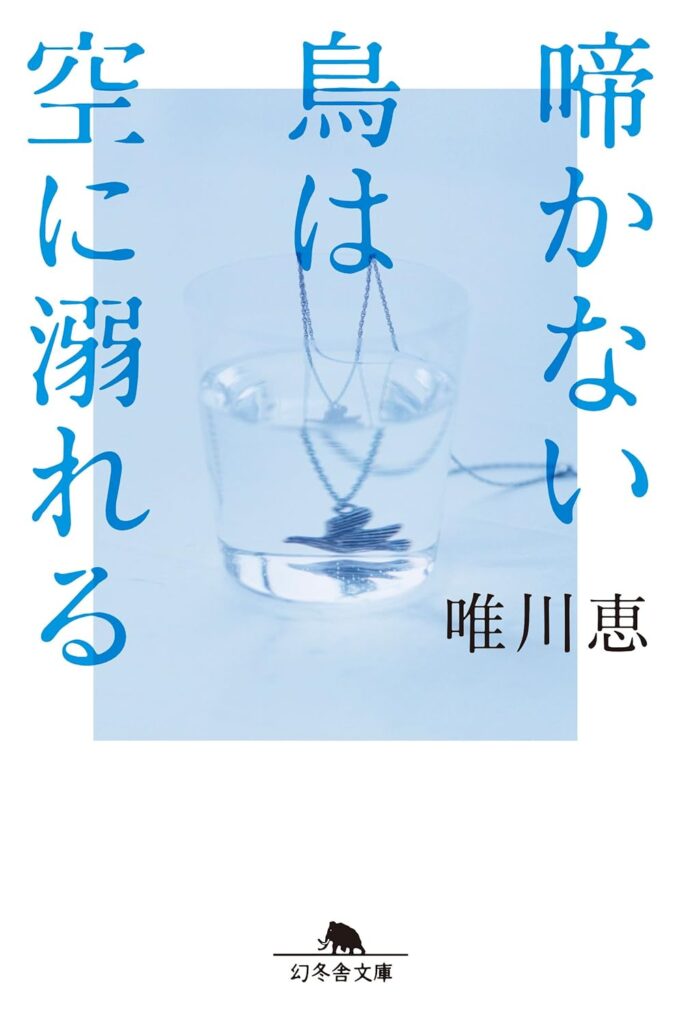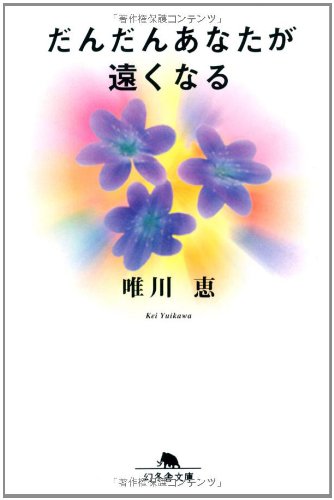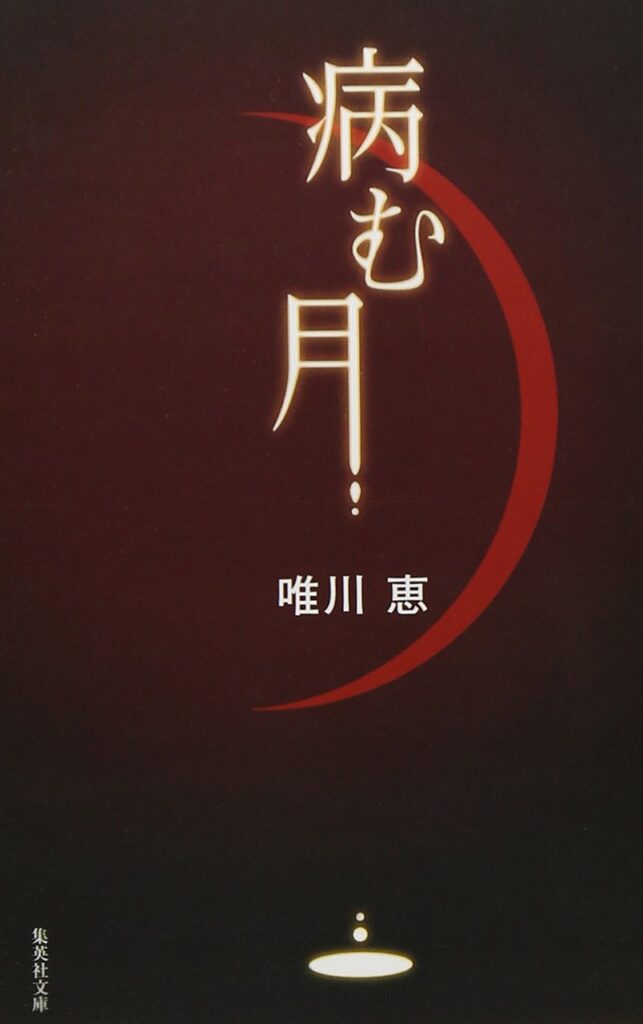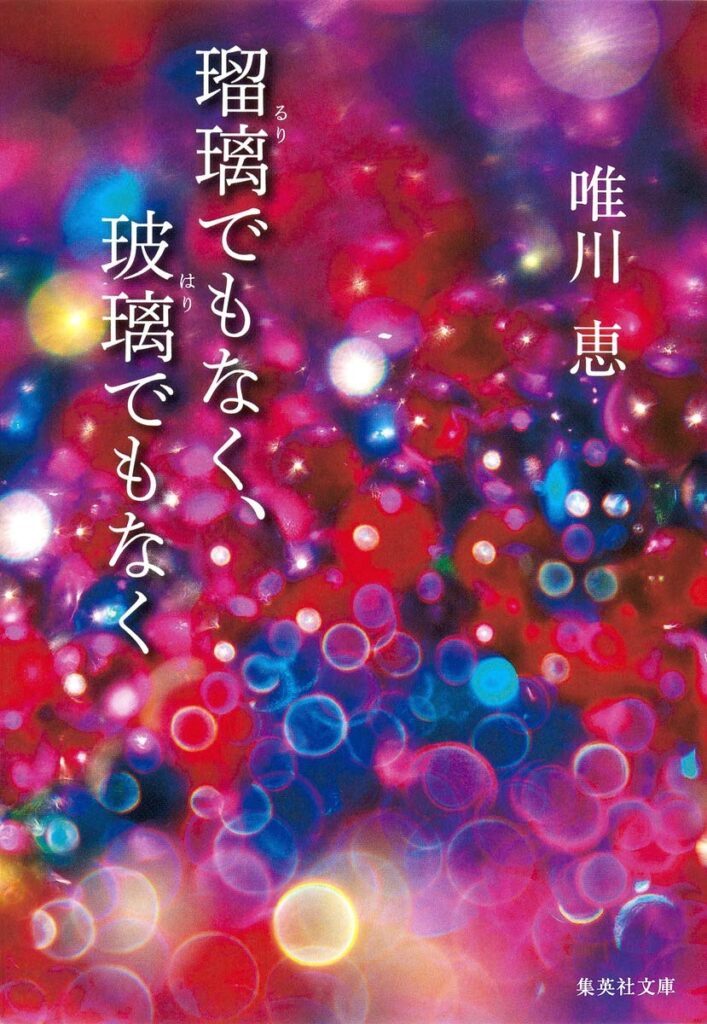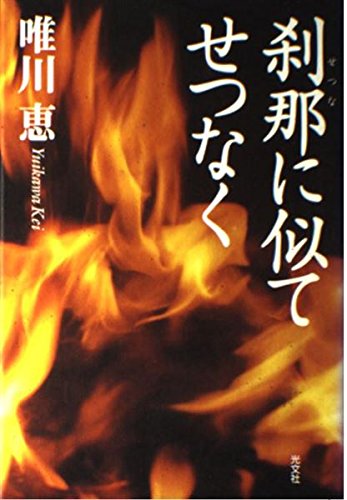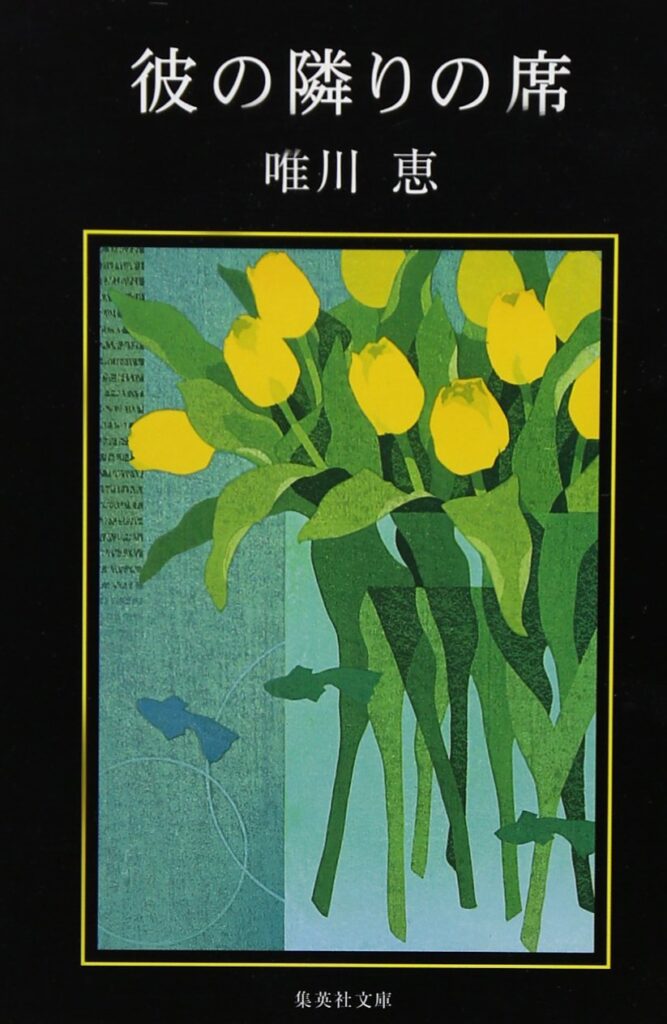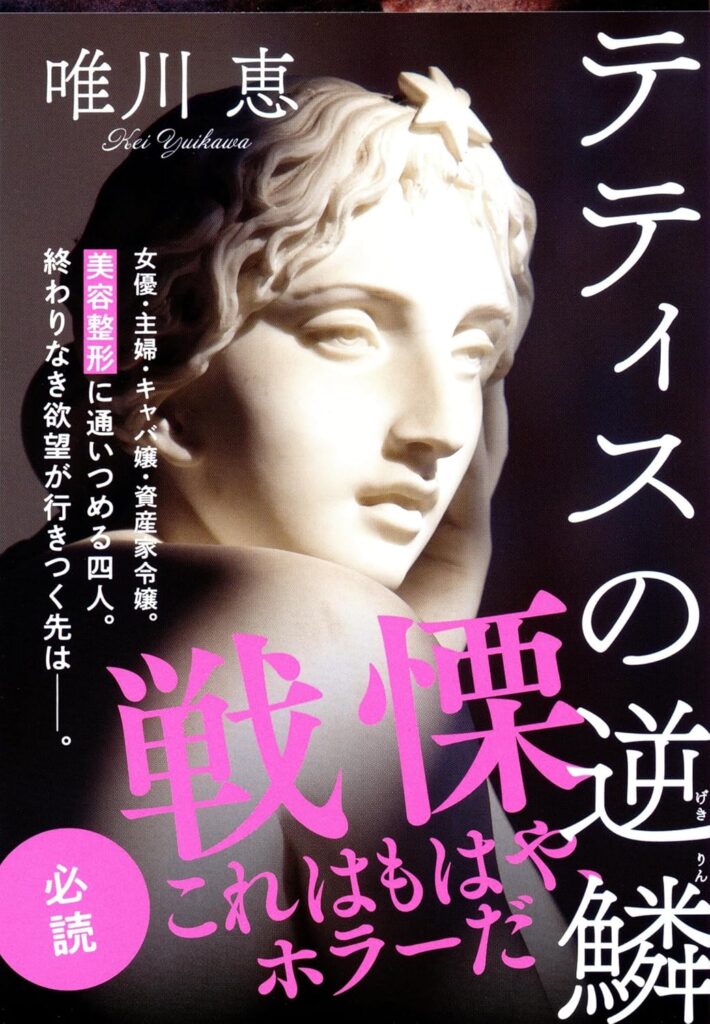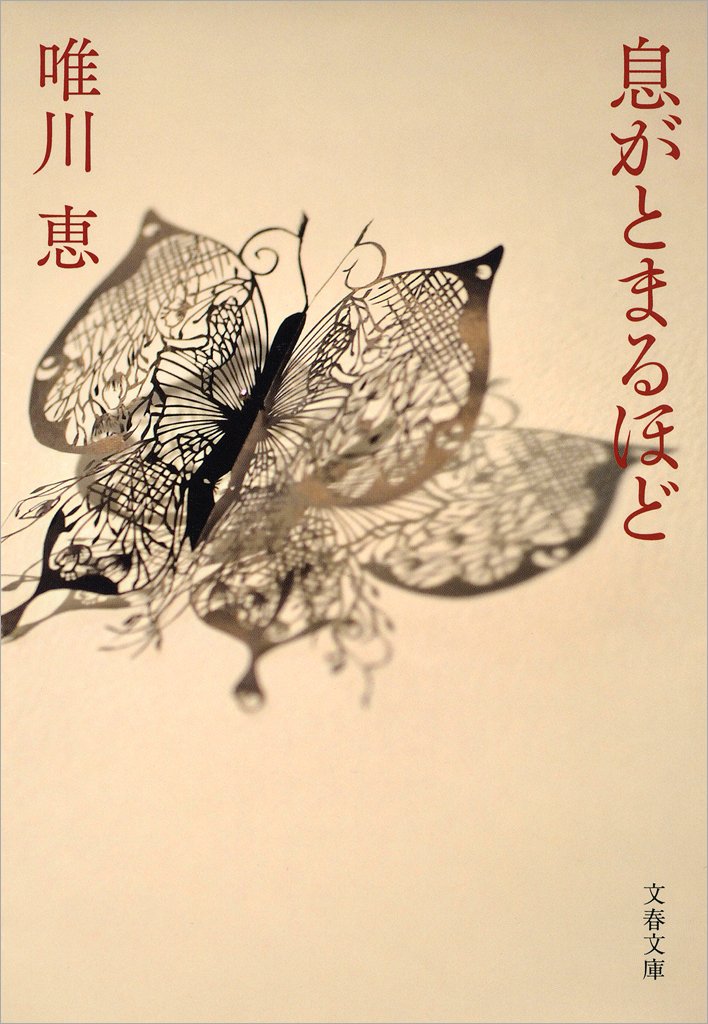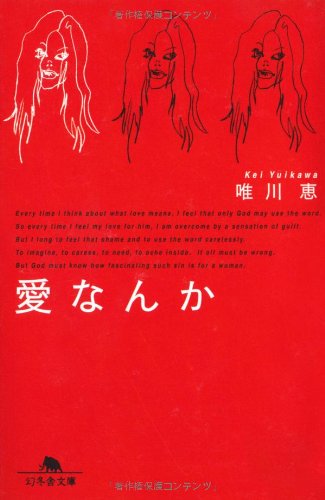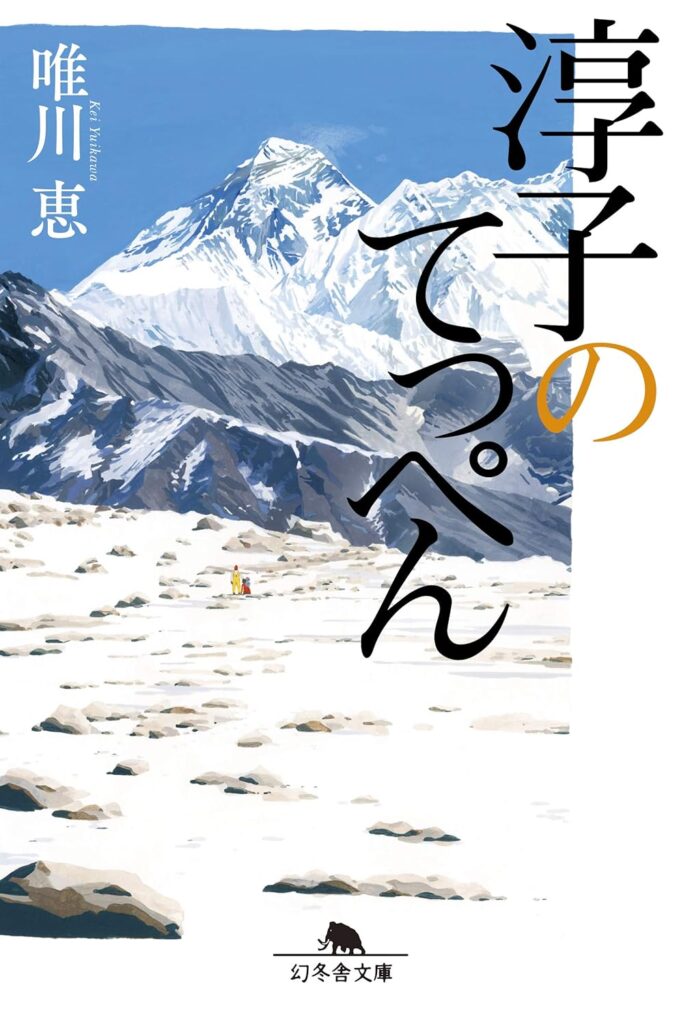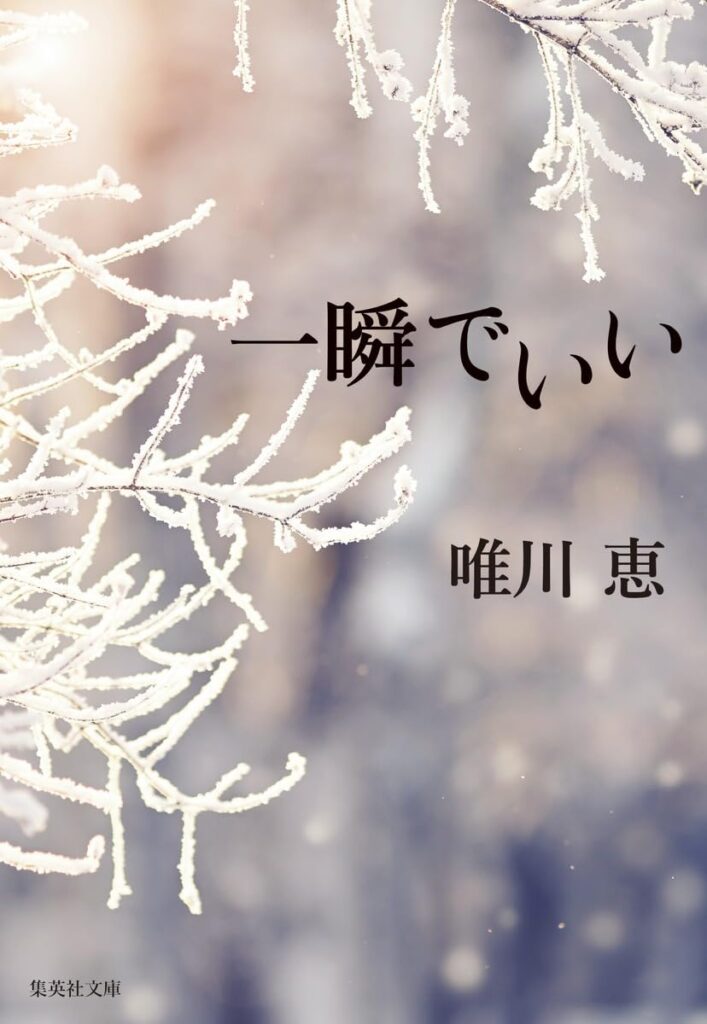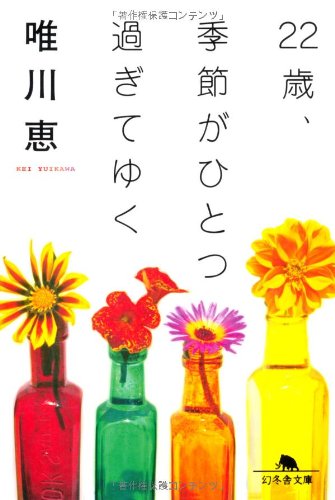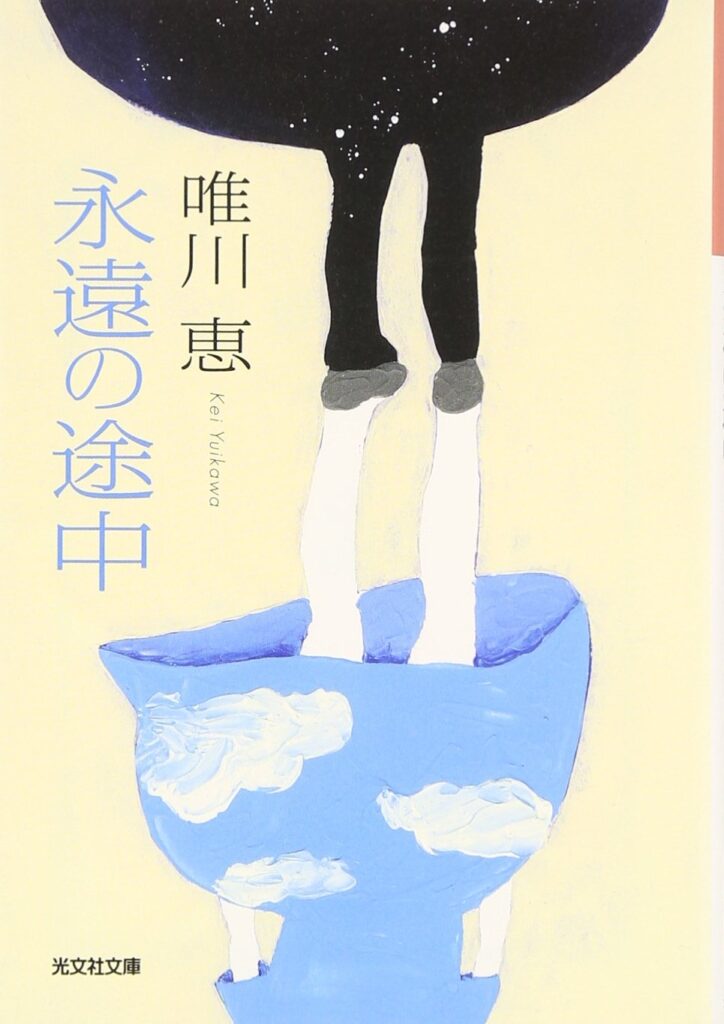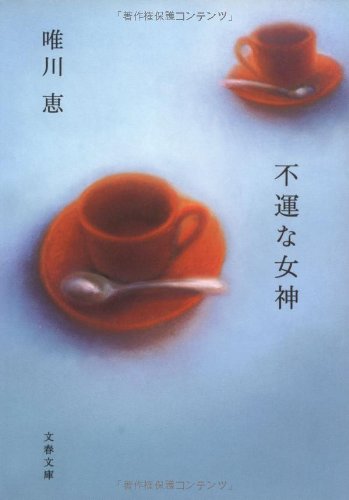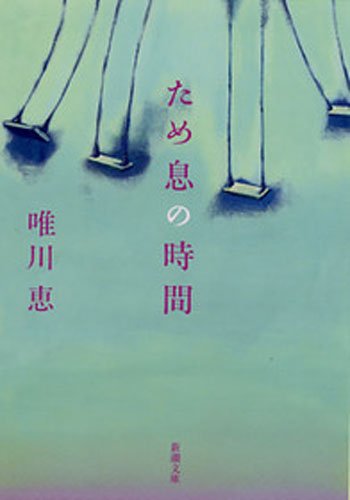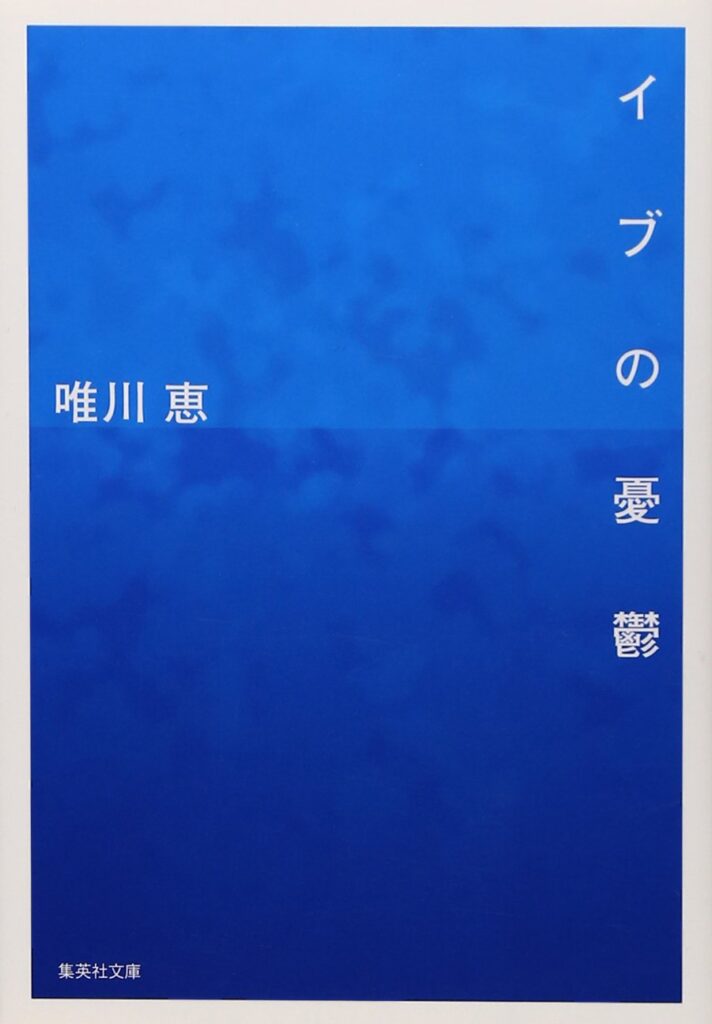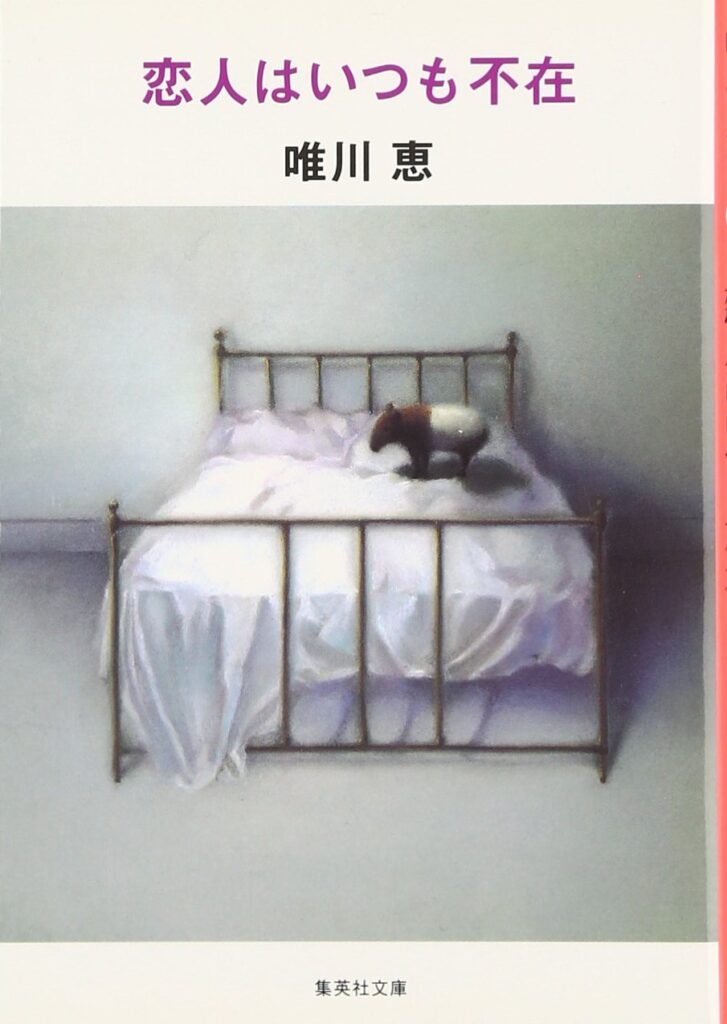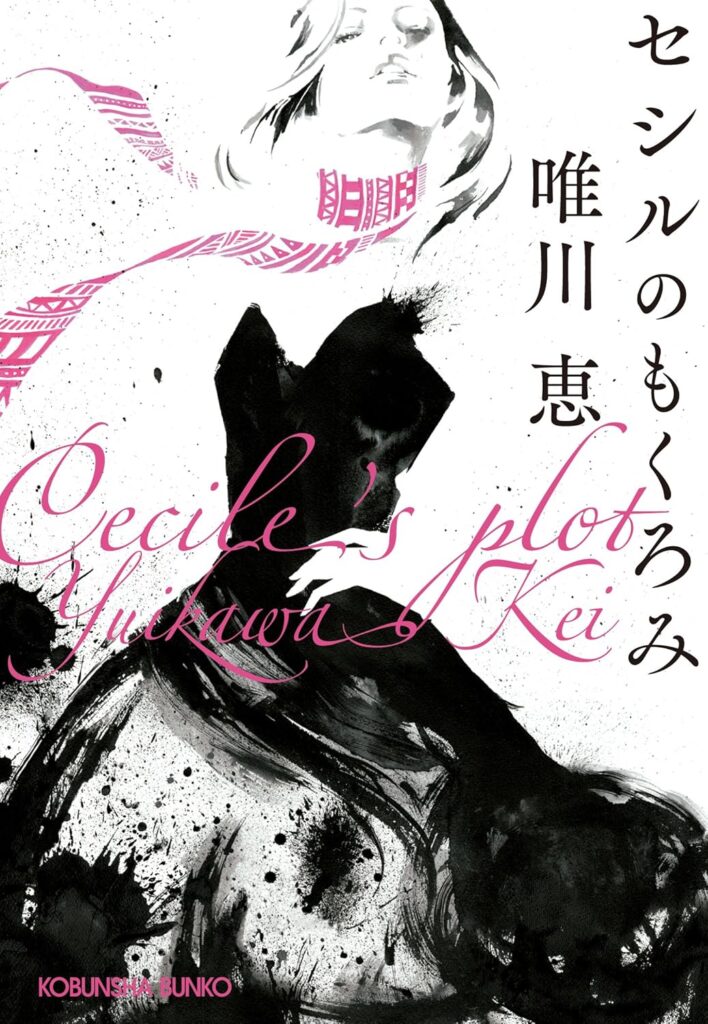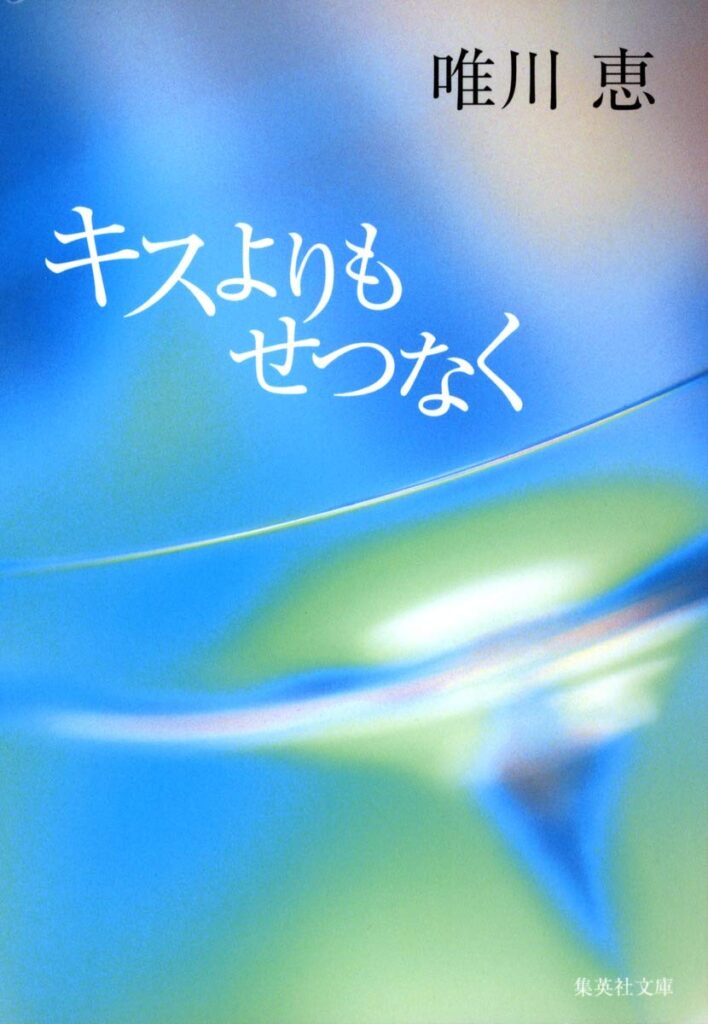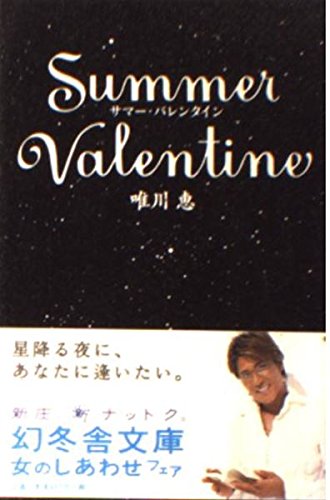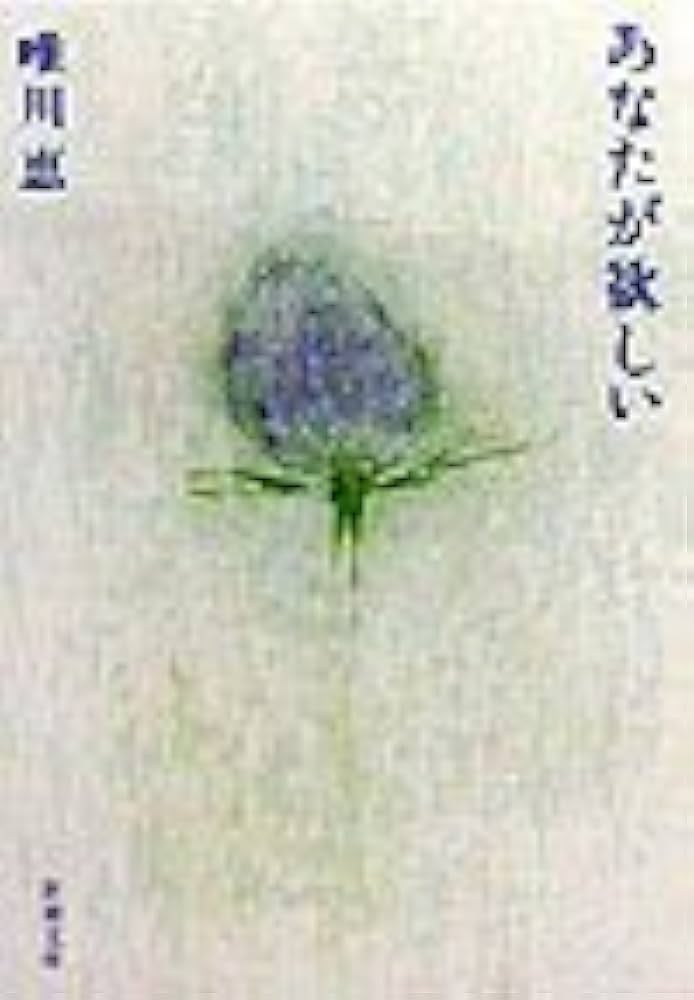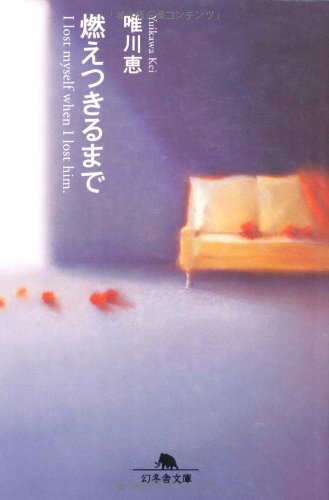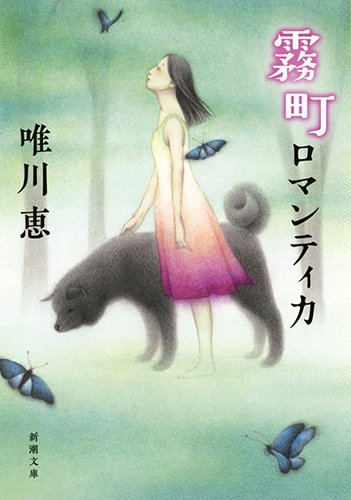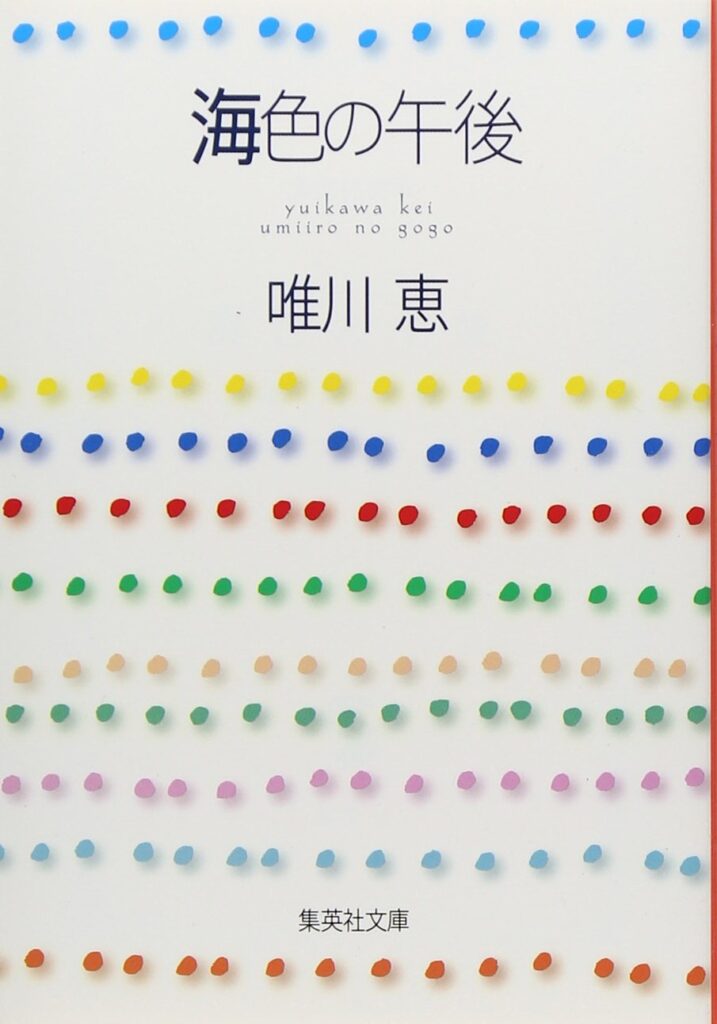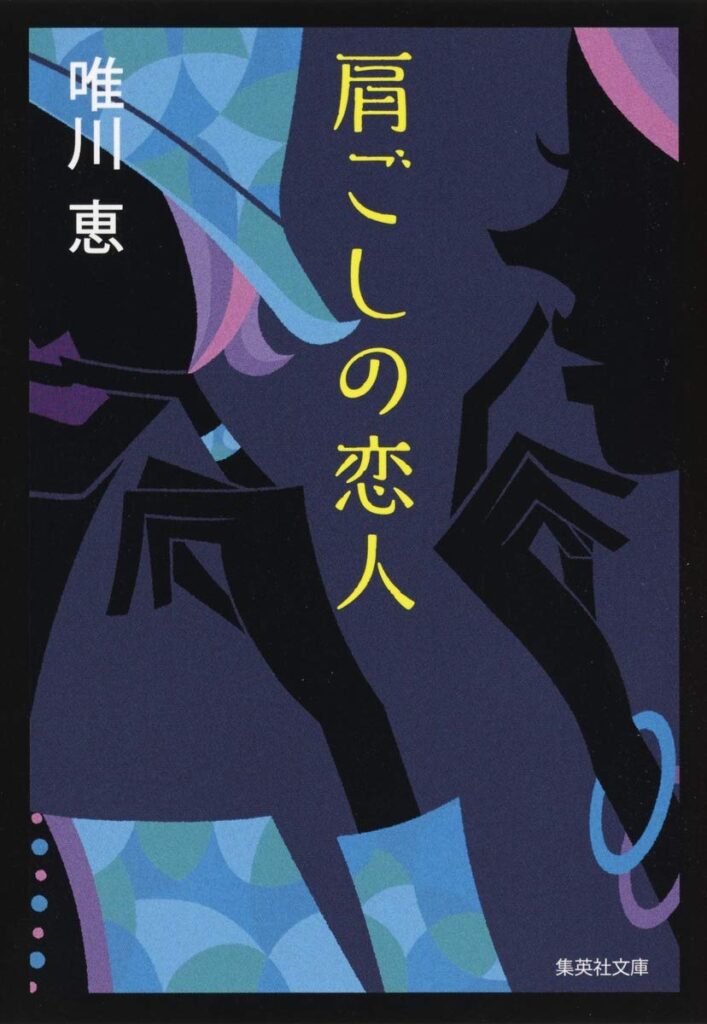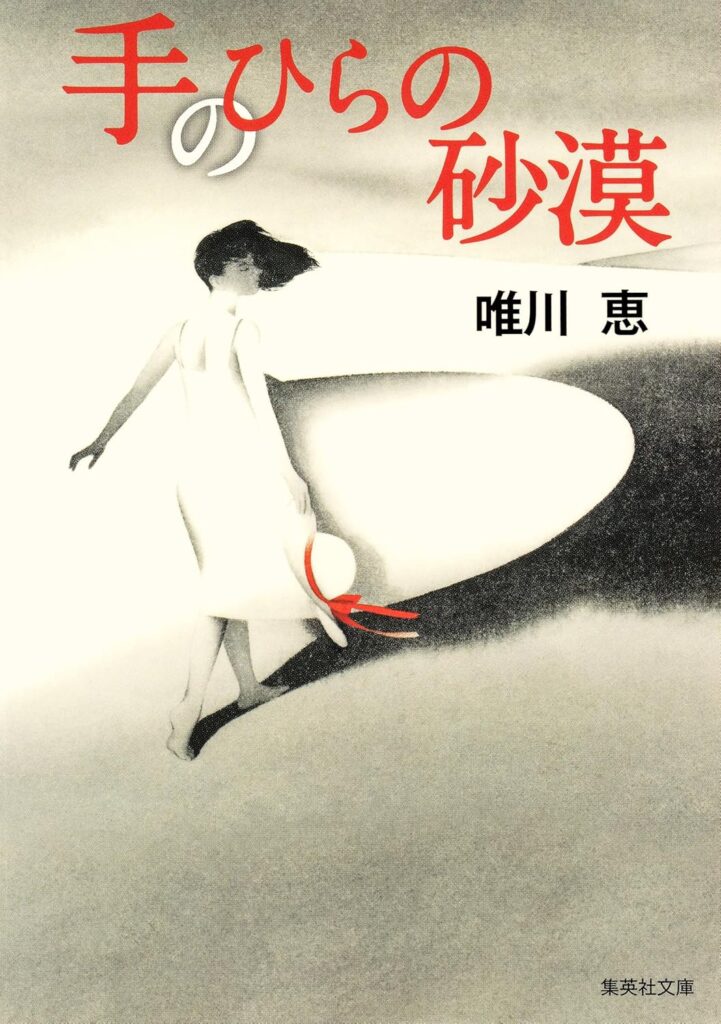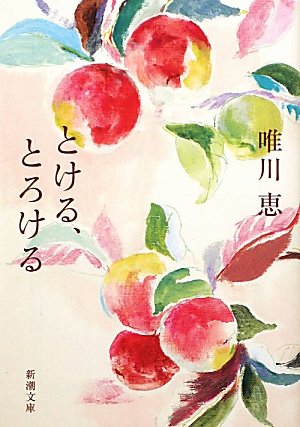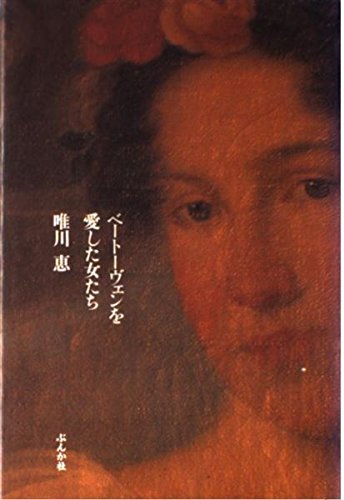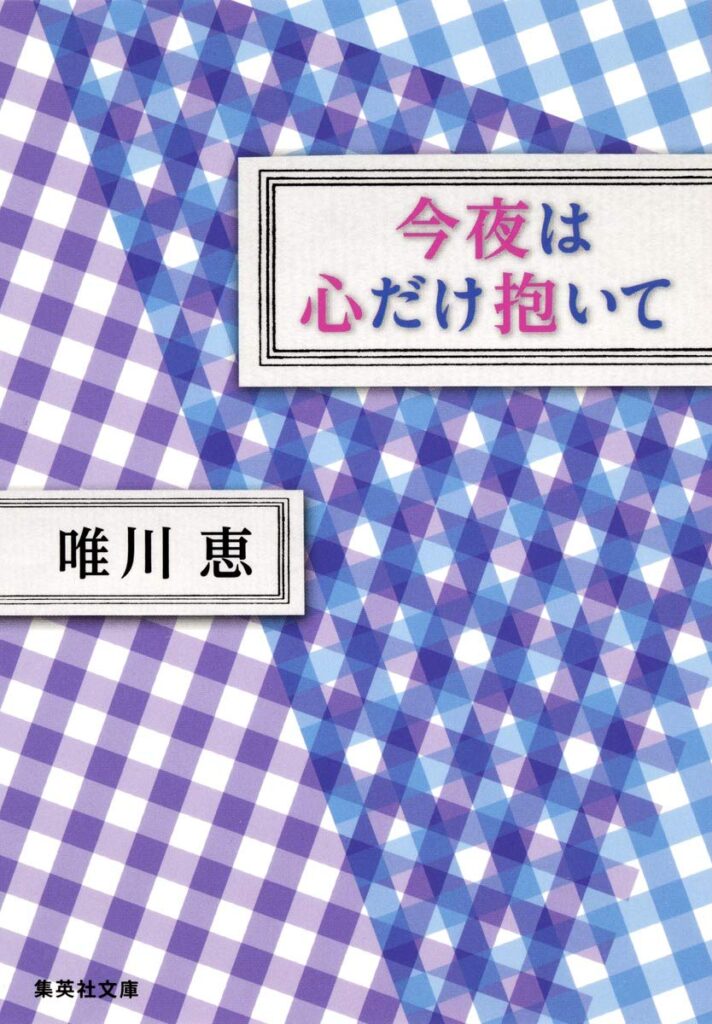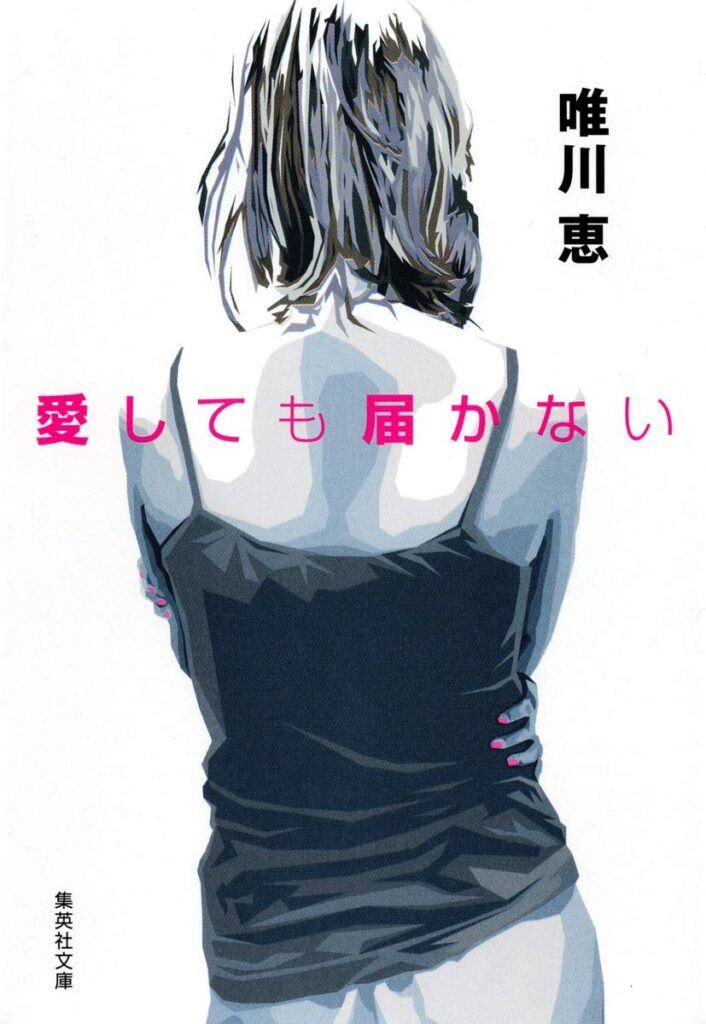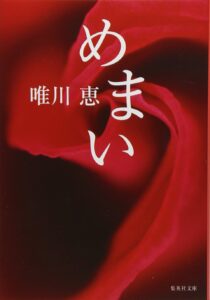 小説「めまい」のあらすじを物語の結末に触れる形で紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。唯川恵さんが紡ぐこの作品は、読む者の心を深く揺さぶり、日常に潜む愛と狂気の境界線を巧みに描き出しています。十編の物語が収められており、それぞれが異なる女性の視点から、心の奥底に潜む感情の渦を描いています。
小説「めまい」のあらすじを物語の結末に触れる形で紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。唯川恵さんが紡ぐこの作品は、読む者の心を深く揺さぶり、日常に潜む愛と狂気の境界線を巧みに描き出しています。十編の物語が収められており、それぞれが異なる女性の視点から、心の奥底に潜む感情の渦を描いています。
この物語集は、愛という感情が時としていかに危険な姿をみせるか、その危うさを私たちに突きつけてくるかのようです。読み進めるうちに、登場人物たちの切実な想いや、そこから生まれる執着、嫉妬、そして時には復讐心といった感情が、まるで自分のことのように迫ってくるかもしれません。
それぞれの物語は独立していますが、全体を通して流れるのは、人間の心の脆さや、愛ゆえに踏み越えてしまう一線といった、普遍的でありながらも目を背けたくなるようなテーマです。読後には、タイトルの通り、くらりとするような感覚や、心にずしりと残る何かがあることでしょう。
この記事では、そんな小説「めまい」がどのような物語なのか、そして私が各編を読んで何を感じたのかを、物語の核心に触れながら詳しくお伝えしていきたいと思います。この作品が持つ独特の世界観に、少しでも触れていただければ幸いです。
小説「めまい」のあらすじ
唯川恵さんの短編集「めまい」は、十人十色の女性たちが抱える、愛にまつわる心の揺らぎや、時として常軌を逸してしまうほどの強い想いを描いた物語が集められています。それぞれの物語は、読者の心に静かに、しかし確実に波紋を広げていきます。
例えば、「きれい」という物語では、美容外科医となった女性のもとに、かつて自分をいじめていた同級生が患者として現れ、自分とそっくり同じ顔にしてほしいと依頼します。過去の複雑な感情が渦巻く中で、美を追求する行為がどのような結末を迎えるのか、緊張感が漂います。また、「誰にも渡さない」では、親友の男性に長年想いを寄せる女性の、純粋ながらも歪んだ執着心が描かれ、その一途さが次第に不穏な空気を帯びていく様子に引き込まれます。
「青の使者」では、失踪した男性を巡る複数の女性たちの関係が、不気味な影を落としながら展開します。愛憎が絡み合い、日常が静かに侵食されていく様は、まるで心理的な迷宮に迷い込んだかのようです。「眼窩の蜜」では、双子の姉妹間の積年の競争心や嫉妬が、子供を強く望む姉の常軌を逸した行動へと繋がり、読む者に強烈な印象を残します。食べるという行為が生々しく、そして恐ろしく描かれています。
さらに、結婚詐欺に遭い絶望の淵に立たされた女性が、謎めいた青年と出会う「翠の呼び声」や、元教え子との再会がきっかけで、自身の結婚生活が静かに崩壊していく「降りやまぬ」など、過去の出来事や人間関係が現在の主人公たちに大きな影響を与える物語も収められています。これらの物語は、時に救いようのない状況や、人間の心の闇を容赦なく描き出します。
夫からの暴力に苦しむ美容師の女性が主人公の「嗤う手」では、彼女の日常と精神が徐々に蝕まれていく過程が描かれ、読者は息苦しささえ感じるかもしれません。一方で、短編集の最後に収められた「月光の果て」は、病院内で盗みを働く女性と、それを目撃し脅迫する少年との間に芽生える、どこか切なく純粋な関係性を描き、他の物語とは少し異なる読後感を残します。
これらの物語を通して、愛という感情がいかに多面的で、時に人を強くし、時に人を狂わせてしまうのかを、まざまざと見せつけられるのです。登場人物たちの行動や心理描写は非常に巧みで、読者は彼女たちの感情の揺れ動きに、いつしか深く共感し、あるいは戦慄を覚えることになるでしょう。
小説「めまい」の長文感想(ネタバレあり)
唯川恵さんの小説「めまい」を読み終えたとき、私はしばらくの間、言葉を失いました。それぞれの物語が、まるで短編映画のように鮮烈な印象を残し、読後には深い余韻とともに、人間の心の奥底を覗き見たような、ある種の「めまい」を感じたのです。愛という美しい響きの裏に潜む、執着、嫉妬、憎悪、そして狂気。それらが、ごく普通の日常の中で、いともたやすく顔を出す様に、私は何度も背筋が寒くなる思いをしました。
まず、冒頭を飾る「きれい」。美容外科医の庸子と、かつてのいじめの加害者でありながら庸子そっくりの顔を求める吉江。この設定だけでも十分に衝撃的ですが、物語が進むにつれて明らかになるのは、美しさへの渇望の裏に隠された、歪んだ復讐心と自己肯定感の欠如でした。吉江が手に入れた「美」が、結局は彼女を真の幸福には導かないであろうこと、そして庸子の心にも癒えない傷と複雑な感情が残り続けるであろうことが示唆され、読んでいるこちらの胸が苦しくなりました。美とは何か、許しとは何かを考えさせられる一編です。
次に「誰にも渡さない」。主人公の朋子(仮にそう呼びます)が抱く章吾への想いは、純粋な片思いから始まりながらも、いつしか「誰にも渡したくない」という強烈な独占欲へと変貌していきます。章吾の無邪気さが、かえって彼女の心を追い詰めていく様は、読んでいて息苦しさを感じるほどでした。結末で示唆される彼女の行動は、愛が狂気に転じる瞬間を鮮やかに描き出しており、その静かな恐ろしさに鳥肌が立ちました。「人を呪わば穴二つ」という言葉が脳裏をよぎり、一方的な想いの危うさを痛感させられます。
「青の使者」は、この短編集の中でも特に異質な空気を放っていたように感じます。失踪した男性、森岡を巡る妻と二人の愛人。貸した金の返済を求める容子の行動は、次第に不穏な影を帯びていきます。特に、もう一人の愛人ユリと会った後の彼女の決断は、日本の古い呪術である「蠱毒」を彷彿とさせ、物語にオカルト的な恐怖をもたらしています。愛憎が絡み合った女性たちの執念が、日常を超えた領域にまで踏み込んでしまう様に、人間の心の闇の深さを感じずにはいられませんでした。
「耳鳴りにも似て」は、過去の人間関係の力学が、現在にまで影響を及ぼす様を描いています。宏美にとって、かつて自分を支配していた小夜子の再来は、悪夢の再演のようだったでしょう。マルチ商法という現代的なテーマを絡めながら、人の弱さや欲望、そして裏切りが生々しく描かれています。小夜子の巧みな言葉に、宏美だけでなく、周囲の人間も翻弄されていく様は、現実社会でも起こりうる話だと感じ、他人事とは思えませんでした。タイトルの「耳鳴り」が、過去のトラウマのしつこさや、心の不協和音を象徴しているようで印象的です。
そして、おそらくこの短編集で最も強烈な印象を残すであろう一編が「眼窩の蜜」です。双子の姉妹である語り手と祥子。幼い頃から病弱な祥子に全てを奪われてきたと感じる語り手の屈折した感情と、子供を欲するあまりに魚の目を食べるという祥子の常軌を逸した行動。このグロテスクとも言える描写は、生理的な嫌悪感とともに、人間の持つ根源的な欲望の恐ろしさを突きつけてきます。「眼窩の蜜」というタイトル自体が不気味で、祥子の狂気がどこまでも深く、暗いものであることを感じさせます。姉妹間の愛憎という普遍的なテーマを、ここまでショッキングに描いた作品は稀有ではないでしょうか。
「闇に挿す花」は、離婚し花屋で働く真弓が、店の客である堂本と不倫関係になる物語です。堂本の娘の話を嬉々として聞く真弓の心理には、どこか危うさが漂っていました。関係が終わった後、彼女が選ぶ道が具体的には描かれないものの、そこには彼女自身の過去のトラウマや、歪んだ嫉妬心が深く関わっていることが示唆されます。闇の中に一輪の花を求めるように始まった関係が、結局はさらなる闇へと繋がっていくような、救いのない読後感が残りました。
「翠の呼び声」は、結婚詐欺に遭い、愛猫の死も重なり、生きる希望を失った音絵の物語です。彼女の絶望感は痛いほど伝わってきて、読んでいて非常に辛かったです。まさに命を絶とうとする瞬間に現れる謎の青年。彼の存在は、一筋の光のようにも見えますが、この短編集のトーンを考えると、新たな不安の始まりではないかとも勘繰ってしまいます。しかし、他の物語とは少し異なり、どこか儚い希望のようなものも感じさせ、音絵には幸せになってほしいと願わずにはいられませんでした。
「嗤う手」は、夫からのDVに苦しむ美容師の女性が語り手です。美容室を訪れる客たちの話と、自身の過酷な日常が交錯する中で、彼女の精神が少しずつ壊れていく様が克明に描かれています。逃れられない暴力の恐怖と、誰にも理解されない孤独。タイトルの「嗤う手」が、暴力を振るう夫の手なのか、それとも追い詰められた彼女自身の心の叫びなのか、様々な解釈ができるでしょう。日常と狂気が隣り合わせにあることの恐ろしさを、改めて感じさせられました。
「降りやまぬ」では、元家庭教師の澤子の元に、かつての教え子が訪ねてきたことをきっかけに、彼女の結婚生活が崩壊へと向かいます。問題の根源が、教え子の父親にあることが示唆され、過去の秘密や過ちが、時を経て現在の幸せをいとも簡単に打ち砕いてしまう非情さを描いています。降りやまない雨のように、過去の出来事が澤子の心に重くのしかかり続けるのだろうと思うと、やりきれない気持ちになりました。
最後に収められた「月光の果て」。病院で盗みを繰り返す教子と、それを目撃し脅迫する少年・篤志。最初は歪んだ関係から始まるものの、二人が交流を深めるうちに、そこには確かに純粋な感情が芽生えていくように見えます。この短編集の中では異質とも言える、ほのかな光を感じさせる物語でした。もちろん、手放しでハッピーエンドとは言えないかもしれませんが、暗闇の中で見つけた小さな灯りのような、切なくも温かい余韻を残してくれます。他の物語が人間の心の闇を深くえぐり出すのに対し、この物語は、そんな闇の中にも救いや変化の可能性があることを示唆しているのかもしれません。
この十編を通して、唯川恵さんは、愛という感情が持つ多面性と、それが時として人間をどこまでも残酷に、そしてどこまでも愚かにさせてしまう様を見事に描き切っています。登場人物たちは皆、特別な人間ではなく、私たちの隣にいるかもしれない、ごく普通の人々です。だからこそ、彼女たちの心の揺らぎや、一線を踏み越えてしまう瞬間に、私たちは共感し、恐怖し、そして目が離せなくなるのでしょう。
文章は非常に読みやすく、スラスラとページをめくることができるのですが、描かれている内容は決して軽やかではありません。むしろ、その読みやすさが、じわじわと心を侵食してくるような、独特の怖さを持っているように感じました。短編でありながら、それぞれの物語が非常に濃密で、読後に様々なことを考えさせられます。
特に印象的だったのは、女性たちの心理描写の巧みさです。内に秘めた嫉妬心、独占欲、復讐心、劣等感、そしてそれらが複雑に絡み合い、やがては破滅的な行動へと繋がっていく過程が、実にリアルに描かれています。それは、女性であれば誰しもが心のどこかに持っているかもしれない感情の断片であり、だからこそ、読んでいてヒリヒリとした痛みを感じるのかもしれません。
この「めまい」という作品は、単に怖い話を集めたものではなく、人間の愛と業、そして心の深淵を巧みに描き出した文学作品だと感じました。読んでいる間は、登場人物たちの感情に引きずり込まれ、苦しくなることもありましたが、読み終えた後には、人間の複雑さや、愛というものの計り知れなさを改めて考えさせられました。美しい装丁とは裏腹に、心に深く刻まれる棘を残していくような、忘れがたい一冊です。
まとめ
唯川恵さんの小説「めまい」は、愛という名の感情が持つ、美しさだけではない、もう一つの顔――執着、嫉妬、そして時には狂気へと変貌する様を、十編の物語を通して鮮烈に描き出した短編集です。それぞれの物語に登場する女性たちは、愛するがゆえに、あるいは愛を渇望するがゆえに、心の均衡を失い、危うい淵へと足を踏み入れていきます。
この作品を読むことは、人間の心の奥底に潜む、普段は目を背けているかもしれない感情と向き合う体験とも言えるでしょう。物語の結末に触れる形でその内容をお伝えしてきましたが、実際に読んでいただくことで、登場人物たちの息遣いや、じわりと迫りくるような心理的な緊張感をより深く感じていただけるはずです。
各編の読後感は決して明るいものばかりではありません。むしろ、ずしりとした重みを心に残したり、タイトル通り「めまい」を感じるような感覚に襲われたりするかもしれません。しかし、それこそがこの作品の持つ力であり、人間の感情の複雑さ、そして愛の深淵を巧みに描き出している証左と言えるでしょう。
もしあなたが、人間の心の機微や、愛という感情が持つ光と影の部分に興味があるのなら、この小説「めまい」は、きっと忘れられない読書体験を与えてくれるはずです。美しい言葉で紡がれる、少し怖くて、そして切ない物語の世界に、ぜひ触れてみてください。