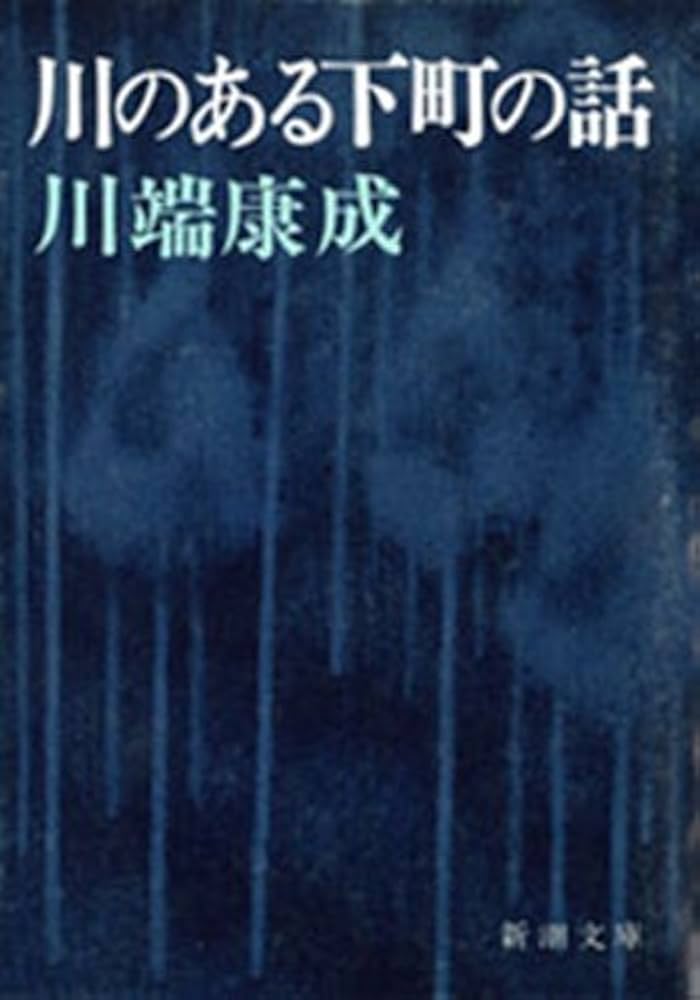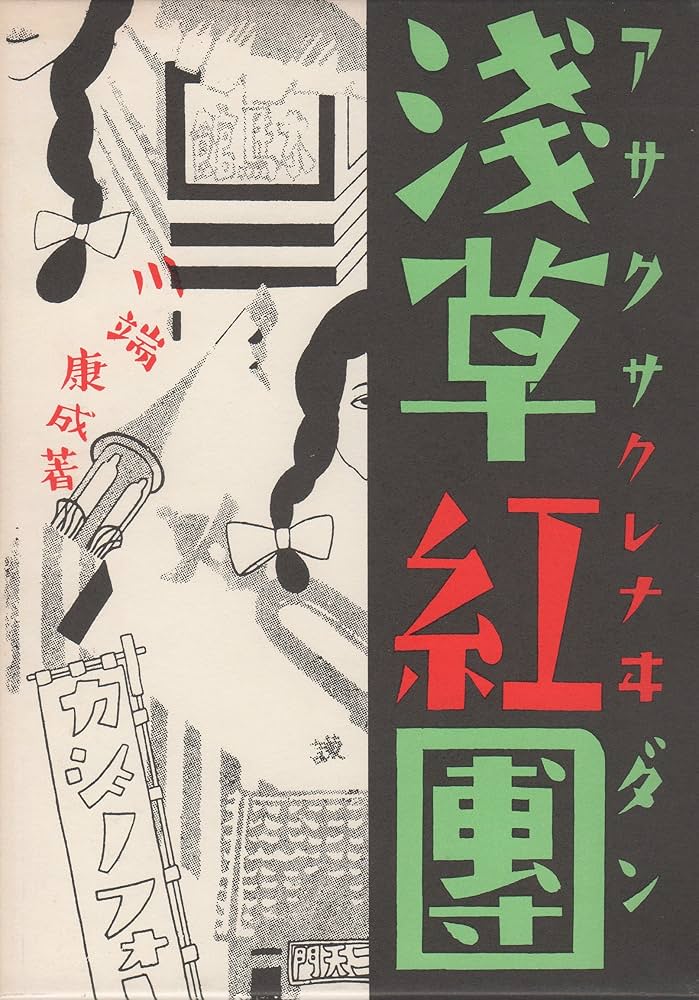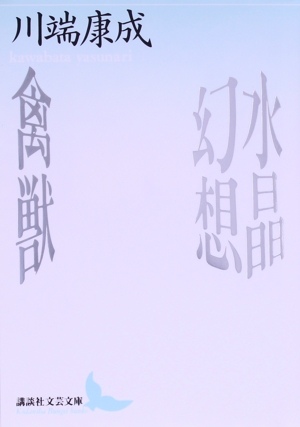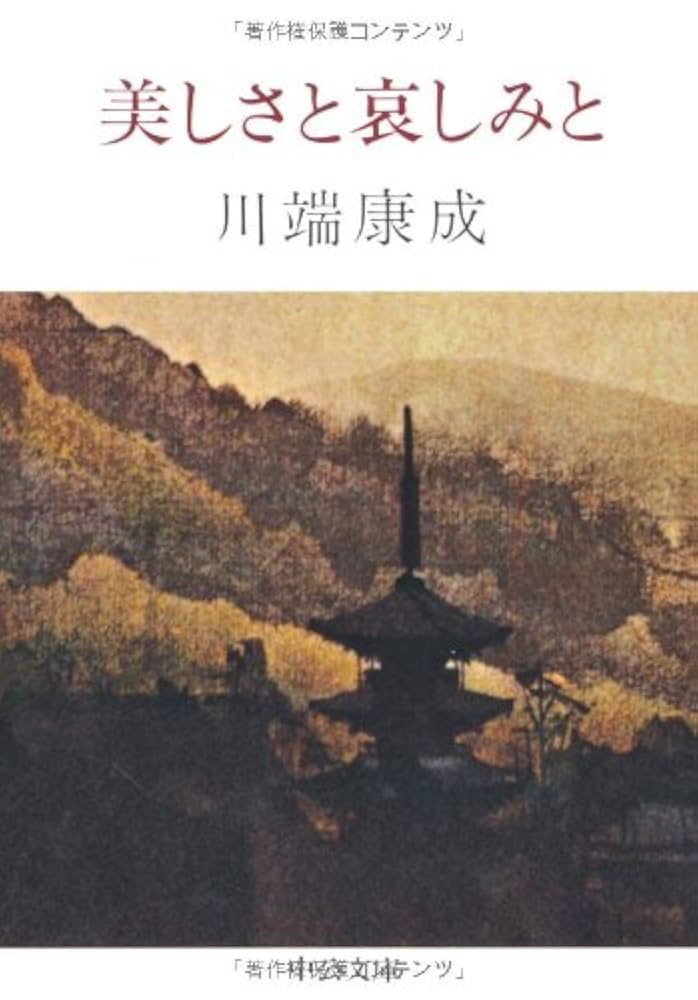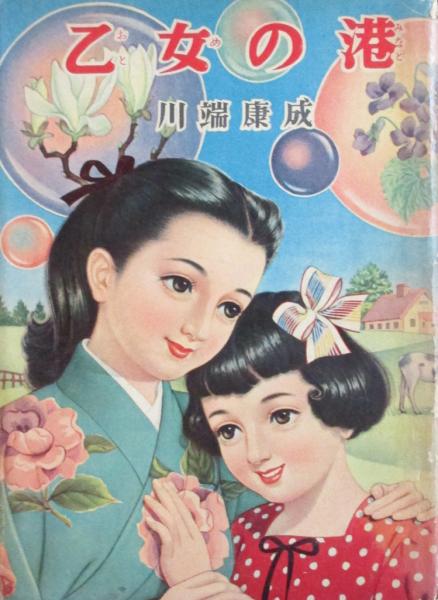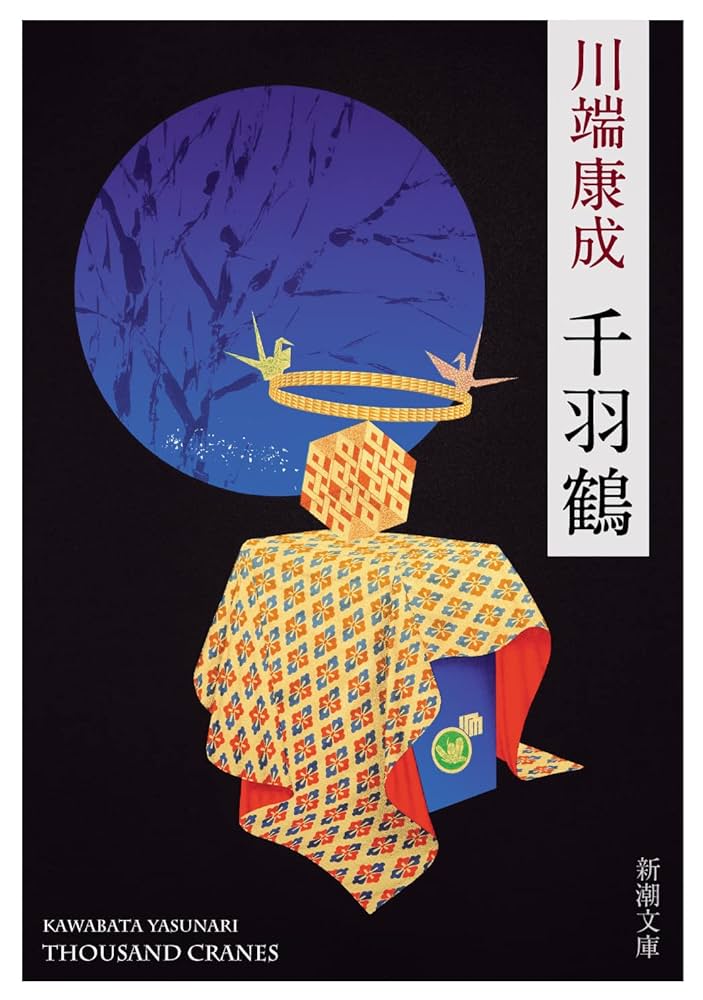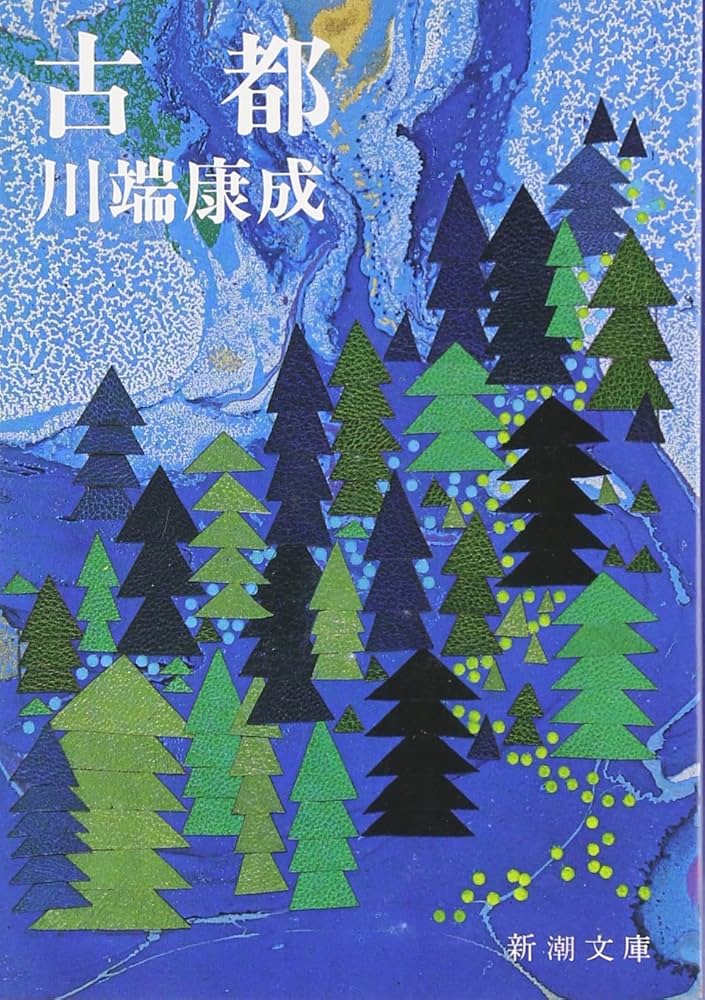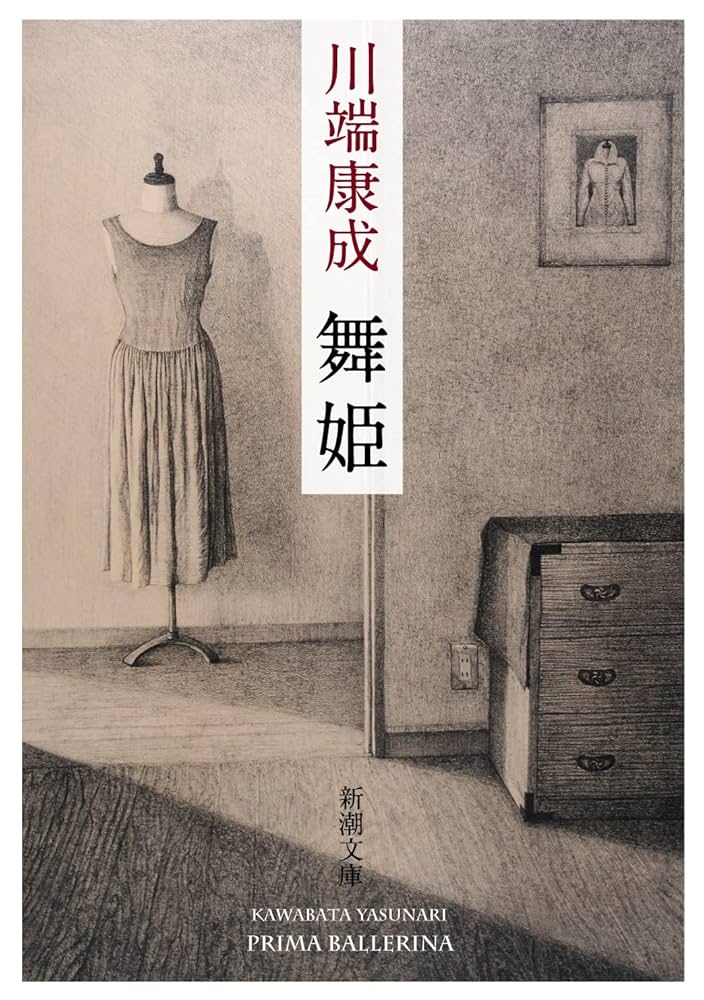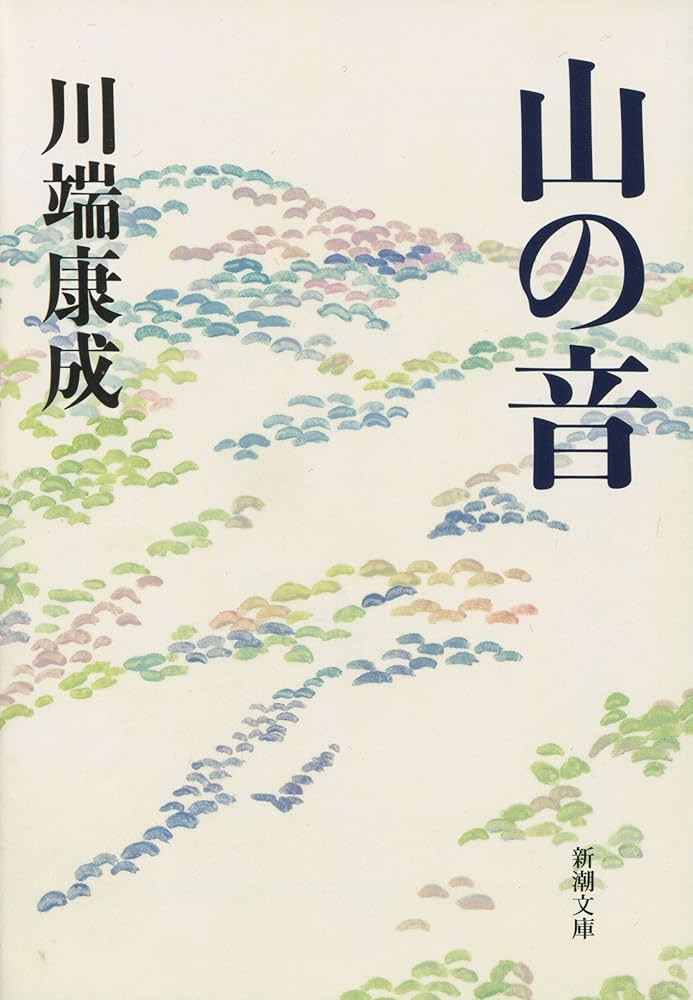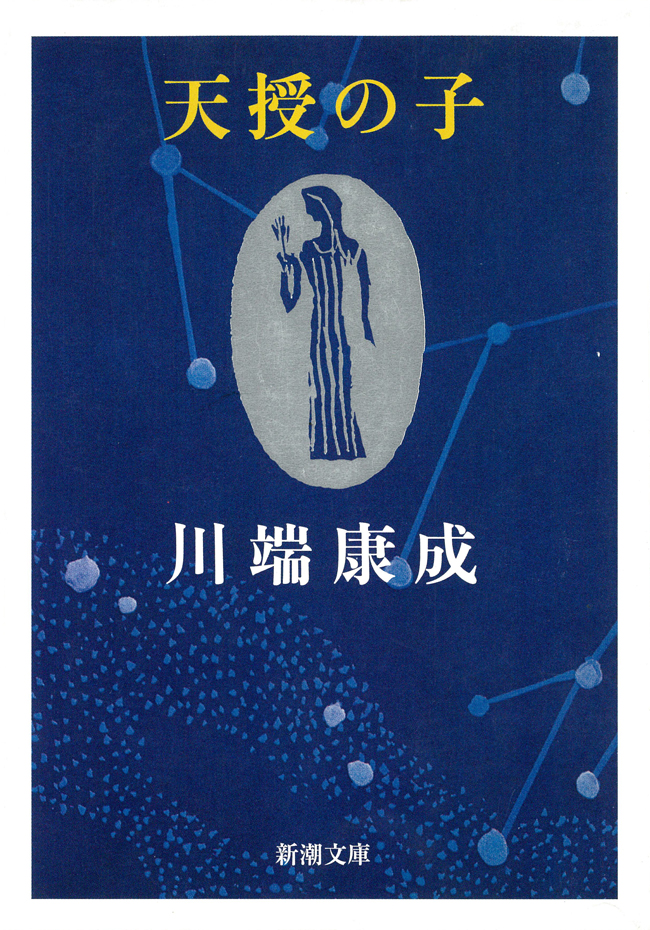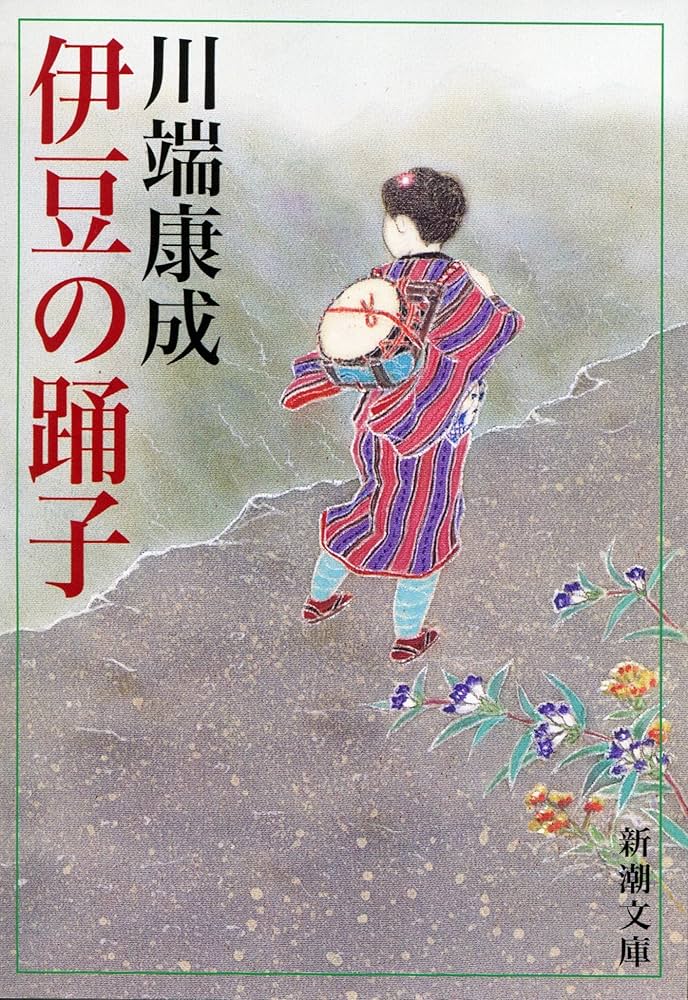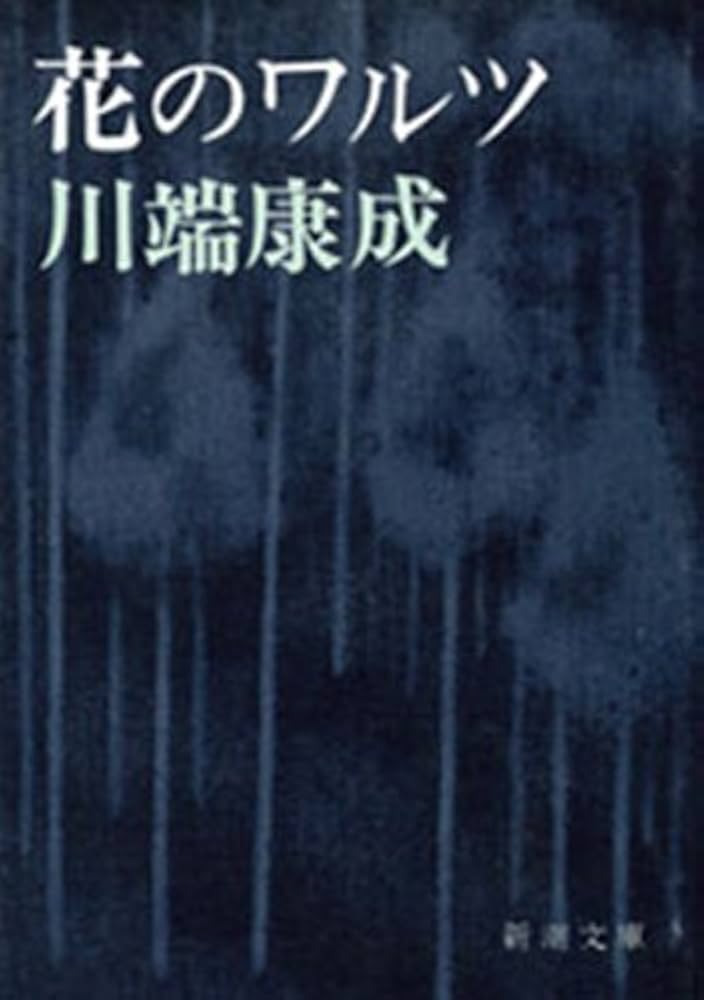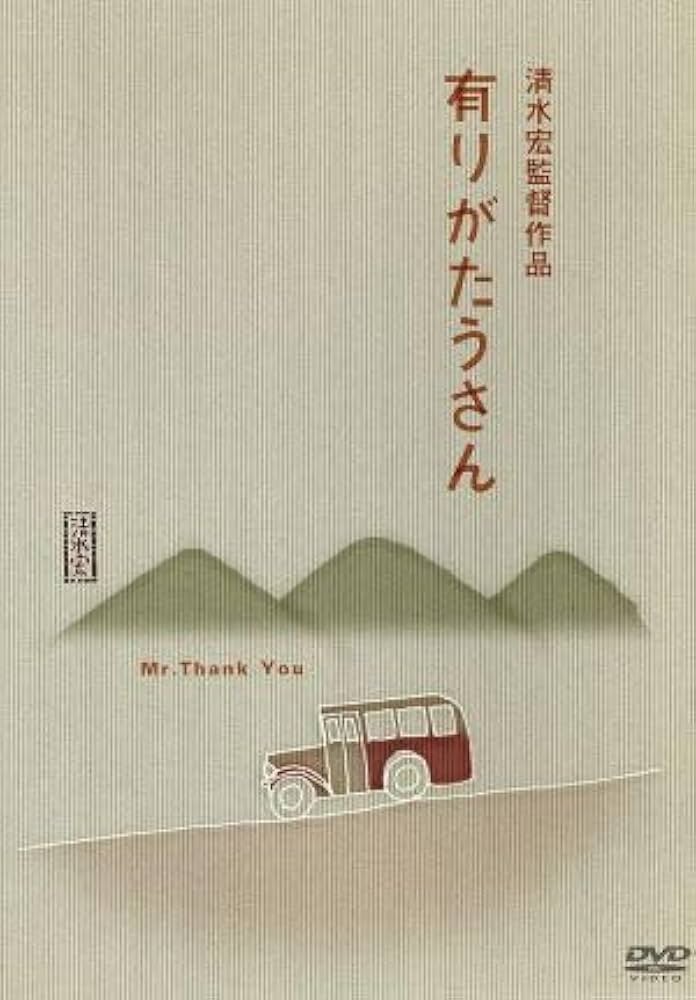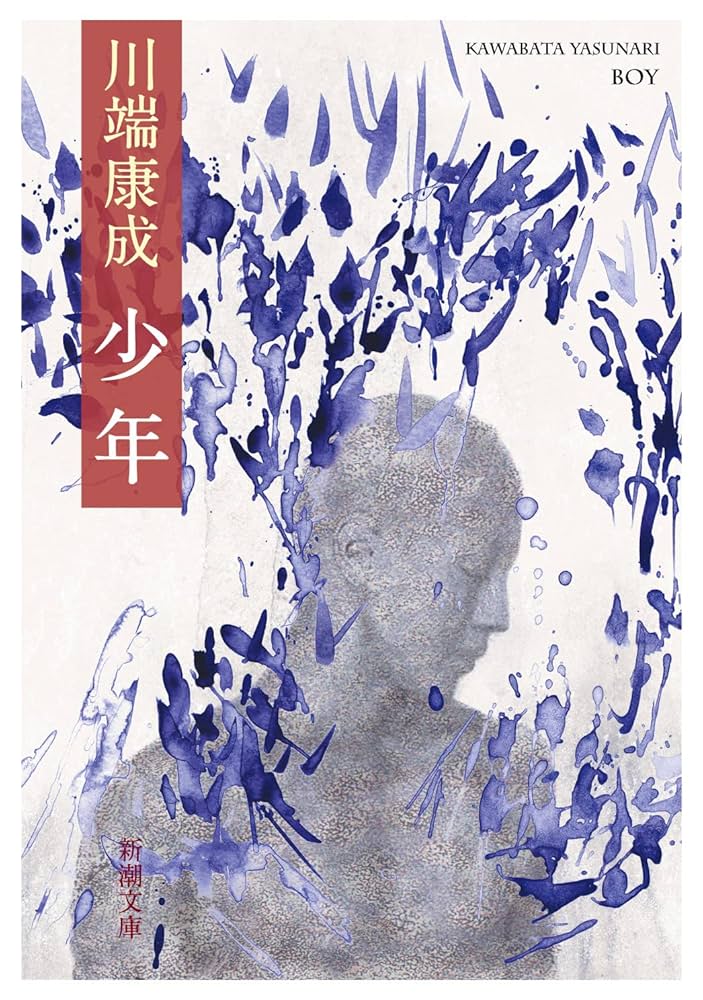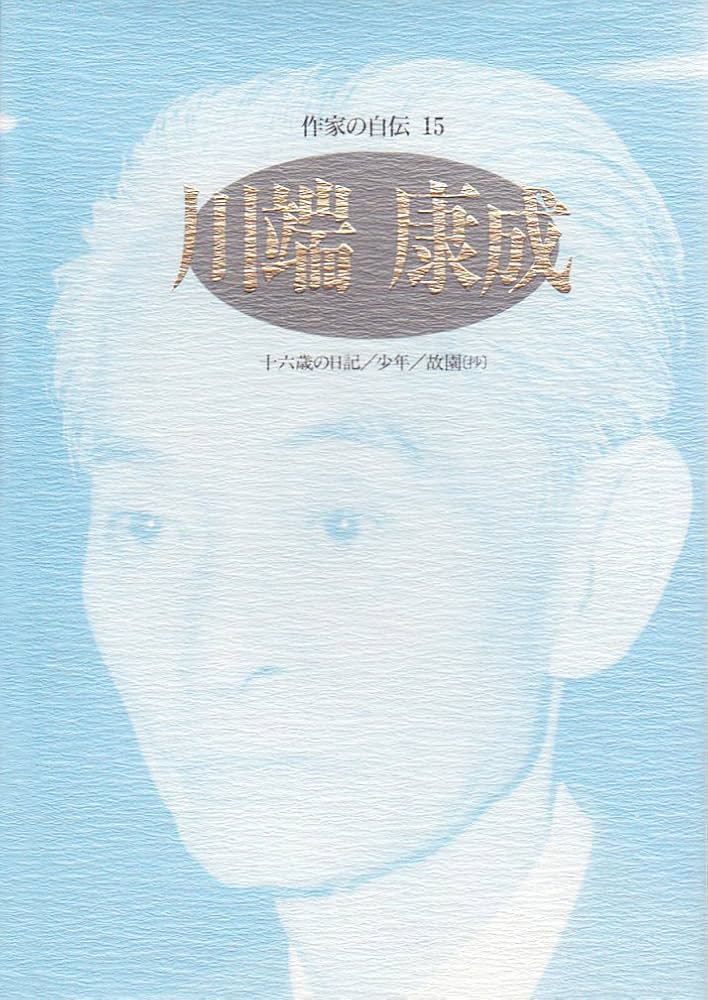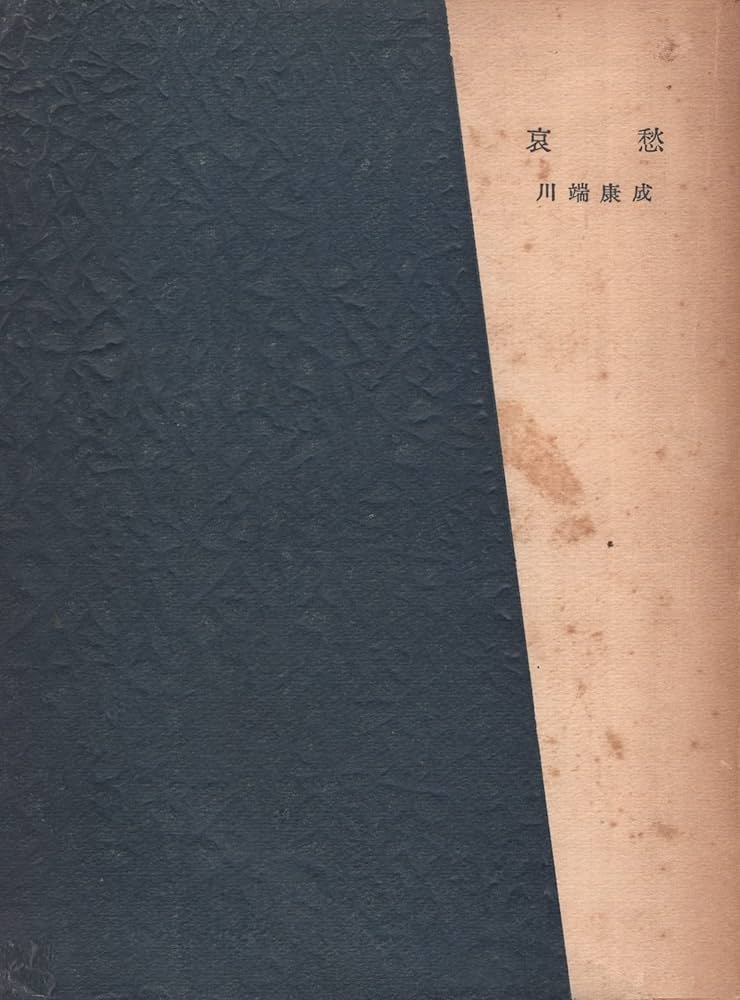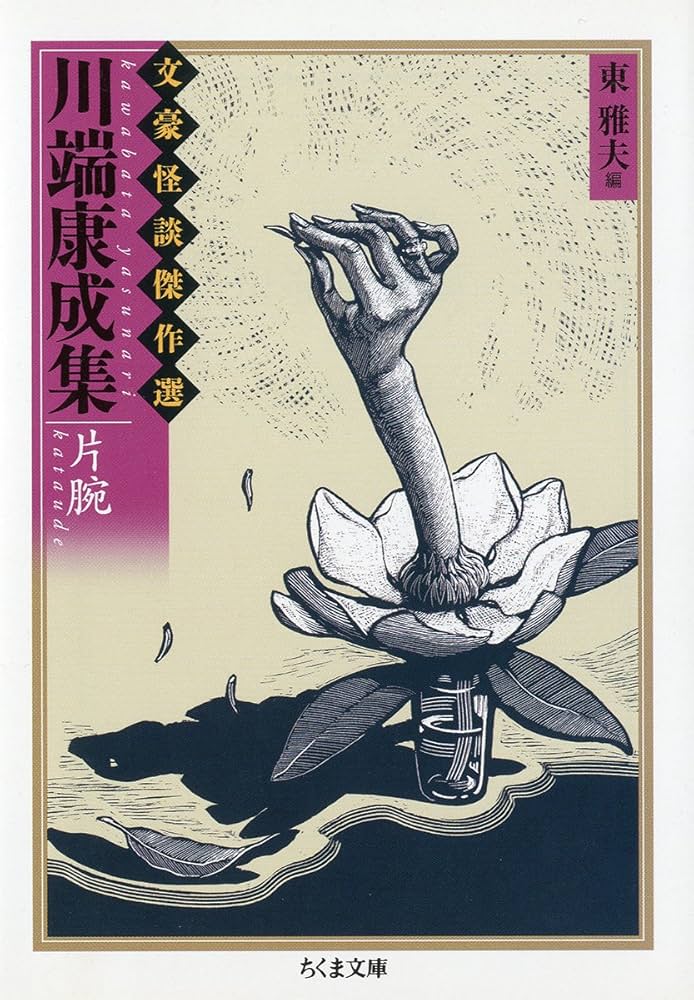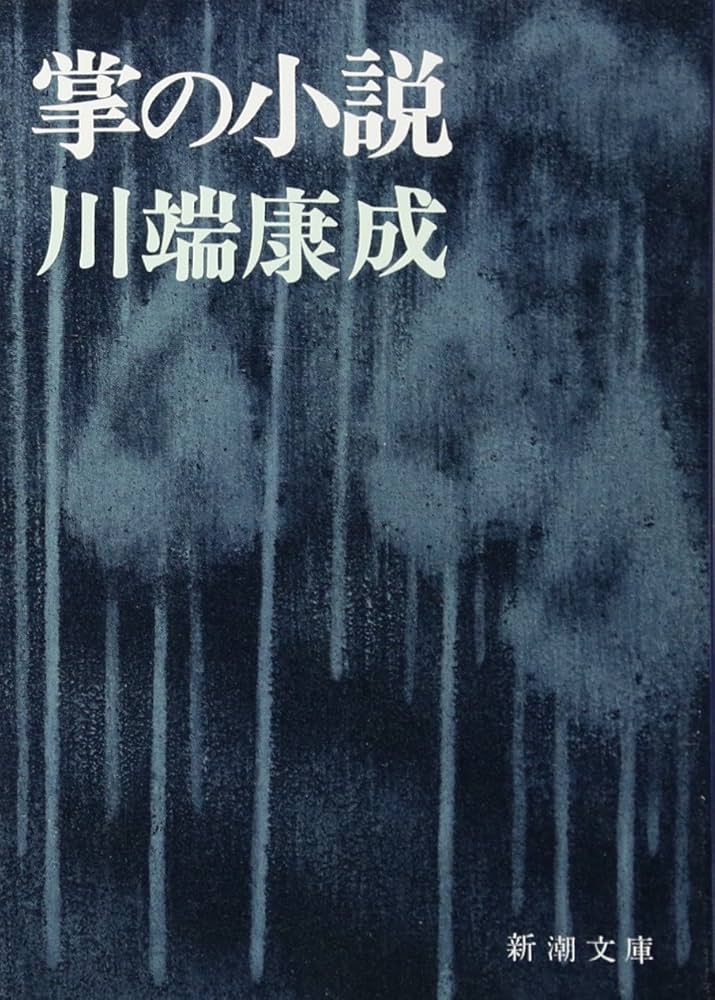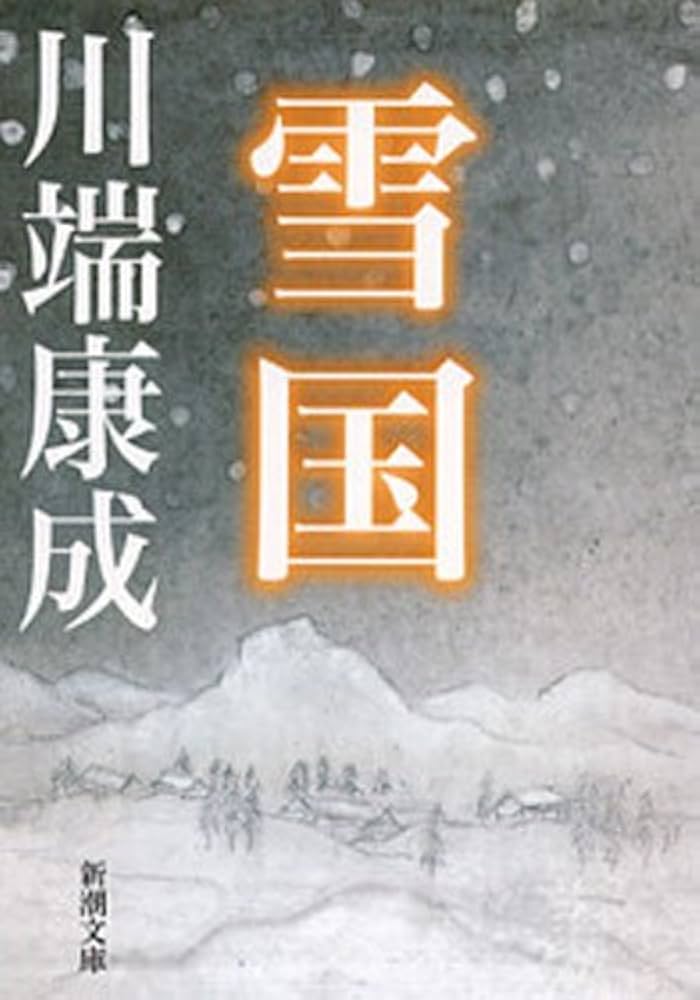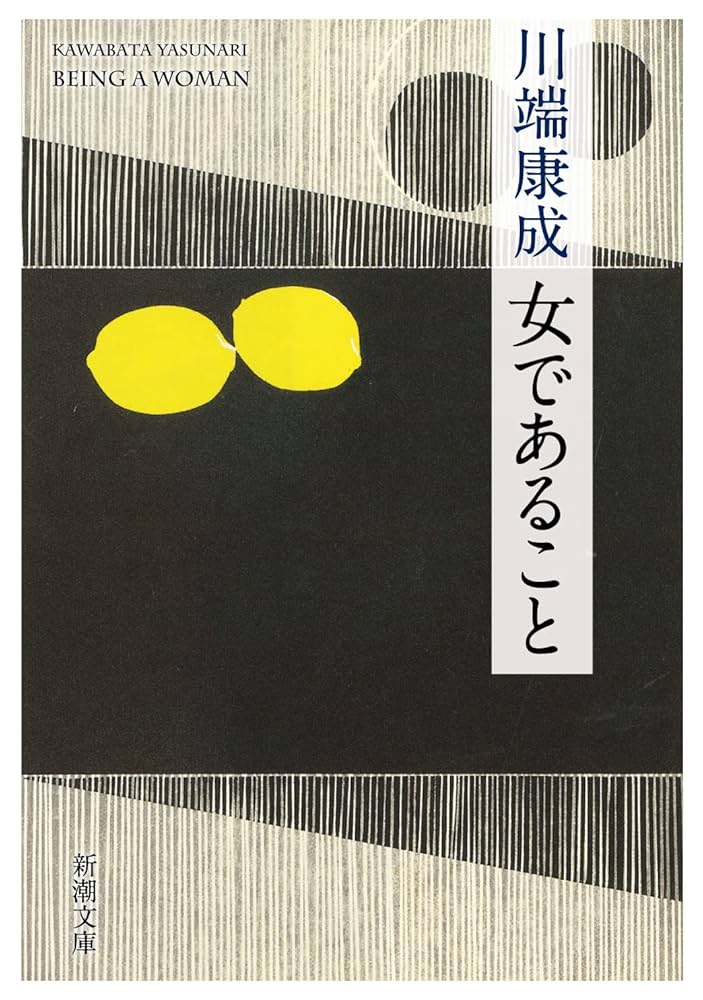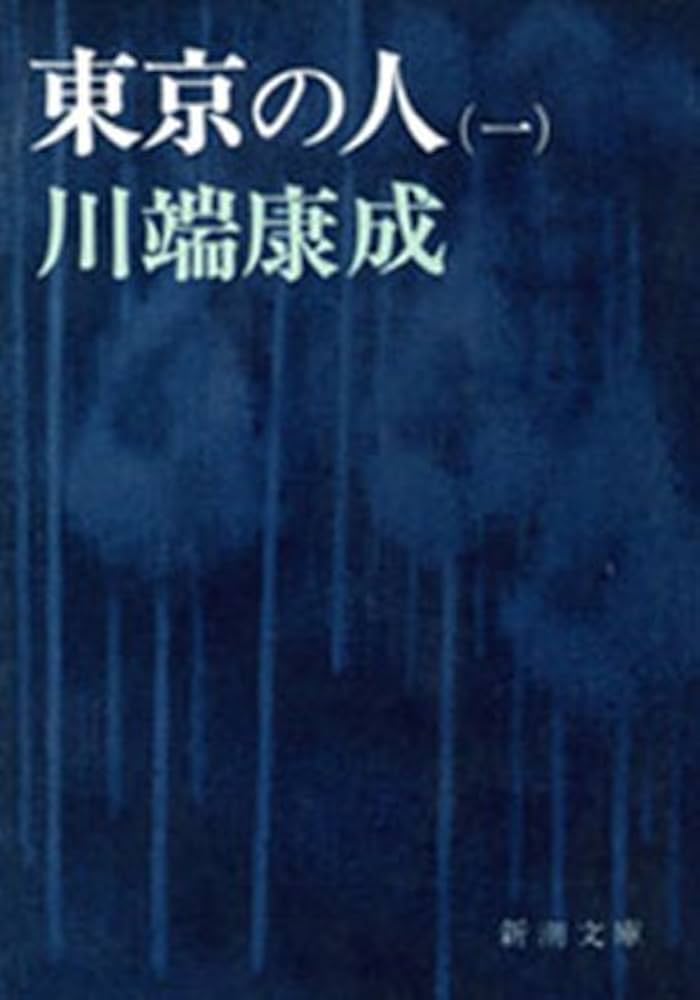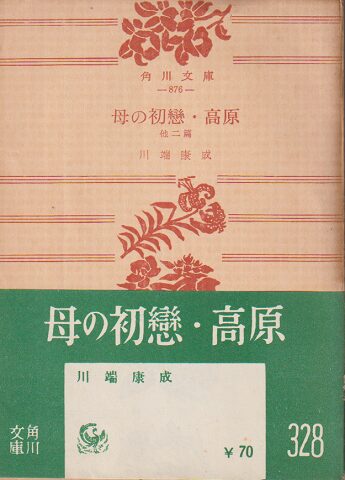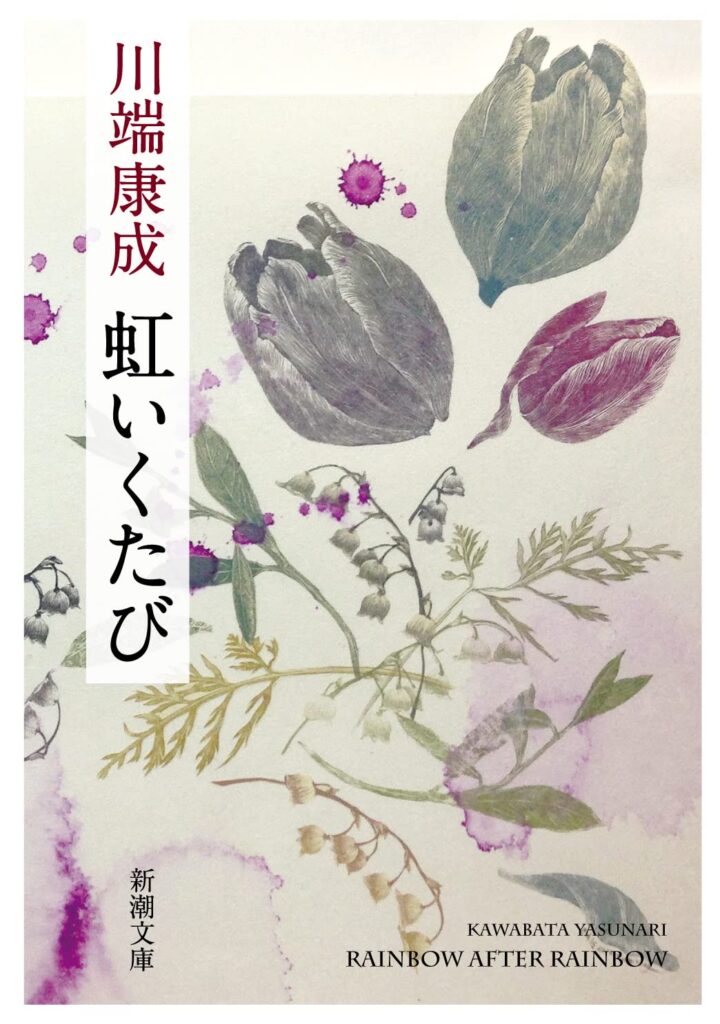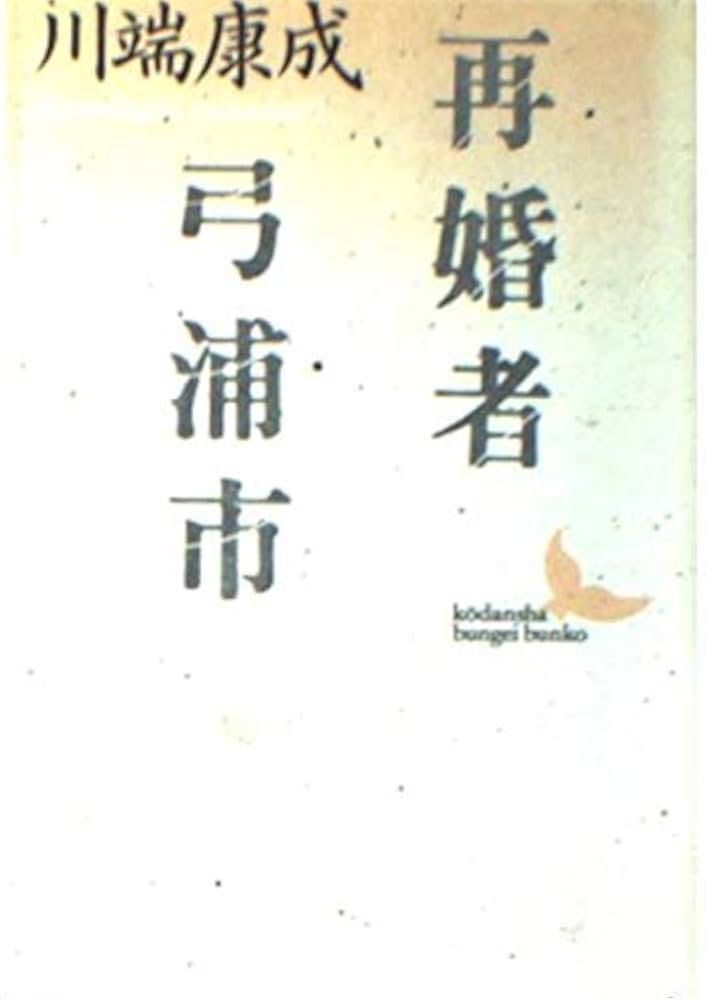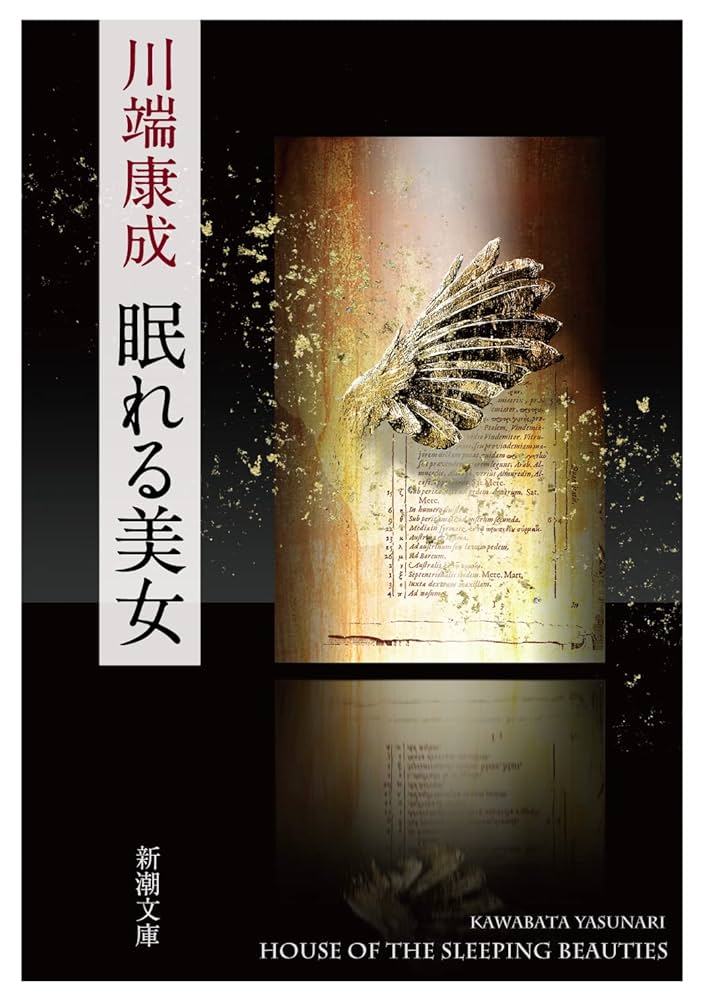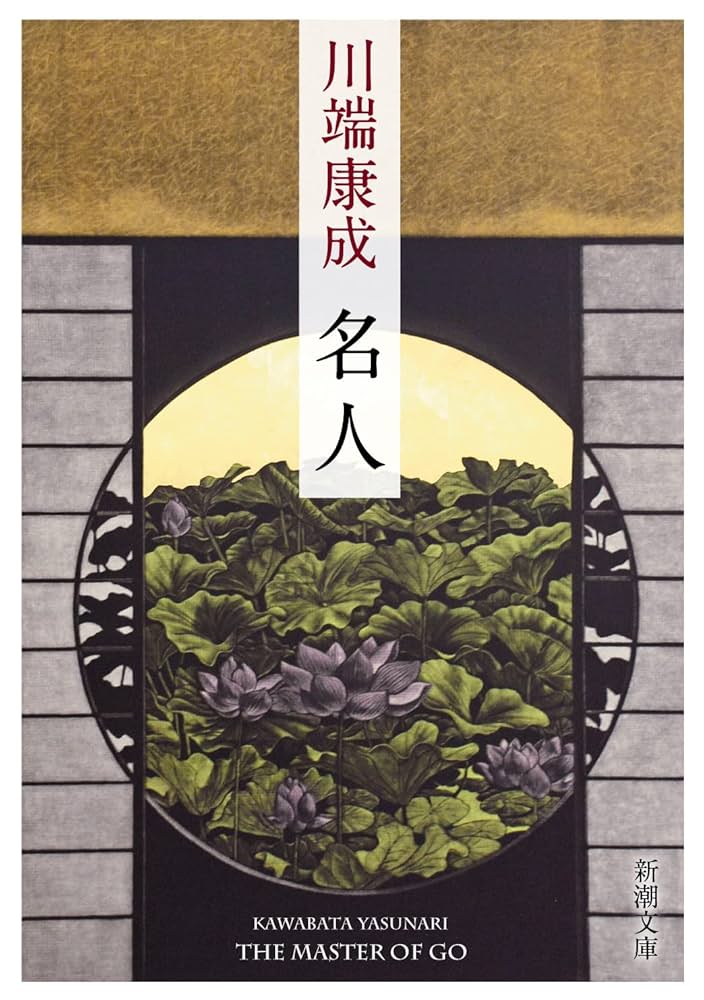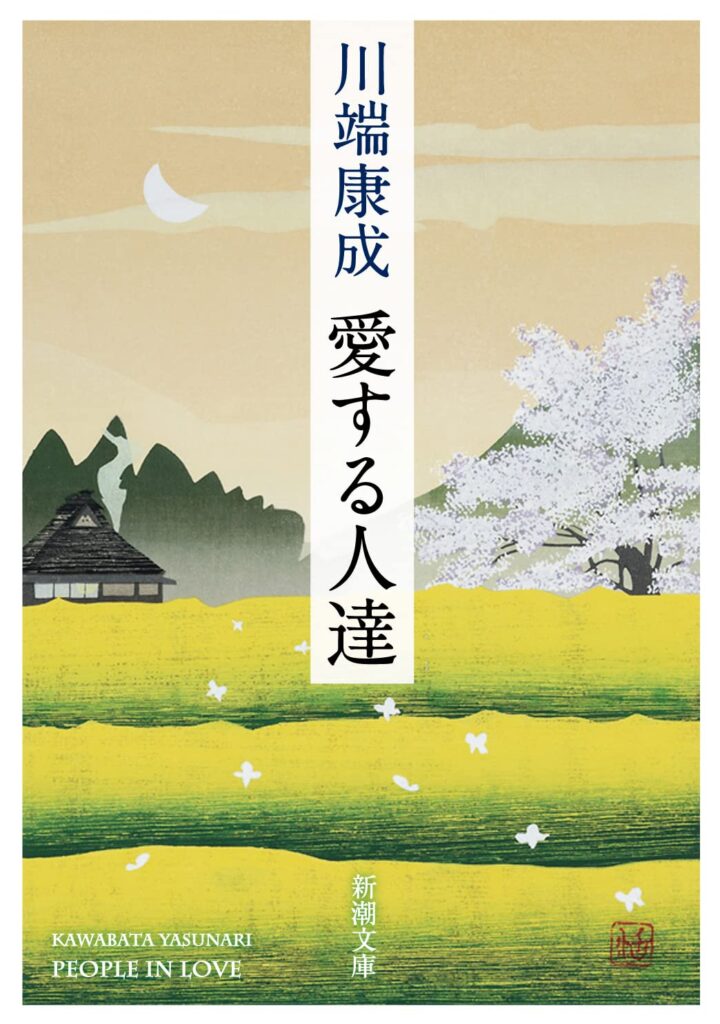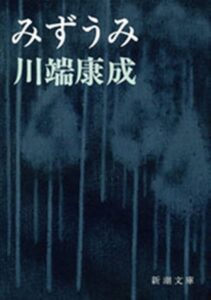 小説「みずうみ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「みずうみ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
川端康成の作品群の中でも、ひときわ異彩を放ち、読む人を選ぶとまで言われるのが、この『みずうみ』ではないでしょうか。発表された当時から、その難解さと背徳的な内容で、大きな議論を巻き起こした問題作です。ある人はこれを川端文学の極致と称賛し、またある人は強烈な不快感を表明しました。
物語を牽引するのは、桃井銀平という元高校教師の男性です。彼は、美しい女性を見かけると後をつけずにはいられないという、抗いがたい衝動に駆られています。この行為が、物語のすべてを動かしていくのです。しかし、それは単なるストーカー行為として片付けられるものではなく、彼の心の奥底にある「美」への渇望と、深い劣等感が複雑に絡み合った、魂の彷徨として描かれます。
この小説の最大の特徴は、物語が時間通りに進まないことです。「意識の流れ」という手法が用いられ、主人公である銀平の心に浮かぶ記憶の断片や幻想が、過去と現在を行き来しながら、万華鏡のように紡がれていきます。読者は銀平の精神世界に迷い込み、彼の内なる「みずうみ」の深淵を共に覗き込むことになるのです。
この記事では、そんな『みずうみ』の物語の核心に触れながら、その魅力と謎をじっくりと読み解いていきたいと思います。美しさと醜さ、聖なるものと俗なるものが混じり合う、川端康成が描いた「魔界」。その世界へ、一緒に足を踏み入れてみましょう。
「みずうみ」のあらすじ
物語の主人公は、34歳の元高校教師、桃井銀平。彼には、美しい女性を見かけると後をつけずにはいられないという、倒錯した習性がありました。この習性が原因で、彼は教師の職を失い、流されるままに日々を送っています。物語は、銀平が夏の終わりの軽井沢にあるトルコ風呂にいる場面から、彼の「意識の流れ」と共に始まります。
彼の脳裏にまず浮かぶのは、教職を失った後に東京で後をつけた、水木宮子という女性のこと。彼女の美しさに惹かれて追跡した銀平は、恐怖に駆られた宮子にハンドバッグで殴られます。その際に彼女が落としたバッグには大金が入っており、銀平はその金を盗んで軽井沢へと逃げてきたのでした。宮子は、ある裕福な老人の愛人であり、銀平は彼女に自分と同じ「魔界」の住人の匂いを嗅ぎ取ります。
意識はさらに過去へと遡ります。銀平が教師の職を失う直接の原因となったのは、教え子であった玉木久子との関係でした。彼は久子を執拗にストーキングし、二人は歪んだ主従関係のような密かな関係を築いていきます。しかし、その関係が学校に露見し、銀平は教壇を去ることになったのです。
そして現在、軽井沢で銀平の新たな執着の対象となったのが、犬を連れた美しい少女、町枝でした。彼は町枝の純粋無垢な美しさに魅了され、彼女こそが究極の美の化身だと信じ込みます。銀平の追跡は、やがて彼の過去の女性たちと町枝とを繋ぐ、思いもよらない宿命の網を浮かび上がらせていくのです。
「みずうみ」の長文感想(ネタバレあり)
桃井銀平という男を理解するためには、彼の魂に深く刻まれた傷、その根源に触れなければなりません。彼が抱える最も根深いコンプレックスは、彼自身の「足」でした。「猿のように長くて、しなびている」と彼自身が語るその足は、単なる身体的な特徴ではなく、彼の存在そのものを規定する象徴となっています。この醜い足こそが、彼の自己嫌悪と劣等感の源泉なのです。
彼の世界認識は、この足への執着を通して歪められています。美しい女性を追いかける行為も、「肉体の一部の醜が美にあくがれて哀泣するのだろうか」という、ほとんど哲学的な問いへと昇華されます。彼のストーキングは、自らの醜さを埋め合わせるための、宿命づけられた行為として描かれており、ここに物語の最初の「ネタバレ」があります。彼の行動は、単なる欲望ではないのです。
このコンプレックスの起源は、彼の出生にまで遡ることができます。銀平は、名家の出身で美しい母と、「格の違う醜い父」の間に生まれました。彼は父の醜さを受け継いだと信じ込み、そのことが美しい母を失望させているのだという罪悪感を抱え続けます。美と醜という根源的な対立が、彼の内面で常に戦いを繰り広げているのです。
そのトラウマを決定的なものにしたのが、父の謎に満ちた死でした。銀平が11歳の時、父は母の故郷の湖で、頭に傷を負った溺死体として発見されます。自殺か、あるいは他殺か。真相は闇の中です。この事件により、物語のタイトルでもある象徴的な「みずうみ」は、父性の醜さ、暴力、そして未解決のトラウマと分かちがたく結びついてしまいました。
銀平の歪んだ心を形成したもう一つの重要な記憶が、初恋の相手であり従姉のやよいとのエピソードです。少年だった銀平は、捕まえた鼠をやよいの目の前で湖に力いっぱい投げつけます。この行為は、従姉であるやよいに対して抱いてしまった不純な欲望を、自ら断ち切ろうとする痛ましい儀式でした。この最初の恋の挫折と自己否定が、彼の人生を決定づけるパターンを形成します。
物語は、銀平が軽井沢のトルコ風呂にいる場面から始まります。湯女の美しい声に触発され、彼の意識は過去へと旅立ちます。最初に思い浮かべるのは、東京で後をつけ、その金を奪って逃げてきた水木宮子のことです。彼女は有田という老人の美しい愛人であり、銀平は彼女に自分と同じ世界の人間、つまり「魔界」の住人の気配を感じ取っていました。この感覚が、後の展開の重要な伏線となっていきます。
次に彼の意識は、高校教師時代へと遡ります。彼が教職を追われる原因となった、教え子の玉木久子。銀平は彼女をストーキングし、二人の間には奇妙な共犯関係が生まれます。彼は久子に水虫の薬を買ってくるよう頼むなど、自身の足のコンプレックスをさらけ出すことで、歪んだ親密さを求めたのです。この関係の倒錯性を象徴するのが、久子の「先生、また私の後をつけて来て下さい」という囁きでした。
そして、物語の現在軸である軽井沢で、銀平は新たな美の化身、町枝と出会います。彼は可憐な少女である町枝に、これまで追い求めてきたすべての美を超越した、究極の美しさを見出します。彼女の「黒いみずうみ」のような瞳の中で裸で泳ぎたい、という願望は、彼の美への渇望が到達した一つの極致と言えるでしょう。この純粋さへの埋没願望が、物語の後半の悲劇性を際立たせるのです。
ここから、物語は驚くべき「ネタバレ」へと進んでいきます。銀平がバラバラに追い求めてきたかに見えた女性たちが、実は見えない糸で緻密に結びついていたことが明らかになるのです。銀平とのスキャンダルで転校した久子。その転校先の学校の理事長が、水木宮子のパトロンである有田老人でした。さらに、宮子の弟の友人が、町枝の恋人である水野だったのです。
この事実が明らかになった時、物語の様相は一変します。これはもはや、一人の男の異常な執着の記録ではありません。登場人物全員が、抗うことのできない宿命の網にかかった、悲劇の登場人物だったのです。銀平は自由な捕食者ではなく、自らも網にかかった一匹の虫に過ぎなかった、という構図が鮮やかに描き出されます。
物語の幻想的な頂点となるのが、蛍狩りの場面です。恋人の水野が入院していると知った町枝は、彼のために蛍を捕まえようとしていました。その姿を見た銀平の心に、珍しく清らかな気持ち、言うなれば「仏ごころ」が芽生えます。彼は籠いっぱいの蛍を捕まえ、それを町枝に気づかれないよう、そっと彼女の帯に引っかけて闇に消えます。これは、彼の醜い存在が、理想の美に触れることなく奉仕するという、純粋で美しい幻想の成就でした。
しかし、この小説は、そのような美しい幻想のままで終わることを許しません。物語の結末は、この美学的な世界を無慈悲に打ち砕きます。蛍狩りの後、安酒場で酒を飲んでいた銀平は、雨も降っていないのにゴム長靴を履いた、魅力のない中年女に声をかけられます。この女の登場が、物語の力学をすべて反転させるのです。
これまで「追う者」であった銀平が、初めて「追われる者」になります。彼は嫌悪感を抱きながらも、病的な好奇心から逃れられません。彼は、長靴の中の彼女の足が、自分のものと同じように醜いに違いないと想像し、吐き気を催します。女は逃げる銀平を追いかけ、ついには小石を投げつけます。その石は、彼のコンプレックスの源泉である足首に命中するのです。
この結末は、美的な幻想の完全な崩壊を意味します。銀平がこれまで築き上げてきた、抒情的な文章によって美化されてきた倒錯の世界は、ゴム長靴の女という、ロマンを一切拒絶する「現実」そのものによって粉砕されます。彼女が投げた石は、銀平を幻想の世界から、彼が最も軽蔑する身体という現実へと引きずり下ろす、物理的な一撃でした。
本作で繰り返し現れる「みずうみ」という象徴は、人間の無意識そのものです。そこには、空を映す「美」もあれば、父の死体が沈む「トラウマ」もあり、投げ込まれた鼠に象徴される「欲望」と「死」が渾然一体となって存在します。銀平が町枝の瞳という「みずうみ」で泳ぎたいと願ったのは、醜い自己を美しい意識の中に溶かしてしまいたいという、根源的な渇望の表れだったのでしょう。
また、川端康成は「美」と「醜」を単純な対立として描きません。両者は病的なまでに依存しあっています。銀平の醜さがあるからこそ、彼の美に対する感受性は、ほとんど神聖なほどの強度を帯びるのです。結末で醜い女に惹かれるのも、「この女がみにくければみにくいほどよい。それによって町枝の面影が見えて来そうだった」からであり、醜さが美を呼び覚ますための触媒として機能しているのです。
そして「魔界」という概念。これは銀平個人の地獄ではなく、宮子や久子も住人である、共有された心理空間です。そこでは、追う者と追われる者の間に、暗黙の了解が存在します。久子が銀平に「またつけて来て」と願う場面は、この「魔界」の存在を肯定する、恐るべき瞬間です。それは、倒錯が合意の上で成り立つ世界であり、読者を深い不安に陥れます。
最終的に、桃井銀平の人生は、自らの醜さという現実からの、必死の逃避行でした。純粋な美の幻想世界を構築することで、彼はトラウマから身を守ろうとしたのです。しかし、ゴム長靴の女との遭遇は、その試みが完全に失敗したことを突きつけます。彼は、自身の「醜い足」から逃れることはできませんでした。なぜなら、自分自身から逃れることは誰にもできないからです。物語は救済のないまま、静かで冷厳な現実への帰還をもって幕を閉じます。
まとめ
川端康成の『みずうみ』は、主人公・桃井銀平の歪んだ魂の遍歴を通して、美と醜、聖と俗が渦巻く人間の深淵を描き出した作品です。美しい女性を追い求める彼の行動は、単なる異常行為ではなく、自身の醜さへの絶望と、手が届かない美への痛切な憧れが表裏一体となった、魂の叫びのようにも感じられます。
物語は「意識の流れ」という手法で描かれ、時系列はバラバラになり、読者は銀平の記憶と幻想の迷宮を彷徨うことになります。そこで語られるあらすじは、断片的でありながら、彼のトラウマの根源と、登場人物たちを結ぶ宿命的な繋がりを、徐々に浮かび上がらせていきます。ネタバレを知った上で読むと、その緻密な構成に改めて驚かされるでしょう。
クライマックスである蛍狩りの幻想的な美しさと、それを無慈悲に打ち砕く結末の対比は鮮烈です。美の幻想の中にしか生きられなかった男が、醜い現実そのものによって打ちのめされるラストシーンは、読む者に強烈な印象を残します。救いのない結末は、しかし、この物語が人間存在の本質的な孤独と哀しみを、どこまでも誠実に描こうとした証なのかもしれません。
この小説は、決して心地よい読書体験を約束するものではありません。しかし、その底知れない深さと、一度読んだら忘れられないほどの妖しい魅力は、川端文学の到達点の一つであると感じさせます。人間の心の暗い湖を覗き込むような、唯一無二の文学体験がここにあります。