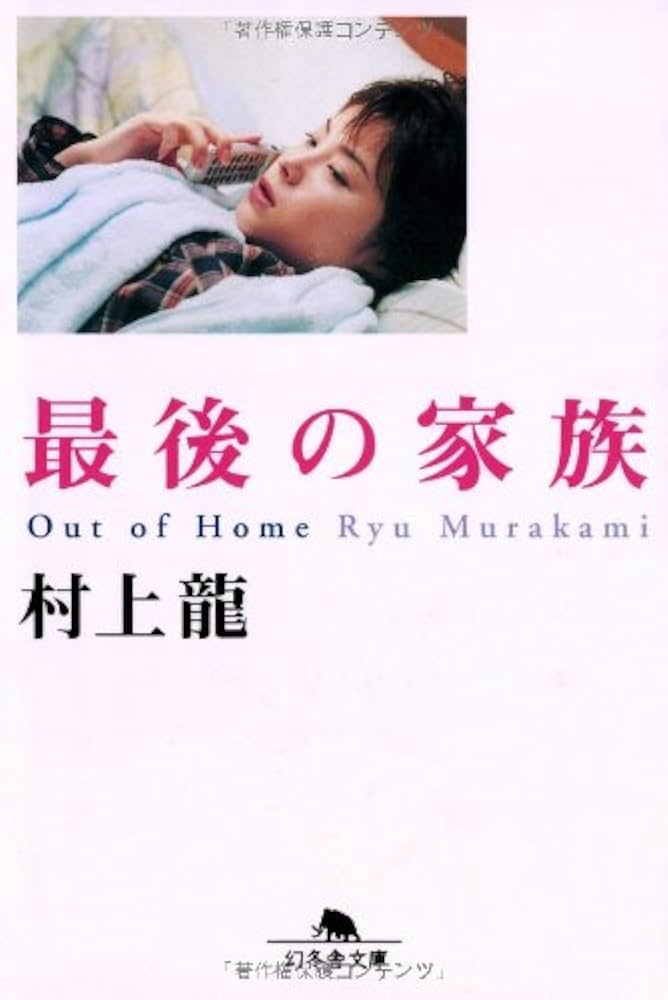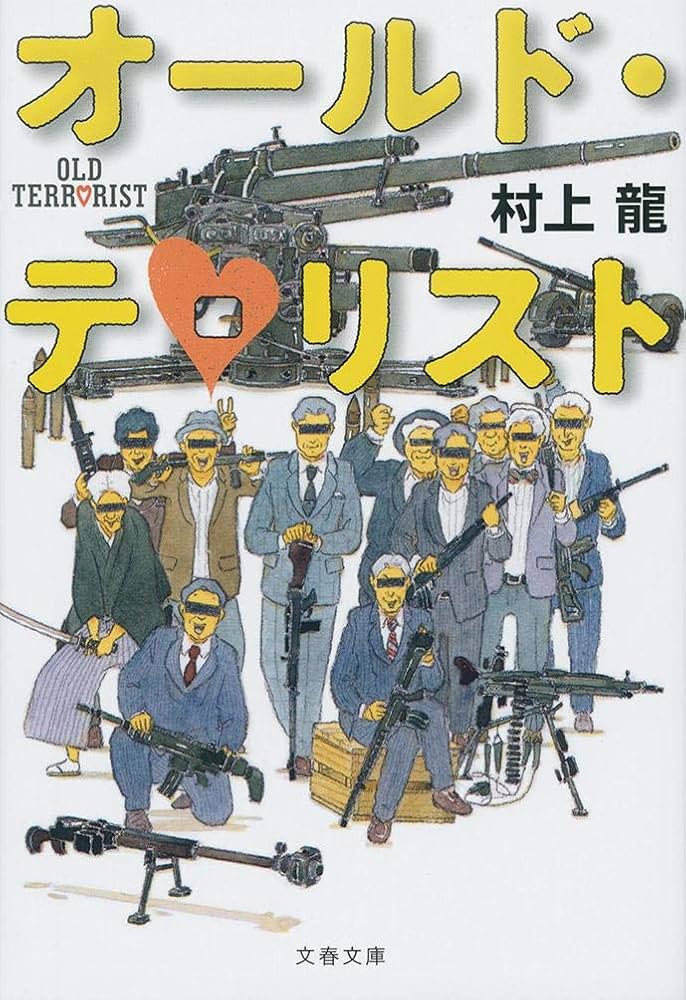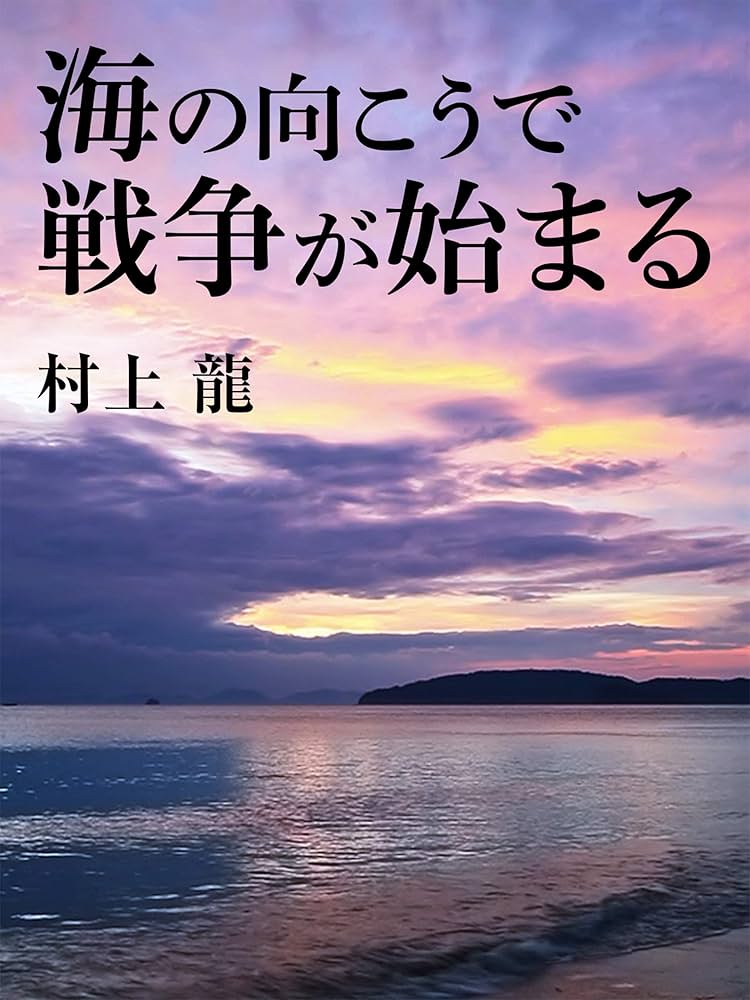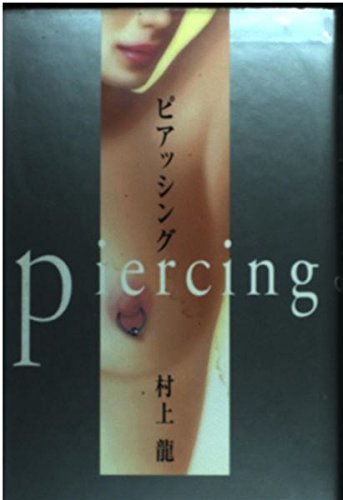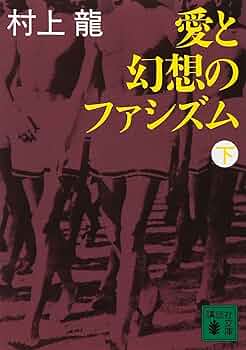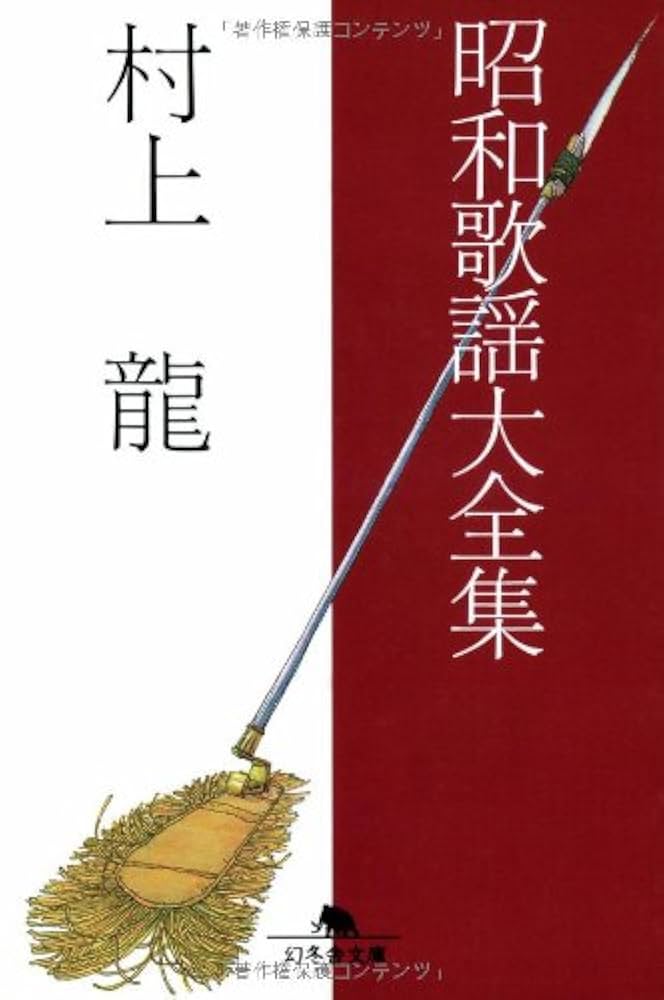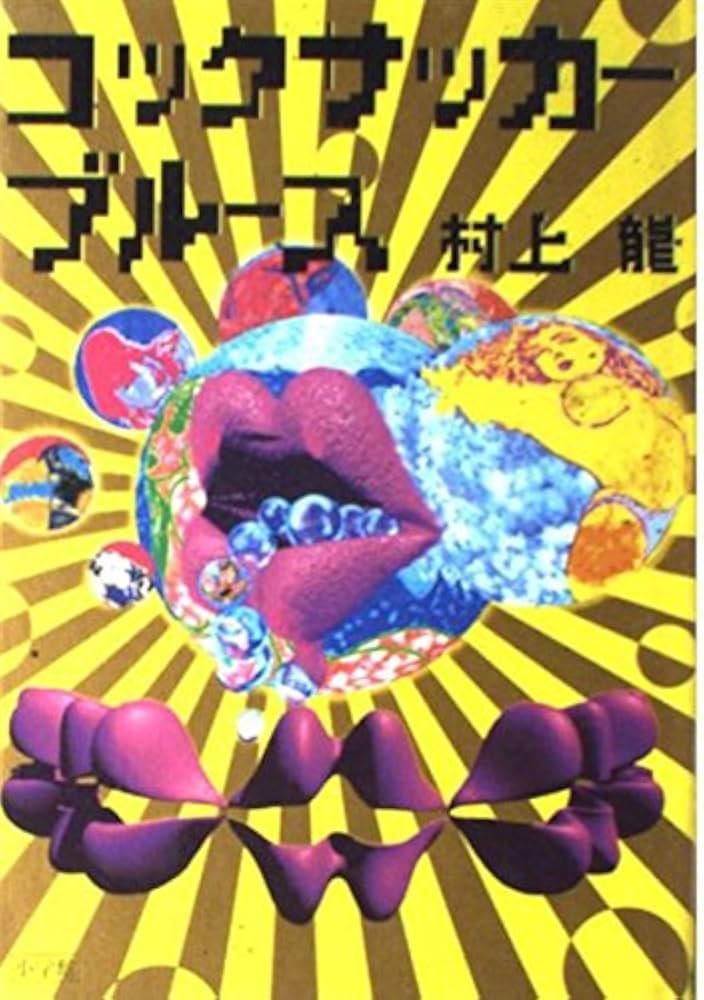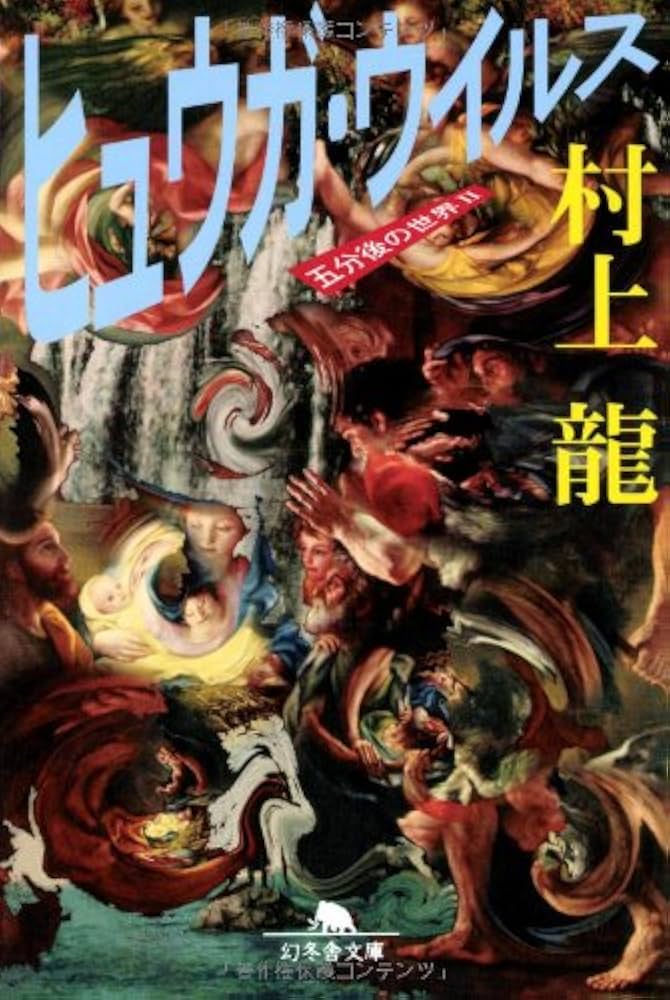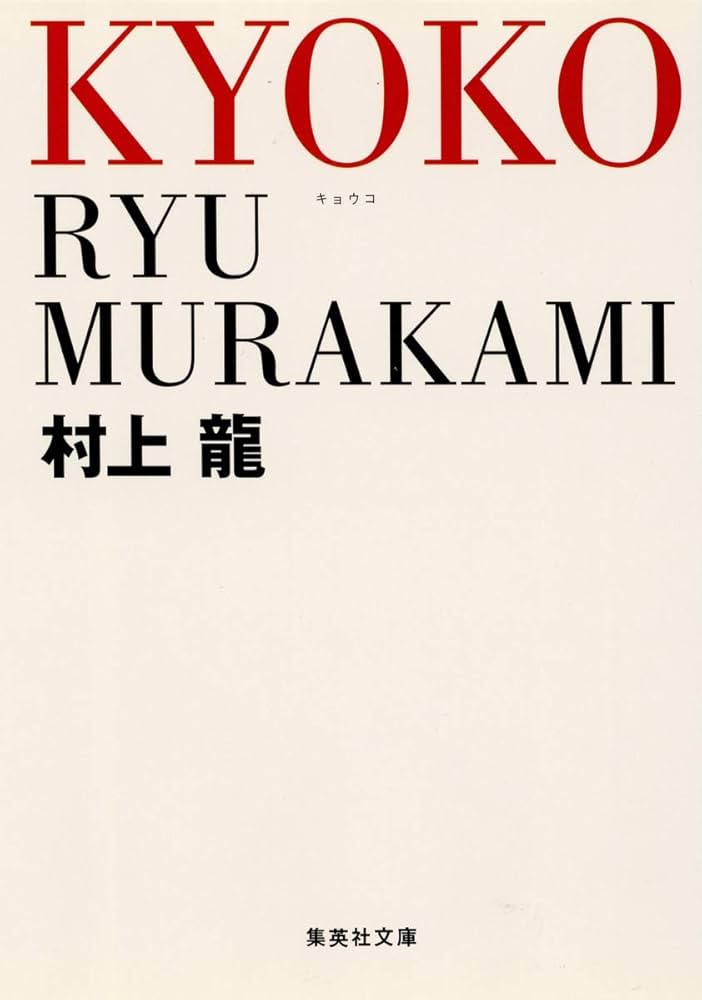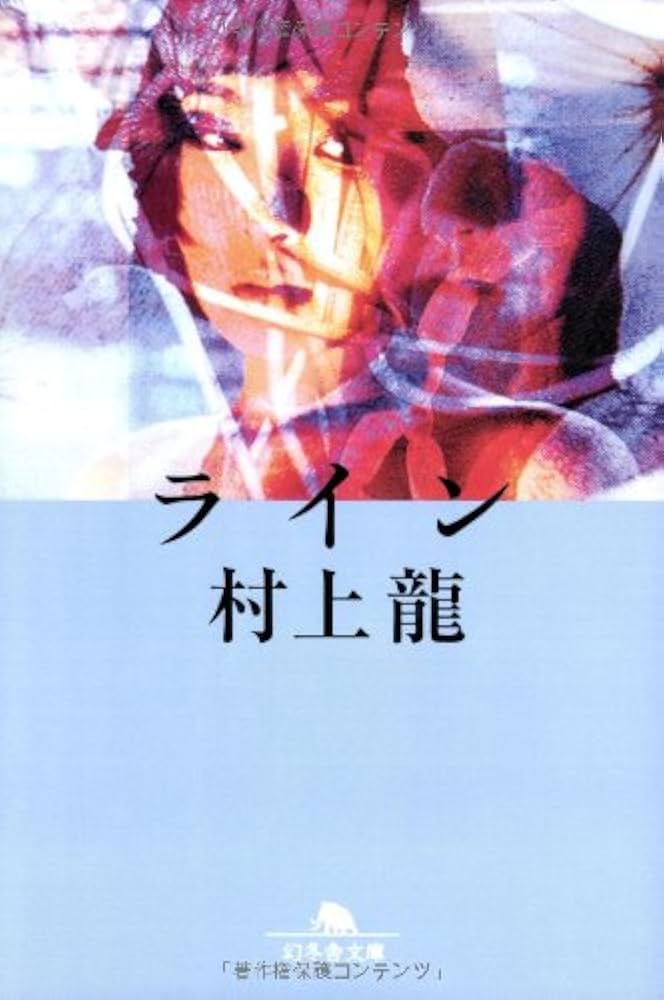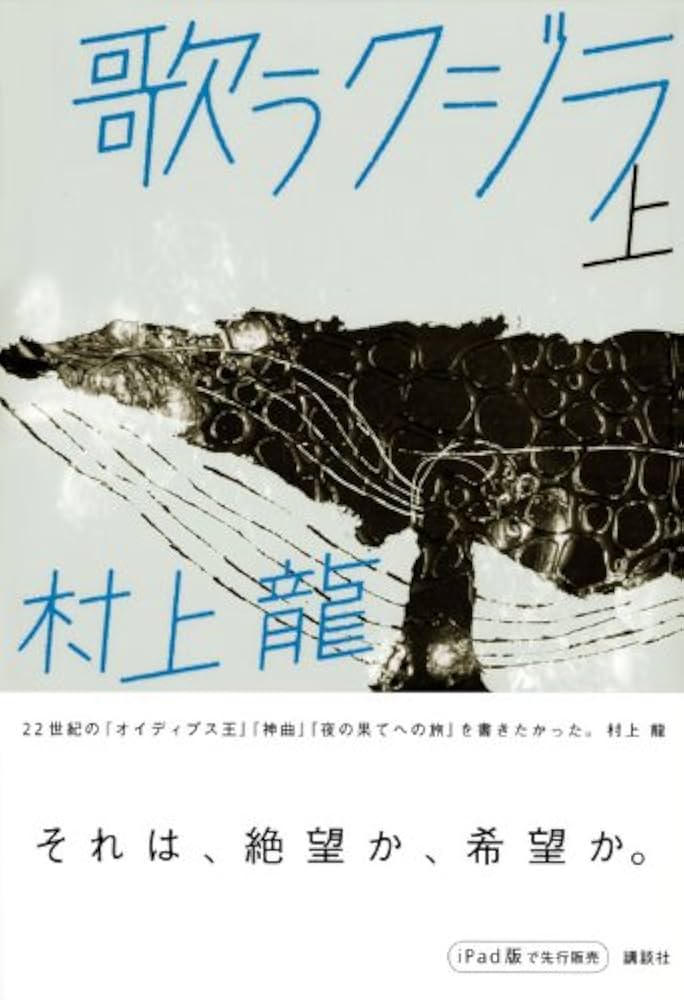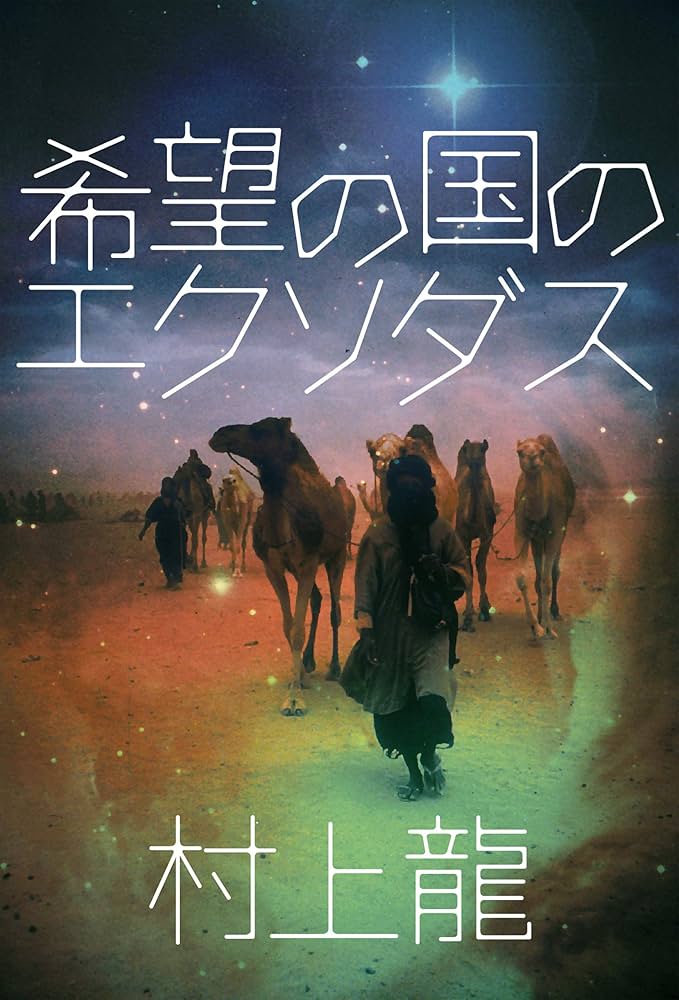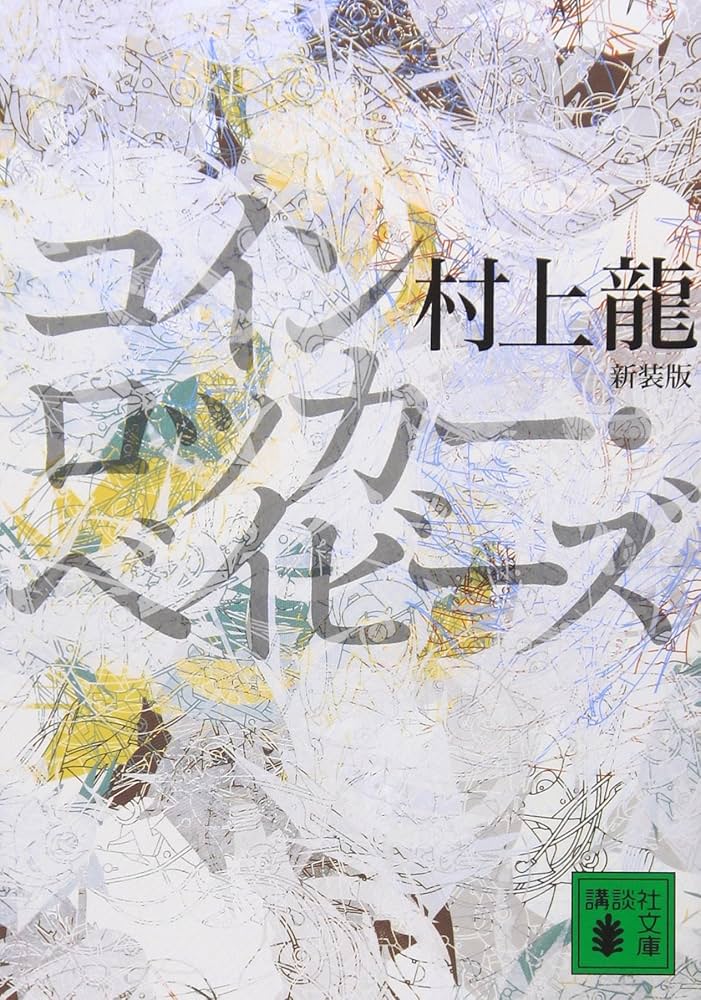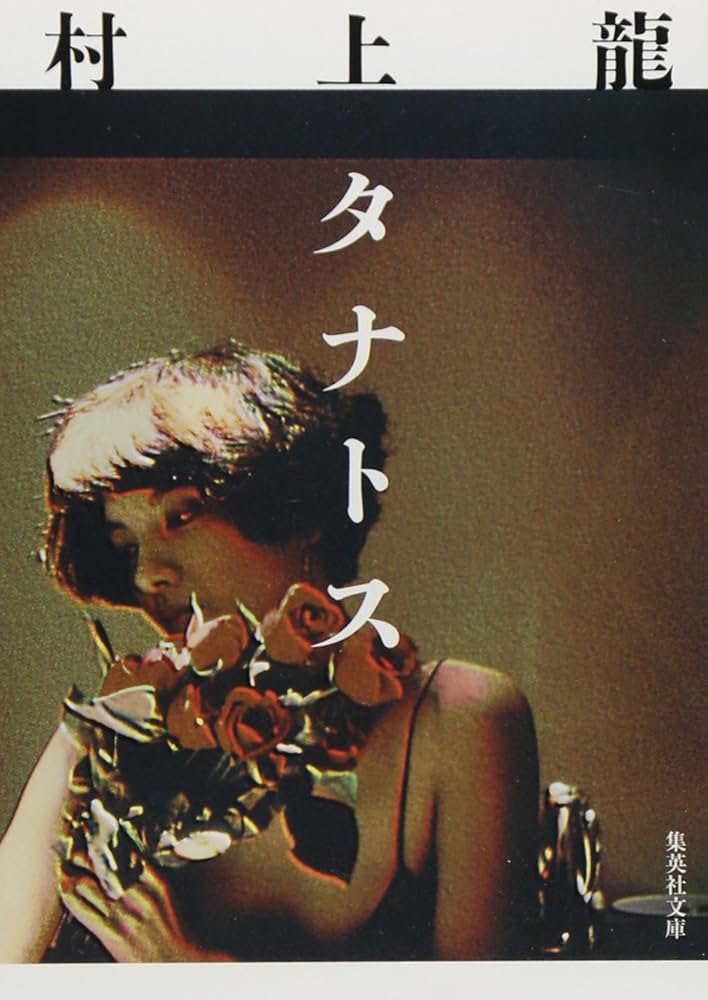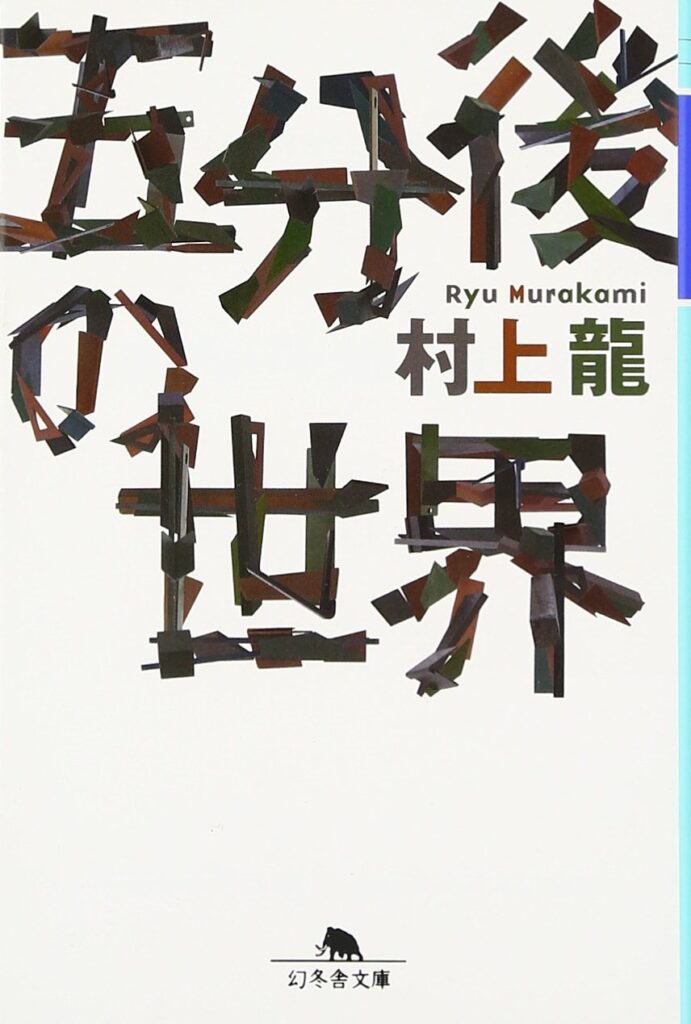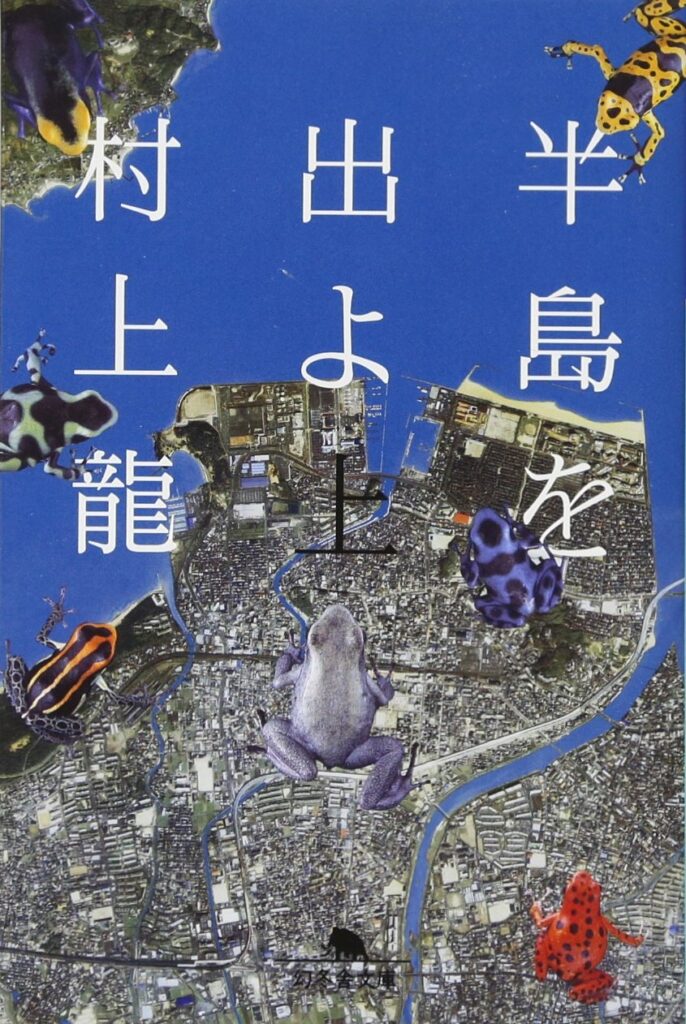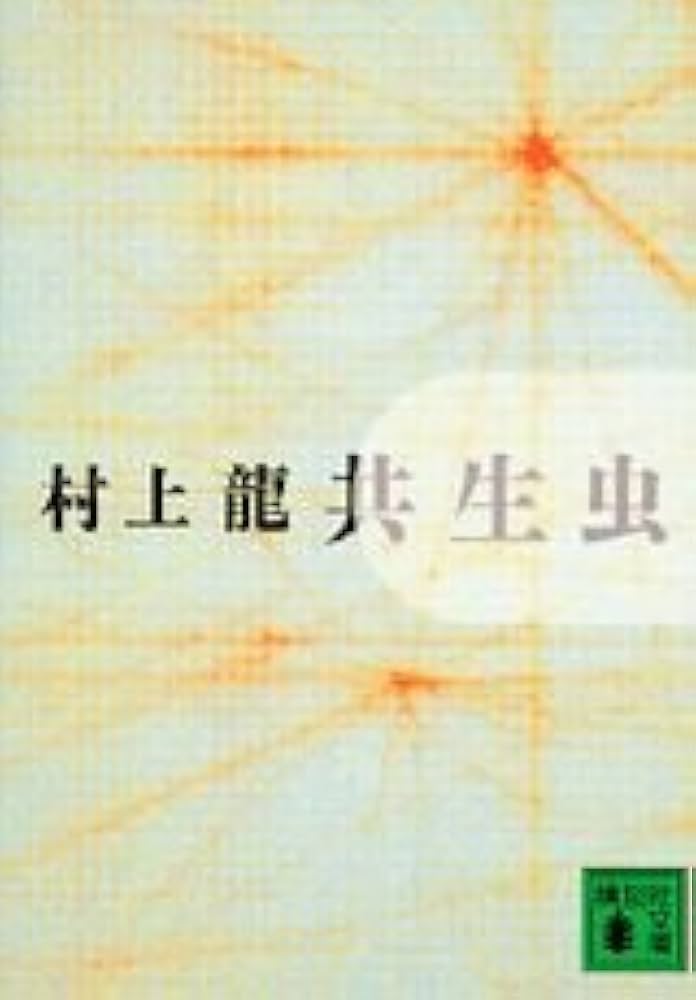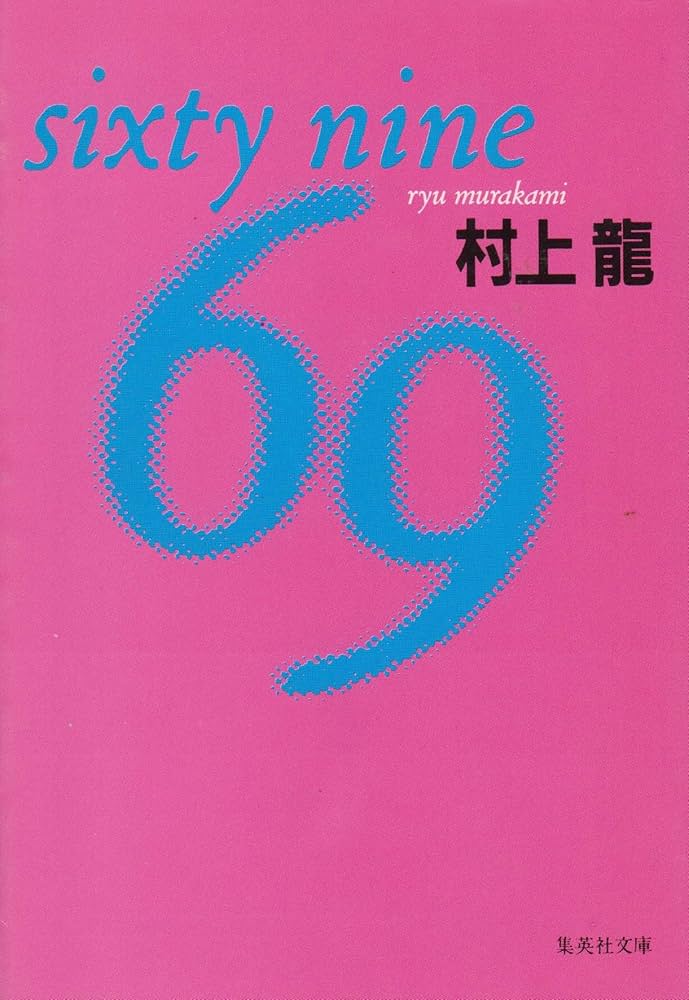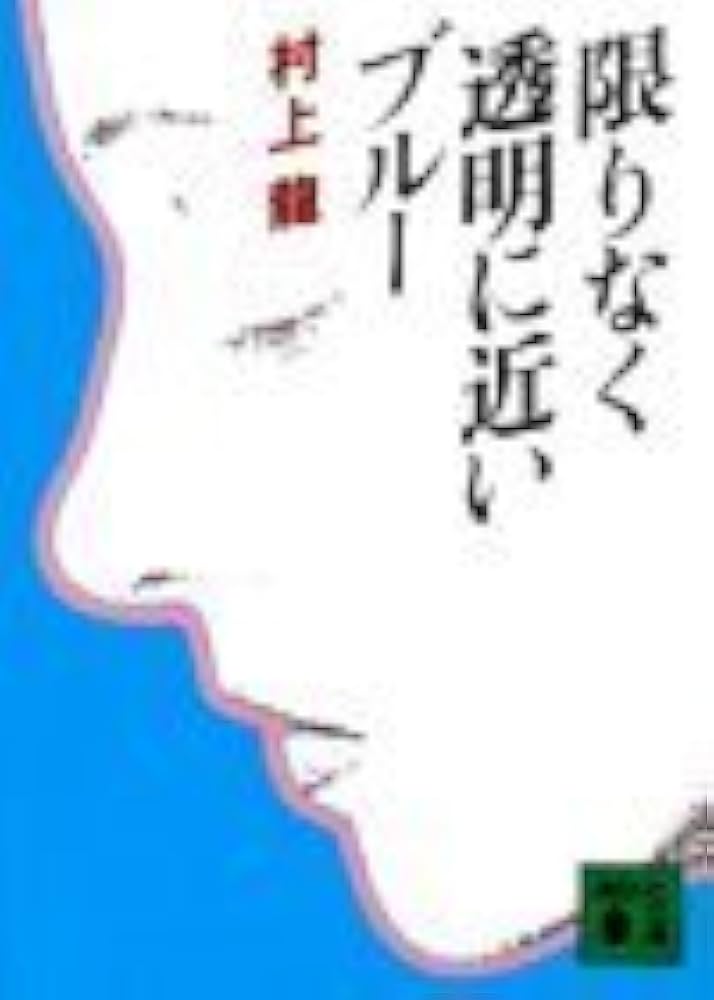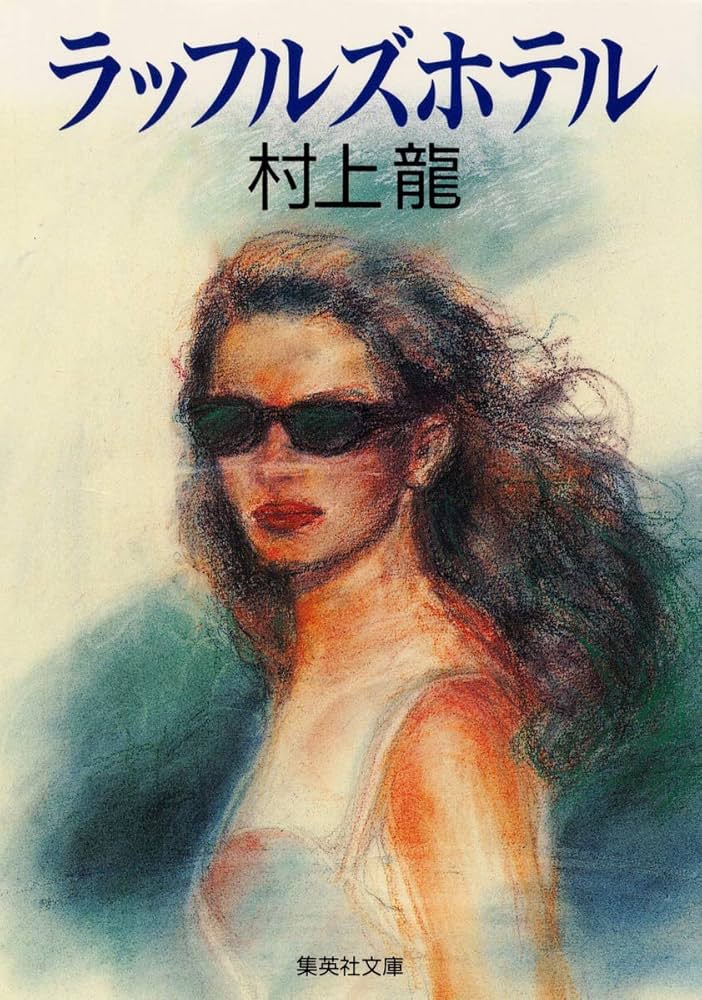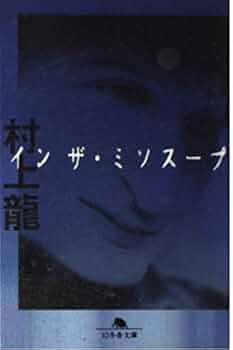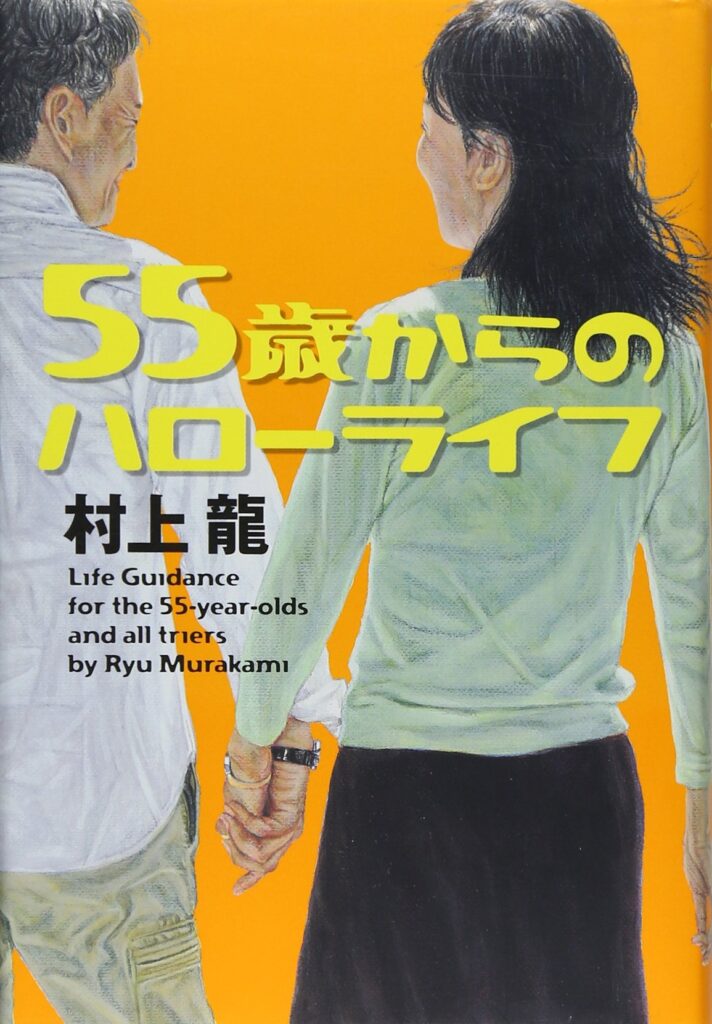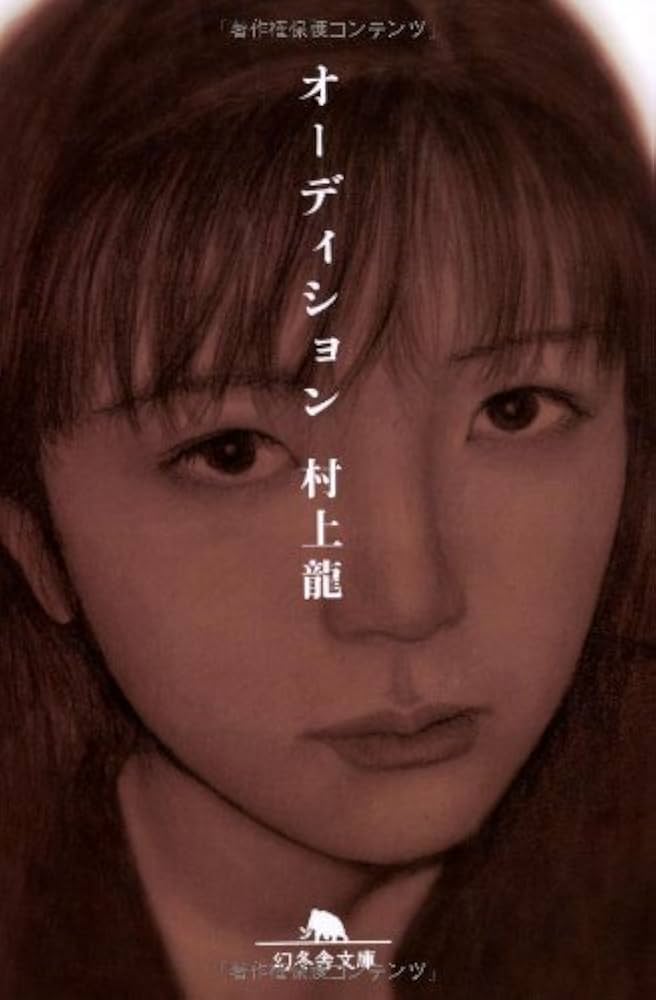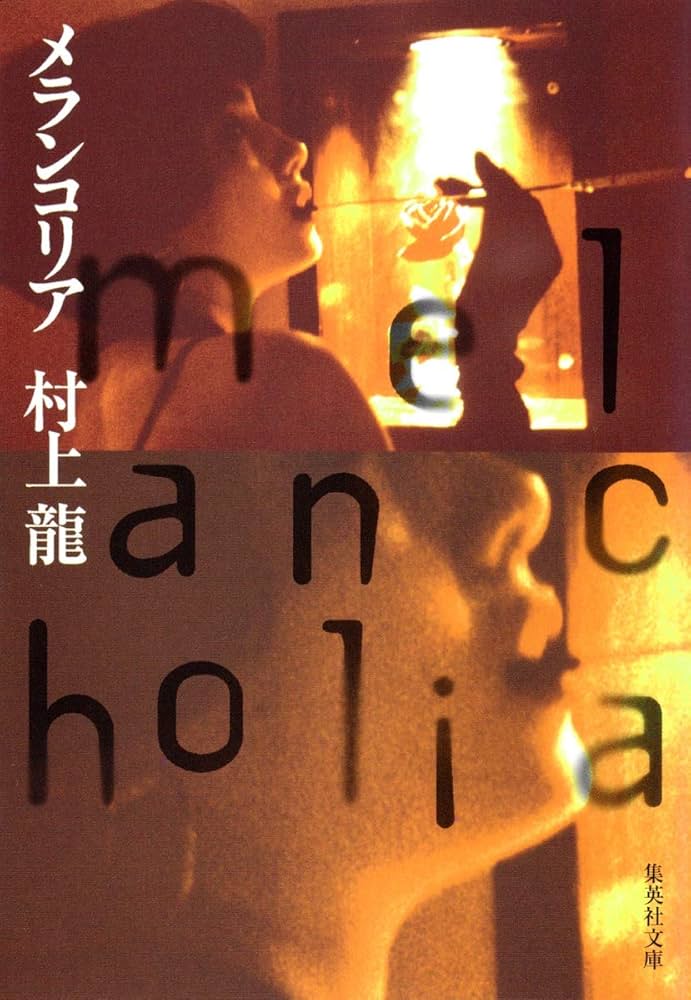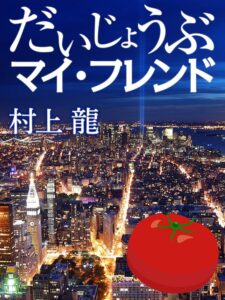 小説「だいじょうぶマイ・フレンド」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「だいじょうぶマイ・フレンド」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、1980年代という時代の空気を色濃く反映しながらも、今なお私たちの心に不思議な光を灯してくれる、唯一無二の作品です。村上龍さんという作家の、底知れない魅力が詰まっています。
空から降ってきた異星人と、東京に暮らす若者たちとの、ひと夏の冒険。そう聞くと、どこか陳腐なSFコメディを想像するかもしれません。しかし、この「だいじょうぶマイ・フレンド」は、そんな単純な言葉では到底片付けられない、奇妙で、切なくて、そして途方もなく優しい物語なのです。
この記事では、まず物語の骨格となるあらすじを追いかけ、その後で核心に迫るネタバレを含んだ、より深い読み解きと個人的な思いを綴っていきます。この奇想天外な物語が、なぜこれほどまでに読者の心を掴んで離さないのか、その秘密に迫ってみたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。
「だいじょうぶマイ・フレンド」のあらすじ
物語の始まりは、気だるい夏の終わりのプールサイドです。強い個性を持つ少女ミミミ、誠実なハチ、そしていつもハーモニカを吹いている物静かなモニカ。そんな3人の若者たちの平凡な日常は、突如として破られます。空から人間の形をした何かが、轟音とともにプールへと墜落してきたのです。
彼らがプールから助け出したのは、ゴンジーと名乗る不思議な男でした。彼は遠い星からやってきた異星人であり、地球人の何万倍もの力を持つ超人だと語ります。しかし、故郷の星へ帰る途中、なぜかその飛行能力を失ってしまったというのです。彼の突拍子もない身の上話と、どこか寂しげな瞳に、ミミミたちは次第に心を動かされていきます。
3人は、この孤独な異星人を匿い、彼が再び飛べるようになるまで手助けすることを約束します。しかし、彼らの前には、ゴンジーのその超人的な肉体を狙う、巨大で不気味な組織「ドアーズ」の影が忍び寄っていました。遺伝子工場、ファミリーレストラン、精神病院を世界的に経営するこの組織は、ゴンジーを捕獲し、その能力を自らの野望のために利用しようと画策していたのです。
ミミミたちは、ドアーズの執拗な追跡をかわしながら、ゴンジーの失われた力を取り戻すため、南の島へと向かいます。若者たちと異星人の、奇妙で切ない逃避行が始まります。果たしてゴンジーは無事に故郷の星へ帰ることができるのでしょうか。そして、彼らを待ち受ける運命とはどのようなものなのでしょうか。
「だいじょうぶマイ・フレンド」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の核心に触れる重大なネタバレを含みます。まだ未読の方はご注意ください。この「だいじょうぶマイ・フレンド」という物語が、なぜこれほどまでに私の心を捉えるのか。その理由を、物語の細部を振り返りながら、じっくりと語らせていただきたいと思います。
まず、この物語の冒頭、プールサイドにゴンジーが「降ってくる」場面。これは単なる物語の始まりではありません。村上龍さんが描き出す、乾いた現実の世界に、圧倒的な非日常が暴力的に割り込んでくる、その宣言です。若者たちの退屈な日常が、この瞬間、ファンタジーへと塗り替えられます。この現実と幻想の衝突こそが、物語全体を貫く独特のエネルギーを生み出しているのです。
ゴンジーを演じるのが、アメリカン・ニューシネマの象徴であるピーター・フォンダであるという事実は、非常に示唆に富んでいます。彼はアメリカ文化の断片的なイメージをコラージュしたような存在として描かれます。H・P・ラヴクラフトの小説に出てくる地名「インスマウス」で育ち、最初に覚えた言葉は「メリー・クリスマス」。彼はアメリカという巨大な文化の象徴でありながら、その本来の力を失い、途方に暮れているのです。
彼を追う敵対勢力「ドアーズ」の存在も、極めて象徴的です。遺伝子工場(生命の創造)、ファミリーレストラン(生命の消費)、精神病院(精神の管理)。この三本柱は、生命そのものをシステム化し、商品化しようとする現代社会の歪みを体現しています。80年代のバブル経済期、際限なく拡大していく企業論理への痛烈な風刺がここに込められています。
ドアーズを率いる「ドクター」の目的は、ゴンジーの体細胞からクローンを大量生産すること。個性を許さず、すべてを規格化し、管理しようとする全体主義的な欲望のメタファーです。そんな彼らにとって、ユニークで制御不能な力を持つゴンジーは、最高の研究材料であると同時に、自らの秩序を脅かす最大の異物なのです。この対立構造は、個人の尊厳と巨大なシステムとの戦いという、普遍的なテーマを浮かび上がらせます。
一行はゴンジーの飛行訓練のためにサイパンへ向かいます。この南の島でのシークエンスは、束の間の楽園として描かれます。ハンググライダーで健気に練習するゴンジーの姿は、どこか滑稽で、同時に切実です。しかし、この希望に満ちた時間は長くは続きません。ここでのネタバレになりますが、ドアーズの追手によって、物語は悲劇的かつ、あまりにも馬鹿げた展開を迎えます。
彼らの逃走車が突っ込んでしまったのは、なんと地元の「トマトまつり」。そして、ここでゴンジーの致命的な弱点が明らかになります。彼は、トマトによってその超人的な力を完全に失ってしまうのです。スーパーヒーローの弱点としては、あまりにも日常的で、拍子抜けするような設定。しかし、この不条理さが、本作の持つ独特の味わいを深くしています。
宇宙的な存在であるゴンジーが、大量生産されるありふれた農産物によって無力化される。この構図は、シリアスな展開の中に強烈な脱力感と乾いた笑いをもたらします。どんなに強大な力も、思いもよらない些細なことで覆される。この感覚は、予測不可能な現実の世界を生きる私たちにとって、妙なリアリティを持って響くのではないでしょうか。
捕らえられたゴンジーは「トマトづけ」にされ、ハチは脳に装置を埋め込まれて感情のない「衛生人間」に改造されてしまいます。個性を奪われ、企業の歯車として無気力に働き続ける「衛生人間」の姿は、当時の社会で若者が直面していた同調圧力への強烈なメッセージです。個性を殺してシステムに順応することへの、静かな、しかし確固たる抵抗がここに見て取れます。
絶望的な状況の中、ミミミとモニカによる奪還作戦が始まります。彼女たちが使う武器は「ジューシイキャンキャン」という、あらゆる固体を溶かすスプレー缶。この、まるで子供の空想のようなガジェットが、ハイテクで冷徹なドアーズのシステムを打ち破るという展開が痛快です。論理や合理性だけでは測れない力が、世界には確かにあるのだと、この物語は教えてくれます。
そして、本作で最も謎めいた場面の一つが訪れます。衰弱したゴンジーが、自らのズボンの内に手を入れるという謎の行為によって、スーパーパワーを完全に取り戻すのです。この場面には、論理的な説明など一切ありません。それは、生命の根源的なエネルギー、友情や信頼といった、科学では解析不可能な力がもたらした奇跡として描かれます。ドアーズが理解しようとした「力」が、彼らの論理の及ばない場所から湧き上がってくる。この非合理なエネルギーの肯定こそ、本作の核心にあるように思えます。
力を取り戻したゴンジーは、ドアーズの本部を破壊します。しかし、物語はここで終わりません。物理的な脅威は去っても、ハチをはじめとする「衛生人間」たちの失われた自我は戻らないのです。ここからの展開こそが、「だいじょうぶマイ・フレンド」という物語が、単なるSFアクションではないことを証明しています。
ゴンジーのスーパーパワーですら、彼らの心を癒すことはできません。絶望的な沈黙が流れる中、モニカがハーモニカを吹き、ミミミがロックンロールを踊り始めます。すると、その音楽とダンスの力が奇跡を起こし、洗脳されていた若者たちの魂を揺さぶり、彼らの自我を呼び覚ますのです。この結末には、本当に胸を打たれました。
このクライマックスで、ゴンジーは静かに呟きます。「君らはいいなあ。音楽がやれるし自分の生まれた星に住んでいるのだから……」。この台詞に、本作のすべてのメッセージが集約されています。物理的な破壊をもたらすスーパーパワーよりも、魂を救い、人と人とを結びつける音楽や文化の力こそが尊いのだと。どんなに強大な力を持っていても、故郷を失い、孤独なゴンジーは、彼らを羨むのです。
この物語は、超人的な力への憧れを描いているのではありません。むしろ、人間が本来持っている、友情や、音楽を奏で、共に踊るといった、ささやかだけれどもかけがえのない力の素晴らしさを高らかに歌い上げているのです。その視点の優しさと温かさこそが、この奇想天外な物語に、深い感動と普遍性を与えています。
自らの役目を終えたゴンジーは、友人たちに別れを告げ、故郷の星へと飛び立っていきます。彼の去っていく姿を見送る若者たちの表情には、寂しさだけでなく、確かな成長と明日への希望が感じられます。
そして、物語は美しいエピローグで幕を閉じます。クリスマス。ミミミたちが空を見上げていると、遠い宇宙からゴンジーの声で「メリークリスマス」というメッセージが届くのです。物語の序盤、彼の孤独な過去の象徴だったこの言葉が、最後の最後で、友情と愛情に満ちた温かい贈り物として返ってくる。この見事な構成には、思わずため息が出ました。彼らの冒険が、決して夢ではなかったことの証として、心に深く刻まれるラストシーンです。
まとめ
小説「だいじょうぶマイ・フレンド」は、一見すると荒唐無稽なSFコメディのように思えるかもしれません。しかし、その奥には、80年代という時代の空気感、巨大なシステムに対する個人の尊厳、そして何よりも友情や文化といった人間的な営みの素晴らしさを描いた、深く心に響く物語が隠されています。
空から来た孤独な超人と若者たちの交流を通して、村上龍さんは、本当に大切なものは何かを問いかけます。物理的な強さではなく、魂を震わせる音楽や、共に笑い、助け合う仲間の存在。そういった、手触りのある温かいものこそが、人生を豊かにするのだと。このメッセージは、時代を超えて私たちの胸を打ちます。
物語の結末を知った上で改めて読み返すと、散りばめられた多くの仕掛けや言葉が、より一層深い意味を持って迫ってきます。ネタバレを知ってもなお、色褪せることのない魅力がこの作品にはあります。
もしあなたが、日々の生活に少しだけ疲れていたり、現実の世界に窮屈さを感じていたりするのなら、ぜひこの物語の扉を開いてみてください。きっと、ゴンジーとミミミたちが、あなたの心に「だいじょうぶだよ」と、優しく語りかけてくれるはずです。