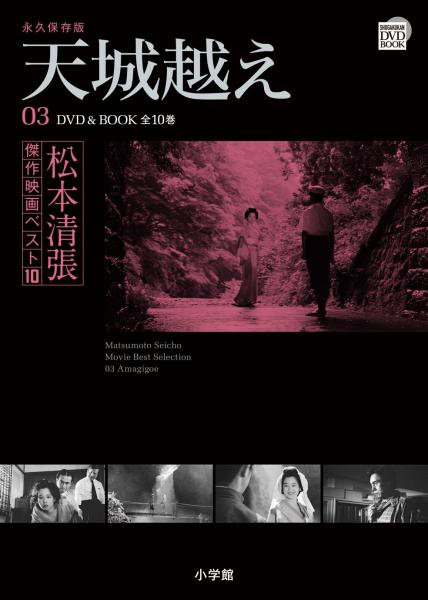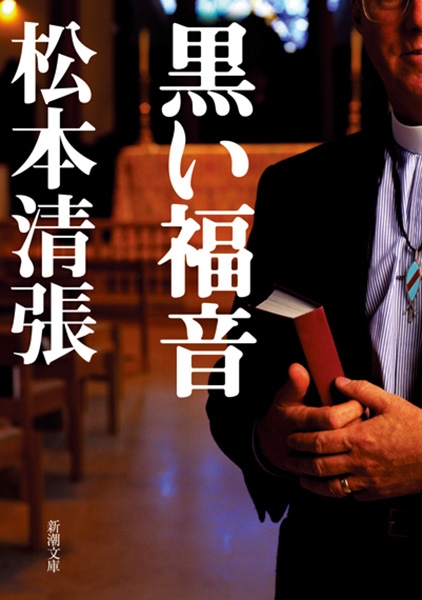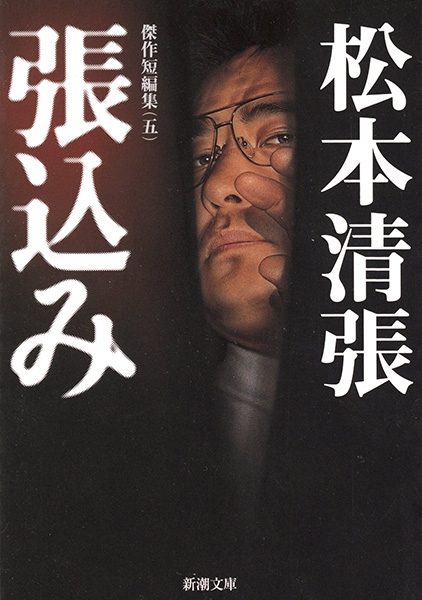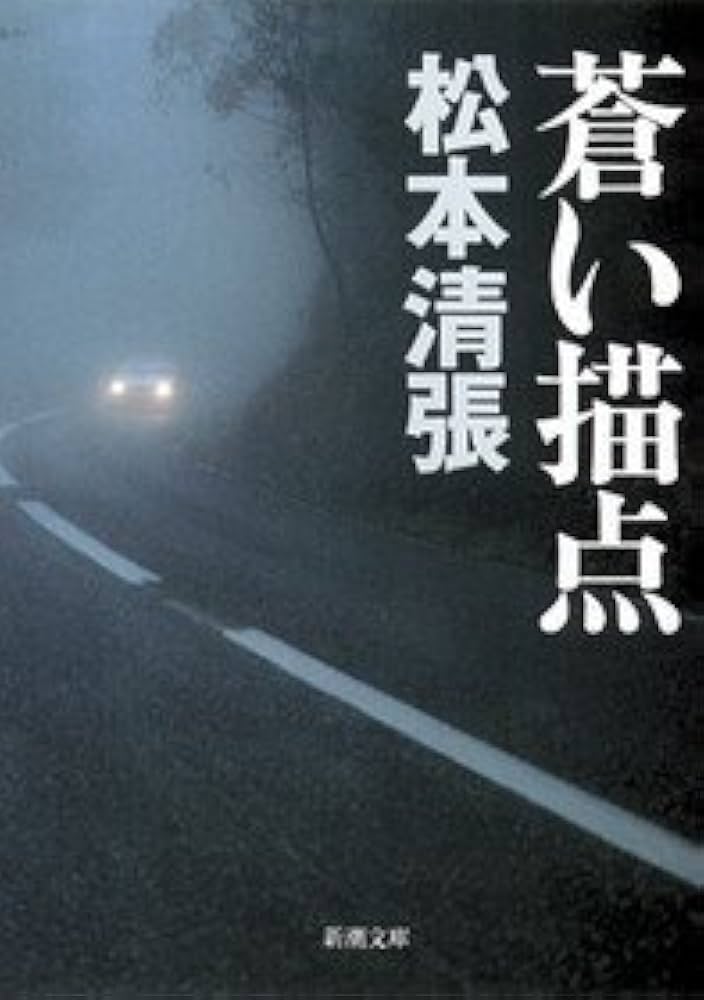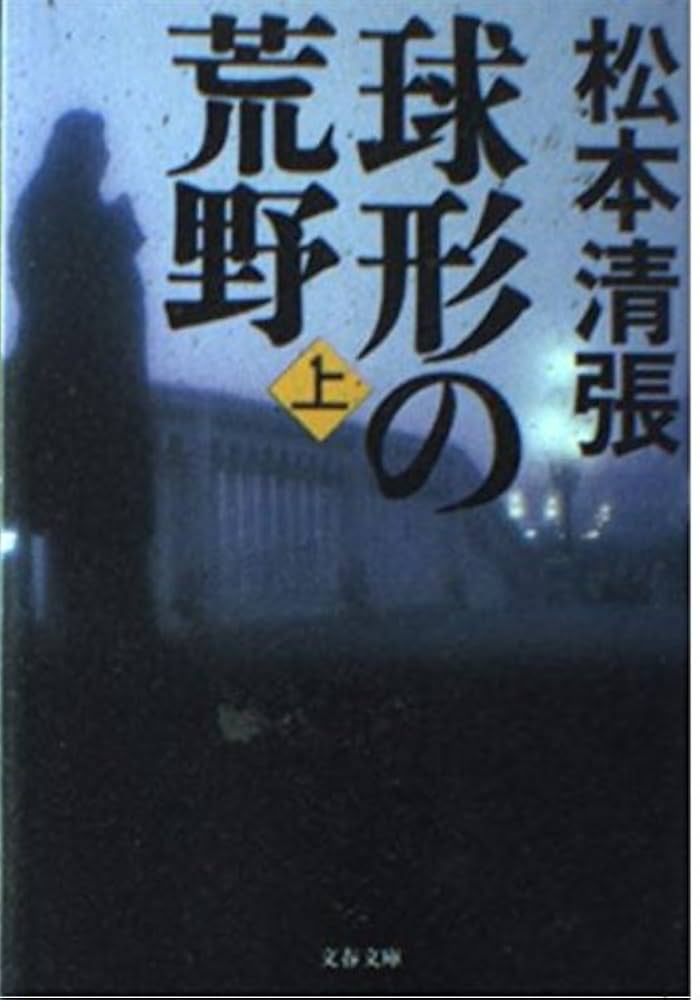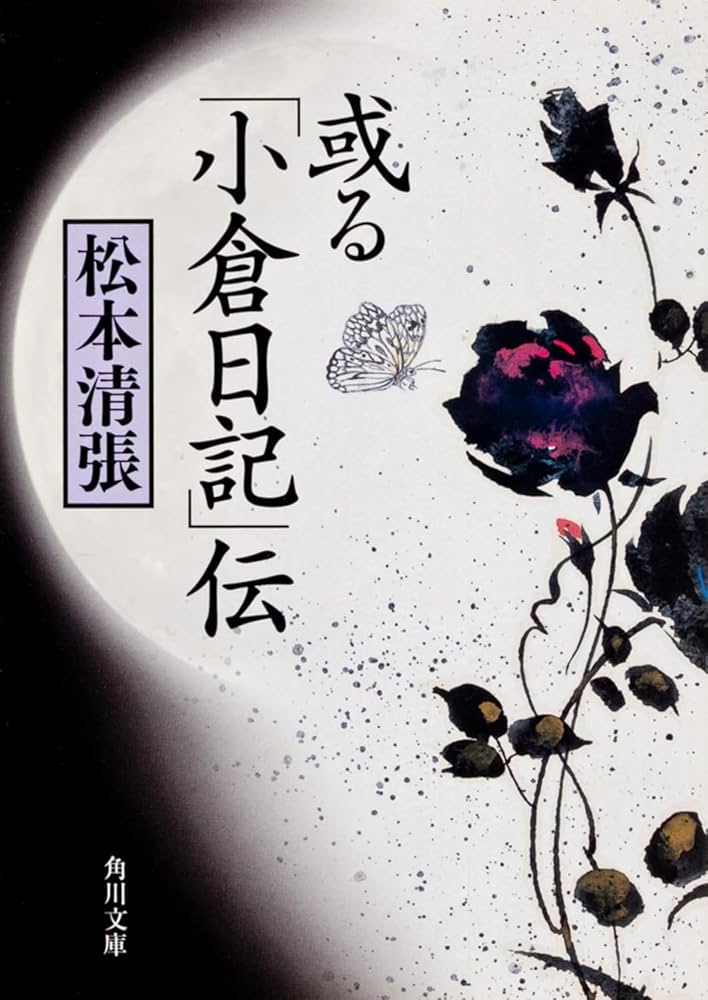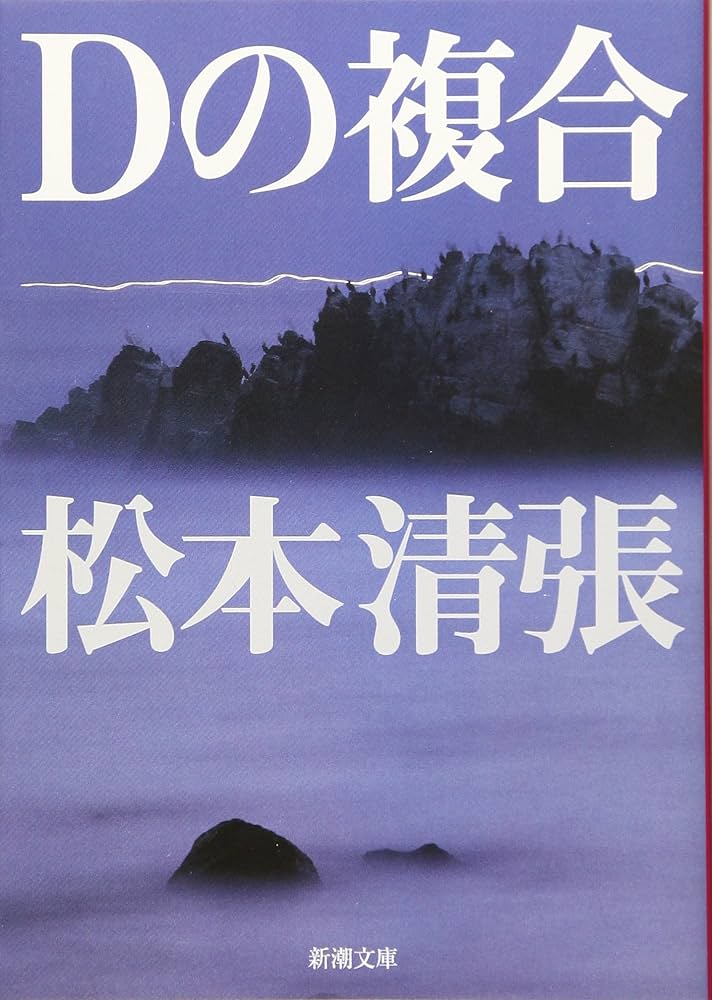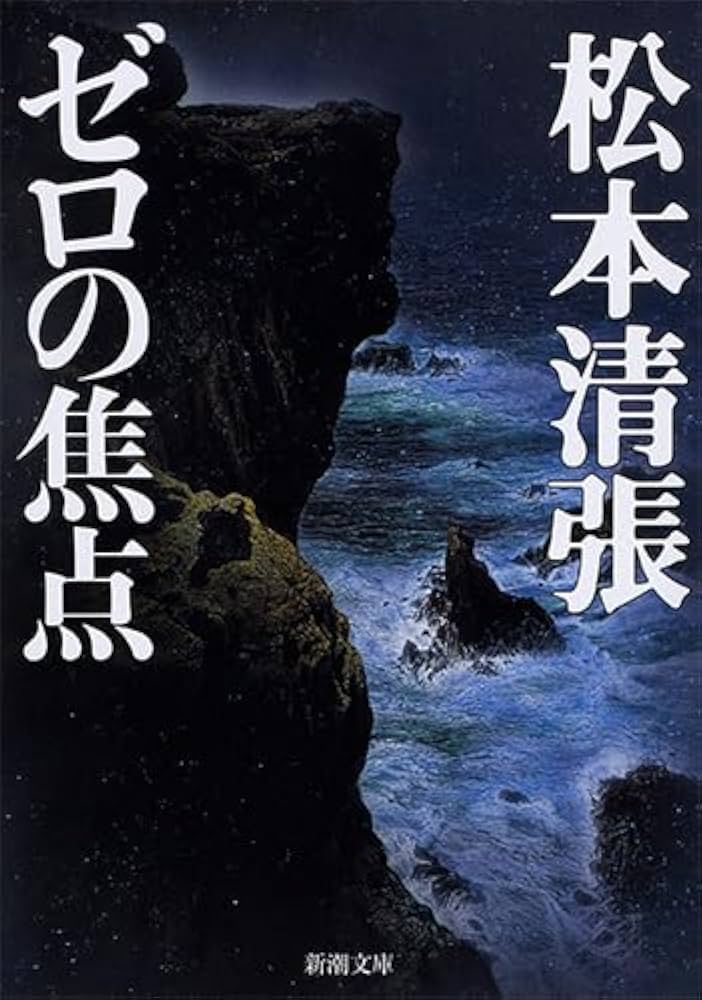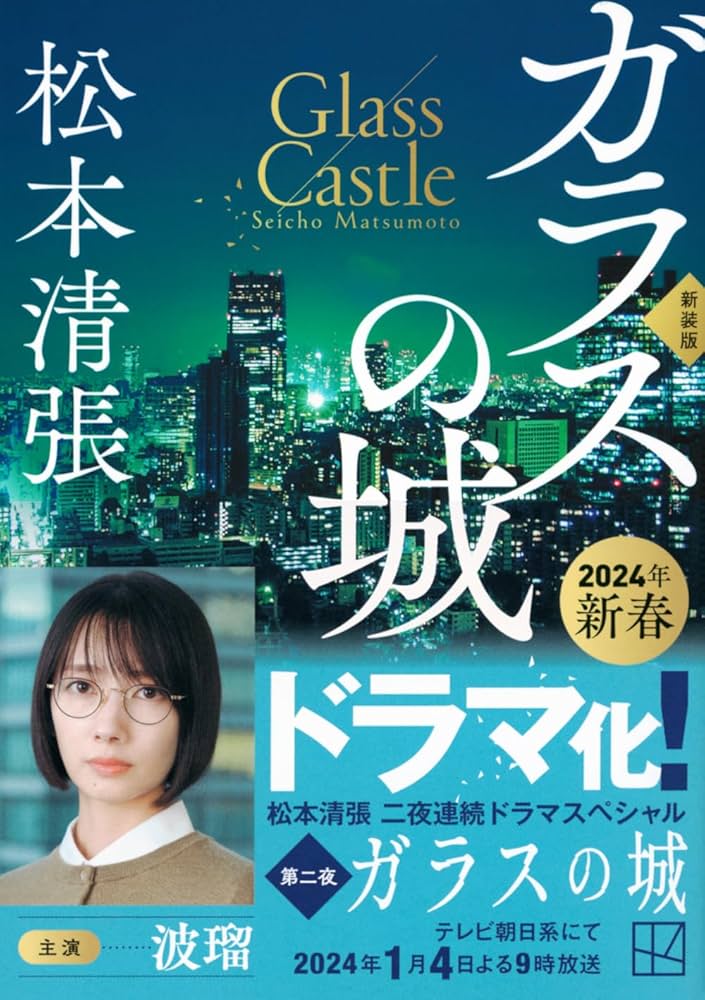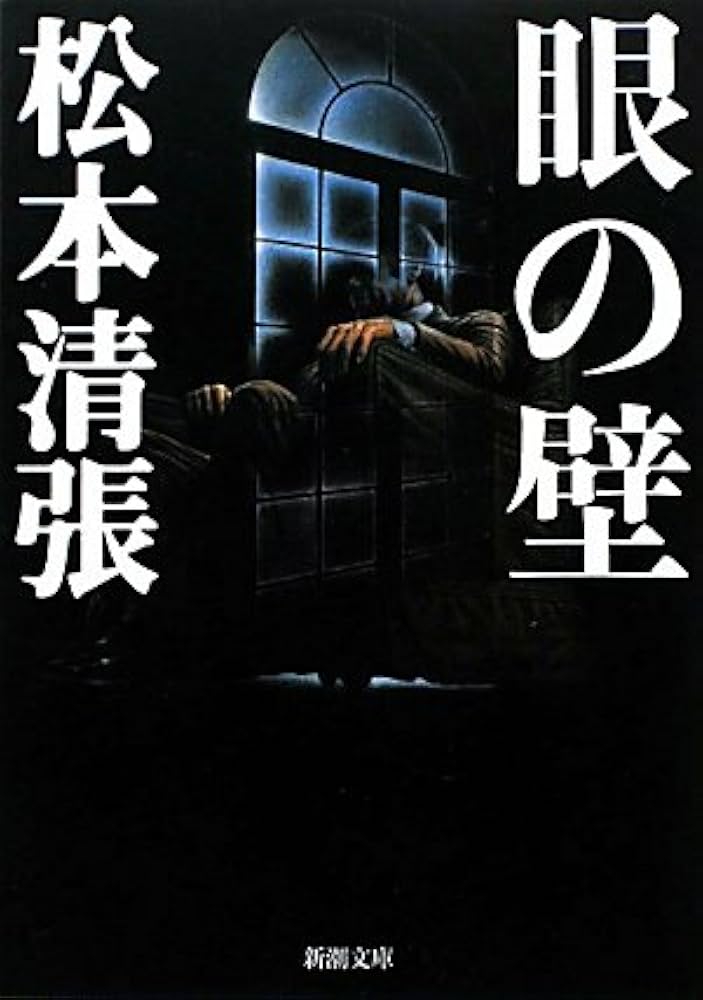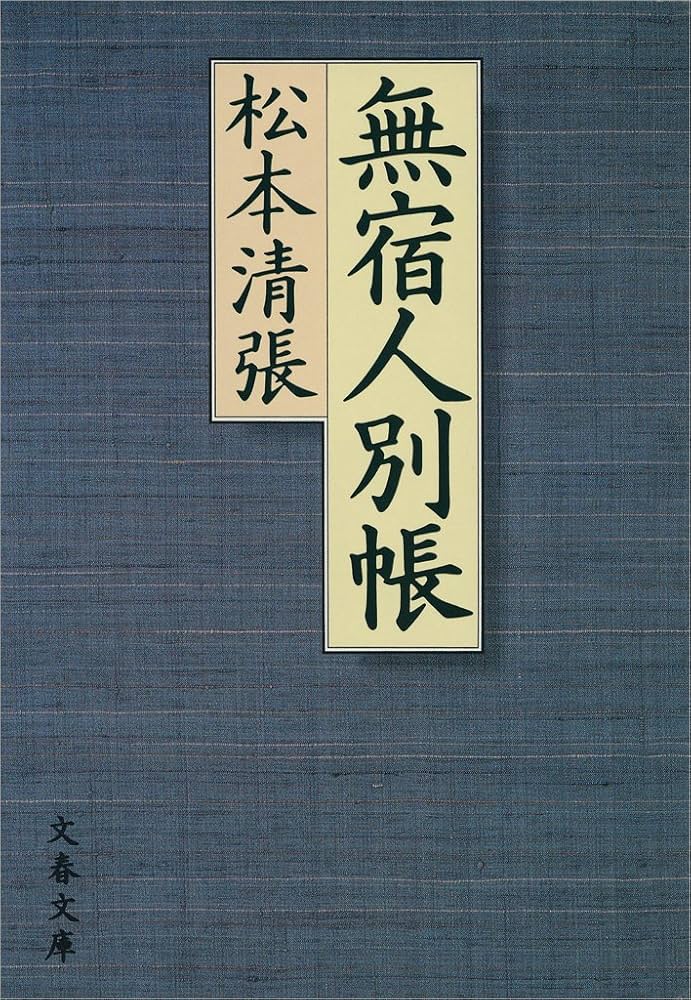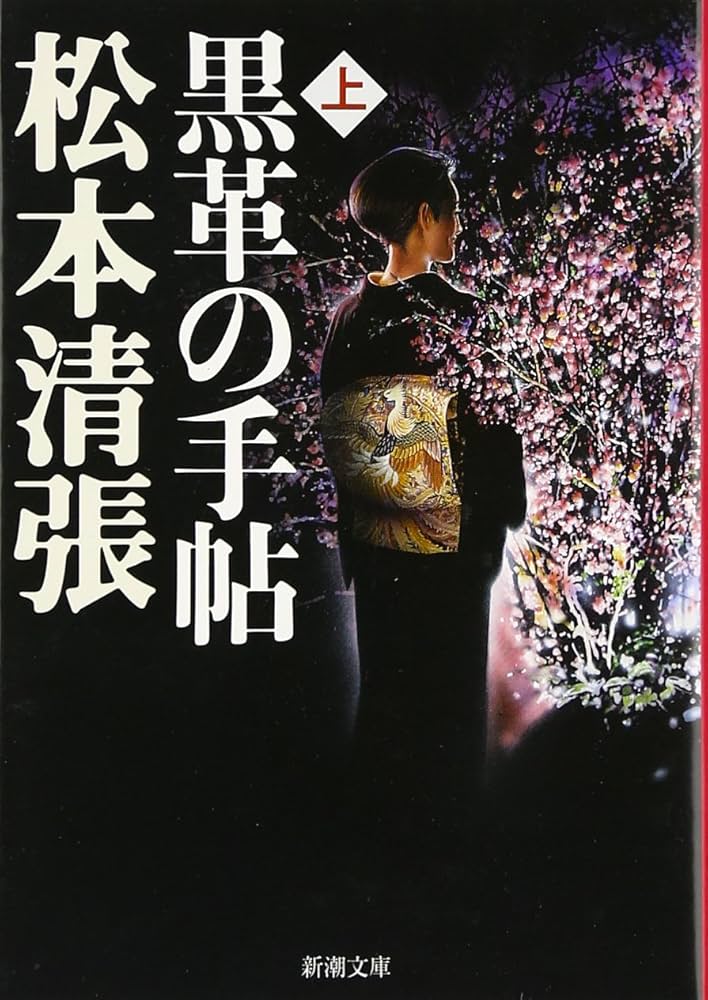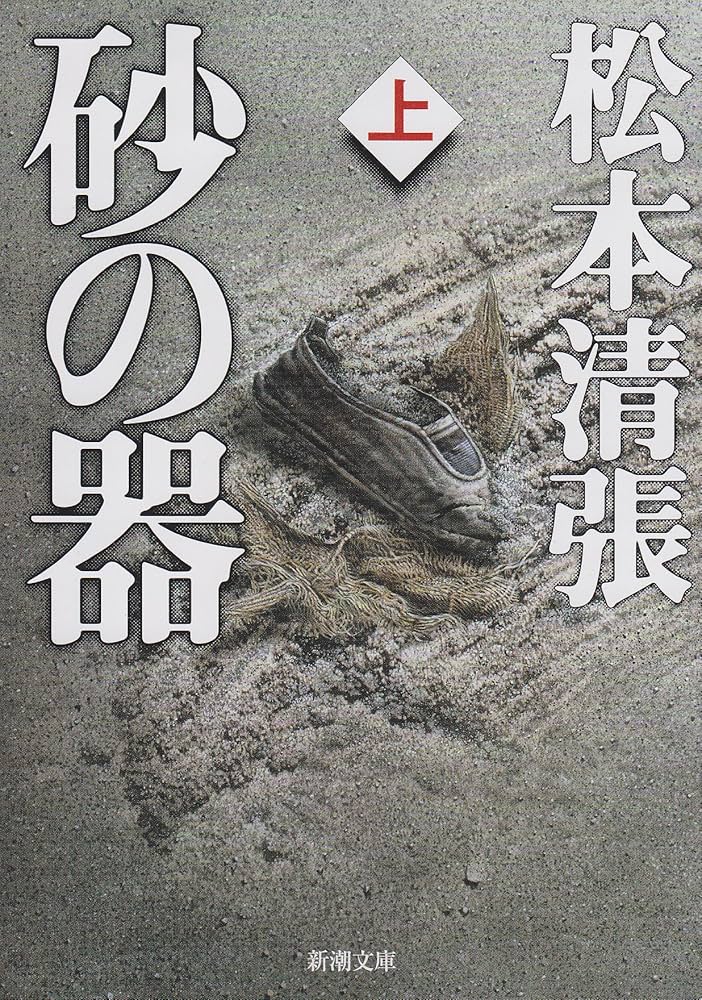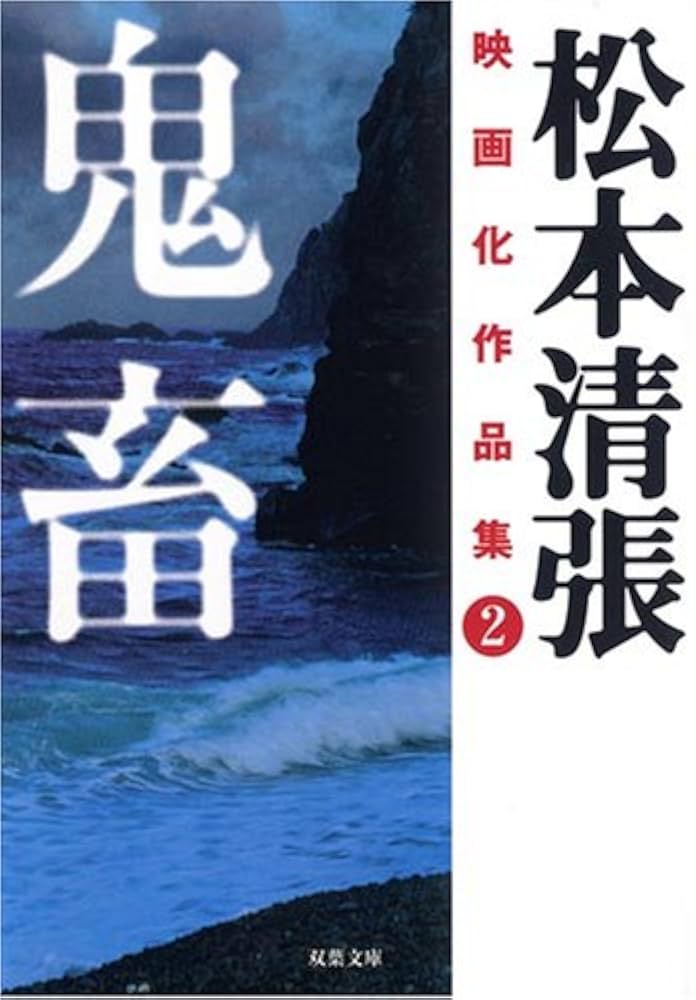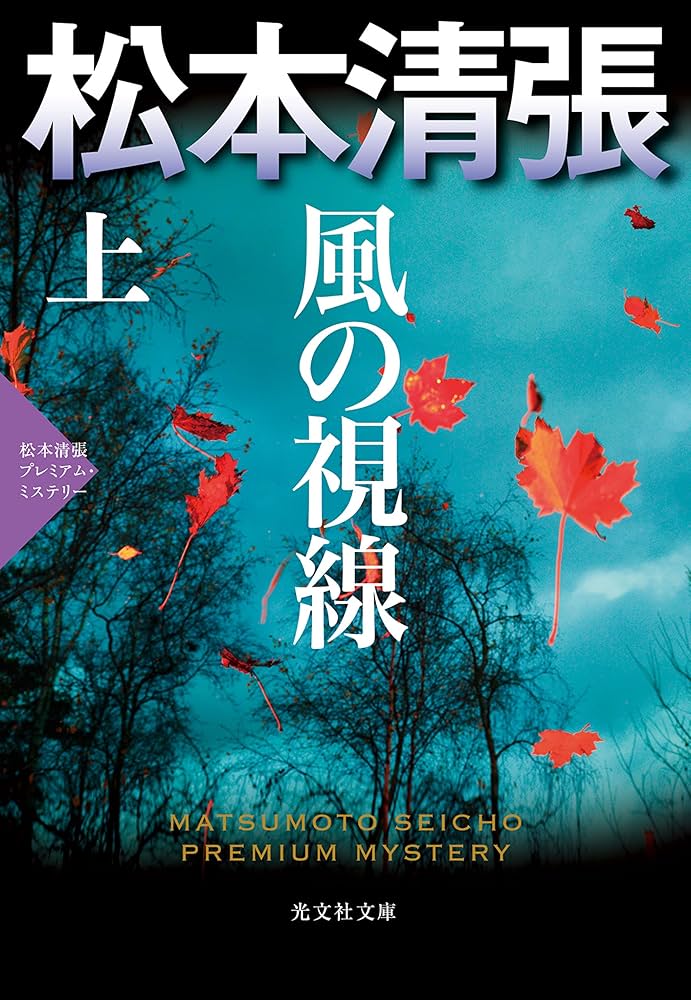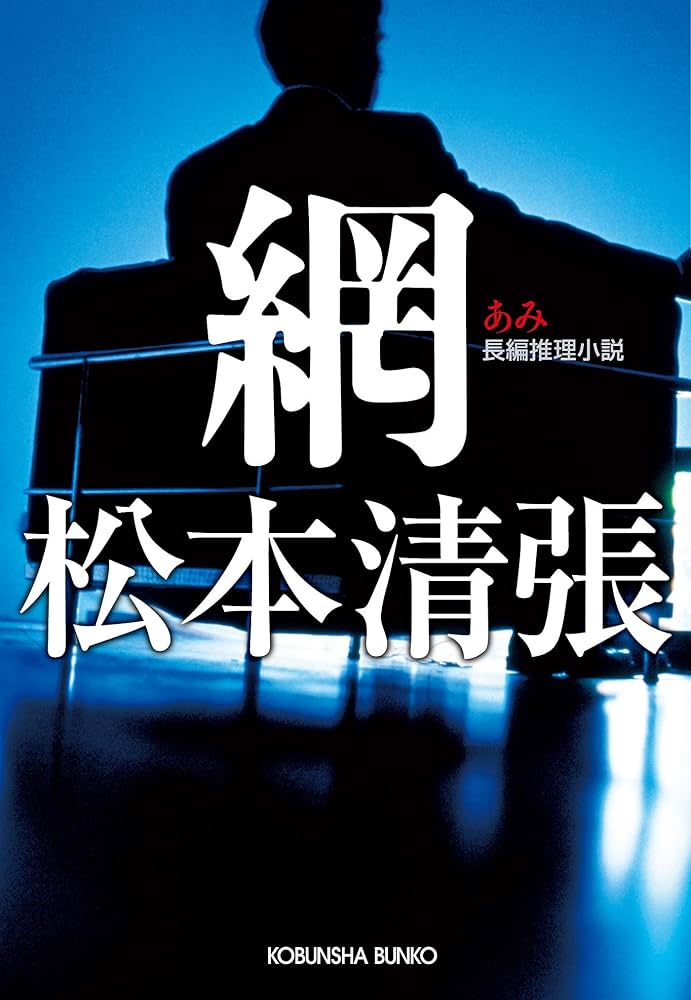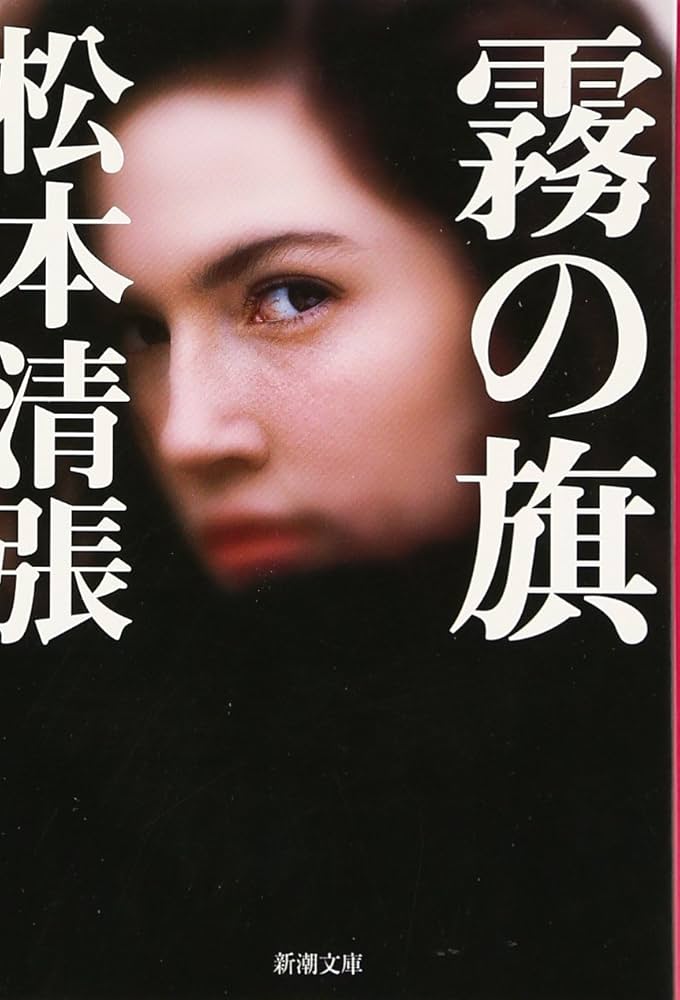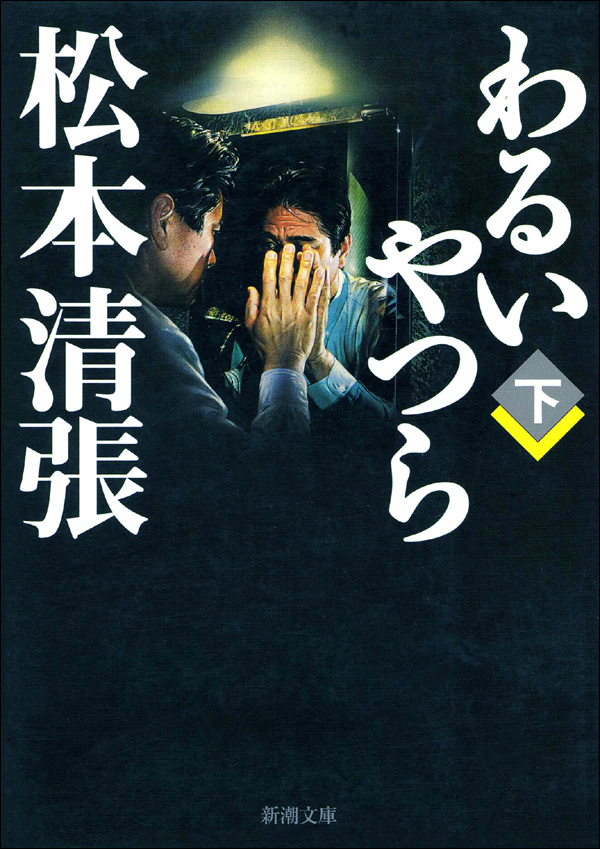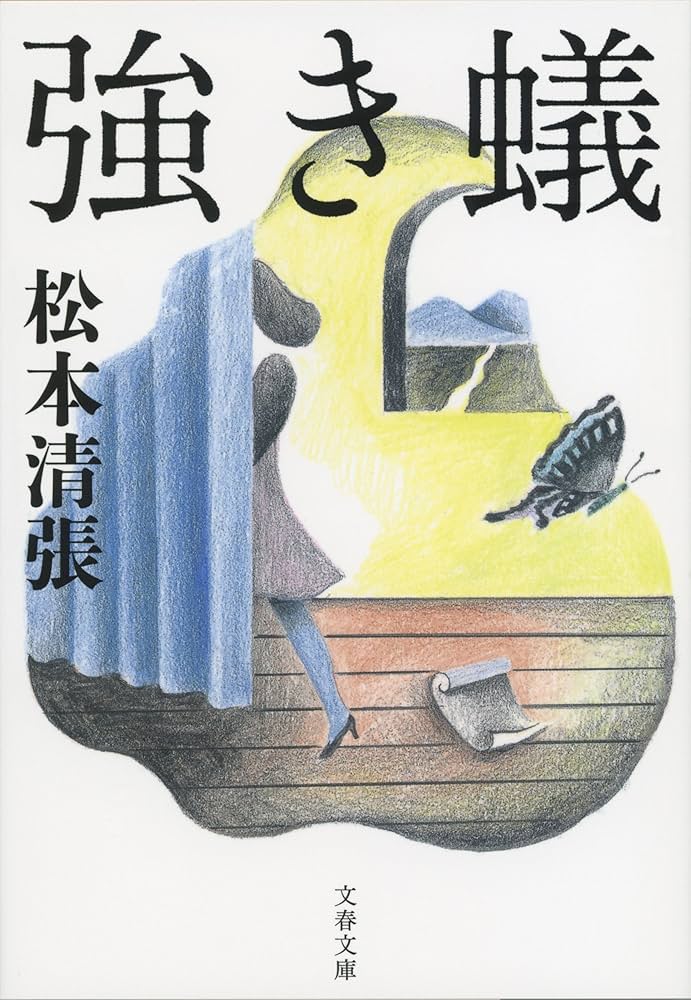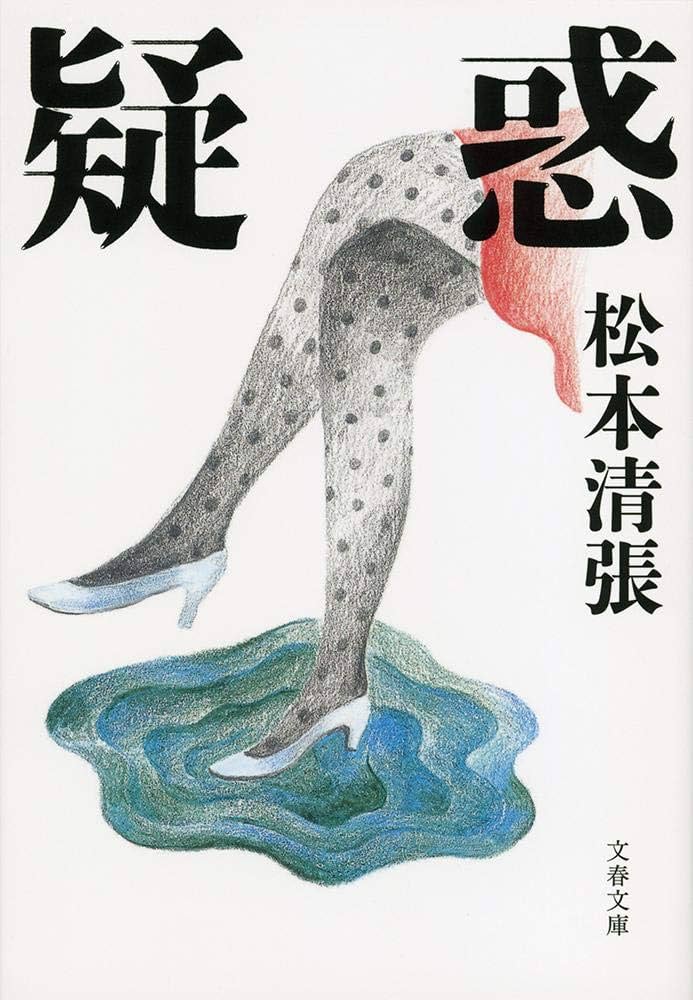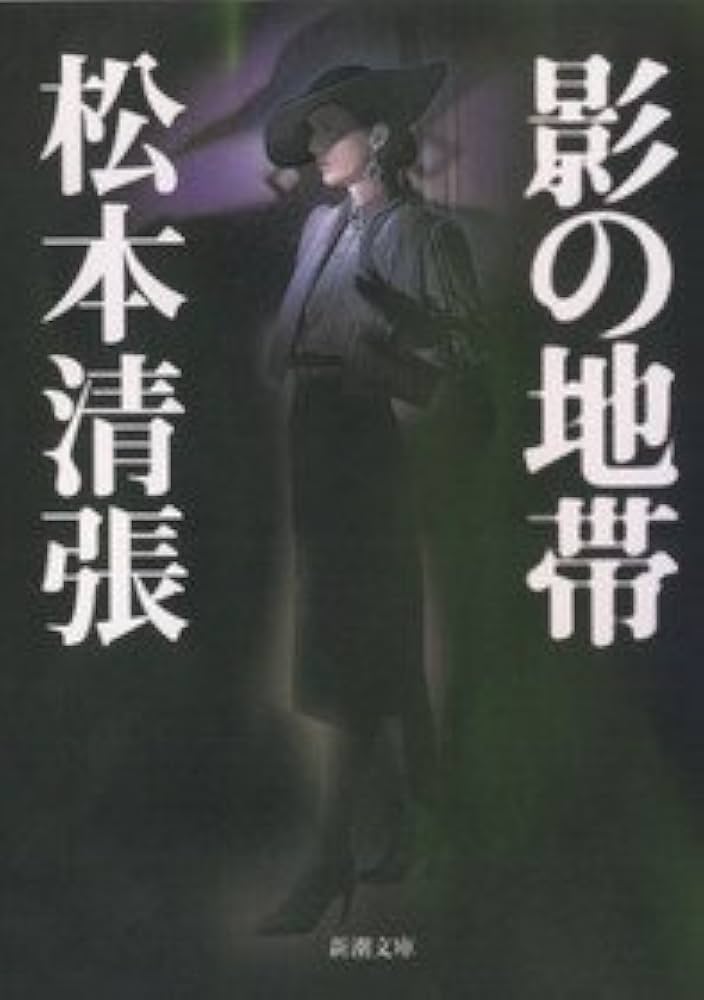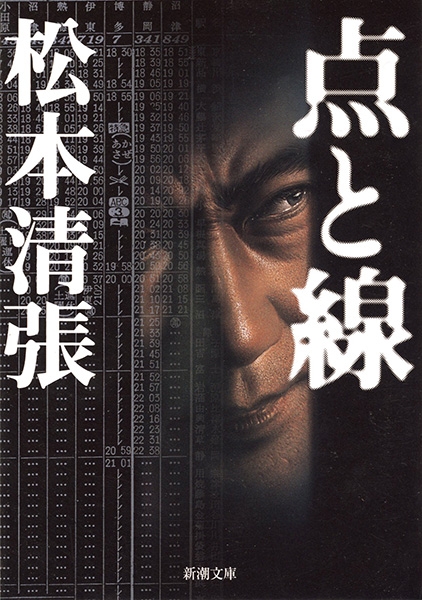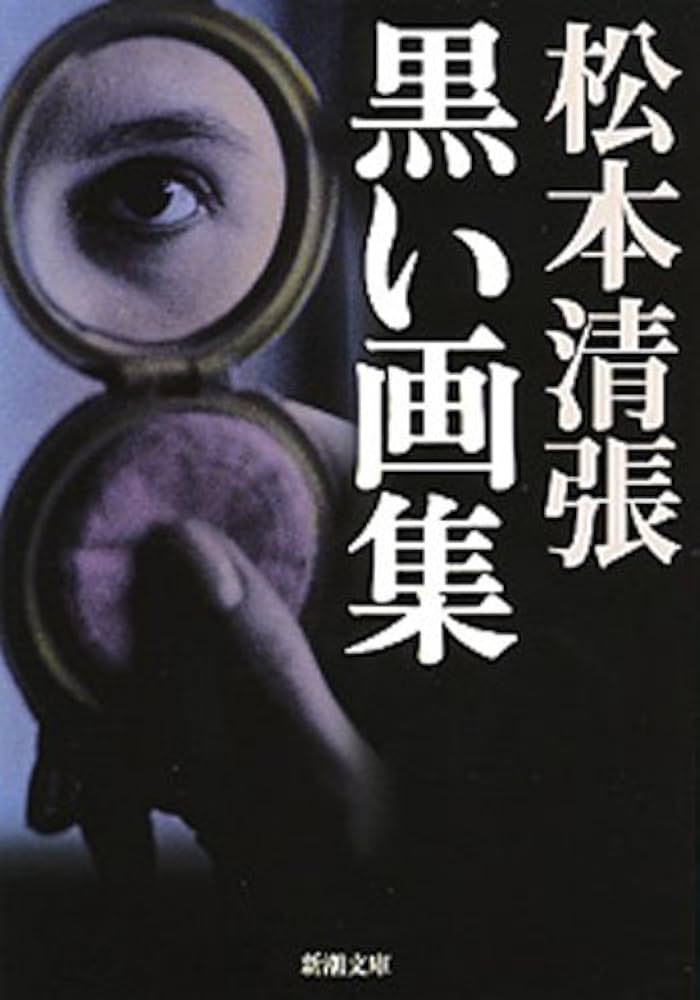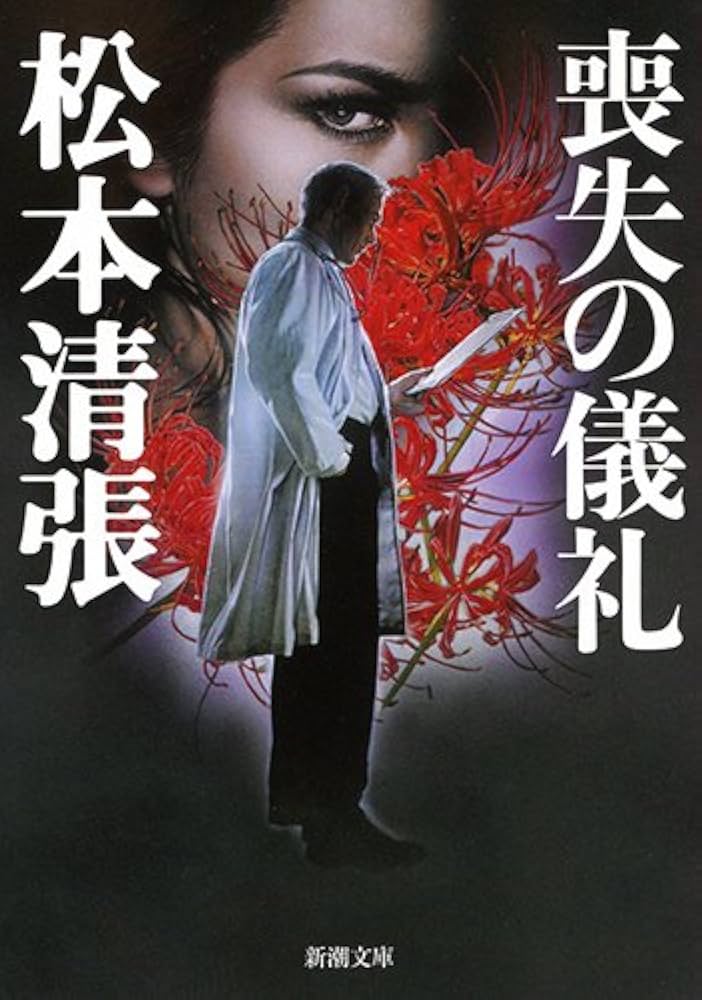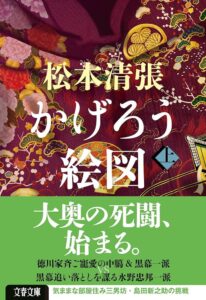 小説「かげろう絵図」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「かげろう絵図」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
松本清張が描く時代小説は、ただの歴史物語ではありません。そこには、現代社会にも通じる権力構造の闇や、組織に生きる人間の業が、鋭いメスでえぐり出されています。この「かげろう絵図」もまた、その代表格と言える傑作です。
舞台は、江戸幕府の権威が内側から腐り始めた天保年間。将軍をないがしろにする大御所、その大御所さえも裏で操る黒幕、そしてきらびやかな大奥に渦巻く女たちの野心と嫉妬。この複雑に絡み合った権力闘争の構図こそが、物語の最大の魅力なのです。
本記事では、まず物語の序盤のあらすじをご紹介し、その後、物語の結末まで踏み込んだ詳しいネタバレを含む感想を綴っていきます。この壮大な人間ドラマが、読後にどのような感情を残すのか。その一端に触れていただければ幸いです。
「かげろう絵図」のあらすじ
物語は、江戸城で催された華やかな観桜の宴から始まります。第十一代将軍・家斉の寵愛を一身に受ける側室・お美代の方と、懐妊中の若き側室・お多喜の方が競い合うように歌を披露する、一見優雅な場面。しかし、この宴の裏では、すでに恐ろしい陰謀が動き出していました。
歌くらべに勝ったお多喜の方が、桜の枝に短冊を結びつけようと踏み台に乗った瞬間、悲劇は起こります。彼女は足を踏み外し、激しく転落。この事故で流産し、ついには命を落としてしまうのです。これは本当にただの事故だったのでしょうか。その場にいた誰もが、お美代の方の存在を意識せずにはいられませんでした。
この事件のさなか、一人の下級女中・登美が機転を利かせたことで、お美代の方の目に留まります。彼女は異例の抜擢を受け、大奥の深奥へと足を踏み入れることに。しかし、彼女の真の目的は、お美代の方とその背後で権力を握る中野石翁の不正を暴くため、改革派の密命を帯びて潜入した間諜だったのです。
一方、江戸市中では、武士の身分を捨て気ままに暮らす浪人・島田新之助がいました。彼は、改革派の旗本である叔父の身を案じるうち、知らず知らずのうちに、この巨大な陰謀の中心へと引き寄せられていきます。大奥に潜入した登美と、市井に生きる新之助。二つの視点が交錯する時、物語は大きく動き始めるのです。
「かげろう絵図」の長文感想(ネタバレあり)
ここからの内容は、物語の核心に触れる重大なネタバレを含んでいます。未読の方はご注意ください。この「かげろう絵図」という物語が、なぜこれほどまでに心を揺さぶるのか、その理由を深く掘り下げていきたいと思います。
まず語るべきは、この物語の舞台設定の見事さでしょう。将軍・家慶はいるものの実権はなく、父である大御所・家斉が権力を握っている。しかし、その家斉でさえ、相談役の中野石翁とお気に入りの側室・お美代の方にいいように操られている。この「三重の権力構造」が、物語全体に不気味な影を落としています。
この歪んだ構造は、現代の会社組織や政治の世界にも通じるものがあり、読んでいて背筋が寒くなるほどのリアリティを感じさせます。誰が本当の権力者なのか、その実態はまるで陽炎のようにつかみどころがない。まさに「かげろう絵図」という題名が、物語の本質を射抜いているのです。
この物語の主人公は、まぎれもなく島田新之助です。彼は武家の次男坊で、家督を継ぐ望みもなく、飄々と生きています。しかし、その胸の内には確かな正義感と、物事の本質を見抜く冷静な目、そして卓越した剣の腕を秘めています。
彼の魅力は、完全無欠のヒーローではないところにあると私は思います。叔父たちが進める改革運動にも、どこか冷めた視線を向けている。正義のためという大義名分だけでなく、身内を案じるという個人的な動機で、巨大な陰謀に立ち向かっていく姿に、人間的な魅力を感じずにはいられません。
そして、もう一人の主人公が、大奥に潜入した登美(本名・縫)です。彼女は、正義の世を実現するため、そして密かに想いを寄せる新之助のために、命がけの任務に身を投じます。彼女の視点を通して描かれる大奥の描写は、息苦しいほどに生々しいものです。
そこは、女たちが嫉妬と野心を燃やす戦場。美しく着飾った女中たちが、裏では僧侶と密通を重ね、それが幕府全体を揺るがすスキャンダルに発展していく。登美は、いつ密偵であることがバレるとも知れない恐怖の中で、たった一人、腐敗の証拠を集め続けます。彼女の覚悟と孤独を思うと、胸が締め付けられます。
物語の中盤、新之助が傍観者ではいられなくなるきっかけが、隣人である心優しき町医者・良庵の失踪事件です。この事件を追ううち、彼は中野石翁一派による殺人事件の証拠をつかんでしまいます。ここから物語は、時代小説でありながら、上質なミステリーの様相を呈してきます。
新之助が外部から得た物証と、登美が内部からもたらす情報。この二つがパズルのピースのようにはまった時、初めて陰謀の全体像が明らかになる。この内外からの連携プレーが、物語にスリリングな緊張感と奥行きを与えているのです。
物語の最大の敵役である中野石翁の存在感も圧倒的です。彼は、自らの血を引く者を次期将軍の世継ぎにするという壮大な野望のために、邪魔者を容赦なく消していく冷酷な人物。しかし、彼を単なる悪役として片付けられないのが、この物語の深いところです。
彼の行動は、紛れもなく「悪」です。しかし、彼の敵対勢力である脇坂淡路守ら改革派もまた、大義のためには謀略を厭わない。正義を掲げながらも、やっていることは石翁たちと紙一重。この物語は、善と悪の単純な二元論では割り切れない、権力闘争そのものが持つ魔性を描き出しているのです。
そして物語は、大御所・家斉の危篤をきっかけに、息もつかせぬクライマックスへと雪崩れ込みます。石翁は、意識の混濁した家斉に、自分の曾孫を世継ぎとする「御墨付き」を書かせることに成功します。この一枚の紙を巡って、江戸の夜を舞台にした壮絶な争奪戦が繰り広げられるのです。
このクライマックスの展開は、まさに圧巻の一言。もはや知略の戦いではありません。むき出しの暴力と欲望がぶつかり合う、凄まじい活劇です。新之助は、愛する女性を人質に取られながらも、たった一人で石翁の軍勢に立ち向かい、ついに「御墨付き」を奪い取ります。
読者はここで、悪が滅び正義が勝つ、痛快な結末を期待するでしょう。しかし、松本清張は、そんな安易なカタルシスを私たちに与えてはくれません。ここからが、この物語の真骨頂であり、最も語るべきネタバレの部分です。
石翁は失脚し、水野忠邦ら改革派が権力を握ります。表面的には、新之助たちの勝利です。しかし、その現実はあまりにもほろ苦いものでした。最大の功労者であるはずの登美(縫)は、新政権の暗部を知りすぎたがゆえに、用済みとして切り捨てられ、悲劇的な最期を遂げてしまうのです。
この結末には、本当に言葉を失いました。命を懸けて戦ったヒロインが、自らが勝利に導いたはずの味方によって消される。これほどまでに救いのない結末があるでしょうか。権力とは、かくも非情で、残酷なものかと思い知らされます。
生き残った新之助にも、栄光はありません。彼に残ったのは、信じていた正義がもたらした空虚な結果と、どうしようもない幻滅感だけでした。結局、一つの体制が倒れても、また別の人間が同じように権力を握り、同じようなことが繰り返されるだけ。多くの犠牲の果てに手にしたものは、陽炎のように実体のない幻だったのです。
このやるせない読後感こそが、「かげろう絵図」という作品の核心なのだと私は思います。英雄の活躍が必ずしも幸福な未来を約束するわけではない。むしろ、権力闘争に関わった人間は、勝者でさえもその魂を蝕まれていく。
この物語が突きつけるのは、そうした厳しい現実です。しかし、絶望だけが残るわけではありません。全てを失った新之助の傍らには、恋人・豊春の存在があります。公的な世界の醜悪さから離れ、個人的な絆の中にささやかな救いを見出す。それこそが、人間にとって唯一の希望なのかもしれないと、かすかな光を感じさせてくれるのです。
まとめ
松本清張の「かげろう絵図」は、単なる時代活劇の枠をはるかに超えた、人間ドラマの傑作です。きらびやかな大奥を舞台にしたスリリングな諜報戦、手に汗握る活劇、そして巧みに仕組まれたミステリー。エンターテイメントとして、非常に高いレベルでまとまっています。
しかし、この物語の本当の価値は、そのネタバレを知った後に訪れる、深い感慨にあるのかもしれません。正義の勝利が必ずしもハッピーエンドに繋がらないという、ほろ苦い結末。権力というものの虚しさと、それに翻弄される人間の悲しさが、胸に重くのしかかってきます。
物語のあらすじを追い、登場人物たちの運命を見届けた後、読者はきっと「かげろう」という言葉の意味を改めて噛みしめることになるでしょう。人々が命を懸けて追い求めたものは、本当にそれだけの価値があったのか。
もしあなたが、ただ面白いだけでなく、読んだ後に深く考えさせられるような物語を求めているのなら、この「かげろう絵図」はまさにおすすめの一冊です。歴史の闇にうごめく人々の欲望と、その果てにある切ない真実を、ぜひその目で確かめてみてください。