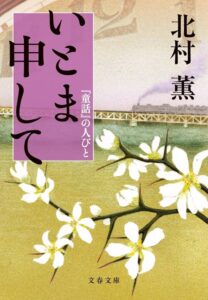 小説「いとま申して『童話』の人びと」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「いとま申して『童話』の人びと」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、一つの家族の、とりわけ父と子の間に流れる静かで深い愛情の記録です。作家である息子が、亡き父の遺した日記帳を開くところから、すべては始まります。そこに記されていたのは、息子も知らなかった父の青春時代の夢、文学への熱い情熱でした。父が青春を過ごした大正の終わりから昭和の初めという時代が、まるでセピア色の写真から色彩を取り戻すように、鮮やかに立ち上がってきます。
物語の舞台となるのは、かつて存在した児童文学雑誌『童話』。父は、この雑誌の熱心な読者であり、そして投稿者でした。驚くべきことに、その誌面には、後に日本中が知ることになる、あの金子みすゞや淀川長治といった人々の名前も並んでいたのです。父が、そのような才能たちと同じ場所で、同じ夢を見上げていたという事実。それが、この物語に特別な輝きを与えています。
本書は、一人の青年の個人的な記録を丹念に辿りながら、同時にその時代に生きた人々の息吹や文化の香りを私たちに届けてくれます。歴史の大きな流れの中では見過ごされてしまうかもしれない、けれど、確かにそこにあった個人の小さな、しかし大切な物語。父の夢の行方を見届ける息子のまなざしを通して、私たちは時間というものの切なさと、記憶を受け継いでいくことの尊さを感じずにはいられないでしょう。
「いとま申して 『童話』の人びと」のあらすじ
物語の主人公は、宮本演彦(のぶひこ)という一人の青年です。時代は、大正デモクラシーの自由な空気がまだ残る1924年。横浜のハイカラな街で、感受性豊かな少年期を過ごす彼は、大変な読書家でした。国内海外の文学作品に夢中になり、映画館に通い詰める、知的好奇心にあふれた少年時代を送ります。
彼の心を特に捉えたのが、当時、コドモ社から刊行されていた児童文学雑誌『童話』でした。美しい挿絵と詩的な物語で飾られたその雑誌は、演彦にとって憧れの世界そのものでした。彼はただ読むだけでなく、自らも筆を執り、童話や詩をその雑誌に投稿するようになります。自分の名前が活字になる喜び、選ばれなかった時の悔しさを味わいながら、彼は「童話作家になる」という夢を育んでいきます。
その『童話』の投稿者欄には、きら星のような才能が隠れていました。後に不滅の詩人として再発見される金子みすゞ、そして「サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ」の名調子で愛される映画解説者の淀川長治。演彦は、彼らと同じ誌面で、同じ夢を追いかけていたのです。彼は自分の才能と向き合い、仲間たちと同人誌を作り、文学への情熱を燃やし続けます。
やがて時は流れ、演彦は旧制中学校の卒業という、人生の大きな節目を迎えます。文学への夢を抱き続けたまま、彼は新たな道へと進むことになります。童話作家になりたいという切なる願いは、果たしてどのような形で結実するのでしょうか。あるいは、別の未来が彼を待っているのでしょうか。物語は、青年の夢の行方を静かに見つめます。
「いとま申して 『童話』の人びと」の長文感想(ネタバレあり)
この本を手に取った時、私はまず、その題名に心を奪われました。『いとま申して』。この言葉が、著者の父上が亡くなる際に遺した句から採られているという事実を知った時、この物語が単なる評伝ではなく、亡き父に捧げられた、深くパーソナルな鎮魂の書であることを理解したのです。
作家・北村薫が、父・宮本演彦の遺品の中から見つけた古い日記帳。それは、父が14歳から20歳までの多感な時期を記録した、宝物のような遺産でした。この日記を道標として、息子は父の青春という未知の領域へと足を踏み入れていきます。それは、時間の中に埋もれてしまった夢の痕跡を掘り起こす、愛情に満ちた考古学のような作業だったに違いありません。
物語の舞台となるのは、1920年代の日本。関東大震災からの復興期であり、軍国主義の暗い影が差し込む前の、つかの間の平和と文化的な活気に満ちた時代です。主人公である若き日の父、宮本演彦は、横浜の比較的裕福な家庭に育ち、知的な探求に没頭する自由を享受していました。
彼が通った旧制中学校のリベラルな校風は、彼の感受性を育むための最高の環境でした。教師は最新のトーキー映画の鑑賞を勧め、授業では北原白秋が論じられる。そんな豊かな土壌の上で、演彦青年はドストエフスキーを読み、前衛映画に触れ、文学への憧れを募らせていくのです。この描写の丹念さは、読者をまるでタイムトラベラーのように、その時代の空気の中へと誘ってくれます。
演彦青年の情熱が注がれたのが、児童文学雑誌『童話』でした。この雑誌は、彼の物語における中心的な太陽のような存在です。最初は一人の愛読者に過ぎなかった彼が、やがて自らの作品を投稿するようになり、その採否に一喜一憂する姿は、創作を志したことのある者なら誰もが共感するのではないでしょうか。
そして、この物語が読者に大きな驚きと感動を与える核心部分が、この『童話』という雑誌を介して明かされます。演彦青年が投稿していたその誌面に、二人の、後に伝説となる人物の名前が並んでいたという事実。一人は、詩人の金子みすゞ。もう一人は、映画評論家の淀川長治です。
著者は、父の歩みと並行して、若き日の金子みすゞの物語を織り込んでいきます。演彦が一人の投稿者として奮闘していた頃、みすゞはすでにスター作家として誌面を飾っていました。しかし、その後の彼女を待っていたのは、悲劇的な人生でした。若くして世を去り、その才能は半世紀もの間、忘れ去られてしまうのです。
一方で、若き日の淀川長治の投稿文も紹介されます。後年のお馴染みの口調を彷彿とさせる、エネルギーにあふれた文章。この対比が、物語に深い奥行きを与えています。同じ雑誌に集った若者たちの夢が、いかに多様な道を辿り、異なる運命を迎えたのか。その残酷さと不思議さを、私たちは目の当たりにすることになります。
この発見は、単なるトリビアではありません。無名の一青年であった父を、誰もが知る著名な人物たちと並べることで、著者は父の抱いた夢が、決して独りよがりなものではなく、本物の文化的なうねりの中に確かに存在したのだと証明してみせるのです。父の青春は、こうして普遍的な価値を獲得します。
この作品のもう一つの大きな特徴は、その独特な構成にあります。父の日記からの短い引用と、それに対する息子である著者の詳細な調査や解説が、交互に提示される形で物語は進んでいきます。それはまるで、父が投げかけたボールを、数十年後に息子が受け止め、その意味を解き明かしていくような、世代を超えたキャッチボールのようです。
ミステリ作家として知られる北村薫の真骨頂が、ここにあります。日記に記された「〇〇を読む」「△△を観る」というわずかな記述から、その本の内容、その映画が当時どのように評価されていたか、そしてその日の社会では何が起きていたのかを徹底的に調べ上げ、文脈を与えていく。この手法により、父の個人的な記録は、「小さな昭和史」とでも呼ぶべき、立体的な歴史ドキュメントへと変貌を遂げるのです。
この「パッチワーク」のような構成は、この物語の内容と分かちがたく結びついています。著者は、完成された物語を提示するのではなく、記憶を発掘し、再構築していくプロセスそのものを読者に見せてくれます。私たちは、著者と共に、断片的な過去のピースが一つひとつ丁寧につながれ、意味を帯びていく瞬間に立ち会うことができるのです。
物語の核心にあるテーマは、誰もが経験するであろう「夢とその行方」です。演彦青年が抱いた童話作家になるという夢は、しかし、劇的な形で破れるわけではありません。物語は、その情熱の炎が、いかにして静かに、そしてゆっくりと消えていったかを克明に追います。
その要因は一つではありません。時代の変化と共に雑誌『童話』そのものが変わっていったこと。文筆で生きていくことの現実的な困難さ。そして何より、彼自身の興味が、成長と共に他の分野へと広がっていったこと。歌舞伎の魅力に目覚め、友人たちとの同人誌活動に新たな喜びを見出していくのです。
物語の第一巻は、彼が慶應義塾大学の予科に入学するところで幕を閉じます。それは、文学的な成功ではなく、学問という新たな地平への一歩でした。童話作家になるという夢に、彼は静かに「いとま」を告げ、研究者、そして教師となる新たな人生へと歩みを進めていくのです。
私がこの物語に深く心を打たれたのは、この「夢の終わり方」の描き方です。それは、一般的にイメージされるような「挫折」の苦々しい物語ではありません。むしろ、一つの季節が終わり、新たな季節が始まるような、自然で穏やかな変化として描かれています。夢から「卒業」していく、とでも言うべきでしょうか。
この静かなリアリズムこそが、本作の最大の魅力かもしれません。成功か失敗かという単純な二元論では語れない、人生の機微。若き日の夢を、怒りや後悔と共にではなく、大切な思い出として胸の奥にしまい、次のステージへと進んでいく。多くの人が、自らの人生を振り返り、同じような経験を思い出すのではないでしょうか。その静かな諦念と新たな希望の入り混じった感情に、本作は優しく寄り添ってくれるのです。
結論として、この「いとま申して 『童話』の人びと」は、単に「父の物語」という枠組みを遥かに超えた作品です。それは、息子から父への、そして父が生きた時代そのものへの、この上なく誠実で愛情のこもった返歌なのです。父が遺した辞世の句『いとま申して』という言葉に応えるように、息子は父の失われた青春が決して忘れられることはないと、この一冊をもって宣言しているように思えます。それは、私的な記憶を、公的な記念碑へと昇華させた、類いまれな文学的達成と言えるでしょう。
まとめ
この記事では、北村薫さんの小説「いとま申して 『童話』の人びと」について、物語の核心に触れながらその魅力をお伝えしてきました。この作品は、著者が亡き父の遺した日記を紐解きながら、父の知られざる青春時代を再構築していく、感動的なノンフィクション・ノベルです。
物語の軸となるのは、大正末期から昭和初期にかけて、父・宮本演彦が抱いた「童話作家になる」という夢です。彼が情熱を注いだ児童文学雑誌『童話』を舞台に、物語は展開します。驚くべきは、その誌面で若き日の金子みすゞや淀川長治とニアミスしていたという事実で、個人の記録が時代の大きな流れと交差する瞬間が鮮やかに描かれます。
この物語が多くの読者の心を打つのは、夢の「終わり方」を非常に穏やかに、そして温かく見つめている点にあります。それは苦い挫折ではなく、成長に伴う自然な変化、いわば夢からの「卒業」として描かれます。父の個人的な記録を通して、私たちは一つの時代の空気や、普遍的な人生の機微に触れることができるのです。
もしあなたが、家族の歴史や、忘れられた夢の物語、そして静かな感動を味わいたいと願うなら、この一冊はきっと心に残る特別な読書体験を約束してくれるはずです。父から子へと受け継がれる記憶のバトン、その重みと温かさをぜひ感じてみてください。






































