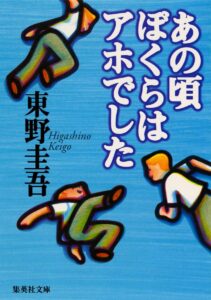 小説「あの頃ぼくらはアホでした」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「あの頃ぼくらはアホでした」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
東野圭吾という名を聞けば、多くの者は精緻なトリックや人間の深い闇を描いた物語を想像するに違いありません。しかし、「あの頃ぼくらはアホでした」という作品は、そうした一般的なイメージとは一線を画しています。これは、ある一人の男が、自らの少年期から青年期にかけての、およそ誇れることのない記憶を、赤裸々に、そしてどこか冷めた視線で綴った自伝的エッセイ集なのです。そこには、ミステリーの巨匠となる片鱗など、微塵も存在しないかのようです。
筆者は、過ぎ去った日々を「アホでした」と断じます。その言葉には、単なる謙遜では片付けられない、乾いた自嘲の色が滲んでいます。輝かしい青春の思い出など、この作品においては幻想に過ぎません。描かれるのは、失敗し、恥をかき、どうしようもなく格好悪かった、等身大以下の若者の姿。それは、我々が普段、成功者の物語に触れる際に意図的に排除する、無様で滑稽な現実そのものなのです。
この作品は、読者に安易な共感を求めようとはしません。むしろ、筆者の醒めた視線は、読者自身の過去をも透過し、その甘い感傷を打ち砕くかのようです。果たして、我々は自身の「あの頃」を、「アホでした」と断じきれるほどの正直さを持ち合わせているでしょうか。この一冊は、そんな面倒で、しかし避けては通れない問いを、静かに、しかし容赦なく突きつけてくるのです。
小説「あの頃ぼくらはアホでした」のあらすじ
「あの頃ぼくらはアホでした」は、東野圭吾氏が自身の小学校から大学時代に至るまでの体験を基に綴った、極めて私的な記録です。物語は、華やかな成功への軌跡などではなく、むしろ失敗と挫折、そしてどうしようもない愚かさに満ちた日々に焦点を当てています。これは、我々が知るミステリー作家のイメージとはかけ離れた、あるがままの、あるいはそれ以下の人間ドラマです。
小学校時代のエピソードは、既に社会の不条理に対する筆者の鋭い、それでいて諦観にも似た視線が垣間見えます。特に強烈な印象を残すのは、給食に関する記述です。保護者が参観する特別な日と、普段の給食の質のあまりにも露骨な違い。それは、子供心にも、大人の都合というものが、いかに安易に真実を歪めるかを理解させるには十分すぎる経験でした。ゴムのように固く、味気ないちくわ、色の濁った脱脂粉乳。それは単なる食事ではなく、権力に対する不信感を植え付けられる儀式のようなものでした。
高校に入ると、その「アホ」ぶりはさらに拍車がかかります。推薦入学組の学力テスト対策に知恵を絞る様は、ある種のシステム攻略術であり、後の作家の片鱗を思わせなくもありません。しかし、それが「0点を回避する」という極めて低次元な目標に向けられている点において、やはり「アホ」なのです。また、文化祭での映画製作は、若者特有のエネルギーが、見当違いの方向へ暴走する典型例として描かれます。熱意と結果が全く比例しない、無様で滑稽な顛末は、読む者に乾いた笑いを誘います。
大学時代に至っても、その迷走は止まりません。デート費用を捻出するための定期券偽造計画は、当時の若者の経済的困窮と、それを乗り越えようとする(誤った)努力の証です。結局、この計画は未遂に終わるのですが、その杜撰さも含めて、やはり「アホ」という言葉以外に見つかりません。これらのエピソードは、後の作品に直接的に繋がるような劇的な出来事ではありません。しかし、これらの些細で、しかし筆者の心に深く刻まれたであろう経験が、その後の人間観や社会観に微妙な影響を与えているのかもしれない、そう思わずにはいられないのです。
小説「あの頃ぼくらはアホでした」の長文感想(ネタバレあり)
「あの頃ぼくらはアホでした」を読み終えて、まず感じるのは、一般的な自伝や回顧録とは全く異なる、その特異な立ち位置です。通常、人は過去を語る際に、どうしても美化や脚色を施したがるものです。成功体験はより輝かしく、苦労話はドラマチックに。しかし、この作品において、筆者はそうした甘い感傷的なフィルターを一切持ち込みません。描かれているのは、徹底して格好悪く、どうしようもなく愚かで、そしてどこか滑稽な、過去の自分自身の姿です。そこに容赦はありません。むしろ、積極的に「アホ」だった自分を晒し、読者に対して「どうだ、これが俺の過去だ」とでも言いたげな、ある種の開き直りすら感じさせます。
小学校の給食のエピソードなどは、その最たるものでしょう。保護者の視察がある日とない日の給食の質の落差は、子供ながらに社会の裏側、大人の狡猾さを学ぶには十分すぎるものでした。美味しい給食を提供できる能力がありながら、普段はそれを隠し、不味いものを平気で食べさせる。それは、単なる食事の問題ではなく、権力を持つ側が、持たざる側(子供たち)をいかに軽んじているかを示す象徴的な出来事です。この経験は、後の筆者の作品に度々現れる、システムに対する不信感や、欺瞞を見抜こうとする視点の原点の一つになったのかもしれません。しかし、それを単なる苦い思い出として語るのではなく、どこか突き放したような、あるいは諦めたような筆致で描かれている点に、この作品の魅力があります。
高校時代の学力テスト対策のエピソードもまた、「アホ」の極みと言えるでしょう。推薦入学組が0点を回避するために、知力を結集して編み出した攻略法が、マークシートの全てを同じ記号で埋める、方程式はx=1と書く、図形問題は定規で測る、といったレベルなのですから。これは、当時の受験システムがいかに牧歌的であったかを示すと同時に、筆者たちの置かれていた状況の切実さ、そしてそれを何とか乗り越えようとする(方向性は完全に間違っていますが)ある種のエネルギーを感じさせます。しかし、ここでも筆者は、当時の自分たちを英雄視するわけではありません。あくまで「アホ」な行動として描き、その滑稽さを強調します。そこには、過去の自分に対する愛情と同時に、どこか見下すような、乾いた視線が存在しています。
文化祭での映画製作のエピソードも、強烈な印象を残します。恋愛映画を求める女子と、パロディを熱望する男子との対立。結局、筆者の書いた「必殺仕置人」のパロディ脚本が採用されるのですが、その内容は低俗極まりないギャグの連続、素人以下の演技、そして意図せぬところで発生する爆笑の連続。結果として観客には大ウケするものの、それは決して質の高い作品だったからではありません。むしろ、そのあまりの稚拙さ、計算外の間の悪さ、そして下品さが、観客の生理的な笑いを誘ったのです。筆者はこの成功を、手放しで喜ぶわけではありません。むしろ、自分たちが意図した形とは全く異なるところで評価されてしまったことに対する、ある種の困惑や、あるいは虚しさすら感じているように見えます。これは、芸術や表現といったものが持つ、制御不能な側面を示唆しているのかもしれません。それはまるで、満月を目指して吼える、牙の抜かれた狼のようでした。理想と現実の乖離、そしてその中で生み出される、歪でありながらも人を惹きつける力。
大学時代の定期券偽造未遂のエピソードは、さらに「アホ」を通り越して、危うさすら孕んでいます。デート費用を捻出するために、本物の定期券を加工して使用期限を偽造しようとする。これは、明らかに犯罪行為です。しかし、筆者はこの行為を、罪悪感や反省の念を強く滲ませて語るわけではありません。あくまで、当時の自分たちの置かれていた経済的な困窮と、それを何とか打開しようとする、若者特有の短絡的な思考の表れとして描いています。もちろん、これが犯罪行為であるという認識はあったでしょう。しかし、それを「アホ」な行動として語る筆致からは、ある種の開き直りや、あるいは遠い過去の出来事として割り切っている様子が窺えます。このドライな語り口が、かえって当時の彼らの心理状態をリアルに伝えているのかもしれません。
これらのエピソード全体を通して、「あの頃ぼくらはアホでした」は、単なる懐古趣味の書物ではありません。筆者は自身の過去を顧み、その愚かさを認めることで、一体何を問いかけているのでしょうか。それは、我々読者自身の過去に対する視線、あるいは現代社会に対する問いかけなのかもしれません。SNSが普及し、誰もが自己の輝かしい部分だけを切り取って発信する現代において、自身の「アホ」な部分をこれほどまでに赤裸々に、そして冷めた視線で晒すという行為は、ある種の挑発とも受け取れます。完璧ではない自分を認め、その愚かさをも含めて自分であると受け入れること。それは、簡単なようでいて、実は非常に難しいことです。この作品は、そうした自己肯定とは真逆のアプローチ、すなわち自己否定とも呼べる手法を用いて、読者に内省を促しているのです。
筆者の語り口は、この作品のもう一つの魅力です。愚かでみっともないエピソードを、決してウェットにならず、むしろ乾いた筆致で描くことによって、その滑稽さが際立ちます。読者は、当時の筆者の行動に呆れ、笑い、そしてもしかしたら自分自身の過去の愚かさと重ね合わせるかもしれません。しかし、筆者はそうした共感を深追いさせず、常に一歩引いた場所から、冷めた視線で物語を語り続けます。この距離感が、作品に独特の緊張感と深みを与えています。
「あの頃ぼくらはアホでした」は、ミステリー作家・東野圭吾のファンにとっては、意外な一面を知ることができる貴重な一冊であると同時に、普遍的な人間ドラマとしても読むことができます。それは、華やかな青春の物語ではなく、むしろ多くの人が経験するであろう、失敗と迷走の日々の記録です。しかし、その「アホ」な日々こそが、その後の人生を形作る上で、何らかの意味を持っていたのかもしれません。そう思わせるだけの力が、この作品には宿っているのです。これは、単なる回顧録ではありません。自身の過去を徹底的に解剖し、その愚かさを認めることで、人間の本質に迫ろうとする、ある種の哲学的な試みと言えるのかもしれません。そして、その試みは、我々読者自身の心にも、静かに、しかし確実に波紋を投げかけるのです。自身の「あの頃」を「アホでした」と断じられるか、否か。その問いに対する答えを見つける旅は、この本を閉じた瞬間から始まるのかもしれません。
まとめ
「あの頃ぼくらはアホでした」は、東野圭吾氏の作家人生の基盤となった輝かしい青春の記録、などではありません。これは、筆者自身が「アホでした」と断じる、どうしようもなく愚かで、そしてどこか愛おしい、若き日の失敗談を集めた異色のエッセイ集です。そこには、精緻なトリックも、人間の業の深淵も存在しません。あるのは、ただひたすら、みっともなく、滑稽な一人の若者の姿です。
しかし、その赤裸々さが、この作品に抗いがたい魅力を与えています。自身の過去を美化することなく、むしろ積極的にその愚かさを晒す筆者の姿勢は、ある種の清々しさを伴います。それは、社会的な成功を収めた人間が、敢えて自身の「負」の部分を露呈することで、読者に何かを問いかけているかのようです。我々が普段、目を背けがちな自身の失敗や後悔と、この作品は静かに、しかし確実に直面させてくるのです。
結局、「あの頃ぼくらはアホでした」は、単なる昔語りではありません。それは、自身の過去を「アホだった」と認めることの困難さ、そしてその承認がもたらすかもしれない、ある種の解放を示唆しているかのようです。この作品は、読者自身の「あの頃」を振り返らせ、その愚かさと向き合うことを促します。そして、その過程を通じて、自分自身のありのままの姿を受け入れる勇気を、静かに与えてくれるのかもしれません。
































































































